#UDCアース
タグの編集
現在は作者のみ編集可能です。
🔒公式タグは編集できません。
|
●
思い出せないことが多い。
極端に物忘れをしているのではなくて、何かがあったことは覚えがあるのに、その内容を詳しくは想起できないでいた。
深く考え込むと胸の中にずっしりと鉄でも流し込まれたような重さを感じて、あからさまに不快感でいっぱいになる。
だから、――きっと、いけないことなのだと蓋をしてきた。
「どうしてこんなことするの」
耳鳴りがうるさい。
高音に眉をひそめながら、意識をたどった。冷たい空気が体を冷やしていくのがわかる。ずいぶん久しぶりのような、遠い心地がした。
今日は、何月で何日だっけ。
「ねえ」
床に散らばる赤と、歪な三角形たちが血とガラスなのだと理解したのは、もう少し後のことだった。
今もこれが夢のような気がしてならないし、そうだと願っているし、そう思っている――心から。
だって。
「ゆみちゃん」
三角形に反射した自分の顔は、とても人間のものだとは思えなかったから。
●
「私は猫派だ」
ヘンリエッタ・モリアーティの内在する人格が一人、マダムと名乗る其れが猟兵たちを集めた途端の一言といえばそれだった。
グリモアベースにてその黒は「自由気ままで付き合いやすい」とその生き物を評する。君たちはどんな生き物が好き?と、猟兵たちにたずねる顔には感情の波が目立たない。
「でも、人間が一番好きかな」
――事件の話をしようか。
猫の画像を無数に映していたタブレットを切り替えれば、ARホログラムが規則正しく展開していく。浮かび上がる光景は、世界にしてUDCアース。都会のベッドタウンらしき場所でのことだった。
「動物による人間の不審死が相次いでいるという。襲われた、という話だよ」
――グリモアが予知した時点で、それは間違いの情報だが、と付け加えた。
淡々と黒は紡ぐ。
「最初はそれこそ、犬や猫が犠牲になったらしい。しかしどうにも歯形の特定がうまくいかず、熊なのか何なのか不明瞭で対策もできなかったというのが表向きだ」
事態の混乱は、より現実的であるべきである。
山の向こうを過ぎれば都会が広がるその場所は、野生動物も多い。わざわざ人間を狙うまでに狂暴化した獣とはいったい何なのか。
と、衆目を身近な仮想脅威に向け、十分に騒がせておきながら調査を進めたのはUDC組織であった。
「しかし、――邪神の仕業で間違いないらしい。尤も、私が視たのは関与しているという事実だけだけどね」
供物にささげられているのか、それとも単純な「食事として」なのか。復活に必要な儀式の一環であるのは間違いないが、その意図までは見えないままである。
しかし、世界と未来の使徒たる猟兵たちにとって、世界を蝕む者どもが動きを見せたとあらばそれだけで動機に足るだろうと黒は微笑む。
「人間を獣にさせるような能力――いいや、元から人間には獣性というのが備わっているのだろうか。私は自分が動物になったら、ああ、人間も動物だけれど。そういう占いっぽいのは見当がつかないな」
首をゆるく傾げてから、元に戻す。生来より他人が己の話をどう聞いているかは気にしたことがなかった黒は、骨のきしみの音の後に説明を続ける。
奇々怪々な事件には警察はもちろん、UDC組織も協力的である。
人間の心の隙間に根付き、寄生し、その情動を増幅あるいは、顕現させては凶行に走らせるとなれば手掛かりを集めてまず根源を突き止めねばなるまい。
感染型とは異なるが、狂気に大勢が巻き込まれる前に止めるのは最善だ。ふわり、ホログラムが空気を漂うように回路を走らせている。徐々に隆起を作り、街並みを作り出していた。
事件現場と思しき場所に赤い点が灯っていき、その数が両手を埋める数を超えたところで「まあ、今覚えなくてもいいかもしれないけど」と黒が口をはさむ。
「人間がかかわると事件は複雑に思われがちだ」
なにせ、ヒトは動物と違うのでね。と、冗句とも何ともつかぬ声色で黒が微笑めばゆるり、グリモアは猟兵たちを歓迎する。
ゆっくりと空間に蜘蛛の巣を伸ばしながら、その赤が地面に触れるところでのんびりとした声が好奇心たっぷりにささやいた。
「君たちにはどんな獣が宿ってる?」
――そっちのほうが気になるな。
赤い網目が猟兵たちを迎え入れるころには、目の前に広がる景色がのどかな田舎だっただろう。
凄惨な事件とは縁も遠そうな昼間である。
広い空には電線がただ在るだけで、左右を見れば川と、荒い仕上がりの橋があって欠けたっきり放っておかれる歩道がやや高い段差を作っていた。
そして、大きな山があって――鳥が一羽、木々から逃げるように飛び出していく。はらり、冬のにじむ空気に触れながら木の葉が散った。
さあ、のけものはどこだろうか。
 さもえど
さもえど
●さもえどです。
動物は好きです。
一章:推理パートです。邪神と「けもの」の行方を追いましょう!
どのような手段を使ってもOKです。
二章:皆様には自分の中の「けもの」を見つめていただきます。
それは、もしかするとご自分の傷跡の象徴かもしれませんし、昔の自分かもしれません。今の自分かもしれません。
詳しくは該当章の断章、もしくはMSページなどご参考ください!
三章:ボス戦です。「けもの」と邪神との対峙となります。
プレイング募集は断章公開後、締め切りについては断章とMSページをご参照願います。
暫く採用人数を絞ってご案内できればと考えておりますので、あらかじめその点ご了承ください。
目安は無理なく……、といった感じです!
当シナリオでの手掛かりは、以下の通りです。
どんなプレイングでも推理はよきように扱ってまいりますので、気軽にご参加ください。
それでは、皆様の素敵なプレイングを心よりお待ちしております!
第1章 冒険
『真実は散歩道』

|
POW : 手あたり次第に手がかりを探す!
SPD : マップを記録してルートを探す。
WIZ : 情報収集をしてルートを絞る。
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴
|
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
いつも通りの時間に、目が覚めた。
重苦しい夢を見ていた気がして、まず、スマートフォンが鳴らすアラームの音を止めるために伸びを一度挟む。胸の中に鉄っぽい味が広がったような気がしてむせれば、白い吐息が部屋に溶けていった。
どうやらいつの間にか、エアコンは消してしまっていたらしい。
すっかり冬が始まってしまった。ついこの前までハロウィンだなんだと聞いていたのに、今年もその流れに乗れないまま過ぎていったのを思い出す。
――ああそうだ、仕事にいかないと。
ハロウィンの夜も、きっとクリスマスの夜も、同じことをしているだろう。去年もそうだった。それにもの悲しさはあるけれど、それよりも懸命に働く自分への肯定感のほうが勝る。
一人暮らしではあるが、住処に選んだ場所は家賃もそこそこな2LDKの間取りに、オートロックの施錠とカメラ付きのインターホンまでついていて、広い。
この辺りは家賃の相場が安いから、時給も低いのだと学生時代を苦労したらしい先輩が言っていた。だから、それほど逞しくなられたのですか――なんて真面目に返したら、余計に笑われてしまった。
鐘を鳴らす。
リビングとキッチンはそのままつながっているけれど、西の角には小さな仏壇を飾っている。母が眠っているのだ。
毎日朝起きて、お供えにするためのご飯を少しだけ盛ってから、ささげる。寒くなってしまったから、自分のコーヒー一杯を注ぐための湯を少し多めに入れて、温めていた。
小さな杯に注いで飾れば、あとは慎ましく両手をそろえて、瞼を閉じて「おはよう」の挨拶をするだけで――母が、まるでそこにいるような気がしてしまうのだ。
「いってきます」
朝食もしっかり摂り身だしなみも整えて、夢の証である警察手帳がちゃんと胸ポケットに入っているかどうかを確認してから、敬礼を遺影に向ける。
写真の中の母は、死に顔を忘れさせてしまうくらい穏やかに微笑んでいた。
駅まで徒歩五分の立地だ。普段使うことはないけれど、学生たちはこのあたりに住んでいて苦労がないように見えて、ぎりぎりまで家にいたらしい。急ぎ足で寒空の下を走っていく彼らの足取りは軽やかだけれど前のめりで危なっかしい。
職場に着くまでには十分な余裕を持つようにしている。駅とは反対方向へ歩くたび、この町の人たちすべてを見ているような心地がした。
――守りたい人々だ。
家族のために働くお父さん。
勉学よりも友達のほうが大事そうな中学生。
不安げな顔をしている高校生は、時期的に期末を気にしているのか、それとも受験か。
同じ歳くらいの女性たちはそれぞれ身だしなみに差があって、見ていて飽きない。気の強そうな人もいれば、そうでない人もいた。
――守らなきゃ。
職場に足を踏み入れるとき、いつも心が引き締まった状態である。
「上村か、いつも早いな」
「おはようございます、西警部」
西警部。
無精ひげのある彼は髪の毛を短く切りそろえ、必ず前髪が目にかからないように気にかけている人でもある。
濃い目の黒い体毛は鍛えられたからだとも相まって、動物でいえばゴリラのようだと例える人もいるが、私からすれば雄のライオンのような人であった。
ライオンは、雄が狩りを行うことはない。
西警部もそうだ。現場にわざわざ出向きはしないが、私をはじめ部下たちのフォローやバックアップ、逮捕状の手配やかけあいなどを取り持って下さる大先輩はすなわち群れの象徴で、それから、「顔」に当たる人である。
部下が不当な扱いや案件を押し付けられれば、跳ねのけることはしないが「次はないですよ」と釘を必ず刺してくださるていねいな上司だ。まるで、ほかの群れの雄を追い払う雄々しい牙を持つように思える。
現場に出ることもないのに体を鍛え続けているのは、万が一に備えてだと彼は笑うが、家族に恵まれているからだと推測できた。左手の薬指の輪と、デスクに飾られた家族写真は最近子供が二人に増えている。
「おはよう。早速だが、お前の持ってる案件。今日がっつり進むみたいだ」
「本当ですか!ああ、早く来てよかった」
「だな。――頼もしい人たちなんだが、お前には詳しく説明しときたい。……お前が『早すぎ』出勤なのに合わせててよかったけどさ」
早くに出勤してくることをやんわりと窘められてから、二人分のコーヒーを注いで――まだ誰もいない職場で二人、来客用の机で向かい合って座る。
パイプ椅子はすっかり固くなってきていて、「買い換えないとケツが痛いな」なんて笑いながら太い眉を寄せて西警部はようやくおさまりのよいところを見つけたようだった。
「猟兵、ですか」
「ああ。他言無用で頼むぞ。まあ、誰かに言ったところで、だけど」
「――ええ、でも、その。大変心強い方々がいらっしゃるのなら、私としても」
説明を聞いていた。
知らない世界の話だった。それを抱えながら、うまく手を取り合って、彼らはこの法治国家である日本をそもそも壊さないために脅威から守ってくれている存在だという。
動揺が走っているのはわかる。すっかり淹れられたコーヒーの味もうまく感じ取れなくなってきていて、緊張は指先に震えで現れる。
「無理しなくていいぞ。降りるか?」
俺は責めない。と、西警部は低い声でやさしく声をかけてくださった。
――以前より、事件を一つ抱えている。この辺りで相次ぐ恐ろしい怪奇事件はあまりに「つじつまが合わない」から、報道には別の情報を掴ませて操作をしやすくしているのだと思っていたのだ。
事実、それは違って、もっと私の知らない「なにか」がかかわっている事件だったというのが種明かしである。西警部も、つい昨日の夜聞かされたところでこちらの身を案じて夜のうちに連絡をするのはやめたらしい。
「お前は真面目だ。ど真面目すぎるところがあるから」
「やります」
「いいのか」
「やらせてください。捜査を続けます。私の調べていることが、猟兵さんたちのためになるのなら」
――それが、守りたい人々のためになるのなら。
正直、捜査は手づまりもいいところだった。
特定できない人間なのか獣なのかわからない歯形も、死体の状況も、被害者を洗ってもつながりが見つからない。気持ちばかりが焦って、から回っているのも納得がいってむしろ清々しいくらい思考はクリアだった。
ためらいのない私の目に、西警部も少し沈黙を置いてから「わかった」と頷いて現場に出るよう指示を下す。あついうちに飲もうと息を吹きかけて、コーヒーを口に含んだ。
よかった、ちゃんと味は戻っている。
――平和な日々だって、きっと、絶対に、戻せる。
「行きます」
「頼むぞ」
ホルスターに収まった拳銃に意味があるかどうかはわからない。
だけれど、自分の身は守れるくらいの度胸がある主張にはなるかもしれない。自分に割り振られた番号通りのものを上着で隠すように着なおす。
前を開けるのは許されたいけれど、外の空気は寒いだろう。なのに、どくどくと脈打つ自分の体が「はやくいきたい」と叫んでいた。
カミムラ ユミコ
「上村由美子」
「はい」
敬礼を互いに交わして、私だけが署から出る。
電車に吸い込まれていく人たちの群れは、まだまだ続いていた。
●
プレイングの募集は、11/23 9:31~ 11/26 21:00とさせていただきます。
 久津川・火牙彦
久津川・火牙彦
SPD
ちわっす優誠警備保障の久津川でぇす
ざっくりと敬礼
いやマジで猟兵っすよ
ぶっちゃけウ○○ラ警備隊っすよウチの警備は
などと宣い捜査資料を見せてもらう
確認するのは被害者の傷の形状
被害者の経歴
被害にあった場所
周辺の環境、時間、その土地の古い伝え事
それと、上村刑事について
全て記録して、筋道をつけてやろう
あ、ドキッとしました?
いやぁね、昔っからあるんすよ弥生時代よりも前から
思い込み過ぎて取り込まれるタイプの性質の悪ぃ奴
こんだけ調べてりゃ考え方までそうなっちまう危険性がある
何か変わった所無いっすか、彼女?
上記を統合し定めるのは怪異の中心
人か物か事か
定めた場所へ向かい
次の事件から推定被害者を警備してやらあ
 零井戸・寂
零井戸・寂
◎
……モリアーティ女史の案内。更に獣の噛み跡……「食事」ねぇ。
(思わず首をさする。あんまり良い思い出はない組合わせだ。)
まぁいいさ 仕事は仕事だ。
…… さて、まだギリギリ「僕」の領分だな。前みたいな事にならない様に気を引き締めてこう。
さて、現場に赴き次第早速やろうか。ゲーマーかつエージェントらしく行こう。
"Ready, Player."
今回はありきたりな推理モノのゲームと洒落込もうか。
現実世界にゲームの仕組を上書き。……僕以外には別段普段と変わらない世界に見えるだろうけど
僕には「怪しい箇所と謎解きの材料が見える」。
――さあ、どんな謎解きに繋がるピースが見つかるかな。
 琴平・琴子
琴平・琴子
◎
近くに山があるなら害獣被害でもおかしくなさそうですけど
犬や猫なら烏…とは思いますがかじり痕はできません
人を襲えるくらいの動物は多くなく、熊ならニュースになって大騒ぎですが
その大騒ぎにならない様な何かが犯人でしょうか
でもなぜ噛んで殺すんでしょう
殺すだけなら刃一つでも十分でしょうに
土地の地図を用意して
犯行が行われた場所を調べてマーク
加えて被害獣、被害者の共通点もないか確認です
犯行のあった場所にも向かえたら行きたいですけど
悲惨な状況であれば眉を顰めてしまいますが
此処は事件解決のため、眉を顰めても耐えますとも
儀式のために殺されたなら何か残ってませんかね
例えば呼ぶための紋みたいな跡だとか
 冴木・蜜
冴木・蜜
これはまた
根が深そうな案件ですね
脚で稼ぐ情報収集は不得手です
私は専門分野で情報を集めましょう
刑事さん方から
遺体のお話を聞かせて頂きましょうか
特に歯形の精査をしたいですね
どうにも獣というのが引っ掛かります
……、本当に?
そんな単純だとは思えませんがね
これが致命傷なのか
死後の傷なのか
被害者によって違うのか
そもそも何のためにつけられたのか
肉が抉られているなら食べている
ただの痕なら歯形を付けることが目的
どちらにせよ
儀式の手掛かりにはなりそうですが
持ち主が特定できないというのは
毎回歯形が違うからでしょうか
それとも実在しない、生物学的にあり得ない歯形か
ふむ
歯科は専門外ですが
模型でも作って共有しましょうか
●
「ちわっす。優誠警備保障の久津川でぇす」
『人の住みよい社会の為に』。いかにもなモットーを掲げた社訓をとはやや乖離した声が響いた。
捜査室、――という名の、少し広めな会議室である。警備員など呼んだ覚えはないがと目配せしあう如何にも重役の顔ぶれに「やだなぁ」なんてとぼけた返事が間を作った。
「久津川・火牙彦(火産霊の旧支配者・f30781)っす。いやマジで猟兵っすよ、ご安心を」
未知なる怪物やトンデモ宇宙人と戦う奇妙な戦闘集団。施設警備から貴重品の運搬、警護さらに「人類の脅威」には調査、駆除、あるいは封じ込めなども請け負うウルトラなヒーロー組織と一緒だなんて説明で、すべての口がぽかんと開いてから一拍おいて敬礼が帰ってきた。
火牙彦の敬礼とは対照的なその姿勢に、「はあ」なんて言いたげに口が薄く開く。
元より表情筋を動かせるほうでもないが、何やら信頼は得ているようだった。つまり、「お手上げ」の事態に彼らは直面していたといっていい。
「そんで、事件の資料はどこまで閲覧していいんすか」
火牙彦が長机との距離を詰める。座る人数はざっと見て五人程度だ。どれもこれも「こういった」事件は耳にしたことがあるようだが、まさか自分たちが巻き込まれるとは思っていなかったらしい。
「こんな――田舎でまさか」
「田舎だからっすよ。山で人が死んでもわからんでしょ」
「狩猟会が見回ってるのに」
「何言ってんすか。御年六十、七十のじいさんとその愛犬じゃ、悍ましいものがあっても愛犬が近寄らせやしないでしょう」
白髭を蓄えた彼らに突きつけるのは、混乱を冷やすための客観的な評価だ。
火牙彦の「ガワ」――本体ではない、人間のかたちをした目だけで見てもわかる。この組織とやらはかなり身内を過信していて、さらに隙が多い。
都会のエリートが集まる警視庁とは大きく異なる。同じ国家公務員の集まりであっても、彼らはすっかり現場からも遠ければ安楽椅子のほうが近い老人の集まりだ。
こうして長机に座って資料をちりばめて「いやあ、さっぱりわからんな」と頭を悩ませるのが仕事なのである。やることはやったかどうかの確認係に、火牙彦も時間を割くつもりはない。
「で、閲覧の範囲は?」
やや小柄な成人男性からの圧力は、「でも」「しかし」を押しのけて、代わりに目の前に一冊のファイルを持ってこさせる。
片手で持てる程度の薄いものだ。いかにも「気持ち悪い」案件に触れたくないという保守的な姿勢が見て取れた。火牙彦はゆっくり細い目でそれを眺めてから、「これの整理をしている方はどちらで」と聞いてやる。
そうすると、それぞれの口が所在のありか――責任の押し付けられるところを探すのに躍起になった。
「橘だ!資料室にいつもいる、黒髪の、眼鏡で、小さい女の」
「それを見せれば大体教えてくれるさ、そうだ、担当の検視官の居場所も」
「橘さん。了解っす――ご協力感謝でした」
仰ぐ程度にしか使えなさそうなファイルをちゃんと「あいさつ代わり」に振ってやりながら足のペースは崩さずに退出する。
静かに、不自然なくドアを閉めて深く息を吐いた。「あの感じじゃ、上は噛んでなさそうっすよ」とトランシーバーにささやく。しっかりとした防音のドアにも壁にも火牙彦の声は吸われて消えた。
無機質なトランシーバーからは「了解」と少年の声が響く。「続けてくれ」の命令を受けて、火牙彦は二度ほどアンテナで頭を掻いてから「了解」と呼応する。
「おや、これはまた」
「うーん……」
「ねえ? だから言ったでしょう」
眼鏡、眼鏡、それから緑色の美しい少女の瞳。
小太りの男は検視官、水原という。今年も検診でひっかかってしまって、なんて油ぎった顔で微笑む彼の朗らかさはあまりにも室内とイメージが違った。
――検視官は、資格が存在するわけではない。
ただし法医学を警察大学校において修了する必要があり、警部または警視の階級を有する必要があるものだ。
短い髪の毛を撫でつけるしぐさからは焦りがうかがえた。それは、己を疑われているのではないかという不安よりも「わからないもの」への恐怖の表れである。
「歯形の再現をしてみましたが」
冴木・蜜(天賦の薬・f15222)は人の形をとるブラックタールだ。
複雑を極めた人類の姿は擬態には数が多く有利であるが、生きていくにはやや効率が悪い。実質、流動体である蜜の体は常にめぐり続ける必要がある。のんびりと垂れた黒い液体が悍ましいと思われない「世界の恩恵」には感謝した。
どっぷりと黒が――「つめもの」の中に入っていく。
「歯科は専門外なばかりに、すみません」
「いいえ。これは僕としてもねえ。ちょっと、まいってたんですよ」
歯形だ。プラスチックの樹脂を3Dプリンタで出力した結果生み出されたのは、とある被害者に噛みついていたであろう「けもの」のものである。
蜜にとってすれば不思議であった。歯科には医療記録が残る。例えば、――どんな犯罪者だって歯の治療というのは「生まれた時から」逃れられないものだ。
総入れ歯にでもしない限り、どうやっても「どこのだれかと」治療痕が一致するはずである。歯というのは、見える骨だ。これ以上の証拠は無いだろうと思っていたからこそころりとひっくり返したときに凝固した己の一部分に、困り眉を余計に寄せることになってしまった。
「出鱈目ですね」
背筋ただしく、どう形容したものかと蜜が悩んでいる間に言いたいことを見事的中させたのは琴平・琴子(まえむきのあし・f27172)である。
小さなお嬢さんにこんなところ、と大きな腹をさすりながら水原がうなったのを「大丈夫です」と姿勢だけで押しのけた逞しき少女だ。
お守りに防犯ブザーだってあるのだから。からからと笑うようにかばんで揺れる黄色いそれを、水原が視線で追っていた。
「色んな事を考えました。犬や猫なら烏……とは思いますがかじり痕はできませんし、これは」
黒いデスクの上でてらてらと【盲愛】の恩恵を受けて形どる模型の姿を指さして、蜜を見る。無礼だったかどうかをはたと考えるが、特に蜜は気にした様子もない。
むしろ、小さな子供が必死に机に片手をついて身を乗り出し、主張する姿には素直に受け入れの姿勢をとっていた。膝だけ椅子に乗った姿に――転げないかは心配であったが。
「どの獣のものでもありません。まるで、――本当に子どもの悪戯のよう。いろんな歯を繋ぎ合わせたこれがまさか、凶器でしょうか」
「致命傷には違いないかと。何度も噛まれた痕があったそうです。しつこく、息の根を止めるまで。おそらくこの……失礼、ボールペンを」
蜜が己の一部で作り出した模型に、水原から受け取ったペン先を這わせる。「犬歯にあたるといっていいでしょうか。人間でいえば尖頭歯、糸切歯などとも言われます」隆起の激しい歯をゆっくり撫でてやる。乱雑な歯並びはトラバサミのようにも思えた。
「間違いなく人間の歯ではありませんが、人間の歯の部分もあります。口を開かせましょうか」
うぞりと、まるで――ぐずぐずの柘榴の中身を見てしまったような感覚がする。
琴子が眉を顰めたのも無理はない。純粋な子供ですら「きもちわるい」部類の密集体だった。すべて、歯である。しかし蜜が注目したのはたった一点であった――端と、端だ。
「ここが、人の歯です。そして、顎からもわかることが。英語を母国語にされる方々というのは、喉と顎をとても使います。なので、顎が発達するのですがこの顎は比較的丸いといってよいでしょう。日本語を母国語にしている。顎をあまり使っていない発音の形跡がありますので」
元より、そんなに単純な話だとは蜜も思っていなかった。
確かにこの在り方は「どこにも存在しない」獣のあぎとだ。「しかし、異常発達した――あるいは、移植した異常な犬歯で獲物の気道を塞いでいる。ネコ科のようだ。重なり合う牙はサメのつもりでしょうか」
脳内で解剖すればするほど、複雑に入り組んだ意図を感じてしまう。まるで、これでは、「報告書によれば窒息死とありますが、血を失わせるために噛みついていたとすればあまりにも無駄が多い」呑まれてしまうような気さえする。
「大丈夫ですか」
はた、と思考の渦から引き上げるのは、やはり凛とした琴子の声であった。「すみません、つい」と白衣を恭しく折って頭を下げる蜜に、彼女は「いいえ」と首を振る。
「私だけでは理解できない事ばかりでした。感謝を」
――しかし、疑問は浮いたままである。
「もう一点だけ、お力添えを頂けませんでしょうか」
「はい、どのような。私でよければ――」
「あなたも」
「えっ、ぼ、僕も!? ああ、何か力になれたらいいけど」
プロファイルは三人とも専門外だ。しかし、事実を客観的に見ることならば彼らほど長けたものもいるまい。
琴子は此度、犯行が行われた場所にも訪れようとしたものだが、やはりあらかた――死体は司法解剖に回されてしまうし、いつまでも保管されるのも難しいもので、片付けてくださいと懇願する遺族もいたと水原が教えてくれたものだから踏み入りはしなかった。
代わりに、凄惨な事件現場のままの写真を見ようとして、ファイルに手をかける。手が止まって、蜜と水原の視線がかち合った。
やはり、小さな女の子に見せるべきものではないのではと言いたげな水原の視線はいかにも人間らしい。
彼の判断は尤もなのだが蜜としては、「見る」という選択は琴子が行うべきだと思った。
一度目を閉じた幼い彼女が、ファイルを開く。
真っ先に目に飛び込んだのは、一頭の秋田犬がかみ殺されていた事件だった。
大型の血統である。日本犬の中でももさもさとした彼の毛皮がすっかり酸化した血で、錆柄が余計にさびて見えて、純粋さゆえの共感覚がツンと鼻に鉄臭さを感じさせた。
痛ましい姿だ。
――どうしてここまでする必要があった?
「なぜ、噛んで殺すんでしょう。殺すだけなら刃一つでも十分でしょうに」
「噛むことに意味があるんじゃないかな」琴子の声に、思わず水原も考え込む。
「支配欲の象徴?いいえ、――サディズムでしょうか」蜜も同じく、組んだ右腕でそっとほほを支えながら眺めている。
琴子は、次のページをめくる。
猫。
犬。
猫。
――鳥?
犬。
そして、人間。
人間、人間。赤子、人間、大人、老人。
「ここからは、人間ばかりです」
琴子がようやく白紙のページを捲って、息を吐く。
それから、顔を上げた。蜜が目を見開いていたのは、先ほど感じた「呑まれる」感覚の理解を果たしたからである。
作られた歯、出鱈目な歯列。土台が人の顎。トラバサミ。
「練習してたんだ、動物で。成功したから、人間に移動した。だって、人間のほうが数は多いんだ。動物よりも」
脂汗がどわっと噴き出して、水原が首を左右に振る。
「ここ一帯は、狩場なんだよ――こいつの」
●
「快楽殺人の線は薄いっすか」
「そうだねぇ。私が集めてた限りではそんな感じがしなかったなぁ」
――橘と呼ばれた女は、背は小さく乱れた髪を特に気にしていないようなずぼらという言葉が似合う。
火牙彦が資料室を訪れた際にも、彼女といえば「コーヒーはいる?」というシンプルな問いである。「いただいていいっすか」と返せば喜んで用意した。
正義よりも探求心で生きているのだ。彼女のものではなかろう部屋の内部はすっかり散らばった文房具とコーヒーサーバーと、通勤のかばんが床に寝そべっていた。
「それにしても、なんでこんなに資料がスッカスカなんすかねぇ。協力的だってこっちは聞いてたんですけど」
――トランシーバーのスイッチは入りっぱなしだ。ざりざりとノイズが時折混じっても、特に橘は気にしている様子がない。「すんませんね」と愚痴を詫びる火牙彦に、「いいや」と橘も同意を示した。
「もってっちゃったんだよ。あのハリキリ刑事が」
「ああ、上村刑事でしたっけ」
資料を漁ろうにも、「ど真面目」な上村巡査がすっかりこの未解決事件の担当になってからというものの、泊まり込んで調べようとするものだから、見るに見かねた西警部が「持って帰っちまえ」と一喝したのだという。
「持ち出していいんすか?」
「よくないよ。本当はね。でも、健康を損なわれるほうが困るから」
カフェインのにおいで満ちた部屋で橘が言うようなことではないとも彼女は理解していそうな口ぶりである。
パイプ椅子にクッションを敷いて資料の管理と精査をする彼女の背中は細く、そして丸い。ちらりと火牙彦も上村巡査の姿を見ただけではあるが、不健康なのは橘のほうだ。
「経験則っすか」
「まあね」
ず、とコーヒーを啜る。
「じゃあ、橘さん。経験則で教えてください」
パソコンをたたく彼女の両隣に、片方はコップで、もう片方にトランシーバーごと手を置く。
ちょうど背を覆うように、二人の秘め事が誰にも聞こえないような演出にドラマならば見えただろう。この緊張感さえなければなと橘が冷汗をうなじに垂らすのを、火牙彦が見た。
「あ、――ドキッとしました?」
「まあね。あまり経験がないから」
「いやぁね。事件のことがわからなくても、自分はともかく他のデキる猟兵さんたちってぇのは、無いところからも有るものを探し出しちまうんですよ」
火牙彦の瞳は、ずっと揺らがない。
「自分には、目に見えたものを掘り起こすことしかできないんっすよ」
漆黒には輝く四角の画面を映していた。
「資料が持ち出されて無くても、俺が知りたいのは事件のことより――彼女のことで」
教えていただけますよね、と低くうなる。橘が身をよじって、頭を抱えた。
「いやぁね、昔っからあるんすよ弥生時代よりも前から。思い込み過ぎて取り込まれるタイプの性質の悪ぃ奴」
身に覚えはありませんか?と橘の後頭部にささやいた。
「こんだけ調べてりゃ考え方までそうなっちまう危険性がある。家に持って帰るほど? ありえねえ。仕事っつうのは家帰ってまでやるもんじゃないんですよね」
――何か変わった所無いっすか、彼女?
画面が、橘のクリックで切り替わる。
マウスホイールが露出したタイプのワイヤレスマウスがころころと回転音を立てながら、渋々と言わんばかりに火牙彦に視線で追われながら動いていた。
「仲間を売るような、って思ってたんだけど。毒されてたのは私かもしれない」
がり、がり、がりと印刷機の走る音がする。インクを垂らして排出すれば、どんどん失われたはずの情報が出てきた。
そう、アナログで資料を纏めることもあれば――ここまで情報に固執する橘が「自分用の」バックアップを取っていないはずがない。
「隠すつもりはなかったんだろうけどね」
「精神に異常が?」
「誰だって異常はあるさ。私の収集癖みたいなもので」
だいたいの束になったところで、――火牙彦がコピー用紙を両手にする。先ほどのファイルよりもずっしりと質量を感じさせられた。
●
そもそも、この依頼の概要を聞いた時から。
塞いだはずの傷を焼かれたような気がして――気分はあまりよろしいものではなかった。
「つまり? 上村巡査は精神疾患があるってこと?」
「そーいうことみたいっすね。まあ、隠して仕事してるやつなんてゴマンといる時代っすけど」
零井戸・寂(FOOL・f02382)が聞いて思ったことといえば「ロールプレイが上手なのかな」という極めてゲーマーな感想だ。
事実、猟兵にも精神的な揺らぎがあったり、やや衝動的なところを抱くものたちはいる。寂とてそうだ、彼にも「二面性」がある。
それは確かに診断を下せば何らかの異常として認められる可能性がないとはいえない。だから、――市民を守ることに躍起な彼女が「不健康」であることには特に違和感がなかった。
寂のいるところといえば、できれば「以前」のような事にならないためにもできる限り事件とは遠い場所で、かつ、支援係として活躍しきるための最高のポジションを陣取ることにある。
会議室を一つ貸してほしいと声をかければ「いいですよ」とやわらかい声で婦警が対応してくれたのだ。
――やれ、いくつ? だの。やれ、大変ねだの。
――いえいえとんでもない! こう見えてもベテランなんですよ!なんて。
わざわざ波風を立てる必要もあるまいから、口八丁でいなしてから「どうぞごゆっくり」で解放されたのだ。
もし、今パイプ椅子に足を組んで座って行儀のなっていない姿を先ほどの婦警が見たら「やっぱり子供ね」なんてほほえましく思うのだろうが、寂の見えている世界とはかけ離れている。
【Ready, Player?】
寂にとって、今のこの場は推理ゲームだ。
コイン型の電子データが彼の操作してよいキャラクターの数を生み出す。ちゃらりちゃらりと降るのは三枚のコイン。
命令に忠実に動き、冷静に立ち回る動く存在。火牙彦。
協力を申し出たときに「そのほうがうまくいくならいいっすよ」なんて呆気なく呑んでくれた彼である。
「次は、――お二人が作った地理プロファイルから察するに自分は動き回ったほうがよさそうっすね」
「そうだね。プレッシャーを与えたほうがいい」
寂が命令(コマンド)を出す。
「最善は次の被害者を出さないことだ。常に誰かが警戒しているという状態で相手に緊張感を与えよう。本当に『けもの』なら、自分のナワバリに入った奴らが動き回ってたら気が散ってしょうがないだろうしね」
――それが謎解きに一番有効打であるから。
「了解。ほかの方々に上村刑事の資料を配っていきます」
「頼むよ。共有は早いほうがいい」
ぶつりと通信が途切れて、寂の操作から火牙彦は離脱状態になる。
ふう、と肩をゆすってから――二人の声が響いた。
「PTSDですか」
「P……?」
「トラウマ持ち、ってことかな。わかりやすく言うならね」
琴子と蜜もまた、協力の姿勢でプレイキャラクターとして寂に情報を与えた存在である。
通信機を介さずとも、二人が追ったことは寂を介し火牙彦に伝われば、逆もしかりの作用があるのだ。
――この四人の中で、寂はプレイヤーでありサーバーの役割を担っている。
誰もいない空間に反響する自分の声が大きく聞こえて、そっと声をすぼめた。「センシティブなところだから、どこまで掘り下げるか悩むな」と困った眉の間を人差し指で伸ばす。
「母親を亡くしてるみたいだ。自殺だってさ」
「自殺」琴子が、言葉を繰り返す。
親が朝起きていたら死んでいたなんて状況、小さい子供がまともに見てしまったらどう思うだろう。
「両親ともいない。虐待の経験もあったけど、母親の死後は親戚の家で育ってるね。無事に警察大学に進んでた」
「ああ、なるほど。生真面目な方だと聞いてはいましたが、反抗期も無いと」
『反抗期がない』という子供は年々増えている。
子供のころに自分の人生を選択できないでいると、子供は自主性を失う。親はそれを喜んで、子供を意のままにソフトコントロールしてしまうことも多い。
管理下の自由がもたらすのは、圧倒的に「依存的な大人」を生み出す可能性が上がるのだ。
しかし、――あの生真面目さはどこか「いい子であろう」とする姿に蜜からは思われた。
「犯人の像からは異なりますね。しかし、事件に固執するのですから、少しトラウマを刺激されたのでしょうか。被害者に母親と似た年齢の人が――」
「いや、たぶん、違うと思う」
寂は、事件資料を頭の中でまとめながらできる限り自分の心を殺して告げた。
「母親の遺体には、噛み痕がたくさんあったみたいだった」
歯形から、それは上村由美子本人のものだと判断された。
――父親の所在については、死亡届と死因が描かれている程度で「なぜそうなったか」は察することが難しい。
それでも、寂の視界には赤いポイントがいくつも明滅している。
「調べられる」ところには「調べなくてもいい」ところがある。消去法で一つずつ虱潰しにやっていっても、追い付かないだろう。タイムリミット付きの捜査ゲームはどんどんカウントダウンを進めている――何の?
「空腹だったのでしょうか」琴子のますます不可解らしい声色に、寂が静かに考えていた。
空腹なら、わざわざかじるだろうか?
それこそ包丁で削いで、食べたいだけ口に含めばいい。
死んでいく母親の姿を見ながら食べたいと思う犯人は、――以前に出会ったことがあるが、今回の上村由美子とはかけ離れている。
事実、上村由美子本人は年何回か行われるストレス耐性のチェックにも軽度で合格していたのだ。
精神的な疾患を取り繕ってこのハードな行政の仕事を成し遂げられるとは、さすがに思えない。寂が唸って、「あ」と口を押えた。
「そうか」
どうして、見落としていたのだろう。
火牙彦が言っていたではないか。
「そういう思考に呑まれる奴は昔からいる」と。危うく、自分がそうなるところだったと気づいて思考の海から遠ざかる。
「噛むという行為には、確認の意味があるって。乳幼児とかだ。えー、と、まず食べられるかどうかを確認するのと」
「親に」
記憶をたどるように寂が声を紡いでいたところで、蜜が答えを知っていたから、続ける。
「――どこまで許されるかを試していたのでしょうね」
まるで、親にすがる子供が。
お母さん、私を見てと主張するように。
小さな子供が仕掛けた悪戯は、――母という絶対の安全圏を失った。
「なんだこれ」
寂がたまらず眼鏡をはずして、汗をハンカチで拭う。
暴いてしまってはいけないようなものの気がした。他人の傷痕そのものだ。
恐らく今も上村由美子本人が外を歩き回りながら必死で捜査しているのは「母親とよく似た死体を見た」せいに違いあるまい。現に、眼鏡をかけなおした寂の周りには「ビンゴ」の文字が浮いている。
「――仕事だ、そう、仕事なんだよ」
たとえ、それが。
「自分で作り出した死体だ」と「知らない」結論であっても。
成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴
 シキ・ジルモント
シキ・ジルモント
◎
人間を獣に…どうにも、他人事とは思えない
…まずは、仕事だな
現地で調査を進めている警察官から直接話を聞いてみたい
事件直後の現場の様子や、気になる情報はなかったか
小さな引っかかりでもいい、むしろそういうものの方が役に立つ事もある
その話を踏まえて、最初の事件現場を調べてみたい
復活前の邪神の力の及ぶ範囲はそれほど広くはないと予想している
最初の現場の近くに邪神や、邪神に深く関わるものが存在していたと仮定して、痕跡を探りたい
物証や…後は、何か匂いが残っていないか
匂いを探って追跡する事は、狼の姿に変身して嗅覚を駆使すれば可能かもしれない
…獣の感覚に頼るこの方法は、あまり好みではないが
仕事の為だ、仕方がない
 サリア・カーティス
サリア・カーティス
犬や猫も犠牲に……ですか。
それは見過ごせませんわね(根っからの犬派
そうですわね……こういう時のセオリーはよく分からないのですけど……今犯人がどのような存在か判別出来ないのなら、当時を知る「被害者」に聞くのはどうでしょう。
まず、ケーサツ? の方々に【礼儀作法】を以て犬等が被害にあった場所を尋ねますわ。
場所が分かったらそこに赴き、被害にあった犬の霊を自分の身に【降霊】。あなたに何が起きたのか、私に見せて頂戴?
私が使役してる犬の霊達にも周辺を調べてもらいましょうか。動物の感覚で何か分かることもあるかもしれませんわ(【動物使い】使用
●
人間を獣に堕とす業とは、なかなか身に覚えもあって――緊張感も高まるものだ。
「まずは、仕事だな」
「ええ、見過ごせませんもの」
シキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)とサリア・カーティス(過去を纏い狂う・f02638)は人狼である。
真面目で堅実、かつ、ストイックなシキの足取りは確かなもので、サリアといえば人間は殺しつくしたけだものであるが、この場すべての人間が犬を食い物にするようなものばかりとは思えない。
情報の共有を受けて、二人が訪れるのは町の一角である。
家屋の背が低く、特に高いビルも見受けられない。
地域柄の調査から始めようと、二人がその点を指摘したところ景観保護法がどうだとか聞いたが、シキはともかくサリアの耳はアンテナのようにくるくると言葉の理解をはぐらかしていた。
空が広い。仰ぎ見れば広がるのは青空と、やや近くにある雪雲である。
「話を聞いてもいいか」
シキがこの場を訪れたのは理由がある。
一か月ほど前に――犬を殺されたという老夫婦の家であった。
夫婦は、孫たちに早く住居から抜けて一時的にも屋敷を手放して避難するように言われていたらしいが、やはり何十年と苦楽を共にした場を無人にするわけにもいかず、さてどうしたものかと悩んでいたところであったという。
故に、成人した孫たちが出た手段といえば、この奇天烈怪奇な事件のリークをしない代わりに、老夫婦の警護に警察を使えということであった。
被害者遺族を警護する程度、摩訶不思議を好奇の視線に晒すよりはずっと処理も楽であるから、地方公務員――「お巡りさん」たちがやや広い日本家屋の四隅にて車中で待機していた。
「はっ、はい!『猟兵様方』とお伺いしております」
「被害者遺族と接触は可能か?」
軽自動車――覆面パトカーから出てきた警官が慣れない手つきで敬礼するのを、シキは咎めない。
「あ、えー……と。そうですね、問題はないかと。自分が先にご説明をして、住居に立ち入っていただいてもよいかを確認して来ます」
「助かりますわ。ああ、お待ちになって。ケーサツ?の御方」
サリアがふさふさとした漆の尻尾を緩やかに左右に振りながら、家屋のインターフォンに近づく警官に歩み寄る。
「寒い中、ご苦労様です。大変でしょう」
色白の指の先には赤いネイルが目立った。
やさしく添えられた十指に支えられる缶コーヒーのパッケージがやけに輝いて見えているらしい警官は、どう返事しようかやや呆気にとられて「ええ、ああ、お気遣いを」なんて使い慣れない敬語で受け取る。
「私、多少犬には詳しいものですから。出来れば犬舎や、お庭を拝見したく思いますの。でも、どんな人でもずけずけと徘徊されるのは苦手かと思いますので」
――お願いは、皆まで言わずとも伝わったようである。
屋敷のインターフォンを押して、老夫婦に客人に紹介をする警察官の後姿を見ながら「俺が聞き出すほうがいいか」とシキが問うた。
「あら、よろしいのですか」なんてサリアが言うものだから「あまり人間が好きそうには見えなくてな」と青い瞳が正直な答えを返す。
くすくすと形の良い唇で三日月を作り、まさかまさかと髪飾りの赤が揺れる。
「こういうときのセオリーがよく分からないだけですわ。ですが、私はずっとミステリに疑問がありましたの。――『どうして被害者に聞かないのでしょう』?」
シキが屋敷に迎え入れられる。根回し通り、サリアはふらり――気まぐれな足取りで誰の視界にも囚われないうちに、庭を歩いていた。
立派な庭である。砂利を敷き詰めているのは防犯対策といえよう。松の木が何本もあり、このあたりの家の中でも取りわけていねいに手入れがされている。
「すみません、お客様などたまにしかいらっしゃいませんから」
「お構いなく。仕事とはいえ、突然の来訪を許していただいたことに感謝を」
通された客人用の応接室は和のつくりであっても立派なものだ。
掛け軸はシキの目で見ても価値がいまいちピンとこないが、ほこりをかぶっていないところから見て持ち主の老夫婦が大事にしている値打ちのあるものなのだろう。
世帯主である老いた男がゆっくりと座布団の上で胡坐をかき、シキと対面になる。上等な木で組まれているらしい長机のようなちゃぶ台は、まるで懐石料理でも並べられる旅館のもののようだった。
「早速だが、――事件のことを聞きたい。警察官にある程度聞いてみたが、どうにもあまり口を開きたがらないもんでな」
無理のない範囲で構わないから、と。
夫婦に気を遣ったシキが目の前に熱い緑茶を蓄えた湯飲みを置かれる。
犬は、古来より人間に依存し家畜として生きる道を選んだ生き物である。
そのルーツは狼であるが、事実、狼は人に懐くということがない。犬は遺伝子の単位で人間に寄り添い、依存し、そうすることが種族の繁栄に繋がると理解し家畜となった生き物たちだ。
故に、人間といえばほとんどが犬を家族として愛する。
犬の寿命は人間よりはるかに短いが、全身で人間を愛するひたむきな生き物でもある。まるで、子供のようだったろうか――。
「ええ、おそらく下っ端の」
言葉を詰まらせた男主人に、シキは「構わない」と首を振る。
「俺は警察じゃない。続けてくれ。気にしない」
「――すみません。あまりにも、腹ただしくて」
男主人の隣に、寄り添うように女主人が座る。白くて薄くなった前髪を撫でつける掌はこわばっていた。あかぎれの薄い指は痛ましい。
「あの子は」
声が震えている。シキの耳が、ひょこりと女主人に向いた。
「私たちの番犬として、孫が与えたものでした。主人も私も、子供を送り出してからというものの特にすることもなく、この家もどうしたものかと考えていた時に迎え入れた子なんです」
かつて、整えられた庭の隅で、老夫婦に撫でてもらいながら――昔話を聞くのが好きだったという。
「そう」
白いアンティーク調の椅子に腰かけるサリアは、穏やかな風景を見ていた。
――サリアが人目を避けたかったのは、降霊術のためである。
シャーマニズムといえば理解も深まるが、初対面の黒ずくめの女が突然、目に見えぬものと会話しだしたら不審を煽るだけだとしてシキに老夫婦の視線を盗んでもらって、彼女は『被害者』と交信することに成功した。
「やさしいお二人だったのね」
愛された犬は、たった一匹の彼である。
野犬の母が産み落とした犬だったそうだ。保護団体らしい人影に助けられて、さあいよいよどうなるかと怯えていた時に迎えに来てくれた集団の中に二人の姿があった。
まだ黒さが多く残る髪の毛をした二人が、ていねいに家のルールを教えてくれた。
雨の日でも散歩に連れていき、泥まみれになった足と腹をふいて、まとめて風呂に入ってしまおうかなんて笑う男主人と一緒に湯舟で遊んだ。
ああ、お前が来てから子供たちがいない家が楽しくなってしまった――。
なんて、笑いながら爪を整える手つきがやさしい。犬は、幸福であった。
「だから、まだ離れられないのでしょう」
――サリアが、目じりに涙をそっと浮かべる。
彼女自身が泣いているわけではない。犬がそうしているのだ。
赤い瞳を潤ませられながら、犬の記憶をたどる。
とある晩のことであった。その日は木枯らしが吹き、季節の変わり目を知らせるものだと理解していても、何せ勢いのあるものだったから、ばしばしと何度も窓が揺れてやかましい夜である。
犬は屋敷を自由に歩き回れる身であった。もとはといえば番犬として家族に迎え入れられ、訓練も受けていたのである。
だからこそ――危機には聡かった。
明らかに風の音だけではない、窓をたたきつける音が聞こえたのだ。
廊下を走る。犬は、四足をしっかり使って飼い主たちを起こさないよう手際よく走っていった。足の裏は毛がはみ出ないようにきれいにそられていて、滑ることもない。
何か変なものが二人を襲おうというのならば、この体で追い払ってやろうと見回っていた時である。玄関に、不思議な影を見た。
ずんぐりとした背丈のある毛むくじゃらの何かが立っている。
いろんなにおいが混じっていた。
人のような手足をしているのに、地面にぺたりとくっつけて、ううううと唸りを上げている。
目はギラリと見開かれていて、ここを開けろと言いたげな姿勢に犬も威嚇を示した。
勇敢にも、犬は戦ったのである。
――しかし、結果としては、殺されてしまった。
「また二人が襲われないか、心配ですのね」
犬は、この屋敷からまだ殺された日のまま離れることができていない。
自分を失った二人がすっかり元気をなくし、この家すら手放せと言われていることもどうしてやることができないのだ。
ふがいない、自分が死んでしまったから。悲痛の思いがじんわりとサリアに響き渡る。
「やさしい子」
いいこ、いいこ。
夫婦のようには撫でてやれない。しかし、代わりに寂し気で血まみれの茶色い背中を慰めるようになでてやることはできた。
黒い服の上から己の胸を撫でて、息をゆっくり吐く。
「私たちが解決しますわ。だから、あなたは――もう少しだけ、ここで守ってくださる?」
犬の霊が尻尾をゆるりと振って返事とする。
言われなくてもそのつもりだったと言いたげな、凛とした顔色が見えてサリアも目じりの涙をぬぐう。
さて、と立ち上がって彼女の「犬たち」を屋敷の外で待つ。
「――おい」
「あら」
ああ、帰ってきた。と思って目を遣った先には、狼がいた。
しっかりとした鼻面には見覚えがある。「シキさんなの? 素敵だわ!」――サリアは根っからの犬派であった。
狼の姿と化したシキは【ハンティングチェイス】の名残である。ぶるぶると体を一度大きく振って、泥やほこりを飛ばしてからサリアに寄った。
「屈まなくてもいい。服が汚れる」
ふす、と鼻で息を吐いてから横腹を後ろ足で掻く。「この辺はダニが多くて困るな」サリアの使い魔たちは霊体であるゆえに影響はないが、シキのような健康状態のよい獣は害虫に付きまとわれやすい。
「手がかりはあったか。お互いに共有をしておきたい」
「ええ。犯人の姿を視ていました」
「何?」
「――ですが、なんと形容してよいのかわかりかねますの。毛むくじゃらのように見えましたが、手足は確かに人のものでした。女性だと思います」
「においは」
「わかりませんわ。混ざりすぎていて、特定ができないような――」
やはりか、とシキが唸る。
シキが老夫婦の屋敷から出て、彼らの「目撃情報」や事件現場そのものの印象を聞いた時にもしやと思いあたりを駆け巡ったのだ。
獣の感性に従った方法は、理論的でないが今回ばかりは仕方があるまいと――狼の姿で走った。
「被害者の周りには、無数の動物でできたDNAが見つかったそうだ。羽根や、体毛、唾液。どれもこれも、特定ができないのだと」
「……獣が寄ってたかって殺した、とでも?」
「あり得ないだろうな。しかし、『あり得る』のかもしれない」
サリアの犬たちも、彼女の周りでぐるぐると徘徊しながらきゅうんきゅうんと情けない声を上げて心細くしていた。
彼らもシキも、走り回って嗅ぎまわったものの――結論としてつかめたのは『無数の動物の痕跡がある』という点である。
生態系としては当然のことだが、たった一匹の獲物を襲うのにわざわざ集団で種族を問わず襲うはずがない。お互いで殺しあったほうが余程野性的だ。
「老夫婦から地域の情報も得た。警察では信ぴょう性の観点から除外された情報のようだが」
つまるところ、「オカルト」は専門外である。
法治国家の日本では、超能力及び心霊現象、邪神の干渉を基準に法律が作られてはいない。
仮にその力を使ったとしても誰も裁くことはできないだろう――だからそもそも、この一件には警察も関与したがらないのだ。
立件すれば「超常を認める」ことになってしまう。
UDC組織と提携しているとはいえ、片田舎ではその理解も行き渡っているようで末端にはしみ込んでいないらしい。
「復活前の邪神の力の及ぶ範囲はそれほど広くはないと予想していたが、案の定だ」
べろり、真っ赤な舌が上顎を舐めた。
「上村家は、この辺りじゃかなり『いわくつき』らしい」
――すっかり怯えた様子の犬たちの思念をなでてやりながら、「ああ」とサリアが納得の声を漏らす。
「この子たちも怯えてしまって当然ですわね」
たった一人の少女に降りかかった邪神の手が、たとえば「一族の業の結果」だとしたら。
――裁けるだろうか。
身に覚えのない罪で火あぶりにされる少女の中身が獣だなんて、どれほど痛ましいことだろう。
屋敷には、犬の霊が座り込んで東の方角を見ていた。
成功
🔵🔵🔵🔵🔴🔴
 百鳥・円
百鳥・円
相も変わらず邪なカミサマ方が潜む世界ですねえ
ぽーんと復活して貰っちゃあ困るんです
この世界で悠々と遊ぶことが出来ないでしょ?
わたしも人間がすきですよう
ニンゲンの内に潜む獣性が凶暴化したらどーなるんでしょーね
それはそれで面白いことになりそーではあるんですが
メンドー事を増やされたらたまったモノじゃありません
真面目に探しましょーね
さてさて、何処に行きましょーか
けんけんぱっとステップを踏みながら橋を行きましょ
そのまま大きな山の中を探索開始ですん
動物の言葉は聞こえませんし話せませんが
心をちょーっぴり覗かせて貰いましょ
聞き耳を立てて周囲の音にも注意を向けておきます
心の内に生きる獣
んふふ、気になっちゃいますね
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン
(ひとの巣と、森の域が近い
なればその二つを隔て守るのは、森番の仕事だ)
(ひとを守るものに会ってみようか
相手が猟兵を知っているのなら話が早い
警察に協力を申し出て、現場を確認させて貰い
【野性の勘】で【追跡】
獣の骸を見つけたら
「森臥」
魂を小さな獣に変え、その目を借りて)
…あとで土に還すから。
少しだけ、借りるよ。
(この辺りでは、ひとは一番食いでのある肉だろう)
…それとももう、それしか求めない程に育ったか。
(ひとが幾ら探しても見付けられないならば
ひとからけものへ、けものからひとへ
何処かで切り替わるんじゃないだろうか
…ああこれは、おれには答えの出せない問だ)
……ひとは、どんなときけものになるんだ?
 ウィータ・モーテル
ウィータ・モーテル
◎
邪神とけものの行方を探す為に「情報収集」するよ。
死んだ人達の霊からも、何か手がかりがあるかな……って。
UCで。黒猫のユランにお願いする。手伝って欲しいの。
*
僕も猫好きだよ! 猫だしね♪……え?聞いてない?
少年姿で、ウィータと一緒に死霊を呼ぶお手伝い。
警察は……情報があるに越したことはないけど。あんまり、見られたくないかなぁ?
おねーさんは怪しーけど。
ひっそりと、死霊、霊魂達の話を聞きながら、後を追って行こっか。
邪神は救えないだろうけど、死んだ人達ならまだ、救えるかも。
*
死んだ人達の霊には、お祈りだけしておくね。
助けられなくて、ごめんなさい。
来世が、恵まれていますようにって……
 ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
獣、な
元より獣に近いらしい私には、人間とて頭と手先が進化した獣のようなものに見えるが
……まァ違うのだろうなァ
これは「残虐で」「およそ人間らしくない」事件なのであろうし
便利な能力があるんだ
活かさない手はない
適当に目星をつけた現場を回って歩こう
兎に角、数を回れるようにルート取りしておくか
起動術式、【死者の岸辺】
さて霊魂どもよ、ここらで何が起きたのかは見ているな?
なるべく詳しく伝えろ。見せるでも聞かせるでも体験させるでも構わん
数が欲しいんだ、本人じゃあなくても教えてくれると助かるが
さて何があったにせよ
本当に恐ろしいのは理性を奪う化け物か、それとも理性を捨てた人間か
全く、分かりゃせんなァ
●
ひとの住処と、森の域が近い。
――その二つを隔て守るのは、森番の仕事である。
ロク・ザイオン(変遷の灯・f01377)は樹の上に昇って、まず森の景色から見える人の文明を見た。
森に至るまで、先にひと側の守護者にも会っている。
彼らはみな口をそろえて、ロクの身分を理解したうえでこういったのだ――「我々末端は何も知らなくて」。
知らぬ存ぜぬも無理はあるまい。
事実、下手に知っている状態のものを増やすと口封じもままならなくなるのが当然であるが、ロクにはひとのきわめて社会的な事情はわからないでいた。
「すみかを守らなくていいのか?」
知らないままでいいのか、と。ざらついた声は問う。
すると、警官どうしはきょとんと顔を合わせあって「それもそうだ」「調べれば」「どうせノンキャリアだし」「やってから後悔したほうが」と団結を高めていた。
ロクが無意識にやったことは、絡まった木の枝をほぐしてやることと似ている。
一つ一つは空高く伸びることができるのに、風やほかの枝に邪魔されて絡み合ってしまった彼らをただせば、のびのびとありたい姿に成長できるような感覚と似ていた。
「おーい、ロク。眺めはどうだ?」
下から低く、ロクのものとは違って渋い声が響く。
樹のほぼ頂点から空と町を眺めていたロクが、そのまま体を丸めて後転すれば――がさがさと葉の隙間を抜けて、美しくしなやかに枯葉を踏んだ。
その姿を、ニルズヘッグ・ニヴルヘイム(竜吼・f01811)は微笑んで見届ける。
ぶる、と一度頭を振ったロクが、はらはらと木の葉を体から落とした。
「ここはいい。ひとが、森と暮らしを分けている。森に、ひとのにおいが少ない」
――それもそのはずである。
ロクが協力を申し出たときに、フィールドワークが得意であるというのもあって警察から許可が出たのは森の散策だ。
このあたりの森は特に手入れされている様子がなく、獣たちも潜むには都合がいいようだった。
巣ごもりの準備をしているシマリスの姿はニルズヘッグも何度か見たものであえる。
しかし、確かに誰かの土地ではあるため、こうして立ち入るにもいちいち許可を取らねばならないのだった。
ロクにもニルズヘッグにも、いまいちその非効率さのよさがわからないが人の条理に逆らう彼らではない。
昼を過ぎてから降りた許可通りに、山道に慣れたロクが先行し、木々をかき分けるような巨体を翼と尾で持つニルズヘッグが踏んでいく。さながら、獣道があっという間に作られるのを追いかける少女が二人。
「――に、してもぉ。相も変わらず邪なカミサマ方が潜む世界ですねえ。そう、ぽんぽーんと復活して貰っちゃあ困るんですが」
百鳥・円(華回帰・f10932)が肩をすくめつつも、けん、けん、ぱのリズムで小石や枝を踏まないまま跳ねる。
かさりかさりと彼女が跳ねるたびに耳障りのいい音が響いた。寒空はちらりちらりと雪を落とし始めて、鼻の頂点に白を乗せては水に変える。
この世界で悠々と遊べないのは困る。円はトレンドにも興味があれば、移り変わるネオン街すら興味深いし、まだまだ味わい足らない夢があるのだ。
「メンドー事を増やされたらたまったモノじゃありませんが、この森がもはや証拠のような気がするのって円ちゃんだけですかぁ?」
――それは、そうだけどやっぱり現実的な理由が欲しいんじゃないかな……。
自由奔放、天真爛漫な円がある程度整理された道を歩くように、彼女の足場を使ってついていくのがウィータ・モーテル(死を誘う救い手・f27788)であった。
無表情なラベンダー色の少女は、思念だけで会話をする。ロクの耳が音の出所を探そうとしてくるくる動き、こてりと首を傾げた。
テレパスの類だろうなァとニルズヘッグがささやけば、「てれぱす」と頭が正面に戻る。
「にゃはは、だから僕たちに出来るのは、目に見える物証集めってトコじゃない?目に見えないものに頼ってさ」
「しゃべるねこだ」
「猫もしゃべる時代かァ」
「あー、見たことあります。美少女の戦士が連れてるやつとかカワイーですよねぇ」
ウィータの肩に陣取っている黒猫が飼い主の代わりにしゃべっていても、特に違和感がない集団でよかったと張本猫、ユランも安堵した。
事実、あまり自分たちの姿を警察と呼ばれる姿に追われたくもなければ、今から行うことを見られたくもない。
「あ、でもでも。こーいう手段で集めるやりかたって、証拠としてふじゅーぶんってことになっちゃわないでしょうか?」
「いけないのか」
円が木々を見上げて、ロクがそれに不思議そうに返す。
「人間社会は複雑でなァ。この事件の犯人が『けもの』ならば射殺せねばなるまいし、『ひと』ならば――裁判にかけねばならんのだ」
面倒だよなァ、とニルズヘッグも思う。
ニルズヘッグからすれば、獣も人も似たようなものだ。手先が器用になり、腹と背の力が強いから大きく発達した頭を持ち上げるようになった種族である。
言葉を使い、絵を書き、言葉を持ち、繁殖するだけの――動物にしか思えないのだが、それはニルズヘッグが竜種である観点だからであり、この地球上尤も生息する大型の動物としての彼らが、四足の動物とは違うというのならば、それもそうなのだろうと認めていた。
はてさて、いったいどちらが残虐であるのか。
「あの刑事がかかわっているのは確かであるらしいが、洗脳して自供させることも証拠としては不十分らしい」
「えー、それじゃあほんとーに手詰まりなんだねぇ」
「なァに、私たちが本気を出せばなんとでもなるだろうさ! ま、万事任せろ。なんとかしてやる」
こじつけ、詭弁、誘導尋問でもなんでもいい。
いいのだが――より「現実的」な証拠が見つかれば、上村巡査にも突きつけやすい事実となるに違いない。
かさり、かさり。水分を失った木の葉がどんどん土くれに代わっていこうとするのを踏むのは、その手伝いをしてやっているだけのことだ。
ロクがしゃがみこんで――鼻に感じたにおいをたどり、地面をためらいなく両手でかき分けだした。
「おや、どーしました?」
円がのんびり尋ねる。冬支度をしてふくふくに太った狸が、皆を見ていた。
「――、いたちが死んでいる」
ロクが抱きかかえるのは、腐りかけたイタチの死体であった。
立ち込めるはずの腐臭すらほとんどかぎ取れない。自然の力に分解されている状態の亡骸は、すこしでも使い方を粗雑にすればボロボロに朽ちるだろう。
「死んでまだ二日くらいだ」ざりざりの喉でロクがか細く鳴いてやる。同情の音ではなく、本能からくる慰めの音であった。
「ほォ。食われたわけではないな。同種との争いにしちゃァ少し、傷が深い」
ニルズヘッグが冷静にその死体を見て、ならばこのあたりか――と、周囲を仰ぎ見る。
この森の持ち主は、上村由美子の親戚である。
いいや、――正しく言えば上村由美子のもの「だった」。
生真面目な彼女が「いらない」といったので、親戚の手に渡されたらしい。
高い値段で土地を売るよりも、彼女は堅実な組織で働くことをよしとした。
商いには向いていない性質なのだといって、彼女は「財産」を捨てたのだ。
予め、先の猟兵たちによって地図にはマッピングがされてある。ウィータが用紙を広げて、ユランが文鎮代わりにその上に座っていた。
「じゃあ、僕たちは北からやってくよ」
「おう。ならば私は西を」
「――おれは、こっち」
「おや、円ちゃんはじゃー南で」
それぞれが、背中を向けあうようにして四方向に祈る。
――助けられなくて、ごめんなさい。
――来世が、恵まれていますように。
ウィータの祈りを、【誓約の名のもとに】、悪魔であるユランが届ける。
悪魔らしい行いではない。死者の魂を食らうのが「らしい」行いであるが、何せ誓約というものは彼らにとって絶対だ。
邪神は救えないが死んだ「なにか」の魂程度なら救えるかもしれないとウィータが願うならば、ユランもそれに応えるだけである。
意識を集中すると、木々の揺れる音に紛れていろんな思念が聞こえてきた。
あまりにも数が多い。
――死んだ獣が多い。
いまさら。もっとはやく。どうして。いたかった。たべないのに。へんなの。ふしぎね。みたことない。なかまじゃない。
「仲間じゃ、ない?」
ウィータの驚嘆とともに出た呼気に、思わず声が乗る。
起動術式、【死者の岸辺】。
死霊どもはニルズヘッグにすがるように常日頃よりたかるものだ。
助けてくれ、わかってくれ、見つけてくれ、抱きしめくれ。
――勝手な霊魂どもである。彼の隣から離れたことのない姉ですら、そうされれば悍ましくてたまらないというのに。
誰もニルズヘッグの心中すら察さずに次々と集まるものだが、動物の霊たちは異なった。
「なるべく詳しく伝えろ。見せるでも聞かせるでも体験させるでも構わん」
ニルズヘッグの声が響けば、うぞりと動物たちの霊魂がうごめく。
それぞれの言葉はたどたどしい。しかし、ウィータと同じ結論にたどり着く。「あれは仲間じゃない」と。
――ひとでもないし、動物でもないとくれば。
「それは、怪物だと?」
獣の言葉はわからない。
だけれど、円の瞳にはホロスコープよりも確かな能力があった。
指を組み合わせて、中を覗き込むように器用にひっくり返す。狐の窓と呼ばれる組みかたをして、じいっと指の間に出来た穴を覗き込んだ。
――獣の心がわかる。
食べられると思って逃げまわした彼らは、自分の体をかじるだけだった獣の姿を不思議に思っていた。
動物は、食べないのにわざわざ獲物を襲わない。そうすることに悦楽を感じていないからだ。
腹が減れば食べ、そうでなければ襲わないのが自然の在り方であるというのに、――「怪物」はその掟すら平気で踏み荒らしていった。
「いやあ、それは不思議でしょうねえ」
そして、山である。
さらさらとどこからか川の流れる音がした。かたたんかたたん、電車の走る足音すら混ざる。
自然と文明の間にあるこの山ですら、かの怪物はひとり、――のけものだ。
食べるために人を襲ったのではなく、ただかじり、それに何かしらの意味を感じて行っていた。
ロクは、心底不思議である。
そも、ひとから獣になったとしても、この行いは「しなくていいこと」のはずだ。
獣らの中にすら秩序があるのに、それができないというのは森ですら受け止めきれないだろう。
東――太陽が昇る方角から、イタチの死体にそっと触れた。【森臥】は、イタチの瞳を霊魂とともに開かせる。
「借りるよ」
あとでちゃんと、土に還すから。
ロクの瞳は、イタチの見たものと同化した。ロクが動き出すころには、ニルズヘッグも、円も、ウィータもユランも歩き出している。
それぞれの足が同じ方向に歩んでいたことが、すべての結論であった。
「――ひとは、どんなときけものになるんだ?」
ざりざり、がりがり。喉をうならせ、木々をどかせるロクの問いに、ニルズヘッグが考える。
「そうさなァ、それぞれ度合いはあるだろうが」
「決まってるじゃないですか。寝てるときですよん」
――寝てるとき?
ウィータの思念が響いて、「そーです」と円が返す。
「どんなどーぶつもそうでしょぉ。動物園でねんねころりしてるライオンと、呑んだくれて寝てるオジサマってよく似てません?」
四人の足が止まる。
洞穴があった。人間が人為的に作ったものではない。自然が作り出した地面のくぼみと言っていい。
つついて蛇が出るか鬼が出るか。一行が様子見に覗き込むのを、「僕がいくよ!まっかせて」とユランがするりと入っていった。
「大丈夫なのか?」ニルズヘッグが心配するのも無理はない。
内部からは――とんでもなく、むせかえるほどの獣のにおいと、呪詛の気配がする。
飼い主であろうウィータを見てみるが無表情だ。代わりに、思念の彼女といえば――すみません、すみません、と腰が低く焦っているようである。
間もなく戻ってきたユランがくわえてきたのは、とらばさみのような例の骨であった。
「わ、おしゃれなマスクですねぇ。うーん、一周回ってここまでくるとイカしてます」
それを拾い上げることない円は、指紋がつかないように意識しているようである。ならば私がと呪詛に耐性のあるニルズヘッグが手にした。
「人の骨――? いいや、話に聞いていた通りこいつは少し複雑だな」
「証拠になるのか」
「そこまではわからんが、持ち帰ってみてもいいやもしれん。ここの居場所も皆に共有しておこう!」
さァ、振り向くんじゃないぞとニルズヘッグが三人を隠すように翼を広げた。
ロクが瞳孔を丸くして、こくりと頷き帰路を拓いていく。
「んふふ、気になっちゃいますねぇ」
――本当に恐ろしいのは理性を奪う化け物か、それとも理性を捨てた人間か。
ニルズヘッグには見えていた。無数の「歯」があの洞窟の中には埋まっている。霊魂たちが集まっていて、膨大な数が嘆いていた。
儀式の場にもあそこを使う気なのだろう。ならば、あの歯はすべて供物なのだろうか。
それとも、――願望のあらわれか。
「ふはは、全く、分かりゃせんなァ」
楽し気な円の声に、少し疲れの混じる声で返すころには。
中を見たユランがウィータにおもしろおかしく怪談話をするように語るのを、少女の思念が悲鳴をあげたところで探索は終わる――。
成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴
 六条寺・瑠璃緒
六条寺・瑠璃緒
◎
獣。理性のない彼らが唯食う為に殺めるのなら罪はないけれど、邪神の意図が絡むなら話は別だね
儀式なのか只の食事なのか
儀式の線を追うなら、犬猫が犠牲になった位置も含めて地図上で何か規則性はないかな
時間の発生時刻から、獣は夜行性なのか昼行性なのかくらいは判るだろうか
幾つか現場も見ておきたい
上村さん、案内してくれる?
君の前では堂々とオカルト捜査をして良いらしいから
現地で降霊を試みる
君が見たのはどんな獣?
獣は君に何か言った?
伝えたいことは何かある?
被害者に手短に質問を
どうか安らかにと催眠術混じりの慰めの言葉を掛けて終話…除霊は専門外なので
ところで上村さん、今の被害者って、美味しかったと思う?
 桜雨・カイ
桜雨・カイ
上村さんと現場へ調査。よろしくお願いしますね。
犯人の目的は何なんでしょう
遺体は現場に残っているんですよね?たとえば現場から消えた物はありますか?持ち物とか…その、身体の一部とか
(儀式の可能性を考える)
人を守りたいですか……ですよね。
私は人形ですから。人に大切にしてもらえた人形なので
だから人を守りたいと思うんです。
上村さんが色々調べているなら、それ以外の所を調べますね
現場周辺にある「物」に対して【物がたり】発動
犯人に関する情報を聞き込み。
(どういった外見か?何か言っていなかったか?など)
次の調査に行く前に…はいどうぞ(缶コーヒー差し入れ)
お仕事に頑張る人が飲むものとテレビ(CM)で見ました
 ディフ・クライン
ディフ・クライン
【WIZ】
まずは事件の詳細を聞かないとかな
上村さんに聞けるのなら、静かにゆっくりとした口調で緊張を落ち着かせつつ
【Palette】の飴を一つあげたら気を許すかな
詳細と歯型のこと
それから合わない辻褄のことを詳細に
彼女という人物の観察も忘れずに
心なき人形だからこそ何か見えることもあるだろう
気づいたことがあれば【Neige】の雪精の力で仲間に情報を伝えてもらう
この時期ならば雪がちらついてもおかしくない
この身を守ることも忘れぬよう
それにしても獣、か
動物は大体好きだけれど
この身に獣性などあるのだろうか
エラーで生まれた偽りの人格
感情なき器だけの心を満たすのは知識と経験と、僅かばかりの実感
…あるわけないね
 グウェンドリン・グレンジャー
グウェンドリン・グレンジャー
つけもの
違った、のけもの
私、鳥が好き。今、UDCアースの、都会だと、ハヤブサが、住んでるよね
(目を閉じて、どこに行こうか、誰に聞こうか考える)
なるほど、第六感に、ピンときた
動物による、人間の不審死。でも、動物も、犠牲、なってる
例えばだけど、けものが、地を駆けるモノ、なのであれば、空を飛ぶモノ、なら、逃げたり、目撃できた、かもしれない
もしくは、死んだ人間や、動物を啄んで、違和感、覚えたとか
くわ、くわ、くわわ
(ビルの屋上。パウチのキャットフードを報酬にカラスたちを呼び寄せ、動物と話す能力と読心術で聞き込み開始)
へんな、したい。へんな、どうぶつ。みたことある?あったことある?
アドリブ歓迎
●
六条寺・瑠璃緒(常夜に沈む・f22979)といえば、空に群がるカラスを見ていた。
どんどんと雪雲が立ち込める中、彼が訪れたのは数々の被害者が事件の災禍に見舞われた場ばかりだ。
思い出したくもない痛ましい現場だったから、掃除してくれと頼んだ遺族もいて――最初の事件の被害者こそ、獣の欲求や目的と一番近そうであるのに消されてしまっていたのは難であったが。
とはいえ、神たる瑠璃緒はそれに焦る様子もない。むしろ、理不尽に切り付けられた心の傷を開いてしまったようで申し訳ないと恭しく美少年の顔で詫びた。
瑠璃緒は、神である。しかし、人のすがた形をしている。
「――君の前では堂々とオカルト捜査をしていいらしいから、彼女もああしているのだけど」
「……鴉と会話が出来るんですか、彼女」
「どうだろう。君はできると思う?」
波風を無理に立たせる必要がないからこそ、「下がるときは下がって」物を見るのだ。
神は人の信仰なしに神として認められない。しかし、人は神からしか生まれない。二つの関係は複雑ではあるが、いつだって神は御赦しになる。
どころか、――こと瑠璃緒に関しては、人の子の逆上程度、愛らしいぐずりのようでもあった。
上村由美子としても、この少年の姿をした彼が「神だ」と自己紹介したときは妄想症を疑った。
二人で被害者宅が見える公園のベンチに座り、あたたかなコーヒーを手にして暖をとっている。
「神様もコーヒーを飲むんですか?」
「そうだよ。君たちが飲めるものは、僕たちも飲めるから」
人はみな、神の子であるゆえに。
――胡散臭い宗教の本よりもずっと説得力を感じさせるのは、彼が猟兵である事実も相まってだろう。
ほかほかと白い煙をまとうコーヒーを手にして、瑠璃緒は散る雪を頭にのせながら微笑んでいた。
「くわ、くわ」
つけもの、ああ――違った。のけもの。
グウェンドリン・グレンジャー(Heavenly Daydreamer・f00712)は鳥に聡い。
「くわわ」
彼女に植え付けられた愛情の結果がその能力を与えたのだろう。
ビルの屋上は、見下ろせば上村由美子と瑠璃緒が見える。黒い頭が二つ見えれば、グウェンドリンに至ってはそれでよかった。
動物と会話するのにこれほど手間がかからないのに、どうしてか――人間と会話をしようと思えばいささか齟齬が出やすい。
グウェンドリン自体はそれを気にしたことはないが、周りが彼女のフォローに回るのが常だ。ならば、此度は最初から周りに人を置いておけばいいと判断して空に啼いている。
集まるのは鴉たちだ。都会であろうが、田舎であろうがどこにでも存在する彼らである。
やはり巣は山の近いこの辺りが作りやすいようだから生息数は多い。
「くわー」
――カァ、カァ、ア、ガァ。
奇妙な光景に、上村は空を見上げるばかりだった。黒い渦巻きが自分たちを中心に作られているような心地がする。
「ああやって、皆の意を聞いているんだよ」
すごいよね、なんて。まるで美しいショーを見ている心地で瑠璃緒が言うのだ。
グウェンドリンは、かわるがわる鴉たちと鳴き声を交わしている。コミュニケーションをとってから、パウチのキャットフートをひとかけふたかけ、順番に与えながら情報を集めていた。
――へんなしたい。あじのおかしいしたい。
――いっぱいあった。
――どうぶつはみんなこわがってる。
――かいぶつだ。
――あいつはなかまじゃない。
――へんなやつだ。
鴉たちは、物覚えが良い。
鴉に悪戯を仕掛けた子供の声を覚えて復讐するほど、実のところ利口な彼らである。
害獣扱いを受けるのは、その頭脳が人間の裏をかくのにも適しているからだ。生き延びるためならば順応し、逞しく生きる黒の一族はグウェンドリンに協力的である。
「やっぱり、みんな、おなじね」
鴉たちのビー玉のような瞳を覗き込んでやって、彼らのくちばしでは届かない頭のあたりを指先でこするように撫でてやる。
グウェンドリンが鴉たちから共有した情報は、有力なカードがひとつ。「ねえ」鴉たちに告げる。
「あの刑事、の、家――って、本当に、ひとつ? あの人の、においがする、場所、ほかに、ない?」
缶コーヒーを人数分用意したはずなのに、公園の端にある自販機から戻ったころには、グウェンドリンの姿がなかったものだから。
桜雨・カイ(人形を操る人形・f05712)は、「おや」と柔和な表情を作る彼らしい驚きの声を上げたのである。
瑠璃緒が手にしている缶も、上村のそれも、彼が手渡したものだ。
「犯人の目的は何なんでしょう。――遺体は現場に残っていたんですよね?」
仕事に頑張る人が飲むものだと、いつかテレビで見たものだから。
ふっと過ぎったそれは、彼の確かなやさしさである。事実、上村由美子の顔色は化粧でごまかしていてもいささか白い。
「すみません、お疲れなのに」
気分の悪い話をしてしまって、なんて。素直に詫びるカイには「いえ、そんな」と上村も心底申し訳なさそうに返す。
「――指が震えている。血糖値が下がってるのかも」
朗かな空気の中に溶けていたのは、ディフ・クライン(灰色の雪・f05200)だ。
表情が動くことのない、完璧な美の権化である人形はじいっと彼女を見ている。些細な変動にも敏感に対応できるよう、集中していた甲斐あって――飴をひとつ、ころりと手袋の上に転がした。
「甘いものを食べたほうがいい。安心して、コーヒーに合うようにミルクにしたから」
「すみません、気を遣わせてしまって」
そういうわけでは、ないのだけど。
気を許せるかどうかだ。ディフが得ようとしているのは、事件解決に足る一手である。
皆が共通して――この上村由美子が犯人であるというのはほぼ共通理解にまで至っていた。
しかし、問題点が一つ。はらはらと散る雪にまとわせた精霊の力で得ているのは、彼女が「精神疾患」を抱えていることである。
これは、ディフにとっては由々しきことであった。人形の彼には、心というものが無い。――無いのだ。
隣に座る人形のカイには表情があり、善意があり、思いやる気持ちがあるというのに、対照的にディフには「ない」。
なぜならば、ディフはエラーで生まれた偽りの人格である。
器はある。心という器に、知識と経験と、わずかばかりの実感を詰め込んでいるだけで、それはほぼがらんどうに感じられるのだ。
心らしい心など、――あるわけながない。だから、理解するのが難しかった。
一体何がこの女を化け物にしてしまうのか。どうして、この女がのけものになってしまうのか。心を持たぬ人形は、心の病を持った人間の痛みが遠い。
「上村さんは、遺体を見たことがある?」
ジェフの問いに、上村はためらいなくうなずいた。
「最初の発見者は、私です」
上村由美子がこの事件と出会ったのは、第一の事件からであった。
もとより真面目な彼女である。老夫婦の夫のほうが大けがをしたときなどは、妻の足腰を案じてたびたび様子を見に来ることもあった。
小さな町ですから、お互い支えあっていかないとね――と健全に笑う彼女にほとんど皆が心を許していたのだという。
その日も、なぜか夜中に目が覚めた。汗をぐっしょりとかいていて、秋の三寒四温に苦しめられたのだと思って夜風に涼んでいたところである。
どうにも胸騒ぎがして、近所を徘徊していた。すると、叫び声が聞こえてかけつけると――血まみれになった犬と、それに膝をついてすがる妻と、茫然と立ち尽くす懐中電灯を握った夫が立っていたのだ。
誰がこんなひどいことを、と衝撃を受けた上村は、それから相次ぐ怪事件に頭を悩まされることになる。
「そこからどうにも胸騒ぎがして。あまりに早く出勤するものだから、西警部が見るに見かねて」
申し訳ないことをしちゃったな、と言いながら缶コーヒーに息を吹きかけた。
「目的はわかりません。でも、私が思うに……あの獣は、何かしら愛されているものに執着してるように思えて」
「へえ、どうして」
顔を覗き込むように、長いまつげを震わせた瑠璃緒が興味深そうに尋ねる。
息を詰まらせて、口に含んだ珈琲をごきゅりと飲み込んだ上村も顔が悪い部類ではないのだが――絶世の美少年相手に間近で見つめられるとこっぱずかしいものがあった。
「ええ、と。なんというか。これも、主観かもしれませんが」
人の被害が出初めて、赤子が殺される事態があった。
「――赤ん坊相手に、なんてことをと思うくらいに、こう」
悍ましい。
語るのも気分が悪いが、逸らしてはいけない現実をスチール缶にぶつける。しっかりと握りこんで、息を吐いた。
「……噛みつくどころか、引き裂くような」
散らばる臓腑を思い出していた。
やわらかい乳幼児の未発達な皮を割いて、内臓をぶちまけている。
この行為に何の意味があるのかは、カイが顔をこわばらせるのも無理はないくらいに、上村由美子とて不可解であった。
血まみれの赤子が獣の毛玉と、自分のうつくしい血にまみれて死んでいた。
まるで、呪うように。
まるで、暴いたように。
まるで、否定するように。
まるで、――八つ当たりのように。
「――酷い」
カイが声を震わせても、ディフは淡々と上村を見つめているだけである。
嘘をついているようには思えない。悲壮な顔も、おそらく現場を見たその表情も、まったくもって「本心から」だろう。
「事件現場にたどり着いたのは、いつ?」瑠璃緒がそうっと問うてやる。まるで、赤子を起こすかのような声だった。
「――朝です。通報が朝だったので」
「じゃあ、獣は夜行性なんだね」
瑠璃緒が暴いて見せたのは、その習性だ。
「夜行性の生き物だと仮定しよう。昼間はどこにいるんだろう? 理性のない彼らが唯食う為に殺めるのなら罪はないけれど、邪神の意図が絡むなら話は別だからね」
夜に一人で歩き回って、寂しくないだろうか。
瑠璃緒の慈悲深い言い方にも、上村の理解は追い付いていない。「――可哀想だなんて、遠い話では?」
「そうかな」
ひとの子の疑問に解を見出すのが彼である。
「どんな罪人にも苦はあると思うよ。痛みを知らないのに誰かを痛めつけたいなんて思わないだろうから」
――幼少期に。
統計的に、虐待や性被害、親の不健康により崩壊した家庭を持つ少年少女というのは大抵犯罪のリスクが高くなる。
彼らには善悪の基準があいまいなのだ。叱られなくてもいいことで殴られ、責められなくてはならないことで放っておかれる。
力をつけ始めた思春期ごろに、恐れていた親の力を上回るようになってしまって大体歯止めが利かなくなっていくのだ。
近年、犯罪の低年齢化の背景にあるのはこういったループから縁が切れていないところも大きく響いている。
親に管理された自由を与えらえる子供は依存的になり、己の判断で善悪を推しはかることが難しくなっていく――瑠璃緒からすれば、それがひとの選んだ道ならばよいとしていたが。
その「芽」で邪神が「花開く」のは見過ごせまい。
「根を断つのは簡単だけれど、向き合うべき問題は次に同じ花を咲かせないことだからね」
――瑠璃緒の周りには、堂々と霊たちが揺蕩っている。
【舞台下に与ふ慈悲】であるが、上村にはぼんやりとしか見えていないらしい。カイとディフにはくっきりと見えているが、彼らも特に口をはさんでこないところを見るに、意味のあることだとは伝わっているようである。
獣は、被害者に何も言わなかった。ただ唸り、噛みつき、窒息まで追いつめて、噛みつき、痕を残して消えていく。
伝えたいことは「どうしてあなたが」とたったそれだけのフレーズだ。
「現場から消えた物はありますか?持ち物とか…その、身体の一部とか」
「ええ、と」すっかり瑠璃緒の話に引き込まれた上村が、頭の中の資料を呼び起こす。
「歯、でしょうか」
被害者たちからは、歯の一部が盗られていた。
凶悪犯罪者が己のトロフィーにするために被害者の一部を持ち帰るのはよくあることであり、邪神の儀式にも使うこともある。
よこしまな術というのは、いつだって意味のないものに意味を感じれば始まるものだからだ。
「ひどい時は顎の単位で持ち帰っていることがありました。このあたりの行方不明者とか、――山中の自殺者まではさすがにさかのぼっていませんが」
「あの山、死ぬ人がいるのかい?」
ディフが聞き逃さない。
「ええ、――まあ、めったに人も入りませんから。いるとは思いますが、わざわざ探したがる人もいません」
警察という立場も、事件が起きてからではないと動けない。
ひっそりと山の中で死ぬ人はもとより多いという。自殺スポット、というわけでもないが落ち葉の下で眠る人間は多そうだと思われた。
なにせ町のほとんどが昼は仕事に出て夜は寝に帰るだけの街である。そもそも山にすら目を向けている暇もないのだ。
「守ってあげたい、のですが。こればかりは」
「わかります。届かないところに対する、むずがゆさというか」
カイが寄り添うようにうなずく。
人に大切にされた人形であるカイは、人の心にジェフとは違う意味で過敏だ。
心より上村が嘘をついていないのも察しているが、――【物がたり】はどうにも、彼女の言い分とは異なる。
公園のベンチは見ていた。
遊具は、鉄棒は、ごみ箱は、水飲み場は見ていたという。
血まみれのけだものは、どんどん毛皮を脱いで行って、女の姿に変わっていったのだ。
うめき声とも鳴き声ともつかぬおどろどろしい声色を上げながら、上村由美子は夜のうちに獣になる。
――うつろな瞳と、血まみれの仮面を口から外して、喘鳴をさせながら家に帰っていくのだ。
涙を流して、家なき子のように階段にすがるのを公園が見ている――のに。
「届かないことは、悲しいですよね」
どうして、――「彼女」はこれほどまでに、真面目なひとなのだろうか。
カイが悲しみを浮かべながら上村に返事を終えたころに、ディフがゆっくりと立ち上がった。
「終わったかな」
「そのようだよ。グウェンドリンさんがある程度情報を集めてくれたみたい」
瑠璃緒がいつの間にやら止んだらしい合唱に気づいて、ディフはグウェンドリンが降りてくるのを待っている。
「ねえ、上村さん」
「はい」
瑠璃緒が――振り向いた。
「今の被害者って、美味しかったと思う?」
「……人間を食べたことがないので、なんとも」
●
「上村、由美子、の、家。ふたつある、みたい」
「一つは今の居住区であるアパートだね」
グウェンドリンは、一羽の鴉を右肩にのせていた。この彼が皆を案内するらしく、どうやらその地域のごみ箱を仕切る力のある鴉のようである。
「そもそも、上村、由美子の家は、旧家、なんだって」
鴉が言うには、人間たちの間でも「あの上村」と言われるほどには悪い意味で悪名が連なる家であったらしい。
新興宗教、選挙活動、それから高利貸しを生業とし、親戚同士の銀行を通さない現金でのマネーロンダリングもあれば、とにかく金に意地汚いものが多いと有名だった。
それも戦後からバブルの崩壊までの出来事ではあるが、何せこの一族はきょうだいが多く、前当主――すなわち、上村由美子の父親はその座を奪い取るために、それは手ひどいことをした男だったという。
「皮肉」
グウェンドリンが、そう付け加えた。
小悪党が成り上がった一族は、いよいよ人口の少なくなった町の中で嫁を娶るのをやめて町の外から仕入れてきた。
それが上村由美子の母親であり、俗にいう「カタギ」に当てはまる人物である。
従来の気が強いのもあって、親戚同士のもめごとにも時に立ち向かい、かわし、どうにか一人娘の由美子だけは立派に育てようと思っていたが――彼女とて二十四歳で赤子を生んだばかりだ。
どんどん奪われる自由と、尊厳、権利に病んでしまった時があったのだ。
「悪い、親から、良い子が、生まれて」
――まるで、黒い白鳥の逆だ。
真っ黒な白鳥しか住まない世界に、本当に白い白鳥が生まれてしまったのである。
空は、ハヤブサが飛んでいる。人間たちのややこしい人間模様すら空から見れば小さなものであるというのに、放っておけばここまで腐ってしまうのだ。
たった一人の人間を――怪物にする程度には。
「ひとり、ぼっち。のけもの、ね」
四人がたどり着いたのは、上村由美子の実家――今はその親戚が住まう、大豪邸である。
「これは、これは。欲深そうだ」
楽し気に笑った瑠璃緒の感想が、その家を表すすべてであった。
成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴
 ティオレンシア・シーディア
ティオレンシア・シーディア
◎
はぁい刑事さん、ご協力ありがとぉ。よろしくねぇ?
…まあ、こういうイチからの調査ってあたし正直得意じゃないんだけれど。
さぁてと、どこから手をつけたものかしらねぇ?
えー、と。遺体の状況にも被害者個人にも共通点はナシ、と。んー…となると「場所」かしらぁ?
何処かを中心に放射状に広がる、何か図形を描く、一定距離を開けて現場が繋がる…
資料と首っ引きでとにかく思いついたことを検証してみましょうか。
地味でもなんでも「違うことがわかる」だけでも前進でしょぉ?「100-99(ハズレ)=1(アタリ)」ってね。
頼りにしてるわよぉ、マクドナルド警部?
…まあ、彼女が「アタリ」の可能性も当然考慮しなきゃいけないんだけど。
 リーオ・ヘクスマキナ
リーオ・ヘクスマキナ
◎
うーん、感染型とは別種なら……「汚染型」?
カテゴライズしなきゃいけない程に多発して欲しくはないけどなぁ
……さて。まずは"巣"を割り出したいけども
「事件発生場所で最も離れた二箇所を直線で結び、それを直径とした円の中心付近に犯人の拠点があると考える」って捜査方法があるけど……(円/重心仮説)
コレ、確か人間の心理から考案された方法なんだよねぇ。"獣"になってても、この心理って適用できるのかどうか……
それに、本職の警官さん達が念の為にやってないとも思えない
……けど、猟兵としての視点で見れば、何かしら見えるものもあるかもだし
余計な可能性を潰しておく、って意味ではそう無駄にはならないかな?
 鳴宮・匡
鳴宮・匡
犯人を捕捉するなら、必ず足を運ぶところを探せばいい
要は、“次の事件現場”だな
グリモアベースで見た事件現場の赤い光点と、警察署にあるだろう捜査資料
照らし合わせて、事件現場全ての正確な位置と時間、状況を把握
資料をどこから貰うって?
弟分が中にいる、融通してもらえるだろ
一人で歩き回ってちゃ時間が足りない
【無貌の輩】達も現場に足を運ばせて、状況を検分させる
推理より経験則を使うほうが得意なんだろうな
誰が、何故、がわからなくても
辿った軌跡から“ここでこうするだろう”を導くことはできる
……でも、今は
わからないはずの“何故”を切り捨てずに
考える余分も、できた気がするんだ
それがいいことなのかは、わからないけど
●
「はぁい、刑事さん。お疲れだったりしない?」
ティオレンシア・シーディア(イエロー・パロット・f04145)はまず、上村巡査の足を止めさせる。
彼女の進行方向に自然によれば、声をかけられた上村は素直なほどにぴたりと動きをやめ、ティオレンシアをやや目を細めながら見つめて「いえ、まだいけます」と返事を返した。
――疲れてはいるらしい。
無理もあるまい。この「ハリキリ刑事」こと上村は、それこそ快活ではないがゆえに静かに動き回るところがあるのだ。
まるで警察犬のような女に見えて、ティオレンシアも思わず苦笑いする。
――ほぼ容疑者で間違いないのに。
「私が、疑われているようで」
「あら、バレちゃってるのねぇ」
だからこそ、引き留めたというのもある。
「あたしもね、刑事さん。そりゃこの猟兵の活動も結構やってきてるけどぉ――とてもじゃないけど、あなた、人とか動物を喜んで殺すタイプには見えないのよぉ」
あたりを引いたはずなのに、どこかつかみどころが悪いように感じられる。
ティオレンシアが危惧したのは、第一に『彼女が本当に無実だった場合』だ。
「だから、あたしたちが考えてるのはねぇ、刑事さん。『100-99(ハズレ)=1(アタリ)』の可能性よぉ」
たとえば。
確かに、上村巡査が人を殺していたと仮定する。
とすれば、何かしら理由があるはずだ。いかにも規範的で、組織に忠実かつ、他利的な彼女にまさか凶悪な芽があるようには思えない。
人殺しに慣れているよりも、凶悪殺人者相手に物怖じしないことになれている顔つきであるのは、会議室に集まった『人を殺すのに長けた』三人から見ても明らかであった。
さて、ならば――その動機は、彼女ではなくて、彼女の血筋が背負った業や、この地域にまつわる風習から成り立つかもしれないのだ。
「うーん……多発してほしくないけど、俺だったら名付けるとしたら『汚染型』かな」
「型が増えようが、こっちのやることは変わらないけどな」
リーオ・ヘクスマキナ(魅入られた約束履行者・f04190)が几帳面にコンパスで地図に円形を書いていくのを、鳴宮・匡(凪の海・f01612)は眺めていた。
匡には、ほとんどカメラアイと言って差し支えのない超常の記憶力がある。極限状態で生きてきた彼の「生きるすべ」は奇しくも今、事件解決のために振るわれている。
「ベースで見た個所と、あと――俺の弟分からもらった資料の通りに赤でポイントは済んだけど。問題なさそう?」
「うん、今のところは順調! いやぁ、本職の警察さんたちには劣るかもしれないけどやれることはやらないとね」
「あらぁ、大丈夫よぉ。ここにも『マクドナルド警部』を連れてきたしぃ」
事件発生場所で最も離れた二箇所を直線で結び、それを直径とした円の中心付近に犯人の拠点があると考える。
犯罪心理学で用いられる理知的なプロファイリング方法であった。「間違えてないかな?」とリーオが困り眉で聞けば、完璧です、と上村は返す。
「私もやってみたのですが、心理学はとらなかったので……」
匡も彼女の姿を見ればそれはわかる。
姿勢がよい。若さもあるが体は引き締まっていて、毛の艶もよい。健康状態は疲労以外に問題なさそうで、かつ、爪の状態もすこぶる良いといえる。
歩幅は広く、足はよく上がり、体の動かし方は軽やかだ。デスクにかじりついているよりも、体を動かすほうが得意なのは明らかである。
逆三角形の引き締まったからだと、広い肩幅から考えるに恐らく柔術や合気道が得意と思われた。
――格闘を知らない男程度ならば、制圧できそうである。
「うん、やっぱり結構偏りがあるね」
リーオのとるやり方は、匡にも理解しやすい。ティオレンシアも細い目を少し開いて、まじまじと地図を覗き込んだ。
さて、もっとも離れた犯行地点が犯人の行動範囲――つまり、「なわばり」の終点であり、二か所をつなぎ合わせて線を作る。そこから、真ん中の点を割り出してコンパスでぐるりと円を描けば大まかな行動範囲がわかる。
上村は、「あ」と声を漏らす。「何かあった?」聞き逃さない。声に揺れを感じた匡が、すかさず上村に介入した。
「私の、――実家が中心になる」
「気づいちゃったかぁ」
リーオが半ば、そうあってほしくなかったと願望を乗せたため息を漏らす。
二度、ペンのキャップで中心をたたいた。「コールサック効果っていうのがあるんだ。犯人が自宅付近で犯行に及ばない、っていうのがあるんだけど――残念ながら今回はあてはまらない。なぜかわかるかな」
上村は、いまだ地図の客観的な照明を眺めながら茫然としている。口元を抑えて、指先が震えていた。
恐怖している。匡は、眉を潜めた。――人も獣も殺しておいて恐怖を覚えるなんて、まるで人間らしい反応だったからだ。
「この犯人はね、かなり無計画なんだよ。『無秩序型』と呼んでもいいと思う」
リーオは、この一連の犯人をまず、『人間』の行動パターンで分析を始めた。そこでわかった可能性は「この犯人に高度な知能がないこと」である。
「証拠は残すし、自分のDNAを置いていく。死体を隠すこともしないし、フェチズムも感じさせない死体の損壊。顎を奪うことには確かに目的があると思うんだけど、やり方が乱暴なんだ。引っこ抜いたみたいで、こだわりは感じない」
――リーオの隣でふわりと浮き上がる【赤■の魔■の加護・「化身のイチ:赤頭巾」】は、うるうると唸りながら上村を見ていた。
『赤ずきんさん』が警戒する限りは、彼女もまた、リーオの予感通りのことを察しているのである。
「ねえ、上村さん。あまり、こういうことを聞くとよくないかもしれないけど」
ペンは、ゆっくりと地図の上を転がっていった。
「上村さんは、『解離性同一性障害』じゃないかな」
【絞殺】と【無貌の輩】を用いて、ティオレンシアと匡が集めた情報は、ほんの数十分前にさかのぼる。
リーオとともに匡本体が漏れなくていねいにマッピングをする中で、彼は「彼だけが歩き回るには時間がない」と判断した。
獣は夜行性だ。夜になり、――上村巡査が眠りにつくと目覚める。
「頼んだぞ。しっかり働いてくれると思うから、あとはよろしく」
「任せてちょうだぁい。さ、行きましょうかぁ。おちびさんたち?」
ティオレンシアが現場に歩く影に、わらわらと小さな匡たちが群がっては溶けていったのだ。
そうすれば移動のリスクは格段に減り、ティオレンシアの移動速度とともに無貌の小さな兵士たちは活躍の場を広くする。彼らは、くまなく怪物のなわばりを歩いた。
「あらぁ、そうだったの。あそこのおうち、上村さんのお世話になってたのねぇ」
――被害者たちの共通点は、性別、年齢、出自に絡み合うところはなかった。
しかし、たった一か所がそれぞれ綺麗にかぶった点がある。
「この前ねえ、お花を持ってきてくれて」
「仏壇に手を合わせてくれてねぇ」
「犬のこともかわいがってくれてたんだけど」
「うちの子が生まれたときも」
――全員、被害者は上村由美子に接触したことがある。
根拠としては十分だった。つまり、彼女の中に住まう怪物は彼女の「目」を借りて、獲物を選んでいたのである。
それは何かしらの琴線に触れたのであろう。愛らしい子供の姿が、幸せいっぱいの家族が、寂しそうな老人の顔が、怪物の目を覚まさせてしまった。
「なるほどねぇ。これ、考察通りなら本当に災難な話だわぁ」
いっそ、振り切った悪人の所業ならば煮え切らぬ思いをしなくてすんだやもしれない。
ティオレンシアが坂道を登り切って、ため息をついた。ガードレールにもたれかかりながら、やけに澄んだ冷たい空気で肺を満たして雪空に白い吐息をうやむやにされていく。
邪神は、きっとそこにうまく「沁みて」しまった。
元より狂気に汚染されやすい彼らというのは、病んでいるか欠けているかのどちらかといっていい。
心の傷は深かったと思われる。無貌の兵士たちがえっさほいさと資料を集め、現場の呪詛の痕跡をたどり、時にわーわーとネコに追われたりしながら得たのは――洞窟の奥の話だ。
上村家の持つ山には、古い社があったという。
もはや今、その社には何も宿っていないだろう。上村家が金に溺れて力に酔いしれるころから、すっかり手入れをされることはなくなった。
ただ、――新興宗教で金を稼いでいた彼らは事もあろうにその神域を持ちながら「かみさま」をでっちあげるビジネスをしだしたのだ。
上村由美子の父を教祖とし、彼を政界進出させる話が持ち上がり、町一つを囲む選挙活動などもあったという。
あなたも成り上がれますよ、救われますよといってあの時どれだけの人が夢見たことだろうか。思い出話のように語る古くからの住民たちは、どこか小ばかにした語調でもあった。
お決まりに、「あの家からあんないい子が生まれるなんて」と付け加えていたのがまた印象深い。
己らの利のために、彼らが踏みにじったものが祟ったのかもしれない。彼ら自身にではなく、末裔の由美子にたまたま呪いが纏ったのかもしれない――。
「虐待の経験があるって?」
匡は、単刀直入に尋ねた。
リーオが踏み込むかどうか悩んだ事を、彼は「わからない」からこそ尋ねる。
踏み込んではいけない領域だ。しかし、「それを聞くには理由がある」。彼女の中にもう一人の怪物を作ってしまった理由は、果たして呪いだけの話だろうか?
一体何がたった一人の善良な女を怪物にしてしまったのか。その根源を辿らない限り、この連鎖は終わらないように思えてしょうがない。
これを、刑事ドラマならば「デカの勘」といったのかもしれないが、匡のそれはほぼ危機察知能力だ。
上村は応えない。
かち、かち、と奥歯の震える音が響いていた。幸い外からは窓もカーテンをかけられていて、彼女の異変は悟られない。
「無理には言わなくていいわぁ、でも、そうね――できれば教えてほしいけどぉ」
ティオレンシアが考えるのは、「ああやはり」という直感の正体についてだった。
上村由美子が殺していたのではない。彼女の中にいる『怪物』が殺して回っていたのだ。
あまり刺激を加えたくはないから、どうしたものかと悩んでいる。腕を組んで、何がスイッチになるかわからないうちに――出入り口の扉を塞ぐように背からもたれた。
「ある、と思います。ですが、あまり覚えていなくて」
「どこか遠いことみたいな……カーテンの向こう側みたいな。そんな感じがする?」
「はい、ええ、――夢だと、思っています。今も」
刺激しすぎてはいけない。
匡が上村の目線が床を向いたのをきっかけに、質問を一度止める。
「座ろう」リーオが促した。上村は、体をこわばらせている。カタレプシーだった。
「大丈夫よぉ」ティオレンシアが腕をほどいて、しゃがみこんで表情を見上げた。
上村は、――涙すら流せず、ただ事の大きさに目を見開いていた。表情も作れず、声に抑揚もない。
自分のことなのに、どこか遠い心地がしているのだろう。匡には、その経験がある。
彼女のように「自分を割る」まではいかずとも、「自分を偽る」経験はあった。自己防衛の方法が違っただけだ。たったそれだけの、同じ人間の痛みの具現に違いなかったのに――。
「私は、人を、たくさん殺したんですか」
――それにどうして、「それをやったのはあんたじゃないよ」と言ってやれないのだろう。
状況証拠は恐ろしいほどそろってしまう。たった一人、上村由美子という人間の罪が立証されていくのだ。
. モウヒトリ
『怪物』は、まだ眠っている――。
成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴
 誘名・櫻宵
誘名・櫻宵
🌸神櫻
◎
ねぇカムイ
ひとはねケダモノなの
無垢でひとが好きな神様に
ひとのそんな所をみせるのは気が引ける
あなたはほんに
かぁいい神様だこと
飛ばす「呪華」の蝶
甘美な秘密を集めておいで
獣の仕業なら足跡や臭いは残っているのかしら
獲物の共通点
やわこい臓腑から喰らうのか
それとも歯応えがある手足?
獣の好みも分かるやも
丸呑みにするような獣ではないよう
噫、美味しかったかな
おいしそう
なんて冗談よ
カムイ
私はケダモノじゃない
食べないわ
神血の禁厭を一雫
舐める
歯型ね…
所有の証のようにもみえる
愛を刻むの
之は私の物だと報せるの
気がついてと叫ぶように
遺すのは
知らせるため?
ほんとうは
見たくないのかも
まっすぐな心ほど
歪みやすいものだわ
 朱赫七・カムイ
朱赫七・カムイ
⛩神櫻
◎
サヨ
ひとはひとだよ
例え心の中に獣を飼っていようとも
その獣に飼い殺されて欲に飲まれたならば…ひと、ではなくなってしまうのかもしれない
己の中の獣などきっと誰も観たくないもの
…私はでも
そんな脆さや醜さをもつ
ひとが好きだよ
カラス、周囲の偵察を
刑事の動きを探ってみよう
唯の勘だよ
偉い子だね
強く守護を願う心
その中に理由があるかもしれない
捜したいのか
見つけたいのか
示したいのか
いい事をしたら褒められる
狩場だというなら襲う場所に癖や法則があるかも探る
サヨ
たべてはいけない
私の血(禁厭)を一雫
…きみの中の何かを抑えるそれを舐める様
私の巫女はこんなにも可愛い
噛まれてもいいのに―噫
これか
噛み跡を遺すという気持ち?
●
「ねぇカムイ」
美しい龍は、まるで世界のすべてを見通したような口ぶりで残酷な事実を語るのだ。
「ひとはね、ケダモノなの」
誘名・櫻宵(爛漫咲櫻・f02768)は、桜色の龍である。
人を食らい、呪いを抱え、愛をむさぼり、識り、――そしてひとになった。
冬空の下でも桃色の輝きは失せることがない。それどころか、季節外れのこの風景にすら溶け込んでいきそうなほど薄い輪郭を隠すこともなかった。
視線の先には、赤い神がいる。
護る為の龍たる櫻宵はまず、己の知っている人間のあさましさから披露した。
あたりは竹林が生い茂り、人の住んでいた名残のある空き家が並ぶ背の低い家屋ばかりである。野良猫が背を丸めて日向ぼっこしている地面は、コンクリートであるというのに十分な地ならしもされていない。
地面に固めるためだけの物質が注がれたぞんざいな道は、山道とさほど差もないような心地がした。
「サヨ」
朱赫七・カムイ(約彩ノ赫・f30062)は、黒から蘇る彼である。
「ひとはひとだよ、例え心の中に獣を飼っていようとも」
美しいかんばせこそ、つい少しの前まで厄に憑かれて獣性をあらわにしていたというのに、今のカムイといえば櫻宵から見れば「ほんにかぁいい神様」である。
カムイは、無垢であり、人が好きだ。
ものを知らぬわけではない。人の愚かさも見かけ、未熟ゆえに正面から長い両腕を広げて受け入れられるだけの器量がある。
しかし、それを――友人としても、櫻宵はどこかほほえましくも、まるで子供が興味で危険なものに触れているのを見るような気分に至るのもまた、事実である。
カムイは、人が好きだ。その脆さも醜さも、彼らだからこそだと知っている。しかし、その体にある獣性が「余計なもの」に煽られた結果暴れて手が付けられないから、今回のような悲劇が起きてしまっているのだ。
「この地は、ひどく呪われているね」
「ええ。あなたに障らないかが心配なくらい」
はらはらと花弁の代わりに雪が散る中、ふたつの神が動かないのは理由がある。
「どこも、人の呪詛でいっぱいだわ」
けがらわしい、とは口にしなかった。櫻宵が、嫋やかに服の袖で鼻から口までを覆う。
欲深いひとの一族が生み出したのは、静かなる地獄であった。
罪を作ることが悪いわけではない。その罪で一体何人を犠牲にし、追い出し、時になかったことにしたのだろうか。
――ひとの世界には、神が関与できぬ秩序というものがあるはずなのに、蓋を開ければこの地には混沌ばかり蔓延っている。
【呪華】の蝶が、神性を失われないよう、神々の代理人として空を飛んでいる。カムイはそれを見上げて、ゆっくりと白い息を吐いた。
「邪神とのかかわりが根深いのかな」
「金に目が眩んだひとが多いとは聞いているけれど、この地に満ちた気配から察するには、そうでしょうね」
哀れね、と櫻宵が侮蔑めいて言葉にしても、カムイは頷かなかった。
「知らなかったのだろうね」
――ああ、どこまでもこの神は、ひとに肯定的だ。
櫻宵は龍であるが、カムイは神である。神は、残酷なまでにその実「すべてを平等に愛する」存在だ。
神の前では赤子の命も尊ければ、死刑に処される罪人の命もまた尊い。赤子に洗礼があるように、死出に聖典が読まれることからもその寛大さがうかがえる。
それが、――仕組みとはわかっているけれど。
カムイの遣いたる鴉たちは、電柱に留まって同意の上に軟禁状態となった上村を監視している。
「偉い子だ」
――強く守護を誓い、ひたむきに生きてきた背中が今はとても小さく見えてしまう。
まだ若い人の子は、カムイが鴉の目を通して視てやっても呪いに満ちていた。
「ひとの事をよく見ている子だわ」櫻宵が、同情なく続ける。「誰も社の中を見てはいけないのと同じよ」
お守りの封を開けてはなりません、社の裏を見てはなりません、立ち入ってはならないところなのです――。
護るものを障って暴いてはならないのだと、当たり前のことなのに。
「あの子はきっと、『立ち入ってしまったことがあった』のよ」
神ならではの、悟りであった。
呪いを背負う龍である櫻宵が感じている通りのことを、カムイも悟っている。
「いなくなった神の領域に、足を踏み入れてしまった」
――そこに、新たな神が巣食っていたともしらないで。
カムイの悲壮な声に、櫻宵は肩を寄せる。あなたのせいじゃないのよと言いたげな声色で、続けた。
「けものは、美味しかったかしら」
ひとの事を考えないように、次は純真な彼の視線を「けだもの」に向ける。
やわこい臓腑から食らうのか、歯ごたえがある手足から噛みついていたのか。いつもいつも、窒息死を願っていたから、きっと首がすきだったのだろうか。
首にはふとい血管があって、圧迫すれば人は血の流れを失うし突き刺せば真っ赤な血が噴水のように噴き出る。
浴びるほど飲んだだろうか。じゅるじゅると啜りながら、ひとにもけものにも戻れない怪物として、その命を確かめただろうか。じぶんは、――孤独の「のけもの」だと自覚しただろうか。
「おいしそう」
「サヨ。いけない」
「冗談よ、カムイ」
――それでも、と差し出された彼の掌から、じんわりと血が一滴にじむ。
己の巫女を律するのもまた、神のつとめである。カムイは、まるで薬のように血を与えた。櫻宵も、大丈夫なのにとはいうけれど――獣性を抑えるように、それを飲む。
こくりと静かに喉の鳴る音がして、噫、これがとカムイは感覚を知った。
「きっとね、愛を刻んでいたのよ」
櫻宵が、赤の染みた唇で語る。
巫女は人の心を神につたえ、神の考えを人に語るのが仕事であるゆえに、カムイにささやくのを許されていた。
「愛を刻むの。之は、私のものだと報せるために。気づいてと、叫ぶように」
――覚えがある。
愛する人の体に噛みついたときの高揚感は忘れらない。ぞくりと背筋に熱が灯るような心地がして、櫻宵のうなじが赤らむ。
「ここにいるのよ、と知らせるために」
噫、嗚呼。
遺したい気持ちは、――こういうことだったのだと、神は知った。
カムイは、あの少女の中に「もうひとり」がいると鴉の耳で聞いている。
名前の与えられない、もう一人の怪物は、確かにあの中にいるのだ。自分の形を人間の体に押し込められたけだものは、確かに女の脳から生まれたのに、存在が認められることがない。
人のこころの病だと聞いた。それでも、なんとむごいことだろうと思った。
――与えられない。認められない。愛されたくとも、親にすら知られないいのちが、のけものの正体である。
「まっすぐな心ほど、歪みやすいものだわ」
そして、きっと半身である上村由美子にすら、その存在は知られていない。
同じ体にいるのに。おなじ手足で歩いているのに。「のけもの」のいのちは、どこにも証明されないのだ。
なんと、むごいことだろう。
「カムイ?」
神は、――哀しんでいた。
「見つけてあげないと」
人の心の弱さに悲哀を感じる彼の、なんと無垢で、うつくしくもやさしすぎることだろう。
櫻宵は、それ以上を言わずに只、「ええ」と肯定した。
「きっと、母を探しているのだろうね」
いつか、――母の亡骸にもそうしたように。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 草守・珂奈芽
草守・珂奈芽
【晴要】
行方探しなら実際に見たら早いんでないかな?
ってわけで事件現場の一つに来てUCさ使うのさ!
事故当時の様子を――う、食べ、られてる?
人が、中が、真っ赤で……きもちわるい……。
でも、目を背けちゃ、ダメ。
「行こ。早く、あんなの止めなきゃ」
腕を引いてもらって歩くけど、過去と今で視界が重なってブレるし、まだ気持ち悪い。
……おぶってくれるの?ちょっと悔しいけどありがと。
ふふ、頼りになる背中なのさ。
背負われて過去の痕跡を追ってきたけど、疲れて見えづらくなってきたのさ。
探偵さんのお手伝いもお願いできる?
気付いた物があれば教えて。わたしももうちょっと見てみるからさ。
……最後まで頼りっぱなしで、ごめんね。
 西塔・晴汰
西塔・晴汰
【晴要】
最初は珂奈芽におまかせ
過去視の間、転ばないように腕を引いて歩く
…大丈夫っすか、かなり顔色悪いっすよ
やばいモン見てるのは分かるっすけど、代われるわけでもないし…
足元も覚束ないし…いやだめっすね、背負ってくっす
珂奈芽が目ならオレは足、ってね
痕跡を追うっすよ!
珂奈芽が視えないとこまで来たらオレの出番っす!
これでも失せ物探し専門の探偵……の見習い、家業の手伝いっすけど
目鼻耳は利く方っすからね
ほんとにけものが居るなら、体毛なりなんなりの痕跡があると思うんっすよ
でなきゃあ異質なモンの匂いをたぐるか、何か追えるといいんっすけど……
オレは過去とか視られないっすからね、こういうのはカバーしあいっすよ!
●
――その屋敷に立ち入ったのは。
ここが、事件現場の中心地であり、おそらく獣の拠点であろうとして、広い庭の一部に二人が忍び入ったのが始まりだった。
「どーどーと正面から行きたかったんすけど、ねぇっ、と! 珂奈芽、どこも怪我してねえっすか」
「うん、大丈夫さ!ありがとね」
西塔・晴汰(白銀の系譜・f18760)も、草守・珂奈芽(小さな要石・f24296)も、礼儀を知らぬ子供たちではない。
まして、二人とも正義感にあふれる性格傾向だ。常に正しい道を最善に選び、ひたむきに行動する。
だから、此度――猟兵たちが突き止めた上村家、その本家といっていい広い屋敷の敷地内に「捜査」で入るためには、ていねいに挨拶をこころがけてインターフォンを押した。
が。
「捜査令状は」
その五文字で、突き返される。
「ったく、自分とこの親戚が人殺しかもしんないのに、なんであんなつっぱねるんすかね……」
「世間体とか、そーいうの気にしてるんじゃないかな。それか、知られたくないことがあるとか、さっ」
二人が正攻法で頼み込んでも、上村家の親戚――今、この土地を持ち広い屋敷を管理する彼らはけして協力的ではなかった。それよりも、警察という組織を毛嫌いしている印象が強い。
晴汰にはいまいち、世間体を気にするメリットが理解できない。
守るべきものは守ればいいとは思うが、自分の身内が他人様に危害を加えたのならば、それは詫びるべきだとすら思えるからだ。
晴汰が粗相をしたら両親が頭を下げるようなことと同じではないのか、と――思いながら。失せ物探しの見習いは、『抜け道』を見つけて広い庭に侵入する。
珂奈芽の腕を引っ張りながら、その衣服を破かないように気を付けてまず、黒い塀を登った。
綺麗に並べられた晴汰が靴を脱いだ足になっているのは、靴の痕を残さないためである。細かい砂利目の敷地内に自分の靴を落としてから、よっこいしょと声を上げて珂奈芽をいったん自分の膝に乗せる。
「しっかり捕まっててくださいっすよ」
「もちろん。わかってるのさ」
晴汰の首に腕を回して、正面からしがみつく。固定された肘を確認して、晴汰は頑丈な体で飛び降りた。
高い塀から落下してももろともしない両足はまさに奇跡の子の体現といえる。ジャッ!と鋭く落下の音は響いたが、周囲にどうやら人はいない。そうっと珂奈芽を下ろし、あたりの様子を気にしながらお互いに足音を潜めて歩く。
「広いお屋敷っすね」
「車もいっぱいあるのさ。高そう……」
ガレージの影に二人で息をひそめる。成り上がりの一族が所有する家屋には、外車をコレクションするための倉庫があった。
タイヤがあまりすり減っている様子はないし、覗き込んだ運転席は大してメーターも刻んでいない。金持ちの道楽、その欲望の権化ともいえる。
「中には入れてもらえないっすけど、こっちには水路があるっす」
倉庫から抜けると、裏手にはちょうど庭をぐるっと囲う水路がある。雨水などを排水するためのものであろうが、たとえば――血を洗ったりしていたのならば、ここは必ず通る場所だろう。
「いいっすか」晴汰は、珂奈芽に尋ねた。「うん、十分。やってみるから、さ――」
珂奈芽は、クリスタリアンである。
隔世遺伝、先祖返りの存在だ。蛍石の変わり種は強く在ることを願い、そのために立ち向かうやさしき少女の姿をしている。
純度の高い石ゆえに、彼女は神通力もしくは精霊との交換力が高い。人形を扱うこともあるが、今回は【サイキックオムニシエンス】により、その場の歴史を読むことが可能なのだ。
晴汰からすれば、無い感覚である。
珂奈芽が見つからないように、晴汰はゆっくりと二人、転ばないように手を引いて歩いていた。その意識が集中できるように、確かに護る手で連れる――。
息が、詰まるような心地がした。
「こんなところにいたの」誰かの声がするが、それは珂奈芽に向けられたものではない。
視界が現在と過去に混ざり合っているが、過去の世界は暗いものだった。珂奈芽のように、手を連れられている女の子がいる。
泣きそうな顔をしていた。顔の半分は真っ赤に腫れて、ぶたれたばかりだとわかる。「早く家に入らないと、お父さんがまた怒るわよ」というのは、母親だろうか。
風貌は、見ただけでわかった。幼いころの上村由美子である。
今のようなりりしい目つきではない。泣きじゃくることなく、力なく家の中に入っていく。
――お父さんは、どうして私が嫌いなのに、家の中に入らないと怒るの?
思念が耳の奥で響いて、ぞっとした。
手を握る珂奈芽の脈が早まっている。晴汰は、声をかけるか迷って止めた。
瞬きをはさむと、目の前に死体がある。足を止めた珂奈芽に、晴汰も連れられて止まった。
「食べ、てる?」
真っ赤だ。
真っ赤な中身が見えた。
上村由美子の父親は、実の娘にその場にあった手ごろな石で何度も何度も頭をたたきつけられている。
母親が静止に入っても、一瞥もせず腕一本で突き飛ばしている。この由美子は中学生くらいの姿だった。セーラー服が真っ黒なのに、返り血で余計に赤く染まる。
恨み言は発していなかった。代わりに、唸りと怒りの叫びが混じった。
何度も、何度も、何度も。
砕く、砕く、砕く――。
目を背けるべきだったが、それはできないでいた。あまりにも、衝動の勢いが強すぎる。釘付けになった蛍石の輝きは、「本当の、最初の被害者」を知る。
あり得ない光景だったのだ。大の男を少女が組み敷いていることも、腕一本で母親を突き飛ばしたことも。
上村由美子はいたって標準的な体形に思えるし、どうやっても父親が反撃すれば負けそうだったのに、もはや父親はだらんと手足を伸ばして砂利に埋もれたまま、動かない。
「もういいの、ゆみちゃん。ゆみちゃん、やめて」
母親が背中にしがみついてようやく、石を振り上げるのは止まった。
「お父さんが悪かったのよね。そうよ、そう、――お父さんが、他に子供なんてつくってくるから」
火事場の馬鹿力、というのがある。
人間はもとから、「ある程度」能力を制限しているところがあるのだ。
たとえば、人に危害を加えるとき、自分に危害を加えるとき、思ったよりも痛みを感じられないのと似ている。
無意識なセーブといってよい理性が、今は外れてしまっていたのだろう。これが、まぎれもなく「のけもの」が誕生した瞬間の出来事であった。
「……きもちわるい」
珂奈芽の嘆き声を聴いて、すかさず晴汰が「大丈夫っすか」といたわる。
「顔色――かなり悪いっすね。背負ってくっす」
「いいの?」
「はい! 珂奈芽が目ならオレは足、ってやつっすよ。さ、追うっすよ!俺も見えるとこでカバーするっす」
強くあろうとするのに、やはりどうしても、一人ではおぼつかないらしい。
正直な指摘には珂奈芽も逃げることができなかった。「ありがと」と返して、背負われる。
頼りになる背中。――左ほほをぺたりとくっつけて、続きを見ていた。
ゆっくりと動く晴汰の鼓動につられて、珂奈芽の鼓動も落ち着いてくる。だから、『あの日』にあった上村家のことが遠く思えた。
正しい位置に自意識が戻ってきたところで、事の顛末を見届ける。
父親の死体は、上村由美子が土管に入れていた。今の彼女の印象とは大きく異なる手つきであった。
母親は、その砂利に着いた血をホースから水ですすいで、流している。水路に血が吸われて行って、脳漿ごと下水に流されていった。
土管を横転させて、由美子が転がしていく。「ゆみちゃん、どうするの」母親の声を無視した背中は、珂奈芽と晴汰の前を過ぎ去っていった。
「――ん?」
晴汰が声を上げて、珂奈芽を背負ったまま、そっと砂利をかき分ける。
失せ物探しの専門の探偵――その見習いの目線は「探す」ことに秀でているのだ。すん、と鼻を利かせて砂利とも土とも、雨ともちがうにおいの違和感に気づいていた。
掌で平らになめしながら、浮き出てくるものを探す。そこには、一枚の羽根があった。
「……黒い羽根っすね。鴉とは違うっす、でもこれ、結構最近のみたいっすね。……邪神の名残でしょうか」悪寒がする。晴汰がまじまじと見ながら、眉間にしわを寄せた。
「そのへんに、たくさん落ちてるのさ。たぶん」
「なんでわかるっすか?――まさか、獣がこの先に?」
やや身構えた晴汰の背で、ううんと首を横に振り、額をこする珂奈芽である。
「地下室が、あるのさ」
風の音がする。
晴汰が耳を澄ませながら、珂奈芽の通りに前へ進んだ。慎重な足取りで、吹き抜けるものの正体を見る。
ハッチがあった。晴汰が珂奈芽を背負ったままでも十分に通れそうな四角形の入り口は、真っ白な砂利に隠されている。晴汰が足でどかすと、――真新しい血の跡も、そうでない血の跡も、獣の繊維も、たくさんこびりついていた。
「そこに、最初の被害者の死体があるのさ、これが、もう動かない証拠になるの」
「わかりました、一度――戻るっすか」
「うん。……最後まで頼りっぱなしで、ごめんね」
「何言ってんすか、お手柄っすよ」
励ます晴汰の声を耳にしながら、珂奈芽がどこか安堵する。
――ああ、でも。これで、裁かれてしまうのは。
「のけもの」ではなくて、きっと上村由美子なのだ。それだけは、どこか、やり切れない心地がした。
「もうちょっと――見れたら、なぁ」
「のけもの」を捕まえるための材料は、あと少し。
孤独の巣を見つけて、他の猟兵たちに共有するまでは晴汰の背で、珂奈芽が休めていただろう。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 エミリア・ジェフティー
エミリア・ジェフティー
好きな動物…羊とか良いと思うんですよね、ふわふわして抱き心地良さそうですし!
…っと、現地の治安組織に協力を扇げるなら利用しない手はありません
捜査資料を可能な範囲で見せて頂きましょう
繋がりの見えない事件との事ですけど、
儀式的な意味があると仮定すれば見えてくるものもあるんじゃないでしょうか
それを読み解ければ次の犯行現場…けものの行方も追える
というわけで、偽装隠匿しておいたセシャートにオウレットアイを通じて情報連携
データを学習させ、ネットに侵入して収集したオカルトな情報とかと組み合わせて演算、推測させてみます
鬼が出るか蛇が出るか…ああ、出るのは邪神でしたっけ
…有益な情報を得られたらいいんですけどねぇ
 霧島・クロト
霧島・クロト
◎
終夜(f28722)と。
――まぁ、こんなんじゃ普通は犯人は『わからない』だろう。
そりゃ『人間』という『獣』の噛み跡なんて想定、普通はしないだろうし。
で、件の刑事が犯人だと『仮定』するなら、だ。
たぶん。これは、『自分を受け入れてくれる他人』を探し回っていた。
……だけなんじゃないだろうか。
そう、『いい子じゃない』、噛み付いてしまう程の自分を。
被害者の死亡推定時刻と、上村刑事の動向を両方とも調べておこう。
ひょっとしたら当人が直接起こしている訳でなく、
『当人』から乖離した何かが犯人かもしれないし。
……俺には正直分からんけどな。
噛み付けるようになった、『悪い子』には分からん話さ。
いいこでいるってのは。
 終夜・日明
終夜・日明
◎
クロトさん(f02330)と
……過去を詮索するのは本来なら憚られることですが、
【情報収集】と【ハッキング】を利用して当時の彼女の状況を知る方の連絡先を確保しアポを試みます。
可能なら父親も含めた当時の上村家の事情を知る方にお伺いしましょう。
犯人の特定も事件の解決も、恐らく彼女の幼少期が鍵を握っているハズ……
関係しているのは母親の自殺だけではないかもしれない。
クロトさんの仮説が当たっていれば――の、想定な上僕の直感に過ぎませんけれどね。
……受け入れてもらえないということに感じる痛みと悲しみを抑えるのは難しい。
開き直れる程の心を持てる土壌があったかなかったか――きっとその違いでしかないのです。
 カイム・クローバー
カイム・クローバー
◎
俺が関わった過去の事件にも凄惨な事件は幾つかあった。拷問を繰り返した惨殺事件の犯人が年端も行かない少女――なんて事例も過去にある。
ああ、それと――犯人を見付けてもその拳銃を撃つのは止めときな。逃げ遅れるだけだ。
死体はあるかい?見せてくれ。出来るだけ新しいヤツで損傷の激しいのが良い。死体には歯形があると聞いたがどの獣の歯形とも一致しないんだって?
一ヶ所なのか、複数個所なのか?致命傷はどの部位か。喰った形跡はあるのか、それとも殺しただけか…。被害者に共通点は?
死体の発見場所とかも聞いとくか。飼い主とじゃれ付いたにしては少々被害がデカすぎる。
俺の中の獣ねぇ…可愛らしいヤツだと良いんだが(肩竦め)
●
「エミリア・ジェフティー(AnotherAnswer・f30193)です、この捜査拠点で一番いいマシンってどれですか?」
正直なところ、この片田舎での文明発展については期待などしていなかったエミリアである。
ええ、とか、はあ、とか曖昧な返事のあと、通されたのはシステム対策課と名付けられたチームの席だった。
急いでパソコンを準備するように言われた丸刈りの男が、わたわたとしながら「どれがいいっけ」というものだから、「あ、もうサーバー室に放り込んでください」と手を上げたほうが早かった。
エミリアが快活に提唱すれば、あっけなくサーバー室のセキュリティは解除される。
クロムキャバリアに乗る彼女からすれば、機密データを保持する場所の割にはあまりにも緩く思われたが、中のマシンはこの文明の中でもなかなか悪くないように思えた。
「可能な範囲で情報を精査してもいいですか? あ、ブラウザの閲覧履歴はもちろん内緒にしておきますから!」
猟兵、オブリビオン、未知の技術――それを知るのが命題である。
任務よりも興味のほうが勝つ彼女の本性を知るものからすれば「絶対に守られたい」ところであろう。だが、それをエミリアが約束に出したのだ。
茶目っ気たっぷりなウインクもつければ、警官たちは何に安心したらいいやらわからない顔でお互いを見合わせた後、頭を下げて出ていった。
「さあて、やりますか。な、に、が、出てくるかなっと」
――彼女の相棒は、今この場にはいない。
正しくは、目に見えないようステルスが貼られたうえで、偽装隠匿の加護のもとに隠れている。
「有益な情報を得られたらいいんですけどねぇ……」
セシャート。思考に関わる特殊技能を持つキャバリアの名である。彼と接続できるオウレットアイを、サーバー室の中にある一台のパソコンとつなぎ合わせた。
ディスプレイなどは必要ない。セシャートがデータを照合し、行動パターンを演算で割り出していく。
客観的すぎる数字と計測は、人の心を推し測ることはないが人の感情を抜きにした「のけもの」の足跡を追うには最適であった。
いかに無秩序型の犯行とはいえ、目撃情報や画質の悪く古びた防犯カメラとの照合などからは逃れられまい。
必要なのは、その足取りと、「どうしてこうなってしまったか」の――二次被害を防ぐための解析だ。
「お、っと、ヒット」
がり、がりがりと読み込む音が激しくなった。まるで釣り糸を垂らして震えるのを待つばかりだったエミリアが、楽しむ声を上げる。
どれどれと微笑みながら繰り出される「オカルト」の情報は、以下のとおりである――。
上村家は、成り上がりの家である。
もっとも力をふるったのは、上村由美子の父である上村譲司であった。
譲司は、新興宗教団体を立ち上げ、当時の街を復興させた手腕のある経営者でもある。
彼の言う宗教というのは、誰でも信じれば救われるというセオリー通りのものでありながら、己らのマネーロンダリングや高利貸しに加担させる手法である。
田舎ヤクザ、と片付ければいいものだったのだが、彼の持つ土地にある山には、昔から地元ではそこそこに知られた神社があった。
今は、もうその名も残っていない。しかし、譲司が一番強かった時代では、古くからの慣習やしきたりを当然にあったものとして扱う世代が根強かったのである。
戦後まもなくのこの土地では、ほとんど警察もそのあくどいやり方には協力していた。
なにか信者がひどい目にあえば、都合よく警察が手を貸して助けてやることもあるし、過度に相手を責め立てることもあった。
暗黙の力は次第に「本当に譲司は選ばれた人なのだ」と思いこませ、立派だなんだと持て囃すようになったのだ。
そして、彼を政界に進出させようと選挙に出たときである――上村家は没落した。
選挙に敗退したのだ。
あれほど信者の力を借りたといえど、しょせん片田舎の井の中の蛙だったのである。
幽霊の正体みたり、という次元の話ではない。神が人だったことに、多くの人々が絶望した。
上村家は力を一気に失い、豪邸と資産は残れど、村の中ではすっかり「ばちあたりな一族」として名が残ることになる。
しかし、暗黙の刷り込みであろう。いまだに、かの一族には誰も対等にはモノが言えない――。
「どこで邪神は介入したと思いますか」
「政治に手ェ出しはじめようとしたあたり、じゃねえの。たとえば、『このツボ持ってりゃ成功しますよ』とかいってさ」
成り上がりたての調子に乗った金持ちほどだまされやすいんだ、と霧島・クロト(機巧魔術の凍滅機人・f02330)が言うように。
終夜・日明(終わりの夜明けの先導者・f28722)もまた、そうだろうなと頷いた。
生命特攻の毒素を持つ彼故に、本質的に人間に嫌われやすいのも相まってであろう。聞き込み調査をしても、誰も彼に話そうとはしなかった。
しかし、――そういったことがあったのだとは、隣にいるクロトが彼に対して無警戒であるからこその「かろうじて」の手がかりとして手に入れる。
それだけわかれば、あとは十分だった。日明は、上村が所属するこの警察署の事件データベースをハッキングしながら、ネットで手に入れた個人ブログサイトの語り文句を要約していた。
「で、件の刑事が犯人だと『仮定』するなら、だ」
「ほぼ確定ですけどね」
「そうかァ? 俺は、ちょいとそれは早すぎると思うぜ」
「……道徳や倫理の話ですか?」
「いいや、どっちかつーと法の話」
上村由美子が、重度の解離性同一性障害であるとしよう。
昼の彼女は由美子であり、夜の彼女は「のけもの」である。
こうして猟兵たちがそろえているピースのひとつひとつがそろっていったところで、結論として罪に問われるのは由美子のみだ。
「悪魔を裁けと?」
「お前は悪魔を宿したやつごと殺すほうがはやいって?」
「合理的ですから、被害者たちはそれを願うでしょう。僕も、クロトさんが感じている通りのことを思っていますけれど」
「そりゃそうだろうな」
――あくまで冷静沈着であろうとする彼に、クロトもそれ以上は言うまい。
上村由美子を弁護したいわけではなく、彼女自身は本当に、被害者なのではないかとクロトは思うのだ。機械の腕を交差させながら、処理されていくバイザーに浮かぶ情報に目を細める。
「たぶん。これは、『自分を受け入れてくれる他人』を探し回っていた。……だけなんじゃないだろうか」
――『いい子じゃない』、噛み付いてしまう程の自分を。
のけものには、名前がない。のけものには、戸籍もない。
のけものは、獣にもなれず、人にもなれないでさ迷い歩いている。
ここにいるよ、私はここだよ、誰かわかって、愛して、と言いたげに誰彼構わず「殺した」のではなくて、「甘えていただけ」だとしたら。
――それしか「甘え方」がわからなかったのなら。
「……、上村刑事には」
「巡査です。刑事という役職はありませんから」
「いいんだよ。わかりやすいだろ。――虐待された経験があるって?」
「日常的なようでした」
クロトには、ますますわからない。
クロトは、『悪い子』だ。噛みつき方はわかっているし、そうすることで自分を守ることもできる。
たとえそれが親であっても、身に覚えのない己自身の衝動であっても戦うことができた。やりたくないことはつっぱねるし、そうでないことは引き受ける覚悟を持つ。
「治療カルテはあるか?」
「――はい。今、出力します」
日明とクロトのバイザーの前に、文字列が増える。
「精神科には通ってないのか」
「偏見を――恐れたようです。この地域には、あまり心理学の必要性が周知されていないようで」
「そりゃあそうだろうな。なんせまだ百年程度の学問だから」
嘆きとも呆れともつかない声で白狼は唸る。
「受け入れてもらえないということに感じる、痛みと悲しみを抑えるのは難しい」
治療記録を二人で見る。
ひどいむち打ち、頭の切り傷、どれもこれも『事故』であり、『本人の過失』で過ぎ去られた言葉たちが添えられている。
次に、学歴からこれまでの稽古事を見た。
――ぞっとするようなほどのスケジュールがクロトと日明の前で組まれていく。上村由美子は、常に塾と稽古事に通い、学校生活からはかけ離れていた。
父親がペテン師である。母親は、せめて子供だけでも立派にしてやろうとしてノイローゼになっていた。
母親にも精神科に通った形跡はないが、何度か内科で精神安定剤と睡眠薬を与えられている。
「開き直れる程の心を持てる土壌があったかなかったか――きっとその違いでしかないのです」
傷ついても、壊れても。治せる場所がどこにもなかった。
誰も彼女の痛みを理解できないで、知らないで、当たり前のように声をかけていたのだろう。
――よその家のことに触れないように。
――『あんな家の子のこと、ほうっておきましょう』と。
「俺が関わった過去の事件にも凄惨な事件は幾つかあった。拷問を繰り返した惨殺事件の犯人が年端も行かない少女――なんて事例も過去にある」
カイム・クローバー(UDCの便利屋・f08018)は、慰めにもならない言葉をかけながら、上村由美子の前に座っている。
本人に合意をとっての軟禁状態となっている。この彼女が、逃げ出さないようにと猟兵たちが極力刺激を与えないよう、今は監視していた。
上村は、両手を組み合わせて膝の上に置き、じっと背中を少し丸めて座っている。
「ずっと追いかけてた犯人が、自分だって思ってんだよな。おい、その拳銃。こっちに寄こしちゃくれねえか」
カイムの声掛けで、ようやくはっとしたようである。
「あ、ッ、す、すみません」
「いいさ。ただ、ソレを使うのはナシだ。逃げ遅れるどころか、あんた――脳みそぶちまけて死ぬことになるからな」
責任を負っている女の顔は、今にも自分の息の根を止めてしまいそうなほどに切羽詰まっているように見えて。カイムはジョークの範囲で終わってほしい願望を口にする。
机の上に、重々しくホルスター事拳銃を置いた上村は、指先の震えを自覚する。
「寒いかい」
カイムが尋ねた。
「いいえ。あの、おかしいんです」
「どうした?」
「……指先とか、の、感覚がなくて」
カイムがチョーカーに触れる。婚約者からの贈り物が揺れた。
「緊張してる、といいたいが――ちょっとした症状かもな」
「そんな」
「大丈夫。すぐにバチッと入れ変わるもんじゃないらしいぜ」
それよりも、と。カイムが座るものと同じパイプ椅子が、彼の隣にある。長机をはさんで、上村が彼の手の動きを見ていた。
拳銃と入れ替えるようにして、封筒を置いた。「開けてみな」と声をかけると、従順に上村は封筒を開く。
「……これ、は」
「死体だ。最近の、死体。あんたが殺した――って暫定で言っちまうけど、そういうことだ」
見慣れた死体のはずなのに、自分が知らずに殺していたそれだと意識すると、途端に重さが違う。
う、とうめく上村を、カイムはじっと見つめた。「逃げずに、出来れば見てくれ。それで、思い出してほしいんだ」
これは、無理やりスイッチを押す方法でもある。今の銃を取り上げて最も恐れるべき事態である自殺の可能性は消えた。
「教えてくれ。この歯形には何の意味があったんだい」
「私は」
「あんたに聞いてるんじゃないんだ、俺は、――あんたの中にいるやつに聞きたい」
【話術の心得】。
呼び起こすための誘惑だった。語調はとても甘く、そしてひらひらと目線で追いたくなるであろう蝶のようであっただろう。
「なあ、俺はあんたが知りたいんだ」
己の中にいる獣が、かわいらしいものであればいいと思う。
――その願いは望み薄だとは、目の前の上村由美子の表情を見れば理解できる。
「はじめまして、でいいんだよな? 言葉はわかるか」
ふつ、と上村の表情が無表情になったのだ。
先ほどまで緊張と動揺が見て取れた顔は失せて、代わりにぱちくりと目を見開いた女がそこに座っている。
人は表情が違うだけで、こんなにも異なるのかと――カイムが少々気をとられた。
「ぁ」
どうやら言葉がはなせない。
赤子のような発声に、「そうか」とカイムが頷く。「何もしない。だから、あんたも何もするな。できるか?」
――まいったな、と髪の毛をかきあげた。目の前にいるけものは、ぱちぱちと瞬きを繰り返して不思議そうにカイムを見ている。
夢見心地なのか、それとも今は腹が減っていないのか、心が『察知』されたことで満たされているからなのか。
「あー」
「わかったわかった」
じゃれついたにしては被害がデカすぎるのにな、と思い――延ばされる手を右手でのけようとしたときである。
腕から、羽根が生えていた。
「上村由美子さん自身が触媒になっちゃってますねぇ」
【エンドオブミスティック】でエミリアが暴いたのは、邪神と上村家の関わり合いである。
上村家は、その力をさらに伸ばそうとしたときに――邪神を何らかの手段で手に入れた。
それはとある信奉者からのコンタクトがきっかけであったらしい。眷属の一部が人間に成り代わったものかもしれないが、それはささやいてしまった。
「生まれてくるあなたの赤ん坊に、この羽根を食べさせてごらんなさい。そうすれば、願望を具現させるでしょう――」
エミリアからすれば、よくある詐欺の手段である「いいように言ってるだけ」だとも理解できたが、この時の上村家というのは狂騒の時代である。
よいものはなにもかも手に入れ、都合のいいように扱おうとしていた。自分の子供ですらたくさんいればいるほどいいだろうと、上村譲司は認知するわけでもないのに外に子供を作っていた程度の男である。
「無責任もいいとこです。――鬼が出ても蛇が出ても、邪神が出てもいいとは思ってましたが」
呪いは、末裔である彼女を腐らせた。
「まさか最初の被害者が、最悪の犯人とは。しかももう――失踪、いいえ、死んでいるし」
一族を絶やす呪いである。それは、邪神のものからではない。この地に浸った人間の怒りとねたみ、恨みだ。
上村家の被害にあった人間たちは、ネットに書き込むような時代に生きていない。だからこそ、口々に呪ったことだろう。
――いつかばちがあたればいい。
「警護を固めてくれ。中には入らなくていい、それと、中も見るな。いいか」
カイムが指示を出す。上村家の地下室が暴かれる時間帯は、夕方であった。
今の状態の上村由美子を連れていくことは危ういゆえに、落ち着いた「けもの」を警察署に残す。
幸い、今は誰かを襲うことを考えてはいないらしい――だからといって、油断はできない。
「変な音がしたら、すぐに連絡してくれ。俺たちのだれでもいいから」
大人しくしていればいいのだけれど。
締め切られたカーテンのむこう、けものは椅子に座ってぐるぐると写真をかじっていた。
味わっているのでもなく、ただ、――誰か気づいてくれないだろうかと、様子をうかがうように甘えていた。
黒い羽根が、部屋にはらはらと落ちていく。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト
◎
人の心は複雑怪奇と言うが
被害拡大阻止を優先
界離で全知の原理の端末召喚。魔力を溜めた体内に召喚し自身の端末機能を強化
『刻真』と併用し全ての時間において情報を走査
事件の痕跡を辿り邪神と「けもの」が如何に関わっているか、及びそれらの現状の把握を試みる
いつの時点で、どのような経緯で邪神が介入を始めたか
影響を受けたものがどれだけいて、各々の程度はどれくらいか
介入の端緒となったもの、邪神活性化の理由など調べ得る限りを
現時点で新たな被害が出そうで、介入すれば防ぎ得るのなら実行
その際は『刻真』で無限加速し即座に現着し介入、魔眼・封絶で停止させる
 水衛・巽
水衛・巽
◎
推理するにも今は情報が足らない
殺害現場周辺の、目につきにくい物陰に隠れてもらいつつ
雑鬼にも情報収集を手伝ってもらいましょう
まずは犯人像より被害者像のほうが知りたい
社会的弱者か、それとも共通の特徴でもあるか
あるいは噛み痕が同じ場所であったか、等々
コミュ力でもって聞いて回りましょう
それほど時間は経っていないようですから
断末魔が呪詛として現場に残っているでしょうけど
もし背後から急所を一撃、だったなら望み薄ですかね…
一応呪詛が残されているかも調べてはおきましょう
濃いものを発見できれば絶命の瞬間の情報くらいは手に入るはず
まあ、あまり何度も見たいものではありませんけど
これも陰陽師の御役目、仕方ありません
 橙樹・千織
橙樹・千織
◎
調査ですか
では私は現場をまわってみましょうかねぇ
現場にある物や構造物にも共通点があるかもしれませんし
時間も一緒に照らし合わせ、その時間がどんな状況なのかも確認しましょうか
時間によって人通りや雰囲気も変わりますからねぇ
あとは…そうですねぇ
ご近所の方に何か普段と違ったことが起きていなかったかも聞いてみましょう
小さなことでも実は…ということがありますからねぇ
聞き取りをする時は警察の方に付き添ってもらい、
コミュ力や礼儀作法、ほんの少しの言いくるめを使って会話を進めていきましょう
急がず、焦らず、確実に
情報整理のために見直すのも大事なことですからねぇ
 ヴィクティム・ウィンターミュート
ヴィクティム・ウィンターミュート
◎
……獣、ね
何かを獣にする力や作用があるとして…それをコントロールできているのか、出来ていないのか
自発的になるのか、誰かを強制的にそうさせるのか
分からないことが多いな…現場と遺体をしっかり見とくか
Balor Eyeを撒いて、複数の現場を一気に見てみよう
ロケーションから推定できるのは、計画性の有無だ
獲物を見定めて計画を立てて、ハンティングするなら身を隠せたり、視界が悪かったり…見つかりにくい要素が多いなら、狡猾な手合いだ
逆にそうでないなら突発的…自発的な獣化ではないか、制御できてないかが分かる
さて、その後は痕跡だな…小さな皮膚片でもいい
辿れるアテがあるなら、こっちから直接出向いてやるまでだよ
●
人の心は複雑怪奇というが、超常の残骸がが人の心と体をかたどるだけのアルトリウス・セレスタイト(忘却者・f01410)には、まずその物自体が理解できていない。
数字とは大きく異なり、世界の理とは在り方がそもそも違う。人のこころというのは、目に見えないというのに何通りもパターンが存在し、その数だけ痛みと甘さを持っている。
幾ら怪物よりも神よりも恐ろしい力を持った構造の男といえど、痛みの重さも、えぐれた傷の深さも推し測ることはできない。
「――、俺のことは気にしなくていい。最大限に力を貸す、好きに頼ってくれ」
「言われなくてもそのつもりだぜ、リキダイザ持ちに俺もあやかりたいとこだった」
ヴィクティム・ウィンターミュート(Winter is Reborn・f01172)は、壊れている暇のなかったサイボーグである。
少年の心には年齢に伴わない大きな傷跡がたくさんついている。
「このクソ田舎でまさかここまで調べるのに苦労するとは――悪魔を証明するのは骨が折れるね」
『のけもの』との直接対面に成功した猟兵がいる。
その猟兵の報告通りであれば、『のけもの』は精神的に幼いわけでもないが、人間的な情動を見せないようであった。
まるで人間の体によくわからない何かがいるような雰囲気は、目を見てみればわかるだろう。
ヴィクティムの【Balor Eye】は彼女を監視するために警察署をうろうろと飛び回っているし、――得体のしれなさというのは確かに感じられた。
あまりにも無知な赤子のような表情であるのに、落ち着いて机の上に座ったり、たまに寝転んでみたりしながら、あくびをしたりしている様は本当に、ただのけもののようなのに。
「……だいぶ邪神の影響を受けてるな。『生きる触媒』ってことだ」
腕から羽根が生えている。真っ黒な色は、鴉のそれとは言えない。神話に興味はないが、例えるなら堕ちた天使が相応しいであろう。あまりにもきめ細やかな繊維の細胞を、ヴィクティムの目が解析する。
――生物学的に一致は、無し。過去の邪神データには在り。
「処分をするか」アルトリウスが尋ねる。
「程度による」ヴィクティムが右手の人差し指を立てて指を振った。
猟兵として出来ることは、邪神の召還を不完全なままで止めてそれを討伐することが最善といえる。
それに付属する――例に挙げれば、オブジェクトなどは壊すか、組織に明け渡せば保管されるだろう。ただし、人間本体となってくると違うのだ。
動物一匹よりも人間の脳を持っていることが厄介なのである。腕を組みながら、ヴィクティムは屋敷を見上げた。
上村由美子の親族が住まうという屋敷は、沈黙を保っている。
「ローク(複雑)なんだ、人間ってのは」
己が手繰る電子の機器よりも、アルトリウスが扱う原理よりも。
決まった形が無く、リアルタイムで形を変えるパズルのようなものはヴィクティムのようなランナーですらおいつかないほど目まぐるしい。
毎日を『生きる』。生きているということは、日々アップグレードがあるということだ。
アルトリウスにもわかりやすく言葉にしてやれば、「ああ」と機械に近い論理の思考をした彼が頷く。
「だから、俺にはわからないのか」
「わからない、つうよりは難しいってことだ」
「似ている」
「気の持ちようの話だからな」
ヴィクティムの『目』が、屋敷に侵入している。
生粋の悪人であるヴィクティムからすれば、不法侵入もプライバシーのどうのこうのも関係があるまい。屋敷の中は広く、豪奢なものがたくさんあった。
――この中のどれかでも売りさばくか買わなければ、もう少しまともな末路があったであろうに。
「身の丈に合わないことする奴は、どいつも金持ちっぽくありたがるよな」
中継映像を腕のコントロールパネルから映し出す。ARで表示された画面を興味深そうにアルトリウスが覗き込んだ。
「人がいないな」
「いるよ。デブの男と、ガリガリの女」
『目』が音もなく、緩やかに空間を移動する。和風のつくりをした長い廊下は旅館にも近い。ずうっといくつもの障子を超えて、仏間の前を通った。
――いくつかの畳を飛び越えたあと。最奥の部屋で、男と女の焦りがあらわになった声が響いている。
ああ、やっぱり。あんな子なんて早く追い出せばよかった。
だから私も行ったじゃない、あの子は前からちょっと変な子だって、兄さんの子よ!?
お前の兄貴がどういう奴かはみんなが知ってる!でもまさか子供まで、人を殺すなんて――。
あの女が嫁なんかに来たから――。
「聞くにたえませんわ、こんなん」
水衛・巽(鬼祓・f01428)は、ヴィクティムの『目』に玉乗りの用に乗っていた己の【雑鬼召喚・群】、その一体から声を聴いていた。
うきうきとした雑鬼たちをこの場に解き放った際から察してはいたが、この一家の積み上げてしまった業というのはあまりにも根深すぎる。
何人を殺してきたのだろう。間接的にも、儀式と形容して間引いたのもあったのだろうか――呪いに呪われ嫌いに嫌われ、死んだ年月が遠いというのにあまりに濃すぎる。
吐き気すらするような人間の情念を前に、巽がうずくまることなく両足で立っていられたのは、彼の陰陽師としての自覚の問題だ。
――親やというのに、よくもまぁ。
神仏への侮辱は容認したとしても、家族としての在り方についてはまるで己の子供すら「金さえくれてやればいい」として、育てていた男の情念が残っている。
その正体は、上村譲司であった。
巽は思うのだ、この男は親として失格だと。
――怒りすらこみあげるほどの下賤な言い分が聞こえてくる。今は冬の寒さなのか、底知れぬ冷たいひとの心のせいなのかもわからない。指先が冷えて白んでいても、巽は気にしている暇もなかった。
庭が広いというのも考え物で、一人二人が侵入したところで広い屋敷に二人で住んでいる親族たちからは巽の様子すら感じ取れないのだ。
幸いにも、周りにはアルトリウスの【界離】の恩恵で屋敷の中身から見える光景が制限されているらしかった。
「体調悪そうだな。チューマ。休んでてもいいぜ」
「――いえ、まだ大丈夫です」
すうっと球体が横切るついでにねぎらっていった。巽は、その声で現実に少し戻ってくる。
ある程度の情報は出そろってきていたし、ならばあとは「最初の被害者から」の言葉を聞くだけだろうとして、殺された上村由美子の父親の場にやってきたのだ。
庭で実の娘に殴り殺された彼というのが、いったい何をしてきた男なのか。純粋な興味もあったが、それが『のけもの』を知る大事なピースであろうと思って――試してみたのである。
黒いすすけたほこりのような雑鬼が、ネコのような尻尾を揺らしてきいきいと土の上に転がっている。
楽し気な彼らを眺めながら、――情念の解析を急いでいた。
「もうちょっと、話をさせてもらいますよ。譲司さん。――あんた、子供をペットやと思とるんでしょう」
巽の問いかけには、男の笑い声とも、怒りとも、なんともつかぬ情念が返ってきた。
譲司は、生まれて間もなく恵まれた生活をしてきた男である。
譲司の父といえばこのあたりの地主であった。戦後まもなくの場で彼のリーダーシップというのがいかんなく発揮され、住む場所に困った難民状態の人々を受け入れ、土地を分け与えてその恩賞で生計が立ったわけである。
小学校を作るというのならば、その土地を善い値段で売ってやり、それから工事をするのならば結束のある仲間を連れて奉仕した。
そのような父も、切り捨てるべきだと判断した人は切り捨て、時に犠牲にしてきたものである。
父は譲司ほど冷淡ではなかったが、経営者としては判断の出来る冷静な男であった。
しかし、――譲司が生まれてからというものの、彼もまた毒されたといっていい。
譲司は親の七光りをそのまま譲り受けて大人になった。
子供のころから手に入らないものがあれば癇癪を起し、俺の親を知ってるかと相手を脅し、お前の家も俺の親がいなければ今頃、と小さいうちから無意識に刷り込みを行ってきた。
住民たちもずうっと、「上村の家には世話になっているから」と昔話を繰り返すものだから、誰も彼に言い返せないまま――そういうものだと思って受け入れていたのだ。
それを譲司の親は、「うちの息子は出来る子だ」と思ってしまったのである。
ほしいものは何でも買い与え、存分にふるわせ、罪を犯せばその圧力でもみ消してきた。
譲司には、反省の文字がないままの生が与えられたのである。きょうだいの中でも一番豊かに。なんでも一番のものを与えられた彼は己の子供にもそれを求めるようになった。
「子供に金がどうのこうのの話をして、恩に着せがましい言い方をして――」
美しい女との間に出来た長女の誕生を喜んだ。
――男でなかったのは正直残念がったが、生まれてきた由美子は奇しくも人一倍『あたまがよい』子だったのだ。
親のいうことはよく聞き、なんでも素直に吸収し、わがままを母親が咎めれば大人しく引き下がる。
まるで、犬のようだと。
そう思ってしまった時から――この男は、きっと親にはむいていなかった。
「思い通りにならなかったら、叩いて蹴ってと繰り返し――」
譲司には反省の文字がない。
きっかけは、五歳の由美子がピアノの練習中に音階をはずして、「もうできない」と泣いて教師を困らせたことである。
この優れた己の子である由美子が、まさか「できない」という結果を出すとは譲司が思わなかったのだ。
由美子にはありとあらゆる金を使って教育を施してきた。
母親の腕に抱かれるよりも長い時間を教育の時間にあててやった。
――子供にとって、親のそばにいるというのは疲れた心や体を回復できる時間であったというのに、それを取り上げたのである。
いくら由美子が優れた子であったといえど、ひび割れてしまった心も体も、治す時間は与えられないまま毎日を拷問のように過ごした。
由美子は聡い子であった。
小さな己が逃げ出しても、どこにも居場所がないことはわかっていたのだ。
逃げることをあきらめた彼女は、耐える道を選んだ。
「お前にいくら金を出したと思ってる、なんて。小さい子に言う言葉じゃなかったでしょう、なぜもっと――」
巽とて。
小さいころから、水衛の子であるからとその道と教育を受けてきた。
少年ながらに反発心も抱きながら、それでもつとめのために今はこうして彼らしくも陰陽師を遣っている。
憧れと、――少しの対抗心を父相手に抱きながら、それでも先代の彼を尊敬しながら、超え続けることを目標としてつとめを果たしているのだ。
親と子の形に正解があるとは思わない。
しかし、明らかにこの譲司と由美子の関係というのは、まるで。
「金だけ出して世話したらへんって、そんなん――犬かて猫にかて劣るようなこと、よくも」
業を背負った者の痛みも知らないで。
「あらぁ……お母様は自殺でなかったのですか?」
橙樹・千織(藍櫻を舞唄う面影草・f02428)は、ひそひそと団地の集まりに関わっている。
ツシマヤマネコの耳がひこひこと動いていても、誰も気にした様子はない。この辺りに住んで長いのだという婦人会の奥方たちが彼女の話し相手であった。
千織に付き添うことになったのは、婦人警官である後藤である。
髪型は黒のショートカットで遠くから見れば男と間違われそうな体格をしており、静かな女であった。背丈は高く、一七八センチの図体である。
嫋やかな千織の護衛にちょうどよかろうと同伴を引き受けたときも「はい」と返事のみ返して、歩幅を合わせて歩く彼女はよく目立った。
「聞き込みをされたいのならば、私を目印に人の目が集まるでしょうから」
「あらあら――」
無表情な彼女なりの気遣いでもあったらしい。案の定、警察と見慣れぬよそ者が賑わいだした小さな町では、うわさ好きの暇を持て余した主婦たちが路上でひそひそと話し込んでいたのだ。
そこに「こんにちは」と飛び込んだのが、千織である。
「そうじゃないかって噂よぉ。あ、ごめんなさいね刑事さん」
「いえ。続けてください」捜査の否定をされても、特に情動が動くことはないらしい後藤が、主婦の言葉を容認する。
「でも、首をつって亡くなっていたと聞きましたよぉ。それを娘さんが見てしまったって」
千織が愛らしく首をかしげると、「そりゃあんな家にいたら死にたくなるだろうけど、旦那さん亡くなって間もなくよ? どれだけ遺産が手に入ると思う?」と返ってきた。
――ああ、なるほど。と千織も頭の中でそろばんを思い出す。
正直なところ、森の奥深くで巫女としてつとめる千織にとって、金の執着というのはほとんど無縁だ。
だからこそ、冷静にその事実を「利益」として勘定する。俗世に遠いからこそ、問題を多角的に観察することができた。
「あたしたちは親戚がやったんじゃないかしらって思ってるのよ。あそこ、お家の中もドロドロなんだから」
「きょうだい多いしねえ」
「娘さんはいい子だったのに」
「――奥さんはどんなお方だったんですか?」後藤にも尋ねてみる。
「物静かで美しい人でした」淡々とした言葉で返ってきた。
「でもあの人どこの出かって言ったら、宗教家の娘って聞いたわよ」
「でしょ? 私もそう聞いてたのよぉ。でも勧誘とかしてこないしねえって」
「変わった人には変わった人がつくもんだと思ってたわぁ」
――ふむ、と息をついて。
急がず、焦らず。確実に情報を見直していく。
上村由美子の父親、上村譲司が邪神との関わり合いを持ったのは、おそらく上村由美子の母と結婚してからのことだろう。
――宗教家の娘である彼女が、父親の紹介で結婚したのだという。
「お金持ちの旦那さんのところに、自分の娘がお嫁さんに行けば、パンフレットなんて刷り放題ですもんねぇ」
神は、信仰を集めることで力を手に入れる。それを邪神に当てはめてみれば――この地に満ちた呪詛を吸って、よみがえろうとしているのだろう。
地獄を作るために町一つを邪神は利用したのだ。
上村由美子、その母の家族の目論見が果たして其処迄を予期したものであったかどうかはわからない。しかし、小さな子供をいけにえにして今日の日を迎えていた。
現に、今刻々と――この場で猟兵たちが掘り起こした「真実」は呪詛としてあふれ始めている。
井戸端会議に気に入られた千織は、一緒にカフェに行くかどうかを提案されたがていねいに断る。
まだ仕事中なんです、と残念そうに言えば、「じゃあ終わってからお話ししましょう!」と返されるほどには打ち解けていた。後藤の案内で、猟兵たちが集まる場所に移動する。
――上村家の屋敷に、呪詛が立ち込めているというのだ。空は、雪雲とはいいがたい暗雲がにじみだしていた。
「後藤さんは、どう思います?」
「どの件をですか」
空を眺めながら歩く千織が、広い背中をした後藤に問いかけてみる。白い息をお互いに置き去りにしながら、冷たい空気で肺を満たした。
「上村さんのことですよ」
「日頃の職務に、責任の持てないことをすべきではなかった、と思っています」
「厳しいんですねぇ」
「――ですが」
ぴたり、大きな動きが止まった。
「本当に、彼女が悪かったのかとも、思っています」
振り向いた後藤の顔は、無表情であった。それでも、瞳の奥底に――哀しみがあるように感じられる。
きっと。
上村由美子は、この事実のあとにはここに戻ることなどできないだろう。
千織にも、隠しておきたい自分がある。獣性にまみれて、すべて赤に塗り替わった空間で、狩りに興じる自分の姿があまりにも悍ましかったように。
恐ろしい。自分が恐ろしくて、きっとたまらなくなる。何もかもを手放したくなって、逃げ出して、どこにも居場所がないことにまた泣かなくてはならない。
臆病になってしまう――自分を隠したくて、取り繕うとして、彼女がまた『割れたら』それは悲劇の連鎖には違いない。
だから、千織はこの後藤の表情には驚いた。
「出来る限りを尽くしますよ。みんな、納得できるような結末が一番ですからねぇ」
待ってくれている人がいる。
見失ったら、悲しむ人がいるのだと――恐ろしい側面を知っても、それがあなたの全てではないから、と想う人がいることに。
「きっと、帰ってきます」
後藤の瞳が少しだけ和らいだのを見て、息をついたころである。
無線の音が響いた。緊急を知らせるトランシーバーに、千織も耳を傾ける。
それは、――「上村由美子が逃亡した」という報せであった。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 叢雲・源次
叢雲・源次
【義煉】◎
(事前情報はUDC組織から仕入れ、現地に赴く。見た所、変哲もないベッドタウンのようだが…さて…と、傍らの相棒へ視線を向ける)必要事項は事前に話した通りだ。ただの獣であれば俺達が駆り出される事もなかった…つまりは…そういう事だ。
捜査手段
・インターセプター、アナライザーによる地形・痕跡調査
・近隣住民への聞き込み
・上記に二点を踏まえた目標の足取り調査
討滅対象のUDCは…おそらく寄生型か感染型…となれば、その対象となる生物の共通点はなんだ…これまでの材料を加味する
『対象となる生物は、単独もしくは群れから孤立した個体』
…クロウ、少し、試したいことがある。今から30分、単独で行動する。
 杜鬼・クロウ
杜鬼・クロウ
【義煉】◎
(邪神絡みだからかやけに熱入ってンなァ、源次)
あァ、確認済だ
いつも通り行こうぜ
被害者の共通点や敵の意図は図り兼ねてたが、成程…
寄生もしくは感染型なら一連の行動も腑に落ちる部分はあるな
今回はヒトの行動では無く”ケモノの習性”から攻めてくンだろ?
狩りみてェで滾るわ
罠とか張るか?
通常とは違うだろうが音や匂いに敏感と読む
田舎寄りで人気薄い処、静かな場所ら辺を中心に捜索(情報収集・聞き耳
人への聞き込みを主に担当
現場も幾つか洗い直す
手掛かりや見落としがないか確認
…待てや(源次の肩掴み
お前、何する気だ?
別行動は構いやしねェが、イヤな予感がする(第六感
ち、止めた所で無駄なのは解ってたケド
気ィつけろよ
●
――インターセプター、アナライザー起動。
「クロウ、少し、試したいことがある」
杜鬼・クロウ(風雲児・f04599)の相棒といえば、叢雲・源次(DEAD SET・f14403)である。
フォーマルスーツに身を包んだ鉄の男は、身も心も鋼だ。
黙し、じいっと獲物を見つめ、的確なタイミングで襲い掛かる彼といえばまるでクロヒョウのようである。
雄々しくもしなやかで、己の職務に私情をにじませない彼が――此度、現地にたどるまでに積み上げた情報はすさまじい。
現地に先に到着した猟兵たちからの情報を纏め、地形のマッピングから痕跡を察知し、残るのは『答え合わせ』となり、上村由美子を検挙するだけの証拠は揃えてしまうほどの速さがあった。
「――待てや、何する気だ、お前」
それを、『気合が入っている』という言葉で片付けてはいけない気がしたのだ。
クロウが相棒の肩を掴んだのは、二人がある程度の聞き込み調査を終えたときである。上村由美子、いいや――『のけもの』が逃げ出してしまった、ということだった。
しかし、猟兵たちの監視がなかったわけではない。間もなく見失ったのは溢れかえる呪詛が光や認識阻害を起こさせたからで、人間はおろか、呪詛に秀でた猟兵たちも見失ってしまうほどの汚染が広がり始めている。
どこを嗅いでも、見ても、「けものくさくて」しょうがない。むせ返る呪詛の根源を探しながら、ひとまず住民たちに避難するように声掛けをしていた時であった。
「今から30分、単独で行動する」
「――構いやしねェが」
「必ず落ち合う。頼むぞ」
「オイ! 源次、気ィつけろよ。――これだけは言っとくぜ、間違っても殺すなよ!」
めらめらと滾る彼の猪突猛進さが、クロウには恐ろしさすら感じられた。
「チ、……」あっという間に姿を消した相棒の名残を感じながら、思わず舌打ちをした。
源次は、真面目な男である。彼の地獄を背負う点からも感じられるが、非常に今回の件と彼の経歴が似ていた。
――過去に、マキナ教団と呼ばれる邪教団に攫われ、サイボーグに改造され邪神の依代にされかけた時、鋼の男は目覚めたのだ。
全身から地獄の炎を噴き出しながら静かに燃える怒りをあらわにするかの男を末路とするならば、上村由美子も辿る道かもしれない。
問題は、それが「辿れなかった場合」だ。
「『古来より太陽神に司りし者よ。禍鬼から依り代を護られたしその力を我に貸せ──…来たれ!我が命運尽きるまで、汝と共に在り』」
召還、【杜の使い魔】。
クロウの呼び声に応じて、閃墨――三本足の八咫烏は姿を現す。
空を覆うほどの翼を広げて地面に足を付けた彼にまたがって、クロウは空からの捜索を開始した。
「ずいぶんため込みやがッて」
この世でいっとう恐ろしいのは、地獄を作ってしまう人間であるというのならば、護るものであるクロウは地獄を晴らしてやるのがつとめである。
上村家にあてがわれた妻というのは、何者だったのかクロウからすれば明らかであった。
巫女である。名を、上村結花といった。
神に遣える女を、より一層神が豊かになるために結花の一族は送り出したのである。これは、計画的な犯行であったといえた。
美しい花を咲かせるために、適切な土壌を選ぶのと同じことだったのだ。子の幸せよりも、信じる邪神のことを願う――時間をかけにかけた、「儀式」である。
儀式の完成を由美子とした。由美子は生きる触媒となって、その人生を真っ黒な痛みで染めていく。
猟兵たちの監視映像、その最後の――由美子、「のけもの」の姿といえば、形容しがたいものだった。
空を飛ぶには不揃いな羽根をして、四つん這いになって走っていく。手は人間のものに近いのに、鋭く爪が変形していた。
顔は面影も薄い。犬とも猫ともつかぬまま、瞳だけが彼女のものだったような気がする程度で、全身からは不ぞろいな羽根が生えていた。
「――あ? 閃墨、降りろ。水路になんか落ちてら」
人間にもなれず、獣にもなれず、自分が何なのか揺らいだ彼女に降り注いだ悲劇は名もなき怪物を生み出してしまった。
いっそ哀れな運命である。この壮大な儀式に巻き込まれたのは、由美子たちのほうだったのだ。
彼女を探してやらねばならぬとくまなくクロウがひとつひとつ洗っていった。のけものは巣に帰っていないようである。
いいや、荒らされたのを確認して、ここには居れぬと逃げていったらしい。上空からたどった痕跡と、避難させるついでに住人から相次いだ目撃情報の「毛むくじゃらの何か」の足取りと比べていた結論だ。
ならば、――と探していた時に見つけたのは、黒い羽根である。
いっそ罠でも敷くか、それとも習性に合わせておびき出すかどうか悩んでいた時に、クロウはある程度の捜査方針を決めていた。
音や匂いに敏感ではないだろうか、と。
人気が薄く、夜が近づいてきてもほとんど人目につかず、明かりの少ないところといえば――上村家の所持する土地に含まれる、広大な田んぼである。
畑の上に鴉の影が溶けてしまうほどの時間になるころに、目を凝らしてようやく見つけた一枚の羽根であった。安全着地を心掛けた閃墨のくちばしをなでてやりながら、たっぷりと呪詛を孕むそれを拾う。
「あッづ!おいおい、やべェな」
クロウは、神である。ヤドリガミだ。人に愛された彼には、どうやらこの人間の呪詛をしみ込ませた羽根は有害であるらしい。ほぼ爛れたような指先がぐずぐずと皮膚を溶かしていたが、間もなく復元される。
「二つの家ぶんの呪詛吸わせて、町一つをぶち壊し、何も知らねえまともな子供一人犠牲にして、どういうクソ田舎だッてンだ」
とうてい、人に扱えるようなものではないのに。
深々とため息をついて、――色違いの瞳は、水路の先を見た。羽根が散らばった跡があって、両腕が爛れるのも気にせず漁る。
「綿毛か。この羽根も、こっちも」
ふわふわと浮く羽根たちは愛らしいものだ。弱弱しい繊維がクロウのほほを焼いたが、気にも留めない。
代わりに、舌打ちをひとつくれてやった。
「生え揃えようって?おいおい、ッざけんじゃねェ」
●
その男は、依然沈黙を続ける屋敷の扉を蹴破ったのである。
「ひぃ、いい、い」
「――貴様らか」
不法侵入だなんだと喚いた小太りの男を、軽く蹴った。つま先だけで倒された巨体を、夜の色で黒く塗られた源次が唸る。
この怒りに満ちた姿を相棒に見せていたら、きっと咎められていただろう。しかし、今は怒りの青すら口内で輝くほどではあるがセーブできている。
発熱がある、冷却機能を起動し、己の脈拍を強制的に安定させていた。
「何、何の話、だ!私たちは何もしていない!あの子にだって、ちゃんとした学校に行かせてやっていた!」
「俺が問うている。聞いたことにだけ答えろ」
大理石で作られた玄関までの階段を乗り越え、豪奢な玄関には赤い絨毯が敷き詰められている。
古の日本家屋と相まって、ノスタルジックな内装は男から発せられる怒りの青によって、もはや冷たい地獄のような様相であった。
「上村由美子の母、――上村結花を殺したか」
「な、」
「殺したのか」
源次は、この事件を追っていたのではない――別の事件を突き詰めていた。
「殺人の時効は法改正により撤廃されている。貴様らの所業、ここで吐け。自首として扱うよう警察に掛け合ってやる」
源次も、けして多くはない近隣住民に話を聞いた。
彼が見定めたのは、上村家をねたんでいたり、嫌っていると噂される一家である。エンジンを駆動させ、真っ先に会いに行った。
その家の妻は、源次に上村家の名を出されただけで『おかえりください』と嫌悪感を突きつけるほどである。これは、あたりだと思ったのだ。
教えてもらえないか、どうか、と頭を下げた。「どうして其処まで。よそ者のあなたに何がわかるんですか」と声を掛けられ、答えることは単純である。
「――どうしても、許せそうにない」
冷静な男である。
源次は、人を裁くような立場ではないと理解している。
今回の一件とて、もはや悲劇といって差支えがない。たった一人の罪なき女にすべての禍が起爆したのだ。
「遺産と保険金、そしてこの広大な土地、山。すべて金か。金目当てに、この愚かなことを為したか」
上村家のことをひどく嫌っていた女主人は、かつてこの家に使用人として雇われていた女であった。
彼女は、目撃者である。
上村結花をこの男と、その妻が殺したのを見ていたというのだ。
黙ってておいてくれと金を渡されても、――黙っているかわりに、その金を一円も使わなかったほど、ていねいな女である。
「た、ッ、逮捕状もないだろうに! バカなことを、あれは自殺だった! 死亡届にもある!」
たまらず、刀を抜きかけた。
代わりに、その鞘で大理石をたたく。突き刺すような動きに、ばきりと床が割れた。
「俺の、聞いたことに応えろ」
シン、と静まり返る屋敷で、源次は低くうなる。間違っても殺すなよ、と相棒の声が頭の中で再生されていた。
「上村結花を、殺したのか。彼女『ら』の目の前で」
それが、いつか来る儀式の完成に必要であるからと。
朝目覚めた由美子の前には、ドアノブで首を吊ったように見せられた母親の姿があった。
何度母をゆすっても、声をかけても、冷たい温度と固まった表情しかない。だらりと垂れた舌を見て、「あ」と気づいてしまったのだ。
由美子は、常に極限の状態にあった。
父親からの暴力は相次ぎ、突然彼は「失踪」する。失った稼ぎ頭のあとを追うように、母親もこうして由美子を残して自殺したように見えていた。
耐え難いストレスを、とどめに浴びせられてしまったのだ。割れないように、と保っていた器が割れてしまった。
注がれる地獄と呪詛を前に、彼女の自我は「傷つくのに耐えきれず、器を増やした」のである。
その自我が――安定してしまった。上村由美子は、この事件をきっかけに「ふたつ」になってしまう。
ストレスが水であるのならば、人格はコップだ。
コップから水があふれないうちに、次のコップを用意したまでの、自己防衛の方法である。
――『のけもの』もまた、母親を心配した。きっと、死んでいることすらわからなかったのだ。言葉をもたない彼女が、ころりと寝転がって死体に甘えていたに違いない。
腹が減って、甘えるようにかじって、血も肉もあるのだと知って、かじった。
●
「源次」
「――クロウか」
姿かたちは変わっていないように見えた。源次からの連絡で、警察が動き――ひとまず、親戚夫婦二人は避難所にて事情聴取となる。
サイレンの音が響いている。異常事態は、ガスの漏れということで処理されているようだ。
げほごほと噎せる彼らを横目に、屋敷の庭にたたずんでいた源次の隣にクロウが到着する。
「大丈夫かよ」
「ああ」
「ひでーツラしてンぞ」
「……ああ」
何も気が晴れない。
源次が、己の顔を覗き込んだクロウに視線を交えた。
「まだ終わってねえ。何かしら、手段はあるはずだぜ。寄生されてンなら、取り外せるかもだし。汚染されてンなら、破魔で晴らしてやれっかもしれねェ」
「そうだな」
両手を握る。息をゆっくり吸って、呪詛を内なる地獄で燃やしてから吐いた。
「――そうだとも」
のけものは、きっと泣いていた。
どこにもいない母を探して、これも違うあれも違うと知って、打ちのめされて、『いい子である』ために歯を奪っていった。
己の手柄という象徴が、それしかなかったのである。獲物の一部でもぎ易い場所が、それだけだったという話だ。
――母が、見えているのだろうか。母という帰る場所は、どこにあるのだろうか。
きっとのけものはそこにいる。母を感じられる場所に、帰ろうとしていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 神狩・カフカ
神狩・カフカ
◎【相容れない】
何が悲しくて姫さんに纏わりつく虫と調査なんざ…
そりゃこっちの台詞なんだがなァ?
ま、これも巡り合わせってことかねェ
おィ、ちび。ちんちくりん
巫山戯るのは面だけにしとけよ
本当にやる気あんのかァ?
ほーん…そンじゃお前さんは今日はおれの助手ってことで
おれは人の世では探偵で通ってるからな
聞き込みねェ…
おれは事件もそうだが
刑事さんのことが気になるなァ
どうだィお嬢さん
この後おれ達とお茶でも
なァんてな!
けれど気になるのは本当サ
最近身の回りで何か変わったことはないかィ?
――さて、目星は付いた
あとは裏付けだ
おれの眷属に歯型の持ち主を追ってもらおうか
へェ…その聖者の勘ってやつも見せてもらおうじゃねェの
 ジン・エラー
ジン・エラー
【相容れない】
◎
はァ~~~~ン?ンでお前と組まなきゃなンねェンだァ?
お前ンとこにも人はいンじゃねェ~~の?
あァ、そ。ま、誰と組もうと構いやしねェけど。
あァ~~~してるしてる。調査。してるゥ~~~~
うるせェ~~なァ~~~調査だ推理だ追跡だァ~~なンてのは性に合わねェ~~~ンだよ
聞き込みィ?怠ィからパァ~~ス!!
つゥ~~わけで天狗野郎、任せた
………こっちだなァ
何ってそりゃァ~~~アレよ。聖者のカンってやつ。ウッヒャラハハ!!
ほォ~~~~らァビンゴォ~~~~~!!
オレがいて良かったなァ~~?
●
「はァ~~~~ン? 」
「――はァア……何が悲しくて姫さんに纏わりつく虫と調査なんざ……」
「ンでお前と組まなきゃなンねェンだァ? お前ンとこにも人はいンじゃねェ~~の? 」
「そりゃこっちの台詞なんだがなァ?」
神狩・カフカ(朱鴉・f22830)とジン・エラー(我済和泥・f08098)といえば、相容れない。
ただでさえ呪詛に満ちて空気も淀んでいるというのに、お互いにこの状況になってまで組む相手が互いであることには、巡りあわせとカフカはとらえていた。
神を信じない聖者であるジンからすれば、カフカのことなど胡散臭い天狗と認識している通りに『信じてはいない』のである。
「ま、誰と組もうと構いやしねェけど」
「おィ、ちび。ちんちくりん」
「はァ~~~~~~~~~~????????」
「巫山戯るのは面だけにしとけよ、本当にやる気あんのかァ?」
「あァ~~~~してるしてる。超してる。調査してるゥ~~~~~~~~~~~」
『のけもの』が逃げ出して数十分。水路に残った羽根のかたまりは、まるで雛から成鳥に代わるような生え変わりの跡であった。
カフカが軽く噎せるほどの呪詛が満ちている。体にずいぶんと呪いを背負ってしまっているらしいのは、救い手であるジンから見ても明らかである。
「こりゃ時間の問題かもなァ」ジンがその有様を見てそういったものだから。
「あァ――あっという間に割れちまうだろうぜ。人間の器じゃそう長くは持たねェ」
「そんじゃァ~~~~さっさとズバッと解決してやれよ探偵サンよォ」
「お前さんも今日はおれの助手なんだからちゃんと働いてくれやァ。なァ?」
はたから見ても、仲が良くはない。
カフカからすれば懇意にしている羅刹の女に付きまとうようなジンが気に入らないし、ジンもまた秋色のこの神が気に入らないのだ。
とはいえ私情はあったところで、この二人とて己の役割を忘れているわけではない。
「まだ『由美子』だったころに話は聞いといたケドさ」
「あ?????何ヌケガケしてんだこの天狗野郎???つかあの時なんか聞けてンなら早く言えやタラタラタラタラ歩かせやがってよォ~~~~~~~~~~~」
「見落としが無いかどうかは確認したほうがいいんだよォ、ま、踏み荒らされちまってるけどサ」
「あァ~~~もういいもういい、さっさと本人から聞いたヒント言え」
先ほどから二人は、ずうっと上村家の周りをうろうろとしていた。屋敷を孤立させるようにぐるっと田んぼが囲んでいるつくりである。
あまり手入れがされてはいない。雑草が生い茂っていて、持て余すなら売っちまえばよかろうにとカフカも思っていたのだ。
だから、そこを聞いてみた。由美子自身に軟派な笑顔を作って身の回りを尋ねてみたのは、朝のうちのことだった。
「――どうだィお嬢さん、この後おれ達とお茶でも」
「え、っと」
「間に受けなくていい~~~~~ぜ。こいつそ~いう病気ね、ビョーキ」
「はァ?」
カフカが穏やかに、美しい顔で忙しそうにする上村由美子の行く先を体で遮った。
神としての感覚が告げていたのだ。その時点で、かなりこの女に呪詛が付きまとっていることはわかっていた。
特別に濃い。――皆がこの女が「獣」の正体ではないかと言い出していて、カフカもジンもそうだろうなと察していたのだが、それにしても特別「濃い」物を感じた。
何百、何千に呪われている。
――こいつァちょいと、とんでもねェもんに祟られてンな。
神に祟らているのならばまだ話は早い。神は赦す存在であるから、無礼の結果が祟りであっても、手順を踏んで反省の気持ちを示せば大抵はそれ以上の試練を与えることもないのだ。
しかし、カフカの美貌に魅入って少し息を止めたらしい上村由美子の表情からは想像もつかないほどの呪詛で、彼女はがんじがらめになっている。
人間に祟られているのだ。
数々の思念が彼女を取り巻き、恨み、その血を許さない。
ジンも嫌な予感が脳に警笛として響く。眉を潜めこそはしなかったが、同時に彼女の罪ではないことも予感していた。
彼女ではなくてどれもこれも、やはりその血統を恨んでいるのだ。
「いンや、気になっちゃってサ」
ずい、と一歩詰め寄る。穢れの呪詛がぐるり、渦を巻いた。秋色の翼をふるえば一度は霧散する――息がしやすくなったのか、上村の顔色はよくなった。
「……最近、身の回りで何か変わったことはないかィ?」
「変わったこと」
「そ、たとえば……知らない場所にいた、とかサ。ものがなくなった、とか」
ひとつもジンはそのやり取りを聞いていないように、興味のなさげなそぶりをしていた。髪の枝毛を探すのに夢中なような顔を作っておいて、女の解答を待っている。
もし本当に意味のある事ならば、きっと隣の神が己に伝えるだろうとは理解していた。二人とも相容れずとも、目的はひとつだ。
――未来を救済すること。
少し考える間をはさんで、由美子は言った。
「……、変かもしれませんけど」
「複雑怪奇は大好物サ!」
空に、【月夜鴉】が飛んでいる。
宵色の鴉は、ふわりふわりとカフカのもとに帰ってきた。
「自分ちの地下室にいたってサ」
「ほォ~~」
「夢遊病だと思ッちまって、誰にも相談しなかったんだと。まァ、前からちょいちょいと自分に不信感はあったみてェだが」
――髪の毛が濡れてるんです。寝る前は乾かしていたのに。
――風呂の電気がつけっぱなしだったり。
――洗濯物が増えてたりとか。
捜査に夢中だったから、切り詰めていたのだろうかと自分で思っていたらしい。
日常業務には差支えもない範囲であったから、この事件が終われば長めの休暇をとろうとしていて――彼女の器はとうとうひび割れてしまったのである。
それは、たとえば卵が割れるように。
「じゃァ~~~~もう帰る場所っつゥ―か、今いる場所なんて決まってるよーなもんじゃん」
「へェ。根拠はあるのかい」
「そりゃァ~~~アレよ。聖者のカンってやつ。ウッヒャラハハ!!」
「アー、そうかい。その聖者の勘ってやつも見せてもらおうじゃねェの。おれの眷属と答えが同じかどーかも確かめてェし」
目星はついたから、あとは裏付けだ。
とはいえその裏付けが、ジンの勘であるというだけで神たるカフカは一度賭けてみることにしたのである。
この聖者の欲は好かないが、侮れないところがあるのも確かだ。道化のようななりふりをしながら、この男が何度か色違いの瞳をきつく細めて呪詛のあとを眺めているのを見ている。
探偵として名の通る神は、相手をよく見ることが仕事だ。それが敵であれ味方であれ、一切加減をすることはない。
だから――根拠あって、ジンが「使える」とは認めていたのである。文句を言いながらもついてきて、田んぼをかきわけて歩くジンは静かなものだった。
「こっち」
つぶやく声が、確かな確信を持っている。
「おッと。こりゃあ、でかい排水路だ」
カフカの身長は、183.7センチと平均的な身長よりも高い。
そのカフカを飲み込むほどの広い口をした排水路が、屋敷の足場にあった。岩を積んでさながら城のようになっている立派な上村家は、ここから水の処理をしていたらしい。
「見てみな」
ジンがあごだけで、排水路の中身を示しながら躊躇いなく足を進めていく。
乾いている中身はすっかり使われていないらしいが――羽根が、乾いた血痕が中に続いてる。
辿って歩いていくのだ。アリの巣のように無数に分岐する道でも迷いはしなかった。時折先行するジンの背を押しこんだり、それに肘で返したりなんてしながらたどり着いたのは、よく冷えた空間である。
「なるほどねェ。こっから地下室に繋がってたってワケだ」
「ほォ~~~~らァビンゴォ~~~~~!!」
――隠し部屋ならぬ、隠し階の登場である。
やはり溢れた呪詛の痕跡はこの場に満ちている。空気を入れ替えるかと考えて、カフカが地下室への入り口を探して、地下からハッチを開けようとした時だった。
「オレがいて良かったなァ~~?」
にんまり、にやにや。へらへら、げらげら。
――真っ赤な舌を出して笑う汚泥に、神が返したのは重く、呆れの混じったの笑いであった。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ロニ・グィー
ロニ・グィー
◎
なるほど!謎は全て融けた!お爺ちゃんは常に一人!
いやこの場合は刑事ドラマ寄りの方がいいのかな?
なるほど、ピースはもう揃ったみたいだね
ボクは全然分からなかったけど!これが集合知の力ってやつだね!
じゃあ…ピースが揃ったのなら解答編を始めよう!
●開幕・QED・閉廷
UCを発動して証人と被害者(一時的に蘇生させる)と容疑者とみんなを集めて法廷か、某警部の解決シーンみたいな時間と空間から切り離された場を用意しよう
出るのは鬼か、悪魔か、それともやっぱり人間?
でもオブビリオンだとちょっとつまんないよね
さて、答えは出たようだね!
これにて閉廷!
さあ、もう種は割れたんだ。枯れ尾花の正体を見せてごらんよ!
 ゼイル・パックルード
ゼイル・パックルード
◎
昔、蛇に例えられたっけ……獣ではないか。そこらへんの獣よりも厄介な自信はあるけどね。
なんとなしに言った言葉、というかよく言いそうな言葉ではあるんだけど、どんな獣が宿ってるね
邪神の眷属まがいにされてるなら、そういう素養があってもおかしくはないよな。他の人間は殺されてるわけだし
事件のことよりずっと昔の、犬や猫とかの殺害記録とか、そういうことをしてたヤツがいる噂を探してみるか。その周りのイジめとかそういう噂とかもあれば。
獣性とかいうか、人に不要なものは抑えつけられがち。でもストレスとかそういうのを受けるとあっさり顔を出すしな。
何も手がかりがなくても、可能性が一個潰れたのが手掛かりってことで。
 花剣・耀子
花剣・耀子
◎
此処まで回ってくる案件が、厄介でないわけはないけれども。
これ以上を赦さないのが、あたしの仕事だわ。
……、あたしもねこがすきよ。
おいで。
猫の分霊を呼び出して、手分けして情報収集。
探すものは、――そうね。
事件に計上されていない痕跡がないか。
死骸や遺体は、かならず残っていたのかしら。
現場として挙がっていない場所に現場と似た痕跡等があるなら、
行動範囲や狙いの傾向が判るかもしれないわ。
まだ見つかっていないものがもしあるのなら、
……あっても、何も出来ないけれど。無駄にしない事は出来るもの。
きみはヒトが入るには難しい場所の調査をお願いね。
そんなところにも手がかりがあるのなら、敵の大きさや輪郭も判るかしら。
 コノハ・ライゼ
コノハ・ライゼ
猟兵の手が入ったと知っているなら、次の動きはかなり慎重になりそうか
まあ少しの間大人ししてくれたら楽ナンだけど
ソレに彼女が「知らない」のだというなら捜査という行動の裏でも無意識に
「獲物」を探してるンじゃねぇかしら
彼女の事ももう少し詳しく知りたいトコだけど
先ずは彼女の活動範囲を辿りましょう
事件の捜査に向かった先々、プライベートで立ち寄る場所
特に、今日念入りに調査してる場所は押さえておこうか
他にいつからこの辺りにいて、外から見た人柄は
彼女の住居近辺も洗っておきたいねぇ
次の標的となりそうなのを絞っておいて
何かあったらすぐ動けるように
彼女については聞き込みの体で露骨にならないように
営業スマイル全開でネ
●
「なるほど! 謎は全て融けた!お爺ちゃんは常に一人!」
「何か色んなものまざってなァい?」
「お爺ちゃんって常に一人じゃね」
「孤独死……になってしまうような気がしたわ」
地下室。
――上村家、広大な屋敷の下に設置されたそこに、ロニ・グィー(神のバーバリアン・f19016)とゼイル・パックルード(囚焔・f02162)が潜入を試みていた時である。
UDC組織の犬と自称しながらほぼ猛犬どころか、手のつけようのないものと悪名を持つコノハ・ライゼ(空々・f03130)を、花剣・耀子(Tempest・f12822)が連れ、二人を先行することとなった。
「此処まで回ってくる案件が――厄介でないわけはないけど」
「邪神の眷属まがいになってるなら、救出は結構めんどくせェんじゃないの。斬捨てるほうが楽だけどね、たぶん」
【《花映》】。
ふわり、猫の分霊が体を淡く光らせながら四人の足元を照らしている。ひげをレーダーのように真横に広げ、時折動かしながら風の動きや、呪詛の流れを察知していた。
分霊を使って、耀子の手に入れた情報といえば、ほぼ「同上」の「裏付け」を可能とするものだ。
結論、上村由美子を裁くことはできても、彼女をここまで追いつめた親族は、――殺人とその共謀で捕まえたとて、彼女ほどの罪を背負うことになるだろうか。
何度も裁判にかける余罪はあるだろうが、恐らく極刑には至らない。きっと、彼らだって人間の司法の前では平等に「異常」と認められる。
上村由美子は、――「けもの」は、どうだろう。
考えても詮無いことだとは、耀子もわかっていた。
それでも考えさせられるのは地下室に満ちた呪詛が尋常ではない濃度であるからだ。現場慣れをしているからこそ、さほど動揺は顔色に出ないが隣のライゼなどは凶暴な色を瞳に宿している。
「それにしてもスゴイとこネ」
紛らわせるような笑みを含んだ言葉でさえ、隠しきれない獣性があふれているようにも聞こえた。
「壁に何人を埋めてるンだかわかったもんじゃないし、死体のにおいもする」
「死体?」耀子が、体に緊張を走らせた。
「――何か思い入れのあるものかもねぇ。『のけもの』の」
ライゼが得た情報は、耀子の知った「裏付け」とほぼ同じと言っていい。
だけど、――『失踪したが行方不明のまま見つからなかったため、死亡扱いとなった父親』の行方は面白おかしく怪談話として噂程度に小耳にはさむ。
「ここの当主?ってさぁ、歯フェチなのかな」
「フェチ、っつうかなんか、それこそトロフィーみたいに思ってそうだけどな」
『あんな人、殺されたんじゃないの。あの家の地下に埋められてたりしたら笑っちゃうけどね』。
悪意を隠すことなく、中年の女がライゼに毒を吐いたのだ。
昼の太陽が高いうちだからか、悪口を言っていても己の心に影があることも気づかないらしい。ライゼがご機嫌に上げ膳据え膳でトークの場を作ってやって、初めて出てきた言葉だった。
それを皮切りに出てきたのが――たくさんの推測と事実の混ざった噂話たちである。
ロニが風を頼りに届いた呪詛に、もちろん噂も混ざっていた。
「うまいことやってくれるなぁって思ってたんだよね」ロニが狭い肩幅をよりすくめて「噂話って人間、だーいすきでしょ?そしたら、もう悪口っていう呪詛なんて蔓延りほうだいだよ。汚染型って名前結構ピッタリかもね」
その土地に寄生して、汚染する。
邪神の呪いは確かに人を媒介としてふりまかれていたのである。たった一人の少女を起点にして、『再臨』できるように。
ゼイルが己の胸元からあふれる炎で足元を照らしていた。コンクリートでできたような足場は一件、ぼこぼことした石が埋まっているように見えるのに、細かな粒子の違和感に気づく。
――歯だ。
歯が、この足場にはちりばめられているのである。
「牙って、力の象徴だからな」
「そーなの?」ロニが知りたいままに問うた。
「ライオンの牙を抜いたりするだろ。まぁ、爪もだけど――そいつが抵抗できないようにだよ」
奥の部屋に至るまで、ゼイルが口元を襟に隠されていなければ、微笑んでいるのが見えなかっただろうか。
ゼイルには理解できた。この屋敷の当主が何を考えていたのか。どうして、獣が――被害者たちのあぎとを盗んでいたのか。
「人に不要なものは抑えつけられがちだ。特にストレスに弱いやつとかもそう、獣っぽさなんてもっとそうだな」
だから、この地下室に隠しておいたのだとわかっている。
上村家の犠牲者たちがこの場に一部分残され、呪われた血脈をより呪われるようにし、仕上げの我が子に被害者の歯を持ってこさせるようになったのは。
「服従の証なんだよ。見て、私はこんな獲物を殺してきたよ、だから赦してってな」
蛇めいた顔で、笑う。
そのあたりの獣などよりも、もっと己は厄介である自覚があった。
捕食者の気持ちがゼイルには理解できてしまう。獲物を食らうのならば、一番熟した時が良い。
お楽しみは最後までとっておくのが一流の悪党というものだから――この当主は、己が「人間」である間の挫折を知った時に、「次」の段階に移ろうとしたのだ。
地下室は直線構造である。獣の痕跡が至る所に残っていて、「おいで」と耀子が猫に声をかけた。
ひょいひょいと服にしがみ付いてきた背をなでてやる。そのまま抱き上げて、静かに扉を見た。
「開けるワ。下がってて」
ライゼが声をかける。耀子にウインクひとつして、鉄でできた扉をなでた。
「それじゃあ、いよいよ解答編かな? 鬼が出るか、人がでるか、……邪神じゃちょっとつまんないけど」
暴虐の神が悦楽を金色に浮かべて笑っている。
――ごめんなさい。
――ごめんなさい、お父さん。
――できない子でごめんなさい。
――お金をかけてもらったのに。
――私は一人娘なのに。
――ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
――ぶたないで、蹴らないで、捨てないで。
――お前がいてよかったよって、言って。
「そんなことはない、と思いたかったンだよね」
ライゼが目にしたのは、地下室の最奥の光景だった。
まるで書庫の用である。広い空間にぎっちりと詰まった本は、いっそ異質だった
歴史の本から、価値のわからない図鑑や、周辺地図と思わしきものもあれば、邪教を信仰する宗教本すらたくさん並んでいる。
――まもなくほかの猟兵たちもたどり着くだろう。その書庫で、うずくまるようにして『のけもの』は寝転んでいた。
腐りかけた何かを抱いて、真っ黒な羽根の塊が四人を見る。
これは、悪い夢だと思っていた、と――上村由美子は言っていた。
自分が虐待されていたという事実をどこか遠くに見ていた。年表があって、事件が描かれている程度にしか思えたことがないのだと話す彼女は、悲しそうな顔をしてはいなかった。
問われれば困ったような顔をして、その事実を認められないどころか、他人事のように感じている。
受け入れられない己の不幸を認められない彼女は「虐待されていた自分」を切り離してしまった。
「普通に、学校に通っている子だった。大学にも進学して、友人もできていた。尊敬する上司は理想の父親像に近かった」
言葉すら忘れて、ただ殺してしまった獲物の牙をもぎとってくる。
まるで朝、由美子が家を出るときに母親の仏前へ手を合わせるのと同じことだった。『のけもの』はそれを、供物としていたのである。
「だから、『あなた』は気づいてしまったのよね。『あなた』にはそんな人生がなかったことを」
――自分が、不出来だったから何もかもおかしくなったのだ。
責任感が子供のうちから強い由美子であった。耀子の聞いてきた限りでは、自分の職務に大変忠実で、請け負った事件は必ずやりとげたいと悔し涙を流すこともあったという。
皆を守るのが己の仕事であり、そうすることが幸せなのだと誇っていたという彼女は、この環境で育ってしまったがゆえに近くで見れば「異常」であった。
事件への執着からも伺えるが、――まるで、「失敗することを恐れている」ように見えたのだと、西警部が唸っていたのを思い出す。
耀子が、しゃがみ込む。獣の長い髪の毛に触れてやることもできないまま、代わりに猫を抱きしめた。
「『あなた』は、ずっと、こうしてたのね」
『のけもの』は、父親に愛されたかったのである。
父親が嬉々として人を痛めつけ、支配し、小ばかにするのを見てきた。
気まぐれに『のけもの』にやさしくし、気に入らなければぶつ彼に『認められたい』とずっと思ってきた。
――じゃれついて殺してしまったのだ。石で殴りつけたのは、彼がよく『のけもの』を拳骨で殴っていたからである。
それがこの親の愛なのだと思っていたのだ。甘え方はそうするのだと知って、由美子が感じた怒りのストレスでスイッチが切り替わって。
由美子の感情にふたをするように――前へ、出てきてしまった。
「以上が、検察側の主張である」
ロニが、前に出た。
小さな体のままで神は両腕を広げてまるで天秤のようにしてみせる。
「なるほどなるほど、痛ましい事件だ!つまり、――被告」
【歪神】は、ずばりと右手を前に向ける。黒い羽根に包まれた『のけもの』にではない。
その中ですっかり骨になっていたはずの、『腐りかけ』の死体に微笑んでいた。
「アナタは、娘のか弱い心を踏みにじり、何度も痛めつけ、自分の願望をかなえるために愛すら犠牲にしてみせた! 骨になっても愚者は治らないとは世紀の大発見、これにはボクも吃驚だ!」
ずる、ずると――顔だけが見えている。骸骨に腐肉がへばりついたような彼が笑った気がして、ゼイルが身構えた。
「生きてるぞ」
「死んでるはずだわ」
「蘇生してるんだよ。ちゃぁんと、何か弁護があるなら言ってもらわないとね!」ロニがにんまりと笑って。
――まあ、ボクがこうしなくても、『かみさま』になるつもりだったんでしょ?
死肉がげたげたと笑い声を上げた。『のけもの』の羽根を大きく広げさせて、風を巻き起こさせる。
風圧を前に耀子の盾になったライゼが、思わず舌打ちをしてからにやりと獣性をいよいよあらわにした。
「はッは――そうよねェ。『死んでも死ぬか』ってところよねェ?」
上村譲司は、悪人であった。
何の上でもありたがり、家庭の支配者であり、町ひとつを手にして、いよいよ国にすら乗り込もうとした野心のある男である。
――この男が初めて失敗を経験したときに、計画したのだ。この地下書庫にある本がその執念を象徴している。
「実の娘を触媒に、自身は邪神の一部として顕現しようなど言語道断! 問答無用で極刑だよ――閉廷だ、これにて解決! 手段問わずに、この場で処してあげるからね!」
やってみろ、と言いたげな暴風が巻き起こって本棚から書があふれだす。
ばさばさと鳥のように舞う彼らは、町一つをつつんだ呪詛を吸い上げて猟兵たちを狂気の世界に引きずり込むのだ。
ああ、けだものが鳴いている。
『のけもの』を食らわれながら、欲にまみれた人間の顔をして『かみさま』に変貌を始めた。
――自身に服従して逆らわぬ娘の体の血肉になる。最後の『汚染』が、始まろうとしていた。
儀式は、刻々と完成へ近づいていく。冷たい冬の、満月の日であった。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
第2章 冒険
『老紳士が遺した書斎』
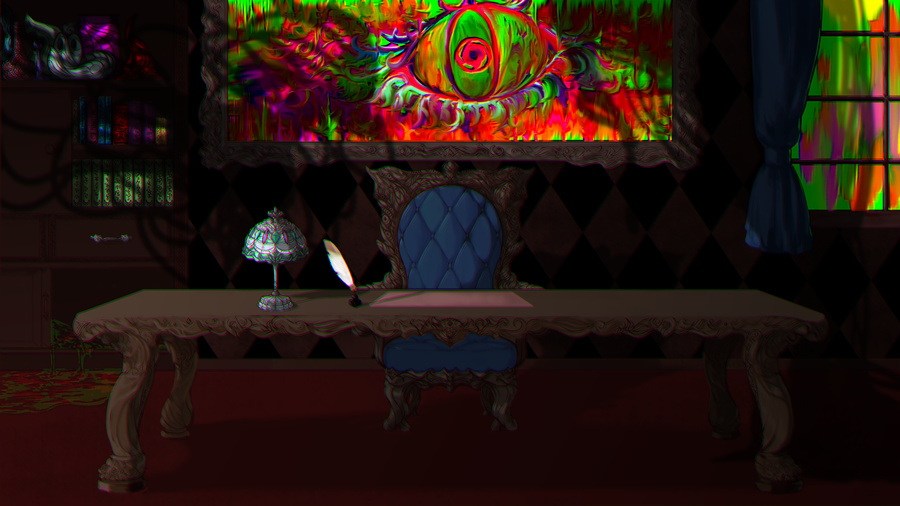
|
POW : 気合いで狂気に耐え、必要な書物と手紙を回収する
SPD : 狂気に陥る前に必要な書物と手紙を回収する
WIZ : 必要な知識だけに絞り、書物と手紙を回収する
イラスト:柴一子
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
――昔、父の書斎だとここを案内されたことがある。
お母さんにも、誰にも内緒だよと教えられてから、それを忠実に守っていた。
本が無数に並んでいるのに、どうにも鉄っぽいにおいがして噎せる私を笑う父がいる。
「なんだ、本当に動物みたいなやつだな」
人間だって、動物じゃないのかな。
幼いながらにそう考えていた。母曰く、父は子供に大人の様な対応を求めてしまうのだという。
小学校二年生の私を相手に「気の利かないやつだ」と怒り、「何も知らないのか。教えられていないのか。お前は犬か猫か」と怒鳴る彼は、最愛の母ですら止めることができずに自尊心を肥大させていた。
「お前に父親らしいことをしてやれなかったから、ちょっと今日はやってみようと思ってさ」
――憎らしいのに。
やはり、私もこの人の子でしかないのだ。親という存在から気まぐれに与えらえるやさしさに、乾いた心が喜んでいる。
そこから先は、覚えていない。表紙の黒い本から、父が一枚の羽根を取り出していたのを最後に「私」の記憶は途切れている。
「やっぱり、犬とか猫みたいだ、お前は」
――どうして?
●
猟兵たちが地下にたどり着いたころ、上村譲司がその昔、とある邪教の男から授かった呪術の知恵を用いて「ある老紳士の書斎」を再現した。
完璧な再現には至らない。
代わりに、鼻腔をくすぐる汚泥のような中途半端に熟した呪詛が、猟兵たちの側面を舞い散る本に様々な言語をかたどる文字列で映し出す。
呪詛に聡い猟兵ならば気づいたかもしれない、それは――君たちの「何か」が奪われたあかしであった。いそいで取り戻さなければ、と焦燥から、あるいは反射的に、または興味本位で本を捲るだろう。
その中身は、君たちの「自我(アイデンティティ)」。
本を開いた合図に、無数の文字列から「猟兵」が飛び出してくる。
――、本を手にしていたはずの両手には、あっという間に何も残らない。
『本』は『けもの』に成った。猟兵の足元に、あるいは前に、後ろに、上に、隣にいる言葉を持たぬ彼らはまぎれもなく「君たち」だ。
――ある獣は唸り、ある獣は鳴き、ある獣は甘えてみせるだろう。
それは、君たちの一部だ。
――ある猟兵の隠したい部分であり、気づかぬ部分であり、傷ついた己自身かもしれない。
人生とは一冊の物語である。ほんの数ページを失えば、物語は成り立たぬ。
――傷ついた獣を抱きしめるのか。襲い来る獣を調教するのか。それとも、何もできずに見つめあうのか。されるがままに噛みつかれるのか。
獣の首に巻かれた羊皮紙が、君たちの自我を取り戻す手紙になる。
手にできたのなら、言葉にして読み上げるといい。読み上げられない仲間がいれば、代わりに呼び起こしてやればいい。そこには、君たちの名が書いてある。
さあ、猟兵たちよ。自分を見失い狂気の淵に落ちる前に、「君たち」を取り戻せ!
*******
・皆様には自分の中の「けもの」を見つめていただきます。
・それは、もしかするとご自分の傷跡の象徴かもしれませんし、昔の自分かもしれません。
はたまた、今の自分かもしれません。
・美しい魚かもしれませんし、傷ついた猫かもしれませんし、醜い毛玉のような野犬かもしれません。
※爬虫類や(奇)虫、クモガタなども好きなのでもし心のカタチなどがそういったものであってもOKです!◎
・その「けもの」の名をご自分の名で呼べるでしょうか。
PC様の成長/現状把握/課題発見程度にご利用いただければ幸いです。
プレイングの冒頭に以下の記号をつけていただきますと、そのようにリプレイを描写させていただきます。
◎→克服、成長。または認知。
△→現状維持。
×→課題発見。停滞。※◎や△の方に名前を呼ばれて起こされますのでご安心ください。
それでは、皆さまの自由で素敵なプレイングを心よりお待ちしております!
プレイングの募集は12/3 8:31から、12/5 21:00までとさせていただきます。
 終夜・日明
終夜・日明
◎
僕は化け物だ。
それは否定しようのない事実で、だからこそ猟兵になったのだと思う。
生命の埒外にある者を世界が選ぶのなら、尚更だろう。
お前は化け物の僕の象徴。
生命を殺すという本能に従い、子供のように無邪気に残酷に殺す《蠱毒》の本質。
昔の僕はそれを受け入れられなかったな。
お前のせいで皆に嫌われるのだと、寂しがりの子供は泣いていた。
お前がいなければ、僕は僕の護りたいものすら護れない……それに気づかなかったから。
僕はもうお前を拒絶しない、生命が欲しければくれてやる。
だから力を貸せ、化け物(レムレス)。
……恐らく一度腹を貫かれるでしょうが【激痛耐性】で耐え、目の前のけものをUCとして受け入れを試みます。
 ゼイル・パックルード
ゼイル・パックルード
×
鋭い目つきで威嚇する様、これは綺麗な誇り高い狼と言いたいけど、どう見ても餓えた野良犬だな
満足できる相手と、満足できる死に方を求めて生きてきた、慣れ親しんだ俺の獣性。
そんなこと今更見せつけられなくても分かってると、それこそ前の俺ならば言えた、はずだ
俺の獣性は今も昔も、変わらない。変われないと諦めたはずだし、それがどんな欲望かも理解している
なのに、今こうして見るけものに違和感を感じるのは何故だ。
直感で分かる、この餓えた獣は俺自身で今も昔も変わらない。
なのに、餓えに満ちた眼に少し違和感を感じる。
……なら変化したのはそれを見る俺の人間性?
その獣の眼は―――人間性を疎んでいるのか?それとも求めて―――
●
ばらばと散った紙たちをかき分ける。
視線を遮る白色の長方形は薄い。しかし圧倒的な質量でもあった。空間を満たし、――真っ白な世界に書き換えられた心地すらあした。
終夜・日明(終わりの夜明けの先導者・f28722)は、片目のバイザーから生体反応も瘴気も消えた二つの姿を認識して「隔離された」と悟る。
一つの空間が呪詛によってそれぞれ隔離されたとみていいだろう。スキャン結果が数字で羅列する限りは、それぞれの猟兵たちの反応が脳波計から計測するに、芳しいとはいえない状況にある。
他人のことを心配している場合ではない。
しかし、日明に出来ることは極めて冷静で在り続け、人類の味方であることである。
ここでブレてしまっては――その体内に宿る『蟲毒』がそれこそ、暴発しかねない。蒼色の稲妻を手に走らせて警戒をあらわにした。
反応が増えている。
どこから発生したのかの判定値はエラーを吐き出しバイザーにどんどんガリガリとノイズが走るようになってきて、使い物にならないのを悟った。バッテリーの節約をすべきだと、目を細めてスイッチに指で触れる。
一度瞬きを挟んで、次に瞼を開いた時には。
「――、お前は」
そこにいたのは、藍色の毛並みと、白い手足を持った狼であった。
ぐるぐるとうなりながら鼻面にしわを無数に作り、指先は緊張しているのか逆立つ毛並みとともに四肢が小刻みに震えている。
感じられる感情は怒りや、いら立ちや、嫉妬――バイザーがなくとも、脳波が見えなくても日明には瞬時で理解できる。
「お前は、僕だな」
見ればわかる。
ただの狼ではなかった。口を開けば、真っ赤な口内が見える。やがてあっという間にだらだらとよだれの代わりに黒い液体を吐き出していた。
楕円の黒い何かが真っ白な空間に溜まりをつくる。まるでインクをこぼしてしまったかのような緊張感があった。
しかし、日明はその獣に揺らがない。これを己だと認めながらもなお、その獣の異常におびえた様子もなかった。
「化け物だ」
事実の羅列をする。がう、と強く狼が黒をまき散らして吠えた。
インクのような唾液が飛び散ってまるで吐血のようなのに、鉄臭いにおいはひとつもしない。代わりに、臓腑を煮込んだような形容しがたい香りがした。
ほほに飛び散る黒い液体に肌を焼かれた。爛れた一部分をぬぐうこぶしにすら、ひりりとした緊張感があった。
「お前は化け物の僕の象徴――そうだろう」
狼は、まだ小ぶりな体をしている。
つやのいい毛皮がどんどん毒素で濁って溶けていく。胸の前などは爛れて腐って見るも無残に筋肉や骨まで見えていた。
それでも狼も退かぬ。一度吠えたきり、態勢を低くして日明を睨んでいた。ぞぞぞぞ、と尻尾にまで緊張が行き渡ってしなる。
日明は、生命に対して特攻ともいえる蟲毒を体に宿す少年である。
けして非人道的な教育を受けたわけではないが、彼こそ戦うために作られた強化人間の工作員である。
毎日を終わらせる夜があるなら、夜明けを作るのが彼の仕事であり宿命だ。それを今は割り切ることができている。
しかし、――手足がまだ伸び切らないころの日明は違う。
「泣いていたな」思い出すような言葉は、どこか懐かしむようだった。
狼がそれを否定するように襲い来る。地を蹴った怒りの化身は、容赦なく日明の鍛えられた腹に噛みついてはぐるりと顎をひねる。
「ッ、ぐ!」
胃の中ごとかき混ぜられて、毒素がにじんで文字通り煮えくり返るような熱さを感じたと思って息を詰まらせる。
そのまま獲物を引きずらんとした狼は、思考の暇も与えないうちに何度も首を横に振り日明の腹を破かんとして激しく攻撃を繰り返した。
日明といえば、その狼に攻撃を仕掛けることはない。腹を貫こうとしたあぎとをがっちりと手で固定して鼻を塞ぐ。呼吸が苦しくて狼は暴れるが、口を離せば解決できることだ――。
「ふ、ッ、ゥ、ッ僕は――ッ、むかしの、ぼくはッ」
無邪気だった。
元より冷静沈着なたちではない。ここまで至るまでに日明が積み上げてきたのは、経験と時間である。
幼い日明は人から嫌われることが耐えられなかった。――当然である。大人たちが「戦うため」に子供を作っても、子供にそんなつもりが最初からあるはずがない。
当然のように愛される子供たちが周りにいたのを自意識で理解したときに、血まみれの伸びきらない両手を見たのだ。
まだ爪は丸いのに、もう真っ赤に染まっていた。
それが当然のことなのだと思っていたし、そうしたいから、そうした。
生命を殺すという本能が、日明を動かしていたのだ。幼いながらに意味はわからずとも、やりたいことといえばそれであった。
残酷に殺し、気が済むまでそうしてきたのに――なぜか誰もかれもに拒まれる。当然といえば当然なのに、成長途中の青い心では理解ができない。
おなじような年頃の子供が積み木遊びを好むように、日明にとっては埋め込まれた本質から導き出した答えが殺しであったというだけなのに。
「寂しがりの子供だった、なぁッ」
狼の鼻っ面を掴んで、言い聞かせるように体すべてでその頭を覆う。抱きしめるように、受け入れるように大人になった体で顔を隠してやった。
子供のころの傷を恥じることはない。あの頃は無知であったのだと、日明は大人になったいまだからこそ理解できる。
「お前がいなければ、僕は僕の護りたいものすら護れない」
ふさふさの耳に語り掛けてやる。
いい子だ、良い子だと――あの頃誰にも与えてもらえなかった親愛を込めた掌で未熟な頭を撫でてやった。
「僕は、ッもうお前を拒絶しない、生命が欲しければくれてやる」
切れ切れの言葉をしっかりつむごうと、ゆっくりと語り掛けてやる。逆立った毛の流れをただすように、鼻を抑えていないほうの腕で背を撫でてやった。
首に巻き付けられた羊皮紙を握り、強く瞼を閉じて宣言する。
「――だから」
レムルス
力を貸せ、化け物。
【《蠱毒》顕現/舞台脚本『破滅人形』】。
狼が口をいよいよ離したころに、その毛皮があっという間にほどけた。溶けだしていたからだから、男の姿が雪崩のように生み出される。
――日明に瓜二つの顔は、あどけない表情で眠っていた。
足元に転がった殺すための力はどうにも幼い衝動のままなものだから。思わず、日明もその上に重なり合うような形でもたれかかり、微笑みともせき込みともつかぬ声が漏れる。
「まったく、手のかかる化け物だよ。僕たちは」
ねえ、そうだろう。
――終夜・日明。ふたりの一つの名前を唱えて、狂気のひと時から夜が明けた。
●
さて、ゼイル・パックルード(囚焔・f02162)が己の獣と対峙した際には、周りの姿はちっとも見えなくなっていた。
どういう絡繰りかどうかなどを気にしていては、目の前の獣にのどぼとけをかき切られそうなほどの殺意を向けられている。
己の一部分が出てくるときいて、さあどれだけ良いものが出てくるものかと半信半疑に待ち構えていたところでやってきた獣は、痩せた四つ足である。
「綺麗な誇り高い狼と言いたいけど、どう見ても餓えた野良犬――ってとこだな」
野良犬というのは、たちが悪い。
ゼイルの故郷である世界でなくても、野犬は恐れられるべき存在だ。数々の疫病を持ち、今のところ最新の医術を用いても治癒できない病を人間に噛みつくことで感染させることもある。
剣を構える。犬相手に、とはどうしても思えなかった。
まだらの毛色である。まるで体が燃えているような色合いであった。茶色の体に黒い染みが波打つように刻まれていて、金色の瞳は煌々ときらめき火花すら放ちそうである。
この世の生き物とは思えぬ唸り声は明らかな警戒の色をはらんでいた。うう、ううう、と唸る口からは唾液と鼻息があふれている。むき出しの歯茎がより凶悪な牙を主張していた。
「――?」
ある程度。ゼイルの中では、己の獣性というのが理解できている。
白い牙で「俺は武器を持っているぞ」と主張する姿などは、ゼイルの今までの生き方と同じだ。
これが側面であるといわれても理解できるはずであった。なぜならば、ゼイルは確かに飢えた犬のように人を殺していたのである。
満足できる相手を、満足できる死に方を求めて自棄ともいえる戦いを挑み、何度も死線を超えて若さのまま走ってきた。
今更見せられても「ああそうだろうな」と斬り伏せていたぶり、今までの己と今の己の強さの差を目視で確認できたことに喜んでいただろうし、満足もあったはずである。
現に、今見えている犬の姿に抱くのは恐怖や共感よりも――ずっと遠い感情であった。
「っ、と」
思考に耽るゼイルに怒り狂う獣の牙が襲い来る。痩せているのに体を使うのには慣れているからか、飛び出してきた犬の速さは恐ろしいものであった。
剣ではじけば「ぎゃん」と醜い声を上げて転がるのに、たちまち起き上がってまた襲い来る。
――俺はこういうやつだった。
純粋に殺すことだけに体を使い、命を燃やし、心を動かしてきた。
ゼイルの生き方はそれしかなかったわけではない。彼の興味や好奇心さえ外に向けば、たとえ傭兵の父のもとで育ったとしても別の生き方があったはずである。
だというのに、一つ覚えの殺人に執着するのをやめられなかった。
人を殺さなければならない極限状態にいたわけでもないのに、進んでその道を選んだことに後悔はない。
なのに、なぜこの犬の相手をするのが此処まで「気持ち悪い」感覚になるのだろうか。
「ち、ィ――ッ」
しつこいんだよ、と叫んでその顎を蹴り飛ばす。
痩せた犬の体はあっけなく吹っ飛ばされるのに、器用にもゼイルの足首に歯を滑らせた。ナイフで切られたように血が飛ぶ。
違和感ばかりなのだ。
言われなくても理解できる。ほとんど直感で動き、見境なく食ってかかるゼイルの衝動の具現であることなど、少しじゃれあうだけでもびりびりと感じられた。
傷を炎で塞ぎ、あっという間に皮膚同士をつなぎ合わせてやるゼイルとは対照的に、まったく獣は傷を治すそぶりがない。
だらんと真っ赤な舌は血で染まっているのに、息を切らす顔はどこか笑っているようにも見えた。
「気色悪いやつだな」
――あれ。
自分の口から自然と出た言葉だった。
思わず手の甲で隠すように己の口を覆う。
なぜ「気色悪い」と思ったのか? 自分は「こういうやつ」だったのではないか?
――けものは笑っている。
どんどん口を広げて、牙を見せつけるように笑っている。
「お前」
言葉がわかるとも思えないのが不思議だった。
ゼイルは確かに殺人を好むが、良識や「世間」というものに疎いわけではない。
それぞれの世界にはそれぞれの秩序があり、悪というのは混沌であるために秩序を知る必要があったのだ。
何もかもを気にせず殺して回るのならばそれこそ、害獣として駆除されるのは明らかである。だから、ゼイルは「悪らしく」生き残ることを選んだ。
「あ」
――そう。
選んでしまっているのだ。
獣がとびかかってきたのに気づかなかった。
弾丸のような速さでゼイルの腕に噛みつき、縫合したほうのそれを引っこ抜いてやるといわんばかりにぶんぶんと首を振る。
「ッで、ぇッ!?」思わず言葉が漏れた。やせぎすの獣の体が生み出す力は、ゼイルの体を浮かせてしまうのである。
鍛えられた少年を終えた青年を振り回す力に圧倒された。対処をする前に地面に何度も体をたたきつけられ、引きずられる。
――そう。
飢えた少年は、大人になってしまった。
大人になった彼は、少年である彼のことを「俺だ」と言ってやれない。
あさましく、はずかしい生き方をしているのは明らかだったのだ。見境なく人を殺すことにこだわってきたが、ゼイル自身は彼の人生を「生きる」ためにあったわけではない。
死ぬために生きてきた。そのはずだったのに、――ただただ、未熟な凶暴さを前には理性的な大人の悪らしさなど対応できるはずもなかったのである。
恥すら認めねばならぬ時期が来ているのを、ゼイルは理解できただろうか。獣が怒りと好奇に満ちた瞳でぼろ雑巾のようになったゼイルを見下ろしていた。
――人間性を疎んでいるのではない。
――その「強さ」が欲しいのだ!
「ゼイル」
獣が凶悪な歯並びを魅せて彼ののどぼとけを食いちぎろうとしたときである。
がぱりと開いた口内をさらした姿は霧散した。は、と気づいた時には肺になってい消えていく。
「ゼイル・パックルードさん」
最初に獣を吹き飛ばしたときである。首に巻いた紙が失われていたことにもゼイルは気づけないでいた。
己の獣性と戦う彼を、ようやく起き上がる気力が体に廻った日明が援護に入ろうと呪詛の結界を解く「名前」を呼ぶ。
ぱんと弾けた音がして――世界は現実に戻っていく。ゼイルが急いで身を起こして、汗だくの体に走る激痛にうめいた。
「ッ俺、は」
「皆同じような状況です。損傷も。――戦えますか」
「戦える、けど」
子供であることを失った。大人であることを得ていた。
なのに、まるで牙で食い込まれるように教えられたのは――痛みどころか、じくじくと内側から熱せられるようなもので。
何故か刀をうまく握れていない気がするのだ。ずっしりと確かな質量がある大太刀を、今一度確かめるように握りなおす。
こんなにも自分の掌は大きくなっていたのだと、彼は知るだろうか。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 エミリア・ジェフティー
エミリア・ジェフティー
×
肉食獣のような呻きが背後から聞こえた
振り返った先にいたのは、胸に大穴が空いた全身血塗れの子羊
身を低くして睨む瞳を無意識に見つめ返していたら、知らない光景が脳裏を過って…
焼け野原になった街
鉄屑と化したキャバリア達
馬鹿みたいに大きな怪物
そいつが大口を開け、どこか遠くへ光条を放った次の瞬間
怪物の右胸が弾け飛んで
誰の物かも分からない声が頭の中に流れ込んでくる
"着弾!ですが、あの位置では人質達は…!"
"…やった…のか。俺が…娘を…?"
"奴さんまだ動くぞ!気をしっかり持て中尉!"
『…お父さん、お母さん!』
…今の、は
けものは怒りと侮蔑と…少しの羨望のこもった目で私を見るだけ
あのけものは…私の何を知ってるの
 鳴宮・匡
鳴宮・匡
◎
本を取る手に、躊躇いはない
どんな自分も“自分”だと認めて
それを疑いも隠しもしないと決めたから
――俺にも、俺のかたちはわからない
でもそれが“傷ついた”自分だというなら
一心不乱に俺自身を傷つけるんだろう
ああ、そうだよな
自分が生きるために“自分”を捨てて
痛くなんてない――“そんなもの初めからなかった”と言い張って
痛いのに、苦しいのに
“なかったこと”だから誰にも気付かれなくて
誰にも――自分にも、受け止めてもらえなくて
行き場を、なくして
黒い海の底に、沈むしかなかった
……俺のことを、許せなくて当たり前だ
それを――受け止める
受け止めて、名前を呼ぶよ
――ごめん
もう、切り捨てたりしない
ちゃんと、連れていくから
●
肉食獣のようなうめきがして、勢いよく振り返った。
エミリア・ジェフティー(AnotherAnswer・f30193)は相棒であるセシャートとの連絡が取れないことを確認して、真っ先に自衛を試みる。
高濃度の認識阻害汚染を受けている。相棒との交信履歴は、そこで止まってしまったのだ。今のエミリアはほとんど丸腰といってよい。
「――ッ」
生存本能と好奇心のはざまで、己に近づく何かへ躊躇いなく振り向いた。
たかだか肉食獣相手ならば念動力でどうとでもできるかもしれない、と判断できていたのに、さあいざと振り返った視線の先にいたのは前を向いた飢える目ではない。
「羊、――?」
エミリアの目の前に現れたのは、胸に大穴を開けた羊である。
そもそも、草食獣が「立ち向かう」ことなど通常あり得ないのだ。
彼らはそのために常に身を軽くしており、食べるものも質量がほとんどない草である。どんどん消化して常に垂れ流すのは獲物に襲われても即座に軽やかに走ることができるための機能であった。
そう、逃げることに特化している彼らは、敵意を向けることがまずない。
身を低くしてこの異常な獣に警戒する。ぶるる、ぶるると鼻を震わせる羊を相手に、エミリアは冷静であろうとしていた。
顔の真横に着いた目は、頭を動かさずとも自分の真後ろを認識できる。羊は耳が大変よく、恐らくエミリアの緊張した息遣いも聞こえていた。
白い空間に、どす黒い血だまりが広がっていく。
――怪我をしているから、警戒しているの?
エミリアの側面であるというのならば、「怪我をしたことがない」などということはない。
実際、生きていれば何らかのストレスは受け、失敗を恥じ、時には武装をメンテナンス中のワイヤーに腕をはじかれてみみず腫れを作ることだってある。その「失敗」の集大成がこの羊だというのならば、理論的には納得もできた。
しかし、明らかに目の前の羊は「怒り」でいっぱいである。
「っ」
ジ、と視界にノイズが混じる。
まるでこめかみを殴られたような心地がした。緊張に耐えかねて酸素が薄いのかと考えていた時に、足元の真っ白が――荒野に代わっている。
「えっ」
少女の声に、動揺が走る。
顔を上げた先には、無数のキャバリアの死骸があった。
鉄くずとなった彼らは大きな体をばらばらにしてよこたわっている。遠くの風景を顔を持ち上げると同時に、理解しようと試みた。
――街が、壊されている。
ビルをなぎ倒す大きな怪物がいた。「馬鹿みたいな」大きさのそれは、容赦なく場を混沌に変えていく。飛び散るがれき、吹き飛ばされる命、爆ぜる空が赤く染まって、悲鳴、悲鳴、悲鳴。
「何」
――一冊の本は、猟兵たちの人生を綴る。
開かれた本の中身をエミリアは読んでいるのだ。「あったこと」を見ているだけなのに、この光景を見せつけられているような気がする。
覚えていない。ショートヘアの髪をかき混ぜるように、優秀な脳の詰まった頭を撫でた。
怪物が大きな口を開けている。街ひとつ飲み込もうとするような無数の牙は、花弁の展開のようにも思えた。ぐわりと真っ赤な口内が見えて、どこともつかぬ方角に光条を走らせる。
光の速度は音より早い。ぴか、と光った視界が真っ白に一瞬だけ染められて、風圧とともに轟音が響いた。
「何なの」
エミリアは、体を乱暴に風で撫でまわされても、動けないでいる。体の真横にがれきが落ちても、驚くことすらなかった。
怪物の右胸には、大きな穴が開いている。
――着弾! ですが、あの位置では人質たちは……!
エミリアの足元に、スクラップと化したキャバリアの無線装置が転がっていた。
――……やった……のか。
ざ、とノイズの走る交信に、聞き覚えがある。
羊は、群れでありたがる動物だ。
――俺が、……娘を……?
群れから引き離されると酷くストレスを感じ、暗いところから明るいところにいきたがる家畜である。
危険に対する反応は第一に逃亡であるが、第二に――家族を持った雌に見られる傾向があった。ぶるる、ぶるる、と羊が鼻を鳴らす音にカツカツと鋭い蹄の音が混ざる。
「ねえ、――これは何?」
――奴さんまだ動くぞ! 気をしっかり持て、中尉ッッ!!
ストレスに直面すると、羊は真っ先にパニックを起こし逃げたがるのに。エミリアの頭の中で響く蹄の音は、けしてそれを許さない。
怒り、侮蔑、――ほんの少しの羨望を孕んだ目があまりにも強烈に脳裏に焼き付いている。崩壊と混沌を交えた世界が次の嵐を巻き起こすのを、ただじっと見ているしかなかった。
『――お父さん、お母さん!』
悲痛に叫ぶ迷子の声の正体すら、誰のものかわからないままで。
●
本を取る手に、躊躇いはない。
鳴宮・匡(凪の海・f01612)が今までの彼ならば、きっとこの紙たちを視界の邪魔だと思うことはあっても、「手にする」という行為には至らなかっただろう。
奪えるものがあるなら奪ってみろとすら思っていたかもしれない。亡くして困るものなどもうないのだからと、捲ることもなかったかもしれなかった。
――もう、今はそうではない。
自分という存在を有象無象の一部と考えなくなった。世界が球体であるというのならば、どこの「点」も中心になるように、匡の選択は「その中心であること」であったのだ。せめて自分の両腕を精一杯伸ばした視界では、彼が世界の中心で在れる。それが、たとえ赦されなくても――自分で赦せなくても、そうあろうと選択した。
明日消えてもいい命だ。だけれど、それは明日じゃなくてもいい。
――だから、向き合う覚悟ができたのかもしれなかった。
「お前は」
匡の目の前に現れたのは、海獣、イルカである。
明確にクジラとの差が大きさでしかないと言われる彼らであるが、非常に高度な知能を持っていた。一度も泳ぐのをやめないで息継ぎを忘れず海を生きる彼らは、右脳と左脳を交互に眠らせることができ、片目を閉じながら泳ぐときは「どちらかが」寝ているときであるというのだ。
非常に高度な生き物である。しかし、肺呼吸であるので風邪をひくし、やや人間のような生態をしていた。人間とおなじだけの体温を持ち、脱水症状にもなるし、時には仮病をしてイルカショーに酸化したがらない個体もいるほどである。
「わ、っと」
ケケケケ、と威嚇の声を隠しもしない声を漏らしながら、尾で匡を振り払うようなしぐさをした。水が無くても呼吸ができるイルカの皮膚はひび割れが目立っている。
人懐っこくて好奇心旺盛な彼らは、人間の次に脳の質量をほこり、非常に頭がよいとされているのだ。だから、匡の考えていることを悟った――それこそ「視ている」のだろう。
「ごめん」思わず匡がそんな返事を返しても、イルカは不機嫌にくるくると床を周り、滑る。
ああ、そうだよな――と納得してしまったのである。
イルカが匡を嫌うのも無理はない。一生懸命にぶんぶんと尻尾を振って、匡の体をなぎ倒そうとする顔が悲哀に満ちているのだ。何をいまさら、どうして触るんだと言いたげな彼に、思わず足が止まる。当たりにはいかないが、すれすれでかわす様にして体を動かしてやっていた。
「そうだよな。――赦せなくて、当たり前だ」
匡は、結局のところ「自分で自分が許せない」のである。
自分がやってきた今までを知っている。そんな手段をとらなくてもよかったかもしれないのに、生きるために「自分」を捨てて、心の底でもう嫌だと泣いている自分に蓋をして、その首を絞めてきた。
何も言わないでくれ、これが精一杯なんだ、俺にはそんな資格がない、こうするしかないんだ、そんなものはじめから持ってないだろ、なかったことにしてくれ、何も考えるな、だってそうしたら――生きるのが苦しくない。息継ぎもいらない。どうせ普通に生きても八十年で死ぬような命なんだから、何も考えないで、沈んで、沈んで、海の底みたいな無意識に閉じ込めてやるから。
「全部、俺が勝手にやったことだ」
問題の先送りでしかなかったのだ。
匡の「今まで」を作ってきた世界はそれでもよかった。
傭兵の間では隣で飯を食った仲間が死ぬことなんて言うのは当たり前だし、いまさらそれに対してどうのこうのなど思えない。だけれど、「そんな世界」だけが彼にとっての「海」ではなかったのだ。
群れからはぐれたイルカは、大きな海に出た。
もとより好奇心旺盛なイルカは、ずっとずっと泳いで、泳いで、新たな群れと出会って受け入れられていくうちに、広い世界を見ただろう。海を変えれば泳ぐ仲間も変わり、小魚すら色が変わる。海の温度も違うし、その透明度すら異なっているのに気づいたのだ。
だから、今までの歴史がいかに短くて、間違いだらけだったのかを理解した。
生き恥だなと己を嘆いたこともある。
無意味に「泳いできた」だけの自分の若さを受け入れられない時だってある。俺の今までは何だったんだとイルカからすれば恵まれた皆を見て、恥ずかしくなった時だってあった。
だけれど、ああ――誰にも気づいてもらえなくてもいいと思っていたのに、イルカの周りにはイルカよりも賢い命がいれば、イルカよりずっと小さな命があって、きらめいている。
仲間になろうよとイルカのまわりを泳ぎ、海の王国に連れていく彼らと。
頼れる仲間たちと、――ずっとそばにいたいと願ってしまった光を見たときから、イルカはもう海の底にいることはできなかったのだ。泳ぎだしてしまっては、止まれないのだから。
「ごめんな」
イルカのしなる尾を抱きとめて、確かな質量に掌で撫でてやる。
「もう、切り捨てたりしないよ」
何度かその尾を叩くように撫でてやりながら、イルカの瞳を見る。つぶらな黒が潤んでいるような気がした。
「――ちゃんと、連れて行くから」
おいで、と尾をやさしく地面に置いて、名を呼んだ。
失われた温度とともに、――鳴宮・匡はひとつになる。
●
「エミリア。――エミリア・ジェフティー」
どこかで聞いたことがあるような声が脳に響いて、蹄の音が遠ざかる。は、と意識を戻したときには書斎の中にいた。真っ赤な絨毯の向こうに、コンクリートと犠牲者の歯が埋められているのだっけ――。
「あ、ッ、私は」
「戻ったみたいだな」羊皮紙を手にした匡がその名を呼んでやったのだ。「立てるか?」としゃがみ込んで聞く彼の声で、エミリアは自分がすっかり膝をついていたのを知る。
愛機との接続も再試行され、今は無事に――エミリアの感情すら抑制できるよう再調整されている。念動力を操る体に弱い電磁が走ったような心地がした。
「皆同じような状態になってる。だけど、休んでる暇はなさそうだぜ」
『のけもの』は、書斎から姿を消している――。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 琴平・琴子
琴平・琴子
△
けもの→腹を負傷した龍の子
琴は龍を模した楽器だと言う
その名を持つ私は龍の子、か
唸るその姿は触れるな、近寄ると言わんばかりの警戒心
触れないと治せないのに、近寄らないと分からないのに
友も要らぬ、一人で良い、独りで良いと思って意地を張る
本当、私によく似ている
いつまでそうしているつもり?
その傷を負わせた奴に仕返しでもしないと気が済まない?
ええ知ってる
けれどそうじゃない
「許さない」のでしょう?
自分よりも弱い者を狙って虐げた輩が
今ものうのうと生きて
手を出しているかもしれない事に
その傷を誰かに言わないなら
自分で舐めて治しなさい
頭を撫でてくれる人なんて居ないのだから
ああでも
何時か気を許せた人に言えると良いね
●
腹に傷の入る、龍の子がいる。
琴平・琴子(まえむきのあし・f27172)は、その姿をしゃがみこんで見つめていた。
なぜこの龍が己の一部であるというのだろう、と考えれば理由は直ぐに至る。琴なのだ。
琴というのは龍を模した楽器である。磯にわたる龍を模したそれは、琴子には縁が遠いようで、ある種「深すぎる」ものであった。かさぶたを見つけてしまったような気持ちになって、目を細める。
その視線がうっとうしいのか、龍は甲高くも幼い悲鳴を上げて威嚇をしてきた。きゃあんと啼いた幼い体は、小さな手で精一杯真っ白な地面を掴んで体をうねらせている。美しい啼き声も怒り任せにはじけば酷い騒音になってしまうのに、もったいないなと琴子も思う。
「――いつまでそうしているつもり?」
唸る姿は、傷に怯えてしまっているのだ。
触れるな近寄るなと怒るのも無理はない。生命の防御反応であるのに、どうにも琴子にはまるで赤子の駄々を垣間見てしまったような心地がした。
琴子とて、まだ九つといえど己の自意識をしっかりと持った少女である。
世界を見るために足は常に前を向いて、帰るための不屈のこころで歩み続ける気概がある。親に恥じぬ「よいこ」である彼女は、幼稚さに呆れの目をしていた。
理解できるところもあるから、余計に「どういう顔をしたらいいのか」わからない。
「触れないと治してやれないでしょう」
こっちにおいで、と両手を広げてみても。五指に怯えてきゃああんと鋭く鳴いて転がり、体をくねらせて悶える龍の姿などは思わず目をつむってしまう。何と情けない、と言いかけて――客観の大事さを幼い心で学ぶことになってしまった。
きっと、クラスで琴子を嫌っていたあの子も、どの子も、こんな気分だったのだ。
友も要らぬ、一人で良い、独りで良いのだと強がる女の子のことを誰がかわいらしいと思うのだろう。言葉も交わしたことのない誰かのことを誰が理解できるのだろう。
受け入れられないからといって悪口を言われるのはいささか安直な結末だったと思うが、言いたくなってしまうのは今の琴子が身をもって体感している。
――恥ずかしい子だ。
「その傷を負わせた奴に仕返ししないと気が済まない?」
龍が、カァッと口を開いた。
「ええ。知ってる。そうじゃない」
ようやく話す気になったのね、としゃがんだ膝に肘をついて、両手で自分の顎を支えた。龍を見下ろす翠の瞳は、冷静である。まるで、子を咎める親のようでもあった――。じくりと爪先が痛む。
「『許さない』のでしょう?」
――自分よりも弱いものを狙って虐げた輩が、今ものうのうと生きていて、手を出しているかもしれない事に。
龍の瞳孔が細くなっていたのに、丸く形を作っていた。威嚇の現れよりも興奮であることのほうが大きいだろう。翠色の怒りは、然りと肯いているようでもあった。
――あの子も悪いんじゃないの、と言われることのなんと癪なことか。
確かに、絶対に非がないということは琴子を含めた命すべてにあり得ない。
命同士がこの狭い世界に密集するのだから、時に肩をぶつけてしまうこともあれば、大きな声で歌うのを煩わしく思われることもあろうし、うまく琴が弾けないことをどこかあきらめられた目で見られることもあるだろう。しかし、それは――「悪いこと」ではないのだ。
其処まで至るには、余計な道を辿らなくてはならない。琴子が「小さな大人」になってしまったように、いばらの道を歩かねば理解できない世界であろう。「その傷を誰かに言わないのなら、自分で舐めて治しなさい」戒めるように龍に言ってやった背中は小さい。
ひげをふわふわと浮かせていた龍が、「こと切れた」ようにへたりと長い二本を地面に着かせてしまった。
「頭を撫でてくれる人なんて居ないのだから。当然でしょう」
何をへこんでいるのよ、龍よりも「ちょっと先」を知っている琴子が呆れと笑みの混じる声で立ち上がる。
同じような場所がじくじくと痛む気がしてしょうがなかった。片手で未熟な腹部を抑えながら、いよいよ龍を置いていこうかと踵を返す。
「知らないわ。自分で決めて歩きなさいな。そうしてきたのでしょう」
きゅーきゅー、と情けない声を小さく上げた龍に聞こえるように声を張ってやる。しゃんとしなさい、と言いたげな声量に、いよいよ蛇めいたからだが小さく委縮した。
やがて、ずるずると腹の傷をかかえながら、龍は蛇行を繰り返して琴子のあとをついてくる。
呪いのように自分に言い聞かせた言葉でもある。
だけれど、それに恥じぬような女性であり、駆けつける王子様であろうと――ひとを助けようとする姿勢を恥じたことはひとつもない。
間違っていない志だと、知っていた。
「――琴平の子なのですから」
ああ、でもいつか。気を許せた人に言えると良いね――。
大成功
🔵🔵🔵
 シャト・フランチェスカ
シャト・フランチェスカ
△
襤褸布みたいな猫だった
白かったのか模様があったのか
変色した血や汚泥にまみれて
伸び過ぎた爪では毛繕いも出来まい
哀れなけもの
僕だけを視て
心を教えて
僕をちゃんと証明して
僕が汚くても肯定して
猫が言ったのかもしれない
僕の口が言ったのかもしれない
覚束ない足取りで猫が歩んでくる
抱え上げれば当然のように
牙が、爪が
肌を食い破った
紅い色を見ていると
きみも落ち着くでしょう
それは生きている色だもの
いたくないよ
ちっとも、いたまない
離さないで
離さないで
左腕の硬化した皮膚
繰り返し抉ったその証
【僕】の爪が引き裂くと
猫諸共に己の身体も炎上する
離すものか、【シャト】
他の誰に頼めるって言うの?
燃える、燃える
一緒に燃えて
愛して。
●
襤褸布切れのような猫であった。
錆びた色の細い猫は、うるうると喉を鳴らし広くひげを伸ばしている。
そのひげの長さが均等ではないことを、シャト・フランチェスカ(侘桜のハイパーグラフィア・f24181)は知っていた。
色が混ざりすぎていて、右足は白いのに左足は黒い。体は赤いのに、どこかベースに茶色が混じり、やはり染みのように黒がひろがっているはずが、ところどころ修正液を垂らしたような白が目立つ。
伸びすぎた爪では毛づくろいもできない。とぐ習慣がないわけでもあるまいに、――ああ、そうだった。このけものはきっと。
「哀れなけもの」
樹下で眠らされて、昇ることも許されていないのだ。
シャトは、桜の精である。尤も、本人はその在り方を種族や年齢や、性別でくくるのを嫌っていた。幻朧桜から確かに生まれた彼らは転生をつかさどる能力を得ているが、シャトが固執し、魅せる能力は――ひとえに、「創作活動」である。
「僕だけを視て」
ひたり、猫の前に両ひざをついた。美しい上着が地面に広がるのも気にせずに、悪戯な桜の花弁は唇に上機嫌を乗せる。
「心を教えて」
猫を意識して口を開く。同じく猫も、口を開いた。
「僕をちゃんと証明して」
おおよそ、――他人に求めていい感情ではない。
「僕が汚くても肯定して」
そんなことはとっくに理解しているのに、やめられない。猫が言ったのか、シャトが言ったのかもわからないままにお互い口を開いて、真っ赤な言葉を塗り重ねた。
よたよたと歩いてくる猫は、ひげが切れてしまっているのだ。平衡感覚を失ったかのけものは身軽のはずだった体をひきずるように、右に左にとぶれて、シャトの膝までやってきた。
それを、やさしく抱き上げてやる。確かな質量を感じて、――思ったよりそれが軽くて、ころころとシャトは穏やかに笑う。
当然のように猫は、爪を立てシャトの腕に赤い傷を作る。それから、躊躇なく肌を食い破る牙を突き立てた。
ネコ科の牙というのは、引き裂くためにできている。鋭い二本の牙は、窒息させるために使われるものだ。だが、此度は違う。純粋に、シャトを傷つける為に遣われたのである。
「いたくないよ」
やさしく、ささやいてやる。
煩わし気に猫が耳をぴるぴると二度ほど揺らした。うううう、と激しく抵抗するようなうめきすらいとおしくて、シャトは恍惚とした瞳のままで「いたくない、いたくない」と子供をあやす様な温度でゆらゆらと腕と体をゆすってやった。
猫が言ったのか、己が言ったのか――どちらも求めすぎる言葉であるにはかわらないのに、それをまるで赦すかのような手つきである。桃色の髪の毛が猫の背に垂れた。口づけるように背中を嗅いで、ちなまぐささにまた笑みを深めるのだ。
「紅い色を見ていると、きみも落ち着くでしょう」
――生きている色だもの。
何度も確かめたのだ。それは若い心が考えうる限りの自殺ごっこで知ったものだった。
左腕の、すっかり固まった皮膚がある。ケロイドのようになってしまったみにくい傷痕を、猫の鼻が探り当てた。がぶ、と強く噛みついてまた傷が増える。
「いいよ」猫の頭を撫でる。離さないで。とその痛みを許していた。
ワタシヲハナサナイデ
――【華 焔 綴】。
ぼう、ぼう、ぼう、と傷口からシャトの体が燃えだした。桃色の髪の毛を照らす赤色の炎に滴る赤色をまるで油のように捧ぐのだ。あっという間に猫とともに、シャトの体は燃え広がる。血の痕だけ、ぼうぼうと燃えていく。
「離すものか」
――愛して。
そう、これもまた「創作活動」なのだ。
人生は物語である。
一つのお話を綴る美しき火焔のシーンをまた刻んだだけに過ぎない。
だからこれは、成長でも、後悔でも、なんでもなく「そうである自分」を確かめるだけの、自殺ごっこに違いない。ナイフを腕に滑らせたところで、手首を落としても死ねないように。
さて、桜の樹の下に眠る『彼女』は確かに猫だった?それとも、その猫が誰だった?
抜け落ちた文字はこれで元通り? それとも、乱丁落丁のあるものがたりのお問い合わせは地獄行き?
これからまたインクで綴るものがたりは本当に黒色のものがたりだった?
「シャト」
燃え上がる愛の熱量のなかで、たしかに――名を呼んだ。
大成功
🔵🔵🔵
 冴木・蜜
冴木・蜜
◎
ふと視線を落とせば
傍らで蹲る薄汚れた白衣
人型が融けかけた震えるけもの
……私に毒は効きませんよ
それを知っている
あの時彼に使われ数多を蕩かした死毒
私も忘れていました
いいえ、忘れたふりをしていた
耳にこびり付いた悲鳴と苦悶の声が恐ろしかった
でも同時に心地よかった
毒であることを望まれて
そのように使われることが心地よかった
死毒としての本能、けものが私の中にいる
それ何より恐ろしかった
だから蓋をしたのでしょう
それでも
どんなに目を背けても
あの時の毒もきっとわたし
私は結局
どこまでも死毒なのです
この事実は変えられない
私は死毒であるわたしを認めた上でなお
人を救う毒になりたい
だから、――。
借り物ではないその名を、呼ぶ
●
圧倒的な呪詛とその質量を前に、特にどうこうしてやろうという気持ちよりは、はたしてどうしたものかと思った程度の動揺のほうが巡るのは早かった。冴木・蜜(天賦の薬・f15222)にとって、この程度の呪詛を前に命の危機を感じることはない。
――だが。
目の前がさすがに真っ白に染められたときは、まばゆい世界に目をしぱしぱとさせられる。眼鏡をずらして目をこすろうとしたが、間もなく視界に「なにもない」ということを理解して、やめた。
ここはさしずめ、本の中である。
それよりも、傍らでもごもごと何かが動いていることが気になった。
白い世界と同化してしまっているが、輪郭から察するに、それは白衣である。
白衣の中で何かがうごめいているようで、じっと見下ろした。
視線に気づいたのかごそごそとした動きを止めた白衣が、じんわりと黒色の何かを溢れさせている。
「私に毒は効きませんよ」
否定するわけでもない語調で、諭すように。びくりと白衣が縮み上がって、観念したかのように顔を出した。
ヒョウモンダコである。
肉食性のタコであり、共食いをするほど食欲が旺盛でありながら、人間でさえ近づかれれば噛みつくほどの攻撃性を持ち、他のタコ同様に体色を素早く変化させ時に体をヒョウ柄模様にして警戒をあらわにする彼らは、スミこそあまり吐かないうえに泳ぎの不得意な種族である。
スミを吐き散らかしながら素早く逃げる必要がないのは、彼らには強力な毒素が味方しているためである――フグにも含まれるが、自然界ではマイトトキシンに次に恐れられるテトロドトキシンだ。
身の危険を感じれば噛みつき、唾液を吐いて注入する。難治性の皮膚潰瘍を起こす猛毒は全身に潜んでおり、食しても危険とされていた。
――己が猛毒であることを知っているがゆえに、逃げる必要のない彼らである。
それなのに、この蜜の一部分を切り取ったけものは震えていた。何を恐れるのか、と問われれば蜜自身が言葉を持たぬタコの代わりに応えるだろう。
「――死毒が、恐ろしかった」
タコは、己の毒がまさかそれほどのものだとは思っていなかったのである。
ずうっと、その事実を忘れていたふりをしていた。
何もかもに怯えているようで、その実、もう蜜は己の存在というものに割り切りを持っている。
海の中ですら毒性の強すぎる力を持ったヒョウモンダコは、襲われても返り討ちにしてしまえる。
悪戯につつこうとするカニにやり返して、その体をむさぼってやることだってできるのだ。だから、海底でゆっくりと這いまわっているだけでよい。
それは――「彼」に求められ、毒であることを望まれた蜜の生き方と同じだ。
耳にこびりついた悲鳴と苦悶の声は恐ろしい。蜜の毒をおそれ、怯えた声は痛ましい。だけれど、同時に心地よかったのだ。己の在りたいままに在れるし、それを求められることのなんと嬉しいことか。
悩む必要もないままに、死毒としての本能のままに溶かしてしまえばよかった。なあんだ何も悩まなくていいんじゃないか、と溶けかけた自分を恐ろしく思ってしょうがなかった。
「だから、蓋をしたのでしょう」
それではいけないのですよ、と体をまるめてタコに向き合う。
ヒョウモンダコはちかちかと警告色に輝いていた。海の底でもないのに体は濡れていて、まるでひとしきり泣いているこどものよう。
「この事実は変えられない」
ゆるく首を左右に振った。
過ぎてしまった過去を後悔するなということではない。向き合うべきは未来であり、過去のことは「認める」しかできないのだ。
確かに過去の蜜は研究精神に溢れ、友人に依存し、暴威を振るい、振るった後でなんてことをしたのだと自覚してしまう愚かさがあった。だけれど、愚かでいいではないか。
大人の蜜が、過去の蜜の象徴である――罪の八本足に諭す。
「それでも」
目を背けてはいけないのだ。
自分が今まで何をしてきたのかを考えて、悩んで、哀しんで、嘆いて、途方もない過ちがあって、今がある。
掌を向ける。どろりと垂れた黒い液体が、ヒョウモンダコを覆うように水たまりを作った。
「私は死毒であるわたしを認めた上で、なお人を救う毒になりたい」
だから、あなたが必要なんです。
残酷なまでに突きつけるのは、未来への道だけだった。
――怯える八本足だって、私なのだから。
借り物ではない名前を呼ぶ。一緒に行きましょう、とささやく。
ゆっくりと垂らしたスミのような黒に、タコがゆらりと溶け込んだ。
大成功
🔵🔵🔵
 ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
嵯泉/f05845と
×
おまえがいるって聞いてない……
でも良かったかも
一番見られたくないけど、一番信頼出来るから
痩せぎすの蛇だ
嵯泉にすら怯えて、そのくせ怒ってる
飲み込みたくて仕方ないだろ
この世の全部を
認められないわけじゃない
認めちゃいけないんだ
これを「私」だって認めたら、絶対押さえが利かない
私は何も恨んじゃいない
何も憎んでないし、何にも怒ってない
そうじゃなきゃ、世界の味方じゃいられなくなる
跡形もなくしたいんだろ
よく知ってるから抗わない
お前は、生まれてきて、生きて、笑ってる――私が一番、憎いんだ
……ごめん、助かった
嵯泉は……おまえが大丈夫じゃないわけないか
本当、おまえ、変わった奴だよなあ――
 鷲生・嵯泉
鷲生・嵯泉
ニルズヘッグ(f01811)同道
◎
其れは此方の……否、彼女の頼みにお前が居ない筈は無いか
ああ、信置くものが傍に在るならば、私も耐えられよう
身を低く感情を露わにする傷だらけの四足の獣
喪失に抗い、抑え難い憤りと悲しみが己が身を傷付けようが構わない
命すらも削り猛る、其の様は――正しく私の姿だろう
だが、お前はもう護るべきものを再び手にした事を
爪牙を奮う先は己ではない事を認めろ
鷲生嵯泉――其れがお前だ
傍らの「己」に呑み込まれそうな――呑み込まんとしている其の【名】を呼ぶ
ニルズヘッグ……おいで
其の憎しみも含めた総てが在ってこそ、君は伴に在る者なのだから
何、獣の調教は慣れている
――其れはお互い様だろうよ
●
「お前がいるって聞いてない――」
「それは此方の、――否、彼女の頼みにお前が居ない筈が無いか」
ニルズヘッグ・ニヴルヘイム(竜吼・f01811)の子供めいた抗議は、まるで参観日に予告なくやってきた父親を疎ましがる少年のようだった。
鷲生・嵯泉(烈志・f05845)は確かにかの黒の兄である彼が、この場にいないだろうと考えていた己の思考にあった常識という名の隙間を埋める。このニルズヘッグという男は、そういうものだ。
きょうだいのために動き、家族のためになんでもこなし、世界を肯定し、愛し、何かから護っている。
もはや完璧にこなしすぎて、嵯泉や彼と同じくらいの目線でニルズヘッグを見れるものからではないと、行動に陰りも見えないほどに完成されていた。
揺らがない守りの竜である。世界樹の根っこをかじり、腐らせるはずであるのに、――名前に反したことをするのだ。
「でも、良かったかも」
あどけない少年のような口調で彼が言うものだから。
嵯泉が隻眼でちらりとニルズヘッグを見る。二人して対峙するものがそれぞれあった。
ニルズヘッグの視線の先には、黒い鞭のような大蛇がいた。
蛇の名は、アミメニシキヘビという。
やせ細っているからか、質量は感じられない。しかし、とぐろを巻くからだから背骨が浮いていてもなおその長さは感じ取れた。世界最長の蛇は、しゅるしゅると舌を何度も震わせながらニルズヘッグと嵯泉に威嚇を始めていた。
「一番見られたくないけど、一番信頼出来るから」
――哀しいことに。
ニルズヘッグにとって、この蛇というのが己の側面であるとしても、認められない事情があった。
痩せた蛇を満たしてやれない。ニルズヘッグの拒絶にも似たその言葉に、シャアッと鋭く息を吐く蛇が文字通り体をスプリングにして飛んできた。驚き――は直ぐに失せて、両腕で飛ぶ頭を掴んだ。じたんばたんと体を震わせる蛇に「おい」と嵯泉が声をかければ、彼にも容赦なく胴体と尾をふるう。
「此れは」
「私じゃない」
――嘘だ。
否定じみた嘘の意図を、嵯泉は汲み取る。
鋭い言葉は直ちに作られたのだ。魔術師のニルズヘッグらしくない、ほぼ反射で作られた言葉である。
「どこにこんなッ、――うぉ」
蛇の頭を両手でつかんでいたのに、にゅるにゅると器用に体をくねらせて力ずくで抜けられていく。勢いよく十指のわっかから抜けた蛇は、素早く体をくねらせて次の攻撃態勢をとっている。ふしゃ、ふしゃ、と鋭く息を吐くところなどは猫に似ているのに、人を呑める口を開きながら二人の周りをぐるぐると旋回始めた。
大きな円で二人を囲うように、逃げるなよと言いたげな蛇の仕草にニルズヘッグは笑えない。
嵯泉もまた、――背中合わせになるようにして、警戒を高めていた。蛇に作られた円形の中に、二人以外の息遣いが増える。
「虎か」
ベンガルトラである。
古来、中国では虎こそ百獣の王であるとされてきた。龍に匹敵する霊獣であると信じられており、未だにその骨は漢方の薬になると言われているほどである。
武勇や王者の具現であり、軍事的な象徴や勇猛ぶりを指すときに与えられる異名にも虎は多い。
四肢を撓めて体を低くし、ぐるぐるごるごると唸る大きな虎は筋骨隆々といってよい。
前足はしっかりと太く短く、獲物を押さえつけるのに特化している。傷まみれであるのはそれほど野性を生き抜いてきたあかしだ。
後ろ足は長い。跳躍するのに長けており、嵯泉を具現しているといっていいだろう。奇しくも、牙を使う虎の姿は――刀を振るうときに踏み込む嵯泉と同じ動きをするのだ。後ろ足で蹴り、飛ぶ。体を支える。まさに豪傑の象徴である彼相応といえた。
しかし、唯一違う点といえば。
「ッ鋭いな」
とびかかる虎を弾く。牙と刀が競り合うが、刀を砕かれる前に勢いよく腕を引いた。がちりと噛みそこなった虎の顎の音が激しい。
虎は、顎が発達している。獲物の喉に深く食らいついて逃がさず、その気道を塞ぐためのものだ。問答無用で嵯泉の首を狙い続ける執拗な攻撃と戦う嵯泉の呟きに、ニルズヘッグも内心焦っていた。
――嵯泉が己と戦っている。
――ニルズヘッグは、戦えないのだ。
認められないのではない。頭の中では、この痩せた蛇が――虎すら食おうと目論んで己の体のながさと、それぞれの重さを比べている蛇こそ己の姿であると理解している。
「認めちゃいけないんだ」
ちいさく、孤独の声が漏れた。
なにも恨んでいない。恨んではいけない。
何にも怒っていない。怒ってはいけない。
何も憎んでいない――そうしないといけない。
「そうじゃなきゃ、」
蛇の渦巻きが激しくなっていく。刻々と時間が過ぎるのを責めるようなしゅるしゅるとした腹ばいに体中が炙られたような心地がした。
息がだんだんか細くなっていく。体中を取り巻く呪詛に敏感になっている自分がいたのだ。ぞ、ぞ、と背筋に何度も寒気が走って、首まで肌が泡立つ。
――世界の味方でいられなくなる!!
額を抑えた自分の左手の感覚が確かめられない。瞬きをしないまま、ニルズヘッグはきつく口を一文字に結んでいた。
呼吸を抑えるような仕草は、背面越しに嵯泉も感じている。虎と斬りあいながら、時に鋭い爪に腕を割かれてもなお、抵抗を続ける。いよいよ虎がまずは鬱陶しい鋼から奪ってやろうと片腕で彼の手から弾いた。
「――ッぐ」
がん、と背の筋肉を強かに打ち付ける。地面に押さえられた嵯泉の声を聴いて、はたとニルズヘッグの世界が戻った。
「さぜ、」
「来るなッ!」
びく、と両肩を震わせたニルズヘッグが己に視線を向ける前に、嵯泉は鋭く叫ぶ。ニルズヘッグを狙っているのはかの大蛇だ。少しでもにらみ合いをやめれば、その体じゅうの骨をへし折って飲み込もうと巻き付くに違いない。
「大丈夫だ」
切れ切れの息をどうにか長く吐いて、嵯泉は虎の上顎と下顎を掴んでいる。首に噛みつこうとするそれを、片足で腹を押しながら持ち上げていた。だらだらぼたぼたと垂れる唾液に血が混じっている。
「命すらも削り、猛る、――其の様は正しく私だ」
虎の赤の目がぎらぎらと輝いている。己の力を示すための怒りの色だった。
本来――嵯泉という男は、直情的で短気で、だからこそ武人に向いていたのもある。
今思えば若さの躍進だったのかもしれない。しかし、その自分を恥じることはないのだ。問題は、まだこの「側面」が「理解」をしていないことである。
「いいか、虎よ」
首の力で胸を浮かせ、ごづ、と鈍い音を立てて虎の額に己の額を押し当てる。
「喪失に抗い、抑え難い憤りと悲しみで己が身を傷つけようが構わん。己が身ならば、な――」
見つめあう。互いの瞳に同じ色を映しながら、ゴアアと吠える虎に負けじと声を張った。
「だが! お前はもう護るべきものを再び手にしたことを――爪牙を奮う先は己ではないことを認めろッッ!そうだろう鷲生嵯泉、『もう』血迷うなッッ!!」
虎よりも雄々しいではないか。
低い声が白の空間にびりびりと響いて、ニルズヘッグが己の蛇を見つめる双眸をゆがめた。
「跡形もなくしたいんだろ」
まるで、――帰る場所にやっと帰れる迷い子のような表情で。
「お前は、生まれてきて、生きて、笑ってる――私が一番、憎いんだ」
勇気を得た。ほんの少しだけ、自分の傷を眺められる心の余裕ができた。
自分自身にすら否定されて、どこに帰ればいいかわからない思いの渦が蛇を作っていたのだ。心の持ち主にすら、蛇は追い出されて――痩せた体を満たす愛という名の餌も与えられなかった。
「おいで」
かすれた声で、嵯泉が呼ぶ。
「ニルズヘッグ」
其の憎しみを含めた総てが在ってこそ、彼は彼であると認めるものがいる。
「――君は、伴に在る者なのだから」
振り向いた「ひとり」に、落ち着いた声で微笑みかける傷だらけの男がいた。
喪った怒りを己にぶつけ、それでもまた、喪いたくないものを手に入れた人間は愚かだ。だけれど、あさましい彼らがいるから――救われる「けもの」がいる。
ニルズヘッグと蛇がともに、上体を起こした嵯泉に歩んでいく。どんどんと黒い体が黒い塵に代わっていって、残ったのはニルズヘッグだけだった。
「ごめん……助かった」
「何、獣の調教は慣れている」しれっと、しかし愉快気に語る嵯泉に頭を下げたニルズヘッグが思わず顔を勢いよく上げる。
「何笑ってんだよ」
「いや?」
「笑ってる」
「見間違いだ」
嵯泉を立たせてやろうとして両腕を差し出したのに、立ち上げてやる気が少しだけ失せてしまった。
ちょっとため息をついて――ああ、今度はしっかりとどちらの腕にも感覚がある。
「なんだよ、――本当、おまえ、変わった奴だよなぁ」
「――其れはお互い様だろうよ」
ここにいる。
確かに世界の中心で、ふたつが手を取り合っていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 西塔・晴汰
西塔・晴汰
【晴要】
◎
傷だらけの狼…っすか
ああ、分かるっすよ
前に前にって出て傷ついて
人懐っこくすり寄って
傷ついても笑ってる
…オレは知ってる
傷だらけの姿を見せちゃ相手は笑ってくれない
でも、オレは知ってる
友達の為に、傷ついても笑顔を見せなきゃいけない時もあるって
ああ、分かるっすよ
お前は確かにオレっすね
珂奈芽の方は……珂奈芽?
しっかりするっすよ…!?
声をかけても手を取っても震えが止まらない、なら
ちっこい頃父さんや母さんがしてくれたように
落ち着かせる為のハグ
そうだ、オレは知ってる
これは珂奈芽の一面でしかない
鉢から飛び出して自由に空を泳いで
皆を照らしてくれたのが珂奈芽じゃないっすか
オレは珂奈芽の強さを信じてるっす!
 草守・珂奈芽
草守・珂奈芽
【晴要】
×
この金魚さん知ってるのさ
ヒレがすごくキレイで、でも直ぐ傷つくし弱りやすい子
…これがあたし?
鉢の中で優しく守ってもらって、ガラス越しで外を知った気になって
そう、あんな酷い仕打ちも、愛されない絶望も知らなかった
人がぐしゃぐしゃに潰れる恐怖も、あたしは、何も
猟兵になって強くなった筈じゃないの?
無知で無力で、まだ鉢の中で守られてるの?
違う。嫌だ。こんなのあたしじゃない!
――呼ばれてる?あったかくて、優しい鼓動の音
ぎゅっと抱き返せば本物の感触。晴汰くんだ
あたし、ちゃんといる?怖い、どれがあたしか分かんない
…ああ、キミの気持ちはあったかいね
いつか本当に強くなって応えるから、その信じる心に
●
少年少女が本に手を触れた。
飛んでくる質量から少女を護ろうとした少年が、西塔・晴汰(白銀の系譜・f18760)である。
ばさばさと一匹の鳩のようだった。見開きのノート程度の薄さをした紙たちに触れれば、あっという間に――世界は白く染まる。まばゆくて目をぎゅっと閉じたとき、隣にいた少女の姿は消えていた。
「――珂奈芽!?どこ、どこっすか、ねえッ! 珂奈芽!」
途方もない白い世界が広がっている。自分かかろうじて立つ場所に影が落ちているから、地面があることは理解できた。両腕が広げられる範囲で空間に壁が無いことを理解する。ただ、風の流れはない。導き出された答えは、結界であった。
――閉じ込められた!
二人で並んでいたのに、ちょうど埋めきらない距離の間に壁を作られてしまっている。何度体を回しながらあたりを見ても、探す姿は見つからない。代わりに、ひとつの影が増えた。
「狼、っすか……?」
その狼は、とすりと座っている。
へふへふと舌を出して、ただ傷だらけの彼であった。
オオカミはひとに懐くことはない。彼らが長い時間をかけて飼いならされ、遺伝子の判断から人間に依存して生きる種族としてイヌに分岐するのであるが、オオカミといえば人と共存することはなく、お互いを認知することを選んだ種である。
――そう、人に「慣れる」ことはあるのだが。
晴汰の姿を見たオオカミは、明らかに体を跳ねさせて尻尾をぶんぶんと振り始めた。遊ぼう、遊ぼう!と跳ねている姿はわんぱくといっていい。オオカミのコミュニケーションは主に、表情や吠える声、またはボディランゲージで行われている。
きゃ、きゃっと小さく吠えながら動き回る姿に呆気にとられて、晴汰はまだ幼獣を相手に体を横から押し付けられ「わた、たっ」と体をよろけさせた。
「なんつー力っすか、もう。わんぱくっすね」
わしゃわしゃとごわごわの毛をなでてやると、嬉しそうに目を細めるのである。
オオカミは、明らかに晴汰のことを人間としては見ていないようであった。それもそうだろうな、と心の奥で納得がにじむ。
晴汰は、確かに人間であるが――人狼の父と、人造羅刹の母がいる。
混ざりに混ざった血の果てが「人間」である彼なのであって、おおよそ「ヒト」というには情報が多い。オオカミもそれを嗅ぎ分けていて、晴汰のことを「じぶん」と思っているから、こうして甘えてくるのだ。
――君もオオカミっすよね!あそぼうっす!
体全部で伝えてくる獣に触れている間に気づくのは、その傷の多さだ。
浅い傷から、よく見ればほほのあたりがすっかり毛を失っている。他にもけがは目立つし、きっともう治ることはないのだろう。代わりに、周りの毛皮が隠してくれているようだった。
「ああ、分かるっすよ」
――知っている。
晴汰は、友人に尽くすたちだ。それは、仲間という「群れ」を護る雄の本能かもしれない。なぜならば、オオカミは最低でも狩りに二匹で挑むのだ。相手と呼吸を合わせ、確実に獲物の息の根を止める。
お互いの様子を見ながら、今日はあきらめようかと引き下がるときもあるし、仲間のことを思ってもう片方がかばうことだってある。相棒を失ったオオカミが社会性を失って群れで孤立することもあるほど、情動が感じられるけものであった。
――晴汰も、そうだ。とても情に厚い。
仲間のための傷がほとんどだろう。晴汰とて、このオオカミとて、己の力量を知らないはずがないのである。
一匹で挑んでも勝てない敵に友人をつれていくのならば、喜んで友人の肉盾にもなるだろう。そうしてきたのだ。なぜならば、友人たちのことを好んでいる。
「大丈夫っすよ!」と明るく笑い飛ばしていたのに、それでも友人たちが悲しむ顔を見ると、すっかり晴汰も哀しくなってしまうのだ。
――それでも、笑ってほしい人がたくさんいる。難しい顔をした晴汰のほほを、べろべろと舐める赤い舌があった。
「わっぷ、ッ――ちょ、ちょ、っと! くすぐったいっす、はは!」
そう、こうやって。
自分の傷を見せてしまうことになっても、笑ってほしい人がいるのだ。
灰色の毛並みをしたオオカミが笑うように、晴汰も笑顔を自然と浮かべた。
「お前は、確かにオレっすね」
●
ちゃぷ、と水面の揺れる音がして何度も瞬きをした。
「――これが、あたし?」
草守・珂奈芽(小さな要石・f24296)の前に現れたのは、金魚鉢に入った魚である。
この金魚の種類には覚えがあった。津軽錦、と呼ばれる種類だ。
近年絶滅からの復活を遂げたこの種は大変美しい種である。ランチュウの血をもつのに肉瘤が現れず、背びれを欠いているがその分尾びれが長くあるのだ。
ひらりひらりと水槽を泳ぐ様は確かに美しく、細長い体の腹は黄金に輝いている。空気の反射に合わせてきらきらと深い緑にも輝いてみえる美しい体は、まだ成長途中もあって繊細で弱りやすいのだろう。
珂奈芽からすれば、受け入れがたいものであった。
鉢の中はたいそう泳ぎやすい。そのひれが傷つかないように余計なものが入っていないのだ。
透明な水の中は呼吸もしやすかろう。やさしい水草に体をこすったところで、鱗ひとつもはげやしない。ふわふわと上機嫌に泳ぐ金魚が己だと突きつけられて、少女は自分の理想からかけはなれた――現実を知ってしまうのだ。
あこがれていた世界がある。
草守の家は代々ヒーローのドラゴニアン一族があり、その分家に生まれた女児が珂奈芽であった。
変わり種として生まれてきた彼女は疎まれるのではなく、むしろ「草化様」などといったその地でしか名を持たぬ神の再来だと持て囃すばかりで、彼女に夢見る世界を与えてはくれなかった。嫌気がさしていたころに、世界から選ばれたときは――それはそれは、喜んだものである。
石の体は確かにもろいが、鍛えればきっとなんとかなると信じていた。
世話を焼かれずとも、それよりも先に友達に世話を焼けば珂奈芽は己の強さがわかると思っていたのだ。
――現実は、大きく異なった。
珂奈芽は、自分の境遇が窮屈で不幸なところから始まったと思っていたのである。
空にミサイルが飛ばず、隣人が死ぬこともない世界で、ただ「裕福な不幸せ」を感じていたにすぎない。それが確かに十四年生きた少女の理解であり、世界に違いなかった。
しかし、――「ヒーロー」というのは、「どんな痛みをも知ったうえで残酷に助けなくてはならない」仕事であるとは、彼女の世界ではわかるまい。
「強くなったはずじゃないの?」
悔しい気持ちでいっぱいだった。
どこか、驕った心があったのだ。猟兵になって確かに命を懸けたことがあった。
戦争に巻き込まれ、仲間たちと一緒に歩むことがあった。ともに戦い、苦労して、勝利をもぎ取る達成感を得て、強くなったはずなのだ。なのに、――心の成長が、追い付いていない。
受け入れられない世界をこの一件で目撃してしまった。愛されない人たちは、いったい何人いるのだろう? 当たり前のように過ぎ去る毎日で、同じような語調で、淡々と読み上げるニュースキャスターの事件報告を真面目に聞いたことがあるだろうか。
虐待の意味を知らないのである。
珂奈芽の「過干渉」も見方によれば、迷惑であると本人が感じているのならば確かに虐待に当てはまるが、その判断基準は珂奈芽に依存するものだ。明らかに他人である場所から見て、あの「親子」は「親子ではない」と思わされてしまった。
「無知で、無力で」
――優しい少女であるからこそ、珂奈芽が向き合うにはあまりにもひどい現実が待っていた。
蝶よ花よと可愛がられた子供である珂奈芽の前には、むごたらしい痛みを受ける少女の姿があったのに、何もできないのだ。知らないことに対処ができるはずがないから、それは当然だというのにどうにも自分を納得できない。ふわふわと浮いてご機嫌な金魚を見てても、ただただあさましくて恥ずかしい!
児童虐待の相談件数は、年々増え続けている。
毎日を笑顔で珂奈芽が過ごしていた時間で何人もの子供たちが存在を否定され、その傷を抱えたまま大人になっていくのだ。
「まだ鉢の中で守られてるの――?」
見てはいけませんよ、と何度か子供のころに言われたことがある。
その意味も解らないまま、「見てはいけない」から目をそらしたものが、一体いくつあっただろうか?
「嫌だ」
わからないことが罪だと知っていたのに。
それでも、大人たちが珂奈芽から「見てはいけないもの」を見せないように守っていた理由もわかってしまう。あまりにも、珂奈芽は――!!
「こんなの、あたしじゃないッッッ!!!!」
金魚鉢に向かって叫んだ少女の悲鳴ごと、抱きとめるようなぬくもりだった。
「珂奈芽、――珂奈芽、しっかりするっすよ!」
あたたかくて、先ほどまで沈んでいた孤独の冷たさが一瞬で消える。大雨のあとに差し込む日差しのような彼の声に、覚えがあった。
どくどくと脈打つ心臓の音が鼓膜を揺さぶる。落ち着いた感覚の脈動に、珂奈芽の意識がゆっくりと足音を立てながら戻ってくるような心地がする。固まった体は恐怖体験によるパニック発作で震えていたのに、ぴたりといつも通りの動きに戻った。
「晴汰く、」
「金魚は、――この珂奈芽は、珂奈芽っす」
自分がどこにいるのかわからない。抱きとめて温める体は、珂奈芽の知っている優しい温度だった。
晴汰は、小さな太陽のような彼である。
皆を守り、心を燃やし、時に命を燃やしながらもその足元を照らす器の広い少年だ。しっかりと遠くからでも迷った友達ひとり見つけられないでは失せ物探しの名が廃る。割れた結界の向こうで叫ぶ珂奈芽の声を聴いて、精一杯打ち破った。
呪詛を晴らし、うずくまる体を揺さぶり、何度も声をかけて――悲痛な声を聴いた。
晴汰は、「珂奈芽が嫌いな珂奈芽」も、「珂奈芽」だと肯定する。
「否定しちゃダメっす。だって、珂奈芽は、こっから出てきたじゃないっすか」
はた、はた、と涙が伝う。珂奈芽の幼い輪郭を濡らす輝きを指先で拭いながら、その顔を覗き込んで無邪気に笑う晴汰だ。
「そりゃあ、ちょっと――キビシー世界ってオレたちが知らないところで、いっぱいあるっすけど。でも、それを照らしてあげられるのが珂奈芽じゃないっすか」
――そうだ。
ヒーローは、人を救う。
もっともよい答えは「事件を未然に防ぐこと」だが、それよりも重視されるのは「解決した後のフォロー」である。
街を壊しながら守ったって、有難迷惑なのだ。散らかしたがれきは撤去するし、綺麗に建物だって治さないといけない。それと同じだと、晴汰は金魚の鱗を照らす。――乱反射した光で、鱗は何色でも輝ける。
目を凝らせば緑色に。少し見方を変えれば銀色に。
「オレは、珂奈芽を信じてるっす!」
――よくよく見ていれば、虹色に。
「――うん」
涙が止まらない顔を見せたくないから、しっかりとぬくもりを覚えていようと晴汰の体に腕を回す。ぎゅうっと力強くしがみついて、何度もうなずいた。
「あたし、――ちゃんと、いつか」
「うん」
「本当に強くなって、応えるから」
「待ってるっす、ずっと!」
信じてくれる心に。
きっと、これからも厳しい世界をたくさん見る。「守られてきた」ゆえに「守られない」世界に飛び出した金魚は、何度も鱗をはがすことになるし、尾ぐされもするだろう。
だけれど、そのたびに――寄り添ってくれるオオカミがきっと駆けつけてくれるから。
ああ、どうか目をそらさないでいて。
きっと、――明日は二人の空も晴れるのだから。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ウィータ・モーテル
ウィータ・モーテル
◎
けもの……これは、炎の鳥?
違う……これは、私の中にいるもう1人の私だ。
そうだね。私は、昔、故郷をオブリビオンに滅ぼされた。
ユランに助けられるまで、瓦礫の中で、街の人達が死んでいくのをただ見ているしか出来なかった。
私は、オブリビオンに復讐するとかよりも……故郷を、取り戻したいと思ったの。でも、同じくらい、辛くて、苦しくて……そして、あなたの存在を、知った。
怒りという炎に包まれた炎の鳥だけど……傷ついてる。ずっと、ずっと辛かったんだね。
ごめんね。
こんな私だけど、これからも……一緒にいてくれるかな?
……『フロル』。それが、あなたの名前だよ。戻ってきても、忘れないでね。
●
――炎をまとう鳥がいる。
それが何かを一瞬、ウィータ・モーテル(死を誘う救い手・f27788)は理解するのに時間を置いた。燃え盛るけものは伝承で見たことはあれど、こうして間近にUDCアースで輝くそれを見つめることはそうそうない。じっと表情の変わらない瞳に映して、揺らめく炎を見ていた。
こんな時こそお喋りな猫に話してほしいものだったが、どうしてか黒猫のユランは肩からすとりと降りて、それを見守るように丸まっている。視線こそ二つ見ているが、体は待ちきれないらしく、ころころと白い床を転がったりしていた。
「――もう一人の、私だ」
発せない声がクリアに頭の中で響いて、ウィータは遠くの景色を思い浮かべる。
故郷をオブリビオンに滅ぼされていた。崩れる街と、逃げ惑う人々をがれきの隙間から眺めている日々を思い出そうとすれば、いくらでも鮮明に考えられる。
――何もできない痛みがあった。
体中はすりむいたり、切ったりして傷だらけなのに、胸の奥の奥がずうっと痛い心地がして、コンクリートに覆われたがれきの間で呼吸を出来ていることに喜ばず、殺される人々を見て「ああ、自分は助かった」などとも想えずに、ただただ涙を流していた。
どうしてこんなことをするの、と――叫びたいのに叫べない。肺を熱で焼かれて喉もまともに使えない。喘鳴がして、ざらざらの気道を感じた。なんて無力だろう、と死にゆく街を止められない。
もうやめて、と言いたくても、誰にも声が聞こえないのだ。逃げ惑い、助けた人すら殺され、何もかもを喪っていく――。
「そこから助かったのは、私だけだったんだよね」
心の声は届いた。
鳥がゆるりと瞬きをして、煌々と燃える炎の体を膨らませる。ぶるる、と興奮をあらわに小刻みに体をゆすれば火の粉が散った。
「あの時にユランと契約したのは、私だけ」
代償に感情表現と、言葉を失っている――だけれど、ウィータは喪われた街をたしかに取り戻したのだ。善意の彼女は人格が分離しているまま、「何もかもを救いたい」と悪魔と契約した。だが、この人格(かのじょ)は違う。
――燃え盛る火の鳥は、何もかもを燃やしたくてたまらない。
奪われたのならば奪って返したいし、やられたのならやり返すのだ。容赦はない、慈悲など要らぬ、そんなもので何が救えるのかと凶暴な心を持っている。まるで、ウィータからごっそりと抜け落ちた衝動のような根源は、ひとつの「人格(ひと)」になった。
それが、この火の鳥の姿をとっている。暴れるものかと思いきや、静かに燃えているだけだった。
――対話の意思があるとみてよいだろう。怒りの炎は、その身を焦がすだけなのだ。
「私ね、ずっと――復讐とかよりも、故郷を、取り戻したいって思ってた」
ゆらり、黒猫の尻尾が揺れる。
「でも、同じくらい辛くて、苦しくて」
やり場のない怒りで身を焦がすほど、己の無力さに打ちのめされることだってあったのだ。
鳥は、きっとそれをわきまえている。ウィータをつつくことなどせずに、白い床に足をつけて言葉の続きを待っていた。赦すのではなく、お互いを対等に眺めるための姿勢にウィータも言葉をどうにか絞りだす。
「―――、傷ついてる。ずっと、……ずっと、辛かったね」
私たち、ふたりとも。
泣きそうな声が思念になって広がった。ウィータの感情が乗って、動かない表情が世界に波形となって広がっていく。呪詛の結界内に満ちたとき、火の鳥は確かに彼女の顔を見た気がしたのだ。
「ごめんね」
――フロル。
名前を得た鳥が、火の粉を散らしてウィータに似た姿をとる。きりりとした瞳が、やはり鳥の美しい瞳のままだった。
「こんな私だけど、これからも一緒にしてくれるかな――」
「分かれることなんて無理だろ」
「それはそうなんだけど……」ずばりと根本を言い切られてしまって、あからさまに思念にのせた涙が引っ込んだ。
だけれど、――こうして対等に会話が出来るのは、初めてな気がして。
「忘れないでね」
「忘れるもんか」
「鳥頭なんじゃないのー?」退屈そうに鳴いたユランには鋭く舌打ちをして、怒りの化身はウィータとひとつになる。重なり合った手から混ざり合うように――ふたつは一つの体に戻った。
ちらり、ちらりと火の粉が散り、爆ぜて結界を打ち破る。広がる世界は、確かに現実のものだった。
胸の中が温かくなったような気がして、思わず思念は微笑む。
――フロル。
――うるさいな。覚えてるよ。
機嫌のよい少女の声と、とげとげしい声が頭の中で響きあっていた。ふたつは、あるべき場所に戻っていく。
大成功
🔵🔵🔵
 六条寺・瑠璃緒
六条寺・瑠璃緒
△
嗚呼、随分と…可愛らしいのが出て来たね
…獣にすらもなれない真の姿を突き付けられるより気が楽だ
現れたのは豪奢な馬具…の成れの果てに血を滲ませて、凛と顔を上げた手負いの黒馬
さぁ、おいで、と、黒馬の首を抱き締める
君には申し訳ないとは思っている
けれど、人の子が求める限りは健気に尽くすだけ
神罰とばかりに振り落とし踏み殺すことは容易いけれど、僕達自身が其れを望まないのだから
…背負う荷が重く蹄の先から朽ちようとも
馬の首を撫でながら羊皮紙を手に取り、囁く様に読み上げる
…瑠璃緒
「其れでも僕はヒトが好きだよ」
…さて
三文芝居で申し訳ない
悪趣味な邪神はこんな感じの演技でご満足かな
周りを起こして討ちに行こうか
 シキ・ジルモント
シキ・ジルモント
×
『けもの』に飛びかかられ、咄嗟に躱し銃を構える
現れた『けもの』は銀色の被毛の狼
痩せて、酷く飢えた様子を隠しもしない
狼に変身した自分に似ているせいか、毛を逆立て牙をむきだして唸る様子に嫌悪感を覚える
理性の無い、まさしく獣だ
…本を手にした瞬間は取り戻そうと思った
しかし、姿を目の当たりにして考えが変わっていく
取り戻すという事は、あれを自分だと認めるも同然
認められない
あんなものが自分だと、こんな本性を持ち合わせていると知られたくない
ずっと目を背け、隠し続けてきたのだから
あれは違う…俺は、獣ではない
目の前のこれを斃せば
俺の中のけものごと、消えて無くなってくれるだろうか
銃を構えたまま、そんな考えが浮かぶ
●
「嗚呼」
神になりたがるヒトというのは、何時の時代にもいる。
六条寺・瑠璃緒(常夜に沈む・f22979)は、そんな人間の歴史を何度も見てきた。不敬であると思ったことはない、むしろ、瑠璃緒――神からしてみれば人の子が「祖」にあこがれるのは喜ばしいのだ。
今回選んだ手段はよいとはいってやれないが、その気持ちを赦していた。だから、真っ白な空間に漆黒の髪をかき混ぜられても微笑みは絶やさなかったし、何でもてなしてくれるのかと楽しみにしていたのである。
「随分と――可愛らしいのが出て来たね」
瑠璃緒の今までを形容するのは、辞書のような厚さをした本であった。これだけでは事足りないが、『しょせん』邪神程度が遡れる範囲など限られている。
一冊のそれが飛んできたかと思うと、手品のように紙がばらけていったのだ。無数のまっしろな蝶に包まれるような視界の果てにあったのが白紙の世界であった。
天井も、左右も、地は瑠璃緒の足元に影が落ちているから地であることは理解できたが、やはり白い。そこに在ったのが瑠璃緒だけではなく、もうひとつの息遣いであったから臆すことなく対峙した。
黒い馬である。からだに血をにじませていても体毛で分かりづらいが、ツンとした鉄臭い匂いに瑠璃緒が理解を示した。足を折りたたんで横たわっていた彼の目は、瑠璃緒を見ていない。視線の先には、壊れた馬具があった。
――豪奢の名残がある。
「かわいそうに」
さあ、おいで。と語りかけた。歩み寄る瑠璃緒を拒絶することなく、馬はゆったりと首を持ち上げて凛とした顔を見せる。長いまつげが美しい。
「触るよ」と声をかけ、ぽん、ぽんと強くはたくように撫でてから、太い首を抱きしめてやって、毛並みに従って何度も撫でてやる。瑠璃緒の扱いなれた手つきに、馬は冷静であれた。
元来、馬とは――人と酷似した遺伝子を持つ生物である。ゲノムでいえば四分の三は人に一致し、家畜化されたこともあってイエイヌと同じく人の表情を理解し、そのこころに共感ができる。
草食であるゆえに穏やかな生き物であるが、大変耳が良いため音に敏感で、臆病な一面も併せ持つ。彼らの祖先は二百万年ほど前から人間と共存を続け、ともに戦い、ともに暮らし、今もまた人間と手を取り合う存在であった。
その体は人間と似た構造でできているからと、民間薬としても名高い。馬油などは解熱の効果もあるうえに、様々な効能が解明されている。
「君には申し訳ないと思っている」
――それが、瑠璃緒の側面であるといわれれば、そうだろう。
瑠璃緒は神である。人の子の祖であり、彼らを平等に赦し、この一件とてかの男に憤りは抱かず、人の子らを邪道に導く冒涜的な神々を嫌っているだけにすぎない。
馬の耳にささやいてやれば、ふるふると揺れた。ぶるる、と唸る彼は肯いているような心地がある。「わかるよ」と言いたげな瞳には、瑠璃緒の真意がわかるようであった。
「――けれど、人の子が求める限りは、健気に尽くすだけ」
なぜならば、神なのだ。
馬と人が近ければ、人とて祖である神に近い。
しかし、神である瑠璃緒が神罰とばかりに猛威をふるえばあっという間に人間たちは踏み殺されてしまうほどか弱いのだ。
間引くことはある。しかし、すすんで「やりたい」わけではない。
「背負う荷が重く、蹄の先から朽ちようとも」
ちらりと、馬の足を見た。
血がにじんでいる。――蹄に打ち付けられた蹄鉄がゆがんでいた。
蹄は、馬の第二の心臓である。
指が進化した蹄には、多数の血管が入り組んでいる。蹄が地面に触れ、歩くことで、拡張と収縮を繰り返す作用があり、それによって馬は重い体を支えながら遠くの位置にある心臓に血液を送り出すことができるのだが此処が壊れてしまっては、あっというまに組織が壊死し、「馬は歩けないと命に関わる」という言葉通りに、横たわってただ死ぬのを待つだけになる。
それでも、馬は人に寄り添い続けるのだ。
蹄の手入れが上手くなされなくとも。劣悪な環境で遣われても。鞭を打たれながら走っても。
それが、人の望むことであるのならば――隣人を愛すように、馬は応ずる。
「瑠璃緒」
神とてそうだ。
人を許し、愛し、その罪を認め、ただ照らす。
いかに人間が愚かであっても、瑠璃緒の名を掲げて戦おうとも、――全て瑠璃緒のせいになろうとも、それを許すのが神である。
首に巻き付けられた羊皮紙に、当然の名前が書いてあった。ささやくように読み上げて、馬とともにその名を呼ぶ。
「其れでも僕は」
――ヒトが好きだよ。
●
銃を構えた。
『けもの』が現れたのは、ほとんど直感で判断できる。
シキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)は飛びかかってきた四つ足の姿を見るよりも早く、手にした本を投げ捨てて身を翻して銃を構えた。
どすん、とシキの居た場所に――四つ足の息遣いが響く。
オオカミであった。銀色の被毛で、ごるごると唸りながら牙をあらわにしている。痩せて飢えたけものは鼻に険しいしわを刻みながら、身を低くして逃げた獲物をどこからかみ砕こうか考えているようだった。
ぞ、と嫌悪を全身に感じる。うなじに垂れた汗を意識して、シキが悪態をついた。
「理性の無い、――まさしく、獣だ」
その姿は、あろうことかシキに似ている。
正しくは、病に侵されたシキの作用に似ているのだ。人狼病――人間、オオカミ、狼獣人の三つの姿を持つ感染者がシキであった。
満月を見ると人間性を捨て、凶暴化することもあれば、その体の寿命は限られる。
こんなものになりたいはずがなかった。喪われる人間性をかき集めてきわめて、シキは人間としてのシキであろうとつとめている。
生まれたときからけだものだったわけではないのに、受け入れられるはずがないのだ。
「――ッ!!」
がちん!と鋭く牙同士がかみ合う音がした。
シキの首を狙った狼の突撃である。があっと開いた真っ赤な口内が恐ろしく、思わず体を反らせた。空虚をかむことに成ったオオカミは、その前足でシキの胸を突く!
「っは」胸骨を砕かれたような心地がした。ばきぼきと嫌な音が立てられて、続く後ろ足でいよいよ膝から崩れ落ちるほどの蹴りを胸に食らわされる。
シキを飛び越える形になったオオカミは、そのまま追撃を仕掛けてくるかと思いきや――じいっとその様を見ているのだ。
獲物を食らうためではない。
この行為は、「いたぶる」ためのものだ。
痛みとともにじくじくと腫れあがる胸筋をかばいながらうずくまるシキは、横目でオオカミを眺める――べろりと舌なめずりをして、にやにやと笑っていた。
本を手にしたときは、取り戻そうと思ったのだ。
シキを作る歴史にこの「病」も切り離せない。感染したという事実が無ければ、シキの今日にいたるまでの戦いは無かったことに成ってしまう。
人を思いやり、仕事を完璧にこなし、約束や信用を重んじ、丁寧に暮らしていた。
別離の過去を抱く彼は常に冷静であるように心がけているのに、――今の彼は、冷静ではあれなかった。息をするたびにぶるると唇が震え、ごぶりと血が口からあふれる。はたはたと唾液交じりの赤が地面に染みを作って、体中から汗が噴き出していた。
おそろしい。
――あれが俺だと?
認められるはずがない。
シキは、「シキ・ジルモント」でありたいのだ。
そうあろうとして、ずっと目を背けてきた。人の目にさえつかなければ、誰も本当のシキを知らないままに過ごしていけると思っていた。勝手な期待だ。そんなことは出来ようもない、いつか解ける隠匿であるというのに、――「できればいいな」がいつしか無責任な人生を丁寧に塗ってしまった。
自分が「おかしくなってしまった」ことを認められない。
「ぅ、ッ」
吐き気すら催す。
シキ・ジルモントという男はあのような獣ではないと言いたいのに、オオカミはいびつに笑い、はふはふと舌を垂らして獲物が苦しむ姿に愉悦を覚えているではないか!
――俺こそが俺であると言いたい顔が、憎らしくてたまらない!
銃を構える。慣れた手つきだった。うずくまった体を支える腕の隙間から銃口を覗かせる。
オオカミはこてりと首をかしげて、「できるのか?」と笑っていた。
このオオカミを殺せば。この「自分」を殺せば。
「――俺の中から、消えて無くなってくれるか」
なんて、情けない祈りだろうか。
口にした時に思わず自分で自分を笑い飛ばしたくなるほど、滑稽で、身勝手で、都合のいい――妄言に違いなかった。
「シキ・ジルモント」
穏やかな声色だった。
オオカミとシキの自己否定の戦いに、永遠の少年が歩み寄る。
細い輪郭の声で、すうっとオオカミは姿を消した。シキの傷も、――瞬きをしたころには見当たらない。声をかけたのは瑠璃緒であった。
「酷く魘されてたみたいだったから。声をかけてしまったよ」
お楽しみだったのかな、と首をかしげる。【而して夜は明けず】、瑠璃緒が気になる場所には「開けよ」と命じれば開くのだ。苦しむシキを囲う呪詛の結界など、神の前では無力に等しい。
――戻ってこれた。
現実に戻ってきた意識があまりにも鮮明で、頭痛を覚える。シキが頭を右手で押さえながら「助かった」とまず礼を伝えた。
「あんたは何ともなかったのか」あせだくの額を撫でて、シキが問う。
「下手な三文芝居をさせられたくらいで、他は『なんともない』よ」
――獣にすらなれない姿を見せつけられるよりは。
向き合えない現実が多くある。知られたくない秘密が多くある。
これが、ただの悪夢であればよかったのに。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック
◎/◎
(――駆けつけたのは、"鎧"の方でだった
捲った本から「自己」が漏れ出て形を創る)
(ザザッ) ケモノ
――成る程 "怪物"だな。
(ごわついた獣毛が逆立って威嚇する様にしている
毛で大きく見えるようで その実、見た目ほどは大きくないのだろう
嘗て虐げられた事への恨み
悪と強者への害意
強さへの妄執
己の弱さへの怨嗟
――何とも「寂しい」生き物で
そして間違いなく「自分自身」だ)
――馴染みのあるフレーズを敢えて使うなら
”我は汝、汝は我"なのだろう。
――戻って来い
強さと弱さ
どちらが欠けても
「僕/本機」じゃないんだ。
解るだろう。
(少なくとも
ジブン
"僕/本機"はそう望む。
オマエ
"本機/僕"はどうだ?)
●
――駆けつけたのは、“鎧”の姿であった。
捲った本から出てきたものが、たとえどんなものであってもジャガーノート・ジャック(JOKER・f02381)は立ち向かう。
だから、この姿で正解だった。この姿で戦うことを、気弱な少年は「卑怯」と思わない。「勝ちに行くための最善の手段」なのだ。
吹き飛ぶ本の中から直感で手にしたものは、黒いものだった。ページを捲れば、文庫にしては珍しく上下を分かつ線が中央に入っており、一枚で二枚分の話が読める仕組みではないか。
解析する間もない。紅い液晶の向こう、別の生体反応が本から検出された。あっという間に、「自己」が漏れてあふれだす。
スキャン結果、精神体。一致率95%、該当者、――一名。零井戸・寂。
ケモノ
「――成る程、“怪物”だな」
ノイズの走る籠った声の主は、目の前に現れた四つ足のそれを見て納得した。
そこに現れたのは、ごわついた毛並みのクロヒョウである。
通常のヒョウの黒化個体である彼は、基本的に劣性遺伝であるため、突然変異体として称される。
よく目を凝らせば豹紋を目視でき、個体識別も特殊な手段を用いれば可能な――「異常であるけれど普通」の種だ。
威嚇も相まってふくれあがる毛並みは、黒い彼を大きくみせる。異常な色におそれを感じさせるが、さほど大した脅威にはならないだろう。なぜならば、応対するのが「ジャック」だからである。
それでも、理解はできる。
勝てない相手に息を吐きながら、まるで雷のような音を喉から立てて威嚇する彼は、まぎれもなく――たくさんの感情を溢れさせていた。
嘗て虐げられた事への恨み。
悪と強者への害意。
強さへの妄執。
――己の弱さへの怨嗟。
夜行性で群れを作らず、単独で生活するヒョウは人間を襲うこともあれば、虫でも食らう強かさがあった。生き汚いと言われればそれまでだが、害獣や娯楽の対象として狩られ続け居場所を奪われ、もはや今では絶滅危惧種の該当する猛獣である。
今この場には逃げる場所もない。樹に登り生活するヒョウがジャックに向かって威嚇するのも無理はないだろう。来るならこい、とことんやってやる!と言いたげな威嚇をするわりには、飛びかかってこないのだ。
人の態度がたちまちにに変わることを、「豹変」というように――なんとも「彼ら」にふさわしい言葉であるが、元来の意味通りに考えても相応しい。
その言葉は、『豹の毛が生え変わり鮮やかな模様が現れる様に、君子は自らの過ちをはっきりと改める』という良い意味で用いられるのだが、どうにもこの獣は誤解している時期の「彼」らしいのだ。
戦うために手段を使いきるのが悪いことである筈がない。
戦い方に応じて「自分」を使い分けることはきわめて合理的だ。
護る為に欺く強さだって必要であるし、時には自分より強い誰かを「使う」ことだって必要なのだ。なにも、「使われる」ことを知らぬ強者ばかりではないのだから、ジャックたちの要請に応じて動くかどうかは、強者にゆだねてやれる。
多くの世界と、関わり合いを――広い森で相棒と見てきた「彼ら」だからこそ、このヒョウを見ても恥ずかしいと思わなかった。
未熟な生き方をしてきた。だけれど、其れの何がいけないというのか。他人を羨んでも努力を怠ることはなかったし、自分を顧みて、時に仲間と支えあってきたのだ。
「寂しい生き物だな」
目線を合わせてやろうと、腰を曲げる。
【 THIS IS ME 】
「――それも、"僕/本機"だ」
今はもう、知っている。
ざり、ざり、と響くノイズにヒョウは目をぱちくりとさせた。聞きなれない言語を目の当たりにしたかのように、くるくると耳をレーダーのように動かしている。
ひげがふわりと広がって、認知されたことに理解が追い付かないようだった。
「戻って来い」
強さと弱さどちらが欠けても「僕/本機」じゃないんだ。
「解るだろう」
――お前は僕で、僕はお前だよ。
それが、ジャガーノート・ジャックを作るすべてなのだから。セーブデータが欠けてはいけないように、黒い鎧は手を伸ばす。鋼鉄の体に戻って来いと、クロヒョウに声をかける。
委縮していたけものが、おずおずと体を低くしたまま前足を少しずつ前に出すものだからますます、「僕だな」と思うのだ。
「もう大丈夫だから」
黒い獣を抱きとめたとき、やはりその体がずっと細かったことは、鎧越しでもわかってしまうのだった。
大成功
🔵🔵🔵
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン
◎
…そんなに小さいのか、おれは
(あねごはこれを、猫に似ていると仰っていた
三角耳と長い尾、鋭い爪
いびつなキマイラが蹲っている)
それとも、もう、こんなに小さくなったのか。
(耳障りに喉を鳴らし
鬣を逆立て爪を立て牙を剥く
けれど向かい合うまま)
うつくしいひとになりたかった。
あねごと違う、お前でいるのがいやだった。
(獣に指を伸ばして喉を擽る
お前が寂しがりなのを、おれはよく知ってるよ)
なあ。
烙(ろく)。
育っていいんだよ、お前も、おれと。
(御手の、御言葉の
何もかもが全てで、うれしいことなのだと
そういう想いがおれにもわかる
御心の在処を知らないままの幸福を)
行こう。
ひとごととは、思えないもんな。
●
「そんなに小さいのか、おれは」
ロク・ザイオン(変遷の灯・f01377)の前に現れたけものといえば、小さい毛玉のようだった。
ぴるぴると橙色の毛並みを揺らしながら、ひげが真横に広がっている。緊張から瞳孔は丸くなっていて、ぎゃーとか、ん゛ぁーとか、何ともつかぬ鳴き声を上げていた。
思わず笑いが漏れてしまう。しゃがんで、その様をじいっと見ていた。
――ロクが知る「あねご」は、これを猫に似ているとよく言っていた。
三角耳と長い尾、鋭い爪は確かに猫のようなのに、猫というには愛らしさも少し足らず、代わりに獰猛な幼獣に思える。
「それとも、もう、こんなに小さくなったのか」
まぎれもなく、キマイラといっていいだろう。
ぐちゃぐちゃに組み合わされた奇形のような、何にもなれない「なにか」の獣は、あからさまな威嚇の姿勢をとって見せた。
ぶしゃーとか、ぶぎゃーとか、聞いてきても耳障りな壊れた喉が震えている。
ぼわぼわぼわぼわ、と鬣が逆立ち、爪をがりがりと白い空間に立たせて牙をむいている。ロクが少し身をよじるたびに、「ぎゃびゃ!」と鋭い悲鳴を上げた。
「なあ、何もしないよ」
飛びのいた獣の前に、掌をみせる。両手の指先になにもないことを教える手つきに、ふすふすと猫のような何かが、鼻を寄せた。
あたたかい鼻息は、体の中で焔が燃える証であろう。
そのままゆっくりと恐れぬ手で、獣の喉を擽ってやる。
獣は一度身をよじってふしゃふしゃと拒否をするものの、手で追いかけてすりすりと顎をこすれば、目を細めてころころと愛らしく甘えられるではないか。
「うつくしいひとになりたかったなあ」
――あねごと違う、お前でいるのが嫌だった。
こんな毛玉が、人間になれるはずもないと思っていた。人間にあこがれる奇形の怪物は、人に寄り添う立場でありながら望みすぎていることを知っていた。
それでも――それが、ロク・ザイオンという彼女の「にんげん」というかたちであったと、今ならわかる。
人生はそれぞれだ。この世界に何億の生命があるのなら、何億通りの在り方がある。
【"Like a --"】
「烙」
触れる。
心の傷ではない、あやまちでもない、その優しい温度に両手で触れた。ゆっくりと掲げるように抱き上げてやって、対等な視線になる。幼い痛みの象徴は、寂しがりであると知っていたのだ。
「育っていいんだよ」
誰かに言ってほしかった言葉を、今ならば自分に言ってやれる。誰にも言われなかった言葉を、自分のためにささげてやれる。
きっとこれからも、うつくしいひとと違う自分をつらく思うときがあるのだろう。だけれど、そのたびにきっと今日を思い出せる。「違ってもいいじゃないか。それがおれだろう」と、声をかけてやれる。
――御手の、御言葉のすべてに喜んでいた幼い己の姿を見て、思い出す。
きっと今の姿を、あの時の世界を作っていたひとびとに見せれば「つまらなくなった」というのだろう。
それでも、構うものかと今なら笑って人のそばに寄り添える。
御心の在処を知らないままに、ただ幸福であることを信じ、享受し、生きるという作業を繰り返すだけの日々は確かに楽であるが罪であると今になって知ったのだ。
きっと、あのけものも――いつかの烙と同じで、寂しくてたまらないに違いない。
どこにも自分の居場所などないではないかと泣き叫ぶ忘れられたもうひとりに、教えてやらねばならないのだ。
世界には、親がいなくとも――たくさんのともが居て、守ってくれるひとがいて、支えてやれる森があることを。
ロクがレグルスとして輝くように、森番でありながら、世界と未来を守る「にんげん」であることを自信をもって誇れるように為れた今だからこそ、次は隣人に気持ちを裂ける。
胸にあふれる光があってこそ、ようやく誰かの足元を照らしてやれるともうわかっていた。
「ひとごととは、思えないもんな」
すべてを受け入れる、森(せかい)を教えてやろう。
行こう、と声をかければ――毛玉はふわりと焔の塊になる。
ロクの心にぬくもりを求めるように、胸の中に戻っていった。じんわりと喪われた熱を取り戻す様な心地がして、ゆっくりと息を吐く。
全身に人間めいた熱量を取り戻して、呪詛が晴れていく心地がした。
大成功
🔵🔵🔵
 紅砂・釈似
紅砂・釈似
△
一頭の黒豹。心の奥でひとを疑い、恐れ、憎み続ける私。
他人が怖いから、いつも先に恨んでいないと落ち着かない。人を見ればすぐに斬り方を考え出す。刃を振るって殺さなければ、誰も彼も憎くて夜も眠れない。
その憎悪は、そうまでしてのうのうと生きたがる私自身にさえも向くのだろう。
良いよ、来れば。私達が交わせるものなんて、暴力(それ)以外にありはしないのだから。噛み付くも引き裂くも、好きにしろ。お前が噛むなら歯を砕き、爪を振るうならそれを剥ぐ。猛獣の躾は厳しいに越したことはない。
いつか、私は真に獣に堕すだろう。その前に己で始末をつける必要がある。でもまだ首はやれないよ、「釈似」。
●
一頭のクロヒョウがいた。
雌のヒョウである。しっかりとした前脚で白い空間に存在するさまは、よりこの空間の「殺風景さ」を際立たせていた。
ぐるぐるとうなる低い音が響く。猫などよりもずっと太い前足をそろえ、佇むように座っていた。不機嫌に揺れている尾先が、それ以上近寄るなと警告する。
紅砂・釈似(流殺煙刃・f27761)は、その獣を眺めて斬りたい、という気分よりも、それが己である認知のほうが勝った。
腰に携えた刀の重さを感じながら、今はおとなしく見つめあうだけの獣を見る。
「いいよ」
ひくりと、そのひげが動いた。
「来れば」
焚きつけるわけでもないが、まるで手綱を離したような言葉が――合図となった。
か、か、と鋭く息を吐いたクロヒョウが釈似の小さな体にとびかかる。神域に至る人間の剣技を以て、横にまず薙いだ釈似の剣筋すら飛び越えていった。ど、っと前足で着地した黒は、鋭く後ろの足で器用に蹴りを放ってくる。かするだけの爪で、振り向きざまの右腕に切り傷が与えらえた。距離を取ろうと後ろに跳んだ釈似を、逃がすものかと低く跳躍した獣の牙が襲う。
――その表情は、憎悪のものだった。
生まれついて、暴力の中で育っている。
父子家庭における異性の子供の扱いというのは、どうしても持て余してしまうらしい。
姉が一人おり、その姉は釈似を残して就職してから出て行ってしまったのもあり、ここまで獣に陥ったのは家から出るのが遅れた釈似のほうであった。
異様に屈強で頑丈な体を持っていたから、父親からの暴力を前にほとんど無傷であれる。
釈似は、平然とした顔で勉学の道も歩んだことがあり、さらりと大学まで卒業してみせたほどだ。『仕事』がある限り、彼女の学生生活は奨学金に頼ることもなければ、子供も満足に育てられない父親を頼る必要もなかったのである。
『仕事』の影響も大きかっただろう――やはり、釈似は暴力の女である。
荒事はそこまで好ましくあらず、どちらかといえばおとなしく日々を過ごしていたいたちだ。
しかし、幼児期に必要だった安寧が暴力になり替わってしまった女の倫理や価値観、「平穏」の基準は大きく異なる。
心の奥で、いつも人を疑っている。
――他人は恐ろしいのだ。何せ、一番距離が近いのに血のつながった家族すら、釈似に「平穏」を与えては呉れなかった。
少しでも相手に不穏な動きがあれば、いつでも五指を刎ねてやれるように集中している。毎日人を憎み、先に怨むことで心の平穏を図っていた。
憎らしいに決まっている。このクロヒョウが一人でいたがるのも、そうなのだろう。
のうのうと毎日を無駄に暮らしている奴らが憎らしいし、いつでも人を攻撃してよい瞬間を、今のクロヒョウのようにずうっと見定めている。少しでも琴線に触れた行いをしたものがいれば、容赦なく刀を抜いてきた。
クロヒョウは、釈似が「わかった」フリをして声をかけただけでこのありさまだった。
じゃれるよりも果敢な「殴り合い」と言って等しい人間と獣の武闘が始まっている。
噛みつきに来た顔を、刀を握った手で殴る。牙がはじけ飛んでもなお、獣は圧倒的な質量で釈似にのしかかる。
「躾のなってない奴だ」
横っ面を左肘で「斬った」。肘は、人間の身体で頑丈であり、鋭い部分である。
肘鉄による裂傷行為はプロボクシングの世界で禁止されているほどの威力があり、人間ならば誰しも持っている刀であった。獣が間合い以上に飛び込んできたところで、釈似の刀はその全身にある。
ぎゃあっと悲鳴が上がって血が噴き出す。びしゃびしゃに赤で顔を塗られて、目を少しつむった。眼球に血が入っては視界に悪い。よろけた獣を横になぎ倒してから、ごしごしと腕で顔を拭いた。
「――調教は厳しいに越したことはない。そうだろ」
暴力こそが、世界だったのだ。
クロヒョウに圧倒的な暴力を振るう自分が、スゥーッとした息のしやすさを感じている。
人なみの道徳と感性をもっていても、この「くせ」だけは治らない。釈似は、それを理解していた。
戦闘嗜好症である。明確な病としては存在しない故に、これは病ではない――「くせ」なのだ。どうしようもない習慣である。
わざわざ食事をしないというエネルギーを元より減らす行為と、脳を侵すニコチンのおかげで三日に一回のペースで発作は抑えられているものの、「それでも」止まらない。
父親が釈似たちに暴力を振るうことを「父親という立場」で行った時から、釈似は「暴力」が「自己表現」につながってしまっているのだ。
自分のストレスを発露するための一番気持ちの良い方法が、他人を真っ先に恐れ、故に怨み、その「暴力」を正当化する。だから、相手を初めて見たときに「どう斬るか」を考えているのだ。
なぜならば――「怖かったから、こいつが私に悪いことをしたから、殺したのだ」という主張は、生きている釈似が主張すれば正当である。殺された側は「なんて悪い奴だったんだ」といわれて死んでなお釈似に殺されるのだ。
「そうまでしてのうのうと生きたがるんだよ」
いけないか?
いけないに決まっている。
釈似の知っている道徳は、そもそも「安全に」生きてきた人間たちが決めた暗黙のお約束事ばかりだ。人を傷つけてはいけません、人を許しましょう、人を助けて合って生きていきましょう、だなんて――確かにそれはかなえば美しいのは間違いないのに、「そんなものは存在しない」から釈似が生まれていることには誰も気づいてくれないのである。
クロヒョウが口の端から泡とも血とも着かぬ何かを吐いていた。ぐったりと寝転ぶ横顔は、すでに血にまみれているのに釈似を見上げている。
「なんて目をするんだ」
――いつか、真の獣に堕ちる日が来るだろう。
刀の切っ先で、首に巻かれる羊皮紙をほどいてやった。「あるだろうな」と思っていた名前が書かれている。
「首はやれないよ、『釈似』」
どうせ、死ねば罪人も善人もどこに行けるかわかったものか。
後悔ならきっと地獄でするだろう。ただ、今じゃなくていい。いつか己で始末をつけるのだから。
だから、それまでお預けだよと――内なる憎悪の黒に囁いてやった。
大成功
🔵🔵🔵
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト
◎
けもの
さて。取り立てて目立つ何かが無いとすれば、俺が出て来ような
なれば姿などあるまい
がらんどうの残骸に絶無を詰めて駆動するもの。中身に色も形もありえぬのが道理
無論それに名もありはしない
強いて言葉にするならば、全。或いは空虚
名がある理由すら無いものに名付けるのは無意味だが、無ければ一個体であるものには認知すら出来んのが困りものだ
解っていたことだが再確認だな
中身も、それに感動がないことも
発生時点で形状以外に人らしい要素は得ていなかったということ
ならば。矢張り猟兵であったことは幸い
眩い「ひと」に迫る脅威と対峙しうる身であったことを喜ぶとしよう
 グウェンドリン・グレンジャー
グウェンドリン・グレンジャー
×
(足をつつかれて、足元の存在に気が付く。図体の割には、随分と気弱そうなワタリガラスだ。目線を近くしてみる)
あなた、けもの?
(大鴉の嘴と蹴爪にはまだ新しい血。気弱に見えても捕食者かつ、死肉喰らいだ)
一生に一羽としか、番わない鳥、なんだっけ。あなた
うーん、ピンと、こない……スキって、気持ち、分からない……
(突然、気弱そうだった大鴉が狂暴そうに劈く)
(一瞬、なぜだか脳裏に翳るよこしまな発想。完全に邪神に堕ちたら、きっと絶対に斬りに来てくれる人ならいる)
(瞬間的に浮かんだその考えは、すぐ潜在意識の底へ沈む)
どうしよう、ぐるぐるする……やめて、痛い痛い、つつかないで
うわ、でっかくなった
※アドリブOK
●
ぼんやりと、足元をつつかれていた感覚に気づく。
グウェンドリン・グレンジャー(Heavenly Daydreamer・f00712)は、自分の前に一冊のファイルが飛んできたから、エサを与えられる雛のようにそれを受け取ったのだ。
ばさばさはたはたと中身の書物を鳴かせながら駆けつけるような動きは、グウェンドリンにとってまるで人に懐いたオウムのように思えた。触れれば、あっという間に真っ白な世界が生まれる。四方八方、どこを見ても白いものに囲まれて――どうしようかなあ、なんて呑気に考えていたところに、その感覚があった。
「あなた、けもの?」
己の側面だという。
ワタリガラスである。並のカラスが「クロウ」と英語で称されるが、彼らはあまり好いイメージを持たれない。生ごみを漁る不浄の象徴とされるカラスと性質も傾向も似ているが、こちらは「レイブン」と訳される種だ。
人間の四歳程度の知能を持ち、その生きざまは「将来を見据えた行動をとる」と研究結果で明らかになっているほど、高度な知能を持つ鳥である。UDCアース、イギリスでは「ロンドン塔からワタリガラスがいなくなると、イギリスは滅びてしまう」なんてジンクスもあるほど高位な存在であった。
とはいえ、いざ対面してみると大きな羽をもつわりに両足で跳ねて、すこしこの個体は臆病であるらしい。目線を近くしてみて、グウェンドリンはしゃがみこんだ。
「――血がついてる、よ」
北欧神話での偉大なる神のみつかいと言われるほどであっても、やはり死肉喰らいであり食べるものは並のカラスと変わらない。くちばしに触れてやろうとして、烏が後ろにてんてんと跳ね拒絶されてしまった。
行き場をなくしたグウェンドリンの右手が、どうしたものかとその足を見る。新しい血がついていて、真っ赤な足跡を白い空間に残していた。
臆病な烏も、やはり捕食者である。――グウェンドリン自身が捕食者であるように。
胃腸の調子が悪ければ草を食むが、基本的には肉食だ。「食べられればなんでもいい」という気分はあっても、かなりの偏食である。そう、好き嫌いを判別するだけの頭脳はあって、なにより。
「一生に、一羽としか、番わない鳥、なんだっけ。あなた」
くる、とグウェンドリンと物理的に距離を取っていた首が彼女を見る。カァ、と相槌のような小さな声に、「そう」と返事をした。
「……、うーん」思案する声も無理はない。グウェンドリンは、確かに夫婦の間から生まれてきた一人娘である。とはいえ、その親同士の愛情が確かに機能していたかどうかは記憶に遠く、父親のエゴあふれる愛情の結果が今の姿だ。両親は謎の失踪をしていて、まさか長期のハネムーンと洒落こんでいるわけでもあるまい。
グウェンドリンの身の回り――特に、親族にはそういった「お手本」がないのだ。
「ピンと、こない。……スキって、気持ち」
カラスから目を逸らす。
「分からない」
――ぎゃあああ、と鋭く鳴かれてしまった。
目をぱちぱちと瞬きして、突如暴れだす烏の姿に表情の乏しい少女がわずかに驚きをあらわにする。「ど、したの」と声をかけても、烏は黒い羽をまき散らして暴れるのだ。両翼でグウェンドリンの足を叩くように羽ばたき、跳ねて、まるで責め立てるように彼女に詰め寄る。自然と、グウェンドリンはそれに合わせて一歩二歩と後ろに下がってしまう。
「え、なに、ねえ、どうしたの、ちょっと」
足すらつつかれだしてしまって、たまらず獣の情動に恐怖する。グウェンドリン自身、ここまで心を揺さぶったことがないのだ。この獣を見ていても、到底自分のものなのは思えないでいるのに――。
「あ」
ふと、よぎってしまうのは。
よこしまな考えであった。グウェンドリンに寄生させている邪神の破片を、好きなようにさせてみたら、――必ず斬ってくれるだろう彼がいる。
望んで手に入れたものではない器官は、確かに父の愛からのものだ。ならば、自分もその「愛」を使って「愛」を得るのが正当ではないか?
「あっ、――どうし、よ」
ぐるぐるする。がくんと膝から力がぬけて、ふらつく。カラスの責めるようなついばみに「痛い」と短く悲鳴をあげて、いそいでその邪念を消した。いけない、いけないことだった――どうして「そうだ」と笑ってしまったのだろう。自分の頬から感情が失せたことを、これほど安心したことはない。
「わ、でっかくなった」
両頬を抑えて首を振ったグウェンドリンが、無意識に感情を押し込んだとき――大鴉はずんぐりと、彼女が認めない感情の分だけ大きくなっていた。
●
何もなかった。
アルトリウス・セレスタイト(忘却者・f01410)の前に広がる光景には、いつまで待っても獣のすがたが現れない。少し楽しみにしていたのだが、――おおよそ、彼を単位で表現できるけだものなどいないのだ。
「まあ、わかっていた」
襟首を撫でてから、腕を組む。白い空間はどこまでも白く、ずっと眺めていればたちまち自分がどこに立っているのかも分からないだろうと思われた。
アルトリウスは、がらんどうである。
たとえるなら数式であるといえば最も近い。書かれた文字と数字は正しい答えを導き、人々の解明したいものを解き明かすしるべとなる。せかいそのものを取り巻く大きすぎる力、その残骸が彼だ。
いうなれば「無限」であり、「無限」であるがゆえに質量として表記できない故の「ゼロ」なのだ。
彼という「ひと」はどこにもいないのである。この呪詛結界がうまく働かないのも、無理はあるまいと思えた。
「――名が無ければ一個体であるものには認知すら出来んか」
困ったものだな、とまるでそんな素振りもない口調でつぶやいた。
アルトリウスには、元来名前が必要ない。掲げる登録名も、識別として「ひと」の発声の範囲で可能な言語で選出した文字の配列に過ぎない当たり障りのない名であった。
結局、「おおきすぎて存在がわからない」ものなのである。邪神程度で彼を計測することもできないだろうし、彼とて本当に自分がどれくらい大きな存在なのかは機械的に算出はできても、きっと途方もくれる時間がかかるだろう。それほど、絶対の存在だった。
故に――彼を形容できる獣は、どこにもいないというのが解である。
解っていたことだが、再確認に過ぎない。
肩を少しすくめていた。当然の結果だ――どんな掛け算にも割り算にもゼロを代入すればゼロになるように、足し算引き算においてもゼロ相手では「かわらない」。
アルトリウスには中身もなければ、感動もないのだ。発生時点で形状以外に人らしい素養は得ておらず、そこから感情の発露も乏しい。成長、という点においては――なにもない、というのが結果だ。
「ならば、幸い」
それがわかっただけでもよい。
真黒な手袋を握った。キィ、と甲高い音がして――呪詛域ははじけ飛ぶ。アルトリウスを隔離するような空間の破裂とともに、隣で鴉につつかれる少女の姿を見た。躊躇いもなく近寄って、鴉の首から落ちたであろう羊皮紙を手に取る。
「グウェンドリン・グレンジャー」
――眩い「ひと」に迫る脅威と対峙しうる、絶対の味方である。
それを喜ばずとして、何を喜べというのか。アルトリウスだからこそ、この呪詛は「ゼロ」にできる。
「落としていたぞ」
大きな烏にいじめられていた少女に語り掛ける背は、ちっとも揺らがない。
青色の瞳を、逃げ回るうちにくしゃくしゃになった髪のまま、グウェンドリンが見つめ返していた。
「あり、がと」
「いいや。――傷を治す。そのあとからでも、追うのは容易い」
動揺こそ顔に現れぬ烏の少女の傷を次に見て、アルトリウスが書斎を見回す。
獣の気配もない。代わりに、部屋には無数の直方体があった。真っ白のその数だけ――猟兵たちが閉じ込められている。
「もう少し時間もかかりそうだからな」
向き合う時間だった。
蓋をした感情にも、思い浮かんだ顔にも、心にも、――あの烏が怒り散らす理由を考える空白の時が与えられる。
グウェンドリンは、なぜだかどくどくと自分の脈が早まっているような気がして、そうっと自分の足に出来た無数の傷を撫でていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 百鳥・円
百鳥・円
×
なにかが抜け落ちたような気がしますね
それが何なのかはわかりません
本は答える口は持ち合わせてないのです
八つ裂きにすれば喋るのでしょうか
返せよ
はあ、何です?コレ
ニンゲンを翻弄する狐
夢喰らいの羊
微睡む姿は獏でしょうか
不完全に混ぜ合わされた出来損ないの獣の姿
わたしの姿を見せてるんですか?
なんだかおかしいじゃあないですか
わたしならば何故眠りから醒めてないんです
何故、涙を零しているんですか
纏わりつくような水色の花弁たちが鬱陶しい
違和感ばかりで腹立たしい
全て全てを八つ裂きにしてやりたい気分だ
わたしは人を喰いものとする夢魔
血も涙も必要ない
満たすのは享楽のみでいいんです
何故
溢れるような雫が焼き付いて、離れない
 橙樹・千織
橙樹・千織
△
目の前で唸る瞳以外が漆黒の獣
大型の体躯に角と翼
その特徴に息を飲む
…所詮、私は獣ということ
浮かぶのは自嘲の笑み
容赦無く急所を狙ってくる獣
確実に狩りに来ていると理解はすれど
致命傷を避け、受け流し、いなすのがやっと
…!
ほんの一瞬
己を睨む深紅の瞳と目が合った
本能の向こうに見えたのは
孤独への恐怖
あぁ…そう
そういうこと…
抵抗をやめ
その爪を牙を受け入れる
前世を覚えている
本能を秘めている
それらを知った彼らが離れてゆくかもしれないということが
まだ
こわい
影のような黒さは
それを押し殺し
ひた隠しにしているから
そう、ね
紛れもなくお前は私
だから
その爪が牙が誰かを傷付けてしまう前に
帰って、来い
あかに染まるのは
私だけでいい
●
本を見下ろした。
「あー、なんっか」
わざわざ整えてきた髪の毛を左手でかき回す。
「抜け落ちたような気がしますね――」
百鳥・円(華回帰・f10932)から抜け落ちたものが何かが思い出せないでいた。わざわざオシャレな服まで着て、ご機嫌に森の中まで歩いて事件の解決に努めていたご褒美には納得できない。
あまりにも、気分の悪い術式が働いたような気がするのだ。今なら指を喉の奥に突っ込んで吐き戻したほうがすっきりしそうな気までしてくる。
「返せよ」
ブーツで本を蹴った。
飛んできたから受け止めてやったらこの仕打ちである。ブックカバーはつぎはぎで、ちっとも洒落ていない。ばさばさと薄いページ数はまるで絵本めいているのに、中身は真っ白でがらんどうだ。世界は、呪詛に包まれて――すっかり円は囲われていた。
眩しい世界に色違いの瞳を細めていたら、のしのしと前から歩いてくる何かがいる。
呪詛から呼び起こされるものが円の側面であるという筋書きならば、それはそれは、愛おしいものが出てくるに違いないとは思っていたのだ。一日の苦労を動物でいたわれるというのならば、まだ許せていたのに。
「はあ?」
目の前にやってきたのは、とても「かわいい」とは言えなかった。
のたのたと歩いてきたそれは、ばたんと円のそばにやってきて寝そべっている。
顔はキツネだ。鋭い鼻っ面が特徴的であった。薄い顎と細い喉をさらけ出して、舌を垂らして眠っている。しかし、その顔の横には――在ってはならないものがあった。角である。
羊の角だった。キツネの顔にはおおよそついていないはずの大きな鞠のような体は、もこもことした毛皮も相まって、おおよそ豚のように膨れ上がっている。しかし、その足を見てみれば――ゾウのようだった。結論としては、これほどまでに腹を膨らせても歩ける構造と言えばバクであろう。
尾はキツネであるらしい。ふわふわの尾先が、また腹正しかった。
「何なんです? コレ。悪趣味すぎるでしょ、笑えませんよ」
――誰にあたれるようなことでもない。
どう見ても、不完全な出来損ないの獣である。おおよそ「いいとこどり」をしようとして大失敗をしてしまったような毛玉のお人形のよう。円が、その痛ましい姿を自分として受け入れられないのは必定であった。
「なんだかおかしいじゃあないですか」
――だってだって、円ちゃんはこんなにもかわいいんですよぅ。
気にかけているとも。
夢魔と狐の混ざりものだ。醒めない夢を届けるには、やはり円自身が「夢」の象徴であらねばなるまい。
美しく、かわいらしく、堕落にいざなうために妖しく、色と茶目っ気たっぷりに導くのが円である。
望むものを与えて対価を得る。人を食い物にして、偽りに置き換えて想いを得る。喰らうも集めるも好き勝手にやってみせて、つらい現実なんてなんと馬鹿げているのだと教えてやるのが魔の役目なのだ。
己を生み出した両親が、どういった意図で混ざり合ったかなどには微塵も興味が無いが――。
「何故、涙を零しているんですか」
どうして、獣は眠りこけているのだろう。
いびつな獣であることは否定しないにしても、これではまるで、円そのものを否定するようなものだった。これでは、「夢」に食われているのは円のほうではないか!
ぐったりと眠る肉のかたまりは、ほろほろと涙を零している。なんど体をゆすっても、起きる気配が一向にない。
「どうして」
水色の花弁が、獣の涙からはらりひらりと変わっていく。
あふれるようなそれが、円の体を撫でまわして空気の流れもないのに、白の空間に飛び立っていくのだ。
「なぜ」払いのけているからである。円がもがくように、水色の花弁を振り払っていた。
――血も涙も必要ないのに。
「おきてください」
獣の、体を揺さぶっている。ぼたぼたとどこからかこぼれた液体が、毛皮を濡らしてしまっていた。混ざる黒は、円の化粧の色だ。せっかくきれいに仕上げてきたそれも台無しになっているのがわかっているのに、どうしてか止まらない。
「ちょっと」
すべて、すべてを八つ裂きにしたい気分で――何もかもが、おかしい気がしてしまう。
熱いしずくに頬を焼かれているような気がしてしょうがない。ぼたぼたと頬に水路ができてしまって、壊れたように流し始めてしまった。
――人を食い物にしている。
それ以上はないはずだった。享楽的で、楽しいことだけを食べて、おいしいところだけ持っていく。
悩むことなんて一つもいらずに、ただただひと時をいかに快適に過ごすかだけを考えて生きていればいいだけ。そう、そのはず、なのに。
どうしよう――。
初めて、円は「悩んでいる」。
わからない、ということが頭の中にいっぱいになってしまっておそろしい。自分は、一体どこにいるのか。どうして、この獣は円だというのならば夢から醒めてくれないのか。ずっと眠りっぱなしのそれは、円の――どこなのか。
「教えてください」
まるで迷子なのは。
「どこからきたの」
――円だけだ。
●
漆黒の獣がいた。
大きな体はしなやかで、しっかりとした力を感じさせる。羊の角を持ち、鳶色の翼を背にしたそれが、まるで空間を支配するかのように羽を広げる。
橙樹・千織(藍櫻を舞唄う面影草・f02428)は、息を呑んだ。己の獣性に理解を示したのは、つい最近のことである。出来れば、誰にも知られたくない血なまぐさい己であった。
――しかし、やはりこの大きさと強大さ、煌々ときらめく真紅の瞳に理解が及ぶ。とても、隠せたものではないのだ。
所詮、千織はけものである。
強大な己の側面を前に、思わず顔に浮かんだのは自嘲の笑みであった。こんなものを、いつまでも隠せると思っていた己は明らかに愚かであったし、よくも今まで目を逸らせていたものだと思わされる。
ネコ科の轟くような鳴き声を上げながら、真っ赤な口内を晒して獣は吠えた。
ひと鳴きするだけで、びりびりばりばりと空気が揺れる。「襲い掛かるぞ」という警告の音に、たまらず素早くなぎなたを手にした。戦闘態勢が整えば、獣は容赦なく襲い来る!
急所を的確に狙う獣は、まず千織の細い体を横に薙ぎ倒そうと左手で横に爪を振った。鋭く薙刀で応戦しようと振る千織は、その腕を確かに裂く。しかし、痛みで退かない獣は――ぐっと押し込んでくるのだ。
「っきゃ」
思わず悲鳴が漏れる。体が浮いた!
空間には終わりが見えない白である。ここで地面という確実な足元を奪われた恐怖は、通常の戦闘空間と異なった感覚があった。たまらず、すばやく離脱を試みる。押されてはじかれる体にじんじんと痛みを走らせながら、しかし着地はつま先からしっかりと行う。ざ、ざざ、と右足のつま先を起点として、左足を後ろに下げればちょうどコンパスのようだ。半円を足で書いてから、薙刀を構え直す。
しかし、獣も息を吐く暇も与えてくれない!
ぶうんと大きな尾で脳天を狙ったテールアタックが待ち構えていた。真正面から受ける気はなく、後ろに飛ぶ。したたかに白の空間に打ち付けられ、足場が揺れた。ひび割れることがないのが幸いだと頭の片隅で思う。
――獣は、確実に狩りに来ている。
「ッは、――はァ、ッ、は、っ」
案の定、千織は何度か爪と己の武器をかち合わせてみるものの、正直なところ応戦がやっとだ。
討伐という文字に至る活路がなかなか見いだせないでいる。驚異の象徴である「自分自身」の側面のおそろしさをその身で味わっていた。
こんなおそろしいものを、ずっと隠してきた。
「――、!」
睨む深紅と目が合った。
獣は真っ黒で表情こそうまく読み取れないが――その目は本能にぎらついているのに、何か別の、焦りにも似た物を感じさせる。
「ああ、そう」
それは、千織が何度も鏡の前で見たものと似ていたから。
「そういうこと」
血煙とともに、千織は爪になぎ倒された。
あっけない。細い彼女の体は、獣がとびかかると同時に強く床に打ち付けられることとなる。のしかかった獣が、抵抗をしない千織の顔を覗き込みながら、聞いたこともないような鳴き声を上げていた。
「こわい」
ぽつり、呟く。
――獣の獰猛な息遣いが止まった。
右手は爪の裂傷で動きそうにない。代わりに、左手をゆっくりと持ち上げた。薙刀を握っていない細い指で、柔らかい体の上に乗った獣の頬を撫でてやる。
「こわいわよね」
――隠れようとしていた。
影のような黒さは、この毛並みは、ひた隠して、人に好かれるのは「好い自分」だけでいいと思っていたからだ。
愛らしく微笑んで、皆のために微笑みかけ、やるべきことは理性的にやれる自分だけを知ってもらえればいいと思っていたのである。
なのに、――もう、「わかってもらえない」ことは怖くてたまらなかった。
前世を、覚えている。置いて逝った罪を犯してしまったことからもう目をそらすことはできなかった。
本能を、秘めている。真っ赤な血肉を貪る獰猛な獣である自分を隠すことは、もう難しかった。
知られてしまうことは恐ろしい。受け入れられないと突き放してしまう人もいるかもしれない。
だけれど、もう目を逸らせない「いままで」を自分で認めてやれないのも、つらくてしょうがない。
「お前も、寂しいでしょう。だから、――帰って、来い」
どうして、自分で自分を認められることがないのに、誰かに代わりを願おうと思ってしまったのだろう。
どんな自分でも愛せるのは結局のところ、自分だけなのだ。
他人にそれを任せることの重さを知っていたから、隠していたことは間違いではないのに――自分のことを自分で認めないのは、いたずらな自傷にもよく似た抑圧である。
「あかに染まるのは、私だけでいい」
この獣に内から食い破られたとしても。
きっと、この獰猛な黒い獣のこころを知った今ならば、「いいんだよ」と抱きしめてやれるから。
千織は紡ぐ。その獣が一番求めていただろう、『認める』言葉を。
「お前は、私だよ」
――帰ってきていい、居場所の話を。
●
【剣舞・柘榴霹】。
躊躇いなく二つの空間が切り崩された。真っ白な立方体が無数に並んでしまっている書斎内を見渡した千織は、すぐさま隣の四角をこじ開ける。ばきんと割れた空間に――丸くなって眠る円の姿があった。
「百鳥・円さん」
体をゆすってやる。呪詛から呼び起こすための、彼女を彼女たらしめる名前を読んでやった。丁寧で穏やかな声を耳に注がれて、円はゆっくりと――潤んだ世界で目を覚ます。
「あれ」
「起きられましたね。ああ、よかった」ほっとした千織の顔色には安堵が広がった。
「ああ、っと――すみません、寝ちゃってましたねぇ。おきます、おきます」
円が未だにまどろみから抜け出せない瞼の重さにあらがおうとするのを、「いえ、いえ」と逆に千織は座らせる。
「ひどく顔色が悪いので、少し休みましょう。まだ出て来れない皆さんもいますから」
「――でも、大丈夫ですよぅ」
「あの」
気にさせては申し訳ないのですが、と付け加えて「ずっと、先ほどから泣いていらっしゃるので」と千織は二つの潤んだ宝石を見る。円は、「はえ?」ととぼけた調子で声を返したが――ああ、とどこか納得した素振りがあった。
「そ、ですね。ちょっと、疲れたのかもしれません」
「ええ」
詳しくは聞かない。だけれど、隣に両膝をついて座る。うなだれるように華奢な自分の太ももを眺め、へたりこむ円の背を優しくなでてやりながら、――孤独の獣は、確かにその力を取り戻していた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 霧島・クロト
霧島・クロト
◎
――心配すんなよ、
兄弟以外誰も信じられないって面しやがって。
今の俺も、お前も、そういうことにはならねぇよ。
白狼……の割に汚れちゃいるのも知ってた。
なにせお前は『出来損ない』と
罵られてた俺の源流でしか無い訳だ。
気に入らねぇ奴は噛み潰すのは一緒だ。
――おっと、怯えんなよ。今の『俺ら』は認めさせたからな。
だが、悪りィな。お前が居ないと出来ねぇこともある。
そう、気に入らねぇ奴を噛み潰しに行くのさ――
『いい子』を喰い物にしたクソ野郎が俺は『気に入らねぇ』。
お前は俺の源流である以上、
お前が戻ってこなきゃ、俺は『俺』じゃねぇ。
だからこそ――『戻ってこい』よ。
※アドリブや連携可なのでお好きに!
 ティオレンシア・シーディア
ティオレンシア・シーディア
×
――現れたのは、黒檀色。
とめどなく滴り落ちる緋色に濡れた焼け焦げた羽、しかしながら体には傷一つない。
鳴くでも飛ぶでもなくただそこにいてこちらを見つめる、一羽の鴉。
…結構前の話だけど。幻影で負の感情を引き出す邪霊に言われたことがあったわねぇ。
「殺意と憎悪と絶望、お前の感情はもう一つある。それは怒りでも憎悪でもなく――埋めようのない悲しみであろう」…って。
…ねえ、「アタシ」。
そういう感情があるのはわかってる。
だからそういう場面ではそういう演技(フリ)もできるし。
最近も一度だけ、泣きたくなったこともあったけど。
――「悲しい」って…どんなのだっけ。
(参照シナリオid:10404・10616)
●
現れたのは、黒檀色の鴉だった。
どこの都会でも見かけるハシブトガラスである。
死肉をも食らい、飛び回り、生き汚い彼らが小さな雀と元は同じというのだから不思議なものだ。
――ティオレンシア・シーディア(イエロー・パロット・f04145)の前に現れたけものは、鳴くでも飛ぶでもなく、ただじいっと持ち主を見ている。
「なによぉ」
咎めるでもないつぶらな黒色は、まるでガラスで出来た眼球のようだった。
テン、テン、と跳ねてやってきた両足にはくれない色がにじんでいる。鴉が跳ねて寄った痕がよくわかった。この鴉は、けがをしているらしい。
飛ばないのではなくて、飛べないのである。
焼け焦げた羽根はほとんど使えないだろうとティオレンシアから見てもわかった。
空を飛ぶ彼らは、その羽の一枚一枚が大事なのだと――酔っぱらいの間で博識ぶる男が、しんみりぶって語っていたのを覚えている。
こんな時に「うんちく」も役立つのだからバカにできないなと思いながら、その鴉が改めて自分の側面だと見せられていた。
とても、似ているとは言い切れない気がするのだ。
「かなり前の話なんだけどねぇ」
覚えてる? と鴉に問いかけながら、しゃがみ込んでみる。
都会でも田舎でも生きていけるこの鳥は、自分とは大きく離れた存在のように思えるのに、そういえば「どんなとき」も見かけたなと思ったのだ。
「言われたことがあるのよぉ」
――あの時は、さすがに居なかったように思えるが。
『殺意と憎悪と絶望、お前の感情はもう一つある。それは怒りでも憎悪でもなく――埋めようのない悲しみであろう』。
敵の言ったことを真に受けるほど、ティオレンシアも日和っているわけでない。
しかし、どうにもずっと、痛いところを踏まれたような気がしてならないまま引きずっているのも事実だった。
ここらで少し、この鴉相手に愚痴程度にもつぶやいて見ようかと思っただけであるのに、なぜだかその焦げた羽根をみていると――思い出すのは、あの時の衝動だった。
できるだけ甘ったるく話し、愛想よくふるまってきたティオレンシアは、人間として生き延びるためにその感情を「喪った」と思っていた。
燃え盛る空、紅い龍、血、肉、死体、死体、死体、――『あの子』。
思い出すだけで、全身にぐわっと熱が灯ったような心地になる。細めた目が大きく見開かれて、緊張が体中に走っていた。
この鴉とは対照的だ。鴉は、燃えた羽をつんつんとつついて血を垂らしても痛みをあらわにしない。
「どうして涼しい顔してられんのよ」
――思い出すたびに、ティオレンシアの神経は昂ってしまうのだ。
厳重に蓋をしたものが緩んでしまった、というのもある。
一度心は閉じ込められたストレスを解き放たれてしまうと、何度でも飛び出させたくなってしまうのだ。
もっと早くにこの感情と向き合っていれば、今ティオレンシアがうずくまって呼吸を整えようとする手に血はにじまなかったかもしれない。ぎゅうっと爪が掌に食い込んでいた。
「そういう感情があるのはわかってる」
じいっと話を聞くだけの鴉に、何を言っているのやら。
本当に聞こえているかどうかもわからぬけもの相手だから、語れているのかもしれない。
「だからそういう場面ではそういう演技(フリ)もできるし――最近も一度だけ、泣きたくなったこともあったけど」
大好きな子の幻影を見た。
見なければよかった、取り戻せるなんて思わなければよかったと今でも思う。
後ろ髪を引かれるどころではない、ただただ、あの場所に必要だった自分が、必要な役目を果たせなかっただけだと理解できているからこそ、後悔でいっぱいになって――ツンと鼻の奥が痛む。
「教えてよ、鴉って頭いいんでしょ」
泣いてあげられたなら、申し訳ないと自分を【絞殺】しそうなこの苦しみから逃げることができるだろうか。
解放されたい、と思ってしまう自分がどこまでも卑怯だ。しょせん、あの町に必要だったのに力不足だったことには変わらない――もっと覚醒するのが早かったのなら、とどれだけ後悔しようとしたかわからない。
そんなことをしたら、またあの地獄の中で殺意を振りまいていた自分から戻れそうな気がしなくて。
ふ――ッと長く、息を吐く。
「『悲しい』って、――どんなのだっけ」
鴉は心底、不思議そうであった。
だって、もう十分――悲しんでいるように見えていたから。
●
「心配すんなよ」
目の前に現れた四つ足のけものは、すっかり体を丸くしてうう、ううう、と唸り声をあげている。
怒りというよりも、怯えのほうが勝っていた。
へっぴり腰の威嚇は情けない有様だが、それが霧島・クロト(機巧魔術の凍滅機人・f02330)の側面だと言われれば、本人である彼は「ああ」と納得できるところがあったのだ。
「兄弟以外誰も信じられないって面しやがって」
むしろどこか、懐かしむような顔で困り眉をつくってから、微笑みかけてやる。
片膝をついて、しゃがんでやった。
機械の体がきしむ音に驚くオオカミに、「大丈夫だって」と声をかけた。
――白狼のわりに、汚れている。
泥だらけの狼である。恐らく十分に毛づくろいも出来ていなければ、そういったことを群れの中でも優先されなかったのであろう。
クロトは、おおよそこのオオカミの境遇を予想できた。
なにせ、『出来損ない』と呼ばれていたクロトである。
如何なる氷結の魔術を扱う機械のオオカミになったとしても、望まれていたのは天狼だ。それに匹敵しない「クロト」などは、必要のないものとして扱われていた。
「だが、気に入らねぇ奴は噛み潰すのは一緒だ――おっと、怯えんなよ」
お前の事じゃないよ、と両手で制す。
すっかり耳を真横に倒したオオカミに、からからと笑いかけてやったのだ。「今の『俺ら』は認めさせたからな」と、まるで悪戯を共有する少年のような温度でささやく。
「クロト」は、事実上の成功作となった。
――兄を見つけ、祖である父を知るまでに至る。
結局のところ、「認めさせる」には十分な実力を備えたのは、己の欠陥を理解し、受け止め、気に入らぬものを噛み砕く熱量を持ったこの鉄色にそまったオオカミだったのである。
野生の世界と同じだ。
要らないものから淘汰され、必要なものだけ残るように、クロトは「生き延びる」ことで存在を周囲に認めさせることに成功した。
それは時に、敵相手のことでもあり。時に、猟兵同士の交流における友情のことでもある。
強ければ強いほど、仲間にもそういった人物が集まりやすい。
単純に、強い仲間を信じるというのはクロトにとっては「固い」手だ。
兄弟以外誰も信じられないというところから、――「きょうだい」以外の世界を知った時、オオカミは己の汚れを誇ることができたのである。
だから、今のクロトにはこのオオカミを超えることができる力が備わっている。
「だが、悪りィな。お前が居ないと出来ねぇこともある」
じゃあ、俺なんて要らないんじゃないの――そう言いたげにおずおずと後ろに下がったオオカミに、ずいっと一歩近づいた。
「お前も俺で、俺もお前なんだ」
このオオカミは、クロトの源流だ。
「そりゃ、お前は今の俺よりずっと弱いぜ。ぶっちゃけ、最低の俺だと思う。実力でも、なんでも」
ずびし、と指先で示してやれば、あからさまに落ち込んだオオカミだ。情けねえ顔しやがって、とその頭を突きつけた指を作った手で撫でた。
「だけど、必要なんだよ。お前が居たからなんだ。俺は、お前の源流じゃねェか」
もっと誇っていいんだぜ、と弱さに震えるけものの頭を何度も撫でてやった。「来いよ」と声をかけて、両腕を広げた。やはり弱弱しい足取りで寄ってきたオオカミを、ぎゅうっと抱きしめてやる。
「気に入らねェ奴を噛み潰しに行くのさ。お前だって、気に入らねェだろ?あんな――『いい子』を喰い物にしたクソ野郎はさ」
こんな気持ちを感じることすら、どうしてだろうと震える時代があったのだ。
どうして命じられたことを淡々とこなせないのだろう。同じ顔をした兄は、ほかの「クロト」たちはそうでなかったのに、どうして「俺」だけは――妙にこころなんてものをたくさん持って生まれてきてしまったのだろうと、鉄色の毛並みを恨んだ日々だってあった。
だが、今は「だからどうした」と鼻で笑ってやれる。
「『戻って来いよ』。一緒に行こうぜ」
それが、霧島・クロトだ。
サイボーグのくせに感情を喪うこともなく、任務に感情を交え、己の行動には合理性よりも「どうしたいか」で選ぶ。
半端もの上等だ、とオオカミは力を誇ることにした。かまうものかと開き直ったと言われてもいい。――それで、多くを助けることで自分が『スッとする』のならば。
「やろうぜ、『俺』」
今目の前に、『助けたい』奴がいるんだから。
ここで動かないやつが一番恥ずかしいんだ。そうだろう――。
●
「おーい、……えーと。ティオレンシア・シーディア」
はた、と意識が戻る。
うずくまって硬直していたらしい。額を抑えていた手がやけに痛むのは、ずっと頭蓋を圧迫していたからだ。ようやく前頭葉の血のめぐりが良くなったような気がして、ティオレンシアは顔を上げた。
「あらやだ――何分経ってんのかしらぁ」
「俺があんたを発見してから五分くらいだから、まあ奴さんとは三十分差くらいかもな――オイ、大丈夫か」
「え?」
「いや、――気を悪くすんなよ。今、酷いカオしてるぜ」
もう、目の前に鴉が居ない。
ティオレンシアのそばにさっきまで、沈黙のまま責めるような鴉が居たのに――結局、それから聞けることは一つもなかったな、と思う。緩く首を振って、いつも通りをこころがけようとほほに触れるのに表情筋はすっかり固まってしまっていた。
「大丈夫よ」声の間延びもできない。舌がもつれていた気がして、咳ばらいを挟んだ。
――大丈夫、そう、大丈夫。
悲しいなんてわからなくても、――大丈夫のはずだったのに?
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ロキ・バロックヒート
ロキ・バロックヒート
×
※名乗るのは名前のみ
てっきりよくそれっぽいって云われる猫かなにかだと思ったのに
目の前に居るのは尾を噛もうとする蛇だ
どこからか伸びた鎖の枷を外そうと暴れて身を地に擦り
辺り構わず噛んだ歯もボロボロで
それはあまりに必死で滑稽なほど
“完全なもの”に成ろうとしている
そもそも尾を噛めるほど大きくなっていないし
皮膚に食い込む枷にも縛られて
もうほとんど動くこともままならない
ただ蜜彩の瞳だけが爛々と輝く
こうまでしておまえが成りたいものってなんだろう
“ ”は全知全能でないといけない
“ ”は慈悲深く救いを与えないといけない
私は―“ ”とはなんだっけ
たまにわからなくなるから
気付けば蛇のように己の指を噛もうとしている
 カイム・クローバー
カイム・クローバー
△
俺の中の獣性は狼。銀色の毛並みに所々に返り血を浴びた、図体はデカくて口からだらしない涎を垂らした力に飢えた獣だ。猟兵の中にも力を求めるヤツは多い。――俺も例外に漏れずその内の一人だ。
俺を殺して取り込もうって腹らしい。普段俺が抑えている欲望を解放したいんだろうが…生憎と好きにはさせてやれないぜ。
魔剣を持って対峙。力を求める己の獣性を俺自身の力で叩き潰す。きっと何の証明にもなりゃしない。
俺の中の獣は今もずっと俺の力に関心を示してる。身体に眠る邪神の力を欲してる。解き放ちたい。暴走させたい。――スベテヲコワシタイ。
UCで獣性を殺して落ちた羊皮紙に目を落とす。
俺は人間だ。…化物になるつもりはねぇ。
●
てっきり、「よく似てる」と呼ばれる猫が現れると思っていたのに。
ロキ・バロックヒート(深淵を覗く・f25190)の前に現れたのは、円を作る蛇であった。
「立派だねえ」
のんきな声で、そう呼ぶ。
――とにかく、口から息でも吐かないと場に満ちた呪詛に「あてられている」のが自分でもわかってしまうのだ。
もとはといえば、ロキは邪神である。ゆえに、この状況は「とても心地が良すぎてしまう」のだ。
邪神が再誕する準備を整えているこの場は、あまりにも彼にとって豪勢な料理の並ぶホテルバイキングに等しい。
だから、何度もひとがたに詰まった内臓を動かして、気をそらす。
しゅるしゅると、どこに潜んでいる蛇であるかまではロキも知らぬ。そもそも、蛇に多種多様な模様があったとて、さほど気にならないたちでもあった。
ロキのことをちらりと見ることもなく、懸命に自分の尻尾を追いかけている蛇はどこか甲斐甲斐しい。
「無理だよ」
教えてあげても、全くいうことを聞かなかった。
どこからか伸びた鎖の枷をはずそうと、時折体を持ち上げてぶらぶらと揺れる。
それから、地面に己の重さを使って砕こうとするのか、首に締められたわっかを擦り付けたりなどをして逃れることから必死だった。
「無理だってば」
ロキは、知っている。
答えを見透かす神に、ふしゃああと威嚇の口が開かれた。「黙ってろってこと?」とロキが返事をすると口を閉じる。はいはい、と肩をすくめてやった。
そもそも、――尾を噛もうとするにはまず、長さが足らない。
蛇は大きくなっていない。獲物がまずないのだろう。痩せた蛇は背骨を浮かせて、それでももがこうと必死に時に波打っている。
横目でそれを見ながら、どこか苛立ちを感じさせられていた。
滑稽を通り越して、哀れでもあり、怒りを覚えるような心地があるのは――まさに正しく、同族嫌悪であろう。
皮膚に食い込む枷に縛られ、自由はない。
それでも蛇は、体に紅い染みを作りながらも必死だった。
ただ蜜彩の瞳だけが爛々と輝いていて、終わりのない抵抗にあきらめるようなそぶりがない。
痩せた今ならばわっかから抜け出せると思っているのだろうか――どうせわっかは締まるだけなのに。
「無理でいいのに」
――あきらめているだけでしょう。
いつかの「もしも」の声が響く。あれは、夢の話だった。
今も夢のようなものだ。いつだって、ロキは邪神たる己の中身に向き合わないままのらりくらりとおしゃべり上手な猫ぶっている。
その実、彼は――猫のような愛らしい毛皮を持たないというのに。
蛇は、人に共感できないのだ。
飼育するうえで「懐く」ことはない彼らである。
大きな個体は腹がすけば人間一人を丸のみにしてしまうし、実際、大蛇が飼い主に襲い掛かり、全身を大きな体で圧迫し骨を折り、苦しませず窒息死させた死亡事故も多いのが現状である。特定の種族では愛玩の目的で飼育するのを禁じられるほど、ヒトへの共感能力は無い。
彼らができることは、共存のみだ。
「これは食べられるけど今じゃないな」を繰り返して、人という存在に「慣れる」ことしかできないのである。
「それでいいんだって」
――中性の声で、誰に言い聞かせているのだろう。
こうまでして、蛇は何になりたがっているのだろうか。
ロキには、無駄なこととしか映らない。
ろくでもないなどと形容されるロキは、神であるゆえに人の判断基準で倫理を持たないのだ。とうとうつまらなくなってきて、つま先をこすり合わせながら三角に座った。
長い足をたたんで、膝を両腕で抱く。
――“ ”は全知全能でないといけない。
――“ ”は慈悲深く救いを与えないといけない。
「うるさいなぁ」
どうして邪神の『ロキ』にそれを求めるんだろう、と不思議でならない。
ずるずると這いまわる蛇の腹の音が耳障りで、そっと自分の両耳を塞いだ。
耳を塞いでも名残がただ頭の中に残るような気がして、気分が悪かった。はああと深くため息をついて、なるべく蛇を見ないように両手の爪に集中する。
私は――“ ”とはなんだっけ。
「わかんないことばっかり、言わないでよ」
わからないようにしているのだから。
――気付けば、蛇のように己の指を噛もうとしていた。
●
「だからッ――かわいいのがいいって言ったろーが!」
がちん!と鋭い咬み合わせが、男の残像を残した場に食らいつく。
カイム・クローバー(UDCの便利屋・f08018)は己の獣性が何であるかは大体予想がついていた。
「ッッぶねえなぁ!一応、俺から出てきたんだろお前――!」
抗議のカイムの声を遮るほどの唸り声が帰ってきた。その音の主は、オオカミである。
銀色の毛並みはところどころ血がにじんでいて浅黒く変色していた。
図体は大きく、オスらしい体をしている。血走った瞳にはカイムだけが映っていて、激しい息遣いは彼の興奮を表していた。
猟兵の中にも『力』というものを追い求めるものが多い。
まぎれもなく、カイムもその一人であった。戦うことは、彼にとって宿命であり欲求でもある。
飛びかかってきたけものに銃弾を撃ち込む。がうんがうんがうん!と鋭く放たれる鉄の塊は確かに百発百中の冷静さを保って繰り出されるのに――このオオカミもまた、カイムと同じく力を求めている存在だった。
殺して、食らって、さらに強くなるために、その欲望を開放したいと考えているのだ。
オオカミの口から銃声と同じ数だけの鉛玉が転がってくる。にたぁああと紅い口を広げて笑ったけだものを前に、思わず「おもしれえ」と興奮をあらわにした。
「だが、生憎と好きにはさせてやれないぜ」
カイムも強ければ、このオオカミも同じだけ強い。
いいや、むしろカイムよりもこのオオカミのほうが――ある種、「たちが悪い」といえるだろう。
銃弾の節約が必要だ。直ぐに、カイムは剣を掲げた。オオカミも牙をむく。鼻の皮でしわを作って、ぎらぎらとした目のまま飛びかかってくる。
それに、カイムは冷静に剣をふるうのだ。
火花が散り、たかがけもの一匹と人間一人の争いとは思えないほどの苛烈な戦いが続く。
カイムが剣を振れば、けものは飛びのく。冷静な立ち回りだ――けものの牙では、カイムの邪神を宿した質量に勝ち目がない。
体に備わった武装を壊される前に一歩引いて、一撃必殺の瞬間を探っているように思えた。
楽し気な表情に、カイムも納得する。このけものは確かに、カイムの側面なのだ。
解き放ちたくてたまらなくなってくる。
まさに、「けものであったら」の存在と言って差支えが無いだろう。
人間の器用さを兼ね備えたカイムの剣技を、獣性という衝動で乗り越えてくる。
白い地面に鋭く振り下ろした剣を飛び越えられ、刃を足場にして飛びかかるけものの執念には思わず口笛を吹いた。
「やるねぇ」
――だが。
オオカミとカイムに違う点がある。
オオカミは、何も気にしなくていいのだ。己が暴走し、やりたいようにやり、『スベテヲコワシタイ』と願っても――誰にも迷惑が掛からない。それは、いつかのカイムが見た未来の己にまっすぐ突き進むだろう側面だった。
だからこそ、カイムは剣をふるっているのである。
猟兵としての力が欲しい。それは、確かに「強くありたい」という彼の闘争心からも湧き出るものであるのは確かだ。だが、それだけが全てではない。
――守るべき婚約者がいる。
まだまだ幼く、これからうんと美しくなる女の子だ。
生まれて間もなく孤独だった彼女とめぐり合い、カイムは確かに「好き勝手」ではいられなくなった。そんな彼のことを、丸くなったという人もいただろう。
しかし、――きっと、もっとこのオオカミよりもオオカミらしくあったに違いない。
オオカミは、群れで生きる生き物だ。その生涯につがいはたった一人であり、少数の群れを大事にしながら生きていく。時にともに戦い、体を寄せ合い、過酷な現実に立ち向かう彼らは誇り高い。
「化物になるつもりはねェよ」
飛びかかったけものの体を、ぐっと剣で押し込む。拮抗するわずかな空虚に、カイムが――その体を高くはじいた。オオカミは宙に浮き、狙いすました剣先が見上げる。
「怖い顔する俺なんか、嫌われちまうだろ――?」
それじゃあ、困るよな。カイム。
【紫雷の一撃】。
オオカミが消し飛んだあとに、ひらりと舞い降りた羊皮紙には、見慣れた自分の名が書いてあった。
獣性があることを認めよう。ただし、それがカイムの守るべきものを襲うのであれば、容赦なく「叩き潰して」教えてやる。何の証明にもならなくていい――ただ、カイムは「人間」のままで守れるのだと、伝えられればそれでよかった。
●
「――ロキ?」
苗字らしい名前のない羊皮紙を拾ったカイムが、その名を呼んでやる。
待ちくたびれた子供のような顔をした神が、いつのまにやら閉じ込められた白い立方体の底で声のほうを見上げた。角を切りくずされたことで解けた結界が、寂し気な彼の姿を映す。
「大丈夫か、あんた」
「――んー」ぐぐぐ、と両腕を上に伸ばして、ようやく呼吸のしやすさに安堵する。「だいじょうぶかも」と柔く笑うロキの顔には、緊張の名残は無い筈であった。しかし、まだ立ち上がれないのが現状であろう。
ふわわ、と気まぐれにあくびを一つして、ロキは両手でピースを作って見せる。
「大丈夫なら構わねえェが」
――本当にそうだろうかとは思っても本人がそういうのならば、それ以上をカイムも追求しない。
まだまだ閉じ込められた猟兵たちは多く、削られた心と体力に苦しむ者もいた。
あたりをゆるりと見まわして、それぞれの状態を見比べる。
「盛大な時間稼ぎに巻き込まれちまったな」
深く息を吐いたカイムの吐息に、もう獣らしい激しさはなかった。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 神狩・カフカ
神狩・カフカ
◎【相容れない】
誰そ彼とも彼は誰ともつかぬ色に染まった鴉
瑞祥の赤烏が己を見つめている
予想は付いていたサ
おれは元々は鴉の化生だったらしい
それが人の身を得て
裕福な人間夫妻に拾われ愛し育ててもらったよ
己が人間じゃないって気付くまではな
だから家を後にした
それからは山修行や諸国漫遊を経て
いつの間にか山神やら大天狗なんて呼ばれるようになっていたンだったか
ま、色々とあったサ
心配してくれンのかい?
そういや親の死に目にゃ会えずじまいだったか
人の一生なんざ瞬きする間に終わっちまうが
おれの生は終わらない
まだまだ付き合ってもらうぜ
お前はおれだもンな
はぁ…起き抜けに見るのがお前の顔とはな
姫さんの口付けで目覚めたかったぜ
 ジン・エラー
ジン・エラー
【相容れない】
◎
黒の躰に聖なる光。蛇に似た胴の長い竜
オ~~イオイオイ!飲ンでもねェのに竜のオレがいるじゃねェか!!
──ああお前、よくもそンな体で。
切創。裂創。割創。刺創。擦過傷。銃創。etc.etc...
内も外もボッロボロ。それでもオレに向かってくンのかよ。
痛々しい傷が、実ンとこ全部聖なる傷痕ですってか?阿呆らしい
付き合ってやるからさっさと返せよ
オレとお前を、一緒にするな。
"オレは人間だ"
解った上で、この道を選ンでンだよ。
"けもの"の涙なンて要らねェし、勝手に憐れむなよ。
じゃあな。
よォ~~~先生?
タマ(魂)はしっかり取り返したか?クヒャラハハ!!!
●
誰そ彼とも、彼は誰ともつかぬ色だ。
きらめく艶のある体は、まばゆく神狩・カフカ(朱鴉・f22830)の瞳と同じものであった。大きく膨れた瑞祥の赤烏は、その色に恥じぬ小さな太陽のよう。
「予想は、付いてたサ」
何せ、人の子らに混じるときには名探偵と名乗っているものだから。
探偵らしくあるコツといえば、事実を客観的に、そして平等に眺めることだ。
もとより、神であるカフカにとっては何ら苦労することでない。己という存在すら冷静に眺めてみせ、得体のしれない男らしくふるまうことだってできるのだから、「何もかも」に落ち着いた心を向けることだって容易いのだ。
――もともと、鴉の化生であった。
いつのまにやら、小さな太陽の色をした鴉は赤色の少年へと姿を得る。
偶々の縁あって、人の道理がわからぬ神の器を裕福な人間夫妻が招き入れた。
鴉は、不思議であった。人の世界というのは目まぐるしい。
――「ひと」としての側面を鴉は作り上げていく。人の子の姿になったときなど、このカフカらしい情緒は持ちえなかった。
死肉をついばみ、餌を食らい、時に不吉の象徴として親しまれることもあれば、賢者の証としても名高い彼らである。
人在るところに鴉在りならば、その心は人の中に溶け込んで当然であった。
ていねいに愛され、美しい着物を与えられ、学びたい儘に知る日々が続いていて――鴉は、莫大な知恵を得て気づいたのだ。
――人間ではなく、己は神なのだと知った。
神は確かに人の祖である。
人からは知覚できないほど大きな存在であるはずが、起源が小さな鴉から始まったからであろう。カフカという神は鴉の性質を持っていたからこそ、限りなく人に近い神と成り得たのだ。
すべてを理解したときに、ここに居てはならぬと愛された巣を飛び立った。
それは、まるで巣立って行く雛のように懸命な判断だったに違いない。
それからは、神として修練を積まねばならぬと一心不乱に山修行と諸国漫遊に打ち込んだ。懸命なカフカは、神としての素養が高い。
何せ、この世で最も数が多く、弱く、罪深い「人間」に育てられた彼だったのだ。
醜いところも短い雛の時期に見てきた。人同士は愛し合うこともあれば、いたずらにお互いの命を奪い合ってしまうときもある。
しかし、それを認め――それを赦すのが神であった。
哀れな姿を恥じてやってはならないし、叱りつけるのを飲み込んで、ただ「ひと」の選択を認めるのは苦しい修行である。
「ま、色々とあったサ」
ゆっくりと白い地面に胡坐をかいた。
懐かしくも今に至る、苦労した日々を思い出す。
いつしかカフカが――人の身近であり、幸の一角である山の神だとか、大天狗だのと呼ばれるようになるまでは途方もない歳月をかけていた。
「心配してくれンのかい?」
ちょん、ちょん、と鴉が跳ねて近寄る。
太いくちばしでカフカをつつくことはせず、その膝に乗って首をかしげていた。
覗き込むような仕草にどこか気恥ずかしさを感じて、カフカも目を細めて笑う。
「――そういや、親の死に目にゃ会えずじまいだったか」
今のカフカを見て、両親は喜んでくれるだろう。
自分たちが育てていた子供がまさか神の子とは知らずだったに違いない。
突然の別離にきっと酷く驚いて、泣きながらカフカを探したに違いないのだ。
でも、それももう、――うんと遠くの話である。当然といっていい。カフカが神として力を得た時間の、ほんの少しで人は死ぬのだ。
人の一生など、カフカの瞬きの間に過ぎ去ってしまうことは理解している。
だから、――忘れていた。じんわりと遠くに置いてきた愛の日々を、鴉の温度で思い出している。やわらかな毛並みに触れてみると、鴉はすうっと目を細めた。
「まだまだ付き合ってもらうぜ」
愛の温度を、覚えている。
ひとを守らねばと、その心に炎が宿る限り。人を照らせる力が、その背にある限り。
「――お前は、俺だもンな」
ひとに愛されて育った雛は、ひとを愛しているとも。
●
「オ~~イオイオイ!飲ンでもねェのに竜のオレがいるじゃねェか!!」
ジン・エラー(我済和泥・f08098)は、正しく聖者である。
真っ黒な体に下品な笑い声と、おおよそ戒律違反の洒落た衣服を許せぬ神はまっぴらごめんであるが、彼は彼の規律通りに今まで人を救ってきた。
目の前にいるのは――「彼」である。
黒の躰に、聖なる光。きらきらと鱗が輝く美しい胴長の竜がいた。
ごるごると喉を威嚇に鳴らしながら、ジンを見下ろしている。
「――ああお前、よくもそンな体で」
圧倒的な存在を前に、ジンといえば慄くこともなかった。
まして、その巨大な彼に両腕を伸ばしているのである。まるで、抱きしめてやろうといわんばかりの動きには竜のほうが戸惑っているようであった。
興奮のあまり荒くなった鼻息に、ジンが首を左右に振る。「大丈夫だ」と語る声は、普段の彼から想像もつかないほどに優しくて甘い。
「切創」
両腕を拒む竜は、古くから『人間に倒される』生き物だ。
「裂創。割創」
彼を悪の象徴とし、倒せば救いの証としたものがたりは多い。
「刺創。擦過傷」
傷だらけの竜の体は、まぎれもなく「救った」証であった。
「銃創。etc.etc...――痛々しい傷が、実ンとこ全部聖なる傷痕ですってか?阿呆らしい」
お姫様を攫うのは竜であり、地獄の長は怒れる竜であり、その姿はまがまがしく、魔王といえば竜王があがるのだろう。どの世界でも、竜というのは「殺される」ことで救いとする。
龍は、目を見開いて真っ黒な体をきらきらと輝かせていた。
――オレが全部、救ってやる!!
叫びにも似た、まるで雷のような咆哮がとどろく。ばりばりと空気は揺れ、結界内の全てが震えた。
ジンはその姿を両目に焼き付かせている。――つくづく、本当に、愚かでどうしようもない竜が心の底からいとおしくもあさましく見えている。
鼓膜を割られそうな風圧にも臆すことなく、その様を見ている。
傷だらけの両腕は、背は、翼は、長い体は無数の痛みの痕があった。
「耐え忍ぶこそ美徳だってェ――?」
これだから、神様は嫌だ。
ジンは心の底から「人間」を理解していない神様を好かない。
何故戒律などというふざけた掟があるのかも、全くもって納得できないでいたのだ。神は人に認められないとそこに在れないくせに、人に「こうありなさい」と求めるばかりで何も叶えてやらないではないか。
いたぶるだけの都合がいい御約束事などごめんだ!
前髪をかき混ぜる風の主を見すえた。顔を覆うためのこぶしで、どうにか息をする間を作り――告げる。
「お前はそれで助かったのかよ」
――助かってなどいない。
この竜こそ、ジンが助けるべき「救済対象」であった。
傷だらけの口から溢れる銀食器は凶器だ。
血とも汚泥ともつかぬ唾液とともにがらがらと崩れ落ちる音はジンの笑い声とよく似ている。
笑えば万事がうまくいくはずがないのに、それで心を救った気でいるのだ。
――そのままでは助からないなんてことを見失って、ただただ、笑う。竜の眼からどろどろと血の涙があふれていた。
「――ッち」
さっさと、返せよ。
まぎれもなく確かにこの竜はジンの側面なのであろう。それがわかってしまうから、早く胸の内に締まってやりたくなる。
「おい」
地面を強かに踏み抜きながら、飛ばされないようにジンは一歩一歩と竜に詰め寄る。
「よく聞けよ――“けもの”がよォ」
“オレは人間だ。”
神様にはなれない。魔王にもなってやらない。
「解った上で、この道を選らンでンだよ」
――勝手に憐れむなよ。
涙を流す獣をかき消すほどの、【オレの救い】を見せつける。
すべてを救うのだ。ジンは「ジン」のままで救う。人々が彼をなんと形容しようとも、関係があるか。彼が彼自身で彼を定めるのである。
あさましいことだ。いかにも不遜で、いかにも不敬で、いかにも傲慢で――世が世ならば磔刑になっている。それでも、「馬鹿みてェだろ」と笑えるのだ。
「じゃあな」
愚かでなければ――人間ではないのだから。
●
「よォ~~~先生????? 死んだ???? ねェ~~~死んじゃったァ???? センセ~~~~????」
「―――――、はぁ…………」
「あ????? オイなんだそのクソデカため息はよォ~~~~~????? 起こしてやったんだから感謝しろよなァ~~~???? ン~~???」
「姫さんの口付けで目覚めたかったぜ……おれは……」
「タマ(魂)はしっかり取り返したよォでなにより!!!!!クヒャラハハハハハハハ!!!」
人を愛する神と、神を嫌い、人を愛する人がふたつ。
――彼らは彼らのまま、きっとこれから、ずっと誰かの「未来」を身勝手に助けていくのだろう。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ロニ・グィー
ロニ・グィー
△
やぎさんはがらがらどんと雷のような呻き声をした
怒ってる?嘆いてる?
ああそういえばそんな風に言われたことがあったと
『のけもの』くんたちを見て思い出したから
――優しくしないで
――赦さないで
――放っておいて
――横暴な羊飼い(看守)のきまぐれな優しさにすがるようなことをさせないで
ボクはみんなみんな愛してるけれど
どんな生き方をしてたってつらい目に遭うこともあるさ
どんな生き方をしてたっていい目に遭うことだってある
別にそれでいいじゃない、そう納得したんじゃないの?
思うままにするといいとボクはキミたちに言ったよ
ボクはそうしてる!
だから―――やめてあげないし!愛してるし!何度でも赦すし!さあボクに構わせろー!
 久津川・火牙彦
久津川・火牙彦
×
コイツぁ厄介っすね……
見えてきたのは炎の獣、ああ、そうか××ゥ××……
それは鳥の様であり、獅子の様であり、蜘蛛の様であり
得体の知れない邪悪そのもの――否、そんな概念などそもそも無い
星から来た炎は大地を割り全ての源となった
その炎が私自身、クトゥの本質
故に、自分には何も無いのだ
何故生まれた? 二十数年前に九州の遺跡で何があった?
目の前の炎がニタリと、半月に歪む
炎は、どうして人の形を取ったのだ
寂しい? 苦しい?
そんな事星のシステムが思う訳が無い
じゃあ何すか、アンタは思い出せって言うんすか?
今を紡ぎ真実を暴けとでも
どちらにせよここから出なければならないっすね
最悪、自らの身を削ってでも――間に合うか?
●
やぎさんはがらがらどんと雷のような呻き声をした。
――はたして無事に、三匹の山羊は丸々と太って帰ってこれた?
「んふ」
ロニ・グィー(神のバーバリアン・f19016)の前に現れたのは、大きな山羊である。
あまりに強大すぎて、最初見たときは真っ白な山のように思えた。真っ白な空間に後ろがあることを理解して、全景が見えるまで後ずさってみればなんてことはない。
「怒ってる? 嘆いてる?」
山羊は応えない。
ただただ、じいっとロニを見ていた。それから、また雷のようなうめき声を響かせる。
――優しくしないで。
リフレインする声が、その山羊の喉から響いた気がするのだ。
こてりと愛らしい顔を傾けて、不思議そうにロニが聞いている。
――赦さないで。
「どうして?」
――放っておいて。
「なんで?」
――横暴な羊飼いのきまぐれな優しさにすがるようなことをさせないで。
「意味わかんないよぉ。皆納得して、そうしてたんじゃないの?」
ロニは、神である。
昔の己がかたどってきた権威の象徴などもう忘れてしまったが、神であるがゆえに「無責任」であった。
赦したのならば、律することも求められてしかるべきである。
放っておいたのならば、最後まで放っておくのが常である。
優しくしたのならば、相手が満足するまでやさしくするのが当たり前である――そう、ひとの道理では。
「願うだけ願ってさぁ、ボクの自由がないって変じゃない?」
ねえ、やぎさん。と微笑みかければ、山羊は反響する音が煩わしいのか、ぶるぶると首を振った。
「そうだよね、うるさいよねえ」
困っちゃうなぁ、と小さい体であたりを見回しながら、見えぬ声の主たちが不思議でならなかった。
――のけものになった者たちを見て思い出したことがある。
自分も、そういう風に言われたことがあった。
「どうしても、なにもねぇ」
そうしたかったからに違いない。
犬猫のように欲求に忠実なロニである。
食べたいものは食べ、寝たいときに寝て、ぬくもりが欲しい時はぬくもりの相手を探す。とはいえ、弁えもあって――「嫌がる」他人を相手にはそうしない。
お喋りなロニである。必ずすべてに声をかけるのは、全てを愛して、それぞれを知りたいからだ。
まんべんなく、等しく、選り好みをせずに。
「どんな生き方をしてたってつらい目に遭うこともあるさ!」
だから、――神は寛大であり。
「どんな生き方をしてたっていい目に遭うことだってある」
無慈悲であった。
ロニという神が語るのは、あまりにも「できすぎた」理論であった。
何がおかしいのかまったくわからないのだ。人の道理がこの暴威に通用すると思ったのがそもそもの間違いなのである。
美しい少年の愛らしい表情のまま、残酷なまでのやさしさを吐く彼の「やさしさ」など誰にもわからなくてよいのだ――ヒトでは理解できない「慈悲」であった。
「思うままにするといいとボクはキミたちに言ったよ。ボクはそうしてる!」
ほらね、とパフォーマンスを見せびらかす様な足取りで歩いて、それから山羊に一目散に走り寄った。
「だから――やめてあげないし!愛してるし!何度でも赦すし!さあボクに構わせろー!」
大きな山羊は、然りと肯いてもぐもぐと口を動かしている。
何を食べているのかな、とその首に飛び乗ったロニが、崖を登るように四肢でしがみ付いて右に、左にと体を傾けて鼻っ面にたどり着いた時に正体はわかるだろう。
「わぁ」
――よくよく見れば、平たい臼歯に食われていたのは人間らしい肉塊であった。
●
炎の獣が現れたときに、「厄介だ」と判断出来た。
うねっている。絶えず意思があるように感じられる炎の流れは、様々な形を作っているように見えた――のだが、それは狂気の濃度が高いせいだと、久津川・火牙彦(火産霊の旧支配者・f30781)は判断した。
得体のしれない邪悪そのもの。
概念すら超越した狂気の炎は、ゆらゆらと空気すら燃やしてまるで火牙彦を眺めて愉悦に浸るようであった。
――はるかかなた、地球外の星からやってきた炎は、大地を割って全ての源となったのだ。
その炎こそ、クトゥの本質であり、火牙彦自身を象徴すると言われてはいても――何もない。
今この炎が火牙彦から抜けてしまった時点で、あるのは人の身である。
火の精である偉大なるそれは、無数の光の球をまるで眼球のように炎の中心で動かしていた。
まるで指先一本から呼吸の一つ、髪の毛の先から、つま先の果てまで眺められているような気がして気分が悪い。
――なぜ生まれた? 何があった?
1999年某日。平原遺跡周辺の地下大空洞より首の無い巨人像と共に身元不明の少年と巨大な祭具が発見される。
調査により超古代、邪神と称されるUDC群との争いに用いられた人型兵器である事が判明。以降KAGABIKOのコードで管理される。
更なる調査の結果Cthughaなる邪神の力を利用した精神感応型機動甲冑である事が判明。
――20年の歳月をかけ制御方法を解析し、戦力として運用すべく組織に暫定登録される。
何度も目にした事実の羅列から汲み取られることなどない。火牙彦の中にあるのは、ただがらんどうだ。
それなのに、目の前の炎がにたりにたりと半月に笑うのに心当たりがない。
炎がどうして――この火牙彦の姿を作り出したのか。
「人間の体は非効率のはずっすよ」
生きていくには、あまりにも効率が悪いのである。
人間の体は器用であるが、文明ありきに発揮される能力ばかりだ。――そもそも彼の素である火の精にとっては、その顕現した体のままに暴れまわるほうがずっとやりやすかろうに、わざわざ選んだのがよりによってこの骨も間接も多すぎる躰である。
ちょっとしたことで傷をつけるわりに治るのは個体差があるし、それぞれによって弱りやすい部分も違う。
人間の利点を考えれば――数が多いことだ。
無数の命の中に紛れてやっていくには、確かに良いといえる。なにせあまりにも「大きすぎる」この炎は、その凶暴さゆえ永久的な狂気に陥ったほどだ。
――狂気に耐えかねたか?
――孤独であることを恐れたか? いいや。
「星のシステムが思う訳が無い」
即座に否定した。
火牙彦の脳が考えうる限りのことで、このガワの「核」が思い描くすべてを理解できるはずがないのだ。
それこそ、その身を火にくべでもしない限りは――。
「じゃあ何すか」
煩わしそうに、頭を右手で掻く。
「思い出せって言うんすか?」
――今を紡ぎ、真実を暴けとでも?
炎が、ゆらゆらりと笑っていた形を燃え上がらせる。声は聞こえてこないが、どうやら『大うけ』であることは間違いないらしい。
蜘蛛とも鳥とも、獅子とも言えぬ惑星の自浄作用は、忙しく姿を変えながら火牙彦をからかうように火の粉をちらつかせる。
「さっさと出ろってんでしょ――はあ」
この火の神は、危険な存在だ。
地球に最も早く降り立った旧支配者でありながら、召還するのも容易い筈が信仰の形跡がほとんどないことからも伺える通り、火牙彦から言わせれば「荒い上司」のようなものである。己の中に在りながら、肝心の道は敷いてくれない上に足元を照らす火を少しもわけてくれないのである。
「わかりましたよ」
――フングルイ、ムグルウナフ、クトゥグア、ホマルハウト、ウガア=グアア、ナフル、タグン!イア!クトゥグア!
――フングルイ、ムグルウナフ、クトゥグア、ホマルハウト、ウガア=グアア、ナフル、タグン!イア!クトゥグア!
三回、唱えねばなるまい。気道が焼かれて呼吸が苦しくとも続けねばならないのだ。
この炎の化身を満たすために、この外の世界を知って――彼の真意を知った時、目的が果たされるというのならば。その目的が何であるのかを、知らねばならない。
それが。
「――フングルイ、ムグルウナフ」
久津川・火牙彦が、生まれたすべてであるというのならば!!
●
「久津川・火牙彦さーん」
「ッて――あれ?」
まるで、病院の待合室で寝落ちてしまっていたような温度だった。
喉から出てきた声は先ほどのものとは打って変わって、燃え上がる胸の炎に焼けた心地もない。やけに冷えた空気が、躰に寒さを思い出させていた。
――UDCアース、上村邸。その地下室の書斎で、確か。
「自分は、寝てましたか?」
「そりゃあもうぐっすり!箱? みたいなところにみーんな入ってて、そこですやすや~って! ボクも隣で箱?の中に入って、すやすやって寝てたんだよぉ」
ごめんねえ、と服の袖をこすり合わせて詫びているつもりらしい少年は、ロニである。
「すんごく気持ちよさそうだったんだけど、起こしちゃった!起こしたほうがいいよって皆がいうから」
「――はぁ」
「うわ~ん!寝たかったよね!ごめんね」
「いえ、充分」
ぴょんぴょんと跳ねながら瞳を潤ませるロニに、火牙彦はどう慰めたものかととっさの言葉が出てこない自分のほほを右手で撫でる。
「――夢を見たんで」
まだ、輪郭がひりひりと燃えている心地がした。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ディフ・クライン
ディフ・クライン
△
何を抜かれた
彼の魂か
それだけは、取られるわけにはいかないんだ
反射的に捲ったページ
途端両脇に触れる感触
二羽の白鳥だった
けれどどちらも朧のようだ
触れれば消えるのだろうか
初めて覚える「恐ろしさ」のせいか、触れられない
これは彼とオレか
選べというように二羽の白鳥はオレを見ている
…選べるわけがない
あの人が愛した魂も、「いきなさい」と願われた偽物のオレも。どちらか、など
誰に相談すべきことでも誰に背負わせるべきでもない
答えはオレが一人で出すべきで、故にきっとオレはこの先も一人で果てに行く
「……ディフ・クライン」
それは二羽の白鳥の名前
同じ名で、全く異なる二つの意識の名
とても大切で、酷く重い、選べぬ二つの魂の名
●
何を抜かれたやら、分からない隙間があった。
ディフ・クライン(灰色の雪・f05200)は自分で認知できる範囲でも、空っぽの人形だ。
極寒の地で生まれた彼は、ずうっと籠の鳥としてその場にあった。
眠ってしまえば埋め込まれたコアの熱が失せてしまうから、それを怯えて眠らないように――人形は、甲斐甲斐しいのである。
「返してくれないか」
だから、悟ってしまったのだ。抜かれたのは尤も「欠けてはいけない部品」である。
――『彼』の、魂であった。
ディフは、未だに己というものを見いだせないままでいる。
少しずつ心を学び始めて、本を読むのも慣れていた。
人のそばで生きていく決心をした彼といえば、一生懸命に頁を捲り、ひとつひとつの情動を己のわずかな波形と照らし合わせて「これか」と地道な答えを得る日々である。
無駄で、途方もないことだ。
たとえるのならば、砂漠の砂をひとつひとつ数えるのと等しい。
それでも、ディフはひとつひとつ確実に数えていた。どうせ朽ちない人形の躰であるから、せめて――『彼』の理想に届かなかったこの仕組みを変える歯車を探していたのだ。
反射的に、頁を捲る。
奪われた感覚を頼りに手に取ったのは、アンティーク調の文庫であった。
黒と白の表紙は、どちらが表か裏かわからぬまま――人形はかまうものかとちょうど真ん中に指を滑らせて開いてしまったのである。
とたん、景色が白く染まった。
上も下も真っ白だ。左右も、奥行すら狂わされる感覚があった。
しばらくあたりを警戒していると、ふわふわとした何かが両の視界端に映る。
――白鳥であった。
朧な輪郭をした白鳥は、両脇で、ディフを挟むようにして座っている。
立ち尽くす人形を責めるわけでもなく、優雅なそぶりであった。
「これは」
触れてしまえば、溶けてきえていきそうなくらいの淡い二羽を見て、理解してしまう。
「――彼と、オレか」
ハクチョウは、騎士の証である。
各国でハクチョウがモチーフとなる騎士伝説は多く、日本でも古来の英雄が霊魂の姿にハクチョウを使うほどだ。元から渡り鳥である性質もあって、親しまれやすいのもあろうが――その白さと冬という季節に惹かれた人間も多い。
きりりとした目つきで、ディフを見つめる二羽はまさしくたたずまいが美しい。
まるで剣を携えたようなカリスマとプレッシャーがあった。ディフがしゃらりと装飾を鳴らして、二羽にに緩く首を振る。
「選べるわけがない」
――この二羽は、どちらも騎士であった。
ずい、とハクチョウたちは初めて動く。一歩、ディフに寄った。
緩く、力なくディフは首を横に振る。
ディフの中には、ずっと迷いがあった。それがきっとこのハクチョウとして顕現したのだろう。
――製作者である『あのひと』が愛した魂、『彼』と、『いきなさい』と願われた偽物のディフだ。ディフは、『彼』の模倣品である。
小さな背中が懸命にディフを作っていたのを知っている。マエストロの腕は確かなものだったのだ。人形である彼が今日まで美しくあるのは、全て『あのひと』の努力の結果である。
――ただ、『こころ』だけはどうしても完成させることはできなかった。
それを、ひどく人形は申し訳なく思ってしまうのだ。
人形は人間ありきのものである。人間にめでられるために生まれてきた彼らが、『人間を満たせない』ということ異常の絶望はないだろう。
凍てついた表情は、紛れもなく。
「どちらか、など」
両拳を握った。
ディフのことをディフとして認めてくれる仲間たちがいる。
「お前はお前だろ」なんて言ってくれる頼もしい声だって何度も聞いた。なのに、――「それでいい」と思えないこの感情を、何というのだろうか。
まるでいつまで経っても親元を離れられない、依存的な幼児のようではないかと思わされる。すっかり顔は「彼」らしく美しいのに、まったく心が追い付いていないのだ。
――ないものを増やしているから、仕方ないのだが。
「誰に相談すべきことでも誰に背負わせるべきでもない」
『べき』という語調は、やめたほうがよいと本で見たのに。
「答えはオレが一人で出すべきで、故にきっとオレはこの先も一人で果てに行く」
それは、自分の可能性を自分から削る行為であると知っているのに。
人形は、子供の駄々のような結論を絞り出して――コアを埋めた胸に手を当てて、名を告げるのだ。
「ディフ・クライン」
それは二羽の白鳥の名前。
同じ名で、全く異なる二つの意識。
――とても大切で、酷く重い、選べぬ二つの魂の名であった。
それがずしりと胸に戻った心地がして、摩擦が始まれば酷く苦しいのに。どうして、心の底から「よかった」などと思ってしまったのだろう。
人形は、まだ騎士になれないでいる――。
大成功
🔵🔵🔵
 水衛・巽
水衛・巽
×
猿か猫の頭に狸か虎か鶏の胴 脚は狸か虎 尾は狐か蛇
けものと言うから何かと思えばどこからどうみても立派な鵺とは
獣と言えば獣ではありますが さて
姿形の通り捉えどころがなく
そのくせやんごとなき御方を呪い殺さんとする身の程をわきまえぬ所業
発する声が凶兆とされたことも
まったく、これ以上相応しいケダモノもそうそういない
妖異を祓わねばならぬ陰陽師の本質は鵺でした、など
己の獣性に気付いていなかったわけではない
ただ、それを手懐けることはもちろん
討つことも手遅れだっただけ
だからお前の首を、こうして、ここで絞めてしまえば
この腹の中から出てきたお前を今殺してしまえば
うまくいく はず きっと
 スキアファール・イリャルギ
スキアファール・イリャルギ
◎
……妙な胸騒ぎを感じて来てみれば
"これ"は、なんだ
「けもの」と名付けてもいいのか
形は不安定
鳴き声も歪だ
目と口だらけで顔は何処だ
何本脚かもわからない
なぁ、怪奇/化け物
おまえはとんだ我儘だよな
自身の手で私の心を壊したがる
誰かの手で私の心が壊れるのは赦さない
今迄何度私が壊れる機会があったと思ってる?
誰かの手で死にかけた私を生かして、生かし続けて――そしてまた待つのか
……まぁ
その訳の分からない執着は、「けもの」らしいのか
いいよ
その執着が他の誰かに向かわぬように
"真境名・左右"は死ぬまでおまえと一緒にいてやるよ
但し、死んでも狂い果ててやるものか
――なぁ、"スキアファール・イリャルギ"
それでいいんだろ?
●
その顔は、猿か、猫か。
大きな胴は虎か狸か、はたまた鶏か。
よくよく見れば脚が狸で虎だったか、尾は膨れた蛇なのか狐なのか――正体不明の化生が、かの陰陽師の前にある。
「さて」
――水衛・巽(鬼祓・f01428)の家は、特殊を極めた一族であった。
この現代において、未だ根強く陰陽の血筋を引き、たった一つの好敵手と呼ぶにも呼べぬ家同士の争いがある。
信仰の争いというのは異常に根深いが、UDCアース日本においての最初の戦争は、確かに宗教戦争だったのだ。時に政治に遣われ、国の左右を決め、人の命を多く奪い、代わりに倍以上の繁栄をもたらすものである。
昨今は科学の発展もあって、だいぶ無宗教の人口が増えてしまったのもあろう。皆「陰陽道」からどんどん離れていくゆえに、苛烈な椅子取り合戦が始まっていた。
――少ないのならば団結すればいいのに、それぞれが「血筋」を護る為にどんどん削れていく席を奪い合っている。
「まったく、これ以上相応しいケダモノもそういない」
その渦中に巻き込まれた水衛家に生まれた唯一の長男――巽は、まさに彼の家を生かすための存在と成った。
目の前で体を低くさせ、耳障りな嘲笑のような鳴き声が鼓膜を震わせる。
「妖異を祓わねばならぬ陰陽師の本質は鵺でした、など」
――水衛の家は、正しいことをしたように思えるが、人道としては「最悪」だ。
そもそも、嫡出子と非嫡出子が在る時点でおかしいのである。父のことを恨んでいるわけではない。適した子が必要だったのは、その血が呪われる故の選択だ。
尊敬している。――不器用な父が戦ってきたそれまでを、悪いとは言わない。
だが、今までの積み重なった呪いの形が、この「鵺」である。
社会的に、きわめて客観的な立場から水衛の家を見てみれば、「ていのいい人体実験」でしかあるまい。
遺伝子を掛け合わせてよりよいものを作るなど、ジャガイモの品種改良と似ているではないか――義務教育で誰でも習うだろう。最近では、遺伝子を弄るのは悪しきことであるというモラルまで働く思想まで出てきている。
掛け合わされて混ぜ合わされた「最高」は、「雑種」なのだ。
純血であることは極めれば美しかろう。ゆえに、弱りやすい。だから、水衛の血筋はかねてより「雑種」である。様々な分野で秀でたものたちの血をまぜこぜにすることに、確かな同意があったとしても、それが「未来のため」であるという大義名分を傘にしたところで、――最悪の所業といえよう。
それが「宗教」なのだ。盲目的な道である。目を閉じていなければ、社会から自分を切り離し、その道とは違うのだと割り切っていかねばなるまい。
故に修行の道があり、南無阿弥陀仏を唱えるものも居れば、神を信じ祝詞を捧ぐ姿勢が必要になる。
とはいえ。
この化生が巽の側面である、というのならば――すべては「間違い」だったのだ。
やんごとなき御方すら呪い殺そうとする化生は、いかにも姿かたちが「わからない」。
破かれた喉笛から漏れる息のように、か細い声が不気味だ。寂し気な啼き声であるところが、ますます巽のこころを炙る。
何故、巽が凶将全てと相性が良かったのだろうか。
吉将に比べてあからさまに、彼らは全て人間に害を為すものをつかさどる。扱うには相応の技術と、「才能」が必要であろう。
「おぞましい」
――それこそ、獣性ではないか。
まぜこぜの呪い、その血筋の結果の最高傑作が「鵺」でなければ、「すべてに協力を持ちかける」ことが出来なかったという結末なのだ。
気づいていなかったわけではない。目の前の雷獣がけらけらと笑い、おもしろおかしく顔を切り替えては、巽を翻弄するようにぐるぐると周りを歩き回るこころの動きがわかってしまう。
――手懐けることはもちろん、すべて、手遅れだっただけだ。
求められた才覚を手に入れた。
ほしかった結末を手にした。
その手で、ちゃんと屠った存在があった。
仇は打った。力を手にした。扱いを心得て、家族の輪を取り戻した――のに。
気づけば、鵺の首を絞めている。
「うまくいく」
自分の首を絞めている心地がした。
「はず」
ここで「鵺」を殺せば、きっと巽はさらなる高みに至れるはずであると、信じている。すがるように、まるでじりじりと焼ききれそうな自分の何かを守るように、獣の首を絞めていた。
――蓋をしないといけない。
感じてはいけない。この獣を、己と認めてはいけない。心を動かしてはならない。
求めてはならない。救いを探してはならない。もう、巽は――陰陽師なのだから。
「きっと」
道の、侭に。
●
――妙な胸騒ぎを感じて、来てみただけだった。
「なんだ」
スキアファール・イリャルギ(抹月批風・f23882)の腕に飛び込んだのは、真っ黒なノートであった。UDCアースで見かける文庫のわりにはつくりが古い。ぼろぼろの表紙を捲れば、真っ白な空間が広がった。
そこに、のそりとした大きな影がある。
スキアファールが目を細めてやっても、いまいち姿は判然としないのだ。ゆらゆらと輪郭がぶれていて、自分の形がわからないらしい黒である。
まるで鳥のように仲間を求めている鳴き声ですら、いびつで聞き取れたものではない。手あたり次第真似できるものを真似るようであった。
脚などは時折増えたり減ったりしているし、明らかに四本ではなかったのに瞬きをするうちに一本足になっていたりする。
「忙しないやつめ」
――たしかに、「野獣(のけもの)」であろう。
スキアファールには狂人の自覚がある。
こんなものが「彼」だというのならば、確かにそうだろうなと受け止める彼の倫理は壊れていた。
「なあ、――」
影に寄る。けたたましい鴉と鶏の混じった鳴き声で啼いたそれに、一度脚を止めた。
少し呼吸を置いて、やはり近寄る。
「お前はとんだ我儘だよな」
今が、そうだ。
在りたい形に必死になる。仲間が欲しくて啼くわりに、自身の手でスキアファールを壊したがり、彼の身の回りに大きな爪痕を残していく。
まるで独占欲の象徴だ。
愛しているよと囁いて愛しい人を殴るいびつな男の姿のようで、哀れでいとおしい。
そのくせサディストではないから、スキアファールが誰かに傷つけられるのは赦さないし、とびきり彼の傷を舐めてやるのもこの「影」だ。
ちぐはぐな有様はまさにダブルバインドといっていいだろう。飴と鞭という塩梅ではない。
気まぐれと、――わがままという最悪の味付けなのだ。
窒息しかかったところで黒い呪いをほどいて、外の空気を味あわせてやるのを繰り返すことで恐怖と快感にしばりつける。
何度も何度も同じ痛みを与えることで、「そうある」ことが幸せなのだと刷り込んで、教えて、心をむしばむのだ。
それで、スキアファールが何度壊れたであろう。何度も心をくじかれて、なんども演技をやめて、なんども新しい姿を探して、無い未来と罪の数だけ放浪した。
おぞましい呪いを抱えて人間と怪物の間で揺らめきながら、居場所をのない彼に「ボクが友達だよ」と寄り添ってやったつもりなのだろうが、もうそうはいかない。
影と人間は、対等な存在である。
「――まぁ」
その訳の分からない執着は、おおよそ「けもの」らしい。
見つけた獲物を永遠に追い回す執念は蛇のようなのに、もてあそぶさまは猫のようなのに、寂しがって啼くのは鳥のようだし、寄り添う姿は犬のようである。
どろどろでぐちゃぐちゃの中身が見えない真っ黒な獣は、よくよく見てみればスキアファールと同じ背丈をした「思ったよりも小さな」黒いけだまだ。――それをわかられたくなかったから、今まで好き勝手にスキアファールを弄んだのかもしれないが。
ただ、どんな「けもの」もそうだが――それは、獲物が逃げまわしたのも原因である。
「いいよ」
だから、「えもの」は赦したのだ。
もう逃げないよ、と振り返る。伸びる影を、そのままにはしておかぬと青年は認めた。
「その執着が他の誰かに向かわぬように。"真境名・左右"は死ぬまでおまえと一緒にいてやるよ」
どこが顔ともわからぬ影に向かって、まっすぐな黒い瞳を向けてやった。
人間だ。
いつまでも、――スキアファールの行動理念は人間であろう。怪物の特性をもっていながらでも、何度でもそれを主張しよう。怪異であることを恥じぬように、これらかも戦っていくのだ。
両腕を広げて、怪物と向き合う。
「但し」
孤独にうまくなじめず、形がとれなかった。ようやく主のもとに飛び込もうと身を撓めた不安定な怪物に、一喝の条件を突きつける。
「死んでも狂い果ててやるものか」
――今度は、こちらが『飼いならす』番だ。
対等な生き方というのを、この怪異に教えてやろう。
誰にもわかってもらえない、未来を望めない、あまたの犠牲を作ってしまった罪の行く末を最後まで――大切な人たちが願ってくれた分だけ、脅迫めいて締め付けあって生きていこうではないかと、「影(とも)」に微笑む。
「それでいいんだろ?」
――なぁ、"スキアファール・イリャルギ"。
●
「水衛・巽さん」
――耳に届いた名が、自分のものだと気づくまで少し時間がかかった。
巽がようやく名を受け入れたときには、彼の体はすっかり正座のかたちであったらしい。畳み慣れた脚とは言え、長時間そうしていたからか――感覚は遠く、しびれがわかった。
「はい」
応ずる声は、冷静である。
【叉拏】で結界を打ち破ってから、落ちていた羊皮紙を手にしたスキアファールが読み上げた名の持ち主はゆるりと笑みを作ってみせる。
――大丈夫か、とは言わない。スキアファールにも覚えがある「演技」であった。
「まだ全員の救出に時間もかかります。他の猟兵たちも、精神汚染の可能性があるので少し休まれてください」
「いえ、私は」
「休んでいてください」立ち上がろうとした巽の脚に力が入っていない。脚をくじく前に、スキアファールが制した。
「あなたは、人間ですから」
――どこか安心した心地すらある。
自分の顔が人間のものであることを影の男から発せられる言葉で確認出来て、巽はようやく「ひとらしい」呼吸ができた気がした。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 サリア・カーティス
サリア・カーティス
△
……!(ピン、と立つ耳と尾。顔に現れるのは焦燥
せっかく、思い出せたのに……!
私の獣は血まみれの犬……まあ、そうでしょうね。しかもほぼ返り血。
……「家族」が死んだ事に気づいた、あの時の姿ね。
ええ、そして「あの時」と同じようにさ迷うのね。「家族」を探して。
でも、その先は駄目。
忘れるのだけは、もう駄目なの。
ただでさえ私のせいで死んだようなものな「家族」を、忘れるなんて
犬を捕まえて腕でがっちり拘束するわあ。大丈夫、あなたは引き裂いたりしないから。
……「家族」を殺したあれらとは違うものぉ。
もうどこにも行かなければ、それでいいのよ。
●
奪われたものは、かけがえのない「自己」であった。
「せっかく――思い出せたのに……!」
サリア・カーティス(過去を纏い狂う・f02638)の記憶は、ほとんど地獄で補われている。
嫋やかに微笑みを作って見せる彼女は、もとはといえば復讐で動く存在であった。
人狼病に感染したこの美しき黒の女から生まれた形は、イヌである。
オオカミではなくて、――イヌなのだ。DNAの単位でヒトとともに寄り添い、生きることを選んだ家畜の姿をとった。尾の先をゆらゆらとさせて、悲痛の叫びを聞いている。
サリアがその姿に気づいて、「ああ」と目を細めていた。
イヌのからだは、血まみれである。
黒い毛皮であるから目立たないだけで、美しい毛並みがところどころブロックを作り、固まっているのがわかってしまった。鉄を含んだ油分に固められていて、可哀想でならない。イヌは汗をかかないから、洗ってやって、よく梳かしてやらないと汚れも落ちにくいし皮膚病になってしまう。
――痛ましさは、その事実だけでなく、感傷も含まれていた。
サリアは自分から奪われたものが何かおおよそ見当がつき、「これしかないだろう」という判断があった。最近取り戻したばかりの、「家族」のことである。
「だめよ」
イヌに、こちらにいらっしゃいと声をかけた。
サリアが何を言っているのかはわかっているらしいのに、いまいち反応は鈍い。どうしようか考えあぐねているらしい四つ足は、ぶるぶると体を回した。
「ほら。やっぱり、痒いでしょお。梳かしてあげるから」
少し体を近寄らせると、イヌは遊んでもらえると思ったのか――た、た、た、と近寄った分だけ下がっていった。
追いかけっこしよう!と言いたげな顔が明るくて、思わずため息が漏れる。
「おいで」
違うわ。と首を振る。
サリアの声の温度がわかったのか、尻尾が垂れてしまった。
犬が寂しそうにひすひすと鼻を鳴らし、項垂れている。途方に暮れた、という表現が正しいかもしれない。
――家族が死んだことに気づいた時のサリアと、よく似ている。
さまよっていたのだ。家族を喪ったサリアには、もう家がなかった。
家族よりも家族らしくしていた家族を、よりによって家族の手で失ってしまったサリアの今まではおおよそ狂人らしい。どこの世界に、――元々は人間の身でありながら、イヌこそ真の家族だと言える女がいるだろうか。
イヌは、家畜である。
イヌは確かに人間を家族と思うだろうが、人間はあくまでイヌをイヌとして仲間に入れる。ただ、イヌが遺伝子の単位で人が好きな生き物であるがゆえに「主従」という関係で成り立つので合って、そこに「対等」な「家族」はない。
きわめて異常な依存ぶりであり、壊れた価値観だ。
――それでも、サリアはそれが正しいと思っているのである。
サリアにとって恐ろしいのはイヌよりも人間であった。
人間はお互いをだましあうし、時に優秀すぎる頭が壊れることだってあるし、今回の事件だってそうだ。――結局、イヌは何も悪くなかったではないか。
「こっちにおいで」
忘れてはならない。
おいで、おいで、と声をかけて、固まった犬を抱きしめる。
「無垢なあなた」
寂しいでしょう、寒くてしょうがないのでしょう。
抱きしめてやると、犬の喘鳴めいた音が止む。かわりに、口を舐めているらしい水音がした。
「――忘れるのだけは、もう駄目なの」
ようやく、「家族のために」生きる事が出来ている。
戸惑いはあった。いつの間にか喪った家族は、自分がのんきに鎖などに繋がれていたから助けることができなかったのだ。
罪の意識で、サリアは世界を渡っている。
大事な――「かぞく」を連れて、無数の黒い犬に愛される日々を過ごせているではないか。
「大丈夫、引き裂いたりしないから」
見落としはないか?
「――『家族』を殺したあれらとは違うものぉ」
それは、逃避ではないか?
本当にサリアをむしばむ病は人狼病だけであろうか。いいや、きっともっと奥の奥に、彼女を蝕む何かがあるのだ。
だって、サリアは――オオカミでもなければ、イヌでもない。
「もうどこにも行かなければ、それでいいのよ」
ねぇ、サリア。
まるで、いとおしい我が子に語りかける母親の温度で名前を紡いでいた。
大成功
🔵🔵🔵
 桜雨・カイ
桜雨・カイ
△
けもの…どこ?
気配は感じるのに、水や煙のように姿が言えない。
見えない…大きさは…攻撃は…望みは…?
分からない、怖い
近づいてくる、境界が分からない…飲み込まれる!?
災いを避けるようにともらった【藤色の房飾り】に触れる
落ち着いて「私」を思いだす
主の力になりたいと思った
人を愛しいと思った
向けられる優しさを嬉しいと思った
私を構成する”思い”。
…あなたは「いつか未来で出会う、今の私が知らない感情」なんですね。
※激情や愛情などの感情
出会った人達の思いがまだ理解しきれないように
自分の中で生まれていく思いもまだ理解しきてれていない
でも、確かにあるんです
得体のしれないものではない。いつか理解できるもの…きっと
●
――気配はするのに。
桜雨・カイ(人形を操る人形・f05712)のけものは、すでに顕現していた。
人形である己から何を切り取るというのだろうか、と身構えていた間にもカイに隙は無かったはずだ。きり、と繰糸を張る己の指の感覚はいつでも鮮明で、おおよそ何かを奪われたとしても直ぐに反応できたであろう。
――どこ?
息を殺しても、姿が見えない。
恐怖だった。カイはヤドリガミである。操る人形を破壊されれば、それが本体であるゆえにカイもろとも消えてしまう。望まれたかたちが喪失しかねぬ「見えぬ」敵というのは、あまりにも脅威でしかない。逃げ方もわからず、戦いかたもわからぬ――だというのに、「漠然とそこにある」のは確かだった。
「わッ!」
呑まれる。
いや、――これは、吸われているのだ。
確かに吸引のものだった。カイの足先からするっとどこかに送り込まれているらしい。真っ白な景色でわからなかったが――この獣もどうやら「白かった」のだ。けものの腹の中は真っ黒で、何も見えない。すりつぶされることのないまま丸のみにされたカイは、ひとまず暴威に壊されなかったことに安堵した。
どく、どく、と内臓が脈打つ音がする。
「お腹の、なか」
人形にはない部品だ。
絡繰り人形の体は軽い。なにせ、糸で操らねばならぬからである。
故に、おおよそカイには――その本体には縁遠い感覚であった。送り込まれた場所は、「けもの」に呑まれたとしたら確実に、胃であろう。
だというのに、まるでコンサートホールのようだった。様々な鼓動がする。
臓器に血液が流れ込まれている音、動いている音、獣が身をよじったらしい筋肉の音まで幅広くさながら生命のオーケストラである。
「――私には、ないものだ」
そうだろうか。
【藤色の房飾り】に触れながら、カイはゆっくりと意識を集中する。
落ち着く鼓動は規則正しい。どくり、どくり、と一定の間隔をあけたそれは、足取りのようでもあった。
カイは、主人の力になりたいと思った甲斐甲斐しい人形である。
もとより「人在りき」な性質もある。操り手が無ければ動けない存在だった――今は、その糸の先を探しながら、誇らしく思う。
人形は、香炉に出会った。
それから、他人を愛しいと思った。向けられる優しさを嬉しいと思った。
人に願われた形を保ちながら、人のために在ろうとより懸命に働くようになった。
自分の歴史を覚えている――自分という作品が変わっていくのを、認められる。
「わ」
その時に、まるで記憶の海のような水が空間に流れ込んできた。
カイの躰は流れのままに押し出されていく。溺れないように、まず躰から力を抜いて流れに逆らわないでいた。
――どこにいくのだろう。
ふと、漠然と思っていた時に――躰は水圧に押し上げられる。
「あなたは」
飛び出した人形だった。
初めて、その「けもの」を上から見ることができる。
「いつか未来で出会う、今の私が知らない感情――」
巨大な白鯨であった。
カイを飲み込んだらしい彼は、ちっともカイのことは見ていない。潮吹きと同時に吐き出した彼のことなど、感じられないのだ。
大きないきものだ。――まるで、今まで会得できなかった感情のすべてを表しているよう。
理解するのにとても時間がかかるだろう。繰られるまま過ごしてきたぶんだけ、カイは感情が周囲よりも出遅れてしまっている。それでも、目の当たりにしたこの白鯨が、――「可能性というのならば」。
「きっと、いつか理解してみせます」
まさか、こんなものが隠れているとは。
大きすぎて見えないものを、ようやく遠くから見ることができた。彼に必要だったのは、ある種「客観的な」ことだったのかもしれない。
――白鯨の鼓動が、まだ耳に残っていた。
大成功
🔵🔵🔵
 誘名・櫻宵
誘名・櫻宵
🌸神櫻
◎
私は獣
違うわ
私は龍よ
そうよ
私は八岐大蛇
食べたい
甘い愛を
愛しい人魚を愛する神を
唯の甘いだけの甘味料ではなく真なる愛をくれるというふたりの人生を
ひずめて
根絡め捕らえ
咲かせて
滅茶苦茶に喰らいたい
離れぬように
何と穢れた巫女でしょう
嘯く大蛇に笑み深めて食いつく悼みごと抱きとめる
前なら目を背けていた
受け入れてるの
私の慾を
これが私
私の大切な師(神)を堕とした愛なる呪
這いずり慾を煽る、お前
私が祓い斬るその日まで
寄り添い生きる
お前に私は喰わせてやらない
愛喰う貪婪(ひと
愛咲かす護龍
私は、誘七櫻宵
カムイ
私の甘い災い
おいで
私の神様
私はあなたの凡て受け入れる
あなたの厄は私の厄に足りえない
だってこんなに美味いの
 朱赫七・カムイ
朱赫七・カムイ
⛩神櫻
×
真紅の三つ目
前の私…神斬
至らないと責めに来たの
己の神威すら儘ならぬ
君に頼りきり
斬るべきナニカを思い出せない私を
信仰も社も名前も
全てサヨがくれた
私自身の力ではない
神斬との縁と愛故
私達は裏表
一つの魂
重なる二つの神格
転じれど同じ
八首の蛇が唆す
踏み越えろと
連れ去り隠してしまいたい
慾を
蛇を斬った神斬が嘆く
大蛇を前にしてもまだ
斬るべき敵を思い出せないのかと
あの子を守れないと嘆く
私は私で前世とは違うと人は云ってくれる
けど私は君の事も
のけものにしたくないのに
思い出したら凡て変わってしまう気がして
櫻宵
私はきっときみの厄災だ
私の加護は君の籠に…
巫女に愛を強請るよう身を寄せる
情けない神だ
櫻宵
私を呼んで
招いて
●
獣だと、以前はやや自分を卑下していた。
見境なく血に狂い、愛を憂い、求め、大事にしたいと願うのに食べてしまう理性のないものなのだと嘆いたことがある。
「違うわ」
今ならば、その醜い姿すら誇らしく語れるだろう。
血の匂いは馨しい。否定しても仕方がないことだ。――そう思ってしまうのも無理はない。
「私は龍よ」
誘名・櫻宵(爛漫咲櫻・f02768)は、八岐大蛇である。
甘い愛を求め、貪り食う八つ頭の大蛇は彼の目の前に現れた。
桜の華の角からひらひらと散らせるのに、たちまち花弁は落ちる間に腐って消えていく。呪いが蝕むように、桃色を黒く染めては灰に変えるのだ。
「おなかが空いているのね」
しゅる、しゅる、と――大きな蛇は白い空間を埋め尽くすほどの質量で、地を這う。
大きな躰はこの無限に見える結界の中ですら狭いらしい。ぞるぞると長い体をくねらせながら、ねだるように櫻宵の足元に首があてがわれた。そのまま、大きな頭で櫻宵を見下ろす。
――食べたい。甘い愛を。
――愛しい人魚を、愛する神を。
――唯の甘いだけの甘味料ではなく真なる愛をくれるというふたりの人生を。
「ふふ」
くすぐったそうに笑って、櫻宵はそのあぎとを抱きとめて撫でてやる。
よくよく、気持ちがわかってしまうのだ。この龍の本性こそ悪辣である。
他人(あいて)の機微などどうでもいいのだ。相手の気持ちの左右などに今更揺るぐような性根でもあるまい。きわめて「いいひと」であろうとしたのが間違いで、「こうあるべき」なのだと、大きな龍の顔を撫でてやる。
――ひずめて、根絡め捕らえ、咲かせて、滅茶苦茶に喰らいたい。
首たちが、餌を求めてうごめいている。櫻宵の足元をさらい、掲げるように頭の上に乗せた。他の首がまた彼に抱きしめられたがって、鼻先を持ってくる。
よく利く鼻だ――愛の名残りを探している。
愛の持ち主はどこに行ったのだと、鋭い灰色の瞳が見つめてきた。
「何と穢れた巫女でしょう、私たち」
前なら目を背けていた。今は、もう慾を認めている。
偉大なる龍の首は、ひとつふたつの愛で満たせるほど小さくない。
愛をむさぼり、骨まで喰らい、長い時間をかけて躰に溶かしてしみ込ませたいに違いない。ああ、いつまでたっても渇いているのだから、求めることの何が悪いのか。
渦巻けばいい。様々な思考で練られた愛ほど美味いものもあるまい。それを楽しむことが外道だというのならば、然りと頷いて見せよう。
――これが私だと、誇ることさえできるのだ。
悪辣ゆえに尊敬する主を堕とした愛なる呪の姿である。
「私が祓い斬るその日まで、寄り添いましょう」
――散る桜が腐るように。
生き汚いと言われても儚くは死ねまい。
神すら堕落させる己の因果が、いとおしくてたまらない。一本一本の首を撫でてやりながら、ひとつひとつに何度もささやいてやった。愛の吐息くらいは、茶菓子程度にくれてやる。
「わかるでしょう。お前に私は喰わせてやらない」
――食らうのならば、私でしょう。
愛喰う貪婪(ひと)、愛咲かす護龍。
徹頭徹尾愛のみで作られた呪いの化生は、真っ赤な口を薄く開いて笑うのだ。
「私は、誘七櫻宵」
――あまりにも、けがらわしくもうつくしい呪いの名で。
●
真紅の三つ目が、こちらを見ていた。
「神斬」
――それは、朱赫七・カムイ(約彩ノ赫・f30062)の「前」の名である。
黒桜が散って、ようやく硃桜が咲いたのだ。災い転じて福となす、の輪廻どうりに彼は顕現した。
――したはずだった。
「至らないと責めに来たの」
目の前の黒櫻は、やはりカムイと切っても切り離せぬ関係である。
間違いなく神たるカムイが持つ「獣性」であろう。神としての時間も、カムイになってからの信仰も、この黒桜には届かないのだ。
「己の神威すら儘ならぬ、君に頼りきり」
わかりきったことだ。
白い空間に満ちるのは、自分の至らなさを恥じて、――どこかでやはり呪っている自分のことばかりである。
「斬るべきナニカを思い出せない、私を――!」
すべて、総て、凡て、統べて。
どれもこれも、己の巫女が与えたものだ。
カムイは神として幼い。生まれて間もない再約の神は、神に至る修行もないまま上げ膳据え膳に何もかもを用意されたのだ。
それは、櫻宵にはる「神斬」との縁と愛故のもので、カムイのためでありながら、「彼だけのものではない」。
――どれほど、申し訳ないと思ったことだろうか。
至らぬ神であることを自覚する日々であり、己の未熟さと、知らぬことの罪を自覚させられる日々である。カムイの神性は確かに強く輝かしいのに、扱う彼はどこまでも純な性質であった。
この巫女が居らねばまだ何も出来ぬ存在なのである。だから、ともに世界を往こうと歩いてくれるのだ。
「私達は、裏表だ」
――踏み越えろ。
連れ去り隠してしまいたいその慾を顕わにしてみないか、と。
ほんの少し巫女と離れさせられた今だって、とてつもない「囁き」が聞こえてしまう。
いけない、と首を振っても、彼と「神斬」は同一の存在なのだ。
――奪ってしまえばいい、攫ってしまえばいい、思うようにすればいいではないか。
――だって、私は「神」だ。
思わず、カムイが己の額を抑えた。三つ目の瞳が覆われてはじめて、自分がとめどない緊張に駆られているのを感ずる。指先に、感覚が無い。
蛇を斬った神斬が嘆いている。脳に響く声が、まるで根付いたまま離れてくれない。
――大蛇を前にしてもまだ斬るべき敵を思い出せないのか。
――それではいつまでも、あの子を守れない。
――情けない。
「嗚、」
カムイはカムイだ、と云ってくれる人がいる。
――「彼」とは違うと人は何度も言い聞かせてくれる。
しかし、それはこの「神」が求めている言葉ではないのだ。神ゆえに、カムイは悪しきすら愛してしまえている。神ゆえに、「のけもの」を作りたくない。
神の前では邪すら人と等しく、愛する対象だ。――邪から生まれたカムイなど、もっとも邪に近い善であろう。
だから、思い出したら凡て変わってしまう気がしまう。
純白であるということは過酷な道のりである。少しでも黒い汚れがついてしまったら、もう「純白」などとは呼べないのだ。
「櫻宵」
――ああ、情けない。
結局、しっかりとした肉付きの首から出てくるのは、祝詞でもなんでもなく、いとおしい巫女の名であった。
これではいつまでも親もとを離れられない子のようで、いつまでも雛のままだとわかっているのに、己の「試練」に幼い神はまだ戦うすべを持てないのである。
だから、「龍」は呼ばれたままにやってきてしまう。
「カムイ」
【朱華】が、おさない神を囲う結界を切り裂いた。
まるで紙でも斬捨てるかのような軽さで、膨大な呪詛を刃で一振りしてしまう櫻宵である。
「おいで」
子を迎えに来た親のような温度だった。
――私の神様。そう笑って見せる櫻宵に、カムイはいったいどんな表情をしていたのだろうか。「噫」とこぼす吐息は、震えている。
寒さに震える幼い神に、龍は恭しく頭を一度垂れてから、両腕を広げた。
「私はきっときみの厄災だ」
巫女に愛を強請るよう身を寄せてしまう。
――これが「よくない」ことだとは分かっているのに、出来立ての神格がひび割れてしまう気がしてたまらなかった。芳しい櫻の香りに、温かさを取り戻していく。
濡れた神のほほの感覚に、いとおしげにため息をこぼす龍である。
「まさか。あなたの厄は私の厄に足りえない」
ばらばらと散っていく結界の向こうには、呪詛が渦巻く書斎がある。
『のけもの』を作った現実の世界が待っていた。それでも温めるようにして櫻宵が着物ごと両腕でカムイの頭を包む。
すう、とその香りを味わって――艶めかしく双眸が三日月にゆがんだ。
――だってこんなに美味いのだから。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 叢雲・源次
叢雲・源次
【義煉】△
叢雲源次はここ数年で完成された。正確にはその数年のみの記憶で構築されている。復讐に生きてきた。得た物も喪った者もある。結果的に得た物の方が多かったがそれは元より持ち合わせていた物が皆無に等しかった事による相対的な結果だ。そして失ったものは二度と戻らない
今日まで自分が積み上げてきたものが『狼』として目の前にいる。なんと悍ましく猛々しいのか。だが、それを飼い慣らしてきたのが己だ
鋼の意志で獣性を制御してこその『人』だ。けものに理が備わればそれは誇りとなる。それが数年でのみの記憶で完成させた俺の『けもの』だ。それを自覚して覚醒する
「元より自覚していた事だ…今更だろう。そちらこそ、どうなんだ」
 杜鬼・クロウ
杜鬼・クロウ
【義煉】◎
杜鬼クロウは故郷で育ててくれた主と主の娘(初恋の人)による人格形成が基盤
義も人の心も
例外で強敵見ると血が騒ぐ戦闘狂の野獣もいた
手懐ける
其れは真
だが不完全
黄金鏡が映すは出会った人々や敵以外に知らぬ顔も
篠笛の音が響く
幾度見た月の曜(創造主。天上人)、日の曜(真の姿の俺)と対峙
『坊と儂が交わるのは久方ぶりかの』
「器の玄に余の記憶を明け渡すは如何に」
『…』
「解っておる」
鏡が創られし刻
場所は高天原まで遡る
片割れに別の作り手(黒髪の男)がいた
創造主が鏡(俺)を使い妖と戦う日々
記憶の荒波に呑まれるも日の曜が持つ欠片を掴む
名は─
源次と同時に現実へ
(俺が生まれる前の゛俺゛
…どおりで)
ケリつけてきたか?
●
杜鬼・クロウ(風雲児・f04599)は、神器である。
その心を作ったのは、主と主の娘であった。
人々と生きてきた月日は永い。何せ、ヤドリガミである。人の目に触れることなく大切に保管されていた鏡は、数々の人々をありのままに写し乍ら学びを得てきた。
義も、情も、移り変わりも。
等しくすべてをありのままに受け入れ、すべてを見通してきた今だからこそ向き合う気になった。
「――手懐ける」
血を求める戦狂いの野獣(のけもの)、すら。
――篠笛の音が響く。
白い空間に在るのは、クロウの他にも二つあった。
金色の男と、――クロウを作った月の彼である。
金色の顔には見覚えがある。着飾る苦労とは相反して、きらびやかな衣装に身を包みながらも「豪奢」であることを求めない。
神たる己にふさわしい衣服しか纏わぬ、もう一つの己の姿こそ――日の曜である。
会話は必要あるまい。互いに、自分が何者かと理解しているのだ。
――坊と儂が交わるのは久方ぶりかの。
届かぬ声が、響き渡った。
このような呪詛に満ちた場におおよそその声があってよいとは思えぬが、元はといえば「神」を信仰するらしい地でのことである。
ちょうどよかったのかもしれない。輝きを集めた金色の鏡の光は、天に便りを届けられたのかもしれないのだ。
「器の玄に余の記憶を明け渡すは如何に」
何度も聞いた声がした。
――天の彼からの声は聞こえず、ただ、「解っておる」という返事だけが続く。
クロウを置いて話をしているのではなく、彼を例えるのならば「審査」していたのだろう。
鏡は、高天原に在った。
神々が住まう地である。山の頂にあるそこで丁寧に作られた。
片割れの存在には別のつくり手も居り、それぞれが己の役目を得た。
――鏡は、妖と戦う。
未来をむしばむ見えぬ脅威たちを見透かし、鬼と人とがともに戦う世界で、ただただ神々の神具として正しい道を写してきた。
「――ッ」
膨大な歴史の頁は、本にならない。
この結界に至る際、クロウの腕に飛び込んできたものは、巻物だった。落とせばころころと転がった円柱は、ずうっと長い道のりを描く。
神々が人を見守りながら守ってきた歴史を、――そこにクロウがいたことを――それから、彼の役割のすべてを人格を伴った今こそ、流し込んでくるのだ。
俗世を知った。
人を知った。
色を知った。
――求めても求めても、手に入らぬ欲を持った。
「っ、ォ」
飼いならさねばならぬ。
神たるクロウは、己こそを飼いならす必要があったのだ。
怒涛の情報が身に流れたのは、日曜の己が持つ欠片を導かれるままに掴んだときである。
あまりにも異常な量だった。忘れていた神格を取り戻すというのは、とてもつもない苦痛を伴う。それは、――盃に異常の勢いで歴史という水を流す行為である。
「ぎ、ッ」水圧で器には罅が入るだろう。
求める力があるのだ。
クロウは確かに現時点でも強く、頼れる神である。しかし、――もっともっと、誰かが己を求めても、その重さなど羽のようだと笑ってやれるようでありたい。
「ぅおお、お、オ――」
俺にとって、お前は。
枷でも何でもねェよと――言わずとも、相手が分かるくらいの強さが欲しい。
欲だとも。慾ゆえにこれほど「再臨」は痛々しいのだ。それでも割れぬ。鏡は、みしみしときしむ体に鞭うって、耐える。
ありのままの己の力を、輝かせるために!
●
叢雲・源次(DEAD SET・f14403)は、ここ数年で完成された。
結界に閉じ込められた源次は、まず己の状態を確認する。手首に触れ、それから、喉に走る亀裂より回路の異常を計測させた。
――バイタル正常値。
――血圧、通常の範囲です。
――喪失コードを確認しました。記憶の参照を始めます。… … … データが破損しています。リトライまで …10 9 8
復讐に生きてきた。
源次は、復讐に生きて地獄を燃やす男である。
その男の権化が、今目の前にいるオオカミがすべてであろう。猛々しく唸り、しかし物静かに――悍ましいほど理性の在る瞳で源次を見ている。
オオカミは、とても利口な生き物だ。
狼王と呼ばれたかの実在するオオカミに至っては、彼をとらえようとした人間たちの罠をわざわざ嗅ぎ分け馬鹿にするような仕打ちをかけたこともある。
人に懐かず、然し共存を選び、――けだものらしからぬ社会を作って、群れを護る為に牙を振るう。
積み上げてきたものだろう。
源次は、そのオオカミをサイバーアイでスキャンしてみても己と全く同じデータが出てくることすら見越していた。
燃え盛る炎を内に飼っているらしい。よくよく見てみれば、オオカミの瞳孔がぎりぎりとピントを絞っているではないか。
「――得たものも、喪った者もあるな」
語り掛けるように、源次は言うのだ。
鏡に話しかける趣味はないが、不思議なものである。獣の姿をした己の具現には、素直に今までを振り替えるための言葉が出てきた。
「得たものの方が、ここまで多かったか。元より持ち合わせたものも無かったが」
相対的なことだ。
源次という男の今までは、ほとんど「無かった」といっていい。
数年で完成させられた男の今までは、ほんの少しの時間に凝縮されている。それがこうして、今目の前でオオカミとして形を為しているだけでも――「得たもの」ではあろう。「喪った」ものの代償ともいえる。
しゃがみ込む。オオカミは、噛みついてくるそぶりはない。
唸ってはいるものの、それは源次だって同じことだ。刀を抜かないでいるが、やはりいつでも抜けるようには意識している。
互いに、赤い瞳を見ていた。
「――俺は、『ひと』だ」
そして、このオオカミは『けもの』だ。
誇り高き彼らが、まさに源次の象徴といえる。
群れと呼んでよいほどの縁を得た。狩りを共にする相棒がいる。
自分が噛みついてしまいそうになる前に、「まあ待て」と知らぬ社会を教えてくれた。
――狂犬にならなかったのは、今まで得た縁と、捨てたもののおかげに違いあるまい。
「走りぬいたな」
オオカミは、口を閉じる。
「まだ走るぞ」
鋼の意志である。
燃え滾る地獄に封をするのは、己のみだ。オオカミの口から青い炎が漏れて、高らかに吠えさせた。
あふれる炎熱の高温が――まるで源次を歓迎するかのよう。てらてらと青色に輪郭を焼かれながら、ゆっくりと目を閉じた。
これからも、誇りを胸に歩いていく。
理を捨てない。これからも、社会という理の中で生きていく。取り戻した記憶(メモリー)を――ニューロンにあてがった。
名を呼ぶ。これからも走り続ける、男の名を。
――CODE:DEAD SET_
――検出中… … …承認しました。再起動します |
●
「よォ」
目が覚めて、相変わらず目の前には呪詛による空気の汚染からかノイズが激しい。
瞬きを一度挟んで、グラフィックを切り替える。識別感度を上げて――ようやく、「標準的な」視界を取り戻した。隣の男からの声に反応するまでに、ラグは0.1の単位で済む。
「ケリつけてきたかよ」
「元より自覚していた事だ」
「そォか」
「――そちらこそ、どうなんだ」
「俺がスカると思ってンのかァ?」
【贋物の器】は、笑って見せる。
「いいや」
――まばゆいものを見た気がして、鋼の男は目を細めていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 コノハ・ライゼ
コノハ・ライゼ
△
目前に現れたのは髪が銀のままの己によく似たヒト、即ち「あの人」
事ある毎に現れる表情が見えぬソレに、またかと食傷気味に笑おうとした刹那
物凄い速さと力で首を掴まれ
これまでにない満ちた殺意に思わず目を瞠る
当然の報いだ、なんて思考はすぐに掻き消える
間近に覗いた顔は紛れもなく、自分自身で
考える間にもその容は獣毛に覆われ、鼻先は伸び、獰猛な牙からは赤が滴る
飢えた本能のまま獲物を求めるただの獣
ああ、コレがオレの。そして――
耐えつつ両手伸ばし頬に触れ、そこから首へ辿る
我慢、しなくていい。お前はお前だ
飢えているならオレを、満たされるまで喰らえばイイよ『コノハ』
その言葉は、遠いいつかに聞いた様な心地で
●
目の前に現れたのは、――髪が銀のままの、「あの人」だった。
コノハ・ライゼ(空々・f03130)は、ああまたか、と思う。
真っ白な空間に現れた「あの人」は、その輪郭だけ見ていれば今にも溶けて消えてしまいそうなほど儚い。白のよく似合う――藤色の髪が綺麗だった。
たたずまいだけ見れば、ライゼも「あの人」を模した存在であるから同じようなものなのに、どうにも届かない美しさを見せつけられている。
それに、どうせその顔を覗き込もうとしても、都合のいい自分の性根が邪魔をして表情を認識させてくれないのだ。いつものお決まりである。自分の中にある今更な理性が彼を隠して連れ去ってしまうのだから。
とはいえ、見る資格があるとは思っていないけど「オレってかなり一途ネ」なんていつも通りに笑おうとしたら――首を掴まれて、「ひゅ」と喉が鳴る。
油断していたとはいえ、信じられぬ殺気だった。
目にもとまらぬ速さで、首を絞められている。
「ァ、っ」
息が詰まる。声が出ない。
抵抗したくとも。締めあげられた首の痛みが邪魔でどうしたらいいのか思考も回らない。
「ぅェ゛――」気道を塞がれ、喉に痛みが走る。
両手でものすごい力で締め付けられたまま、勢いよく押し倒される。
――ああ違う、「あの人」は。
胸にのしかかる彼の姿は、確かな質量があった。ぎりぎりぎちぎちと喉の筋肉を引き裂かんとする腕はどんどん毛深くなって往く。
一瞬過ぎった、ライゼの中にある「しょうがない」などという感情は過ぎ去ってしまって、ただその変容を見ていた。目を見開いて、「ああ」と思う。
そういえば、おかしいなと思っていた。
「あの人」は「けもの」ではなかったのだ。
美しい姿をしていたのは、何より狐でありながら耳も尾も出さないコノハが証明しているではないか。あの人こそ、「けもの」という言葉からは一番遠い――。
それでは、目の前にいるこの藤色は誰だというのだ?
「あの人」の顔はどんどん醜く変容していく。
月のような毛並みをした鼻が伸び、犬めいた口が開かれた。むき出しの牙は鋭く獰猛で、地獄めいた赤の口内がねばっこい血を溢れさせている。
――ああ、これは。
「オレ、――?」
飢えている。
野獣(のけもの)であった。
獲物を食らうために窒息させる両手が、すっかり「あの人」からは遠くなった毛むくじゃらで。
吐息は血なまぐさく、何もかもがあの人から遠くて、服も破けてしまった。
ぼふぼふと膨らんだ尻尾には礼節がない。興奮のままに大きくなった様は脅威を通り越して滑稽にも見えた。
興奮する血走った瞳には、何を考えているやら真意も読めないうえに、――その躰は興奮で震えている。
そういえば、ライゼの体は「あの人」に化けていたのだっけ。
「アぁ」
わかってしまった。
両手を伸ばす。その血まみれの顔に触れてやる。ゆっくり、首に這わせて抱き寄せるようにしてやった。
「あの人」があの時に見た世界は、こうだったんだと理解したとき、言い難い快感が背筋に走る。見たことのない立場でのことであった。
この痛みも、強烈な殺意も、おそれも、いとおしさも。何もかもすべて、――「あの人」とおそろいに至っている。これ以上の悦びがあるのだろうか?
「イイ、よ」
無いだろう。
「我慢しなくていい、お前はお前だ」
獣の手が、躊躇いに緩んだから。
そうっと腕に力をこめて、その獣を抱きしめてやる。鼻っ面が肩にうずめられてくすぐったい心地がした。
ライゼの両腕を回してもなお、その背は抱きしめきれない。
そうだ、そうだ、この感覚が寂しくてたまらなくも、いとおしくてしょうがなかったのだっけ――。
「飢えているならオレを、満たされるまで喰らえばイイよ」
遠いいつかに、聞いた様な心地がした。
救われた気がするのだ。求めてしょうがないのに、目をそらしたものから解放された心地までしていた。
「『コノハ』――」
血が良く映えた物言わぬ「あの人」の顔が、どうしてあんなにも優しいものだったのかが、分かった気がした。
どうかこれが――妄想(ゆめ)ではありませんように。
大成功
🔵🔵🔵
 夕凪・悠那
夕凪・悠那
◎
この先に続く未来を自由に生きてと
そう願われた
ほんとうに?
彼はその選択を後悔しなかったのか
私ではなく彼が生き残るべきだったんじゃ
そんな疑念から、不安から、目をそらした
観測しなければ確定しない猫箱のように目を瞑っていれば何もなかったのに
箱は今、開けられてしまった
傷ついて、それでも平気を装って、何時しか本当(アタリマエ)になった黒猫
痛くないの?
――痛いよ、当たり前だろ
でもね……笑ってた
怖いとか嫌だとか全部呑み込んだ不器用な笑顔で言われたんだよ
だから
悔やむことだってあるし、辛いときだってあるけど、私も前を向くの
目をそらしていたから気付かなかったけど
そんなこと、ボクはとっくに受け入れてたんだ
●
黒猫がいる。
夕凪・悠那(電脳魔・f08384)は、未来を譲られた。
勝負師としては、もはやそれは勝利と言えない結末である。
己が手を尽くして尽くした限りで得た未来ではなく、他人が自ら勝利の道を諦めたゆえの――不戦勝だった。
「ほんとうに?」
あの時も、今までも。
同じ問いかけを自分に続けている。
白い空間に切り替わることに動揺はなかった。バトルフィールドが変更になることなど、よくあることだし、何ならば「ボスキャラ」が逃げることなどしょっちゅうだ。
演出上のことだろうと――思っていたから。そこにいた黒猫に目を丸くした。
さしずめ、此処は「回想シーン」なのだろう。冷静な悠那は、明らかに離人を伴ってそこまでを見ていたのに、その猫の瞳吸い込まれるかのように――そらしていた実感がわいた。
夕凪・悠那は、キャラクターではない。操作できる存在だが、彼女はアバターではないのだ。
「あ」
ぞ、っとする。久々の現実的な感覚に、思わず息をのんだ。
目をそらしていた事実がある。感じられないからわからないと決めつけていた。
悠那のこの躰ですら、ゲームを操作するためのコントローラーのようなもので、それ以上の価値はないのだとどこか自分で思っていたから、平気だっただけで――忘れていても、よかったのに。
黒猫は、傷だらけの躰で頭を抱えた悠那のことなど何処吹く風な振る舞いをして見せる。
顔を洗い、ていねいに毛づくろいをし、ごろんと転がって、自由気ままだ。
――彼は、本当に後悔しなかったのか。
ずっと、悠那は勝負師でありながら悩まされてきた。
譲られた勝利であろうと勝利は勝利だと割り切る自分と、「そうじゃないよ」と首を振る自分が居て、後者を突き放すことにしたのだ。
それは――逃避と言われればそれまでだが、離人の症状である。ただしくは、脳が生命を守るために行った作用であった。
受け止めきれないショックを前に、「それは悠那というキャラクターが遭ったことだ」と他人ごとにする。そうすることで、今にも砕け散りそうな自意識を守ったに過ぎない。
だから、視なければきっと忘れていられた。
――猫箱のようにずっと扱っていればよかったのに、此処に来てとうとう悠那は、開けてしまったのだ。
猫が自由に転がっているところに、ぼやけた視界で声をかける。
「痛くないの」と問えば「痛いよ、当たり前だろ」なんて――いつかの声が頭に響く。
しかし、猫の顔は穏やかなものだった。
にゃあんと黒い顔に赤い口が笑みを作る。甘えと親しみがこもった音が、悠那の空間に広がった。
「そっ、か」
そういえば、そうだった。
――思い出したくなかった記憶を、丁寧にたどっていく。
不器用な笑顔だった。恐怖も、嫌悪も、苦痛も、絶望も、すべて飲み込んだその顔で、「生きろ」と「がんばれ」を貰った。譲られた「未来」を、――手に入れた。
「悔やむことだってあるし、辛いときだってあるけど」
猫は、ころころと丸まっていた体をうんと伸ばす。
球体に見えていた小さな体は、猫が気ままに体を伸ばせば案外大きい。
無数に体に入った傷痕は、ところどころ黒い毛に隙間を作っていたけれど、それを恥じることのない猫は――ご機嫌に鼻をひくつかせて啼いたのだ。
「それでも、私は前を向くの」
譲られたのだと、どこかで罪悪感があった。
あの『ゲーム』の日々で、『奪い取った』のならばまだ、ここまで苦しい日々はなかったかもしれない。だけれど、譲られたからには何か意味があるのだと悠那なりに勝ち続けてきた。
賽を振られたあの日から、――ずっとずっと、「未来」を探して勝ち続けてきて、今がある。
「そうだよね」
『勝つこと』だけを考えていた。
猟兵になってから、いつの日か『譲られた日々』を、素敵な一生にできたと満足するまで戦い続けることを、これからも繰り返すだろう。
「ボクもとっくに――受け入れてたんだ」
わがままに生きている心地がしたのに。
存外、悠那はやはり、ストイックで確実な勝負師なのだ。
黒猫を抱き上げてみて、傷が無数に走る毛の塊を眺めてから、抱きしめる。
まるで誰かに自分も抱きしめられている心地がして――、どこか、懐かしい温かさを得たような気がした。
目をそらしていた日々を捨てて、これからはさらなる「勝ち筋」に乗らねばなるまい。
――夕凪・悠那のアップデートは、すぐそこまでやってきていた。
大成功
🔵🔵🔵
 ヴィクティム・ウィンターミュート
ヴィクティム・ウィンターミュート
◎×
まぁなんだ…長い永い付き合いだ
俺の中のけもの……或いは、起源──『強奪』
けものでありながら人の形をしたけもの、か
あらゆるものを恨んでいて、どんな抑圧にも抗って、世の中の何もかもを奪いたがっている
昔の俺はお前に全部任せてた節があったな……『人間性』を取り戻してから鳴りを潜めてたが、猟兵になってから意図的に開放してやったんだか
こうして直接対面して、よーく分かるよ
確かに俺はお前だが、"お前は俺ではない"
お前の根源は、"俺に元々あったものではない"
どこから来た?お前はなんだ?どうして俺に?
───返答は『強奪』か
今はそれでいいよ…ここで俺は死ぬが、また会おう
それでは、一時の死の後…目覚めるとしようか
 花剣・耀子
花剣・耀子
◎
着物姿の、やせっぽちの子ども。
真っ赤に染まっている。
怪我なんて無いくせに。
代わりに死んだひとがいるくせに。
このせかいに来る前の、野良猫のような目をした、あたしの影。
判っているのよ。
それでも生きていかなくてはいけない。
立って歩いて、進まなくてはいけない。
代わりになんてなれないから、あたしはあたしにできることを、しなくてはいけない。
師匠がいきていたならもっとたすけられただろうひとたちを、たすけなくては、いけない。
いけない。いけない。いけない。
雁字搦めのやくそくを、――それでもあたしは、重たく思ったことなんてない。
おいで、耀子。
あたしはもう、なくしたものを指折り数えるだけのこどもではないのよ。
●
「まぁなんだ……長い永い付き合いだ」
そう言えたのは、明らかに目の前の「けもの」が「ひと」だったせいだろう。
ヴィクティム・ウィンターミュート(Winter is Reborn・f01172)は、真っ白に囚われた。空間のスキャンはほぼ領域展開と同時に行ったのだが、どうやら「囲う」だけの意図しかないらしいこの茶番は、殆どが時間稼ぎであろう。
とはいえ、ギミックつきでアンロックはすべての猟兵共通のことだ。ならば有効活用したいのがヴィクティムである。幸い、目の前の「けもの」相手には彼しか対峙できない。
「――話をしようぜ」
「何をいまさら話すことがあるんだよ」
「向き合ってこなかったからな」
「ツケが来たんだ」
「わかってるよ」
あらゆるものを怨んでいる瞳が返事をした。
ヴィクティムと背が変わらない。この「けもの」はヴィクティムと共に育ってきているのだ。今までも、そしてこれからも彼の半身になりえるのだろう。
となると、まず――いかに「見てこなかった」としても、今一度自分の姿をよく理解しておくことは必然と言える。自分の力量を知らないことほど戦場でみっともないこともあるまい。
いいや、――これも言い訳だった。
ヴィクティムは、自分を確かに戦場での損益では顧みたことがあれど、今までただただ走り続けてきた男だ。骸の海から蘇った仲間を屠り、ようやく禊を済ませた今だからこそ、心は四人分の重さのほかにも余裕ができた。
思考の余白に、「ヴィクティム」という人物をプロファイリングできる時期がようやくきたのである。
「お前は――名づけるなら『強奪』だ」
「ハ、テメェの名も忘れたか?」
「イジワルめ。識別するためのコードだよ」
どんな抑圧にもあらがってきた。
虐げられて育ったヴィクティムの性根は、確かに強奪の化身である。
彼の育った社会の中では当たり前のことだ。明日を生きるために必要なのは金であり、金が無ければ人から奪うのがよい。パン一切れ盗んで何になるのだ、住む場所だって、服だって、弱い奴から奪っていけばいいことである。どうせやるならことは大きくと生きてきた彼らの過酷さが拍車をかけた日々は――ギャングよりもおぞましいものにさせる。
「昔の俺はお前に全部任せてた節があったな」
「他人事みてェに」
「まァな」
「のらりくらりと、甘ェんだよ」
「――『人間性』ってやつだよ」
ああ、そうだ。
ヴィクティムは話術を磨いた。
どんな物事にも交渉事は必須だ。特に、猟兵の世界に来てからというものの確かに彼の電脳魔術に勝る「何か」を持っている存在はあまりにも多かった。
英雄になり損なった少年は、わざわざ『端役』という名を名乗って舞台装置で在りたがったのである。それはもちろん、罪の意識からというのが一番大きな理由だが、――この『強奪』の本性は、違う。
大きなことが出来る誰かの影に隠れて、その技を見ているのだ。
どこをどうしたら自分がそれを『再現』して『盗める』かを考えている。
体を鍛えずとも自分の体に数式と魔術を巻き付ければ、幾らでも『役を盗める』はずだ。
発想こそこのヴィクティムの最強の武器であり、――可能にする技術が確かにあった。
「こうして直接対面して、よーく分かるよ」
そういう衝動に駆られたこともある。
何もかもを奪って、壊して、身勝手にスッとしたいときがあった。
ヘタクソな男の夜遊びのような、寂しい余韻に浸りながら皮肉めいて笑ってればいいと――思った時があって。
「確かに俺はお前だが、"お前は俺ではない"」
ヴィクティムは、両腕を組んだ。
戦う意志を見せないが、守る意志を『強奪』の男へと向ける。
「お前の根源は、"俺に元々あったものではない"――そうだな?」
意図的に何度か、使ったことがある。
その時の自分と言えば、もはや見ていられなかった。暴れるような戦いぶりには、さすがの『名端役』も「アレは最悪の舞台だったぜ、次があるなら謹んで降りるよ」なんて誰にでも言うだろう。
「――どこから来た」
『強奪』は応えない。
「お前はなんだ? どうして、俺に?」
ヴィクティムのその『素養』があることは確かだ。
だが、ここまで『行儀が成っていない』のは彼とそもそもの『スタイル』が異なる。
優しすぎる尋問ではない問いかけに苛立ったのは――『強奪』らしかった。
「くだらねェな。知りたいなら、探してみろよ」
『彼』の凶悪な口元を最後に、たちまちヴィクティムの視界は、暗転する。
「”世界の果てまで、”――」
●
それを見たときは、猫かと思った。
大きな猫は大体その大きさくらいあると、花剣・耀子(Tempest・f12822)もテレビで見たことがある。ラグドールだったか、何だったか。巨大猫はいったいどれくらいふわふわな毛並みをしているのだろうと想いながら、仮想の大きさに腕を動かしたりなんかもした。
――目の前に現れたのは、猫ではなかったが。
「あたし」
着物姿の、やせっぽち。
怪我などないくせに真っ赤に染まった、――犠牲を伴って生き残った、野良猫のような少女だ。
幼いころの耀子は、その体に背負うにあまりに過酷な運命を数えてきた。
成長した今の耀子が語り掛けてやっても、少女は幼い指を折るのをやめない。十指を何度も繰り返して折る仕草は、まさに呪われていた。
「死んだ人を数えているのね」
頷きは返らない。
でも、耀子は知っていた。
――もっと強くならなきゃいけないの。
「そうね」
幼い瞳だけが見える、真黒な影のよう。
小さな指で、死なせてしまった数を数えながら影が言うのを、耀子が肯定した。
幼いころから、足らずの己を恥じた。幼いころから、勉学はからきしのくせに刀の使い方とわきまえだけはよくわかっている。それを、――あたしは狡いなと思う自意識も、変に育ってしまっていた。
判っている。
繰り返し指を折って数えていく辛さは、よくよく身に染みている。
それでも生きていかなくてはいけない。
立って歩いて、進まなくてはいけない。
代わりになんてなれないから、あたしはあたしにできることを、しなくてはいけない。
――師匠がいきていたならもっとたすけられただろうひとたちを、たすけなくては、いけない。
「ええ」
どれもこれも、もうわかっている。
やらないといけないの、と涙ぐむ幼い自分と視線を合わせるために、白い空間にしゃがんだ。
長い髪の毛が床に垂れてしまうのも構わずに、両腕を広げる。
「おいで、耀子」
――誰かに、そうしてもらいたかった自分を、自分で抱きしめる。
親代わりの師を失ってからというものの、終ぞ誰かに甘えることができないから、耀子は大人になるしかなかった。
涙を飲み込み、もう嫌だと逃げ出したい気持ちを殺し、自分の痛みすら忘れるようにして、前へ前へと血まみれの体を引きずっていく。UDC組織に救出されるまで、只ひたすら、ひたむきに戦場を超えてきた。
自分の傷を、「ごめんなさい」の気持ちを体現したかのように傷を増やして、血達磨になって帰ってくることもあるのは、今もそう変わらない。
幼いころから、今までに至るまで、何千の屍を超えた。
重なり合う夫婦の死体を見た。
子を抱いたまま死ぬ母親たちの、腐っていく様を見た。
地獄を知った。何度も、何度も見てきて――また、地獄を得た。すべて耀子が「至らない」故の、痛みばかりを責めていた。抱きしめて見れば、その苦行を超えた子供の体は、思っていたよりももっと小さかったのである。
『傷』を自分で温めていた。幼心で処理しきれるはずがない痛みの数々を数えてばかりの子供を抱いた。
雁字搦めの約束と因果に、どうすればいいのかわからず、ただやみくもに刀を振っていた孤独を慰める。
「もう、――あたしは」
『どうしたらいい』がわからない子ではなくなった。
解っている。
繰り返し指を折って自分の改善を考えるくせは、よくよく身に染みて、習慣になった。
それでも失敗を重ねて生きていきたいと思う。
立って歩いて、進んでいたいと願う。
代わりになんてなれないから、あたしはあたしにできることを、したいと思う。
――師匠がいきていたならもっとたすけられただろうひとたちを、助けたい。
「あたしはもう、なくしたものを指折り数えるだけのこどもではないのよ」
かえろう、耀子。
誰かに迎えに来てほしかった、誰かに「頑張ったね」と言ってほしかった少女は――剣を握る女傑に為る。
●
「ヴィクティム、――ウィンターミュート」
「おっ、と」
最後の箱がほどける。
ヴィクティムの解放で全員救出となったらしい書斎の中は、目覚めたヴィクティムのサイバーアイが再起動してまもなく――その質が変わったことを伝えていた。
「助かったよ。サンキュー」
「ええ。問題はない?」耀子が短く尋ねた。
「ああ、――ちょっと死んだくらいだ」
比喩、だろうか。耀子が声をかけたのを心臓マッサージに代用してくれたのならば何よりだったかもしれない。
ヴィクティムの両目で観測できる通りに、あたりは猟兵たちそれぞれが苦悶の表情をしていたり、その彼らを介抱してやる流れが取れている。まもなく動き出せるだろう、ということは――時間を与えてしまったということだが。
「待てよ」
場に残留した『呪詛』の濃度がこれだけ高い、ということは。
「――思ったより吸えてねえな、これは」
猟兵たちも「数」に入っていたということである。
彼らを再起不能にすれば、その分だけ情念から新たに呪詛を吸い上げることができると考えたのだろう。欲をかきすぎたらしい賭けの行方は、――大損となりそうだ。
「完全復活にゃならねえだろうさ。俺たちの誰もがディナーになってない」
「あら。じゃあ、好都合だわ。『残り物』はさげてしまわないと」
【《黒耀》】。
――起動された『同類』の蛇が、けたたましい音を立てて周りの瘴気に飢える。
「斬り祓う」
満ちていた呪詛が、耀子の剣戟でごっそりと削れる。
それをきっかけに猟兵たちを苦しめていた瘴気は、たちまちそれぞれの方法でかき消されていくだろう。
ようやく「けものくささ」をかき消してから地上に出てみれば世界は漆黒に染まっている。
皆がきっと、山を見た。真っ暗な世界に驚いて、光をそれぞれ探すまでもなく原因に気づくだろう。
大きな影が――月を隠してしまっていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『黒の王』

|
POW : 生成
【対象の複製、または対象の理想の姿】の霊を召喚する。これは【対象の持つ武器と技能】や【対象の持つユーベルコード】で攻撃する能力を持つ。
SPD : 母性
【羽ばたきから生み出された、幸福な幻覚】が命中した対象を爆破し、更に互いを【敵意を鎮める親愛の絆】で繋ぐ。
WIZ : 圧政
【羽ばたきから、心を挫く病と傷の苦痛の幻覚】を放ち、自身からレベルm半径内の全員を高威力で無差別攻撃する。
イラスト:山本 流
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠ヴィル・ロヒカルメ」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
なんともいえない生き物が、意識の中に居た。
思い返せば、ずっと知らないふりをしていたんだと思う。
――虐待を受けていたとして、一時的な保護下にいた私は、管理される中でカウンセリングを何度も受けてきた。
最初は、名前が言えなかった。何が自分の名前なのかわからなくて、この名前は自分の名前ではなかったような気がした。
私じゃなくて、私によく似た誰かのことじゃないかと思い始めて――「つらいことはありませんか」には、「ありません」と答えていた。
優しいはずの独特の白い空間が、狭苦しく感じられたのを覚えている。
白衣の女医が、丁寧に両手を握ってくれたのがとてつもなくうれしかったのに、ただただ涙がこぼれてしょうがなかった。
「お父さんとお母さんを守ろうとしてるのね」と胸中を見透かされたときは、叫んでしまいそうだった。
――心のどこかでは、わかっていたのだ。
うちの家庭はおかしいのだと、一般的な幸せからは遠かったのだと。
だからといって。自分が逃げられるような身分でなかったこともあって、助けを求めるなんてことも他人にできなかった。「周りに頼って」どうしろというのだ、そんなことしたら家族が逮捕されて、明日の家がないかもしれないのに。
放浪することも考えたのに、結局いつも決まった時間に家に戻ってきてしまうのだ。
与えられないとわかっているのに、どこかで両親に期待する自分を捨てきれないままでいる。
――じゃあ、誰が助けてくれるのだ。
助けられなかったから、母は殺された。
助けられなかったから、父は行方不明になった。
助けられなかったから、誰も、――好きな感想を言うばっかりで、責任もとらずに何もしてくれなかったから。
「たすけてほしかった」
人にそうすることで、いつか助けられると思ってた。
目の前にいるずんぐりとした羽根の塊は、震えながらこちらを見ているらしい。
「たすけてほしかったよ」
つぶやく。
問題の先送りだった。
今までの人生の傷を振り返らないで、他人に尽くすことばかり考える私は、結局のところ「家族」の代わりを周りにもとめていたのだ。
傷ついた自分のことなんて、「なかったことにして」。
「ごめん」
――今まで見捨ててごめんね。
手を伸ばして、その大きな体を抱きしめようとする。
『のけもの』が暴れ狂う。視界が真っ黒な翼と鎖でおおわれる中、少しずつ意識も落ちていく。
まるで、――何も知らないのに、やさしくしないでと泣き叫ぶ迷子のようだった。
●
子は結局、親からしか学ぶものがなかったのである。
上村由美子は、己の感情に蓋をした。親を憎んでしょうがない自分と、親を盲目的に愛してしまう自分に蓋をして、ふたつが混ざり合って煮立つのから目を背け続けていた。
ひたむきな良い子であろうとして、その象徴である「警察官」になるあたりで、もはや彼女の喪失された愛情への執念は、「親譲り」に異常であったといえるだろう。
――望み薄い、と猟兵たちは悟っただろうか。
山の「巣」を基盤として、空を覆うほどの黒い羽を広げて見せた「黒の王」は巨大ながら不完全な復活といえるだろう。何せ、吸う予定だった猟兵たちの情念がさほど得れていないのだ。
しかし、生きる触媒となった上村由美子は完全に取り込まれてしまっていた。
――助けられるだろうかと言われれば、限りなく難しい状況である。
君たちの前には、それぞれの能力に合わせた理想が、絶望が、忘れていたかったものへの情念が立ちふさがるのだ。
君たちは、まず君たちを助けねばなるまい。
それから、――考えてみるといい。たった一つの命を救う無茶な賭けに出るか、それとも「しょうがなかった」と捨てて明日をもぎ取るのか。
見捨てて討てば「一〇〇」を救える。たった一つを足したところで「一〇一」になるだけだ。それでも、君たちは。
「のけもの」を救けるだろうか。君たちの業を精いっぱいに背負いながら。
***************************
・それぞれの選択したユーべルコードで「黒の王」のコードの作用が働きます。
一歩先の理想を乗り越える、求めていたものを捨てる、絶望を残酷に踏み越えるなどなど、キャラクター様に合わせて楽しんでください。
・同行者でコードを合わせる必要はありません! お好きに考えていただいてOKです!
・プレイング募集は 12/12(土曜日)8:31~12/15(火曜日)21:00 とさせていただきます。
それでは、皆様の素敵なプレイングをこころよりお待ちしております!
***************************
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト
◎
立ち塞がる理想など無い
オブリビオンが消え去り、猟兵というシステムが不要になった世界
俺の意味と価値を無くすことが俺の理想
故に俺の理想は何一つとして他を阻み得ない
役割を終えたシステムは駆動しない
上村由美子が戻るか知り得ぬが邪神は討つ
破界で掃討
対象は戦域のオブリビオン及びその全行動
それ以外は地形含め「障害」故に無視され影響皆無
高速詠唱を幾重にも重ね『刻真』『再帰』で無限に加速・循環
瞬刻で天を覆う数の魔弾を生成、全方向へ斉射
更に射出の瞬間を『再帰』で無限循環、間断なく継続
戦域を魔弾の軌跡で埋め尽くす
届く攻撃は『絶理』『刻真』で触れると同時に終わらせ影響を回避
必要魔力は『超克』で“世界の外”から供給
 ウィータ・モーテル
ウィータ・モーテル
◎△
WIZ
諦めたく、ない……救いを求めるのなら、何であっても助けたい……!
それが、私の存在意義だから……!
「気を付けて。生半可な気持ちだと、君が死んじゃうから……」
痛くて、心が挫けそう……死ぬ方が良いと思えるくらいの、苦痛……でも、私は、死ぬ訳にはいかない。絶対、絶対……!
黒のあなたも、ずぅっと、痛かったよね。辛かったよね……優しさが、分からなくなるくらい。
今更って言われても、いいよ。漸く、あなたはその姿になることで、助けてって言えるようになったんだから。
まだ、遅くない。UC発動。
あなた達の心も、ここにいる皆も、助けたい。
今持てる、私の力で。
命の灯火を、皆に。傷も痛みも苦しみも、救ってみせる!
 シキ・ジルモント
シキ・ジルモント
◎
現れたのは人狼では無い自分
尾が無く、耳も人間と同じ
確かに一つの理想の姿だ
その姿に応戦しつつ躊躇い、ようやく決心して真の姿を解放(月光に似た淡い光を纏い、犬歯が牙のように変化し瞳が輝く)
人の力だけで決定打にならないなら、相手が持ち合わせていない獣の感覚と身体能力を引き出し反撃、『理想』の撃破を試みる
『理想』に反するような獣の力に頼ってでも為すべき事が有る
目指すのは上村由美子の救出
先程助けられたように、彼女が自分を保てるよう、黒の王へ踏み込み上村由美子の名を呼ぶ
触媒を失えば不完全な神は滅びる筈だ
討つだけでなく救出を選びたい
完璧な仕事の為、自分の望みの為
…諦めれば、今度は自分の心にすら背く事になる
●
現れたのは、人間であった。
シキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)の前に現れたのは、紛れもなく「にんげん」のシキである。この現象が黒の王が魅せる理想のせいだと頭では理解できているのに、心が追い付いていない。
まず最初に、――ガンナーであるならば一番避けねばならない状態に陥ることになった。
「ッ!!」
銃声。
躊躇なく大口径のマグナムでシキの額を狙う鉛玉を避けたのは、残酷な現実の象徴である彼の耳のおかげである。オオカミの耳は、ヒトのそれよりもずっと音を拾うのに長けている。発された敵意と殺意の塊に心の傷を抉られながらも即座に対応できるのは、病のおかげであった。
シキが目の前のシキに見せてしまったのは、硬直である。
「く、そッ――」
がうん、がうん、がうん!
吠える声よりも猛々しい音が響いた。
煙のかおりがツンと鼻をくすぐって、シキはどんどん己が追いつめられていく感覚から逃げられない。――敵として現れたシキの姿は、あまりにも理想であった。
「逃げるなよ、オオカミ。見苦しいぞ」
厳しい目つき、しかし余裕のある口元である。
逞しい体はいまのシキと変わらないのに、耳も人間のもので、尾もありはしない。
応戦しようと銃を引き抜くまでの僅かな虚で、目の前の「にんげん」たるシキは人狼であるシキを狩るには充分のテクニックを持ち合わせていた。
――人狼病にならずとも、人間として戦場に立ち、戦うシキの姿で。
息が詰まる心地がする。
この病を心底嫌っていた。
戦場で何かへまをして死ぬだとか、何かを守ろうとして死ぬのであればきっとシキだって後悔は無いだろうに――望みもしない獣性をほどこされて、いたずらに消費される己の生をどれほど嘆いたか分からない。
確かに強力な力を得たというのに、目の前の「理想」はそれを「持ったまま」で今のシキと渡り合ってしまうのだ。
【コンセントレイト・ラピッド】。
二連続で吐き出される弾をかわしながら――同コードにて撃ち合う。
確実に仕留められる間合いでの撃ち合いであるはずが、お互いに家屋に身を潜めながらの「狩り」に持ち込まれていた。
住民の避難は終わっており――元より田舎で空き家も多い。窓を割り、中に転がり込む。い草の香りすらしないぼろ家へ身を潜める暇はなく、シキはその場が和室であることを理解してから弾かれるように走った。
「オオカミ」のいた場所を、「狩人」の銃弾が撃ちぬいていく。
「そこだな」
優れた耳も、発達した鼻すらもっていない筈なのに、自然に「狩人」は「オオカミ」を見つけてしまうのだ。
「オオカミ」が潜んだリビングがあっという間に銃弾の餌食となっていく。煤けたフローリングが穴だらけになる音を聞きながら――「オオカミ」は息を殺して押入れの中で「狩人」の姿を見ている。
どこまでも、人間だった。
――シキも、そうであるはずだったのだ。
疎ましい尻尾も要らない。余計な力も必要ない。満月に気後れすることもなく、いつ死ぬかわからない自分の寿命に怯えることもなく、ただ――仕事をこなしたいだけだった。
どうして、人間であることをとりあげられてしまったのかを考えても詮無いことだとはわかっているのにこの病はシキをしばりつけて苦しめるばかりだ。
――ああそうだ。これは。
間違いなく、シキの理想である。
「ゥ、――」「オオカミ」が、唸った。「ウォオオオオオオオッッッ!!!!!!」
押入れの歪んだ隙間からのぞいた「狩人」めがけて飛びかかる。
向けられた大口径を反らすために、まずその腕に組みついたのだ。シキは、銃を持っていない。
【ビリーフカラー】に染まっている。
煌々と月の光を身にまとい、鋭い牙を隠さずに唸っていた。「怪物めッ!!」吐き捨てるような「狩人」の言葉には、「そうだッッ!!」と吠える!
「為すべき事がある――俺は」
願うならば人間の姿でありたかった。
しかし、――獣の力を頼ってでも、為したいことがある。
シキの頬を張り飛ばそうとする肘を、組みついたまま頬で受ける。然し揺らがない!
ぐっと体を踏み込んで――狩人の体を床に強く倒す。呻く彼の声を押しつぶすように、額同士をぶつけあった。ぐらりと脳震盪を起こした狩人の前髪を握り、下顎に彼の銃を押し付ける!
「自分の心に背く事は、御免でな」
――あきらめない。
救けてやりたい、と思った。
自分を保てない女の姿は、不幸なものであった。今のシキと同じだ。
望んでその生になったわけでもなければ、彼女が確かに精神の異常をきたしていたとしても、それは彼女の責任ではないとすら思える。幼いまま、知らず知らずのうちに掛け違えた歯車をどうして気づけるだろうか。
「仕事の、――いいや」
ぎゅ、と一度口を結んでから、「オオカミ」は凶悪な牙を隠さずに告げる。
「これは、『俺』の為だ」
銃声が、響く――。
●
身を焦がす様な熱に襲われた。
「しっかりして、ウィータ」
山のような邪神が生み出した羽ばたき一つで、まるで世界が燃えてしまったような心地がした。
ウィータ・モーテル(死を誘う救い手・f27788)の体中に炙られたような痛みが走る。
体をかき抱いてみても、どこにも炎の気配はないのにただただ熱く、呼吸を繰り返せばどんどん気道が焼かれていく。喉は焦げてしまっていて、鉄っぽい味の広がる口内からも火を噴いているような感覚がした。
目の水分を奪われて視界がぼんやりする。猫の声が、やけに遠くに聞こえた。
「生半可に挑むと、君が死んじゃうから」
――死なないよ。
叫びたい。
いつか故郷を焼いたあの痛みがウィータの全身を襲っていた。燃え盛る感覚に汗が噴き出して、全身の水分が奪われて膝をつく。
叫んでも声が出ないのがわかっているのに、もんどりうってしまう。
美しい衣服に土がついてもどうしようもなかった。跳ねるように躰が痙攣している。
主たるウィータの苦しむ悲鳴は、間違いなく悪魔である黒猫には聞こえているのだ。赤い瞳を細めて、「あーあ」と首を振る。
「だから言ったのに」
悪魔には、わからない。
ウィータが懸命にあの黒い邪神に立ち向かおうとする理由が理解できないでいた。
――契約主たるウィータがそれを願うのならば、叶えるのが悪魔、ユランの役目である。
諦めるわけにはいかない、絶対に助ける、痛かったよね、つらかったよね――。
【命の灯火】を駆使しながら、両手の治癒の光で大きな邪神を照らしていた。それで自分を癒せばいいのに、とユランは思うのに、ウィータは彼のように利己的であれない。
世話の焼ける主を持ってしまった。
ユランは、大きくため息をつく。
――黒のあなたも、ずぅっと、痛かったよね。辛かったよね……優しさが、分からなくなるくらい。
――今更って言われても、いいよ。
それは、間違いなく無責任な善意だ。
ユランから見れば、ウィータの声かけがいかに残酷な意味を持つかがわかった。
ウィータ達は猟兵である。世界と未来を助けることは確かに責務であるが、もはや邪神とほぼ同一化した人間を助けることは「ボーナス」であれど必須ではない。なのに、それを率先してやりたがるのだ。
光に照らされた邪神が――地響きにも似た悲鳴をあげている。
ウィータ達はたとえ、ここで上村由美子を助けてやっても、これからの彼女の未来を保証できない。それどころか、ここで死なせてやったほうが都合もよいだろうとユランは思えていた。
――あなた達の心も、ここにいる皆も、助けたい。
それはウィータの自己満足だ。
助けた「あと」のことをウィータは計算にいれていない。
たとえ上村由美子が助かったとしても、ユランが知っている人間の秩序の中で彼女は「処分」されるのだろう。
少なくとも、もう健全な人間としては扱われることがない。死刑を免れても、今のウィータが火にあぶられる感覚がするように、ずっと閉鎖された病棟で老いて朽ちるのを待つだけになるかもしれない。
「やれやれ」
だというのに、残酷にも『たすけたい』と願う主の輝きはまぶしかった。
ウィータがこころを挫かないというのならば、ユランはそれに従うほかないのである。
「後悔するかもしれないよ」
――後悔してもいい!
強い思念の波に、猫のひげが広がる。
――まだ遅くない。救けてって言えるなら、救けてあげたいの!
「あーもう。わかったよ。ウィータ。でもそのままじゃ、永く持たないと思うから――呼んできてあげるね」
にゃあん、と黒猫が尾を揺らしながら空を見る。
浮かび上がっていた「超常」の存在に対する合図であった。
●
アルトリウス・セレスタイト(忘却者・f01410)の前には、立ちふさがる理想などはない。
彼は、正義や理想や悪意で動いているのではない。正しく、世界の機能であった。
故に――この目の前にある山のような邪神の姿など、少しの数字の狂いにしか認識していないし、掃討しようと思えば呆気なく滅ぼすことができる。彼は、「なにもない」ゆえに見境ない破壊を作り出すこともできるのだ。
そこに善意もなければ、悪意もない。
小さな町一つを見下ろしながら、やはり彼の理想など「常に一つ」しかないのだ。この場に再現されないのならば、きっと両手を握らずとも再現できてしまうのだろう。
――完全にオブリビオンが消え去り、猟兵としうシステムが不要になること。
それが、アルトリウスというひとのかたちをした世界の仕組みが願う理想である。
果てのないことだと言われてもアルトリウスにも限界はない。人の心がわからないなりに、――彼は彼としての手を尽くすだけなのだ。
人の命の輝きだけは、この世界の機構でも作り出すことはできない。
だから、――すべてを壊す力で、猟兵たちに力を貸すことを選んでいるだけだ。
そのに感動はない。役割を終えたシステムが駆動しない日が来るまで淡々とエラーを処理するだけの彼に、この目の前の邪神と同化したらしい彼女は「引き算」の対象であった。
どうしようとも思わない。
ただ、――エラーは処理すべきである。
【破界】を起動させる。痛みを想起させるという羽ばたきは、たちどころにアルトリウス「だけ」を避けるように割れた。
甲高い悲鳴めいた邪神の叫びはどうやら怒っているらしいが、眉一つ「システム」は動かさない。
「どうやら」
猫の合図を見る。
照らされた光から体をのけぞらせるように、何度かいびつな体を動かす邪神の姿を無機質な青に写す。
――、魔弾、展開。
「お前を助けることを、少なくとも俺と同範囲にいる猟兵は選んだらしい」
掃射。
――道を作る。
アルトリウスの無限に作られる蒼の魔弾は、まず地面を抉った。
シーソーの原理と似ている。地面を無数の魔弾で穿つことで、地形を隆起させる。山の頂上に顕現した邪神めがけての「ショートカット」には、一頭のオオカミが走っていた。
月光を身にまといながらなりふり構わず走る彼の姿に、アルトリウスも目を細める。
アルトリウスにできるのは、破解のみだ。
人の心の仔細などはあまりにも小さすぎて強大な彼には理解できない。
しかし、――この地形を眺めながら思うのは、やはりヒトこそがこの場を動かし、守り、一人一人で文明を築き上げてきた軌跡である。
「お前もその一人だった」
――何でもない俺よりは、人の間で求められているはずだ。
「上村由美子ォッッッ!!!!!!!」
血まみれのオオカミは、叫ぶ。
傷はウィータの光で治されている。今もなお輝き続ける彼女の光は多くの猟兵たちを癒すことに成るだろう。
シキは隆起した土地の上を走った。がむしゃらに走って、暴風をかき分ける!
「大丈夫だ――」
無責任な言葉かもしれない。それでも、その言葉が皆のすべてであった。
いつか、自分がかけてもらいたかった言葉だった。
「自分を認められないだろう、拒んでしまうだろう――だが、『お前たち』は!!」
必ず、助ける。
まるでシキの為だけに作られたような台座から跳ぶ。
跳躍した躰が高く、宙に浮いた。人から外れた脚力で「黒の王」を飛び越える。
――人間ならば為せなかっただろう。
――「理想」ならば、叶わなかっただろう!!
「俺たちが、救出するッッ!!!」
吠え猛る彼の声とともに、二丁の拳銃が火を噴いた。
――理想を生み出す翼が二枚、大穴を開けて砕け散る。為すべき「未来」のために、その呪われた翼を破いてみせた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
嵯泉/f05845と
分かるよ
と言われたくないだろう、レディ
……それも分かるよ
私の理想
金髪に紫の目
当たり前に愛されて、世界を愛する
今と正反対の「私」
……くだらね
叶わない夢を捨てるのは、生憎慣れてるよ
生きるしかないんだ、レディ
死ねば何も手に入らなかったと認めることになる
普通に愛されて、衒いなく愛したかった
それがもう出来ないなら
憎んで恨んで苦しんで
どうしようもなく「普通」ぶって
苦しくないふりして生きるしか、ないんだよ
……な、嵯泉
何も諦めないって約束したけどさ
出来そうにないのは、どうすれば良いのかな
反故にしたくないんだけど
もう手の届かないもの、思ったよりいっぱいあるみたいだ
……難しいこと言うなあ
 鷲生・嵯泉
鷲生・嵯泉
ニルズヘッグ(f01811)
――見た事のある様な姿だ
己には判り得ぬ心と痛みを抱えて生きるものの苦悶
何を云う事も出来ぬが故に……問う
死して手に出来るものが在るのか
総てが「喪われずに済んでいたなら」
続いた時間であったならば幸せだったろう
だが違う
私は今を生き、此の手に在るのは喪ったからこそ得たもの
戻らぬものへと伸ばす手は、もう持ち合わせない
……そうか
出来ないなら仕方が無いさ、無理を望む訳じゃない
唯――沢山の届かぬものがあるとして
其れでもどうしても胸の裡から消せぬものが現れるかもしれないだろう
何時か心の奥底から湧き上がる、其れさえ諦めずにいてくれれば良い
……失敗しても駄目でも、遣り直せば良いという事だ
●
「――、くだらね」
欲しいのは、共感ではなかった。
己の何を知っているのだと、ニルズヘッグ・ニヴルヘイム(竜吼・f01811)は何度も名前通りの自分を押さえて、心の奥にねじ込んでは笑顔を作るようにしてきた。
ニルズヘッグの周りは、今でこそ無責任なことをいう人間が減ったものである。
しかし、学び舎――若さ、というのもあろうが――にいたころといえば、それはそれは、無責任な同情と不完全な慰めがあったものであった。
故郷が焼けたからなんだというのだ。
――喪った片割れならここにいるではないか。
孤独だったことの何が悪いのか。多くを敢えて語らず、人を拒絶しないニルズヘッグに向けられた数々の「よかれと思って」の言葉は、もはや鋼鉄の処女に彼を押し込めると同義であったと言ってよいだろう。
目の前には、「理想」がいる。
「ニルズヘッグ」などという名を与えられなかったであろう、誰かの騎士だ。
美しい顔に、金色の髪の毛。紫色の瞳と、――美しい鎧。真っ黒な自分とは正反対の、真っ白な王子がそこにいた。
燃え盛るものを胸の奥に感じて、ぐっと喉を鳴らして唾を飲んだ。自分を律するかのような痛さが喉に灯る。
「叶わない夢を捨てるのは、生憎慣れてるよ」
起動術式、――【此岸の境界】。
この場といえば、すっかり黒の王がかき集めた呪詛で満ちていた。この場こそニルズヘッグの尤も得意とするところであり、目の前の騎士は辛かろう。
血を吐き出しながら剣を握る彼を、色違いの瞳で眺める。
「苦しいか」
――そんなもんじゃなかった。
泣き出してしまいそうな声が漏れる。お互いのどちらとも付かぬか細い声だった。
周りの呪詛が直ぐにその音すらかき消す怨嗟でとぐろを巻く。強大な蛇の姿をした黒の集合体は、可視化できるほどの密度を孕んでいた。
それでも、目の前の王子は剣を握っているのだ。
――来るなら来いと猛々しく叫ぶ弱い姿のなんと美しいことか!
「なァ、知ってるか。――白は黒に勝てないんだ」
『魔王』よろしく、怨嗟の竜が真っ赤な口を開いてゆるりと首を横に振った。
「知らないよな」
●
剣鬼同士が鍔迫り遭う。
先ほどの「虎」とは違う太刀さばきであった。――さすれば、これは「鬼」か。
鷲生・嵯泉(烈志・f05845)が闇色の世界で眼光を遺しながら鋭く銀を振るった。
空気を裂くどころではない。その速度で生み出す衝撃波を含めた二段重ねの攻撃であった。しかし、目の前の「鬼」もまた同じ手法で撃ち合う。己の足場がわずかに揺れたのを感じて、嵯泉が間合いを取ればちょうど立っていた場所――その背後にあった家屋の壁が「砕けた」。
まるで大砲で穿たれたかのような大穴をじろりと赤で見る。
「鞘か」
そう、――目の前の「鬼」もまた嵯泉である。
是とも何とも言わぬ悪鬼よりも苛烈な瞳をした目の前の男は、いつか見た自分の姿なのだ。
その瞳が「死ぬのだ」と血走っている。
見開かれた隻眼と、ぎゅうっと締まる唇がすべてを語っていた。ああ、今までの己の姿はこれほどに「張りつめていたのか」と嵯泉はいっそ、冷静を通り越した達観を得ていた。
獣を受け止めた彼である。己の中にある苛烈な獣性を手懐けた今とあれば、その「鬼」がありとあらゆる手段を用いて己を殺しに来ることは悟れていた。
太刀筋、その速度の衝撃波、そして、「隠し」の鞘での突撃。どれもこれも「確実」の業だ。
「問う」
ぱらぱらと散らばる破片は名残めいていた。
見えぬ速さで――「鬼」は男へと迫る!踏み込みの前に蹴られた地面は陥没しておりその威力を示していたのだ。そして、嵯泉が息を吸うのと同じ時間で刀を「突き出す」ッ!!
「死して手に出来るものが在るのか」
迫りくる殺意に、男は揺らがなかった。
気迫――鬼の闘志を前には、どんな生き物も委縮するだろう。この「突き」は確かに確実の業だが、まず相手を固まらせることが第一の目的だ。ならば、男は臆さぬ。
ちん、と一つ音を鳴らすだけでよい。
鞘から親指で弾いた刀がその突きを反らせた!頂点の鋼と平面の鋼がぶつかり、火花が僅かに散る。
飛び出した鋼を握れば押し出され、折れてしまうのが関の山である。男は次に「鞘」を握った。
飛び出していく刃と真逆、姿勢を低く撓める。それから、踏み込みだ!!
突撃してくる長躯のさらに下を潜るように体を畳んだ。そのみぞおちをめがけて鞘で突き入れ、押し上げるッッ!!!
「鬼」の人とは思えぬうめき声が漏れ、内臓の破裂による血潮が口からあふれるころに――弾かれた刀を再び握れば「落ちる」躰はもはや丸太同然である。
あとは、ざっぱりと立ち上がる拍子に斬り捨てた。再び鞘に刀を仕舞えば、あとは静寂のみがある。
これぞ、――秘剣、【剣骸刹狩】!
「喪ったからこそ得た」
聞こえては――いないだろう。
「戻らぬものへと伸ばす手は、もう持ち合わせない」
その言葉は、決別の声である。血だまりに沈んでぐずぐずに溶けていく「鬼」に男は振り返らなかった。
「私は、今を生きる」
――「死に場所を見つけたり」は、もう古い。
●
「生きるしかないんだ、レディ」
呪詛に、――男の声が混ざっていた。
真っ黒な世界だ。何も見えなくて、ただもがいている。
かきわけてもかきわけても、ふわふわとした感覚が邪魔でしょうがない。
「死ねば何も手に入らなかったと認めることになる」
それは、嫌だ。
叫んでも声は出なかった。
――私の人生には、何もなかったわけじゃない。
友達もいた。同僚もいた。頼れる先輩がいて、確かに私には将来の夢があって。
「普通に愛されて、衒いなく愛したかった。それがもう出来ないなら」
さっきからかき分けている黒に触れている自分の両手が、濡れている。
――ああちがう、鉄っぽいにおいがした。どろどろで、これは油と汗が混じってるんだって今になってわかってしまう。
これは『のけもの』の中だ。
真っ黒な獣の体の中に仕舞い込まれて、まったく出れない。死にたくない、と思っていたけれど――どんどん「もういいかもしれない」と思えてきた。
だって、やってきたことは。
「憎んで恨んで苦しんで」
無駄ばっかりで。
「それでも、――どうしようもなく『普通』ぶって」
涙が出てきた。
この黒い羽根の中で死んでしまったほうが、私は幸せかもしれない。
「わたしたち」はこの世界に必要なかったのかもしれない。だって、ああ、でも。
「苦しくないふりして生きるしか、ないんだよ」
――かけられる声の言っていることは、わかってしまうから。
●
銀色の髪を、真っ黒の渦がかき混ぜていた。
まるで撫でまわす様なそれは、よく見れば抱擁のように思える。かわいそうに、とニルズヘッグを抱きしめる誰かが頬擦りをしているに違いない。
「な、嵯泉」
ひとりぼっちの迷子を見つけた男――嵯泉は、田舎の風景に背を少し丸めたニルズヘッグの後ろまでやってきていた。
耳ざといのではない。ニルズヘッグの周りに渦巻く呪詛たちが、教えていたのだ。
甲高い悲鳴をあげていた黒の王が、まるでさめざめと泣いているような心地がする。黒い呪詛が頭からあふれて、だばだばと森に注がれていく。
やがて、――ここは腐り落ちるのだろう。このままにしておけば、確実に終末の洪水となるに違いない。
「何も諦めないって約束したけどさ。出来そうにないのは、どうすれば良いのかな」
振り向かない彼の顔に、涙はないはずなのに。
嵯泉には、その彼こそ泣いているように思えてならなかった。
「そうか」
故に、隣に並ぶだけにとどめる。ともに、山に浮かぶ大きな邪神を見ていた。
「出来ないなら仕方が無いさ、無理を望む訳じゃない」
反故にしたくないからこそ、問うているのだと理解している。嵯泉が息を吐けば、呪詛は霧散していった。
「唯――沢山の届かぬものがあるとして」
そういえば、このニルズヘッグという男は。
誰かに言う言葉を自分に少しは向けてやればいいのにと、ゆるりと瞼を閉じながら嵯泉も思う。
「其れでもどうしても胸の裡から消せぬものが現れるかもしれないだろう」
「鬼」の時からこの考えに至るようになったのは、少なくとも。
「何時か心の奥底から湧き上がる、其れさえ諦めずにいてくれれば良い」
――お前が、切欠だったと云うのに。
「難しいこと言うなあ」
「……、失敗しても駄目でも、遣り直せば良いという事だ」
呆れたような語調の嵯泉に少しだけニルズヘッグがほほを膨らませる余裕を得たところで、「続きだ」と嵯泉が促す。
呪詛に長けたニルズヘッグならば彼女の「中」に言葉を届けられるのだ――多くの猟兵たちの声を拾って、なげかけてやればいい。
「一人じゃないさ、なぁ」
この言葉も、きっと無責任だろうか。
それでも、――多くの「あきらめる」に含むには易すぎる気もするのだ。
山が哭いている。まるで、初めて届けられた声に震えているようだった。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 百鳥・円
百鳥・円
●真の姿
あーあ、サイアク
お化粧したのに台無しじゃあないですか
取り繕うのも億劫で
全て剥がれてしまえと諦観が沸き立つ
視界に映る髪
流れ落ちたアイラインのような黒
ほんっと可愛くない
けれども捨てられないのは、あなたと揃いの、
知らない景色に女が立っている
わたしに掛け合わされた半血
ママ
あなたの心の色は、未だ見つからない
こんな幻、馬鹿げている
偽りだと分かるから苛つきが止まない
幻想なんて八つ裂きにしてやる
嵌め込んだ不揃いの色は涙と零れ落ちた
揃いの紫にお前を映そうか
望めよ。助けてと願えよ
我慢なんて必要ないのに
虚勢で繕って何の意味がある
そんなこと、きっと理解さえ出来ない
望むのならば救ってあげる
お前を救う努力をしよう
 冴木・蜜
冴木・蜜
私の毒はたったひとつでも
救い上げるためにある
たとえそれが
か細い糸を掴むようなものでも
私の理想
人を害さぬ万能薬
叶わないと知っている
けれど頭から離れないゆめまぼろし
ですが理想に私は斃せない
まっさらなものを穢すのは簡単
ただ一滴、毒が混ざればいい
そうすれば全て私になる
理想も何もない
ただの死毒に
かつて彼がそうしたように
理想の私すら取り込み毒を濃縮
ただ救うという意思一つ繋ぎ止め
理性を手離し『陶酔』
邪神を包み融かしつつ
上村さんとの繋がりを融かす
愛されたいと願っていい
憎んでもいい
どうか生きることを諦めないで
願い続けて
私たちは貴女のその手を掴み返してみせましょう
 ゼイル・パックルード
ゼイル・パックルード
◎
強者や理解者に殺されたいという、こうなって欲しい理想は持っていたが
こうなりたいという自分自身の理想を描いたことはなかった
殺戮だけの獣になるか、もっと影に深く染まる悪になりたいのか、仲間と普通の幸せを謳歌のか
そういう迷いを全て捨てたのが、理想の自分なのか?
……やはり実際見ると違和感がある
この胸の迷いを払いたい理想……きっと今、甘えてる自分自身の見せた姿。本当は違っても、そう見える
迷いがないなら悔いもないだろ。消えろ、俺はこの迷いの答えが見つかるまで、生きてやる
お前はわかった矢先で何で、変われないと諦める。たすけてほしかったのか、その先の言葉があるのか俺にはわからないが……死んだらその先はないぞ
 ティオレンシア・シーディア
ティオレンシア・シーディア
◎△
…そうねぇ。「仕方がない」って切り捨てるほうが、間違いなく楽なのよねぇ。
…わかっては、いるんだけど。
だからって諦めるのは、どうにも癪なのよねぇ…!
焼き尽くす熱波と引き裂かれる傷の幻覚…あたしだと、たぶんコレよねぇ。
ホント、死ぬほど痛いけど…なんでかしらねぇ。「無傷だった」あの時のほうが、ずっとずぅっと「痛かった」わぁ。この程度で止まるわけないでしょぉ…!
●蕭殺展開、刻むのはマン(自己愛)に准邸観音印。その権能は「人間道の救済」…あたしは説得とかガラじゃないもの、このくらいの〇援護射撃はしないとねぇ。
あなたを「助けてくれる」お人よしって、思ったよりも多いみたいよぉ?
…少なくとも今は、ね。
●
いつから化粧というのが「標準装備」になってしまったのだろう。
そもそも、女が自分を引きたてるためのものでもあり、これは彼女たちの武器であり、男たちを喜ばせ、時に自分で彼らを飾るためのものであった。
丁寧に毛穴を埋め、顔色を可憐にさせてみせ、目を際立たせ、唇の色で欺く。
どれもこれも時間をかければかけるほど「美しく」なっていくこの業はまさに努力が完成を約束するものだ。
――しかし、「化ける」と書くように「暴かれる」ものでもある。
「あーあ、サイアク」
百鳥・円(華回帰・f10932)の顔といえば、どろどろになってしまっていた。
元より顔の形が良いのもある。崩れた己の顔もいっそ美しかろうといつもなら言えたに違いないのに、今は取り繕う暇もないほど「溶けて」しまっていた。
もう構うものか、と思っている。いつもなら例えば――汗やほこりで汚れた顔はすぐに手入れをしてやるのだ。この場でだって、ちょっと空いた家に入ってしまえば蛇口から水だって出る。いつもなら、きっとそうしていた。
「台無しじゃあないですか」
――黒髪が視界に垂れる。
「ほんっと、可愛くない。イモくさいんですよ」
夢いっぱいに自分を飾ってきた。
この田舎の景色ですら際立つのはその努力のおかげだ。きらきらと輝く自分を常にイメージして、夢を体現する。美しく愛らしい少女という誰もが求めるだろう「理想(ゆめ)」の形を作って、髪色すら染めて――円は円になったというのに。
〇は円で、零のカタチなのだ。
黒髪に触れる。乱暴に風にかき回されたそれは数本垂れた横髪の名残だ。やけに長い鎖のようだなと思った。
見慣れぬ景色に、どうにもミスマッチな黒がいるような気がした。
――目線を上げてはならない気がするのに、項垂れた円の顔はほとんど本能のようにそちらを見てしまう。
「ママ」
半血の女がいた。
妖狐と夢魔のまざりが円であるのならば、母であるこの女はどちらであろうか。円だけが、答えを知っている。
迷子の声に、女は立っているだけだった。手を伸ばすそぶりもなければ、立てるでしょうといいたげな瞳である。
――心の色が見つからない。
表情すら、作られない。これが幻だとどこかで円は理解している。こうして幻の中で出会えただけでも、母との絆を感じて幸せを得てしまう自分があまりにもあさましくて愚かしい。
「ママ」
二度目を呼んでも、鎖で繋がれた母は一つも動かない。
異様に冷めた瞳に、円の中にある「子供」の心はすっかり委縮してしまっていた。
この歳になってもまだ「ママ」などと呼んでしまう自分を、大人になりつつある円自身も馬鹿らしく思える。それでも、その表情にとんでもなく切り付けられたような痛みが胸に走った。
「――ママ」
幻の中だって。
どれほど円が美しくなっても、どれほど素敵だと思うものを瓶に詰めても、ちっとも母の色にならないのだ。
それは、たとえるなら子供が描き慣れないクレヨンを使って母親の似顔絵を描くようなことと似ている。自分の中にある母という絶対愛の象徴を一生懸命に可視化して、「うれしいわ」と受け止めてほしいだけの、独りよがりな甘え方とほとんど崇拝めいた気持ちと同じだった。
喜んでもらいだけ。
揃いの黒髪を捨てられないみじめな子供の、ただの純粋な「願望(ゆめ)」。
「馬鹿げている」
真っ黒な鎖を引っ張った。
あっけなく「母」の象徴はぐらりと引き寄せられて、円はその女の細い腰を抱く。
――ああ、本当にばかげている。
「八つ裂きにしてやる」
混ざった紫色の双眸は、獰猛に火照っていた。
泣いても見つからないのならば、そこには何もなかったのだと――残酷なまでに爪が愛をかきわけていく。
●
か細い糸を掴むような、一筋にもならない頼りない光かもしれない。
それでも、それを垂らすことはやめなかった。
――冴木・蜜(天賦の薬・f15222)の前には、美しい白色の蜜がいる。
真っ黒な蜜は元がタールだ。油をすっかり「洗われた」のか、「分離した」のかは分からないが、確かに目の前に現れた蜜というのは、美しかった。
自信のあるらしい背はしっかりとまっすぐで、肩を内に巻いた蜜とは違う。猫背気味の長躯で、まっすぐ向き合う形となった。
田舎の風景には似合わぬ姿の正体を、蜜は知っている。
「人を害さぬ万能薬となった私、ですか」
「ええ」
美しい薬は応える。
「――羨ましいですか」
「いいえ」
蜜はゆっくりと首を振った。
「毒であることを忘れた私を見て、恥ずかしいなと思っただけで」
身の程知らず。
ささやくような言葉で、冷静に事実を並べていた。
蜜の防衛手段ではない。――目を見開いた白い蜜が、初めて凶悪に笑っていた。
【陶酔】の攻防が始まる。
蜜二人は動きすら見せることはあるまい。お互いの毒素の津波が、混ざり合うだけのことだ。ぐるぐると渦潮のように地面を浸した黒と白は、あたりのコンクリートを溶かしながら毒素の海で浸している。
さざ波のように黒が引けば、勢いづいた白がのしかかる。強く黒が押せば、白は押し込まれていく――毒の海で二つが混ざり合うのを、紫の瞳で見ていた。憂いよりも性質の悪い感情の渦を巻く白を、冷静に黒が見る。
「どうして、冷静ぶるのですか」
「あなたが興奮しているからですよ」
――頭から離れない理想の形は、傲慢だった。
それはそうなってしまうのも、蜜には分かる。ありとあらゆる病を治し、どんな生き物もまず喪いたがらない「命」を必ず助けることができる万能薬は、今ならばその「おそろしさ」がわかる。
人が死なないということは、老いないということ。
老いないということは、成長をさせないということ。
未熟な命だけがただ増え、痛みを知らぬ生き物たちは自分たちを俯瞰で見合うこともなく――美しい楽園で美しいままに腐っていくだろう。
それを、知らなかった。
――だから、蜜は目の前の理想をばかばかしくも想える。
「まっさらな物を穢すのは簡単」
ゆっくり、黒が海の割合を広げていく。
呑むような仕草でどんどん落ち着いた波が沸き立つ白を侵していくのだ。泡立つ悲鳴すら飲み込んで、徐々に黒は白の足を蝕む。
「――なぜ」
「例えるのなら、あなたが完璧なゲノムだとしたら」
白は、何よりも美しい色であり。
「私は、――完璧なウイルスだったというだけのことですよ」
何よりも弱い色である。
精巧に組み上げられた「理想」を分析するのはさすがに途方もない。ただ、代わりに蜜ができる事といえば、「地道に崩す」ことだった。完璧というのは、すべてがそろってこそのものなのだ。
たった一つのタイルがはがれてしまえば、それはもう完璧ではない。二重らせんの一本でも欠ければあっという間にバランスは崩れて落ちていくように。
理想のない黒がどんどん白を脅かす。身じろぎした美しい理想すら、脚をからめとられて動けない。さらに、――溶けだしていく。
「馬鹿な!」
「愚かだったのは」
かつて、「彼」がそうしたように。
「私たちだった」
噎せれば、たらりと口から油が出た。
真っ黒な粘っこいタールを指先に絡めながら、――手放した理性の痕跡を見る。
「救う」ことこそ、蜜が出来る「暴力」だ。白をなぎ倒すような津波が起きて、それは山と浸食する。何度も満ち引きを繰り返し、徐々に徐々に昇り詰めていく様は、海そのものだった。
●
強者や理解者に殺されたい、――在ってほしい姿があった。
それは間違いなく押し付けで、ゼイル・パックルード(囚焔・f02162)は結局他人から毟り盗るようにみせかけただけの悪童でしかない。
依存であった。彼は、「こうなりたい」という自分自身を描いたことがない。
目の前に現れたゼイルの姿は、確かにゼイルであった。
心を凪いでいるといえばいいだろう。迷いのない瞳には、いつもの苛烈さが目立たない。
まるで氷のような金色の瞳に、不思議な心地がした。
――殺戮めいた獣になることもなく、悪に染まりきることなく、仲間との幸せを見つけたわけでもない。
「何だ、お前」
思わず、そうつぶやいた。
ゼイルの目に映った「理想」はがらんどうなのだ。
ゆっくりと理想が剣を握り、ゼイルも反射で応対する。踏み込んできた一撃は――はるかに今のゼイルを上回っていた!
「ッお」
思わず驚く。
みしりと肩がきしんだだけではない。振り下ろされた剣が、確かにゼイルの肘を壊した。曲げた部分から突き出た骨がすべてを語る――この理想は、確かに強い!
弾けるような血しぶきを見て、次に内なる炎を燃やす。何かを考える余裕を与えれば、この理想に先手をくれてやることになる!! 爆炎を腕にまとい、半ば強制的に飛び出た骨を腕に戻しながら――振り下ろされた剣を押し上げた!
「てン、め」
しかし、ゼイルは追撃できない。
弾かれた静寂の彼が、地面に降り立つ。ゼイルのような爆炎を使うのではない、纏うような炎すら、まるで蛇のように彼を中心にとぐろを巻いて立っていた。ゆらゆらと燃えるそれは、ひどく落ち着いている。
「何スカしてんだよ、なぁ――」
ゼイルの腹には、ナイフが突き刺さっていた。
弾かれると同時に飛び出した暗器は、尻がちりちりと燃えて赤い。爆炎の遣い方も、ゼイルの大振りとは違って、丁寧なものだ。
「ちょっとは喜べよ、ヤられ甲斐がねぇだろ」
――ゼイルが腹に刺さった暗器を抜けば、どばりと血があふれた。
肝臓を狙われたのだ。血流がもとより多い急所である。炎熱で燃やし、傷を塞げど喪った血の量は多い。ぐらりと失血に応じて体が傾いても、睨むのはやめなかった。
何も、感じていないのだ。
――「理想」のゼイルはただそれを傍観していた。
人を殺しても何も思わないのである。自分がいたぶる獲物に大して快楽すら感じない。
サディズムもなければ、果てにあるのは――何がこの強さを生み出すのかを考えていたら、顎に蹴りを鋭く入れられていよいよゼイルが膝をついた。
ばたばたと鮮血が垂れて、遅れて炎が灯る。
蹴られた勢いのまま弧を描くように、時計回りに体を捻じって刀を振るうも、なめらかな炎にそれを遮られる。炎を断ち切る先には何もなく、二歩ほど後退したところに「理想」はいた。
「俺に、何も思わねえってか」
――「理想」のゼイルは、「何もかもを他人に依存した」彼である。
強者や己よりも優れた誰かに、その評価を任せている。
獲物の強さがどうこうではなくて、彼の「周り」がいかに「殺した」事実を受け止めるかを考えているのだ。
爆炎を上げながら切りかかるゼイルを、炎の蛇鞭がからめとる。そのまま地面になぎ倒して、転がし、しかし止めを刺さない。
――まるで、誰かに見られていることを意識しているように。
「ッ、の――くたばれ、クソ」
理解を得たいのではない。
誰かに「考えてほしい」のだ。
自分の形が分からない。表現の仕方もうまくいかないばかりで、とうとう「最低」の手段に出た。
それが、「自分で表現するのを諦める」こと。誰かに依存して、――その「誰か」に「お前はこういうやつだ」と定めてもらいたがる、究極の依存による完成形である。
みじめだった。
これが――「理想」だというのが、子供らしくてたまらない。
考えることを止め、ただ無心に日々をむさぼり、獣よりももっと価値のない「もの」同然ではないかとゼイルも思う。しかし、確かに「楽」な生き方だ。
「ふざ――けんなよ」
首を振る。
たまらない。こんな姿が「自分」の理想などと、思いたくはなかった。
「失せろッッッ!!!!!」
【紅葉狩り】。
子供の癇癪めいた悲鳴とともに、地形が炎で塗りつぶされていく。
迷いも悔いもすべて「他人任せ」のゼイルを飲み込むさまを見て、――ゼイルは熱で焼かれる喉の心地を得ていた。
「俺は、『生きてやる』」
――自分の頭で、考えて。
●
仕方ない、と切り捨てるほうが間違いなく楽で、リスクもない。
ティオレンシア・シーディア(イエロー・パロット・f04145)は理解していた。元より、弁えが良い彼女である。
下がるべきところは下がり、押すべきところは押す。用心棒としての習慣もあるが、女同士のやりとりに慣れた彼女の生き方というのは「まんべんなく波が立たない」ものだ。
「わかっては、いるんだけど――」
燃え盛る地獄にわざわざ虫すらも入りこみはしないだろう。
この強大な敵を相手に、ティオレンシアは自分が何かをできるとも思っていなかった。
明らかに大きさが違うのだ――優れた「殺す」能力を持つ己が挑むほどのものではない。出来れば、いつも通りに仲間の支援と、ちょこまかと走り回る小細工でデコイに努めるべきだった。
だというのに、今日は。
「だからって諦めるのは、どうにも癪なのよねぇッッ!!!」
――自らの痛みの中に飛び込んでいる。
焼き尽くす熱波の前に、まず肌が痛かった。
露出している顔を覆うために両腕を前に出す。手首がじりじりと焼ける心地がして、痛みにたまらず叫びそうになるが、ぐっと唇を閉じる。もはや乾燥してぱりぱりとした上唇を、一生懸命口内に閉じ込めていた。
鼻で呼吸をしていても熱風を前に肺が燃やされている心地がする。とても、――人間であるティオレンシアを前には酷すぎるものであった。
いつかの痛みである。
体中からひりひりとした痛みが湧き出した。
――全身を引き裂かれるような心地がする。脚を一歩前に出すたびに、躰がばらばらになってしまいそうな心地がした。
前に進む。それでも、少しずつ――確実にティオレンシアは脚を進めていた。
歩くたびに肌が裂けた痛みに襲われている。体中からはぼたぼたと水分があふれだして、どこかしこも脱水を起こし始めていた。
もがくように、走った。
駆ければ躰はまず揺れる。ぐらっと右方向に倒れそうな体を、どうにか左に頭を奮うことでまっすぐに立て直す。そして、止まらず走った。
死ぬほど痛い。
――言葉で形容するなら、それがすべてだった。
ティオレンシアを襲う痛みのほかには、場には呪詛が満ちている。うずまくそれは猟兵の干渉が入ってやや視界をよくしたといえど、やはり濃い。
通常でも息をするのが苦しいほどの淀みだというのに、ティオレンシアには熱を伴って襲い来る。
明らかに、常人に少しばかりの恩恵が宿った彼女には地獄であった。ここできっと折れても、誰も攻めれないだろう。何せ、ティオレンシアという「人間」を過ぎる存在は猟兵の中にも無数にいるのだ。
わかっている。それでも、走り続けた。
――痛かった。ずっと、痛かったのだ。
この痛みが何だというのだ。これで立ち止まったほうが、きっと自分を許せない。なぜならば、あの時の「無傷だった」時のほうが、今よりも倍以上に痛かった!!!!
「この程度でッッッ――――、止まるわけ、ないッでしょぉぉ…………ッッッ!」
展開、【蕭殺】。
体中を蝕む痛みを代償に、魔術刻印を施した拳銃を穿つ。
弾丸は大きすぎる的へと向かうのだ。震える両手で確かに穿つたった一点は――「黒の王」の胴体に大きなひび割れを――いいや、魔術の鼓動であった!
「あなたを、ッ――『助けてくれる』お人よしって、さぁ。――は、ッ、思ったよりも、多い、みたいよぉ……?」
びしりと蔓延った赤い刻印は、経である。
救いのために施された言の葉が、ティオレンシアの「救い」である。
お人好しには結局のところ、自分も含まれるのだ――助けられなかった昔を憂うくらいには、弱っているのもあった。ゆっくりと拳銃を降ろして、座り込む。
「少なくとも、今は、ね――」
躰からどんどん熱が消えていく。
――一発の打開を現した銃弾が、一瞬のゆるみが、「人間道の救済」を約束した痛みが仲間たちの呪詛をふつりと途切れさせてみせた!
「望めよ」
――「夢」は叶えたいものだ。
ひとの脳を具現させたものをむさぼるのが、この円の所業だ。
「――助けてと、願えよ」
【獄双蝶】が、空を舞う。
夢を願わせなければ円はそれを叶えてむさぼってやれない。心の形が見えないのは、どうにも気に入らぬ。黒い髪をかき上げながら、夢魔のまざりは堕落の糧を乞うた。
「寄越せ」
――我慢など、できやしないのだ。
救う努力ならばして見せよう。黒油に飲まれる邪神がもがく様に、火を注ぐ。ぼうぼうと燃え盛る「財産」すらも根絶やしにしてやろう。――それが「助かる」かたちならば。
「愛されたいと願っていい。憎んでもいい」
その様を眺めながら、蜜が言葉を投げかけ続けている。
「いいんです」
両腕をゆっくりと広げた。「どうかそれでも」燃やされていく呪いの象徴は――やがて屋敷にも広がるのだろう。
「生きることを、諦めないで」
――願い続けて。
手を伸ばしてくれなくては、その手を握ってやることもできないから。
黒の中でうごめく女性の両腕を探している。どろどろの流動体が黒の王を燃やしながら、かき分けようとしていた。
ゼイルは、それをただ眺めている。この果てに何があるかは彼には予想がつかなくて、圧倒されていた。かけてやれる言葉が無くて、――悔し紛れな声がやっとだった。
「何で、変われないと諦める」
ゼイルは、わからなかったのに。
「死んだら、その先は無いぞ」
ぴしり、と。
黒の王の頭に浮かぶ赤黒い宝石がひび割れた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 西塔・晴汰
西塔・晴汰
【晴要】
◎
幸せな幻覚…
先日夢の中で見た物を思い出す
自分の中の寂しさを知ってしまった夢
両親共ごく普通の一般家庭で
いつ帰っても自分一人なんて事もなくて
いつも両親と笑っていられてたら
更にもし兄弟とかいたら、きっと寂しさなんてない家庭で…
先日の夢は別な事も教えてくれた
もしもとある友人が受難の生まれをせず幸せに生きていたら
そんな仮定の夢
でも
そうはならなかった
辛くて悲しくて寂しい世界でオレ達は生きてる
だからこそ、その先に夢より楽しい未来を描かなきゃならないんだ
…オレは、先へ往く
飛び込んでく珂奈芽を援護する為に
炎の矢で支援射撃
できればのけものも諦めたくない
珂奈芽の手はまだ、伸ばせば届くところに在るはずだから
 草守・珂奈芽
草守・珂奈芽
【晴要】
◎
幻覚が辛い、怖い
体が脆かった頃に感じた痛みも、それよりずっと苦しい感覚もあるの
昔の上村さんはきっとこれより怖くて痛くて
今のわたしになんて救えないかもって思えてくる
それでも、わたしだって照らせるって晴汰くんが教えてくれた
ならせめて、最後まで手を取ってもらえないなんてさせない!!
それが今のわたしでもできることならッ!!
晴汰くん、行かせて。今飛ばなきゃわたしは何にも勝てなくなるから!
翼を広げて黒の王まで突っ切るよ
体の鱗と魔力結晶で全身を覆って、捨て身の勢いで突っ込む!!
取れる手が無いなら抱き締める勢いでぶつかるしか!
由美子ちゃん、その辛さも貴女だけど――頑張ってきた貴女も本物でないのさ!!
●
鎖が、まるで線引きのように垂れていた。
ここから先は西塔・晴汰(白銀の系譜・f18760)に立ち入るなと警告するような重さである。両手首を縛るそれが地面を蛇のようにうねっていた。視線をやれば、そこにあるのは――晴汰と家族である。
晴汰は、一般的に見れば幸せだ。
両親が死んでいることもなく、育児を放棄されることもなく、甲斐甲斐しく育ててもらいながら、彼らとともに仕事をさせてもらえている。仕事が彼にとっての学校のようなもので、毎日を懸命に働きながら生きていた。
傷だらけになりながら、誰かの傷を癒そうと笑顔を振りまき、「はい喜んで」と仕事を請け負って、どこまでも照らす強い男の子だ。
――そう、まだ、男の子なのだ。
両親とも、一般的であればよかった。
確かに晴汰とて、聞き分けのない子供ではない。両親が今までどのような苦労を得て寄り添ってきたのかは、見えない二人の絆が奇跡の子と呼ばれる晴汰がいる時点で明らかだろう。
二人が教育を施し、晴汰に晴汰という名を与え、今日この日までその健康を願い送り出している日々も、きっと嘘ではない。二人が望んだ幸せだった。
だが、――晴汰の「しあわせ」は違う。
「あ」
目の前にいる『かぞく』は。
――晴汰のものであり、晴汰のものではなかった。
幼いながらに気にしないようにしてきた傷である。
一般的な家庭で育った晴汰がいた。思わず釘付けになってしまったのは、今この場にいない両親が栗毛の自分を撫でながら楽し気に過ごしている顔を見てしまったからである。
父親には尾もなければ、狼らしい特徴がない。母親には忌々しい角もなければ、一般的な女性らしい嫋やかさがあった。母の腕には、赤ん坊が抱かれている。
――きっと、寂しくないんだろうなと思ってしまったのだ。
晴汰の中には、「うちはうち」で割り切ってきたことがある。
まだ十五年程度しか生きていない人生で、多くのことを諦めてきた。
勉学に励むことなく、代わりに家業のことに専念することに成った晴汰である。まだ齢にして十にもならぬころから、懸命に両親の背を追いかけてきた。
学び、駆けて、時に転んではべそをかいて、今がある。――それが「当たり前」だから、気にしてこなかったのに、ふと思うのだ。
家に帰っても、誰もいない時がある。
仕事から疲れて帰ってきても、家の中はいつも明るいというわけでもない。
家があるだけまだマシなのだと、いつも「最低」を考えて蓋をしてきた。
晴汰にはきょうだいも出来っこない。――彼が「唯一」の「奇跡」だったのである。両親は、元より子が出来るはずではなかったのだ。
だから、晴汰も望まなかった。弟でも妹でもいればきっと、この寂しさと辛さを分け合って励ましあうことができて――のびのびとやれたに違いないと。
どうして、自分ばかりがこうなってしまうのだろうと思うときもある。
「最低」でないだけじゃないかと叫びたくなる時もある。なぜならば、まだ、晴汰は「聞き分けがいいだけの男の子」なのだ。
――もっと甘えたい。よくやったと褒めてほしい。この日々会える時間すら少ない家庭なんて家庭じゃない。オレは父さんと母さんの満足のために生まれてきたんじゃない!
手首に巻き付けられた鎖が、悲鳴めいた晴汰の心を反響させて手首に食い込む。
「いた、ッ」
思わず声が出た。
痛みで目をそらした晴汰の脳に、ひとつの記憶が舞い戻る。
とある友人の夢を見たことがある。
――あの子が、受難の生まれをせずに、幸せをかみしめて生きていたらという夢を。
●
救えないかも、と思った。
「いた、ぁ」
草守・珂奈芽(小さな要石・f24296)は、苦労を知らぬ子だ。
彼女なりの苦難は数多くあるが、それがすべて「世間一般的な」苦労ではないと、先ほどから見せつけられていた。
むしろ、珂奈芽の苦労というのは「ぜいたく」なものである。
生まれたときから蝶よ花よ、美しいおまえと持て囃されて生きてきたのだ。
汚いものをわざわざ見る必要などないのだといって、珂奈芽から目をそらさせていた大人たちの判断は正しかったと、珂奈芽は今なら「痛いほど」理解できている。
体中がひび割れるような感覚がした。躰が脆かったときのような痛みが指の先から突き刺さり、ばきばきときしんでいるような心地がする。何度も目視しても腕には外傷ひとつないのに、まるで内側から破壊されているようだった。
「ぁッ」
痛い。
――割れる感覚が、怖い。
石が割れたときが果たして絶命であろうか。それとも、珂奈芽はもう二度と珂奈芽としては生きていけないだろうか。がくがくと膝がわらって、両手をついて四つん這いになった。
体を支えていられないのだ。ばきばきと中身が割れるような嫌な音が頭に響いて、ぎゅうっと目を閉じてしまう。
もっと、痛い感覚があった。
それは、――「思い知ってしまった」苦しみである。
珂奈芽は、自分の傲慢ゆえの無知さを知った。
確かに珂奈芽は努力家である。己の脆い体を鍛えながら、誰かを守ることに全力であるのは間違いではない。――ただし、それは「自分で自分を守れるようになってから」のことである。
自分を守る、という手段において彼女が知っているのは「自分を鍛える」ばかりで、「人を使う」という発想がないのだ。ゆえに、精神的なダメージを「もろに」受けてしまった。
「――晴、」
晴汰の名を呼ぼうとして、口を閉じてしまう。
ちょうど珂奈芽の前に立ち、風よけの役割をする彼は「立ち止まっていた」。
手首を鎖に縛られて、うつろな表情は珂奈芽からは見えないが――この彼に「救けて」とはできないのだ。
「しっかり、する――のさっ!!」
それは、自分に向けたことばである。
上村由美子を取り込んだ邪神は、絶叫こそ止めたものの、体を溶かされながらもぐるぐると円錐の体をよじっていた。回るたびに風が巻き起こり、猟兵たちのいろいろな痛みを呼び覚ます。
それは、珂奈芽のように――本当に「あった」痛みであり、珂奈芽の知らない晴汰の痛みの権化が巻き起こされたりするのだ。
どうにかして、まずはあれを止めないと――とはわかっているのに、珂奈芽は激痛を前に立ち上がれない己を叱咤する。
「や、んなきゃ――」
照らせる。だから、待ってると言ってくれた。
目の前で傷にとらわれる晴汰が、珂奈芽を先ほど照らしてくれたではないか。
「なんないのッッ!!!」
珂奈芽は、不器用なのだ。
「最後まで手を取ってもらえないなんてさせない!!――それが今のわたしでもできることならッ!!」
珂奈芽自身でも情けなくなるくらい、粗削りで、まっすぐすぎて、何も見えていない。なのに、――やるときめたことは必ずやりたいと思ってしまえば、頑固なものだった。
【 草 化 竜 為 ・ 蛍 舞 】 !
晴汰を起こしたのは、緑色の輝きであった。
は、と瞬きを繰り返す。大きな竜が、甲高い叫びをあげながら邪神めがけて突っ込んでいく!!
「――珂奈芽ッッ!!!!!」
向かい風に背を煽られて、栗毛がぐしゃぐしゃになった。上着をめくりあげられながら、真っ白な息すら風に巻き込まれていく。――美しき翠の竜が、珂奈芽が!! どどう、と捨て身とも思える勢いで邪神をなぎ倒す!!ざりざりざりと燃える山の上を滑りながら、二つが絡み合って地響きを立てていた。
「あッう」晴汰の鼓膜すら破りそうな音波で叫ぶ「のけもの」を、竜が懸命におさえつけている。
「――しっかりするのさ、由美子ちゃんッ」
黒い翼に顎を押し上げられる竜を、【覇狼槍炎襲】――晴汰が援護する!
炎の矢の正体が何かは分かり切っていた。ほぼ反射で弓引く晴汰も、しかりと肯いて次の矢を構える。ぼう、ぼう、ぼうと炎が空に宿り――晴汰の弓と同時に降り注いだ!!
「その辛さも貴女だけど――頑張ってきた貴女も本物でないのさ!!」
邪神は暴れる。
もがく巨体を押さえつけながらも、竜は噛むことがない。ぐいぐいと押し戻されても翼を炎が焼いてくれるから、ただただその頭に何度も声をかけてやる。
. ・・・・
「貴女たちだって、未来があるはずなのさッッッ!!」
だから、手を握って。
晴汰には、解っていた。
――どうしようもなく、人生とは孤独が多い。
それでも、だからこそ「みんな」で生きていく。
この先に、夢よりも楽しい世界を描くのだ。たとえそれぞれに、辛くて、悲しくて、寂しいことがあっても「大丈夫だよ」と隣にいれば、手を握ってやれる。
「握って」
あきらめたくない。
――竜と少年が、その咢で吠える思いは、いよいよ邪神の宝石を砕いた。
真っ赤な核から、赤い液体を浴びてこぼれ出る。竜の掌に受け止められたのは、紛れもなく「上村由美子」であった。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 朱赫七・カムイ
朱赫七・カムイ
⛩神櫻
△
抑えていたものが
溢れて零れて戻らない荒狂う神
黒の羽はまるで鴉の羽のよう
よくない
サヨの障りになる
――!!
身体が軋む
声も出ぬ程の激痛と
神格ごと溶かされるような不快感
大蛇が這いずるように渦巻く憎悪がこころを侵す
大切な失いたくないものを侵し歪ませるこの痛み
しっている
噫、神斬
君が抱えていた大蛇の呪の痛み
なら私にだって耐えられる
進める
はやくサヨの所へ
あの子をすくう
どんな理想より私にとってサヨは櫻宵
一番なのだと
本当は救われたのは私だ
巫女の手を握れば痛みなど無くなる
私に
ひとの子がすくえるのかな
…いや掬う
救えねばならない
そうでなければ
サヨも救えない
きみが私を神にしてくれる
負けられない
私は君の神なのだから
 誘名・櫻宵
誘名・櫻宵
🌸神櫻
◎
現れたのは理想の私
理想?今の私が一番でしょうに
ひとも喰らった事も無い顔をして
凛と正しく清廉で
然して親しみ感じ惹かれる美しく咲き誇る桜龍
噫、嗚呼
わかってしまった
あなたは私――前世の私(イザナ)
私の、師が最も愛した存在
私の魂も紲された愛も
元は皆あなたが築いたものだった
私達は同じなのに
私はあなたにはなれなくて
でもいいの
私は私よ、誘七櫻宵
ねぇ理想のあなたを喰らったなら
私はもっと理想的になれるのではないかしら
「咲華」
認められなかった哀れな子
見てると昔の私を思い出してよくないわ
救ってあげる
戻っておいで
私の為にあなたを救う
救いましょう
私のカムイ
あの神を斬り、すくう
出来るわ
だってカムイは
私の神だもの
●
現れたのは理想の姿である。
――理想?今の『私』が一番でしょうに。
櫻が吹雪く。雪が呪詛を受けてそう見えているだけだと、誘名・櫻宵(爛漫咲櫻・f02768)にも解っていた。
呪詛に満ちた田舎風景のせいもあるだろう。月さえ隠された世界で、美しく咲く龍がいるのに、何ら違和感もなかった。人一人いなくなったこの領域は、もはや神域に近いのである。
凛と正しく清廉、然して親しみ感じさせられる顔だった。整った目鼻立ちだけでなく、どこか惹かれてしょうがない。櫻宵をじっと見て、警戒の色すら宿していない。
「噫、嗚呼」
――わかってしまった。
イザナ。それは、――紛れもなく誘名・櫻宵が「かつて」その姿であった時の彼である。
「私の、師が最も愛した存在」
駆け寄ろうなどという無粋なことはしない。
ただ、伸ばしてしまいそうな両腕を胸の前で握る。求めてしょうがなくなってしまうのも、仕方がないことであろう。
何せ、今の櫻宵とは「全く以って逆」だ。
櫻宵といえば、悪辣な存在である。
己が最優先だ。桜色に乗る口弁といえば、己のためのものばかりである。
己が心地よくあれるならなんでもよい。周りを元気づけてやるのだってその一環だ――己と神さえよければよいために、そっと手を添えて励ましてやることだって苦でもない。
それを救いだとうそぶくのも止めないし、美しい着物の裏側でいびつに笑うのも誰の迷惑にもなりはしないのだ。
――蛇めいた執着心の果てこそ、呪いの先こそ、この噯ゆえに。
「私の魂も紲された愛も、元は皆あなたが築いたものだった」
しかし、「イザナ」は違う。
人を食らうようなこともなく、まして、己の幸せを願うような彼ではなかった。
己とは人のためにあり、そのために美しく咲き、ただしく世界を廻らせるために――神に仕える身なのだと、何もかもを等しく愛して、だからこそ「師」に最も愛されていた。
「私達は同じなのに、私は――あなたにはなれなくて」
いけないかしら。だなんて。
声に出さなくても、わかるだろうと――屠桜がぶつかり合う。
ぎゃりりり、と鋭い音を立てて競り合った。美しい顔がこちらをにらむのを、櫻宵は心からわくわくとしてしまう。もっといびつに歪めばいいのに、と心のそこで思いながら「だからあなたは愛される」と納得する。
迷いなく次の手がねじ込まれた。
刀を弾いた姿勢から、低く体を撓めてくる。「イザナ」の間合いに引きずり込まれたと知ったのは、猛々しい尾を掴まれたからであった。引っ張られるまま――体を任せ、つま先だけで時計回りに体を捻じる!尾をぶうんとそのまま振るえば遠心力だ。イザナが脚を浮かせられることになり、ふたつの大きな傘が咲いた。
羽織を翻しながら戦うこともあるまい。尾から手を離したイザナが、地面に足の裏で滑っていく。
しかし、その間もこちらへの敵意を込めた瞳は切らない。
ちきり、と牙を鳴らしながら互いに似た姿勢をとった。切っ先を相手に向け、刀の腹を天に向ける。
――荒々しくも強く。
そして、戦っていても「美しい」。
それを、かつては羨ましいとは思った。
――今は、もう思わないが。
イザナサヨ
「私は私よ、【咲 華】」
真っ赤な血まみれのような口内を魅せながら、呪われた桜が笑う。
「ねぇ理想のあなたを喰らったなら」
――私はもっと理想的になれるのではないかしら。
●
「――――、あ」
抑えていたものが溢れて零れて戻らない。
朱赫七・カムイ(約彩ノ赫・f30062)の祖は、荒狂う神である。
ぶわりと背中が疼いた。目出度く陽だまりのような赤がどんどん黒く染まっていく。
「よくない」
黒の羽はまるで鴉の羽のよう。
――こうあれかしと、何かがささやいていた。
体がばきばきと軋みの悲鳴を上げて、神の体を見えぬ呪いで縛り上げていた。
「待っ――てく、れッ」
――サヨの障りになる。
目先で理想の己と戦う巫女の姿を見る。
ここで神である己が情けない声をあげでもすれば、たちまち巫女はこちらを振り向いて戦いに集中できまい。ぐうっと空気を飲み込んで、激痛に彼は耐えていた。
荒れ狂う黒の意味は解っている。――目の前に「サヨ」がいるのだ。
まるで体をはい回るような痛みは、蛇の溶解液に溶かされているようにひりひりじくじくと体に赤い渦を作っていく。
「――ッふ」
唇を強くかんで、耐えていた。カムイは己の悲鳴すらかみ殺して、この呪いを御し、立ち向かう。
這いずるように渦巻く憎悪がこころを侵すのだ。
まるで躰が自分のものではないような心地がして、気高い神格すら奪うような激しさでとぐろを巻いている。頭を太い縄で縛られたような痛みがして、今にも頭を掻きむしりもんどりうってしまいたくなる。
全身が言いようもない熱に侵されて、どんどん呼吸が浅くなって――大切な、失いたくないものを見たときの己の顔が見えなくてよかったと、心から思った。きっと、とてもつもなく、けがらわしい――。
「しっている」
――噫、神斬。
権能は揺れ、未だ定まらない未熟な神である。
ひとに試練を与えるどころか、己の祖にすらこうして弄ばれてしまうほどの雛だ。
目の前で斬りあう巫女の姿は猛々しく、雄々しいというのに。どこまでも己というのは「がわ」ばかりなのだと痛感させられる。だからこそ、――がりりと奥歯をかみしめた。
嘗ての呪いに呑まれた「あれ」が己だというのならば、今割れてしまいそうなこの神格ですら押さえてみせようと、踏み込む。
櫻宵は、「イザナ」との交戦において確かに斬り結んではいるが――やはり、「師」からの恩恵が足らない。徐々に切り傷が躰に増えていっても、まるでいとわない姿がいっそ美しかった。手を伸ばして、ならば私がと、カムイはようやくその名を呼ぶ。
「サヨ」
――あの子をすくう。
振り向いた。
櫻宵が、熱狂する中――神の声を聴いたのだ。
巫女の手を握る。
虚を作ったその二つめがけて、「イザナ」は躊躇いなく太刀を奮う、が――。
「カムイ」
ひたり、と。
左の指先二つで、櫻宵はその牙を挟み食い止めていた。
かちかちかちかち、と震える「イザナ」の牙、そしてその持ち主である「イザナ」は、目を驚愕に見開いている。
両手で懸命に櫻宵の右手を握るカムイは、ぎゅうっと閉じた両目を開いた。
――血の雨が降り注ぐ。
「救われたわ」
「イザナ」が躰から血を咲かせながら、倒れていく。立つのは「カムイ」の愛した「櫻宵」だけだった。
――頭の中で響く絶叫が、ようやく止んだ気がする。「ありがとう」と微笑む巫女に、ぶんぶんと神は首を横に振った。
「噫、――救われたのは私ばかりだ」
「何を云うの。カムイは、私を救ってくれたわ」
二人で、山を仰ぐ。
「私に、ひとの子がすくえるのかな」
「すくいましょう、カムイ」
今度は、血まみれの顔をぬぐうことなく櫻龍が嫋やかに微笑む。
取り巻く呪詛すら彼を恐れて失せていく。カムイは、どこか息のしやすさを感じていた。それは、炎が燃えるための空気が贈られるのと、同じような心地で――。
「そうだね」
――『掬わねばならない』。
そうでなければ、サヨも救えないのだから。
人の子ひとり掬ってやれずに、龍一匹が救えるものかと血にまみれた神が頷く。
汚らわしいとも思わない。この血潮を糧に、――神は己の力へと還る。櫻宵の手を握る両手は、左手だけになった。
「きみが私を神にしてくれる。負けられない」
櫻宵が握る右手には、彼の牙がある。
その右手を、右手で覆って――龍を背から包む形になった。ともに一本の刀を構え、邪神に狙いをつける。
「私は君の神なのだから」
認められなかった哀れな人の子のことを、櫻宵は考えていた。
見てると昔の自分を思い出してよくないのだ。きっと、あの竜に抱かれた少女よりも――邪神の『中』にいる『のけもの』のほうがつらくてたまらないだろう。
自分からも自分を認めてもらえずに、どこにも居場所が無くて、ただただ自分がいるという証拠を作り、存在しない両親に赦しを求めるその姿は、いつかの自分のようで。
「救ってあげる――戻っておいで」
噫、気に入らぬ。
ならばせめて「神」と己のためにこの哀れな人の子を掬って見せようではないかと微笑んだ。
――いましがた自分が「じぶん」にしてやったように。
【再約ノ縁結】。
降り注いだ神罰が、二人を取り巻く呪詛を打ち消す。――書き換えられた「約束」が履行された。
邪神の胸から、人の子が「生える」。ぐったりとした様子はほとんどの猟兵が身に覚えもあろう。
翠のやさしさに埋もれる彼女、「上村由美子」とは別の、「のけもの」の肉体だった。
「『あなた』にも、与えて見せましょう」
――いつかの『未来』の続きを、どうぞ櫻に夢見て。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 琴平・琴子
琴平・琴子
◎△
私はあの時助けてくれた王子様になりたかった
でも今は違うわ
それをお前は今愚弄するの
王子様の手にはお姫様がいない
あるのは愛という重たい一振りを捧げるための白い花束
お姫様がいない王子様なんて王子様じゃないから良かった
容赦無く、戦えます
王子様なら、姫君と一緒に踊ってくださる?
王子の心を射止める黒鳥の一蹴りは心臓へ
重たい愛が籠った花束は白鳥のしなやかさで受け流しそのまま貴方にお返ししますね
お転婆お姫様のお相手をしていた方だとは思えませんね
それも当たり前
貴方は王子様じゃないのだから
最後に私がなりたいものを教えてあげる
私は私以外になれやしないから
私という揺らがない「私」になりたいの
さようなら、王子様
●
――あの時助けてくれた王子様になりたかった。
「今は違うわ」
琴平・琴子(まえむきのあし・f27172)は、視線の前に現れた少女の姿を見ていた。
「その姿、愚弄するのね」
これが理想だとするのなら、いかに愚かな言い分であろうか。
――呪詛渦巻く田舎町に現れたのは、王子様の輪郭だけをかたどった琴子である。
確かに弱きを助け、困った人に手を伸ばすことは「王子様」といってよいだろう。だけれど、社会という蓋を開けてみればなんてことない行いだ。「誰でもできる」ことである。
されど、それを『王子様』だなんてメルヘンチックなものに喩えないといけなかったのは――己の童心に違いなかった。とはいえ、まだ琴子は九つである。
『王子様』らしい衣服を着飾った琴子の姿をじっと見て、緑の色は一気に冷めた。
「欠けているわ」
まるで、曲がったタイを指摘するように。
ぴ、と人差し指を伸ばしてやった。失礼だなんて当たり前だ、「自分」相手ならば、礼儀も何もあったところで代わりはしない。
愛である。王子様の格好をした琴子の小さな両手には、その年齢に似合わない――酸いも甘いもまだまだ知らぬ身にはほどほど似合わぬ愛という重たい一振りを捧げるための白い花束があった。
さらに、まったくもって嘆かわしいことに「助けてやった」みたいな顔をしているではないか。まるで琴子に指摘されたことは予想外だと言いたげに、自分の衣服を眺めまわしていた。
違うわ、と首を振って、やはり琴子はその手に握られたブーケについてしっかりとクレームをつけてやる。
「そこには、お姫様の手があるはずよ」
ばかばかしい。
――これでは、「王子様」失格だ。
払いのけるような拒絶の一言がきっかけとなった。もはや、これ以上の言葉は必要あるまい。
【オデット・オディール】は前を向いている。びゅ、と素早く放たれる少女の足は、もはや突撃といっていい。つま先ではなく、その踵で蹴り殺すような勢いを伴った一撃が――「可憐過ぎる」王子様の胸を穿った。
「助けてくれとは申しておりませんし、そも――出番もないのに出てきてはいけないでしょう?」
容赦のない蹴りに「う」と「王子様ぶった琴子」が情けなくうめく。
「ほら、王子様だというのなら、一緒に踊ってくださらないと」
続いて足払い。
体を丸めた「王子様気取り」に容赦はない。「この程度は躱して頂かないといけませんのに」とあきれた言葉を呟きながら、琴子は「王子様っぽい」誰かの膝をゆがませる。
がくんとバランスを崩した――偽物は、苦し紛れに花束で琴子を射止めようと必死なものだった。
大ぶりなブーケのハンマー相手に、ひらりと半歩左足をずらして柔らかな背を反らせる。
まるで湖面で踊る白鳥のよう。ふわりと香る心地よい衣服の擦れたにおいすら、今は動きの苛烈さを物語るアクセントだ。
「アプローチもなっていませんし」
あまりにも、程遠いわ、なんて。
琴子といえば、「愛らしい」けれど「かわいい」子ではなかった。
蹴られ、躱され、想いを届けられない「情けないひと」の顎を蹴り上げる。
「それでは姫君も訪れないでしょう」
お転婆な気性である。
ここに座っていなさいと言われて黙って座っていられるような子ではなかったのだ。
幼いながらに物を考える力があり、自立していて、自分というものをしっかりと握ってしまっている。それが――琴平の娘であることが起因するかどうかはこれからの人生のほうがうんと長いものだから、ただ言い切るとすれば「三つ子の魂百まで」といえよう。
ひとえに、どんな大人も「手を焼く」ような子ではあった。
それが愛らしいところではないかなんて言えるのは、琴子のことを何も知らない誰かか、それこそ「王子様」くらいである。――この程度の「戯れ」についてこれないなど、まったくもって「その資格がない」。
「私がなりたいものを教えてあげる」
舞踏会でダンスすら満足に振舞えないにせものの胸を、鋭くつま先で蹴り飛ばした。
ふわ、と体を浮かせた細い体のなんとあさましいこと。できもしないことをやってみせようとしたからだと、罵ってやりたくもなった。まったくもってくだらない、形ばかりの理想は張りぼて同然で、だからこそ腹が立った。
――琴子には解っていることがある。
琴平・琴子は、「じぶん」を揺らがせないのだ。
「私は私以外になれやしないから、私という揺らがない『私』になりたいの」
どこかに小学校があるのだろう。狂わされた下校の最終チャイムが鳴り響いた――十八時だ。
まっしろな息を吐きながら、琴子はぐったりと力尽きたよく似た人形を見下ろす。
手を取るようなこともしてやるもんかと、横たわらせるように細い体を足蹴にした。まるで缶でもころがすかのように、スカートの裾をつまんだ優雅な一撃である。
恭しいカーテシーも必要あるまい、振り向くこともなかった前足はやはり前を向くのだ。
「さようなら、王子様」
――したたかなお姫様が、ガラスの靴など履くものか。
大成功
🔵🔵🔵
 カイム・クローバー
カイム・クローバー
◎
正義のヒーロー(猟兵)なんてのは専門外だ。請けた依頼にも『救ってくれ』、なんてのは含まれちゃ居なかった。
つまり無理に助ける必要なんざねぇ。――違うか?
ああ、俺は金に汚ぇクソッタレに言ってるんじゃない。
銃を構えて、翼を撃ち抜いていくぜ。王だか神だか知らねぇが、無様に這いつくばってるのが似合いだぜ、アンタ。
俺は――上村由美子、アンタに聞いてるんだ。今度は『のけもの』としてのアンタじゃなく、な。
取り込まれてるから聞こえないって?なら、何でも良い。俺にアンタの希望を伝えな。
『助かりたいのか?』それともこのまま『死にたい』のか?
ハッ…悪くねぇ選択だ。便利屋Black Jack。俺が請けるぜ、その依頼!
 紅砂・釈似
紅砂・釈似
◎
POW
理想として現れるのは今の自分と少しだけ違う姿
耳を貫くピアスが僅かに減り、真っ直ぐに前を向いていて、そして目が全く違う その目には何の疑いも迷いもない
分かっている。虚ろな人斬りでしかいられないのは私が弱いから。他人を信じられたら、自分に抗えたら、生まれ持った才を別の、正しい方向に活かせたはずだ。目の前の姿はそういう自分。きっと、私は斬るべき血に餓えた鬼に見えるのだろう。
正しい。私は恐らく死ぬまで人斬りだ。それでも、やるべきことはある。獣になろうが鬼になろうが、お前は殺す。そこからは、味方って連中に任せる。
UC【佉羅騫駄】での一撃 理性も慈悲も捨てた後は、言葉もなく敵へ【暴力】を振るうのみ
●
わかっていたとも。
――虚ろな自分でしかいられないのは、そうでしか生きていけないのは、紅砂・釈似(流殺煙刃・f27761)という女が弱いからだ。
目の前に呪詛から呼び出された理想の釈似というのは、ピアスの数を減らして生き生きとした瞳で刀を握る女であった。
まっすぐに間を向いていて、目には疑いがない。衣服にも気を遣っていて、生きることを消費するのではなくて楽しんでいるようなそぶりが見えた。亡霊のような釈似に、少しだけ目を丸くして――それでも刀を抜くところなどは、性根が似ているようではあったが。
釈似は、まばたきもしないままそれを見ていた。
――刀で斬られたような心地はしないし、胸を貫かれたような感触もないのに、体の中がじくじくと弾けたような気がする。
見せつけられた「正解」の姿に、――理解をしてしまっていた。
こうなるべきだったのだ。今のような姿でいてはいけなかった。
ぶおんと振るわれた刀同士がぶつかり合う。圧倒的に「正しさ」で斬りこんでくる釈似は、今の釈似と等しい怪力を誇っていた。さらに、その太刀筋は「天才」に「技」が乗せられたものである!
拮抗する刀をはじいて、「正しく」虚を作る。ほぼ、反射で釈似が手を前に突き出せば――その手のひらに深々と刀が刺さった。ぐりりと刀身を廻す判断が早く、手の甲の骨が聞いたこともない音を立てて粉々に折れていく。
左の手で防衛した、ということは――狙われたのは心臓だ!
当たれば即、終わる。本能で嫌悪した「死」の感覚に、釈似もやや目を見開いた。
がくん、と肘の力を抜いてその切っ先から逃れる。ほぼ力の流れに従うようにすれば、押し出される腕のままに――刀に血と脂を塗りたくってやりながら抜けた。
そして、まもなく突っ切っていく横っ腹めがけて膝を打ち込む。
ぐ、と空気を噛んだらしい声を聞く限りでは手ごたえがあったが――にやりと横顔が凶悪さを魅せつけた!
これが、ひどく。
――強さなのだと、魅せつけられる。
釈似は、才能の持ち主であった。
乱暴の家庭に生まれ育った彼女が、剣の道に通ずるのにわざわざ道場に通うことなどありはしない。
ただ、掌で叩くと自分の手もやられてしまうから、どうせなら「わかりやすい」殺す武器がよいのだと刀を握れば天下布武といって差支えのない才能が芽生えたのだ。
それを、正しく使っていればよかったのに、どうしてか臆病な自分を鍛えてやることはできないままに「思うがまま」の太刀筋を得てしまった。
それは、――釈似にも解っている。太刀筋は乱暴で、迷いばかりなのだ。
「鬼め」
はじめて、「正しい」自分からの評価を聞いた。
指先だけで回転させる。「正しさ」は、体を横に吹っ飛ばされながら――釈似の脇腹を切り裂いた。
パ ッ と血しぶきが飛ぶ。
さほど痛みを感じていないこの状況こそ、「おかしい」のだと解らされてしまった。
「正しい」釈似は口から血とも唾液ともつかぬ粘っこいものを吐き散らしながら汗ばむからだに「戦える」という喜びを掲げて挑んでくる。
対して、釈似といえば――「すべてを怖がる」故に否定的な太刀筋で応戦するばかりであった。
――そうだとも。
これほどまでに「やれる」ならば、「やれば」よかったのだ。
「お前は」
ばきん、と幾度目かになる鋼同士の噛み合いである。
「――、私が何に見える?」
「みじめな鬼に見える」
釈迦に似ている、と書くのに。
血に飢えた鬼を討つことは確かに正しかろう。だから、この「正しさ」の釈似には、常に背負ったロケットがあるのだ。それこそ、バイアスである。
己こそ正しいゆえに、誰かを助けることにきっと躊躇いもない。――娘として一時期可愛がった狼のことも、きっと丁寧に世話をしてやっているに違いないのだ。釈似と違って、「間違った道」をわざわざ選ぶまい。
死ぬまで、――人斬りになるだろう。
「そうか」
言葉はいらなかった。
【 佉 羅 騫 駄 】 。
ぎろりと眼の色を変えた釈似こそ、修羅であった。あまりの気迫を前に、「正しさ」はほんの一瞬臆してしまう。それが、――勝敗の決め手であった。
釈似は、ずっと臆しているのだ。ずっと何もかもを恐れて、どれもこれも消えてなくなればいいと怨んで、八つ当たりのように人を殺して、それを間違っていることを認めることで自分を正当化している。
生き方に間違いなどあるはずがない。
――勝てば、正しいのだから。
此度、鋼をはじいたのは釈似の方からであった。突き飛ばされるようにして「正しさ」が少しばかり浮ついたのを、仕留める牙が脳天より叩き下ろされる。
真っ二つに、割れた。
――「正しかった」が死んでしまえば、「間違い」である。
「さすがに、……ここから戦うのは、難しいな」
血まみれの体を片手で抱きながら、草臥れたように釈似がその場に座り込む。
もう見えない真っ赤な血だまりが、まだ視界の端に残っているような気がする。斬って切って死にかけたというのに、今はタバコが欲しくてしょうがなかった。
●
「オイオイオイ、えげつねえことになってんなァ」
笑う彼の声すら、いつものような余裕は薄れてしまっている。
カイム・クローバー(UDCの便利屋・f08018)に襲い来るのは、今まで彼が打ち勝ってきた試練からの痛みばかりだった。一歩戦域に踏み込んだだけで体中の古傷がうずき、痛みの前に膝を折られそうになるが――ここであきらめるような男でない。
そも、カイムというのは。
きわめて合理的な彼である。
依頼された金以上のことはやらない。まして、オーダー外のサービスなど専門外だ。
生憎「便利屋」である彼のところにはいつもひっきりなしに依頼が飛び込んでくるものだし、仕事に困っているわけでもない。猟兵としても実力がある彼の前ではダブルワークでてんやわんやの大盛況である。今更、余計なことをして名前を売る必要もないのだ。
銀髪を猛烈な羽ばたきにかき混ぜられながら、紫の瞳が二人を映す。竜の手に包まれていた「上村由美子」が、守られながら家屋にもたれかけられていた。
ぼんやりと瞳が開いていることをちらりと確認して――己の声がかき消えぬように、まずカイムは「のけもの」を胸から生やした神の翼めがけて「オルトロス」を構える。
依頼は、不完全な邪神の討伐である。
その分だけの金額は保証されている。生きて帰れば間違いなくもらえる約束されたものだ――つまり、無理に「ハイスコア」など目指さなくてもいい。
「他の奴らは知らねェが、俺ァ――仕事人でね!金以上のッ、サービスなんざまっぴらごめんだッ、なあそうだろ!? 違うか!? 聞こえてんのか上村由美子ッッッ!!!」
【銃撃の協奏曲】。
吠え猛ける狼たちの声が鉛玉となって、風を巻き起こす忌々しい翼を打ち落としていく。
無数のそれを前に骨の折れる抵抗だ。カイムがすかさずリロードをしようにも、刻み込まれた今までの積み重ねといっていい――古傷たちの痛みがじくじくとはじまる。
「クソッ!」舌打ちとともに己の手を見た。震えてしまっていて、上手く銃が握れていない。新しい弾を装填するにも時間がかかるが、それでもまだまだ常人よりは早い!
絶え間ない羽ばたきを前に、カイムは臆すことがなかった。必要なのは、たった一つの言葉だけでいいのに――上村由美子は、そのカイムの姿を眺めているばかりで口を開いてくれない。
「なァ、あんた、頼むぜ――ボサッと座ってんな!」
がなる声にようやく、ハッと意識を取り戻したらしい。丁寧な処置を望んでいたとしたら、カイムに当たってしまったのが運の尽きと言えよう。
「急いでんだこっちは、寝てんじゃねえよ!!」
「は、ッ――は、い」
「今は何も考えるな、いいか――俺の質問に、応えろ!!」
いよいよ次の弾すら落としそうになってしまう。
全身から噴き出した汗に体の限界を感じていた。目すらかすんでしまっているのだ――ひどい過労状態である。「面白いことしやがる」と険しく笑みを作ってから、カイムは続けた。
「上村由美子、あんたは賢い選択をするって俺は思ってるが」
両手で固定する。
銃をしっかりと構えた筋肉質の体は、鉛のように重くなった腕を胸の筋肉で持ち上げて――振るえる照準を無理やりに肘で固定した。がっちりと腋をしめてようやく打てる体勢が整うほどだ。
ここまでお膳立てしてやったんだぜ、と愚痴めいた言葉にすら笑みが乗っている。由美子には、それが不思議でならなかった。
――迷惑をかけているはずなのだ。
なのに、なぜ目の前の彼は――いきいきとしているのだろう。
「『助かりたい』のか? それともこのまま『死にたい』のか? ――それとも」
顎でカイムがしゃくる。
由美子は促されるまま、視線の先を見た。
「あれ、は」
「あんたの同居人だよ」
邪神の胸から生み出された「のけもの」はぐったりとしてしまっている。
邪神が動くたびに体を振り回されて、それでも意識が戻っていない――呼吸すらできていないかもしれなかった。だから、カイムは焦っているのだ。
「『あいつも助けてほしい』か!?」
――切り離してしまった。
二つは元が一つだった。だけれど、いつの間にか別れた二つは確かに「人格」として生きてしまったのである。
由美子が会話に難がないというのに、カイムの知っている限りではあの「のけもの」は言葉がつかえない。おそらく知能レベルに差があるということは、――「知っている」ことも異なるだろう。
食べ物の好みだって違うはずだ。由美子が警察官を目指したように、「のけもの」にだって描いた未来があったかもしれない。
酷な話だ。助けてやれるなら、誰だって助けてやりたい。呪いは彼女らのせいでなかったのだから!
「――どうすんだ?」
それでも。カイムは「プロ」であるから。
ちゃんと「オーダー」が降りない限りは、彼が動くことはできないのである。
無償で助けるだなんて胡散臭い肩書がついてたまるものか、そんなもので助かるのならば、カイムの手すら必要あるまい。
故に、たずねる。
――上村由美子に、その判断を問うたのだ。
黒い翼がはじけ飛ぶ。
暴れる巨体がもんどりうつこともかなわない。漸くまともに息が吸えた気がして、カイムは大きく肺を動かして息を吐いた――。
「ハ、――悪くねぇ選択だ」
薬莢の転がる音が合図である。くるくると回った円柱が、狼煙となった。
「助けてくださいだとさ、野郎ども――淑女諸君も盛り上がっていこうぜ、なあッッ!!!!!!」
吠える。
遠吠えめいた大声で猟兵たちを読んだ。冬の寒空に響いて、――カイムの声に合わせて猟兵たちが「討伐」と「救出対象の増加」に動きを加えて今、動き出す!
はためくコートは仲間たちの勢い任せだ。風にあおられてカイムの体を隠す青黒が、ゆっくりと上村由美子に振り向いた。泣きはらした顔に、かがみこむ。
「便利屋Black Jack。――俺が請けるぜ、その依頼!」
メーデー
お代は、その「救難信号」で十分さ。
にかりと笑ってやって、仲間たちが紡ぐ明日のためにまた銃を握る。
――撃鉄は、確かに明日「ふたつ」を救う一撃を繰り出した!!
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 エミリア・ジェフティー
エミリア・ジェフティー
◎
自動操縦で呼び寄せたセシャートに搭乗
…上村さんを取り込んだ邪神に散弾砲を向けた途端、さっき見た場面が脳裏を過って発砲を躊躇う
その一瞬で見せられた幻覚は…多分、幼い私
両親を助けてくれた恩人が娘を連れて訪ねてくるからって、柄にもなくおめかしをして
そうして現れたその人は
…どうして
貴方が来るんですか
教官
何かが聞こえる
さっきのけもの…ただの幻覚?
偽りの絆を噛み千切るように歯を食いしばって
"アイツと同じ事をしたら許さない"
そう訴えてるように見えた
…全部思い出せたわけじゃないけど
やるべき事は分かってる
精神汚染を厭わずオウルアイで情報収集を開始
ブルーローズ起動
…必ず見つけます。あの子達を助け出す手段を
●
――必要なのは、助け出す手段だ。
その思考に無駄があってはならなかった。現状、冷静な解析を踏まえてエミリア・ジェフティー(AnotherAnswer・f30193)は愛機のセシャートに乗って見せたはずである。
「救出対象」を検知。コックピットに現れる無機質な英文字の言いたいところはわかっていた。
新たな生命反応、受肉の成功――名もなき「のけもの」に与えられた肉体が、ぐったりと邪神の胸から生えている状態を解析する。
サーチゲージの溜まり具合を常に視界の端で意識しながら、周辺を取り除くことが第一であろうとした。ほぼ溶けだしている邪神は、周りの瘴気を吸い上げることで回復を目論んでいるのだ。
「セシャート!」
エミリアの意識に応じて、愛機は鋭く武装を構えた。
――はずだったのだ。
もはや視界いっぱいに広がったモニターには、強大な敵を捕らえたサインも出現している。
毎秒に何発も打ち込んでいれば「確実」に仕留められるとパーセンテージまで味方していて、あとは引き金を引くだけだったのにこんな時まで、エミリアは自分の脳が信じられない空虚を作ってしまったのだ。
「ッ」
三流である。
兵士あるまじき戦場に置いての精神の揺らぎは、先ほどの「知らない」場面のせいだ。
――エミリアの脳には、先ほどの光景は「ありえない」物のはずだった。
幼いころの自分の顔が思い出せてしまう。昨日まで、そんなものは気になりもしなかったのに今はこびりついて離れない。
セシャートとの連携を表すパーセンテージに揺らぎが現れたのを、どこか情けなくも思うのに、やはり目の前にあるモニタはどこか遠く感じられてしまうのだ。
幼いころの自分は、何をしていたっけ。
ずいぶんと、ませていた。
両親を助けてくれた恩人が、その後の容態を確認しに、己の娘を連れて訪ねてくれるのだという。
それはそれは、粗相がないようにまず見かけから気にかけたものだ。
命がけで助けてくれた両親の娘が可愛くないなんて、どんなドラマでも映画でもあってはならないことである。だから、その日といえば一番お気に入りの服をわざわざ引っ張り出してきた。
今の時期には少し合わない色じゃないか、とも思ったのだが、これを着ている自分が一番かわいいと確信があったのだ。悩んでいるうちにも時間はどんどん過ぎていくものだから、靴下をはき合わせるころにはほとんど直感での組み合わせでアクセサリーも選んでいた。
子供ながらの精一杯なおもてなしで、恩人に「ありがとう」を伝えるために、チャイムの音には駆けつけよう。
跳ねるように音のするほうへ走っていく。ワクワクとした気分で――ドアの認証コードを押せば、無機質なスライド音がした。
「どうして」
――貴方が来るんですか、教官。
呼吸がいつの間にか乱れている。
操縦士のバイタルが崩れていると、セシャートが心配しているのだ。右手の上にホロ画面が浮かび上がり、不整脈と――過呼吸を必死に伝えていた。
「ッは、――」
たまらず、体がのけぞって汗が噴き出す。
頭頂部をごりごりとチェアに押し付けて、酸素に潰されるような苦しみを肺に感じた。
「ァ」もがいて、体をよじる。それから、まずは呼吸を取り戻そうとするのに、まるで体だけは何かからおびえてたまらないようだった。海から釣り上げられた魚のようにもがく相棒に、セシャートが攻撃態勢を緩めないまま後方へと下がる。
「せ、しゃ――と、ッ」
助けて、と念ずればいい。
操縦席の天井に、小さな立方体の窓ができる。酸素吸入ボンベといっていいだろう――小さなスプレー缶ほどのそれを両手で握って、どうにかノズルマスクで鼻と口を覆った。
強制的に穏やかな呼吸を得る。常に空気の巡りは善いはずなのに、極限の緊張状態に陥った体はパニックになっていたのだ。エミリアが自分の体を客観的に理解し始めたころに、甲高い耳鳴りがした。
―――――――、"アイツと同じ事をしたら許さない"。
ぎり、ぎりと。
まるで歯ぎしりをしているらしいヒステリックな痛みの音がして、両目を反射的につむる。生理的な嫌悪をぞわぞわと背筋に走らせ、瞼を開いた。
「今の、は」
サーチ。
――機体に侵入者は検知されませんでした。
――痕跡、なし。
――通信、なし。
――異常は見つかりませんでした。戦闘行為に影響はありません。続行するには、____。
「全部、思い出せたわけじゃないけど」
それでも、やるべきことは解っているから。
耳に残る痛みの音と、懐かしくも苦い記憶が、じわじわと「エミリア」を苦しめている。
それでも、引き金に手を描けるだろう。コントロールパネルが無数に広がり、最適解を見出すための瞳は冷静でありながら、どこか「忘れていた」ものを探すような必死さがにじむ。
「――必ず、見つけます」
セシャートと共に世界へ羽ばたけば、見つけられぬものはないはずだから。
――Set,【CODE:O"ブルーローズ"】
散弾がまき散らされる。邪神の再生しようとする呪詛を端から潰していった。
まるで、――「答えを探すように」。
大成功
🔵🔵🔵
 久津川・火牙彦
久津川・火牙彦
ハッ……やっぱりどうして、こんな物かい
聳え立つ黒を見上げ嘆息し、全デバイスを展開
夢見るままに何とやら
夢のままであれば少なくとも社会の安寧は守れた、だからか?
――こちらA1、特A級怪異出現、全装備……勝手に使うぜ
だがしかし、内なるアイツに主導権は渡せねえ
判決死刑執行で終わらせる訳にゃあ行かんのですよ、なぁ
北落師門より来たる凶星、取り敢えず自分の言う事を聞きやがれッ!
未覚醒状態で炎神機を、念動力全開で制御する
悪ぃけど焼き尽くせないんすよ、コンプライアンスで
あとは意地……かな!
幸福な幻覚もきっと炎だろう
親愛も何も分かり切っていた事だ
炎で黒き翼を焼いて、絆という綱でそれを御し
夢は夢のままで終わらせる!
 ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック
◎
(目の前の"のけもの"
ジブン
怪物
二つが脳裏で歪に重なる)
(――ザザッ)
そうか
"助けてほしかった"か
(抑圧された獣性
狂おしい殺意
愛に飢えた心
どれも余りに覚えがある
そうしてお前は獣になったんだろう
人としての理性だった「上村由美子」は
のけものの獣性に呑まれてしまうのか)
(なら)
一つ言うなら
(風が吹く
いいだろう、其の儘受け入れよう
その幸福を見せる風を――
ノイズ
【砂嵐】で受け其の儘返す。
お前の「理性」も「獣性」も
ただ叫ぶ事だけを望んではいないんじゃないか
"敵意を鎮めて"互いを見ろ
お前達は元から唯一無二の絆を持ってるだろう)
自分の一番の理解者は自分自身だ
まず自分自身で
自分を助けてやれ(ザザッ)
 ロキ・バロックヒート
ロキ・バロックヒート
◎△
たすけてほしい?
その言葉の羅列はピンとこなかった
“ ”はひとを救う側
その逆はあり得ない
あのヘビは諦め切れない証左のようで
“ ”を表しているかのよう
幾らひとに混ざり笑い合い甘く睦まじく過ごしたところで
簡単にひとの道理を外れて
それをなんとも思わない
どこまでもひとに近くてひとから遠くて
矛盾だらけの不完全な“ ”
それでも完全になりたくて
自らには諦めすらも赦せないのだと
汚泥も赤黒い血も啜ってすべて呑み込んで
認め抱えて這って往く
そうして笑って“ ”の振りをする
ほらお言いよ上村由美子
たすけてほしいって
その胸にあるものを曝け出して
祈り願え
“神”が―聴き届けて赦してあげる
嘆きも絶望も
ぜんぶ連れて行ってあげる
 ディフ・クライン
ディフ・クライン
お前は何者にも成れぬと誰かの声がして
この身体を蝕んでいく
痛まぬはずの身体とコアが軋む
「彼」にも己にも成れぬまま、心も感情も知らずに果てろと
…いや、いつかきっとオレは選ぶよ
「彼」であれ、オレであれ
この身体に相応しいものになると
最期に約束したんだ
だから、知ろうとしているんだ
それにオレは人形だから
心は無い
無いものは挫けない
体は作り物だ
痛んだとて壊れてさえいなければ、動ける
海を喚ぼう
彼女を助けよう
苦しくても、傷から目を背けても、彼女は今まで生きてきた
真っすぐ真面目に、人に寄り添って
人を率先して助けてきた貴女の生き方は消えない
貴女が手を伸ばすなら
掴む者は居る
いるよ
ユーラ、泣いている彼女を浄化しておくれ
 グウェンドリン・グレンジャー
グウェンドリン・グレンジャー
◎
今の私、に、この、邪神を、傷つける……こと、は、とても、難しい。色々と
でも、やらなくちゃ……殺らなくちゃ
(青い光が灯るGlim of Anima。浮かぶ「三つの月」の紋章)
きっと、私の、理想の姿……丈夫な心臓、持って生まれた、赤毛に、青い目のままの、グウェンドリン
でも、おかしい
その姿の、私……は、こんな力、使えない、のに
打ち払うしか、ない
もっと深い、心の昏い方、自分から、進んで……あなたに、克つ
(ラムプを掲げ、自分の心から顕現する夜の鳥を降霊させる)
羽ばたいて、エレシュキガル。もっと、昏い方へ
移動力を5倍に、攻撃回数、半分に
この鳥そのもの、呪殺弾にし、もう一人の、自分へ、放つ
眠って、健康な私
●
「は、――」
所詮、こんなものが現れるだけだった。
いびつな黒の羽はむしられど、何度もそののけぞる体を揺らして痛みを訴えれば周囲の呪詛から力を得る。
「何せ、年季が違うってね」
それこそ、この一族が怨まれ始めたのは本当に「近代」のみであろうか?
怨まれるものというのは、その「才」があるといっていい。恵まれる才があるのだ、それを他人に使っていれば崇められるだろうし、――逆に私欲に走る性根がすべてにあるとなれば、所詮カエルの子はカエルである。渦巻く怨嗟が何よりの証拠だ。きっと、この地に「染みすぎて」いる犠牲者はもっと多い。
久津川・火牙彦(火産霊の旧支配者・f30781)は『案の定』の空模様に溜息が隠せなかった。
自分の両手を、広げる。その掌をじいっと見つめて、吹き荒れる呪詛の風に瞼を閉じた。
燃え広がるような――心地がする。
夢を見ているような浮遊感だ。まるで微睡みといっていい「走馬灯」が目の前に広がっていった。
燃え盛る姿が見える。――あれは、間違いなく火牙彦であろう。
「――こちらA1」
もはや繋がっているかも確認できぬノイズまみれのトランシーバーに囁く。
無断で使うのと、「自分はあのとき言いましたよ」と記録に残っているのとは大きく処遇が異なるのを理解していた。図体が大きくなるにつれて得たのは小賢しさであるが、――今、喪われた『彼』の炎がとぐろを巻く。
「特A級怪異出現、全装備……勝手に使うぜ」
――、『北落ノ師門ヨリ来タル凶ツ星、昏キ闇ヲ赤キ炎ニテ祓ヘ給ヒ清メ給フ事ヲ』。
その炎の神は、「世界」のシステムだ。
故に誰にでも「呼び易く」、「扱いづらい」。
異端者は燃やし尽くし、間違いなく世界を脅かすことしかできない人間たちにも炎罰を下す。絶対的な炎熱こそが「彼」こそ、火牙彦であり、――。
そう、この輪郭を燃やす己の熱が、あまりにも愛おしく感じてしまうのだ。
縛られる心地よりも、ずっとずっと暖かい。
これは確かに「幸せ」な夢だろう。喉の奥に引っかかっていた魚の骨を漸く飲み込めたような感覚は、あまりにも今までの御する己をバカバカしく思わせた。
己のことを守り、炎は渦を巻いてその権能の偉大さを示す。呪詛たちは巻き込まれて燃えてゆき、悲鳴めいた声が赤へと捧げられ消えていく。誰にも聞かれることのない終末に、火牙彦の口元が吊りあがった。
そうだ。――これが当たり前であったではないか。
何を我慢することがある。世界がその力を望んでいたのだ。
今こそその力を解放してやらねば、――生命が産んだこの業ごと「いったん」燃やし尽くしてやらねば森もできまい!!!
「『イア! クトゥグア!』」
【 炎 神 全 開 】 ッ ッ ッ ! ! ! ! !
永劫無限の灼熱が、久牙彦の体を包む――!!
両腕を勢いよく掲げる彼の姿は、果たして本当に火牙彦かと、彼を知っている皆が思っただろう。
燃え盛る全身からは人のカタチがみえども、彼の色はどこにも見当たらないのだ。炎から突き出た鋭い爪、ぎらぎらとした火の粉の中には人の体が残っているとも考えづらい。口と思わしき箇所からは常にぼうぼうと火炎があふれ、彼の立つ足元は「臨界」――即ち、溶けている。
どろどろと粗いコンクリートに描かれた「止マレ」の白い文字がみるみる泥じみた真黒に呑まれて消えた。
●
お前は何者にも成れぬと誰かの声がした。
人形は、空っぽであった。
故に、「ひと」に愛される立場である彼らは、人の声がよく届く。美しさの向こう側は罵る声の通りにがらんどうで、余計に反響した。
――ディフ・クライン(灰色の雪・f05200)は、一歩も動けないでいる。
大きな山ひとつをのみこもうとするほどの邪神は、空を黒い羽根で覆いつくしてしまっていた。
どんどん周りの猟兵たちが苦悩と幸福に打ち勝つのをどこか遠くから見ている心地がした。吸い寄せられるように背の低いビルの屋上にやってきたのは、「何物にもまざれない」彼らしい。
彼のためでない黒髪をかきまぜられながら、時に顔を露出させられていた。
その顔をよく見せてごらん、と顎を持ち上げられて――やはり、お前は違うと強く風に頬を打たれるような心地がする。
すべて、幻なのだ。
ディフは、「ゆめ」で出来た人形である。
「彼」のために主人が用意したのだ。
「彼」を喪ったことに耐えられない主が逃避の末に生み出した欠陥人形である。――いいや、見た目は完璧であった。
きっと、何も知らぬ誰かがディフを見れば「ああ、なんと美しい人だろう」とまた「ゆめ」を見せるに違いない。
しかし、――彼は、「主人が望まない」故に欠陥であった。
コアがきしむ音がする。ひび割れそうな痛みが、体中に巡っていった。大きなダメージを目視できない故に、ディフの思考からは「なぜ」すら消える。
びしびし、みしみしと関節が悲鳴をあげ、呼吸の必要でないからだが固まってしまってディフの中は混乱という空白でいっぱいになっていた。
「果てろというのか」
前までならば、それを呑んでいたかもしれない。
望まれない人形がどこに歩けというのだ。
愛してくれる主人から捨てられたのならば、ジャンクになるのが常である。ディフは、いくつもの割れた彼らを見てきた。
いつか己もこうなるのだろう、いいや、「騎士」にすらなれなかった己は――疾く、こうなるべきであると自分で自分の首を、何度も何度も締めてきた。思いあがるなと御して、理解できない自分の感情を何度も何度も、「ジャンク」にしてきた。
芽生えた端から、こなごなにして首を振る。わからないと、崩れた砂の前に言葉を落とすだろう。
だから、――わからないのだ。
「いや」
首を、振る。
「いつかきっと、オレは選ぶよ」
ディフは人形だ。
――人形だと、自分に言い聞かせている。
「彼」にならない自分は心をもってはならないのだと、自分に何度も呪いをかけてきた。自分自身に暗示をかけ続けて終わらない冬にいる。だから、――わかっているとも。
「約束したんだ」
この体に相応しいものになる。
――知ろうとしているものは、途方もない。それは海が枯れるまで水をくみ上げるのと同じことだろう。そして、くみ上げるバケツがディフなのだ。底の抜けたそれで何度も水をかいたって、しぶきがあがるだけだろう。
それでも、きっと「バケツ」は知る日が来る。「新しい底を探そう」と、自分の欠点を埋めたくなる日が来るのだ。――それが、誰かとの約束であり、「誓い」である。
「この身体に相応しいものになる」
くじけない。まだ、人形はジャンクなどでないのだ。
渦巻く【深海輪舞】の友を呼ぶ。「ユーラ」静かなディフの声をかき消さないように、無数の水の矢が顕現した。流動を保ちながら、埋め尽くす翼めがけて放たれる。
「泣いている彼女を浄化しておくれ」
●
――今の自分では、とてもこの邪神に打ち勝つことはできまいと思った。
グウェンドリン・グレンジャー(Heavenly Daydreamer・f00712)の前に現れたのは、赤髪の少女である。
「今にも死にそうね」
「そう、あなた、は――今にも、殺され、そう、ね?」
それでも、戦わねばなるまい。
目の前に現れたのも、また、『グウェンドリン』である。いいや、彼女の『あるべき姿』といってよい。赤い髪に、青色の瞳。美しい肌の色から血色の良さを知り、丈夫な心臓を感じた。
それでも、思わず首を傾げてしまう。
「――おかしい」
「何が?」
「その姿の、私は」
かたや、一人ぼっちの死肉喰らい。正反対のそれは、愛されたオオガラスといえばいいだろうか――背に、グウェンドリンと同じ翼をもっている。
「こんな力、使えない、のに」
外科医の父と、人類学者の母がいた。
ロンドンで生まれたたった一人のその娘には、生まれつきの心臓疾患があり、体は求められる未来に対してあまりにももろかったのだ。
生まれて早々に彼女の未来をあきらめなくてはならなかった両親、特に父は異常な行動に出るきっかけになってしまったのである。故に、この「元気な」グウェンドリンが翼を持つのは「筋違い」なのだ。
「変、だわ」
翼の打ち合いが始まる。
無数の黒色で作られた弾幕が、まるで噛み合う咢のようにぶつかりあった。はじかれる硬質化された翼たちが地面を転がり、コンクリートの上をからからと転がっていく。烏の小さい悲鳴のようであった。
生まれついての不幸な彼女に、奇跡を与えることにしたのである。
外科医の才を生かした父は、奇跡の生体素材として「UDCの体組織」と刻印を移植して見せた。すると、たちまち――一家はみんな「死んだ」。
まさに、呪われたと言っていいだろう。今のグウェンドリンも体は健康だが、すっかり色も落ちてしまって体は細い。捕食器官となった翼は彼女を「人間」から遠くした。
「こう、ならない、はずでしょ」
「――お馬鹿さん」無機質なグウェンドリンに対して、「理想」の彼女はがらがらと笑って見せる。
我が物顔でゴミ場を占領する烏の群れのようだった。響く大笑いに、グウェンドリンも口を紡ぐ。
「なろうがなるまいが、『こうなる予定』だったのよ」
「――黙って」
生半可なことを言う「理想」に元より愛想は持ち合わせていないが、じりりと胸をあぶられたような感覚がしたのだ。一定の周期しか刻まないはずの心臓が脈打って、反射に瞳孔が少し開く。
掲げたのは、――暗い、昏いラムプである。
冥界の奥底の女神をそこに宿して見せた。
「あなたには、きっと、わからない」
「わかってたまるものですか!」
真っ赤な髪の毛を翻した「あるべき姿」は、その羽を広く広く広げた。赤黒く血がにじんだと思いきや、ぼうぼうと火がともっていく。
「燃えて頂戴」
「嫌」
【Queen of the Night】。
強大なフクロウの化身が、冥府の女神より力を授かって――その炎の翼たちと交わった。
火の粉を散らしながら羽を押しやろうとする赤を、黒がみるみる飲み込んでいく。悪食ここに極まれり、黒は火すら喰らっていくのだ!!
「あなたには、わからない、のよ」
まるで、自分に言い聞かせるような語調だったろう。
ラムプを片腕で掲げながら、その暗くも美しいひかりに輪郭を隠される。グウェンドリンは、もはや赤のことなど見ていなかった。見届ける必要などない、どんどん己の羽が「肉」を喰らっていく感覚は絶えずあったのだ。
「――眠って」
健康な肉は、血も滴る新鮮さで。
じゅるじゅると神性めいた炎すらすする強欲の翼は、表情ひとつ変えぬグウェンドリンの何を暗示するだろうか。
●
どれも、余りに覚えがある。
「そうか――」
鎧から発せられるノイズまみれの声に、上村由美子は身を委縮した。
恐怖を感じても仕方があるまい。何せ、彼女も負傷が目立った。いくら邪神から分離できたとは言え、彼女を探す巨体の動きも合わせてジャガーノート・ジャック(AVATAR・f02381)が分析する限りは、体に呪詛をため込みやすい状態と言える。
「"助けてほしかった"か」
遅くなって、すまなかった。
無機質なはずの声に宿るのが、まるで――詫びばかりで、思わず由美子といえば目を丸くしていたのである。ジャックに抱えられてずいぶん遠いところまできた。無人になったビルの屋上に避難させられて、そこに立つディフが海を呼び起こしている。ジャックに傷の具合を分析されながら、適切な処置をするよう彼が他の猟兵に通信で呼びかけるさまを見て、まるで軍人のようだと呆けていたところもある。
あまりにも、何もかもが現実離れしすぎていて。
「いえ、そんな――」どう声をかけていいやらわからない。「私が、」弁明する方法もわからないのだ。
ジャックには、目の前で項垂れている彼女と同じ想いで覚えがある。
「ァ、う」
由美子がうめき声をあげてうずくまるのは、これで何度目であろうか。
体中から血管が浮き出していて、吐き戻すのは吐しゃ物ではなくて、黒い羽毛ばかりであった。
ジャックのモニターにノイズが無数に走る――無理もない。『特濃』の呪詛を体に宿しているのである。あの『邪神』を生んだのは、間違いなく依り代であるこの由美子なのだ。
邪神が苦しむたびに、由美子の体も悲鳴をあげている。冷静にジャックは解析を進めるが――もんどりうつ彼女の体を支えているうちに、サーモグラフィーの異常に気付いた。
「ひどい熱だな」数値にして、40℃。このままこの由美子の体温が上がっていけばいずれ脳細胞が死にはじめていくだろう。冷却ファンをオンにして、手のひらから涼しい風を流してやる。鋼鉄の掌がひやりとしていて、由美子は額にあてがわれるそれに救いを感じた。
信頼を作ろうとしたわけではない。
――ただ、ジャック――いいや、寂――の中には、苦しみに理解がある。
抑圧された獣性。
いけないとわかっていて、己の欲望を我慢していた日々の辛さ。
狂おしい殺意。
届かぬものを握り潰してやりたいと思うのに、それをあきらめきれないもろさ。
愛に飢えた心―――――。
「一つ、言うなら」
『ジャック』に成れたのは、不幸でありながら幸福でもあった。
こうして『獣』であることを隠さなくていいのだ。『獣』として戦うことで、『少年』は『少年のまま』であれる。しかし、この上村由美子はそういうわけにはいかなかった。
彼女は不運だ。不幸を通り越して、世界に愛されなかったといえよう。
呪われし一族に生まれ、その体に生まれつき羽を宿し、孵化する今日この日まで地獄から目をそらしたかったに違いない。誰にも助けてもらえないことを理解して、何度もあきらめたことがあったであろう。
だから、――『これはロールプレイからは少し外れるかもしれない』。
【砂嵐】が、上村由美子とジャックに吹き付ける風を受け入れる。そして、――其の儘邪神に返してやった。打ち消され合った風圧は凪を生む。
ひたりと止んだ風の愛まで、ジャックは教えてやるのだ。吹き荒れる怨嗟に聞き取りづらい声を誤解させないために、ゆっくり、しっかりと噛み締めて。
「自分の一番の理解者は自分自身だ」
ひととしての理性、上村由美子。
のけものの獣性には呑まれてよい存在ではない。この二つは元は一つでも、もう、二人になってしまったのだ。
神の「書き換え」による奇跡で受肉したならば好都合である、ジャックは、立てた右手の人差し指を――「のけもの」に向けた。
「まず自分自身で、自分を助けてやれ」
結局、この「呪詛」というのは心で出来ている。
口から黒い羽根を吐き出し続ける由美子の症状を、解析できたのだ。ジャックは、「互いを冷静に見ろ」と指し示す。
呪われた絆ではない。一つだった卵が二つに割れただけで、二人は「ふたり」ではないか。
その自我が早かったか、それとも遅かったかの問題で、ふたりはふたりに違いないのである。
「警察官だろう」
上村由美子にジャックができるのは、導くことだ。
「デカ魂とやらを見せてくれ」
――その痛みを、その傷を、よくよく知っていたから。
●
たすけてほしい、と人の子がいうものだから。
破壊神であるロキ・バロックヒート(深淵を覗く・f25190)には、よくわからない。
――“ ”はひとを救う側であるが、本来、彼は違う。
「不思議だねぇ」
のらりくらりとした享楽の神であるはずだった。何も考える必要なく、日増しに増えていくいのちを当たり前のように引き算してやればいいだけの悠久が約束されているのもある。
今更、首輪をつけられたこの状態でも悩むことなどほとんどなかったのだ。
ひとの子の中に混ざっていて、笑いあったり時に知を共有することがあっても。
怒りを分け合って痛みを分かち合ってやることがあっても。
悲しみを感じあってお互いを跳ねのける日もあれば、寂しさに付き合った甘くも睦まじい日々を過ごしたところで、神は「何とも思わない」。
“ ”は人の祖である。
――故に、どこまでも人に近くて、ひとよりもうんと遠いのだ。
矛盾だらけの不完全な“ ”は、永遠に自分の尾を探し求める蛇のように考えるのを止めなかった。
なかなかに掴み切れないその尾に見出していたのは、「完全」の文字である。
ひとの子のことを理解できても、その道徳には付き合ってやれない。だからこそ、“ ”らしく、せめてむごたらしくすべてを知り、考えながら高めることに必死であった。
汚泥も、欲も。
悪しきも、外道も。
むごたらしさも、業すらも。
すべてすべて愛おしく呑み込んで、けがれを孕んだ蛇の体で世界を抱きしめるために這って往くことを、――“ ”の振りを続けている。
課せられた役目は今も果たせない。悲哀ばかりを聞き届けて、故に彼は夜の化身と為り得る。
「はは」
いとおしいなあ、と甘い声で“ ”は笑う。
炎に狂っている男がいた。
――いいや、あれもまたロキと存在が近い。
「言うことを、聞きやがれェええええええええええッッッ……!!!!!!」
地獄よりももっと深いところにいる彼の痛みの声だった。火牙彦である。
おやおや、と金色の瞳をロキが細めたのも無理はない。彼もまたよこしまであるように、この火牙彦も「分類的には同義」である。荒っぽい火の粉を肌に感じながら、そっとロキが細長い指をこすりあわせてそのさまを空に揺蕩いながら見ていた。
「判決死刑執行で終わらせる訳にゃあ行かんのですよ、なぁ――コンプラって知ってますッ!?」
燃える炎を制御しようと必死の獄炎が、みるみるうちに空に大穴を開けているのだ。体中に鎖を巻き付け、己の体を縛り上げながら空を作っている。
「やるねぇ」
ロキがのんびりとした語調で、それを見守っていた。
夢をゆめのままで終わらせようとする、「神ではない」誰かを見つけた。ロキが「完璧」を目指すように、「夢は夢でいいのだ」とする道もある。
呪詛がみるみる燃えていって、一体の空気の澱みは薄れていた。さすがに燃やされるのはたまらないと、空気の流れも変わるようであって――次は、海に呑まれている場をロキが見た。
苦しくても、哀しくても、それでも彼女は生きてきたのだと――人形はまるで本を読むように、知っている。
伸ばした指先の指し示す先が、くたりとした「のけもの」を目覚めさせようと必死であった。
「いるよ」
優しい声色は、間違いなく「彼」ではなくて、ディフのもので。
「ここに、居る」
――あなたを知れる人は、世界は、あるのだと。
空っぽの人形が哀色の渦潮で燃やし尽くされそうな民家を美しく洗う。そして、浄化の働きはまさに「水に流す」といっていいだろう。海が過ぎ去るところは、きれいさっぱりに呪詛の痕跡が失せていた。
ディフを止めようとする鎖を、烏の翼が穿っていく。――ロキが目を凝らしてみれば、そこにはグウェンドリンがいた。
「みんな、いる、よ」あなたは一人じゃないんでしょう、と言いたげな烏の小さい声である。
的確にそれぞれに伸びる鎖を穿っていく冷静さは、彼女でしか出し得ない。口笛のひとつでも吹きたくなってしまったが、ロキは――ようやく気まぐれな体を落ち着けた。
「届けてくれるか」と、隣に降り立った彼にジャックが声をかける。
「いいよ」
柔らかく笑うロキが、ジャックに頷いてから――口から黒い羽根を吐き出し続ける上村由美子を見下ろした。
「祈り願え」
“神”が―聴き届けて赦してあげる。
【終幕】が始まる。
呪詛たちが端からきれいさっぱり光に包まれて消えていき、いよいよ黒の王は原型すらあやしい。殆どただのオブジェのようになりつつあるその「芯」は神の寵愛外――「あの男」の情念で出来ているのだ。
由美子が、その輝きを見ていた。
――ロキが微笑んでいるかどうかは、彼の後光で判別ができない。
それでも、ジャックが教えてくれた。ディフが、声をかけてくれた。皆が、――「あなたが悪いわけじゃない」と認めてくれるから。
「いっしょに」
たった一人の「かぞく」が、そこで生まれたのなら。
「いきてみたいの」
――見ないふりをしたあなたを、また隣に宿していいというのなら。
――次は表裏でなくて、隣同士で話をしたい。
揺れ動く邪神の悲鳴で、囚われたままの「のけもの」はゆっくりと目を開いた。
――伸ばされた手に、気づいたように。作られた「居場所」を、見ていた。
悲劇の終わりまで、あともう少し。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 霧島・クロト
霧島・クロト
◎
日明(f28722)と。
――なぁ、全ての命に嫌われてるであろうお前は『どうしたい』?
已むを得ないからその『毒』で殺す?それとも……。
そうだな、俺は『その言葉が聞きたかった』。
なら、お前の揺るがぬ意志で躾けてみせろよ。この狼をさ。
【高速詠唱】から【指定UC】。
今回の俺の拳は特別製だ――
【属性攻撃】【怪力】の乗った手荒い凍拳じゃねぇ。
当たった先からくだらねぇモンを【捕食】する、狼の牙。
……つまりは、『俺』のモンだ。
ああ、ありがとう。態々今の俺を用意してくれて。
理想ってのは――あの臆病な俺の為の『腹の足し』なんだよ。
あの俺が本物の『貪狼』になる為に、
てめぇのいらねぇのは喰わせて貰う。
そして……
 終夜・日明
終夜・日明
◎
クロトさん(f02330)と
蠱毒で常に相手に【恐怖を与える】状態ですので、恐らく僕を排除しようとしてくるハズ。
それを利用して【おびき寄せ】ます。
クロトさん。
――彼女をどうするかは、貴方に委ねます。僕はその間、決して貴方の邪魔をさせぬよう囮役を努めましょう。
僕は、"終わらせる"ことしかできないから。
ええ、"だから"こう言っているんです。
救けたくても僕にはできない――だからお願いします。
【指定UC】を発動、【乱れ撃ち】で牽制をしながら【情報収集】。
【地形の利用】ができそうな箇所を【地形破壊】して【破壊工作】、動きの抑制を試みます。
僕にはもう幻は要りませんよ。
今は肩を並べて戦える仲間がいますから。
●
「――なぁ」
「はい」
霧島・クロト(機巧魔術の凍滅機人・f02330)は、貪欲でありながらわきまえのある狼のようであった。
人の社会の道理のことはよく理解しているつもりである。
あの胸の中で目覚めた「のけもの」が無事に生まれてきたとして、はたしてどれくらいもつだろうか? 人の社会のことを知らぬ獣が、人になるにはずいぶん時間がかかるはずだ。
狼に育てられた子供たち、という創作めいた話を聞いたことがある。心優しい牧師に育てられた野生児たちは、確かに社会を知っていきながら終わりは別々に――そして、早くに亡くなった。今ではその信ぴょう性も疑われ、創作ではないかと裏付けられない奇跡を事実でねじ伏せる流れがある。
それと、きっと似た道をたどるだろうなと思ったのは、一種のアイロニカルでもあるが、どちらかといえば「客観的」な評価だ。
「全ての命に嫌われてるであろうお前は『どうしたい』?」
故に、主観で問うた。
猟兵たちが「主観」に基づき彼女らに納得する未来を与えようと戦っているのを、見て、彼に意見を仰ぐ。
「――彼女をどうするかは、貴方に委ねます。」
はっきりとした語調で、終夜・日明(終わりの夜明けの先導者・f28722)は告げる。
「いいのか? 已むを得ないからその『毒』で殺す――なんて言うかと思ったが」
「少し考えました。ですが、今の状況では我々に効率が悪いので」
日明は、元より自分の感情を殺す天才である。
衝動的になりやすい自分を御しながら、あくまで、ずっと「冷静」に物事を考えるのだ。
「僕はその間、決して貴方の邪魔をさせぬよう囮役を努めましょう。僕は、"終わらせる"ことしかできないから」
「――ハ、そうかい」
それは、事実の羅列だ。
彼の命すら殺す『蟲毒』は、日明の未来すら削ってしまう。故に、未来に対する見解というのは、日明からは少し縁の遠いものであった。
社会的に見れば「彼女ら」は無事に生きていくことはできないだろう。
むしろ、「急に存在が発覚した」双子の片割れを得てしまったようなものだ。上村由美子は、きっと職場に戻ることもできないし、職もない。ずっと口から呪われる羽を吐き続けて、ようやくできた「家族」とともに――それこそ、日明と同じで、その体かかり続ける負荷はこのままでははかり知れない。きっと、十年だって生きることは難しいだろう。
「救けたくても僕にはできない――だからお願いします」
下手な希望を持たせるよりは、とも思える。
それでも、彼女たちがわずかにでも家族のぬくもりを取り戻せるのならば、どちらがいいだろうかと考えて日明はここで、『主観的』な判断に出た。
「救援要請を受理。これより、ミッションを開始します」
「了解、さァ――ついてこい。お前の揺るがぬ意志で躾けてみせろよ。この狼をさ!」
意識を得たのけものが、言葉にもならない悲鳴をあげている。
劈くような叫びも無理はない。赤ん坊の癇癪のようなものだ――ノイズをかき消すように日明が遮蔽物に身を隠していた。団地の空き家である。
普段はここに生活保護が必要になる人間が住まうのだと言っていたが、人間の数はずいぶん減ったらしく、過疎化が進むこの地域では空き家が目立つ。ベッドタウンに選ぶならば確かに「ここでは」貧困層も過ごしにくかろうと、日明は思った。
とまれ、身をひそめるところがあって好かったと思う――日明に立ちふさがるのは、彼の『蟲毒』であった。
今、日明が身をひそめる家屋に歩みを進める獰猛な顔をした日明がいる。「屈服した姿」といえよう。理性で己を縛るのをやめて、ただ闇雲に暴れようとする姿だ。
どすどすと足音を立てて玄関を蹴破り、さらに足を進めてくる。そこを、――半身を見せて、【【制限解除】疾風怒濤】を撃ち込む!!!
ばぢぢぢぢ、ちゅい――と鳥の鳴くような音を立てさせてから日明は駆けだした。彼が身を潜めていた柱を腐らせるほどの毒を纏った拳が飛び込んできたのだ!!
計算通りである――雷すらもどろりと溶かして見せる衝動の権化は確かに凶悪であったが、「夢中」なのだ。
追いかけようと一歩踏み込めば、そのきゃしゃな体が爆発とともに吹き飛ぶ。
何が起きたのかわからない、と言いたげな横顔が、次の壁に体を隠していた日明の隣を過ぎていった。
「僕にはもう、幻は要りませんよ」
したたかに壁に背を打ち付けるかの姿に、容赦なく電流を浴びせかけてやる。受け身すらとることもできなければ、脳に流れる電流すら打ち消す隙も与えない。電圧で黒焦げになった衝動にようやく息を長く吐いてから、――日明は次に、手にまとった電流を逃げた家屋のブレーカーに掲げる。
「お願いします」
ぶつ、と街から――光が消えた。
「あァ――くだンねえなあ」
穿った。
殴りつけ、壊し、割り、そしてまた砕いた。
恐怖心の己に魅せつけてやるように、獲物をいたぶってその肉を割った。
【氷戒龍装『氷龍呑みし貪狼』】はもはや撃ち合う己同士の拳すらも「喰らう」ほどの獣ぶりを見せつける。電気の消えた町ゆえに、クロトのこの苛烈さは誰も見るまい――状況把握のために日明が見ている程度だ。彼に今更、この凶暴さを隠すことはないとも。
「『腹の足し】になるだけだァな、こういうのは――さァ!!!」
踏み込みとともに打ち付けた拳で、何体目になるクロトが凍り付いた。
ダメ押しの肘鉄でそれが粉々に砕け散る。いつもの乱暴な喧嘩殺法ではなく、ただただ獲物を喰い殺すための狩りの手法であった。
本物の『貪狼』にはならないとも。
日明に「しつけてみろ」とは宣ったが、クロト自身は――『賢狼』といえる。
人の道理によくなじみ、その世間を知り、故に戦う理由を思う存分機械の体に乗せられるのだ。
「暴れたりねェ――」
悲鳴を上げる赤ん坊の声の意味もよくわかっているとも。
目覚めたばかりの世界は戦いの場で、ここに己の居場所があると聞いても怖かろう。パニック状態で口からやはり黒い羽根を吐き散らしていた。――そんなにもがいては、呪詛の浸食も早まるだろうとクロトが溜息をつく。
「なァ、ッと!!!!!!!」
六花の壁が出来上がる。
巨大な氷にはりつけられるように、邪神は固定された。どろどろに溶けている体を光を失った世界で、どうなっているのかもよくわからずにもがこうとしている。
「これで、だァいぶ砕きやすくなったんじゃねえか? なァ」
「ええ――効率的です」やはり、どこからともなく――ノイズが混じるのは呪詛のせいであろうが、電波に乗った日明の声が聞こえた。
「だろ」
は、と鼻を鳴らしてクロトが腕を組む。
「もうちょッとだけおとなしくしてな。『賢く生きる』のが長生きの秘訣だぜ」
「のけもの」に声をかけてやって。狼は、群れに帰っていく。誰からも嫌われる毒の少年とともに、――明日への道を切り開いた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ロニ・グィー
ロニ・グィー
◎
ドーンッ!
それドーンッ!
あはははははっ!
やったなー!次はこうだーっ!
その度小さくは砲弾のよう、大きくは小天体のような球体をぶつけあう
決着は……このままじゃ着きそうにないなあ
…あれっ?そもそもなんでボクたち同士で戦ってるんだっけ?
いやコピーって戦うものじゃない?
えーそおかな?
そういえばそもそもボクたちってどっちが本物だっけ?
あれっ?
よしそこはほら一時休戦!彼女を助けよう
どうやって?
そこは、ほら!いつものだよ!
ああいつもの!
勘【第六感】に任せてUCでドーンッ!をダブルで
生きてるね、えらいよ!
助けてって言えたね、えらいよ!
えらい!
えらい!
人って生きて、寝て、起きるだけでえらいんだ
そこ大事だからね!
 サリア・カーティス
サリア・カーティス
【真の姿発動:下半身が犬の半身なスキュラのような姿】
彼女の境遇には、私も思うところがありますの。私も家庭環境……というか父親が良くなかったみたいですから。
でも、傷の舐め合いをする気はありませんの。
「解決する」と約束しましたし。
私はそちらを……邪神の討伐を優先しますわ(人嫌いではないが人の命は犬より軽視しがちな女であった
幸せな幻覚……
映るのは私の「家族」が生きていたあの過去か、死ななかったもしもか。
何度も過去を突きつけられて、それがもう有り得ないとわかっている私が、引っかかるわけないじゃなぁい?
【人狼咆哮】ではばたきごとかき消すわあ!
そのまま下半身の犬たちと【蹂躙】するわよぉ。
 シャト・フランチェスカ
シャト・フランチェスカ
表情豊かな僕だ
誰にも後ろめたさを覚えず
道楽として物語を綴る
人生を謳歌している満開の桜だ
嘘をつくな
きみへのルールはそれだけ
僕がそんなふうに笑うわけないだろ?
【彼女の後悔が膿んだ残滓
桜の樹の呪縛が産んだ紛い物】
血潮の色した愛の手紙は届いたかい
きみは僕と同じ【業】を遣うみたいだけれど
根底に昏い気持ちがないのなら
僕は文章を書かないし
戦うこともなければ
そもそも存在すら出来るかどうか
矛盾の塊が綴る駄文
ああ、つまらない
僕と同じ形をしているくせに
幸せそうに振舞うなよ
嫉妬の熱量が筆を走らせるってこと
どうせきみは知らないだろう
ただ、在るだけで
きみは丸ごと嘘をついてる
自壊する?自害する?
最期まで視ていてあげるから
●
「ドーンッ!!!」
「それ、ドーン!!」
きゃらきゃら、からから。
まるで子供同士の戯れのように、ロニ・グィー(神のバーバリアン・f19016)は暴威の象徴と殴り合っている。
砲弾のような大きさの球体がぶつかりあうたびに細いからだと幼い手足がくるくると宙を舞って、思いっきり力を使う全身の心地よさと、相手から与えられる反応がおもしろくてたまらない。
神であるゆえに、――その様相はまさに、メチャクチャだと言っていいだろう。
「やったなぁー!」
「次はこうだーっ!!」
呪詛を吹き飛ばすほどの剛力がまた、ぶつかりあう。
破壊の化身として猛烈な暴風を伴いながら、ロニたちは小天体のような大きさをした鉄球でぶつかりあっていた。
衝撃波を産めば当然、家屋の瓦が吹き飛んでいく。
風圧が色んな窓を無茶苦茶に割り、コンクリートの地面を陥没させ、木の葉は毟られまいあがるばかりだ。
「きゃはははははははッ」
神である彼らにとって、人の文明など些細なことである。
壊せば壊すほど、人が文明を「よりよく」するのは感覚で理解しているのだ。
ロニといえば享楽を愛する暴威であった。
歌や芸能、芸術、その時代に即したトレンドをよく知恵とし、砲や火薬での争いをひどく嫌う。
寛容どころかいいかげんな采配を持つのはまさに神らしいといっていいだろう。
すべてを救わないが、目にしたものは確かに「どれもこれも愛してはいる」。しかし、彼の基準は畜生と同列であるのをきっと――誰もが理解できなかったことであろう。
爆発音のような重なり合いは、ロニにとって快感である。
全力で体を動かすことの心地よさは、彼の暴力に対抗できる「彼」がいるから行えることだった。
もし、ロニが本気を出して人間に指先一つで触れようものなら、水風船のように割れてしまうかもしれない。それはとても「呆気なくも愉しい」時間であろうが、やはり「長続きする楽しさ」の前には勝てないのだ。
「――あれ」
ぶつかりあう砲弾、その次を生成しようとしたところで風はぴたりと止まる。
「そもそもなんでボクたち同士で戦ってるんだっけ?」
はたりと正気に戻ったような口ぶりに、ほとんど変わらない姿をしたロニが首をかしげる。無防備になった向かいの姿に鉄球を叩き込んでやる気にならなかったのは、単純に「それでは面白くない」からだ。
「んー?」
考えるそぶりをしながら、人差し指で顎をおさえる。
楽しいことに夢中になってばかりで、先ほどよりも呼吸が断然しやすいこの状況に覚えがない。
仲間、――そうだ、猟兵たちが何やらを叫んだり、魔術を紡いだりしているのはかすかに聞いた覚えもあるが、風圧に混ぜてすっかり遥か彼方のものとしてしまっていた。
ロニは、救う神でない。
万物を壊すことに長けており、それを愛しているかどうかは彼自身の理由の話だ。
なんのためにこの場に来たのかすらも思い出せないが、愉快に合わせて空を飛べば、遥かかなたまでたどり着いてしまったようである。
「いや、ちょっと待って。コピーって戦うものじゃない?」じゃらり、鎖が戸惑う。
「えーそおかな?」ぐらり、鉄球が揺れる。
「見たことないの? そういう映画いっぱいあるじゃん!」ぱたぱた、両足が空を掻く。
「泣けるやつね!あるある」ぽんぽん、と両手は重なり合った。
「いやあるんじゃん!」けらけら、腹を押さえて笑う。
「あれはモンスター同士の戦いだったし」ふわふわ、愛らしい顔を作るのも忘れない。
「まあ確かにボクたちは神だもんねぇ」うんうん、優しくうなずいて。
「そういえばそもそもボクたちってどっちが本物だっけ?」
――それからようやく、地上を見た。
「「――あれっ?」」
●
「のけもの」の境遇には、思うところもある。
――サリア・カーティス(過去を纏い狂う・f02638)といえば、おおよそ「人間だった」とは思い難い感性の女だ。
その両足を縛るように、――どこにも行くなと言いたげな鎖が組まれていて、思わずサリアは呆れた顔をした。
「サリア」
両親が、目の前にいる。
この場に居るはずのない存在達を相手に、まるで「そうありなさい」と決めつけられるような幸福が不快であった。
「せめて、イヌがたくさんいて、皆が尻尾を振っているとか――そういうのだったら靡いたかもしれませんのに」
田舎町の風景にぽつんと、母はともかく父はともにきたがらないに決まっている。
サリアの父は、厳格であり、支配的であった。
子の幸せを己の価値基準でしか測れない彼だったのである。サリアも、その理屈はわからないでない。歳も歳ゆえに――それが彼という「人間」の考えることだったのだろう。
「生憎ですが」
サリアは、ひとだった。
間違いなく美しい女として生まれ、不幸にも人狼病に感染してしまった。
彼女を守る為であり、己らを護る為にも父は彼女を閉じ込めてしまう。
それは確かに「許容できなかった」という彼の脆さであり、親になり切れなかった部分でもあろう。もしかすると、父親としてできることが其れしか思い浮かばなかったのかもしれないのだ。
しかし、当時のサリアからすれば――あまりにもむごい仕打ちに感じられた。
好きで病になったわけではない。
どうせならば、「俺が代わりになってやれたら」と手を握って泣いてくれるほうがまだ救われただろう。何日も過ごすうちに、寂しさは変質していく。
孤独に震える我が子に、金があるままに物を与えるばかりでまるで人として扱ってくれないのだ。
――私の手に負えない。
――あれは、もうどうしようもない。
どこの世界に、子供を「あれ」と呼ぶ親がいるのか。
なぜ子供を諦めてしまうのか。どうして、死にゆく子供に向き合って死ぬまで泣いてくれないのか。
「私は、あなたたちの家族ではありませんので」
それは、サリアが――――「イヌ」だったからだと、知らずのうちに自分の中で定義した。
間違っているとは、今も思わない。
だって、親と子とはそういう成り立ちを歩むはずではないからだ。金を与え、欲しいものを欲しいがままに与えるばかりで、寂しさから感じる心細さをあたためてくれるのはいつだってサリアの「イヌ」ばかりだった。
だから、――幸せの象徴が両親だったことには、酷く腹を立てる。
凶悪な顔で笑ってやった。がるがるとおおよそ少女のものとは言い難い怒りの喉を震わせ、真っ赤な歯茎を見せつけるように口角を持ち上げれば、狼らしい顔になる。
それは、「人間だった」場合の幸せではないか!!
【人狼咆哮】。
があ、っと大きく口を開けば、ァゥウウウウウウウ――――――――……ンンンン……と一匹の黒毛の四つ足になり果てる。
すると、鎖で縛られた足に群れが集うのだ。なんだなんだ、どうしたどうした、と言いたげな彼らが、「常識」で縛られるサリアの「あたりまえな幸福」を噛み砕いていく。
なんだこれは、――こんなものがあっていいはずがない、かわいそうに!
ばきばきと砕けていく鎖には、獣たちの怒りと慈愛があった。そのまままるで、サリアの脚の代わりになろうと彼らが同化する。
さながら、――イヌでできたチャリオットだ。
車いすなどよりよほど凶悪なそれを手に入れたサリアが、慄く「あたりまえ」の姿に唸る。
「ねえ、何度も私が引っかかるわけないじゃなぁい?」
そんな幸せは、サリアの幸せではなかったのだから。
●
表情豊かな、己が居た。
やわらかく笑い、何かを諦めたようなそぶりもない。
筆を執る手にはたしかにペンだこが見えるのに、特に掌がインクで汚れたような痕跡もなかった。
やわらかく笑う「それ」に、――シャト・フランチェスカ(侘桜のハイパーグラフィア・f24181)は濁った瞳で睨む。
口元だけは同じ形で笑っているが、宿した重さが違うのだ。
「なんだよ、それ」
「そっちこそ。書くのは楽しくないのかな」
――いちいち、癪に障る。
まるで新しく敷いた原稿用紙に、呑みかけの緑茶をぶちまけてしまったような不快をふつふつ胸の内で煮立たせる感覚があった。
シャトは、――昏い気持ちで文章を書いている。
それは、シャトにとって懺悔ともいえる行為に近いのだ。
シャトは、「シャトでない」が、シャトとしての証拠を残すために文字を綴る。「シャトでない」シャトの足跡を繰る為に、己という筆跡をダイイングメッセージとして自己表現に使うのだ。
とてもいびつな創作活動である。彼にとって、筆を執るというのは拷問に近いのだ。
文豪ならば文句があるというのなら、まずお互いの【創作】で語り合うべきである。
ゆえに、――それに則って、シャトたちはお互いの【業】を見せあうことに成った。
筆跡を辿る。展開される筆跡を読み込んでいけば、たしかにこのシャトもルーツは同じだ。しかし、読んでいてどんどん織りなす「陳腐さ」に笑みも引きつらせてしまう。
「何だいこれ、ひどいよ」
それを言いたいのは、こっちのセリフであった。
二流どころか、三流通り越して、ほぼ四流といってよい文字の羅列を垣間見る。
確かに同じ姿で文字を武器にするのに、此処まで大きく異なるのである。ぶつけ合った【Abyssus Abyssum InvoCAT】の誓約通りに、ふたつは互いに嘘をつかない。
「キミのは、とってもジメジメしているよ。病んでるようだ」
――紛い物のシャトが書いた紙飛行機の中身は、あまりにも自閉的である。
好きな言葉を並べた散文といえようか。確かに紛い物の中では何かが完成しているらしいのに、連ねられたお題目通りのはずの愛の言葉はあまりにも自分勝手である。
今すぐにでも丸めて捨てたくなるのに、それができないでいたのは、――その「道楽」という感性がシャトにはないからだ。
案の定、不思議そうに首をかしげる「紛い物」はシャトの言葉を読み上げてしまう。
「【彼女の後悔が膿んだ残滓、桜の樹の呪縛が産んだ紛い物】」
くすくすと笑われる焦燥が、耳たぶを焼いた気がする。
「ポエティックだね」
――ぶるぶると、シャトの手が震えた。
「詩的、だって――?」
思いを連ねる文章が詩的でなくてどうしろというのだ。
シャトが開いた紙飛行機の中は、びっちりと「理論」が書かれていて気分が悪い。
どうして「ボク」が「キミ」を想うのかを異常な文字数でこれでもかと書いた論文は、見るに堪えない。読み進めるだけで自分が暴かれるような心地と、愚弄と、踏みにじられた自尊心を感じてしまうのだ。
「曖昧だから、曖昧なことばかり君は書くけれど。これでは何を言いたいのかが伝わらないね」
――もっともっと現実的な言葉を使って御覧よ、だなんて興の削ぐようなことをいうものだから。
シャトは、この「紛い物」が確かに虚であることを理解する。
「幸せそうに振る舞うなよ」
「幸せだからね。なぜいけない? キミに卑屈になるなと言えばいい?」
「――どうせきみは」
知らないだろう。
嫉妬に狂いそうな頭を掻きむしってしまいたくなる。シャトの胸にぎしぎしと桜の枝が刺さったような感覚が抜けない。
「嘘をつくな」
子供の喧嘩のようだったろうか。
「――きみは丸ごと、『嘘』だ」
そうあれたら、きっと未練がましく文章を書くこともなく、今頃あたたかな屋敷やらで珈琲でもすすりながら、「シャト・フランチェスカ」を名乗ることなく執筆を楽しんでいたのだろう。
矛盾の塊が狂おしいほど羨ましくて、どうしようもなく、「こんな話はつまらない」。
突きつけた「矛盾」は作用する。約束を破った――解離したシャトに、天罰が下った。
想いの乗せられた紙飛行機に、はたたと赤い花弁が散る。
●
そうだそうだ、彼女を援けるんだった――とロニたちが一時休戦をしたころには、邪神の胸から人間が生まれていた。
「わあ!人だ、人だ」
「そっくりさんだ!ボクたちみたいだね!」
なんて笑いあって、いつも通りに力技を何度も邪神にぶつけあう。
甲高い悲鳴とも付かぬ音波が二人の神を押し上げようとも、「せえの」の後にやってくる鉄球は、激励とともに物ともしない!
「生きてるね、えらいよ!」
「助けてって言えたね、えらいよ!」
「えらい!」
「えらい!」
「人って生きて、寝て、起きるだけでえらいんだ」
「そこ大事だからね!――忘れちゃ損だよ!」
ぶん、ぶん、ぶん。
デンプシーといっていいだろう。何度も邪神の腹に食らわされる鉄球で、「のけもの」はぐらぐらと頭をゆすられていた。どうなっているのか理解が追い付かない彼女が、邪神から抜け出そうと精一杯あがいている。
「あれれ」
「抜けないの?」ロニが二人で腕を組んでいる間に――戦車が果敢に走ってきた。
地鳴りをさせながら無数の犬が土台となって、彼女の道を作り出す。どどどどう、と砂煙を上げながら山を駆け上がり、散らばる羽根を拾い食い、その味を覚えた牙たちがどんどん「根源」である躰に噛みついてく!
「上から抜けないのなら、下から切り崩せばいいのではなくって?」
「すごぉい!」
「あったまいい!」
サリアが獰猛な顔つきで犬たちに貪らせるのを、ロニが手を叩いて歓喜する――。
まさに、そこは地獄そのものを作っていたといえよう。
食いちぎられて逃げようともがき苦しむ巨体が、まるで氷のように溶けていくのがシャトの場から見えていた。
何もない、がらんどうの日本家屋の庭でそれを眺めている。
――足元には、誰のものやらわからぬ桜が散っていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 杜鬼・クロウ
杜鬼・クロウ
【義煉】◎
俺の答えは揺らがねェ
総て守り抜く
俺の力はその為にこそ在る
理想の源次見て一言
今のお前でなければ
俺達は出逢ってねェンだ
だから
謝るな
敵の幸福に囚われる
愛慾を抱いた桜鬼の姫君と結ばれる夢
一緒に堕ちて尚、永遠の時を過ごす
でも違うンだ
俺の居場所は
あァ、人の器を得た理由が
果たすべき使命が
そうでなければ
結末は違ってたのかなァ
愛しく思えば思う程乖離する
自ら望んだ悔い無き途とはいえ
結局何一つ掴めず手離してばかりだ
常春桜を抱き締め突放す
変わるいろ
溺れるおもいを焔で一掃
お前、その姿
…そうだな
軽く目擦り迷いを断つ
源次を追い核を掬う
のけものは、いねェ
上村由美子の命を救えたらUDC組織へ渡す
心のケアには時間が必要
 叢雲・源次
叢雲・源次
【義煉】◎
(相対する。自分が心の何処かで理想としていた自分に。未練と言ってもいいかもしれない。その姿は今よりよほど人間らしく、今よりよほど真っ当に生きて来たであろう邪神とは関わらなかった在り得たかもしれない自分だ)
「すまんな…俺はお前には成れなかった」
(唯の一刀、斬り捨てる)
上村由美子、おそらく俺にお前の精神は救えないだろう
だが精神を蝕んでいたモノは殺す事が出来る。救う救われぬはそれからだ。
「炎獄機関…制御コード解放…対神義装、変換完了…対神兵装、抜刀」
「折れかかっている暇はないぞ親友、神殺しの時だ」
(真の姿を開放し、蒼炎荒ぶる対神太刀を抜き先んじて駆ける。神殺しの太刀に蒼炎が宿り振るわれる)
 鳴宮・匡
鳴宮・匡
痛い、苦しいって叫ぶ自分を
切り捨てて、なかったことにして
見ないふりをして“今”ばかり考えてた
――同じ、だと思った
だからだろうか
手を差し伸べて、名前を呼んでやりたいと
そう、思ってしまうのは
今更そんなことは許されない、諦めてしまえって
“空っぽだった自分”の幻覚が目の前で告げる
ああ、わかってる
散々、伸ばせたはずの手を伸ばさずに
何もかも切り捨てて生きてきて、今更だ
――それでも、もう
この胸の裡に在るものを、なかったことにしないと決めたから
真の姿を開放
幻覚を払って、前を見据え
青を帯びた瞳で捉えた因果
――上村と邪神の“繋がり”を断ち切る
――帰ってきなよ、上村由美子
あんたは大丈夫だ
もう、“ここ”にいるんだから
 桜雨・カイ
桜雨・カイ
浅ましいと思いつつ願うのは弥彦たちのいる風景。
きっと被害者の周りの風景もそうだったはず
…そして世一と同じように、殺された。
多くの奪われた命と、大事な人を失った悲しみを無くす事はできない
それでも…
「ごめんなさい」
幸せな幻から手を放し現実へ帰る
それでも…ひとりで泣いている彼女を放ってはおけないんです
【援の腕】発動
問いは『今までつらかったでしょう?』
浄化するのは触媒の黒い羽根。黒の王との繋がりを断ち切る為に
泣いている身を抱きしめて浄化
もう一つ
安心させるようになでてやります
噛みつきも呪詛も、技能を使って耐える
もう試す必要はないですよ、
何を言ってもいいんですよ
今までつらかったでしょう?
助けに、きましたよ
 スキアファール・イリャルギ
スキアファール・イリャルギ
◎△
躰がぐちゃぐちゃにされる痛み
……嗚呼、また"人間"を否定される
心を挫かれ、壊され、怪奇であることを強要される
――それでも、だ
呪いと苦痛で雁字搦めになったあなたを見捨てるなんて出来ない
……私に似ている気がしたから
攻撃や救助は任せ【Yaka】で一時的に無力化しましょう
この身を襲う苦痛を
猟兵たちを襲う幻覚を
あなたに纏わりつく悍ましい呪詛を
私が私で居られるギリギリの時間まで
……こんな私でも居るんです
私が生きる希望を持てなくても
周囲が人間として認めてくれなくとも
生きてほしいと願い、死ねない理由を作ってくれる人たちが
それは、あなた"たち"にも――
だから生きていてほしいんです
のけものになんてさせない
 夕凪・悠那
夕凪・悠那
◎
事件がなく、私も彼も普通の友達として―ああ、或いはそれ以上かもしれないけれど
なんて
ソレ
幻覚はもう何度か見てるんだ
残念だったね黒の王
お前が教えてくれたんだ
そして、自覚したならこんなことだってできる
正直あまり使いたい手段じゃないんだけど
自分にハッキング
一時的に離人を深化する
敵意とか、親愛とか
"イベント"に感情移入することはあっても目標が定められてたら攻略を躊躇うゲーマーはいないんだよ
目標:「黒の王」の討伐
EX:「上村由美子」の救出
―ミッション、スタートだ
【Take Over】オンライン
上村さんと邪神を接続している基盤のシステムを掌握、切断を試みる(ハッキング+略奪)
好きにはさせない
返してもらうよ
●
あさましいとは理解していて、それでも願ってしまうものがあるのも解っていた。
自分のせいで失わせたものがたくさんある。桜雨・カイ(人形を操る人形・f05712)は、それを望んではいけないのも充分理解していた。
だから、目の前に現れる幻影に――違和感がない。
そういうものだろう、自分が見るのならという納得もある。
弥彦がいる。己を作った主が、家族に囲まれてカイがこちらにやってくるのを待っているのだ。――自律して歩くようになった人形を誇らしげに眺めてくれる主の瞳がやさしすぎて、都合のいい考えにぎりぎりと関節が緊張で軋む。
あり得ないのだ。
こんなことは、もうあり得ない。
主の子は世一という。世一は、その母は――殺されたのをカイも見ていた。
あんな光景を二度と忘れてなるものかと何度思ったやらわからない。今でも瞼を閉じれば、残酷な風景が焼き付いてしょうがないのに、目の前の幸せにはすがりたくなってしまう。
ああ、きっと。
「ごめんなさい」
彼女らも、この気持ちだったのだろう。
「放っておけないんです」
カイを縛る親愛の鎖を前に、人形は腹の底からようやく絞り出した声とともに、深く深く頭を下げた。
主人に対する無礼である。以前までのカイなら、幻惑に立ち向かうことは出来なかったかもしれない。それでも、今は――心に灯った小さな炎がある限りは、桜雨・カイという人形の人格を失うわけにいかない。
「弥彦、どうか」
ぎゅうっと瞼を閉じた人形は、おそるおそる地面を見る。
親愛で繋がれた感覚は断ち切られていないが、そのまま顔をゆっくり上げた。つま先から――家族を見る。
「ひとりで、泣いている子がいるから」
――――、立派だな。
残酷な理想だった。
カイが、言ってほしかった言葉をあたりまえのようにつぶやいて、笑顔をにじませる彼の顔がたまらなくまぶしい。
きゅ、と唇を縛って人のガワで頷く。人形は、確かに人のために在りたいと思ったのだ。
絡繰りで操られ、人々を喜ばせる性根である。
笑ってくれない子供が居れば笑わせてやりたいし、どこにも行く場所がないのだという人の子にはともに居場所を探してやりたい。
救われない未来があっていいはずがない――泣けない子供には、泣いていいのだと泣き終わるまで抱きしめてやりたいのが、「人のため」である彼の気持であった。
消えゆく幸福の理想に、眉を寄せてかみしめる。
いつか、こころより、「そうでしょう」と応えられる日を考えていた。
●
自分の理想と相対した。
――あり得たかもしれない身近さを感じさせられるからであろう。
叢雲・源次(DEAD SET・f14403)の前に現れたのは、「人間」の源次である。
源次も何度か「人」でありながら剣鬼の才を持つ猟兵とは相対してきた。彼らを見るたびに、思わされるのである。「そうだった自分もいたかもしれない」――と、マイナス値のパーセンテージというイフを考えることもあった。
今よりよほど、人間らしく生きているらしい。
血色の良い顔と、瞳には光が宿っている。源次のサイバーアイの輝きとは大きく異なるそれに、瞬きの必要がない源次が魅入っていた。
「今のお前でなければ、俺達は出逢ってねェンだ」
隣に杜鬼・クロウ(風雲児・f04599)が居なければ、今頃真っ二つだったやもしれぬ。
人間のほうがずっとサイボーグの源次よりも脆いのだ。だから、目の前の「イフ」は警戒度を最大に引き上げて冷静な顔を作り、臆病な本性を隠しているようである。バイタルから見ても明らかな数値の異常は敵から感じられるものなのに、すっかり源次は――斬られるだけの存在になりそうであった。
一瞬の虚を見逃すはずがあるまい。「ひと」の源次が踏み込んで勢いよく刀を抜くのは、しっかりと解析できていた。確かに神速といってよい――どころか、常人のそれよりも遥かに速い!!
だが、「パターン」もやはり「源次通り」なのだ。
振りぬかれた刀の軌道は、解析通りの筋を通る。避けられる剣戟の間を縫うように、ねじ込まれる悔悟の刀筋は――的確に、「ひと」を殺した。
「すまん」
血をまき散らしながら頽れていく感覚が邪神よりはるか遠くて、こうなるべきだったのは己ではないかと思わされてしまう。源次が、ゆっくり目を細め鋼を鞘におさめる。
「謝るな」
クロウも、源次がそうなってしまう理論はわかる。
「あり得たかもしれない」ものがクロウにも見えているのだ。
クロウを襲ったのは幸福な幻覚である。ぞわりと身の毛よだつ多幸感が体を襲った。芯から温められて暴れたくなってしまうのも無理はない、――源次が魅入るように、クロウもまたその幻覚に煽られているのだ。
愛慾を抱いた桜鬼の姫君が、目の前でクロウに求められている。
これは、確かに「堕ちた」幸福であろう。
お互いにつとめなど忘れて、馨しきひと時に汗も涙もすべて注いで一心不乱に愛し合う姿は、確かに「結ばれている」のだ。
抱きしめれば抱きしめ返し、求めるままに応じてもらえる己は酷く幼い顔で喜んでいるではないか。まるで自分の神域などどうでもいいのだと衣服とともに捨て去ってしまったかのような脳まで幸福に漬けられただらしのない顔に、――もう、「これは無い」のだと思い知らされる。
人の姿を得た理由が、使命がなければ、こうなっていたかもしれない。
愛しく思えば思うほど届かなくなってしまう。
自ら望んだ捨てた道だ。何一つ掴めなくてもよかったと思いたいのに、どうにも口惜しい。
こちらに気づいた愛欲のそれが、美しい顔で馨しい雌の香りをさせながら、招くように五指をうごめかせている。
おいで、おいで、と笑ってくれる。
――堕落への道だと知っているから、困ったようにクロウは笑ってしまうのだ。
歩いていく。寄って、そっと抱き寄せる。
「俺の答えは揺らがねェ」
その体を抱く両腕が震えている。幸せに歪む鏡写しの自分が憎らしくて、たまらなくて、情けなくなって――。
「総て守り抜く――だから」
すべて、燃えた。
叫び声すら上げることなく、瞬く間に花弁を燃やす様に。すべてを一瞬で灰に変えて、項垂れた。
「済まん」
何もかもを燃やせる権能がある限り、クロウはたった一つを愛せばすべてを捨てることに成る。
両手をぐっと握りこんで泣きそうな顔を、ぎりぎりと下唇を噛むことでせき止める親友の姿が痛ましい。それでも、蒼の炎は目をそらすことなく見届けた。
「折れかかっている暇はないぞ親友」
親友であるクロウの性分はよく分かっている。
博愛であらねばならぬ立場である彼が、たった一人を想う重さも理解は出来なくても、どういうことかは知っていた。だから、源次はその姿を「情けない」とは思わない。
戦ったのだ。クロウは、自分と戦った――。
「神殺しの時だ」
「ああ」
――炎獄機関――制御コード解放。
――対神義装、変換完了。
――……対神兵装、抜刀___ |
【炎獄煉装】を纏った源次は、親友の前に手を差し伸べる。
「そうだな」
だから、クロウは握れるのだ。挫けそうになっても、立ち上がることができる。正しい道を邪道で大回りしても、必ず示す相棒がいる限りこの男の炎は潰えることがない。
「UDC機関と連携をとるぜ」ず、と鼻を一度啜ってから、目をこすれば手袋にラメが残る。「――届けてくれるか、源次。メッセージをよ」相棒が崩れたメイクでいつもの笑みを浮かべたのなら、煉獄の男は頷きで返すのみであった。
●
体が、ぐちゃぐちゃに切り刻まれるような痛みがする。
スキアファール・イリャルギ(抹月批風・f23882)と鳴宮・匡(凪の海・f01612)が彼女らに感じた気持ちは同義であった。
突風に体を押されながらも、匡がぎらりと青い瞳を輝かせて前に進む。人の躰である彼ならばたまらず吹っ飛んでいるはずなのに、今は確かに脚が前に、前にと進みたがっていた。
――同じだと、思った。
お前と同じなんかにしてやるなと、誰よりも聞いた自分の声が反響しては過ぎ去っていく。
邪神の足掻きに等しいだろう削れた大羽の羽ばたきは強い台風よりも激しいのだ。――諦めてしまえば、匡はきっと楽に飛ばされる。
今更そんなことをするなよ、と服の裾を掴まれているような気がする。それでも、振り向かなかった。鍛えた両腕を壁にして、呼吸のできる隙間を作りながら低い姿勢で歩みを進めていく。
――どうしてそこまでするんだよ、俺は弱いんだ。無駄だよ。ぜんぶ、意味がないんだ。
「わかってるよ」
今更だ。
匡が、自分の武器であるうちの体内器官である耳を風圧に嬲られながらつぶやいた。きっと、隣で邪神に向かっていくスキアファールにも彼の声は聞こえていないだろう。
散々、伸ばせたはずの手を伸ばさずに見てきた。
助けられる命を見殺しにしたこともある。
ここで匡が見逃せば、きっと明るい未来があった命がたくさんあった。
仕事通りに果たさなければ、後悔しない犠牲が山ほどあった。
それでも、それをすべて見ないことにしてきて、――ただただ毎日を無心に生きて、無味無臭の日めくりを続けてきたのに、ここ数年で取り戻そうとしている自分の都合のよさはよくよく分かっているとも。
だから、目の前の「あれ」が――まるで自分のようだからといって、援けたいと思うことの都合のよさだって、よくよくわかっている。
「でも」
そうしたい、と思った。
痛い、苦しい、助けてほしい、と泣き叫んでいた自分を、何度も押さえつけて、「だまれ」と首を締めあげて静かになるまで沈めてきたのを、今更――誰かを助けることで満たされたいと思うあさましさなんて、痛いほど自覚があるのに、「やりたい」と思えば匡というのは頑固であった。
「できるかどうかじゃない」
――失敗したらどうするんだ。
「やっていいかどうかじゃない」
――お前にそんな資格はないだろ。
振り払うように、短い髪の毛を靡かせながら首を振った。もがくようにも見えたかもしれない。無数の風圧をかきけすための両手で、見定める。
「やるんだよ」
青の光が、決意に満ちるのだ。
スキアファールも、同じである。
呪いと苦痛でがんじがらめになった二つの因果がある。
人間であることを否定されて、波打つような包帯の軌跡を見た。しゅるりと音を立てて何度も人の形を保とうとする「しつけ」の黒が恥ずかしい。
それでも、――そうありたいと、想う。
人間だったことを忘れないために、怪奇であることを認めるのだ。今はもはや体の一部として認められる異常のそれがどこか頼もしく思える。
獣であることを受け入れて、それが確かに自分の形をした「誰か」であることを上村由美子は理解した。きっと、未だに意味が解らずに喘いでいるのは――かの「のけもの」だけだ。
攻撃や救助は己の得意ではない。
もし、あののけものに直接触れることがあれば怯えさせてしまうかもしれない。今、スキアファールが目視できる限りでも、あの「のけもの」は「美味しそう」に見えてたまらないのだ。
怪奇や頂上が好む器そのものである。呪いの煮凝りといっていい彼女の姿は今、あまりにも無垢で純真から作られていた。
「――こんな私でも、居るんです」
痛みに軋む体を、前へ進める。
両腕を、ゆっくりと持ち上げようとした。
「私が、生きる希望を持てなくても」
風に両腕が弾かれる。ぐらついた体を、長い左足で支える。また前に押し出して、なんとか両腕をまた前に突き出そうとする。
「周囲が、人間として認めてくれなくとも」
何度も、愚かな顔をしてきた。
己が怪奇であることを忘れたくて、人間ぶって生きてきた自分が暴かれたときは、恥ずかしくて惨めだった。
だが、それでも――。明日も、「おかえり」と云ってくれる仲間たちがいる。
「生きてほしいと願い、死ねない理由を作ってくれる人たちが、待っている」
見えなかっただけだ。
ずっと前から、そういう縁があったのに、心のどこかで自分は独りぼっちだと思い込んだほうが楽だったから、誰にも理解されないと決めつけたあの日を今思えばどこか幼く思える。
誰が理解できるというのだ――他人に求めることではない。
スキアファールが「彼」であることを定義するのは、自分しかいないのだ。
せめて仲間たちには自分を偽らないで、ありのままに、小さくならずに――向き合いたいと思って生きている。
この道はとても険しい。吹き荒れるこの痛みの風で思い起こされる痛みのほうが可愛らしいくらいだ。だけれど、それでも、――「生きてほしい」と想うのは、罪だろう。
「生きてほしいんです」
少しでも長く。
たとえ、その命が短くあっても。
蝕まれた体にどれほどの長さが残っているかはスキアファールも予想できない。もしかすれば、明日には死んでしまうかもしれない。それでも、――誰にでも、「生きてほしい」。
「のけものになんて、させない」
伸ばした両腕が、ようやく風景を切り取るように、指先で「写真」を作った。
中央には、もがく邪神が映る――。
【 Y a k a 】
「好きには――させないッッ!!!!!」
ふつり、と風が止んだ。
うごめく呪詛が猟兵たちを解放する。その間を、夕凪・悠那(電脳魔・f08384)も観測した。
「残念だったね、黒の王」
悠那は、『攻略済み』である。
――事件がなかったときの都合のいい夢ならばもう見たのだ。
「彼」も悠那も、普通の友達、それ以上の関係性になって幸せに生きる日々を過ごすという「イフルート」の出来は散々だ。キャラクターが成長するどころか「脳死プレイ」の連続に思わずため息が出る。
「脚本家を変えたほうがよかったね」
まして、もう終えたものであるから。
悠那は風が止む前に幸福からは脱出していた。あまり自分に使いたい手段ではないが、――一時的に「離人症」を悪化させる。
自分自身にかけたハッキングは彼女を「ゲーマー」として昇華させるのだ。
「敵意とか、親愛とか」
――NEW RECORD!
――新しいトロフィーを獲得しました。
――新しいミッションが解放されました!
「"イベント"に感情移入することはあっても目標が定められてたら攻略を躊躇うゲーマーはいないんだよ」
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【Take Over】_ONLINE◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇目標:「黒の王」の討伐
〇EX:「上村由美子」の救出
〇EX:「XXXXXXX」の救出◃
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【Take Over】_ONLINE◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
数多の数式の羅列が悠那の前に現れる。複雑怪奇を極めた仮想ディスプレイはさながらパズルゲームであった。カウントダウンが始まっている――この時間内に解かねば失敗のデスゲーム、ベットされるのは「二人分」の命である。
「――ミッションスタートだ。返してもらうよ」
狙うは完全攻略の四文字のみ。そもそも、悠那はこの戦いに「恋愛趣味レーション」を求めにやってきたのではない。
MMOだ。それぞれのキャラクターにはプレイヤーが接続されていて、一つの大きなイベントを攻略するために齷齪としている。ギミックの一つを「やりこんだ」悠那が解除すれば、後は仲間たちが確実に「目標達成」に導くだろう。
だから、これは「キャリー」であり――「チームプレイ」が鍵となる!!
「黒の王と上村由美子――ベータと呼ぼうか。彼女との接続を今から阻害する」
どこからともなく響く悠那の声が、暴風の止んだ世界でスピーカーから大きく響き渡る。
「完全分離のきっかけを作るよ。生憎解呪までは手が回りそうにないから、君たちが頼りだ。名も知らないプレイヤーからのオーダーでごめん、でも時間がない」
もつれそうな舌すら、今は遠い。悠那がリズムゲームで叩くかのように素早くホロを動かしていく。かき分けるように、繋げるように、ぐちゃぐちゃにかき混ぜられた呪詛の中からたった一本のコードを探す手は止まらなかった!
――握った其れに、確信がある。
「当たれ」
――勝負に出た。
画面の中で握ったコードを引きちぎる。
絶叫が響き渡って――悠那が黒の王へ振り向いた。ぼろぼろと崩落する邪神の体で、「ベータ」が戸惑っている。
「帰ってきなよ」
【彼方の光】が差し込む。
ひとごろしの銃弾で、彼女を縫い付ける邪神の胸――その心臓を射抜いた匡だ。
「あんたは大丈夫だ、まだ――あんたの名前はないけど」
ばきばきとひび割れる亀裂に、人間の血の気配はない。
「もう、“ここ”にいるんだから」
それにひどく、救われた気がした。
匡が、一発の弾丸でひび割れをつくったのならば――そこに駆けこむのが、源次だ!!
ぼうぼうぼう、と燃えながら剣を振りぬく。
精神はきっと、救えない。だから――神殺しの太刀はせめて「逃げやすいように」王の左翼をすべて根から斬り落とす!!!
「ァ」
どうしよう、と驚愕する獣の顔を映すのは、鏡だった。
【贋物の器】は、まるで赤子をあやすかのようにくるくると回る。「随分祟られてンな」と苦笑いを交えてクロウが言えば、光の反射を使って――くるりと振り向いたもう一枚の鏡に、カイの姿がうつる。
「今まで、つからったでしょう」
【援の腕】は、光り輝いていく。
きらきらと輝く救いの光は、まるで太陽のようである。クロウの偽神体との連携もあって、ますます降り注いでいた。真っ暗な田舎町が、――惨劇の姿をあらわにする。
「もう、試す必要もないんです。もう、何を言ってもいいんです」
口から吐き戻していた羽が止まって、「本来の」上村由美子が目を丸くした。
高熱で魘された居た躰が落ち着いて、自分を包む誰かの感触がする。
「救けに、きましたよ」
――のけものの口からも、羽が止まった。
そのまま、黒の王はみるみる崩落していく。空いた穴から落ちていくのけものが、「わ」と声を上げた先に待ち構える源次が、受け止める体制をとった――、だが!
「――――ッ、ぎゃ、ァ!!!!!!」
堕ちる子供の髪を、引っ張り上げる真っ黒な腕が見えただろうか。
「お前は」源次が、怒りをあらわに確信を抱く。
そう。
この「神」は、上村家に向けられた呪詛でできている。
――「あの男」の呪詛で、できているのだ。逃がしはしないと、いびつな歯たちが笑みの形を作って黒の王の中から現れていただろう。
かえっておいで、ゆみちゃん。
今更、家族らしい言葉を使って――「生まれようとする命」を絡めとる。
「上村譲司、か」
諸悪の顔が、割れた赤の代わりに燃え盛るあぎとになって浮いていた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 水衛・巽
水衛・巽
◎△
本当に、実に、趣味がよろしくない
ですが文句を言ってもどうにもなりません
なので早々にご退場願います
当然彼女は置いていっていただくのでそのおつもりで
同じ力量と技と武器ならば
常に相手が複製と知り先手を打てるオリジナルが勝るのが
定石かつ道理でしょう
その程度の発想に王を自称し酔っ払ってる時点で
いかにも過去の残滓に縋るしか能のないオブリビオンらしい
――なので、
こちらを潰しに来るだろう複製は無視し黒の王一点狙い
「上村由美子」を取り込んだ「王」の概念のみを拘束する
無謀と言うなら止めてみせればいいでしょう
私の複製を主張するのならば!
気に入りませんね
無責任と言われても全部気に入らない
彼女に何の救いもない事が
 橙樹・千織
橙樹・千織
◎△
可能性が少しでもあるならどちらも取る
それに、無茶の一つや二つ
今更でしょう?
破魔を浄化を纏い対峙する
身体を思考を蝕む何か
翼を斬り落とされる錯覚
そして
前世を、獣を知った彼らが離れてゆく幻覚
辛い
痛い
苦しい
…こわいっ
目を逸らさず認めても
孤独への恐怖を認めても
まだ“認めただけ”
深紅が光り
咆吼が聴こえる気がする
…わかってる
目を逸らさないと決めたの
孤独を恐れていると認めたの
震える手で幻覚を刃で祓う
ちりりと首飾りの鈴が鳴り
香が薫る
由美子さんには
彼女を想い、待っていてくれる人がいる
それを知っていて
助けない筈が無い
誰かが悲しまないで済むのなら
この手で護れるものがあるのなら
私が持ちうる全てをもって舞唄い
王を狩る
 リーオ・ヘクスマキナ
リーオ・ヘクスマキナ
◎△
あそこまで汚染されちゃったら、もう……
けれど。けれどだよ?
もしも殺さないで済むのなら、ソレはきっと素敵な事だと思うんだ
『理想』は、俺が大人になったような男性と、同じくらいの歳の金髪の女性
但し女性の方はノイズだらけ
……赤頭巾さんの『理想』なのかな?
男性の方は即座に消滅。女性の方が凄まじい戦闘力に
普段の連携戦闘では勝率が無いと判断。防御術式の制御権を返しつつ、UCを発動して気絶
……目的は、彼女の救出
けれどリーオの時とは状況が違いすぎる
魔眼と防御術式の応用で『理想の私』を拘束。大鎌で一刀両断
その後、魔眼の最大出力で彼女を拘束
後は他の猟兵に任せて、拘束に集中するわ。失敗は出来ないでしょう?
 コノハ・ライゼ
コノハ・ライゼ
◎△
ハロー、理想のオレ
模す事も飢える事もなく、ケドだからこその喜びも知らない
言葉に呪詛籠め動き見切り躱し捕食
理想のアンタにゃ人を喰らうナンてできないでしょ?
ねぇ「けもの」
寂しくて悔しかった?
でもソレはアンタが悪いンじゃない
ましてや誰かの為に生まれてきた訳でもナイ
今からでもイイ
誰に認められ、今誰に愛されたいのか
――先ずは自分で自分を、生きた自分を認めてあげて
アンタは、アンタだ
さあ「上村譲司」はドコ?
イイモノ見せてくれたお蔭かね、失くした記憶が言ってンだ
てめぇの様な親には存分に、礼をしろってネ
「柘榴」へ【天齎】発動
暁の空色を宿し邪神に捩じ込み
2回攻撃で傷口抉ってたっぷりとどす黒い生命を頂いてこうか
●
――本当に、実に、趣味が悪い。
あともう少しで助かるところを、わざわざ見せつけるようにして奪っていく。
きっと、「こうなる」ことは予測していたのだろう。忌々しき諸悪の根源の腕が、娘の体を真っ黒な腕でからめとって引きずり込もうとしていた。
由美子――分離したまだ柔い肉体は、呪いの侵食を猟兵たちの手によって浄化された為に止めてはいるが、時間の問題だ。視界に映る父親は、どす黒くえぐみのある匂いを放っている。
思わず、着物で鼻を覆った。
「気に入りませんね、そうでしょう」
水衛・巽(鬼祓・f01428)を見透かしたように語る幻影もまた、巽である。
「ええ」即座に吐き捨てた。「何もかもが、気に入りませんよ」
二つの間に、黒ずんだ符がはらはらと揺らめき、炭と化して消えていく。
この「模倣」を相手に巽は、己の持てる手段を素早くぶつけた。この相手が確かに巽と同じだけのことができるのならば、「天空」をぶつけるのは最悪手と想定される。才に溢れた陰陽師同士で「最凶」を展開すれば巽よりもきっと、世界のほうが耐え切れない。
それを想定しての「乱れうち」となった。相手が精霊を選ぶ前に、巽が決めてしまう。先手を打ち、まずその体力をそぐ。もちろん巽ももう「天空」を呼ぶほどの力は残っていない。――あえて、残さない方針だ。
長く、息を吐く。
「文句を言ってもどうにもなりませんが」
「承知の上です。何回言わせるんですか、気に入らないだけですよ」
「おや、いつのまにそれほど熱血に成れたのか。気になりますね」
「老い先短いのに、と?」
「ええ、血は水よりも濃いものですし」
――諦めたような顔で、ひょうひょうとしてきたではありませんか。
思わず、渇いた呆れの笑い声が巽のかたちのよい唇からあふれる。肩を震わせ、せっかく保っていた呼吸を乱されてしまうほどだ。からからと壊れたように笑う「真」相手に、「偽」は首を緩く傾げた。
「とうとう気でもおかしくなったとか」
「はは、は、まあ――そうかもしれません」
呪われている。
水衛の家に生まれたときから、それは「避けようのない」因果といえよう。
いくら巽が人生にルートを増やしたって、いつかその線路の先は消えてしまうものだ。普通に生きていても、ある日突然事故に巻き込まれて死ぬようなものだから、気にしないようにしていたけれど――「それ」は、知らないのと知っているのとは心の持ちようが違う。
次の朝日は拝めないかもしれない。
瞼を閉じたら、心臓も止まるかもしれない。
脳だけが死んで、躰は生き延びるのかもしれない。
――だから、自分の人生に多くを望まないし、他人にも求めすぎることはないようにわきまえてきたつもりではあった。誰にもそれが悟られないように、懸命に自分と他人を守っていることに誇りもあった。
無責任だ、と――それまでの縁に恨まれないために。
「全部気に入らないんですよ」
今は、もう違う。
数多の呪詛に巻き付けられて、懸命に「けもの」はもがいている。
どこにも居場所がないと思っていて、犠牲を積み上げないと与えられなかったこの領域に哀れは隠せなかった。
助けたところで恐らく十年ももたないだろうという事実も、巽には「先読み」の才で理解してしまえる。ここで「援ける」ことは、巽が自分に課してきた路線変更のボタンを押すことと同じだ。
少しでも長く生きるためにレールを切り替えても、ゴールまでの距離は同じである。
直線に進むか曲がって進むかの差で、目の錯覚だ。どちらも同じ長さに違いないのに、「こっちのほうが長い」と思わせるだけで、終わりは変わらないのだ。
――それでも、いいと思った。
巽の命は、明日潰えるかもしれないのだ。
取り繕って何になる。今までの貸し借りを毎秒ゼロにしてしまうかもしれないリスクがあってこそ人間ではないか。
「彼女に、何の救いもないことが!」
据えたにおいが、不快を煽る。
『お誂え向き』の精霊が己には味方しているのだ。目の前の巽に時間を割いてやるのはここまでである。どん、と胸に片手を当てて――集中のために目を閉じる。
「まさか」
「気づいてしまいました?」この精霊は、「天空」ではない。
じゃらじゃらと装飾が神の息吹に震え、その姿を呼び起こす。
「あなた、――――」
「その『名』を名乗る重さを知っているはずですよ」
呆れたため息の正体は、この虚像の「出来の悪さ」だ。
所詮、オブリビオンのコードなどで呼び出されたものなど「偽物」で「劣化」で「過去」である。常に未来へと歩き続ける巽の日々には到底追いつけまい。
こんなものは定石で道理の筋書に決まっていたのだ。呪詛が晴れ、空には満天の星空が浮き――巽を起点に光が舞う!!
一分でも、一秒でも前にいるのならば、巽は自分を突き放せる。
――ああ、それは、大得意だとも!
「さあ、止めてみせればいいでしょう。――あなたが、『私』だというのならばッッッ!!」
●
可能性が少しでもあるのならば、たとえそれが傲慢だと言われてもどちらも取りたい。
今更――無茶の一つや二つも、兎が二兎になったて、変わりはしないのだから。
橙樹・千織(藍櫻を舞唄う面影草・f02428)を襲う痛みの幻覚は、彼女の足を止めさせるには充分なほど現実的であった。何度も恐れた痛みと、実際に味わった痛みが脳を次第に侵していくのである。
じり、と焼けるような感覚がこめかみに走り、思わずうつむいた。
「いたッ」悲鳴よりもか細い声を上げてしまえば、口から呪詛が入り込んでしまう。
ぎぢぢ、と体中が軋む。
みぢみぢと聞きたくもない音が耳元で立てられて、背中が燃えるような感覚がした。思わず両膝をついて、倒れこみそうな体をどうにか両腕で支える。
「ァ、っ――ぐ」悲鳴を上げて転がってしまいたい。やめて、やめてと声に出さない代わりに、両手で背中を押さえようともがいた。何に攻撃されているのかがわからない脳は、「なんともない」背中に混乱を酷くさせる。全身からどうしようもない焦りが湧き出して、ふつふつと皮膚が煮立つような気がした。
――確かに、翼を切り落とされたような気がしたのに。
「き、ッう」大きな翼で自分を包む。ここに千織はいるのだと思い出そうと、狂気を振り払うために己をとび色に仕舞ってやって――誰にも聞こえないように、痛みをかみ殺す。
ぶるぶるがたがたと躰が震え、細い両腕がわなわなと歪み、両目はすっかり潤んで何も見えなくなりはじめていた。呼吸はどんどん浅くなり、緊張感を伝える脈拍が喉でどくどくどくどくとやかましい。
くれない色の瞳が、咆哮を上げたような気がして。
「――こわい、ッ」
千織の頭には、たくさんの失望と、それから、侮蔑と、畏怖と、別離の声が響いていた。
――そんなひと、いいえ、けものだったんだ。
――醜いわ。
――ボクにはキミに似合う愛なんて描けないかも。
――俺よりも獣らしい。
――俺の味方に寄るな。
――やはりこう、間近で見ると、な。
――やぁだ。俺様に触んないで。
――こ、怖くねえよ!ほんと、ほんとだって、怖くない、よ。
――寄らないでくれ。「障って」しまう。
千織は、己の姿を認めた。このあさましい獣性すら自分だと、つい先ほど理解したばかりで「まだ弁えはついていない」。
素知らぬふりをしていた孤独とも向き合って、己がいかに耐性がないのかも認識したが、それだけだ。理解しきらないまま、むけたての雛が仮想の痛みにつつきまわされている。
震えるたびに、ちり、ちりり、と鈴が鳴った。首に備えたそれが、ふわりと香を立ててくれる。ああ、――そうだ。櫻の彼もこの場にいた。
見知った顔はみな、立ち向かったのである。千織も皆の同行は風のままに戦火の中、聞いていた。
追い付きたい。逃げられるかもしれない絆を、手繰り寄せて――それでも、「仲間だ」と輪に迎えてくれる彼らを自分の思想で下げてどうするのだと、両頬をばしりと張った。
「わかってる」
行かねばならぬ。
この体を、今の様相を、おそろしいと思われるかもしれない。
それでも、――ここでそれを「決めつける」のは彼らに失礼なのだ。
「待ってくれる人がいるの、その子には」
だから、返して頂戴。
頬を赤くさせた両手で、再び武器を握った。びゅ、びゅん!と鋭く空気を薙げば、破邪の作用が働く。
割かれた呪詛の隙間から――――いびつな「王」を見上げて、告げてやった。
「娘たちは愛されてる」
誰かが悲しまないで済むのなら。 この手で護れるものがあるのなら為してみせよう。
「――あなただけよ!!!」
――橙樹・千織は、世界のために舞う!!
●
「あーあ、タンパクな味だこと」
コノハ・ライゼ(空々・f03130)は、つまらなさそうに理想の己を食らっている。
倒すのは簡単であった。なぜならば、理想のライゼというのは「あるべき姿」というだけだからである。
模すことも、飢えることもなく、ゆえにその悦びを知らない上に、強さもない。――ひとがたに食うも食われるも想定していない無防備さは、そのあたりの鹿よりも狩りやすい存在だ。
ぺろりと赤を一滴舐めて、つまらなさそうな顔はくるりと振り向く。
「てめぇは美味しいといいンだけど、ねえ。上村譲司サン?」
――ライゼには、この男の怨嗟が聞こえる。
上村譲司は、生まれ持ってのサディストであった。
「なんでも支配したくてたまらないんでショ」
生まれついた時より、彼は王を約束された立場である。
先祖が代々作り上げてきた功績という玉座にはいどうぞと座らされた、まだ良識も酸いも甘いも社会も知らぬ子供を置いたのが過ちの始まりであった。
何か己が咎められることがあれば、親すら脅した男である。
――いいのか、俺にそんなことを云って!!
「キツネにも劣るし、タヌキ以下。アンタ、娘に求めることも赤ん坊以前の問題よネ」
故に、初めての「敗北」は彼のプライドを大いに揺らがせ、煽ったのだ。
この俺が負けるはずがない――と思っていたのである。すべてを恐怖で支配した気になっていた。
体のいい演説をして、街に昔から住まう彼らに金を握らせ、どうかよろしくなんて笑ってやっていたというのに、「公平」な場ではその力も無意味だったのである。
「身の程を知りゃァこの子たちも、こんなことにならなかったでショ。でも、それが出来てりゃこんな事を仕組む阿保でも無ぇよネ」
柘榴、と名の付いた牙をくるくると手で弄びながら、黒の王――その一部と貸した悪しきを見つめる。
「死ぬなら一人で死ね」
吐き捨てるような怒りを含んだ侮蔑に、がたがたがたがたと歯がかみ合う。存外煽られやすいたちらしいのは、ライゼにとっては愉快であった。
「はッは! 図星? イヤ、ちょっと今日はイイモノ見せてくれたお蔭かね――調子がいいのヨ」
あんたの相手はもういいや、とナイフを目の前で振る。
「ねえ、――お名前は何ていうの?」
徐々に取り込まれていく躰がある。
切り離した真っ白な四肢は、猟兵である神から与えられたものらしい。
先ほどからUDC組織の無線がライゼの耳元でやかましいが、――どうやら、彼女を「受け入れる」体制が組まれているようであった。
「箱の中はちょっと窮屈だけど、いいトコみたいヨ。そんなサ、古臭い、田舎っぺのトコロなんて出ちゃえばイイんだって」
ライゼの声が、よく通る。
これも、猟兵たちのおかげだ――なにせ彼は狐である。虎の威は存分にあやかっていくものだ。
ひくりと反応した動物的な振り向き方が思ったよりも愛らしいのだ。ふ、と微笑んでやって、まだ名前のない「彼女」を見た。再び体内に仕舞い込まれそうに、ゆっくりと呪いという縁で出来たワイヤーで引きずりあげられていく。
「寂しくてさ、悔しかったね」
聞こえているのならば、声をかけ続ける。
呪いとは、結局「こころ」なのだ。打ち砕くのも、「こころ」である。
――助けるという方法は、直接断つのもよいだろう。ただ、「自分で解かせる」のも方法の一つだ。
「今からでもイイの」
諭す様な言葉は、頭を撫でているような温度だった。
「寂しかったよ、って哭いてごらん」
名のない女が、拙いそぶりで口を開こうとする。
言葉を覚えていないのだ。だけど、「赤ん坊」らしく絶叫めいた涙をながすことはできたらしい。
びゃあ、びゃああ、と暴れてもがく彼女に驚いた呪いたちが――動きを緩める。
ライゼは、暁の色をつう、と刃先に指で宿してやって――一対のナイフを十字に見立てて組み合わせた。
「よくできました。さァ、返してもらうヨ」
ぎ、と狐が睨む。
「アンタらにくれてやるには、綺麗すぎるンでね」
●
――あそこまで汚染されてしまったら、きっともう助けることは難しい。
リーオ・ヘクスマキナ(魅入られた約束履行者・f04190)の経験で考えても、明かなことであった。猟兵たちが手を尽くしていくら浄化しても、ただの延命治療でしかないことと思えてならないのは彼もであった。
敵を殺すことに長けた彼である。命を奪うのが得意だからこそ、この命が「終わる」だろうことは想定できていた――が。
「もし、殺さないで済むなら」
それが、一番良い。
甘くなったのではなく、先ほどから心のどこかで「そうあってほしい」と願ってしまう自分がいるのだ。幻想と相対しながら、その猛攻を懸命にかわしてどうにか糸口を探っている。
リーオの目の前に現れたのは、リーオによく似た男と――自分の『赤ずきんさん』と同じ金色の髪を持つ女の姿である。
この姿で苦労することはあれど、リーオは今の自分に不服はない。どころか、むしろ金髪の彼女に思い当たるのがたった一人の可能性しかないのである。となれば、恐らくこの理想を見ているのは――『赤ずきんさん』のほうだ。
かの姿を横目で見て見ても、何の反応もあるようには思えない。茫然としているのか、真っ黒に覆われた顔だけでは判別できなかった。
「赤ずきんさ、――」それに、声をかけようとしたリーオは吹っ飛ばされてしまったからである。
何度も明滅する視界が、がたがたとゆれて安定しない。自分が転がっているせいだと気づいて、しかし痛みすらも置き去りにするような速度であった。ほぼ反射、すこし遅れて展開された防御の術式が追撃を防ぐものの、やはりヒステリックな連撃が打ち込まれる!!
「わ、わわ、ちょ」
――ぞっとした。
あまりにも殺意が込められすぎている。どうにかしてでもリーオを殺してやると鬼気迫るその両手は震え、血が滴りだしても止まる気配がない!!ばきゃ、 んッ――と防御術式が両手で破かれたのを最後に、リーオは気を失う。
「――やってくれるわね、ほんと」
首をがっちりと捕まれていた。おそらく、チョークスリーパーと同じ圧力が細い首にかかってしまったのだ。気道を塞がれ酸素の回らなくなった脳は、確かにリーオの戦闘不能を示す――が。
【夢想式・怪演現界「赤の女王」】が、姿を現す。
金色の瞳を見開き、鋭く目の前の女を蹴り上げた。ヒールがしっかりとみぞおちに入り、嗚咽とも何とも聞き取れぬ声が漏れる。
「邪魔をしないでよ。それに、無粋だわ」
――消えた『大人になったリーオ』の痕跡に腹を立てていた。
噫、まるで虫唾が走る。固まったその体が、首を絞め続けようというのならば余計に固めてやるだけだ。好都合だと――大鎌を呼び出す。
「乙女の謎を暴かないで頂戴」
ぶん、と切り捨てた。
扱いすらも馴染む。手に吸い付くような感覚がして、相変わらずの切れ味に目を細めた『赤ずきん』は、女王として戦場へ向き直った。
――目的の再確認。 救出対象を認識。随分と戦局は猟兵たちの有利で、あともう一息で解呪と破壊が可能となる。ならば、ここで「固定」してしまうのが先決であろう。
前髪をかき上げて、呼吸を置く。それから、女王は目を見開いて――――。
「失敗はできない、そうでしょ」
リーオがそう願っていたのだ。「殺さなくていいなら、それが一番いいことだ」と。
●
クレーンのように「彼女」を引き上げる呪詛の腕たちが止まった!!!
「『縛り穿て、玄武』――――!!!!」
【玄武捕縄】、凶の亀が巽に応じて力を貸す。
無病息災、子孫繁栄の恩恵を持ち、不誠実の代償を得て――黒蛇の尾が鋭く息を吐けば姿を変えた!
無数の棘が縄となり、「偽」と王の体を締め上げる!!
「なッ」
「ほらどうしました、止めましたよ――私のほうが早い!!」
圧力に耐えきれまい。ただの人間の身だ、「偽」が水風船のように弾けるのは早かった!
黒の王はその体をがっちりと巻かれ、少女をくみ上げることもできない。それでも、恐るべきはその執念である。
――返せ、これは俺の子だ。
「どのツラさげてそう言うンだか」
その体を切り刻んでいくのは、ライゼであり――。
「もう遅い―――――!!」
【舞唄・春月光】を振るい、解呪の連撃を叩き込む猛獣が千織である!!
傷つけられた光沢からあふれ出した呪詛に身をそれぞれ焦がされながらも、懸命に祓い、もがき、「たったひとり」に手を伸ばすのだ!!!
「返せェエエエエエェエエ――――――ッッッ!!!」
それは、どちらの輪の叫びだったろうか。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン
◎
(己が病葉となる幻
ととさまの、あねごのために、清くあらねばならなかった
かつての己ならばこの苦痛にどんなに怯えていただろう)
怖いのも痛いのも、嫌いだよ
それでも、おれは、もういいんだ。
(真の姿を解き放ち)
何度でも治してやる。
しゃむ、
(この機械の猫は、きっと幻を見ない)
おれの、喉の、かわりに。
(「叫嘩」
【大声】として、言葉として
胸に抱えた、熱いけものを吐き出そう)
おれは、森番だ!!!
キミに、世界を、見せに来た!!!
(その言葉で己を奮わせ
幻を破り、黒の王に【焼却】の一撃を)
(さみしいけもの。
この声はキミを呼ぶ遠吠えに、なるだろうか)
 ヴィクティム・ウィンターミュート
ヴィクティム・ウィンターミュート
◎
みんな、飢えてるのさ
大半はそれを隠して、上手くやり過ごす
だがそれができない、俺たちみたいな『けだもの』もいる
人の世はけだものには厳しいよな
それでもな、いるもんだぜ
けだものを愛してくれる奇特な奴がね
同じけだもの同士、盛大にやろう
痛みや苦しみは、もう食べ慣れてしまったよ
皆の皿に盛られたそれは俺が奪う
飲み込まずに噛み締めて、無様に前に進もう
なぁ、人の世は確かに優しくないけど
背を向けるには惜しいと思わないか?
のけものと一緒に、まだ居てみなよ
いらないものは、俺がもらってやるから
なぁに、『過去』を食べるの二回目さ
こういうのはさ、俺みたいなどうしようもない奴に押し付けとけ
いずれ人の世から放逐される俺に、さ
 花剣・耀子
花剣・耀子
◎△
目の前に在るのが理想のあたしであるのなら。
きっと、諦めたりはしないのでしょう。
語るも無駄よ。かかってきなさい。
だれかをたすけるには、力が要るの。
遠くて、高くて、届かなくて、……だからこその理想だけれど。
どれだけ傷を受けたって、諦める理由にはならないのよ。
――ええ。どうしたらいいか、わかっているわ。
諦めずに手を伸ばす。
超えられない理想に意味は無い。
おまえがあたしの理想なら、あたしが超えられるのは道理だわ。
全て斬って果たしましょう。
なかったことにはできないし、なかったことにはさせないわ。
過去に立ち戻ることはできなくても、過去を抱きしめる事は出来るのよ。
どうしたかったの。
……どうしたいの?
●
己が、病に蝕まれている。
ロク・ザイオン(変遷の灯・f01377)の体にもたらした違和感の正体は、まさしくけがれであった。
嫌悪感はぬぐえないが――この侵食を幻覚だと割り切っている今は、恐れは抱いていなかった。
じくじくと両手が蝕まれている。真っ黒に変色する。饐えたにおいは腐敗にも似て、ロクの感覚を狂わせるには十分だった。
かすれた喉で何度も噎せて、しかし、それから目をそらさない。
――ととさまと、あねごのために、清くあらねばらなかった。
ロクは、仕組まれた聖者である。生まれ以って恩恵を与えられたのではなく、そうあれかしと刻まれた聖痕で組み立てられたけものだ。ゆえに、この苦痛を心底嫌い、恐ろしく思うが――今は、そんな自分すらも抱きとめてやれる強さがある。
「痛いのも」
じくじくと腐り往くこの感覚も。ゆっくりと両手を握りこんで、手を燃やした。
「怖いのも、嫌いだよ」
――それでも、もういい。
両腕の炎は、女の体を燃やした。
つま先も、髪の毛の一本一本も、余すことなく燃やしていく。
この温度を――使命だとするのなら、呪いとはきっと性質が似ている。
何もかも奪う炎を扱う森番は、森を滅ぼすことのできる力を扱うのだというから、理屈が通っている。
腐ったところを燃やして、どんどん生まれ変わっていく。
――この体が嫌いだった。
ロクは、いつまでも人にあこがれる獣であった。それは、己に「けものであれ」と言い聞かせていた自分からの呪縛のせいである。
ロクはロクでいいのだと、何度も教えてもらった。それを信じられるときもあれば、信じられない時もあって、紆余曲折を得て――止まっていた時間が、考えが、人生が始まったばかりだ。
ひとつひとつ、歩んでいかねばならない。
己を焦がすのではなくて、包むように焼くのだ。
病に侵された枝葉をかき分けて、その症状を見つめるように自分の姿を思い描けばいい。
根まで腐らせるまえに、要らないところは炎にくべてやる。ロクの炎は、確かに森をも燃やせるが――いのちをあたためる炎でもあるのだ。
美しくあれ、と願われたから、美しさを目指すのではないのだと理解するまで、本当に長い時間がかかったのは無知故である。それは恥ずべきだと今でも思うが、それでも、ロクは――ロクがたとえ忘れてしまっても、何度だって教えてくれる相棒と仲間たちがいるから。
「何度でも、治してやる」
灼けた喉で、告げる。
炎の中から――烙が生まれてくる。
火の粉をかき分けるように、両腕で払った。左右に切り開いた炎から咲いて、じっと前を見た。
――随分と侵されてしまっている。
ロクの前に映った光景は、ちょうど黒の王から呪詛があふれ出したところであった。
滝のように黒が現れるのを、猟兵たちがそれぞれせき止めている。破邪の恩恵を授かるものも多い、固定された王は暴れようがないし、傷だらけの躰はじきに――潰えるはずだ。
だからこそ、この異常な量の呪詛はせき止めねばなるまいとなると、やはり「触媒」を壊すことが優先されるだろう。
――助けたい二人のうち、二つをつぶすか。
それとも、二つを取って、町一つを救うかという汚染濃度を前に。
ロクは、ゆっくりと猫めいた瞳を細めて「相棒」を手にする。
「しゃむ」
音声入出力式ネコ型自律ネットワークデバイス――「SIAM」という。
黒い立方体の箱に猫らしき耳と尾がついており、ロクの炎熱にも耐える頼もしい存在だ。気道とともに目らしき赤をぱちぱちとさせて、愛らしく口を開いた。
――機械は、幻を見ない。
以前までのロクなら、きっとわからなかったから頼れなかったことだ。愛嬌たっぷりのこの機会は、どうしても生きている気がしてしまうのである。
「おれの、喉の、かわりに」
――届けてくれるか、と。
箱の頭を撫でてやる。甘えた声が呼応して、ロクはゆっくりとざらざらの喉で冷たい息を吸い上げた。口の端から、浄化の炎がちらちらと燃え、空に舞い上がる。
●
目の前にあるのが、理想であるのならばきっと「二つは変わらない」。
花剣・耀子(Tempest・f12822)は何度も剣を交えている。二つの間に会話など不要だとわかっているからこそ、剣戟は苛烈かつ素早い。
耀子が一歩を踏み込めば、作られた耀子はそれを受ける。
真正面から受け止めてしまうのが己らしくて、ならばと押しこめば拮抗状態に陥るのだ。ゆえに、耀子が取ったのは足払いである。鋭く機械剣《クサナギ》をかち合わせたのならば、弾く。火花を散らせながら、体を直ちに撓めて態勢を低くした。角をかすめるかどうか、というあたりで回転鋸が過ぎていく――が!
そこで、薙いだままが耀子ではない。躱されたと分かれば暴力的なまでにエンジンをふかせて直角に方向を切り替える!!び ゅ、ッ――と空気に布を裂くような悲鳴をさせながら、耀子に振り下ろす牙があった!
位置エネルギーで考えれば、圧倒的に不利である。
上をとられた耀子のほうが姿勢をうまく保てていない。相手は落下する力を使って「断ち切り」に来ているのだ。この状況、どうすべきか――体中の警笛が鳴り響く。生存のためにこの一瞬で数多の方法を考えた。眼前、回転鋸、振り落ろし、――絶命。
かわすか、退くか、諦めるか―――――否!!!
迎 え 撃 つ ッ ッ ッ ! ! ! ! ! !
「あたしだものね」
理想の耀子が、まるで認めるような口ぶりでそうこぼしたものだから。
どう返そうかは悩まなかった。
耀子は、己の無力さを知っている。
遠くて、高くて、届かない――もう、どうやっても会えない人がいるのだ。まだ、会いたくないと今は思えるほどに耀子は心が強くなった。
がむしゃらに戦うのではなくて、自分が生き残るために戦えるようになった。
明日も仲間や友達のところに、ぼろぼろになった自分の体を見て呆れさせてしまうに違いないが、「ただいま」と言いたいのだ。
案の定、迎え撃った耀子の両肩は悲鳴を上げた。
振り下ろす己の怪力が恐ろしい。――【花剣】の力だ、互いに地形を陥没させるほどの衝撃を海ながらびしびしと剣気だけで頬を、手の甲を、脚を斬られる。
どちらの血が真実のものかもわからない。だが、生き残ればそれが「耀子」だ。
「教えてやるわ、あたし」
肩がはずれそうになるのを、肩甲骨に意識を集中して、どんどん押し上げていく。
偽の耀子の細い足が、つま先だけで立ち始めてきた。
どうにか押し込んでやろうと、ぐ、ぐ、ぐ ッ と体重をかけてくる。それでも、止まらない。オロチのエンジン音が興奮しきっていて、真っ白な煙を上げていた。
「理想は、超えるものよ。おまえがあたしの理想なら」
曇った眼鏡の向こうで――澄んだ青が「明日」を見ているのである。
「あたしが超えられるのは、道理だわ」
弾いた、――否、打ち上げたッッッ!!!!!
ば、ッ ぎぃいいいいいん――――――と鋭い音が響き、偽の姿は高く打ち上げられる。
無防備なその姿が落下に伴った重さでさらなる追撃をかけようとするのなら、耀子はただ、もう一度オロチの尻尾を掴んでやるだけだ。
「斬り果たす」
蛇の狩りのようだった。
落ちてくる耀子の体を、オロチの牙で――理想のすがたごと、横なぎにする。
受け止められた回転鋸は側面であった。薄いボディがあっというまに削れ、割れて、血の花を咲かせて内臓と血潮を飛び散らせる。
体全部に己の血を浴びて、それがどうにも――嗅ぎ慣れたものだったから。
耀子は、永く息を吐く。くずれ堕ちるその体を抱きとめてやって、消え果てるまで傍にいた。
●
「あ、あッ――」
聞こえる。
けものの遠吠えが、聞こえた。
「―――おれは、森番だッッッッ!!! きこえるか、きこえて、いるかァ―――――ッッッッ!!!!!!!!!!!」
響いているとも。
【叫嘩】をともなった四角のスピーカーは、着飾らないロクの遠吠えを空に響かせる。
どうか聞こえてくれ、と想う彼女の通りに、その声は「上村由美子」に届いているのだ。
父の姿を、あの「王」に見てしまった時。
どうしても、「かえりたい」と思ってしまった。
父が己を求めるのなら、抱きしめてやりたい気持ちに溢れてしまう。だって、上村譲司といえ人の子なのだ。確かに人を食い物にしてきた今までは赦されるものではなかろう、ここまで盛大に世界を揺るがせるほどの情念を煮やしたのは彼の責任だ。
己を「子供」ではなくて、「道具」や「けもの」として可愛がっていた日々は、人間としての最大の侮辱に違いないのに、どうしてかその両腕のぬくもりを忘れられなかった。
これからどうしよう、なんて明日も思い浮かべないのである。居場所があっても、仕事ももう続けられない。人のためになることで満たしていた心は一気に渇いて、――おいでおいでと手招く父にすがりついてしまいそうな自分を引き留めたのが、その遠吠えだった。
なかまが、いる。
「ッ――キミに、世界を、見せに来た――――ッッッ!!!」
「ぁ、ッ――」
父が、燃えていく。
由美子を探し求める悲鳴を上げながら、彼は燃えていた。助けてくれ、どうか、どうか!!どこにいったんだ由美子!!お前だけなんだ、俺の家族はもうお前しか残っていないんだ!! お前がいればいい! お前もここで死ね―――――――!!!
叫び狂う真っ黒な姿に、おやおやと頭を掻く少年――いいや、もう青年だ。
「みんな、飢えてるのさ」
ヴィクティム・ウィンターミュート(Winter is Reborn・f01172)は、上村由美子の意識を父から「奪う」。
振り向いた彼女にやわらかく微笑んでやって、機械の両手で身振り手振りをしながら諭した。
「大半はそれを隠して、うまくやり過ごす。それこそ、頭ンなかは自由だろ? 豚みたいに飯をただ貪りてえって思う奴もいれば、犬みたいに雌に腰を振りたい奴もいる。言わないだけだ、皆そう」
あんたも、と向けた左の掌で、「俺もそうだ」と己の胸を叩く。
「人の世はけだものに厳しいよな。だけど、――いるもんだぜ」
両腕を広げて、注意を誘う。叫び続ける黒の王を裁断するための鋸がすぐそこまで迫っていた。ヴィクティムの背後を駆け抜けていく耀子の姿は、由美子で目視も難しい。
「こーんなにも、奇特な奴はいる。すげえだろ? これが、世界ってやつだ。あの文字通りにホットな女が言うように、さ」
にかりと笑った。
右手の親指で指し示す先には、燃え盛るロクの姿がある。
切り刻み、溶かし、燃やし――戦場一帯の呪詛は掻き消えて、すべて美しく消えていくのだ。
熱波めいた季節外れの風だけではあるまい。由美子の顔は赤らんでいた。ああ、生きている色だとヴィクティムも悟る。
この女には、明日があって、未来があるべきだと。
「同じけだもの同士、盛大にやろう。な」
さあ、手を取って。
両手を伸ばして、立ち上がれない彼女の掌を握る。
「――何を」
「あんたの過去――呪いを食う」
「え」
「心配すんな。もう二回目だし、食べ慣れててね」
「いやあの」
「痛みもないさ。お触りもこの握手だけ。ただ、綺麗さっぱりあんた「たち」からは貰っていく」
「そうじゃなくて、」
「いいんだ。気にするな」何を言いたいのかは、わかっている。
ヴィクティムがはぐらかすのをやめて――握った手をゆすった。
「人の世は、確かにやさしくない。でも、背を向けるには惜しいだろ」
な、そうだよな。と繰り返すことで、相手の同意を得る。これは、狡いトークの術だ。
俺は無理やりそういうことをしたのではなく、誰かを助けるためにやりましたとまっとうな理由がついてくる。
「のけものと一緒に、まだ居てみなよ」
目を見開いて、「でも」と告げる彼女に「いいんだって」と口を尖らせた。
「――、こういうのはさ、俺みたいなどうしようもない奴に押し付けとけ」
きっと、彼女は知るまい。
もう、ヴィクティム・ウィンターミュートという青年の因果は、ねじれにねじれて狂ってしまっている。二度とずれたチェーンは戻らないだろうし、いつまでもシナリオは筋書き通りにいかないまま、破綻した最悪のエンディングが待ち受けているだろう。
死刑執行――その猶予の間なのだから。
「いずれ人の世から放逐される俺に、さ」
いい人ぶったって、いいじゃあないか。
――――【Forbidden Code『Robbery』】。
無数のガラス片が、その呪いを吸い上げて青年の躰に突き刺しては宿していく。
黒の王はみるみる形を崩して、崩れ落ちるパーツがいっそあわれだった。燃やされ、斬られ、もうその言葉は「呪いの解けた娘には届かない」。
「ごめんなさい」
「謝るなよ、カッコ悪くなっちまう」
「――ありがとう」
「そうだ、それでいいんだよ。な」
項垂れる女の血色が、みるみる良くなっていく。黒い羽根を吸い上げたヴィクティムが噎せれば、掌いっぱいに羽毛がこびりついた。
「ほら、オシャレになったしさ」
――あんたには、「ひと」の居場所がトゥルー・エンドだ。そうだろ?
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 神狩・カフカ
神狩・カフカ
◎【相容れない】
さァて、どうする?
ま、聴くまでもねェか
初めて意見が合ったなァ
そンじゃ、お前さんの救いってやつを見せてもらおうか
現れたのは姫さんの幻覚
これはいつの姫さんだったか…おれは彼女が生まれ変わる度に見守ってきたからな
添い遂げた過去もあれば手に入らないこともあった
変わらないのは纏う桜の香りと
同じ時間を生きられないということ
それが永遠みたいにおれに笑いかけて――
あー…虫唾が奔る
なんてもン見せやがる
そいつァ、邪神風情が簡単にかたっていい女じゃねェ
俺自身が現実にする永遠だからな
幻を風で吹き飛ばして
おーい、由美子さんよ
まだ間に合うぜ
救って欲しいなら自分で手を伸ばしな
ここには神も聖者もいるンだからな
 ジン・エラー
ジン・エラー
【相容れない】
◎
どォ~~するもこォ~するも……
……お前、よォく分かってンじゃねェ~~~かァ!!
ビャハヒ!言われなくても見せてやるよォ~~!
ウヒャララヴァハヒハハハ!!!!
まァ~~~たそォ~~いうパタァ~ンかよ芸がねェ~~~なァ~~~~!!
で?オレと同じヒカリが使えるンだろ?やってみろやニセモノ
あ~~ァあァ足りねェ~~~足ァ~りねェ~~~なァ~~~~
お前には光も、救いも、呪いも何もかも、足りちゃいねェ
やっぱ所詮カミサマなンかにゃオレの救いはわからねェってこった
あばよ。
無理も無茶も無謀も
のけものだろォ~~がばけものだろォ~~~が
オレが全部救ってやるよ
ほら、来たぜ。
●
――現れたのは、愛しい彼女の幻覚であった。
これは、いつの彼女であっただろうか。神狩・カフカ(朱鴉・f22830)の前に現れたのは、桜の香りを連れた血に飢える彼女である。
カフカは、神だ。
故に、人の生涯もなにもかも、瞬きのうちに過ぎ去ってしまうといっていい。
ああ、ようやく周りの顔ぶれに馴染んできたなと思ったころにはあたりに住まう人はすっかり変わってしまっているし、あっという間に友人たちは切り替わる。
悠久を生きる彼にとって、――輪廻転生は当然の事であった。
愛した女を手に入れたこともある。あっという間に死んでしまうのに、何度生まれ変わっても逢えるからといつのまにやらすっかり彼女を探すようになっていた。
この神であるカフカと魂を添い遂げたものだから、女は何度身に覚えが無くても、どんな姿でもカフカに出会うのである。
ただ、カフカは――寛大であった。
愛した女がそれらしく、愉しく過ごせていればそれでいいのである。自分のものになれば確かに一番よいのだが、そのひとときもいずれ泡沫になってしまうのだ。
手に入らないときもあった。他の男に寄るのもカフカは赦す。
ほんの一瞬貸してやるだけのことで、人間にとっての寄り添う五十年など、神にとっては時間にもならない。
幸せそうな家庭を作る姿も、己の隣で笑う姿も、どれもこれもいとおしいのだ。
だから、――結局のところ、カフカは傲慢にも一人の女を愛し続けている。
今日この日も彼女を思い浮かべば、逢いたいと思って胸の内が熱くなるほどにはたまらなかった。
二人の関係は変わっても、その世代になっても、変わらないものがある。
――櫻の香りと、同じ時間を生きれないという因果。
「あー」
思わず、赤い髪をかき混ぜる。右手だけでぐしゃぐしゃとさせて、深くため息をついた。
「虫唾が奔る。なんてもン見せやがンだ、えェ?」
まるで、その姿が永遠の時間存在するようだから。
浮かべた笑みすらいとおしくてたまらないが、これが夢のものだというのはカフカに理解できる。
何せ、――それこそ、永遠に愛す女の姿である。
あっというまに「切り替わる」はずのものが、ずっと在る時点でもはや彼女ではない。
さらにいうなれば、「ずっと笑っていてほしい」わけでもない。
「そいつァ、邪神風情が簡単にかたっていい女じゃねェ」
怒って、泣いて、楽しんで、時にくじけて、辛いと叫んで、それでも――生きていてよかったと死ぬ其の顔すらもいとおしいのだ。
ただただ笑っているだけの女をこのカフカが愛するはずもない。これは、侮辱であった。
神が怒るのも当然である。
「俺自身が現実にする永遠だ」
――【夕暮鴉】のつがいは、生涯たった一羽だけなのだ。
煙管の煙が立ち上り、夕陽色の鴉が怒りをあらわに飛び出してくる。消えゆく呪詛を突き破って、愛しい彼女の姿は羽ばたきで消してやった。
代わりに、――無数の鴉たちはどんどん神を呪縛から解いていった。
縛れる黒の王を射止め、くちばしで貫き、抉る。
家族という唯一の財産と武器を喪おうという亡者の悲鳴などどうでもよい。さっさと還って――もう還れないだろうが、在るべき場所に逝けと想うだけだ。
ようやく晴れた愛と情の空間から、何度か隻眼で瞬きをして。カフカは、ゆるりと空を見上げた。
「おーい、そこの――由美子さんじゃないほう」
吊るされたまま、どうにか出ていこうともがく女の姿はあられもない。
生まれたままの姿であるから、直視するのもどうかと想いつつ目をそらす。
女の裸など見慣れているが、振る舞いからして明らかに心は清純な女児のものだ。味も何もかも知っているカフカがいたわりの気持ちを持つのも無理はない。
「ほら、まだ間に合うぜ。早く降りて――生まれておいで」
ここには、神だっているし。
「あんたを待ってんだ、皆さ」
――聖者だっているのだから。
●
「「ウヒャラララララヴァハハハヒハハハハハハハハハ!!!!」」
もはや、ファンファーレと等しい音量である。
げらげらぎゃらぎゃらと笑いながら、ジン・エラー(我済和泥・f08098)がお互いを指さして笑いあう。ぎざぎざの歯はまるでのこぎりのよう。きらきらと輝く無数のピアスすら、お互いを馬鹿にして祝福しているようだった。
「まァ~~~たそォ~~いうパタァ~ンかよ芸がねェ~~~なァ~~~~!!」
「おめェ~~~もひとの事言えねェ~~~だろォ~~~がァ~~~!!!!???」
「あァ~~~~~~~~~??????ンなことねェ~~~~~~~~~~~~~し???オレはチョ~~~~~~~~使えるもんねェ~~~~~!!!」
矛盾の存在が腹を抱えあってお互いを見つめあう。
おどけた調子で話すわりに、見比べる目は真面目なのだ。
お互いに見定めている。目の前にいるジンは、いかに己より優れているかどうかを考えている――どちらがより、聖者にふさわしいかを値踏みしているのである。
「で?オレと同じヒカリが使えるンだろ?やってみろやニセモノ」
「だァ~~~~れがニセモノだ~~~???おめェだよなァ~~~~?!!???」
「うるせェ~~~よ~~~!!はやくしろマジで時間が押してンのこっちは~~~~~」
「アーーーーハイハイハイわかったわかりましたよォ~~~~!!!ンじゃあ~~~~よォオオオ~~~~く目ェ開いてな」
言われずとも、見るつもりだった。
光に影は、あり得ないのだ。だから、その光に本当に黒がないかどうかを見届ける必要があった。ジンは、誰よりも、まっとうな――聖者であらねばらなない。
【オレの救い】を見届ける。
それは光そのものである
慈愛の心そのものであり、神のない彼の心であり、究極――ただの親切心そのものを指す。
ジン・エラーという男は、いつくしむ彼であった。
此度だってそうだ。崩れそうな己の内面を見ても、結局ここまで食らいついている。
すべてを救うと、誓っていた。ジンは神を信じない。ゆえに、彼が信じるのは彼自身のみであるといえる。彼に救われた人が、どうなるかまではその人を信じるしかないが――いかにそれが傲慢であり、驕傲でありながら、不遜だとののしられたとしてもこの姿勢だけは変えられないのだ。
なぜならば、神は平等に「愛している」のだ。
人間の価値観が基準の問題ではない。ジンが人も怪物をも『たすけたい』と想う感情は、奉仕であるが――神に奉仕の心はないのである。ジンからすれば、よほどそれのほうが傲慢に思えるのだ。
「あ~~ァあァ足りねェ~~~足ァ~りねェ~~~なァ~~~~お前には光も、救いも、呪いも何もかも、足りちゃいねェ」
輝く己の姿に、ほとほとがっかりとした。
明らかに肩を落とした彼の姿に、ニセモノが絶句する――そうだろう。
助けられないもの、感謝されないこと、があってはならない。なぜなら、これは慈愛であり、奉仕であり、自己犠牲なのだから。
「やっぱ所詮カミサマなンかにゃオレの救いはわからねェってこったな」
只の、再確認にしかならない。
このジンは確かに理想の姿であろう。恐らく、神を信じて「聖職者」としての理想らしいジンだ。
――――どォりで腑抜けた輝度だと思った。
などは口にしてやらない。ジンは、いくらそれが「にせもの」の己であったって、傷つけるような真似はしないのだ。すべて平等に愛して、「救い」という奉仕をする彼である。
「あばよ」
せめて、――彼の光で照らしてやった。輝く姿が、光そのものになる。輝いて、輝いて、輪郭を消し飛ばして、――黒の王を浄化させていく。
電気を喪った街に、まるでひとつの星が生まれたようだった。
呪詛の縄がほどけた彼女が落ちていく。幼い顔を見上げて、受け止めようとカフカが手を伸ばす。
「さァて、どうする?」
「どォ~~するもこォ~するも……生まれてきたらやるこた一つだろォ~~~~が」
「ほォ、初めて意見が合ったなァ」
「お前、よォく分かってンじゃねェ~~~かァ!!オイなンだよ実はいい奴でしたオチ~~~!!!???やっべェウケるウギャラララハハハヒヒヒハハハハ!!!」
「あァ~~~~うるせえなァ~~~そんなに笑ったら赤ん坊が泣いちまう。ほら、見せてくれよ。お前さんの救いとやらを」
「ビャハヒ!」
皆が救いたいと願って、――呪いから断ち切られた彼女が、カフカの両腕に、とすんと収まった女の姿を見た。
「そンじゃァ――、洗礼の時間だ。ほら、来たぜ」
街に、灯が戻っていく。
喪われた電気と、――激しい怨恨の爪痕がまるで、口惜しいと叫ぶ男の最後を表していた。空にはぽっかりと大きな月が浮かんでいて、皆をそれぞれ照らしていく。
「月の子、汝の罪は今、――――――ここで」
●
・報告書
・yyyy/mm/dd
UDCに汚染された一般人二名の保護、その処遇について経過報告。
YとYaは猟兵によって作られた体を持つが、体内組織として同一人物である。二人の血液検査をした結果、クローンとして判別するのが相応しい。
しかし、YよりもYaのほうが傾向としては非常に呪詛への影響を受けやすいことが明らかになった。ただいまの浸食率は――――%、定期的なケアで上昇率を抑えることに成功している。
UDCを呼び出すための生きた媒介となった彼女らには、今のところ「再発」の兆候は見られない。
Yは非常に正義感に溢れ、真面目である。たびたび己の加減がわからないところから、怪我をしていることに気づかなかったり、突如カタレプシーを起こすこともあるために、重度の解離性障害であることが確認された。
元警察官であるために身体能力も非常に高く、職員ともコミュニケーションがとれている。非常に学ぶ意欲が高く、また、自身の今後についても前向きな傾向がみられる。
猟兵たちに恩を感じており、彼らの役に立つようなサポートを一職員としてまっとうしたいと考えている。→審査中。 耐久力に問題あり。ほぼ却下、後述の異常点も含む。
Yaは非常に攻撃的で、かなり警戒心が高く、たびたび拘束する必要がある。IQテストでは高得点を誇るが、人や社会に興味がない。代わりに、学ぶことには夢中なようでよく本を読んでいる。
猟兵が因果を捻じ曲げた結果に生まれた肉体であるため、耐久テスト結果は非常によいが社会性に問題があるため、非行青少年更生プログラムを民間団体より導入。情動の発達が遅れていると思われる。週に二回、カウンセリングが必要な状態。
運動能力も高いが、こちらも加減の調節が難しい。また、免疫力が異常に落ちることがあるので、ストレスとの付き合い方を模索せねばならない。
猟兵たちに恩を感じており、彼らの話には興味を示す。
Yと引き離されると不安定になるため、YとYaは隔離場所を同一とした。この二人を移送する場合は、同じ「箱」の中に入れることを重視する必要がある。
刑事罰についてはどうするか?→不安定な状態であるには変わりないが、本人の状態から見るに発達の遅れは否めない。責任能力を問うのは難しい。また、司法の手に負えるものではないとして、現状保留。
また、YとYaは邪神の触媒であったことから、xxxxとxxx値に異常があり、投薬中。
→経過観察。YとYaの寿命は、現時点で十年以内との医療チームからの報告アリ。
→投薬後の副作用反応は少ない。改良を続ける。
・音声記録
「――助かって、どう? その」
「どうとか、そういうの、わからない。ちゃんと、言葉にして」
「……ごめん。あの、……嬉しいと、思えてるかな」
「嬉しい。なぜ?」
「……、私と、二人きりだし」
「嫌って、思ってない」
「そ、っか」
「……由美子は、由美子、でしょ」
「――そうだね。由美は、由美」
「たすけてもらえて、よかった」
「うん」
「かぞく、と、いっしょ」
「――うん」
・結果
xx邸跡地含め浄化作業を終了。
あたり一帯の濃度は一か月安全圏の数値を確認。――異常なし。
記憶の浄化完了。Yの処遇については、今後とも公安と議題に挙げる。
以上、「XX市 邪神召喚儀式における一般人二名の保護、その経過について」の報告を終了とする。
●
君たちは、「一〇二」を救って見せた。
一つを見捨てず、ふたつを作り、其れすべてを握り、明日への未来に運ぶ。
きっと、彼女たちは今度こそ家族を――群れを、見失わないだろう。それから、きっとお互いの巣を探してこれからも生きていく。
その命が潰えるまで、君たちに与えられた居場所を、――だいじなひと(かぞく)の手を確かに握りあいながら。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵


 さもえど
さもえど
 久津川・火牙彦
久津川・火牙彦  零井戸・寂
零井戸・寂  琴平・琴子
琴平・琴子  冴木・蜜
冴木・蜜  シキ・ジルモント
シキ・ジルモント  サリア・カーティス
サリア・カーティス  百鳥・円
百鳥・円  ロク・ザイオン
ロク・ザイオン  ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
ニルズヘッグ・ニヴルヘイム  桜雨・カイ
桜雨・カイ  ディフ・クライン
ディフ・クライン  グウェンドリン・グレンジャー
グウェンドリン・グレンジャー  ティオレンシア・シーディア
ティオレンシア・シーディア  リーオ・ヘクスマキナ
リーオ・ヘクスマキナ  鳴宮・匡
鳴宮・匡  誘名・櫻宵
誘名・櫻宵  朱赫七・カムイ
朱赫七・カムイ  草守・珂奈芽
草守・珂奈芽  西塔・晴汰
西塔・晴汰  エミリア・ジェフティー
エミリア・ジェフティー  霧島・クロト
霧島・クロト  終夜・日明
終夜・日明  カイム・クローバー
カイム・クローバー  アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト  水衛・巽
水衛・巽  橙樹・千織
橙樹・千織  ヴィクティム・ウィンターミュート
ヴィクティム・ウィンターミュート  叢雲・源次
叢雲・源次  杜鬼・クロウ
杜鬼・クロウ  神狩・カフカ
神狩・カフカ  ジン・エラー
ジン・エラー  ロニ・グィー
ロニ・グィー  ゼイル・パックルード
ゼイル・パックルード  花剣・耀子
花剣・耀子  コノハ・ライゼ
コノハ・ライゼ 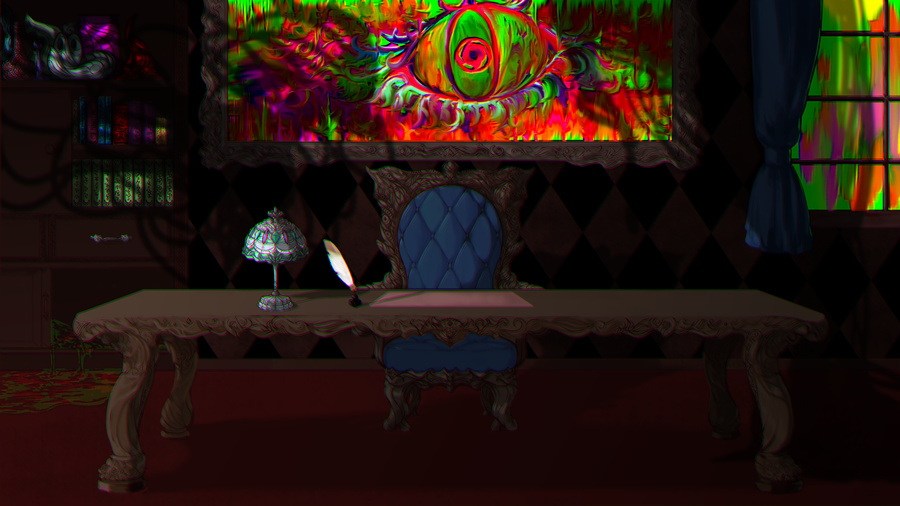
 終夜・日明
終夜・日明  ゼイル・パックルード
ゼイル・パックルード  鳴宮・匡
鳴宮・匡  琴平・琴子
琴平・琴子  シャト・フランチェスカ
シャト・フランチェスカ  冴木・蜜
冴木・蜜  ニルズヘッグ・ニヴルヘイム
ニルズヘッグ・ニヴルヘイム  鷲生・嵯泉
鷲生・嵯泉  西塔・晴汰
西塔・晴汰  草守・珂奈芽
草守・珂奈芽  シキ・ジルモント
シキ・ジルモント  ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック  ロク・ザイオン
ロク・ザイオン  紅砂・釈似
紅砂・釈似  アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト  グウェンドリン・グレンジャー
グウェンドリン・グレンジャー  百鳥・円
百鳥・円  橙樹・千織
橙樹・千織  霧島・クロト
霧島・クロト  カイム・クローバー
カイム・クローバー  神狩・カフカ
神狩・カフカ  ジン・エラー
ジン・エラー  ロニ・グィー
ロニ・グィー  久津川・火牙彦
久津川・火牙彦  ディフ・クライン
ディフ・クライン  スキアファール・イリャルギ
スキアファール・イリャルギ  桜雨・カイ
桜雨・カイ  誘名・櫻宵
誘名・櫻宵  朱赫七・カムイ
朱赫七・カムイ  叢雲・源次
叢雲・源次  杜鬼・クロウ
杜鬼・クロウ  夕凪・悠那
夕凪・悠那  花剣・耀子
花剣・耀子 
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト  ウィータ・モーテル
ウィータ・モーテル  シキ・ジルモント
シキ・ジルモント  鷲生・嵯泉
鷲生・嵯泉  冴木・蜜
冴木・蜜  ゼイル・パックルード
ゼイル・パックルード  ティオレンシア・シーディア
ティオレンシア・シーディア  西塔・晴汰
西塔・晴汰  草守・珂奈芽
草守・珂奈芽  誘名・櫻宵
誘名・櫻宵  琴平・琴子
琴平・琴子  カイム・クローバー
カイム・クローバー  紅砂・釈似
紅砂・釈似  久津川・火牙彦
久津川・火牙彦  ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック  ロキ・バロックヒート
ロキ・バロックヒート  ディフ・クライン
ディフ・クライン  グウェンドリン・グレンジャー
グウェンドリン・グレンジャー  霧島・クロト
霧島・クロト  終夜・日明
終夜・日明  ロニ・グィー
ロニ・グィー  サリア・カーティス
サリア・カーティス  シャト・フランチェスカ
シャト・フランチェスカ  杜鬼・クロウ
杜鬼・クロウ  叢雲・源次
叢雲・源次  鳴宮・匡
鳴宮・匡  桜雨・カイ
桜雨・カイ  スキアファール・イリャルギ
スキアファール・イリャルギ  夕凪・悠那
夕凪・悠那  水衛・巽
水衛・巽  橙樹・千織
橙樹・千織  リーオ・ヘクスマキナ
リーオ・ヘクスマキナ  ロク・ザイオン
ロク・ザイオン  花剣・耀子
花剣・耀子  神狩・カフカ
神狩・カフカ  ジン・エラー
ジン・エラー