●
無理だよ、倒せっこない。ここは一旦退きましょう? 仕方ない、猟兵を呼ぼう。
本来ならば、そんなやり取りが行われるはずだった。だが、彼らの口をついて出た言葉は。
「俺はどんな敵にでも立ち向かってみせる! 災魔、覚悟しろ!」
「ああ、こんな深い深い所であなたはひとりぼっちだったの? 私がもうあなたを独りにはさせないわ」
豹変した仲間達を見た少年は、慌てて踵を返し、元来た道を辿る。助けを呼ばなくちゃ。敵を倒さなきゃ。ああこの道は辛い。ああなんて暗い。あの敵は危険だ。早く敵を倒さないと。敵を。
「……あれ?」
ああ、出口が見えてきた。早く学園に行って――学園?
「敵って……何だったっけ?」
なんでもいい。倒せばいい。殺せ、殺せ、殺せ、殺せ――。
●
長い長い苦難の道を行き、少年少女は迷宮の最奥に辿り着きました。
ですが、勇猛果敢な少年は強大な災魔に立ち向かい、命を落としてしまいました。
心優しい少女は孤独な災魔を憐れみ、共に生きる事を誓いました。
臆病で聡明な少年だけは、災魔と戦う事を諦め、帰還を果たします。
帰還した彼は英雄となり、静かな余生を送るはずでしたが、友人や家族を次々と殺しました。
彼は辛い道行きの果てに、狂っていたのです。
――『或る悲劇』のあらすじ
●
「ってカンジの話でね。あたしはろくに本なんか読まねーけど、これは駄作だと思う」
二本木・アロはそう吐き捨てたが、地下迷宮の奥に潜む災魔『スペシャル・ライター』が綴る物語は、完璧だと伝えられている。曰く、外連味溢れる表現でありながら、仰々しい言い回しにも嫌味なく、読者を引き込む構成と感情移入させる言葉選び、いつまでも後を引くように語り尽くせぬ読後感。
問題は、その効率性。かのライターは自身の作品に修正を必要としない。物語の登場人物を――ライターの元に訪れる生徒を都合よく『修正』し、物語の齟齬となる猟兵を『修正』する。生徒の人格を改変し、猟兵を殺すのだ。
人格の改変など出来るのかという問いに対し、アロは迷宮の罠も問題なのだと答える。
「一つ目の罠が『常闇の迷宮』。とにかく真っ暗で何も見えねーんだわ。普段頼ってる感覚を突然失うっつーのは案外疲弊するもんだ。時間の感覚をなくしやすいしな、想像以上に長い時間に感じるのかも」
この迷路のように入り組んだ区画は、光を吸収する魔石で作られている。いかなる道具を持ち込もうと、何の役にも立たないと思われる。
「二つ目の罠が『幻惑の回廊』だ。強烈な催眠とか暗示とか、そーゆーの。一歩踏み込むと『怖いもの』を見せてくる」
怖いと思うものは人それぞれだろう。複数人で同時に突入しても、同じ幻覚を見るとは限らない。
「自分の嫌いな虫が群れで這い上がってくるかもしれないし、昨日観たホラー映画の殺人鬼に追い回されるかもしれない。……過去のトラウマ、友人が事故で死ぬ場面とかを繰り返し見せてくるかもしれないし、今恐れている事――例えば、大切な人を失う場面を見る羽目になるかもしれない。とにかく見たくないもんを延々と見るコトになる」
そうして罠を抜けた頃には疲労困憊だった生徒達。茫然自失の状態にある彼らに、効率的な作家は『ルール』を宣告した。
「そいつは『自分の登場人物として振る舞う』コトを要求した。こんな一方的な命令すらルールとしてまかり通るんだからやってられねーよ」
幸い、予知で生徒達の探索を中止させる事が出来た為、事件は未然に防いでいる。
「みんなにはこの災魔をぶっ潰してきて欲しい。こんな駄作、あんたらの物語に書き換えてやれ。猟兵の物語は『めでたしめでたし』で終わるって相場が決まってんだ」
 宮下さつき
宮下さつき
スチパン大好き宮下です。
宮下の文章力では災魔さんの綴る完璧な物語は表現出来ませんが頑張ります。
●世界
アルダワ魔法学園です。
●二章、幻惑の回廊について
あなたの「怖いもの」を教えてください。幻覚に対して何らかの対処法が書かれている、技能が活かされているとプレイングボーナスがつきます。
特に怖いものが書かれていなかった場合、無難にホラーな目に遭うと思われます。ちなみに宮下はゾンビが好きです。
それではよろしくお願い致します。
第1章 冒険
『常闇の迷宮』

|
POW : 何があろうと突き進むのみ! 転ぼうがぶつかろうが関係ないね!
SPD : 感覚を研ぎ澄ませて進もう。周囲の小さな音や空気流れを感じ取るんだ。、
WIZ : ここに来る前に地図を記憶してきた。問題ない。
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴
|
 コイスル・スズリズム
コイスル・スズリズム
WIZアドリブ歓迎
目を瞑り、左手の袖口を挙げて
心の中でイメージするのはジャズ
暗黒の中で広がるのはニューヨークのスタイル
あらかじめ地図は覚えた
←はAm、→はE7、と進行方向をコードに置き換えたわ
あとはそのコードに沿って
軽やかなステップでフロアの入り口目指す
持ってきたのはただのメロディ
暗闇でもかき鳴らされたメロディは消えない
浮かぶのはニューヨークの光景
ピアノ、ベース、ドラム
シンフォニアらしく「歌唱」なんかをのせて
何曲分だってもうすでに記憶してる
無事にたどり着いたら
演奏終了の合図として左手をおろす。
いくつかアドリブのコードを入れたけど、
すずの「修正」もなかなかだったでしょ?
待っててね、ライターさん。
「わあ、本当に真っ暗ね」
まるでただの幕間の暗転か何かのような気軽さで。事も無げに言ったコイスル・スズリズムは目を瞑り、そっと左手を挙げる。微かな衣擦れは、彼女のステージの始まりの合図。何一つ躊躇う素振りも無く、闇の中へと身を投じた。
と、と、ととと、と。
障害物を確認する素振りはない。見えぬはずの分かれ道も、曲がるべき所で曲がる。独特のリズムを刻む足音を伴って、コイスルは暗闇を進む。
(「持ってきたのはただのメロディ」)
広大な迷宮の地図も、コードに置き換えれば覚えるのは容易かった。メロディという名の地図を携えた彼女には、闇を恐れる道理など無い。
と、とと、と、とと。
漆黒に、光が生まれる。窓という窓に煌々と明かりが灯り、カラフルな看板が姦しく主張を始める。サーチライトが光の川を作り、彼女の脇を流れてゆく。
(「暗闇でもかき鳴らされたメロディは消えない」)
ここはブロードウェイ。コイスルは瞼の裏に浮かぶ目抜き通りを歩く。
「~♪」
ジャズのメロディに、コイスルの歌唱が加わった。愛らしい声が楽器のようにハーモニーを奏で、彼女のステージはいよいよ盛り上がりを見せた。惜しむらくは、観客が居ない事だろうか。
と、と、と。
ピボットコード。迷宮は複雑に入り組んだ区画へ。それでも彼女のステップは淀みなく、コンテンポラリーを踊るかのように続く。そして。
「――いくつかアドリブのコードを入れたけど、すずの『修正』もなかなかだったでしょ?」
左手を下げ、演奏終了。いつの間にか闇は途切れ、彼女の目の前には扉がある。
「待っててね、ライターさん」
打鍵の音すらも、すずが音楽に変えてあげるね。先に潜んでいるであろう敵を想い、少女ははにかんだ。
大成功
🔵🔵🔵
 テト・ポー
テト・ポー
人を修正するなんて……おいしいごはんもおいしくなくなる訳でしょ? それはよろしくない、とてもよろしくないな!
おいしいごはんをおいしく食べてこそ、ハッピーエンドってものだと僕は思うね。
暗くて見えなくても、総当たりで行けばなんとかなると思う。右手を壁に当てて、それに沿って進めばいつかはゴールにたどり着ける……といいな!
……着くまでにお腹すいて倒れたら嫌だし、曲がり角がある度に【食料カバン】からマカロンとか金平糖とか出して食べよう。
ついでに暗い中で敵に会ったらこわいし、UC「空腹の充足」で強化だけしとこ……
あと、他の人と会ったらおやつをお裾分けしつつ喋りながら一緒に行きたい!
暗いし一人だし面倒だし!
 オスカー・ローレスト
オスカー・ローレスト
【連携・アドリブ歓迎】
【SPD】
……ほ、本当に……な、何も見えない……俺がいた森とはまた違った種類の暗さ、だな……(実は:森暮らしだった小雀
い、一応俺は【暗視】ができるけど……む、無理そうなら【野生の勘】頼みで進むしかない、よな……あとは……武器の【裁ち鋏】を杖がわりにして、先を当てた感触で壁を探して、手で触れた感触で壁伝いに行く……とか。……は、鋏が他の猟兵に当たらないように、気配にも気をつけないと、な……
人を修正するなんて、とテト・ポーは暗闇の中でぼやいた。
「おいしいごはんもおいしくなくなる訳でしょ? ――それはよろしくない、とてもよろしくないな!」
ライターの思い通りに捻じ曲げられる人格。今まで大好きだった食べ物も、作家が『嫌い』と植え付ければ口に出来なくなってしまうかもしれない。きっとそれは、とても恐ろしい事だ、とテトは思う。
「おいしいごはんをおいしく食べてこそ、ハッピーエンドってものだと僕は思うね」
食に対する比重はどうあれ、人生に彩を添えるもののうちの一つである事は間違いない。そんな事を考えていると、後方から微かに金属の音と、石を引っかくような音がした。
「ええ……敵がいるとは聞いてないし、猟兵だと思うけど。誰かいるのか?」
「……ほ、本当に……な、何も見えない……」
俺が居た森とはまた違った暗さだ、とオスカー・ローレストは呟いた。可視光線だけでなく、光という光を全て吸収しているのだろうか。ならばこの迷宮に使われた魔石とやらは、相当高性能に違いない。
「は、鋏が他の猟兵に当たらないように、気配にも気をつけないと、な……」
頼みの綱は野生の勘。裁ち鋏を杖代わりに、壁伝いに進む。小柄な方とはいえ、オスカーの身の丈程もある鋏の刃が仲間に当たれば危ない。周囲の気配を探りながらの歩みは極めて慎重だ。
勘に従えば、恐らくこの道は先行した猟兵が通った後だろう。その時、不意に声がした。
「誰かいるのか?」
びくりと身体を強張らせたが、すぐに仲間だと気付き胸を撫で下ろす。
「お、俺は……猟兵、だ。か、壁伝いに……ここまで、きて」
「ああ、僕と一緒だ」
テトもまた胸を撫で下ろし、一緒に行こうかと誘う。
「そ、それなら、俺と……場所、代わって……おくれ、よ。俺、が、先を行く」
「いいのか? ありがとう」
万が一にも鋏が当たれば危ないから前を歩きたいとオスカーが申し出れば、テトは快く場所を譲る。壁から手を離さぬように気を付けながら交代すると、オスカーは少しばかりむずがゆいような感覚を覚えた。
(「……ありがとう、か……」)
オスカーは故郷の昏い森よりもなお暗い闇に居ながら、不思議と気持ちは明るくなったような気がした。テトはテトで、手探りの行軍が面倒臭くなり始めていた頃合いに現れた同行者を、心底歓迎していた。左手を食料カバンに入れ、何やらごそごそと漁っている。
「お腹すいてないか? これ、良かったら」
オスカーは鋏を抱えたまま、どうにか背後に手を伸ばす。二度三度空振りはしたものの、掌に円い何かが乗せられた。
「……マカロン……?」
「何味かわからないけどな」
僅かな逡巡の後、オスカーは闇の中で顔を隠す必要などない事に思い至り、面布を外すとそっと口に運ぶ。さっくりとした歯触りの後、じわりと染み出すような甘味。
「……ピスタチオ」
「当たりだ! おすすめなんだ」
「……ん。おいしい……ね」
「期間限定のもあるんだ――が、こう暗いとどれだかわからないな」
テトの思案する様子が伝わってきて、オスカーは思わず口元が緩む。
「ま、まるで……闇鍋、のようだね」
「闇鍋か。それもおいしそうだ」
食べ物を粗末にするような楽しみ方なら勘弁願いたいが、普通に食材を持ち寄る分には楽しそうだ、とテトは頷いた。
なんだかんだと言葉を交わし、時折甘味での休憩を挟みながら、二人は着実に攻略を進めていく。多少の時間は掛かれど、スペシャル・ライターが目論んでいたような過酷な旅にならなかった事は間違いないだろう。
成功
🔵🔵🔵🔵🔴🔴
 木常野・都月
木常野・都月
最近、野生の狐から妖狐として生活が変わって、字を覚え、本を読むようになった。
本は面白い。
まだ難しい本は読めないけれど…俺が体験した事がない不思議な事がいっぱい書いてある。
でも…学園に通う、幼いヒトの子達には、こんな酷い物語に関わって欲しくない。と思う。
まずは1つ目の『常闇の迷宮』か。
狐は夜目も効く。[暗視]で見えるかどうか…
夜目があまり効かないような状況なら、闇の精霊様や風の精霊様に、周辺の状況を教えて貰いたい。
加えて、野生だった頃の特技だった嗅覚・聴覚など…[野生の感][第六感]を積極的に使って迷宮を進みたい。
闇。視界を幾重にも覆ったかのような、完全な黒。故郷の森も月の無い夜は暗かったが、このように不自然な闇では無かったはずだ。夜目が利くはずの狐ですら、目を凝らしても数センチ先が見えるかどうかといった状況に、木常野・都月は素直に精霊に頼る事にした。
「闇の精霊様、俺の前に障害があれば教えてください。風の精霊様、空気の流れをご教示ください」
精霊の声に耳を傾け、静かに踏み出す。何も見えずとも、共に歩んでくれる存在があるという実感は、恐らく何よりも心強い。
「学園に通う、幼いヒトの子達には……こんな酷い物語に関わって欲しくない」
もしも防ぐ事が出来なければ。もしこの状況に置かれたのが、精霊を伴って進む自分でなく、生徒達だったら。そう思うと、表情に出す事は無いものの、心優しい妖狐は胸を痛める。空気の流れに従い、右折した所でぽつりと零す。
「――本は面白い」
長い間、狐として野に生きてきた都月は、字を覚えてから日が浅い。難解な本はまだ読めないものの、それでも本の楽しさは知っている。
「俺が体験した事がない不思議な事が、いっぱい書いてある」
例えば氷に覆われた世界。常夏の島国。遥か空の彼方。たくさんの狐にまつわる民話や伝説。猟兵になってから様々な世界に赴くようにはなったけれど、まだこの目で見ていない風景は、それこそ星の数ほどある。本は知識の宝庫であり、最高の娯楽だ。
「……声」
ピンと立った両の耳が、ふと小さな音を拾った。精霊のものではない、誰かの歌声。
「匂い」
誰かが何かを食べたのだろうか、甘い香りが残っている。視覚を奪われようと、野生の名残が先行した猟兵達の痕跡を拾う。追跡の技能を持つ都月は、少しずつ濃くなっていく猟兵達の気配を感じ取る。ゴールはもうすぐだ。
精霊達に礼を言い、真っ直ぐに前を向く。
「本は、ヒトの子達の未来を奪うものではないんだ……」
成功
🔵🔵🔴
 ロイド・テスタメント
ロイド・テスタメント
【WIZ】※アドリブ歓迎
心情:
地図は完璧に覚えてきました。
『闇』は恐れてはならない、光があるからこその闇でしょう?
私もまた『闇』の住人、つまり暗殺者ですから恐れは一切ありません。
行動:
「光を奪う事をしてまで闇に拘っている様ですね」
感覚を失わぬように、一定の間隔で十字架を揺らす。
そして、歩調もそれに合わせて歩き進む。
(本職がこの様な形で役に立つとは思いませんでした)
お守りを握り締め【第六感】と【暗殺】をフル活用して、自分を身体の感覚を失わない様に。
「視覚を奪われても、音や進むべき方向は見失いません」
物語を紡ぐモノの通りには、絶対させたくありません。
私の物語は、私で決めるモノですから。
常闇の迷宮を、音も無く淡々と進む者が居た。手で探る事も無ければ、何かに誘って貰っている様子も無い。日の下を歩くのと何ら変わりなく、背筋を伸ばし、顔を上げ、彼はただ自分の足で歩む。その品のある所作は、暗黒の只中に居るとは思えぬ程に美しい。
「光を奪う事をしてまで闇に拘っている様ですね」
歩く速度を落とす事なく、ロイド・テスタメントは呟いた。辺りは僅かな光も許さない、一切の闇。徹底的に特殊な素材を敷き詰めた迷宮の創造主には、一種の偏執的な拘りすら感じる。
(「『闇』は恐れてはならない」)
多くの人は闇を恐れる。遺伝子的なレベルで刻み込まれた生存の知恵だ。この迷宮もそれを狙って作られたのだろう。だが、ロイドには恐れる理由が無い。
(「光があるからこその闇でしょう?」)
ましてや彼は『闇』の住人だ。暗闇を恐れるようでは、暗殺稼業は務まらない。さりとて慢心するでもなく、常闇を進む上で必要な対策は講じてきた。
「視覚を奪われても、音や進むべき方向は見失いません」
ゆら、ゆら。彼の手元では、黒いカサブランカの意匠が凝らされた十字架が、振り子のように揺れている。その揺れは目に見えずとも、空を切る微かな音を、鋼糸を伝う振動を、ロイドの感覚は拾っている。
目を開けていればどうという事はない歩行も、目を瞑った途端に真っ直ぐ進む事すら困難になるものだ。空間識失調を警戒し、自身の身体の隅々にまで意識を巡らせる。平衡感覚さえ保てれば、あとは記憶した地図通りに進むだけだ。
(「――本職がこの様な形で役に立つとは思いませんでしたが」)
この先に待ち構えるオブリビオンに思いを馳せ、物語を紡ぐモノの思い通りになど絶対にさせるものかと心に誓う。
「私の物語は、私で決めるモノですから」
成功
🔵🔵🔴
 木鳩・基
木鳩・基
都合よく書き換えて作った話ねぇ
私もつまんないと思うなぁ
「噂」の話になるけど、結局自然に広がってる話が集めてて面白いんだし
とにかく、進んでみるけど……
くらっ! 完全に黒一色じゃん
そういえば、視界の悪い状況の怖さは、自分がどこにいるか分からなくなることだって昔聞いたかも
入口からワイヤーを垂らしていこう
辿ればいつでも戻れるし、ガンガン進むしかないな
ワイヤーが足りるか不安ではあるけど、【勇気】があれば関係なし
足りなくなったら進み方を記憶して、巻き上げてから再出発だ
……そういや私も「組み換えて戦う」のが基本だし、あんまりとやかく言えないか
だったら、どっちの想像力が上か、ぶつかり合いだな
アドリブ・連携歓迎
「おっと、こっちは行き止まりかぁ」
ぺたりぺたりと壁を触り、木鳩・基は口を尖らせた。だがどうという事はない。間違っているのなら、戻れば良いだけだ。然して気にする風でもなく、基は手元のワイヤーを手繰る。
「くらっ! 完全に黒一色じゃん」
分岐点まで戻り、先程自分の来た道を見やれば、明るかったはずの迷宮の入り口すらも見えない。改めてワイヤーを伸ばし、垂らしながら進む。
「視界の悪い状況の怖さは、自分がどこにいるか分からなくなることだ――ってな」
霧や雪による視界不良は、遭難の大きな原因だ。それもこうしてしるべを残していけば、少なくとも迷う事はない。
「昔誰かに聞いたような……誰だっけ?」
ぽつりと零れたのは小さな疑問。無意識のうちに帽子に付けられた鳩のバッジを撫ぜ、まあいいかと前へ進む。
「……それにしても、都合よく書き換えて作った話ねぇ」
少し細い通路を直進しながら、最奥に待つオブリビオンの事を考える。
「私もつまんないと思うなぁ」
噂に限った話ではあるが、自然に広がっていった話を集めるのは面白いと基は思う。話し手に因るものか、土地柄に因るものか、広まるにつれて全く違う結末を迎える噂話もあれば、遠く離れた地域で同じ噂が流れている事もある。中には辻褄の合わないものもあるが、不完全だからこそ面白いものもあるのだ。
完璧な物語は文学的な価値は高いのかもしれないが、果たしてその『修正』は必要な事なのだろうか。
「……そういや私も『組み換えて戦う』のが基本だし、あんまりとやかく言えないか」
足りなくなったワイヤーを巻き上げながら、独り言つ。かの作家のように他者を弄る真似はしないが、再構築という点で見れば似ているかもしれない。
「うん、順調順調」
綺麗に巻き取れたワイヤーを触り満足気に頷くと、軽い足取りで再び歩き出す。に、と口元に笑みが浮かんだ。
「どっちの想像力が上か、ぶつかり合いだな」
成功
🔵🔵🔴
第2章 冒険
『幻惑の回廊』

|
POW : 自ら痛みを得るなど気合いで通り抜ける。
SPD : 目を瞑って進むなど視覚に頼らず通り抜ける。
WIZ : 模様を解析するなど要所を見ずに通り抜ける。
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴
|
常闇の迷宮を抜け、次の階層の扉を開いた猟兵達の目に飛び込んできたのは、一面に奇妙な模様のある通路だった。この模様が『怖いもの』の幻覚を見せる暗示とやらに関係があるのかもしれない。
とはいえ壁、床、天井。隙間なく刻み込まれた模様から目を反らすのは容易ではない。ならば『怖いもの』の幻覚に、どう対処すべきか。猟兵達は考える。
ふと思う。
――そもそも自分の『怖いもの』とは何だろう?
 コイスル・スズリズム
コイスル・スズリズム
POWアドリブ歓迎
すずが怖いもの
ある日突然それこそ魔法が解けたように
魔法学園でのこの日常がなくなって
元のアース世界の、ただの一学生だった自分に戻ること
見せられる幻影と悪夢に正面から歩く
以前にも見た悪夢だ
こういう時にはきまって
テレビウムグミを袖から取り出して齧る
コーヒー味はもうただのフレーバーじゃない
コーヒー「ハウス」フレーバー
仲間との家の味が込められてる
大事なものが増えると怖いものが増える
だったら全部、全力で
「全力魔法」を試しに何もない場所に放ってみる
怖いものはいつだって怖い
私は
全部
受け止めて
痛みごとそれが見合う靴跡を作り続けるよ
…幻影って魔法学園っぽくてちょと安心する。
変かな、ライターさん。
終業のベルが鳴る。はたと我に返り辺りを見回せば、次は移動教室だっただろうか、生徒達は教科書を手に部屋を出ていくところだった。机の上に視線を移す。『現代社会』と書かれた教科書を机の中にしまう。――現代社会?
「あれ、行かないの? なぁに、たった今、夢から覚めたみたいな顔して」
心配そうに声を掛けてくるクラスメイトに、コイスル・スズリズムは背筋に冷や水を掛けられたような感覚を覚えた。
――夢から覚めた?
そこで気付く。ここがアルダワ魔法学園ではなく、アース世界の学校である事に。
(「違う。あの日々は夢じゃない。夢になんてしない」)
立ち上がり、幻影の教室を歩く。
「えっ、どこ行くの? 次の授業は……」
自分を何処かへ誘おうとする幻覚に背を向け、コイスルは自分の意思で歩く。
(「以前にも見た悪夢だ」)
周囲の生徒達が着ている制服ではない、自身の服の袖からお菓子を取り出した。パッケージは一見するとこの学校の売店でも買える輸入菓子と似ているが、そのフレーバーは唯一のもので。一粒取り出し、口の中に放り込む。
(「大事なものが増えると、怖いものが増える」)
ふにふにと頼りない食感の、だが確かに仲間達と過ごした日々の証左がここにある。目の前には平凡な日常が広がっているが、どちらが現実なのか、コイスルには瞭然としていた。
「だったら全部、全力で」
偽りの平和を甘んじて享受するには、大切なものが多すぎる。いつまでもこの虚構に囚われているわけにはいかないのだ。この手で、この声で、この魔法で。少女は幻影を破壊する。
彼女の放った魔法は偶然ではあるが、いみじくも壁画の一部を削り取った。暗示を成さなくなった壁を見やり、ぽつりと零す。
「……幻影って、魔法学園っぽくてちょっと安心する」
災魔の潜む迷宮で、平穏とは程遠い、それでも大切な日常を実感する。
(「――怖いものはいつだって怖い。私は全部受け止めて、痛みごとそれが見合う靴跡を作り続けるよ」)
成功
🔵🔵🔴
 テト・ポー
テト・ポー
……怖いもの、かあ。
昔はそんなになかったけど、今の僕が怖いものって、なんだろう。やっぱり、「食べられなくなること」……いや、「食べないこと」かなあ。
頭がふわふわして、なにも考えられなくなって……
悪い思い出という訳じゃないけど、今となっては、そうなるのが恐ろしい……
ああ、そうか。僕が怖いのは「死」だ。僕も、誰かも、それ以降ごはんを「食べられなくなる」し。
でも、「死」の幻覚にどう抗うんだろう?
……いや、気合いでなんとかなるんじゃない?
【食料カバン】にはまだまだたっぷりごはんあるからね。
UC「空腹の充足」で身体を強化して、フライドポテトでも食べながら行こうかな。
きっと大丈夫。食べれば死なない!
「……怖いもの、かあ」
テト・ポーはぼんやりと考えてみるが、正直な所、心当たりは多くない。それこそホラー映画にそこまで心を動かされる事もなく、怪奇小説に至っては恐怖よりもページを捲る面倒臭さが勝ってしまう程度には。
「やっぱり『食べられなくなること』……いや、『食べないこと』かなあ?」
『ごはんを食べるためだけに生きている』とはテトの言。人生における楽しみであり、猟兵としての原動力。
「……ん?」
ふわ、とバターの香りがした。匂いを辿るようにそちらに首を向ければ、湯気の立つじゃがいもが置かれたテーブル。溶けたバターが黄金色に輝いている。
あまりにも怪しいと思いつつ、興味本位で手を伸ばしてみれば、テーブルは近付いた分だけ遠ざかっていく。
「怖いというより、嫌がらせ?」
首を傾げたテトは、次の瞬間ひゅうと息を飲んだ。
「えっ……これ、僕の腕
……?!」
伸ばした手は自分のものとは思えぬ程に痩せ細り、皺が寄っていた。まるで老人だ。人間を模した自身の肉体が、酷く痩せ衰えている。
「ああ、そうか。僕が怖いのは……」
――『死』だ。訪れたら最後、もうごはんを『食べられなくなる』事象。
これを繰り返されるのか。飢える幻覚に苛まれながら歩む回廊は、想像するだけでげんなりとする。
「……いや、僕にはこれがある!」
テトは携えた食料カバンを開けた。食べられないとわかっている幻覚の食事なぞに手を出さずとも、ここにはたっぷりとごはんがある。
「いただきまーすっ」
選んだのはテトの好きなじゃがいも料理、フライドポテトだ。少しばかり湿気た食感でも、濃い目の塩気で美味しく食べられる。
「でも、帰ったら揚げたても食べたいな。かりっとした歯ごたえにほっくほくのじゃがいも……」
気合が幻覚に打ち勝ったのか、それともテトのユーベルコードの効力か。いつの間にか肉体もいつも通りの彼に戻り、幻覚に惑わされる様子もない。
「きっと大丈夫。食べれば死なない!」
大成功
🔵🔵🔵
 木常野・都月
木常野・都月
俺は昔の記憶がない。
猟兵になったのもつい最近。
まだ怖いものはない。
そう思って踏み出して。
あった。1つだけ。
血の気が引いた。
野生だった頃の…狐狩り。
犬、人、馬。
それ自体は怖くない。
でも銃が揃うと、走り続けなければ。
朝から晩まで。
猟犬の鼻と銃が追ってくる。
逃げる先には、人の仕掛けた罠。
森の強者、狼や熊も罠には勝てない。
集中して罠を避け、日が沈む、さらに向こうへ。
そこは別の生き物の縄張り。
気力・体力が尽きた状態で、天敵の縄張りに入れば命はない。
疲れて動けなくても、安全な場所を探さないと…
狐狩りは…嫌だ…
尻尾がキュッと丸まる。
震えて…杖を握って…
…杖?
そうだ…俺は…妖狐…猟兵だ…
尻尾、しっかりしろ。
「怖いもの……」
木常野・都月は自身のルーツを知らない。気付いた時には狐として生きていたし、自分が妖狐である事を知らなければ今も狐として生きていたかもしれない。猟兵として経験を積み始めたとはいえ、怖いものと言われてもピンとくるものが無い、というのが正直なところだった。
回廊へと一歩踏み出したところで、身の毛がよだつ感覚を覚えた。さわさわと鳴る木々。湿った土の匂い。全てが懐かしく、慣れ親しんだ故郷の森の風景だとはっきりとわかる――が、今は。今、近付いてくるこの気配は。
走る。直後、自分の居た場所の地面が銃弾に抉られた。背後から聞こえるヒトの舌打ちと、馬の蹄。
(「狐狩り
……!」)
ヒトや馬が速く走れない、足場の悪い道へと逃げ込むが油断は出来ない。何故ならば、
(「……来た!」)
進路に回り込むように、犬が割り込んだ。牙を剥いた口が嫌に生臭く感じられる。都月は近くの太い幹に爪を喰いこませて駆け上がり、古木の向こう側へと逃げる。背後では飼い主を呼んでいるのだろう、猟犬の声が引っ切り無しに響いている。
「ガルルッ!」
(「しまった、熊の縄張りに――」)
ぴょんと跳ねるように草むらに飛び込み、ひたすらに走る。追ってくる様子の無い熊を怪訝に思い振り返れば、足に鉄製の罠が喰い付いているのが見えた。
(「森の強者も、罠には勝てない……」)
一刻も早く安全な場所を見つけなければ。不安からか、都月は杖を掻き抱いた。
「……杖?」
杖。それを持つ手は当然の事ながら、銃を振りかざすあのヒトと同じ形をしていて。
「そうだ……俺は……妖狐。――猟兵だ」
知恵だけで逃げ回らねばならない狐ではない。戦う力を持つ者だ。縮こまるように体に張り付いた自らの尾を叱咤する。
「尻尾、しっかりしろ……!」
前を向く。ゆら、と大きな尾が悠然と揺れた。大自然の幻影は未だ小動物を嬲るように広がっているが、都月は逃げる事なく真っ向から立ち向かっていった。
成功
🔵🔵🔴
 ロイド・テスタメント
ロイド・テスタメント
【SPD】
※絡み、アドリブ可
心情:
見えるモノだけが、恐怖の全てではなく……見えないモノの方が最も恐ろしい。
殺す側としては、それを良く知っております。
行動:
困っている猟兵がいたら、手を差し出して手助けをします。
「一人で進むよりマシでしょう? 視覚的恐怖ならば、見なければ良いのです」
【第六感】と【暗殺】の経験を活かして、聴覚や風の流れを肌で感じながら進みます。
(見た目の恐怖は一時的なモノであって、誰かの歪んだ心や思考はオブリビオンと似ていますね)
こんな簡単な方法で防げるならば、本当の恐怖を知っている身としては容易い。
恐怖を与える模様に興味はありますが、一切見ないまま出ます。
「甘い、考えでしたね?」
「視覚的恐怖ならば、見なければ良いのです」
本来迷宮を前にして何の衒いも無く言える事ではないのだが、今回ばかりはこの罠を考案した者も『相手が悪い』と観念せざるを得ない。現にこのロイド・テスタメントは視覚を要さずに罠の一つを突破してきているのだ。目を瞑り、回廊へと踏み込む。
――ぞくり。
「……なるほど、これはこれは。せいぜい扉を開けた時の一瞬だけでしたが、視界に入ったのでしょうか。なかなか強烈な暗示のようですね」
目を閉じている以上、幻覚は無い。ただ、『悪意の篭った視線』や『憎悪の念』、そして『殺気』。そういったものに晒された時の感覚が、ロイドに纏わりつく。
「見えるモノだけが、恐怖の全てではなく……見えないモノの方が最も恐ろしい。ええ、殺す側としては、良く存じております」
暗殺者として研ぎ澄まされた神経が、敏感に殺気を察知する。だが、ロイドにとっては取るに足らない事だ。
「先行した猟兵は、無事に抜けたようですね」
それこそ博愛主義的な一面を覗かせる程度には。幻惑の中に放り込まれてなお他者を案ずる余裕を見せるロイドは何処までも泰然自若として、周囲の音と肌を撫でる風を頼りに回廊を進む。
(「こんな簡単な方法で防げるならば、本当の恐怖を知っている身としては容易い――」)
どれだけ害意を模倣しようと、彼は周囲に人の気配が無い事も知っている。実体の無い殺気を向けられた所で、怯えようがない。暗示が上書きされる事も無く、ロイドは次第に幻惑の効力が薄れていくのを感じる。
「正直、恐怖を与える模様に興味はありますが」
幾許かの好奇心の為に無駄な時間を費やす事もあるまいと歩みを進め、空気の流れが変わった所で立ち止まる。手を伸ばせば、扉の取っ手が触れた。回廊の出口だ。
「甘い、考えでしたね?」
投げかけられた言葉は、迷宮の創造主に宛てられたものか、それともこの先に待つ作家に向けられたものか。小さく笑みを浮かべ、扉に手を掛けた。
成功
🔵🔵🔴
 オスカー・ローレスト
オスカー・ローレスト
【怖いもの:殺人鬼としての自分。獲物を仕留めた感触を心底楽しむ、隠したい、殺人鬼の、自分】
【SPD】
よ、良かった……あの暗い所からちゃんと、抜け出せたみたい、だ(一瞬ホッとした表情になる、が
……(見えたものにひゅっ……と息を飲む)
……ち、違う、違う……俺、俺は、そんな事全然、楽しく、なんて、思って、ない……!!
確かに、何度かの戦いで、相手を射抜いた時、顔が引きつってた気はする、けど……でも(自分が浮かべた引きつった笑み、僅かでも確かに感じる歓喜を思い出すも否定する小雀)
は、早くこんな場所からは出ない、と……逃げ、ないと……(【逃げ足】使用)
一刻も早く、ここから、離れる事だけ、考え、る……
「よ、良かった……あの暗い所からちゃんと、抜け出せたみたい、だ」
急に視界が開けて一瞬目が眩んだが、幸いにも扉の向こうは薄暗い森だった。これならばすぐに目が慣れるだろうと思ったのも束の間、オスカー・ローレストはそれが異常だと気付き顔を上げる。
「え、なんで、森に」
地下迷宮には奇妙な空間が多数存在する為、扉の向こうが山だろうが海だろうが驚きはしないが、予知では『回廊』だと聞いていた。それに、ここは。
「な、なんで……っこの森、にっ」
あまりにも見慣れた場所だった。昼だというのに薄暗く、時折霧や靄が立ち込め、何処となく陰鬱で、――姿を隠し、待ち伏せるには最適だった。かつてオウガに支配されていた、忌まわしき地を見紛うはずがない。
そして目の前には、哀れな被害者(ロビン)が横たわっている。
『誰が駒鳥殺したの』
「……っ」
誰かに問われた気がして、口を開く。だが欷泣するオスカーの声は音にならず、ひゅうと喉が鳴るばかりだ。碧落を滲ませる水の膜が決壊し、じわりと面布へと染み込んだ。
(「俺の弓で、俺の矢羽で」)
「……ち、違う、違う……俺、俺は」
言い訳をしたいわけではない。殺したのは自分に違いなく、それは認めている。ただオスカーは哀れな獲物(ロビン)を見た時に生まれた薄暗い愉悦を、ようやく絞り出した声で否定する。
「俺は、そんな事全然、楽しく、なんて、思って、ない……っ!」
怖いものは自分自身。当然望んだ配役では無かったし、本当は救いたかった。だというのに、標的を射抜く度に心の奥底で歓喜に震える自身を自覚させられる。誰にというわけではないが、薄布一枚では心の内を見透かされてしまいそうで、オスカーは歪む口元を手で覆った。
「は、早くこんな場所からは出ない、と……逃げ、ないと……」
一刻も早く離れなければ。犠牲者の幻影に背を向け、オスカーは走り出す。ずきり。小さな羽の古傷が、僅かに痛んだ気がした。
成功
🔵🔵🔴
 木鳩・基
木鳩・基
怖いものなぁ
今居る人と、永遠に話せなくなることかな
母さんとか他の親戚とか、学校のみんな、組織の人たちや仲間の猟兵も
消えられること自体は、そんなに怖くないと思う
残り香を残して消えた後の、無音がきっと怖い
普通の毎日が崩れて残骸だけ佇まれたら……そりゃゾッとするわな
でも、今の私はそんなに非力じゃない
壁と床を触ってピースに変換、大砲の大きな砲撃で我に返る
これ、体感的にはどう映るんだろ
日常の残影に触れてることになるのか?
まぁ、触ることさえ忘れなければ大丈夫だろ
空元気でもいいから、自分を【鼓舞】して切り抜ける
私としても、これ以上無くしたくないんだよ
死人に口なしって言うじゃん?
話はみんなでした方が面白いしね
「怖いもの、なぁ」
そう呟いた木鳩・基の脳裏に浮かぶのは、見知った人たちの顔だ。母を始め、親戚、学校の友人や教師、UDC組織の人たちに仲間の猟兵。
「……今居る人と、永遠に話せなくなることかな」
ぎぃ。回廊の扉を開き、中に踏み込む。
「え?」
基が立っていたのは、自宅の居間だった。大きな窓から差し込む光が、自分を温かく照らしている。奥のキッチンに目を向ければ、直前まで煮込まれていたのだろうか、鍋から濛々と湯気が上がっている。
「母さん?」
傍らには盛り付ける為の皿まで用意されているというのに、母の姿は無い。家の中に人の気配を感じられず、外に出る。
「そっか、怖いのは消えられること自体じゃなくて――」
友人の家の前を通る。庭の向こうにリビングが見えるが、点けっ放しのテレビだけが嫌に明るく、観ている者が居ない。商店の前を通る。綺麗に商品は並べられているのに、店員も客も居ない。不自然な場所で停止している車に運転手は乗っておらず、公園には持ち主の居ないボールだけが転がっている。
――無音。
「普通の毎日が崩れて残骸だけ佇まれたら……そりゃゾッとするわな」
人が居ないのに営みの痕跡だけが生々しく残っている。ただ一切合切が消え失せるよりも異様で、不気味とでも言うべきか、ある種の不快感を抱かせる。
「でも、今の私はそんなに非力じゃない」
それは自身への鼓舞。凝然と立ち尽くしていた基は、そっと屈んで地面に触れた。彼女が触れた所から光の線が走り、地面から壁へ、空へと伸びてゆく。亀裂というには整然としたそれは、日常の風景を切り分け、やがてパズルのピースと化した。
「私としても、これ以上失くしたくないんだよ」
パズルは基の意のままに組み上がり、大砲を形作る。轟音と共に撃ち出された砲弾が、日常の幻影を打ち砕いた。見知った風景がぱらぱらと崩れ、その下から一部を抉り取られた迷宮の壁が顔を覗かせる。
「話はみんなでした方が面白いしね」
回廊の先に、扉を見つけた。仲間達はきっとあの向こうだ。
大成功
🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『スペシャル・ライター』
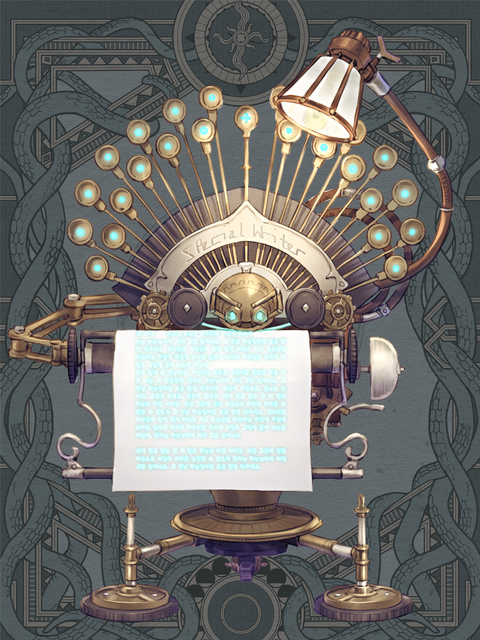
|
POW : 修正箇所
【修正箇所を確認する目の青白い光】が命中した対象にルールを宣告し、破ったらダメージを与える。簡単に守れるルールほど威力が高い。
SPD : 印字作業
【26個のキーから青白い光】を放ち、自身からレベルm半径内の全員を高威力で無差別攻撃する。
WIZ : より良い作品を
対象のユーベルコードに対し【正確に全く同じユーベルコード】を放ち、相殺する。事前にそれを見ていれば成功率が上がる。
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴
|
かたん。かたかた。
広い部屋の中央で、『スペシャル・ライター』は物語を綴っていた。レトロな音が響く中、妙に近未来的な青白い光が紙上に文字を綴り、何ともちぐはぐな光景だ。
『嗚呼』
声と呼ぶにはあまりにも機械的だ。人の声を模した音が、作家から発せられた。
『嗚呼、ト我ハ言ッタ。ソレハ物語ヲ壊サレタ事ヘノ嘆キ、或イハ無粋ナ猟兵トイウ存在ヘノ憤リ』
かたかた、かたん。
『コノ物語ニ猟兵ハ不要ダ。故ニ、我ハ告ゲル。貴様ラヲ排除スル、ト』
 コイスル・スズリズム
コイスル・スズリズム
POW
アドリブ大歓迎
袖の中から取り出すは
12個ぶん「物を隠す」してたドラゴンランス
これね、この日のために、あなたのために用意したの
ねえ、
あなた
に
飛んでいく、この、すべてのランスが奏でるアドリブの音楽は
“ソレ”
どんな物語の歌詞付けたら収まるんだと思う?
私のドストレートなエフェクター抜きな音と
あなたの修正で、セッションしましょ
ガッカリさせないでね、“さっきの悪夢分”
全力魔法を込めた【UC】で攻撃
相手POW:アドリブねと笑い演じながら上述の攻撃。卑猥なものはNG
相手WIZ:やっぱ面白いわ、私の攻撃は。
でも、同じUCでも込めた思いが違うね。あと全力魔法が
防御は「見切り」の後、12ランスでの「武器受け」
 テト・ポー
テト・ポー
やあやあ、あなたが親玉か。
いろいろ言いたいことはある気がするけど、面倒だからひとつだけ。
おいしいごはんを害する気なら、神が許しても僕が許さないからな!
UC「暴食の飢餓」で自分を強化して、飛び回りながらちょっとずつダメージを与えていくよ。
敵の注意を逸らせるならそれがベストだけど、無茶はしない方向で……
でも、ほかの人をかばえそうならなるべくかばっていきたいな。その分攻撃のチャンスは増える……よね。
宣告されたルールにはある程度なら従ってもいい……かな?
当然「人に危害を加える」みたいな面倒そうなのは従わないけど。
そして、「食べ物を粗末にする」系のルールなら話は別だし、何があっても一撃ぶん殴ってやる!
ひらりとローラーから離れた紙がテト・ポーの足元に落ち、彼は何気なくそれを拾い上げた。
「やあやあ、あなたが親玉か」
ぢっ、ちちちち。テトの声に反応するように、青白い光が猟兵達に向く。生き物であれば目に相当する部分のようだ。頭から爪先まで過ぎった光は、値踏みをするような視線とでも言うべきか。実際にはスキャナーで読み取られているような印象ではあるが。
『原稿ガ汚レルノヲ見タ我ガ、不快ニ思ッタノハ致シ方アルマイ。貴様ニるーるヲ告ゲヨウ。<食ベルナ>』
先程食べていたフライドポテトの油だろう。テトが少し指をずらしてみれば、紙に小さなシミが出来ていた。
「……いろいろ言いたいことはある気がするけど」
汚れるのを厭うならば、床に放置するのはいかがなものか、だとか。それでもテトは律義に原稿を床に戻し、たべもので膨れたカバンから目を逸らす。
「面倒だからひとつだけ。おいしいごはんを害する気なら、神が許しても僕が許さないからな!」
テトの宣言に、作家は返答の代わりに目から放つ光で攻撃した。後方に飛び退いたテトの居た場所に、レーザーを撃ち込んだような焦げ跡が残る。
「ねえ」
ちょっと道でも尋ねるかのような調子で声を掛けたのはコイスル・スズリズムだ。手品でも披露するかのように悪戯な笑みを浮かべ、大きく広がった袖を見せつけるように掲げると、ひょこりとドラゴンが顔を覗かせた。
「これね」
一頭、二頭。コイスルの袖からドラゴンが飛び立つ。
「この日のために、あなたのために用意したの」
五頭、六頭。リボンを巻いてめかしこんだドラゴンや彼女の庭で遊んでいたのだろうご機嫌なドラゴン、それぞれ個性豊かな面々が、宙を舞い踊る。
「あなたに飛んでいく、この、すべてのランスが奏でる音楽は」
全部で、十二。コイスルを取り囲むように浮遊するドラゴンが、竜騎士の槍へと変貌した。
「――『ソレ』。どんな物語の歌詞付けたら収まるんだと思う?」
ドラゴンを愛でるように傍らの槍を撫で、コイスルが小首を傾げる。
『我ガ物語ニ必要ナ演出デハ無イ。<歌ウナ>ト、我ハ猟兵ニ言ウ』
「あら、意地悪なのね」
ならここからはアドリブね、と微笑んだ彼女が動くより先に、作家の目が光る。だが、その攻撃が彼女に届く事は無かった。
「危ないな」
コイスルと作家の間に割って入ったテトが、む、と口先を尖らせる。攻撃を受け止めたのだろう、フォークからしゅうしゅうと煙が出ている。
『貴様、何処カラ』
「上から、かな?」
作家の攻撃をひらりと跳んで躱す。否、彼は『飛んで』避けていた。
「それがルールだから従う。従うよ? でも……おなかすいた!」
ガン、と音がした。テトが作家を背後から殴りつけた音だ。前方で飛翔していたはずの彼が何故、と作家が疑問を口にすると、テトは不満を爆発させる。
「君が言ったんじゃないか、食べるなって。わかるでしょ、この空腹を!」
空腹感に比例した戦闘力の増強。食べる事によって力を得るはずのフードファイターが空腹によって力を得るなど、作家にも想像がつかなかったようだ。右から左から、テトの拳が作家を襲う。
「ふふ、いい音。私も仲間に入れてちょうだい?」
テトとやり合うだけで手一杯といった様子の作家に、コイスルは槍の切っ先を向けた。
「私のドストレートなエフェクター抜きな音とあなたの修正で、セッションしましょ」
十二の槍が一斉に降り注ぐ。射出武器さながらの速度で四方から飛来するそれは、降るなどという表現では生温いかもしれない。コイスルの槍はテトを避け、吸い寄せられるように災魔のみに直撃する。
「ガッカリさせないでね、『さっきの悪夢分』」
ヂィ……ンッ! シュッ。
槍の一つが改行を促すベルに当たった。条件反射的に、キャリッジリターンが行われる。――行われてしまった。
『……何トイウ事ダ……』
不要な改行。全て計算し尽くされていた文章に出来た、不自然極まりない改行が、完璧を自称する作家の自尊心を傷つける。
『アアアアアア!!』
瑕瑾なく綴られていた物語の崩壊に、作家の悲痛な叫びがこだました。
成功
🔵🔵🔵🔵🔴🔴
 木常野・都月
木常野・都月
学園の子供達の読者のために。
問答無用で倒したい。
物語のために現実を捻じ曲げたって面白い物語にならない、と俺は思う。
誰かのためを想って書かれるから、ヒトは物語を読んで感動するんだ。
だから、書き手は凄く大変だと思う。
でも、だからこそ。
その先に、産み出した作品の一文に、救われるヒトもいると、俺は思う。
UC【精霊の矢】を雷の精霊様の助力で使用。
とはいえこれは相手に相殺されてしまうかも…
なので、こちらが本命。
[全力魔法]を乗せた雷の[属性攻撃]で攻撃をしたい。
仮に。
相殺で競り負けてたり、相手から攻撃が来るようなら[野生の感][逃げ足]で回避したい。
逃げ切れないようなら[オーラ防御]で致命傷を避けたい。
 ロイド・テスタメント
ロイド・テスタメント
※アドリブ、連携可
これは、良くも悪くも私の物語です。
だから、駄作と言われようが紡ぎ続けるだけですよ。
戦闘:
【真の姿】
「失礼致します。さぁ、楽しませてくれ、御主人様」
『礼儀作法』で優雅に敵に向かって言います。
UCで攻撃力下げ、敵のUCが発動したら鉄の処女で『武器受け』しつつ『第六感』で回避できるものはする。
「おや、御主人様。本日の進捗率が悪い御様子で」
『暗殺』で影から『咎人の双剣』を『投擲』する。
『罠使い』で鋼糸を足元に仕込み掛かったら『部位破壊』だ。
「物語にはイレギュラーな存在が必要、だろう?」
執事の立ち振る舞いは変えずに。
「さぁ、御主人が紡いだ物語は全て、無へ……」
決められた物語は嫌いです。
「失礼致します。さぁ、楽しませてくれ、御主人様」
一礼。見惚れる程に洗練されたロイド・テスタメントの慇懃な挨拶も、物語にけちを付けられて怒り狂う作家には届かない。孔雀の羽のように突き出たキーが、青白く光る。
「おや、御主人様。本日の進捗率が悪い御様子で」
『猟兵サエ居ナケレバ、滞リナク書キ終エタモノヲ、ト。我ハ遺憾ニ思ウ』
作家から放たれた光は横殴りの雨のように宙を走った。かたかたと鳴る打鍵音も激しさを増し、雨音のようだ。ロイドはニュルンベルクの乙女を盾に光の驟雨を凌ぎ、紅い双剣を繰りながら隙を伺う。
「……物語のために現実を捻じ曲げたって面白い物語にならない、と俺は思う」
オーラを纏い、腕輪の展開するシールドの陰で荒々しい雨が過ぎ去るのを待っていた木常野・都月は、学園の子らを想いながら正面の敵を見据えた。そのような事をしてまで些かの瑕疵もない物語を紡いだとして、果たして誰の心を動かすだろう。
「誰かのためを想って書かれるから、ヒトは物語を読んで感動するんだ」
目の前の作家が読み手の事を想っているとは到底思えない。その完璧さへの固執は、最早作家のエゴだ。
「書き手は凄く大変だと思う。でも、だからこそ……」
ちりちりと音を立て、光の粒子が都月へ集う。雷の精霊は彼の想いに応え、矢の形を成した。
「その先に、産み出した作品の一文に、救われるヒトもいると、俺は思う」
閃光。雷を帯びた矢の一つ一つは小さいが、数が集い視認が困難な程に眩く輝いた。しかし、それと同時に同数の矢が作家から放たれる。
『其レハ暗ニ我ガ作品ガ……ツマラナイト言イタイノカ』
光と光がぶつかり合い、ストロボのように瞬く。光の合間で、闇が――ロイドが動いた。都月の耳が、ひゅ、と風を切る音を捉える。
『コノヨウナ光、目眩マシニモナラヌ』
死角より投げられたロイドの剣を、作家は難なく避ける。だが。
「ああ御主人様、お足元に御注意を」
避けた先、石造りの床の上には目を凝らさねば見えない程に細い青があった。ロイドの言葉で作家は漸く足下へと注意を向けるが、既に遅い。青い鋼糸は生き物のように古美色の足へと絡みつき、手枷や拘束ロープと共に作家の自由を奪っていく。
「物語にはイレギュラーな存在が必要、だろう?」
ロイドが僅かに指を動かしただけで鋼糸の拘束は強まり、ぎちぎちと食い込み続ける。そして。
『我ガ物語ニ、貴様ノ存在ハ要ラヌ!』
「いいえ御主人様。これは、良くも悪くも私の物語です」
キン、と軽い音がした。次に、ガチャンと重たい金属の音が響き渡る。とうとう鋼糸が作家を支える足の一本を切断したのだ。
「だから、駄作と言われようが紡ぎ続けるだけですよ。そして、彼は彼の物語を紡いでいます」
災魔の綴る物語の一片になどなってやるものかと、ロイドは柔和な微笑みとは裏腹に、確固たる意志で答える。そのロイドの視線の先では、都月が膨大な数の精霊に助力を乞うていた。
「精霊様、ご助力ください」
極限まで練り上げられた雷の魔法は、まるで小さな太陽のようだ。光球はばちばちと音を立てながら、都月が振るったエレメンタルロッドの動きに合わせ、一直線に作家へと撃ち込まれる。作家は都月の攻撃を目の当たりにしながら、ロイドに捉えられている為に動けない。
「さぁ、御主人が紡いだ物語は全て、無へ……」
ドォオオオンッ!
劈くような爆音が響いた。部屋の中に、粉塵が舞い上がる。
『嗚呼……』
立ち込める煙が晴れると、凹んだ床の中心で焼け焦げた作家が呻いていた。
『マサカ、マサカソンナ』
ごとり。用紙を送る為のローラーが、床に落ちた。
『貴様ラァアアアア!』
室内にあった原稿の尽くが焼失し、新たに給紙する事も叶わない。スペシャル・ライターの物語は、文字通り無へと帰したのだ。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ニニニナ・ロイガー
ニニニナ・ロイガー(サポート)
ど〜も~
要請を受けて参りました、UDC職員のニニニナとドビーちゃんっす。
よろしくっすよ〜
そんなわけで、どんな触手がご入用っすか?
長い触手に太い触手、幅広触手に細触手。
鋸歯つきのゴリゴリ削れる触手にヒトデみたいな手裏剣触手、
ドリル触手に粘着触手に電撃触手その他色々行けるっすよ。
あるいは溶解液を吐く触手とかご所望っすかね?
麻痺触手に毒触手に石化触手になんなら自白用の催眠触手とか…
後は耐熱耐冷耐衝撃触手に再生触手なんかもOKっす。
マニアックな所だと按摩触手に美肌ローション触手、電脳アクセス触手とかも便利っすね。
あ、触手本体は見えないようになってるので、
一般人が狂気にとか気にしないで大丈夫っすよ~。
綴っていた物語を、そして自身のあらゆる部位を破壊された作家が怨嗟の声を上げる中、場違いな程に軽い声が響いた。
「ど〜も~。要請を受けて参りました、UDC職員のニニニナとドビーちゃんっす」
突然乱入したニニニナ・ロイガーに災魔は殺気立つが、彼女は何処吹く風とばかりにへらりと笑い、問う。
「そんなわけで、どんな触手がご入用っすか?」
底抜けに明るい問いかけは、彼女の生来の気質に因るものか、はたまた日々の激務に因る寝不足が引き起こしたものか。何にせよ、ニニニナの飄然とした態度は作家の怒りを買った。
『失セヨ!』
烈々たる打鍵音と共に、青白い光が部屋を満たした。遮蔽物の少ない部屋で放射状に放たれた攻撃は避けるのも困難で、無防備な姿のニニニナに直撃した――かのように見えた。
「ふー……、ご機嫌ナナメっすね」
光が止んだ時、作家の前に佇んでいたのは触手で雁字搦めになったニニニナだった。全身を覆っている為に、肉塊が喋っているように見えなくもない。
「あれっすか。ライターさん、締め切り前ってやつっすか?」
ずるりと解けた耐衝撃触手の下から顔を出した彼女は傷一つ無く、何事も無かったかのように口元を緩め、提案した。
「オイル注してあげるっす」
次の瞬間、スペシャル・ライターの身体を構成するパーツの一つ一つを、油にまみれた触手が這い回る。
『グ……ッ、離セ、ヤメ……』
タイプライターの注油作業が非常に繊細で、専門の技術者が行うべき作業である事を、彼女は知らない。作家の悲鳴ともつかぬ呻きが漏れていたが、ニニニナは満足そうに頷いた。
成功
🔵🔵🔴
 オスカー・ローレスト
オスカー・ローレスト
【アドリブ歓迎】
はぁ……はあ……っ!(ほうほうの体でやってきた小雀
い、一方的に役割を押し付けて、心を書き換えて、作られた悲しい物語なんて……そんなの、許せない、よ……
……うん、だから、お、俺は、戦うん、だ……予知されたような事が今後起きないよう、に(言い聞かせるように。「だから楽しみのために為に戦い殺す訳では無い」と言いたげに。どうやら先程の事を引きずっている模様
き、基本後衛で、敵の攻撃範囲外から戦う、よ。
【切実なる願いの矢】でキーボードを狙って……破壊を試みたい、かな(【スナイパー】、【部位破壊】使用)
「はぁ……はっ……!」
荒い息を整えながら、オスカー・ローレストは作家の正面に立った。迷宮の最奥に至るまでに与えられた苦痛によって顔色は悪く、既に憔悴しきっているようにさえ見える。
「い、一方的に役割を押し付けて」
それでも酷く乾く喉を唾で湿らせ、奮う者は声を上げた。
「こ、心を書き換えて、作られた悲しい物語なんて……そんなの、許せない、よ……」
『我ハ貴様ノ許シナド要ラヌ、ト告ゲル』
作家のすげない返しは想像の範囲内だと、オスカーは小さく頷いた。矢を番えようと掲げた腕は微かに震えが残り、無意識のうちに先の恐怖を引きずっている事が伺える。とはいえ眼前の作家もまた、猟兵達の奮闘によって満身創痍だ。
次で、決する。矢尻のぶれを止めようと、オスカーはゆっくりと息を吐いた。
「……うん、だから、お、俺は、戦うん、だ……予知されたような事が、今後起きないよう、に」
何処か言い訳めいた呟きは、打鍵の音に消える。作家の二十六のキーに、光が灯った。
「俺、には。戦う理由が……ある」
発した言葉は決意か、免罪符か。作家が苛烈な光を放つより先に、願いの矢が放たれた。オスカーの魔力を多分に乗せた矢は、正確無比にキーの一つを穿つ。
ギィ……ン!
『……ナントイウ事ヲ』
折れて転がったのは、アルファベットならばEに相当するキーだった。即ち英文タイプにおいて、最も頻出する文字。作家の動揺は想像に難くない。
『貴様ッ』
激昂した作家の放った青白い光がオスカーの腕を掠めたが、彼は攻撃の手を緩めない。続いてAを、そしてTを。使用頻度の高いキーを狙いすまし、撃ち落とす。
『嗚呼、我ガ作品ガ……』
至る所を破壊され、作家はもう新たな物語を紡げない。スペシャル・ライターはぎぃぎぃと軋む音を立て、やがて動かなくなった。
「め、めでたしめでたし、で、終えられた……の、かな?」
オスカーの疑問にも、作家は何も答えない。ただ、鉄の塊がそこに在るだけだ。
『或る悲劇』は作家の非業の死という形で物語を終えた。アルダワ魔法学園の生徒達が繰り広げる物語は、そして猟兵の――あなたの物語は、まだ続いてゆく。
大成功
🔵🔵🔵

 宮下さつき
宮下さつき
 コイスル・スズリズム
コイスル・スズリズム  木常野・都月
木常野・都月  ロイド・テスタメント
ロイド・テスタメント  木鳩・基
木鳩・基 
 コイスル・スズリズム
コイスル・スズリズム  木常野・都月
木常野・都月  ロイド・テスタメント
ロイド・テスタメント  木鳩・基
木鳩・基 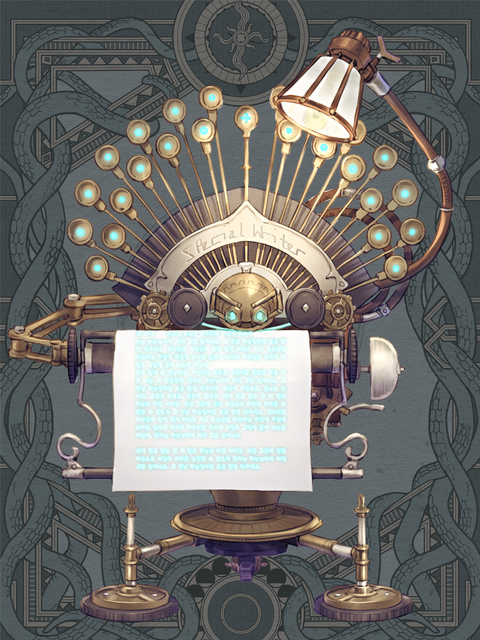
 コイスル・スズリズム
コイスル・スズリズム  木常野・都月
木常野・都月  ロイド・テスタメント
ロイド・テスタメント  ニニニナ・ロイガー(サポート)
ニニニナ・ロイガー(サポート)