その道に進むべき意味はあるか
●第四層
常闇の地上。
それは光差さぬ土地であると同時に世界の全てであった。
過去形でしか語れぬのは、その地上であると思っていた場所が地上ではなく地下であったからだ。
これまで猟兵達は数多の世界を見てきた。
オブリビオンに敗北した世界。
それがヴァンパイア支配盤石たるダークセイヴァーである。この常闇の世界にあって、陽光が差さぬのはヴァンパイア支配による力であると思われてきた。
だが、現実は違った。
『地下第四層』。
これまで猟兵たちも、ダークセイヴァーに住まう人々も『地上』であると思われていた場所が『地下』でしかないことを今まさに知る。
『第五の貴族』と呼ばれるオブリビオンたちとの戦いを通じ、それを知った猟兵達は次なる戦いの段階へと足を踏み入れる。
『常闇の燎原』――それはダークセイヴァーの辺境を更に超えた人類の居住区域の完全なる外側。
そここそが『第三層』に繋がる場所への何かが隠されている可能性があるのだ。だが、『常闇の燎原』はすでに人外魔境。
『狂えるオブリビオン』――『異端の騎士』がゆっくりと兜の奥にある狂気に満ちた瞳を輝かせる。
「……愛も、忠義も、誇りも、何もかもが私には必要のないこと。叛逆の騎士たる私には、それを語る資格などない。ただ鏖殺する。殺意に理由などない。あるのは事実だけ。もはや私がたどるべきは血に塗れた道のみ。贖罪も許しも必要ない。血まみれの道をこそ私は欲している。罰も、罪も、何もかも染めあげていく血の赤こそ私は欲しているのだ」
『常闇の燎原』に満ちていく『異端の騎士』のつぶやき。
それは闇に溶けて消えていく。誰にも届かず、さりとて届けようとも思わぬ声は、ただ狂気を色濃くしていくだけであった――。
●問いかけ
それは全身から黒い炎を噴出させ続けるオブリビオンであった。
痛みはなく、熱さも感じず、ただ佇んでいた。
その異様なる光景。ただ、彼女もまたぶつぶつとつぶやき続けるだけであった。
「何故進むのです。その意味はなんなのです。やっても意味のないこと。死が生命の終着点であるのならば、過程の意味などないのではないですか」
『問う女』は、その美しき姿から噴出し続ける黒い炎と共に夜明けなど来ない山の頂きに佇む。
そう、問いかけ続けているのだ。
己に、他者に。
だが此処に他者はいない。彼女の問いかけは罪を問うものばかり。業罪、善悪、正誤。
それらの問いかけを受けた者全てを黒炎に包み込んできたが故。
「私の問いかけに応えるということは、己の生に対する価値を問いかけられるということ。生命の終着。死を持って完結するのならば、今息をしていることすら無意味でないとどうして言えましょう。応えてください。生の意味に。何故生きるのかを」
ただ、待っている。
解答者を。己の心に落ちるような正しさを。
けれど、ああ、けれど。
どうしたって彼女が納得する答えを人が出せるわけがない。生命の意義。生きているだけですでに罪を犯しているのが人間であるというのならば、彼女の問いかけはあらゆる意味で無意味であり、同時に誰しもの心にある影を踏むものである。
ゆえに彼女は夜明けの来ない山に佇み、あらゆるものを拒絶するように問いかけ続けるのだ。
「あなたの道に意味はあるか―――」
●常闇の燎原
グリモアベースへと集まってきた猟兵達に頭を下げて出迎えるのは、ナイアルテ・ブーゾヴァ(神月円明・f25860)であった。
「お集まり頂きありがとうございます。今回皆さんにお願いしたことがあります。それはダークセイヴァー世界、その『第三層』に至る、もしくは繋がる場所の探索です」
ナイアルテはこれまで『第五の貴族』たちとの戦いで、このダークセイヴァーの世界が『地上』ではなく、『地下第四層』であることが判明したことを告げる。
陽光差さぬ世界。
常闇の世界であると思われたダークセイヴァーに夜明けが来ないのはヴァンパイア、オブリビオンによるものではなく『地下』であったことに由来していたのだ。
ならばこそ、何処かに『第三層』に至る場所があるはずなのだ。
「ですが、支配階級であるヴァンパイアにすらこの世界が階層上の構造をしており、今まで地上であったと思っていた場所が地下であることを知らされていなかったのです」
完全に手かがりが見つからない状況である。
けれど、辺境にはまだ道筋が残っている。その辺境を超えた更に先、人類の居住区域の完全なる外側……『常闇の燎原』にこそ、光明を見出すことができるのだ。
「おおよそ生物の生存を許さない区域ですが、この階層を支配するヴァンパイアですら知らない何かが隠されている可能性は十分にあるはずなのです。この『常闇の燎原』を目指し、辺境へと踏み込んでいただきたいのです」
それは危険を伴う行動であるだろう。
辺境に足を踏み入れれば、辺境にうろつく『狂えるオブリビオン』が襲ってくる。
これはこれまで確認された『狂えるオブリビオン』と同じく理性のない存在である。この『狂えるオブリビオン』、『異端の騎士』から得られる情報はないだろう。
「これを撃破し、先に進むしかありません。辺境の過酷な状況は相変わらず。私が予知したのは、辺境の山岳地域。この暗闇の世界で山岳地域を登っていくことは危険極まりないことです。ですが、その頂きにこそ私の見たオブリビオンの姿があるのです」
ナイアルテが言うには、この辺境、『常闇の燎原』に至る辺境の果てたる山岳の頂きに座すオブリビオンこそが最大の難関であるという。
「『問う女』と呼ばれるオブリビオンです。彼女は全身から『黒い炎』を噴出させ、皆さんに襲いかかってきます。そのオブリビオンは『同族殺し』や『紋章持ち』に匹敵する力と……『あらゆる防護を侵食し、黒い炎に変えて吸収してしまう能力』を持っているのです」
それは『問う女』と呼ばれるオブリビオンの攻撃を受けた瞬間、あらゆる武器、防具、服、肉体は黒い炎に変えられ、『問う女』の力を回復してしまう。
「対処は一つ。攻撃を受けず、見切って回避しなければなりません。ただそれだけのことでさえも困難なのは彼女の能力が強力なオブリビオンと同等であるからです」
危険な敵に冒険。
本当にそれは必要な道のりであるのだろうか。
そう思わずにはいられないほどに危険と苦難に満ちた戦いになるだろう。
ナイアルテは猟兵たちを危険な道に送り出さねばならない。
けれど、彼女は微笑むのだ。きっとだいじょうぶだと。自分がそう信じねば誰が信じるのだと言うように――。
 海鶴
海鶴
マスターの海鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回はダークセイヴァーに存在するであろう『第三層』へと繋がる何かを探索するために『常闇の燎原』を目指して辺境を踏破するシナリオになります。
●第一章
ボス戦です。
皆さんが『常闇の燎原』を目指して辺境地帯に踏み込むと、辺境にうろつく『狂えるオブリビオン』の一体である『異端の騎士』が襲いかかってきます。
『異端の騎士』は言葉を発していますが、理性がありません。
問いかけても、皆さんの問いかけに正しく応えることはなく、ただただ言葉を紡ぎながら皆さんを排除しようと苛烈なる攻撃を仕掛けてきます。
情報収集は望めないため、倒して先に進むしかありません。
●第二章
冒険です。
辺境にある山岳地域を踏破するために危険な山岳を登らなければなりません。
この常闇の世界であるダークセイヴァーにあって、視界が暗闇に閉ざされた山岳を登ることは危険極まりない行いでしょう。
いくつかのルートを見つけることができるはずです。
この山岳を上り、頂きへと至りましょう。
●第三章
ボス戦です。
辺境地帯の果て、夜明けの来ない山岳の頂きに座す一体の強力なオブリビオン『問う女』との戦いにまります。
彼女は全身から『黒い炎』を噴出させており、『同族殺し』や『紋章持ち』に匹敵する力を有しています。
さらに『あらゆる防護を侵食し、黒い炎に変えて吸収してしまう能力』をもっているため、彼女の攻撃を受けるのではなく、見切って躱す必要があります。
あらゆる武器や防具、服、肉体は彼女の攻撃を受けた瞬間に黒い炎に変わり、吸収されてしまい、それまでに追わせていた傷を回復されてしまいます。
この恐るべき力、攻撃に対処し、辺境地帯の果てを乗り越え『常闇の燎原』へと至りましょう。
それでは、『第三層』を目指す冒険と戦い、その皆さんの物語の一片となれますよう、いっぱいがんばります!
第1章 ボス戦
『異端の騎士』

|
POW : ブラッドサッカー
【自らが他者に流させた血液】を代償に自身の装備武器の封印を解いて【殺戮喰血態】に変化させ、殺傷力を増す。
SPD : ブラックキャバリア
自身の身長の2倍の【漆黒の軍馬】を召喚し騎乗する。互いの戦闘力を強化し、生命力を共有する。
WIZ : フォーリングローゼス
自身の装備武器を無数の【血の色をした薔薇】の花びらに変え、自身からレベルm半径内の指定した全ての対象を攻撃する。
イラスト:神手みろふ
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠山田・二十五郎」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
辺境の地は生命の存在を許すことはない。
そもそもこのダークセイヴァー世界にあって、陽光は無縁のもの。それもそのはずである。この地上だと思っていた世界は『地下』であったのだ。それ以前に此処が『第四層』である事実すら、ヴァンパイアたちは知らなかった。
人々が求めた陽光。
それはいまだ遠き場所にある。
猟兵たちが求めるは『第三層』。
果たして何処に其処に繋がる場所があるのか、それさえも未だ判然としない。
見果てぬ闇の先にそれがあるのか。
その答えを持つ者すら見つけられない。ならば、進むしか無いのだろう。どれだけ困難な道であったのだとしても、進まなければたどり着けないのだから。
「叛逆は私自身。私自身の体は血に塗れていなければならない」
乾いた大地。
辺境へと至る道の半ばに、『異端の騎士』が揺らめくようにしてさまよい続けていた。
彼が生前如何なる騎士であったのかは最早知る術もない。
あるのは人々を護る存在から脅かす存在に成ったという事実のみ。
『狂えるオブリビオン』となった『異端の騎士』は、己以外の生命を屠るためだけに存在していた。
乾いた大地に血の滴りを持って潤さなければならない。
此処に生命がなかったことが幸いであったのかもしれない。
「大地を血に染め、満たし、湿潤の如き様相に変えねばならない。私はそのために存在している。生命を殺し、生命を裏切り、生命を生命を生命を生命を」
壊れたように呟き続ける『異端の騎士』の眼光は狂気そのもの。
猟兵達は、これを打倒し道を進まなければならない。
もはや自身で止まることのできぬ存在。
『異端の騎士』の歪み果てた人生に幕を下ろすのだ――。
 フォルク・リア
フォルク・リア
「地上に至る道は中々に厳しい様だ。
それでも、道がありそれが見えるのは幸いだろうね。」
と気持ちを新たに。
異端の騎士の言葉を聞き
「血か。そんな物に塗れて潤う大地なら
永遠に乾いたままで良い。」
シャイントリガーを発動して己の手を炎で包み
敵の放つ薔薇の花びらに向って熱線を撃ってそれを焼き。
花びらの数が減ったところで炎を纏いながら敵に近づき再度攻撃。
今度は攻撃すると共に光線によって敵を目晦ましして
己の【残像】を発生させて移動し幻惑、その隙を突いて
【全力魔法】を放つための魔力を集中。
両手を重ねて相手に向け高温の熱線を敵に放って仕留める。
「この手に在るのは偽りの太陽。
しかし必ず陽光(ひかり)を掴んでみせる。」
常闇の世界、ダークセイヴァー。
それはこれまでの常識を覆す世界の在り方を猟兵達に見せつけていたことであろう。
地上であったと思っていた場所は地下であった。
それも己たちが今存在する場所ですら『第四層』と呼ばれる地下であることが判明している。
さらにこの上に『第三層』が存在し、其処へ至るための場所が存在しているであろう辺境の果て『常闇の燎原』を目指さなければならない。
「地上に至る道は中々に厳しい様だ。それでも、道があり、それが見えるのは幸いだろうね」
フォルク・リア(黄泉への導・f05375)は、『第四層』と呼ばれた自身が今いるダークセイヴァーの世界の大地を踏みしめ、辺境へと足を身入れた。
そう、確かに遠き道のりであろう。
けれど、確かに地上が在る。陽光に溢れた場所があるという確証があるのならば、其処へ至るための努力を惜しまないのが人という生命である。
気持ちを新たにフォルクは辺境に座す『異端の騎士』の前に一歩を踏み出す。
「叛逆の騎士こそが私。如何なる理由においても、叛逆の事実は変わらない。人を裏切り、ヴァンパイアに恭順した騎士に誇りなどあってはならない。あるのは血に塗れた路のみ。此処は乾いている。血に塗れさせなければ」
『狂えるオブリビオン』である『異端の騎士』が剣を構えている。
こちらを敵と認識したのだろう。
そこにあったのは、狂気をはらむ鋭い視線だけであった。
「血か。そんなものに塗れて潤う大地なら、永遠に乾いたままで良い」
『異端の騎士』の言うところの血路とはすなわち、闘争だけが支配する世界であろう。
人々の嘆きと悲しみだけが支配するのが血に塗れた大地であるというのならば、フォルクは外套の奥に隠れた瞳を輝かせる。
「この掌に在りしは天の日輪放つ撃鉄。降り注ぐは浄戎の炎。我に仇為す汝らに、等しく光あれ」
彼の黒手袋から太陽光に比肩するほどの炎が立ち上る。
それはシャイントリガー。フォルクのユーベルコードは、陽光なき世界を照らす。
対する『異端の騎士』は己の剣を薔薇の花弁に変えて解き放つのだ。
「私の路は血に塗れていなければならない。私には最早それしかないのだから」
放たれる薔薇の花弁。
けれど、フォルクの黒手袋から放たれた熱戦の一撃が、その花弁を焼き切りながら『異端の騎士』へと放たれる。
「狂っている……正気ですらない。自分がオブリビオンであるという自覚すらなく、辺境をさまよい続けているというわけか」
フォルクにとって、それは同情に値するものであったのかもしれない。
決して許されず、正気にも戻れない。
裏切りの誹りすらも感じ取ることのできない『異端の騎士』にとって、それはまさに生き地獄であると言えるだろう。
誇りも、矜持も何もかもが地に失墜したのであるのならば、それはもはや存在している意味すらないだろう。
「この手に在るのは偽りの太陽」
フォルクは黒手袋から放つ熱戦で敵の花弁を焼きながら走る。
残像すらもたらす速度で走り抜け、輝き放つ黒手袋を掲げる。
彼の掲げた両手の間で光線が収束していく。
フォルクのユーベルコードの輝きは、陽光知らぬ者たちにとってまばゆいものであったことだろう。
「しかし、必ず陽光(ひかり)を掴んでみせる」
それがダークセイヴァー世界に生きる人々を闇より救い出すことに繋がる。
地上を目指す暗夜行路。
答えは得られど、それでもなお道は険しい。
「そのためには……『異端の騎士』よ、お前は此処で眠ってもらう」
掲げた両掌に収束した高温の熱線が『異端の騎士』の胸を穿つ。
熱線の一撃が、まさに陽光に照らされたように暗闇の辺境を明るく照らす。今はか細い光であったのだとしても。
それでもいつか、この世界に生きる人々を陽光降り注ぐ元へと導いてみせる。フォルクは、その決意と共に『異端の騎士』を打倒するのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 外邨・蛍嘉
外邨・蛍嘉
人格:クルワ(鬼/男)にて
武器:妖影刀『甚雨』
空のある場所へと向かうためにも。ワタシも力を尽くしマショウ。…先にワタシだけ来まシタシ。
…ここが一般の方がいるような場所ではなくて、助かりマシタネ。
血液はワタシにはなく。見えるのはエクトプラズムでのギソウデスガ。
マア、流す理由もないノデ…ただ、この刀で斬るのみデスヨ。
そして、武器を振るうデショウガ。それは結界術で受け止め、藤流し投擲でズラす。
ここに何も流しはシマセンヨ。
エエ、光を目指していく。これがこの世界の謎に迫るためでもアリマスからね。
人々が陽光を忘れて久しい世界。
それがダークセイヴァーである。この陽光差さぬ世界、地上ですらない地下の世界にあってもなお、人は陽光を求めるだろう。
この世界は間違えだらけである。
陽光なく、闇ばかりが続く。
夜明けなどなく、ただ絶望ばかりが広がっている。だと言うのに、人はそれでも希望を捨てない。
夜明けを求める人々の叫びは世界の悲鳴と成って猟兵に届くことだろう。
「贖罪など私は求めていない。贖う罪の意味すら私は失っているのだから。だから血だけが私の求めるもの。血を、この大地に満たさなければならない。私は叛逆の騎士であるがゆえに」
『異端の騎士』は胸を熱線に貫かれても立っていた。
その姿に嘗ての高潔さはない。
あるのは彼が人類を裏切り、ヴァンパイアに恭順を示したという事実のみ。
「空のある場所へと向かうためにも。ワタシも力を尽くしマショウ」
外邨・蛍嘉(雪待天泉・f29452)は多重人格者の悪霊である。
その人格の一つである『クルワ』が言う。手にした妖影刀『甚雨』が常闇に煌めく。
それは月光を思わせる輝きであったことだろう。
この世界にあって陽光はない。
けれど、空を求め、陽のあたる場所を目指す者たちにとっては僅かな光であっても道標になるだろう。
『クルワ』は己がたどる路をこそ轍とする。
その轍をたどり、いつかダークセイヴァーの人々が空を目指すだろう。
「……ここが人の住まう場所でなくてよかった」
『異端の騎士』の咆哮が響き渡る。
彼の手にした剣が、これまでこの大地で流された血液をもって殺戮形態へと変貌していく。
異形にして異端。
その刀身の禍々しさは言うまでもない。己に血液はない。血を流したように見えるのはエクトプラズムでの偽装のみ。
血を流す理由もない。
これ以上、この大地が血にまみれていい理由など『クルワ』には持ち合わせていなかった。
「血を。血を。満たして、満たして、満たして、池のようにしなければ。それだけが私の求めるもの」
『異端の騎士』が迫る。
肉薄する技量は確かに『狂えるオブリビオン』そのもの。
単体であっても猟兵を凌駕する力を有している。だが、猟兵は繋ぐ戦いをする。胸に穿たれた傷痕は深い。
熱線で焼かれ再生も追いつかぬのだろう。
ふるわれた剣の一撃を結界で受け止め、手裏剣の一撃で斬撃の軌道をずらすのだ。
「ここに最早血は流させはシマセンヨ」
そう、これ以上血の一滴も。
「光などないというのに。無間に続く常闇だけが続く世界にあってもなお、それを求めるか」
『クルワ』の瞳がユーベルコードに輝く。
それは、棘一閃(キョクノイッセン)の一撃。
妖影刀が『異端の騎士』の片腕を一刀のもとに両断する。それは渾身の一撃にして会心の一撃であったことだろう。
「エエ、光を目指していく。これがこの世界の謎に迫るためでもアリマスからね」
ただそれだけの理由でいい。
きっといつか、自分たちがたどった道を人々は歩くだろう。
その時のために『クルワ』は己にできることをするのだというように、叛逆の騎士に痛烈なる斬撃を見舞うのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ニノマエ・アラタ
ニノマエ・アラタ
過程か。
……結末に迎い刃を振るえば変化するモノがある。
……。
言ってて、テンション下がった。
綺麗ごとを言う気は無ェんだ。
俺の血をタダではくれてやらんし、
大地を染めると言われて悦に浸られても気持ちが悪い。
俺は血ってモンに特別な思い入れも無ェからな。
何だろうな、綺麗か汚いで問われたら
……汚い、で返すかな。
実験体だった頃の思考の名残りかな……。
血を流すことに価値があるとは思わない。
俺にとっては、この一閃の向こうにある命に価値がある。
敵に接近し鎧の隙間を狙って斬り飛ばす。
そのために大剣の軌跡をくぐり抜け、肉迫する。
薔薇の花をまかれても、アンタの心眼ごと端緒の光で焼き切るぜ。
ここまで刃を届かせてみろ!
『異端の騎士』が辿ったであろう本逆の過程。
それは人が知ることのない事実であり、知ったところで彼の結末は変わることはなかっただろう。
『狂えるオブリビオン』となった彼に生前の記憶はない。
あるのは己が人類を裏切り、ヴァンパイアに恭順を示したという事実のみ。
猟兵に寄って穿たれた胸は虚のごとく。
切断された片腕が握りしめていた剣を残された片腕で掴み上げ、その刀身を薔薇の花弁へと変貌させていく。
「終わらない。この程度で私の叛逆は終わらない。終わるわけがない。人の血を求めている。この血を、池の如く血で満たさなければならない。私が裏切ったのはそのためなのだから」
どれだけ高潔であったのだとしても。
どれだけ誇り高い矜持があったのだとしても。
それでもオブリビオンへと変わり果ててしまえば、それさえも歪み果てていく。
「過程か……結末に向かい刃を振るえば変化するモノがある」
ニノマエ・アラタ(三白眼・f17341)は言葉にして己のテンションが下がってしまうのを感じていた。
綺麗事を言うつもりはなかった。
抗う意志があればこそ、結実したものがあったのかもしれない。
それは言うに及ばず、存在しなかった結末でしかない。選び取られなかった選択の結果だ。
「俺の血をタダでくれてやらんし、大地を染めると言われて悦に入られても気持ちが悪い」
アラタは薔薇の花弁が舞う辺境の暗闇の中にあって、その眼光を鋭く『異端の騎士』を見据える。
血に特別な思い入れがあるわけでもない。
「血を満たせ。血に満たせ。私の薔薇はそのために」
『異端の騎士』の瞳は狂気の光しかない。それが同仕様もなく汚いと思ってしまう。
実験体であった己の過去を思い返す。
血の匂いが充満していた記憶。血の赤が染め上げる視界。血しぶきが染める何か。血を流すことに価値があるとは思えない。
「それがお前が求めた最後だというのなら。俺はこの一閃の向こうにある生命に価値があると知る」
アラタは薔薇の花弁舞う暗闇の中を疾駆する。
「心眼すら焼く光の炎、とくと見よ」
抜き払った妖刀の刀身から円環の端緒(エンカンノタンショ)、その目をくらませるほどのまばゆい金色の光が放たれる。
それはあらゆる視界を染め上げる黄金。
陽光の輝きにも似たまばゆい輝き。この常闇の世界にあっては、決して見ることのかなわぬユーベルコードの輝きであったことだろう。
薔薇の花弁が止まる。
空中で静止して見えるのは、『異端の騎士』の視界が黄金の輝きによって塗りつぶされ、標的を見定めることができぬからであろう。
「ここまで刃を届かせてみろ! それができぬというのであれば!」
アラタの振るう妖刀の一撃が肉薄した『異端の騎士』へとふるわれる。
苦し紛れに『異端の騎士』が薔薇の花弁を元の剣の形に変えて闇雲に振るうのだとしても、アラタには届かない。
そう、このまばゆき輝きは人々が求める光そのものである。
日の当たる場所を求めたい。
人が人らしく生きる場所を欲する。そのためにアラタは黄金の輝き放つ妖刀の刀身を煌めかせる。
振るった一撃が袈裟懸けに『異端の騎士』の鎧すらも両断し、その虚の如き鎧の内側を断ち切るのだ。
それこそが輪廻宿業。
断ち切るべきは叛逆の過ちのみ。そう云うかのようにアラタは振り切った刀身の先に見える『異端の騎士』の嘗てを幻視するのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
そうですか。私も同じです。
立ち向かい、抗い、叛逆する。
吸血鬼と異端の神の血に塗れ、屍を踏み越える。
そうしていった先に、人の生きる世界があると信じています。
そのためであれば、何度でもこの銃は敵を撃ち抜きましょう。
軍馬の頭部を狙う『威嚇射撃』で敵の移動を阻害しつつ、攻撃を避けていきます。
小回りを活かして敵の側面や背後を取ったら【氷炎殺界】を使用、氷と炎を纏う真の姿に変身し、片手に「フィンブルヴェト」片手に「ラグナロク」を持ち、氷と炎の弾丸の『乱れ撃ち』による『弾幕』で漆黒の軍馬ごと異端の騎士を撃ち抜きます。
この世界を人の生きられる世界にするため、退いてもらいます。
ダークセイヴァー世界、その常闇にあって更に闇色濃き場所こそが辺境の地であった。
人の居住区域からさらに外れた場所。
そこは人外魔境そのものであったし『狂えるオブリビオン』や『異端の神々』しか存在しない場所でもあった。
けれど、猟兵達はその危険極まりない辺境をこそ踏破しなければならない。
言うまでもなく、このダークセイヴァー世界を構成する『第四層』から『第三層』へと至るための手がかりを見つけるためである。
猟兵たちが求めるものが果たして辺境の果て、『常闇の燎原』に存在しているのかどうかすら定かではない。
「それでも私を越えていくゆくか。この叛逆の騎士の屍を越えてでも――」
片腕を両断され、胸を穿たれ、鎧を切り裂かれても尚『異端の騎士』は斃れなかった。
その姿は自罰的ですらあったことだろう。
だが、その瞳にいまだ残る狂気の光は潰えず。ユーベルコードの輝きと共に漆黒の軍馬にまたがる『異端の騎士』が猟兵を睥睨する。
「私は血を満たす。この大地を、血で満たすことこそが私の叛逆なればこそ」
暗黒の大地を漆黒の軍馬と共に『異端の騎士』が縦横無尽に駆け抜ける。
その速度、荒々しさを前にしてセルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)は怯むこと無く、その瞳で持って彼を射抜くのだ。
「そうですか。私も同じです。立ち向かい、抗い、叛逆する。吸血鬼と異端の神の血に塗れ、屍を踏み込める」
セルマにとって、それはやらなければならないことであった。
この暗闇だけが支配する世界に生まれ落ち、猟兵として数多の世界を見てきた。
何処にでも当たり前のように存在している陽光。
この世界だけ、それが存在していない。地上だと思っていたのは地下であった。何故、自分たちが陽光なき世界に閉じ込められ、生命をもてあそばれているのか。
そんな理由など存在していいわけがない。
「そうしていった先に、人の生きる世界があると信じています」
構えたマスケット銃『フィンブルヴェト』から放たれる弾丸が漆黒の軍馬の頭部を撃ち抜く。
一瞬の攻防。
頭部を撃ち抜かれた軍馬が体勢を崩し、崩れるようにして『異端の騎士』を大地に振り落とす。
軍馬を駆る『異端の騎士』の機動力は凄まじいものであり、歩兵であるセルマにとっては驚異そのものであった。
だが、随伴する存在のない騎乗騎士にセルマの用いたマスケット銃は防ぎようのない攻撃。軍馬を失った騎士を待つのは背後より肉薄するセルマであった。
「そのためであれば、何度でもこの銃は敵を撃ち抜きましょう」
『異端の騎士』が振り返り様に剣を振るう。
だが、その斬撃はセルマを捉えることはなかった。
「逃しません……あなたは、ここで殺す」
それは炎氷殺界(ヒョウエンサッカイ)。
彼女は炎と冷気を手繰る真なる姿に変貌していた。手にしていたのは二丁の銃。氷の弾丸を撃ち放つ『フィンブルヴェト』。
そして、もう一丁は炎の弾丸を撃つ銃『ラグナロク』。
隻腕で振るう『異端の騎士』の剣が弾幕のごとく放たれる炎と氷の弾丸を切り払う。
だが、そのすさまじい乱れ打ちの弾丸の速度に剣が追いつくことはない。
軍馬が健在であれば、機動力を持って後退することも出来たのだろう。しかし、セルマはそれをさせない。
氷と炎の弾幕は、『異端の騎士』をこの場に釘付けにする。
逃さないと告げたのは、真であったのだ。
彼女の瞳がユーベルコードに輝き続けている。そう、逃がすつもりはない。
「この世界を人の生きられる世界にするため」
セルマの猛攻は続く。
彼女がこのダークセイヴァー世界で望むことは一つ。
支配者への叛逆である。彼女にとって、ここは人間が住む世界ではない。数多の世界を知るからこそ、強く願うのだ。
常闇からの支配の脱却。そのために彼女は氷と炎でもって、その支配の異端を撃ち貫き続けるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル
…吸血鬼達の支配から人類を解放する
その為に今まで戦ってきたし、それはこれからも変わらないけど…
…まさか求め続けてきた陽光がこの地に存在しなかったなんて、ね
「写し身の呪詛」の残像を囮に敵の攻撃を回避して受け流し、
過去の戦闘知識から敵UCの能力を見切りつつ魔力を溜めUCを発動
…いかに狂えるオブリビオンといえど、
今さら異端の騎士相手に遅れを取る気は無い
…生憎だけど、お前に構っている暇は無い。邪魔をするなら排除するまでよ
呪詛と氷結のオーラで防御ごと敵味方問わず捕縛する呪氷の嵐を放ち、
生命力を共有した軍馬と騎士を同時に3回攻撃する氷属性攻撃を行う
…確かめる必要がある。この常闇を越えた先に、何があるのか…
絶望するにはまだ早いとリーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は思ったことだろう。
このヴァンパイア支配が続く世界、ダークセイヴァー世界にあって、人類を開放するために戦ってきたのは他ならぬ彼女自身の意志であった。
虐げられる人々が居る。
生命を弄ばれる人々の悲嘆の声が今も耳に刻まれているかのようでもあった。
だからこそ、彼女は陽の光を求めたことだろう。
他世界を知る猟兵であるからこそ、知っている。あの陽光の暖かさを。その陽光の元で見る人々の表情はこのダークセイヴァー世界に生きる人々と比べるべくもない明るいものであった。
希望に溢れていると言ってもいい。
「……まさか求め続けてきた陽光がこの地に存在しなかったなんて、ね」
ある者にとって、それは絶望の事実であったことだろう。
地上であると思っていた世界が地下であったなどと誰が想像しようか。『第五の貴族』との戦いで得られた事実は残酷そのものであった。
「地に、血を満たさなければ。私が裏切り、鏖殺し、生命を捧げてきたのは、このために」
『狂えるオブリビオン』である『異端の騎士』は言うまでもなく強力な敵である。この辺境の地にありながらいまだ存在を保っている事実こそが、その証拠である。
猟兵たちの攻撃に晒され、片腕を失い、胸を穿たれ切り裂かれ、弾丸の雨に打たれても尚、彼は立っている。
さらに漆黒の軍馬に再びまたがり、辺境の暗闇の中を疾駆し、剣をフルワンとしている。
リーヴァルディに迫る軍馬の嘶きを彼女は聞いただろうか。
いや、彼女はそれを聞かない。写し身の呪詛でもって生み出された残像が剣に切り裂かれて消えていく。
「……如何に『狂えるオブリビオン』といえど、今更『異端の騎士』相手に遅れを取る気はない」
過去に戦った『異端の騎士』、その戦いの術を彼女は知っている。
同一の個体ではないだろう。
嘗て胸に抱いていたであろう矜持も、誇りも、異なるものだろう。如何なる過程を経て、『異端の騎士』となったのか。人類を裏切ったのか。
それをリーヴァルディは振り切るようにして疾駆する。
「私の叛逆は終わらない。終わらせてはならない。この生命の意味が、血に塗れて消えていくまで」
「……生憎だけど、お前にかまっている暇はない。邪魔をするなら排除するまでよ」
リーヴァルディの瞳がユーベルコードに輝く。
呪詛と氷結のオーラが解き放たれる。それは呪氷の嵐そのものである。これこそが、吸血鬼狩りの業・絶凍の型(カーライル)。
呪氷の嵐は漆黒の軍馬ごと『異端の騎士』を氷の中に閉じ込めていく。
暗闇に会っても尚、人は陽光を求める。
たとえ、見上げた先が夜空ではない、ただの天井であったのだとしても。その先にあるものを求めるだろう。
リーヴァルディはこれまでダークセイヴァー世界に生きる人々を見てきた。
時に絶望し、時に渇望し、時に悲嘆にくれる人々を。
けれど、彼らは再び立ち上がろうとしている。それを知っているからこそ、彼女は確かめる必要があると理解しているのだ。
「……確かめる必要がある。この常闇を越えた先に、何があるのか……」
彼女が求めるものが存在しているという確信はない。
徒労に終わってしまうかもしれない。されど、それでもリーヴァルディは人々の絶望と悲嘆を拭う希望を見出すために常闇へと足を踏み出す。
彼女の背後には氷漬けにされた『異端の騎士』の姿があった。それに背を向け、リーヴァルディは歩み続ける。
「……呪氷封印。凍てつきなさい。その魂まで……」
そう、どれだけ遠き道のりであったのだとして――。
大成功
🔵🔵🔵
 大町・詩乃
大町・詩乃
この世界の夜明けはまだ遠い…。
ですが目指す方向が見えた以上、まずは第三層に辿り着きましょう。
異端の騎士とは戦うしかありませんね。
せめてこれ以上の犠牲者を出さないよう、此処で討ち果たします!
UCにて創造した煌月の複製に炎の属性攻撃・破魔・浄化を付与し、1100本を彼に差し向け、薔薇の花びらを燃やし清めつつ包囲しての貫通攻撃で追い詰める。
包囲を逃れた花びらには、身体の周囲に展開した結界術による防御壁とオーラ防御で防ぎつつ、煌月の複製の一部(残り30本)にて同様に燃やし清めます。
花びら以外の攻撃は第六感で予測して見切りで避けたり、天耀鏡の盾受けで対応。
最後は数多の煌月の複製を彼に突き刺して倒します。
数多の世界を知る猟兵であるからこそ、ダークセイヴァー世界の常闇は異常なるものであったことだろう。
日登らぬ世界。
それは生命にとってあまりにも過酷な環境であり、同時に生命を拒絶するかのような冷たさがあった。
辺境の地においては、それはさらに顕著であった。
『異端の騎士』が己の体を封じる氷を吹き飛ばしながら隻腕となった腕を振るう。
「地に血を満たせ。私が叛逆の騎士であるのならば。私は裏切ったのだ。どれだけ高潔さを、矜持を振りかざしたとしても、私が裏切ったという事実は消えない。消えないのだ。この暗闇に夜明けなど来ない」
ヴァンパイア支配に恭順を示した騎士。
堕落した騎士。その過去に如何なることがあったのかは最早知る術は何処にもない。
『狂えるオブリビオン』となった『異端の騎士』にとって、存在しているということ事態が身を苛む苦しみであったことだろう。
ゆえに大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)は辺境の地に足を踏み出したのだ。
「この世界の夜明けはまだ遠い……ですが目指す咆哮が見えた以上、『第三層』にたどり着きましょう」
詩乃が見据える先に在る『異端の騎士』。
もはや救うことすらかなわぬ。いや、救われることさえも拒絶するような狂気が『異端の騎士』の瞳にはあった。
戦うしかない。
「せめてこれ以上の犠牲者を出さぬよう、此処で討ち果たします!」
互いのユーベルコードが輝く。
『異端の騎士』の剣が薔薇の花弁に変わっていく。
それはあらゆるものを斬り裂き、大地を血で満たさんとする『異端の騎士』を突き動かすただ一つの衝動を示すようでもあった。
「煌く月よ、空を舞って世界を照らし、清浄なる光と刃で悪しき存在を無に帰しなさい」
対する詩乃のユーベルコードが顕すは、煌月舞照(コウゲツブショウ)。
神力によって創造された煌月、オリハルコンの刀身輝く薙刀の複製が数千にも及ぶ数でもって暗闇の世界に舞う。
激突するユーベルコードの輝き。
それは常闇の世界にあって明滅するほどの光であった。
穏やかな陽光には及ばないことを詩乃は知っていただろう。
けれど、それでも辺境の地にあってこれを見る者はいない。世界はもっと穏やかな光で包まれているべきなのだ。
詩乃は激突する花弁と薙刀が散っていく様を見る。
「光あれなどと。この支配だけが色濃く残る世界にあって、血だけが私を慰めるもの。誇りも矜持も、私を癒やしてはくれない。血の赤さだけが私を私たらしめる」
薔薇の花弁が薙刀の群れをかい潜って詩乃へと迫る。
しかし、それらを結界が防ぐ。
どれだけ敵が強大な存在であったのだとしても、詩乃は暗闇の中にこそ夜明けを求める人々の願いを見る。
それは切なる願いであったことだろう。
誰もが望んでいる。支配される日常ではない。虐げられる日常でもない。
人が人らしく生きることのできる世界。
「そのためには、過去よりにじみ出るオブリビオンの存在は必要ないのです」
過去は過去に。
人の歩みを止めるのはいつだって過去よりの悔恨であろう。
『異端の騎士』が叛逆を悔いたように。
その悪しき意志を断ち切らんと空に舞う煌月の群れが『異端の騎士』を捉える。
降りしきる雨のような薙刀の突撃が彼の鎧を砕いていく。
虚の如き内側。
もはや叛逆したという事実しか、彼の中には残っていないのだろう。その空虚なる存在を憐れむように、暗闇の世界に存在しない陽光の如き輝きを持って詩乃は『異端の騎士』を打ちのめすのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 愛久山・清綱
愛久山・清綱
一つの大きな謎が暴かれ、新たなる謎が姿を現した。
此の世界の『真なる敵』は、一体何処に居るのか?
『上』の果てか、『下』の果てか、其れとも……?
■闘
彼の騎士は、完全に理性を喪ってしまったようだ。
何か訊ければよかったが、最早討つしかあるまい……
刀の柄を握りつつ、真正面から【ダッシュ】し懐を目指す。
強化された大剣が振るわれる瞬間に合わせ、刀を抜かんと
する【フェイント】をかけながら、【残像】を見せつつ
剣閃をすり抜けながら死角へ潜り込む。
上手く入り込んだら【早業】の手つきで瞬時に抜刀し、
反撃される前に【真爪】を放ち大ダメージを狙うのだ!
此の闇の果てには、何が待っているのだろうか。
※アドリブ・連携歓迎
薔薇の花弁の中で『狂えるオブリビオン』、『異端の騎士』が陽光の如き煌きの中で打ちのめされる。
砕ける鎧の中は虚。
鎧の内側に存在しているのは、血肉ではなく空虚そのものであった。
『異端の騎士』である彼に残っているのは矜持でもなければ贖罪でもない。あるのは叛逆したという事実のみ。
生前の高潔さも。誇り高き矜持も、何もかもが骸の海に置き去りにしてきたのだろう。
「私の罰が、ここで終わって言い訳がない。叛逆こそが私。私こそが叛逆。ならばこそ、私は、ここで終わるわけには」
『狂えるオブリビオン』に理性はない。
あるのは、衝動の如きたった一つの狂気のみ。
「一つの大きな謎が暴かれ、新たなる謎が姿を表した。この世界の『真なる敵』は一体何処に居るのか?」
愛久山・清綱(鬼獣の巫・f16956)は暗闇に覆われた世界の中で独りごちる。
天を見やれば、それは天ではなく偽りの空。
暗闇に包まれた世界。
猟兵として討たねばならぬ敵は何処に存在しているのか。
『第五の貴族』は地下世界。『第五層』に在った。されど、此処が『第四層』であるというのならば、『第三層』とは、この世界を覆う天。
辺境の地にあって、その『第三層』へと至る道筋を見つけようと清綱は一歩を踏み出す。
目の前には『異端の騎士』。
完全に理性を粋成った存在。何か知ることがあったのかもしれない。けれど、斯様な有様ではそれもかなわぬと彼は知る。
「最早討つしかあるまい……」
刀の柄に手を掛ける。
その瞬間、その敵意を感知したのか『異端の騎士』の手にした剣が殺戮形態へと姿を変える。
猟兵たちの攻撃に寄って隻腕となり、隻腕となり鎧を砕かれても尚、生ける屍のごとき様相でもって『異端の騎士』は清綱に刃を振るうのだ。
対する清綱はその攻撃を前に躱すこと無く真正面から突っ込むのだ。
「かつて在りし矜持も、誇りも何もかも捨ててきたか」
己の眼前に迫る刃を見据えながら清綱は、空虚の如き虚から発せられる狂気と、それを宿す瞳を見た。
そこに如何なる感情も見出すことはできなかっただろう。
ふるわれた斬撃を残像を残すほどの速度で駆け抜け、剣閃をかいくぐり死角へと潜り込む。
頬を切り裂かれる。
完全にみきったと思った回避は、されど『異端の騎士』が元より尋常ならざる力を持つ存在であることを示していた。
「……もらったり」
されど、その上を往くのが猟兵である。
柄に掛けた手が握りしめられる。
一瞬の抜刀。
死角に回り込んだ清綱をさらに切り裂かんと迫る『異端の騎士』の刃がふるわれるよりも早く撃ち込まれるは、真爪(シンソウ)。
清綱の抜刀は神速。
ユーベルコードにすら昇華した剣の一閃は『異端の騎士』を斬り裂き、その空虚なる狂気を打ちのめす。
反撃の一撃は虚空を斬り裂き、大地に『異端の騎士』の剣の切っ先が打ち込まれる。
それを背にしながら清綱は辺境の果てへと進むのだ。
「此の闇の果てには、何が待っているのだろうか」
つぶやきは闇に溶けて消えていく。
誰も答えを持っていない。誰もわかり得ぬ未知。
しかし、それは踏み出さねば何もつかめぬことと同義。ゆえに、清綱は進むしかないと知る――。
大成功
🔵🔵🔵
 ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー
地元の依頼に来たのは初めてだが、地下だったのか。此処。おれが泳いでいた海は地底湖だったのか?
潮の匂いは確かにあったし……おれにとっては海でいいか
血の海は生命の根源として大地を満たすだろう。だが、悪いけどおれはきみの辿った道筋に興味がない
地上に太陽があるとして、そこに海はあるのだろうか。今のおれの頭中にはそれしかないんだ
相手との距離はまだあるかな。手始めに氷槍の投擲を行い、追うように距離を詰める。相手の攻撃に合わせてUCを。間合に入ったら鎧の隙間を狙ってレイピアで刺突しよう
血を被ったことすら忘れてしまう程に求めるならば、一度頭を冷やしたらどうだ。太陽がきみに与えるのは熱湯だが、植物には丁度いいさ
薔薇の花弁が『異端の騎士』の周囲に舞い散っている。
それは彼の剣が姿を変貌させたものであり、近づくものすべてを切り刻み、肉塊に変えるユーベルコードの力であった。
彼は血を求めている。
己が本逆の騎士であることを証明するように。
人類を裏切り、ヴァンパイア支配に恭順を示した証であるというように狂ったように、傷ついた体を気にした様子もなく力をふるい続けるのだ。
「薔薇の花弁を大地に敷き詰めるように、血で地を満たすのだ。それこそが私の在り方。何もかも血に染めていかねばならない。乾いた大地は、血によって潤さなければならない」
嘗ての矜持も、誇りもなにもない。
あるのは狂気だけである。如何なる過程を、道程を重ねてオブリビオンへと至ったのか。それを知ることはでいないだろう。
けれど、それ以上にギヨーム・エペー(Brouillard glacé calme・f20226)の心を占めるのは、故郷の大地が地下であったという驚愕為る事実だけであった。
「おれが泳いでいた海は地底湖だったのか? 潮の匂いは確かにあったし……」
ダークセイヴァー世界。
常闇の世界に生まれ落ちたギヨームによって海こそが彼の心の寄る辺であったのだろう。
それは地下世界にあっては誰も知り得ぬものであったことだろう。
けれど、ギヨームはあっけらかんと笑って『異端の騎士』と対峙するのだ。
「……おれにとっては海でいいか」
そう、それでいいのだ。
誰かがそれは違うと言ったのだとしても、それはただの言葉だ。ギヨームが得た感情は、感覚は、いつだって正しいものだ。
感じることができたのならば、それは真実にも勝るものであったことだろう。
今、ダークセイヴァー世界の謎が一つ明らかにされたのだとしても、ギヨームは依然変わらずギヨームのままだ。
「血の海は生命の根源として大地を満たすだろう。だが、悪いけどおれは君の辿った道筋に興味がない」
そう、何故ならば。
「地上に太陽があるとして、そこに海はあるのだろうか。今のおれの頭の中にはそれしかないんだ」
ギヨームが駆け出す。
そんな彼目掛けて放たれる薔薇の花弁は鋭さを増して、その身に流れる血潮でもって大地を潤さんとするだろう。
けれど、ギヨームの手には氷槍が存在している。
手始めと投げ放たれた槍が迫る薔薇の花弁を尽く蹴散らしながら突き進む。それを影にするようにギヨームは疾駆し、『異端の騎士』へと肉薄するのだ。
「大地を血で満たさなければ。満たして、満たして、溢れさせなければ……!」
薔薇の花弁が再び剣の形を為していく。
隻腕となり、胸を穿たれ鎧を砕かれても尚、目の前の『異端の騎士』に感じるのは空虚なる狂気だけであった。
ギヨームの心のなかにある焦がれるような情動は何一つなかったことだろう。
だからこそ、彼の瞳はユーベルコードに輝く。
「太陽熱に侵される」
手にしたレイピアの切っ先から炎が噴出し、刀身に纏う。
それこそが彼のユーベルコード、É.D.C.S.(エブイヤンテダンシャルールソレイユ)。
レイピアは刺突の為の刀剣である。
放たれた氷槍は薔薇の花弁に削られてボロボロで、たとえ『異端の騎士』に命中したとしてもダメージを追わせることはできなかっただろう。
けれど、それでもよかったのだ。
砕けた氷がキラキラと炎の輝きを反射させ、ギヨームの瞳を照らす。
己が何をしなければならないかなんて、ギヨームにはとっくに理解していた。
「血をかぶったことすら忘れてしまうほどに求めるならば、一度頭を冷やしたらどうだ。太陽が君に与えるのは――」
突き立てられる刀身。
鎧の内側に到達した一撃は、その切っ先より放つ高圧力の熱湯によって『異端の騎士』の背中まで一気に貫き、その身を吹き飛ばしていく。
「熱湯だが、植物にはちょうどいいさ」
炎が辺境の地の暗闇をぼんやりと照らす。
それは篝火のようなものであったことだろう。未だ人々がこの篝火を目指すにはダークセイヴァー世界はあまりにも過酷である。
だからこそ、ギヨームは胸に海への焦がれる慕情の如き感情を抱き、『第三層』に繋がるであろう道を求めるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 月夜・玲
月夜・玲
夜が明けないのはどんな仕掛けかと思ったら何の事は無い天井があったってオチだったのか
とはいえ、これだけの広大な地下を維持するのも普通じゃないんだけど…
まあそれも進んでみなきゃ分からない事か
第3層への手掛かりあれば良いんだけどね
●
《RE》IncarnationとBlue Birdを抜刀
こいつからは情報は得られないか
本当にこんなオブリビオンが辺境をうろついているなんて嫌な世界
【雷鳴・解放】起動
軍馬の速度にはこっちも高速移動で対応
接近して並走し攻撃していこう
騎士の剣を片手の剣で『武器受け』して受け流し、もう片手の剣で攻撃
稲妻を纏わせた斬撃で軍馬ごと纏めて『なぎ払い』斬り割く!
悪いけど君に用事は無いんだ
ダークセイヴァー世界は、数ある世界の中でも常闇が支配する世界である。
ヴァンパイア支配盤石たる世界にあって、それはある意味当然のものであっただろう。太陽の昇らぬ世界。
そこには如何なるからくりが存在していたのか。
太陽を覆い隠す何かがあるのか。
はたまたオブリビオンによる如何なる力によるものか。
考えは尽きねど、答えは得られず。
けれど、そんな世界のからくり、書き割りを引き裂く時が来たのだ。
ダークセイヴァーの地下世界、『第五の貴族』と呼ばれるオブリビオンの言葉によれば、地上であったと思われた世界ですら『地下』――『第四層』であると言う。
ならばこそ、太陽が昇らぬのも道理である。
「夜が明けないのはどんな仕掛けかと思ったら、何のことはない。天井があったってオチだったのか」
月夜・玲(頂の探究者・f01605)は、未だ常闇に覆われる世界の空……否、天井を見上げてつぶやいた。
単純な話であったとは言え、これだけの広大な地下を維持するのも普通のことではない。
如何なる理屈、如何なる理由で人々が地下に追いやられていたのか。
「まあ、それも進んでみなきゃわからない事か。『第三層』への手がかりあれば良いんだけどね」
蒼き光を放つ模造神器を二振り抜刀した玲の前に在るのは『狂えるオブリビオン』である『異端の騎士』が騎乗する漆黒の軍馬である。
こちらを睥睨する『異端の騎士』はすでに隻腕。
胸は穿たれ、鎧は砕かれていても尚、その空虚なる狂気は止まらない。
「叛逆の証を。大地に血を満たさなねければ。私の叛逆は証明されない。血を、血を、血を、大地に血を満たして溢れさせなければ」
そこにあったのは矜持でも誇りでもない。
いかなる理由があり、人類を裏切りヴァンパイア支配に恭順を示したのかはわからない。
「こいつからは情報は得られないか」
玲はうんざりする気持ちであったことだろう。
こんなオブリビオンが辺境の地をうろついているなんて嫌な世界であると、その瞳をユーベルコードに輝かせながら抜き払った二振りの模造神器から開放された雷の疑似UDCの力を身にまとわせる。
雷鳴・解放(ライトニング・リリース)――。
それは彼女を雷の如き速度でもって暗闇の世界を切り裂く力へと変えるユーベルコードの輝きである。
稲妻をまとった斬撃が疾走する漆黒の軍馬すらも物ともせず、並走しながら雷撃を放出し続ける。
「馬上でその得物を長々と振るうのは疲れるでしょ」
確かに騎乗した騎士という機動力は凄まじいものであったことだろう。
けれど、玲はただ一人、生身単身でもって、それを凌駕する速度を得ている。
彼女が造り上げた疑似UDCの力。
雷撃を振り払い、『異端の騎士』が放つ斬撃の一撃を手にした模造神器で受け流し、もう一振りの模造神器が雷撃の力を纏わせた斬撃の一撃を持って漆黒の軍馬ごと『異端の騎士』を両断する。
「悪いけど君には用事は無いんだ」
得られるもののない存在。
ただ、そこに在るというだけの存在。それが『異端の騎士』である。
ならばこそ、そこに時間を掛けるという意味はない。
玲のはなった一撃は、『異端の騎士』の悔恨と贖罪、それすらも空虚に飲み込む狂気ごと斬り裂き、辺境の地へと一歩を踏み出すのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 トリテレイア・ゼロナイン
トリテレイア・ゼロナイン
狂気に呑まれた相手には詮無き事やもしれませんが……
反逆の騎士を名乗るなら、手に掛けんと相対する者をせめて正視しなさい…!
殺戮喰血態の剣に対し怪力で振るう剣と盾で応戦
それが出来ぬなら、貴方が求むる流血を為せぬ私がお相手しましょう
それが、同じ騎士として出来るせめてもの…
幾たびかの剣戟で相手の戦法を情報収集
最早反射という名の残骸ならば、技を見切るのは容易き事
この世界が地の底であろうと
希望を掴む為、果て無き道を私は騎士として歩みましょう
此方のUCの電脳禁忌剣の鋭い突きを放ち、相手の甲冑の関節部を破壊
剣を振るう動作を鈍らせ大盾殴打、相手の剣を弾き飛ばし
貴方はどうなのです…!
諸手で握った剣を一閃
その瞳には狂気しかないことをトリテレイア・ゼロナイン(「誰かの為」の機械騎士・f04141)は知っている。
それが詮無きことであることも理解している。
けれど、騎士を名乗る『狂えるオブリビオン』、『異端の騎士』を前にして彼の炉心は激情を顕すかのように燃え盛るばかりであった。
叛逆の騎士。
「その名を名乗るなら、手に掛けんと相対する者をせめて正視しなさい……!」
『異端の騎士』の瞳に映っているのは、己達ですらないのかもしれない。
目の前に存在する者全てを鏖殺し、大地に血を見たさんとする『異端の騎士』にとって己が屠る者を理解することな無意味であったことだろう。
「血を、血を、血を。血で大地を満たす。溢れんばかりの血路でもってお出迎えを差し上げなければ」
意味のない言葉。
嘗て在りし道程すらも塗りつぶす狂気を前にしてトリテレイアは己を襲わんとする殺戮の剣を見据える。
手にした大盾と『異端の騎士』が振るった斬撃が激突し、火花を散らせる。
猟兵たちとの戦いによって隻腕となり、胸を穿たれ鎧すらも砕かれた空虚なる狂気に駆り立てられる『異端の騎士』は、それでも尋常ならざる膂力でもってトリテレイアを追い詰めるであろう。
「やはり、出来ませんか。ならば、貴方が望む流血を為せぬ私がお相手しましょう。それが同じ騎士として出来るせめてもの……」
贖罪であり、手向けである。
互いの剣が剣戟の音を響かせる。
最早『異端の騎士』にあるのは過去の反芻でしかない。
反射で動くだけの存在。剣をふるわれれば、剣で持って受け止め、ありあまる膂力でもって弾き飛ばす。
隻腕になって尚、その力の衰えは見ることはできない。
それを騎士の残骸、その名残とトリテレイアは理解しただろう。
「この世界が地の底であろうと、希望を掴むため、果てなき道を私は騎士として歩みましょう」
そこに何の感慨も見いだせぬほどに空虚なる存在へと堕したのならばこそ。
機械騎士の精密攻撃(マシンナイツ・プリセッションアタック)は、振るう電脳禁忌剣によって鎧の隙間、その肉体を貫くのだ。
「血に染まった道を。我が誇り、我が忠誠を」
示さねばならぬというように貫かれた体のまま『異端の騎士』がトリテレイアに剣を振るう。
しかし、トリテレイアの大盾の一撃が『異端の騎士』の顔面を捉え、ふるわれんとした剣ごと打ち据えて吹き飛ばすのだ。
「貴方はどうなのです……!」
投げ放つ大盾。
吹き飛ばされた剣が大地に突き刺さる。剣を手放すことは騎士の誉を損なうものであったことだろう。
それすら理解できぬ傀儡の如き『狂えるオブリビオン』へと堕ちた存在を前にトリテレイアは騎士としての矜持を、と両手で握りしめた剣を振りかぶる。
嘗て如何なる理由があったのかを知る術はもう何処にもない。
あるのは叛逆の騎士であるという事実のみ。
その事実だけが、誇りと矜持の抜け落ちた体躯を突き動かしている。哀れとは言うまい。
それは嘗ての騎士に対する侮辱であったことだろう。
応える言葉もなく。
在り得たはずの結末すらも失った存在にトリテレイアは剣の斬撃でもって、終わりという結末をもたらすことしかできなかった。
「騎士として、貴方を滅ぼす。それだけが私にできる手向け。人々が陽光の光を求めるその先に、血に塗れた大地など不要!」
それは血路を拓くのではなく、轍を刻むこと。
いつかこの先に繋がる地上への道があるのだとして。
誰しもが求める道へと到れるようにと願いを籠めて、トリテレイアは騎士としての一閃でもって『異端の騎士』、嘗ての騎士へと袂をわかち、辺境の果てを目指すのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 馬県・義透
馬県・義透
四人で一人の複合型悪霊。生前は戦友
第一『疾き者』唯一忍者
一人称:私 のほほん
武器:漆黒風
遅れましてー。ま、今から行っても大丈夫でしょう。
地上への希望を繋ぐためなんですからー。
さて、血ねぇ。ここに流させるわけにはいきませんし。
漆黒風を投げて、途中から指定UC発動。花には花を…というわけで。
鬼蓮よ、相手を切り刻みなさいなー。
ええ、そちらの花は届きませんよ。私だけでなく、中の三人も結界を張る…四重(風、氷雪、炎、重力)結界になってますのでねー?
この先に向かいますよ。それが希望ってものですからねー。
そう、何が待っていようと、ね。
『異端の騎士』の上げる慟哭の如き叫びは、痛みに喘ぐものであったか。
それとも己が叛逆の騎士であることへの悔恨であったか。
そのどちらも正しくはなかったのだろう。彼は『狂えるオブリビオン』である。その瞳にも、空虚な如き肉体にも、宿っているのは狂気だけである。
「地に地を満たさねば。溢れんばかりの血でもって、満たさなければ私の叛逆は認められない。私の矜持、私の誇り。私の」
最早、狂ったように血を求める隻腕となり、身に穿たれた傷すらも厭わずに『異端の騎士』は辺境の地に足を踏み入れた存在を排除せんと剣を振るう。
振るった剣の刀身が薔薇の花弁となって暗闇だけの世界に舞い散る。
そんな死を運ぶ薔薇の花弁舞い散る中になって、ひときわのんびりとした声が響き渡る。
「遅れましてー。ま、今から行っても大丈夫でしょう。地上への希望を繋ぐためなんですからー」
四柱によって存在している複合型悪霊である馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)の一柱である『疾き者』が辺境の地にある『異端の騎士』の前に姿を顕す。
それは彼を此処で討ち滅ぼすという意志の現れであったことだろう。
「血、ねぇ。ここに流させるわけにはいきませんし」
そう、このダークセイヴァー世界にあっては、人の生命は、その血潮は絶え間なく流れ続けるものである。
ヴァンパイア支配盤石たる世界にあって、人の命とは路傍の石よりも軽いものである。弄ばれ、棄てられるだけのものでしかない。
だからこそ、『疾き者』は手にした棒手裏剣を投げ放ち、薔薇の花弁を突っ切って進む。
その棒手裏剣の一撃は『異端の騎士』を狙ったものであったが、その切っ先が彼に突き立てられることはなかった。
『疾き者』の瞳がユーベルコードに輝く。
「これは『鬼』であった私が、至った場所――四天境地・風(シテンキョウチ・カゼ)」
そう、投げ放った空中で棒手裏剣が鬼蓮の花弁に姿を変える。
それは奇しくも『異端の騎士』が放つユーベルコード、その薔薇の花弁と似通った力であったことだろう。
「花には花を……というわけで。鬼蓮よ、相手を切り刻みなさいなー」
薔薇と鬼蓮の花弁が舞い散る戦場。
鬼蓮の花弁が『異端の騎士』の身を切り裂いていく。
声もなく、慟哭もなく、ただ身を削られる『異端の騎士』。
互いのユーベルコードがもたらす力は、互いを傷つけるものであったが、『疾き者』には薔薇の花弁が届くことはなかった。
「ええ、そちらの花は届きませんよ。私だけでなく、中の三人も結界を張る……四重結界になってますのでねー?」
一人ではない。
もしも、『異端の騎士』にも誰か隣立つ者……彼の行いを諌める者がいたのならば、彼の道行きもまた違ったことだろう。
けれど、それは詮無きことである。
すでに終わってしまったことであるし、そうはならなかったのだ。だからこそ、『異端の騎士』の慟哭に耳を貸してはならない。
嘗て在りし誇りも、矜持も。
オブリビオンとなった身には一欠片とて存在していないのだから。
「この先に向かいますよ。それが希望ってものですからねー」
『疾き者』は花弁の中に消え往く『異端の騎士』を背に辺境へと足をすすめる。
「そう、何が待っていようと、ね」
進まねばならない。
どれだけ困難な道に見えるのだとしても、険しい遠回りの道なのだとしても。
それでも、その先に人々が求める陽光差す大地に繋がる何かがあるのならば。ためらわずに一歩を踏み出すだろう。
それこそが己たちの存在する意義であるというように『疾き者』は未踏の人外魔境へと進むのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
第2章 冒険
『未明の山岳地』
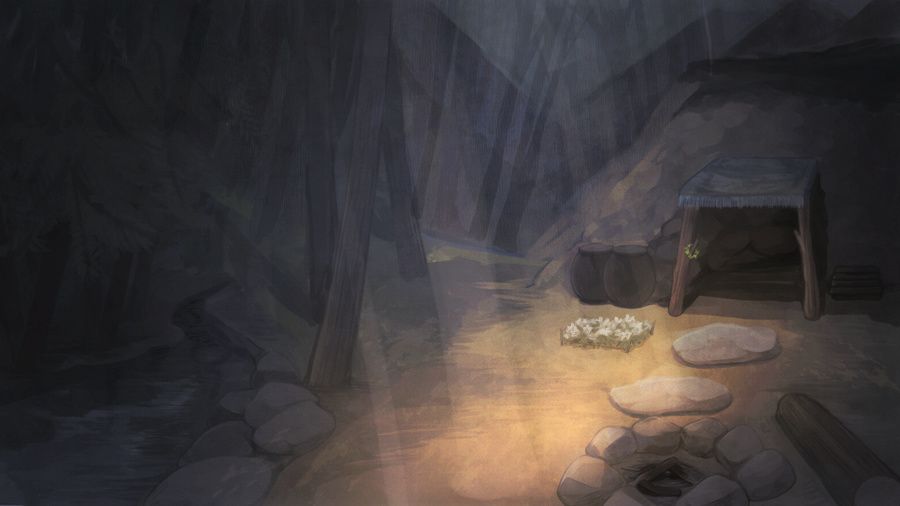
|
POW : 岩壁を登り体力頼みの最短ルートで向かう
SPD : 足場の崩れにくいルートを目視で探す
WIZ : 天気や地形情報から安全なルートを割り出す
イラスト:とりのこ みな
|
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
見上げるは山岳。
辺境の果て。暗闇だけが続く世界にあって、これほどの山岳地域が存在していたことを猟兵達は知らなかったことだろう。
高き山。けれど、その山際を夜明けの光が照らすことはない。
どれだけ登ればいいのか。
この山を越えれば、そこに『第三層』に至るための何かが在るのか。
それさえもわからない。
けれど、この山を越えなければ辺境の果てには辿り着くことはできないだろう。
人を寄せ付けぬ岩肌。
いつ滑落してもおかしくない難所。
落石もあるかもしれない。そもそもルートが存在しているのかも怪しいものである。
全てが無駄足になってしまうかもしれないという可能性は棄てきれない。
瞳を閉じれば、ダークセイヴァー世界に生きる人々の姿が在るだろう。虐げられ、生命の価値すらも塵芥と同じ様に扱われる人々の姿。
彼らの瞳に陽光は輝かない。
なぜなら、この地は地下であるからだ。天を覆うは大地の蓋。
いかなる理由で彼らが、この地に在るのか。
彼らを開放する。
ヴァンパイア支配からも、暗闇からの支配も。
あらゆる軛を取り払い、人々を開放するために猟兵達は今、険しき山へと挑むのだった――。
 馬県・義透
馬県・義透
【馬県さんち】
引き続き『疾き者』
一応、クルワとも長い付き合い。
はてー、また凄い山に着きましたねぇ。
そして、クルワに追い付きましたねぇ。
さて、どうしましょうかねー?
…考えとしては同じですねー。強化した天候操作で風は制御できますし。
では、私と陰海月が先頭でー。
陰海月に乗りましてー。
陰海月が張りきってますねー。こういうところ、得意だそうですよ?いつのまに。
落石は弾力性持たせた結界で、一時的に包みましてー…頼みましたよ、クルワ。
※
陰海月、とても張りきる!密かに訓練した!ぷきゅぷきゅ!
 外邨・蛍嘉
外邨・蛍嘉
【馬県さんち】
引き続きクルワ。『疾き者』とは長い付き合い
…山に気圧されていたら、義透に追い付かれマシタネ。
デスガ、よいタイミングデス。
ワタシは、陽凪に乗って足元の影響を抑えつつ、邪魔な岩は粉微塵に斬ろうかと。
エエ、先頭お願いシマス。
陽凪に乗りマショウ。
オヤ、張りきってマスガ…特訓の成果、ト?いつのまに。
エエ、任されマシタ、義透。その包まれた落石、UC利用の斬撃にて粉微塵にシマショウ。
万一、下に人がいたら危険デスノデ。
※
陽凪、実は陰海月と一緒に訓練してた。ゆらゆら。
その山岳は見上げるだけで暗闇の中に吸い込まれそうな威容であった。
暗闇だけが支配する世界ダークセイヴァーにおいて、山を見上げているのか、それとも谷を見下ろしているのかさえもわからなくなる闇夜は外邨・蛍嘉(雪待天泉・f29452)、その人格の一つである『クルワ』にとって気圧されるものであったことだろう。
先に辺境の奥へと足を進めていた『クルワ』の背後から声を掛ける者がいる。
「はてー、また凄い山に着きましたねぇ。『クルワ』、追いつきましたよー」
のんびりとしたような、間延びしたよな喋り方は、馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)、複合型悪霊の一柱である『疾き者』その人であった。
『クルワ』との付き合いもないが『疾き者』と二人は巨大な山岳地域を見上げ、息を吐き出す。
追いつかれたことに対して別に思うところが在るわけではない。
「追いつかれマシタネ。デスガ、よいタイミングデス」
『クルワ』はドクターフィッシュの『陽凪』の上に乗る。
それは誤ってメガリスを飲み込んでしまった巨大熱帯魚である。本来であれば水中に潜む生物であるが、空中でも泳ぐように飛ぶことができるのだ。
ふわりと不思議な光景を描く『陽凪』と共に『クルワ』が山岳地域を登っていく。
それを見やり、『疾き者』もまた似たような考えを持っていたことに微笑む。
「四悪霊・『界』(シアクリョウ・サカイ)……さて、強化した天候操作で風を制御しましてー」
『疾き者』は『クルワ』と違い、ユーベルコードでもって周囲の環境を己達に利するようにと操作する。
風を制御し、『陰クラゲ』と共に『陽凪』に乗る『クルワ』に先行してふわふわと風に乗っていくのだ。
このダークセイヴァーの山岳地域にあっては、強烈な風や落石も予想できる。二人で協力したほうが早く頂きに到達できると考えたのだろう。
二人は言葉を多くは交わさない。
その必要がないのは、これまた長い付き合いであるからであろう。
「先頭お願いシマス……オヤ、張り切ってマスガ……」
「『陰海月』も張り切ってますねー」
二人が乗るジャイアントくらげと巨大熱帯魚は、こういう時のためにと各自特訓をしていたのだという。
「ぷきゅぷきゅ!」
『陰海月』と『陽凪』は一緒に訓練をしていたと言うように鳴いている。
『いつのまに』と『疾き者』と『クルワ』の言葉が重なる。
本当にいつの間にである。
二匹が得意dと言うので任せたまま、二人は山岳地域を登っていく。風は天候操作でどうにかなる。
こうして追い風のように駆け上がっていく谷風を利用すれば、無理なく山岳地域を登ることができるだろう。
だが、問題が一つある。
そう、落石の問題だ。こればかりはいつ襲ってくるかもわからない。兆候すらも捉えることは難しいだろう。
「とは言え、落石には注意ですねー……」
「……音が、聞こえましたネ」
『疾き者』と『クルワ』が同時に気がつく。何か重い音がした。したように聞こえる、と判った瞬間、二人の眼前に迫るは巨大な岩石であった。
山岳の何処かが崩れたのであろう。
石片を撒き散らしながら転がり落ちてくる岩石は、まともに受けては猟兵であろうとひとたまりもないだろう。
勿論、二人を運ぶ巨大生物たちだってそうだ。
ならばこそ、『疾き者』は落石を弾性をもたせた結界で一時的に包み込む。
「結界が突き破られますねー……受け止めきれないのであれば、頼みましたよ、『クルワ』」
『疾き者』が己の背後に視線を向ける。
弾性を持った結界が弾けるようにして岩石の勢いを殺し、それでもなお落下の衝撃は耐えられるものではないことを知らしめる。
だが、それで十分だったのだ。
『クルワ』の瞳がユーベルコードに輝く。
「エエ、任されマシタ、義透」
目の前の驚異を躱すことは容易であったことだろう。
けれど、この山岳を踏破する猟兵達は未だ後続に存在している。ならばこそ、この岩石は避けてはならない。
『クルワ』が振るう妖影刀の棘一閃(キョクノイッセン)がふるわれる。
それは一瞬にあって巨大な岩石を粉微塵にまで切断せしめる絶技。
万が一ということもある。
降りしきる自然の猛威。誰も止めることのできぬ驚異であるのならば、猟兵達は互いに協力することも必要不可欠であろう。
先行していた二人の行動に寄って落石は対処可能なまでに粉砕される。
「ふぅ、これで大丈夫デショウ。これがダークセイヴァーの山岳。どこまで言っても生命を拒絶スルノデスネ」
『クルワ』は見上げる。
未だ頂きは遠い。そして『疾き者』もまた見果てぬ闇の向こう側を見据えるのだ。
この山岳を踏み越えた先に辺境の果てがある。
そこに『第三層』に繋がる何かが存在していることを今は信じるしかない。道のりは険しく、さりとて確実な道が容易されているわけではない。
「まさに暗中模索というやつですねー……」
しかし、それこそがダークセイヴァー世界という常闇を照らす篝火となる。
この山岳を越えた先が『常闇の燎原』であるというのならばこそ、進むべき道は示されている。
どれだけ果てしない道程に思えたのだとしても、それでも人は進む限り到達することができると知る。
今だ遠き『第三層』。
その道の手がかりを求め、『疾き者』と『クルワ』は危険な山岳地域を登りゆくのであった――。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ニノマエ・アラタ
ニノマエ・アラタ
……敵は存在しないわけだが、
狙撃のポイントを探すつもりで足場を踏みしめ、
安全を確保し移動する。
……頼りにならねェ勘頼みとか、したくはねェけど。
ま、そういう時も自分の今までの経験を信じて、だな。
見上げても空が無いって不思議な風景だ。
山の頂上にこの世界を救うためのナニカがあるって聞いても、
漠然としすぎていていまいち掴めない。
……戦いの中じゃないと掴めない、っていうの
俺の場合多すぎなんだが。
遠足気分で楽しめるほど山を知っているわけでなし。
ただ、この岩肌は溶岩なんだろうか、
どういう地層なんだか、多少疑問に思って触れてみたりはする。
化石が埋まってたりとか……無い?
……多くの血が、染み込んでるんだろうか。
進むべき道はすでに示されている。
辺境の果て――『常闇の燎原』と呼ばれた『第四層』における人類の居住区域の外。
そこに何が在るのか、それとも何もないのか。
確証に至るものは未だ猟兵たちの瞳に触れることはない。
この常闇の世界ダークセイヴァーにおいて、空と思っていたものが天井であったように世界には謎が満ちている。
だからこそ、目の前の山岳を登り越えなければならない。
「……敵は存在しないわけだが」
ニノマエ・アラタ(三白眼・f17341)は、己の目の前に広がる暗闇に包まれた山岳を見上げる。
まるで山を見上げていると言うよりも暗闇の中に堕ちていくような感覚さえ覚える。
通常の登山とはまるで違う環境。
アラタは慎重に足場を踏みしめて、岩肌に手を伸ばす。
掴んだ岩の出っ張りさえも心許ないと思ってしまう。
それほどまでにこの山岳地域を乗り越えるのは難しい。
何も情報がなかったことも響いている。ルートを見定めることも暗闇の世界では難しいだろう。
「……頼りにならねェ勘頼みとか、したくはねェけど」
とは言え、こういうときにこそ今まで培ってきた自分の経験を信じることも必要だ。
見上げても空がない世界。
それがダークセイヴァーであり、他世界を知るアラタにとっては不思議な光景であったことだろう。
この山岳の頂きにこの世界の救うための何かがあると聞いても彼は漠然としていて、雲をつかむような話であるとさえ思っただろう。
「……戦いの中じゃないと掴めない」
それがアラタの人生における一つの教訓であった。
彼の人生経験がどれほどに困難な満ちであったのかはうかがい知ることしかできない。けれど、それでもアラタは自分自身の経験の中では多すぎるとさえ思っていた。
楽に手に入れられるものならば、そうしたい。
けれど、それはいつだって正しいものではないのだ。険しく厳しい道のりの先にこそ、得られるものがあると知るからこそ、岩肌の突起を掴んで登っていく。
「ここはどういう経緯で生まれた山岳なんだ……?」
暗闇の中、それもおそらくは地底の世界。
そこにある山岳は触ってみてもよくわからなかった。
地層であるとか、含有される鉱石だとか、そういった観点からも何か得られるかもしれないと思ったが、アラタには何もわからなかった。
化石とか埋まっていたりしないかと、少しだけ心が踊るものであったが、それもまた限られた時間ではわからないだろう。
そうしたものは多くの時間と資材をなげうって初めて見つかるものであり、あとは偶然という名の運命に任せるしかないのだろう。
「……多くの血が染み込んでるんだろうか」
これまでダークセイヴァー世界では多くの生命が喪われてきた。
それは時に徒に。時に運命に翻弄されるように。
多くの血が大地に染み込んでいった。対峙した『異端の騎士』でさえ、その一滴の染みにしか過ぎない。
ヴァンパイア支配とはそういうものである。
だからこそ、アラタは山岳の岩肌を登っていく。結局のところ、一つ一つ積み重ねていくしかないのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
 リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル
…猟兵になってすぐの頃は一地方の領主を討つ事すら難儀していた
…そんな私が世界の果てを見に行こうとしているのだから、
思えばここ数年で随分と遠くに来たものだわ
…なんて。まだ道半ばも良い処なのに物思いに耽るには早過ぎる、か
…そうね、何も悩む必要なんて無かったわ
例え、この先に何が待ち構えているとしても、私の為すべき事に変わりはない
…人類に今一度の繁栄を。そして、この世界に救済を…
…この誓いを果たすまで、私の闘いは終わらないのだから
UCを発動し風の精霊を降霊し肉体改造を施して精霊化を行い、
残像のように肉体を風に変化して落石等を受け流しつつ、
空中機動力を強化する風のオーラで防御して山道を飛翔して先に進むわ
リーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は己のこれまでの道のりを振り返る。
暗闇の世界ダークセイヴァーにありて、猟兵となった彼女。
彼女がたどる道のりはあまりに険しいものであったことだろう。ヴァンパイア支配盤石たる世界にあって猟兵とは強者を意味する者ではなかった。
一地方の領主を討つことすら困難なことであったのだ。
血に塗れた。
勝利と呼ぶにはあまりにも辛勝である経験もあったことだろう。
喪われていく人々の生命。
弄ばれ、ただ消耗品として扱われるだけの存在。それがダークセイヴァーにおける人間の立場であった。
それを覆さなければならないと立ち上がる気概こそがリーヴァルディの足を止めさせぬもの。ならばこそ、彼女は今の自分を見下ろす。
「……そんな私が世界の果てを見に行こうとしているのだから、思えばここ数年で随分と遠くに来たものだわ」
目の前にそびえる山岳。
この先にある『常闇の燎原』。
そこにこそ『第四層』から『第三層』に繋がる何かが存在しているかもしれない。ならばこそ、彼女はためらわずに進むのだ。
「……なんて。まだ道半ばも良い処なのに物思いに耽るには速すぎる、か」
彼女は頭を振る。
どれだけ険しい山があるのだとしても。それを障害として捉えるのならば、踏破する以外の選択肢を持ち合わせていない。
「……そうね、何も悩む必要なんてなかったわ。例え、この先に何が待ち構えているとしても、私の為すべき事に代わりはない」
彼女の体の周囲に風や光の精霊たちが集っていく。
輝く瞳が発露するユーベルコードは、吸血鬼狩りの業・変幻の型(カーライル)。
己の体に風の精霊を宿し、精霊化した彼女が宙に浮かぶ。
「……人類に今一度の繁栄を。そして、この世界に救済を……」
リーヴァルディが見上げる先にあるの山岳の頂き。
空を舞うようにして飛び立つ彼女に落石が襲うだろう。凄まじい横殴りの風が襲うこともあるだろう。
けれど、彼女は何ものにも怯むことはない。
彼女が立てた誓いはたった一つである。
世界に救済をもたらすこと。今も尚虐げられ続ける人々が、他世界の人々と同じ様に繁栄を手にすること。
陽光の元で笑い合う彼らの姿。それをもたらすまで彼女の闘いは終わらない。
「一気に飛翔するわ……」
加速していくリーヴァルディに襲い来る厳しい自然の洗礼。
けれど、そのどれもが彼女を止めること能わず。
落石を風で受け流し、荒ぶ風すらも精霊化した力によって追い風に変えて飛翔し続ける。
見据える未来を彼女はもう知っている。
いつだってそうだ。
誰からか与えられるものは、ひどく脆いものばかりである。
真に欲するものがあるのならば、己の手で勝ち取らなければならない。それこそが真であると知るからこそ、リーヴァルディは辺境の果て、『常闇の燎原』を目指す。
頂きに至る先に、彼女は見ただろう。
この暗闇の世界にあってなお燻るような黒き炎を――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
さて、この暗さでは頂上どころか中腹も見えませんが、ただの岩肌ではなくここに山があるのでしょうね。
歩いていくのは危険ですが、飛行も衝突が怖い、と。ならば……
【氷晶の巨鳥】を使用し、全長17mの鳥の形の「氷晶ゴーレム」を作成します。
速さよりも耐久力を重視して作りました。この大きさであれば多少の風では揺るぎませんし、落石にも負けません。
自身の『視力』で山肌が見える程度の高度を維持しつつ空を飛んで山を登っていきます。落石は音で察知し、巨鳥の嘴で砕いて先へ進みます。
辺境の果てに踏み込んだ猟兵達の眼前にそびえるは山岳地域であった。
暗闇が支配する世界にあって、これほどの山岳が存在していること事態、はじめて知る者もいたことだろう。
ここが地上ではなく、地下の一つであることを知った後であれば、尚の事である。
暗闇に包まれているせいで、山の際もわからない。
どれだけ登っても今自分が山の何合目に位置しているのかもわからないだろう。そう、ここは人類未踏の地である。
人外魔境たる辺境の果ては、この先に何が待ち受けているのかさえ教えてはくれない。
「さて、この暗さでは頂上どころか中腹も見えませんが、ただの岩肌ではなく此処に山が在るのでしょうね」
セルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)は眼前に立ちふさがる自然という名の障害を前にしても普段と変わらぬ平静さを保ったままであった。
このダークセイヴァー世界出身の彼女であっても、このような山岳地域があることを知らなかっただろう。
猟兵となって他世界を見てきたからこそ、目の前のこれが山であると理解することができる。
同時に山を登るにあたっての危険性もまた理解していたのだ。
急な斜面、暗闇故に視界が確保できずどこに亀裂が走っているのか、それもわからない。飛行して一気に飛び越えようとしても強風に煽られて岩肌に激突することも考えられる。
「……ならば」
セルマの瞳がユーベルコードに輝く。
氷晶のゴーレムが彼女の眼前で作成され、氷晶の巨鳥(ヒョウショウノキョチョウ)へと姿を変える。
羽撃く氷の翼は冷気を撒き散らし、セルマを背に乗せて目の前にそびえる山岳を越えようと飛び上がるのだ。
確かに強風が吹き荒れている。
ただ闇雲に飛翔しようとすれば、風に煽られてバランスを崩して大地に失墜するだろう。
けれど、セルマは氷晶ゴーレムを作り出す際にスピードによる踏破よりも耐久性を重視して作り出した。これだけの巨大な氷晶ゴーレムであれば多少の風でもゆらぎはしないであろうし、落石も余程の巨大さでなければものともしないだろう。
「辺境の果て……これほどの自然の猛威があるとは思いもしませんでしたが……」
だが、それもうなずけるものであった。
これほどの自然の猛威が吹き荒れる地域にあって、虐げられるだけの存在である人類が生存できるわけがない。
故に誰も存在していない。
セルマは氷晶ゴーレムと共に飛翔を続ける。どこまでも続く岩肌。彼女の視力をもってしても、中々山の際、頂きが見えてこない。
「この先が、辺境の果て……『常闇の燎原』……」
如何なる光景が続いているのか。
そして、『第三層』に至る何かが本当に存在しているのか。
何一つ確証のないまま進む道のりは、これまで彼女が生きてきた道のりと同じであったことだろう。
成功が保証されていない。失敗したとしても、やり直す機会が与えられる理由もない。いつだって彼女は支配に抗ってきた。
支配に抗うとはそういうことである。
機会の一つとて与えられない。勝ち取るしかないのだ。
セルマの瞳は頂きに座す炎を見た。
黒い炎。いや、人影である。この生命を許さぬ辺境の果てに座す存在など、ただ一つしかない。
そう、オブリビオン。
『常闇の燎原』という『第三層』に繋がるかもしれない何かが存在する間際にあって、オブリビオンが座している。
「ここが越えるべき障害……」
飛び越えるのではない。そう、踏み越えるために彼女は山頂に座す黒炎を見据えるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 大町・詩乃
大町・詩乃
山岳の頂にオブリビオンが陣取っている以上、ユーベルコードでひとっ飛びなどしようものなら狙い撃ちされて危険ですね💦
地道に山を登って行きましょう。
ですが、田舎で巫女の仕事を日々こなして体力は有るとはいえ、登山の専門家では無いので身体能力だけで登るのは難しい箇所も有るかも・・・。
そういう崖になっている所などは空中浮遊&念動力でふよふよと浮いて乗り越えていきます。
持ち前の幸運で比較的登りやすいルートを見つけ出し、天候操作で強風を鎮め、落石や崖崩れなどは第六感で予測し、UC:慈眼乃光で落石や崖崩れという自然現象そのものを友好的にして危機を脱します。
念の為、結界術による防御壁やオーラ防御も展開しますよ。
グリモア猟兵の予知によれば、この山岳地域の山頂にてオブリビオンが陣取っているということであったのを大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)は思い出していた。
敵に己の頭上を抑えられているというのは、戦いに挑むに際して有利とは言えないものであったことだろう。
だからこそ、ユーベルコードで山岳を一息に飛び越えようとするのならば狙い撃ちにされてしまうかもしれないと、詩乃はその可能性を考えていた。
「……やはり危険ですね。地道に登っていくしかないのでしょう」
詩乃の眼前にあるのは暗闇の世界にあって、これだけの巨大な山が存在していたのかと、ダークセイヴァー世界の謎を深める厳然たる事実。
人の足で踏み越えるにはあまりにも険しい道のり。
急な斜面や、崖と見紛うほどの岩肌。落石もあるであろうし、進めば進むほどに標高が高くなり強風が吹き荒れる。
人の、生命の存在を寄せ付けぬが如き山岳を詩乃は躊躇いなく一歩を踏み出すのだ。
「登れないわけではないようですね」
これでも詩乃は田舎で巫女の仕事を日々こなす猟兵の一人である。
体力には自身があるが、それでも登山の専門家ではない。卓越した身体能力に過信すること無く彼女は山岳を一歩、また一歩と踏みしめていくのだ。
「これは……崖……? 地下世界にあってもこのような地形が生み出されるとは」
そう、このダークセイヴァー世界は、これまで猟兵たちが地上だと思っていただけの世界であり、積層世界であることが判明している。
この『第四層』の地下に広がる『第五層』が存在しているのならば、『第三層』と呼ばれる、この地下よりもさらに上があることを予見させられる。
さらに、この上方の層へと至っても、さらに『第二層』、『第一層』、そして地上と未だ遠い道のりが続いている。
ふよふよと詩乃は念動力による空中浮遊を使って強風に煽られながら崖を踏破していく。
彼女は確かに自身で言うところの登山の専門家ではない。
それ故に彼女が選んだルートはただしものではなかった。けれど、神である彼女の持ち前の幸運で比較的登りやすいルートを自然と選んでいたことは、幸運を越えたものであったことだろう。
「こちらからだと、あの岩肌にアプローチしやすそうですね」
暖かく慈しむような瞳に輝くのは、慈眼乃光(ジガンノヒカリ)。それは彼女が視線を向けた先の全てが彼女に味方をするユーベルコードの輝きであった。
あらゆる生命体、無機物、自然現象が彼女の味方になる。
どれだけ自然の猛威があろうとも、彼女の道行きに障害はない。風ですら彼女が歩む間は止むであろうし、落石すらも彼女を避けて落ちて行く。
それは最早偶然と呼ぶには値しない。
彼女の持ち得た神性と力の為せる業であったことだろう。
念の為にと結界に寄って張り巡らされた防護が役に立つことはなかった。
全てが彼女の道のりから裂けていく。
障害すらもなく彼女は山岳の頂きをその瞳に映すことだろう。
「……あれが、頂に座すオブリビオン……黒炎を纏うオブリビオンなのですね」
詩乃が見やるは、山岳の頂上に一人佇む女性の姿をしたオブリビオンであった。見ただけでわかる。あれが敵であると。
あらゆる障害が避ける彼女であってもなお、詩乃の瞳に映るオブリビオンには関係がない。
暗闇の世界に黒炎がゆらめき、そのオブリビオンの唇がゆっくりと開かれるのを詩乃は見るのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 愛久山・清綱
愛久山・清綱
如何に眼を凝らしても、【暗視】能力を用いたとしても、
辺りに映るのは『闇』しかないな……
だが、今はこの闇の先に『答え』があると信じて進むのみだ!
■行
【WIZ】
何が存在するか分からない。地形を探りつつ進むのが安全だな。
大太刀の鞘を杖代わりにし、慎重に進もう。
勿論、【野生の勘】と【聞き耳】を凝らす事も忘れずに。
基本は一歩進むごとに地形を調べ、『登り道』を探りつつ進むぞ。
少しでも『登っていない』と感じたら、戻って再び道を探す。
移動の際、『大きな物体が転がってくる』ような音が聞こえたら、
音がしない方向へ退避するか、一瞬の抜刀から【無刃・渾】を放ち
流れてきたそれの【切断】を試みる。
※アドリブ歓迎・不採用可
暗闇が支配する世界、ダークセイヴァー。
それは何処までも続く暗闇が世界の全容を覆い隠すものであり、この世界を支配するヴァンパイアの力の強大さを示すものであったことだろう。
人の生命が弄ばれるだけの存在に失墜し、あらゆる尊厳が喪われた世界。
この世界に生きる人々にとって陽光は何をおいても求めるものであったことだろう。
だが、その願いは無情にも打ち砕かれている。
そもそもが此処が地上ですらない。積層した世界。地下であったのだから。
それも『第四層』と呼ばれる地上と思っていた場所の上にさらに三層もの地下が重なっていると推測されている。
猟兵たちが目指す『第三層』もそのうちの一つである。
この『第四層』の地下である『第五層』に通じる門があったように『第三層』に通じる何かがあってもおかしくはない。
「如何に眼を凝らしても、辺りに映るのは『闇』しかないな……」
愛久山・清綱(鬼獣の巫・f16956)は、己の暗視能力を用いたとしても、山頂を見通すことのできぬほどの巨大な山岳を見上げていた。
何処までも闇が広がっている世界。
どうしようもないほどの事実に彼は臆することはなかった。
見通すことのできない『闇』。それがヴァンパイア支配が盤石であるというのならば。
「今はこの闇の先に『答え』があると信じて進むのみだ!」
清綱は山岳に足を踏み入れる。
どれほどの危険が待ち受けているかわからない。地道に探りを入れつつ進むしかないのだ。
安全とは程遠い環境である。
地形はわからず、己が選んだ道もまた正しいという実感さえない。
大太刀の鞘を杖代わりにして、慎重に進む清綱。
披露は未だ無い。
けれど、彼の獣の如き野生の勘と鋭い感覚を持つ聴覚が己に迫る危機を告げる。
地鳴りがするような音。
いや、何か重たいものが転げ落ちてくるような音……それを自覚した瞬間、清綱はその瞳をユーベルコードに輝かせる。
杖代わりにしていた大太刀を構え、研ぎ澄まされた感覚でもって彼は抜刀居合によって無刃・渾(ムジン)を放つのだ。
巨大な岩石が清綱の眼前に迫り、彼を押しつぶさんとする。
けれど、居合によって放たれた斬撃が迫る巨岩を斬り裂き、真っ二つにして彼は事なきを得るのだ。
「……これほどの巨岩が常に振り落ちてくるか……なるほど。生者を寄せ付けぬ自然の猛威というわけか」
清綱は己が切り捨てた巨岩が振り返った崖下に落ちていくのを見やる。
あれほどの質量であれば、如何に猟兵と言えど当たればただでは済まないだろう。
清綱は己が辿った道を探りつつ進む。
一歩前進して、また一歩下がる。暗闇の中では平衡感覚も狂っていくし、方角もわからなくなってしまう。
頼れるのは己の野生の勘だけである。
それが如何に難しいことであるかを清綱自身が理解していることだろう。
「だが、進まねばならぬ。人々を地上に開放するためには、小さな一歩でも、どれだけ小さな事柄でも積み重ねていかねばたどり着けぬ場所があるのだ」
清綱は遠い道のりを見上げる。
未だ頂上は遠い。されど、彼の瞳に揺らめく黒炎が映る。
それは紛れもなくこの山岳の頂上に座すと言われているオブリビオンの影であったことだろう。
「黒炎……ならば、ここが辺境の果てであることは間違いないようだな」
ゆらり、ゆらりと揺れる黒炎。
それは一人のオブリビオンから発せられるものであった。揺らめき続け、ただ座して此方を見ている。
その底知れぬ重圧を感じ、清綱は己の心を叱咤するであろう。目指すべき場所がある。そして、倒さねばならぬ敵がいる。
ただその事実だけで彼は確かな一歩をまた踏み出すのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー
山というよりは、崖だなー。がむしゃらに登っていくのは体力が削られるけども、道がわからないなら多少の無茶はしないとな!
登り方としては素手で壁を伝っていくが、道がなくなったら金属ワイヤーをロープ代わりとして、真上に投擲してみよう。その為にワイヤーの先端には氷の魔力を溜めた鉤爪状の重石を付けておいて、重石が引っかかったらそれを登る
こうも暗い中、空をつたうと平衡感覚がおそろかになりそうだ。おれの夜目は冬の夕闇を昼同様に写せる程度にしか利かないから、はっきりとした向こうは見えないなー
だが、恐怖はない。寧ろ期待や好奇が勝る。この先に強力なオブリビオンが居ても、その先にある景色が見たくて上を目指しているんだ
「山というよりは、崖だなー」
ギヨーム・エペー(Brouillard glacé calme・f20226)は眼前に広がる山岳地域を見上げて、思わずそうつぶやいていた。
このダークセイヴァー世界の『第四層』にあって、これほどの山岳地域が広がっているということ事態、初めて知る事実であったことだろう。
ここが辺境の果てであり、この山岳を越えた先にこそ『第三層』に繋がる何かがあるのではないかと言われている『常闇の燎原』が広がっている。
この山岳を乗り越えねば至ることができぬのというのであれば、ギヨームはがむしゃらに登っていくことをこそ是としていた。
体力が削られるであろうし、無茶であることは承知である。
けれど、この先に至らねばダークセイヴァー世界におけるヴァンパイア支配から人々を開放する手がかりが得られぬというのであれば、その無茶をこそしなければならないと彼は奮起したのだ。
「とは言え、中々難しそうだな」
岩肌は突起やくぼみがあれど、登る事自体難しそうに思える。
それでもギヨームは素手で壁を伝って登っていく。
道なき道を往くことはなれている。それが山か海かの違いだけである。
道がなくとも、道を生み出すことができるのが人間の知性であろう。
彼の手には金属ワイヤーがある。これをロープ代わりにし、先端に氷の魔力を籠めた鉤爪をくくりつけて投げ放つ。
「道がないのであれば、作ればいいってな」
ギヨームが投げ放った金属ワイヤーが暗闇に音を反響させる。うまく引っ掛けられらと手繰る手に加わる感触で判断し、ギヨームはワイヤーを手繰り寄せながら岩肌を踏破していくのだ。
「こうも暗い中だと平衡感覚がおかしくなりそうだな……」
ギヨームの夜目は冬の夕闇を昼同様に写せる程度にしか効かない。それでもこの暗闇の世界ダークセイヴァーにあっては貴重な能力であると同時に必須でもある。
見上げても未だはっきりと頂上を見据えることはできないのだ。
この先に何が待っているのか、如何なる者が存在しているのか。
未だはっきりと視認できぬことにギヨームは、むしろ恐怖よりも期待や好奇が勝るのを感じていた。
こればかりはどうしようもない性質である。
グリモア猟兵の言葉では、この頂上に座すオブリビオンの力は紋章持ちのオブリビオンと同等の力を持っているようである。
けれど、そんなことが些細なことのように思えるほどにギヨームの期待は膨れ上がっていた。
頂上にオブリビオンが座すというのならば、むしろ燃えてくるというものである。
「この先にある景色が見たくて、見たくて、上を目指しているって気持ちになる。こればっかりは、これから戦いがあるっていうのに仕方のないって思うしかないな」
そう、どれだけ困難な道が続いているのだとしても、ギヨームは怯まないし、恐怖しない。
それは恐怖を乗りこなすたった一つの方法であったことだろう。
楽しむこと。
知りたいと願うこと。
地上であったと思われた世界ですら地下であったという事実は、人によっては打ちのめされる事実であったことだろう。
けれどギヨームは違う。
己の胸が踊るのを自覚している。この先に如何なる光景が待っているのか。
ただそれだけのために彼は黒炎が揺らめく頂上へと一気に駆け上がっていくのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 トリテレイア・ゼロナイン
トリテレイア・ゼロナイン
中々の悪路ですが、これを越えられぬようであれば騎士の名折れというもの
ええ、通常であれば馬で山越えなど愚かと言わざるをえませんが…
電脳禁忌剣を一振り
電脳空間に格納(物を隠す)していた機械馬を呼び出し騎乗
私とロシナンテⅡの性能であれば話は別
避ければ怠慢の誹りを免れませんからね
マルチセンサーでの暗視による情報収集で地形把握
断崖一歩手前の傾斜から機械馬の蹄の置き場を瞬間思考力で●見切り
騎馬のスラスターの●推力移動も合わせて跳躍繰り返し、道なき絶壁を駆け上り
落石とは…また難儀な事ですが
UC起動
防御障壁を纏い●怪力で突き出す馬上槍で真正面から粉砕
立ち止まっている暇はありません
いざ、『常闇の燎原』へ!
目の前にそびえる山岳地域。
これを乗り越えなければ猟兵たちが目指す『常闇の燎原』に至ることはできない。
辺境の果てとは、つまるところ生命の存在を許さぬ領域である。
それはオブリビオンの存在以上に、猛威を振るう自然現象をして言うことであったのだと、トリテレイア・ゼロナイン(「誰かの為」の機械騎士・f04141)は見上げる山岳の威容をマルチセンサーで捉えきることができない事実でもって認識していた。
「中々の悪路ですが」
道ならぬ道。
人類の誰もが踏破したことのないであろう領域にあって、怯むことは致し方のないことであったのかもしれない。
けれど、トリテレイアはウォーマシンである。
恐れをこそ排斥することができ、己の機体のスペックを考えればこそ足を踏み入れるのだ。
「これを越えられぬようであれば騎士の名折れというもの」
彼は機械白馬『ロシナンテⅡ』に騎乗していた。
これから行うのは山越えである。それも並の山ではないことは承知の上。それは如何にウォーマシンであるトリテレイアをしても愚かであると言わざるを得ないものであった。
だが、それは通常であればの話である。
「私と『ロシナンテⅡ』の製のうであれば話は別。この障害を避ければ怠慢の誹りを免れませんからね」
彼のマルチセンサーが暗視でもって頂上を見やる。
機械の眼をもってしても、地上の闇を見据えることは未だできない。けれど、それでも己と騎馬が突き進む道を示す事ができたのであれば十分であった。
『ロシナンテⅡ』が嘶くように前足をもたげ、一気に岩肌を蹴っていく。
断崖一歩手前の傾斜から蹄が蹴り飛び上がる。スラスターが噴射され、跳躍を補助し、次々と道無く絶壁を駆け上がっていくのだ。
それはまるで現実味のない光景であったことだろう。
けれど、それはまさしく現実である。トリテレイアは機械白馬と共に断崖のごとき岩壁を踏破していっているのだ。
「……この音響パターン。落石ですか。また難儀なことですが」
彼のアイセンサーがユーベルコードに輝く。
己と『ロシナンテⅡ』を包み込む円錐形のバリアフィールドが形成され、防御障壁をまとったトリテレイアが落石を手にした馬上槍でもって真正面から粉砕するのだ。
それはまるで、鋼の騎士道突撃行進曲(チャージ・アット・ウィンドミル)のようでもあったことだろう。
流れる音はなく。
ただ岩石を打ち砕く轟音だけが響き渡る。
生命の存在を感じさせぬ山岳。
そこをトリテレイアは駆け抜ける。
「立ち止まっている暇はありません。いざ、『常闇の燎原』へ!」
トリテレイアのアイセンサーが頂上を捉える。
そこにあったのは揺らめく黒炎であった。
通常の炎ではない、黒色の炎。その中心に人影が見える。
暗闇の中にあってなお、黒炎が隠すはオブリビオンの姿。
トリテレイアは確信する。あれこそが、この辺境の果てにおける最大の障害であることを。
あれを乗り越えなければ、確証すらない『第三層』へと至る道を見つけることすら叶わない。
見据える先にある障害をこそ乗り越えてこそ、騎士である。
トリテレイアは『ロシナンテⅡ』の嘶きの如きスラスター噴射音と共に一気に頂上へと駆け上がるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 月夜・玲
月夜・玲
うーん、凄い山
もっと平和な世界なら、登山家のメッカになってただろうけど…
そんな余裕はこの世界には無い…か
そういう娯楽が、当たり前の世界にいずれはなって行けば良いんだろうけどね
という訳で一足お先にチャレンジさせて貰おうかな
…よく考えるとユーベルコードで飛べば良いじゃんとかは…無粋だね
ハーケンを岩壁に打ち込みながら『クライミング』
ロープは…まあ良いか、落ちなきゃ問題ないや
打ち込んだハーケンを足場にしながら登っていくよ
普通の使い方とは違うけど…しっかり打ち込めば大丈夫っしょ
なるべく普通に登って…あんまり天候が悪くなるようなら、『天候操作』で私の周りだけ穏やかにしよう
折角だから楽しみながら登りたいよね
思わず仰ぎ見るほどの巨大な山岳地域。
それは見惚れるほどの巨大さであり、ここが地上ではなく地下であることを一瞬忘れさせるものであったことだろう。
暗闇が支配する中にあってなお、その圧倒的な存在感は世界のスケールを狂わせるほどであった。
ダークセイヴァー世界とは、積層世界であることが判明している。
今まで地上であったと思われた世界ですら『第四層』。これより上にさらに3つの層が重なっていることからしても、猟兵達はこれより歩まねばならぬ自身たちの道のりが如何に遠いことかを理解しただろう。
「うーん、凄い山」
けれど、月夜・玲(頂の探究者・f01605)の声は平素と変わらぬものであった。
むしろ、行楽地に歩むような、そんな気軽ささえ在った。
「もっと平和な世界なら、登山家のメッカになってただろうけど……そんな余裕はこの世界には無い……か」
平和な世界を知っている。
此処ではない何処か別の世界。そんな世界に此のような山岳地域があったのならば、人はきっと己の生命を賭してでも踏破しようとしただろう。
けれど、人の生命は弄ばれ、消耗するだけのダークセイヴァーという世界にあって、それは存在しえない概念であろう。
玲は思うのだ。
そういう娯楽と言えるものが当たり前の世界にいずれなって行けば良いだろうと。
けれど、それは未だかなわぬ遠き未来である。
ならばこそ、玲は笑って険しき道を踏破しようとするのだ。
「というわけで一足先にチャレンジさせて貰おうかな」
少し考えればユーベルコードで飛んでいけばいいじゃんと思わないでもなかったが、それは玲にとって無粋である。
だからこそ、彼女は己の身体能力だけで山岳に挑むのだ。
手にしたハーケンを岩壁に打ち込む。硬い岩石。打ち込むのも一苦労する硬さであるが、それは裏を返せば、多少の体重を掛けたとしてもハーケンが抜けることがないという安全の証左でもある。
「ロープは……まあ良いか。落ちなきゃ問題ないや」
気軽に彼女は岩壁に打ち込んだハーケンを足場にして軽々と登っていく。
普段とは違う扱い方をしているが、それでも猟兵の膂力で打ち込めば足場として十分であることはすでに実証済みである。
「とはいえ、山頂まで結構あるなぁ……ま、これも感じ感じ」
玲は確実に一歩を持って山岳を登っていく。
時折吹き付ける風は冷たく、彼女の体を吹き飛ばさんとするほどの強烈な勢いであったが、それでも彼女の模造神器の力は天候すらも操作するのだ。
穏やかになった風の中で玲は暗闇の世界を見下ろす。
僅かに見える明かりは、五指で数える事ができる程度であった。
あれが人の生存圏。
これだけ広大な地下の世界にあって、たったそれしか見つけることのできないのが、今の世界の現状である。
言いようのない現状。
あの明かりの中に人々が闇を恐れながら暮らしている。未来への展望もない。希望も持てない。
そんな人々の営み。
それを玲は背に負ってハーケンを打ち込む。
「せっかくなら楽しみながら登りたい」
あの灯火の向こうにいる人々が陽光の元で暮らすことができる未来。
それを玲は夢想しながら、ハーケンを打ち込む力に変える。岩肌は硬い。まるで玲を拒絶しているようでもあった。
けれど、そんなつれない態度を取る自然にこそ玲は踏み込んでいくのだ。
踏破するということはそういうことだ。
拒絶されても、弾かれても、それでもなお己の四肢でもって歩んでいく。
その道程を玲は楽しみながら、頂上に揺らめく黒炎を瞳に捉え、その道行きの先へと迫るのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『問う女』

|
POW : その価値はありますか?
【これまで抱えた業罪を問う言葉】【今までの善悪を問う眼差し】【これから戦う姿勢の正誤を問う威圧】を対象に放ち、命中した対象の攻撃力を減らす。全て命中するとユーベルコードを封じる。
SPD : その覚悟はありますか?
【自身の身体を媒介に燃え上がる金白の炎】が命中した対象を燃やす。放たれた【抱えた苦悩や後悔の強さで威力の変わる】炎は、延焼分も含め自身が任意に消去可能。
WIZ : 生きてゆけるのですか?
詠唱時間に応じて無限に威力が上昇する【束縛】属性の【無数の粛清の光輪】を、レベル×5mの直線上に放つ。
イラスト:真坂野
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠イージー・ブロークンハート」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
猟兵たちが目指した山岳の頂上に揺らめく黒炎。
それは一人の女性の身の内から放たれ続けるものであった。燃え盛るわけではない。けれど、確実に黒い炎が彼女の見の内側から噴出し、その玲瓏なる視線をもって猟兵たちを一瞥する。
美しい女性であった。
けれど、知るだろう。一瞥しただけでわかる。
あれはオブリビオンであり、これまで猟兵たちが対峙してきた『同族殺し』や『紋章』持ちのオブリビオンと同等の力を持つ強大な存在であると。
そのたおやかな唇が薄く開く。
「何故進むのですか。この先に貴方達が求めるものがあるとは確かではないはずなのに。それでも進むのですか」
問いかけであった。
攻撃ですら無い問いかけ。
意義を問うものであり、猟兵たちを射すくめる言葉でも在った。
「あなた方に意味はあるのでしょうか。生きる意味。戦う意味。勝利する意味。あなた方に意味を見出すことが私にはできない。死を持って完結する生命であればこそ、生きること、その遠回りなる道に意味を見出すことができない」
彼女の言葉は問いかけの言葉ばかりであった。
けれど、感じるだろう。
その言葉、その視線、その攻撃の尽くが黒い炎を伴ってくるのだと。
その黒い炎を受けてしまえば、『あらゆる防護を侵食し、黒い炎に変えて吸収してしまう』のだと、猟兵達は知っている。
受けることはできない。
躱すしかないのだ。
恐るべき力。
その力を振るう『問う女』は、今再び問いかける。
「あなたの道に意味はあるか――」
 馬県・義透
馬県・義透
【馬県さんち】
引き続き『疾き者』にて
死んでも終わりではなかった。それが私たち四悪霊ですし…(クルワを見る)
そう、来たことにも意味はあるのです。
さて、クルワ…此度の前衛は任せますー。四天流星の一部、お貸ししますねー。
私は後衛より漆黒風の投擲。さらに音遮断の結界にてクルワ援護。
視線と威圧は位置錯誤呪詛で避け、言葉は音を遮断。
ええ、もちろん、私も一投一投、場所変えてますからねー?そんな、投擲から位置を悟らせるわけないでしょう?
さらにね…陰海月も投げてたりするので、わかりにくくなってますよー?
※
陰海月、鳴きたいのを我慢して黙って四天流星なげてる。場所変えながらぽいぽい。
 外邨・蛍嘉
外邨・蛍嘉
【馬県さんち】
引き続き『クルワ』にて
(義透の視線受け)ワタシタチもまた、終わりではナカッタ。
デスガ、だからこそ歩めるノデスヨ。知ることも大事デスシ。
任されマシタ。アア、その四天流星、一部お借りシマス。
そのために一度、妖影刀『甚雨』を振るって…位置を間違えてクダサイナ。
ワタシとて、剣鬼と言われた者。斬撃での位置を悟らせる…ということはシマセンヨ。
エエ、見切ってイマスシ、何なら陽凪に乗って上からもやりますカラネ?
ここの先を、知るためにも退いてもらいマスカラ。
※
陽凪、ゆるりと泳ぐ。音はたてない。
ついにたどり着いた辺境の果て。
雄大なる山岳地域を踏み越えた先にあるのは『常闇の燎原』である。
しかし、頂に至らんとする猟兵たちを待ち構えていたのはオブリビオンであった。ただ一人の女。
その身から噴出する黒い炎は、グリモア猟兵の言葉が正しいのであれば、受けてはならぬ攻撃。
受けてしまえば、如何なる防護も加護も意味をなさず黒い炎へと変えられ無機物、有機物を問わずに吸収されてしまうのだという。
恐るべき力である。
そして、それは『問う女』の持つユーベルコードと合わさることによって、さらなる驚異となって猟兵達に襲いかかるのだ。
「死こそが終着。終わり。生命が全て目指すべき到達点。ならばこそ、今という時間を生きることに意味はないのではないですか」
オブリビオン『問う女』の重圧はすさまじいものであった。
ただそこに在るというだけであたえられる重圧は、猟兵にとって相対してきた『同族殺し』や『紋章持ち』のオブリビオンに匹敵するものであった。
死をこそ到達点と言う彼女の言葉は二人の猟兵にして悪霊である存在にとって正しいとは言えぬものであった。
「真でも終わりではなかった。それが私たち四悪霊ですし……」
馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)、その一柱である『疾き者』が外邨・蛍嘉(雪待天泉・f29452)の一人格である『クルワ』を見やる。
「ワタシタチもまた、終わりではナカッタ」
確かに死こそが生命の終わりであろう。
しかし、悪霊である彼らの存在こそが、ただそれだけで終わるものではないと知らしめるのだ。
「デスガ、だからこそ歩めるノデスヨ。知ることも大事デスシ」
『クルワ』は知っている。
例え死した後にも残るものがある。例え、それが自分が扱うものではなかったのだとしても、己の歩いた道、その轍を辿ってより良い場所にいたろうと続く者たちがいる。
そんな彼らのためにできることがあるのだ。
「そう、来たことにも意味は在るのです。さて、『クルワ』……此度の前衛は任せますー」
「任されマシタ」
『疾き者』と『クルワ』が視線だけでうなずき、互いの手にあった鏢を預けるのだ。
『クルワ』が放つ妖影刀の一撃が『問う女』に放たれる。
その斬撃の一撃は暗闇にあって、視線や問いかけ、威圧というものを向ける相手に己の位置をずらすことなど造作もなかった。
『クルワ』とて一度は剣鬼とも呼ばれた者である。
斬撃での位置を悟らせるということはしない。
確かに『問う女』から噴出する黒い炎は恐ろしい。如何なる防御も防護も意味をなさない攻撃。
ただ『問う女』は見るだけでいい。言葉を紡ぐだけでいい。威圧を放つだけでいい。
その証拠に放った斬撃は容易く防がれてしまう。
黒い炎が眼差しを向けただけで放たれ、その斬撃が黒い炎へと変わって彼女の体に吸い込まれていくのだ。
「ええ、勿論。私も位置を悟らせるわけないでしょう?」
『疾き者』が撹乱するように投擲を放つ。
しかし、そのことごとくが視線によって黒い炎へと変わっていくのだ。
あまりにも強力過ぎる。
けれど、それは『問う女』の視界に放たれた武器があればの話である。『クルワ』も『疾き者』も今の攻撃で己の位置を悟らせまいと違いの使役する巨大生物を駆り、暗闇の山岳、その宇宙を掛けるのだ。
『陰海月』も『陽凪』も音を立てずに沈黙のままに空を舞う。
敵の死角をつくことは難しいだろう。
けれど、それでもなお二人は気配を消し、互いの位置を悟らせぬように動くのだ。
「意味などあるとは思えないのです。私には。どうしたって生きる意味など。死して永遠になるために生きるというのならば、人は皆今すぐに死ぬべきなのです。どうして長く苦しい生命という道のりを生きるのですか」
言葉が炎と成って『疾き者』の体を蝕む。
けれど、それでも答えなかった。
『問う女』の言葉は全て過去の化身たるオブリビオンの理屈でしかない。
今を懸命に生きる者たちには必要のない屁理屈でしかないのだ。だからこそ、その瞳はユーベルコードに輝く。
「――」
そう、人は懸命に生きている。
死して悪霊と成った二人であるからこそわかる。どれだけ死の先に見えるものがあるのだとしても、人はその生命を投げ出さない。
全うするために困難に立ち向かうのだ。
放たれる四悪霊・風(シアクリョウガヒトリ・トノムラヨシツナ)の一撃が『問う女』の体に吸い込まれ、その体を傾がせる。
「この先を、知るためにも退いてもらいマスカラ」
ゆるりと飛ぶ『陽凪』の上から『クルワ』が放つは、手渡された四天流星の一振り。
放たれる一撃はユーベルコードの輝きを持って、篠突く藤雨(シノツクフジアメ)のように『問う女』の体に放たれる。
『疾き者』の一撃で体勢を崩していた『問う女』の胸に鏢が打ち込まれ、まるで大穴を開けたような傷痕が深々と刻まれる。
黒炎が噴出し、それはまるでこの世界を暗示するかのように噴出するのだ。
その黒炎を二人は見やる。
どこまで言っても過去の化身は未来には行けない。例え、今を侵食するのだとしても、可能性を棄てた存在に未来という可能性は掴めない。
己達悪霊もまたそうであろう。
だからこそ、二人は今を生きる未来在る者たちのために戦うのだから――。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 ニノマエ・アラタ
ニノマエ・アラタ
見いだせないなら、見いだせないんでいーんじゃねェの?
それがアンタの価値観。俺は否定も肯定もしない。
他人にどうこう言うのって、楽でいいよな。
非難するだけ問うだけなら誰にでもできるんだよ。
……で、そういうオマエはどうなんだ?
自分に価値を見出せたのか?
……できなかったから、オブリビオンになったんだろうけどな。
『問う女』の問いには感情的にならず、静かに受け流し。
金白の炎は空虚な源を見切って避ける。
さて、お喋りはやめだ。
俺が何を見出したか、その意味も。
これを持って答える。
刀身より噴出させた壁のごとき業火により、
『問う女』の視界を遮り、俺の立ち位置と気配を一瞬で消し。
己の炎を突き破って一閃を喰らわせる。
猟兵の一撃に寄って穿たれた胸から噴出する黒い炎。
それはオブリビオン『問う女』の身のうちから発せられるものであり、この暗闇の世界にあって煌々と輝くものであった。
山岳の頂。
そこに座すオブリビオン『問う女』は猟兵たちをして、かつて対峙したであろう『同族殺し』や『紋章持ち』のオブリビオンと同等の力を持っていた。
これが辺境の果て。
『常闇の燎原』へと至る戸口に立つ者の力である。
白金の炎が噴出し、それが黒い炎と交わることなく頂にて篝火のように猟兵たちの視界を覆う。
天を……否、天井を焼き焦がさんとするかのような炎と共に『問う女』は告げる。
「意味が見いだせない。生命とは終わるもの。終わるために生を進むというのであれば、人の生命は疾く終わるべきです。だというのに、何故あなた方は抗うのです」
彼女の言葉はただそれだけであった。
何故、何故、と問いかけるばかり。
「見いだせないなら、見いだせないでいーんじゃねェの?」
ニノマエ・アラタ(三白眼・f17341)は目の前に迫る白金の炎を前にして怯むこと無く見据える。
それが対峙する『問う女』の価値観である。
アラタにとって、それは否定することも肯定することもないものである。
ただ、こう思うのだ。
「他人にどうこう言うのって、楽でいいよな。避難するだけ、問うだけなら誰にでも出来るんだよ」
アラタの言葉は答えになっていないだろう。
『問う女』にとって、彼女の問いかけは生命の価値である。否定も肯定もない言葉は、彼女にとって耳に入れる価値のないものであった。
だからこそ、噴出する白金の炎が黒い炎を伴って新たに放たれる。それを山岳の険しい岩肌の上を蹴って飛ぶようにしてアラタは躱す。
あの黒い炎を受けてしまえば、己の肉体や防護は意味をなさず、黒い炎となって吸収されてしまう。
「……で、そういうオマエはどうなんだ? 自分に価値を見いだせたのか?」
問いかけを問いかけで返す。
その言葉は『問う女』にとっては無意味であったことだろう。
答えはない。いや、答えることなどできようはずもない。彼女はあくまで『問う女』である。答えを持ち合わせているわけがない。
アラタにはそれがわかっている。
過去、骸の海よりにじみ出た存在。それがオブリビオンであるのならば、答えを求める『問う女』にとって、その身の内に答えなど存在していないのだ。
だからこそ、彼女は。
「……できなかったから、オブリビオンになったんだろうけどな」
「……意味などないのです。私が今ここに居る理由も。けれど、目の前に溢れる生命の意味がわからない。どうして存在しているのか。どうして終わらないのか」
尽き果てぬ懊悩を抱えているようなものだ。
誰にも出せぬ答え。それを求めることこそが『問う女』の本質である。
「さて、おしゃべりはやめだ。俺が何を見出したか、その意味も。これを持って答える」
構えた妖刀から噴出するは怒涛の如き炎海。
それは業火剣乱(ゴウカケンラン)なるユーベルコードが生み出した輝きである。『問う女』とアラタを隔てる絶対的な壁にして溝。
彼女には到達できぬ答えを持つアラタが為せる一閃が、炎の壁を突き破って『問う女』の身体へと打ち込まれる。
斬撃は鋭く袈裟懸けにふるわれ、走った傷口から炎が噴出する。
それは白金の炎でもなければ、黒い炎でもない。アラタが生み出したユーベルコードの炎そのもの。
消えぬ炎が『問う女』の身体を焼く。
「生きる意味なんていうのは、懸命に生きている者だけが持てるものだ。過去から一歩も進まず、ただ立ち止まっているだけのアンタには得られないものだ」
アラタの斬撃は『問う女』の疑問を一刀の元に両断する。
誰もが答えを求めている。
だが、見つけることができるかどうかは別の話だ。そのために人は懸命に生きていく。どれだけ価値の見いだせぬ今であったとしても。
それでももがき、苦しみながら伸ばした先にあるものにこそ、己の眼で答えを見出すものであるのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
 ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー
戦う理由、勝利する意味はこの先にある景色を瞳に捉えたいから。何も無くても、何も無いという真実がある。それすらなくても、意味は作ればいい
だが生死についてはなー……結論からいえば、生きる意味はないと思うよ。きみはおれが生きる目的や意志といったものを知りたいんだよな
おれのは単なる暇つぶしだよ。心を躍らせて心臓を打ち鳴らしたいだけだ
だから、きみが死する意味もないと思う
さて、攻略の糸口は事前に貰ってるんだ。見極めていこう! 走り動き回るから詠唱噛みそうだな!!
太陽、途切れ途切れでも温度は維持してくれ。発動タイミングはー……光輪が放たれたと同時に火を散らして潜伏を。黒炎に当たらないように徐々に囲って燃やせ
袈裟懸けにふるわれた一撃が『問う女』の体を引き裂き、その身の内に溜め込まれたであろう黒い炎を噴出させる。
彼女の問いかけに答える猟兵はあれど、その答えに彼女が納得することはない。
彼女にとって生きているということ事態が不条理なのだ。
終わった存在であるオブリビオン。忘れられし者である過去の化身である彼女にとって、生きるということはまさに無為なるものであったであろうから。
「無意味です。この行いに意味はない。生きるということにすら意味を見いだせない。何故戦うのです。何故抗うのです。死は平等に訪れる結果であるのならば、抗うこと、戦うことに意味はない」
彼女の瞳がユーベルコードに輝き、粛清をもたらす光輪が生み出されていく。
それは凄まじい束縛の力を持つ光輪であり、触れれば黒い炎によってあらゆる防護が無意味となる。
強大な存在の放つユーベルコードの輝きを前にしても、ギヨーム・エペー(Brouillard glacé calme・f20226)はためらうことはなかった。
「戦う理由、勝利する意味はこの先にある景色を瞳に捉えたいから」
至極当然の言葉であった。
この先にあるもの。それが如何なるものであってもいいのだ。世界は思っている以上に広いものだとギヨームは知る。
己が海だと思っていたものでさえ、違ったのだ。されど、違っていたからと言って彼が感じたものが変わるわけではない。
どれだけの真実を目の前に積み重ねられるのだとしても、ギヨームが感じた海は消えることはないし、違えることはない。
だからこそ、彼は『問う女』に真っ向から向かうことができるのだ。
「何も無くても。何も無いという真実がある。それすらなくても、意味は作ればいい」
己が海を感じたように。
だからこそ、ギヨームは生死すらも厭わない。
生きる意味など彼の中には存在しない。目の前の『問う女』は他者の持つ生きる目的や意志を知りたいと思っているのだろう。
だからこそ、ギヨームは告げるのだ。
「あなたの生きる意味はなんですか。何故生きようとするのです」
放たれる光輪がギヨームへと迫る。
すでに敵の攻略の糸口は知っている。
受けてはならない。受けてしまえば、あの黒い炎にあらゆるものは侵食され、黒い炎となって『問う女』の消耗を回復させてしまう。
だからこそ、険しい山岳をギヨームは駆け抜ける。
彼の瞳がユーベルコードに輝く。système solaire lotus(システムソレールロテュス)は一万度にまで温度が上昇する魔術の炎を生み出す。
それは百に至らんとするほどの数となって、またそれらが次々と合わさって巨大な篝火へと変わっていく。
温度を保つために合体させているのだ。
「その車輪の轂に太陽は昇る。降り注ぐ御光は輻となり、灯は星と生り円環を回る。紅く咲かせ、日輪の蓮――おれのは単なる暇つぶしだよ」
そう、ギヨームにとってはそうであったのだろう。
今という時間が無為であるという『問う女』の言葉が真実であるというのならば、そう答えるほかない。
なぜなら、時間とは過去に排出されながら進むものである。
ならばこそ、今という時間を有為なるものにするのはいつだって自分だ。自分だけがそれを変えることができる。他の誰にもできないことだ。
「心を踊らせて心臓を打ち鳴らしたいだけだ」
問いかけるばかりで己の心を燃やさぬ者に理解出来る道理など何処にもない。
ギヨームが生み出し、太陽によって維持された火が一気に『問う女』を囲うように散って、彼女を取り囲む。
放たれる光輪をギヨームは躱し、指し示すのだ。
己の心が踊る限り、胸が高鳴る限り、彼女の問いかけに意味はないのだと知らしめるように、取り囲む炎が一気に『問う女』を打ちのめし、炎が再び巨大な篝火となってダークセイヴァー世界、その『第四層』と呼ばれた空……天を覆う層すらも焦がして、己の胸の高鳴りを知らしめるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 愛久山・清綱
愛久山・清綱
当然だ、問い人よ。其の『意味』とは、他の誰でもない、
此の俺が創り決めたものだからな。
(訳:自分の道は自分で切り拓く、それだけだよ)
■闘
相手の眼差しを直視しつつ『己の意味は己自身で創った』旨を
堂々と語り、問いかけを一蹴する。
しかし、問題はやはり黒い炎を纏った炎……被弾は赦されない。
威圧と共に放たれる炎を【見切り】つつ、【残像】を伴う動きで
躱していき、敵の元まで接近を図るぞ。
懐に入ったら【破魔】の力を最大限まで宿した『心切』を抜刀し
【夜見・慈】を放ち、少しばかりでも魂の【浄化】を試みる!
其方といえど、主といえど……我が兵(つわもの)の道、止めること能わず。
※アドリブ歓迎・彼は我が道一直線の男です
炎が篝火のようにダークセイヴァー世界の雄大なる山岳の頂に燃え盛る。
それはオブリビオン『問う女』の肉体を焼くものであったが、未だ人の姿を保っているのは『同族殺し』や『紋章持ち』のオブリビオンと同等の力を有しているからであろう。
その姿は確かに消耗している。
だが、傷痕から噴出し続ける黒い炎が、彼女を斃れさせない。
「意味はない。生に意味はない。なのに人は生きるという。死を恐れ、死を遠ざけ、結果が変わらぬ終焉たる死を忌避する。それは何故ですか? 意味などないのに。生命は終わることでしか完結しないというのに。なのに何故。意味がわからない」
『問う女』の言葉は、今を生きる人にとって無関係ではなかっただろう。
生命が死を持って完結することは言うまでもない。
誰しもが死に突き進む道程の半ばにいることは否定できない。
「当然だ、問い人よ。其の『意味』とは、他の誰でもない、此の俺が創り決めたものだからな」
愛久山・清綱(鬼獣の巫・f16956)にとって、それは当然のことであった。
これまでもそうであったように。
これからも彼は己の道は自身で切り拓くものである。ただそれだけのことであったのだ。
故に『問う女』の眼差しを直視しながらも、その問いかけが放つ黒い炎を一蹴する。
躱した眼差しに意味はない。
強烈なるオブリビオンとしての個が放つ威圧は黒い炎となって噴出し、清綱を襲う。あの黒い炎に触れてはならない。
受け止めたとしても、無機物、有機物関係なしに黒い炎へと侵食し、吸収されてしまうことを知っている。
知っているのならば、対処もできよう。
「どれだけ無意味であると他者の生命を、道のりを否定しようとするのだとしても」
清綱の道を今阻んでいるのは強大なオブリビオンである。
それはどうしようもない障害でしかない。壁だ。今目の前にある壁を清綱は越えなければならない。
いつだってそうだった。
己の前にはあらゆるものが壁となって現れる。
時に理不尽に、時に無作為に。けれど、そのどれもが切り拓くことのできぬものではなかったのだ。
己の足を止めるのは、いつだって誰かではなく己の心である。
ならばこそ、どれだけの壁が目の前にそそり立つのだとしても、切り拓いて進む。踏破する。乗り越えるという気概だけが彼の中にあるのだ。
黒い炎をかわしながら、山岳の岩肌を蹴って飛ぶ。
「無意味です。何故、そのようなことを。抗うことなど意味がないというのに。生命を完結するためには死が必要不可欠なのに」
その言葉を前に清綱は頭を振る。
「其方といえど、主と言えど……我が兵(つわもの)の道を、止めること能わず」
清綱の瞳がユーベルコドに輝く。
それは、秘伝にして、夜見・慈(ヨミ)と呼ばれる敵対者に対する敵意を鎮め放つ絶倒の一撃。
霊力が籠められた刀を一瞬で抜き払う居合の一撃。
『問う女』事態に悪意はない。
あるのは、その存在が歪みはてたという狂気のみ。
ならばこそ、清綱の放つ一撃は痛みを喪わせ、魂の浄化をもたらす絶技。
放たれる斬撃は痛みを感じさせぬものである。それが『問う女』と呼ばれるオブリビオンの狂気を晴らすものであると清綱は知っている。
「秘伝……夜見」
抜刀の後に放たれる居合の一撃は、黒い炎すらも振り切って清綱の背に『問う女』の体に斬撃の痕を刻み込む。
そこに黒い炎は噴出しない。
籠められた霊力は浄化の力。どれだけ問いかけを続けようとも、彼女の求める答えは得られないという輪廻に捕われた彼女の輪を切り裂く一撃。
「救える魂は必ず救う……其れが俺の兵(つわもの)の道」
求める道の頂、その果ては未だ遠くても。
歩まぬ理由にはならぬと清綱は、頂きの先に見えるであろう『常闇の燎原』、その先を見据えるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
意味とは何でしょうか?
私の生きる道、生きる意味が……あなたを納得させるものである理由がありますか?
私の生きる道は私が決めます。
後悔することは色々とあります。炎には強い(『火炎耐性』)とはいえ、黒炎のことがなくとも当たっていいものではありませんね。
【絶望の福音】で敵の放つ金白の炎の燃え広がる先を読み避けていき、
炎の薄いところを狙い「フィンブルヴェト」からの氷の弾丸を撃ち込むことで炎を鎮火、突破し敵に接近します。
接近したなら銃剣による『串刺し』からの氷の弾丸の『零距離射撃』を撃ち込みます。
また一歩、確かに近づいたはず。
これが、私の生きる意味です。
オブリビオン『問う女』の体を猟兵たちの攻撃が削ぎ落としていく。
それは黒い炎を噴出させ、彼女の体の内にある何かを消耗させているようでもあった。どれだけ強大なオブリビオンであっても、猟兵達は打ち勝ってきた。
繋ぐ戦いこそが猟兵の本質であるというのならば、今まさに『問う女』は、その繋ぐ戦いの中にあり此の場に繋ぎ止められていると言っても過言ではなかっただろう。
「生きる意味などないのに。死こそが終末であるのならば、今という刹那こそ無為なるもの。意味を教えて下さい。どうしてそこまでして生きるのか。どうして抗うのか。どうして戦うのか。その戦いの意味をあなたたちは知っているのですか」
彼女問いかけにセルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)の瞳は些かも揺らぐことなく見据える。
「意味とは何でしょうか?」
その問いかけに問いかけで返す言葉は、『問う女』にとって無意味であったことだろう。
そこに答えがないのであれば、彼女は返す言葉もなく身の内から湧き上がる白金の炎と黒い炎を織り交ぜた奔流でもってセルマを襲う。
噴出する炎をセルマは躱していた。
危なげなく、ただ躱す。
「私の生きる道、生きる意味が……あなたを納得させるものである理由がありますか?」
問いかける。
セルマにとって、オブリビオンとは打倒するべき存在でしかない。
支配の象徴でも在り、抗う対象でもある。
彼女はこれまでずっとそうであったのだ。抗い、戦う。その連綿と紡がれてきた経験の軌跡こそが、今の彼女の背中を押すのだ。
噴出する炎を既のところで躱す。けれど、どこにも危うさはなかった。彼女の瞳がユーベルコードに輝き続けている。
後悔することはいくらでもある。
セルマにとって、これまでの人生に過ちと後悔は満ちていた。
マスケット銃の銃口を噴出する炎を躱しながら『問う女』に向ける。放たれた氷の弾丸が、炎の壁となった黒と白金の炎を突き破って道を切り拓く。
そう、それはこれまで彼女が辿ってきた人生という道を切り拓くのと同じであったことだろう。
「すでに結果は決まっているのに。それでも、死という先にあるものを見据えながら、どうして今という刹那を手放さいのです。どこにでも死という終末へと至る道は残っているというのに」
「私の生きる道は私が決めます」
誰かに決められた道ではない。
どんな生命にも死という結末が待っているのだとしても。それでもセルマは己の道は己で切り拓くと決めたのだ。
なればこそ、彼女の放った氷の弾丸が開く道を彼女は一気に走る。黒い炎に触れては、彼女の肉体は侵食され『問う女』の消耗を回復させてしまうだろう。
だからこそ、彼女は黒い炎を見切り、躱して走り抜ける。
マスケット銃『フィンブルヴェト』の先端に装着された銃剣『アルマス』の刀身が煌めく。
炎を受けて、この常闇の世界にあって煌めく刀身。
それは彼女の意志そのものであったことだろう。支配に抗う不屈の精神。放たれた突きが『問う女』の体を貫く。
「また一歩、確かに近づいたはず」
引き金をひく。
それは『問う女』にとっての絶望の福音。
セルマのこれまでの闘いは、まるで10秒先の未来を見てきたかのように、『問う女』の攻撃を躱し続けていた。
確かに彼女の輝くユーベルコードは、瞳に未来を見せただろう。
「これが、私の生きる意味です」
抗う。戦う。そして、その先にある未来を掴むこと。
どれだけ険しく長い道のりであったとしても、セルマは立ち止まらない。
己自身が立ち止まることを許さない。
いつだって誰かに決められてきた。強者という名の支配者。ヴァンパイアに決められてきたのだ。
けれど、決定を尽く覆してきたセルマの力は、今まさに世界の謎にすら迫ろうとしている。
貫いた氷の弾丸が『問う女』に答えの代わりに刻み込まれ、その氷の華を暗闇に咲かせるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 月夜・玲
月夜・玲
うーん、苦労して登って来たのを出迎えてくれたのは
何か意味不明なお喋り女でしたとさ…と
これがもう少し、対話が出来るタイプの敵なら良かったんだけどね…
もう明らかに対話しない感じのタイプじゃん
まあ中々、先への手掛かりは見付からないって事か
一筋縄ではいかなさそうだけど、まあやるしかないか
●
オーバーロード、真の姿解放
外装展開、模造神器4剣全抜刀
業罪も、善悪も、正誤も関係ない
私は私のやりたいようにやるだけ
意味なんて、今は無くて良い
そんなもの後から付いてくるオマケだ
それを問う事自体がナンセンスだよ
まずは接近して4剣全てで『なぎ払い』そして『串刺し』にする
そして【偽書・焔神】起動
斬撃と同時に蒼炎を剣に纏わせておいて、問う女を蒼炎で『焼却』する!
更に追加で連続して斬り付けて、どんどん斬り刻み燃やして行こう
その黒い炎を私の蒼炎で上書きしてあげる
しかし、紋章持ちでも無いのにこの強さか…
黒い炎…厄介な能力だね
まだまだ解明するべき謎がこの世界には多いね
まあそれを探るのも楽しいんだけどね
銃声が山岳の頂に木霊する。
地下の世界であるダークセイヴァー『第四層』にあって、その音は頂きに座すオブリビオン『問う女』の体を貫き、黒い炎を噴出させる。
「何故です。何故抗うのです。意味など無いのに。川の流れのように、水が下流へと流れていくのと同じ様に。あまりにも無意味。あなたたちの為すことは、全てが水泡に帰すと決まっているというのに。何故戦うのです。何故生きるのです」
猟兵たちの攻撃に寄って消耗させられてもなお、『問う女』は問いかけることをやめない。
それはオブリビオンであるという以前に彼女の存在が狂っているからであろう。
どこまで思索を重ねたのだとしても、彼女の求める答えはない。
満足の行く答えなど彼女の中にはなく、けれど彼女の外側にも存在していない。故にこの頂きにおいて彼女は座し、狂えるほどの時間を重ねてきたのだ。
「うーん、苦労して登ってきたのを出迎えてくれたのは何か意味不明なおしゃべり女でしたとさ……と」
月夜・玲(頂の探究者・f01605)は些かがっかりであると肩をすくめ、山岳の頂に至る。
これがもう少し、対話が出来るタイプのオブリビオンであったのならば、このダークセイヴァー世界における謎の一端に迫ることができたのかもしれない。
けれど、目の前のオブリビオンはただ、己の問いかけを続けるだけの存在でしか無い。
オブリビオンとは常に過去に狂わされ、歪められた存在である。
問いかけるというコミュニケーションの手段を持っていながら、こちらの解答に一切の満足を見せぬ相手は、これより先にある『常闇の燎原』にあるであろう『第三層』に繋がる謎の手かがりを得られない相手であった。
「けれど、一筋縄ではいかなそう。まあ、やるしかないか」
玲の瞳が輝く。
それは蒼い炎。彼女が至るは超克。外装が展開され、鋼鉄の副腕が彼女の周囲に浮かぶ。抜き払われるは模造神器。
四振りの模造神器が蒼い炎を噴出させ、黒い炎と相対する。
「全剣抜刀――……業罪も、善悪も、正誤も関係ない」
「何故です。罪はありき。善と悪の境目はありき。正しさと過ちを分かつものがあればこそ、私の問いかけは正しさを持つというのに」
その言葉に玲は笑って答えるのだ。
「私は私のやりたいようにやるだけ。意味なんて、今はなくて良い。そんなもの後から付いてくるオマケだ」
抜き払った四剣の模造神器が放つ蒼炎が斬撃となって『問う女』に迫る。
しかし、その蒼炎は『問う女』の一瞥によって相殺され、消えていく。だが、ここからが『問う女』の本領であったことだろう。
言葉、威圧、一瞥。
それだけで『問う女』の身から噴出する黒い炎があらゆる防護を侵食し、黒い炎へと変えてしまう。
だが、此処に至るは、超克の道へと足を踏み入れた猟兵である。
オーバーロードこそ、あらゆる力を超克し、踏み越えていくものであるというのならば玲がもたらす、偽書・焔神(ギショ・ホムラカミ)の力は黒い炎すらも焼却し、塗りつぶす力の奔流である。
「無意味です。其の行いは無意味です。何故抗うのです。闘い続ける意味は、ないというのに」
「それを問う事事態がナンセンスだよ」
振るう斬撃は四振り。
蒼炎を纏う模造神器が黒い炎を塗りつぶすように切り裂き、凄まじい連撃で持って『問う女』を圧倒するのだ。
オーバロードに至る玲であっても完全に黒い炎を払拭することはできなかった。
ダークセイヴァー世界の支配者である何者かがもたらす『紋章』。その力を付与されていない状態であっても目の前のオブリビオンの力は凄まじいものであった。
さらに噴出する黒い炎。
あらゆる防護を侵食する炎は、攻防一体である。
敵の防護を貪り、己の消耗を回復する。これほどまでに優れた力を持っていながら、尚ダークセイヴァー世界にあっては上がいるという事実。
「まだまだ解明するべき謎がこの世界には多いね」
それは猟兵にとって尋常ならざる事実である。
けれど、玲は笑う。楽しげに笑うのだ。
未知とは恐れではない。
彼女にとって未知とは暗闇の中手探りで進むことではない。一歩一歩着実に踏みしめ、あらゆる状況から知識を得て、前に進むことだ。
それは時として勇気と言えるものでもあったし、それ以上に玲は笑って暗闇の中に身を投じる。
「まあそれを探るのも楽しんだけどね」
「楽しみなど。理解できない。死こそが終末だというのに。至るべき旅路の果てだというのに」
『問う女』は困惑すれど、己の黒い炎を塗りつぶす蒼炎に自身が塗りつぶされていくのを感じたことだろう。
「その黒い炎さ。確かに攻防一体で凄いと思うよ。厄介だってね。だけどさ。それさえも超えていけるんだよ。楽しいね。どんな時だって、踏み越えることのできないものがないってわかっているのは」
故にオーバーロード。
玲が振るう模造神器の四連撃が、嵐のように蒼炎猛り狂い燃やし尽くすように『問う女』の体を塗りつぶし、頂にて蒼炎を篝火とするのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル
…訪れる未来が不確かだから足を止めるならば、
最初からこんな辺境の地には来ないし、
吸血鬼共からこの世界を取り戻そうだなんて思わないわ
無数の「写し身の呪詛」の残像を囮にする集団戦術により、
黒炎やUCを回避しつつ敵を中心に包囲陣を組み、
死角から「黄金の楔」を投擲して敵を捕縛しUCを発動
…これ以上、お前の的外れな問答に付き合う気は無い
退場して貰うわ。私達がこの先に往く為に…
魔法黄金に限界突破した魔力を溜め元素転換を行い、
核熱属性攻撃のオーラで防御ごと敵を浄化する超高温高圧の核融合を放つ
…刮目して見るがいい。これが異世界の術理により究明された太陽の光よ
…私はいつか必ず、この暗い世界を光で照らしてみせるわ
篝火の如き炎が山岳の頂きにて燃え盛る。
その中心いたのは、この頂に座すオブリビオン『問う女』であった。
彼女の上げる黒い炎は蒼炎に塗りつぶされながらも、なお身の内側から噴出するように荒れ狂い、ダークセイヴァー世界の謎を見せつけるように煌々と燃え上がるのだ。
「どうして歩むのです。どうして進もうとするのです。限りなく遠い道の果てにあるのは、どうしたって死であるというのに。何故急ぐのです。何故。何故。何故」
その言葉は『問う女』にとって彼女の身の内側から出たものであったことだろう。
問いかけることだけが彼女の存在意義。
過去に歪み、狂気に彩られたオブリビオンは、『同族殺し』でもなければ、『紋章』持ちですらない。
ただのオブリビオンでしかないはずであるというのに、これほどまでに強力な存在へと至っている。
その重圧は身より放たれる黒炎と共に粛清の光輪が頂きを照らす。
「……訪れる未来が不確かだから足を止めるならば、最初からこんな辺境の地には来ないし、吸血鬼共からこの世界を取り戻そうだなんて思わないわ」
リーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は写し身の呪詛より放たれる残像と共に山岳を駆け上っていく。
『問う女』に狙いを定めさせてはならない。
あの無数の光輪に纏わせた黒い炎は一片たりとて受けてはならない。
どんな防護も、どんな隔てりをも無視して、あの黒い炎は侵食してくる。
だからこそ、残像と共に彼女は山岳を駆け上り、『問う女』へと迫るのだ。
「無意味なのです。その行いも、何もかもが。どうして抗うのです」
どんな答えを放ったのだとしても『問う女』が理解と共感を得ないことをリーヴァルディは知っている。
ヴァンパイアとはそういうものだ。
強者であるからこそ、理解しない。共感でもなければ理解でもない。ただの押しつけ。
この問いかけだってそうだ。
本来ならば答える理由もない。答えたところで納得もしない。
「……これ以上、お前の的はずれな問答に付き合う気はない」
放つ黄金の楔が残像の死角から『問う女』に放たれ、その身より欠系をすすり、彼女の身を頂きに縫い止めるのだ。
「……元素変換、術式反転。天より墜ちよ、太陽の輝き」
リーヴァルディの瞳がユーベルコードに輝く。
吸血鬼狩りの業・天墜の型(カーライル)は、撃ち放った黄金の楔を基点にして、取り囲む写し身の呪詛による残像を囲いとして超高温高圧の疑似太陽をもたらす力である。
「……刮目して見るがいい」
それはダークセイヴァーではない他世界をめぐりリーヴァルディ自身の瞳でみてきたが故に齎される力。
「これが異世界の術理により究明された太陽の光よ」
退場してもらう、とリーヴァルディがつぶやく。
彼女たちがこの先、『常闇の燎原』へと至るために、『問う女』の存在は不要であるのだ。
この障害を排せずして、これより先の道など進むべくもない。
どれだけの障害が待ち受けるのだとしても、リーヴァルディの心には一つの想いがある。
生み出された疑似太陽が『第四層』の天井すらも焦がしながら、山岳の頂に落ちる。
それは山岳をえぐり、溶解させるほどの一撃となって『問う女』の黒い炎すらも消し飛ばしていく。
「……私はいつか甘楽図、この暗い世界を光で照らしてみせるわ」
そう、それが彼女の闘う理由。
告げたとしても『問う女』には理解されないだろう。リーヴァルディは今は偽りの太陽であったのだとしても、この地を僅かな間照らす太陽の光を背に山岳を踏破し、『常闇の燎原』へと迫るのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 トリテレイア・ゼロナイン
トリテレイア・ゼロナイン
貴女は…“鏡”なのですね
問われたからには答えましょう
騎士として抱えた罪業は、この自我が発生した時より無数に
(電脳禁忌剣見遣り)
為した善悪もまた然り
騎士として為した善に歓喜し、犯した悪に苦悶する
それが“私”です
己の所業、そして歩む道程が己を構成してゆくというのなら
例え無明の闇が行く手に広がろうとも、結末が死であろうと
己が己であり続ける為に、騎士として正しきを求める意思を…意味を見出し続けると告げましょう!
威圧跳ね除けUC起動
向上した機動力と運動性で眼差しと言葉より逃れ、黒い炎を躱し続け
闇を打ち払い人々に光齎すは騎士の務め
幾度徒労に終わろうと、不屈の意志を以て進ませて頂きます!
急速接近し近接攻撃
極大なる光。太陽の光を模したユーベルコードの輝きがオブリビオン『問う女』の放つ黒炎すらも吹き飛ばして、山岳の山際を変形させる。
それほどの威力を持った一撃であっても、『問う女』は消滅していない。
これが強大なオブリビオンである証拠であるし、同時にこれほどのオブリビオンが未だ『第四層』に存在していたこと事態がダークセイヴァー世界の驚異を知らしめるものであったことだろう。
「何故戦うのです。何故進もうとするのです。その道に繋がっているのは、例外なく死という同一の結末であるというのに。生きながらにして罪を背負うのが生命。それ故に業は人の末路を示している。理解しながらも、何故進むのですか」
『問う女』の言葉を前に、機械騎士は足を止める。
いや、足を止めたのではない。
己の手にある電脳禁忌剣を見遣ったのだ。
「貴女は……“鏡”なのですね。問われたからには答えましょう」
トリテレイア・ゼロナイン(「誰かの為」の機械騎士・f04141)は慇懃無礼なる態度を崩さず、真っ向から『問う女』の瞳を見つめる。
アイセンサーが揺らめく。
黒炎があらゆる防護を無にし、侵食し、黒い炎へと変える力を持っていることは言うまでもない。
だからこそ、彼は立ち向かわなければならない。
「騎士として抱えた業罪は、この自我が発生した時よりむすに。為した善悪もまた然り」
ウォーマシンという存在。
戦うために生まれてきたがゆえの懊悩など、人ならざる演算速度を持つ電脳は、これまでも幾度も齎されてきた。
その一つ一つをなかったことにしなかったのが、彼の矛盾であり、ゆらぎである。同時に決して捨て置いてはならぬものでもあったことだろう。
「騎士として為した善に歓喜し、犯した悪に苦悩する」
そう、答えは得ているのだ。
例え、その解答が『問う女』の胸に落ちるものではなかったのだとしても。それでもトリテレイアは答えるだろう。
「それが“私”です」
迫る威圧をはねのけ、トリテレイアの格納銃器が排される。
己の躯体に施されたリミットが解除され、超過駆動が開始される。噴出する黒い炎を躱し、凄まじい速度で彼の身体が山岳の頂にある『問う女』へと迫る。
「己の所業、そして歩む道程が己を構成してゆくというのなら、例え無明の闇が行く手に広がろうとも、結末が死であろうと」
トリテレイアの歩みが止まることはない。
己が己であり続けるために、騎士として正しきを求める意志を、意味を見出し続ける。
それが鋼の騎士道(マシンナイツ・シベルリィ)であり、彼自身が見出した道である。
もはや『問う女』の視線も言葉も、トリテレイアを捉えることはできなかった。
黒い炎さえもトリテレイアは躱し、稲妻の如き疾駆でもって『問う女』の姿をアイセンサーに捉える。
光条走るが如きアイセンサーの煌きより放たれるのは電脳禁忌剣の一閃。
「闇を打ち払い、人々に光齎すは騎士の務め。幾度徒労に終わろうと、不屈の意志を以て進ませて頂きます!」
暗闇の世界ダークセイヴァーに閃く剣の一撃。
それは『問う女』の疑問も、矛盾も、狂気すらも切り裂いてトリテレイアの刻む新たなる道となることだろう。
脅かされる生命のないようにと、それらを守り育むことこそをトリテレイアは己の信じる道とする。
騎士として邁進すべき道を見つけた彼に、如何なる言葉も問いかけも理由には成りえないのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
 大町・詩乃
大町・詩乃
真の姿で神性解放。
死という終わりが有るから生命は無意味と断じ、生命無き世界のまま消えて行けば、それは単なる空虚に過ぎません。
世界は自分を必要とし、自分を見る存在を欲する。
だから生命は世界に求められて生じる。
個が死んでも生命の流れそのものは消えません。
途絶える流れ、間違った流れも出てくるでしょうが、それら全てを受容する事で流れ全体が強くしなやかになる。
だから無意味な生命は無いのです。
それが判らないのは貴女が世界と生命を侵す事しかできないオブリビオンだからです。
と詩乃なりの考えで返す。
彼女の言葉を論破し、彼女の眼差しはUCによるオーラで阻害し、彼女の威圧は詩乃が歩んできた道のりを以って否定します。
黒い炎は第六感で予測し、UCによる飛行能力・空中戦・見切りで回避する。避けきれない場合は衝撃波&念動力で吹き飛ばして対処します。
多重詠唱による光と雷の属性攻撃・神罰・全力魔法・高速詠唱で生み出した極大の神雷をスナイパー・貫通攻撃にて彼女に向けて放ちます。
骸の海で自分の間違いを噛み締め、反省しなさい!
溢れる想いが超克を為すというのならば、大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)は、まさしく神性解放(シンセイカイホウ)をした神であったことだろう。
人々や世界を護りたいという想いは、彼女の神性を底上げしていく。
猟兵が超克、すなわちオーバーロードに至る時、真なる姿が開放される。詩乃の神名は『アシカビヒメ』。
植物と活力を司る神性である。
「死という終わりが有るから生命は無意味と断じ、生命無き世界のまま消えて言えば、それは単なる空虚に過ぎません」
詩乃が見据える先にあるのは『問う女』の姿であった。
黒炎を身にまとい、未だ斃れぬオブリビオン。
それが『問う女』であった。彼女が求めているのは、答えである。
けれど、詩乃は知っている。彼女が求める答えには彼女自身がたどり着けぬことを。過去の化身である彼女にとって、世界は停滞したままのものである。
もはやこれ以上先には進めない。
未来という可能性を食いつぶすことしかできないのがオブリビオンであり、今を生きる人々が紡ぐ未来をこそ彼女は守らねばならぬのだから。
「意味がない。死が結末にあるのならば、今という時間は必ず過去に棄てられるもの。何も残らない。何も残せない。だというのに生きる意味があるというのですか」
その言葉に詩乃は天に浮かび睥睨する。
「世界は自分を必要とし、自分を見る存在を欲する。だから生命は世界に求められて生じる。個が死んでも、生命の流れそのものは消えません」
これまで数多の生命が詩乃の目の前を通り過ぎていったことだろう。
途絶える流れもあった。
間違った流れに辿り着くものもあった。
しかし、それら全てを受容することで流れ全体が強くしなやかになることを彼女は知っている。
無意味に思える生命であったとしても、無意味ではないのだ。
「だから無意味な生命は無いのです。それがわからないのは貴女が世界と生命を侵すことしかできないオブリビオンだからです」
言葉に、問いかけに、詩乃は己の言葉で返す。
それは黒い炎を噴出させ、彼女の身を護る加護をも侵食するだろう。
けれど、此処にあるのは神性である。
超克の先に至りし、彼女の視線は黒い炎すらも浄化消滅させる。身にまとう若草色のオーラは、彼女に危害を為すのであれば、それらの尽くを消滅して霧散させるのだ。
「どれだけ私を威圧しようとして無駄です。貴女がこれまで誰一人として皆さんを打倒できなかったように。貴女の行いこそ無意味であると知りなさい」
詩乃に迫る黒炎を彼女は躱し、山岳の頂よりも高き空へと飛び上がる。
どれだけ彼女を捉えようとしても、どれだけ彼女を蝕もうとしても、彼女に黒炎が触れることはなかった。
「正しさも、過ちも、善悪もない。死は平等に全てを迎え入れてくれる。それなのに、あなたはなおも抗うというのですか。そんなこと無意味でしかない。どうして、どうして、そこまでして」
戦うのか。
その問いかけに詩乃は答えなかった。
答えることは必要ない。
何故ならば、これまで生きてきた道のりこそが彼女の神性を示している。
植物と活力を司る神にとって、生と死のサイクルは循環そのもの。それ故に、彼女は多くの道を見てきたのだ。
若草色のオーラが暗闇の世界に広がっていく。
ダークセイヴァーは生命が脅かされる世界である。
太陽すら無い世界。地下にありて、人の営みすらももてあそばれるものでしかない世界。
それを詩乃は見てきた。
何度も見てきたのだ。悲しみも、苦しみも、何もかもがこの世界を包み込んでいる。それはどんなに生死の循環があれど、あっていいものではない。
悲しみと苦しみが在るからこそ、喜びと楽しみという感情が生まれるのだ。
「人とは、その営みの中で生きる者。違えてはならぬことを貴女は違えたのです」
詩乃の周囲に渦巻くは光と雷。
神罰の光が灯り、暗黒の世界を照らす。
天にありて仰ぎ見れば、そこにあるのは空ではなく隔絶する層。
天井でしかない空を人々はこれまで空だと思って見上げていたのだろう。陽光差さぬ世界にありながら、それでも人々は生きてきたのだ。懸命に。
ならばこそ、詩乃はその懸命さにこそ答えねばならない。
「骸の海で自分の間違いを噛み締め、反省しなさい!」
放たれるは極大の神雷。
山岳の抱きに落ちる一撃は『問う女』の黒炎すらも吹き飛ばしながら、彼女の身体を貫く。
明滅し、大気を震わせるほどの轟音が鳴り響いた後、其処に在ったのは炭と化してボロボロと崩れていくオブリビオンの名残だけであった。
ここに辺境の果ては踏破された。
一つの果てを乗り越え、また現れるは未踏の地たる『常闇の燎原』。
そこに如何なる驚異が待つのかを、猟兵は未だ知らない。
けれど、何も恐れることはない。
恐れとは勇気の隣にあるもの。どんな恐怖に隣り合っても、耐え進むことができるのが人間の尊さであるというのならば、その思いを胸に秘め暗闇をこそ踏破すべきなのだ。
『問う女』は言った。
『その道に進むべき意味はあるか』と。
ならば答えよう。
その道の先にこそ、意味は生まれるのだと――。
大成功
🔵🔵🔵
最終結果:成功
完成日:2021年10月16日
宿敵
『問う女』
を撃破!
|


 海鶴
海鶴
 フォルク・リア
フォルク・リア  外邨・蛍嘉
外邨・蛍嘉  ニノマエ・アラタ
ニノマエ・アラタ  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル  大町・詩乃
大町・詩乃  愛久山・清綱
愛久山・清綱  ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー  月夜・玲
月夜・玲  トリテレイア・ゼロナイン
トリテレイア・ゼロナイン  馬県・義透
馬県・義透 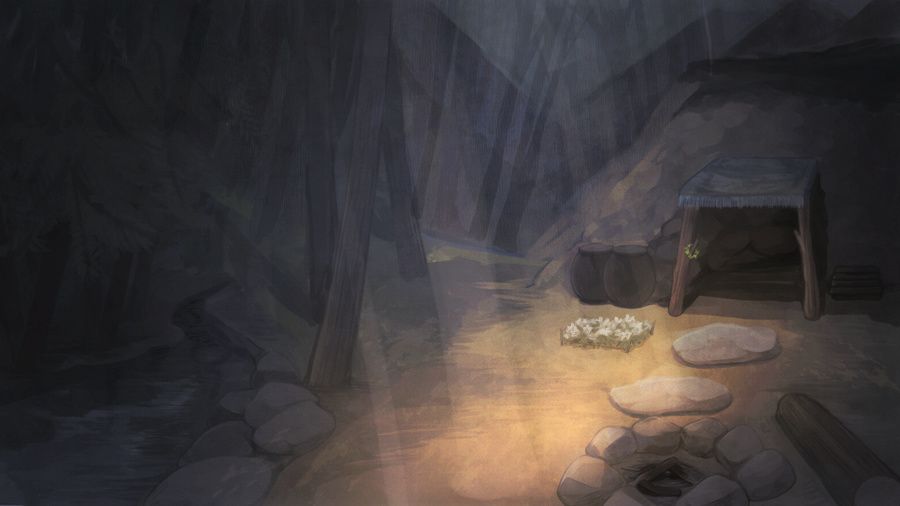
 馬県・義透
馬県・義透  外邨・蛍嘉
外邨・蛍嘉  ニノマエ・アラタ
ニノマエ・アラタ  リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  大町・詩乃
大町・詩乃  愛久山・清綱
愛久山・清綱  ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー  トリテレイア・ゼロナイン
トリテレイア・ゼロナイン  月夜・玲
月夜・玲 
 馬県・義透
馬県・義透  外邨・蛍嘉
外邨・蛍嘉  ニノマエ・アラタ
ニノマエ・アラタ  ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー  愛久山・清綱
愛久山・清綱  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  月夜・玲
月夜・玲  リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル  トリテレイア・ゼロナイン
トリテレイア・ゼロナイン  大町・詩乃
大町・詩乃