【神英戦争】試作品と使い捨て
夕映えの光が、山肌の緑をほの赤く化粧している。
日は既に水平線の彼方へと半ば身を隠し、斜陽が寂寥の残光でもって世界をさび色に映し出している。
紅色の帷幕を敷き詰めた空の下、地平線の彼方まで続く牧草地が、ほの赤く染まった緑の絨毯を、どこかもの寂しげに地平線の彼方まで広げていた。
吹きおろしの風が吹けば、草草は身を捩らせながら踊り狂い、さやさやと葉音を鳴らす。風は牧草地を突き抜け、青々とした原生林の林道を吹き抜け、吹きおろしに小さな村落へと駆け抜けていった。
アンドレイ・ヴィリキツキーの鳶色の瞳は、夕映えの光を反映しながら郷愁の色に揺れていた。郷愁の揺らめきと同居する様に冷徹な眼差しが北部に蓋をする小さな丘陵を静かに貫いている。
元来ならば木立の緑と山肌の褐色の二色のコントラストが鮮やかには、不気味な黒染みが蠢動してみえた。
不気味な黒い葬列は、地平線の彼方で黒い波濤を刻みながらアンドレイが守る村落へと向かい、ひしひしと押し寄せてくる。
この小さな山村へと数多のダモクレスの群れが突如襲撃したのだ。明光風靡な山野の景観は、今、迫りくる異形の神々によって凄惨たる黒色を夾雑されたのである。
万余を超える機械の兵団の軍靴が地を踏み鳴らし、けたたましい騒音でアンドレイの耳朶を揺らしていた。
「アンドレイの兄貴。やりますかい?見たところ、敵のデウスエクスは、雲霞の様な大軍ですが?」
どっしりとした重低音が響いた。声の方へとアンドレイが視線を遣れば、傍らで意気揚々と腕を組む、大丈夫の姿が視界に飛び込んでくる。
軍服を肩にかけながら、男は両手を合わせるとぽきぽきと指を鳴らした。泰然自若とした振る舞いで、男はがっしりとした顎元をしゃくりあげる。挑発するような態度は嫌いではない。アンドレイは軽く肩をすくめながら、悠然と言い放つ。
「戦力比はざっと百対一といったところだろう。だが…この街はやらせはしない」
確固と言い切ると、アンドレイは隣立つタケオから視線を外し、背中越しに村落をうかがった。レンガ造りの家屋から突き出た煙突からは、もうもうと白煙が立ち上っていた。
鼻腔に酸味たっぷりのシチューの香りが漂ってくる。おせっかいで人好きなステラおばさんの作ったシチューの香りだ。
街角に並ぶ街燈が、綿花の様なふっくらとしたオレンジ色の燈火を纏いながら、街々を柔和に照らし出している。柔和な光の綾が、賑わうバーへと向かい喜色満面で雪崩こんでいく男たちの姿や、仲睦まじげに手をつなぎ、足取り軽くあぜ道を進んでいく男女の姿を生き生きと照らし出していた。
耳を澄ませば、商店街で歓談する姿が散見された主婦たちの楽しげな声が、風に乗りながら遥か遠方の丘上に布陣するアンドレイのもとに小鳥の囀りで響いてくる。
牧歌的な農村の光景がそこには広がっていた。
――そうだ。かつて、地球侵略の尖兵の一体でしかなかったアンドレイ・ヴィリキツキーに人の優しさを、愛の深さを教えてくれた人々の精神はこの山村に変わらず根付いている。
そして、なんとも歯がゆいことに、アンドレイが所属するDIVIDE直轄英国第一軍は政争敗北を打開すべく次なる出征に舵取りし、山村を放棄することを決めたのだ。
だが、アンドレイは…。いやアンドレイと共に人類の共生を決めた亡命者たちは、上層部の意向に背き、この街を死守することを決めたのだった。
この街が無ければアンドレイの今は無い。アンドレイの『ヒト』としての生は常にこの街と紡がれ、そして今後も共に流れていくのだ。
緘口令が敷かれていたために、アンドレイが敵の接近の報を聞き及んだのは半刻ほど前の事であった。火急の敵の接近に市民を逃がす時間は最早、残されてはいなかった。
だが、希望はある。
それが第三軍の存在だった。
第三軍の指揮官で知られるラファエルは、政戦両略に優れた型破りの天才として軍内部で噂れていた。
アンドレイは彼に賭けた。
そして、アンドレイの派遣した密使は既にラファエルのもとを訪れ、援軍を取り付けたのだ。事実、つい先ほど、ラファエル率いる第三軍が出立したとの報をアンドレイは得た。
アンドレイが時間を稼ぐことができれば、第三軍は間もなく駆けつけるだろう。
遠景に広がる山村から、前方の山稜へとアンドレイは再び視線を戻す。
黒い波が山を踏破し、新緑が鮮やかに萌える平原へと充溢いくのが見えた。無慈悲な機械音は、今や間近まで迫っていた。
「タケオ、守るぞ。俺らの義父や友、愛すべき人達が愛したこの地を。すまんが、お前の命を俺にくれ」
口端を不器用に歪め、アンドレイは精一杯の笑みを取り繕った。
隣でタケオが苦笑するのが見えた。彼はひとしきり愉快に笑うと分厚い顎元を軽く引く。
気づけば、アンドレイは駆け出していた。
後方に向かい幅広に布陣した外人部隊はアンドレイの突撃に続き、猛然と緑の海の中を突き進んでいく。
しばしの間、平原には水を打ったような静けさが漂っていた。しかし、静寂もつかの間、絹を裂くような銃弾の轟音と共に平原は赤く染まる。
アンドレイを先頭とする小集団は黒い波濤の中心に巨大な亀裂を刻みそのまま突き進んでいったが、しかし、すぐに勢いを落とし、黒い波に飲み込まれていく――。
●
脳裏を掠めたのは、機械の様に怜悧な面差しをした男性の姿だった。迫りくる無数の敵に対して、人の心を宿したレプリカントの青年は仲間たちと共に無謀な戦いに身を投じる事となったのだ。
眼を閉じて、脳裏の映像に意識を傾注させていけば、否応なしに最悪の結末がエリザベスの脳裏へと阿鼻叫喚の地獄絵図となって浮かび上がる。
確かにアンドレイと呼ばれるレプリカントの青年を筆頭とした亡命者たちの奮戦ぶりは目を見張るものがあった。アンドレイを筆頭に、亡命者たちの一団は八面六臂の活躍により、デウスエクス『GLMストーク』の残骸を平野に山と積みあがげいく。
だがそれでもなお、両兵力差は如何ともしがたいものがあったのだ。
一人、また一人と亡命者たちは倒れていき、ついぞ、全滅するに至る。そうしてもはや、守るものがいなくなった山村をデウスエクスたちは我が物顔で蹂躙していく。
市民たちはまともな抵抗もできないままに、巨大な鉄の足に踏み潰され、散弾に体を撃ち抜かれ、青白い閃光により全身を焼灼されていった。
そして――。失われた人々の命を贄としてデウスエクス達はこの地に封じられた機械神『レヴィアタン』の復活を試みるのだった。
エリザベスは目を開く。
パイロットスーツを冷汗がしとどに濡らしているのがわかる。ひとりでに唇が震えだしていた。
今、脳裏に投影されたのは未来の映像だ。放置すれば悪夢の内容は現実となるだろう。
小さく深呼吸し、呼吸を整える。
だけれど…。
首を左右させながら、エリザベスはグリモアベースに立つ。恐怖などおくびにも出さぬように、毅然と表情を取り繕わんと意識すれば、作り笑いと言えども微笑が口元に浮かび上がる。
奇跡を起こす猟兵たちの力は常に奇跡を起こしてきたのだ。
一人、また一人と姿を現していく第六の猟兵たちを前にしてエリザベスは小さく口元をほころばせた。
「事件が予知されたの…。みんなの力を貸してちょうだい?」
ぽつりと紡がれた言の葉は、奇跡の輝きを放ちながら周囲に潮騒の様に満ちていく。
 辻・遥華
辻・遥華
オープニングをご覧頂きましてありがとうございます。辻・遥華と申します。
舞台は再びケルベロスディバイド世界となります。
イギリスの田舎町にて、かつて封印された強力なデウスエクス『レヴィアタン』復活を目論むデウスエクスとの熾烈な戦いが繰り広げられます。 今回は神英戦争の第五話となります。神英戦争は、全五話で第一部終了を予定しており、今回が最終話となります。
神英戦争を通して、登場人物/状況は前話までのものを引き継いでおりますが、前章の参加にかかわらず一話で完結される内容となっています。ご興味湧きましたら是非、ご参加を検討くださいー。
以下、各章の詳細についての説明です。
●第一章
封印されたデウスエクス『レヴィアタン』の復活のために山村を襲撃した無数のダモクレス『GLMストーク』を破壊してください。決戦の場所は、山村郊外の広壮とした平原となっています。やや西日が厳しいですが、比較的戦いやすい戦場となっており、大軍がより利を活かしやすい戦場となっています。多数の敵との交戦を想定した内容、UCを使用した場合にはプレイングボーナスとなります。🔴一つにつき、街の防衛隊員が十人づつ戦闘不能となり、🔴が合計で10を超えた場合には、第三章で決戦配備が不可能となり。🔴≧11の場合は、住民たちが犠牲となり、三章における敵が強化されます。転送時の状況などは断章にて描写します。
また第一章の結果が第二章の内容に影響します。
●第二章
第一章の成否によって内容が変化します。二章における断章を参考になさって下さい。
●第三章
ボス戦となっています。かつての戦いにおいて封印された巨大デモクレス『レヴィアタン』と戦闘します。敵の強さや決戦場所は、第一章、第二章の成否によって変化します。詳細は三章断章を参考になさって下さい。
以上となります。
参加者人数は依頼達成必要な4名様~最大8名様を参加者として想定しています。人数を万が一、超過してしまう場合は、先着順で採用させて頂きます。また、人数に満たない場合は積極的にサポート様にお力添えお願いすると思います。
第1章 集団戦
『GLMストーク』
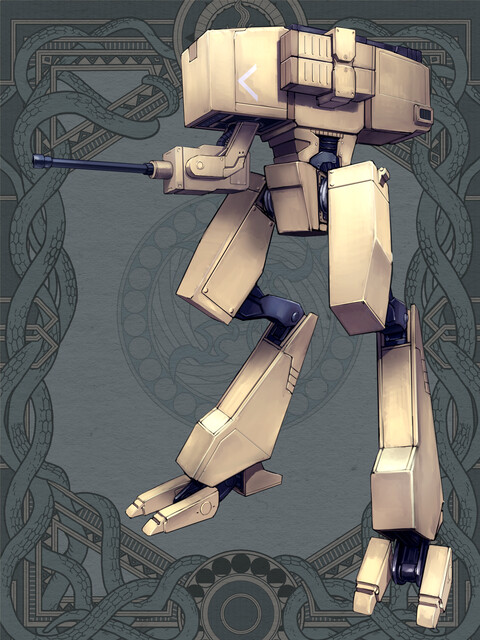
|
POW : プラズマキャノン
【胴体上部に展開した砲台】から【高密度プラズマ弾】を放ち攻撃する。その後、着弾点からレベルm半径内が、レベル秒間【超高熱】状態になる。
SPD : OCSミサイルランチャー
【胴体側面のミサイルポッド】からレベル個の【光学迷彩機構搭載型ミサイル】を射出する。射出後も個々の威力を【光学迷彩の精度】で調節でき、低威力ほど視認困難。
WIZ : 制圧射撃
【胴体下部の機銃】から無限に供給される【高貫通力の弾丸】を、レベル分間射撃し続ける。足を止めて撃つと攻撃速度3倍。
イラスト:Hispol
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『集団戦』のルール
記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
翡翠の光に導かれるようにゲートを潜り抜ければ、鉛の様に重苦しい斜陽が、刺すように猟兵たちを包み込んだ。遠景に浮かぶ山々は茜色の空をくっきりと切り抜き、雄々しく屹立して見えた。
赤ら顔で立ちすくむ山岳地帯より、連なる無数のダモクレスの群れが不気味な黒い霧となって這うように進み出る。
万を超えるだろう『GLMストーク』の大軍は乳白色の武骨な大足で、草の大地を踏みにじりながら、耳障りな駆動音と共に猟兵たちが舞い降りた小高い丘へと向かい、猛烈な勢いで迫りくる。
ふと後方へと踵を遣れば、小丘からやや離れた山間に軒を連ねるレンガ造りの街並みを猟兵たちは見る。街角に携えられた角灯は幻燈の揺らめきで輝きながら、街々をうっすらと包み込み、夜支度を安穏と好奇の表情で待ちわびる人々の喧騒を浮き彫りにしていた。
前方へと再び視線を戻せば、丘上から迫りくる敵デウスエクスの一団へと向かい、今まさに攻め込まんとするケルベロスの一団を猟兵たちは目撃する。その数はおおよそ、百人程度だろうか。
一人一人が精鋭であろうことは間違いないが、万余に及ぶ敵を相手取るには、彼らがいかに精強であろうとも彼らの奮戦は水泡と帰すであろうことは誰の眼にも明らかだった。
だが、ここには猟兵である自分たちの存在がある。ケルベロスと猟兵が力を起こせば、寡兵で大軍を打つことも不可能ではあるまい。ましてや、今、この地にはDIVIDE直轄の第三軍が救援に向かいつつある。となれば、最悪、敵の猛攻を食い止める事さえできれば、援軍により現状の戦力差は容易に逆転するであろう。
敵は刻々と距離を詰めてくる。
背中越しに人々の穏やかな息遣いが、にわかに感じられた。
ふと鼻腔を突き抜けていく夏草の甘やかな香りと共に、戦いの緊迫感が急激に高騰してゆく。一歩、一歩と迫るダモクレスの足音は間もなく戦いの幕が切られるであろうことを如実に物語っていた。
―――――――――――――――――――――――――――――――
以下にポジションについて記載します。
効果は通常の決戦配備とほぼ同様の効果となりますが、名前付きのキャラクターを決戦配備に選ばれた場合は、テイストとしてやり取りなどを描かせていただきます
1.Sn:アンドレイ・ヴィリキツキー
→もと、デウスエクスとして地球侵略の尖兵として戦っていましたが、人の優しさに触れて人の心を得て、ケルベロスとして覚醒しました。射撃に関しては右手に出るものはなく、正確無比な射撃はありとあらゆる標的を寸分たがわずに撃ち抜きます。
2.Jm(ジャマー)、Df(ディフェンダー)、Cr(クラッシャー)、Cs(キャスター)、Md(メディック)
→通常通りです
 大町・詩乃
大町・詩乃
◎
スナイパー要請
他の猟兵さんとも連携
人々を護る為、スーパーロボット『焔天武后』を操縦して出撃しますよ。
アンドレイさんや猟兵さんには「相手の隙を作り出しますので、立ち直る迄の間に皆さんの全力で攻撃して下さい。」とお願い。
機械生命体による万を越える軍勢。
厳しい相手ですので《自然回帰》を発動。
戦場にいる敵全機をシステム停止と電源オフに陥りさせる。
再起動して態勢を整えるまでの間に、皆さんと連携し、全力攻撃(焔天武后によるレーザー射撃・光の属性攻撃・一斉発射・スナイパー)で撃ち抜いていく。
他には結界術・高速詠唱で防御壁を展開したり、武器巨大化してオーラ防御を纏った天耀鏡の盾受けで、自分と味方を防御する。
 エクレア・エクレール
エクレア・エクレール
◎、Sn
まさしく「敵は強大、味方はわずか」といった状況じゃな
その中でなお光を失わず第二の故郷を守らんとするその心意気、誠に見事じゃ
おぬしのような者達の命をあのような無機的な輩にくれてやるのはもったいない
微力ながら力を貸そうぞ
――おぬし達も機械の身
わしの雷に当てられぬようまずは下がっておるのじゃな
移動のルーンの力をもって雷速で上空へ
敵の集団を見据え、雷のルーンの力を解放(UC)
雷雲を引き起こし、敵|軍《群》の全てに雷を落としてやろう
雷槍を構え、雷速で敵陣の中へ
なお動く者達を突き、斬り払ってゆこう
止めはアンドレイ達が確実に刺してくれる筈
わしは大雑把に壊してやるだけで十分じゃ
●
陽光が齎す赤光が平原の緑を赤銅色に照らし出していく。
風は凪ぎ、初夏の山野には仄かな暑気がはびこっていた。林立する木々は、炎とも血とも見紛う朱色に葉木を燃やしながら、微動だにすることなく何かに怯えるように梢を揺らしているようだった。
水を打った静寂のもと、大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)は小高い丘の上に立ち、眼下に緑の平原を臨む。
地平線のかならで無数の黒点が歪に蠢くのを前に、詩乃のふっくらとした唇が緩やかにへの字を描いた。
詩乃が目を凝らせば、膨大な数に及ぶ黒点が互いに身を寄せ合いながら、イナゴの大群を彷彿とさせる不気味なうねりとなって、緑鮮やかな草原を這うようにして蚕食してゆく。
詩乃の藍色の瞳は、山村へと向かいひたひたと迫る機械仕掛けの巨大な機影を静かに映し出していたのだった。
敵デウスエクスはGLMストークと呼ばれる機械兵である。
ただ効率よく人を殺すことだけに主眼を置いて作られたこの殺人兵器の形状は、情緒や風情などとは無関係に、ただ彼らが目的に合致するように無味乾燥な造形でもって塑造されたものであった。
GLMストークは、機械的な箱型の胴体部とそこから突き出した機銃でもって、体幹部を構成する。GLMストークの腹部に搭載された機銃が、黒光りしながら前方を睨んでいた。砲身が軋みを上げながら収斂するたびに、歯ぎしりの様な耳障りな金切り音が周囲に響いていく。
甲虫を思わせる無機質な機械の大足が勢いよく振り上げられれば、無慈悲な鋼鉄の大足が、足元の草草を踏みにじる。
体幹部から突き出た、小柄な胴部とは不釣り合いに巨大な両の脚はまさに冷酷の象徴であった。
両の脚にねっとりとした光沢を滲ませながら、他者を威圧するように、このイナゴの様な二足歩行の機械兵は大地を踏み鳴らすのである。
この機械仕掛けのイナゴには人間の頭部を思わせるような顔面部や、腕部は不要とみなさたのだろう。GLMストークは、腕や顔面を完全に排除した人ならざる不気味な影を丈高く伸ばしながら、ただただ人々の命を刈り取るためだけに山野を進むのだった。
一体一体でも恐怖の象徴たる殺人兵器GLMストークが、今や山野にあふれかえっているのだ。今や、歪な機械のイナゴの大群は、視界を埋め尽くすほどの幅広な横列を、縦深へと何層にも敷きながら黒い波濤となって詩乃らのもとへと押し寄せてくる。
しかし、この異様なイナゴの大群を前にしてもなお、詩乃の藍色の瞳は、楚々たる光を失うことなく冷静沈着そのもの静かに凪いだままだった。
詩乃は人を愛する。そして、人々を愛するがゆえに平穏を脅かすものと戦う刃となることを決めたのだ。
かつては、往流坐葦牙神社にて信奉される八百万の神の一柱であったアシカビヒメが神聖を残しながら猟兵として覚醒したのが詩乃である。
平素は往流坐葦牙神社の巫女として神事を全うしながらも、詩乃は人々に危険が迫れば人々を守る盾となり矛となる。事実、詩乃はジャスティス・ウォーを善神の一柱として人々のために戦い抜いてきた。
木漏れ日の中、境内で猫をあやすのが好きだった。
近所のお年達とお茶菓子を持ち寄って歓談交じりにお茶をたしなむのが好きだった。
縁日の賑わいの中、屈託なく笑う少年少女を遠間よりぼんやりと眺めるのが好きだった。
人々の営みは陽だまりの様な温かさで満たされていたからだ。少なくとも詩乃の故郷はそうであった。
いや、今、詩乃の背後の山腹に横たわる山村においても、人々は詩乃の愛する陽だまりの様な日常の中で生を謳歌しているのだ。
守りたい――と胸が高鳴った。
そして、詩乃には彼らを守る力がある。本来ならば温厚たる詩乃は、今、無辜の人々を守るために自らの力を振るわんことを決めたのである。
詩乃は伏し目がちに左方へと視線を移す。
巨大な石像がそこにあった。
流線形の姿態を描く、数メートルにも及ぶ石像が、暮色の空へと向かい長躯をそびやかせていた。
かの石像こそ、詩乃にとっての刃である。
焔天武后たる鋼鉄の女皇帝は厳粛さを湛えながら、詩乃の傍らで直立不動で控えていた。
焔天武后を傍らに置きながら、詩乃は、でこぼこの砂利道の上を数間ほど進み、アンドレイの陣地へと躍り出る。
詩乃が幕舎をくぐり、居並ぶ兵士たちの前に躍り出るや、決死の覚悟をみなぎらせるレプリカント、ウェアライダー、ドラゴニアンよりなる混成軍の面々が、詩乃へと一様に視線を向けるのが見えた。
詩乃は従容とした挙止でもって、一同に一揖してみせる。
なるほど、さすがは精鋭といったところだろうか。
居並ぶ兵士たちは、予想だにしない来訪者を前にしてもなお、狼狽一つ示さずに、ただ詩乃へと道を開けるだけだった。
詩乃は、兵たちの間を、風雅な足取りでもって進んでゆく。しばし、歩を重ねれば詩乃は直ちに目的の人物を見つけるに至る。
燃えるような赤い髪を風になびかせながら、青年は、丘の突端に立ち、眼下へと鋭い視線を向けていた。
血の気の通わぬ青年の蒼白な面差しがふと眼下の平原から詩乃の元へと向けられれば、怜悧さを湛えた鳶色の瞳が真正面に詩乃を捉える。
アンドレイと呼ばれるレプリカントの青年の姿がそこにあった。
青年の瞳は、夕焼け空を反映したかのような暗い紅色の揺らめきを湛えながら、静かに詩乃を見据えていた。
憐憫の色をにじませた青年の無機質な瞳の中に、しかし詩乃は、人の持つ慈愛の光を確かに見たのだ。命を賭しても人々を守らんとする、高潔の光がそこに揺蕩っていた。
詩乃は挙措を整え、アンドレイに会釈する。そして単刀直入、進言する。
「アンドレイさん、敵への出撃はややお待ちください」
ふんわりとした、鈴を転がすような詩乃の声音が周囲に広がった。アンドレイがいぶかしげに首を傾けるのが見えた。
「あなたは…?」
アンドレイの鳶色の瞳が不思議そうに丸められるのが見えた。鼻腔の奥で底ごもった様に響く、しっとりとした低音が詩乃の声音に交じり、りぃんと茜空に響いてゆく。
一瞬、気恥ずかしさを覚えた。白磁の頬をわずかに染めながら、詩乃は口元を柔和に綻ばせると、アンドレイへと返答する。
「申し遅れました。私、大町詩乃と申しますの。DIVIDEよりあなた様達の救援のために派遣され、ただいま参上いたしました」
清淑な物言いで詩乃が応えれば、アンドレイが小さく首を縦に振る。打てば響く様にアンドレイが詩乃へと謝辞する。
「詩乃さんか…。救援に感謝する――。だが…、あなたの進言は受け入れることはできかねる。すでに敵は刻々とわれらのもとへと近づいている。今すぐにでも敵陣へと打って出なければ手遅れとなることは必定だ」
アンドレイの言葉に詩乃は直ちに首を左右にした。鄭重な物言いそのままに、詩乃はアンドレイに反駁する。
「状況を油断を許さないというのは、アンドレイさんの仰る通りです。ですけれど、無策で挑めば、数で圧倒する敵の前に、間もなく我々は壊滅の憂き目にあうことは間違いありません。だからこそ、皆さんの攻勢に先立ち、先陣を私に任せてもらいたいのです。私が相手の隙を作り出します――。そう、この焔天武后と共に――」
詩乃が左手を振り上げれば、小袖の幅広な袖元がふんわりと優雅に宙を揺蕩った。
白樺の様な指先が虚空を踊れば、やわらかな微光が周囲に迸る。
柔らかな光の飛沫は空を優雅に流れてゆき、無音で聳えるだけだった石像に触れる。
淡い光の粒子が柔らかな指先でもって石像の表面をなぞれば、ただ、静かに屹立するだけだった石の女皇帝は、その素肌に優艶とした紅色をにじませながら色めきたってゆく。
詩乃はアンドレイに膝を詰める。そうして再び安穏とした声音で続ける。
「私と焔天武后が先陣を仕ります。押し寄せる敵の動きを止め、相手に隙を作り出します。皆様は敵が立ち直る迄の間に火力を集中させ、敵に強烈な一撃を与えていただきたいのです」
アンドレイはしばらくの間、ただ静かに詩乃を見守っていた。
感情の色に乏しい鳶色の瞳からは彼の思考は読み取れなかった。アンドレイの朱色と詩乃の藍色が夕日の中で一つに溶け込んでいく。ただ、周囲に満ちていたのは心地のよい静寂だけだった。
この穏やかな静けさの中で、ふとアンドレイが口端をわずかに収斂させるのが見えた。
整った青年の面差しに、不器用な笑みが浮かび上がった。だが、精一杯に作ったであろうこの不器用なまでの笑顔は、決して詩乃を不快にさせるものでは無かった。
同時に、この不格好な笑みこそがいかなる雄弁にも勝る、アンドレイなりの答えだったのだろう。詩乃もまた気づけば相好を崩していた。
そんな詩乃を不器用な笑顔で見守りながらアンドレイが口を開く。
「了解した。詩乃さんの指示通り、われらはあなたに続き動きましょう――。あらためて、詩乃さん、あなたの助力に感謝する。そして…願わくば、この山村を共に守り抜こう」
アンドレイの真摯なまなざしが詩乃を貫けば、たまらず、桃色の微笑が詩乃の口もとをついた。小さくかぶりを振りながら、詩乃はアンドレイに即答する。
「願わくば…ではありません。絶対に守って見せましょう? 皆さんも含めて誰一人として欠けることなく、この街を守るのです」
詩乃は明朗と言い切ってみせる。そうして、隣立つ焔天武后へと手を伸ばす。
覚悟を込めた指先が暮色の空へとするりと伸び、紅色に燃える焔天武后の装甲にひたりと触れた。
ついで詩乃の指先が焔天武后の滑らかな朱色の肌をなぞれば、瞬間、詩乃の全身が透明な光の泡沫に包まれる。
ふわりと詩乃の両脚が大地を離れた。詩乃の全身を心地よい浮遊感が包み、ついでしなやかな姿態が夕焼け空を緩やかに浮遊してゆく。
詩乃の体躯は、しばし優雅に空を遊泳しながら焔天武后の胸元へとぴたりと触れたかと思うと、まるで吸い込まれるように操縦席へと飲み込まれてゆくのだった。
そう、神機はここに一体となった。
今、焔天武后は詩乃を載せ、深紅の女皇帝としての威容を宇内に顕現したのである。
「アンドレイさん――、ゆきます! 私の攻勢に続き、皆さんも敵軍へと砲火を繰り出してください――」
コクピット越しに詩乃は言い放つ。同時に、焔天武后を天高く浮上させる。
女皇帝の巨体が空へと浮かび上がれば、巻き起こった旋風に煽られて、足元の緑が濛々と空に舞い上がってゆく。
詩乃は低空で機体を滞空させると、メインモニター越しに浮かび上がる敵の大軍を見据えた。
今や敵の大軍は、黒い波となって山野へとあふれ出し、飛沫を上げながらアンドレイらが布陣する丘陵地帯へと迫りつつあった。
「自然の営みによらずして生み出されし全ての悪しき存在よ――」
ぽつりと詩乃の声がこぼれた。発声に続き、詩乃は、群がる敵へと向かい焔天武后を飛翔させる。
焔天武后が空をなめらかに走り抜けてゆけば、ものすごい圧迫感がコクピット越しに詩乃の全身に打ち付けた。強烈なGに必死に耐えながら、詩乃が機体を加速せてゆけば、焔天武后は赤い一陣の光弾となって、茜色の空を鮮やかに潤色し猛然な勢いでとGLMストークの集団のもとへと急迫してゆく。
瞬く間に、焔天武后とGLMストークの距離が縮まった。
当初、黒い波となって広がるばかりであった黒い点の集積は、今やメインモニターにて明瞭とした輪郭を取りながら、一つ、一つが歪な鉄の怪異となって映し出されていた。
詩乃はGLMストークの上空で焔天武后を滞空させると、群がる無数の鉄の怪異をコクピットごしに見下ろしながら、声高に宣誓する。
「アシカビヒメの名において動きを止め、本来あるがままの状態に帰りなさい――」
詩乃の柔らかな声音が響いたかと思えば、焔天武后の紅玉色のの装甲より新緑を思わせる柔和な若草色の微光が
あふれ出す。
それまで押し黙っていた風は、まるで詩乃の声音に呼応するかの様に突如、吹きあれ、周囲に揺蕩う若草色の微光を山野一杯に広げてゆく。
今、詩乃の神気を帯びた清浄たる光の微粒は雨となり山野を包み込んだのある。
この一滴一滴こそが、詩乃が使役するユーベルコード『自然回帰』が齎した奇跡の雨粒の象形だった。あふれ出した若草色の雨滴は、山野へと輪を広げ、数多押し寄せてくる機械仕掛けのイナゴを洗い出してゆく。
GLMストークの脚関節がぎしりと軋みを上げた。それまで、不遜な足取りで足場の緑を蹂躙していた機械仕掛けのイナゴは緩慢と動きを鈍らせてゆき、ついぞ、完全に動きを静止させる。
今、詩乃が生み出したユーベルコードの光は、GLMストークの時を凍らせたのである。
詩乃の使役したユーべルコード『自然回帰』により、GLMストークの大群は一時的ながらも機能不全に陥っていったのであった。
押し寄せる不気味な波はここに、完全に動きを止めたのである。
「アンドレイさん、皆様――! 攻勢をよろしくお願いします」
詩乃は語気を強めて言い放つ。
機械仕掛けのイナゴの軍団は、今、完全に無防備である。元来、温厚たる詩乃と言えど、この千載一遇の好機を見逃すほどに気長ではない。
詩乃の指示に続き、焔天武后の後方より、青白い光芒が立ち上がった。
青白い光芒は、一条、二条と長い尾を曳きながら未だ若緑色の雨が漂う空を勢いよく滑走し、機械仕掛けのイナゴの大群へと肉薄するや、その巨大な雷光の大腕でもって、一体、また一体とGLMストークを薙ぎ払っていく。
詩乃の『自然回帰』により敵は動きを止めただけに非ず。
彼らの重厚な装甲は、今や堅牢性を失いつつあった。
もはや、アンドレイ達スナイパー部隊による銃撃をGLMストークの装甲が遮ることは叶わなかったのだ。
間断なく空間を埋め尽くす青白い閃光の束は、GLMストークの分厚い装甲を、まるで紙かなにかの様に刺し貫いていく。今や、若草色に輝く視界は、絶え間なく放たれた無数の光弾によって、鮮やかな紫色に染め出されていた。
淡い光の奔出の中で、一体、また一体とGLMストークの残骸が草の大地へと横たわっていくのが見えた。
イナゴの群れの様になって大地に蠢いていたGLMストークの大群は、若草色の雨に洗いだされ動きを止め、ついで雪崩の様に押し寄せた強烈な雷光の洗礼を受け、粉微塵に粉砕されてゆく。
「皆様――、お見事にございます。さぁ、焔天武后…。私たちも共に!」
未だGLMストークの大部分は不動のままに、アンドレイらスナイパー部隊によるレーザー砲によってじりじりと数を減らしていった。
だが、『自然回帰』により生み出された若草色の光もまた、徐々にとだが勢いを落としているのもまた事実だった。すでに数百を超えるGLMストークは物言わぬ残骸と化し、草の大地の上に鉄の遺骸を積み重ねていた。
だがそれでもなお、打ち破った敵の数は全体のごく一部にしか過ぎないのだ。
敵は未だに万を超す大兵力を有しているのが現状である。
ゆえに、詩乃には光の雨が鳴り止む前に、少しでも敵軍の数を減らす必要があった。
「――ゆきます!」
言い放つと同時に、詩乃はコクピット内で左手を振り下ろす。瞬間、詩乃の挙止を寸分たがわずに再現するように、女皇帝が紅色の流麗たる指先をGLMストークに向かい振り下ろした。
焔天武后の指先より幽玄の白光が迸る。
白光は、周囲に四散したかと思えば、無数の矢となり地上へと降り注ぐ。
眩いばかりの光が迸る。するりと白い光の矢がGLMストークの分厚い胸壁を貫いた。瞬間、爆炎が周囲へとあふれ出し、GLMストークの巨体が激しい炎の中でぐにゃりと歪む。
無数に生み出された白光の矢は続々とGLMストークの集団に押し寄せ、鋭い矢を突き立てていく。
GLMストークの巨大な両脚を白い閃光が貫けば、機械仕掛けのイナゴは自らの巨体を支える事能わずに、ぐずりと地上へと崩れ落ちていく。光の矢が四方から鉄の巨体を貫くのが見えた。爆炎の中を飛翔しながら、光刃が歪な鉄のイナゴを撫で切りにするのが至る所で散見された。
あふれ出した無数の光の矢は、一体また一体と歪な鉄のイナゴを打ち貫きながら、瞬く間に無数の屍を築いていくのだった。
未だ、『自然回帰』の光により微動できぬようで、GLMストークは、光の矢に貫かれ指数関数的に数を減じていく。
今や膨大な黒い波濤は、焔天武后により放たれた天上よりの光弾と、アンドレイらによる地上よりのレーザ砲による焼灼によって、押しとどめられ、じわりと勢力を落としつつあった。
白光の揺らめきと紫色の幻燈が、若草色に輝く空を鮮やか二色の光芒でもって淡く照らし出した。
飛び交う無数の光弾の中、粉砕されたGLMの装甲の破片が銀色の砂となって周囲に濛々と立ち込めていく。
無数の光弾が止み、ついぞ、若草色の微光も霧散する。
銀色の天幕は開かれ、ついで山野が夕映えの斜陽によって重苦しく照らし出されていく。
再び広げられた視界のもと、山野には黒染みとなって広がる無数のGLMストークの残骸が横たわって見えた。横たわる数多の残骸こそが敵の先遣部隊の出鼻をくじいたことを証左していた。
しかし、あくまで打ち破ったのは氷山の一角といったところであろうことが詩乃には伺われた。
詩乃やアンドレイらの決死の攻勢にもかかわらず、損壊を免れ、無傷なままに蠢くGLMストークの姿も多数散見された。
残存する機械仕掛けのイナゴは、『自然回帰』が効力を失うや、多関節の脚部を歪に収斂させながら、無機質な鉄の軍靴でもって再び緑の大地を踏み鳴らす。
一字を動きを止めた黒い波は、再び、勢いを取り戻し、山の中腹に横たわる山村へと向かい魔手を伸ばしていく。彼らは、周囲に山積する友軍の残骸など素知らぬ風で、友軍の屍さえも踏みにじりながらひたひたと進撃を開始するのだった。
詩乃は、焔天武后のコクピット席より、このおざましい機械仕掛けのイナゴの群れを眼下に俯瞰していた。
たしかに彼らは、再始動を再びはじめ、山村へと向かい猛然と野を浸食してゆく。
だが、一見、『自然回帰』より完調したかに見えたGLMストークでが、若草色の光によりその性能を減じていることを詩乃は具に見抜いていた。
大気に溶け込み、完全に効力を失ったかに見えた若草色の雨の余韻は、GLMストークの屈強たる装甲に未だ致命的な綻びを残したままに敵を蝕んでいるのだ。
「あとはお任せしました――」
ユーべルコードの発動に続く一連の攻撃により、さしもの焔天武后といえども、今はエネルギーの大部分を失いつつある。
詩乃は押し寄せる黒い波から踵を返すと、そのままアンドレイらが布陣する小丘へと急行する。
詩乃は身に残された力を振り絞り、結界術・高速詠唱でもって、小丘を中心に防衛壁を幾重にも張り巡らせてゆく。そう、詩乃は、自らは小丘の防衛に専念することを決めたのだ。
詩乃の攻勢は終わった。だが、それは自ら達の攻勢の終わりを意味するものでは無いことに詩乃は既に気づいていたのだ。
遠く鳴り響く雷光が、福音を鳴らしながらアンドレイらのもとへと急行せんとしていることを詩乃は知悉していたのだ。
遠景よりじりじりと響く雷鳴と共に、今まさに猟兵による第二の太刀が振り上げられる。
●
山野へと押し寄せる黒い波を包むように、若草色の光が呟耀の輝きでもって、エクレア・エクレール(ライトニングレディ・f43448)の視界を照らし出している。
夕映えのただれた赤色光を遮るようにして、若草色の雨が戦場全体に溢れ出していた。
エクレアは、大岩の上に片膝をつきながら座り、若草色の雨が降りしきる戦場を悠然とした面持ちで眺めていた。
猟兵たるエクレアは、溢れだした若草色の雨滴の一滴一滴から、奇跡の御業の余韻を肌感覚で感じ取ることができた。
間違いない――。エクレア同様に、別の猟兵もまた、この戦場にて矛を振るっているのだ。
若草色の光雨こそが、友軍の矛であるのだ。
事実、遠景で黒い波となって集簇する機械兵仕掛けのバッタの大群は、身を濡らす若草色の雨滴によって、完全に体動を止めたのだ。
間違いない。あの神々しい光は、味方の猟兵によって生み出されたものだろう。
それにしても、とエクレアはわずかに口端を綻ばせた。
端正な面立ちに快活とした笑みを浮かべながら、エクレアは両の膝に手を当てると岩場の上で軽く屈伸運動を始める。
――雷霆神たるわしが今まさに戦場を駆けんとしたその瞬間に、奇跡の雨が降りしぶくとは、おあつらえ向きにすぎるというものじゃ。
蜂蜜色の瞳が好奇の光を帯びながら、煌々と輝きだす。
鮮やかな金色の瞳でもって、エクレアは閃光飛び交う戦場を観察する。
膝の屈伸運動に続き、軽く手足の関節を伸ばしながら、エクレアは、鵜の目鷹の目で、その形の良い金色の瞳を動揺させた。
光の雨に続き、アンドレイら亡命ケルベロス達によるレーザーライフルの照射が蠢く敵兵を薙ぎ払っていく。
紫色の光が迸り、黒い染みとなってひしめく機械のイナゴの大群のもとを焼灼してゆけば、山野にはデウスエクスの残骸が小山となって築かれていく。
もちろん、攻勢はアンドレイらのものに留まらない。
アンドレイらの斉射に続き、上空よりは白光が鮮烈な光の柱となって降り注いだのだ。
光の柱の一撃は、おそらく友軍の猟兵によるものだろう。淡い光の帯をなびかせながら、光柱は矢となって降り注ぎ、歪なバッタの大群を次々と刺し貫いていった。
攻勢はますます猛威を強め、そうしてついぞ極点に至るや、押し寄せる黒波に巨大な亀裂を穿つのだった。
歪な機械バッタ、GLMストークの装甲はレーザー砲の斉射によって砕け散り、撃ち抜かれた数多の残骸の装甲は今や、大量の白銀の砂となって鮮やかに空を染め出し、銀世界をそこに作り出していた。
すでに若草色の光の雨はぴたりと降りやみ、山野は靄のようになって漂う銀粉に包まれていた。ただ、落日の赤光だけが銀世界をほの赤く照らしていた。
銀世界のもと、無数の黒点が歪に蠢動を始めたのは、光弾が鳴り止み、水を打ったような静けさが周囲に広がり始めたその時だった。
黒点は寄り集まりあいながら、銀の濃霧の中で地響きを響かせた。
立ち込めた銀紛が粉雪の様に降り注いでいくのが見えた。
粉雪が舞い降り、銀世界が晴れ渡ってゆけば、銀色のヴェールによって包まれていた山野に再びGLMストークの大軍団が大挙して姿を現すのだった。
アンドレイらの部隊と、友軍の猟兵によって敵は出鼻をくじかれ、大きく勢いを削られたであろうことは明らかだった。
だが、それでも敵は圧倒的な兵力を有する。
ゆえに先手を制したといえども、未だに情勢は予断を許さない。
おそらく敵は物量に頼って、多大な損害を出しつつもこのままアンドレイの陣地へと毒牙を突き立て、その余勢をかって後方の山村をいずれは飲み込んでいくだろう。
――とはいえ、そんなデウスエクス側の蛮行を許すつもりはエクレアにはさらさら無かったが…。
エクレアは、ふぅと大きく吐息をつく。
そうして準備運動を終えると、大きく身を沈め足場の大岩を勢いよく蹴りぬいた。
瞬間、エクレアのしなやかな体躯がふわりと宙に浮かび上がった。大岩を蹴り上げた脚力を活かしつつ、身に宿った移動のルーンの力を顕現させれば、エクレアの体は矢のような鋭い稲妻となり、雷光の速さでもって空を駆け抜けていく。
一陣の金色の雷光が、空を駆け抜けていく。
雷光は、小さな大岩の上からアンドレイらが布陣する丘の頂上へと一息の間に肉薄すると、山頂へと向かい鋭い軌道で舞い降りた。
落雷と共に丘上の大地がえぐられ、砂塵が濛々と黄色の敷物でもって周囲を閉ざす。
エクレアの両の靴先が丘上の大地を踏みしめる。
周囲に立ち込めた砂埃を手で払いながら、エクレアは軽やかに歩を進めると、巨大な狙撃銃を構えるアンドレイの傍らに進み出るのだった。
音もなく姿を現したエクレアを前に、冷静沈着を絵にかいたようなアンドレイの切れ長の瞳が、仰天した様に丸く見開かれた。
生来の寡黙さゆえか、それとも驚愕ゆえに言葉を失っているのかは判然としなかったが、黙りこくったままでいるアンドレイを横目にしながら、エクレアは一歩、二歩と歩を刻み、アンドレイに隣立つと、遥か遠景に霞んで見える敵の一団へと向かい掌を伸ばした。
丘の上から敵の大軍を臨めども、いまだ、敵は山野にて黒い波となって広がるばかりで、その姿形は曖昧模糊としたものであった。彼我の距離は隔たれており、会敵までしばしの猶予が残されていることが目算される。
とはいえ、時間的な余裕は数分程度が精々だろう。それまでに一万をわずかに下回った敵を無力化することができなければ、アンドレイらが布陣した小丘は黒い波に苛まれ、すべては無へと帰するだろう。
未だにエクレアたちは苦境に立たされている。
…だが、そんなエクレアの口元をついたのは、余裕の笑みだった。
――ふむ、準備運動には屈託しないじゃろうな。
迫りくる無数の敵を前にして、エクレアは内心で独り言つ。同時に、ぽつりとつぶやく。
「まさしく『敵は強大、味方はわずか』といった状況じゃな」
言い放つや、エクレアはアンドレイへと視線を向ける。生真面目そのもの鳶色の瞳が、じっとエクレアの事を凝視していた。
エクレアは、気持ちよさげに鼻息を零しながら、アンドレイに豪語する。
「しかして、巨悪を前にしても決して怯まず、そして希望の光を失わずに第二の故郷を守らんとしたおぬしらの気概や心意気は、誠に見事じゃ」
エクレアは一度言葉を切ると、まずはアンドレイに、次いで彼の指揮下の計百人にも及ぶ中隊の面々一人一人へと順繰りにまなざしを送る。
そこには老若男女、さらには種族を問わずに多種多様な兵士の姿があった。そしてこの場に介したその誰一人からも、諦観の念は微塵も感じ取れなかった。
彼らが面差しからは高潔な命の輝きが煌めいてみえた。苦難の中にありながらも、誰もが生き残り、山村を守る決意に燃えていたのだ。
ならばこそ、エクレアは彼らとの共闘を決めたのだ。
この場に集ったもの達の命が奪われるようなことをエクレアは決して許さぬ。
「おぬしのような者達の命をあのような無機的な輩にくれてやるのは我慢ならぬ。ゆえに、このエクレア・エクレール…。――微力ながら貴殿らに力を貸そうぞ」
豪放と言い放つや、エクレアは前方へと鋭い視線を戻した。
エクレアは、アンドレイ中隊の面々をしり目にしながら、再び迫りくる敵の大軍を鋭い視線でもって睨み据える。
数多の黒点は、新緑に湧く大地を暗澹たる黒色に塗りつぶしながら、濁流となって押し寄せてくる。
面白い――とエクレアはわずかに跳躍しながら体をゆする。両の手を合わせて鼻歌交じりにぽきぽきと指を鳴らす。
自然、笑みがますます深まった。
「まずはわしが、奴らに挨拶まじりに軽く歓待してこようぞ? 見たところ、おぬしらの大部分は機械の身と見受ける。わしの歓迎はやや大仰ゆえな? わしの電にあてられぬよう、主らはここより砲撃に徹しておくれ?」
言いながら、エクレアは前傾姿勢に身を屈める。
瞬間、これより訪れる稲妻に気づいてか、大気が緊迫した様に、ぴりぴりと震えだした。
「では、行って参るぞ?」
背中越しにアンドレイ中隊の面々に告げる。
同時にエクレアは移動のルーンを展開、力強く丘の上を踏み抜いた。
砂の足場を蹴り上げた瞬間、空へと舞い上がったエクレアは一陣の雷光と化した。雷光は激しい金色の光を迸らせながら、猛烈な勢いで一直線に空を流れてゆき、瞬く間に迫りくるGLMストークの大群の上空まで迫る。
エクレアの眼下にはひしめき合いながら地を這う、デウスエクスの大群の姿が伺われた。
小さな箱型の胴部より、不釣り合いな程に巨大な鉄の両脚を伸ばした機械の怪異が、眼下に広がる緑の大地の上で不気味な虫の様に蠢いている。
エクレアは機械仕掛けの怪異の上空で静止すると、滞空したままに手にした雷槍を振り上げた。
そうして、意識を自らの内奥へと没入させていけば、槍の穂先に黄金色の熾火がぽつりと灯った。槍先が金の瞳で茜空を睨み据えれば、晴天の空のもと、どこからともなく暗雲が立ち込めてゆく。
黒雲が瞬く間に膨れ上がったかと思えば、空一面に低く垂れ、差し込む斜光を完全に遮り、地上を濃い影の中に沈めてゆく。
エクレアは振り上げた雷槍でもって上空に輪を描く。
鋭い穂先が一周、二周と上空で弧を描くたびに、雷雲のもとより、稲光が瞬いた。
槍先を優雅に振り回すたびに、一条、二条と金色の雷光が空に走った。槍が旋回を続けるたびに、雷光はますますに勢力を強めていく。
周囲では数多の雷鳴がけたたましい獣の雄たけびを上げていた。
黒く淀んだ大気を横殴りに走り抜けていく、幾条もの稲光が、金色の輝きでもって山野を荒々しく照らし出していた。
ぴたりとエクレアは槍の穂先を制止させた。眼下にあふれる敵の一団を見据えながら、エクレアは勢いよく槍を振り下ろす。
槍の穂先が緩やかな軌道を描きながら、地上へと向かい不可視の鉄槌を落とす。槍先が鋭利な切っ先でもって地上を貫けば、瞬間、大気は激しく振動し、雲間より滝の様な雷の暴流が地上へと降り注いでゆく。
エクレアの身に宿した雷のルーンはいまここに真の力を開放したのである。解き放たれた力の奔流は、今や無数の雷撃となって、地上をわが物顔で蹂躙する無数の歪な機械の昆虫を光の刃でもって容赦なく切り結んでいく。
金色の刃が数多、揺らめいていた。
鋭い刃の切っ先が、天上より降り注ぎ、地の上をすべるようにして駆け抜けてゆけば、群がる鋼鉄の昆虫たちは、吹き荒れる雷撃の中で容赦なくその身を攪拌されていく。
耳をつんざくような雷鳴が鳴り響き、金色の光が周囲に迸る。
金色の光は鋭い牙をむき出しにしながら、空を縦横無尽に駆け回り、鋼鉄の怪異を鋭い矛先でずたずたにかみ砕いていく。
雷光の刃が振るわれるたびに、次々にGLMストークは、切り裂かれ、無残な鉄の残骸へと化していく。
「では終いとゆこうぞ…!」
次々に数を減らしていくGLMストークの大群を眼下に収めながら、エクレアは無慈悲にそう告げた。
エクレアは優雅に槍先を振り上げると、不可視の足場を器用に踏み鳴らしながら、中空に滞空したままにぐるりと体勢を反転させる。
エクレアの体躯が重力に抗したままにぴたりと中空で静止した。
蜂蜜色の質感のある前髪だけが、重力に抗うこと叶わず、地上へと向かい垂れる。
エクレアは、両膝を大きく屈曲させ、両の足に力を籠める。
両足をバネの様に収縮させて、足元を支える不可視の足場を力強く踏みしめた。全身をバネの様にしならせんがら、しばしエクレアは力を蓄える。
徐々に高まっていく両の脚を力があふれかえっていく。力の解放を求めるように、大腿筋群が悲鳴をあげているのがわかる。
しかし、耐える。ぎりぎりまで荷重に耐えながら、まさに力が極点に至るまでエクレアは両の脚に力を込めたのだった。
そしてついに解放の時が到来する。
エクレアは、移動のルーンを活性化させるとともに、両膝を一挙に伸展させて勢いよく不可視の足場を蹴りぬいた。
瞬間、エクレアの両の足は不可視の足場を離れ、雷光の速さでもって空を滑空する。
結果、文字通り稲妻となったエクレアの全身は、瞬く間に地上を掠め、黒い繭の様に蠢くGLMストークの軍団へと強襲するのだった。
上空を一息の間に急降下するや、エクレアは地上すれすれで体勢を変え、地表の眼と鼻の先を猛烈な勢いで駆け抜けていく。
今やエクレアはGLMの群れの中にある。
四囲には不気味に蠢く機械仕掛けの昆虫がひしめいていた。
エクレアは豪快に嗤う。
もはや、乱雑に槍を振り回そうと手にした雷槍が空を切ることはありはしないだろう。
エクレアは、低空すれすれを飛翔しながら、群がる敵兵の間を縫うような進む。
進路を塞ぐようにして敵が現れれば、槍を横薙ぎし敵を薙ぎ払い、すれ違う敵があれば、おまけとばかりに槍撃を繰り出し横腹をつく。
エクレアが空を滑走するたびに、目の前にはGLMストークの武骨な巨体が次から次へと現れては消えていった。
勢いよく雷槍を横なぎするたびに、鋭い一閃がGLMストークの胴部を撫で切りする。槍先が、分厚い鋼鉄の胸壁の上をするりと撫でれば、胸部装甲には深々とした裂傷が浮かび上がり、創部は見る間にGLMストークの胸部全体へと広がってゆきながら輪切りに分厚い装甲を一刀両断にするのだった。
エクレアが雷槍を振るうたびに、鋭い白刃が無限の軌道を描きながらGLMストークの巨体を切り伏せていった。一体、一体とGLMストークの巨体がぐらりと大きく動揺し、力なく大地へと横転するのが見えた。
周囲では未だ無数の雷光が瞬き、GLMストークを次から次にと光の渦で飲み込んでいった。
もちろん、敵軍に対する攻勢はエクレアによるもののみに終始しない。
エクレアの後方からは、アンドレイらによるスナイパー部隊によるレーザー砲の照射が断続的に飛び交い、群がる機械の怪異を正確無比に撃ち抜いていく。
今や戦場は飛び交う光弾により、鮮烈に照らし出されていた。
炯々と煌めく戦場をただただエクレアは雷光の眩さで駆け抜けていったのだ。群がる無数の敵を雷槍でなぎ倒しながらエクレアは敵陣を撃ち抜くことのみに意識を傾注させたのだ。
金色の雷は、黒い波濤の中央をひた走り、分厚い黒い波を一直線に貫いてゆく。金色の光弾と化したエクレアは、微塵も勢いを落とすことなく、敵の重厚な縦深陣を鋭い錐の一撃で穿ちぬいたのである。
空に低く垂れた黒雲が霧散し、茜空が天上に再び顔をのぞかせる。
雷鳴は遠のき、黄昏空の空には妙な静寂だけが木霊していた。
斜陽が再び山野を郷愁の光で照らし出せば、風の凪いだ草原には数多の敵兵の残骸が姿が陽炎の中で揺らめいた。
未だ、鋼鉄の軍靴は無慈悲に静まり返った草原に、異質な夾雑音となって鳴り響いていた。
それでもなお、ここにGLMストークの大軍は大幅にその勢いを減退されるに至ったのである。ここに戦いの帰趨は大きく猟兵側へと大きく傾いた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 月隠・新月
月隠・新月
◎
連携〇
決戦配備:Sn
皆さんは元はデウスエクスですか。特別どうというわけでもありませんが……まあ、奇特なひとだとは思います。
この敵の数……戦力過多にも思えますが、それだけレヴィアタン復活に重きを置いているということでしょうか。
俺ひとりで走り回るよりは、ここの防衛隊員と共に戦った方がよさそうですね(【集団戦術】)。皆さんがより戦いやすくなるよう、【魔獣領域】で強化しましょう。敵の技についても伝えましょうか。足を止めた敵は早く倒すように、とも。
俺は敵を撹乱するために奇襲をかけますので(【遊撃】)、その隙に敵を撃ち抜いてもらえればと思います。
敵の進軍速度を落とせるよう立ち回りましょう(【拠点防衛】)
 トーノ・ヴィラーサミ
トーノ・ヴィラーサミ
◎
連携〇
決戦配備:Cr
大切なものをその身をかけても守りたい、ですか
しかしその為には貴方たち自身もまた、守らねば残されたものの心に傷を残すこととなってしまいますよ
同じような過ちを犯し友に叱られた者の戯言ですがね
猫ならぬケルベロスの手、お貸ししますよ
アンドレイさん達への被害を減らす意も兼ね、【生命力吸収】【火炎耐性】も併用しつつ発動したパラドクスと共に前線で派手に暴れるとしましょうか
敵の同士討ちを【見切り】などを活かして狙いつつ味方(特にアンドレイ達)を巻き込まぬよう位置取りに注意
多少の負傷は【覚悟】のうえ
むしろcaidaの切れ味が増すというもの
もっとも、1人で無茶をするつもりはありませんがね
●
数多の稲妻が、暗雲の深く垂れ込めた曇天の中でて稲光を迸らせていた。
金色の光が裂くようにして空を駆け下りていけば、槍の様に鋭い雷の尾が、鋭い金色の穂先でもって大地を串刺しにしていく。
おびただしい数の雷光が、空で奔騰するたびに空気はつんざくような悲鳴をあげて、激しく震えだす。
絶え間なく鳴り響く天寄りの鳴き声は、勇壮たる雷鳴の残響音が生み出したものか、はたまた雷撃に穿たれ、地上の黒ずみとなっていく、歪なる機械のイナゴの断末魔とも言うべきどよめきの反映だったのか。
詳しいところは分からなかった。
だが、空に立ち込めていた暗雲が霧散し、ついで上空に赤い絵の具で塗りたくったような鮮やかな暮色の空が顔をのぞかせた時、それまで暗雲のもとを縦横無尽に暴れまわっていた雷光はわずかな残光さえも残さずに跡形もなく姿を消し、赤々と染まる空は、森閑と佇むばかりであった。
月隠・新月(獣の盟約・f41111)が丘陵地帯の頂上より眼下を俯瞰すれば、大地には暴虐たる雷光の爪痕が深く刻まれているのがわかった。
草木は薙ぎ払われ、むき出しになった地表には、幾条もの亀裂が生々しい裂創となって走っていた。
雷撃の刃は、地上のありとあらゆるものを一切の区別なく薙ぎ払ったのだ。
それは、群がるデウスエクスとて例外ではなかった。
倒木などに混ざり、平原の至る所に黒い小山が築かれていた。
新月が黒山の一つ一つを凝視すれば、そこには雷によって焼灼されたデウスエクスの残骸が微動だにすることなく、数多、打ち捨てられていることに気づく。
山野には友軍の猟兵の雷撃によってなぎ倒された数多のデウスエクスの残骸がひしめいていたのだ。
当初、敵デウスエクス、GLMストークの大軍により山野は黒一色に塗りたくられていた。
山野の緑は、数多の集簇する黒点の中に隠され、連なる無数の不気味な影は、地平線の彼方までを埋め尽くすように山野へと広がっていた。
しかし、友軍の攻勢によって状況は一変し、山野に敷き詰められた黒色の覆いはわずかにだが取り除かれつつあった。
未だ敵軍は、重厚な隊列敷きながら行軍を続けていたものの、分厚い戦列の至る所には間隙が生まれ、部隊によっては、相互支援できぬほどに隊列を崩されていた。
遠目には未だ敵は健在に見えただろう。
しかし明晰さを湛えた新月の銀白色の双眸は、敵陣の綻びを鋭く見抜き、飽かず敵の急所を模索し続けていたのだった。
敵デウスエクスは、未だに十分な数を残存させていた。
だが、つぎはぎが目立つ陣容から鑑みるに、兵数に反して、軍団単位としての戦闘力は大きく減退しているだろうことは一目瞭然だ。
新月の明敏さを湛えた銀白の瞳が静かに細められた。
新月は視覚情報より得た敵軍の配置と自らの獣の嗅覚が捉えた第六感とを脳裏で処理しながら、思考を深めていく。
機械仕掛けのイナゴの大群が黒い靄の様に四方ひ手を伸ばしながら、再び動き出すのが見えた。
箱形の胴部から伸びた、体幹部とは不釣り合いに巨大な鉄の両足が大地を踏み鳴らすたびに、地響きが無機質に大気を揺らした。
機械仕掛けのイナゴの大群は友軍の遺骸など歯牙にもかけない様子で、山積する鉄の残骸を巨大な鋼鉄の軍靴でもって踏み潰しながら、山野へと再びあふれ出してゆく。
たった一つの山村を攻略するには、戦力過多との誹りを受けかねほどの大量の軍団でもって、敵は今まさに、新月らが布陣する丘陵地帯を後輩の山村へと押し迫っている。
敵が大軍を擁する理由は単純明快を極める。
山村付近には、数十年前の戦いで封印されたという機械神『レヴィアタン』が封じられているという。
かの機械神を封じるために、人類側は代償として多くの流血を支払わざるを得なかったという情報を新月は事前に聞き及んでいる。英国戦線において、DIVIDE側は破竹の快進撃を続けている。必然、英国戦線におけるデウスエクス図は日ごとに委縮していった。
こと、英国においては、デウスエクスは完全に劣勢に立たされているといえるだろう。
故に彼らは、機械の神の名を冠するデウスエクスの復活により、戦略的劣勢の挽回を図ったのだろう。
機械神『レヴィアタン』の復活を金科玉条にて彼らは大兵力、鄙びた山村へと投入したのだ。そして、皮肉なことに英国軍における政治的軋轢がデウスエクスらの進行を手助けすることとなったのだ。
戦略的な敵軍の意図はなるほど凡そ、新月には掌握できた。
となれば、この一戦場においていかにして立ち回るか。その最適解が今、新月には求められる。
新月は、ぐるりと戦場を一望すると、再び黒い波濤となって押し寄せる敵の大軍を具に観察するのだった。
敵陣の生じた綻びから、敵部隊が疎となる地点を見極める。敵部隊の各々の動きを一瞥し、統率性や損害率を概算し、同時に自らの牙を振り下ろすべき敵の所在を冷静に見定めるのだった。
新月は敵の分厚い横陣の一点で視線を固定させる。そこに新月は敵のアキレス腱を見たのだ。
今、DIVIDE直轄英国第三軍は山村の救援へと向かいつつあるという。つまりは、第三軍の到着時まで敵を拘束し、均衡状態を維持することさえできれば、敵は兵力の優位性を失い、趨勢は一挙に覆るというわけだ。
敵部隊を全滅させられるに越したことは無いだろうが、最良を追求したがために限界を超えて戦い、山村防衛に失敗し、ついぞ封印されたデウスエクスを解き放ったのでは本末転倒もいいところだ。
つまり、新月にとっての戦術的な模範解答とは、敵の軍団を混乱させ、その足を止める事であった。
そして、今、敵部隊の中央陣は守りも薄く、ここの最奥に布陣するだろう敵の中枢にさらなる打撃を与えることができれば、敵軍は完全に左右に分断され動きの精彩を失うだろうことが予想された。
上体を倒し、前脚で力強く大地を踏みしめた。敵陣の一点を睨みすえながら、新月は今まさに突撃の体勢を整えるのだった。
まさに大地を蹴り上げんとした、その瞬間だった。ふと新月の後方で軽やかな足音が響く。
「少々お待ちください、新月さん――」
眼下を臨む新月の背を、よく聞きなれた重低音が揺さぶった。
新月が視線を後方へとやれば、屈強な体躯をそびやかしながら、一頭の黒い獣が軽やかに歩を進めてるのが見えた。
胴部から左前脚へ向かって伸びた青白い焔が揺らめくたびに、しなやかな体躯が風雅に揺れた。
青白い焔と差し込む夕映えの二色の微光が、凪いだ湖水の様に落ち着き払った藍色の瞳を優艶と照らし出していた。
ともに戦場を駆け抜けてきた戦友の姿がそこにあったのだ。
そう、黒い獣こと、トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)は、黄昏時の空を背景に、新月の前にその姿を悠然と現前させたのであった。
彼は新月に隣へと躍り出ると、ぴたりと足を止めた。
トーノの理知を湛えた藍色の瞳が覗き込むようにして新月へと穏やかな視線を送っていた。
新月はトーノに対して軽く会釈し、口火を切る。新月の凛然とした声音が、銀色の鈴の旋律でもって、りぃんと周囲に響いた。
「再びの共闘ですね、トーノさん…。ここより敵軍の動静をうかがっていたのです――。機先を制するために今より奇襲をと」
新月が応えれば、並び立つトーノがうなづく。藍色の瞳が、眼下へと静かに視線を落とした。
「なるほど…。おおよそ、敵は八千弱といったところでしょうか――。友軍の攻撃によって出鼻をくじかれ、大きく戦力を削られたとは言え、未だに脅威たりうる大軍勢ですね。それにしても小さな山村を襲撃するためだけにこれほどの大兵力を用いるとは――。レヴィアタンなる機械神の復活に対する敵方の執心ぶりは尋常ではないようですね…。」
眼下をうかがいながらも、落ち着き払った様子でトーノがぽつりと呟いた。
新月は、トーノに相槌を打つと、直ちに返答する。
「そのようですね。とはいえ、レヴィアタン復活に妄執するがゆえにというのでしょうか…。相手方の戦術は硬直化し、結果、こちらの初手により手痛い反撃を受けた様です。トーノさん、あちらを」
言いながら、新月は柔和な曲線を描く顎先を持ち上げる。そうして、顎先でもって、群がる機械仕掛けのイナゴ、GLMストークの大群の一角を指し示すのだった。
トーノの理知を湛えた碧眼がそっと細められるのが見えた。
しばし、トーノは黙りこくったままに新月の指定した地点を眺めていたが、すぐに新月の意図に合点がいったようで、彼は幾何かすると、感心したように瞳を瞠目させ、納得顔で新月へと目合図した。
さすがはトーノさんだと思う。まったくもって理解が早くて助かる――。
トーノを横目にしながら、新月は再び続ける。
「トーノさん、これより、あの地点に奇襲を仕掛けます。あの綻びをつけば敵軍の行軍は鈍るでしょうからね」
新月が応えれば、打てば響くようにトーノが首肯して答える。
「ならば、私もご一緒させていただきましょうか――。数は大いに越したことがないでしょうからね…。一人より、二人です。そして、叶うならば数は多ければ多いほどよいはずです」
愉快気にトーノが鼻を鳴らすのが見えた。
彼の端正な口元は、柔和に綻び、口端から零れた鋭い犬歯が白く輝いて見えた。
トーノは新月に微笑みかけると、一旦、言葉を切って、後方へとくるりと踵を返した。
つられて、新月が肩越しに後方へと視線を遣れば、淡い夕陽の反映の中、丘状に居並ぶ多数の兵士たちの姿が視界に映し出された。
青紫色の鱗でもって皮膚を構成する巨漢や、鋭角を描く獣耳が側頭部から突き出した女、銀色の光沢を肌ににじませた半機械の男など、多種族よりなる混成軍の姿がそこにあった。
彼らは武器を手に手に、憧憬と熱望の眼差しでもって新月らをじっと見据えていた。
山村を守ると決めた勇士たちがそこに居並んでいたのだ。
そんな勇士らの中、自然、新月の視線は、先頭に立つ一人の男へと向けられた。
郷愁を湛えた鳶色の瞳が静かに新月を捉えていた。
男は両の手で、彼の身の丈程ある筒状の巨大な大槍を携えていた。大槍の先端から除かれた鋭い砲口は茜空を睨み、尖塔かなにかの様に聳え立ってみえた。
西日が男の紅鳶の短髪を鮮やかに照らし出していた。
感情の起伏をまるで感じさせない氷の様な無表情が男の端正な面差しに張り付いて見える。
男は確か、名をアンドレイといっただろうか。デウスエクスよりの亡命者であり、彼が率先して山村を守ることを決意したとの趣旨を、新月はグリモア猟兵の投影した映像よりすでに暁通していた。
アンドレイを筆頭にこの場に介した防衛部隊の面々はデウスエクス側より、地球人側へと鞍替えした者たちというわけだ。
彼らの心境がいかなるものであったかは、新月には窺い知れない。
何か特別な感慨を抱いたわけではないが、わざわざ、種の壁を越えて人類に協力し、命を負け戦にまで従事するとは奇特な者たちだとは思う。
しかし、トーノの言った通り、戦力は大いに越したことは無い。彼らのたたずまいや、些細な挙止からは、なるほど彼らが寡兵でもって大軍を迎え撃つことを、決意したのがただの無謀でないことを窺わせるほどの力量が伺われた。彼らは間違いなく、手練れであろう。
この奇特な亡命者たちを戦力として見た時、彼らの価値は万金に値するだろう。
防衛部隊の面々をしばしの間、新月は静かに眺めていた。
不思議と嫌な気分はしなかった。
果たしてそれは、郷愁の陽光の鮮やかさに新月が不覚にも感じ入ったからか。それとも元来、感傷などというものには無縁な新月にたまゆら生じた、たんなる気まぐれ故であったのだろうか。
いや、単に呼気と共にわずかに収斂した表情筋が作り出した幻影であったのだろうか。
理由は曖昧模糊としてわからなかった。
だが、なぜだろうか。
命を賭して人々を守らんとする防衛部隊の面々を目にしたとき、新月の横一文字に噤まれた口端はゆるやかな三日月を描きながら小さく綻んでいたのだった。
それは新月自身にも認識できないほどのわずかな表情の変化にしか過ぎなかった。
だけれども、新月はむず痒い感覚と共に確かに微笑したのである。
ふと新月は、全身を駆け巡る血液が激しく沸騰していくような錯覚を覚えた。膨大な力の奔流が、今、新月の中で膨れ上がり、激しい洪水となってあふれ出さんとしていたのだ。
全身に奇跡の力の高まりを感じる。
奇跡の力が、堤を決壊させんと見る間に水位を増してゆくのがわかる。
新月は静かな眼差しで、居並ぶ面々を見やりながらも、溢れかえる奇跡の力に一定の法則を与えるべく脳裏で演算を開始する。
それだけではただの魔力の暴流にしかすぎない奇跡の力に一定の形を新月は与えてゆく。
魔力の暴流は臓腑を駆け巡り、四肢を循環していくたびに、秩序を得て一つの形へと昇華していくのだった。
魔力の残滓は、血脈を流れそして肺臓へ、そうして、ついぞ肺臓より上方へと駆けのぼり、喉元に集積する。
ふと咽頭部に甘美な発赤が感じられた。
ユーベルコードの術式を構築する傍らで、新月は居並ぶ一同へとぽそりと言い放った。
「…これより、俺は敵陣をかく乱します。敵の混乱に乗じて、皆さんは射撃をお願いします――。それから、敵が足を止めた場合は要注意です。おそらく、敵は雨あられと銃撃を放つでしょう。優先して破壊をお願いします」
言葉短く伝えると、新月は居並ぶ防衛部隊の面に背を向け、再び前方の山野を見下ろした。
新月は、後ろ脚をわずかに屈曲させると、しなやかな両の前脚で大地を力強く踏みしめた。
流麗な曲線を描くが新月の体躯が弓なりに伸展し、新月の鋭い牙が赤く染まる大空へと突き立てられた。高騰した魔力は極限へと至り、新月の中、確固とした形を取りながら、今や今かと放出の時を待っているかの様だった。
両足で大地を踏みしめながら、新月は、小さく息をついた。
糸くずのような吐息が一筋、舞い上がり、茜空へと霧散していった。吐息が消え去るや、銀糸を曳くような、獣の咆哮が轟いた。
りぃん
りぃん
りぃん
銀色の鈴の音色でもって世界が優しく揺さぶった。
りぃん、りぃん
と銀色の鈴の音色は、風に乗りながら周囲へと充溢してゆく。
ユーベルコード『魔術領域』は獣の柔らかな銀糸の調と共に、放射状に山野を走り抜けてゆくのだった。
そは、魔力の奔流たる音の波である。
不可視の魔力の濁流は、歪なイナゴの大群―-GLMストークの大群打ち寄せると、直ちに砕け散った。
砕け散った魔力の泡沫は、その一滴、一滴がいわば矢であり弾丸であった。
突如、山野で前進を続けていたGLMストークの軍団がぴたりと足を止めるのが見えた。GLMストークの箱形の胴部になにかがぶつかったかと思えば、装甲が歪にひしゃげ、次いで爆炎が巻き起こった。放たれた不可視の魔力の泡沫は、一滴、一滴が鋭い魔弾となってGLMストークを撃ち抜いたのだ。
赤い炎柱が至る所で激しく揺らめいていた。
焔の揺らめきの中、巨大な機械仕掛けのイナゴは、打ち寄せる数多の散弾によって装甲を穿たれ、力なく地面に崩れ落ちてゆく。
戦場は、新月の放った魔力の泡沫によりその性質を一変させたのである。
デウスエクスらは、驟雨となって降り注ぐ不可視の弾丸により容赦なく全身の撃ち抜かれながら、数を減らしていく。半面で、不可視の魔力の泡沫は、新月に味方するものを優しく包み、潜在能力を限界まで底上げする。
この不条理な原則を逃れうるものはこの戦場には存在はしえなかったのだ。
「それでは…皆さん、俺は行きます――。援護をお願いしますね」
兵士らに肩越しに言い放つと、新月は身を屈める。隣立つトーノが新月に目合図するのが見えた。
「それでは、同行させていただきますね、新月さん。レディを一人で行かせたとあっては、私の面目も立ちませんからね」
トーノのふっくらとした漆黒の尾が風雅に揺れていた。
れでぃ…なる言葉に一瞬、新月は目を丸くする。
そんな新月を横目にトーノがくすりと、微笑むのが見えた。大人びた優雅な微笑が、端正なヴィーノの面差しに輝いていた。
「新月さん…では、お先に失礼しますね」
軽やかな声音に続き、トーノの前脚が勢いよく大地を蹴った。トーノの巨躯が茜空に浮かび上がり、一条の鋭い漆黒の矢となり茜空を貫いていったのは間もなくのことだった。
トーノにわずか遅れながらも、新月もまた大地を蹴りぬいた。
先行する揶揄い好きな紳士の背を追いながら、新月もまた一陣の旋風となって空をかき分けてゆく。
空をゆく新月の脳裏では、トーノの口をついた、れでぃなる、耳になじみのない言葉が未だ反響して響いていた。
トーノの諧謔か、それとも出自も良いだろうトーノならではの社交辞令を兼ねた鄭重な物言いなのか新月にはわからなかった。
山野を蚕食せんと打ち寄せた無数の黒点は、魔術領域によって降りしぶく不可視の豪雨と互いに押し引きを続けながらも、ついぞ、豪雨の圧力に負けてぴたりと動きを止めた。
そして空を駆ける新月の口端は未だ、わずかにだが綻んだままだった。
戦いの高揚感に酩酊したのでもなければ、ヴィーノの言葉に年頃の少女が感じるような恥じらいを覚えたわけでも無かった。
だが――。
ヴィーノの紳士ならではの軽妙な挨拶も、アンドレイ率いる防衛部隊の面々の殉教者を彷彿とさせる謹直とした面差しに映りだした崇高なる意思の光も、そのどちらも、新月の内奥を春風の様な柔らかな指先でくすぐっていたのもまた事実だった。
この得も言われぬ感覚を胸中に抱きながら、新月は鋭い漆黒の矢となり一直線に空を貫いていく。
今、二筋の黒い旋風が、鋭い軌道を描きながら、山野に黒染みとなって広がるGLMストークの群れの中へと突き刺さる。今、大きく戦いの潮目が変わる。
●
月隠・新月(獣の盟約・f41111)とトーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)の両雄による攻勢の刃が振り上げられるに遡ること十数分ほど前、トーノはアンドレイらが布陣する陣幕へと、攻勢に先立って訪れていた。
味方猟兵により生み出された雷鳴は今や遠のき、山野では雷撃を無事にかいくぐった機械仕掛けのイナゴの大群――GLMストークの大軍団が武骨な鉄の軍靴を響かせながら、無作法に大地を踏みにじってくる。
ひたひたと潮が満ちていく様に、不気味な海嘯を響かせながら、機械仕掛けのイナゴの大群が山野を再び蚕食してゆく姿がトーノには伺われた。
丘の一隅に視線を遣れば、良く見知った戦友の姿が見て取れた。
艶の黒いたてがみを風にたなびかせながら、眼下を鋭く睨み据える、流麗たる一頭の獣の姿がそこにはあったのだ。
茜空に優美たる黒が映えてた。
白銀の瞳は暮日の赤を反映し、宝石かなにかの様に輝いて見えた。
月隠・新月は夕空に浮かび上がるおぼろげなる月の優美さでもってそこに立ち、息をひそめながらも、そのしなやかな体躯に蓄えた力を開放せん瞬間を窺っているようだった。
新月は今、最善の一手を模索すべく敵陣を俯瞰し、奇襲を仕掛けべるべく体勢を整えている。
元来ならば、トーノはすぐにでも新月のもとへと向かい、直ちに敵陣へと強襲を仕掛けたかった。一度、依頼で共闘した折に、彼女の戦士としての類まれなる才幹をトーノは間近で肌感覚で垣間見たのである。
俊敏な身のこなしや鋭い牙や爪撃に加え、新月の卓越した判断力は他の追随を許さぬほどに洗練されたものだった。
トーノと新月が敵陣を強襲すれば、彼我の兵力差など、たちまちに意味を失ってゆくだろう。
自らの力を過信するわけではなかったが、十全の連携のもとに新月、トーノが実力を発揮しうることができれば、千にも及ぶ敵を屠ることも容易いだろうとトーノは見る。
だが、未だ、山野には数多のデウスエクスが蠢いていた。
千の被害とは、確かに敵軍にとっても決して小さな損害ではないだろうが、かといって致命傷になるほどのものでは無いことも事実だった。
かがり火を大火へと昇華させる必要がトーノにはあったのだ。
そして、大火を生み出すには、アンドレイらの協力は必要不可欠だとトーノは見る。
故にトーノは、戦況の分析に先じて、アンドレイらに共闘を打診することを優先させたのである。
そうして、実際にトーノはアンドレイらの陣幕を訪れた時、アンドレイなる男を目の当たりにしたトーノがかの男に感じたのは、奇妙なまでの既視感だった。
アンドレイを目前にした時、まるで鏡を見るような、そんな錯覚がトーノの胸中を鋭い刃で突き刺したのだ。
たまらず、トーノは足を止めていた。言葉も失い、トーノはしばしアンドレイを忽然と眺めることしかできなかった。
レプリカントたる、かの青年指揮官は、トーノが陣地へと通されると目礼がちに会釈し、その後は理路整然とした挙止で部下たちに指令を下していった。
指示を飛ばすと同時に、青年は流れ作業で自らの狙撃銃を解体する。白樺を思わせる青年のがっしりとした白い指先が、流れるような挙止でもって槍の様な狙撃銃の上を滑り、青年の掌大ほどある弾倉を狙撃銃へと取り付けていく。瞬く間に、狙撃銃は解体され、再びくみ上げられていた。
がちゃり、と鉄と鉄とが嚙み合うような乾いた叩打音が響いた。
次いで、アンドレイ青年の鳶色の瞳が彼の手にした狙撃銃からトーノへと静かに向けられる。
鳶色の瞳は、悲哀の色を湛えながら静かに揺れていた。
そこにある青年の姿にトーノは、なぜか既視感を抱いていたのだ。
面立ちも、瞳の色も、髪の色といった外見的な特徴において、トーノとアンドレイとでは共通項を見つけるのが難しくさえあった。
かたや二足歩行で立つレプリカントの青年と、一方は四足で大地を踏みしめるオルトロスである。
にも拘わらず、アンドレイ青年の瞳に浮かび上がった意思の光は、トーノの脳裏に深く刻まれた、ありし日の自らのそれとぴったりと符合して見えたのだった。
かの青年の瞳はただ静かに死を直視してた。彼は銃後の無辜の民を守るために、彼は自らの命を燃やし尽くすことを決めたのだ。
鳶色の双眸は、確固たる意志の光を帯びながら、斜陽よりも尚も鮮やかな朱色に輝いて見えた。
雄弁たる瞳を前にした時、トーノの脳裏を掠めたのは甘美と苦衷で彩られた追憶の翳りであったのだ。
アンドレイなるレプリカントの青年の中に昔日の残光を垣間見た時、気づけばトーノは口を開いていた。
「大切なものを命をかけても守りたい――ですか」
口をついた言葉は、果たして誰に向けられて放たれたものか、一瞬、トーノには分からなかった。
目の前の青年は、表情一つ崩さず、言の葉の一言も漏らすことなく、黙りこくったままにトーノの言葉を傾聴していた。トーノは訥々と言葉を続けていく。
「――アンドレイさんと言いましたね。私はトーノと申します。これは…過去に無謀な過ちを犯し、そして友に叱責された者の戯言として聞き流してもらいたいのですが…」
トーノの言葉が暑気がはびこる大気にじぃんと広がってゆく。アンドレイの熱気交じりの瞳がわずかに細められた。アンドレイが小さく相槌をうつのが見えた。
トーノは再び口を開く。
「他者を守らんとするあなたの意思は汲み取っているつもりです。あなたはデウスエクスのくびきを離れて、人に味方した。あなたは人類への愛を知ったからだ…。私はそれを美しいと思います」
磊落とした声で伝える。
嘘偽りは無い。事実、彼は自己を犠牲にしてでも他者を救わんとした。献身の精神の輝きはいかなる宝石の輝きよりも眩く揺らめく。
嫌というほどにトーノが知悉していることだ。
だが――。
「しかしあなたが山村の人々を愛した様に、山村の人々もあなたを愛しているはずだ。となれば、貴方たちもまた生き残る必要があるのです。あなた達の命が露と消えれば…やはり人々の心に深い傷を残すことなってしまうのですから」
語気を強めてすべてを言い切った。
アンドレイはしばし黙ってトーノの言葉に聞き入っていた。
風貌体裁のまるで異なる二人の男は、夕映えの光の中で、鏡合わせの鏡像を見るように互いが互いを見つめあっていた。
遠方より奇怪な鉄音が丘上へと耳障りな異音となって響いていた。デウスエクスらの大軍は今まさに大挙して山野を駆けあがってくる。
この不快な夾雑音を遮るようにアンドレイが、ゆったりと口元を開くのが見えた。
「たとえ、彼らの心に傷を残すこととなっても、私は――。いや、俺は戦いたい。デウスエクスの裏切り者の名を受けてもなお、人のために生きる半機人としての生き方に俺は誇りを持っている…。死して、村民の心に傷を残そうとも、俺は人の心を持った人として、人のために死んでゆきたいんだ」
熱気交じりの声音が、トーノの鼓膜を揺らしていた。
過去と現在とが、トーノの中で奇妙に交錯し、混淆しているようだった。ふと微笑がトーノの口元をついた。眦を下ろしながら、トーノは答える。
「まったく強情な方ですね。ですが、ならばよろしいでしょう…、アンドレイさん。ならば、あなたは戦えばよい。しかし、貴方を殺させはしません。猫よりは、番犬の方が幾分もお役に立てましょう?猫ならぬケルベロスの手をあなたにお貸します――。ゆえに共に戦うのです」
この冷静さの仮面をかぶった快男児を見捨てるつもりはトーノには無かった。
同時に彼は強い。
戦力として敵軍に十二分に通用する。ならば、彼の命を救い、そのうえで彼の願いも叶えてみせよう。
トーノにならば不可能なことではない。
僥倖とも言うべきか、新月もまた、同じ戦場にある。
アンドレイと、新月…。
そして――。
トーノの目前で、アンドレイが力強く首肯するのが見えた。
言葉を発せずとも、以心伝心、アンドレイによる歓喜の肉声がトーノにも伝わっているかの様だった。
「共闘しましょう。全員で、生き残るために。敵への突貫は、私と、私の友人にお任せください。もちろん、私一人で無茶するつもりはありませんがね。アンドレイさんにも狙撃手として十二分に戦ってもらいます。これは突撃以上に難しい役割でしょうが、ご覚悟くださいね?」
わずかに語調を崩して微笑んで見せれば、アンドレイの口端がわずかに上方へと斜を描くのが見えた。
そうだ――。
ここには、アンドレイなる亡命ケルベロスの青年と、友人たる歴戦のツワモノ、月隠・新月。
―――そして。私がいる。
アンドレイとトーノの決意の眼差しが交錯しあう。朱色と藍色の混淆した時、トーノたちは無言ながらも生還を互いに誓い合ったのだ。
下方より突き上げてくる風が、トーノの体躯を空中で支えていた。
全身を揺さぶる心地よい浮遊感とともにトーノは一直線に空を駆け抜けていく。
前傾姿勢を取りながら前腕をしなやかに伸展させれば、心窩部から左前脚へと伸びた青白い焔が、刃の形を取りながら鋭い切っ先を眼下に群がるデウスエクスの大群へと向けた。
左方では、艶のある黒い毛並みに姿態を覆われたオルトロスの少女がトーノ同様に空を飛翔する姿が伺われた。
二頭のオルトロスは空を駆ける一陣の旋風と化していた。
二条の黒い旋風は、勢いよく空を切り裂いてゆきながら、敵陣の一角を目指す。
トーノらが敵陣へと近づくたびに、遠間にはただの黒い点の集簇にしか見えなかったGLMストークの大軍の全容が明瞭に浮かびあがる。
新月が指示した敵陣の綻びは既に目と鼻の先まで迫っていた。
飛翔しながらに、トーノは新月に目合図する。
トーノの藍色と新月の銀白色が一時、混ざり合う。トーノがわずかに身を屈めれば、体躯は下方へと傾き、落下軌道へと突入する。
両者は一言も言葉を交わすことなく、目配せだけで、互いの意思をやり取りした。
地表へと向かい、二頭の獣は、緩やかに高度を落としていく。
軽やかな浮遊感は頭上よりのしかかる重苦しい重力の掌にとってかわられ、ますますに地上が間近に迫る。
急降下を続けるトーノのもと、後方より、一筋、二筋と紫色の閃光が空を貫いたのは、トーノの前脚がまさに地表を踏みしめんとしたその瞬間だった。
閃光が空を青白く染め出しながら、トーノ、新月らの着陸地点付近で蠢く機械仕掛けのイナゴを飲み込み、淡青色の光で焼灼した。
青く燃えがる炎柱の中で、巨大な鉄のイナゴが白く萎んでゆき、次第に白色は黒色へと変わり、鉄の巨体は崩れ落ち、塵となって焔の消褪と共に大気の中へと霧散していく。
閃光が瞬くたびに歪な鉄のイナゴが青白い焔の中で焼灼されていく。
アンドレイら防衛部隊の放ったレーザーライフルによるものだろう。
新月の『魔獣領域』が生み出した微光は、未だ戦場を祝福の息吹で満たしているのだ。
現在、アンドレイらの放つレーザライフルの一撃、一撃は微光に威力を底上げされ、ユーベルコードにも勝るとも劣らぬ威力を有するに至ったのだ。
淡い幽玄の青色光が二人の着地点周辺の地上よりたなびいていた。地表よりうっすらと巻き起こる青白い光の帯は、まるでそれ自体がデウスエクスらを峻拒する力でも持っているかのようで、レーザライフルが過ぎ去った後、二人の着地点周辺からはデウスエクスの影すらも無かった。
自らの写し鏡たるアンドレイの援護に内心で謝辞しながら、トーノは前脚で大地を踏みしめる。
二歩三歩と草の蹈鞴を踏みながらも、トーノは無事に草の上へと舞い降りたのだ。左方では、新月が軽やかに大地を踏みしめるのが見えた。
互いに視線を交わす。
再び無言でうなづきあうと、トーノ、新月の両名は阿吽の呼吸で反対方向へと駆け出していく。
トーノは右方から、新月は左方から、二人は、目的地目指して機動を開始する。
ふわりと新月が再び宙を舞うのが見えた。
その軽やかな姿態が、曲芸師よろしく宙を舞い、鉄のイナゴの箱形の胴部の上に降り立った。
鋭い爪先が斜陽を浴びて赤黒く輝いていた。流れるような挙止でもって、新月が前爪を箱形の胴部へと振り下ろせば、爪先は吸い込まれるようにして胴部を貫き、ついで、胴部を貫かれたイナゴの腹部より爆風が巻き起こった。
即座に新月が、機械仕掛けのイナゴの上を飛び去るのが見えた。新月の姿態は、ゆるやかな放物線を描きながらしばし空を揺蕩うと、ついで、次なる機械仕掛けのイナゴの胴部へと再び、降り立つのであった。
そこからはまさに新月の独壇場であった。彼女は、GLMストークの胴部から胴部へと機敏に乗り移りながら、その腹部を鋭い前爪で分厚い装甲を刺し貫いていったのだ。
新月がイナゴの群れの上空を悠然と飛び越えるたびに、彼女の足元からは爆炎が上がり、炎の中で鋼鉄の巨体が紙細工かなにかのの様に崩れ落ちていった。
トーノもまた、新月同様に敵陣へと猛然と襲い掛かった。
トーノが這うように地面すれすれを疾駆すれば、鉄のイナゴは何ら反撃できぬままに、トーノへの下腹部の侵入をゆるす。
瞬く間に、トーノの頭上に無防備になった鉄のイナゴの下腹部が現れた。
さらにトーノは前方へと疾駆する。
駆け抜けざま、トーノが左前脚を振り上げれば、疾駆するトーノに続き、青い焔の揺らめきが地表から上空へと向かい逆袈裟に、むき出しになったイナゴの胴部を串刺しにする。
蒼焔がイナゴの下腹部を撫でるようにして滑りながら、内部へと深々と突き刺さる。青い焔で構成された刀身は、機械仕掛けのイナゴの胴部をそのまま抉るようにして突き進んでいくと、勢いそのまま装甲を貫通する。
トーノがイナゴの下腹部を抜け、前方へと走り抜けてゆけば、蒼焔もまたトーノ前進に呼応するようにイナゴの胴部の中を前方へと滑りぬけて、ついぞ、一刀両断に鉄のイナゴを切断するのだった。
イナゴの股下から躍り出るやトーノはさらに走る速度を上げる。トーノに続き、イナゴの腹部を両断した蒼焔が剣の切っ先を下方へと傾けた。
後方で轟音が鳴り響いた。正中部で左方に両断された鉄のイナゴが左右に転倒したのだ。転倒の衝撃ゆえにか、鉄のイナゴは誘爆を引き起こし、結果、トーノの後方では、イナゴの遺骸は原型をとどめぬほどに粉みじんに四散する。
炎が唸りを上げながら舞い上がり、舞い降りる火の粉か、熱い抱擁でもってトーノの背筋をじりじりと焼いていた。
もっとも背筋に走る熱感などはトーノの足を止める要因となりえるはずもない。
トーノは残火が燻ぶる戦場を足早に駆け抜けていく。
どうやら、新月やトーノの奇襲にようやく気付いてか鉄のイナゴの――GLMストークの大部隊が一斉に足を止めた。
トーノの前方にて三々五々で布陣するGLMストークらが、腹部に備え付けた機銃でもってトーノを睨み据えるのが見えた。
鉄の機銃が火を噴けば、激しい轟音と共に無数の銃弾がトーノ目掛けて放たれる。
弾丸は、黒い雨となって、疾駆するトーノのもとへと横殴りに降り注ぐ。
蒼焔を盾に敵の攻勢をやり過ごし、時に鋭い足さばきで銃弾を搔い潜る。
銃弾が、ひゅんひゅんと鋭い鞭の様な音でトーノの肌先を掠めていった。
さしものトーノもすべての弾丸を回避しきることは叶わなかった。時折、銃弾が分厚い漆黒の毛並みで覆われトーノの皮膚を掠め、うっすらとした淡紅色の裂創を刻んでいく。時に銃弾はトーノ皮下へと鋭い牙を突き立て、出血をトーノに強いた。
もっとも多少の負傷は覚悟の上だ。
赤黒い血の雫が、トーノの疾駆に合わせて、茜空に鮮紅色の花を咲かせた。
花弁が一つ、また一つと空に大輪を咲かせるたびに、トーノが口元に加えたcaidaはその鋭さを増していく。トーノがひた走りながら、口元に咥えた刃を横薙ぎすれば、白刃が煌めいた。
鋭い剣戟は寸分たがわずに、鉄のイナゴの心臓部とでも言うべき、箱形の腹部を、鋭い一閃でもって、切り伏せ、鉄の巨体を一刀のもとに両断していくのだった。
わずかな邂逅の後に、足元に鉄のイナゴの残骸が数多、積み重なっていく。
だが、この攻勢はまだ序の口にすぎない。
緒戦を戦い抜いたことで、ここにトーノのユーベルコードもまた、顕現するに至ったからだ。
『黒翼双演』とはトーノのみが使役することを可能とする、彼独自の軌跡の御業と言えるだろう。自らに2倍する漆黒の焔爪牙を持つ狼龍を召喚することを可能とするこの技は、トーノが繰り出した第二の牙であったのだ。
全身に燻ぶる熱い熱気を吐き出すように、奔騰する奇跡の力を解き放てば、狼とも龍とも見紛う巨大な獣が悠然たる偉容をトーノの傍らに顕現させるのだった。
ここに合計三頭の獣が戦場に姿を現したことになる。
三頭の獣は、黒い暴風となりながら、一直線に目的地へと向かい走り抜けていった。
並みいる鉄のイナゴの軍団は吹き荒れる暴風によって煽られ、なんら抵抗できぬままにうち伏せられていく。
トーノや新月らが前進するたびに分厚い石壁となって聳える鉄のイナゴのの群れががらりと崩れていく。黒一色で閉ざされた視界が、徐々に開かれてゆき、そうして終に完全に黒壁が取り払われた時、ついぞ、トーノらは敵陣の一角を完全に突き崩すに至るのだった。
新月が狙いを定めた敵陣の一角とは、長い横陣で守られた敵部隊の中央最奥部にあたる。
いわばそこは敵軍にとっての左右両翼の協調を支える蝶番の部分に相当する。
新月とトーノは、味方猟兵たちの初撃によって生じた綻びをつき、最短ルートでもって、見事に敵の急所への突撃を敢行してみせたのだ。
ここに奇襲攻撃は結実したのである。
今、トーノの前には司令官と思しき、機械仕掛けのイナゴを残し、敵らしき敵は無い。
つまり、目前の敵を屠ることさえできれば、敵の大群はもはや烏合の衆となりはてるも同然だ。
「新月さん――、いきますよ」
トーノ体を左右に揺らしながら、雷の様な軌道で疾駆する。
地上に投影されたトーノのが影がぬるりと伸び、口に咥えたcadiaが匕首を鉄の巨体へと突き付ける。
機銃は絶えず銃弾を吐き出していたが、トーノの影さえも捉える事能わずに遥か後方へと虚しく四散していくばかりだった。
トーノが大地を蹴りぬけば、体は鋭い矢となり空を走り抜けていく。
左方よりは新月が、敵指揮官機へとむかい強襲する姿が伺われた。
放たれた二振りの剣が振り下ろされる。再び黒い旋風と化した二頭の獣は、空を優雅に走り抜けながら、鉄のイナゴに肉薄すると、己が武器を振り下ろしたのだった。
cadiaの切っ先が鋭い弧を描きながら剣戟でイナゴの両の脚を砕き、新月の前爪が銀色の閃光でもって機械仕掛けのイナゴの胴部を貫いた。
剣を振りぬき、トーノは滑空の勢いそのまま草の大地へと降り立った。
数間ほど後方で、巨影が草の大地に沈みこむのが見えた。重苦しい地響きが大地を揺らしていた。
後方へと振り向けば、敵指揮官機は、草の大地へと埋没し、もはや微動だにすることなく静かに横たわるだけだった。
ここに敵中央部を支える指揮官機は、もの言わぬ躯と化したのだ。
中央後部の支柱を失ったことで、全軍が協調した作戦行動は間もなく不可能となるだろう。おそらく、各部隊に指揮官は存在しうるだろうが、彼らだけでは全軍を支えることは叶わぬのは火を見るよりも明らかだ。
そして各部隊の指揮官は別の友軍がすぐに処理してみせるだろう。
ふと、トーノが後方へと振り返れば、はるか遠景にて、連なる丘々が、茜空を綺麗に切り取っているのが見えた。
丘上より絶えず青紫色の光がこぼれ出している。青白い光の束が、丘上から山野へと降り注ぐたびに、鉄のイナゴの軍団らはなすすべもなく、青白い光の中へと飲み込まれていく。
イナゴの大群は明らかに動きを鈍らせつつあった。
となれば、あと一押しだ。
約束したとおりに、誰一人とて欠けることなく戦いを終えるために、再びトーノは山野を走る。
再び二条の黒い旋風が戦場へと吹き荒れた。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 エミリィ・ジゼル
エミリィ・ジゼル
◎
決戦配備:Sn
単純な数が優位となる平地戦ですか
であれば数を生かして戦場に混乱を生み出しましょう
ユーベルコード『暴れまわるかじできないさんズ』を使用
154名の空飛ぶかじできないさんズを呼び出し、鮫魔術の連射を上空から【一斉発射】することで、戦場を混沌へと落とします
かじできないさんズが暴れまわっている間、わたくしは敵を【ハッキング】
これだけの大軍を秩序だって動かすのであれば、現場で優先順位を判断し、各機に指示をだす指揮機的なものが複数いるはず
ハッキングで各機の通信状況を監視しることで指揮機を見つけてアンドレイに連絡
指揮機をスナイプしてもらうことでより効率的に戦場に混乱をもたらします
暑気を孕んだ粘っこい風が、白く澄んだ肌に無遠慮な感触で絡みついていた。
初夏特有のうだるような熱風が、平野からエミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)が所在する丘上へと吹き上げに抜け、色素の薄いエミリィの銀髪を乱していた。
乱れた横髪を指先で繰りながら、エミリィは丘の先端に立ち、眼下に広がる平野を一人、俯瞰する。
斜陽の反映は、エミリィの柔和な緑眼に薄紅色の綾を滲ませていた。
今、夕日の中でエミリィの翡翠は艶やかに輝いていた。
そして翡翠は、今、山野にあふれ出した数多の黒点のうごめきを静かに見据えていた。
草の大地を埋め尽くすように、大量のデウスエクスが黒点となって、ひしめいているのだ。
デウスエクスの一体、一体は、箱形の腹部から二本の巨大な足を生やした、いかにも人工物といった、気味の悪い甲虫の様な造形でもって佇立していた。
デウスエクスには頭部や腕部は無く、彼らは小さな胴部と、そこから突き出た胴部に不釣り合いな程に巨大な2脚のみを有するのみであり、人から大きくかけ離れたその異様からは生理的な嫌悪感を催すような醜悪さがにじみ出ていた。
多関節からなる無機質な巨大な足は、節足動物の脚部を彷彿とさせる構造をしており、デウスエクスが歩を刻むたびに、関節部はぎしぎしと軋みをあげながら歪に蠢動した。
歯ぎしりの様な機械音ともに、鉄の脚部は人の随意運動を模倣するように円滑に伸展と屈曲を繰り返しながら、一歩また一歩と緑の大地を踏みしだいていくのだった。
敵デウスエクスは巨大な鉄のイナゴとでも形容できるだろうか。
この歪な鉄のイナゴの大群が、今、エミリィの布陣する丘へ、さらに後背の山腹に横たわる小村目指して津波となって迫りつつある。
平野にはどこまでも緑が続くだけで、障害物たりえるような地形の起伏や、幅広な河川は存在はしなかった。
阻むものが無い草の大地を、鉄のイナゴの群れは無人の野を行くように我が物顔で突き進んでいく。
平野での戦いにおいては、数の優勢がそのまま戦況に大きく影響を与える。
人海戦術ならぬ、蝗海戦術とでも言うべきか。
山野を貪食する機械仕掛けのイナゴの大群は、数を頼りに攻勢を仕掛けたのだ。敵デウスエクスは、正攻法でもって戦場へと臨んだといえるだろう。
エミリィは一息ため息をつく。
桜の蕾を彷彿とさせる形の良い桃色の唇から零れた銀糸の様な吐息は、白い一条の煙となって夕焼け空へと舞い上がっていくと、ひと時、優雅に空を遊泳しながら、鮮やかな朱色の空へと初雪の儚さで溶け出していった。
翡翠の瞳はたおやかな光の縞模様を帯びながら、敵デウスエクスの挙止を具に見抜いていた。
すでに友軍の猟兵たちとの戦闘により機械仕掛けのイナゴの大群は、総数を当初の六割強程度まで減らしているのが伺われた。
友軍の猟兵の突貫が功を奏して、敵陣の中央部には巨大な間隙が口を開き、そのまま一直線に敵陣を左右に分断していた。
確かに敵の大軍は見た目にもわかるほどに数を減らしていたし、軍団として見た時、その動きは、精彩を欠き始めた。
だが、それでもなお軍単位ではなく部隊単位で見た時、敵部隊からは未だ恐慌や混乱の兆しは一切、感じ取れなかった。
先の友軍の突撃で、敵軍は既に司令官と思しき指揮官を失ったようだ。陣形は修繕がなされぬままに放置されたままであり、それはつまり、総軍の指揮を担う存在するものが退場したことを教唆しているといえるだろう。
しかし、全体としての統一を失いながらも、数十の鉄のイナゴの集団からなる群体は、それぞれが独立した部隊として未だに行軍を続けていた。
果たして、現状をどうみるべきか。
ふっくらとした唇に指先を添えると、エミリィはわずかに首をかしげる。
横一文字に結ばれた薄桃の唇からは、むぅと小さく唸りがあがった。
おそらく、なにかカラクリがあるのだろうと、エミリィは洞察する。そして、エミリィには既に仮説があった。
敵軍は損害率に反して、あまりにも秩序だっている。多少の損害を出しながらも、敵軍は一切混乱した様子が無い。機械兵だからか。いや、それだけでは説明がつかない気がした。
ではなぜか。
おそらくだが司令部とは独立して敵機の中に指揮官機が存在するのだ。
見た目には違いの無い機械兵の中に、一般機を統率する指揮官機がまぎれているのだろうとエミリィは見たのだ。
敵のデウスエクスは、数十体単位で一つの部隊を作り行軍していたが、こうして出来た群体の中に最低でも指揮官機が一機存在し、その指揮官機より周囲の者たちをに指示が伝搬されているのだろう。
軍を人体としてみなした場合、司令官とは大脳を始めとした脳中枢に当たる。そして、司令官麾下の各指揮官とは末梢神経に相当すると言えた。
なるほど敵を敵を節足動物と比喩したのは、予想以上に正鵠を射ていたのかもしれない。内心で自分を褒め称えてあげたいくらいだ。
全体としての統率性は、司令官たる中枢神経を破壊されることで喪失されたが、個々の群体は未だこの末梢神経とも言うべき命令系統に支えられ、混乱することなく隊レベルの行動を可能としているのだ。
ならば数十よりなるそれぞれの群体の指揮官をあぶりだせばよい。
群がる敵機の間で素早く視線を行き来させながら、エミリィは敵機の一機、一機を詳細に観察してゆく。
腕利きの鑑定士が、優れた鑑識眼でもって真作と贋作を腑分けするように、エミリィもまた遥か遠景に霞んでみえる敵機影のわずか挙措や形状の違いから敵指揮官を見極めんと努めたのだった。
敵デウスエクスの姿はエミリィの肉眼で辛うじて捉えられる程度であった。遠目にした限りでは敵機に構造上の差異はもちろん、挙動の違いは一切見受けられなかった。
角を生やしたり、色を派手に塗りたくってくれれば幾分もわかりやすいというのに。
エミリィは内心で愚痴をこぼす。
最も、視覚情報にて鑑別できずとも、敵指揮官機をあぶりだす方法を少なくともエミリィは有していた。
見た目には同一に見える敵機であろうとも、指揮官機と一般機とでは処理する情報の量が大きく乖離しているだろうことは間違いない。
ならばエミリィは彼らが放つ不可視の信号から敵指揮官機を見抜けよい。
そして敵指揮官を見抜く千里眼を、エミリィは有している。
更に好都合なことに、近場には腕の良い狙撃手も控えている。渡りに船とはこのことだろう。
あとは策を実行するだけだった。
エミリィが踵を返せば、フリルレースがふんだんにあしらわれた紫陽花色のスカートが優雅に裳裾をひるがえした。エミリィが一歩を刻むたびに、裳裾はふわふわと空を泳ぎ、紫陽花のヴェールが優雅な揺曳でもって茜空を彩った。
歩を刻めば、アンドレイらが布陣する丘の一隅へと突き当たる。
エミリィは、狙撃銃越しに敵の大軍を睨み据えるアンドレイを発見するや、直ちに駆け寄っていく。
「アンドレイさー―ん! あなたの狙撃の腕を見込んでご協力をお願いできないでしょうか?」
エミリィは足取り軽く歩を刻みながら、鷹揚と言い放った。
突然の申し出に、狙撃銃のスコープ越しに敵を睨み据えていたアンドレイがひょいと顔を左方へとずらし、エミリィへと視線を向けた。
アンドレイの赤みがかった瞳が、もの問いたげにエミリィを眺めている。
ふふんとエミリィは鼻をならしてみせる。
内心で微笑を浮かべれば、エミリィの楚々とした美貌にもまた笑顔の花が咲く。溌溂としたエミリィの声音が響いた。
「今から手痛い反撃を与えてやろうと思うのです。数には数です…そして活路は、空にありです」
途中で言葉を切ると、そっとエミリィは右手を振り上げた。白く滑らかな指先が中天を指した時、茜空に光点が一つ、二つと浮かび上がった。
「さぁ、カモン、かじできないさんズ!」
歌うようにエミリィが声音を弾ませれば、さび色の空に、溢れんばかりの光点が輝きだす。
わずかな沈黙が流れ、ついでアンドレイが思案顔で一度、目を瞬かせた。
「あちらは、一体…?」
半機人の青年、アンドレイが訝しげに空を仰ぐのが見えた。
エミリィは、自信のほどを示すように再び熱気交じりに鼻息を零す。
「敵が地上から攻めるならこちらは敵の攻撃の届かない空から爆撃を加えてしまえばよいのです...! そして敵への爆撃は空を行く無数の鮫魔術師が担当しましょう。ところで…アンドレイさんは鮫魔術をご存じで?」
気づけば、語気は仄かに熱を帯びていた。
鮫魔術について語りだせば、自然、気持ちが高まるのも当然というものだ。
思えば、エミリィは、英国でのデウスエクスとの戦いにおいて、幾度も鮫魔術を披露してきた。
となればそろそろ鮫魔術の偉大さに感銘を受けた人物が現れたとて、なんら不思議はない。
いわんや、鮫魔術ひいては鮫ちゃんの流行の機運は英国にて高まりつつあるとエミリィは見る。この戦場にも鮫好きが一人や二人いても、おかしな事はない。
エミリィは、期待と熱望の眼差しでもってアンドレイをしばし見つめていた。
しかし――。
「いや…、存じ上げていないな。魔術には疎くてね」
アンドレイが静かに首を左右させるのが見えた。
たまらずエミリィは、嘆息がちに吐息を零す。切れ長の目じりが、憂鬱げに下方へと斜を描いた。
鮫ちゃんについては、どうやら、さらなる布教が必要なのだろう。最も、それなら問題ない――。今、まさに茜空に数多現れた、無数の光点の一つ一つは、エミリィ自身となんら変わらぬ鮫魔術の素養を有した鮫魔術師たちなのだから。
「そうですか...。それは残念です。ですけれど、それならばアンドレイさんには特等席で鮫魔術をご覧いただければと思いますよ?」
言いながらエミリィは人差し指を、指揮棒の様に優雅に振りまわす。
しなやかな指先が空気をなぞれば、音もなく虚空にスクリーンが一幕、投影された。
エミリィは続ける。
「まずは、上空より鮫魔術でもって敵の大軍へと雨あられと魔術の応酬を加え、戦場を混沌へと陥れます…。もちろん、作戦はこれだけに終始しません」
空中に映し出されたスクリーンに指先を這わせれば、スクリーン上で数多の信号が飛び交い、画面を色彩鮮やかに潤色していった。
信号の行き来を目で追いながら、エミリィはアンドレイへと続ける。
「敵軍は被害を受けながらも、大軍を秩序だって動かしてくると思います。見た目では判断できませんが、各群体の中に指揮官の様なものが存在するのでしょう。私はこちらのモニターでハッキングした敵の通信上状況をモニタリングして敵の指揮官をあぶりだします。そこで、アンドレイさんには、私が見つけ出した敵指揮官を狙撃で即座に撃ち抜いてもらいたいんです...。鮮やかな鮫魔術とスナイピングで敵軍を混乱の渦に落としてやりましょう?」
ふふんとエミリィは鼻を鳴らした。
上空を見上げれば、幾条もの光が容赦なく地上へと降り注いでいくのが見えた。
光の一条、一条が鮫魔術の光なのだ。銀色の光は鮫達が有した、美麗たる鱗の反映なのだ。銀の砂をまき散らしながら茜空を滑空していく無数の光芒にエミリィは、勇壮たる鮫の姿を見るのだった。
自分でも鼓動の高鳴りがわかった。
流麗たる鮫達の遊泳が今、茜空を彩っているのだ。
エミリィはしばしの間、空を彩る銀の閃光を放心したように眺めていたが、しかし、男の声によってすぐに現実へと引き戻される。
「了解だ…。それでは、私は狙撃位置につこう。それにしても敵方の情報端末を瞬時に解析し、膨大な情報を処理する手腕、大したものだ。適宜、指示出しはお任せする―。狙いは寸分たがわず、私が撃ち抜こう」
茜空を熱狂交じりに眺めるエミリィをよそに、アンドレイは言葉短く、エミリィに返答するだけだった。
彼は感嘆交じりにエミリィへと目礼すると、丘の突端に臨み、うつぶせの格好で、巨大なスナイパーライフルを眼下へと向けて構えるのだった。
バーチャルキャラクターの鮫魔術師のエミリィへにとっては電子戦とは十八番であった。敵の通信を傍受するなど容易いことであった。
むしろ、アンドレイには鮫魔術にこそ感銘を覚えて貰いたかったのだが、彼は無風流なのか鮫にはあまり興味を示していないようだった。
鮫に対するアンドレイの淡白な態度にやや遺憾の念を抱かないでもなかったが、しかし、鮫魔術の素晴らしさに関しては、後に彼に説いて聞かせれば良いだろう。
まずは、現状を打開して…全員で生き残るのが先決だ。
計百五十を上回る光の矢が、地上に群がる黒点を次々に貫いていくのが見えた。
光が地表を穿つたびに地上からは、白煙や砂埃が濛々と舞い上がり、それらは渦まきながら濁った白雲となって低空を這うように進み、地上に濃い影を落とした。
天上より降り注ぐ鮫魔術が鉄のイナゴを続々と破壊していく。
しかし地を這う巨大な鉄のイナゴは屍と化した味方などには一切の俊巡や憐憫を示すことなく、鉄屑と化したイナゴの死骸を踏み越えながら、遮二無二に丘陵地帯へと押し寄せるばかりであった。
白く立ち込めた硝煙の帷帳が、大挙して大地を這い進むイナゴの一群により引き裂かれた。
漂う白煙の中から、鉄のイナゴがその無機質な鋼鉄の体躯をそびやかせながら姿を現したのである。
肉眼的に伺われた個々の機体の造形には違いの様なものは認められなかった。
だが、肉眼には同一に見える敵影であったが、モニター上に映し出された個々の機体が発する信号量には明らかな差異がある。
モニター上に映るは現実の影絵である。影絵を的確に読影するすることさえできれば、目に見えぬ真実が導き出される。そしてそれらをたどれば、影絵はぴたりと現実と結びつくことをエミリーは知悉していた。
色とりどりの信号の奔流が、一点へと向かい集簇していくのがわかった。
信号の中心点に位置する黒点へと、多数の信号がぶつかれば、黒点は押し寄せる情報の濁流を順々に飲みんでいく。中心点が白と黒の二色に明滅するのがわかった。
送信された情報信号はたちどころに中央の黒点により処理され、一瞬、明滅する黒点を除き、モニター上が白一色に染まった。
情報信号は続々と処理されてゆき、点滅を繰り返していた中心点が再び黒色に色を変じるのが見えた。
モニターが白一色に染まったのも束の間、受信波をすべて処理し終えた黒点は再び明滅を始めると、今度は一転、色鮮やかな大量の情報信号を、四囲へと向かい放射状に拡散させていくのだった。
ふたたび、モニター上が色彩を帯びていくのがわかった。
間違いない。
モニター上で信号の送受信を一手に担う黒点に一致して、敵指揮官は所在するのだ。モニターを現実に投影すれば自然、敵指揮官の居場所は浮き彫りになる。
「アンドレイさん…、水平面方向二時の方向です。二列目、左から三番目が敵指揮官です」
エミリィは断言する。
して、エミリィに対しるアンドレイの返答は青白い一陣の閃光によってなされた。
丘上から、紫色の閃光が長い尾を曳きながら空を走り抜けていく。
紫色の光は、鋭い棘を四方へとギラギラと伸ばしながら、エミリィの指定した一体の鉄のイナゴを飲み込むと、勢いそのまま彼方へと過ぎ去っていった。
青い光の中にもみくちゃに攪拌されながら、鉄のイナゴは瞬く間に鉄屑へと姿を変えていく。そうして、鉄屑が微細な芥となって茜空へと霧散すれば、エミリィの目前のモニターは、著明な変化を伴いながら無数の彩色でもって再び塗りたくられていくのだった。
それまで一点へと集まっていた色彩鮮やかな無数の送信波が突如、行き場を失い、画面一杯へとあふれ出し、無秩序な迷走を開始するのが見えた。
充溢していく送信波によって、モニター画面が統一性の無い、混沌とした色調でもって塗りたくられていく。
そして、モニターの混沌ぶりはそっくりそのまま現実の混乱ぶりをも教唆する。
鉄のイナゴの群体の中で、突如、後方へと踵を返すものが現れた。
一機、二機と隊列を乱すものが現れたのだ。呆けた様に空を仰ぐ者の姿が現れ、遂には左右へと無意味な水平移動を繰り返す者さえも現れる始末である。
結果、ひしめき合う鉄のイナゴ達は互いに押し合いへし合いをはじめ、互いが互いをもみくちゃにしながら激しくぶつかり合った。必然、衝突の末、地の上に無様に転倒するイナゴが続出する。
イナゴの一群は、ここに完全に統率性を失い、混乱状態へと陥っていたのだ。
そして、茜空に白点の連なりとなって居並ぶ並行世界よりの来訪者たちは、敵の混乱を見逃すほどに悠長ではなかった。
上空より鮫魔術がイナゴの群体を襲う。
数多の鮫が茜空を滑り降り、そして鋭い刃で混乱状態のイナゴ達を鋭い牙で貪ってゆくのが見えた。
無数の白銀の鮫達がイナゴの群れへと鋭い牙を突き立て、そしていずこかへと過ぎ去っていけば、草の大地には鋭い歯型を刻まれた、無残な残骸がうっそうと小山を築くのだった。
敵の群体を一つ、葬り去った。
しかし、まだまだ敵の行軍は止むことは無かった。
今もなお、鉄のイナゴ達はいくつもの群体を形成しながら、五月雨式に丘陵地帯へと向かい突撃を続けている。
「続いて、アンドレイさん――。水平面方向、十字の方向へ。敵三列目の右から二番目を」
エミリィが声を張る。
山野にエミリィの声音が響き渡る。残響が消失するよりも早く、武骨な狙撃銃が紫色の火を噴いた。
放たれた紫色のレーザーは、音もなく空を駆けてゆきながら、三時の方向から近づくイナゴの群体の敵指揮官を寸分たがわずに飲み込むと、蠢く影を瞬く間に灰燼へと帰すのだった。
指揮官が戦場の露と消えれば、あとは脆いものだった。残存したイナゴ達は狂乱したかの様に各々が、てんでばらばら行動をはじめ、群体は瞬く間に恐慌の渦へと飲み込まれていく。
そうして、混乱を極める敵群体のもとへと、百を五十ほど上回る大量の鮫たちが容赦なく、押し寄せ、イナゴ達を容赦なく殲滅していくのだった。
「十二時の方向、一列目中央の敵機を」
エミリィが声を弾ませれば、再び紫色の閃光が空を駆け抜けていった。
「次は側方からです! 三時の方向…。交尾の一機を狙ってください」
青紫色のレーザーの揺らめきが次なる個体を再び、撃ち抜いた。
エミリィの号令一下、アンドレイは敵指揮官を一機、また一機と撃ち抜いていく。正確な射撃と共に、撃ち抜かれた敵影が大地へと崩れ落ちれば、たちどころに鉄のイナゴの一群に混乱が巻き起こる。
混乱は恐慌へと変わり、ついで、敵部隊は壊走の憂き目を見る。
戦場の至る所で、鉄のイナゴが蜘蛛の子を散らすようにして四散するのが見えた。
そうして逃げ惑う鉄のイナゴ達は、上空より襲い来る鮫達によって容赦なく切り裂かれていく。
鋭い鮫の牙が空に煌めくたびに鉄のイナゴは次々にその身を食いちぎられ、草の大地へと倒れ伏していくのだった。
ここにそれまで息巻いて進撃を続けていた敵の軍団がぴたりと静止した。
打ち寄せる波はついぞ完全に平原にて動きを止めたのである。
敵は、自らの通信状況が第三者へと漏洩していることを悟ったのか、スナイパーライフルの射程ぎりぎりで歩を止めると、つぎはぎだらけになった陣形を再編成を始めた。
黒い点が山野で蠢いたかと思えば、黒点が移動を開始する。
左右と長く敷かれた陣形は折りたたまれ、今度は一転、縦深方向に密な縦深陣を黒点は形成していくのだった。
束の間、両軍の間に硬直が生じた。
不気味な静寂が再び戦場へと得も言われぬ圧迫感と共に丘の上へとのしかかってくる。
とはいえ、明朗快活としたエミリィには、重苦しい沈黙などどこ吹く風である。ユーベルコードの効果は失われ、異世界より訪れたエミリィの分身たちは本来の世界へと続々と帰還を果たしていった。
だが、エミリィ自身、まだ余力は残っていたし、未だ、アンドレイには鮫魔術ひいては愛らしい鮫ちゃん達の魅力を伝えきれてなかった。
再びの衝突に備え、エミリィは鮫魔術を練る。アンドレイに鮫魔術を披露するには、今の状況は絶好の状況と言えた。
風が吹き、木々が震えた。
ついで山野に響いたのは、イナゴの大群の行進が齎した耳障りな雑音だった。
当初の半数ほどにまで数を減らした鉄のイナゴの大群とアンドレイ軍の彼我は、間近まで詰められていた。
そうして、ついぞ、丘陵地帯が鉄のイナゴの腹部に搭載された機銃の射程内に収められた時、機銃は一斉に火を噴いたのだ。
機銃の斉射による弾奏が、戦いの終焉を告げる鐘の音色となって山野を激しく揺さぶる。
大成功
🔵🔵🔵
 暗都・魎夜
暗都・魎夜
【心情】
改めてデウスエクスの侵略にかける情熱には感心するぜ
あんだけ戦ってなお、こんだけの戦力を出す余裕があるんだものな
【決戦配備】スナイパー
そんな勝ち馬を捨てて地球人についたレプリカントってのは大したもんだ
死なせるわけには行かねえ
【戦闘】
極めて高い射撃能力を持ったロボ
それがこの数で押してくるわけだ
シンプルだけど、確実な戦い方だよな
まあ、俺にしてみれば不利なくらいがちょうどいいし、たくさんいる敵を倒すのはむしろ得意だ
「火炎耐性」で自身のみを守りつつ、DIVIDEの前に立って「かばう」
プラズマ弾の攻撃を吸収して、「全力魔法」のUCを発動する
「師匠が言ってたぜ、"退路は前にしかない"ってな」
連なる丘陵が、西日によって暗赤色に染め出されている。
緩やかに傾斜する丘の元、茜空へと丈高く背を伸ばした管制塔がさび色の夕日を受けて、地上に濃い影を落としていた。
丘の斜面に臨んで垂直に伸びた防壁の連なりは、漆喰を彷彿とさせる黒褐色の胸壁を夕空にそびやかせながら、管制塔と管制塔との間を縫うようにして、ぐるりと丘を囲んでいた。
丘陵の山頂は、一応は最低限の防衛陣地としての体裁を繕っていたといえるだろう。
丘の頂上は、全周性に張り巡らされた防壁によって陣地全体を覆われていたし、さらにそこには、敵の攻勢に対する反抗の矛たるアンドレイ率いる防衛部隊が多数控えている。
人型決戦兵器などの高度な戦術兵器はアンドレイ達の様な独立部隊に随伴しようはずもなかったが、それでもなお、火器の類は必要数備えられていたし、それらを扱う勇士たちも一人一人が歴戦の猛者と言えるほどの実力を備えていた。
丘陵に臨み張り巡らされた防壁には、幾つもの銃眼がめぐらされており、そこからは重砲が眼下の睨み据えるようにして砲身を伸ばしていた。
防衛陣地としてはやや心もとないものの、数に数倍するほどの敵が攻め寄せようとも防衛陣地はびくともしないだろう。
だが、果たして彼我の兵力が数倍どころではなく、数十倍ほどかけ離れたものであった場合、結果は如何ようとなろうか。
いかに歴戦の兵士たちが数多存在する陣地と言えども、雲霞の如き大軍で攻め寄せる敵兵を支えることは叶わぬだろう。兵が精強であり、指揮官の統率力に優れていようとも、彼我の兵力があまりにも隔絶していれば、用兵術の妙や兵の精強さとといったものが戦況に介在する余地は最早、存在はしないのだ。
そして、アンドレイらの布陣する丘陵地帯は今、数多押し寄せるデウスエクスの大群によって洗い流されようとしていた。
斜陽は今や山際に完全に身を沈め、茜空には夕暮れ時の朱色に交じり、暮夜の鉛色が滲みだしていた。
今、空は朱色と黒色の二色の混淆の元、宵闇の訪れに備え、夜化粧を整えつつあった。
暮逝く空が見守る中、今、丘陵地帯と目と鼻の先では、数多の機械兵が巨大な森となって縦長に群がっていた。
すでに猟兵たちの度重なる攻撃により、敵軍は五千を下回るほどに数を減らしていた。
当初、敵軍が万余を超えていたことを鑑みれば、敵軍の半数は戦場の露と消えたという事であり、山村を守らんと集ったもの達の健闘ぶりが敵の甚大な損害率から伺われた。
敵は半数を失った。
だがそれでもなお、未だ五千を超える大兵力でもってデウスエクスらの大軍は丘陵地帯の前面で蠢動を続けているのだった。そこにあるは、GLMストーク、歪な機械仕掛けのイナゴの大群であった。
GLMストークの大群は、今や重厚な短い戦列を縦に幾列も敷き、長蛇の列となって、山野に居並んでいた。
そして長蛇の列の先頭部隊が、アンドレイらが布陣する丘陵地帯を己が武器の射程に収めるほどの近距離にまで肉薄したのである。
GLMストーク、巨大な二本の足と、箱形の胴部よりのみ体躯を構成した歪な機械兵は、幾つかの小集団を形成しながら碁盤の目状に平原に広がり、それぞれが搭載した火器でもって丘上へと狙いを定めたのだ。
数百にも及ぶ銃口が、今、丘の上を激しく睨んでいた。
猟兵たちによる結果術をはじめ、丘上の陣地は最低限の防護壁により守られていたが、敵軍の大攻勢を前にした時、防壁群が、直ちに瓦解していくであろうことは誰の目にも明らかだった。
だが、冷酷の象徴たる銃口は防衛部隊へと一切の慈悲を施すは無かった。
機械仕掛けのイナゴの腹部より突き出た機銃が、一斉に震えだし、箱形の胴部より山頂へと向かい顔をのぞかせた大型の砲門が砲口に紫色の光を滲ませた。
紫色の光は光量を増し、腹部の機銃は唸りを上げる。
激しい轟音が山野を鳴らしたかと思えば、デウスエクスらに搭載された数多の砲撃が山頂の防衛陣地へと向けて一斉に火を噴いた。
機銃より放たれた数多の銃弾は、一塊となって、まるで黒い敷物を広げるように空を駆けのぼっていく。
黒い敷物がぬるりと伸び、そうして、胸壁群へと襲い掛かれば、激しい炸裂音が轟いた。ガラスが割れるような甲高い粉砕音と共に、防壁群が紙細工の様に崩れ落ちていくのが見えた。
空を駆ける紫色の光線は、GLMストークに搭載されたプラズマキャノンの光だった。
幾条もの紫色の閃光が、機銃の斉射に続き、丘上へと駆け上っていく。
銃弾の嵐と無数の閃光との二重奏によって、丘上が淀んだ黒色と、眩い紫色で染め出された。今、すべてが光の中に飲み込まれ焼き払われたかに見えた。
しかし――。
ふと丘上の防衛陣地で、紫色と黒色に混ざり、淡い紅色が揺らめいた。
それは遠目には紅色に揺らめく炎柱と見えただろう。見る者によっては、斜陽の反映とも映ったかもしれない。
いずれにしても、赤々と輝くなにかが、丘の頂上へと濁流となって押し寄せるプラズマ弾や銃弾の前へと影を伸ばし、防衛陣地を守るような格好で立ちはだかったのである。
紅色の焔がそこに揺らめいていた。
焔が絹の様な炎の大腕を周囲へと伸ばせば、炎に煽られて、銃弾は溶けだし、迸る閃光は炎の中へと溶け出し霧散した。
数多押し寄せる紫色の閃光も、黒い敷物となって雨あられと飛翔する銃弾もそれらすべては、紅色の微光によって無力化され、丘上を貫通すること叶わず、虚しく周囲へと飛散してゆくのだった。
平原にてけたたましく音を上げていた機銃は徐々に鳴りを潜めてゆき、ついで、紫色の光芒もまた光量を落としていく。
銃声が鳴り止み、山野より紫色の光が絶えれば、再び静寂が山野へと木霊する。
デウスエクスによる射撃が完全に止めば、丘の頂上を覆った焔の盾もまた、赤い火の粉を周囲に爆ぜながら、大気の中へと霧の様に溶け込んでいくのだった。
焔の大盾の残滓が、紅色の粉雪となって山頂へと降り注ぐ中、一人の男がアンドレイらが待ち構える防衛陣地へと舞い降りた。
落下に伴い、鮮やかな朱色に染まった短髪が、勇ましげに風にたなびいていた。意志力の強い紅玉の瞳が力強く揺らめいていた。
そこにあるは、手練れの猟兵たる暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)その人の姿であった。
そう魎夜は、己が展開する防御魔術によって丘陵地帯に布陣する友軍を敵軍の斉射から守って見せたのだった。
朱色の幻燈の輝きの中、魎夜は丘の上に降り立つと、眼下に居並ぶ、デウスエクスの大群を一瞥した。
平原に蠢く数多の敵軍を一望した時、たまらず魎夜の口元を感嘆とも嘆息ともつかぬ、ため息がこぼれた。
これまで、魎夜は英国をはじめ、DIVIDE世界において、数多くのデウスエクスと干戈を交え、多くの敵を屠ってきたつもりだった。
だが、それでもなお、いくら敵を屠ろうとも、デウスエクスは地球侵略のために湯水のごとく兵を投入する。
改めてデウスエクスの侵略にかける情熱というものに辟易とせざるを得ない。
彼らは多くの戦場で敗退してもなお、一戦場に万余の戦力を送り出す余力を有しているのだ。
なるほど、デウスエクスの脅威というものが魎夜にも再認識された気がした。
感嘆気味に小さくを鼻を鳴らしながら、次いで魎夜は、肩越しに後方へと視線を送った。
暮色の空のもと、魎夜の視界には、勇士たちの勇壮たる面差しがくっきりと浮かび上がってみえた。
勇士の中にはもちろんだが、予知の中にあったアンドレイなる青年の姿も見受けられた。魎夜はまじまじとこのレプリカントの青年を見つめながら、再び黙考する。
猟兵の存在が無ければ、地球侵略におけるデウスエクス側の優勢は今もなお続いていただろう。
しかし、この場に一堂に会した者たちは、優勢にあったデウスエクスを裏切り、勝ち馬を捨ててまで、地球人に味方することを決めたのだ。
数多の戦場を潜り抜けてきた魎夜だからこそ分かる。
氷の様に表情筋一つ動かすことの無い、アンドレイなる青年は、その冷静なる仮面の下で高潔なる意思の炎を燻ぶらせているのだ。
青年を眺めるにつけ、自然、魎夜の口元は綻んだ。
微笑を浮かべながら、魎夜はアンドレイへと目配せする。
「俺の師匠の言葉だが、"退路は前にしかない"ってものがあってな。だから、俺が敵軍へと突っ込む。なんで、援護は頼むぜ」
微笑がちに言い放ち、魎夜は再び前方へと視線を戻す。
背中越しに熱いまなざしを感じた。
姿は見えずともアンドレイらが力強くうなづき、持ち場につくのが背中越しに気配から伺われた。
彼らを死なせるわけにはいかないと思った。共に生き、そして後背の村々を守りたいとも思った。
アンドレイらの熱情のまなざしにあてられてか、自然と心が昂った。
気づけば、魎夜は丘の上を進み、その突端にて立っていた。魎夜が悠然と眼下を見下ろせば、火力の一斉照射を無力化されたことに業を煮やしてか、蠢くデウスエクスの大群が再びの攻勢に備えて、一斉にプラズマ砲の砲門を開き、鋭い銃口でもって丘陵地帯を睨み上げるのが見えた。
敵は、極めて高い射撃能力を持った精密兵器である。それが雲霞となって押してくるわけだ
数に頼って高性能な兵器が一心不乱に攻め寄せる。シンプルだが、殲滅戦における確実な戦法と言えるだろう。
最も――。
魎夜は人差し指を持ち上げ、眼下に群がる敵の大軍へと向けると、まるで挑発するように二度三度と指先を屈曲させた。
魎夜の挑発に乗った故か、それとも、予定調和ゆえの狙撃であったのか、詳しいところは魎夜には分からなかったが、魎夜の挙止を窺っていたGLMストークの大群のもと、胴部から突き出たプラズマ砲が、青紫色の光芒を吐き出すのが見えた。
どうやら敵はプラズマ砲による第二射を試みんとしているようだった。
明らかなる攻勢を前にして、魎夜の後方よりアンドレイらの狙撃部隊が、地上の敵へと向かい銃火を加えるのがわかった。
しかし、魎夜はあえて右手を振り上げると、アンドレイらの射撃を制止する。
むしろ、敵軍のプラズマ砲による斉射とは魎夜にとっては願ったり叶ったりの状況の到来を意味するものであったからだ。
そう、この状況をこそ、魎夜は待ち望んでいたのだ。
自らのユーベルコード『レッドダイナマイト』を顕現させるためには必然、敵よりの火器による攻撃を必要としたからだ。
魎夜の十八番の一つである、ユーベルコード『レッドダイナマイト』とは戦場にあふれる熱量を吸収することでその威力を増していくというやや風変わりな術技であった。
この技は非常に強力な技である反面、十全の威力を発揮するには、膨大な熱量を原動力として必要としたのだ。
幸運なことに、レッドダイナマイトの本領発揮に必要な、熱量を担保するに十分な火砲は、今、魎夜の眼下で紫色の光芒となって数多揺らめいている。
すでに敵軍団によるプラズマ砲の第一射をいなすことで、ユーベルコード発動に必要な熱量は役半分ほど満たされた。残り半分を満たす熱量の高まりは、今、眼下にて唸りを上げている。
魎夜が指先に再び魔力を籠めれば、魎夜を中心にして紅色の魔力障壁が広がっていく。
意識を集中させるごとに当初、靄の様に漂うだけだった、火炎の魔力で編まれた一層の防壁は、急速に密度を増してゆき、ついぞ堅牢無比たる紅色の大盾となって魎夜を中心に丘の頂上を包み込むのだった。
眼下で光芒が煌めくのが見えた。
GLMストークの腹部に積載された、プラズマキャノン砲より、数多の閃光が放出されたのである。
放たれたプラズマ砲は、雷撃にも似た紫色の光弾となって、空にジグザグに尾をひきながら猛烈な勢いで上空へと飛び上がると、四方八方から魎夜を飲み込んだ。
赤みを失いつつある暮時の空に、閃光が一条、また一条とたなびいたかと思えば、それらは瞬く間に空を走り抜け、魎夜を包む焔の大盾に、続々と突き刺さっていく。
雷光が魎夜を包む大盾の表面に鋭い紫色の牙を突き立て、大盾ごとに魎夜をかみ砕かんと、紅色の表面をじりじりと圧迫する。
雷光は、大盾の表面に綻びを穿たんと、牙の一撃に加え、時に激しく体動させ、またある時は獰猛たる尾を振り回しながら、幾度も幾度も大盾を横殴りに殴打した。
無数の雷光が激しく蠢きながら、魎夜の表面に張り付いた焔の大盾を引き剝がさんと、飽かず大盾を揺すった。
空気は激しく動揺し、一挙に密度を増していく。
轟音が鳴り響いたかと思えば消え、再び生じては霧散していく。
度重なる雷撃の刃が、幾度も空を紫色に染め、魎夜を飲み込んだ。
しかし――。
紫色の尾は、幾度も炎の大盾の表面を掠めたが、時に弾かれ、時にいなされ、結果、乾いた音を上げながら大気の中で砕け散るばかりであった。
幾条も空を駆けぬけていった数多の閃光は、魎夜を覆う大盾を貫通すること叶わず、結果、虚しく空気へと霧散していくだけであった。
肌先で、空気がひくひくと収斂するのがわかった。雷光の余韻により肌先が熱を帯びているのも知覚できた。
――だが、それだけだった。
プラズマ砲が魎夜へと致命傷を齎すことはついぞ無かったのだ。
むしろ魎夜を掠めた無数の雷撃は、今や、魎夜を中心にして生じた新たなる日輪を構成する膨大な熱量の一部へと昇華したのである。
「全力で行くぜ――!」
言いながら右手を振り上げれば、奔騰する奇跡の力は燎原の火の如く、魎夜の全身を駆け巡り指先へと収束してゆく。
魎夜の指先で、紅玉色の燈火が綿花の様に広がった。
魎夜は勢いよく大地を蹴りぬくと、眼下に群がるGLMストークの集団目がけ、空を滑り落ちていった。
鋭角な軌道を描きながら魎夜が地上へと突き進む。
魎夜が地上へと、近づくにつれ、指先に灯った焔は、一挙に膨れ上がり、魎夜を包み込んでも尚、火勢を増してゆきながらついぞ、第二の日輪となって空一杯に広がってゆく。
夕映えの絶えた青みがかった暮空に突如、新たなる太陽が顔を覗かせた。
第二の太陽は轟轟と燃え盛りながら、地表に近づくにますます体積を増してゆき、ついぞ、その巨体でもって地上を飲み込むのだった。
太陽が炎の大腕でもって、黒点となって蠢くGLMストークの大群を薙ぎ払い、炎柱で包んだ。ありとあらゆるものが燃え盛る炎の中に沈み込み、業火の中で白く身を縮ませていった。
数十体単位で群がるGLMストークの群体は、一つの炎柱によってまとめて一挙に焼き払われた。
至る所で上がる爆炎と、火炎の柱が続々と、GLMストークの群体を飲み込んでいくと。数十を超える群体が炎に飲み込まれてゆけば、最早、機械仕掛けのイナゴは塵も残さずに、魎夜が生み出した太陽の予熱によって焼灼されていくのだった。
結果、千を超える機械仕掛けのイナゴの大群が、瞬く間に灰と化す。
巨大な炎の球体は、千を超える敵デウスエクスの焼灼により、ようやく溜飲を下げた様で、ようやく火勢を落としていくのだった。
激しく燃え盛る炎は瞬く間に消褪してゆき、地上には、しっとりとした夜の帳が降ろされた。
そうして、消え果てた太陽の元、荒野と化した戦場に魎夜が忽然と姿を現したのである。
丘陵附近に布陣した敵軍団は最早、黒い灰となって夜空に漂うばかりであった。
今や、魎夜と丘の頂上で布陣するアンドレイら防衛部隊、金粉となって周囲へとあふれ出した火の粉だけが丘陵附近には残っただけだった。
とはいえ、魎夜にとっての戦いはまだ始まったばかりであった。
薄闇の奥を凝視すれば、未だ遠景にて蠢く無数の敵が伺われたからだ。魎夜の攻勢により、敵の前衛部隊は壊滅するに至り、敵の総数は四千をわずかに下回った。
だがそれでもなお、敵軍は未だに余力を残したままだ。
事実、魎夜の遠景では、機械仕掛けのイナゴの大群が、不気味な黒い葬列となって、縦長に幾重もの陣を敷きながら蠢くのが伺われた。
間もなく敵軍は残余の部隊でもって丘陵地帯を再び強襲するだろう。
となれば、まだ気を抜くことはできないのだ。
口笛交じりに、敵軍を見やりながら魎夜は再び拳を前方へと突き出した。
最も、敵に怯むる事や、絶望することなど魎夜にはありえはしなかったが。
「さぁ、いくぜ――」
ふぅと魎夜は、吐息を吐きだした。退路は前にしかないとの師の教えを苦笑交じりに反芻しながら、鋭い視線でもって薄闇の中で蠢く敵部隊を睨み据えた。
「イグニッション...!」
次いで、勢いよく言い放つと同時に魎夜は、大地を勢いよく蹴り上げた。
――今、ここに赤い稲妻が、再び戦場へと放たれた。
そして、ここに戦いは終幕へと向かい、一挙に加速していくのであった。
大成功
🔵🔵🔵
 ハル・エーヴィヒカイト
ハル・エーヴィヒカイト
アドリブ連携○
▼心情
私もこういった村落の出身でね、くだらない復活の儀式のために犠牲にさせるわけには行かない
戦いは数がものをいうことが多い。だが、単なる物量の差ならば覆せなくて何が猟兵か
▼ポジション
Sn
▼戦闘
戦場に舞い降りると同時にUCを発動
無数の刀剣を内包した領域を戦場に展開する[結界術]
UCの効果で今この戦場にある私が武器と認識するもの
即ち破壊した敵機の残骸や武装も全て我が支配下だ
まずは[念動力]で操作した刀剣を[乱れ撃ち]する[範囲攻撃]で敵機集団を蹂躙
アンドレイにもきっちり敵機のコア部分だけを撃ち抜いてもらい、出来るだけダメージが少ない状態で支配下に置く
支配下に置いた敵機や武装はそのまま相手の攻撃を防ぐ盾とし相手を砕く弾丸とする
数の差は覆った。殲滅の時間だ
相手が放つプラズマ弾は[心眼]でそのタイミングを[見切り]、相手の近くで着弾するように操作した敵機をぶつける事で相手陣営に超高熱状態を付与、
範囲内に侵入しないように遠距離から残敵を打倒していこう
青みがかった空に、淡い光が浮かんで見えた。
今や夕映えの光は完全に絶え、暮夜の訪れを告げる宵空は、凍り付いたような表情でもって冷ややかな眼差しを地上へと向けていた。
黒く透き通った水面には、一つ、二つと明滅する、柔らかな星明りが浮かんで見えた。
風が吹いた。ざらりとした風が平野を駆けぬていったのである。
木々を渡る夜風が、林立する木々の梢を揺らしながら、ナイフで刺す様な鋭い冷気でもって、ハル・エーヴィヒカイト(閃花の剣聖・f40781)の頬を撫でつけていた。
薄闇の抱擁が、今、山野を静かに包んでいる。
丘の頂上に立ちながら、ハルは眼下を一望する。
薄闇の平原にて蠢く無数の影があった。
数多の黒点だ。
薄闇の中で、まるで甲虫類を彷彿とさせる不気味な機械仕掛けのイナゴの様な物体が巨大な両足でもって大地を踏みしめているのが見えた。
彼らは、互いにへし合い押し合いをしながら、一条の絨毯となって緑の大地に覆いをかぶせ、丘陵地帯へと向かい、じわじわと影を伸ばし迫る。
イナゴの一体、一体は箱形の胴部より、円筒状の槍のようなものを伸ばしていた。その筒状の塊が火を噴くたびに、暗紫色の光弾が夜空を駆け上がっていく。
機械仕掛けのイナゴ、GLMストークに搭載されたプラズマキャノンだ。
プラズマキャノンは、暗紫色の微光を周囲にまき散らしながら、一斉に丘の頂上の防衛陣地へとなだれ込む。砲撃が大地を描き、砂埃を巻き上げる中、ハルは最小限の動きで閃光の一撃、一撃を見極めながら、丘の周囲に張り巡らされた結果術による防壁を活性化し、敵の砲撃を相殺していく。
薄紫色の閃光が弾け飛び、濛々と立ち込めた砂塵のカーテンが取り払われ、視界が開かれた。視野の確保された山頂より、無数の火砲が、眼下に群がるイナゴら目掛けて一斉に火を噴いた。
結果、薄闇の中に身を沈めた山野が砲火により赤と紫色の二色に染まる。
レーザ砲と機銃とがイナゴの群れへと次々に突き刺さり、大地へと鉄の残骸が数多、横たわった。
至る所で火の手があがり、火柱が炎の舌でもって夜空を焼き払う。
もちろん、イナゴの大群らも反撃で応じる。
双方より放たれる紫色の閃光が、大地を抉り、礫や砂片を巻き上げた。
機械仕掛けのイナゴが続々と大地へと崩れ落ちていくのが見えた。鉄片が白銀の揺らめきで夜空に四散し、それらは大地の上へと堆く積み重なって、鉄の残骸を山と築いていくのだった。
今、戦線は完全に膠着状態にある。
そう、猟兵たちのここまでの奮戦がついに両者の勢力に均衡を齎したのである。
当初、敵GLMストークは地平線の彼方まで広がり、山野を埋め尽くすほどの勢いで丘陵地帯めがけて行軍を開始した。
彼らは、傲岸不遜たる軍靴の響きでもって大地を揺らし、無人の野を行くように山野を蚕食していった。
だが――、この場に集った者たちの奮戦により倨傲たる侵略者達は大きく戦力を削がれ、今や彼らは辛うじて維持された縦長の密集陣のもと、最後の大攻勢に打って出たのである。
当初、万を超えた敵軍は、三千強まで目減りしており、統率もままならない程であった。とはいえ彼我の勢力には十倍以上の隔たりがある。
しかし、この兵力差を覆す存在が、防衛部隊には味方し続けていたのだった、
ハルが丘の上から前方へと目を遣れば、巨大な人影が視界にありありと浮かび上がって見えた。女性のなだらかな姿態を思わせる巨人の姿がそこにあった。
女皇帝を思わせる巨人は、紅玉色の微光でもって薄闇を淡く照らし出しながら、群がる機械仕掛けのイナゴを切り払い、敵の行軍を堰き止めていた。
山野の一角では雷光が瞬いていた。地上より起こり、鋭い槍の一撃となって続々とイナゴの群れを貫いていく稲妻の起点には一人の少女の姿があった。蜂蜜色の挑発を振り回しながら、少女が戦場を欠けるたびにイナゴの大群が周囲へと四散していった。
闇よりも尚も深い漆黒の旋風が、左右からイナゴの一団へと襲い掛かるのが見えた、旋風の通過と共にイナゴの群れは引き裂かれ、次々に大地へと崩れ落ちていく。過ぎ去っていく旋風の中に、ハルは、旋風の中に二頭の獣の姿を確かに垣間見る。
丘陵地帯からは、アンドレイらが放つレーザーライフルの火砲に混ざって、銀白の光芒が空を暴虐の牙で切り裂いた。銀色の光は、まるで鮫の様な形を取りながら、イナゴの一団へと上空から襲いかかると彼らを貪り食らい、その残骸を地上にまき散らしていく。ハルが肩越しに後方を振り返れば、給仕服に身を包んだ少女と目があった。櫛比の様に額を覆いつくした色素の薄い銀の前髪の下で、楚々とした翡翠の瞳が柔和に見開かれている。
再びハルは、眼下へと視線を戻す。
凝視して闇の一点を窺えば、赤い短髪を夜空に悠然とそびやかしながら、雄々しく大地を駆け抜けていく青年の姿が視界に浮かぶ。青年が敵陣を強襲するたびに至る所で爆炎がたなびき、轟音が響き渡った。
アンドレイらによる防衛部隊もまた、一糸乱れぬ統率のもとで敵軍に対しレーザーライフルの斉射を続けている。
この場に集ったもの達の中に、諦観するものなど存在はしなかったのだ。
今、この場に集ったもの達は、一丸となって敵軍の進行に抗している。
そして、ハルもまた彼と気概を同じくする。
ハルは、腰元の剣の鞘へと左手を添える。剣の鍔を左の親指で軽く弾き、剣の鯉口を切れば、わずかに顔を覗かせた刀身が、さめざめとした銀蒼色でもって薄闇の中で煌めいた。
歩を進めながらハルは丘の突端に立つ。
そこにはアンドレイの姿があった。
無数の銃火が飛び交う戦場のもと、アンドレイは兵の先頭に立ち、顔色一つ変えることなく、貴下の兵らに指示を下しつつも、自身もまた、スナイパーライフルでもって敵軍を次々と撃ち抜いていく。
なぜだろうか。
ハルは隣だつ青年にかつての師の面影を重ねずにはいられなかった。
イング…、ハルにとって教師であり、剣の師であり、兄の様だったあの男がなぜか、レプリカントの中に姿を現したのである。
イング、あの温厚ながらも気高い男は、デウスエクス襲来の折、里を守るために戦いに赴き、そして虚しくも戦場の露と消えた。
あの時の自分は逃げ惑うだけの子供にしか過ぎなった。
だが…。
今の自分はもはや泣きじゃくるだけの子供に非ず。
「アンドレイ…」
気づけば、口元を声がついた。
飛び交う銃火がつんざく様な騒音でもって周囲を揺さぶる中、ハルの声音は小鳥の囀りの如くか細いものであった。果たして、アンドレイに届いたかも定かではない。
事実、アンドレイなるレプリカントの青年は、その燃え立つような炎の瞳でもって敵軍を見据えたまま微動だすることなく、射撃を続けていた。
だが、彼に聞こえずとも何ら支障はない。
ハルは誰にでいうでもなく、自らに言い聞かせるように言の葉を重ねる。
「…くだらない復活の儀式のために犠牲になどさせるつもりはないぞ。村の事はもちろんだ。…あなたのこともだ」
ハルの故郷は、赤黒く爛れた焔によって焼き尽くされた。
黒煙が燻ぶり、おぼろげになった視界のもと焼け落ちた家屋の残骸と共に、数多の遺骸が大地にて黒く焼かれていた。
あの地獄絵図を再び、ここに再現させるつもりは無い。
そして惨劇を止めるだけの力をハルは有している。もはや、ここにあるは無力な少年ではないのだ。
ハル・エーヴィヒカイトは、異世界を戦い抜いた歴戦のツワモノとしての経験を有した、奇跡の力を行使する第六の猟兵なのだから。
敵の数は多い。
だが、ハル・エーヴィヒカイトは奇跡を齎す猟兵の一人である。彼我の兵力差はおおよそ数千。そう、数千程度だ。この程度の物量さを覆すことができず、何が猟兵かとも思う。
ハルは大地を踏みしめる。腰を落とし、抜刀の構えを取る。
ふぅと息を吸い、右足で勢いよく大地を蹴りぬいた。
両の足が丘上を離れ、ハルのしなやかな体躯が、放物線を描きながら中空に舞い上がる。徐々に高度をあげながら、ついぞハルの体は、最高点へ到達し、一転、落下軌道へと入る。
鋭い矢となり空を駆け下りるハルの元へと、無数の暗紫色の閃光が数多、押し寄せたのはその時だった。
むぅとわずかにハルは眉をひそめる。
抜刀でいなすべきか、結界術を展開し多少の被弾は覚悟のもと、敵の攻撃に耐えるか、はたまた、回避に専念することで敵の攻撃をやり過ごすか、ハルはたまゆら、逡巡したのである。
だが、ハルの備えは杞憂に終わる。そう、ハルの背より数多、迸った閃光がハルを守ったからだ。
突如、ハルより起こった無数の閃光が、勢いよく空を駆け抜けていき、GLMストークが放った光弾を側方より激しく叩きつけたのだ。
爛れた暗紫色の光弾と、光沢のある赤紫色の閃光とがハルの目前でぶつかり合って混交し、薄闇の中で、紡錘形の光花を咲かせた。
数多、押し寄せた暗紫色の閃光は、ハルの肌先三寸で、光の花となって、瞬く間に盛りを迎えると、雪の結晶の鮮やかさで砕け散るのだった。
ハルの周辺では、閃光が揺らめくたびに光の花が咲いては散っていった。
そう、GLMストークが放った光弾は、そのすべてがアンドレイによる狙撃によって無力化されたのだ。今や、ハルへと向かった数多の光弾は、撃ち抜かれ、糸くずの様な青紫色の微光となって空中に揺蕩うばかりである。
ハルは口元を綻ばせた。
文句なしの援護と言えるだろう。
急降下の後、ハルは大地へと降り立った。
アンドレイらの援護により、防御に力を振り分ける必要はなくなった。必然、蓄えた力のすべてを、攻勢のために転用することが可能となった。
着地ざま、大地を力強く踏みしめる。
全身に蓄えられた力を吐息と共に吐き出せば、吐く息と共に世界はそのありようを変じていく。
ハルによる結界が今、ここに顕現されたのである。
結界術により、虚空よりは一本、また一本と刀剣が顔を覗かせる。無数の刀剣はハルの後方にて整列を終えると、群がるイナゴの群れへと向け、その鋭い切っ先を一斉に差し向けるのだった。
丹田に意識を込めながらハルは、呼吸を深めていく。
周囲には機械仕掛けのイナゴの群れが三々五々で隊列を組んでいる。
彼らが背負ったプラズマキャノンはただの威嚇のための装飾ではない。ハルの直地に伴い、一瞬、無防備となったハルへと向かい、彼らは雨やあられと射撃を繰り出した。
しかし、今やハルにとっては世界は静止したにも等しかった。今や、閃光の一撃、一撃の軌道をハルは静止画をめくるようにして捉えることが出来たのだ。
閃光が瞬いたかと思えば、鋭い紫色の矢がハルの前方へと迫る。ハルを圧殺するように無数の光の矢が、まるで驟雨の様に横殴りにハルへと押し寄せたのだ。
しかし、ハルの心眼は、一見切れ間なく空を敷き詰めたかに見えた閃光と閃光の間に生まれた間隙を、具に見定めていた。
わずかに身を側方へと捩じれば、閃光は、ハルの側腹部のわずか上方をすべるようにして後方へと走り抜けていった。
左右に身を振りつつ前方へと足を踏み出せば、閃光は、最早ハルを掠めること叶わず、虚空を打ち抜き、左右へと霧散する。
時に、後方に展開した剣の乱舞で時に放たれた閃光を切り払う。
わずかに背を逸らせば、眉間を撃ち抜かんと迫る紫色の閃光が、彼方へと走り去っていった。
GLMストークによる一斉射撃は、そのすべてが空を切った。
そうして鮮烈な光の雨が過ぎ去れば、残るh、無傷で立つハルと言葉を失ったように立ちすくむばかりのイナゴの群れのみ。ここに、敵の群れに完全なる隙が生まれたのだ。
「境界形成――」
ハルがぽつりと呟けば、大気はまるで沸騰したかの様に粟立ち、熱っぽく震えだす。
遠巻きにハルを包囲する機械の軍団の中へとハルはさらに一歩を踏み出した。
わずかに腰を落とし、ついで剣の柄に指を一本、また一本と絡みつけていく。
「状況を開始する――」
両の眼で鋭くイナゴの群れを担見据えすえながら、言い放つ。
流れるような挙止で腰元の剣を抜刀すれば、氷の様に澄んだ刀身が、鞘を滑り抜け、虚空を一閃した。
剣の一閃を呼び水に、ハルの後方で宙を揺蕩うばかりだった無数の刀剣が、一斉に奮いだす。無数の剣が絢爛たる乱舞でもって空中で踊り狂い、ついで、イナゴの群れを一斉に強襲する。
銀閃を瞬いたかと思えば、機械仕掛けのイナゴのもとに剣が去来する。
刀剣は、イナゴの胴部を自らの剣戟の間合いに捉えるや、寸分たがわずに箱形の胴部を刺し貫いていく。
一機、また一機と機械仕掛けのイナゴの箱形の胴部を剣が貫く度に、鉄の巨体が項垂れるようにして、胴部を地表へと向けて、傾けた。
だが、剣による敵の殲滅は、ハルが使役したユーベルコード『閃花の境界・殲』の本懐に非ず。この秘儀の仕上げとは、この後に続く、ハルの念動力でもって完遂されるのだった。
ハルは鋭い視線でもって、剣に貫かれたイナゴの群れの間を見回した。
箱形の胴部に突き立てられた剣は、墓地にて散見される十字の墓標に酷似して見えた。剣の一本一本に自らの思考を送るのだ。
意識を集中させ、剣に貫かれた敵兵、一機一機へとハルは精神波を送り出す。瞬間、ユーベルコードの奇跡の光は、ハルの思念と混ざりあい、ここに一つの特殊な力場を形成する。
剣によって貫かれ、命を絶たれたはずのイナゴの一体が攣縮するのが見えた。わずかな収斂はすぐに振動へと変わり、ついで体動へと変化した。項垂れていたイナゴの胴部が軋みを上げながらも前方をむき、多関節よりなる大足が、軽やかに大地を踏み鳴らし始めた。
一体、また一体と剣で刺し貫かれた機械のイナゴが、体動を開始していくのがわかった。彼らは、両の足で大地を力強く踏みしめると、円を描くようにして後方へと振り返り、丘陵地帯へとなだれ込む友軍の前に立ちはだかった。
全ては、『閃花の境界・殲』によってなされた再誕ともいえるだろう。
奇跡の御業『閃花の境界・殲』が作り出した力場とは、いわば、ハルによって形成された支配の領域ともいえるだ王。
そう剣によって刺し貫かれたすべての機体は、支配権をハルによって完全に掌握されることで仮初の命を得るに至ったのである。彼らはハルの繰る精神波によってハルの傀儡と化したのである。
結果、ここに敵軍同士による同士討ちが幕を開ける。
戦場に乱れ飛ぶ紫色の光弾が山野の至る所で、火の手を上げた。光弾に飲み込まれるようにして、イナゴの群れが続々と大地の上に崩れ落ちていく。
イナゴの群れは互いが互いを己が砲撃で打ち砕きながら、ますますに数を減らしていく。イナゴの大群に阿鼻叫喚の混沌が襲い掛かった。
もちろん、敵軍の混乱に乗じない手は無い。ハルは、自らが使役するイナゴの軍勢と共に一挙に敵陣へとなだれ込んでいくのだった。
この敵部隊での同士討ちにより、防衛部隊側は一気に攻めあがる。
ハルに続き猟兵らによる攻勢が勢いをまし、更にアンドレイらスナイパー部隊による斉射が数多、敵軍を飲み込んでいく。
当初、陥落は時間のものと思われた丘陵部の陣野は未だ健在なままである。対して、敵軍は徐々に徐々にとだが数を減らしていく。
そして――、ここに両者の均衡は、第三者の介入により崩れ、戦いは終幕に向けて加速度を増していく。
ハルの『閃花の境界・殲』により敵部隊は完全に混乱の中へと叩き落された。
だが、それでもなお、敵軍は未だに二千ほどの残存兵力を残していた。
敵軍は、つぎはぎだらけながらも、長い縦陣でもって布陣を続けていたし、司令官を失い、末梢神経たる指揮官の多くを失うことで、統率は失われつつあったが、それでもなお敵は戦線を維持するだけの体裁は整えていた。
この数こそがイナゴの大群にとっての頼みの綱だったのだ。
兵力に頼ることで、GLMストークは余喘ながらも攻勢を続けることを可能としたのだ。
すでに猟兵たちはユーベルコードの力を使い切っていた。となれば、この攻勢が続けば、防衛部隊の中には死傷者が現れる可能性は十分にあり得たのだ。
だが――、現実は少なくともGLMストークらの期待に応えることはありはしなかった。
ハルの元、群がるGLMストークの陣の一角で、突如、炎柱が舞い上がるのが見えた。
いぶかしく思ったハルは、振りかざした刀剣をいったん止め、そうして耳を澄ませる。じぃんと、地響きのような振動音が闇の彼方より響いて聞かれた気がした。
音の出どころへとと向かい、ハルが山野の左方へと目を遣れば、地平線の彼方より人影が一つ、二つと浮かび上がるのが見えた。そして、一つ、二つと浮かび上がった人影は、徐々に徐々に数を増してゆき、ついぞ、地平線の彼方を埋め尽くす膨大な白光となって平原を照らし出すのだった。
地を揺らす振動音はますますに音量を増し、次いで、振動音に交じって火砲が激しい唸りでもって空を揺らした。
「第三軍…ですっ! 救援です。味方の――救援ですっ!」
丘の上より、男の声が響いた。
振動音が果たして何故、齎されたのか、喜色を滲ませながらも響き渡る男の声が、すべてを物語っているようだった。
ここにハルの疑問は氷解するに至る。
地平線の彼方が赤く染まったかと思えば、山野には砲撃が赤い雨となって降り注ぎ、続々と群がるイナゴの軍団を撃ち抜いていく。赤い雨の洗い出されるようにして、鉄の残骸が、山野へとあふれ出していく。
「どうやら、我々の勝ちのようだな――」
爆炎が、イナゴの群れを薙ぎ払っていく。立ち上がる黒煙のもと、辛うじて保たれていた敵陣が徐々に厚みを減らすのが見えた。
地平線の彼方よりは、大挙して友軍機が姿を現すのが見えた。
人型決戦兵器と及ばれる、銀白の装甲に身を包んだ機械の騎士より大軍勢がハルの側方より敵の陣容に向かい突撃を繰り出すのが見えた。
彼らは、一糸乱れぬ連携のもと、一機また一機とイナゴの群れの中へと一斉になだれ込んでいくと、その手に携えた銀槍でもってイナゴ達を切り伏せていく。
結果、銀色の閃光が空に一閃すれば、イナゴの大群が崩れ落ちる。
瞬く間に、敵の陣容が絹かなにかを裂くようにして細切れに分断されていくのが見えた。
そう、DIVIDE直轄英国第三軍による精鋭部隊による強襲が、今まさに敵軍の横腹を刺し貫いたのである。
敵軍は、今や前方をハル達猟兵らによる分厚い鉄壁に前進を阻まれ、そうして無防備にさらけ出した横腹を左方より去来した第三軍により撃ち抜かれる格好で包囲されるに至ったのだ。
ハルは戦術学や用兵術にさほど精通しているわけではなかったが、完全な協調のもと行われた包囲攻撃がどれほどの威力を発揮しうるかは肌感覚で理解できた。
今まさに敵軍は包囲殲滅の網の中にある。
そして、事実敵軍は、、急激に数を減らしつつあった。
ふぅと、ハルは再び剣を振り下ろすと、目前の鉄のイナゴを一刀両断する。
「だが…私たちもまだ手を止めるつもりはないぞ…? なにせ誰一人として死なせはしないのだからね」
炎柱が舞い上がり、火の粉が赤々と夜空を化粧していた。敵軍の混乱は今や恐慌へと姿を変え、僅か前まで二千程度を残した敵軍は、もはや、陣容を整えらぬほどに数を減らしていく。
ハルがさらに敵のイナゴを数機ほど切り伏せた時、すでにハルの周辺には残存する敵の姿は見受けられなかった。イナゴの残骸が山となって、山積する存在するだけだった。
顔をあげて戦場全体を俯瞰すれば、山野を黒一色に塗りたくっていたイナゴの大群の姿は、霧を晴らしたように姿を消していた。
そう、ハルたちが前線を支える間に第三軍による突撃により、敵軍はついぞ壊滅へと至ったのだ。
今や、戦場には機械仕掛けのイナゴが発する歯ぎしりの様な異音は鳴りを潜め、救援に駆けつけた第三軍の人型決戦兵器による駆動音だけが、静観と佇む夜空にこだまして聞こえた。
ふと、後方を見やれば、そこには肩で息をしながらも、誰一人欠けることなく空を臨む友軍の姿があった。
猟兵達を含め、防衛部隊の面々はみながみな、一様に疲れ果てていたし、軽症者の姿は数多く散見された。だが、死者や重傷者の姿は一人として確認されはしなかった。
さらに丘陵地の後景よりは、空へと向かい幾条もの白煙が立ち上り、刷毛で掃きだしたような、無数の糸くずとなって空に心地よげに揺蕩うのがわかった。
白煙に交じり、ふと山間より人々の和やかな声が響いて聞こえた様な気がした。山間よりこぼれ出した、柔らかな人工灯の揺れめきを眺めながら、ハルは安堵のため息をつく。
ここに、『レヴィアタン』復活の前哨戦は、猟兵側の完勝により、幕を閉じたのである。
大成功
🔵🔵🔵
第2章 冒険
『嗚呼、栄光の地方防衛隊』
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
かつて、一機のダモクレスが存在した。
名をアモン・ラーという。機械神『レヴィアタン』の麾下の悪魔たる指揮官が一機は、かつて、英国の片田舎にて、人類に対する一大会戦に挑んだ。
『レヴィアタン』とDIVIDEの戦いの中で、ついぞ『レヴィアタン』が封印されるに至るまでアモン・ラーなる悪魔は、多くのケルベロスの命を奪ってきた。
ついぞ『レヴィアタン』が封印され、そして、デウスエクスの大軍が壊滅に至っても尚、殺戮を繰り返してきたこの悪魔は――、しかし、とある山村の心優しき夫婦一家に命を助けられ、人の愛を知ったのだ。
人の愛を知り、アモン・ラーは世を去った。そしてアンドレイ・ヴィリキツキーなる番犬が生誕したのである。
「明朝に全軍をもってレヴィアタンを強襲する。二の足を踏み、守りに徹すれば同様の機会が起きかねなかろう? アンドレイ大尉、貴殿は一時的に俺の参加に入れ。いかなる理由にせよ、貴殿は持ちこたえたのだ。その実力を俺は買っている」
金色の瞳が、アンドレイの目の前で揺らめいている。
男が女か、そんな事を議論するのはまるで無粋とでも言うべきか、目前には古代の神々を象ったような、若き青年の姿があった。
蠱惑的に揺らめく、切れ長の猫目がアンドレイを正面に見据えた時、しかし、アンドレイは青年の美貌に反し、彼の中でそっと息をする底知れない野心に翳りを確かに見た気がした。
「お言葉はありがたく頂戴します。ラファエル大将――。しかし、私たちが無事に街を守り切ったのは、一重に第三者による援軍があった故です。最も、将官にとっては、この村は命に変えても守るべきものです。なればこそ、非才の身ながらも、明朝の作戦には私も従事させていただきます」
ラファエルなる男の素性はおろか骨型をアンドレイは知る由は無かった。
だが、当意即妙の戦術眼により、この男はこの優しい街を救うために、救援を送ったのだ。
ならばこそ、自らの命を託すに価値ある男だと、アンドレイの直感が告げていた。
「助かるぞ…、アンドレイ。貴殿の部隊は特に疲弊していよう?ならばこそ、今日はこの山村にて英気を養うがいい。明日の貴殿らの活躍に期待するぞ」
言葉短めにラファエルが告げる。
アンドレイは敬礼と共にラファエルなる稀代の天才戦術家に謝意を告げると、そのまま彼の幕舎を辞した。
速足気味に山村へと戻れば、夜も深まり、宵空には宝石の星々が瞬いて見えた。
まるで先刻のデウスエクスの強襲が夢か幻であったかの様に山村では、熱に浮かされたかのように、未だ談笑する人々の姿があった。
第三軍によっても緘口令が敷かれているのだろうか。彼らは先のデウスエクスの襲撃など露も知らぬ素振りで、平素と変わらぬ陽気な態度で街に練りだしては、酒や宴に興じているようだった。
娯楽の少ない山村ゆえの長閑な風景がアンドレイの目の前には広がっていたのだ。
ほっとアンドレイは安堵の吐息をついた。
一重に、この平穏があるのは、突如、アンドレイらに加勢を申し出た謎の独立部隊の存在があったからこそだろう。戦いが終わって後より、彼らの姿はついぞ見かけられなかったが…しかしこの平穏は彼らの助力なしにはありえなかった。
明日、アンドレイらは封印デウスエクス『レヴィアタン』との戦いに赴く。
一切の血を流すことなく、敵のデウスエクスの大軍を破った故に、『レヴィアタン』は仮に復活したとて本来の力を発揮することは出来はしないだろう。
さりとて機械神の名を冠する、かのデウスエクスが一筋縄に討伐出来ない強敵であることは、かつて直属の部下であるアンドレイは嫌というほどに知りえていた。
アンドレイは遠方より、山村をしばし眺めていたが、すぐに踵を返すと自らの部隊の宿舎へと辞するのだった。
『レヴィアタン』との決戦まで、残すところ、時間は八時間を切る。
―――――――――――――――――――――――――――――――
第二章は、『レヴィアタン』との決戦前にて、猟兵の皆様はご自由に過ごしてくださいませ。
・山村で村人たちと接触
・第三軍(以下に記載しています)のメンバーで気になる人物と接触する。
→ex)ラファエルと戦術談義、アンドレイを労う…、姫川とお酒で乾杯などなど。
・戦いに向けて、決心を固める
→合わせプレイなど想定されている場合は、こちらもご検討ください。
・万全を期すために、翌日の戦闘に向けて事前に準備を整える
などなどご戦いまでの時間をご自由にお過ごしください。
以下にポジションや二章にて接触可能なキャラクターについて記載します。
【神英戦争】のタイトルが付記されたエピソードに登場した第三軍所属の全兵員が今回、山村へと駆けつけました。
二章/三章ともに、同行するDIVIDE部隊は以下の面々となります。
二章では、会話パートが主体となり、決戦配備の能力は適応されませんが、一応、三章における効果を下記に付記しました。
基本的には通常の決戦配備とほぼ同様の効果となりますが、名前付きのキャラクターを決戦配備に選ばれた場合は、テイストとしてやり取りなどを描かせていただきます。
Cr:ラファエル・サー・ウェリントン:
→美貌の天才司令官。第三軍の総司令官です。常に前線に赴き、陣頭指揮を執ります。
優れた用兵家であり、人型決戦兵器(支援ロボをキャバリア風に改装したもの)による奇襲戦術の大家でもあります。
Df:イゾルデ
→皮肉げな、褐色肌の美丈夫。第三軍の副司令官にあたります。一般部隊を指揮し、主に防御面で支援します。嫌煙家であり、たばこは苦手な酒豪。
Cs:ゆきむら&カエシア
→風貌体裁の怪しげな自称ベテランケルベロスと、女子高生ケルベロスの子弟コンビです。カエシアが魔術結界を張りめぐして、支援に当たります。
Jm:ファレル
→個の武勇に関しては英国軍最強とも目されています。2mを超える偉丈夫で、戦斧をもっての突撃により敵部隊へと混乱をもたらします。
Md:姫川・沙耶
→医師であり、どこか浮世離れした風変わりな女。結界術や回復魔術でのサポートを主体に、仲間を援護します。
Sn:アンドレイ・ヴィリキツキー
→もと、デウスエクスとして地球侵略の尖兵として戦っていましたが、人の優しさに触れ人の心を得ると共に、ケルベロスとして覚醒しました。射撃に関しては右手に出るものはなく、正確無比な射撃はありとあらゆる標的を寸分たがわずに撃ち抜きます。
 トーノ・ヴィラーサミ
トーノ・ヴィラーサミ
【双狗】
◎
連携⚪︎
決算配備:DF
さて、まずはひと段落、といったところでしょうか
とはいえこれはあくまで前哨戦
気を緩めすぎる事なく、されど英気を養う重要性も忘れずに
などと考えつつ、新月さんと手分けをして周囲の様子や改めての作戦、陣営の確認など情報収集を行います
ユーベルコードを使用し先の戦闘で変化した周囲の地形などについて下調べをしたうえで…
ふむ、そうですね
では此度の防衛の要ともなるであろうイゾルテさんと少しお話が出来ればと
防衛に長けた方と伺っております
彼から見た先の戦闘についての感想や、この後の戦いでどのように動かれるおつもりか、などうかがえればと。
味方として連携することもあるでしょうし、ね
 月隠・新月
月隠・新月
【双狗】
◎
決戦配備:Cs
トーノさん(f41020)と手分けをして【情報収集】を行います。
まずは【ブランクオベリスク】で周囲の地形等を調査しましょう。
俺はカエシア・ジムゲオアさんに会いに行きましょうか。少し前に共闘しましたが……ジムゲオアさんには大きな伸びしろを感じましたので。明日に向けて今の力を確かめさせてもらいたいのです。味方の戦力把握は大切ですからね。
……しかし、今もゆきむらさんは自分をケルベロスと偽っているのでしょうか。ケルベロスにはすぐにわかると思いますが……まあ、お二人の問題ですからね。必要そうであれば、無茶はしないよう伝えましょう。
トーノさんとも情報の共有をしておきたいですね。
●
空を仰げば、群青色に塗りたくれた宵空が、凍り付いたような表情でもって、トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)に迫ってくる。
氷とも海とも見紛う宵空のもと、中天にかかった三日月は、艶のある青白色を湛えていた。三日月より、ぐるりと視線を泳がせ、空を一望すれば、宝石の様に鮮烈な光を上げる白点が、無数、夜空に瞬いているのが見えた。
そこに星々があった。宝石を彷彿とさせる白光を湛えながら、数多の星々が夜空に張り付き、柔らかに地上を見下ろす星明かりが夜空を彩っていたのだ。
今、地上は、三日月の放つ妖艶たる銀青色の月光と、無数の星々より降り注いだ星明りとによる幻燈の輝きによって、淡く照らし出されていた。
山野は静謐と佇んでいる。
先ほどまでのデウスエクスとの戦いが、まるで嘘だったかの様に、音の絶えた山野には柔らかな緑の楽園が広がって見えた。
もちろん、デウスエクスとの戦いにより、大地には裂け目が散見されたり、クレータの様な巨大な陥没が穿たれたりしていた。
木々や緑は焼灼され、地肌のむき出しになった土石の大地が山野の至るところで散見され、未だ、撤去作業が一向に進められていないデウスエクスの残骸が、宵闇の抱擁の中で山野のあちらこちらに浮かび上がって見えた。
だが、星光は戦いの傷跡を優しく内包しながらも、ただ静かに山野を飲み込んでいたのだ。
デウスエクスとの戦いの傷跡もまた早晩、色褪せ、そしてすべては過去との中に埋もれていくのだろうと、この山野の光景を前にした時、確かな想いでトーノの中に去来していたのだ。
命が繋がれてゆく限り、いかなる傷跡もいずれは癒されていくのだ。
トーノは、草の大地を前脚で踏みしめると、暗闇が立ち込める丘陵地帯のもと、トーノは視線を闇の中の一点へと固定した。
地平線の彼方まで伸びる草の海へと視線を這わせ、そのまま遠景へと移していけば、草原は途切れ、かわって北方へと向かうに従い大地は緩やかに傾斜してゆきながら、小高い山稜地帯を形成していく。
まるで城塞かなにかの様に、ごつごつとした山肌をそびやかしながら、山岳地帯が水平線の彼方に蓋をしていた。
トーノの視線はただ静かに丘陵地帯の一点へと注がれていたのである。
かの山岳地帯に、トーノは迫りつつある戦乱の芳香を嗅ぎつけていたからだ。
敵の先遣部隊による襲撃は未然に防いだ。
まずは状況はひと段落、といったところだろう。
無血にて初戦を勝利で飾ったことに対する達成感はもちろんだが、感情面を排し、仮に作戦レベルで現状を分析した時、市民の命が一人とて失なわれない現状は、今後の戦いにおいてもまた重要な意味を持つ。
機械神『レヴィアタン』は、今まさにトーノが凝視する山岳に封印されている。
そして、『レヴィアタン』が機械神なる至尊の冠を頭上に戴くためには、無数の人々の血と肉を必要としたのだ。そう、人々の無数の屍の上に、暴虐たる王の戴冠ははじめてなされるのである。
しかし、トーノらの奮戦により、『レヴィアタン』は自らが糧とするべき贄を失った。
必然、機械神『レヴィアタン』は不完全な状態での復活を余儀なくされるだろう。
そして、トーノは、かの機械神が所在する根城の正確な位置をすでに突き止めることが出来ていた。そう、トーノの第二の眼は、今、機械神の巨体を確かにトーノの網膜へと投影していたのである。
数多の影が、宵闇の沈む草原を横切った。
風の凪いだ草原では、草木は眠り、野鳥や獣の類の存在すらも見受けられなかった。
人々の息遣いは、トーノが所在する丘陵の後方より、陽気に立ち上った白煙と共に感じられていたが、眼前に広がる山野には人の姿なと影も形も見受けられなかった。
しかし、今、山野には蠢く無数の影がある。
人や獣とは形態をまるで異とする無機物が今、荒野に数多、溢れていたのである。
薄闇の中、尖塔のようなものが、縦横無尽に山野を三々五々で風の様に走りぬいていくのが見えた。
尖塔は、宵空へと向かい、丈高く背を伸ばしながら朗らかに揺れ動いて見えた。
数にして、尖塔は凡そ三百弱ほどを数える。
乳白色に塗り固められた尖塔が、おおよそ百五十柱ほど、燃えるような紅玉色で夜空を染め出す尖塔が、おおよそ百三十柱ほどの数で、夜の山野をわが物顔で泳ぐように駆け回っているのだ。
差し込む月光を全身にあびれば尖塔の鏡面の様に磨き上げられた表面より、反射光が青白い微光となって周囲に散乱する。
微光は、まさに猛きん類が持つ鋭い眼だ。
この光こそが、深い微睡の中にある山野を観察し続けていたのだ。
そして、この尖塔の一本、一本がまさにトーノにとっての第二の目でもあったのだ。
尖塔が山野を駆けてゆくたびに、トーノの網膜に映し出された映像もまた目まぐるしく変化していく。
時に、原生林の木立が網膜に浮かび上がったかと思えば、ついで、焼け野原となった草原の一部が映し出された。無数の映像信号が網膜に浮かび上がり、それらは、視神経を介して、電気信号となってトーノの脳裏へと確かな映像を投影していく。
めまぐるしく変転する視野情報こそが、尖塔が齎した情報の濁流なのだ。
これら一つ一つを処理し、統合することで、今、トーノの脳裏には山野の全容が一枚の立体像として浮かび上がりつつあった。
そう、元来の肉眼にて得られた実像と、計百三十ほどからなる尖塔によって絶えず送られてくる膨大な視野情報によって山野の全容が、トーノ中で徐々に徐々にと形成されつつあった。
尖塔こそが、トーノによる、ユーベルコード『ブラッドオベリスク』の産物であり、第二の眼であるのだ。
『ブラッドオベリスク』とは、ただの矛に非ず。そは真実を見抜く雄弁たる光の象形にこそ本質はある。
この無数の目による監視網こそが、遠景にありながらも、トーノにおいて山野の地形を詳細に脳裏にて描き上げることを可能とせしめたのである。
そして、この監視網こそは研ぎ澄まされたトーノの刃であり、次戦への布石でもあった。
デウスエクスの第一の牙は、緒戦において完膚なきまでに粉砕されたと言えるだろう。万余を超えるデウスエクスは今や、戦場の露と消えた。
もちろん、先の大勝利は喜ばしいものであったが、GLMストークの大軍との戦闘は、あくまで前哨戦の範疇を超えるものでは無かった。
決定的な戦いで敗北を喫すれば、緒戦の勝利によって積み重ねられた戦術的優位性などは直ちに失われる。
不完全な復活を遂げようとも、これよりトーノらが対峙するのは『機械神』の名を冠するデウスエクスであるのだ。一筋縄でいく相手ではない。
ゆえに、トーノは、そして月隠・新月(獣の盟約・f41111)の両名は、かの機械神との戦いに備え、戦場の地形を把握することを優先したのだ。
勝って兜の緒を締めよとは言うが、トーノは戦いの趨勢を決するであろう次戦に備えて万全の状態を整えるべく行動を決定したのである。
そしてトーノや新月の行動は功を奏した。
生み出された監視網は、山野の状況を、トーノの遠景で屹立する山奥に巨体を横たわらせる一頭の巨大な鯨を確かに発見したのだから。
鯨は山はあろう程の巨体を微動だにさせることなく、戦いに備えてか、静かに身をうずくまらせているだけだった。
かつての戦いの激しさを物語るように、銀の光沢を帯びた装甲部は所々が剥がれ落ち、つぎはぎ状になった鋼鉄の皮膚の元、物々しい計器類や毛細血管の様に張り巡らされた導線によって構成された機械仕掛けの内臓組織が、鯨の随所から見受けられた。
傷だらけの巨体がそこにある。だが、それでもなお、大鯨が齎す威圧感は並々ならぬものがあった。
オベリスクよりの視野情報より間接的に機械神『レヴィアタン』を目にしただけで、彼が腐っても機械の神を名乗る理由が理解できた。かの機械神はただ一機存在するだけで戦況を覆すほどの能力を秘めているだろうことが、トーノには否応なしに伺われたのだ。
神とは万物を創造する。
そして彼が神なる不遜の名を負う理由が、今のトーノにはなんとは無しに理解できる気がした。
穿たれた傷跡の奥、機械仕掛けの大鯨の巨大な内臓の中で、なにかが蠢くのが見えたのだ。
蠢動する黒点をじっと伺えば、そこには先の戦いにて打ち破ったGLMストークと姿かたちを同じくする、無数の機械兵の存在が伺われたのだ。
そうだ。
『レヴィアタン』とは、ただの戦術兵器に非ず。
それ自体が、無数の機械兵を生み出す生産工場であり、国であるのだ。
つまり、トーノらは、再びの会戦において無尽蔵の兵と戦うことを覚悟しなければならない。
ふっと小さく嘆息とも微笑ともつかぬ吐息が、トーノの口元から零れていた。
理知を湛えた紺碧の瞳は、瞠目がちに見開かれ、瞳孔の奥で微笑の影がわずかに揺らめいた。
敵は強力ある。とはいえ、事前の偵察により『レヴィアタン』のカラクリは知ることはできた。
そして、大鯨の明らかな弱点をもトーノは戦闘に先んじて知りえたのである。
大鯨の背部にて大口を開けた傷跡の奥、幾つかの障壁を挟んで、レヴィアタンが有する生産工場が顔を覗かせていた。この綻びを突き、『レヴィアタン』内部の生産工場を破壊することさえ出来れば、敵の生産力という優位性を奪うことも不可能ではないだろう。
さらには先の戦いで凹凸に隆起した山野における詳細な地形図をもまた、トーノと新月は得ることが出来た。
明朝のレヴィアタン攻撃にあたり、トーノと新月が得たこれら二つの情報は間違いなく有益となるだろう。
思索を深めながらも、トーノは、意識を集中させ、再び尖塔を駆け巡らせる。
尖塔は、降り注ぐ星々のシャワーを身にまといながら、草木をかき分けつつ夜の草原を駆けてゆく。
草の大地をかき分け、地表に走る幾条の亀裂をうまく踏破し、陥没した大地を走り抜けていく。
そのたびに、トーノの網膜には山野の全体像が細部にわたるまで映し出されていった。そうしてついぞ、山野の全体像が一枚の青絵図として製図されたところでトーノは左方へと首を傾けた。
トーノの左隣、トーノの挙止に続き、新月が鷹揚と首を動かすのが見えた。
宵闇が暗く立ち込める中、艶のある漆黒のたてがみが、黒絹の瀟洒さでたなびくのが見えた。
銀白色の瞳は、澄んだ湖面の様に落ち着き払っていた。沈着さと怜悧さを湛えた視線が、雄弁たる意思の光でトーノを貫いていた。
トーノは口火を切る。
「新月さん。山野の状況はおおよそあぶり出すことことが出来ました…。そちらはどうでしょうか?」
トーノが言えば、感情の起伏に無縁たる銀色の瞳がわずかに細められるのが見えた。新月の凛然とした声音がトーノに続く。
「こちらもおおよそは把握できました。山野は先の戦いで大きく変貌しているようですね。更には敵軍の残骸も数多、残っています。やや悪辣かもしれませんが、利用できるものはすべて利用すべきだと俺は思います。第三軍の布陣の際には彼らの残骸を防衛壁として役立てることができるのではないでしょうか」
新月が、要点を掻い摘んで答えた。
彼女の言葉は常に的を得ている。凛とした声音も相まって、彼女の言葉の一言、一言はしみ込むようにしてトーノの中へと溢れていくようだった。
相槌を打ちながら、トーノもまた声音を弾ませて応える。
「えぇ、私も同様に考えます。して、新月さん…陣取るべき最善の位置とは?」
トーノは、再び新月へと問答する。
いわばこれは半ば予想の見えた、答え合わせだった。新月は、彼女の明晰さの示す通り、常に模範解答を導き出す。そして、トーノには新月が間違いなく、自らと同様の答えを用意してみせるとの確信じみた直感があった。
そのうえでトーノは、自らと新月、両者の解答を細部まで照応し、わずかな齟齬を修正することで最適解を模索したのだ。
一瞬、新月が視線を落とすのが見えた。
彼女はわずかの間、何かを沈思していたが、すぐにトーノへと視線を戻すと、間髪入れずにに口を開く。
凛とした声音が宵空へと再び、りぃんと響いた。
「…そうですね。『レヴィアタン』が北方の山脈にて身を隠していることを考慮するならば、やはり、位置は麓でしょうか。ここならば、第三軍の砲台も敵部隊を捉えることが出来ますし、なにより先の戦いによる敵軍の残骸も数多存在します。これを障壁として利用しつつ、『レヴィアタン』の襲来に備えるべきでしょうかね」
新月の答えに、たまらず、トーノの口端が綻んだ。
口端から零れた白色の犬歯が月光を浴びて、生き生きと輝きだすのが自分でもわかった。
「新月さんも同様に考えていましたか? 私もまったく同様に」
彼女の解答は、トーノが導き出したものとぴったりと一致していた。
トーノは滔々と言の葉を重ね、ブラッドオベリスクの偵察にて得られた情報を新月へと伝えていく。そう地形の解像度を高めていくためだ。
レヴィアタンの状況はもちろんのことだが、互いが互いに見落としかねない、些細な情報を口頭で補足しあいながら、山野の輪郭を確かなものとする。そうしてトーノと新月はしばし情報を交し合いながら、両者の足りない情報を付け足していく。
空白のピーズは瞬く間に埋まっていく。
両者のわずかな確認の後、ついぞ、トーノの百三十の眼と、新月の百四十を上回る眼によって得られた視覚情報は、完全なる山野の立体像をここに塑造するのだった。
すでに尖塔は姿を消し、山野には艶のある暗がりが横たわっていた。
だが、今のトーノには、無数の眼は無くとも、山野の細部に至るまでを完全な形で見渡すことが出来るようだった。
この情報は間違いなく、明日の戦いの雌雄を決するだろう。となれば、この新鮮な地形図をあとはいかにして第三軍に知らせるかが問題となる。
「あとは…状況を第三軍の首脳陣へと伝えるだけですか――。さて、どうしましょうかね、新月さん?」
トーノは言った。
先の戦いで、共闘したアンドレイ青年を頼るべきだろうか。
かの青年には好感も持てたし、明日の戦いにおいて、青年が重要な役割を担うであろうことは容易に予想された。
とはいえ、戦いの全権を握るのは総司令官であるラファエル・サー・ウェリントンであり、彼を支える褐色の美丈夫イゾルデである。
また、アンドレイは、ラファエルの指揮下の兵ではない。となれば、可能ならば、ラファエル、イゾルデのいずれかと直接接触した方が、より手間が省けるというものだ。
また、トーノとしては、イゾルデらの戦術眼がいかほどのものであるのかという事に対して興味が無いわけでは無かった。
いずれにせよ、可能ならば直接に首脳部に面会できれば吉との思いがトーノにはある。
しかし、沈黙がちにうつむけど、足元には茶褐色の大地が広がるばかりであった。
答えなど出ようはずもない。
しかし、トーノの沈黙は、再び、闇夜にりぃんと響いた声音により直ちに破られることとなる。
「ツテというほどではないのですが…やりようはあると思います。少し気になっていることもありますし。よければ同行してもらえますか、トーノさん? 直接、第三軍の司令本部へと向かい、司令官に面会しましょう?」
頭をあげて新月へと見やれば、新月が静かに会釈するのが見えた。
彼女は小さく頭を下げると、トーノに先行し、丘陵地帯から山村にかけて巨大な陣を構える第三軍の陣野へと一歩を踏み出した。
トーノも彼女に続く。
思えば、新月はこれまで英国での戦いに幾戦も従事してきたと聞く。
となれば、彼女もDIVIDEを支える一人として第三軍で認知されていてもなんら不思議は無い。
しばし、トーノは新月と共に歩を進めていった。
丘をめぐり、野営地へと足を踏み入れた。
無数に張り巡らされた天幕や、溢れかえった兵士らの間を縫うようにして奥へと進んでいけば、新月とトーノは、第三軍の首脳陣が集まるやや豪奢な装飾のなされた陣幕へと直ちに到着するのだった。
ふと陣幕の入り口付近を見やれば、怪しげな風貌体裁をした妙に顔立ちの良い男と、内省的な光を湛えた三白眼をおっかなびっくりといった様子で見開きする高校生くらいの少女の姿が伺われた。
新月は二人の前に立つや、なにやらを告げる。男がどこか演技かかった大仰な挙止でもって新月に受け答えするのが見えた。
隣立つ少女は、新月と妙に顔立ちの良い男の間で視線を行ったり来たりさせながら、黙って二人の言葉に聞き入っているようだった。
男は決して大物には見えなかったが、新月とのやり取りを終えるや、軽薄そうな声音でもって、新月やトーノへと声掛けして、第三軍の副司令官たるイゾルデのもとへと二人を足早に案内するのであった。
こうしてとんとん拍子で、トーノ、新月の両名は、第三軍副司令官イゾルデとの謁見を果たしたのである。
●
「なるほど――。貴殿たちの獅子奮迅の活躍にまずは敬意を表したい。そして同時に、貴殿の慧眼ならびに敵の所在に関する報告に関して、気まぐれな我らが姫閣下司令官に代わり、副司令官よりイゾルデから謝辞を送らせていただきましょう。ようこそ参られた、ミスタートーノ、ミス新月」
濡れた様な黒真珠の瞳が、心地よげに揺らめいていた。
月隠・新月(獣の盟約・f41111)、トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)の両名が、司令官の陣幕へと通されるや、二人を出迎えたのは、褐色肌が鮮やかな偉丈夫であった。
皮肉げな双眸をいかにも愉快気に綻ばせながら、褐色肌の青年は歓待でもってトーノを、そして新月を迎えたのである。
そう、彼がイゾルデだ。
まるで舞台役者を思わせる整った面差しを輝かせながら、豪奢な勲章を装飾した軍服に身を纏った二十代後半くらいの青年が、穏やかな微笑と共に、新月らの前に立っていた。
歓迎の一言と共に副司令官たるイゾルデは、傍らに立つ近習に足元に絨毯を敷かせると、席を立ち絨毯の上に腰を下ろす。
トーノ、新月もまた、絨毯の上で後ろ足を折り、鄭重に絨毯の上に腰を沈めると、膝を詰めて、イゾルデの招きに応じるのだった。
互いに軽い紹介を済ませるや、トーノが口火を切る。しっとりと響く重低音が海鳴りの様に室内へと響いてゆく。トーノの声色や理知的な話しぶりが気に入ってか、皮肉げな貴公子は、トーノの言葉に聞き入っているようだった。
一言をトーノが語ればイゾルデが嬉しそうに相槌を打つ。トーノが戦場の地形図を詳細に語れば、イゾルデが瞠目する。そうして、トーノがついに『レヴィアタン』の弱点部について言及すれば、利発たる皮肉の貴公子は、目を見開きながらも、ついぞトーノへと質問を返すのだった。
トーノ、イゾルデの両者は声音を弾ませながら、互いが互いに言葉を交わしていく。
二人の話題は多岐にわたっていた。
二人の話題は、最初、野戦における防衛戦術の妙帝について始まり、徐々に、明朝における具体的な布陣について移り、『レヴィアタン』攻略に関する具体的な戦法にまで移行していった。
なるほど、トーノ、イゾルデ共にそれぞれが、片や武名を轟かせる勇士であり、片や優れた戦術眼を有した名将である。
才知に優れた両名は、性向的には間反対であったが、思考の明晰さについては、ほぼ同等というほどに優れた認識力や理解力を有していたのだろう。
両者は戦術論を皮切りに、直ちに意気投合したようだった。
イゾルデの物言いには、毒が滲みだしており、皮肉屋ならではの、鋭い棘の様な批評が、例えば英国第一軍や二軍に関して話題が移るような時などには、随所で顔を覗かせた。
しかし、さすがはトーノといったところだろうか。
物腰柔らかく、温厚であるかの紳士は、イゾルデの言葉に苦笑を浮かべながらも当意即妙の諧謔を交えつつ、闊達とした調子で、イゾルデの棘を包み込んだのである。
そんな二人のやり取りを横目にしながら、新月はただ二人の話を黙って傾聴するだけだった。
献策にせよ、状況の報告にせよ、淡白のきらいがある自らが行うよりかは、挙措も洗練された、英明闊達を絵にかいたようなトーノに任せた方が円滑にすすむだろうとの思いが新月にはある。
わざわざ口を開き、二人の会話に横車を押すのも無粋であろう。
自分の存在が、二人の歓談にとって有益となろうとは思えなかった。それならば、イゾルデとの折衝はトーノに一任し、自分は沈黙を貫いた方がよい。
新月の役割とは、一重に敵『レヴィアタン』の所在を突き止め、そして山野の現状を正確に見極めることにあった。もちろん、状況を報告するところまで想定はしていたものの、相手とうまく打ち解け、快活と談笑し、相手の内奥を引き出すというのはやはり自分の得意とする所ではないと思えた。
また、新月には、明日の戦いに臨み、確認しておきたい事案が無いわけでもなかった。ゆえに、新月は、イゾルデとのやり取りをトーノに任せると、自らは早々に陣幕を辞去し、野外へと向かうのだった。
帷幕を首でそっと持ち上げると、新月はそのまま陣幕の外へと身をさらした。
陣幕の外へと新月が一歩と前脚を進めるや、夜風が新月の黒い毛並みを撫でた。瞬間、新月は陣幕の傍らに立つ、人影に目がいった。
薄闇の中で、不明瞭な二つの人影が、新月の視線を受けて、びくりと身をすくみ上らせるのが見えた。
好都合とはまさにこのことだろうか。
なにせ、そこには新月が目的とする人物の姿があったのだから。
月夜に照らし出されるようにして、二つの人影は徐々に徐々にと鮮明に照らし出されていく。一つは長身の男であり、もう一つは小柄な少女のものであった。
幕舎の入り口付近で、石像かなにかの立ちすくむ二つの人影へと交互に視線を遣りながら、新月は小さく一揖する。
「幸村さん、カエシアさん――、ご案内をありがとうございました...。お二人は…ところでこちらで何を?」
青白い光の中で、三白眼と、切れ長の垂れ眼が輝いていた。
そう、瞳の輝きが二つの人影の正体を雄弁と新月に告げていた。
かたや、カエシア・ジムゲオアであり、もう一方がゆきむらのそれである。
カエシア・ジムゲオア、メンターゆきむらの両名は、月明かりの中でどこかぎこちなげに体を硬直させながら、新月を茫洋と眺めていたのだ。
おそらく二人は、興味本位から、トーノとイゾルデのやり取りに、外から聞き耳を立てていたのだろう。また予想の域は出ないものの、ゆきむらの主導で、カエシアも行動を共にすることを決めたに違いない。
最も、新月には、二人を叱責するつもりもなければ、詰問する意図も無かった。
ただ、平素と変わらぬ口調で淡々と二人へと尋ねたに過ぎなかった。
だが、しかし、当のゆきむら、カエシアと言えば、慌てふためいたように瞳を右往左往させながら、互いにぱちぱちと目配せするばかりであった。
ようやくして、まるで教師に叱責された生徒の様に、長身のゆきむらが、肩を落としながら項垂れた様な恰好で、言の葉を零した。
「いやぁ、探偵業が身に沁みついてしまいましてね…。情報聴取というやつでしょうかね――。えっと…あなたは確か…」
「あの時の――オルトロスのお姉...さん?」
ゆきむら、カエシアが交互に言い放った。
カエシアは、臆病そうな三白眼をぱちぱちと瞬かせている。喜色の光を湛えた眼はどこか懐かしそうな眼差しでもって、新月を眺めていた。
それにしても――。
再びお姉さんとは…。
確かにカエシアの面立ちは小顔であり、頬も柔和で、未だに少女特有の幼さを色濃く残していた。
しかし、廃校の探索時の状況から鑑みるに、カエシアもまた、今年で十七歳となるはずだ。新月とカエシアとの間には年齢の偏りはないはずだったが、新月へと向けられたカエシアの視線からは、若者より年長者に対して向ける一種、畏怖感と敬意の念とが複雑に入り混じった得も言われぬ感情の光がにじみ出して見えた。
新月が気にかけた存在とは、まさしく、カエシア・ジムゲオアこの人に対してである。
以前、廃校探索の際に共闘した折より、新月は彼女に戦士としての素養を見出していた。
底知れない潜在能力を有したカエシアは明日の戦いにおける戦力としてはもちろん、今後の英国第三軍、ひいてはDIVIDE全軍の中核を担う可能性を秘めていると新月は見る。
最も、能力が優れているとは言えどもカエシアにもまた不安材料が無いではない。内気であり、戦いに対して気おくれするようなところがカエシアにはあったからだ。
そして、現在の彼女の挙止からは才幹以上に不安材料こそがより際立って見えた。
ため息交じりに吐息をつきながら新月は両者へと一揖する。
「ご無沙汰しています。あの時は、自己紹介できませんでしたが、俺は新月。月隠・新月です...。この度も、先の戦いに参加させて貰いました」
そこまで言ったところで一旦、口を噤む。
まず、ゆきむらを一瞥すれば、妙に顔立ちの良いこの男は、取り繕ったように敬礼して新月に応える。
次いでカエシアへと視線を移せば、彼女はまるで小動物の様に身を震わせながら、緊張交じりに一礼する。
ふむと、頷いてからから新月は再び口を開いた。
「お二人とも、イゾルデさんとトーノさんのやり取りはうかがっていたと思いますので、既にご存じだと思いますが、明朝、機械神と呼ばれるデウスエクスとの間で戦端が開かれることと間もなく決まるでしょう」
滔々と新月が続ければ、さしものゆきむらも、神妙そうな顔つきで頷いた。
「そのようですね。ははは、任せて下さい、俺と…それから、カエシアが全力で援護してみせますよ」
ゆきむらが、端正な口元を綻ばせれば、白光する歯が、赤みを帯びた唇の隙間から零れだす。
妙に自信ありげに微笑む男から、新月は直ちにカエシアへと視線を移すと、今度は彼女を正面に見据えた。
ぴくりと、少女の華奢な肩元が震えだすのがわかった。
直ちにカエシアが、伏し目がちに視線を落とし、いかにも自信投げに瞳を動揺させるのが見えた。カエシアの視線が大地の上で力なく八の字を描きだす。
新月は、可能な限り声音を丸くして、端的に少女に尋ねる。
「そこで…その明日の戦いに備えて、一応、力のほどを確かめさせて頂きたいのです。味方の戦力把握は重要ですからね――、たしかカエシアさんは、キャスターとして味方の陣営の強化を主体に動かれるのでしたね? 一度、実際に見せていただけないでしょうか」
新月が尋ねれば、カエシアがわずかに顔を上げた。
少女の面立ちはこわばり、やや蒼白気味にひくついていたが、そこからは、新月に対する拒否感の様なものは感じられなかった。
しかし、パクパクと口を閉口させるばかりのカエシアからは、否応なしに彼女の緊張感が伝わってくるようだった。
内心で新月は首を傾げずにはいられなかった。先の戦いでは、彼女は強力なデウスエクスを相手にしても尚、勇敢に立ち向かっていたはずだ。
にも関わらず、今のカエシアと言えば、友軍の新月を前にして戦々恐々としているありさまである。
「大丈夫ですよ…新月さん。なっ、カエシア! メンターの俺もいるんだ。いつもみたいにやればいいんだよ。元天才ケルベロスの俺のお墨付きだ。まっ、軽く肩の力をぬいてな? 俺の言葉を信じろって」
にやりと口端を吊り上げてゆきむらが笑うのが見えた。男は明日の戦いがどれほど重要なものであるかなど存じていないのか、恬淡とした様子で目合図さえする始末だ。
どこからこの男に自信が沸いてくるのかは分からなかった。彼はケルベロスでは無かったし、異様に優れた頭脳だとか、人並外れて頑強な肉体などといったものとも無縁なはずだった。
だが…。
ゆきむらの掌が、カエシアのなで肩をがっしりと鷲掴みにした時、ふと少女の震えが止まった。
カエシアの小首がわずかに上方へと伸び、俯くばかりだった視線が、新月へと向けられた。
ただの一言。
そう、メンターと呼ばれる軽薄そのものの男の一言に、少女は鼓舞され、立ち上がったのだ。
まったくもって、少年少女特有の曖昧な感情の機微というものが新月には理解できなかった。
…だが、理解できずとも、感情の昂りが多くの者に、信じられぬ力を齎す事例を、新月はこれまでいくつも目撃してきたのもまた事実であった。
そして、なぜだろうか、理解できないとは分かりつつも、人々が義憤や他者への愛のために戦う姿が、新月には妙に眩しく感じられた。
深く立ち込めた宵闇の中で、少女の三白眼は優美に輝いて見えた。
カエシアが左手を伸ばすのが見えた。
白い陶器の様な指先が、闇を絡めとり、そうしてうすぼんやりと青く輝きだすのが見えた。
青ざめた微光がカエシアの指先よりこぼれ出す。それは白砂の鮮やかさにも、舞い散る青桔梗の花弁の美しさにも似た輝きで闇夜へと蒼い光芒を滲ませながら空中に六芒星を描き出していく。
「わかりました――。新月さん、これが…私の」
声を弾ませれば突如、六芒星より、青い光芒が豪雨となって周囲へと充溢していく。
微光の飛沫は、六芒星を、陣幕を中心に巻きおごり、空一杯に手を広げながら、丘陵地帯全体を包み込むようにしてあふれ出していく。墨黒の宵空が、柔らかな雨によって、束の間、蒼穹へと空模様を変じた。
光の雨滴は、青白い光で宵闇を照らし出しながら、すべてを穏やかに濡らしていく。
もちろん、新月とて例外ではない。
気づけば、新月のの漆黒の毛並みは降りしきる青い雨によりしとどに濡れていた。
暖かな雨だった。
翠雨を彷彿とさせる、溌剌とした生命の雨だ。
精神が研ぎ澄まされ、急に音が遠のいていくのが分かった。すべてが濃縮されてゆき、時間感覚が引き延ばされていくような錯覚さえ覚えた。
体内では魔力の奔流が濁流となって奔騰していた。
否応なしにわかる。
全てはこの光の雨が齎したものだ。
高騰していく力の源泉とは、少女が齎した光の雨によるものだ。
この柔らかな雨が、新月の力を限界まで賦活化させたのだ。
「文句のつけようもありませんね、ジムゲオアさん。すさまじい潜在能力と思っていましたが、予想を凌駕するものです」
感嘆交じりに呟いていた。
新月が言えば、カエシアが、面映ゆげに顔を赤らめた。隣立つゆきむらもまた、なぜか自信満々といった様子でうなづいてる。
徐々に光の雨は、雨脚を落とし、糸雨へと変わりついぞ、鳴り止んだ。
山野は、再び乏しい星明りで照らされ、暗がりの中には水を打ったような静寂が再び漂い始めた。
しかし、そんな闇夜の中で、少女の三白眼は、鮮やかな光彩を放ちながら、嬉々と輝いて見えた。少女のつぶらな瞳は、一心に彼女のメンターであるゆきむらへと向けられていた。
そこに浮かび上がるは、親愛の光か、それとも恋慕の揺らめきか、カエシア・ジムゲオアの複雑な胸中を、新月は露として伺い知ることが出来なかった。
少女が男に抱いた思いはもちろんのこと、果たして、カエシアは、ゆきむらの力の欠如を知悉しているのか。それとも、彼女は盲目的にゆきむらの言葉を頑なに信じているのか、そんな事さえ、新月が知る由は無かった。
おそらくケルベロスの力を有しているカエシアにならば、メンターと仰ぐ男がケルベロスの力を有さないただの一兵士であることを容易に察することが出来たはずだ。
しかし、彼女の真意を知りえるのはカエシア自信をおいて他にない。
だが、どうやら、彼女はゆきむらを必要としているのだ。
二人で一つ。
しかし、力の無い師と、才覚に溢れた弟子とが奇妙な紐帯で結ばれ続けているという事実を前に、なぜか新月は、穏やかに瞳を細めている自らの存在に気付いた。
カエシアは強い。そして、その力を十全に発揮するにはゆきむらの存在は不可欠だ。
「ジムゲオアさん、ゆきむらさん…。お二人ともどうかご無理なさいませんように。特にゆきむらさんは、ご無理はくれぐれもなさらないように。元は精鋭と言えども、今は力は失われているのですから。…しかし――、明日のお二人のご活躍については期待しております」
凛然とした声音は、わずかに熱を持っているように自分でも感じられた。
光の雨による余韻が未だ、全身に燻ぶっているのだろうか。
だが――、この気持ちは決して不快なものでは無かった。
戦いは間近に迫っていた。そして、熾烈を極める戦いの前夜にて、青い雨に打たれながら、たまゆら気分を高揚させるのも、一時ならば悪いものでは無い。
今の新月には確かに、そう実感されたのだ。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 暗都・魎夜
暗都・魎夜
【心情】
ひとまず緒戦を終えて、8時間後に本格的な戦いか
事前の準備を終えて、開戦を待つってのは、たしかに気楽に出来るもんじゃねえな
俺も気持ちは分かるし、昔、学園でやってたみたく壮行会でもやるとするか
【行動】
「コミュ力」で村人や現場にいるDIVIDEに接触を取り、「鼓舞」する
「宴会」っぽい簡単につまめる食事も用意しておく
「(ビデオカメラ回して)これからの戦いに向けて、意気込みを一言どうぞ」
真面目にやれって思われるかもしれねえが、少なくとも暗い気持ちでいて勝てるなら苦労はしねえさ
こういう時には生きるぞって強い意志を持つ
俺はそうやって生きてきたからな
【決戦配備】Md
姫川・沙耶も会いに行き、同様に
●
薪にくべられた篝火が、火の粉を爆ぜながら、宵空高く、紅い焔の舌を伸ばしている。
焔柱は、ゆらゆらと揺れ動きながら、闇夜の中に一条の紅色の敷物を広げているだった。丈高く背を伸ばした焔柱が、薪を囲む様にして三々五々で集まった兵士らの姿を照らし出していた。
兵士らは皆が皆、焚火によって顔をにわかに発赤させ、目を光らせつつ、熱っぽく呼吸を続けていた。
至る所で人いきれが立ち上がり、それらは互いに寄り集まりあいながら、綿花の様な白雲となって、夜化粧を終えた宵空を優雅に揺曳していくのだった。
この無数の息遣いと、数多灯された篝火の齎す熱気によって丘陵地帯は、咽ぶくような暑気で満ち満ちていた。
DIVIDE直轄英国第三軍の到着により、鄙びた山村周辺には村民を超える兵員が一時の間とは密集したのである。
第三軍は、三万ほどの大軍を有していた。
第三軍は、アンドレイの急報に触れ、おっとり刀で戦場へと駆けつけた。村落が彼らを収容することは、人数から見れば事実上不可能である。
結果、第三軍はその三万に及ぶ人員を収容できるほどの大規模な野営地が、山村から丘陵地帯には設営されたのである。
今や、アンドレイら百名が閑散と布陣しているだけだった丘陵地帯は、今や人々でごった返し、天幕や監視塔などがまるで所狭しと、まるで網の目の様に丘陵地帯を埋め尽くしていた。
暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)は、野営地の一隅にて、巨大な大樹に背を預けながら、大きく背を反らしつつ、幾分も寛いだ気分で人々の営みを俯瞰していた。
野営地には、決戦の準備を終え、就寝につく兵がいる一方で、いまだ、ぎらぎらと眼を光らせる者たちが数多、散見された。
焚火を囲んで、かけ事に興じるものがあり、酒杯を交わすものの姿が散見された。
浅黒い肌に汗を滲ませながら武器の手入れをするものの姿があり、輪を作りながら、互いにじゃれあう若兵らの姿も散見される。表情を固く強張らせる者、、酒気に顔を赤らめる者、意気揚々と明日の戦いについて談義する者の姿もあった。
人の数だけ思いは存在する。
多種多様な者たちが千差万別な想いを胸に抱きながら、迫り来る決戦に備える姿を、今、魎夜は目の当たりにしているのだ。
兵士らの熱狂は度を越えすぎたり、無秩序となるようなことは無かったが、
しかし今、第三軍の陣野は興奮と緊張の渦の中にあるのは間違いない。多くのものは、迫り来る戦いを前に、熱狂と恐怖の狭間で揺れ動いているだろうことが魎夜には手に取るように分かった。
決戦前夜の熱望と恐れ、高揚や忌避感といったものは今や混然一体となり、立ち上れる人いきれと共に野営地全体へと波及しているのだ。
緒戦を勝利で飾るところまでは事を上首尾に進めることが出来た。緒戦の勝利が味方してか、兵たちの士気は高いことが伺われる。
なるほど、陣容の雰囲気も悪くは無かったし、兵らの挙止は落ち着いていたし、各々は秩序だって統率されているようにみえた。
とはいえ、集団として見た時の軍全体の雰囲気と、個々人が抱く不安感だったり、焦燥感といったものは完全に切り離して考えなければならない。
一見、落ち着き払った軍と映ろうとも、蓋を開けてみれば、内実は戦々恐々と身構える個人が数多溢れているなどとう事例も少なくない。
過日、銀誓館学園における学生生活の折、魎夜は決戦前の一種独特たる雰囲気というものを、肌感覚で体験してきた。
熱狂と恐怖が入り混じった、あの得も言われぬ雰囲気は、この野営地にもまた燻ぶてっているのだ。
既に翌日の会戦まで、時間は、残すところ八時間を切った。
まんじりともせず夜を過ごし、そのまま一大会戦に挑むとあっては、体も十全に機能しないだろうし、過度の熱狂や恐怖は実戦において筋肉を緊張させ、心をも委縮させる。
決戦に備え、淡々と戦支度を済ませ、適度に寛いだ状態で会戦に臨む。それが理想だろう。
口で言うのは楽だが、いざ実行しようとした際、誰もが簡単にできる事ではない。
「さてと…とはいえ」
背に手をまわして大樹の表面を軽く跳ね上げる。
そのまま一歩、二歩と魎夜は、歩を刻む。
とはいえ、手をこまねいたまま、傍観に徹するつもりは魎夜にはさらさら無かった。
魎夜は、決戦前夜の第三軍野営地を訪れたのだ。となれば、なんらかの手を打つべきだろうとの思いがあったし、もちろん方策も幾つかは思いつく。
そう、極度に緊張した者や、興奮したものを、心ばかりの歓待で和ませるのだ。
いわば、決戦を前にした壮行会をここに再現するのだ。
かつて銀誓館学園時代に魎夜は、壮行会を催し、友人たちを慰撫し、決戦に向け彼らの状態を万全に仕上げてきた。
つまり、それと同様の事を今から、ここで行う。
そんな決意を胸に抱きながら、魎夜は足早に野営地の中を進んでいくと、さっそく厨房へと足を踏み入れた。
磊落とした挙措でもって料理番に挨拶を済ませると、魎夜は、丸々と太った太鼓腹の料理長と二言、三言歓談を挿み、得意の話術で調理場を借りいれる。
軍の規模が増せば増すほどに、随伴する部隊の兵種も多岐にわたる。
第三軍ほどの大所帯ともなれば、麾下に軍団所属の兵站部隊も持つのも必然と言えた。
おかげさまで、短期の遠征にも関わらず、調理班が備蓄していた食料や調味料の類は豊富であり、魎夜は労せずに宴会向きの軽食をあしらえる足がかりを得たのである。
厨房へと足を踏み入れるや、魎夜は調理棚から包丁や、ボウル、調味料を手元にそろえる。携帯用の冷蔵棚からは、新鮮な状態で保存された果実類を引き寄せてキッチンに並べていく。
最初、魎夜が手に取ったのはアボガドだった。
そう最初の一品はアボガドを使った軽食である。
輪切りに、アボガドの中央に切れ目をいれて、アボガドを両断する。芯部分の種を除外し、アボガドの果肉部分だけをくり抜き、ボールの上で砕いていく。たまねぎをみじん切りにし、レモン、コリアンダーなどをボールに加え、ペースト状になったアボガドと絡め、赤唐辛子と塩をまぶす。
適度に攪拌してゆき、程よくすべての材料が交じり合ったところで手を止める。
これにて料理は完成だ。
なれた手つきで料理皿の中央へとペースト状になったアボガドディップスを小山の様に盛り付け、周囲へとチップスを散りばめれば、グアッカァモーレ、メキシコ風アボガドのディップスが即座に完成した。
まさに、おあつらえ向きな宴会食と言えるだろう。
とはいえ、兵士の数を鑑みれば、一皿だけというのはいささか寂しかろう。ゆえに魎夜は同じような手順で、魎一皿、また一皿とグアッカァモーレを調理してゆき、瞬く間に数皿分ほど仕上げてみせるのだった。
ついで魎夜は、残った玉ねぎをみじん切りに、更に簡易式の冷蔵庫から真鯛を数尾ほど取り出すと、洗練された包丁さばきで、鯛に切り目を入れてゆく。
すぅと包丁が鯛の表面を滑るようにして走り抜けていけば、透明な切り身が一枚、また一枚と料理皿の上へと並んでいく。
みじん切りにしたたまねぎに醬油やニンニク片を絡め、最後にレモンと共にオリーブオイルへと混ぜ合わせれば、専用ソースが瞬く間に完成する。オリーブオイルの淡黄色を主体にしたこのソースこそが、この料理のだいご味であると言えよう。
料理皿の上へと、ソースを流し込めば、蜂蜜色を湛えた水面が、皿上で透明な白身を横たわる白身を浸し、料理皿を黄金色に潤色した。
さわやかなレモンと、オリーブオイルの豊潤な香りの二重奏が、魎夜の鼻腔をくすぐった。鯛の透明な白身が蜂蜜色の水面のなかでうっとりと遊泳していた。
鯛のカルパッチョ、これまた宴会料理の代表が瞬く間に完成したのである。
左手に鯛のカルパッチョが盛られた大皿を載せ、右手の指間に数皿ほど、グアッカァモーレ皿を挟む。
そうして魎夜は、料理番へと軽く目合図して、調理場を辞去し、そのまま野外へと舞い戻るのだった。
料理皿を手に手に、魎夜は、一つ、また一つと天幕を訪れてゆく。
物足りなさげに、携帯食料のレーションを齧っていた若手の兵士たちのもとを訪れては、料理を勧め、同時にカメラを回して彼らの意気込みを取材する。
表情を固くする兵士たちのもとへと足を運び、歓談すると共に一緒に軽食を楽しめば、幾分も晴れやかとなった兵士らが、カメラ越しに、多弁気味に戦いの抱負を語り出す。
魎夜が足を運ぶ場所にはたちどころに人の輪が出来、歓声が湧きたった。人だかりが出来ては消えてゆき、そのたびに、料理皿に盛りつけられたディップスや、カルパッチョはだんだんと姿を消していった。
暗闇の中に沈む野営地の中、朗らかな笑い声が、海鳴りの様に響いていた。
魎夜は、ただただ自然体で寛ぐDIVIDE直轄英国軍の面々をカメラに映していった。彼らの一人一人にマイクを向けて、彼らの生の声を記録し、生への強い思いを確認してゆく。
悲壮感を抱えながら戦いに赴くべきではないとの思いが魎夜にはあった。また他者が掲げる高邁なる大義名分に熱狂し、自己を埋没させるべきでも無いとの気持ちも強い。
生きる。
ただ生きるという意思と共に戦うことだけを一般兵は貫徹すればよいのだ。
少なくとも魎夜は生きるという一心のみを信条にして戦場の戦場を渡り歩き、そして生き抜いてきた。
もちろん、機械神『レヴィアタン』との会戦で遅れをとるつもりは魎夜には無いし、兵たちは全力でことに望まねばならぬとも考える。
だが、この場に集ったものには勝敗を別に生還を第一に優先して貰いたかった。戦いの勝ち負けは司令官によって立つところが大きい。幸いにも第三軍の司令官はラファエル・サー・ウェリントンたる稀代の名将であり、なればこそ兵士たちはただ、生を信じて戦うことのみに没入すればよいとの思いが魎夜にはあった。
次なる天幕を去ったところで、魎夜は空になった料理皿を重ねていく。
魎夜の料理やインタビューは大盛況を博したようで、料理皿に山と盛り付けられていた料理群は、既に大部分が平らげられていた。
鯛の白身も残すところ数切れまで数を減っていたし、アボガドディップスに関しては、もはや皿の上から完全に姿を消していた。
今、魎夜が即席で作った料理により、多くの兵士らは満腹中枢を満たした。
更に、魎夜のマイクインタビューという一風変わった趣向により、あるものは感情の昂りを沈静化し、またある者は、自らの不安を吐露する事で、緊張を解きほぐすのだった。
溢れていた兵士らが一人また一人と陣幕の中へと身を潜らせてゆくのが見えた。未だ、管を巻く者や歓談を続ける者の姿も野営地では散見されたが、人影は目減りし、賑わいは既に盛りを過ぎていた。
丘陵地帯には、心地よげな寝息と共に、穏やかな静けさが満ちていった。
魎夜は、人のまばらになった野営地のもと、厨房へと向け、進路を取る。
月光が砂利道に青白い光の道しるべを敷いていた。青く輝く砂利道を軽やかに踏み鳴らしながら魎夜は、二歩、三歩と歩を刻み、そうして厨房の所在する区画へと躍り出た。
ぴたりと、魎夜は足を止め、視線を野営地の一角へと視線を固定した。
月明かりが、草木が生い茂り、岩々が散在する空き地を青白い光で照らし出していた。
魎夜の視界の先で、月光のシャワーを浴びながら、一人、小岩の上で夜空を仰ぐ女の姿があった。
肩元で波間様を描く黒髪が、銀蒼色の月光を浴びて、優艶と輝いていた。狭い額を櫛比の様に覆いつくした黒の前髪が、吹く風を受けてさやさやと揺れていた。
女性にしてはやや幅広ななで肩は、緩やかな曲線を描きながら、豊満な姿態を形成している。
しかし、女の細面に象嵌された大ぶりな黒の双眸は、彼女の優艶たる体躯に背理して、少年少女の明朗さを湛えながら、夜空の中、日輪の鮮やかさに輝いて見えた。
ヘアスタイルこそ多少は変化しているものの、記憶力に優れた魎夜が女の顔貌を見間違うはずがなかった。
絹の様な艶のある黒髪も、ブラックダイヤモンドの様な鮮やかな瞳も、それらはレグルス襲撃の際に魎夜が共闘した姫川・沙耶医師の風貌とぴったりと一致していたのだ。
眼深に帽子をかぶりながら、魎夜は、厨房に背を向けると、姫川へと姿勢を変えた。
砂利道を踏みしめればじゃりっと、靴音がなった。
靴音に気づいてか、姫川の黒真珠が、不思議そうに魎夜のもとへと向けられた。
俯きがちに歩を進めながら、魎夜は帽子で顔を隠したままに、声音を落としてぼつりと呟いた。
「姫川先生――、これからの戦いに向けて、意気込みを…一言どうぞ?」
マイクを沙耶へと伸ばし、更に二歩、三歩と沙耶へと距離を詰めたところで魎夜はぴたりと足を止めた。
いたずらっぽく鼻を鳴らし、被った帽子を持ち上げる。
瞬間、ぼんやりと魎夜を眺めるばかりであった沙耶の面立ちに笑顔の花が爛漫と咲き誇る。
「あら…あなたは? あの時の通りすがりの超能力者…さん?」
沙耶が形の良い黒真珠の瞳をぱちぱちと瞬かせた。
魎夜は、軽く肩をすくめてみせると、微笑がちに相槌を打つ。
「あぁ、名もない通りすがりの超能力者さ。はは、よく覚えてたな、ブリティッシュレディ?」
軽くからかってみせる。
沙耶が面映ゆげに蕾の様な唇を尖らせるのが分かった。ブリティッシュレディを自称する女は、軽く魎夜へと会釈すると、腰掛けた岩の上に掌をついて身を浮かせる。そうしてそのまま半身ほど左方へと体をずらし、魎夜が腰掛けられる程度のスペースを確保する。
掌を折り曲げながら、沙耶が魎夜を手招きするのがわかった。
沙耶に従い、魎夜もまた、小岩の上に腰を沈めた。
沙耶と横並びに夜空をしばし、眺める。
凍り付いたように青く澄んだ夜空に宝石の様な星々が張り付いて見えた。
そのまま魎夜は、視線を落とすと、手にした空き皿を足元に置き、ついで、小皿の上、数切れほど残った鯛のカルパッチョを沙耶へと勧める。
「どうだい、ブリティッシュレディ、少し残ったんでよかったら食べてみないかい?」
魎夜は、言えば、沙耶が力強く一度二度とうなづいた。間髪入れず、白磁の様な指先が、皿の上へと伸びて、鯛の切れ身を一掴みする。
沙耶は、手づかみにカルパッチョを口元まで運ぶと、愛らしく口を開き、はむり、とほおばった。二度三度と咀嚼し、ついで嚥下する。ごくんと小気味良さな嚥下音でもって沙耶が舌鼓を鳴らすのが分かった。
「おいしぃ...! これ、超能力者さんが作ったの?…だったら、ちょっと多彩過ぎない。レシピとか普通に教えてもらいたいのだけれど」
目をむき出しにしながら、ぐいと沙耶が魎夜へと顔を寄せてくる。好奇の色を湛えた二粒の黒真珠が魎夜の間近に迫る。苦笑まじりに魎夜は答える。
「ちょうど機材や材料がそろっていたから作らせてもらったんだけど、これくらいなら朝飯前ってね。オッケー、レシピくらいは教えるぜ。っと、ブリティッシュレディ。とはいえ、食べた以上はまずは、俺の趣向に付き合ってもらうぜ?」
魎夜が矢継ぎ早に答えてみせれば、魎夜の事を感心顔で眺めていた沙耶が直ちに首を縦に振る。
沙耶の挙止を肯定とみなし、魎夜は、マイクを沙耶へと向ける。
「ところで、明日は一大決戦みたいだけど、ブリティッシュレディ。いや姫川先生、抱負を聞かせてもらえるかい?」
魎夜は正面から沙耶の瞳を覗き込む。
磊落とした、それでいて、力強い意思の光を帯びた黒真珠が、どこか気落ちした様に揺らいで見えた。
ふっくらとした唇が柔和に震えだし、上唇が力なく下方へと下垂する。弱弱しげな声音が宵闇へと流れていく。
「正直…今回は、私たちの手落ちで、危うく山村がそっくりそのままデウスエクスの生贄となるところだった。超能力者さん達のおかげで事なきを得たけれど…。軍内部の政治闘争の生で無辜の住民が命を落とすことになったことに私は未だに納得がいかないの」
そこまで言ったところで沙耶は一旦、口を噤んだ。
沙耶は、しばし、視線を足元でさまよわせていたが、しばらくすると前方の山腹へと向け、次いで、魎夜へと戻した。
「だから、自分たちの失策は、自分たちで挽回してみせる。病巣を絶つために次の戦い、私は精一杯、部隊を支えてみせる。あなたに約束させて? 誰一人として人死になんて出させはしない…って」
再び紡がれた沙耶の言葉は、力強い響きと共に山野へと流れていった。
まさに、魎夜が求めていた答えを沙耶は口にしたのだ。そして、彼女の技量を思えば、その言葉が願望や強がりゆえに出たものでは無いことが魎夜には容易に確信できた。
「いい答えだ。きっとやれるはずだ。先生の活躍期待しているよ」
魎夜が揶揄う様に目くばせすれば、沙耶もまた小さくうなづいてみせる。
なぜだろうか、魎夜にとっては沙耶という女を異性という枠に当てはめることが出来なかった。
丸みのある姿態や、柔らかな相貌に反して、沙耶の性向は自由闊達としたもので、性別や年齢、出自などの概念を超えて、いわば戦友という言葉こそが、彼女には相応しいような気がしたからだ。
「オッケーだ、姫川先生…いや戦友っ! それじゃあ、約束だ」
カルパッチョが盛られた料理皿を小岩の上に置き、ついでマイクをひっこめる。
ぎゅっと右手を握りしめ、魎夜は右拳を沙耶のもとへと突き出した。
沙耶もまた、嬉々とした様子で瞳を輝かせるのが分かった。
沙耶は、魎夜を真似するようにして右拳を固めると、自らの拳でもって、丸めた魎夜の拳を軽く小突いてみせる。
拳と拳が軽くふれあい、こつん、と軽やかな叩打音を闇夜へと響かせてゆく。
叩打音は、周囲に反響しながらすぐに消失していった。だが、燃えるような紅の瞳と、黒真珠の瞳に浮かび上がった、意志力の光は、決して絶えることなく宵闇を眩耀の輝きで照らし出し続けるのだった。
大成功
🔵🔵🔵
 エミリィ・ジゼル
エミリィ・ジゼル
◎
Cs
レヴィアタン討伐までの間に英気を養いつつ、顔見知りの方の様子でも見に行きます
中でも気になるのはメンターとカエシアのコンビですかね。体育館で魚狩りした後、どうなったか知りませんし。
そんわけで魔術結界の様子を見るついでに、団子詰め合わせをお土産に持って冷やかしにいってみます。
ええ、冷やかしです。先の戦いで伝えたいことは伝えましたし、特に追加で言いたいこともないので。
二人がどういう道を選ぶにせよ、好きにすればいいんすよ
まあ、もっとわたくしを見習って自由に生きてもいいとは思いますけど
夜空に月が浮かんでいた。黄金でできた様な三日月がそこにあった。
優艶とした漆黒の夜空のもと、大小さまざまな星々に囲まれながら、三日月は、月明かりを金粉のごとく地上へと振りまいている。
ただ月明かりだけが、翌暁の会戦に備え寝静まったように佇む野営地をうっとりと照らし出していた。
機械神『レヴィアタン』との決戦を前に、DIVIDE直轄英国第三軍が、大量の兵と共に山村付近へと駆けつけたのは、数刻ほど前の暮時の頃に遡る。
津波の様に押し寄せるGLMストークの大軍を前に、猟兵含むアンドレイらとの決死隊は巨大な堤防となって、敵の大高生を妨げていた。
攻勢側と防衛軍の戦いが佳境に差し掛かったまさにその時に、第三軍は電光石火の勢いで戦場へと駆けつけ、敵デウスエクスの大軍を横合いから激しく殴りつけたのである。
前進を猟兵ら防衛軍に阻まれ、翼側を強襲されることで大軍のGLMストークは、挟撃の憂き目にあう。無数の砲火や、人型決戦兵器の突撃を無防備になった翼側に受けることで、大軍を擁したGLMの大集団は、陣を崩され、瞬く間に兵数を減らしてゆき、ついぞ物言わぬ屍となり、山野に無残に打ち捨てられていったのだった。
そうして戦いが終わるや、第三軍は直ちに設営に移った。
今や丘陵から山腹に連なる広大な敷地には、無数の天幕が並び、即席の管制塔や櫓、鉄条網や砲撃陣地よりなる第三軍の野営地が築かれ、今や閑散と佇むばかりだった丘陵地帯は、まるであたかも新たなる町が築かれたかのごとき様相を呈していたのである。
エミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)は、丘の一隅を占める空き地にて、倒木の上に腰を下ろしていた。
野営地の中、北の突端に位置するその場所は、背後を急峻な崖に接していた。
崖の谷間には原生林が埋め尽くし、どうやら、その影響か、空き地には、糸杉が林立していた。足場には雑草が繁茂し、木々の合間では蔦や蔓が複雑に絡みあっていた。
いわばそこは、野営地から取り残された小さな自然公園と言えるだろうか。周囲には、エミリィを除き、しばし前から歓談する二人の姿があっただけだ。
倒木の上に腰掛けたままに、エミリィは眼下の野営地を一望する。
野営地を昼の明るさで照らし出していた角灯や、燈火は既に照明を落とし、篝火も多くは鎮火され、丘陵地帯全体は今や、しっとりとした宵闇の中に全身を横たえていた。
決戦に備え、野営地は眠りについたのだ。
安穏とした静謐とした眠りの中で兵士らがゆっくりと力を漲らせているのがなんとは無しにエミリィにはうかがわれた。
もちろん、力を蓄えているという点においてはエミリィも同様だろう。
彼らとはやり方は違うが、エミリィもまた、レヴィアタン討伐に備え、今、現在進行形で英気を養っている。
倒木の上に敷き詰めたシートのもと、様々な団子が盛り付けられた料理皿が並んでいる。 みたらし団子にヨモギ団子、小豆団子、果てにはご当地ものの笹団子まで、色とりどりの団子が、皿の上に溢れていた。
ひとつ、みたらし団子を手に取り、エミリィが頬張れば、もっちりとした触感と共に、甘さとしょっぱさの協奏が口の中に広がっていく。串にささった団子をすべて食べきると、ついでエミリィは、傍らに置いた抹茶をすすって、口直しにする。
口腔内の甘さが抹茶の渋みで中和されていくのが分かった。ふと巻き起こったのは、得も言われぬ多幸感であった。甘味が齎す、甘やかなるひと時が、綿花のごとき柔らかさエミリィを包んでいたのだった。
ふぅと吐息をつき、脱力すれば、さわやかな夏草の鼻腔へと充満していった。
異国の地にて、夜風に当たりながら夜空を見上げる。
更に団子と抹茶をお供に、宵闇に抱擁されるまま時間を過ごす。
恬淡とした趣さえ感じられる、この至福の時こそが、エミリィの気力や精神力を高めるのだ。
一息つき、エミリィは左方へと視線を移した。
今、倒木のベンチには、エミリィを含め三つの人影があった。
エミリィは、詰め合わせ団子のパックを開け、空皿の上に補充すると、同席する二人へと団子をさらに勧める。どうやら、二人もまた、団子は随分と気に入ったようで、すでに空になった紙パックが二つ、三つと足元には散らばっているのが分かった。
「ゆきむらさん、カエシアさん…まだまだお団子詰め合わせセットは残っていますからね。さぁ、どんどん食べてしまってくださいね」
いいながら左方に腰掛けた人影にぱちりと目合図する。
じっと注視すれば、エミリィの視線の先、頬を団子でいっぱいに膨らませたゆきむらの姿があった。
彼は、エミリィが手にした団子の詰め合わせに気づくと、嬉しそうに表情を綻ばせ、勢いよく数度、口を上下させ団子を咀嚼し、口の中の団子を一挙に飲み込んだ。
そうして、手元にある抹茶で一息つくと、エミリィに勧められるままに、皿を受け取り、さっそく笹団子に手を伸ばすのだった。
「いやぁ、エミリィさんありがとうございます。まさか英国でこんなにうまい団子が食べられるなんて…思ってもいませんでしたよ。それにしてもはお目が高い。このゆきむら、信州上田の生まれですが、越後にて青年期を過ごしてましてねぇ。懐かしい味だ。笹団子、これぞ日本を代表する、団子の王様だって前々から思ってたんですよ。なぁ、カエシア? お前も、笹団子が一番だろ?」
目を輝かせながらエミリィへとそう言い放つと、ゆきむらは器用な手つきで団子の表面を覆う笹の葉ををはがしてゆく。
表面に餡子をたっぷりと塗りたくられた笹団子が顔を現せば、喜色満面、ゆきむらは、串の上で連なる団子を一口で食べきるのだった。
そんなゆきむらの隣、カエシアは、むぅと唸りを上げながら手元の団子と睨みあっていた。
手にしたみたらし団子には、小さな歯型がくっきりと浮かび上がっていた。神妙な眼差しでもって、みたらし団子をじっと眺めながら、カエシアは小さく首を振る。
「メンター。私は、みたらしが一番…だと思います。甘じょっぱくて、優しくて、好きな味…です」
ぽそりとカエシアは反論すると、ゆきむらの非難がましい言葉を無視して、小さな歯型がくっきりと残ったみたらし団子に再びかぶりつくのだった。
ゆきむらとカエシアは決戦を前にしても尚、呑気そのもの自然体でふるまっていた。
明朝の奇襲攻撃によって戦端が開かれるとのことであり、おおよそ、決戦まで残すところ時間は六から七時間といったところだろう。
こと、決戦を前にしても落ち着き払った態度の二人を、エミリィは胸をなでおろす気分でしばし見比べる。
気がかりというほどでは無かったが、戦いに臨み、エミリィは、ゆきむら、カエシアの両名とは一度、話をと思っていた。二人は軍人というよりは一般人との性格が強く、果たして大規模な戦闘において、精神的、能力的に適応できるかとの危惧があったからだ。
DIVIDE直轄の名が現すように、第三軍は軍隊としての特色を色濃く残しつつも、部隊員に軍に所属しない多くのケルベロスをも抱えていた。
多くの兵士は統一された軍服を纏っていたが、兵装は統一されず、専用の戦闘着で戦場へと参戦するものも多くいる。
まさしく、ゆきむらやカエシアはその最たる例と言えるだろう。
片や、ゆきむらと言えば、ぼろぼろのトレンチコートとよれよれのシャツ、年季のはいったスラックスで自らをコーディネートしていたし、カエシアもまた、フリルでふんだんに装飾された、無地のワンピースで自らを着飾っている。
かつて、原罪蛇メデューサが流布した七不思議事件の解決に臨んだ時と同様の格好であり、二人としては一番、動きやすい格好なのだろうが、二人の格好は軍内部ではやや浮いた存在に見えた。
とはいえ、格好がなんであろうとエミリィには些細な問題に過ぎない。
重要なのは想いの強さであり、そしてケルベロスとして、いや仮に一般人だとしても人類を守るために戦う力を有しているかどうかにある。
事実、エミリィがカエシアに接触をと思った最大の要因は、彼女が使役する結界術の精度や性能を確かめる事にもあったからだ。
結界術による祝福は、防衛部隊の盾を強固にし、時に攻勢部隊の牙を研ぎ澄ます。
カエシアがどの程度の裁量権を有しているかは知れなかったが、臨機応変に自らの術で味方部隊や猟兵たちを補助することがカエシア・ゆきむらの両名には求められるのである。
いわば、結界術を使役するキャスターとは、部隊における膠の様な存在と言えるだろう。
とはいえ、彼女の能力に関して言及するのならば、エミリィの懸念は杞憂に終わったと言えるだろう。
さかのぼる事、半刻ほど前、エミリィが駐屯所の一角を訪れた際、幸運にもカエシアは結界術を使役している最中であった。そう、エミリィは好都合にもカエシアが術式を展開している場に偶然にも居合わせたのである。
その時、カエシアは力強く闇の一点を睨み据えていた。彼女のなで肩の華奢な肩元には、ゆきむらの掌が携えられていた。
カエシアが、その繊細な指先を伸ばせば、彼女の指先を中心にして青い微光が漂い、それらは虚空に、六芒星の魔法陣が描いていった。
刻印された魔法陣は、青白い光の泡沫をばらまきながら、粉雪の様な儚さで丘陵地帯全体を包み込んでいく。
淡い白光は、はらりはらりと空を舞い落ちてゆく。
暗がりを蒼く染め上げるように、無数の微光が空を彩ったのである。
青い微光が空を舞い降り、エミリィの掌に触れた。光は弾け、ついで、水の様にエミリィの内奥へとしみ込んでいった。
やにわに、体の中で魔力が奔騰していくのがエミリィには分かった。それも桁違いの魔力が、まるで燎原の火のごとくエミリィの全身に溢れかえっていったのである。
間違いない。カエシアの術技は、及第点どころか、求められる水準を遥に凌駕するものであったのだ。
降り注ぐ粉雪の中で、エミリィは、カエシアのキャスターとしての適性を十二分に知るに至ったのである。
思えば、カエシアは先の戦いでは敵を攻撃することを躊躇うきらいがあった。
そんなカエシアの人となりを鑑みるに、キャスターという役割こそ、彼女には適当だったのかもしれない。
また、先の戦いで、エミリィは二人にケルベロスとしての戦いを身をもって提示した。
人々をデウスエクスから守ること。力の有無や役職などとは関係なく、人々を守りたいとの想いを抱き、巨悪に挑む者こそがケルベロスなのだとのエミリィの想いは、結界術で味方を守るという形で従軍を決めたカエシアにもどうやら受け継がれたという事だろう。
カエシアの想い、結界術の性能ともに申し分ない。
影からカエシア、ゆきむらを見守りながらエミリィはそう確信する。
…となれば、エミリィの残す用事とは…あとは冷やかしだけだった。
そうだ、あと自分がやることは、二人と茶菓子を楽しみながら他愛もない雑談で盛り上がることで十分だった。
すでに先の戦いで伝えたいことはすべて伝えたし、カエシアも、そしておそらく、ゆきむらも、エミリィの薫陶を受けて実行に移したのだ。ゆえに二人は、第三軍への従軍を決めたのだろう。
追加でなにかを伝えるというのも無粋に過ぎる気がしたし、二人と話すのなら別の話題で盛り上がりたかった。
自他共に『かじできないさん』として認知されるゆえに、即席で焼き菓子などは作ることはできなかったが、幸いにも団子の詰め合わせをあらかじめ用意しておいた。今の時代は便利なもので、抹茶もまたインスタントでもよいものが手に入る。
お団子と抹茶という、甘美なる軽食を用意した上で、エミリィはカエシアらの元を訪れ、休憩がてら談笑にふけり、今に至る。
再び、エミリィは二人をじっと見比べる。
ゆきむら、カエシアの両名は、相も変わらず団子を片手に夫婦漫才でも繰り広げるように、じゃれあっていた。
空き地は、人工灯とは無援に、やわらかな月光と慎ましげな星明りによって幻想的に照らし出されていた。清浄とした大気のもと、吹く夜風がひんやりとエミリィの柔肌を撫でていった。
「お団子もだいぶ食べ終わりましたが、いよいよ、決戦までまもなくですねー」
エミリィは、北方へと吹き付けていく微風を目で追いながら、二人へと言った。
「えぇ…。全力で戦い…ます。たくさんの人を守れるように」
カエシアが言葉短く、しかし確固とした言葉で即答した。
エミリィがカエシアを正面に見据えれば、鮮やかな三白眼がゆらゆらと揺れていた。
カエシアは、見た目通りの内向的な性向の持ちで、当初は常に伏し目がちに俯きながら、当初は緊張まじりにエミリィにぽつぽつと受け答えするばかりであった。
だが、エミリィと会話するに従い、徐々に心を開いていった。
そして、今はこうして自分の意思をはっきりとエミリィに伝えるまでになっている。揺れる瞳からは彼女の優しさと意志の強さが伝わってくるようだった。
「だな。まぁ、俺がついる限り大丈夫さ、カエシア。エミリィさん…。まっ、今はケルベロスの力は使えないが…なぁに、今の俺には俺なりの戦い方があるからな」
ついで、白い歯を光らせながらゆきむらが言う。
対するゆきむらと言えば、カエシアとは対照的に社交的であり、鷹揚とした立ち振る舞いで、気さくにエミリィとの会話を楽しんだ。
…しかも、日本出身で学生時代はもっぱら映画ばかりを鑑賞していたという彼は、鮫映画も幾つか履修したとのことである。
もちろん、ゆきむらが知りえた鮫映画と言えば「ジョーンズ」や「シャークタイクーン」などと有名どころが主体であったが、なるほど、ゆきむらの鮫映画に対する独特な着眼点は、目を見張るものがあったし、洞察眼もまた卓越したものであった。
鮫映画好きに悪いものはいないし、そして、鮫映画を鋭く分析できるものは紛れもなく慧眼の持ち主であろう。そこだけは、エミリィは自信をもって断言できる。
「まぁ、気負わずにですよ。英気は養ったのですから、明日は落ち着いて戦えばいいんです」
エミリィは下唇にそっと指先を添えて、楚々たる笑みを二人へと送る。
気づけば、歓談を始めてより 既に半刻ほどが経過していた。
周囲に立ち込めた宵闇は深まり、濃紺色を湛えた夜空には星々が零れ落ちんばかりの勢いで充満していた。
既に皿の上からは団子の山も消え、抹茶もぬるま湯となっていた。
そろそろ、暇乞いしようかと、空皿を一つ、また一つとエミリィは重ねていく。
皿を一枚、二枚と積み重ね、そうして五皿目を重ねたまさにその瞬間だった。カエシアがぽつりと口を開いたのは。
「…あっ、流れ星」
カエシアの言葉につられて、エミリィがふと夜空を仰げば、宵空の天幕を斜に横切るようにして、一条の流星が駆け抜けていった
流星は、長い尾を曳きながら、涙の様な光の糸筋をわずかな間、夜空に滲ませつつも、瞬くうちに、夜空の中へと溶け込み、跡形もなく消え去っていった。
ふとエミリィが隣席のカエシアへと視線を遣れば、弱気そうな三白眼が柔和な光を湛えながら、恍惚と見開かれているの見えた。更にゆきむらへとも視線を移せば、ゆきむらもまた、どこか放心したように夜空を仰いでいた。 エミリィは二人に問う。
「お二人は、なにをお祈りしたんですか?」
はたとエミリィは二人を交互に見つめながら、そう尋ねれば、カエシアは微妙に顔を赤らめながら俯き、ゆきむらは、どこか面映ゆげに一言も言葉を発する事無く苦笑を浮かべ続けた。
しばし、二人は黙りこくったままであったが、エミリィには二人の想いが手に取るように分かった。
ケルベロスに憧憬を抱く男は、自らを偽りながらも、彼が憧れる少女に寄り添い続けた。
三白眼の少女は、自らの力と向き合うことに苦悩しながらも、最愛の人が望むままのケルベロス像を自ら貫き、DIVIDEへと参加を決めた。
二人が互いに抱く感情は異なっていたが、二人は互いを求めあっている。いわば共依存の関係にある。根本的には二人は似通っているのだ。
自由闊達に見えるゆきむらも、内気そのものカエシアも、芯の部分ではどちらもが生真面目であり、不器用なのだ。そして、不器用な二人は、世界を愛したのだ。二人の原動力は他者への愛にあるのだと、エミリィには分かった。
愛らしいまでに不器用な二人を交互に眺めながら、エミリィは微笑を送る。
「二人がどういう道を選ぶにせよ、好きにすればいいんすよ」
エミリィは高らかに言い放つ。相も変わらずに苦笑するゆきむらと、真剣そのものエミリィを注視するカエシアの姿がそこにあった。
エミリィは自然のベンチから立ち上がる。
そうして二人の前に立つと、胸元に手を置き、二人へと鄭重に一揖するのだった。
メイド服の裳裾が宵闇の中で、心地よさげに白波の鮮やかさで揺れ出す。
エミリィが右手を振り上げて、大仰な挙止でもって掌を左右に振れば、ちっちゃな鮫ちゃんぬいぐるみが、ちょうど二体分、どこからともなくエミリィの掌の中に現出した。
一体は、トレンチコートを羽織った鮫ちゃんであり、もう一体は自信無さげに目じりを下ろす、リボンをつけた女の子の鮫ちゃんだ。
「まあ、もっとわたくしを見習って自由に生きてもいいとは思いますけどね。まずは明日の決戦です。お二人がどんな道を選ぶにしても、生き残ることが先決ですからね。幸運の鮫ちゃん人形を二人には差し上げます。無事に生き残って人生を謳歌しなくちゃですよ?」
まくした立てるように一気に言い切ると、エミリィは二人にそれぞれ鮫ちゃん人形を手渡した。
カエシアが、トレンチコート姿の鮫ちゃんを胸にうずめるように抱きしめ、ゆきむらが垂れ目の鮫ちゃんを両手で包むようにして優しく握りしめるのが見えた。
二人を穏やかに見比べながら、エミリィは踵を返す。
「それでは、お二人ともごゆっくりとお休みください...。明日の戦い、お二人にご武運がありますように」
ただ一陣の風が吹いていった。
穏やかな風だった。
微風は、砂埃を絡ませながら、ゆきむらやカエシア、そしてエミリィの周囲を駆け巡り、丘陵地帯を一気に駆け下りてゆく。
風の進路に一致するように、足元の雑草は、背を折り、道標を作っていく。
エミリィは、風の吹くままに、軽やかに草の足場を踏みしめながら、丘陵地帯を下ってゆく。歩を刻むたびに、カエシア、ゆきむらの両名が背中越しに間遠になっていくのが分かった。そして、ついに二人の気配は完全に闇の中へと消えていった。
決戦前夜の野営地は、森閑とした宵闇の中で、眠りへと落ちていく。
ただ満天の星空だけが、微睡の中にある山野を優しげな眼差しで見守っていた。
大成功
🔵🔵🔵
 ハル・エーヴィヒカイト
ハル・エーヴィヒカイト
◎
連携○
▼心情
集まってくれた皆、ほぼ見知った人々だ。時間が許す限り巡ってみようか
▼アンドレイ
先程の戦いの礼を言おう。彼の正確無比な射撃があって私は攻撃に専念することが出来たのだから
彼が背負っている物は予知で知った範囲でしかないが過去は過去、今回の戦いでも期待している
▼沙耶
その後病院は大事ないだろうか?
お友達のことも含め近況を聞けたら御の字だ
医者でもある君の援護があるのなら安心だ。後方支援は任せる
▼ファレル
要塞攻略以来だな。あの時砕けた斧はちゃんと新調できただろうか?
あなたが前線に立つというのなら心強い。私もあの時以上に力を尽くすとしよう
▼ゆきむら&カエシア
やはり二人一緒か。正直ゆきむらは下がっていた方が安全だろうが……
だが彼がいるからこそカエシアは力を発揮できるのかもしれない
二人とも支援は任せた。そして必ずまた全員そろって生きて会おう
▼ラファエル&イゾルデ
彼らとは初めてお目にかかる
あの時は戦場が分かれていたからね
改めて挨拶させてもらい、この後の戦いで巨神も含めうまく使ってもらうとしよう
●
夜空を裂くように、銀色の光沢を湛えた刃がぎらついていた。
それは、巨人が手にした大斧が射しこむ月光を反射させて生じた、雄弁たる殺意の光であった。
今、ハル・エーヴィヒカイト(閃花の剣聖・f40781)の前方にて、緩やかな弧を描くようにして振り上げられた大斧の切っ先が、月光を浴びながら鋭い切っ先でもって夜空を睨んでいた。
凡そ三間ほどの間合いを隔て、暗闇の中、巨躯の男が大斧を構えている。
ハルよりも、頭二つ分ほど長身の巨人が、ハルと正面から対峙するような格好で立ちはだかっていた。
射しこむ青白い月明かりが、男の屈強な体躯を闇夜の中で艶やかに浮かび上がらせていた。
ゆらりゆらりと巨躯が体動する度に、眼光鋭い濃紺の瞳が、左右へと揺れ動いた。黒褐色の軍靴が草の上をすり足で前方へと滑り出せば、巨体が前方へとぬるりと伸び、ハルへと肉薄する。
足さばきはもちろん、筋肉のわずかな収斂や視線の動きに至るまで、大男の挙措は端々まで洗練されていた。
大男は、動きの一挙手一投足に時に無駄とも思われる動きを加え、あえて隙を晒すことでハルの軽挙妄動を誘導する。更には、動きに緩急をつけることでハルの距離感を誤認させるべく男は動きの中に虚実を織り交ぜたのである。
素人ならば、男の晒した隙に食らいつき、一刀のもとに切り伏せられていただろう。
だが、ハルは男の実力を嫌というほどに知悉していた。ゆえに微動だにすることなく、ハルは剣を前方に構えて、男の虚を見抜き、実のみに備えたのである。
男は名をファレルと言った。
過日、マン島要塞攻略時にハルと共に共闘したこの男は、今、実戦さながらの雰囲気でハルとの模擬戦に臨んでいる。
以前の戦いで砕かれた大斧は新調されたようで、仁王像を彷彿とさせる男の盛り上がった両腕の先、まるで両の前腕と一体化したような形で、巨大な戦斧が伸びていた。
互いにすり足で距離をつめることで、気づけばファレルとハルとの距離はついぞ、二間まで迫っていた。
蒼白い月光に洗われたファレルの面立ちが、明瞭とした輪郭でもってハルの前へと迫る。相も変わらず、男は口角を機嫌よさげに歪めながら、余裕たっぷりと豪快な笑みを口元に刻んでいる。まったくまって動じている様子は感じられない。
もっともそれはハルもまた変わらぬことであった。
両の指を剣の柄に絡みつけ、切っ先を上方へと差し向ける。両の足で力強く大地を踏みしめながら、ハルもまた、正眼にてファレルを見据える。
今やハルとファレルを隔てるのはただの二間、いわば四メートルにも満たない距離であった。
ハルとファレルが互いに一歩を踏み出せば、両者が両者を己が矛にて容易に切り伏せることが叶うだろう。
だが、このわずか二間の空間を踏破するのは容易では無かろう。
たかだか二間程度のわずかな間合いは、今やハル、ファレルらが放つ殺気により身を縮こまらせながら、一種特殊な力場を生み出していた。
まるで不可視の石壁がいくつも張り巡らされているかの様に、空間は重々しく蠢きながら、ハルをそしてファレルの侵入を峻拒しているようだった。
だがしかし、あえてハルは一歩を踏み出した。
射すような殺気渦巻く暴風雨の中を、ハルは一歩、二歩とすり足で進んでいく。
ファレルの射抜くような視線や、周囲に立ち込める重苦しい圧迫感をやり過ごしつつ、ハルは、ファレルの挙止に注意を払いつつ、歩を重ねていく。
息も詰まるような沈黙の中、ぴくりとファレルの右肩が微動するのが分かった。瞬転、それまで大型獣の緩慢さでハルに相対していたファレルが一転、俊敏な挙止でもって体動するのが見えた。
ファレルの巨体がまるでバネの様に側方へと捩じられ、両の足が勢いよく大地を蹴り上げた。巨大な軍靴の一歩は、轟音でもって大地を踏み抜き、静寂を激しく殴りつける。
それはいわば、巨大な砲弾とも形容できるだろう。
ファレルはその巨体を大きく丸めながら、ものすごい勢いで低空を滑空し、勢いそのままハルの目前へと躍り出る。
戦斧の先端が、三日月の様な鋭い軌道を描きつつ、上空よりハルへと袈裟懸けに襲い掛かる。
――だが。
ハルは即座に両の肘を屈曲させ、剣の構えを正眼から上段へと変じる。
戦斧の一撃は銀色の閃光となって、見る間にハルの右の肩元へと迫る。
しかし、斬撃の速度や軌道は、いくら早かろうともハルが捉えられるほどのものでは無い。ハルの両の眼は刻々と軌道を変じていく大斧の軌道をはっきりと見切っていた。
ハルの右上空で空気が震えだすのが分かった。中心より迸る銀色の光芒に押しのけられるようにして、空気は唸りを上げ続けていた。
銀色の閃光は、鋭い軌道を描きながら、稲妻の如き軌道でハルの頭上すれすれまで迫る。。
音速を越せる高速でもって自らへと迫る一撃に、しかしハルは最小限の動きでもって対処する。
わずかに右足をひいて、腰を下ろす。そうして、上段で構えた剣の切っ先を、自らに迫る大斧の軌道に合わせて振り下ろす。
瞬間、二対の閃光が並行しながら空を駆け下りていった。
二対の閃光はしばし、並走しながらも、一方がもう一方へと身を寄せ、ついぞ絡みついたかと思えば、両者は軌道を右方へと徐々に変えてゆき、下方へと走り抜けていく。
戦斧と日本刀がぶつかり合った衝撃が、ハルの掌へと疼痒感となって走っていた。
今、ハルが袈裟切りに放った鋭い剣戟は、ファレルの斬撃の軌道をなぞりながら袈裟切りされ、そうして戦斧の表面を撫でるように滑り落ち、斬撃の軌道を肩幅一つ分、ハルの右方へと払いのけたのである。
切り払い、ハルが得意とする剣術の一つだ。
目の前では、ファレルが苦笑気に口端をへの字に折り曲げているのが分かった。苦笑を浮かべるファレルを他所に、戦斧はハルの肩元すれすれを掠めながらも虚しく虚空を切り裂き、そのまま、轟音でもって大地を穿ちぬくのだった。
ぱらぱらと砂塵が舞い上がる中、ハルはふぅと小さく吐息を吐き出すと、剣を鞘に納める。
「模擬戦とは言えど、ひやひやしたよ、ファレル殿。戦斧も新調できたようだし、実力も健在のようだ。あなたが前線に立つというのなら心強い限りだ。明日も今日同様の動きのキレを期待する」
ハルが言えば、目の前の大男が矢継ぎ早に肩をいからせる。濛々と立ち込める砂塵の中で、男が大地をえぐりぬいた大斧を持ち上げるのが見えた。
「まったく…。マン島要塞の攻略戦からただものでは無いと思っていたがね…。まさか俺の一撃をこんなにも容易くいなすとはなぁ。これでは、突撃隊長の面目も丸つぶれというもんだ」
皮肉げな物言いでファレルが恨み言を呟いた。言葉に反して、しかし、ファレルの声音は妙に軽やかに弾んで、ハルには聞かれた。ハルは即座に反駁する。
「いや…ファレル。あなたが本気で大斧の一撃を振り下ろしていたら防ぎきれかは分からなかったよ…」
言いながらハルの脳裏を掠めたのは、充実感に満ちた追憶の残影であった。
DIVIDE世界からは遠く隔てられたブレイド世界なる世界がある。並行世界ともいうべきかの世界において、ハルは日夜、闘技場という研鑽の場において自らの剣技を磨いてきた。
円形のアリーナにて繰り広げられた戦士たちの戦いを、今、ハルは掌にわずかに残るしびれの感覚と共にはっきりと思い出せる気がした。
かつての戦いの中で得た直感が、ファレルの底知れなさをハルに告げていた。
「それは、兄さんも同じだろう? まぁ、なにも仲間同士で全力で戦いあう必要はないがね」
ファレルが、哄笑するのが見えた。いかにも愉快気に笑いながら、ファレルは大斧を背に担ぐとハルに背を向ける。
そうしてファレルは、左手を振り上げると、遠景の闇の中で二人の戦いを静かに俯瞰していた男たちに手合図する。
「姫閣下殿、それから、アンドレイ大尉、どうだったかな、われらの剣舞は…?なかなか様になっていたとは思うがね? 姫閣下殿のお気に召しましたかな」
揶揄う様な仕草でもってファレルが恭しく手を折り曲げ、一礼するのが見えた。
そんなファレルの挙止を前に、両腕を組んだままに起立していた金髪の男が、ふんと小さく鼻を鳴らすのが分かった。
ハルとファレルに模擬戦を提案した男の姿がそこにはあった。
澄んだ金色の瞳は恍惚とした光彩を湛えながら、ファレル、遥翔の間で視線を行き来させていた。典雅たる眼差しでもって男は、ハルたちの挙止を窺っていた。
色素の薄い金の長髪を柔らかな指先でかきあげながら、第三軍司令官ラファエル・サー・ウェリントンが、一歩を踏み出すのが見えた。
「ファレル先輩――。姫閣下殿は、もうやめていただけないかな。もうこの年だし、なにより」
女性と見まがうばかりの美貌より放たれた声音は、思った以上に低く、艶やかなる音律を夜空に響かせる。
風雅な立ち振る舞いは崩さぬままに、ラファエルがその美貌をどこか嬉しそうに曇らせていた。そんなラファエルを前に、ファレルは愉快気に肩をすくませるとハルの隣に並び立つ。そうしてハルへと向かい、豪快に顎を向ける。
ファレルに促されるようにして、ハルはラファエルに一揖する。
「ラファエル・サー・ウェリントン大将に間違いないかな? 私はハル…。ハル・エーヴィヒカイト。独立ケルベロスとして、しばしばあなたの手腕を窺ってきたが、今回もあなたの卓越した用兵術に期待している。卒爾ながら、次なるレヴィアタンの戦いでは、あなたの指揮下で私も戦わせて貰いた…。我が愛機『キャリブルヌス』と共に戦場を荒らしまわらせてもらおう」
ハルは言葉短く告げた。
ふと流麗な曲線を描くラファエルの目じりが、いかにも嬉しそうに吊り上がるのが見えた。ハルの次なる言葉を遮るようにして、ラファエルが応える。
「よかろう、私なりに最善を尽くさせてもらおう。そして、私もまた貴殿の力量をしているぞ、エーヴィヒカイト。…ところでだ」
ついで、ラファエルの口端が愉快な三日月を描く。白く輝く歯が宵闇の中で、妙に煌びやかに輝いていた。
「ところで、エーヴィヒカイトよ。君さえよければ、我が第三軍にどうだ? 私は君の才能を無駄にするようなことはしない。遺憾なく君の力を発揮してみせよう」
自身ありげにラファエルが言い放つ。抑揚のある声音は、彼の高揚感を反映してかわずかに震えて聞かれた。白磁の様な肌が覆う、柔らかな細面のもと、金色の瞳が艶やかなる色を湛えながら百獣の王さながら、ぎらつく光彩を闇夜に滲ませていた。
ハルは、目の前に覇者の姿を確かに見たのだ。
世界が違えば、この男は皇帝にも魔王ともなりえたかもしれない。ディバイド世界に生まれたことが幸か不幸か、この男を優秀なる一司令官に押しとどめたと言えるだろう。
しばし、ハルはラファエルを見返していた。
自らと同じ金色の色に瞳を輝かせる青年を真正面に見据えた時、ハルは、粟立つ様な感覚が胸中に走るのを覚えた。
幸い、ディバイド世界にはハルにとっての仇敵の存在は無かった。仮にハルが猟兵でなく、一介のケルベロスであるのならば、ラファエル・サー・ウェリントンの招きに応じて第三軍の直臣となるのも悪い気はしなかった。
だが…。
「すまないな、ラファエル大将。私は、一か所に留まるのがどうにも苦手でね」
曖昧な言葉を濁しながらハルは首を左右する。ふむとラファエルがうなづくのが見えた。
「なるほど…。まぁ良い。なにも即決する必要はない…。君ほどの男を陣営に引き込めるのならば三顧の礼でも不足といえるだろうからな。まぁ、まずは――」
言いながら、ラファエルがハルの前に立った。
そうして、ハルを覗き込むようにしながら、ラファエルは右手を伸ばす。
「エーヴィヒカイト、まずは君の助力に謝意を示させてもらおう。先ほどの丘陵地帯の戦いにおける戦いに関する君の武勲と、そして明日の戦いへの助力にな」
差し伸べられた右手を、ハルは右手で包み込んだ。掌になにか熱い痺れがあふれていくようだった。
握手しながら、ハルは、力強く男と眼差しを交わす。そうして翌日の決戦における奮闘を互いに固く誓い合うのだった。
ハルには、この男のもとで戦う兵がなぜ皆、屈強であるのかが分かった気がした。
彼の戦術眼や、巧みな用兵術はもちろん、この男は得も言われぬカリスマを放つ。この男の覇気に当てられた時、弱兵は獅子となり、強兵は一騎当千の猛勇と化す。
「あぁ、ラファエル大将――。思う存分、私の力を使ってくれて…」
ハルはラファエルへと答える。そうして、二言、三言と決戦における陣容や戦法について話を交わすと、間もなく、手を離し、傍らに立つアンドレイへと視線を移す。
「そして、アンドレイ大尉。先ほどの戦い、援護に感謝する。あなたの正確無比な射撃があってこそ、私は攻撃に専念することが出来たのだから…。あなたの過去を私は知りえない。そして、私は今のあなたを知るのみだ。となれば、共に人類のために戦おう」
ハルがアンドレイへと告げれば、寡黙な偉丈夫は、黙りこくったままに事務的な敬礼でもってハルへと返答尾する。
鄭重に直立しながら、模範的な敬礼姿で立つアンドレイの瞳には、しかし、氷の様な冷静さと、何かを守ると決めたものだけが持ちうる熱情の光とが曖昧に混淆しながら浮かんで見えた。
ハルもまた口数が多い方ではない。だからこそハルには、アンドレイの落ち着き払った佇まいの中に、この場に集った誰よりも熱く迸る、崇高たる意思の光を見出したのである。
「では、私はこれにて失礼するよ。ラファエル大将、ファレル中佐、アンドレイ大尉…。皆々の武運を祈る。また戦場にて共に矛を振るおう」
一歩後方へと引き、ハルは一堂に会釈する。
ラファエルは、去り行くハルに対して、わずかに相槌する事で答え、ファレルは自らの蓬髪を愉快げに撫でながらわずかな微笑で返答した。アンドレイは相も変わらず敬礼を崩さずにただただ静かにハルを見守っていた。
三者三様のやり方で彼らは去り行くハルの後ろ姿を見守っている様だった。
多くの言葉はいらなかった。ハルは、すでに伝えるべきことはすべてを伝えたのだから。
あとは、振るう刃によって、彼らとの約束を果たせばよい。
自らに力強く言い聞かせながら、ハルはラファエルらのもとを辞去する。
足早に丘を下ってゆけば、ハルは直ちに山村の宿場へと到着する。水平線の彼方へと視線を送れば、天上には艶っぽい夜空がかかり、漆黒の毛布が覆う山野は、寝息ひとつ立てずにひっそりとたたずんで見えた。
遥か北方の山々もまた、暗がりの中で、険しい山肌をどっしりと横たえていた。
日の出までおおよそ六時間を切った今も尚、世界は安穏とした宵闇の中で安眠を続けているようだった。
ハルもまた旅籠の戸口をくぐり、そのままベットの上に横たわった。瞼を閉じれば、ハルの意識は泥の様に眠りの中へと落ちていく。
デウスエクスとケルベロスによる一大会戦へと向かい、夜空は、徐々に空模様を変じていく。
空は、黒いヴェールを脱ぎ捨て、徐々に白みはじめてゆく。
今、夜が明けたのだ。
夜明けの光が菫色に山野を照らし出す中で、ハルら猟兵らと英第三軍による混成部隊は、続々と山野へと布陣を開始する。
朝焼けの中で、無数の兵らが山野を彩ってゆく。
今、英国の未来を決する機械神『レヴィアタン』との一大会戦は最早秒読みまで迫りつつあった。
大成功
🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『レヴィアタン』

|
POW : 巨鯨上陸
単純で重い【脚部ユニット】の一撃を叩きつける。直撃地点の周辺地形は破壊される。
SPD : インビジブル・ワン
見えない【ステルス型ダモクレス】を放ち、遠距離の対象を攻撃する。遠隔地の物を掴んで動かしたり、精密に操作する事も可能。
WIZ : ロールアウト
レベル×5体の、小型の戦闘用【新型ダモクレス】を召喚し戦わせる。程々の強さを持つが、一撃で消滅する。
イラスト:もりさわともひろ
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠山田・二十五郎」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
朝焼けを受け、新緑がばら色に映えていた。射しこむ朝日を浴びて、今、一頭の巨大な大鯨が猟兵達の目前、山間にて巨体をそびやかしてみえた。
山とも見紛う巨躯が体動する度に、重苦しい地響きが山野へと伝わり、山が緑の上を這うようにして滑り出す。
機械神の名を冠した機械造りの大鯨が今ここに、その威容を現出させたのである。
機械神とは、いわば創造の神である。
かの大鯨が大地を蚕食するたびに、大鯨の眉間よりは、GLMストークが一機、また一機と噴出され、大鯨の周囲へと溢れていく。
大鯨の進撃により、山野には無数の黒点があふれ出してゆく。
鉄の大鯨を中心にして、瞬く間に軍団が生み出された軍団は、かの暴虐たる機械神の命ずるままに山野をわが物顔で、がん細胞の様に浸食していくのだった。
だが…彼らを黙って見逃すほどに、猟兵も第三軍も間抜けではない。
山野には万余を超える兵と猟兵たちが存在する。津波の様に押し寄せる兵団を前にしても、万余を超える兵らはなんらひるむことなく、一斉に己が武器で、魔術でもって大鯨たちへと応戦を開始するのだった。
朝日が照らし出す山野にて、今、猟兵たちとレヴィアタンの戦いの火ぶたは切られたのである。
―――――――――――――――――――――――――――――――
第三章は、機械神『レヴィアタン』との決戦シナリオとなります。
戦況に応じて、前編/後編に分かれます。それぞれで、プレイングボーナスが異なるのでご注意下さい。
①前編:レヴィアタンの背部には大きな傷跡が残り、そこから幾つかの障壁を挟んで内臓部に存在する、レヴィアタン内部の工廠部へと至ります。まずは、工廠部の破壊を行います。🔵×6~7で工廠破壊成功となり、本格的な『レヴィアタン』の破壊戦へと移行します。
→プレイングボーナスは「敵の猛攻に備えつつ戦線を維持する事」「ユーベルコードもしくは、ユーベルコードに準ずる威力の攻撃による障壁の破壊および工廠への攻撃」「決戦配備の使用」の三つとなります
②後編:工廠部の破壊に続き、レヴィアタンの破壊に移行します。
→プレイングボーナスは「守りよりも攻撃を主体にした戦法を心がける事」「ユーベルコードを使用」「決戦配備の使用」の三つとなります。
※前編→後編への移行は、タグ欄にてなるべく即時に記載します。一つの目安として、参加者様2~3名で工廠の破壊がなされることが想定されます。
※工廠破壊後も、ユーベルコードSPD、WIZ使用時には、一時的にダモクレスが出現しますが、効果は一時に限定されます。
三章に同行するDIVIDE部隊は以下の面々となります。
基本的には通常の決戦配備とほぼ同様の効果となりますが、名前付きのキャラクターを決戦配備に選ばれた場合は、テイストとしてやり取りなどを描かせていただきます。
Cr:ラファエル・サー・ウェリントン:
→美貌の天才司令官。第三軍の総司令官です。常に前線に赴き、陣頭指揮を執ります。
優れた用兵家であり、人型決戦兵器(支援ロボをキャバリア風に改装したもの)による奇襲戦術の大家でもあります。
Df:イゾルデ
→皮肉げな、褐色肌の美丈夫。第三軍の副司令官にあたります。一般部隊を指揮し、主に防御面で支援します。嫌煙家であり、たばこは苦手な酒豪。
Cs:ゆきむら&カエシア
→風貌体裁の怪しげな自称ベテランケルベロスと、女子高生ケルベロスの子弟コンビです。カエシアが魔術結界を張りめぐして、支援に当たります。
Jm:ファレル
→個の武勇に関しては英国軍最強とも目されています。2mを超える偉丈夫で、戦斧をもっての突撃により敵部隊へと混乱をもたらします。
Md:姫川・沙耶
→医師であり、どこか浮世離れした風変わりな女。結界術や回復魔術でのサポートを主体に、仲間を援護します。
Sn:アンドレイ・ヴィリキツキー
→もと、デウスエクスとして地球侵略の尖兵として戦っていましたが、人の優しさに触れ人の心を得ると共に、ケルベロスとして覚醒しました。射撃に関しては右手に出るものはなく、正確無比な射撃はありとあらゆる標的を寸分たがわずに撃ち抜きます。
 エクレア・エクレール
エクレア・エクレール
◎、Df
あれだけの軍勢を駒に用いて如何なるものを復活させるのかと思っておったが、なるほど軍勢そのものを生み出す力を持つ奴じゃったか
如何に敵を倒そうとそれ以上に増えられてはこちらが消耗するだけ
あの力が切れることを期待するよりも、まずは力そのものを潰しに行くのが得策のようじゃな
イゾルデ殿にはそれまで防御を固めてもらうとしよう
上空から戦場を把握
レヴィアタンを取り巻く敵に対し、自らの意思で敵を縛り、貫く雷鎖と雷槍を放つ
敵軍を混乱させつつ、レヴィアタンの傷跡から内部に侵入
雷鎚を放って障壁を砕き、雷で対侵入者機器を破壊しつつ進もう
工廠部に着いたなら、雷のルーンの力を解放
拳に集めた雷霆破を叩きつけようぞ
 月隠・新月
月隠・新月
【双狗】
◎
連携○
決戦配備:Cs
俺は【ブランクオベリスク】で辺りの偵察を行います。
敵のステルス機は、空気の流れや駆動音を頼りに探しましょう(【気配感知】)。発見し次第トーノさんに連携し、必要であればオベリスクで攻撃したいですね。オベリスクは容易く砕ける脆いものなので、あまり多くを攻撃には使えませんが……砕けた後も破片を【念動力】で操って敵に纏わりつかせれば、ステルス性能を落とすことくらいはできるでしょう。
あとは工廠部の破壊……カエシアさん、力を貸してくれますか? 偵察にリソースを割く以上、自力で高威力の攻撃を放つのは難しい……ですが貴方の支援があれば、この爪で敵を【引き裂き】砕くことも可能かと。
 トーノ・ヴィラーサミ
トーノ・ヴィラーサミ
【双狗】
◎
連携○
決戦配備:Df
イゾルデ
では、参りましょうか
敵から排出されるダモクレスを逃すことのないように決算配備で可能なら防壁を展開
ユーベルコードは常に使用可能状態を維持するよう心掛け
あちらから攻撃してくるものは【カウンター】そうでないものはゼロ距離攻撃【居合】
不可視といえど存在する事に変わりはありますまい
敢えて通行可能なエリアを狭めるなども敵の動きを誘導するなど新月さんと協力しつつ戦場全体に気を配りなるべく注目を集まるように立ち回り戦線を維持しましょう
【生命力吸収】【見切り】【受け流し】【覚悟】
手薄な箇所など気がついたことがあれば即声掛け
イゾルデさんと話し合った内容も活用出来ればと
●
鼓膜の奥で、蝉のなくような耳鳴りが響いていた。しばし、口を噤み、鳴り響く騒音へと耳を澄ませれば、耳鳴りが徐々に音量を増してゆくのが分かった。
耳鳴りは、じりじりと鼓膜を引っ掻くようにして内耳の奥へと反響し、次いで、海鳴りの様な底ごもった重低音へと変じ、ついぞ重苦しい潮騒の音へと質を変えていく。
トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)は、耳朶を揺らす耳障りな不協和音を傾聴しながらも、眼光鋭く前方の景色を凝視する。
黎明時の光が、淡い菫色の微光でもって、山野に敷き詰められた新緑の絨毯をほの赤く染め上げていた。
平素ならば、名工風靡たる里山に抱かれ、瑞々しい新緑を精一杯に伸ばす草原は、しかし、この時ばかりは、トーノの心を和ませることは出来はしなかった。
絶えず鳴り響く潮騒の不協和音と共に、遠景より不気味な黒い山脈の連なりがひしひしと押し寄せる。
安穏とした草原は、トーノの前方より押し寄せる山とも見紛う一体のデウスエクスの侵略にさらされたのである。
そう、英国北部の大平原は、今や機械神『レヴィアタン』の貪婪たる魔手によりじわりじわりと蚕食されつつあった。
遠景にて蠢くは、山に非ず。機械神の名を欲しいままにする大鯨と、彼が生み出した無数のダモクレスの群れにより作られた巨大な軍団である。
彼らは山とも見え、しかしその実はイナゴの群れの様にさえ感じられた。
GLMストークと呼ばれる、レヴィアタンの周りに蠢く、不気味な二脚型のダモクレスの形状が、そもそも機械仕掛けのイナゴを彷彿とさせるものであったという事もあるが、それ以上に、レヴィアタンが草原の上を進むたびに、無残に踏みにじられ、なぎ倒されていくが木々や草草の無残さが、まさにイナゴの大移動を彷彿とさせる凄惨さを物語っていたのである。
とはいえ、山脈の行進とも言うべきレヴィアタンの進撃は、今やその速度を明らかに落としていた。
DIVIDE直轄英国第三軍、一時的にトーノが従軍する精鋭ケルベロスを主体とした英国の刃は、迫り来る敵の大軍を前にして、一歩も怯むことなく、無数の火砲と魔術の応酬でもって敵軍に相対したからである。
トーノは今、首脳部が布陣する本陣にて、敵味方の応酬ぶりを注視していた。
そして、現状において彼我の勢力は拮抗しているとトーノは見る。いや、正鵠を期するのならば、第三軍がやや有利と言えただろう。
それは一重に第三軍の統率力の高さに起因し、第二に昨日のトーノそして、月隠・新月(獣の盟約・f41111)による偵察が功を奏した故と言えるだろう
今、レヴィアタンを中心としたデウスエクスの大軍は、草原に幾重にもなって陣を敷く、英第三軍の分厚い戦列によって、猛攻を押し留められていた。
第三軍の各部隊は、一糸乱れることの無い統率のもと、押し寄せる大軍を前に巨大な石壁となって立ちはだかったのである。
トーノが戦場を俯瞰すれば、戦場の至ると事で火の手が上がるのが分かった。朝焼けの光よりも眩い紅色の焔が至る所で燻ぶり、硝煙が蒼く澄んだ空へとたなびいていく。
爆音に続き、戦端部において、数十からなるGLMストークの群体が炎の中で白い影となって溶け出していくのが見えた。機械仕掛けのイナゴが鉄の破片をまき散らしながら、粉々に飛散し、次々に大地へと崩れて落ちていくのが遠間に伺われた。
一機、また一機と群体レベルでGLMストークの群れが崩れ落ちてゆく。
防衛部隊、いわゆるディフェンダーと呼ばれる前衛部隊の攻撃により、まずは、GLMストークの前列が細切れに分断されていく。
そうして群体が集団としての機能を失い、隊として機能不全に陥ったところで、今度は一転、間髪入れずに第三軍の人型決戦兵器による小集団が三々五々で体勢を崩したイナゴの群体へと遮二無二突撃を敢行していくのが見えた。
銀色の装甲を朝日に眩くそびやかしながら、白銀の騎士たちが雄々しい獅子の疾駆でもって、敵軍の陣形の綻びにむけて一斉に突撃を敢行する。
白銀の騎士たちがその手にした槍を前方へと倒し、イナゴの群体の中へと突き進んでいけば、まるで絹を裂くようにして、歪なイナゴ達は槍に貫かれ、物言わぬ残骸を大地へと力なく横たえていく。
鎧袖一触、白銀の騎士たちの突撃により、GLMストークによる敵の前衛部隊は瞬く間に壊滅の憂き目を味わうのであった。
たなびく硝煙が朝日を遮る中で、白銀の騎士たちは、敵の一陣を完全に無力化すると、敵の二陣の前まで勢いよく疾走しつつも、まるで挑発でもするかのように寸でのところで優雅に踵を返して、そのまま本陣へと帰投を果たしていくのだった。
まさに当意即妙とはこの事だろう。
戦術レベルで見た場合、第三軍は敵のデウスエクスの大軍を遥に凌駕しているだろうことは間違いない。
たまらず、トーノの口元より感嘆の言葉が零れだす。
「お見事です、イゾルデ殿」
ぼそりとトーノは一人、呟いた。ちらりと右方を窺えば、そこには褐色の偉丈夫たるイゾルデの姿があった。
この貴公子は、常に陣頭に立つ司令官に代わり、今は実質上の司令官として本陣より防衛部隊の指揮と全軍の把握に努めている。
トーノの言葉に気分を良くしてか、イゾルデが小さく微笑むのが見えた。
「ミスタートーノ、半ばはあなたの功績故ですよ。昨日のあなたよりの報告通り、こちらの布陣をあらかじめ、山側まで近づけたのが効いていますよ」
皮肉げな口元をわずかに綻ばせながらイゾルデが言った。トーノもまた穏やかに微笑で返しながら、再び、前方へと視線を戻した。
レヴィアタン率いるGLMの大軍と、ラファエルによるDIVIDE直轄英国第三軍は、今、山岳地帯の入り口周辺にて互いに激しく戦火を交えていた。
おおよそ、ラファエルら第三軍の総兵力は三万であり、対する敵軍は四万を超える大軍を擁している。
平原における戦いとは数の大小がものを言う。
数で勝る側は、敵を一部で拘束し、そして、適切に予備兵力を運用して、軍における泣き所とでもいうべき右左翼より劣勢側の包囲を鑑みるのが戦いにおける常套手段と言えるだろう。
包囲戦術と呼ばれるこの戦術機動は、いわば戦力優勢側の特権であり、平原における戦いにおいては、戦力優勢側の指揮官の脳裏を第一に掠める戦術行為とも言えるだろう。
だが、本来、数で勝る側のレヴィアタン達デウスエクス側は、愚直にも正面寄りの戦いに執着している。
果たして、彼らが単調なプログラムで動く機械兵ゆえに、戦術的合理性を無視したからかと言えば、それは違う。
じっと、トーノが山野の左右に目を遣れば、ちょうど、対陣する両軍の左右の延翼方向には、残骸が堆く積み重なり、巨大な山を築いているのが見えた。
まさしく、この人工的な障害物が敵から包囲戦術という選択肢を奪ったのである。
先日の戦いにおいて、山野には数多の残骸が打ち捨てられた。して、散乱した敵軍の残骸は、今、第三軍により戦場の左右へと寄せられて、人工山となったのである。
堆く連なった人工山により必然、戦闘における正面幅は狭まり、両軍は正面よりの純粋なぶつかり合いで雌雄を決することを余儀なくされたのである。
結果、数で劣る第三軍は、地形を利用することで数の有利性が齎す戦術的不利を克服し、更には司令官の巧みな戦術により戦況を互角以上の状態で維持してみせたのである。
トーノが戦場の先端部を窺えば、イゾルデの号令一下、防衛部隊は、防壁を展開しながら敵ダモクレスによる火砲の斉射を防ぎ、ついで敵の攻勢が止むや、ラファエルが陣頭指揮する人型決戦兵器の突撃、アンドレイが指揮する狙撃部隊の斉射による応酬によって第三軍が敵陣を強襲する様が見て取れた。
今も尚、GLMストークは火砲や銀槍に貫かれ、続々と数を減らしてゆき、ついぞ足を止めて、潮が引くように後退していくのが見えた。
現状は第三軍が圧倒的に有利である。
とはいえ、いかに第三軍が奮闘し、やや形成が有利であろうとも、防衛に徹するだけでは勝利はおぼつかない。いや、むしろ、敵の本丸たる大鯨『レヴィアタン』に打撃を与えられぬことには、此方側はじわじわと押し込まれて、最終的に敗北を喫するだろうことは火を見るよりも明らかだった。
「とはいえ…」
歯切れ悪そうに、隣立つイゾルデが口を尖らせるのが分かった。
彼の端正な唇から零れた言の葉は、僅かながらも焦慮の憂いを帯びなが響いて聞かれた。
そうだ、この褐色の貴公子もトーノと思いを同じくするどうことは容易に想像が継ぐ。
理知の瞳でもってイゾルデに目合図しながら、トーノもまた口を開く。
「えぇ。イゾルデ殿。なにかしらの一手は必要でしょうね」
トーノはイゾルデを見返すと首肯して応えた。
機械神レヴィアタン、かの不遜たる名を名乗るダモクレスの最大の強みとは個の強さに非ず。いわば、大鯨自体に内蔵された工廠にあった。
そして、大鯨は今まさに、失われたダモクレスを補充すべき動きを止めたのである。
トーノの遠景にて、レヴィアタンが平原にてその体躯を前傾姿勢に横たえるのが見えた。まるでお辞儀するような格好で、前傾姿勢にて身をうずくまらせる大鯨のもと、眉間部が開口されたのはまさにその時だった。
鋼鉄の皮膚が開かれれば、突如、滑走路を備えた甲板が顔を覗かせた。
甲板上は、数多の機械仕掛けのイナゴ達でひしめき合い、彼らの一機一機は、歪にへし合い押し合いしながら、開口部より地上へと向かい伸ばされた滑走路の上を這うように進み、そうして山野へと溢れだしていく。
直ちに、前衛部隊にできた大穴が、新たに生み出されたダモクレスによって補填され、修繕されていくのが見て取れた。
さらに――。
突如、最前線の一角、友軍部隊のもと、火の手が上がるのが見えた。
周囲を窺えども、敵の姿は無い。しかし、打ち寄せる機銃がますますと味方部隊を打ち貫いていく。
そう――、不可視の機銃が味方部隊を雨とあられと襲ったのである。火の粉が爆ぜ、燃え盛る火炎によって友軍の兵士たちが焼き払われていくのが見えた。
攻撃を受けた陣列にて、兵士らが右往左往するのが見えた。すかさず、隣立つ、イゾルデが通信機を片手に、指示を飛ばすのが見えた。
「敵のステルス機だ。前衛部隊は防壁を展開して、守りに徹せよ。すぐさまに、友軍を送る。しばしの間耐えよ」
言葉短くイゾルデが告げてみせれば、最前列にて魔術防壁が一層、二層とめぐらされるのが見えた。
混乱は、イゾルデの鶴の一声で瞬く間に収束したのだ。敵のステルス機による機銃の斉射が、障壁に弾かれ霧散していくのが分かった。
見事に敵の攻撃をやり過ごす矢、イゾルデは、後方に控える防衛部隊を直ちに前線へと送り、手際よく、前衛部隊の交代を済ませ、負傷者を後方へと輸送させてみせる。次いで、余勢を買って攻めたてんとする敵の一団を、横合いから別動隊でもって強襲することで相手の攻勢の矛を見事に砕いてみせるのだった。
この反撃に巻き込まれて、幸運にも不可視の敵部隊もまた数機程が、爆炎に飲み込まれ、再びの小康状態が両陣営へと齎された。
イゾルデの手際の良さは見事だと、トーノは称賛を送りたいほどだった。
とはいえ、対症療法ともいえる戦法で相対していては、最終的には此方が完全に劣勢に立たされるのは間違いない。
レヴィアタンは未だに体動を止めたまま、工廠における次なる兵団の増産に移っている。となれば、この不気味な均衡状態が長引くにつれ、第三軍はますます疲弊していくだろう。
トーノはすぐさまに思考を巡らせる。
さほどの時間はいらなかった。喫緊の課題とは、まさしく敵ステルス機の破壊であり、最善の一手とは、敵ステルス機破壊後に速やかにレヴィアタンの工廠部を破壊することにある。
直ちにトーノは献策をイゾルデへと伝える。
「イゾルデ殿…。一方向へと敵をおびき出してもらえないでしょうか。ステルス機と言えども、靄や妖の類でない以上は、不可視といえど存在する事に変わりはありますまい。うまく、一方向へと誘い出して頂けば、そこは我々が打って参ります故に」
いいながら、トーノはイゾルデを力強く見やる。打てば響くようにイゾルデが相槌を打った。
「ミスタートーノ、了解した。すまないな、貴殿の力を借りる。最前線第一列目の最右翼を後退させ、敵軍を誘い込む…。申し訳ないが、ステルス機の対処は貴殿に任せる」
イゾルデがいわば、トーノはほぼ無傷なままの右翼付近へと視線を遣る。
まったくもって、戦術の妙を心得ている友軍というのは心強い。即断即決ですぐさまに部下に指令を下すイゾルデを横目に、トーノは前脚でもって、軽やかに大地を踏み鳴らすと、疾走の準備を整える。
「えぇ、お任せをイゾルデ殿。可能な限り、多くの敵を打ち破って見せましょう…。こちらには、優秀な相棒もおります故。彼女の目と私の矛によって、敵陣を攪拌して参りましょうぞ」
言いながら、トーノは、鞘の中へとcaidaを収めると、後方にてトーノ、イゾルデのやり取りを黙って窺っていた、美貌の麗人、月隠・新月を振り返った。
凛然とした銀白の眼とあった。
彼女は多くを語らない。しかし、優艶たる眼光は、彼女の心の内を雄弁に物語っているようにトーノには見えた。互いに視線を交し合うも束の間、明晰さを湛えた、新月の柔らかな声音が周囲に響く。
「ブランクオベリスク…、既に展開済みですよ、トーノさん。敵ステルス機、ほぼ全てを補足済みです」
まったくもって、流石だと思う。
彼女は常に、トーノが求める最善の言葉、いや理想の先をゆく答えを用意している。
冷静沈着たる声音によって紡がれる言葉に、トーノはたまらず満面の笑みをこぼした。
これにて、最善の一手を打つべく状況は整った。
あとは、この一手でもって、至高の答えを導き出せばよい。
「となればお嬢さん、工廠自体の破壊、とどめはあなたにお任せできるでしょうか」
トーノは新月から左方へと視線を移し、尋ねる。
いつよりそこに少女の姿があったかは分からない。
司令部の片隅にて、意気揚々といった様子で両腕を組む少女の姿がある。蝶型のアイマスクによって隠された金色の瞳が闊達とした輝きを帯びながら、揺れ動いていた。
一見すれば、一般の少女と見紛ってもおかしくない。
しかし少女より迸る存在感が否応なしに、彼女が単なる人間では無いだろうことをトーノに教唆していた。おそらくは、トーノたち、同様に奇跡の力を使役できる猟兵の一人であろうことが容易に伺われた。
不敵に口端を吊り上げながら、少女が応える。
「敵はレヴィアタンであったかの? なるほど軍勢そのものを生み出す力を持つ奴じゃったとはの。あれほどの軍勢を駒に用いて、復活させようとしたのも納得がいくというものよ」
少女は腕をぽきぽきと鳴らしながら、鷹揚と歩を刻む。そうして、トーノの左隣に並び立つと、少女は、敵陣を鋭く睨み据え、如何にも愉快気にトーノに目合図する。
やにわに少女の口元から嬉々とした声音が零れだす。
「となれば…如何に敵を倒そうとそれ以上に増えられてはこちらが消耗するだけ。あの力が切れることを期待するよりも、まずは力そのものを潰しに行くのが得策のようじゃな」
少女の掌よりあふれ出した青白い光芒が鋭い銀色の棘を周囲へと伸ばす。それは、少女の内奥で燻ぶる膨大な力の片鱗であるのだろう。
なおさらに心強いというものだ。
――ここにキャスティングボードは完全に埋まったことをトーノは直感する。
新月、イゾルデ、そして金髪の少女へと交互に目合図しながら、トーノは再び口を開く。
「敵の工廠部の敵の背部に…。露払い、そして敵軍の足止めは私と新月さんが請け負いましょう。イゾルデ殿は、敵を誘導しつつ、本陣の守りを固めてください」
端的に告げれば、三者が三様に相槌を打つのが伺われた。
新月が、背を低くして大地を踏みしめ、イゾルデが口早に麾下の部隊へと伝令を下すのが分かった。
最後に金髪の少女が次なる言葉を重ねる。
「了解した。敵の本丸に一つ、わしなりに挨拶して参ろうぞ?」
少女の掌で雷を模した文様が、淡く浮かび上がるのが見えた。おそらく、少女は真の力を開放するにはそれ相応の時間を要するであろうことがトーノには察せられた。
最大限まで彼女には力を蓄えて、敵の心臓部たる工廠部を破壊してもらう必要がある。
トーノは即座に返答する。
「見たところ、技を練り上げるのにお時間を要するとお見受けます。お時間はどれほど必要で?」
矢継ぎ早に尋ねれば、少女が、快活とした様子で返答する。
「五分…いや、三分で済ませようぞ?」
トーノは首を左右する。
戦化粧においては、女人は悠然たりえてこそ本懐だろう。
いわんや、彼女はこれより敵の工廠にて舞を舞うのだ。
となれば、三分の早着替えでは、不相応というものだ。十全たる時間をかけて、彼女には戦支度を整えてもらう必要がある。
――五分程度は、時間を稼いでみせるのが男の甲斐というものだろう。
悠然たる微笑を口端に刻みながら、トーノは返答する。
「いえ…レディを急かせては、男の名折れというものですよ…五分間、ゆっくりと準備ください。それまでは、私たちが、敵の動きを完全に封殺しますゆえ」
言いながら、再び前方を見据えれば、右翼における前衛の一部隊は敵のGLMストークの一群を懐に招き入れるため、後退を始めていた。
必然、味方の陣営が右側に行くに従い斜交した、なだらかな曲線を描く。
自然、後方へと退いた間隙を埋めるように、敵のGLMストークが数多、前進するのが見えた。
敵はまんまと網にかかったと言えるだろう。この罠にて相手を絡み取り、ついで鋭い刃でもって敵を一網打尽とする。そのための矛はここに二対存在してるのだ、
「新月さん…行きましょう」
前脚で大地を蹴りながら、声かけすれば、了解です、と少女が端的に応じるのが背中越しに分かった。
ユーベルコード『流塋刃』発動のために、愛刀cadiaの鯉口をわずかに切る。居合の体勢を整えつつ、左前胸部から前脚へと伸びる蒼焔を迸らせながら、力強く大地を踏みしめた。
「では――」
「えぇ」
トーノが言えば、背後より再び新月が応えた。
短く言葉を交わし、大地を蹴り上げれば、トーノの全身は鋭い矢となって、目的地目指して地表すれすれを走り抜けていく。
今、二条の黒い疾風が戦場を駆け抜けていく。
●
「現れ――」
銀糸を引くような声音が戦場へと流れてゆく。
「写し、砕く――」
零れ、溢れて、そうして包み込むようにして、奇跡の力を孕んだ微光が山野を淡い白色に純色していく。
「此方は、白紙――、白紙のオベリスク」
月隠・新月(獣の盟約・f41111)の言の葉が、凛然たる調べとなって山野へと反響した時、そこに生み出されたるは無数のオベリスク、白き尖塔であった。
穏やかな福音が山野へと響き渡った時、新月が得たのは無数の目であったのだ。
オベリスク、白い尖塔は、今、陽炎の揺らめきでもって数多の兵士でひしめき合う戦場を朧げに照らし出していた。
オベリスクが山野を走り抜けていく。計百五十本を超える白い尖塔が、今、朝日射す戦場の中を駆け回っているのだ。
そして、この百五十を超える尖塔こそが、新月にとっての目であり矛である。
大地をひた走る。
前脚で勢いよく大地を蹴り上げてそうして、着地後、再び空へと飛びあがる。
ただ、速力を得る事のみ意識を傾注させ、そうして一歩、一歩を刻んでゆけば、体は滑るようにして地表すれすれを駆けていく。
得も言われぬ疾走感を全身で味わいながら、文字通り新月は一筋の疾風となって戦場を駆け抜けてゆく。
先を行く、大柄な黒い背中を肉眼で追い、戦場をさまようオベリスクより得られた視覚情報より戦場の全体像を具に観察しながら、新月は先を行く大型の黒い獣、トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)に続き戦場へとひた走るのだった。
新月は、本陣を後にし、碁盤の目状に幾重にも戦列を敷いた友軍の中を突き進んでいく。友軍の列を縫うようにして走り抜けてゆくに従い、当初、周囲に満ちていた平静はうだるような熱気に変じ、静けさは銃火による轟音へと転じていった。
そうして、最前線附近に新月、トーノの両名が躍り出た時、新月らを待っていたのは、片やプラズムキャノンや火砲の斉射でもって敵陣を崩さんとする機械仕掛けのイナゴの大群と、片や防壁を張り巡らせながら、分厚い壁となって敵部隊の攻勢を必死に押しとどめんと抗する友軍の姿であった。
三々五々で隊列を組む機械仕掛けのイナゴの大群が、胴部より突き出た機銃でもって、魔術防壁を張り巡らせる第三軍の兵士らを睨み据えていた。
イナゴの大群は、胴部に比して歪に巨大な両の足でもって大地を踏みしめながら、激しく体を揺すっていた。イナゴの大群が全身を揺さぶり、耳障りな駆動音がけたたましく周囲に鳴り響いたかと思えば、ついで、横に連なった銃列が一斉に火を噴いた。
武骨な大口径の銃口より数多の銃弾が飛び出し、黒い雹雨となって激しく唸りを上げながら、魔術障壁へと押し寄せた。
まるで、巨大な波濤の如き勢いで、一斉に降り注いだ銃弾の雨は、しかし、蒼白い一層の、ガラス細工の様な魔術障壁に触れたかと思えば突如、静止する。
魔術障壁に阻まれ、銃弾の嵐は、大きく勢いを落としたのである。
しかし、銃弾は山と存在する。
十の銃弾が動きを止めようとも、後方から百を超える銃弾が、五月雨式に障壁へと迫る。
群がる銃弾の嵐が、障壁表面に続々と鋭い牙を突き立ててゆく。
押し寄せる銃弾を前に、障壁が内側へとわずかにたわむのが見えた。
これを好機とみてか、銃弾がますますに障壁へと押し寄せてゆく。瞬転、障壁が、ゴムかなにかのように、内側へと弓なりに窪むのが見えた。
だが、大きくしなりを上げた障壁は、決して砕けることは無かった。
内側へと弧を描くようにして凹んだ魔術障壁は、今度は一転、大きく前方へと反撥を開始する。
極限を超えて収縮したバネが、力を開放され一挙に伸長するように、障壁もまた、前方へと勢いよく跳ね上がり、表面に突き刺さった無数の銃弾を払いのけていくのだった。
数十発、数百発という銃弾が、魔術障壁により弾かれ、周囲に飛散していくのが見えた。
瞬間、すべての銃弾は虚空を掠めながら、力なく地上の上へと零れ落ちていく。
もはや、黒く視界を埋め尽くした雨はもはやそこには無い。
晴れ渡った視界の元、そこにはあるは、機銃の斉射を不発に終わり、いかにも呆然と立ちすくむ、機械仕掛けのイナゴの群れの姿だけであった。
GLMストーク機械のイナゴによる機銃の掃射は、魔術障壁の一枚も破壊できぬままに無力化されたのである。
銃弾による嵐はここに鳴りを潜めた。
そしてここに攻勢は、防衛部隊の手へと移ったのである。
新月の傍らで友軍による魔術が敵軍目掛けて、飛び交うのが見えた。
大岩ほどあろう火球が居並ぶイナゴを飲み込み、青紫色の閃光が機械仕掛けのイナゴの腹部を刺し貫いていくのが見えた。
イナゴらが炎の中で黒い残骸となって大地へと力なく沈み込んでいくのが見えた。続々とイナゴの大群が炎に焼き払われていくのが分かった。
今、新月らは戦いの激戦地の真っただ中たる最右翼に身を投じたのである。
戦場を、左翼、中央、右翼と見た時、今、新月らが駆け付けたこの右翼こそは、トーノ、イゾルデ両名による陽動策の要の位置とも言えた。
敵GLMストークならびにステルス機を懐へと引きこむために、部隊はあえて弱点を晒し、偽装撤退にて守りを固めつつ敵軍をおびき寄せている途上にあったのだ。
そしてトーノ、イゾルデ両名の策は八割がたは成功を収めていると言えただろう。
味方は秩序だって戦列を整えたまま、後方へと退きつつあったし、敵軍は続々と前進を続け、まんまと網に絡めとられんとしている。
現状は第三軍はさしたる被害を出すことなく、目的を果たしつつあった。
兵は精強であり、イゾルデの采配は絶妙であった。どうやら、イゾルデはキャスター部隊を、撤退部隊の後方へ出向させて、魔術結界で彼を補助したらしい。
白いワンピース姿の少女と、くたびれたトレンチコートに身を包んだ無駄に顔立ちの良い青年の姿を新月は、周辺の陣列の一隅に確かに見たのだ。
――カエシア。彼女は今も一心に、最前線部隊を魔術結界によって支えているのだ。彼女の魔術結界による魔力の賦活化により、防衛部隊は強靭な魔術障壁を維持し続けているのだろう。
カエシアの能力や、防衛部隊の魔術障壁の堅牢性は疑う余地はない。
だが…もちろん、油断はできない。
敵にはインビジブルフォース、いわば、ステルス型のダモクレス部隊が未だ後方にて鋭い牙を光らせているのだから。
魔術障壁は、防護性を高めるため、時間的、空間的な集中を前提に展開されることが一般的である。
基本的には障壁は、全周性に張り巡らせることは無く、敵の進行方面に対して展開され、更には敵の攻勢に応じて、間断的に使用されるのが常であった。
だが、敵は数多のステルス機を有する。
そして彼らの姿は、視角やレーダの埒外にある。
彼らが、魔術障壁の展開の隙間を縫うようにして、こちらへと強襲を仕掛ければ、たちまちに戦線は崩れてゆくだろう。
ステルス機に自由に動かれれば、囮として敵を引きこんだつもりが、かえって、壊滅の憂き目に立たされる可能性すらもありえた。
だが――。
「トーノさん、右方向に敵、ステルス機三機です。ブランクオベリスクの破片が表面をコーティングしています。それを目印に攻撃をお願いします」
だが、ステルス機に自由に動かせるつもりなど、新月には毛頭無かった。
双狗が振るうは、不可視を切り裂く刃である。
新月が使役する無数の目は、秘されたすべてを白日のもとへとさらけ出してみせるだろう。
新月の言葉に応じるようにして、前方をゆくトーノが、勢いよく右方向へと駆け抜けていくのが見えた。
漆黒の体躯が、群がる機械仕掛けのイナゴの大群を横目に無人の空間を黒霧のように駆け抜けていく。
まばらになった戦場の空白地帯で、トーノが一瞬、動きを止めるのが見えた。
トーノの屈強な肉体がわずかに前かがみに傾き、ついで、彼の肩元より白刃が煌めいた。
流塋刃と呼ばれた彼独自のユーベルコードによる抜刀術によって左方へと一閃。更に返す刃で、彼の愛刀caidaを肩元の鞘から抜刀し、右方へ横一閃に一薙ぎする。
瞬間、トーノの左右、無人の空間にて爆炎が舞い上がった。
赤い焔の揺らめきの中、胴部分で輪切りに体躯を一刀両断された機影が二機、浮かんで見えた。
そう、敵のステルス機の姿がそこにあった。
「お見事です、トーノさん…。前方の敵は俺に任せてください――」
言いながら、新月はトーノの左方を前方へと向かいすり抜けていく。
巧みに、ブランクオベリスク、白い尖塔を操りながら、前方へと展開させた。無人の空間へとブランクオベリスクが走り抜けていったかと思えば、まるで目に見えぬ岩かなにかに衝突でもしたかのように尖塔が砕け散るのが見えた。
ふと新月が耳を澄ませば、前方の空間でじりじりと何かが駆動する音が確かに聞かれた。
前方の空白地帯をじっと睨み据えれば、砕けちったオベリスクの破片は空気に張り付いたまま、イナゴの様な形状を形成しながら新月に向かって、ますますに距離を肉薄させて来る。
そこに新月は敵のステルス機の姿を確かに見た。最も厄介であった隠蔽性が失われれば、敵機など襲るるに足らず。
新月は巧みに身を左右に振りながら、ステルス機の懐に飛び込むと鋭い前爪でもって、まずは、敵の胸部へと爪撃を一閃する。ついで、後ろ足で大地を蹴り上げ、天高く舞い上がりながら、すれ違いざまに相手の胴部を刺し貫いた。
中空にて下方を窺えば、白い粉塵で全身を潤色された敵機が突如、動きを止めて前方へと倒れむのが見えた。
ぐずりと崩れた敵影は、歪な姿を束の間、顕現させると、切り裂かれた胸部よりバチバチと青白い火花をあげながら、激しく爆散し、残骸を周囲へと飛散させながら、炎の中で灰と消えてゆくのだった。
数間程、優雅に空を遊泳した後、新月はふわりと大地に舞い降りた。間髪入れずに後方のトーノへと視線を送れば、穏やかな紳士の碧眼と目があった。
「トーノさん、次…敵ステルス機、十五機こちらに接近してるようです。位置はブランクオベリスクにて、補足します。俺が目になりますので、直ちに迎撃をお願いします」
新月が言えば、理知を湛えた藍色の瞳が穏やかに細められた。
トーノが首肯し、さっそく、新月の隣に並び立つのが見えた。
互いに横並びになって、大地を前脚で踏み鳴らす。二度、三度と助走をつけてそうして、一挙に大地を蹴り上げれば、再び双狗は黒い疾風となって、無人の空間を突き進んでいくのだった。
ブランクオベリスクにより、白い尖塔を前方の無人地帯に集積させる。四方八方より無人地帯へと手当たり次第に攻撃を仕掛ければ、尖塔は、脆くも崩れていったが、敵の無人機もまた三、四機程度は、オベリスクの攻撃により破壊されてゆく。
爆風が四方で巻き起こり、礫や砂片と化したオベリスクの破片が無人機へとびっしりとまとわりつき、彼らの輪郭を薄白く浮かび上がらせていく。
タネが割れてしまえばなんとも呆気ないもので、どこか間抜けに走り回るステルス型のダモクレスは、次いで、疾風の如く彼らを強襲したトーノの流塋刃、無数の剣戟の乱舞の前に呆気なく切り刻まれていくのだった。
一刀、また一刀と鋭い銀色の閃光が、虚空に走り、敵のステルス機を切り伏せてゆけば、十を超える火柱が無人の空間に舞い上がった。
瞬く間に、新月、そしてトーノの両名は二十に迫る敵機を無力化したのである。
そして、不可視の敵機の破壊に伴い、今、戦況が大きく動きだしたことを、新月は潮目を変えた戦況の変化と共に知るのだった。
新月が後方へと視線を送れれば、味方の最前列はますますに火勢を強めて、敵のイナゴの群れに激しい猛攻を続けているのがはっきりと伺われた。
至る戦線で、イナゴの大群が崩れ落ち、敵の残骸を乗り越えて友軍が一気呵成に前方へと突き進んでいくのが見えた。
新月、トーノのステルス機破壊が呼び水となったのだろう。限界を超えて直進してきたイナゴの群れを、第三軍は返り討ちにして、そうして一気に戦況を押し返したのだ
次いで、新月が前方へと視線を戻せば、GLMストークの大軍のはるか後方にて、項垂れるようにして頭部を大地に横たえていたレヴィアタンの周辺、敵デウスデウスエクスの群れが一時、疎となっていることに新月は気づく。
機械神と言えども、生産能力には限界があるのだろう。特にステルス機を生み出すというのは、神の名を負いしデウスエクスにも相当に負担を強いたのに違いない。未だに敵軍は数多、存在したが、しかし、今ここに一時的ながらも敵の生産能力を、損失が上回ったのである。
「トーノさん…」
新月はトーノへと告げる。新月がすべてを言い切るよりも早く、聡明たる紳士は、磊落とした様子で声音を弾ませる。
「えぇ、ここが好機の様です。最後に我らで一つ、丸裸となった大鯨の元へ、大花火が上がる前の挨拶といきましょうか」
最早、以心伝心、自らの考えが伝わっているようだった。
新月は相槌でトーノに応えると、一旦、友軍の中列ほどまで後退する。
新月の目と鼻の先、純白のワンピースに身を包んだ少女の姿がある。
カエシア・ジムゲオア、小柄な地球人の少女は、露出した肩元を激しく上下させながら、青色吐息で息を整えている。おそらく、これまで、彼女は絶えず友軍を魔力で強化し続けてきたのだろう。疲労の翳りが、蒼白い小顔にはくっきりと浮かび上がってみえた。
そして疲れた少女を前方から守るようにして、ゆきむらは仁王立ちを続けていた。
一見頼りなさげな男の後ろ姿が、なぜか今の新月には妙に逞しく見える気がした。彼は、これ以上、カエシアを疲弊させることなく、自らが盾となろうとしているのだろうか。
だが、ゆきむら、カエシアには申し訳ないが、この千載一遇の好機を逃す手はない。満身創痍とは言え、ここであと一息、彼女には力を振るってもらう必要がある。
部隊の合間を走り抜け、新月はカエシアの目前に立つと、穏やかな三白眼を覗き込む。
果たして、新月の想いが伝わったのか、新月の眼差しを受けて、少女は一度うなづいた。
新月は直ちに少女に問う。
「今、敵軍は此方側の猛攻により、押し込まれています。工廠部の破壊の好機は今を置いて他にはありえないでしょう。これより、俺とトーノさんは、敵軍を掻い潜り、工廠部分へ先制攻撃を仕掛けます。しかし、今の俺の爪はなまくら状態だ。そこで、カエシアさん、力を貸してくれません…?」
そこまで、新月が言い終えたところで、前方のゆきむらが踵を返し、新月、カエシアの両名を正面に見据えた。
平素、落ち着き払った形の良い双眸が苦悩気に歪むのが見えた。カエシアへの想いの強さが、物言わぬ彼の瞳から伝わってくるようだった。
だが…、カエシアは、メンターと呼ばれた男へと淡く微笑して見せると、ついで、再び新月を力強く見返す。
「えぇ、わかりました、オルトロスのお姉さん…。私の残った力、思い切り振り絞らせて貰います」
カエシアの声は力強く響いて聞かれた。
平素は他人の瞳をまっすぐに見据えることのできない内気な少女は、今、新月の瞳を正面からじっとのぞき込んでいたのだ。
「あなたの支援に感謝します…カエシアさん」
とくんと、僅かながら胸が熱くなった気がした。
脳裏は氷のように研ぎ澄まされている。今後、なすべき最適解も、最適解に至る方策もすべてが、新月の中には秩序だって組み立てられている。
だが、冴えた思考に反して、少女を前にした時、新月の胸裏は、なにか熱いもので満たされていたのだ。
そして、時折、感じるこの思いは、決して嫌悪を抱くものの類では無いように新月には感じられた。
そっと、カエシアが指先を新月へと伸ばせば、指先よりこぼれた粉雪を彷彿とさせる青白い光の結晶が、新月の全身を優しく包みだす。
瞬間、祝福の光は、胸中の燈火の揺らめきと相まってか、新月の内奥にて燻ぶる魔力を奔騰させていく。
周囲を淡く照らし出した蒼色の微光は、直ちに空気の中へ新月の中と霧散していった。
深い笑みを口元に張り付けながら、しかし、カエシアは力なくよろめき、彼女の愛するメンターの懐の中へと身をうずめていくのだった。
「オルトロスのお姉さん…。がんばって…ください」
カエシアが弱弱しく囀った。
ふと彼女の声が耳朶に触れた時、新月の口端は三日月型にわずかに綻んだ。
くるりとカエシアに踵を返し、大鯨を睨み据える。
「お姉さんは…禁止です、カエシアさん。私は新月――。月隠・新月です。あなたと同い年なのですから、次からは新月と、遠慮なくお呼びください」
屈託のない言葉が口元をついていた。抑揚の無い、平素と同じ声で答えたつもりだった。
だが…。
「えぇ…。じゃあ、新月ちゃん――。がんばって。応援してる…ね」
しかし、背中越しに響いたカエシアの声音は、平素のうわづったような響きとは無縁に、明朗とした調べでもって新月の背を打ち、早朝の山野へと流れていった。
別にカエシアの言葉に背を押されたというわけではない。
だが、大地を蹴る前脚は普段よりも幾分も軽やかな気がした。
トーノと並び立ちながら、新月は戦場の右端から大回りするような格好で、干戈を交える両軍を横目に、風となってレヴィアタンの座す本丸へと突き進んでいく。
時折まばらに現れる敵機を、一機、また一機と、鋭い前爪で敵を無力化しながら、二人は瞬く間にレヴィアタンの本丸へとなだれ込む。
トーノの抜刀が、そして新月の爪撃が、菫色の微光を湛えた大気のもと、幾筋もの光芒を刻んでいく。
白刃が瞬くたびに、白みがかった空へと向かい、火柱が幾条も舞い上がっていった。
レヴィアタン周辺に散在する敵影は、たなびく黒い旋風によって瞬く間に、切り刻まれて、戦場の露と消えたのだ。
勢いそのまま、新月、トーノは、露出されたままの敵甲板部へと取りつくと、増産されたばかりで、未だ統率が取れずにいる機械仕掛けのイナゴの群れを続々と切り刻んでいく。
ここに、レヴィアタンを守る者は一時、完全に消失した。今や、甲板部の先から大鯨の背部、更には工廠部へと至る巨大な空洞を守る敵影の姿は伺われない。
双狗の刃は、不遜たる機械神の喉元に匕首を突き付けたのである。
そして――。
ふと新月が上空を仰いだ時、白い閃光が明け空を駆け抜けていくのが見えた。
ここに、次なる刃が機械神レヴィアタンの喉元へと切っ先を向けられたことを新月は知る。
●
「四分三十五秒――」
磊落とした声音が透明な大気の中へと響きわたっていく。
雷の如き激しい力の奔流が体幹部から、両の四肢へと走り、指先へと駆け抜けていくのが分かった。
このあふれ出る力故にだろうか、声音が艶っぽく響きだすのは。
エクレア・エクレール(ライトニングレディ・f43448)は、自らの声色に滲みだした喜色の色に一人、口元を綻ばせた。
「四分四十秒――」
再び、時の経過を自ら、呟く。
かの漆黒の獣は五分、時を稼ぐと約束した。
そして、かの紳士は、見事に約束を果たしてみせたのだ。
エクレアは、陣列最後尾の本陣からは、戦場の全容を静かに一望する。
「四分四十二秒――」
勇猛果敢にデウスエクスの大軍を打ち破っていく友軍の雄姿を前に、エクレアは、今すぐにでも駆け出したい焦燥の想いを必死に堰き止め、かの紳士との誓い通りに、封ぜられた自らの力の解放に意識を傾注させ続けるのであった。
ふとエクレアの視界の中、朝焼けに燃える山野を、黒い旋風が、駆け抜けていくのが見えた。
墨汁を零したように、機械のイナゴの大群があふれ出した荒野の中を漆黒の風が突き抜け、今や、巨山となって、山野にて巨体を横たえる、敵の首魁たるレヴィアタンの吹き付けてゆく。
疾風の通り道に一致して火の粉が爆ぜ、白煙が空へとたなびいていくのが見えた。山野の中で赤々と燃える爆炎は、赤い焔の炬火を山野に灯し、そうして、ついぞ、黒々とした巨山の上へと続く焔の道を築くのだった。
疾風の指し示す先で、二頭のオルトロスが、巨山の如き威容を誇るレヴィアタンの額上に降り立った。
着地ざま、双狗が白刃を振るえば、甲板上に群がる機械仕掛けのイナゴの群れが続々と半身に切り伏せられていく。
圧巻とはまさにこのことだろうか。
かの紳士は敵軍の足止めに終始する事なく、敵の本丸に鋭い一撃を加えてみせたのである。
そして、今や戦場の流れは、完全にデウスエクス側から、猟兵およびDIVIDE第三軍の連合軍へと譲渡されつつあった。
今や、第三軍は雪崩の様な勢いで、敵陣を押しに押していた。
人型決戦兵器、キャバリアと酷似する銀白の騎士達は至る所で、並みいるイナゴの群れを大槍で切り払い、狙撃部隊による狙撃や魔術弾は、集簇するイナゴの群れを容赦なく焼き払っていく。
大槍の穂先が煌めき、狙撃銃が紫色に大気を染め出すたびに、イナゴの大群は残骸を山野へと横たえていくのが見えた。
「四分五十二秒…」
歌うように、高らかにエクレアは声を弾ませた。
となれば、エクレアがなすべきことは、友軍の進撃に乗じて敵の本丸を一挙に強襲することだ。
二頭のオルトロスの奮戦により、レヴィアタンを守るべき近衛部隊は存在せず、彼の背部で大口を開いた、工廠へと続く傷口は完全に無防備を晒け出している。
第三軍の活躍に敵軍は完全に後手を踏むに至り、結果、備え付けられた火器群は、上空へと向けられるだろうことは無いだろう事をエクレアは洞察する。
そう、ここに、敵工廠破壊のための道は開かれたのだ。
旋風が吹き抜けた先に、雷鳴は鳴り響くのだ。
そして落雷は、敵の心の臓を見事に貫いてみせようぞ。
「四分五十七秒…」
カウントダウン終了は間もなくだ。
言葉を発すると同時に、エクレアが右足を前方へと踏み込めば、雷撃の力を載せた一歩が、大地へと深々とめり込んだ。
右掌の第一関節を屈曲させ、指関節をぽきぽきと鳴らせば、指先よりは、全身に燻ぶる雷光の余韻が青白い棘となって周囲に牙をむく。
「四分五十九秒――」
雷のルーンは、エクレアの体内で高騰し、今まさに濁流となって溢れださんとしていた。
ふんと小さく鼻を鳴らして、見せる。
よかろう。すべての力を出し切るまでの事じゃ。
「――ジャスト、五分じゃ。ゆくぞ…」
誰に言うでもなく、エクレアは言い放つ。同時に、力を込めた右足で勢いよく大地を蹴りぬいた。
瞬間、エクレアの全身が優雅に空を舞う。たまゆら、心地よい浮遊感が、やわらかな肢体を包みこみ、ついで浮遊感は、全身を上空から押し付ける風圧へと姿を変じていく。
打ち寄せる暴風をかき分けながら、エクレアは空高く舞い上がる。そうして適度な高度まで至るや、今度はそのまま水平方向へと飛翔方向を転じ、山野にて巨山となって、その威容をそびやかす機械神レヴィアタンのもとへと飛翔を開始した。
一呼吸か二呼吸するかの僅かな間に下方の景色は見る間に移り変わってゆく。
目下に、敵軍を猛追するDIVIDE三軍の兵士らが現れたかと思えば、ついで砲火を浴び山野に残骸をまき散らす機械仕掛けのイナゴの大群が茫洋と視界に浮かびあった。しかし、高速で飛翔するエクレアのもと、イナゴの大群は直ちに後方へと遠ざかり、わずかな空白地帯が現れ、ついで、今度は一転、目標であるレヴィアタンが眼下に映し出さるのだった。
エクレアは、前方へと右足を伸ばして、虚空を勢いよく踏みしめた。
神の系譜に名を連ねる雷霆神たるエクレアには、いわば虚空と言えどもそこが足場になる。
右足が虚空を踏みしめれば、それまで勢いよく空を滑走していたエクレアの体は、ぴたりと中空で静止した。
中天にて滞空したままに、エクレアが下方へと視線を遣れば、大鯨の背部にて深々と大口を開いた巨大な空洞が視界へと飛び込んでくる。
大鯨の背部にて鋼鉄の皮膚は裂け、いわば、機械神の筋層とも言うべきか、鋼鉄製の隔壁が幾重にもなって巨人の皮下を覆っていることが伺われた。
友軍の報告によれば、敵の工廠部は、まさに皮下組織の最深部に存在するという事である。
隔壁は、幾層にもなって、大鯨の心の臓たる工廠部を防護しているのだろう。
敵は機械神の名を冠する怪異である。
かたや機械神、一方は雷霆神、二体の神の戦いは本来ならば白黒つかずに終わったかもしれなかった。
そう、仮に機械神が自らの傷跡付近を麾下の部隊によって守りを硬めていた状況を想定した時、さしものエクレアと言えども、敵の近衛部隊を壊滅させ、そのうえで隔壁を全て破壊し、敵の心臓部たる工廠部を貫くというのはおそらく困難を極めただろう。
だが、今や機械神は裸の王、そのものだ。
彼が生み出した大軍は、第三軍との戦いにて身動きできず、また彼が守りの綱としたダモクレス達も、猟兵の刃によって儚くも敗れ去った。
ここにエクレアは、雷のルーンに蓄えた力を全て攻勢へと変じることを可能としたのである。
両神による均衡は、ここには適応されることは無いだろう。
「これにてしまいじゃ、覚悟せよ、機械神レヴィアタンよ」
言いながらエクレアが右手を振り上げれば、無手の右手より巨大な雷槍が姿を現した。
襲雷とは、いわばエクレアの雷霆神が持つ神器の召喚とも言うべき技と言えるだろう。
今、エクレアの右手に握られるはUC級の力を持つ雷霆装が一つ、雷槍である。そう、隔壁を容赦なく穿ちぬける、無慈悲なる雷霆神の刃は今、エクレアの手の中にあるのだ。
半身を捩じりながら大槍を上空へと振り上げた。
白銀の閃光を迸せる雷装の穂先が、僅かに顔を覗かせ始めた朝日とぴたりと一致する。
鞭のように全身をしならせながら、雷のルーンに蓄えた魔力の一部を解き放ち、槍先に雷の力を載せる。雷の力、そして屈曲させた筋群に蓄えられた双方の力を解き放つように、エクレアはやり投げの要領で手にした雷槍を、眼下のレヴィアタン向かい投擲する。
雷槍がエクレアの指先を離れて、大口を開いたレヴィアタンの皮膚表面へと吸い込まれていく。
眩いばかりの雷光が、黎明時の空を一筋の落雷となって駆け抜けていくのが見えた。
して、落雷は、幾重にも張り巡らされたレヴィアタンの隔壁を、鋭い銀白の矛先で突き刺いた。
舞い起こったのは、激しい雷鳴であった。
突如、レヴィアタンの背部で巻き上がった紫色の閃光と共に、激しい轟音が鳴り響き、一つまた一つと分厚い隔壁が撃ち抜かれていくのが見て取れた。
まるで、紙細工を貫くかのように雷撃の刃が、隔壁を瞬く間に数壁ほど撃ち抜いていく。
そうして、計七層の隔壁を穿ちぬいたところで、白銀の刃はとうとう、周囲へと霧散するのだった。
「雷鎚――!」
間髪入れずに、エクレアは叫んだ。
雷鎚…雷のルーンより生み出された雷霆神の力は、次いで大槌となってエクレアの手の中に顕現する。
エクレアは中空で一回転し、地表面へと向きを変える。
両の足で中空にした不可視の足場を踏みしめながら、エクレアは、重力に抗したまま、レヴィアタンの背部にこじ開けられた大穴をきっと睨み据える。
目下の隔壁は雷槍の投擲により溶け出しており、巨大な空洞となって口を開いた傷跡のもと、計器類や電子基板によって構成された機械神の内臓部分がはっきりと伺われた。
未だ健在たる隔壁のさらに奥、機械神の心臓部たる工廠部は存在するのだろう。
となれば、すべての隔壁を打ち抜き、敵が心臓を破壊するのみ。
それが、エクレアにとっての乾坤であった。
不可視の足場を蹴りぬき、エクレアは、レヴィアタンの内部へと急降下する。
落下ざま、手にした雷鎚を振るい、目の前に立ちはだかる隔壁を一枚、また一枚と破壊しながら、機械神の奥深くへと潜り込んでいく。
雷鎚が、隔壁を撃ち抜くたびに、隔壁は砕け散り、そして雷鎚もまた、衝撃によって雷撃の余韻をわずかに周囲に残しながら霧散していく。
雷鎚が消失する度に再び、生み出しては振るい、隔壁を撃ち抜いていく。
雷鎚により、十五を超える隔壁を貫いた。そうしてついぞ、十六層目の隔壁を撃ち抜いたところで、遂にエクレアは大鯨の内臓最奥部へと到達するのだった。
エクレアは、広大な空間へと降り立った。ひたりと右足が鋼鉄で出来たレヴィアタンの内臓壁を踏みならせば、鉄が軋む重苦しい音が周囲に木霊する。
広大なる空間の先、そこにエクレアは鋼鉄の糸によって紡がれた巨大な繭を見る。
繭の中、数多蠢くGLMストークの影がある。数百、いや数千を超える機械仕掛けのイナゴは、鋼鉄の繭の中でそっと呼吸を続けていたのだ。
この巨大な繭こそが敵の工廠部に当たるのだろう。
ふぅと、エクレアは息を吐きだした。
呼吸を整えると同時に、手にした雷鎚を消失させ、かわって雷のルーンに込められたすべての力を開放、右拳を分厚い雷のオーラで包み込んだ。
腰を引き、右足を突き出す。丹田に意識を集中させながら深く呼吸すれば、右拳に収束した雷のオーラはますますに密度と容積を増してゆく。
「―――」
発声するでもなく、エクレアは右拳を突き出した。
瞬間、エクレアの右拳より迸ったのは、金龍を彷彿とさせる、巨大な稲光であった。
眩いばかりの金色の雷光が、じぐざぐに中空を駆けながら、勢いよく巨大な繭を飲みこんでゆく。
そは、エクレアにおける秘中の秘たる雷撃の拳、名を雷霆破という。
エクレアの雷のルーンの力を最大限まで乗せた巨大な一撃は、周囲を眩耀の光で照らし出しながら、一切の容赦なく、敵の工廠部を飲み込んだのである。
眩い光の中で、鋼鉄の糸で紡がれた巨大な繭が燃え尽きていくのが見えた。白光の中で、繭は焼け落ちてゆき、内部にて蠢いていた機械仕掛けのイナゴの大群は、黒い影となって瞬く間に灰燼と化してゆくのだった。
雷光が収束し、周囲の景観が再びくっきりとした輪郭を持ちながら浮かび上がっていく中、エクレアの視界の先にはただ無人の空間が広がるなかりであった。
そこにはイナゴの大群の姿も巨大な繭の姿もなく、ただ、ひっそりとした虚空が佇むばかりであった。
ふぅと、エクレアは安堵の吐息を零した。
そう、ここに敵の工廠は完全に破壊するに至ったのである。
移動のルーン、雷のルーンにわずかに残った力を使用して、エクレアは勢いよく鋼鉄の足場を踏みしめると上空へと飛び上がる。
侵入時の経路をそっくりそのまま逆方向へと突き進み、エクレアは、再びレヴィアタンの上空へと舞い戻った。
未だに、機械神『レヴィアタン』は微動だにすることなく大地にその巨体を横たえたままだったが、しかし、機械神の内臓部深くよりは悲痛なうめきの様なものが絶えず鳴り響いて聞かれた。
果たして、それはエクレアが齎した雷撃の残響であったのか、それとも、機械神の余喘であったのかは、エクレアには露として伺い知れなかった。
甲板部には、もはや新たなる敵機の姿は見受けられなかった。
もはや敵の一体とて見受けられぬ甲板部の閑散が、工廠部が完全に破壊されたという事実を物語っているようだった。
音の絶えた、黎明時の空をエクレアは駆け抜けていく。
エクレアの姿が東空へと消え、ついで、エクレアの残影を負うように朝日が水平線の先よりわずかに上空へと身を乗り出したのと同時に、機械神はここに初めて、露出した甲板部を閉じて、巨大な一歩でもって大地を踏みにじる。
すでにエクレアも、二頭のオルトロスもレヴィアタンの周辺を離れ、第三軍の陣列へと舞い戻っていた。
だが三者による刃により、ここに戦いは次なる局面へと移行したのである。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 大町・詩乃
大町・詩乃
◎
Cr
ラファエルさん達には「一時的に相手の動きを封じますので、合図を出したら全軍で攻撃して下さいね。」とお願いします。
武器巨大化した雷月を持ち、天耀鏡を盾代わりにした焔天武后を操縦して出撃。
相手の攻撃は結界術・高速詠唱で生みだした防御壁や、天耀鏡の盾受けで防ぐ。
防ぎきれないと第六感・心眼で判断した時は空中戦・見切りで回避。
合図を出して《自然回帰》発動。
システム停止と電源オフに追い込む。
巨体だと再起動にも時間がかかりますし、その間、猟兵さん達や第三軍やアンドレイさん達が全力で攻撃できます♪
焔天武后もレーザー射撃・一斉射撃・貫通攻撃で指令室っぽい箇所を撃ち抜いたり、神罰を籠めた雷月で斬りますよ。
●
東空にて日輪が地平線の上に鎮座する姿が伺われた。柔らかなヴェールを身にまといながら、太陽は、今まさに至尊なる姿を現前させたのである。
透明なる陽光が、朝焼けの朱色を反映し、微光でもって地上を薔薇色に照らし出していた。
山野の木々は朝日を浴びて、菫色に葉木を燃やし、人も、無生物も、獣も、生きとし生けるすべての生命は、朱色の色彩でもって自らの輪郭を山野に浮き彫りにしていく。
無数の木々と緑で彩られた平原のもと、しかし、奇岩の如くそびえる大山は、朝の光に燃える清浄たる世界の中、不純たる夾雑物として誰の目にも移っただろう。
大山は、黒い光沢を滲ませた皮膚を、燃える朝日へと向かい居丈高に伸ばしていた。
そうして、まるで陽光を嫌うようにして身震いしたかと思えば、大岩は地滑りするように前方へと滑り出してゆく。
巨大な大足が、大地を踏みしめれば、足元の新緑は踏みにじられ、地表は地肌を晒しながら大きく陥没する。
底ごもった地鳴りのような異音が周囲へとあふれ出し、ついで、ぐらぐらと大地が動揺するのが分かった。
大山が一歩を踏み出せば、おおよそ集落一歩分ほど、巨体が前方へと進みだす。
必然距離が縮まることで、大山の輪郭もまた、幾分も明瞭となった。
そは大山に非ず。
大山の岩肌は、鉱石群から構成されず、無機質な機械によって塑形されていた。山肌の様な温もりとは無縁に、淀んだ黒色の鋼鉄の肌からは、人工物を思わせる冷徹さが滲み出ていた。
大山は、象やサイを豊富とさせる、がっしりとした巨大な四足の足を有し、鯨の様な頭部を有していた。
巨大な足が一歩を踏み出すたびに、大地は悲鳴を上げ、空気はびりびりと震えだすのだ。
恐れ慄く世界の中を、機械神『レヴィアタン』なる大鯨は、まるで無人の野を行くように大地を踏み進んでゆく。
グリモア猟兵は、レヴィアタンを大鯨と評したが、しかし、四足の大足で大地を無遠慮に蹂躙しながら進むさまは、むしろ、鯨というよりは、獰猛な地上生物とも巨大な戦車のようにも大町・詩乃(阿斯訶備・f17458)には見受けられた。
生命の温もりを感じられぬ機械神を前に戦慄する世界を尻目に、詩乃は戦いの意思をますますに固めていく。
負けられないとの想いと共に詩乃は視線鋭く迫り来る敵軍を一望する。
詩乃の視界は、機械神レヴィアタンと、かの大鯨が生み出した数多の機械兵の姿で黒く埋め尽くされていた。
通り数丁ほど挟んだ前方には、イナゴを彷彿とさせる無数の機影がうごめき、更にその遥か後方にて、山と聳える、機械神レヴィアタンの巨体が、朝日の中でぼんやりと霞んで見えた。
巨大な波濤となって押し寄せる敵の大軍に対して、しかし防衛部隊は決して無力であったわけではない。
詩乃が協力する、DIVIDE直轄英国第三軍は、三万ほどの兵力でもって、整然と隊列を組み、巨山の進撃を迎え撃ったのだ。
今、英第三軍は、幾重にも張り巡らされた戦列の元、重砲や人型決戦兵器による白兵戦闘によって敵軍と一進一退の攻防を繰り返している。
戦列の先端部においては、友軍、敵軍との間で火砲による応酬が行われていた。
至る所で銃列が火を噴き、魔術の閃光が透明な大気を紫色に染め、火柱を轟かせた。
両軍の間で無数の銃弾が飛び交い、爆炎が轟き、硝煙が濛々と周囲に立ちこめていく。赤黒い焔と、白い靄に隠された戦場のもと、イナゴの様な形をしたダモクレスの集団が、山野の中の黒ずみとなって崩れ落ちていくのが詩乃にははっきりと見てとれた。
詩乃が見る限り、前衛部隊同士の戦いは友軍の圧勝とも言っていいほどに味方方の勢いはすさまじかった。
友軍が一人負傷する傍らで、敵軍はその五倍程度が戦場の露と消えていく。
第三軍が、一糸乱れぬ連携の元で敵を攻めれば、まるで雲の子を散らすように、イナゴの形をしたダモクレスの群体が離散していくのが見えた。
現状、戦況は、味方方の優勢のもと戦いを展開していると言えるだろう。
それもそのはずだ。
第一に、ラファエル率いる英国第三軍自体が統率されいる。
そして第二に、英国第三軍には、詩乃をはじめ、多くの猟兵らが助力しているのだ。
既に今しがた、味方猟兵達の奇襲攻撃により、機械神レヴィアタンは手痛い一撃を受けたことを詩乃は両の眼ではっきりと、補足した。
吹き荒れる旋風に続き、大鯨の背部を貫いた落雷により、機械神レヴィアタンは、最大の武器とも言うべき工廠部を失ったのだ。
これによって、レヴィアタンの継戦能力は大きく低下しただろうことは間違いない。
もちろん、工廠部を破壊したとは言え、予備部隊は未だ、多少なりともレヴィアタンの中で残存しているだろう。
だが、その戦力は微々たるものと言える。
となれば地上の敵を無力化する事さえできれば、レヴィアタンを破壊することも間もなく可能となるだろう。
ふむと、詩乃は、愛らしい小首をわずかにひき、そうして手を振り上げる。
白漆喰の様な、流線形を描く第二指をわずかに折れば、指先が朝日と重なった。
日輪を浴びえて、肌理の細かい、透明な指先が、ほの赤く染まってゆく。
陽光の揺らめきのもと、まるで陽炎のように何かが、詩乃の後方に突如、姿を現した。
詩乃が肩越しに振り向けば、後方で女皇帝を思わせる機影が、朝日の中で、神々しい偉容を反らす姿がはっきりと伺われた。
「焔天武后――」
詩乃がさえずりにも似た声音で愛機の名を呼んだ。
弦楽器のしなやかさと、打楽器の力強さとが同居した柔らかな詩乃の高音が黎明時の空に響き渡り、そうして、四文字の単語よりなる女帝の名が紡がれた時、突如、女帝の表面装甲が発赤を始めた。
声音に応じるようにして、女皇帝は四肢を燃えるような朱色に染めていく。大理石の柔肌は、次第に赤みがかり、すぐさまに真紅の眩耀を湛えてゆくのだった。
肢体が紅玉の揺らめきを滲ませた時、焔天武后、詩乃にとっての分身とも言うべき巨大な女皇帝は、その真の姿を顕現させたのである。
直ちに詩乃は焔天武后に搭乗する。
ふわりと吸い込まれるようにしてコクピットに乗り込むや、詩乃は、焔天武后を駆り、砲火飛び交う最前線へと一挙に躍り出る。
上空より眼下を臨めば、飛び交う弾丸や魔術弾が両軍の間に生じた僅かな間隙を、色彩鮮やかに埋め尽くしているのが見えた。
隊伍を組んだ機械仕掛けのイナゴの集団が、友軍の魔術弾やレーザーライフルに撃ち抜かれ、続々と崩れ落ちてゆくのが見えた。
対するイナゴの大群といえば、機銃の斉射で第三軍に反撃を試みるも、第三軍の前方に幾重にも巡らされた魔術障壁により、攻撃のことごとくは無力化され、虚しく四散するばかりであった。
現状、防衛部隊の奮闘ぶりにより友軍は戦術的有利性を維持し続けていた。
友軍の奮戦を窺いながら、詩乃は軽く安堵の息をつく。そうして、視線を戦場の正面から、戦線の左方向へと移していく。
激しい応酬を続ける第三軍の最前列左後方に、詩乃は、銀白の装甲に身を包んだ巨大な騎士の集団を目にする。
全長四、五メートルはあろう鋼鉄の騎士達が、敵の攻撃を弾き返す防衛部隊の後方にて、巨大な銀槍を手に手に、楔形に隊列を組む姿が伺われた。
鋼鉄の騎士たちは、確かグリモア猟兵の説明によれば、名前を人型決戦兵器といっただろうか。
DIVIDEにおける支援ロボを、機動力の面に特化させた機動兵器であり、英国内における新兵器であったことを詩乃は記憶している。
人型決戦兵器の一団は、中世の騎士の如き荘厳たる出で立ちでもって、一切、身動きすることなく隊列を組んでいた。
西洋兜を思わせる兜の隙間より除かれた金色の瞳は、鋭い眼光を放ちながら、敵軍の挙止を窺っているようだった。
詩乃は、ラファエル、第三軍の司令官にしてクラッシャー部隊の指揮官たる美貌の司令官が、人型決戦兵器に直接登場し、陣頭で指揮をとっていたことを思い出す。
ラファエルは、今まさに突撃のタイミングを見計らっているのだろう。
となれば詩乃にとっては好都合である。
彼らの突破力は、詩乃、そして焔天武后が持つユーベルコードと相性がよく、互いが互いを補い合いながら、戦況に大きな一石を投じるだろう。
突撃のタイミングを詩乃が作り出せば、戦況が勝利へと向かい、拍車をかけてゆくことは間違いない。
さっそく、詩乃は機内の通信回線を通して、ラファエルへと接触する。
通信回線の周波数をラファエルらのものに同調させれば、焔天武后の機内にて、味方部隊の会話が騒音となって飛び交い始める。
彼らの会話に割り込むような格好で、詩乃は、さっそく献策を彼らに示すのだった。
「ラファエル閣下。こちら、大町詩乃…独立部隊として参戦した友軍です。これより、私は、搭乗する焔天武后と共に敵軍をかく乱を仕掛けます…。一時的に相手の動きを封じますので、合図を出したら全軍で攻撃して下さいね」
柔らかな声音に続き、しかし、通信回線内で、生じたのは、一般兵たちによる海鳴りの様などよめきであった。
だが…。
兵らの同様の声を抑え込むように、詩乃の言葉に応じて男の声が喧騒の中でどっしりと響きだす。
「こちら、ラファエル・サー・ウェリントン。了解した…。あなたの名、そして、戦術行動は承認した。正直、突撃のタイミングを待っていた。あなたに従い、一気に敵軍、そしてレヴィアタンの喉元へと剣を突き立てよう。水先案内人、あなたに任せられるかな?」
ざわめきは潮を引くようにして、ひいてゆく。
一瞬の混乱は、優艶とした男の低音によってすぐに鎮静化されたのだ。
詩乃は、一人、コクピット内で頷くと、レヴィアタン向かい、機体を飛翔させ、敵との中間手ほどまで進んだところで、焔天武后を滞空させた。
焔天武后の右手には神刀『雷月』が、左手には大盾『天耀鏡』が握られていた。これらが焔天武后の矛と盾である。
そして、焔天武后の目とはつまりは詩乃である。
この目こそが、今、焔天武后の目前にて、インビシブル・ワン、レヴィアタンによって生み出された不可視の機影が十数機ほど、群がっているだろうことを明敏に見抜いていたのだ。
計器には敵の反応は無い。
だが、アシカビヒメとしての神聖が詩乃の体には宿っている。
空の青さを映した藍色の瞳は、おぼろげながらも敵影の位置を、いぶり出していたのである。
「焔天武后、いきますよ!」
詩乃が言えば、焔天武后がじぐざぐに空を滑走する。
次いで詩乃が、敵が存在するだろうおおよその位置に目星をつけて、結界術を展開すれば、障壁に弾かれ様にして、虫の様な形をした半透明の塊が、虚空へと弾かれるのが見えた。
弾かれた敵影のもとへと一挙に迫り、半透明な塊めがけて、詩乃は雷月を振るう。
筋肉の収斂に至るまで詩乃のすべての挙止は、焔天武后のものとして昇華される。
詩乃が剣を握り、上段から下段へと振り下ろせば、焔天武后もまた詩乃の動きを寸分たがわずにその場で再現する。
焔天武后の手にした雷月は、するりと空を滑るように走り、半透明な塊を表面より撫で切りする。
瞬間、元来なにものも存在しえない虚空に亀裂が入った。口を開いた亀裂のもとで、爆ぜる火の粉と共に、計器や電子版、鋼鉄の骨格とで構成された機械仕掛けの内臓器官が顔を覗かせていた。
コクピット越しに、何かを切り裂いた確かな感触が詩乃の掌に走っていた。
そう、空気に擬態したステルス型ダモクレスを詩乃は一刀のもとに切り伏せたのである。
半透明な虫型の塊は、矢状面で左右に完全に分かたれ、そのまま地上へと向かい力なく落下していく。そうして、硬い地表へ体を衝突させるや、激しい爆炎を全身から迸らせ、炎の中で燃え尽きていくのだった。
敵を切り抜けざま、詩乃はメインモニタ越しに周囲を窺った。これにて一機を無力化させたが、未だに詩乃の双眸は、十数機にも及ぶ敵の残存部隊を捉えていた。
未だ気は抜けないとの思いと共に、詩乃は間髪いれず、次なる敵のもとへと機体を急行させる。
機体を上下左右に湯らぶりながら、詩乃は動きに虚実を交えながら剣を振るう。
焔天武后は輪を描くようにして空を飛翔しながら、回避と剣戟を繰り返しつつ、雷月でもって、敵機を一機、また一機と切り伏せていった。
剣を振るうたびに、振り下ろした剣の軌道に合わせて、ぱちぱちと赤い火花があがった。ついで、火花を周囲へとまき散らしながら、ステルス機が、一機、また一機と中空で深紅の花傘を開き、爆炎の炎で空を赤く染め上げていくのが見えた。
インビシブル・ワン、いわばステルス部隊とは言え、詩乃と焔天武后の目を欺くことは能わず、結界術と斬撃の一撃、一撃により彼らは瞬く間にその数を減らしていく。
ステルス部隊の機銃は、大部分が結界術により無力化された。
さらには、ステルス機の特攻もまた、詩乃の卓越した心眼によって、すべてが空を切る。
結果、十数機にも及ぶステルス機は瞬く間に壊滅するに至るのだった。
ステルス機が一度、無力化されれば、もはや、天と地において詩乃の奇跡の技を阻むものは、存在しえない。
詩乃は、空中で剣を振り上ろすと、眼下に群がるすべての敵の大軍団へと切っ先を向けた。
鋭い剣閃で敵軍を射抜きながら、詩乃は声高に宣告する。
「自然の営みによらずして生み出されし全ての悪しき存在よ」
焔天武后を通して、淑やかたる声の調が山野を満たしていく。
「あなたたちに命じます」
金の琴を弾奏するような、しっとりとした声音が、菫色へと流れていく。
「アシカビヒメの名において動きを止め、本来あるがままの状態に帰りなさい」
そうして詩乃の抑揚のある声音が周囲へと鳴り響いたとき、奇跡の力は、宇内へと溢れだし、山野を若草色の微光で包み込んでいくのだった。
今や詩乃の声は、焔天武后、そして奇跡の力と相まり、山野を翡翠の粉雪でもって抱擁したのだ。
巨山となって聳えるレヴィアタンを、数多群がる機械仕掛けのイナゴの群れを、若草色の微光は、粉雪の儚さでそっと撫でてゆく。
しんしんと降りつもる粉雪は、温もりと清浄に満ちていた。幻燈の光を帯びながら、粉雪が世界を翡翠色一色に潤色していく。
降る雪は瞬く間に、盛りを迎え、そうして徐々に勢いを弱め、ついぞ、降りやんだ。
世界が翡翠から青空を反映した濃紺へと色彩を変わり、ついで、降り積もった粉雪もまた、大気の中へと霧散していく。
遠景にて巨大な一歩を振り降ろしたレヴィアタンが、態勢を崩してそのまま左方へと倒れこむのが見えた。自然回帰により、敵機は機能不全状態に陥ったのだ。
巨大な地鳴りが響き渡り、ついで、眼下にて大地が激しく動揺するのが見えた。
目下に数多広がるイナゴの大群もまた、完全に動きを止めてゆく。
ユーベルコード『自然回帰』により、今、すべての敵軍はここに時間を止めた。
――敵の本丸へと一斉攻撃を仕掛ける絶好の好機が生まれたと言えるだろう。
「今です、ラファエルさん…!レヴィアタンへと大攻勢を仕掛けましょう」
通信回線越しに詩乃が告げれば、ラファエルの返答は、彼が指揮する銀装騎士達の突撃によってなされた。
眼下にて、ラファエルら率いる人型決戦兵器部隊が、群がる敵の陣列を突破し、体勢を崩したレヴィアタンへと流れ込むのが焔天武后のモニター越しに詩乃にははっきりと見て取れた。
当意即妙とはまさにこのことで、ラファエルの突撃に続き、アンドレイら狙撃兵たちもまた、白銀の騎士たちに随伴し、レヴィアタンをレーザライフルの射程に捉えると、間断ない狙撃でもってレヴィアタンへと斉射を開始する。
紫色の閃光が束とって、群がる機械仕掛けのイナゴの群れを飲み込み、そうしてレヴィアタンの頭部へと注がれた。
閃光の中を銀色の刃となった騎士たちが一挙に走り抜け、レヴィアタンの前頭部へと無数の槍撃を注ぎ込む。
銀白色と紫色の二色の光が混淆し、レヴィアタンの分厚い鋼鉄の皮膚を撃ち抜けば、剝き出しになった頭蓋部より、赤、青、黄の三色に明滅する巨大な計器が顔を覗かせた。
いわば、そこはレヴィアタンの頭脳部とも指令室ともいえるのだろう。
この頭脳部より信号が伝達されることで、大鯨の従える機械の軍団は一糸乱れぬ行軍を可能とするのだろうことが、詩乃には直ちに推察された。
ならば――。
「アンドレイさん、ラファエルさん…あとは私にお任せください!」
コクピット越しに叫ぶと、詩乃は焔天武后を加速させる。
ふわりと、まるで羽のように、焔天武后が軽やかに空を舞い、高速で空を前方へと走り抜けていく。
瞬く間に、焔天武后とレヴィアタンとの距離が縮まった。
移動と同時に、詩乃はレヴィアタンへとけん制攻撃をも仕掛ける。
前傾姿勢で空を駆けながら、焔天武后が神剣『雷月』を横薙ぎすれば、七色のレーザーが、分厚い鋼鉄で守られた計器の表面を焼き払った。
更にレヴィアタンと焔天武后との距離が迫る。
レーザー砲が霧散していくのが見えた。
モニター越し、目と鼻の距離まで迫ったレヴィアタンの頭脳部を包んでいた鋼鉄の覆いは完全に溶け出し、三色光で明滅する計器は、最早、なにものにも守られることなく、無防備に外気に晒されていた。
「雷月よ...!」
後方へと右手を伸展させれば、焔天武后もまた、剣を下方へと傾ける。
加速度を落とすことなく勢いそのまま空を走れば、更に焔天武后とレヴィアタンとの距離が近づいた。
最早、両者を隔てる距離は、焔天武后の拳一つ分程度のわずかなものに過ぎない。
滑走の勢いそのままに、レヴィアタンとすれ違いざま、詩乃は、剣を勢いよく横閃する。
詩乃の動きを再現するようにして三日月の様な鋭い剣戟が、剥き出しになったレヴィアタンの頭脳部の上を滑りそのまま横なぎに計器群を穿ちぬいた。
焔天武后を通して、コクピット内の詩乃の掌にもしびれるような感覚が走っているのが分かった。
焔天武后はレヴィアタンの側方すれすれを駆け抜けていき、そうして大鯨の尾側側より、空を走り去っていく。
大鯨を通り抜けるや、詩乃は再び上空へと機体を返して、高高度より大鯨を見下ろした。
大鯨の頭部で巨大な爆炎があがったのはまさにその時だった。
赤黒い爆炎が轟く中、詩乃は機械神が自らの司令部を失ったのを確かに目撃する。
炎が収まり、その後、第三軍が後退を始めてもなお、大鯨は横たわったままだった。
そうして暫くして後、ようやくレヴィアタンは体動を始めたが、しかし以降の大鯨や群がる機械兵らの動きは精彩を欠いたものであり、機械兵はその後も、第三軍の攻撃によってますますに数を減らしていくのだった。
女神の祝福により戦いはここに潮目を大きく変える。
大成功
🔵🔵🔵
 エミリィ・ジゼル
エミリィ・ジゼル
◎
Cs
工廠部の破壊は成りましたか。いよいよレヴィアタン破壊作戦も大詰めです。いっちょやったりましょう。
「サメダディ、あいつ我々を差しおいてレヴィアタンを名乗ってますよ。真のリヴァイアサンがなんたるか思い知らせてやってくだち!」
レヴィアタンを名乗るクジラロボ相手に、UCにて『すべてのサメの父』ことリヴァイアサンを召喚。
サメダディが放つ大海嘯で小型ダモクレスもろともレヴィアタンを圧し潰しやります。
たとえ機械であろうとも海洋性哺乳類はサメの敵。絶対にぶっ潰す。
巨大怪獣対決になるため、周囲の被害はカエシア様の魔術結界で抑えてもらいましょう。
●
遠間にて、嶮山の如き巨大な影が揺らいで見えた。
白色の光を滲ませた朝空を切り抜くように、山ほどあろう大鯨のシルエットが、エミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)の遠景にて、前後左右へと傾きながら、巨大な一歩を踏み出したのだ。
夏草が一斉に、葉木を揺らしながら震え、大地が激しく動揺するのが分かった。潮騒にも似た地鳴り音が、底ごもった唸りを上げながら、鼓膜をじんとじんと揺らしていた。
顎元に人差し指を添え、エミリィは思案顔で前方の景観を俯瞰する。
近傍から遠景へと向かい視線を這わせれば、僅か先の平野地帯では、突き進むDIVIDE第三軍兵士の勇壮とした姿があり、ついで遠方に従うにつれて、機械仕掛けのイナゴの大群が、そうして広壮とした無人の空白地帯を挟んで、大鯨『レヴィアタン』が如何にも覚束なげに歩を刻む姿が見て取れた。
ふむと、エミリィは頷いた。
敵軍と友軍を比べた時、彼我の兵力差は今や伯仲し、兵の統率力や勢いは、第三軍にある。
今や戦況は、味方側に傾いていることがエミリィにははっきりと理解できた。
最も、現状は当然の帰結とも言えた。
味方猟兵により『レヴィアタン』の工廠部は破壊され、その後、間もなく大鯨の司令部も破壊されたのだ。
結果、レヴィアタン麾下のイナゴの大群は、もはや隊列組むことすらなく、無秩序な突撃を繰り返しながらますますに数を減らしていくばかりであったし、当のレヴィアタンもまた平衡感覚を失ったように、緩慢と身動きするばかりである。
いよいよレヴィアタン破壊作戦も大詰めということだろう。
味方の士気は高く、かわって敵軍の混乱ぶりは極まっている。
となれば、機械神『レヴィアタン』に次なる刃を突き付ける好機はまさに、この瞬間にあると言えるだろう。
「まっ、いっちょやったりましょう...!」
戦況を即座に見積もると、エミリィは踊るように歩を刻む。
一歩を踏み出せば、蒼のパンプスが緑の大地の上を踏み鳴らし、綿花を彷彿とさせるスカートの裳裾が白波の優雅さでひらひらと翻った。
楚々たる花の柔らかさと、しかし、優美さとはかけ離れた大股の一歩でもって、エミリィは鼻歌交じりに野を進む。
翡翠の瞳で戦場を具に観察しながら、大脳を全力で稼働させる。脳をけたたましく働かせながらも、しかし挙措はのびやかに、エミリィは一歩、一歩と歩を重ねていく。
エミリィの視界の先にて、第三軍は、快進撃を続けている。
当初の最前列の猛進に続き、今や第三軍は、全軍が一塊となって陣容全体をじりじりと前へ前へと進めていた。
前衛部隊が、敵陣を切り崩せば、すぐ後方の第二列が前衛部隊に続き、崩れかかった敵陣へと疾風怒濤の勢いでなだれ込み、ますますに敵軍を蹴散らしていく。
軍はまさに流動的に動く、一個の個体となったのだ。
雨あられと降り注ぐ銃弾やレーザーの光の中で、白刃が煌めき、平野に並ぶ機械仕掛けのイナゴの大群は黒く焼き払われ、鋭い槍撃によって切り伏せられていく。
崩れ落ちたイナゴを踏み越えながら、硝煙と焔によって、赤白く染まった山野の中を友軍の兵らが一糸乱れぬ連携のもと、前方へ、前方へと突撃を敢行していくのが伺われた。
今や部隊の熱狂は、連鎖的に後続の部隊へと順々に伝わってゆき、全軍は前のめりになるような格好で、敵の戦列を次々と矛で火砲で打ち破っていったのだ。
突き進む友軍の背中を見送りながら、エミリィは、最前線から視線を外すと山野の半ばあたりを左方に折れて、目的地である味方の救護テントへと歩を進めた。
本陣と前衛部隊の中間点には、今や、救護テントが数多、下ろされ、後方陣地を形成していた。
全軍の前進に伴い、後方の司令部もまた前方へと移されたのだ。
見れば、周囲には負傷兵に交じり、幕僚たちの姿も散見される。
そして、この場所こそがエミリィにとっての目的地のひとつであったのだ。
エミリィは、足取り軽く天幕の前に立つと、入り口付近に降ろされた帷幕をひとつ、またひとつと持ち上げ、天幕の内部をきょろきょろと伺った。
もちろん、第三軍と言えど、無傷とはいかない。敵よりの攻撃により少なからず負傷するものもあり、彼らは負傷兵としてテント内へと収容されたのだ。
事実、テント内といえば、負傷兵と医療スタッフとで埋め尽くされており、至る所で処置を受けて悲鳴をあげる患者らの姿が散見された。
とはいえ、負傷者の大部分は軽症疾患者であり、打撲や単純骨折、軽度の熱傷などのものがほとんどであるようで、簡易的な処置によって皆が皆、直ちに戦線へと復帰していく。
また、中には負傷とは関係なく、魔力を回復のために一時休息をとる者の姿も数多、見受けられた。
そんな負傷兵たちを横目に、エミリィは、三つ、四つと天幕の中を窺い、そうして遂に、五つ目の天幕へと足を踏み入れた。
ふと視線を左右へと交互させれば、部屋わきのベット上で、眠たそうに身を横たわる少女と目があった。
微睡みがかった三白眼は、当初、いかにも力なさげに目じりを下垂させるばかりであったが、エミリィの姿をぼんやりと眺めるうちに、徐々に徐々にと瞬きの回数を増やしていき、いくばくかすると、仰天がちに大きく見開かれる。
三白眼の少女は、ベットの上に横になったまま、ばたばたと両手をばたつかせる。
そのたびに、肩元にふんだんにあしらわれた花柄のフリル模様が、白い花弁を優雅に震わせた。
大多数の兵士らが、統一された軍服で全身を固め、室内で身を寛がせる中、無地のワンピース姿に身を包んだ少女の存在は他者に奇異の感すら抱かせるだろう。
最も、エミリィとしては少女がワンピースに身を包もうが、パンクスタイルでふるまおうがそれが些細な問題でしかないことを知り尽くしていた。
ケルベロスとしての実力が服装や武器で規定されるものでは無いのだから。
エミリィは、口元に微笑を浮かべる。
そうして、少女へとあいさつ代わりに手を振れば、少女カエシアは、汗ばんだ小顔をどこか面映ゆげに赤らめながら、エミリィに鄭重に会釈して応えてみせるのだった。
エミリィはそのまま二三歩と天幕内を進み、カエシアのベットの前に立つ。
カエシアの傍らには、くたびれたトレンチコートを羽織る、怪しげな長身男の姿もあった。
寂れた探偵風の風貌をした男と、少女趣味を絵にかいたような少女の両者の間で視線を交互させながら、さっそくエミリィは口火を切る。
「ゆきむらさん、カエシアさん、おはようございます。…お休みしているところ申し訳ないのですが、再び二人の力をお借り出来ないでしょうかね?」
エミリィが言えば、カエシアがベット上で半身を起こすのが見えた。直ちにカエシアが応える。
「もちろんです、エミリィさん…。私はばっちり休憩しました。魔力も戻ってきたので…お手伝いさせてください」
カエシアが小首を縦に振り、エミリィに首肯すれば、ゆきむらの妙に逞しい両腕がカエシアを抱きかかえるような格好で、華奢な両肩を支えた。
カエシアの仄かに赤らんだ白磁の頬が、まるで林檎のように真っ赤に染まりあがるのが見えた。
ゆきむらの肩を借りながら、カエシアが、どこかたどたどしげに立ち上がる。
そんなカエシアの姿をにんまりと眺めながら、エミリィは言の葉を連ねてゆく。
「お加減大丈夫そうですかね・・・? 実は、今から敵のサメロボットに真なる海の支配者が何者かってことをわからせてやろうと思うんです。ただ、真の海の王…サメダディの大海嘯はちょっと手加減が効かなそうでしてね。今、勢いよく攻めてる友軍の皆さんたぶん、巻き込んでしまうんですよ。なので、カエシアさんには一つ、魔術結界で友軍を守ってもらって、被害を抑えて貰いたいんですよ」
捲し立てるようにエミリィが一息のもとに言い切れば、カエシアはしばし目を丸く見開きながらも、二つ返事で、首を縦に倒した。
エミリィもまた目礼してカエシアへと返答した。
それにしても実際に機械神『レヴィアタン』が話題に上がるや、エミリィの脳裏には『レヴィアタン』の名を名乗る不遜なクジラロボットの姿が苛立ちの感情ともにより鮮明に浮かび上がっていくようだった。
クジラが『レヴィアタン』を名乗ることに、エミリィは内心で得も言われぬ怒りを抱かずにはいられなかった。
鮫ロボットならば、無機物とは言え、海獣『レヴィアタン』の尊名を自称することも多少は理解できる。
だが、敵は鮫ならぬ鯨なのだ。
海洋性哺乳類である鯨如きが、王の名を名乗るとは不敬が過ぎるというものだ。
ディバイド世界はもちろん、ユーディシー世界において、鮫は恐怖の対象であり、皆から愛される海の王者である。
比べて、鯨など一部国々が口を尖らせながら捕鯨禁止を叫ぶ程度の愛玩動物に過ぎない。海の王を名乗るには分不相応にすぎる。
しかも、かのクジラロボットは自らを海の王と自称し、海では鮫に対抗できぬことを知ってか、陸上をわが物顔で蹂躙する始末である。
卑劣にして、そして不遜なるクジラロボットに制裁を下さなければ、鮫魔術士の名も廃るというものだ。
エミリィは力強く拳を固める。
そうして内心で独り言ちるのだった。
――たとえ機械であろうとも海洋性哺乳類はサメの敵。絶対にぶっ潰す。
一人無言のまま、自らへと固く誓いを立てる。
すべての鮫を代弁するように誓いを固めるや、エミリィは頭をあげて前方を見据える。
ふと視界に飛び込んできた、カエシア、ゆきむらの両名の表情からは、なぜか緊張感の様なものが漂って感じられた。
クジラロボットとの激戦を前にすくんでいるのだろうか。
二人を幾分も寛がせようと、エミリィは、楚々たる笑みを二人へと送る。
そうして。エミリィは、カエシア、ゆきむらの両名を連れ立って、三人して最前線附近へと一挙に躍り出るのだった。
攻めに攻める友軍を横目に、エミリィ、カエシア、ゆきむらの三人は、戦場を大きく迂回して戦場の先端部へと一挙に迫る。
ますます激しく火砲で応酬する両軍を尻目にしながら、エミリィはさっそくサメダディ召喚の儀を開始する。
召喚の儀式と言っても大層な仕掛けを必要とするものでは無かった。
「カモーン! サメダディ!」
空を仰ぎ、エミリィは声高らかに叫ぶ。
ただそれだけで儀式は完遂される。
奇跡の力を帯びたエミリィの言の葉こそが、うつせみの世と特殊な異空間、通称『謎のかじできないさん空間』を繋げる鍵であり、サメの父たる『リヴァイアサン』を呼び出す儀式のすべてなのだ。
エミリィの声音が、朝日射す蒼天へと響き渡ってゆけば、突如、天空に巨大な亀裂が一筋、走った。
ふと何かがエミリィの頬を流れ落ちていった。
雨だ。
雨の雫がエミリィの頬を撫でたのだ。
ふと見れば、大きく穿たれた亀裂より、無数の雨粒が零れだす。
雲一つない、蒼天のもと、亀裂よりこぼれ出した豪雨は、ますますに雨脚を強めながら降りしぶき、山野の緑を、兵士らを、機械仕掛けのイナゴの大群を激しい雨粒で洗いだしてゆく。
雨は瞬く間に、足元に水面を作り、エミリィの膝丈まで水かさを増していく。
それでもなお、斜に降り注ぐ雨が止むことは無く、ついぞ降りしきる雨により水面は、エミリィの大腿部までもが水中に浸水するまでに水位を上げるのだった。
ゆったりと、雨が途切れるのがわかった。
ふと周囲を見やれば、それまで猛攻を続けていた友軍が水に足を取られてぴたりと前進を止めるのが見えた。
後退する敵軍との間に必然空白が生まれるのが分かった。
ちょうど、巨大な大鮫一頭分が姿を顕現させるに十分な間隙が彼我の間に生まれたのである。
こほんと、一度咳払いすると、エミリィは再び叫びをあげる。
「カモーン! サメダディ!」
エミリィの柔らかな声が響き渡れば、中天に穿たれた亀裂はますますに広がってゆき、まるで薄氷がひび割れるように空が砕け散った。
歪な欠損孔が青空に大口を開いたいのである。
ぎょろりと黒い巨体が、虚空に穿たれた大穴より姿を覗かせるのが見えた。巨大な影は、ふわりと飛び上がると、大穴を超えて、勢いよく地上へと舞い降りた。
巨体は、対峙する両軍の合間に悠然と降り立つと、その巨体を水面の上に寝ころばせながら、鋭どい牙をむき出しにする。
朝日が、銀蒼色の鱗を優艶と照らし出していた。優雅な曲線を描く肢体の先、魚類を彷彿とさせる、勇ましくも愛らしい面差しがきらきらと輝いていた。愛くるしくも凶暴そのものの眼には、海の王者の如き荘厳さが滲みだしているようだった。
そこに現れたのは、巨大な一頭の大鮫であった。
四海を股にかけ、全てのサメを使役する、サメの父『リヴァイアサン』がここに姿を現したのである。
リヴァイアサンの勇壮たる姿を目の当たりにした時、エミリィは、自らの胸中で奔騰する熱狂と感嘆の濁流に飲み込まれかねないほどだった。
「カエシアさん、それでは、あとはお任せします。みなさんの事を守ってあげてくださいね!」
言葉短く言い放つと、エミリィは早速駆けだした。
泳ぐようにして水面を進み、サメダディの傍らへと躍り出ると、エミリィは、ダディの銀蒼色のサメ肌を優しく一撫でし、ついで、ダディへと告げる。
「サメダディ、あいつ我々を差しおいてレヴィアタンを名乗ってますよ」
エミリィが言えば、ダディがエミリィへと顔を寄せるのが見えた。
愛らしいどんぐり目が、エミリィをじっと正面に見据えていた。エミリィは、そっとダディの頬を撫でると、ダディの頭部にしがみつき、そのまま額の上にて仁王立ちする。
両腕を組み、背筋を伸ばせば、ぐっと大空が近くに迫ってきた。蒼天へと向かい大きく背を伸ばしながら、一度深く呼吸をつくと、エミリィはさっそく啖呵を切る。
「ねぇ、ダディ。私たちで、あの偽物に本物の実力を教えてやりましょう?」
エミリィが告げれば、やにわに足元が動揺する。
そう、エミリィを眉間に載せたサメダディが、山野の彼方、未だふんぞり変えったままのクジラロボ『レヴィアタン』のもとへと首を向けたのだ。
振り落とされまいと、エミリィは両の足に力を込めて、ダディの額の上に踏みとどまる。
ぐるりと足元が旋回すれば、必然、エミリィの前方に再び敵の大軍が浮かび上がる。
群がる無数の機械仕掛けのイナゴの大群がそこにはあり、彼らに守られるような格好で、平野の奥で身を縮こまらせるクジラロボ『レヴィアタン』の姿が見て取れた。
クジラロボとダディの距離は、おおよ小さな村落一個分、離れているが、サメダディにとってのこの程度の距離は目と鼻の距離と言えるだろう。
そう、敵は、大海嘯の距離範囲内にある。
誰が海の王を名乗るに相応しいか、さっそく、クジラロボットにわからせてやろう。
「ダディ、とっておきの技で、あのクジラロボに真のリヴァイアサンがなんたるか思い知らせてやってくだち!」
エミリィがいわば、阿吽の呼吸でサメダディが尾ひれを逆立てるのが見えた。
サメダディがその巨体を水面の上で勢いよくばたつかせれば、突如、水面は総毛立ったように、ぷつぷつと泡を浮かべ、至る所で水しぶきをまき散らす。
サメダディが、円を描くようにして、遊弋を開始する。
銀蒼色の鱗が水面を打つたびに、飛沫がきらきらと上がり、水中が舞い上がった。一周、二周と巨体が円を描くたびに、水面は渦を巻きながら荒々しい波濤を形成し、ダディの周辺で獣の様な唸りを上げるのだった。
これこそが、真のリヴァイアサンのみが使用することを許された、大海嘯の前触れだ。
エミリィは、水平性にぐるぐると回転する足場のもと、微動だにすることなく、雄々しく両腕を組み、ダディの大旋回を共に体感した。
水平性に揺れ動く足場は、たしかに多少の浮遊感と眩暈の感覚をエミリィにもたらしたが、周囲でますますに渦を巻き、そうして渦潮を形成していく水面を眺めれば、不快感などどこ吹く風、心地よい笑みがエミリィの口元に浮かび上がった。
ダディが五週目の旋回を終えて、そうして六週目へと差し掛かるや、山野に溢れた水面は、ダディの周辺にて集積し、大海嘯を生み出す。
ダディが六週目の旋回を終えて、ぴたりと動きを止める。
瞬間、波はますますに荒れ、水面は高まり、山々を飲み込むほどの巨大な津波がダディを中心に水面よりせり上がったのである。
「大・海・嘯…!」
エミリィは言いながら指先を優雅に空中で泳がせる。
口元の笑みがますます深まった。
周囲で水柱が幾条も舞い上がるのが見えた。
足元のダディが、気持ちよさげに目を細めている。
歌うように鼻を鳴らしながら、エミリィはしなやかな指先でもって、群がるイナゴの群れを、クジラロボット『レヴィアタン』を指し示す。
エミリィの挙止に応じるように、ダディが水面の上で毬玉のように跳ね上がった。
浮遊感に次いで、着水に伴う圧迫感がエミリィの足元に走った。
水しぶきが光のシャワーとなってエミリィの周囲で迸しる。
して、淡く迸る水沫の中、激しくうねりをあげた水面は、ダディの着水に押し出されるような格好で、巨大な津波となって群がる機械仕掛けのイナゴの群れを目掛けて押し寄せてゆく。
巨大な津波は、濁流となって木々をなぎ倒し、岩々を砕きながら群がるイナゴの大軍を飲み込んだ。
津波は、上方より機械仕掛けのイナゴの群れを飲み込むや、激しく波を砕き、無数の飛沫でもって、機械仕掛けのイナゴ達をかみ砕いていく。
荒ぶる波濤の中、イナゴ達は水圧によって全身を攪拌され、四肢を歪に屈曲させながら、津波の中で黒い藻屑となって朽ち果てていくのが見えた。
津波が広がるにつれて、山野に蠢く無数のイナゴは続々と砕かれ、圧殺されてゆく。大量の機影が、放たれた大海嘯の中で黒い小点と化して沈んでゆくのが見えた。
だが、津波の猛威は未だに収まることなく、イナゴの群れの奥で佇む、大鯨『レヴィアタン』にも迫る。
巨大な水壁が、大鯨レヴィアタンを上空より飲み込めば、山ともある巨体は海嘯の白い光の泡立つ濁流によってその巨躯を横殴りにされる。
高水圧の飛沫が大鯨レヴィアタンの鋼鉄の皮膚を穿ち、鉄の骨格を砕き、電子基板と計器、無数の配線で構成された内臓を貪り食らう。
大鯨が濁流の中で、身もだえしながら数町程、後方へと流し出されていくのが見えた。
大鯨レヴィアタンが後方へとずぐりと崩れ落ちれば、再び地鳴りが鳴り響いた。
レヴィアタンは腹部を天井に晒しながら、仰向けにその場に転倒していた。海の王を自称するには、あまりにも無様な姿が今、白日のもとに晒されたのである。
大海嘯は、徐々に潮を引いていきながら、まるで夢幻のように足元を浸した水面と共に大気の中へと霧散していった。山野を満たした水面が消失すれば、サメダディもまた、その輪郭を大気の中へと曖昧に溶け込ませていく。
エミリィは、ダディの額の上から飛び降りると、大地の上に降り立った。
すべての鮫の父『リヴァイアサン』も、一時周囲を浸した水面もその後直ちに消失し、かわって、山野には全身を砕かれて、巨体を力なく大地に横たえる『レヴィアタン』と、小山となって堆積した敵ダモクレスの残骸だけが残った。
ここに海獣の名を冠するのが、誰にこそ相応しいかが、証明されたのだ。
これにて多少は溜飲を下ろすことはできた。ふふんと口端を綻ばせながら、エミリィは満足顔で後方へと振り返る。
友軍への被害という点において、多少の危惧感を抱いていたエミリィであったが、カエシアの結解術により、友軍にはさしたる被害は無いようだった。
万事はうまくいった。
ほっと胸をなでおろしながら、エミリィは、軽やかに踵を返すと友軍もとへと合流を果たし、次なる攻勢に備える。
この後、機械神『レヴィアタン』は再び進撃を開始するが、しかし、友軍の大部分を失い、鋼鉄の装甲をつぎはぎだらけにするその姿からは、かつての威容は完全に失われていた。
そして、機械神はこの後、さらなる醜態をさらすこととなる。
大成功
🔵🔵🔵
 暗都・魎夜
暗都・魎夜
【心情】
ダモクレスのとんでもなさは理解しているつもりだったが
このデカさで地上をズカズカ歩いているんだから大したものだぜ
こいつに好き勝手暴れられると困ったもんだが、ここで倒せばひと段落だ
一気に決めてやろうぜ!
【決戦配備】Sn
UCの発動のタイミングを作れるよう、支援射撃を依頼
【戦闘】
バイクを「運転」して移動
「天候操作」でレヴィアタンの攻撃を阻害
「戦闘知識」「勝負勘」で有効そうな場所を分析し
「リミッター解除」「限界突破」して、UCの「捨て身の一撃」を叩き込む
お前さんらにも事情があって、そのために必死なんだろうさ
だが、そのために戦いを引き起こそうって言うのなら、いつだって俺はその前に立ってやる
「ダモクレスのとんでも無さは理解しているつもりだったが…このデカさで地上をズカズカ歩いているんだから、大したものだぜ」
巨山は今や姿勢を翻し、山野に尊大なる体躯を仰向けに横にしていた。
機械神『レヴィアタン』は猟兵の度重なる攻撃を受け、今しがた横転したのであった。
かの巨山とでも言うべき機械神が転倒した様を目撃した、暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)の口元をついたのは、感嘆の言葉であったのだ。
猟兵により齎された、塩気まじりの雨は今や降りやみ、ついで足元に堆積した湖も夢幻のように消えさった。
木々や緑の上を濡らす、真珠の様な雨雫だけが、豪雨の名残として、今や山野にていかにも儚げに残存するのみであった。
もちろん豪雨の残滓は、雨の雫となって葉木の上で煌めくだけだったが、豪雨の後、相次いで引き起こされた大海嘯は、より大きな傷跡を山野に、いやレヴィアタンを始めとした敵軍に残していった。
雨後の山野には、今や物言わぬ残骸となって小山を築く機械兵が所せましと散在していたし、機械神レヴィアタンもまた、装甲の表面を穿たれ、深々とした創傷を巨体のあちこちに浮き彫りにしていた。
心地よい静寂の中、東空より差し込む朝日は、雨に濡れて炯々と深緑をきらめかす夏草と、無慈悲に打ち捨てられ鉄の残骸と化した敵軍とを、相反する陰陽の対称性でもって照らし出していたのである。
魎夜は大きく息を吸い込むと、もはや三々五々で平野に散在する機械仕掛けのイナゴの群体から視線を外し、機械神レヴィアタンを注視した。
敵ダモクレスの残党は、山野にて少数ながらも残存していたものの、レヴィアタンの護衛部隊は今や存在はしなかった。
今こそまさにレヴィアタンへと追撃を加える好機といえるだろう。
これ以上、レヴィアタンに暴れられるのも厄介である。
魎夜達の遥か後方には山村が控えており、レヴィアタンが前進を続けていけば、村民に被害が出る可能性がある。
おそらく、レヴィアタンには、DIVIDE直属英三軍の猛攻を防ぎきるほどの余力は残されておらず、山村まで迫ることは不可能に近いだろう。
だが、仮に第三軍とレヴィアタンが会敵すれば、第三軍の損害率もうなぎ上りに上昇していくことは間違いない。
となれば、レヴィアタンの矛が友軍を捉える前に、レヴィアタンを撃つ必要がある。
村はもちろんの事、兵士たちの損害を減らす為にも敵をここで討伐できればひと段落である。
魎夜は拳を握りしめると、友軍の合間をすり抜けるようにして駆けてゆき、陣列の最前列へと躍り出た。
軍の先頭に立ち、後方を振り返れば、居並ぶ兵士らの熱い衆目が、魎夜へと突き刺さる。
彼らのまなざしを微笑で受けながら、魎夜は声高らかに、兵士らを鼓舞する。
「こいつに好き勝手暴れられると困ったもんだが、ここで倒せばひと段落だ。一気に決めてやろうぜ!」
右拳を固く握りしめ、中空へと向かい振り上げれば、東空にかかった太陽と魎夜の拳がぴったりと重なった。
陽光を浴びた右拳は熱気を孕み、魎夜の心臓はますますに早く鼓動する。
ぐっと魎夜が兵たちへ向かい右手を突き出せば、兵士らが、おう、おうと怒号を上げながら武器を手に手に振り上げるのが見えた。
魎夜の言葉に、彼らは一斉に戦意を高揚させたのだろう。
兵士らの昂った士気がひしひしと空気の中に伝搬し、熱情の濁流となって魎夜へと流れ込んでくるようだった。
そして、彼らの魂の昂りを目の当たりにした時、魎夜は自らの中でユーベルコードの力が噴火寸前まで奔騰していくのが分かった。ぐっと力を制御しながら、魎夜は視線を兵らの間でさまよわせる。
ふと魎夜が、戦列の一角を窺えば、先の戦いにおいて、共に敵軍を打倒したアンドレイの姿が目に付いた。
冷静を絵にかいたアンドレイは、熱狂する兵らの傍らで一人静かに銃を構えているだけだった。
だが、しかし、多くを語らぬかの青年の中に魎夜は、激しい魂の律動を感じ取ったのである。
この場に居合わせたいかなるものより、かの青年は機械神レヴィアタン討伐を渇望しているように魎夜には見えた。
彼のことは信頼できると、魎夜の直感が告げていた。
いや、自分の背中を任せられるのは彼を置いて他にありえないと、魎夜は確信する。
必然、魎夜は、アンドレイへと体勢を向ける。
鷹揚とした挙止でもって、右手を振りながら、アンドレイへとあいさつ交じりに、声掛けする。
「今から、相手に強力な一撃を叩きこもうと思うんだが…発動にはちょっとばかし時間が必要でね。アンドレイ大尉、援護は任せたぜ」
「あぁ、任せてくれ。レヴィアタンの時間はわれら狙撃部隊が封じてみせよう」
撃てば響くようにアンドレイが返答した。
重くどっしりとしたアンドレイの声音からは、平素感じられぬ、抑揚のようなものが滲みだしていた。
魎夜はアンドレイへと首肯でもって謝意を示すと、居並ぶ兵士たちに背を向けて、レヴィアタンへと体勢を戻す。
遠景で仰向けに倒れたレヴィアタンが左右に激しく身を捩らせるのが見えた。
振り子のように、巨体が左右へと揺れていた。
二度、三度とまるで赤子が体を捩らせるように巨体が左右に傾き、徐々に徐々にと振幅を増してゆく。
そうして、ついに振り子運動が極点を超えた時、大鯨の巨体が大地を離れ宙へと鮮やかに舞いあがるのを魎夜は目撃する。
それはなんとも不思議な光景だったが、大鯨は、魎夜の遥か遠景にて軽やかに空中を踊り、優雅に反転を終えたのだ。
天上を向いていた鋼鉄の四肢が下方へと向き、次いで、鉄の巨体が重力に従い、大地へと向かい沈み込む。
ずぐりと巨大な大足が大地を激しく踏みしめれば、つんざく様な地鳴り音が魎夜の鼓膜をびりびりと揺らした。
激しい地鳴り音に続き、まるで足場は支えを失ったように、崩れゆく砂の様な心もとなさで、ぐらぐらと動揺を開始した。
魎夜の視界、木々も草草もすべてが激しく揺らいで見えた。
機械神『レヴィアタン』は、ただ体勢を整えただけであった。
奇抜な方法であったとは言え、ただ身を捩らせて起き上がったという一連の行為によって、地響きを起こし、地上のすべてのものがすくみ上がらせたのである。
規格外の化け物はまさにこの事だろう。
魎夜は嘆息まじりの苦笑を零す。
はは、と乾いた笑いを口元から零す。
口元をついたのは苦笑であったが、しかし、巨山とも見紛う怪異を前にしても尚、魎夜の中で戦意がくじけることは決してなかった。
内奥で熾火のように燃え盛る戦意の炎も、ユーベルコードの光もそのどちらもがますますに勢いを増しているのが魎夜には分かった。
激しく動揺する足場で、魎夜は鋭くレヴィアタンを睨み据える。
彼我の距離は遠く、徒歩では、接敵までかなりの時間を要するのが目に見えている。
下手に敵に時間を与えれば、山野にて散り散りになった機械兵が再び密集し、陣列を再構築する可能性もありえた。
となれば速度が求められる。
して、魎夜はその解決を自らの愛機レッドバージョンに託すことを即断する。
魎夜は振り上げた右手の元、指を鳴らす。
指と指とが擦れあり、乾いた音が周囲へと鳴り響けば、魎夜の傍ら、大型の自動二輪が虚空より姿を現前させるのだった。
レッドバージョン、魎夜にとっての愛機がそこに姿を現したのだ。
魎夜は流れるような挙措でもって、革製のバイクシートに腰を埋めると、両のペダルを踏み込んだ。
大腿部に力を込め、両足で挟み込むような形で体幹を車体に固定させる。
ついでグリップ部分を一度、二度と力強く捻れば、レッドバージョンは、百獣の王の如き咆哮を上げながら、激しく車体を上下させる。
肩越しにアンドレイへと手合図する。
三度、四度とグリップをひねれば、愛機レッドバージョンは、黒い息を吐きながら、ますますに激しく胎動を開始する。
魎夜は車体の上で体勢を前かがみに倒すと、全開までグリップをひねりあげた。
瞬間、レッドバージョンは獰猛な獅子となった。
車輪を激しく回転させながら、レッドバージョンは獅子の疾走でもって、急発進したのである。
夏草の絨毯の上を魎夜を載せたレッドバージョンが走り抜けていけば、草草は車輪に煽られて、舞い散っていく。轍より巻き起こる草の覆いの中を魎夜を載せたレッドバージョンは突き進んでいく。
魎夜の全身には激しい風圧がのしかかっていた。
高速で二輪を駆っているのだ。向かい風が齎す圧力は、尋常では無い。
レッドバージョンが進むたびに、ガタガタと車体が動揺し、車輪に弾かれた小石が周囲に飛び交った。
だが――、魎夜の笑みはますますに深めるばかりである。
体の芯を揺らす心地よい疾走感が、むしろ魎夜に、歓喜を齎していたのである。
しかし、内心で燻ぶる歓喜の念とは対照的に、思考は、研ぎ澄まされ、冴えわたっていくのが分かった。
魎夜は、せわしなく視線を動かしながら、機械神『レヴィアタン』の全身を隈なく注視し、敵を具に分析する。
視野情報は、視覚野へと伝搬され、直ちに処理されていく。
視覚野の得られた情報は、記憶野の中に眠る、これまで魎夜が蓄えてきた戦闘知識と混淆し、大鯨の弱点をあぶりだしていくのであった。
瞬く間に魎夜は大鯨の弱点部を見抜くのだった。
朱色の双眸が見つめる先、大鯨の下腹部よりは、蒼白い微光が零れていた。
魎夜が目を細めて、微光の発生元へと視線を這わせれば、下腹部の左上方から右下方へと走る裂創にすぐに行き着いた。
裂創の内部より、何か巨大な装置群がわずかに顔を覗かせている。
どうやら、蒼白い微光は装置群の一部から、外部へと流れ出しているようだった。
魎夜の勘が、かの装置群こそが機械神にとっての動力部であろうことを告げていた。
それは数多の戦場を戦い抜いてきた戦士ならではの直感であった。そしてこの種の直感は、総じて、的を得ているだろうとの確信が魎夜にはあった。
魎夜は、動力部へと至るだろう裂創部へと視線を固定して、鋭く睨み据える。
裂創は表層部分に留まり、装置群は、鋼鉄の皮膚と、幾重にもなって張り巡らされた特殊合金による骨格によって、重厚に守られている。
通常攻撃では分厚い装甲に阻まれて、動力部を穿つことは叶わないだろう。
だが、ユーベルコードならば話は別だ。
『紅蓮撃』が齎す、超威力の火炎撃ならば、いかなる装甲だろうとも打ち抜き、見事に動力部を破壊してみせるだろうとの自信が魎夜にはあった。
すでに魎夜の中ではユーベルコードの力は発現寸前まで高まっていた。
魎夜は、ユーベルコードの顕現に意識を集中させつつも、レッドバージョンのグリップ部分をさらに力強く捻りしめると、愛機をますますに加速させた。速度計は瞬く間にレッドゾーンに突入するも尚、魎夜は決して速度を緩めることはしなかった。
駆動音が益々に高まり、車体が勢いよく大地を滑走していった。
ここに魎夜を載せたレッドバージョンは赤い一条の矢となった。
そして放たれた矢を止めるものなど、何人たりとも存在しはしなかったのだ。
激しい駆動音を上げながら、レッドバージョンは無人の野を瞬く間に踏破し、僅かな間に機械神レヴィアタンの足元までに肉薄する。
下腹部の裂創が、今や魎夜の目と鼻の先に浮かんで見えた。
片手をハンドルから離すと、魎夜は、震鎧刀を右手に握る。同時に、魎夜は自らの体内で奔騰し、濁流となって駆け回るすべての力を、手にした震鎧刀へと収束させていく。
夜空を彷彿とさせる、青ざめた刀身がやにわに発赤していくのが見えた。
焔の妖気が今、震鎧刀の刀身にて集い、そして具現化したのである。ますますに、刃が紅蓮の色を湛えながら激しく燃え盛っていくのが分かった。魎夜は全神経をユーベルコード『紅蓮撃』発動のために傾注させる。
もはやユーベルコードは発動は間近に迫りつつある。
なればこそ、魎夜に求められるのは最良の一撃を繰り出すことだ。敵との距離を測りながら、魎夜は、剣戟の構えを取る。
左手でのみ、大型自動二輪を操り、右手を下方へと下ろし水平に剣を構えた。
ずいと、レッドバージョンが前進すれば、更に魎夜とレヴィアタンの距離が迫る。レッドバージョンが、地上へと落とされたレヴィアタンの黒影へと差し掛かった。
あと、呼吸一つ、二つの間に、魎夜を載せたレッドバージョンは、無防備にさらけ出された大鯨の下腹部に潜り込み、腹部すれすれを滑走しながら、大鯨の傷口を頭上に捉えるだろう。
しかし――。
まさに魎夜が下腹部に潜りこまんとしたその瞬間、魎夜の視界が、黒鋼鉄の塊によって閉ざされた。
そう、魎夜の目前で小山のように屹立したレヴィアタンの右前脚が魎夜を遮るようにして振り上げられたのだ。
自らにレヴィアタンの脚部ユニットが、ものすごい勢いで迫ってくるのが分かった。
今、魎夜はユーベルコードの発動に意識を完全に集中させている。
回避や防御に意識や切り替えれば、レヴィアタンの一撃をいなす事も可能だろう。だが、仮に守りに徹すれば、千載一遇の攻勢の機会を魎夜は逸する事となる。
しかし、魎夜は回避か攻撃かで逡巡するつもりなどはなかった。
魎夜の瞳は閉ざされた視界の先を見据えていた。間もなく、目前の視界が開かれることを、魎夜は確信していたのである。
魎夜の後方にて、空気が激しく震えだすのが分かった。震えだした空気の中、魎夜の左手はグリップを力強く握りしめたままだった。
そう、この瞬間をあの男が見逃すはずがない。。
魎夜を載せたレッドバージョンは、魎夜の目の前で鉄壁となって立ち塞がるレヴィアタンの脚部ユニットへと勢いそのまま突き進んでいく。
まさに、車両がレヴィアタンの大足に衝突せんとしたまさにその瞬間、しかし目の前に降ろされ鉄壁は、側方より押し寄せた青紫色の巨塊によって滑るようにして右方へと押しやられた。
黒く閉ざされた視界がこじ開けられ、視界が一挙に開かれた。
まさに絶妙のタイミングでの友軍寄りの支援に、たまらず魎夜の口元より微笑があふれた。
間違いない。アンドレイら狙撃部隊によるレーザライフルの照射がレヴィアタンによる攻撃を未然に防いだのだ。
レヴィアタンの巨大な大足が、レーザライフルの斉射によって煽られて、魎夜の上空で虚空をさまようのが見えた。
巨大な大足は、魎夜の上空すれすれをふらつきながら、そのまま軌道を反らしてゆき、ちょうど魎夜の体二つ分ほど右方の大地を踏み抜くのだった。
大足が大地を踏み鳴らせば、大地は再び激しく動揺し、砂礫や砂埃が周囲に巻い起こった。
とはいえ、地鳴りや礫片や砂埃ごときでは魎夜の進路を妨げることなど叶うはずもない。
魎夜は、風を操り礫片や砂埃を払いのけ、開かれた進路を突き抜け、一息の間にレヴィアタンの股下へと走り抜けていく。
魎夜の頭上で、大きく顔を覗かせた傷口より蒼白い光がこぼれ出していた。手を伸ばせば、もはや鋼鉄の皮膚に刻まれた裂創に指先が届くほど、今、魎夜はレヴィアタンを至近に捉えていた。
「前さんらにも事情があって、そのために必死なんだろうさ」
魎夜は、深く抉られた傷跡を覗き込みながら、一人呟いた。
レッドバージョンの上に跨ったまま、上体を水平方向へと倒すと、震鎧刀の切っ先を下方へと傾けた。
敵は傷つきながらも退くことなく戦いを続けている。彼らデウスエクスは、グラビティチェインの枯渇という事態に瀕し、種の存続のために地球を侵略したのだと聞く。
善悪を別にして、なるほど一応の理由が敵にもあるのだろう。
だが…。
「だが、悪いな。いかなる事情があろうとも、あんたらが戦いを引き起こそうって言うのなら、いつだって俺はその前に立ってやる」
力強く剣の柄を握りしめた。
両の眼で鋭く、傷元を睨み据える。
魎夜は両足と左手のみでレッドバージョンの上で姿勢を維持しつつ、水平方向で体を維持したまま、剣を振りかぶる。
するりとレッドバージョンが、動力部の真下まで進み抜けた。
今や、機械神レヴィアタンの動力部が魎夜の真上に明瞭に浮かび上がってみた。
「こいつの威力は一味違うぜ! 食らいな」
前方へと駆け抜けていくレッドバージョンの上で、魎夜は激しく半身をひねりながら勢いよく剣を振り上げた。
瞬間、振り上げた剣は、鋭い軌道を描きつつ、大気を一閃し、そこに朱色の閃光を生み出した。
紅蓮撃、ユーベルコードによって生み出された光の剣戟がそこにあった。
業火の如き赤い揺らめきを放つ剣型の衝撃波が虚空に姿を現したのだ。
震鎧刀が弧を描くようにして振り上げられれば、空中に生み出された光の刃は、震鎧刀に押し出されるような格好で空を駆け進み、まるで吸い込まれるようにしてレヴィアタンの下腹部へと殺到していく。
朱色の刃が、大口を開いた傷元へと切っ先を突き立てるのが見えた。
紅い刃が、鋼鉄の皮膚に触れれば、皮膚表面は赤く爛れ、まるで粘土かなにかのように焼灼されていく。
ぷつりと黒い皮膚が裂かれるのが分かった。
だが、紅の刃は、一層皮膚を切り裂いただけでは飽き足らぬようで、深く刀身を機械神の奥へと突き立てていく。
紅蓮の刃は、鋼鉄の皮膚を断裂させるや、焔の刀身でもって、合金製の筋肉群を刺し貫いていく。
ずぐりと、赤い刀身が深々とレヴィアタンの内部へと沈み込んでいくのが見えた。
鉄が焼ける匂いが魎夜の鼻腔に立ち込める中、特殊合金で塑形された筋層が続々と、炎の刃によって貫かれていく。
紅の刃は、幾重にも張り巡らされた合金の筋層を貫くや、筋層群の最奥部に刀身を潜らせ、ついぞ動力部にあたる計器群をも鋭い刃でもって刺突したのである。
紅の刃が、複雑に入り組んだ動力部の計器群を一つまた一つと穿ちぬいていくのが分かった。
計器がひしゃげ、断裂され、焼灼されれば、下腹部の裂創より青白い微光が、雪崩をうってあふれ出す。鋼鉄の皮膚のもと穿たれた傷口より、微光が激しく噴出するのが見えた。
魎夜を載せたレッドバージョンは、青い微光に洗われながら、前方へと駆け抜けていく。
震鎧刀を鞘に納め、魎夜は再び、右の手をグリップ部に添えると体勢を起こし、再び前傾姿勢を取り、機械神の股下を走り抜けていった。
魎夜の視界を染めて青白い微光は瞬く間に後方へと過ぎ去った。
魎夜はレッドバージョンを巧みに借りながら、両の足の隙間を縫うようにして進み、ついぞ機械神レヴィアタンの尾側側より山野へと舞い戻った。
ますますにレッドバージョンの加速度を上げてゆけば、機械神はあっという間に遥か後方へと霞んでいく。
ふと魎夜が肩越しに後方を振り返れば、突如、機械神レヴィアタンの下腹部で巨大な爆発が生じるのが見えた。
先ほど、魎夜が剣を突き立てた傷口より、赤黒い炎が海となって手を広げていた。焔に煽られ、機械神レヴィアタンが激しく巨体を動揺させる姿が見て取れた。
赤黒く燃え盛る炎の中、くぐもったような騒音が、激しく大気を揺さぶっていた。
耳をつんざく様な騒音は、魎夜には、大鯨の慟哭とも悲鳴とも感じられた。
炎が、レヴィアタンを、そして蒼天を煌々と赤く染めたのも束の間、燃え盛る炎は急速に火勢を弱めてゆく。
おそらくレヴィアタン内部の緊急装置により消火がなされたのだろう。
しかし動力部を破壊され、そして、全身を炎で焼かれた機械神は、もはや満身創痍とありさまで辛うじてそこに立ちすくんでいるように魎夜には見えた。
それでもなお、鋼鉄の皮膚を焼かれ、動力部や司令部さえも失ったレヴィアタンを魎夜は、脅威とみなしていた。
未だ、決して膝をつくことなく、偉容を誇る機械神が放つ威圧感に、魎夜はただならぬものを感じ取っていたのだ。
朝日射す草原の中を、魎夜はレッドバージョンと共に駆け抜けていく。
レヴィアタンは遥か後方へと消え去り、変わって魎夜の前には友軍の陣容が姿を現した。
して、魎夜は、友軍の中に良く見知った猟兵の姿を目にする。
微風に長髪をなびかせながら、かの猟兵は金色の瞳をやおら見開き、レヴィアタンを静かに伺っていた。
――あとは彼に任せれば良い。
神を滅するにはそれ相応の刃が必要だ。
そしてかの青年は、デウスエクスを滅する刃と呼ぶにおあつらえ向きの人物と言えた。
青年へと目合図しながら、魎夜は、味方陣を通過し、そのまま草原を走り抜けていく。
今、魎夜の後方では、研ぎ澄まされたケルベロスの刃が機械神へと振り下ろされんとしていた。
大成功
🔵🔵🔵
 ハル・エーヴィヒカイト
ハル・エーヴィヒカイト
◎
連携○
▼ポジション
Cr
彼の指揮能力そのものが私の攻撃能力を高める決戦配備となるだろう
▼心情
内部に潜入した皆はやってくれたようだ
残すところは本体の撃破か
では終わらせよう
▼戦闘
事前に機体性能をラファエルに共有
妖精の羽根は敵味方を区別しない。だが彼ならばきっとうまく使いこなしてくれるだろう
私はこの一時、ラファエルの剣としてこの戦場を全力で斬り開くまでだ
巨神キャリブルヌスに[騎乗]して外套を完全に展開した真の姿へと機体を変移させる
キャバリアサイズで再現された[結界術]によって取り出された無数の刀剣を[念動力]で[乱れ撃ち]してレヴィアタンを攻撃
弾幕のように展開する[範囲攻撃]でステルスタイプのダモクレスもまとめて押し返す
そしてラファエルが考える最善のタイミングでUCを起動
自身以外のあらゆる人工物を分解する蝶の羽根のような光の翼を広げ高速で周囲を飛び回り、
相手の装甲を砂にしながら手にした刀剣ですれ違いざまに斬り裂いて、レヴィアタンを消し飛ばそう
全てが終わったら見知った皆と健闘を称え合おう
四囲を鋼鉄に守られた操舵席は、閉塞感とは無縁に柔らかな光で満ちていた。
剣の騎神との名を冠するキャリブルヌスは心の臓に当たるコクピット部分を分厚い装甲にて覆い隠していたが、それでもなお、かの装甲の堅牢さがハル・エーヴィヒカイト(閃花の剣聖・f40781)の視界を遮ることは無かったのだ。
操縦席に仁王立ちするハルのもと、視界を遮るようにしてせり立つ前面装甲は、現在、透過された一枚の鏡面となって、前景に展開される光景を肉眼と変わらぬ鮮明さで映し出している。
いわゆる、モニター画面と言えるだろう。
原理はハルには分からなかったが、ハルがキャリブルヌスに騎乗すれば、決まって前面装甲は鋼鉄の堅固性を維持したまま、透き通った一枚のスクリーンをそこに投影するのだった。
ハルが一枚の透明なスクリーンを通して、青空を仰げば、青一色で塗りたくられた蒼天や、銀色の棘を伸ばした太陽が、現実そのものの立体感でもってハルへと迫ってきた。
ついで視線を前方へと落とせば、陽光により葉木を瑞々しくそびやかす木々や、遠景にて青く霞む山脈の連なりが肉眼にて捉える陰影と変わらぬ臨場感でスクリーン上に映し出される。
巨神キャリブルヌスが両の眼で捉えた視野情報とは、搭乗者であるハルの視覚そのものであったのだ。
巨神の四肢とはハルの手足であり、巨神の全身に張り巡らされたセンサー群は、ハルへと鋭敏に体性感覚を伝える神経叢であり、ハルの微細な筋収斂を巨神へと伝え、精緻に挙動を再現するための運動神経にも相当した。
鋼鉄の隔壁により外界と隔たれた操縦席の中、しかし、ハルは甘やかなる夏草の香りさえも嗅ぎ取ることが出来たし、初夏特有の熱気交じりの微風を柔肌に感じることも出来た。
ハルにとってのキャリブルヌスへの騎乗とは、機体の操舵というよりも、むしろ機体との同化という言葉で表現した方がしっくりくる気がした。
ハルが剣を振るわば、キャリブルヌスもまた、手にした剣を下方へと振り下ろす。
ハルが脳裏にて一歩を踏み出せば、ハルの思念はそっくりそのままキャリブルヌスへと伝わり、巨神もまた草の大地を大足で踏み鳴らす。
ハルが鋭く目を細めて前方を見据えれば、キャリブルヌスもまた瞳を縮瞳させ、虹彩を絞り、巨神の網膜に相当するスクリーン上にハルの目的物を明瞭と映し出す。
突如、スクリーン上にて巨山が映し出された。
黒褐色の岩肌に全身を覆われた巨大な山である。
巨山は、機械的な凸凹とした輪郭を取りながら大鯨の様な形を塑形していた。
巨山が 平原の片隅にて蠢動する度に、大地がぐらぐらと揺らぎだす。
よく見れば、大鯨には四肢があり、巨大な尾の様なものがあった。
ハルは、敵影を静かに伺った。
仮に肉眼では、スクリーン上に映し出された鋼鉄の大鯨の全容は、巨山の様相をとりながら、うすぼんやりとした輪郭でもって視認されたに過ぎなかっただろう。
だが、今やハルの視野とは、巨神キャリブルヌスが捉えた視覚情報により形成されたものであり、千里眼とも言うべきキャリブルヌスの藍玉の瞳は巨山の如き姿で聳える、大鯨『レヴィアタン』を、細部に至るまで克明に前面モニターに映し出していた。
猟兵たちの攻撃によりつぎはぎ状になった鋼鉄の皮膚からは、随所で電子基板などにより構成された機械神の内臓器官が顔を覗かせていた。
穿たれた傷元よりは、蒼白い飛沫が飛散し、皮膚を伝いながら草の大地へと滴り落ちて大地に青白色の水溜まりを広げていた。傷口からは、青白色の出血と共に赤い火花が迸り、それらは金粉の様な鮮やかさでもって黎明時の空を彩っている。
機械神『レヴィアタン』は、瀕死の巨体に必死に鞭うちながら、巨大な四肢で大地を踏み鳴らしながら、蚕食するように山野を進んでいる様だった。
流血をも辞さず、かの機械神は一心不乱にハルらが待ち構える陣列へと歩を進める姿は鬼気迫るものがあり、さ畏敬の念すら感じさせるものがあった。
もはや、レヴィアタンは自らの崩壊を知ったのだろう。せめて一矢報いんと、捨て身の攻撃に打ってでたのだ。
キャリブルヌスが布陣する第三軍陣地と大鯨レヴィアタンとは、現在、数十町の距離を隔てているまでに切迫していた。
長距離とも見え、高速戦闘を主体とするキャバリアにとっては、両者を隔てる間合いは、近距離に分類される。
このまま、徒に時を過ごせば間もなく敵は第三軍を攻撃の間合いに捉えるだろう。
正直、機械神の執念ぶりには、感嘆の思いさえも禁じえかった。
――だが、申し訳ないが、ハルには機械神に本懐を遂げさせてやるつもりは毛頭無い。
そして、ハルが一時的に自らの指揮権を委ねたラファエル・サー・ウェリントンも、ハルと存念を同じくするようだった。
「ハルよ…。君の出番だ。来るぞ…! 敵の最後の攻撃だ」
艶のある重低音が、キャリブルヌスに内蔵された音響装置より操縦席内に反響する。
言わずもがな、王者特有の気品さと剛毅さを兼ねそろえた声の主は、ラファエルその人のものに他ならない。
「了解だ、ラファエル――。今より、ケルベロスの刃となり、敵の本丸に突貫する。ラファエル、あなたには、私の眼としての役割を任せたいが…お願いできるだろうか?」
ハルは、矢継ぎ早に返答する。
して、ハルに応えるようにしてコクピット内に木霊したのはラファエルの優雅な笑い声であった。
「任せてもらう…。俺には見えるんだ…目に見えぬものが。空気の乱れや、戦場の空気の動揺が。そして、わずか先の未来が瞼の裏側にくっきりと浮かんで見えるのだ。…ハル・エーヴィヒカイトよ――」
軽やかな余韻を残しながら、ラファエルの声音が、突如鳴り止んだ。
一瞬、水を打ったような静けさがコクピット内を満たせば、モニタ越し、巨山のように聳える大鯨がぶるぶると体を体動させるのが見えた。
蠢動するレヴィアタンを他所に、銀糸を引くような、しっとりとした声音が、再び、海鳴りの柔らかさでもって、コクピット内に響き渡る。
「…敵ステルス機だ。工廠部は破壊されたが、それでも奴のはらわたで、少数の敵機が胎動を続けていたのだろう。空よりこちらに飛翔している――。仰角六十度、水平面八時の方向に、敵の小隊がある。今すぐに迎撃に向かってくれ」
ラファエルの声音からは確信めいた自信のようなものが滲みだしていた。
もちろん、ラファエルの指定した空域をモニター越しに窺えども、敵影の姿は露として見て取れなかった。
だが、ラファエルの金色の眼は不可視の機影の所在を正確にあぶりだしたに違いない。
ハルは、この一時、ラファエルの剣として戦うことを決めた。
ならば彼の才幹を信じ、その声に従い、空白の戦場を己が剣でもって斬り開くまでだ。それが刃たるハルの役割である。
「了解した、ラファエル。今より、敵残存部隊を打ち――」
一瞬言葉を切り、拳を固めれば、指先は剣の柄に絡みつき、強固に剣を支える。
指先から伝う鉄の柄が齎す冷感は、指先から前腕へ、そして上腕から全身へと伝わる過程において、熱っぽい高揚感へと変じていくのが分かった。
この感覚が果たして、いかなるものであるかをハルは知悉していた。
意識を集中させながら、ハルは、自らの中で奔騰していく力を開放させていく。
まずは一段階目として、キャリブルヌスの外部装甲を展開、封じられたキャリブルヌスの力を解き放つ。
ハルの思念に従うように、キャリブルヌスが纏った鋼鉄の外套が、折りたたまれた翼を一枚、また一枚と広げてゆき、八枚の拡翼を背より展開させるのが分かった。
次いで、ハルは剣を振り上げて上段にて構える。
視線を、機械神レヴィアタンから上空へと移し、、雲一つない蒼穹へと固定する。
蒼天を睨みすえながら、ハルは、軽やかに声音を紡ぎつつ、ラファエルへと豪語する。
「――敵残存部隊を打ち、敵本体、レヴィアタンの撃破へと移行する。私とキャリブルヌスによって、この戦いを終わらせることを、ハル・エーヴィヒカイトの名において、サー・ウェリントン、あなたに誓おう」
言いながら、ハルは一挙にキャリブルヌスを加速させる。
鉄の巨体が宙を舞えば、キャリブルヌスは一陣の閃光となり、巨体からは創造できぬ高速でもって空を飛翔してゆくのだった。
軽やかな浮遊感に次いで、疾走感がコクピット越しにハルを揺らせば、キャリブルヌスは、一息の間に敵のステルス機が数多、蠢動するという空域へと肉薄する。
滑空と共に、ハルは剣を横に倒すと、コクピット内にて結界術を発現させる。
瞬転、剣先より閃光の様なものが走り、ハルを中心に結界が紡がれてゆく。
して、顕現した結界は操縦席を中心に周囲へと見る間に膨張してゆくと、キャリブルヌスの全身を包み込むような形で不可視の障壁を周囲に張り巡らされのだった。
ハルはスクリーン越しに前方を見据える。
そこには青空が広がるだけで、敵影の影も形も見て取れなかった。
だが、ラファエル・サー・ウェリントンは、ハルの目前の空域に数多の敵が存在すると断言したのだ。
ならば、空間の全域を剣の乱舞でもって間断なく埋め尽くし、不可視の敵影を全て穿ちぬいてみせればよい。
ハルと、キャリブルヌスにとっては造作の無いことだ。
ここにハルはキャリブルヌスにとって、第二の束縛を解き放つ。
ハルが精神を集中させるにつけ、キャリブルヌスの後背より突き出た八枚翼が収斂する。
翼同士が互いに折り重なりあったかと思えば、突如、キャリブルヌスの背後にて、空間が歪曲し、無数の黒い陰影が虚空より姿を顕現させていく。
黒い陰影は明瞭な輪郭を取り、剣の形となって空を埋め尽くす。
結界術に次ぐ、剣の召喚――、ハル・エーヴィヒカイトが得意とする秘儀をキャリブルヌスもまた再現してみえたのである。
キャリブルヌスは滑空を続けていけば、ラファエルが指定した空域へとさらに接近する。
さらに一歩を踏みこみ、ハルは剣戟へと移るべく指先に力を籠める。次いで、剣を振り上げんとすれば、突如、無人の空間にて、紫色の光芒が数多、揺らめくのが見えた。
光芒は一つ、二つと紫色の燈火を空に灯してゆき、瞬く間に空一面を紫色の灯で埋め尽くした。
燈火は、膨張し、綿花の様な厚みのある光弾となるや、キャリブルヌス目掛け、一斉に空を走り抜けてゆく。
今や、メインモニターは濁流となって押し寄せるプラズムキャノンの光弾によって、紫一色に塗り固められていた。
数多の閃光は、間もなくキャリブルヌスを捉え、鋭い矢尻でもって切り裂くだろう。
最も、そんな未来が訪れぬ事をハルは知りえていた。更に言うならば、現状はハルに味方したとさえいえる。
射撃により敵は、おぼろげながらも自らの所在をハルに露呈したのである。
閃光の発生源周辺に敵影は存在するというならば、そこに剣を叩きこめばよい。
相手が数多の閃光でキャリブルヌスを襲うというのならば、更にその数を上回る刀剣でもって閃光ごとに敵機すらも切り払ってみせよう。
ハルは側方へと伸ばした剣を、そのまま前方へと薙いだ。
剣の切っ先が、迫り来る無数の閃光を睨み据えれば、キャリブルヌスの後方で待機していた剣の群れが、一斉に前方へと滑り出す。
ハルが掌を返せば、手にした剣が激しく振動を始めるのが分かった。
流れるような挙措でもってハルが剣を下方から上方へと逆袈裟に振り上げれば、キャリブルヌスの無数の剣は、束縛の鎖から放たれ、轟轟と迫り来る閃光の豪雨目指して、勢いよく空を切り裂いていった。
キャリブルヌスを挟んで、剣の乱舞と閃光の驟雨とが激しく、干戈を交える。
当初、紫一色だったメインモニターに銀光が夾雑したかと思えば、銀光は次第にに紫色を払い、紫色に銀白色を滲ませた。
剣と閃光とは、鋭い牙をむき出しにするや、激しくぶつかり合い、互いが互いを押しのける様に鍔競り合い、押しては引いてを続けながら角逐を続けてゆく。
剣の刀身が砕け散り、銀粉が舞い散る傍らで、剣に切り裂かれた閃光が、紫色の糸くずを大気に散りばめるのが見えた。
互いが互いを貪り来るわんと剣と閃光とが激しくぶつかり合う。
白銀と紫色とで彩られた淡い光の奔流は、ますますに勢いを増していき、しかし、瞬く間に極点へと至るや、立ちどころに両者の趨勢を決定づけるのだった。
閃光が一つ、また一つと絹のように裂かれていくのが分かった。
それまで剣が一本砕かれれば、閃光も一条が裂かれるという様な具合で、ほぼ互角の状況のもと展開された剣と閃光の応酬はここに一気に潮目を変えたのだ。
当初、紫色一色で塗り固められていたメインモニターのもと、わずかな夾雑物として混在するだけだった銀光は、ますますに勢いを増していき、気づけば完全に紫色を押しのけて、視界を銀閃の瞬きで支配していた。
無数の剣が閃光を切り裂きながら、無人の空域へと押し寄せていった。
眩らむような銀白の閃光が虚空を掠めるたびに、爆炎が続々と巻き起こってゆく。
元来、なにも存在しえない空間にて、火の手が上がり、赤く燃え盛る業火の中でイナゴを彷彿とさせる機影が、剣に腹部を突き刺され、力なく地上へと崩れ落ちていくのが見えた。
無数の剣が縦横無尽に空を走り回っていた。
輪を描くように、無数の剣が空を乱舞するごとに、至る所で焔が揺らめき、ステルス型のダモクレスが剣に刺し貫かれ、息絶えていくのが見えた。
ただ、キャリブルヌスは、焔の中を機械神レヴィアタン目掛けて、速度落とすことなく、突き進んでいく。
極超音速の壁を越えた機影は、無人となった大空を貫き、瞬く間に機械神レヴィアタンの前方に躍り出た。
もはや、キャリブルヌスを遮るものは何もない。
ハルの目前には、すべての護衛を失い、茫然自失と立ち竦む丸裸の大鯨があるだけだった。
満身創痍の大鯨を前に、ハルはキャリブルヌスを縛る第三の鎖を開放する。
「外套展開――」
ぽつりと声を零し、次いでハルは剣を鞘へと納めた。
溢れた吐息が、コクピット内に溢れてゆけば、キャリブルヌス周辺に展開された結界は霧散し、現出した無数の剣もまた、吸い込まれるようにして大気の中に姿を隠していく。
「フェアリーシステムを起動する」
ハルは誰に言うでもなく、冷ややかなる声音で、言質を吐いた。
ハルの声は、無慈悲なる終焉と同時に、寂寥たる静謐を機械神へと齎すだろう。
コクピット内に伝搬したハルの声が、巨神の装甲を通過し、蒼天へと響いてゆく。
凛然とした旋律は、ここに宇内を律する法則を捻じ曲げたのである。
それは、ユーベルコードと呼ばれた。
猟兵のみが有した奇跡の御業だ。
キャリブルヌスとは巨神と呼ばれる神代の王である。ハルの持つ奇跡の力と、キャリブルヌスが持つ力とが混淆した時、ユーベルコードは、神をも打ち滅ぼす光をこの世に発現させたのだ。
搭乗者のハルでさえもキャリブルヌスの力の片鱗をわずかに知りえたに過ぎず、キャリブルヌスが秘めたる力がどれほどのものかは想像だにできなかった。
だが、キャリブルヌスに付随する神なる尊称がいかなるものかと想像した時、キャリブルヌスの真名は、おそらく、機械神レヴィアタンの対極にあるだろうとハルは見る。
創造の神をレヴィアタンとするのならば、キャリブルヌスは破壊神の名こそが相応しい。
ハルが発動させたフェアリーシステムこそ、キャリブルヌスが破壊神を名乗る証左と言えるだろう。
キャリブルヌスの背より突き出した鋼鉄の八枚翼が互いに擦れあい、冷たい羽音を周囲に響かせるのが分かった。
銀色の鈴が穏やかな音律を奏でるように、静寂の中、羽音が不気味に広がっていく。
八枚翼が収斂し、互いに表面をこすり合わすたびに、羽音に伴う弾奏はますますに勢いを増し、翡翠の微光を周囲に放散させてゆくのだった。
翡翠の光は、キャリブルヌスの後方より緩やかに広がってゆき、妖精や蝶の羽を彷彿とさせる光の翼をキャリブルヌスの背に形成する。
微光により構成された半透明の羽は、淡い緑色を湛えながら、ゆらゆらと幻想的にはためいていた。
光の翼がはためくたびに、翡翠の粒子が鱗粉のように宙を舞う。
淡い翡翠の鱗粉は、風にあおられるようにして空を舞い、そうして、レヴィアタンのもとへと押し寄せ、大鯨を上空より優しく抱擁するのだった。
煌びやかなる翡翠の鱗粉は、霧雨とも、粉雪とも見紛う柔らかなる光の薄膜でもって大鯨を包み込んだのである。
幻燈たる翡翠の微光は、儚げでありながらも、しかし、その実、破壊神の無慈悲なる息吹でもあった。
翡翠の鱗粉が、レヴィアタンの鋼鉄の皮膚を優しく撫でた。
赤子を撫でるがごどき柔和なる母の指先が、鋼鉄の皮膚の上をなぞれば、瞬間、レヴィアタンの装甲は砂かなにかのように崩落を始めるのだった。
鱗粉が、大岩の様なレヴィアタンの脚部ユニットに触れれば、巨岩は跡形もなく砕け、レヴィアタンが巨体を大きく傾けた。
ただただ、機械神レヴィアタンは、舞い散る翡翠の鱗粉の中でなすすべも無く、文字通り、砂となって崩れていく。
仮に、レヴィアタンが自らの麾下部隊を増産する工廠部を保有し、更には動力部たる心臓部を十全に機能させていれば、創造神たるレヴィアタンはフェアリーシステムになんらかの対策を講じることも出来ただろう。
だが、今やレヴィアタンには、自らを守る兵団を生み出す力も、自らを包み込むように障壁を張り巡らせる力も残されてはいなかった。
結果、レヴィアタンは降り注ぐ翡翠の微光を一身に浴び、破滅という現実に身を委ねたのである。
前後の右脚が崩れることでレヴィアタンは自重を支える事能わず、大地へと沈み込む。淡い粒子により、レヴィアタンの外装は完全に霧散し、ついぞ、鋼鉄の皮膚のもと、電子基板と薄い合金とで構成された内機関がむき出しとなる。
気づけば、キャリブルヌスの背より生み出された、光の翼は消失し、翡翠の粒子もまた、機械神の外部装甲を消滅させ、霧散していった。
現状のキャリブルヌスでは、おおよそ数秒間程、光の翼を顕現させるのが限界であった。
仮にこれ以上の時間フェアリーシステムを展開させれば、かえってキャリブルヌスが自壊していく可能性もありえた。
おそらく、キャリブルヌスは未だに本来の性能を十分には発揮できてはいないのだろう。
果たしてそれは搭乗者たる自らの不足が招いたものか、それとも、ハルの知りえぬ制約がキャリブルヌスを縛っているのか、詳しいことはハルには分からなかった。
だが、現状においては、フェアリーシステムは十全に目的を果たしたと言えるだろう。
すでに機械神レヴィアタンは、大破し、青色吐息で大地にて身をうずくまらせている。
となれば、あとは剣で戦いを決すればよい。
それはハルの得意とする所だ。
「ゆくぞ、キャリブルヌス――」
ハルが言えば、キャリブルヌスは再び矢となり、空をかき分けながら、前方へと走り抜けていく。
見る間にキャリブルヌスとレヴィアタンの距離が縮まり、瞬く間にゼロとなった。
剣を返し、鋭い刃先をむき出しになったレヴィアタンの内機関目掛けて横薙ぎすれば、刀剣は鋭い軌道でもってレヴィアタンを切り裂いた。
飛翔の勢いそのままに、キャリブルヌスが、レヴィアタンの側方すれすれを滑空していけば、内機関に突き立てられた刀剣もまた滑るようにして前方へと走り抜けていく。
コクピット越しにハルの掌に鉄を切り裂く感触が、しびれるような感覚となって走っていった。
力強く剣を握りしめたまま、ハルはますますにキャリブルヌスを加速させると、横一文字にレヴィアタンを切り裂いていく。
頭側から尾側にかけて、蒼天を一筋の閃光が走り抜けた。
走り抜けた閃光に続き、眩いばかりの剣閃が、機械神の胴部に横一文字に切れ目を入れ、機械神を真っ二つに横断していった。
切り裂かれたレヴィアタンの上体が力なく、大地へと崩れ落ちていく。
静謐と佇む山野にて、地表へと崩れ落ちた機械神の上体が壮麗たる鐘の音となって響き渡ってゆくのが、キャリブルヌスのコクピット越しにハルにも聞かれた。
体躯を上下で切り裂かれた機械神は、ここについぞ動きを止め、物言わぬ残骸と化したのだ。
厳かなる地響きこそが、機械神の落命の証左と言えるだろう。
キャリブルヌスは低空をいくばくか飛翔すると、今度は一転、天高く舞い上がり、東空へと走りぬいていく。
眼前に赤く燃える太陽があった。
後景では、未だ荘厳たる鐘の音が鳴り響いている。
今、夜明けが到来したのだ。
かつて、ロンドン市内でハルが耳にした夜明けを告げる鐘の音は、今や、ロンドン市街に留まらず、英国全域に福音となって響き渡ったのである。
重苦しい鐘の音色は徐々に間遠となり、かわって音の絶えた空の元、キャリブルヌスのメインモニターにて日輪は、ますますに眩く輝きだす。
ここに英国における夜は終わりと告げ、デウスエクスとの人との戦いの序章は人類側の勝利という形で幕を下ろしたのである。
夜が明け、世界は昼の眩さに向かい加速を始めた。
人類の行き着く先を知る者は存在はしない。
だが、目の前で優艶と輝く太陽を目の当たりにした時、ハルの口元をついたのは確かな微笑であった。
遠間にてわずかに聞かれた鐘の音が、ついぞ鳴り止んだ。
今や、目の前で輝く日輪だけが、夜の闇に代わり、明朗たる朝が訪れたことをハルへと教唆していた。
ふと、コクピット内の音響装置より歓声が上がった。そうだ第三軍の兵らの声だ。
耳朶を揺らす、明朗たる喜色の声に耳を澄ましながら、ハルはキャリブルヌスを駆り彼方へと飛び去っていく。
長い尾を曳きながら銀色の流星は彼方の空へと消えていく。光が過ぎ去った後、山野を吹き抜けていったのは柔らかな初夏の風だった。吹く風に、木々は陽気に葉裏を返しながら囀りを上げる。
変わらぬ平穏が、英国の片隅に齎された。
今、夜明けは遠ざかり、世界は、眩い燈明の光で満たされた。
大成功
🔵🔵🔵


 辻・遥華
辻・遥華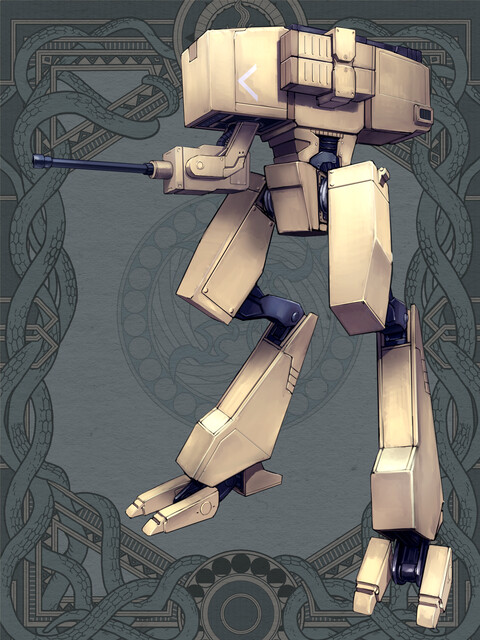
 大町・詩乃
大町・詩乃  エクレア・エクレール
エクレア・エクレール  月隠・新月
月隠・新月  トーノ・ヴィラーサミ
トーノ・ヴィラーサミ  エミリィ・ジゼル
エミリィ・ジゼル  暗都・魎夜
暗都・魎夜  ハル・エーヴィヒカイト
ハル・エーヴィヒカイト 
 トーノ・ヴィラーサミ
トーノ・ヴィラーサミ  月隠・新月
月隠・新月  暗都・魎夜
暗都・魎夜  エミリィ・ジゼル
エミリィ・ジゼル  ハル・エーヴィヒカイト
ハル・エーヴィヒカイト 
 エクレア・エクレール
エクレア・エクレール  月隠・新月
月隠・新月  トーノ・ヴィラーサミ
トーノ・ヴィラーサミ  大町・詩乃
大町・詩乃  エミリィ・ジゼル
エミリィ・ジゼル  暗都・魎夜
暗都・魎夜  ハル・エーヴィヒカイト
ハル・エーヴィヒカイト