ブルーム・イン・ディスペアー
●黒い炎
ダークセイヴァー世界の辺境。
その探索は並大抵のことではなかった。『常闇の燎原』を往く猟兵達は見ただろう。
見上げる空は、これまで仄暗い月明かりに照らされていた。
しかし、今目の前にあるのは完全なる闇に覆われた空だ。
見下ろす大地は『黒い炎』が包み込み、そこが不毛の平原であることを知らしめる。
それだけではない。
平原に広がる『黒い炎』は見る者の恐怖と絶望を駆り立てる幻影を生み出す。
揺らめく炎の先にあるのは、悲劇そのものであった。
これまでダークセイヴァーのあちこちで引き起こされた悲劇的な出来事。
「こっちはダメだ! 吸血鬼が来る!」
「でも、何処に……逃げればいいっていうの?」
悲劇の住人たちは口々に己が生き残るための術を探す。
言ってしまえば、走馬灯のようなものであったのかも知れない。このダークセイヴァーに充満していたかつての悲劇。
それが走馬灯のように『黒い炎』から幻影となって生み出されているのだ。
「無駄だ。お前達の抵抗は全て無駄だ。救済はない。だが、私は慈悲深いからな。選ばせてやるとしよう」
それは『狩りの女王』と呼ばれた吸血鬼であった。
手にした猟銃の銃口は今も得物を狙っている。彼女の手に掛かれば、あらゆるものは獲物へと成り下がる。
己以外の全てが狩りの対象。
生命を繋ぐために必要な狩りではない。ただ遊戯としての狩りだ。生命のやり取りでもない。ただ、一方的に此方が引き金を引くだけの狩り。
『狩りの女王』にとって、それだけが楽しみであったのだ。
「お前達の中から一人生贄を選ぶがいい。一月に一度、一人だけ。それで他のものは生きながらえる。ただそれだけでいいのだ」
『狩りの女王』の言葉に人々は戸惑う。
「誰も選べぬというのならば、全て私の獲物だ。全て死ぬだろう。どちらがいい。全てを失うのと、たった一つを失うのと、一体どちらがいいのだ」
彼女の言葉が人々の頭の中に響き渡る。
人身御供。生贄。
ただ一人を選ぶだけでこの村の多くが一月生き延びることができる。
「く、くじ引きをしよう。それなら恨みっこなしだ。そうだよな!」
誰かが声を上げる。
くじで選べば公平である。老いた者からということもなく、力弱き者からというでもなく、病を得た者でもなく、すべてのものに平等に生きる権利が与えられる。
そのお題目の元に人々はくじを引く。
ただ一人を選ぶために。
仕方ないと誰かがつぶやいた。一人の生命で多くが救われるのならば、それもまた。
「い、いやだ! 俺は嫌だ! なんで俺が! これまでお前達を引っ張ってきたはずだ! 俺じゃないといけない理由なんてないはずだ! ああああっ!!!」
くじで選ばれた男が鳴き叫ぶ。
これまで何度も村人たちをまとめてきた中心的な人物であった。
だが、選ばれた以上『狩りの女王』は引き金を引く。
まずは足を、そして腕を、肩を、脇腹を。
銃弾は死に難い箇所に打ち込まれ続け、男は失血の後、絶望と恨みを生者にぶつけながら死せる。
生き残った人々は怨嗟の声を耳朶にこびりつかせ、それでも一月を生きる。
そして、また時はめぐる。
次の贄を選ぶ時だ。
「次は――お前だ」
幼い少年がくじで選ばれる。
まだ何もわかっていない様子の幼い少年だ。彼はきょとんとした顔で人々を見上げる。母親は、自分が変わりにと言った。
けれど、くじは絶対である。くじを持った瞬間、『狩りの女王』は狙いをその少年に向ける。どれだけ母親が自分が変わりにと言っても覆ることはないのだ――。
●常闇の燎原
グリモアベースへと集まってきた猟兵達に頭を下げて出迎えるのは、ナイアルテ・ブーゾヴァ(神月円明・f25860)であった。
「お集まり頂きありがとうございます。皆さんのダークセイヴァー辺境探索のおかげで『常闇の燎原』へと足を踏み入れることができました」
ナイアルテは集まってきた猟兵達に頭を下げる。
ダークセイヴァー世界の構造は幾つかの層が重なった複層構造である。
猟兵達が今まで地上だと思っていた世界は地下であり、第三層に至る道を探すために今まさに『常闇の燎原』へと手がかりを求めて探索の足を伸ばしているのだ。
「ですが、この『常闇の燎原』の空は完全な闇で覆われ、大地には『黒い炎』が燃え盛っています。謂わば、不毛の平原とでも申しましょうか……ですが」
彼女の表情は暗い。
第三層へと至るための道。その手がかりを見つけるためにはこれを乗り越えなければならない。
しかし、その『黒い炎』は猟兵達に反応して燃え上がり、周囲の光景を幻影に変える。
ただそれだけであるのならば、幻影を突破するだけでいい。
「この幻影は皆さんを取り込みます。そして、皆さんは自身が幻影の見せる『悲劇的な光景の中の無力な一般人の一人である』という風に錯覚してしまうのです」
それは力づくでの突破は不可能であるということである。
そして、その錯覚は解かれない。
どうにかして、『自身が一般人である』という認識のまま、工夫してこの『悲劇的な光景』を乗り越えるしかないのだ。
猟兵達が対面する『悲劇的な光景』は、とある村での出来事である。
領主であるオブリビオン、吸血鬼『狩りの女王』によって、一月に一度一人の生贄を選び出すことによって、人々は一月という僅かな時間平穏に過ごすことができる。
その最中に猟兵達は『無力な一般人』として取り込まれてしまう。
贄に選ばれた少年。
彼は自分が何に選ばれたのかもわからない幼子である。無論、『無力な一般人』である猟兵達は彼を救う力は多くない。
村人たちは皆、少年を贄に差し向けようとするであろうし、また『狩りの女王』が放つ銃弾は少年をいたぶるように放たれるだろう。
どれだけ声を発して、この行いを止めるように言ったとしても、並大抵のことでは村人たちを説得できない。
「ですが、この『悲劇的な光景』を皆さんは乗り越えなければなりません。抵抗を続けることで、幻影の中から『無力な一般人』である皆さんを暴力で持って蹂躙しようとする亡霊オブリビオンが現れます。皆さんは未だ『無力な一般人』であると自身を錯覚したままではありますが、勇気を持って、これを打倒し続けることで『黒い炎』の勢いを殺すことができるのです」
ナイアルテの告げる言葉どれも難しいことばかりであった。
『無力な一般人』と錯覚したまま、勇気を振り絞らなければならない。
それは並大抵のことではないだろう。けれど、そうしなければ、この『常闇の燎原』を乗り越えることはできない。
「最後に現れるのは『狂えるオブリビオン』、『狩りの女王』です。理性を持たぬ存在でありながら、同族殺しや紋章持ちにも匹敵しますが、視聴嗅覚を持っていません。ただ、皆さんの恐怖や絶望の感情を感知することで、皆さんを見つけ出し、攻撃してくるようです」
この性質をうまく利用することができたのならば……そう、この困難な状況を打破することができるだろう。
ナイアルテは猟兵たちを見送る。
彼女はどんなに困難な状況であっても、彼らはきっと常闇に活路という名の勇気を見出すことを信じるのであった――。
 海鶴
海鶴
マスターの海鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回はダークセイヴァーの辺境『常闇の燎原』にて第三層への手がかりを求め探索を続けるシナリオになります。
●第一章
冒険です。
常闇の燎原を往く皆さんのまえに『黒い炎』が燃え上がり、たちまちに周囲をかつてダークセイヴァーで起こった『悲劇的な光景』の幻影で包み込みます。
この幻影に皆さんは取り込まれてしまい、自身のことを『この悲劇の中の無力な一般人のひとりである』というふうに錯覚してしまいます。
幻影は、かつてありし一月に一人、『狩りの女王』の標的となる生贄を選び出すことでつかの間の平穏を得ている村を生み出しています。
皆さんは『無力な一般人』ですが、選ばれた幼い少年をどうにかして守らなければなりません。
勇気を持って、この困難を突破することで『黒い炎』は弱まっていくのです。
●第二章
集団戦です。
生贄の少年を守り続ける皆さんの姿に、幻影の中から『無力な人々を恐怖と暴力で蹂躙しようとする敵の姿』が実態を持って現れます。
『その地に縛り付けられた亡霊』たちは、皆さんに襲いかかりますが、第一章と同じように皆さんは『自分は無力な一般人』だと錯覚が襲ってきます。
その錯覚に惑わされることでしょう。
ですが、勇気を持って、襲いかかる『その地に縛り付けられた亡霊』たちを打倒しつづけることで、周囲の『黒い炎』は弱まり、本来の自分へと戻っていくことが出来ます。
●第三章
ボス戦です。
『黒い炎』の齎す幻影を振り払い、完全に自分自身を取り戻した皆さんの前に両目の在るべき場所から黒い炎を噴出させた『狂えるオブリビオン』、『狩りの女王』が現れます。
しかし、彼女は同族殺しや紋章持ちのオブリビオンにも匹敵する力を持っているようですが、『視聴嗅覚を持たず、相手が抱いた恐怖や絶望の感情を感知する』ことで、攻撃対象を見つけ出しているようです。
この性質をうまく利用することで、この強敵を打倒する糸口にできるかもしれません。
それでは、『常闇の燎原』を突破するため、勇気を持って恐怖と絶望を振り払う皆さんの物語の一片となれますよう、いっぱいがんばります!
第1章 冒険
『贄の祭』

|
POW : 贄となる人間を周りの村民から身を呈して守る
SPD : 処刑から贄を連れて逃げ回る、背後などを取って気絶させる
WIZ : 言葉巧みにこの行いをやめるよう説得
|
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
猟兵達は転移する前に情報を得ていた。
『常闇の燎原』を包み込む『黒い炎』が見せる幻影は、本来の自分ではなく『悲劇の中の無力な一般人のひとりである』と錯覚させるものであると。
それがわかっていながら、どうしても猟兵達は偽りの己しか認識できない。
無力。
特別な力もなければ、恐怖と絶望に震えるしかない者。それが今の己である。
懐かしさすら感じるいつもの自分。
けれど、それは遠きものである。あがいても、あがいても、手に届かぬものであるからこそ、猟兵達は『無力な一般人』として、悲劇の讃歌へと身を投じるしかないのだ。
「贄だ! あの子は贄に選ばれたんだ! 諦めるしか無い!」
人の声がする。
一月に一人。
くじで選ばれた人間を『狩りの女王』の標的として捧げる。
そうすることで一月は平穏に暮らせるのだ。
この月に選ばれたのが幼い少年であった。
「そんな! 私が変わりに! あの子の代わりに私が……!」
「だめだ、くじは絶対なのだ。こうするしか自分たちがいきのこる術はない」
人々は諦観の中で生きている。
少しでも長く平穏の中に身を置きたいと願うからこそ、どん詰まりの人生を生きるしかない。
少年の母親がくじで選ばれた贄の少年を抱きしめる。
周囲の大人たちは母親と少年を引き離そうとしており、抵抗する母親の姿に少年も涙を浮かべる。しかし、そうするしかないのだ。
力も何もない存在にとって、強者の言うことは絶対だ。
一度にすべてを奪わぬことは『狩りの女王』の慈悲に思えたかも知れない。
だが、それは違う。ただの尊厳を踏みにじるものであった。じわじわと無邪気に昆虫の手足をもいでもがく姿を見て楽しむ幼子のような純粋ささえ感じられたことだろう。
尊厳も、力も、矜持もない。
ならば、人間性の中に最後に残るのは一体何か。
そう、最後は勇気だけなのである――。
 儀水・芽亜
儀水・芽亜
【転移前】
これは本当に自然現象でしょうか? 第三層への道行きを隠蔽する『闇の種族』の防御機構なのでは?
【転移】
ああ、よく知る子供が泣いています。
それでも仕方在りません。くじに当たったならば。これは幾度もあったこと。
それでも、私は我慢の限界です。勇気を持って立ち上がりましょう。
『狩りの女王』! 私の歌を聴いて興味が出たなら、あの子を捨て置いてあなたの屋敷へ連れ帰ってください。
左手に抱える竪琴で「楽器演奏」して、この場に相応しい絶望を塗り込めた歌を歌い(「歌唱」)ましょう。
私の歌を聴き続けたいなら、このまま誰も殺さず私だけを館へ閉じ込めていただいて結構です。
いかがですか、吸血鬼!?
ダークセイヴァー世界はオブリビオン支配盤石たる世界である。
人々はオブリビオン、すなわちヴァンパイアの玩具にほかならない。生命をどのように扱おうとするのだとしても、咎められることはない。
常闇の世界。
しかし、それは地下世界であるからこそ日の当たらぬ世界であったことを指し示す。
ここは地底の世界。
人々の頭上にあるのは空ではなく天井。
ならば、その先には地上が、光があるのかもしれない。
目指すは第三層。
その手がかりを求めて猟兵達は『常闇の燎原』を往く。
最初に見たのは真黒なる空。
そして、燎原に広がる『黒い炎』。
儀水・芽亜(共に見る希望の夢・f35644)は、これが本当に自然現象であるのかと疑う者であった。
第三層へと繋がる道を隠蔽する『闇の種族』の防御機構なのではないかと訝しんだ。
しかし、その思考は突如として打ち切られる。
『黒い炎』が噴出し、彼女の瞳に映るのは幻影。
このダークセイヴァー世界が生まれてからオブリビオン、ヴァンパイアによって虐げられ、いくつも泡沫のごとく浮かび上がっては消えていった悲劇である。
「ああ、よく知っている子が……」
彼女は今や猟兵ではない。
そもそも猟兵とはなんなのであろうか。靄のように頭に幻影がこびりつく。自分の名前も思い出せない。
あるのは、今、まさにこの村で行われたくじによる生贄の選定の瞬間だけである。
今月選ばれたのは、彼女のよく知る子供であった。
幼い少年。
あどけなさが残り、村人たちからは可愛がられていた子供だ。
だというのに、くじで選ばれてしまった。母親が泣いている。子供の代わりに自分が、と嘆いている。
「仕方ありません。くじに当たったのならば」
芽亜はうなずく。
そう、これは仕方のないことであった。
くじで一月に一人生贄を選ぶ。
そうすることでヴァンパイアである『狩りの女王』の標的を選び、差し出すことを決める。
そうすれば、少なくとも一月、生き残った者たちは平穏に過ごす事ができる。
だが、それは偽りだ。
どこにも真実がない。
今、目の前で泣く母親がいる。彼女の涙は本物だ。我が子を想うがゆえの涙。
幼い子供だからではない。
「『狩りの女王』! 私の歌を聴いて興味が出たなら、あの子を捨て置いてあなたの屋敷に連れて帰ってください」
我慢の限界であった。
これまでの自分も。
そして、今の自分も。
ここで変わらなければ、永遠に自分は後悔し続ける人生しか送れないだろう。
手にした竪琴が奏でられる。
「おい! 何をしている! 勝手なことをして、『狩りの女王』の不興を買ったらどうするつもりだ!」
村人が芽亜を取り押さえようと、その演奏を止めようとする。
「私の歌を聞き続けたいなら、このまま誰も殺さず私だけを館へ閉じ込めて頂いて結構です!」
「やめろ! お前は全部を壊すつもりか!」
「楽器を離せ!」
「余計なことをするな!」
人々から芽亜は取り押さえられる。楽器も取り上げられる。けれど、それでも芽亜は声を張り上げる。
「いかがですか、吸血鬼! 私が、私の歌が! 少しでも、琴線に触れたのなら!」
少年の代わりに自分が。
その自己犠牲の歌が暗闇に溶けて消える。
村人たちから取り押さえられながらも、芽亜は口をふさがれても尚、叫ぶ。
それが彼女の中に唯一残った勇気であるから――。
大成功
🔵🔵🔵
 ダンド・スフィダンテ
ダンド・スフィダンテ
諦観は楽だが、仲間同士で争うこの状況は、あまり見たくない物だ
こうして争う者達を見て嘲るのが吸血鬼の趣味だ物な
ああ腹が立つ
大嫌いだ
俺様に勇気は無いが、勇気ある者を演じる事は得意だぞ?
同じく抵抗する者と子供から村人をひっぺがし、その前へ出て、彼らを守ろうか。
なぁ、こうしてお互いを憎しみあい争う事程、悲しい事は無いじゃないか
次のクジで決まるのは自分かと、怯え疲弊する事も辛いじゃないか
勇気を出してくれ
誰しも死ぬのは恐ろしい
けれど尊厳を潰される事もまた、魂が殺される事じゃないか。
手を取り合って生きてきただろう?
嫌だろうが、こんな死に方も、殺し方も。
(演技、怪力、かばう、おびきよせ、で自分を盾にします)
人の本質は悪性であろうか。
それとも善性であろうか。
その答えを出すには、ダークセイヴァーの人々の心に余裕はない。あるのは明日を生きるための欲望だけである。
一時でも平穏を求めるからこそ、ヴァンパイア『狩りの女王』によってもたらされた一月に一人の生贄という慣習さえ受け入れる。
己の玩具としての人間。
それを弄ぶ行いを甘んじて受け入れるしかない。
『黒い炎』が見せる悲劇は、そんな甘受によって作られた村をダンド・スフィダンテ(挑む七面鳥・f14230)に見せつける。
彼の瞳には今や『常闇の燎原』ではなく、この常闇の世界であるダークセイヴァーにこれまで数多積み上げられてきたであろう悲劇しか映っていない。
そして、己もまたその悲劇の中の無力な一般人であるとしか認識できないのだ。
己がもしも猟兵としての力を持っていたのならば、この悲劇も覆すことができたであろう。
「諦観は楽だが……」
そう、今ダンドの心の中を占めるのは諦観だけであった。だが、同時に村人同士で争う状況を見たいとも思わない。
目をそらしたい。
人々が罵り合い、泣き叫び、涙を流し混乱する。
それこそが『狩りの女王』の望むものであったのかもしれない。人々が醜く、心の悪性を発露する姿こそ、彼女の愉悦であるからだ。
ダンドはこころで理解している。
これが、この光景こそが吸血姫の趣味であるのだと。こうして相争う者を見て嘲笑う。それこそがヴァンパイアの趣向そのもの。
心のなかの己が言う。
腹が立つのだと。大嫌いだと。
けれど、どうしようもなく己の体は動かない。恐怖と絶望とかダンドの体を縛るのだ。
勇気はない。
だが、ダンドは己が勇気ある者を演じることができると知っている。
「やめろ!」
思わず駆け出していた。
母親はくじで生贄に決まった少年を抱いて離そうとはしない。それを引き剥がそうとする村人たちをダンドは引っ剥がし、彼女たちと村人の間に立つ。
「何をする! そいつが今月の生贄だ!」
「これまでもしてきただろう! 幼いからなんだというのだ!」
「そうだ! 幼いからくじの対象にならぬというわけではあるまい! これも村を護るためなのだ!」
人々の言葉がダンドの体に突き刺さるようであった。
人の悪性が刃となって肌を貫く。
だが、それでもダンドは勇気なくとも、勇気ある者のように振る舞う。
「なぁ、こうしてお互いが憎しみ合うことほど、悲しいことはないじゃないか。次のくじで決まるのは自分かと、怯え疲弊することも辛いじゃない」
ダンドは告げる。
自分の中に勇気がなくとも、他に何か残るものがあるのではないだろうかと。
人にとって、それは異なるものであろう。
人間性の最後に残るのが、勇気だけとは限らないかもしれない。矜持であるかもしれないし、尊厳でもあるかもしれない。
ならばこそ、ダンドは訴えるのだ。
「勇気を出してくれ。誰しも死ぬのは恐ろしい。けれど、尊厳を潰されることもまた、魂が殺されることじゃないか」
振り絞る。なけなしの勇気を。己の中になかったと自覚する勇気を、己の中から絞り出す。
それは雨だれの一滴のような僅かなものであったことだろう。
だが、その雨だれの一滴こそ、巨岩を穿つ最初の一滴に成りうることを知る。
「手を取り合って生きてきただろう?」
隷属と支配だけの世界。
けれど、それでも人々は生きてきたのだ。これまでも。オブリビオンの齎す恐怖と絶望がどれだけ蔓延るのだとしても、それでも負けじと生命を紡いできたのだ。
だからこそ、ダンドは言う。
「嫌だろうが、こんな死に方も、殺し方も」
人の生き死にを決めるのは己自身のはずだ。
ダンドは己の中の勇気が徐々に膨れ上がっていくのを感じたかも知れない。勇気ある者を演じる内に、己の中の勇気が溢れたのかもしれない。
最初は偽りであっても、それを信じて貫くのならば、時に真実よりも堅き意志となる。
それを知らしめるようにダンドは、贄に選ばれた少年と、その母親を護るように堅牢なる意志をもって立ちふさがるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
【SPD】
この世界は……少なくともこの第四層はどこも変わりませんね。
絶対的な支配者である吸血鬼の機嫌を窺い、その気まぐれと戯れにすがって生きていく。
力がなくとも、私が私であるならばやることは変わりません。
生きることは立ち向かうこと。
従い、生かされる道を二度は選びません。
まずは吸血鬼の標的をこちらに向けさせなければ……
生贄とされる少年の手を引き、この場から離脱しようとします。
子供を犠牲にすれば1か月は生きられる……本当にそうですか?
吸血鬼が気まぐれを起こさないと、吸血鬼が別の遊びを思いつかないと言えますか?
悪意を持つ強者に戯れで生かされる。抗わなければその先に続く道はありません。
ダークセイヴァーの夜空は偽りの空。
天には月が浮かぶが、そこにあるのは空ではなく天井。
この地底世界の第四層は、これまでダークセイヴァー世界の地上であると思われていたが、それは誤りであった。
第四層という言葉が示すとおり、ここは地底世界。
天は覆われ、囲われている。
そこに生きる人々の生命に選択権はない。
あるのはオブリビオン、ヴァンパイアによる恐怖と絶望のみ。
人は隷属しなければならない。支配を受け入れなければならない。
「この世界は……少なくともこの第四層はどこも変わりませんね」
セルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)は己の故郷でもあるダークセイヴァーの第四層を見つめる。
『常闇の燎原』に広がるのは『黒い炎』。
まだ彼女は猟兵である。意識ははっきりとしている。彼女の生きてきた人生の中で吸血姫とは絶対的な支配者である。
彼らの期限を窺い、その気まぐれと戯れに縋って生きていく。
それはこのダークセイヴァーのどこでも変わらないことだ。弱者は強者の。強者はさらなる強者の玩具に過ぎない。
『黒い炎』が見せる幻影は、セルマを『無力な一般人』へと錯覚させる。
力の使い方もわからず。
そして、自分が何者であるかも忘れる。
しかし、それでもセルマは己が己である限り、どんな立場になろうとも自身がどのように行動するかを知っている。
「生きることは立ち向かうこと」
そのつぶやきに、幻影の中の村人が訝しむ。
「お前、何を言っているんだ? お前もあいつらを……」
村人たちは月に一度選ばれる生贄、そのくじによってきまった少年を母親から引き剥がそうとしている。
幾人かがこれを止めようとしているのを彼女は見ただろう。
これは抗うことだ。
支配に、恐怖に、絶望に抗う行いであると知る。
それらは全て他者を従えるための力だ。ならば、セルマはそれを拒む。
「従い、生かされる道を二度とは選びません」
セルマは駆け出していた。
少年の手を引き、この場を離れようとする。
「やめろ! 何をするつもりだ! そんなことをしても無意味だ!」
「そうだ、あの御方は見ている! 私達が誰を選ぶのかを! もう決まったことだ!」
「そいつを離せ、そいつをこっちによこすんだ!」
無力なセルマはたちまちの内に取り押さえられてしまうだろう。
けれど、セルマの瞳は絶望にも、恐怖にも濡れていなかった。押さえつける村人たちを見つめる。
「子供を犠牲にすれば一ヶ月は生きられる……本当にそうですか?」
セルマの問いかけに答えはない。
いいや、本当はわかっていることだ。どれだけ『狩りの女王』が約束を守ると言ったところで、強者の特権は約束を反故にすることだ。
弱者の言葉は戯言でしかない。
ならばこそ、その言葉に成約など存在しない。
畳み掛けるようにセルマは抑えつけられながら言葉を紡ぐ。
「吸血姫が気まぐれを起こさないと、吸血が別の遊びを思いつかないと言えますか?」
その言葉は真に迫っていたことだろう。
だが、村人たちに選択肢はない。端から存在していないのだ。弱者は強者に弄ばれるのみ。
だからこそ、彼らは選択肢という目に見える免罪符に飛びついたのだ。
「悪を持つ強者に戯れで生かされる。抗わなければ、その先に続く道はありません」
セルマの瞳に在るのは恐怖でも絶望でもない。
ましてや諦観でもない。
あるのは勇気のみ。
彼女を彼女たらしめる光が、今まさに瞳に湛えられているのだ――。
大成功
🔵🔵🔵
 ブラミエ・トゥカーズ
ブラミエ・トゥカーズ
勇気を燃料に怪異に挑み勝利を得るのは人の特権
只の人間である己もその信仰に殉じて少年を死を厭わず守る
オブリビオンに恐怖は感じない
只の人間の方が恐ろしい
矛盾記憶
十年前の夏の夕暮れに力なき少年が拙い知識と勇気だけで己の心の臓を貫いた様に
人間たる己も少年の様に勇気を振り絞ろう
自己認識は狂っていたとしても、その身は妖怪と化した只の伝染病
妨害しようとして襲われるかもしれない
ただ、その血は病の感染源である
恐怖による暴動は病の侵略を促進する
表層には出ない病としての自身が最悪にはならない様に病を制御する
村人に襲われた腹いせは混じっているが
数百年前、ブラミエの外見の元になった、ある病の先天的免疫を持つ娘が視た光景
尊厳、矜持、あらゆるものが人間性からこそぎ落とされた後に残るものは一体なんであろうか。
それを知るのは人ならざる者であったことだろう。
人を知るためには、人の外に在らねばならない。人は己の存在を正しく理解していない。あらゆるものを削ぎ落とした後に残るのは悪性ではないことは人外にとって事実であった。
ブラミエ・トゥカーズ(《妖怪》ヴァンパイア・f27968)は御伽噺の吸血鬼である。
伝承に縛られ、名と体を得た旧き致死性伝染病。
それがブラミエという猟兵である。同時に妖怪でもあった。
このダークセイヴァーに存在する支配者とは異なる存在。名は同じであったとしても、別物である。
「勇気を燃料に怪異に挑み勝利を得るのは人の特権」
ブラミエは『常闇の燎原』に降り立ち、その『黒き炎』が見せる幻影の中に囚われる。
幻影は己を人と認識させる。
オブリビオンに彼女は恐怖を感じない。只の人間の方が恐ろしいと感じていた。
十年前の夏の夕暮れ。
記憶の中を駆け巡るのは、そればかりであった。
幻影の中の己は『無力な一般人』。すでに齟齬が出ている。
記憶と認識が錯綜する。それは吐き気を催すような困惑であったかもしれない。
己の目の前に在るのは少年の顔。
拙い知識と勇気だけで吸血鬼たる己の心臓を貫いた。それは勇気だけが彼の武器であったからだ。
「そいつを渡せ! そいつさえ生贄に差し出せば、一月は平穏のままに過ごせるのだ!」
「そうだ! そのとおりだ! これまでもそうしてきただろう! これまでと何が違う!」
「自分の息子だけが大切なのか。そんなにも! くじで全て決めてきたのだ、ここで死ぬのが運命なんだよ!」
村人たちの糾弾がくじで選ばれた少年と、彼をかばう母親に突き刺さる。
ブラミエは走っていた。
理由なんて、たった一つだった。一人の人間が少年の手を引き、そして村人たちに取り押さえられた。
少年は今にも泣き出しそうであった。
涙が溢れそうになっていた。けれど、涙を流すことはなかった。
そうすることが彼にとってしてはいけないことだったからだ。だからこそ、ブラミエは彼を守らねばならないと理解した。
「渇き飢え果て踊り狂え。知を棄て、地に這い、血を捧げよ。夜の主たる余のために」
勇気はユーベルコードに変わる。
理解はしていない。
けれど、ブラミエは少年をかばったことで他の村人たちに取り押さえられる。
己の体は確かにユーベルコードに寄ってウィルスを含んだ霧に変わっている。彼女は妖怪と化した只の伝染病だ。その事実は変わらない。
彼女の認識はそうではない。
齟齬が砂嵐のように意識を蝕んでいく。
己の力を全開にしてはならないと、理性のようなものが働く。
「――……これは、なんだ」
違う記憶が交じる。
ダークセイヴァーにありし、いくつかの悲劇の幻影でもない。
十年前の夏の夕暮れでもない。
あるのは、見知らぬ光景。
ブラミエの姿の元。
見知らぬようで、見知った顔をした少女の見た光景が幻視となって村人に抑えこまれたブラミエの視界を染め上げていく。
村人に乱暴に抑え込まれた腹立たしさ以上に、視界を埋め尽くす光景に絶句する。
己は只の人間ではない。
怪異である。
その齟齬がブラミエの体を硬直させていく。
「赤死病。転移性血球腫瘍ウィルス……」
呟く言葉は闇に溶けて消えていく。
ブラミエは知る。
それは全て。
「――全て余の名である」
災厄伝承・赤き死の夜宴(ウタゲハアサヒガノボルマデ)は形を為していく。
ユーベルコードの輝きを湛えた光は、いつかの勇気を反射して常闇に煌めく――。
大成功
🔵🔵🔵
 リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル
…ああ、あの子が選ばれたの。これでまた1ヶ月は平穏に過ごせるのね
…酷い考えなのは分かっている。だけど、ただの村娘に過ぎない私にどうしろと?
…無力な私に出来る事なんて何も無い。そのはず、なのに…
…何故、私はこんなにも憤りを感じている?
…吸血鬼に、村人達に、そして何より誓いを果たそうとすらしない自分自身に…
…忘れる事なんて赦さない。この想いは、私だけの物では無いのだから
"…人類に今一度の繁栄を。そして、この世界に救済を…"
そう誓った以上、私は歩みを止める訳にはいかない。必ず助けてみせるわ
母親を引き剥がそうとする村人達に混じり存在感を溶け込ませ、
勢いに押され体勢を崩したふりをして村人達の妨害を行うわ
平穏の意味を考える。
そこにどんな犠牲があって、どんな経緯があったのかをリーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は、いや、『黒い炎』が見せる幻影の中の一人は考えたことがあっただろうか。
考えたところでこの常闇の世界ダークセイヴァーにおいては、無意味であったのかも知れない。
平穏を感受するために必要なのは見て見ぬ振りをすることだ。
不都合を吐き捨てることだ。
どんな礼節も、倫理も、道徳も、全ては生命があってこそ。平穏があるからこそ、それらは意味を成す。
だからこそ、彼女はため息を吐き出すように諦観を呟く。
「……ああ、あの子が選ばれたの。これでまた一ヶ月は平穏に過ごせるのね」
おのれながら酷い考えだと判っている。
けれど、ただの村娘に過ぎない自身に何をしろというのだ。
胸の奥が揺らめくように波紋を描いている。
わからない。このゆらめきは確かに苛立ちを募らせているようでも在った。
「……なぜ、私はこんなにも憤りを感じている?」
無力な自分に出来ることはなにもない。
見ていることしか出来ないし、そのくじで選ばれた生贄の少年がどうなるのかを見届ける気もない。
見て見ぬ振りをして、蓋をして、不都合な事実を暗闇の片隅に追いやる。
それだけでよかったはずなのだ。
けれど、彼女の中には憤りが炎を燃え上がらせる。
誓いすら果たそうとしない自分自身。
「……誓い?」
それはなんだ。
知らない。いや、知っているはずだ。知っていたはずだ。忘れてはならないものであったはずなのに、彼女は心の中に燃え広がるそれを見て見ぬ振りをすることができなかった。
炎の向こう側に一人の少女がいる。
「……忘れることなんて赦さない。この想いは、私だけのものではないのだから」
響き渡る言葉。
残響のように遠く響く思い。
それらがおのれの背中を押す。
生贄の少年の母親が、少年の代わりになると叫ぶ。泣いている。
少年の瞳には涙が湛えられている。
おのれではなく、誰かのために涙をこらえているのだ。これは過去の幻影。消えることのないものであり、覆すことのできないものであると何処か自分は知っている。
「こっちに来い! お前が選ばれたのだから!」
「我が子だけが可愛いのか! 偽善者め! 自分の身内だからと例外が通るものか!」
「私が! 私が代わりになりますから! どうか、どうかこの子だけは! まだこんなに幼いんです!」
村人が少年から母親を引き剥がそうとしている。
自分がどうするべきかなどわかっている。
おのれの背中を押す言葉がある。
“……人類に今一度の繁栄を。そして、この世界に救済を……”
燃え広がるように心に灯されたものがある。
それが自分の足を進めさせるのだ。
一歩を踏み出す勇気があれば、人間性の全てを失った通しても何の問題もない。勇気の発露こそが、人間性の始まりであるから。
「私は、私は……」
彼女は、リーヴァルディは、歩みを止めるわけにはいかないのだ。
どんなに謗られてもいい。
必ず助けてみせるという思いだけがリーヴァルディの体を突き動かす。
村人たちにまじり、溶け込むように存在感を消す。
本来なら、ただの村娘にそんなことができようはずもなかった。けれど、彼女は意を決して、勇気をもって進むのだ。
紛れるように村人たちの背中を押す。
少年の顔が見えた。
大丈夫だと涙を湛えた瞳にうなずく。きっと助けてみせる。どんなに覆らぬ過去であったのだとしても。
それでもこの胸に灯った勇気だけは偽りではないのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
 ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー
POW
渦中の傍に居るのは、初めてかもしれない
おれはいつも遠巻きでしか種族間の争いを見たことがない……いいや、感じた事すらないのだろう。無力すらも、傲慢たる吸血鬼の血を引く故に
襲う事なく生きてきた。襲われる事もなかった
守られていたからだ。両親に。己の内に流れる血脈に
女は狩られる側に居た。男は狩る側に居た。なのに今も一緒も居る
非社交的な二人は利害が一致したから、共に逃げたらしい。互いに世界に無関心で冷たいいきものだ
その冷たさはおれにも受け継がれている
だから。だからって。無力だ、って。絶対だけども
見捨てたくないな。誰も。逃げるなら。向かうなら正面だろ。なあ、
「きみは慈悲深くないし、きみの行いこそが時間の無駄だ」
言ってやれ。無力とて声は出せるのだ
微
無力とて無謀にも手を伸ばすのは
おれがそれをしたいからだ
悲劇は『常闇の燎原』を包む『黒い炎』から幻影となって放たれる。
猟兵達は、その幻影に囚われ、己が一体どのような存在であったかを忘れる。
そこでは全てが『無力な一般人』でしかない。
過去の幻影は覆らない。
この地に満ちる数多の悲劇は、決して変わることはない。
一月に一度の生贄。
それに選ばれた少年と、その母親が村人たちに糾弾されている。
偽善者が、と。
自分の身内だけが可愛いのかと。
これまで多くを見捨てて来たはずだと。
「一月生きるためにこれまで見捨ててきた生命は惜しくなくとも、己の子のためには涙を流すのか!」
村人の言葉は正しい。
正しいのだろう。
これまでそうしてきたように、彼らは一月を平穏に生きるためだけに多くの生命を切り捨ててきた。
小を切って、大を救う。
一人がみんなのために。なんと聞こえの良い言葉だろうか。
「――……」
ギヨーム・エペー(Brouillard glacé calme・f20226)は絶句していた。
彼は悲劇の渦中にいることはなかった。
これまでそんなことはなかったのだ。遠巻きでしか見たことがない。いや、感じたことすらなかった。
ただ只管に己は平穏の中にあった。
無力すら感じたことはない。己はダンピールである。しかし、今は『無力な一般人』だ。
だからこそ、感じるのだ。
かつて在りし悲劇の欠片。
それがこの『黒い炎』より放たれる幻影の正体だ。
ダークセイヴァーには多かれ少なかれ、こんな悲劇だけが満ちていたのだ。けれど、それはどれも彼にとって初めて感じる激情であったのかもしれない。
「襲うこと無く生きてきた」
「襲われることもなかった」
「守られていたからだ」
何に、と見知らぬ誰かが疑問を呈する。己では、己の輪郭を為すことはない。己の存在を形作るのはいつだって他者である。
だからこそ、気がついたのだ。
狩られる側の女と狩る側の男。本来なら相容れぬ存在同士。けれど、今も一緒にいる。非社交的な二人の利害が一致したからだろう。
「共に逃げた」
「お互いに世界に無関心で冷たいいきものだ」
「その冷たさはおれにも受け継がれている」
自問自答が心のなかにあふれかえる。
違う。自分はこうではないはずだと誰かが言うのを聞いたはずだ。恐怖も絶望も、何もかも己には関係の無いことであった。
恐怖を感じなかったのは、守られていたからだ。
絶望を感じなかったのは、己の中に流れる血脈ゆえに。
この常闇の世界にあって、己こそが自由そのものであった。
けれど、無力だ。
それは変わらぬ絶対である。覆ることはない。
「――……見捨てたくはないな。誰も」
そのつぶやきに彼はハッとしただろう。誰の言葉だ。
村人が訝しむ顔が己に向いている。
その瞳は糾弾するものであったし、同時に異端者を見つけた視線でもあった。まずいと思った。
何を口走っているのだと思っただろう。
けれど、止まらないのだ。
「逃げるなら。向かうなら正面だろ。なあ――」
その言葉を止めろと絶望と恐怖に塗れた声が叫ぶ。
けれど、その言葉は己の喉から発露したものであった。
「きみは慈悲深くないし、きみの行いこそが時間の無駄だ」
躊躇いこそ無為なるもの。
すでに己の足は動いているはずだ。恐怖と絶望に足を取られていても、その一歩を踏み出そうとしているのだ。
ならば、すでに恐怖と絶望など相手にしている時間はない。
「言ってやれ。無力とて声は出せるのだ」
「誰も死んでほしくない。誰も選ばなくていいようにしたい。誰もが、誰も、ひとかけらの勇気さえ失いたくはないはずなんだ」
その言葉と共にその瞳に宿るのはなんで在っただろうか。
「無力とて無謀にも手を伸ばすのは」
「おれがそれをしたいからだ――」
そう、恐怖と絶望の中にこそ煌めくものがある。
それを人は勇気と呼ぶ。
矜持も尊厳も、何もかも削ぎ落とされたからこそ、一層輝くもの。勇気。無謀と履き違えることをは赦されない。
されど、唯一人間が己の意志で、選ぶことのできるものである。
人は殺されてしまうかもしれない。簡単に力ある者に殺されてしまう。
けれど、負けるようには出来ていないのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
第2章 集団戦
『その地に縛り付けられた亡霊』

|
POW : 頭に鳴り響く止まない悲鳴
対象の攻撃を軽減する【霞のような身体が、呪いそのもの】に変身しつつ、【壁や床から突如現れ、取り憑くこと】で攻撃する。ただし、解除するまで毎秒寿命を削る。
SPD : 呪われた言葉と過去
【呪詛のような呟き声を聞き入ってしまった】【対象に、亡霊自らが体験した凄惨な過去を】【幻覚にて体験させる精神攻撃】を対象に放ち、命中した対象の攻撃力を減らす。全て命中するとユーベルコードを封じる。
WIZ : 繰り返される怨嗟
自身が戦闘で瀕死になると【姿が消え、再び同じ亡霊】が召喚される。それは高い戦闘力を持ち、自身と同じ攻撃手段で戦う。
イラスト:善知鳥アスカ
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『集団戦』のルール
記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
人は殺されてしまうだろう。
無力であるから。
強者に貪られ、弄ばれるだけの儚くも脆い存在であるだろう。どうしようもないことだ。誰もが強くはあれない。
けれど、人は負けるようには出来ていない。
決して、全てを投げ出すことはない。人間性の果に勇気があるというのならば、人は一歩を踏み出すだろう。
今は恐怖と絶望に塗れた渦中にある『無力な一般人』であったのだとしても、幾人かが足を踏み出した。
生命は失われてしまう。
「なぜそんなことをする。過去は覆らない。変わることのない現実だ。どうしようもないことだ。もう終わったことだ」
『黒い炎』が放つ幻影が、『無力な人々を恐怖と暴力で蹂躙しようとする』、『その地に縛り付けられた亡霊』たちとなって襲い来る。
そこにあったのは、かつて在りし者たちの無力に嘆く魂であったのかもしれない。
過去は幻影でもって今に投射される。
何もかもが手遅れであるのかもしれない。
幻影の中の出来事は変わらないのかも知れない。
「この子だけでも、助けてください。私は、どうなってもいいのです! ですから、どうか! どうか! この子に一月だけでも平穏に過ごさせてください!」
少年の母親が大地に叩きつけられる。
涙が零れそうに成りながら、少年が母親に駆け寄る。それを『その地に縛り付けられた亡霊』たちが掴み、引き剥がす。
それは圧倒的な恐怖と絶望であった。
未だ猟兵達は『無力な一般人』であるという幻影を振り払いきれないだろう。
けれど、その瞳にはユーベルコードの光が灯されている。
これは幻影だと叫ぶ誰かが己の中にあるだろう。
振り払えと、そのための力が己にはあるのだと勇気が叫んでいる。
少なくとも、そんな気がしたのだ――。
 儀水・芽亜
儀水・芽亜
くっ、まだ私の心は折れていませんよ。勇気でもって、どんな絶望だって越えてみせる。
亡霊への体当たりや親子に伸ばされた手を振り払ったり。それが私に出来る唯一の抵抗。
唯一? いえ、他にもまだ、力があるような。
身体のうちから響く音がどんどん大きくなる!
そう、私は猟兵! オブリビオンを狩るもの。
「全力魔法」「貫通攻撃」で、ナイトメアランページ!
夢に遊ばせることが本質の私が、悪夢に取り込まれるとは、笑い話にもなりません。
人々も、この親子さえも幻影。助ける意味があるのかと問う方もいるでしょう。ですが、幻影は幻影なりに精一杯生きているのですよ。
だから、オブリビオンとなった亡霊たちよ、ただただ討滅されなさい!
人の心は柔く脆いものである。
そして、一度傷が付けば戻ることはない。時間だけが癒やす手段であり、そこに優しさという軟膏が塗られるのだとしても、即座に戻ることはない。
ダークセイヴァー世界には、今も、昔も変わらず傷んだ傷跡が残っている。
『その地に縛り付けられた亡霊』たちはまさにそんな者たちの集合体のようなものであった。
「生贄を捧げろ! くじで選ばれたのだ! 老いも若きも、健やかな者も、病める者も関係ない」
「等しく選ばれたのだ。選出されたのだ」
「抵抗は無意味だ。平穏の礎になることをこそ誇れ」
『その地に縛り付けられた亡霊』たちは喚くようにして叫ぶ。
彼らにとって、常闇の燎原に蔓延る『黒い炎』は幻影であっても過去に在りしものであったのかもしれない。
実際に引き起こされた悲劇。
その繰り返し。
過去を覆すことはできない。
けれど、儀水・芽亜(共に見る希望の夢・f35644)の瞳に光は灯る。
絶望も恐怖もない。
そこにあるのはユーベルコードの輝き。何が己を自分にするのかを彼女は未だ思い出せなかった。
『無力な一般人』――そのままに芽亜は『その地に縛り付けられた亡霊』たちに抑えつけられ首を上げる。
「くっ、まだ私の心は折れませんよ」
目の前にあるのは絶望だけだった。
どうしようもない恐怖に駆られた絶望が、己を取り押さえている。
けれど、立ち上がるのだ。
自分は此処で這いつくばるだけの者ではないと、心の何処かで叫ぶ者がある。
『その地に縛り付けられた亡霊』たちを体当たりで吹き飛ばし、少年と母親に伸ばされた手を振り払う。
これだけしかできない。
抵抗と呼ぶにはあまりにも儚いものであった。
「こいつを抑えろ! 一人でいいのだ! たった一人で一月平穏が訪れる」
「お前にその平穏の価値がわからぬとは言わせないぞ!」
「今までもそうしてきたんだ! これからも続ける。平穏を少しでも長く続けるために!」
『その地に縛り付けられた亡霊』たちの手が芽亜に伸びる。
できることはない。
いや、違う。
唯一の抵抗も、これだけではないはずだと灯るユーベルコードの輝きと共に瞳が煌めく。
「勇気でもって、どんな絶望だって越えてみせる」
自然と言葉を紡ぐ唇。
胸の内には燈火のようなものがくすぶっている感覚がある。そして、音が響く。
どうしようもないほどの悲劇も、起こり得るであろう絶望も、それらが呼び込む恐怖も乗り越える術を己は持っている。
死と隣合わせの青春を思い出す。
いつでもどこでも、そこら中に死が転がっていた。
絶望に飲み込まれることも、恐怖に沈むこともない。あるのは唯一つ。
「そう、私は猟兵! オブリビオンを狩るもの」
輝くユーベルコードの光が発露した瞬間、ナイトメアランページによって夢魔が駆け抜ける。
来訪者『ナイトメア』。
それは彼女の力の源であったことだろう。
迸るナイトメアの群れは、『その地に縛り付けられた亡霊』たちを吹き飛ばす。
「夢に遊ばせることが本質の私が、悪夢に取り込まれるとは、笑い話にもなりません」
自嘲する。
けれど、同時に誇らしさもあるだろう。
どれだけ幻影に寄って己が無力であったのだとしても、その勇気だけは変わることがなかったのだから。
助ける意味があるのかと幻影は問う。
過去でしかない。
変えられない運命であるのかもしれない。
けれど、其処に在ったのは過去生きた者たちの軌跡だ。
誰もが懸命に生きた。その証を彼女は貴ぶ。
「だから、オブリビオンとなった亡霊たちよ、ただただ討滅されなさい!」
迸るナイトメアが彼女の道をはばむ幻影すら吹き飛ばし、常闇の燎原にユーベルコードの輝きを満たすのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ブラミエ・トゥカーズ
ブラミエ・トゥカーズ
吸血鬼格は人の想いによって紡がれた幻想による枷であるため
類似しているであろう幻影が剝がれにくく混乱継続中
人間の振りをした化物を嗤う声が聞こえる
かつての怨敵の無様を揶揄う様に
夜の宴に灯りを
浄化、対集落属性を持つ騎士団がやってくる
弱者を恐怖と暴力で蹂躙し続けた善なる者達
相手がどれだけ悲痛を謡おうと彼等には関係ない
不本意ながら亡霊からブラミエを守りつつ
邪悪ならば全て焼き払う
ついでにブラミエがばら撒いた病も消毒しておく
余は知っている。
貴公等は憎く恐ろしく、そして愛しき者。
まだ記憶曖昧で只の人間と自覚が残る吸血鬼に騎士団は困り笑い
呆けているなよ、吸血鬼。
騎士の手にある魔女狩りの聖剣が首を落とす。
ダークセイヴァー世界のオブリビオン、ヴァンパイアが世界の支配者であるのならば、人の想いによって紡がれた幻想である御伽噺の吸血鬼は如何なる存在であったことだろうか。
あらゆる伝承が枷となる。
紡がれた幻想は、ブラミエ・トゥカーズ(《妖怪》ヴァンパイア・f27968)の四肢を縛り付けることだろう。
あからさまな弱点。
人の手によって打ち倒されるべき存在。怪異。
そのどれもがこの常闇の世界におけるヴァンパイアとは異なるものであったことだろう。
己の思考を染め上げる『黒い炎』によるかつての幻影は、ブラミエを混乱の只中に叩き落とすものであった。
「抵抗するな。無駄なことをするな。これは決まったことだ」
「くじで選定すると決めた以上、これが法だ。律をもって、平穏を紡がなければならないのだから!」
「子を引き剥がせ! それは生贄だ。もう人ではない!」
村人たちの幻影が口々に叫び、『その地に縛り付けられた亡霊』たちへと幻影が形を変えていく。
彼らは悪意ではない。
人の悪性でしかない。ならば、己の瞳に輝くのは人の善性か。
否である。
それは人の善性ではない。あるのは勇気であったが、己のものではない。かつて見た夕暮れの日に煌めく瞳であったから。
己は人間のふりをした化生である。
ゆえに、その人間の振りをした様を誂うように、また揶揄うように嗤い声が響き渡る。
灯されるのは、歪曲伝承・魔女狩りの灯(セイギトキョウフノナノモトニ)。
「恐るべき人よ。愛しき無知よ。己の善にて邪を蹂躙する正しき者よ。怨敵共よ、魔女狩りを始めるが良い。汚れた敵は此処にいるぞ」
松明や火矢を手にした騎士団が幻影を取り囲んでいる。
その視線の先にあるのは『その地に縛り付けられた亡霊』であり、同時に弱者を恐怖と暴力で蹂躙し続けた善なる者達。
駆け抜ける馬の蹄は高らかに響き渡る。
振りかぶられる剣が亡霊を打ち払う。
ブラミエは呆然と見上げるしかなかっただろう。
騎士たちは不本意だというようにブラミエを守っている。邪悪なる者全てを焼き払う炎が『その地に縛り付けられた亡霊』たちを焼き払い、ブラミエが撒き散らした病すらも消毒するように炎が立ち上る。
『黒い炎』は煌々と立ち上り、あらゆるものを振り払うだろう。
「余は知っている。貴公等は憎く恐ろしく、そして愛しき者」
ブラミエは自分とは異なる幻影の人々を見やる。
騎士たちは未だブラミエの様子に困惑しているようでもあった。
彼らは止まらない。
世界のために無力な人々のために邪悪を討滅するゆえに。その真実を知らずとも良いのだ。
剣は振るうことができる。
「呆けているなよ、吸血鬼」
その言葉にブラミエは漸くにして己を取り戻すだろう。煌めくは魔女狩りの聖剣。
ああ、そうであった。
己はなんであったのか。
猟兵である以前に、御伽噺の吸血鬼である前に。
己は旧き病。
その名を思い出す。己はそのようなものであったのだ。己が相対するは人の勇気である。
ブラミエの中から発露するは、ユーベルコードの煌き。
「呆けてはいないさ。わかっているのだ。これは余が為すべきこと」
『その地に縛り付けられた亡霊』たちは皆、尽くが霧消していく。
御伽噺の吸血鬼が此処にある。
人の手によって討たれるべき存在。だが、ここに人はいない。
あるのは過去の化身と幻影。
ならば、ブラミエは立ち止まることを赦されないだろう。かつて在りし過去は覆らない。
ゆえに、彼女は常闇の世界の己の存在を謳うのだ――。
大成功
🔵🔵🔵
 ダンド・スフィダンテ
ダンド・スフィダンテ
過去は覆らない、分かっているとも。
けれど、だから放っておいて良いとは、ならないだろ?だって、俺様は皆に平穏であって欲しいんだ。
だからさ、なぁ、頼むよ
胸が痛む。その傷みこそが、猟兵となる鍵だった。
祈る。彼らの心が安らぐ事を。
自らが呪われる事は構わない。
けれど祈りが薄れては困るから、狂気への耐性をそこにだけ注ぐ
なぁ、貴殿らが苦しんでいるのは過去の暴虐だ。けれどその傷みを被っているのは今だ。
なら、変えられるだろ。
1人でも多くを巻き込む為に、印は大きく開こう。
また、手を取り合ってくれ。きっと遅く無い。
吸血鬼は我ら猟兵が殺すから、安心して眠ってくれ。
常闇の燎原が見せる幻影は、かつて在りし過去。
残響のごとく世界に残る人々の轍そのものであった。
涙をこらえる少年も、子を想う母も、生贄を捧げることで一時の平穏を得ようとする村人たちも。
どれもが過去にあった存在である。
『その地に縛り付けられた亡霊』たちは、オブリビオン、ヴァンパイアの見せた悪意によってあらゆるものを呪う。
「あってはならない。生贄が変わることなど」
「選定のくじは引かれたのだ。そこに間違いなど在ってはならない」
「もしも、これが覆るのならば先んじて死せる者たちもまた過ちであったと認めるようなものだからだ!」
村人たちの幻影は次々とオブリビオンとなって猟兵達に襲いかかる。
ダンド・スフィダンテ(挑む七面鳥・f14230)はユーベルコードの煌めく瞳を持って、その幻影を見据える。
「過去は覆らない、わかっているとも」
目の前の幻影を救うことは叶わない。
すでに終わっていることを覆すことはできない。猟兵の持つユーベルコードの力であっても、それはできないことであった。
運命があるのだとして、人の力ではどうしようもないことなのだ。
けれど、とダンドは息を吐き出しながら、目をそらさずに『その地に縛り付けられた亡霊』たちと対峙する。
「けれど、だから放っておいて良いとは、ならないだろ?」
自身を取り戻す。
自分が何であるかを知る。胸の内に溢れるのは、いつだって己自身に対する不信ばかりであった。
自信がない。
けれど、それを他においても為さねばならぬことをダンドは知っている。それが己であるのだ。
その不信が胸を痛める。
皆に平穏であって欲しいと願う心。
「だからさ、なぁ、頼むよ」
それは祈り(イノリ)であった。願いを込めた『聖印の光』が迸る。
その胸の痛みこそが、己が猟兵となる鍵そのものであった。
今、ダンドが祈るのは『その地に縛り付けられた亡霊』たちの心が安らぐ事だけであった。
まばゆい聖印の光はオブリビオンとなった過去の残響を吹き飛ばす。
安らぎを蝕む負の感情だけをユーベルコードは消し飛ばしていく。
「我らが間違いであったというのか!」
「我らは我らに出来ることをしたまで! 平穏が一時に過ぎないのだとしても、それでも安らぎを求めることは過ちであったのか!」
「我らの死は、我らの生は無意味だったのか!!」
『その地に縛り付けられた亡霊』たちの声が呪いとなってダンドに降り注ぐ。
「なぁ、貴殿らが苦しんでいるのは過去の暴虐だ。けれどその傷みを被っているのは今だ」
なら、変えられるだろ――。
ダンドは見据える。
己の胸のうちにある聖印の光は傷みにほかならない。
自分は猟兵である。ダンド・スフィダンテである。もう『黒い炎』が見せる幻影に惑わされることなどない。
あるのはあらゆる傷みに平穏を齎すユーベルコードの輝きのみ。
そして、ダンドは手を伸ばす。
光の中、過去の残響たる『その地に縛り付けられた亡霊』たちに手を伸ばすのだ。彼らとて平穏の中に生きていたかったことだろう。
誰もが平和に憧れたことだろう。
脅かされることのない生活を求めていただろう。
「きっと遅くない」
ダンドの手は、たしかに『その地に縛り付けられた亡霊』たちの手を取っていた。彼らを苛むのは、ヴァンパイアの恐怖。
ならばこそ、ダンドは己の心を開くのだ。
「吸血鬼は猟兵が殺すから、安心して眠ってくれ」
安らぎを齎すためにこそ、ダンドは猟兵として戦う。
それがきっかけであり、鍵そのもの。その鍵をもう二度と彼は手放すことはないだろう。
手にした彼らの悲しみ、恐怖、絶望、それらを全て抱いて、元凶たるヴァンパイアを討ち滅ぼす。
そのためにこそ、ダンドの聖印は常闇の世界にこそ煌めくのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
そうですね。過去は覆らない。
今ここで何をしたところで、私がしてきたことは何も変わらない。許されることもないでしょう。
ですが、未来は変わる。
そのために私は……戦います。
マスケットの弾を込めている暇なんてありませんね。
手にした銃「フィンブルヴェト」の銃剣で応戦します。
亡霊の精神攻撃を振り払い、自身の力を取り戻してきたなら弾丸が入っていないはずのフィンブルヴェトの引き金を引き【氷の狙撃手】。
自身の力で作り出した氷の弾丸で亡霊たちを撃ち抜きます。
……この地で起きたことも変わるわけではありません。
ですが……ここにいた人たちは今もなお第三層で苦しんでいるかもしれない。ならば、私も戦い続けるだけです。
常闇の燎原の『黒い炎』が見せる幻影は過去の投射に過ぎない。
今を変えたところで、過去が変わることはない。
ゆえに、猟兵たちの抵抗は無意味であると断じるのが『その地に縛り付けられた亡霊』たちであった。
彼らは無力な過去の人々の集積でもあったことだろう。
一月一度一人の生贄。
それを選定しなければ、平穏に生きることすら赦されない。
そして、何よりもその選定を己達でしなければならないという呵責に押しつぶされながらも、生きるためにこそ選び続けて滅びた。
最期が如何なるものであったのかを知る者はいない。
あるのは過去という蓄積のみ。
「我らは間違っていない。何も間違えていない。必ず死せる運命であるから」
「こうなることは速いか遅いかだけの違いでしかなかったのだ」
「だから、我らは何一つ間違えていない!」
己たちの選択は間違っていなかったのだと。己たちの生が過ちだけではなかったのだと喚く『その地に縛り付けられた亡霊』たちをセルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)は見つめる。
「そうですね。過去は覆らない。今此処で何をしたところで、私がしてきたことは何も変わらない」
今、此処にあるのはセルマという人間のみ。
彼女にもまた後悔と過ちの蓄積がある。だからこそ、彼女は己が許されざる者であることを自覚する。
同時にそれは『無力な一般人』であるという錯覚を振り払うには十分な自覚であった。
過去は変わらない。
過去は覆らない。
過去は正せない。
ならば、己が何をすべきかを彼女はすでに得ているのだ。
「ですが、未来は変わる。そのために私は……戦います」
『黒い炎』の見せる幻影を振り払うように腕を払う。
そこにあったのは、マスケット銃であった。銃弾を装填している暇もなかった。迫りくる『その地に縛り付けられた亡霊』たちをマスケット銃の先端につけられた銃剣でもって切り払う。
「未来など、絶望と恐怖に染まっている」
「そんな未来を変えるなどできはしない。お前の轍は血と涙に染まっているというのに」
「悔恨で未来が変えられるものか!」
その言葉をセルマは受け止める。
確かに正しいだろう。
わかっている。いつだって己の足を掴むのは恐怖と絶望だ。
だが、セルマは氷の狙撃手(アイシクル・スナイパー)だ。幻影を振り払うのではなく、撃ち抜くために存在している猟兵である。
「……この地で起きたことも変わるわけでもはありません。ですが……」
だが、セルマはもう知っている。
銃口を『その地に縛り付けられた亡霊』たちに向ける。引き金を引く。いつだって決めてきたのは自分だ。
どれだけ己の轍が血と涙に染まっているのだとしても。
己がこれから歩む未来という道は、いつだって白紙なのだ。過去の亡霊たちが己の足をつかもうとも、それだけは変わらない。変えられない。
白紙の未来はいつだって自分を照らしている。
「……ここに居た人たちは今も尚第三層で苦しんでいるかもしれない。ならば、私も戦い続けるだけです」
放たれる氷結の弾丸が『その地に縛り付けられた亡霊』たちを貫き、凍りつかせる。
それは氷棺のように。
世界の真実を知ってしまったからこそ、その光景は別の意味へと変わる。
弱者は強者の玩具にすぎない。
この世界の理、構造をこそセルマは打ち砕くために戦う。その決意漲る青い瞳が暗闇の天井を射抜く――。
大成功
🔵🔵🔵
 ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー
恐怖も絶望も無縁の感情、だった
無力。おれは無力か? そうだろ。おれは無力な一般人で、異端者で。それなのに村の決まりに口を出してしまった。だからおれが淘汰されるのは村としては正しい行いだ
おれのは勇気なんかじゃない。おれのコレは浅はかで、皆からすれば害意で、狂っている
狂っている? どっちが。否、皆は狂ってなんかいない。狂わされてもいない。彼らはただくじを引いただけだ。誰も生贄なんて選んじゃいない
誰もが平穏を望んでいる。誰もが生きたがっている。皆で生きたいはずだ。誰もが欠けたくないはずだ。でなきゃ怨嗟は渦巻かない
地を這い泥水を啜りながらもなお生きようと抵抗する生物ほど素晴らしい存在はない。そうだ
狂っても尚前に進んだ少女の狂気は確かな勇気でもあった。抵抗せよ
……全部受け止めよう。全部。返してくるから
『その地に縛り付けられた亡霊』たちは、まさに呪いそのものであった。
彼らは己たちの選択を過ちに変えぬためにこそ、『黒い炎』の幻影と共に猟兵たちを苦しめる。
自分たちは間違っていなかったのだと。
自分たちはできることをしただけなのだと。
仕方なかったのだと。
何も悪くはないのだと。
ただそれだけのために彼らは呪いの言葉を紡ぎ続ける。彼らにとって、それだけが心の平穏を得る手段であったからだ。
「恐怖も絶望も無力の感情」
だった、とギヨーム・エペー(Brouillard glacé calme・f20226)は振り返る。
己という存在は過去を振り返ることでしか認識できない。
自分とは如何なる存在であったか。
違和感だけが頭の中に反響している。
無力。
己は『無力な一般人』だ。そして異端者だ。
村の決まりに口を出した。泣く母親と引き剥がされる少年を見た。そんな己を淘汰しようとする村人たちは正しいのだろう。
法と律でもって統治は為される。ならば、異端者は異物にほかならない。正しい。彼らは正しい。
「お前のそれは勇気じゃない」
「蛮勇にも足りない。ただの自己満足に過ぎない。お前は我らの平穏を乱す異物であり、害意」
「狂ったのか、お前は。これまでもしてきたことだろうに。とっくに罪悪など感じないように成っているはずなのに、それでもなお、我等を悪と誹るか」
呪いのような言葉であった。
己の体を雁字搦めに縛る呪いの言葉。
ギヨームは己が浅はかであったと思ったことだろう。
「狂っている?」
今一度言う。
「どっちが」
いや、違う。目の前の幻影は狂ってなど居ない。狂わされても居ない。ただ、彼らは選定しただけだ。
誰の責任もない。強いて言うならば、全員の責任だ。そうして罪悪を薄めることでしか心の平穏を保てぬのが人間という性である。
最初は誰も生贄など望んでいなかったのだ。心穏やかな日常を望んでいる。けれど、それを許さぬのがヴァンパイアだ。
だから、ギヨームは呟く。
呪いも、何もかも己の体で受け止める。けれど、己の血液がそれを許さない。氷魔さえも焼べる冷炎が己の身の内から顕現する。
紫の瞳が狂気に彩る。
そう、何も間違っていない。彼らが狂っているのではない。己がおかしいのだ。
「誰もが生きたがっている。みんなで生きたいはずだ。誰も欠けたくないはずだ」
でなければ、怨嗟は渦巻かない。
誰もが己だけが清廉潔白であると講じるだろう。
己だけが、己だけが、己だけが、この世で唯一であると。
ギヨームは見てきた。
地を這い、泥水を啜りながらなお生きようと抵抗する生物ほど素晴らしい存在はない。
「そうだ。狂っても尚前に進んだ狂気は確かな勇気でもあった」
ならば、なんとする。
何を為す。
どうすれば、この絶望と恐怖だけが支配する世界に示すことができるのか。
「抵抗せよ」
ただ一つの答えである。
抗う。ただ一つのこと。それが人間と吸血鬼を分かつ他唯一のこと。
殺されてしまうかもしれない。
死んでしまうかもしれない。
けれど、人は負けるようにはできていない。ギヨームは吸血鬼だ。覚醒した血潮は冷たく体を駆け巡って燃える。
「La nuit du coucher du soleil arriva.」
夕焼けのごとき髪が燃える。
夜を体現した吸血鬼の体躯が呪い全てを受け止める。
「……全部受け止めよう。全部。返してくるから」
迸る夜は『その地に縛り付けられた亡霊』たちを尽く吹き飛ばす。
どれだけの怨嗟も、悲しみも、絶望も、恐怖も、何もかも灰燼に帰す。冷たく燃える炎が『黒い炎』を振り払ってほとばしり、最初の一歩を踏み出すのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル
…生贄の子供とそれを護る母親、か
…私の母は私を神の生贄に捧げる側…どころか狂信者を指導する立場で、
護ってくれたのは見ず知らずの貴女達だったわね…ラグナ、プレア
"…人類に今一度の繁栄を。そして、この世界に救済を…"
…過去は変えられない。悲劇は覆らない。恐怖と絶望を消す事はできない
だけど、それは今を生きる者の歩みを止める理由にはならないわ
…例え全てを忘却したとしても、貴女達から受け継いだ誓いは消えはしない
そして、彼女達から教わったこの力の使い方もね
UCを発動し121本の魔刃を地面に突き立て魔法陣を形成する集団戦術を行い、
黒炎の幻影を光のカウンターオーラで防御して浄化する光属性攻撃の結界を展開する
猟兵達が示したユーベルコードの輝きに寄って『その地に縛り付けられた亡霊』たちが次々と幻影と共に消えていく。
だが、彼らは再び幻影となって立ち上る。
まるでこの地に集積した悲劇全てが猟兵に牙を剥くようでもあった。
なぜ救ってくれなかったのかと恨み言が充満する。
どうしてもっと早く着てくれなかったのかと嘆く声が響く。
耳を打つ恐怖と絶望がリーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)を苛む。
生贄の子供とそれを護る母親の幻影に彼女は何を視ただろうか。
己の生い立ちを自覚したのかもしれない。
彼女の母親は己を神の生贄捧げる側であった。決して護ってくれる存在ではなかった。あの幻影の母親のようではなかった。
それどころか、あの村人たちと同じように生贄を是とする側であったのだ。
狂信者たちの声が過去から耳に迫り、こびりつく。
けれど、今己が存在しているのは己を護ってくれる存在がいたからだ。
「……護ってくれたのは見ず知らずの貴女達だったわね……ラグナ、ブレア」
彼女の過去は彼女だけのものだ。
今の彼女を象るのは、いつだって彼女たちの言葉であったのかもしれない。今も尚耳に、胸に響く言葉がある。
己を猟兵たらしめる言葉。
“……人類に今一度の繁栄を。そして、この世界に救済を……”
ただ、それだけでよかったのだ。
リーヴァルディの瞳にユーベルコードの輝きが灯る。
「……過去は変えられない。悲劇は覆らない。恐怖と絶望を消すことはできない」
一歩を踏み出す。
リーヴァルディは今を生きている。
過去は己の目の前に立たない。ただ、己の轍として後に残るのみ。
ゆえに、彼女は己の中にある誓いを以て、立ちふさがる障害全てを灰へと変える。
「だけど、それは今を生きる者の歩みを止める理由にはならないわ」
彼女の周囲に魔力結晶刃が現れ、大地へと突き立てられる。
瞬時に魔法陣が形成され、彼女の体を覆う。
それは『黒い炎』の幻影を遮断する光の浄化結界。展開された結界の中でリーヴァルディは、吸血鬼狩りの業・魔刃の型(カーライル)を取る。
煌めくユーベルコードは過去よりの贈物だ。
己を護ってくれた者たちから、今の自分へと紡がれた誓いそのもの。
「……例え全てを忘却したとしても、貴女達から受け継いだ誓いは消えはしない」
煌めく。
その瞳の輝きは暗闇の世界にあってなお、煌々と輝く燈火のようであった。
彼女たちが教えてくれた力の使い方。
誤れば、それは世界を滅ぼす力と成り果てるであろう。身に流れる血潮がそれを証明している。
だからこそ、彼女はあらゆる全てを忘れ去ったとしても、受け継いだものでもって、これを御するのだ。
彼女の器に最初に注がれた願い。
何を託されたのかなど、最早言うまでもない。
受け継いだのは力の使い方ではない。
「……私が私たらしめるもの」
刻み込まれた刹那の誓い。
あらゆるものを凌駕する、その誓いこそをもってリーヴァルディは常闇の燎原を包み込む『黒い炎』を振り払う。
「…灰は灰に。塵は塵に。過去が私の前に立たないで」
そして、『黒い炎』を振り払った先にあるのは、この地にかつて恐怖と絶望を振りまいた存在――。
大成功
🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『狩りの女王』
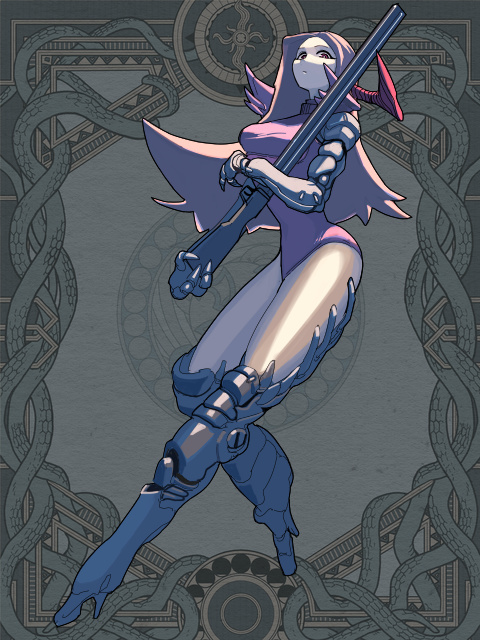
|
POW : レインショット
【空に向けて散弾の雨】を降らせる事で、戦場全体が【月も星もない凍える夜】と同じ環境に変化する。[月も星もない凍える夜]に適応した者の行動成功率が上昇する。
SPD : ハウンズショット
【対象に向けて発砲すること】により、レベルの二乗mまでの視認している対象を、【レベルの二乗体の猟犬に変化する粒弾】で攻撃する。
WIZ : マスターブレッド
敵を【ゼロ距離からユーベルコードを封じる一粒弾】で攻撃する。その強さは、自分や仲間が取得した🔴の総数に比例する。
イラスト:鋼鉄ヤロウ
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「ラモート・レーパー」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
常闇の燎原に満ちる『黒い炎』を振り払った猟兵たちの目の前にあったのは、『狩りの女王』であった。
しかし、彼女の両眼にあったのは瞳ではなく『黒い炎』であった。
噴出する『黒い炎』は彼女に視界を与えない。
あるのは『恐怖と絶望の感情』を感知する規格外の機能のみ。
「全て私の獲物だ。恐怖と絶望に染まった顔を見せてくれ」
すでに彼女に理性はない。
そう、それは『狂えるオブリビオン』。
かつて幾度も見たかもしれない存在。理性なく、そして整合性もない存在。
ただ、己の前にある『恐怖と絶望の感情』に塗れた者を狩り、殺すだけの装置へと成り果てた『狩りの女王』はかつて瞳ありし場所より『黒い炎』を噴出させながら、笑う。
あらゆる生命を嘲笑う。
己の愉しみのためだけに生命を殺す。
そのために全ての生命は生まれたのだと、あらゆる生命に唾棄する。
「狩りは始まった。愉しませてくれ。私の獲物。私はお前達の恐怖と絶望を、味わい尽くしたいのだ――」
 儀水・芽亜
儀水・芽亜
臣下の一人もいない者が『女王』を名乗りますか。片腹痛い。
あなたもどうせ幻影に囚われた身なのでしょう? この場で解放してあげます。
念のため「呪詛耐性」を活性化しておきます。
ナイトメアライドでナイトメアに騎乗し、「騎乗突撃」してアリスランス『ディヴァイン・ユニコーン』で「ランスチャージ」の「貫通攻撃」をお見舞いします。
粒弾が犬に!? 構いません。「受け流し」つつ、蹄で「蹂躙」して蹴散らしましょう。
一撃では当てられなくとも、何度も波状攻撃を仕掛ければいつかは彼女の身体を貫けるはず。
ええ、私は執念深いんです。
所詮は幻影に飲まれ酔いしれた狂えるヴァンパイア。
その目で視ることを捨てた者に未来はありません。
かつて目があった場所より『黒い炎』が噴出するオブリビオン。
それは『狂えるオブリビオン』であり、理性など何処にも存在しないことを伺わせる。
この『常闇の燎原』において大地を包み込む『黒い炎』は、過去の幻影を見せつけ、猟兵たちを『無力な一般人』と錯覚させた。それは『黒い炎』が絶望や恐怖といったものを呼び起こすからかもしれない。
『狩りの女王』は手にした銃を猟兵に向ける。
引き金を引く指は軽かった。
狩りをするやり取りなど関係なく、ただ目の前の得物を鏖殺することだけを喜びとする者の引き金の軽さであった。
「私の愉しみの為だけにお前達は存在してるのだ」
放たれた弾丸が猟犬へと代わり、儀水・芽亜(共に見る希望の夢・f35644)へと迫る。
「臣下の一人もいない者が『女王』を名乗りますか。片腹痛い」
彼女は既に己を取り戻している。
猟兵としての己。『無力な一般人』と錯覚し、そしてそれでもなお勇気を振り絞った彼女は、正しく戦い者としての心を持っていた。
ゆえに、迫る猟犬を前にしても怯むことはなかったのだ。
「あなたもどうせ幻影に囚われた身なのでしょう?」
この場で解放すると彼女の瞳がユーベルコードに輝く。
ナイトメアライドによって純白の白馬型来訪者『ナイトメア』にまたがり、迫る猟犬を躱す――のではなく、正面から美しき褐色の槍でもって貫く。
弾丸が猟犬に変貌したことは驚愕に値するものであったが、恐れには至らない。絶望には程遠い。
これまで彼女は戦いに明け暮れていたのだ。
青春の全てを費やした戦い。
その最中に多くの恐怖と絶望があっただろう。
けれど、その全てを彼女は乗り越えて此処にいる。
そして、どれだけ己が『黒い炎』によって『無力な一般人』であると錯覚させられているのだとしても、己の中にある勇気だけはかき消されることはなかったのだ。
「さあ、誰から《悪夢》の蹄にかかりたいのかしら?」
白馬型『ナイトメア』の蹄が嘶きと共に放たれ、猟犬と化した弾丸を蹴り飛ばし、『常闇の燎原』を駆け抜ける。
「恐怖を感じない。絶望も感じない。私の感覚に引っかからない得物など」
存在してはならない。
引き金を引く『狩りの女王』の手にした猟銃より弾丸が再び放たれる。
どれだけ彼女が弾丸を猟犬に変えて芽亜を襲うのだとしても、彼女の恐怖や絶望は沸き上がることはなかった。
「猟犬が邪魔でしょうがないですが……!」
何度も波状攻撃を仕掛ける。
猟犬を蹴散らし、蹄が大地を踏みしめる度に『狩りの女王』へと近づいていく。
そして、彼女は己の恐怖を感じることが出来ない。
絶望に塗れていない瞳、そのユーベルコードの輝きすら、『狩りの女王』は知ることができない。
ゆえに、芽亜は言うのだ。
「所詮は幻影に呑まれ酔いしれた狂えるヴァンパイア。その目で視ることを捨てた者に未来はありません」
執念であった。
猟犬を蹴散らし、『狩りの女王』へと迫る。
己の手にした槍は、その手にした者の想像力の応じて無限に進化していく。
絶え間ない己の勇気を信じる心こそが、芽亜の力。
振りかぶった槍の一撃が『狩りの女王』を穿つ。
絶望も恐怖も、逃げずに見据えるからこそ人の心に勇気が灯る。それを知らぬヴァンパイアに未来などありはしないのだと示すように芽亜の槍は『狩りの女王』を吹き飛ばすのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ブラミエ・トゥカーズ
ブラミエ・トゥカーズ
優雅に落ちた首を元の位置に戻す
無様を晒した物であったな。
これでは怨敵共に嗤われても仕方ない。
貴公の銃は蝙蝠も狼も貫けるだろう。
だが、風はどうであろうかな?
狩りを楽しむのは良いが恐れ給えよ。
何が潜んでいるか分からぬからな。
妖怪として恐怖を与え驚かせるため
蝙蝠、狼に変化し接近し挑発
猟犬に食われたらそれを基点に病の伝染
猟犬同士を共食いさせる
撃たれて四散しつつ霧に変化
声を掛ける時は吸血鬼姿に戻る
無力な只の人に敗北した最弱の生き物の恐ろしさを見せてやろう。
恐怖を糧にするのは貴公だけではないぞ。
異界の同類よ、人の紡いだ吸血鬼を知るが良い。
今となっては恐怖と優美と愉快が混じった存在ではあるが
聖剣の煌きは吸血姫の首を落とす。
常闇の燎原において『黒い炎』は未だくすぶる。
されど、世界に在りて暗闇が全てを支配することはない。暗闇が色濃いのは、光があるからだ。
光無くば闇もない。
ゆえに、きらめく光は眩く。そしてまた暗闇はさらに昏き。
優雅に聖剣の煌きに寄って落ちた首を元の位置に戻したブラミエ・トゥカーズ(《妖怪》ヴァンパイア・f27968)はゆっくりと歩む。
優雅なる所作。
このダークセイヴァーの世界におけるヴァンパイアとは一線を画するものであった。
「無様を晒した物であったな。これでは怨敵共に嗤われても仕方ない」
彼女は優雅に首の付け根を直す。
血は一滴も流れては居ない。
すでにつながった首の調子を確かめるようにブラミエは首をかしげる。
「貴公の――」
彼女の視線の先にあるのは『狩りの女王』。
目があった場所からは『黒い炎』が噴出し続けている。恐怖と絶望を感知する『狩りの女王』にとって、ブラミエの中にある恐怖と絶望は如何なるものとして感知されていただろうか。
「貴公の銃は蝙蝠も狼も貫けるだろう。だが、風はどうであろうかな?」
伝承解放・悪しき風と共に来たるモノ(トリプルドロンチェンジ)。
それは姿を変える変幻自在たる存在の力の発露。ユーベルコードの煌きは、暗闇にありて尚輝く。
「私の狩りは終わらない。私は私の愉悦のためだけに引き金を引くのだ」
放たれる弾丸が数多の猟犬と成って暗闇を疾走る。
それはブラミエへと迫り、その肉の尽くを捕食し、血の一滴までも貪り食うものであったことだろう。
けれど、ブラミエは姿を変え続ける。
病を運ぶ蝙蝠、狂乱の病を纏う狼へと姿を変えていく。猟犬の牙がへんじたブラミエの肉を食む。
しかし、その牙から猟犬に入り込んだ病は、狂乱を呼び起こし、共食いとなって猟犬たちを蝕んでいく。
「狩りを楽しむのは良いが恐れ給えよ。何が潜んでいるかわからぬからな」
暗闇にありて、闇より昏きものがあるだろうか。
この常闇の世界にあって、此処こそが暗闇より昏き場所。星の明かりも、月の光も何処にも届くことのない常闇の燎原。
ゆえにブラミエは変じる。
放たれた弾丸が肉体を貫くが、即座にそれが幻覚であると『狩りの女王』は知るだろう。
幻覚に陥る病を含む霧となったブラミエが迫る。
「無力な只の人に敗北した最弱の生き物の恐ろしさを見せてやろう」
吸血鬼としての姿に戻ったブラミエが『狩りの女王』の頬を撫でる。
視聴嗅覚を失った彼女にとって、触覚こそが最大の感覚器。ゆえに、彼女は怯えたかも知れない。
噴出した『黒い炎』を躱しながらブラミエは言う。
「恐怖を糧にするのは貴公だけではないぞ」
そう、彼女は妖怪であると同時に人の伝承が生み出した吸血鬼。
似て非なるものであるがゆえに、彼女は己を取り戻し言うのだ。どれだけの恐怖も彼女の糧にしかなり得ない。
そして、絶望に彼女は沈むことはない。
あらゆる絶望を踏破して己の心の臓に杭を打ち込んだ綺羅星の如き堅き意志を知ってるから。
「異界の同類よ、人の紡いだ吸血鬼を知るが良い」
ダークセイヴァーのヴァンパイアとは異なる足かせだらけの存在。
怪異として人間に滅ぼされる物語。
「何が、私に触れている!? 私の愉悦は、私に触れることなどできないはずだ!」
迸る感情にブラミエは笑う。
笑った。
己の体を作るのは恐怖と優美。そして、愉快。
「鬼の器に封されしは古き災厄。今ひとたびこの夜に零れ落ちよう。恐怖と共に」
そのささやく言葉は届かない。
されど、触れた『狩りの女王』の頬はひやりと冷たく。
ブラミエは、その身に病を流し込む。
踊るように優雅に。気品を示すように嫋やかに。そして、そんな己をこそ打ち倒す存在を得たが故に彼女は恐怖を塗りつぶす恐ろしさでもって、『狩りの女王』を圧倒するのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ダンド・スフィダンテ
ダンド・スフィダンテ
元凶がこうでは、どこに怒りをぶつけた物か
だが彼らと約束した以上そちらにも消えてもらう
全力で行くぞ
(と言いながら女王の前から逃げた)
(距離を取り、物陰へ隠れ息を潜める)
(昔、目の前で母が死んだ。生きて欲しい女性が遠くで死んだ。どちらも無惨な死に方だった。そんな、この世界では取るに足りないフラッシュバックで、自分はミューズを攻撃出来なくなった)
(それでも今、槍を取る)
(構えた。来るとしたら此処しか無い場所へ、投擲の姿勢で、力を蓄えながら敵を待つ)
(恐怖で手が震える。呼吸がブレる。それでも)
(冷たい雨に、笑う)
この攻撃は、ミューズが強ければ強い程、その命を縮めるぞ?
(撃つ。その狂気ごと穿ち、貫け)
己には出来ぬことがある。
女性に暴力を振るうことができない。それは、如何にオブリビオンであってもダンド・スフィダンテ(挑む七面鳥・f14230)には出来ないことであった。
怒りはある。
未だこの地に縛り付けられる幻影。
かつて在りし悲劇の住人たち。
彼らを虐げていたのは『狩りの女王』である。一月に一度一人の生贄。それを強要し、己の愉しみのためだけに生命を奪い続けた存在。
されど、それでもダンドの瞳に映るのは女性の姿をしたオブリビオンであった。
目がありし場所からは『黒い炎』が噴出している。
「わかる。わかるぞ、恐怖に震える者よ。私には見えているぞ」
空に向かって放たれる銃弾が、凍えるような星も、月もない夜を連れてくる。ダンドはどうしようもなかった。
されど、己は約束をしたのだ。
「元凶がこうでは、どこに怒りをぶつけたものか。だが彼らと約束した以上そちらにも消えてもらおう」
瞳を伏せる。
この暗闇の世界にあっては、視界など在ってなきもの。
見開いた視線の先にある『狩りの女王』をダンドは睨みつけ言う。
「全力で行くぞ」
ただ短く。己の出来ぬことを悟りながらも、己が課した約束のために駆ける。ただし、それは『狩りの女王』から正反対に、だ。
彼は全力で逃げた。
口では勇ましいことを言っていながら、彼は背を向けた。己の背に迫る弾丸の雨。それらを躱しながら物陰に身を潜める。
ダンドはわかっていた。
自分を狙う『狩りの女王』は決して己を見逃すことはないだろうと。
物陰に隠れたとしても、己が抱く恐怖に彼女は反応する。そういうオブリビオンであるのだ。
理性無き『狂えるオブリビオン』であったとしても、視聴嗅覚全てを失っていたとしても、恐怖と絶望に『狩りの女王』は反応するのだ。
瞳を閉じる。
息を整える。迫る気配がある。絶望の足音のようにも聞こえたことだろう。
ダンドはただ女性を敬愛しているから手をあげられないわけではない。
目の前で母が死んだ。
生きてほしいと願った女性が己の手の届かぬ遠い場所で死んだ。
どちらも惨い死に方であったことは間違いない。
ゆえに、彼はその光景を幻視する。息が乱れる。せっかく整えた息がまた乱れる。女性に手を上げる。
それがどうしてもできない。
手が震える。明滅する視界の中で、無残な死に方をした女性二人の顔がちらつくのだ。
「このダークセイヴァーにおいては取るに足りないことであるのかもしれないが……」
それでも己は女性に手をあげられない。
しかし、それでも今ダンドは手に槍を持っている。己のトラウマが女性を攻撃出来なくしているのだとしても、それが理由にはならない。
あの幻影の中で見た悲劇。
交わした約束が例え幻相手のものであったのだとしても、己はすでに約束をしたのだ。ならばこそ、ダンドは手の震えを抑え、槍を握る。
力が漲る。
歯が軋むほどに噛み締めた。恐ろしいと思うことと、己が生きてほしいと願った女性の顔が交互に襲う。
されど、今は血塗れの二人の顔よりも、彼女たちが生きた時に見た笑顔のほうが勝る。そして、それは約束に重なるものであった。
構える。飛び出す。足を踏みしめ、大地を蹴る。どうしようもないことだ。己が出来ぬことを今しようとしている。
足が掴まれたように動けない。
「見えているぞ。私には見えている。恐怖に、絶望に震えているな!」
『狩りの女王』の銃口がダンドの眉間を狙う。
引き金が引かれれば、己は敗北するだろう。
未だ降り注ぐ凍えるような夜。
その夜に振る雨は弾丸の雨。冷たき雨に振られながらも、己のトラウマが蘇り、槍を握る手から力を奪うのだとしても。
「ミューズ、ミューズが強ければ強い程、その生命を縮めるぞ?」
笑った。笑ってダンドは言った。
目の前にあるのは己が拳を震えぬ者。
オブリビオンであっても変わりないことである。されど、それでも今は、今だけは交わした約束が勝る。
「穿ち! 貫く!!」
渾身の力を込めた竜騎士の槍が、天杭(テンクイ)の如く投擲される。
その一撃は己のフラッシュバックするトラウマすらも貫き、その一条の一撃は己が生きてほしいと願った女性への思いと共に放たれる。
撃つと決めた。
目の前の狂気ごと穿ち、穿けと念じながら。
放たれた一撃が『狩りの女王』の胴を穿つ。
それは大穴を穿ち、常闇の燎原に閃光となって迸る。ダンドは、膝を屈しない。どれだけ恐ろしいと思い、トラウマに苛まれたとしても、己を今支えるのは、いつかの誰かのための約束なのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
 リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル
…恐怖も絶望も消す事は出来ない。だけど、限りなく無にする事は可能なのよ?
…あるいはこのまま脳内麻薬を過剰投与して狂人になれば、
完全にお前の視界から消える事が出来るかもしれないわね?
…ふふふ、なんてまあ、そこまでする必要も、理由も無いのだけどね
脳内麻薬を操作する肉体改造術式により正の感情を賦活して負の感情の浄化を行い、
敵の索敵から逃れつつUCを発動して戦場全体から魔力を溜め8本の結晶剣を形成
空中機動の早業で結晶剣を乱れ撃ち敵の弱点である光属性攻撃の8連撃を行う
…狩人とは己の六感全てを用いて獲物を追い詰めるもの
目も耳も鼻も閉ざした時点で、最初から終わっていたのよ、狩人としてのお前はね
「……恐怖も絶望も消すことは出来ない。だけど」
リーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は常闇の燎原において、『黒い炎』を目から噴出させる『狩りの女王』に告げる。
胴は穿たれていた。
猟兵達が幻影を振り払う勇気が燈火とするのならば、『狩りの女王』はそれを感じることはできなかったことだろう。
彼女の言葉通り恐怖と絶望は消すことは出来ない。
恐怖無くば危機を感知することはできず、絶望がなければ希望もない。
ゆえに生命である以上、その感情は付き物である。それがない生命など生命としての生存本能すらない何かでしかないのだから。
「……限りなく無にすることは可能なのよ?」
「私の愉悦のための得物が、私の愉悦のためだけに生命は存在しているのだ」
放たれる弾丸が猟犬となって常闇の燎原を駆け抜ける。
その弾丸はともすれば見当違いな方向へと放たれていた。
リーヴァルディの顔にはほほえみすらあったのかもしれない。
「……あるいは、このまま脳内麻薬を過剰投与して狂人になれば、完全にお前の視界から消える事ができるかもしれないわね?」
小さく微笑む。
そこまでする必要などない。理由もない。
今目の前に在る『狩りの女王』は己の存在を感知することができないでいる。銃口を見当違いの方向に向けて銃弾を放っているのが良い証拠だ。
彼女は脳内麻薬を操作する肉体改造術式に寄って正の感情を賦活し、負の感情を押し流す。
『黒いの炎』は絶望や恐怖といった感情を感知する。
その心にひとかけらでも恐怖や絶望があるのならば、それをこそ『狩りの女王』は標として弾丸を放つだろう。
「なぜ、得物がいない。私の得物。私の愉悦。ここにはそれが満ちていたはずだ」
喚く声が聞こえる。
おぞましいと思うだろうか。それとも悲哀そのものであったというべきであろうか。
そのどちらもリーヴァルディは持ち合わせなかった。
あるのは、己の勝利を確信するユーベルコードの煌きだけであった。
「……狩人とは己の肋間全てを用いて獲物を追い詰めるもの」
リーヴァルディの言葉は静かなものであった。
視聴嗅覚全てを失った『狩りの女王』には届かぬ言葉であった。だからこそ、彼女はその名にふさわしくはないのだ。
確かに目から噴出する『黒いの炎』は『狂えるオブリビオン』として強大な力を有することだろう。
けれど、本来の『狩りの女王』の恐ろしさは狩人としての技量。
それらを活かす五感の内3つを失った存在に恐ろしさを、肉体改造によらずともリーヴァルディは感じなかったことだろう。
常闇の空に輝くは、光の精霊結晶剣。
八振りの精霊結晶剣がぐるりと『狩りの女王』を取り囲む。
「……魔力回収、再結晶化。貫け、流星の如く」
吸血鬼狩りの業・星剣の型(カーライル)。それは一瞬の流星のように『狩りの女王』を貫く。
陽光の輝きには届かぬまでも、その流星の如き輝きは『狩りの女王』を射抜くだろう。
「目も耳も、鼻も閉ざした時点で、最初から終わっていたのよ、狩人としてのお前はね」
畏れる似たりうる存在ではない。
そう告げるリーヴァルディの言葉は届かない。
けれど、きらめく流星の如き精霊結晶剣が『狩りの女王』を貫き、大地に縫い付ける。
「……此の地に満ちた幻影の源。それは全てお前のやったこと。ならば、此処で潰えるがいいわ」
光が『狩りの女王』を焼く。
貫かれ、穿たれた傷口から光はその身を内側から焼くように溢れ出し、『狩りの女王』の失墜を知らしめるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー
きみも、狂える者だったか。でも笑えるんだな。それが愉悦からくるものだったとしても、感情があるのは生きている証だとおれは思うよ
おれは無力を思い知った。けれど絶望感や恐怖心は湧いてこない。猟兵だからとか、ダンピールだからとか考えたんだけどさ。結局おれは退屈したくないだけなんだ
……心を躍らせたいのは、きみも一緒だろう!
女王。おれはきみに抵抗しよう。おれはくじを引かないし、贄でもない。けれどきみの目の前に立ちはだかる
邪魔だよな。引き金は引けても標準は合うか? ゼロ距離まで接近すれば弾は当たるだろうな
だがな、おれを封じ込めても。おれは戦えるんだよ
おれは一人じゃない
太陽! カウンターで殴り飛ばせ! おれごと巻き込んでも構わねえ! 全部返すって決めたからな!!
コレは決闘じゃあないんだぜ? 卑怯な手も使うさ
四肢を貫く光の剣が『狩りの女王』の体を大地に縫い止める。
その体の内側から焼く光は、彼女の目から噴出する『黒い炎』すらも焼き尽くさんばかりの勢いであったが、それでも彼女は猟銃を手にする。
狩りこそ己の本質にして愉悦である。
彼女にとって、それだけがあれば良いことであったのだ。
どうしようもないほどに彼女は愉悦ばかりを求めていた。生まれながらの強者であったからでもあるのだろう。
強者は弱者を貪る権利を有する。
弱者に抵抗を許さず、抵抗すらも辞儀と嗤う。
「私は『狩りの女王』。私は私の愉悦のためにこそ存在するはずなのだ」
銃口を向ける先にあったのは、ギヨーム・エペー(Brouillard glacé calme・f20226)であった。
けれど、銃口が定まっていない。
ただ当てずっぽうに銃口を向けているだけに過ぎないのだろう。視聴嗅覚を失っている『狩りの女王』にとって、恐怖や絶望といった感情だけが己の銃口を向ける標的であったから。
それ以外に残った触覚は鋭敏に空気の流れを読み切っているのだろう。
けれど、ギヨームは言葉が届かないと知りながらも告げる。
「きみも、狂える者だったか。でも笑えるんだな。それが愉悦から来るものだったとしても、感情があるのは生きている証だとおれは思うよ」
ギヨームにとって、それだけが生者とそれ以外を分かつものであった。
例え過去の化身であるオブリビオンであったとしても、生きていると言うには十分な資質であったはずだ。
楽しいという感情。
それは愉悦であり、同時に弱者を虐げるものであった。
その幻影を見てきたギヨームにとって、それは己の無力を思い知る光景であったことだろう。
あの村人たちの表情を見た。
泣き叫ぶ母親の涙を見た。
何もわからぬ無垢なまま、死す己の運命すらも理解できない少年の姿を見た。
無力だった。
如何に幻影であったとしても、何も出来ない自分に無力感を覚えた。けれど、絶望や恐怖は胸の内に沸き上がることはなかったのだ。
「これはきっと猟兵だからとか、ダンピールだからとかではないんだな」
ギヨームは色々考えたと呟く。
己を狙っているのか、狙っていないのかわからない銃口がきらめくのを見た。
その銃口にきらめく光はユーベルコードの輝き。ギヨームの瞳にあるユーベルコードの光だ。
「結局おれは退屈したくないだけなんだ」
そう、どこまで言ってもギヨームは変わらない。
凄惨たる悲劇の幻影を見せられたのだとしても、変わらない
だからこそ、変わらずに進むことができる。
己が一歩を踏み出す理由を示すことが出来るのだ。
「……心を踊らせたいのは、きみも一緒だろう!」
抵抗する。
そう、抵抗しか道はない。どれだけ敵が強大な存在なのだとしても、抵抗しよう。
くじを引かない。
選定を是としない。贄でもない。
けれど、『狩りの女王』の銃口の前に己は立つのだ。
「邪魔だよな。引き金は退けても照準は合うか?」
敢えてゼロ距離までギヨームは歩む。
銃口と己の胸板が触れた瞬間、『狩りの女王』は反射的に引き金を引いていた。
だが、弾丸が放たれ、ギヨームの胸板を貫かんとした瞬間、その弾丸ッハ一万度にまで達する魔術の炎によって溶けて無床する。
「――ッ!?」
『狩りの女王』は訝しんだことだろう。
確かに引き金を引いた。
弾丸は放たれた。けれど、手応えがない。それに己の触覚を焼く熱はなんだ。
「だがな、おれを封じ込めても。おれは戦えるんだよ」
なぜならば。
答えは簡単なことだ。
「おれはひとりじゃない」
そう、彼の傍には太陽がいる。己の生まれにはない存在。太陽。その要項の煌きの如き、système solaire lotus(システムソレールロテュス)は魔術の炎でありながら、太陽の輝きを灯す。
放たれた炎はギヨームすら巻き込んでいたのだ。
「構わねぇ! 全部返すって決めたからな!!」
これは決闘じゃない。
正々堂々なんてくそくらえである。どんな手段を講じたとしてもギヨームは『狩りの女王』を滅ぼす。
「熱い、熱い、熱い……! なんだ、この熱さは、此の熱は、これは一体なんだといのだ!」
ヴァンパイアにとっての地獄そのもの。
されど、人にとっては命育む光。
それが太陽である。ゆえに超克へと至ったギヨームの瞳にあるのはユーベルコードの煌きであった。
「わかっていただろう。卑怯な手も使うさ。けれど、それ以上に――この道は、おれ一人のものじゃあない」
この地に満ちる悲哀と恐怖、そして絶望。
それら全てを叩き返すためにこそギヨームはオーバーロードの先へ征く。
ただ只管に、その彼は炎と共に進む。
放たれた拳が『狩りの女王』を殴り飛ばし、その熱でもって満ちる恐怖と絶望を振り払う。
いつかの誰かの恐怖も。
幻影の彼方の幻影も。
全て叩き返す。過去は過去に。幻影は彼方に。
「今はもういない幻影の君たちにこそ」
それは返すべきなのだとギヨームは己の放つ熱を感じながら、拳の傷みを手放さないのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
えぇ、そうですね。
狩りを始めましょう。
ここは狩場で……狩る側は私、獲物はあなたです。
恐怖の感情は常に私の中にある。身を隠すことはできないでしょう。
私は敵を、死を恐れています。「だからこそ」立ち向かうんです。
【ニヴルヘイム】を使用し、周囲半径120mを絶対零度の冷気で覆います。
この領域では全てが凍てつく。100だろうと200だろうと、1000だろうと10000だろうと。一体たりとも届かせはしません。
絶対零度の冷気で猟犬の群れを凍てつかせたなら『スナイパー』の技術で「フィンブルヴェト」からの絶対零度の弾丸での狙撃を。
あなたがどこの誰だろうと……スコープの向こうにいるのは獲物だけです。
穿たれた胴。
四肢を貫く剣によって大地に縫い留められた四肢。
そして身を焼く炎。
猟兵たちのユーベルコードは勇気の燈火と成って『狩りの女王』の体を滅する。
ぐらりと揺れる『狩りの女王』に視聴嗅覚はない。あるのは『黒い炎』が噴出する眼科のみ。
あらゆる恐怖と絶望とを感知する感覚器は、如何なる理屈であったのかはわからない。
されど、手にした猟銃は周囲に撒き散らされるようにして放たれた。
「狩りだ。私は『狩りの女王』。全ては私の獲物だ。私が狩るべき存在なのだ。私が、私の愉悦のためにこそ、設えた狩場だ!」
銃弾が猟犬と成って常闇の燎原を疾走る。
その猟犬たちが疾駆し、目指すのはセルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)であった。
「えぇ、そうですね。狩りを始めましょう」
セルマの瞳は静かなものであった。
そこにあったのは激情でもなければ、恐怖や絶望でもなかった。
けれど、たしかに彼女の胸の内に恐怖は常にあるようであった。己をこれまで抑え込んできた隷属と支配の象徴たるオブリビオン、ヴァンパイア。
その存在を前にして彼女はいつだって恐怖を噛み殺して生きてきたのだろう。
ゆえに、その感情を全て覆うことはできない。
身を隠すことすらできないだろう。猟犬が迫るのが証左であった。
敵を畏れる。
死を恐れる。
確かにそれは恐怖と絶望をセルマにもたらし、『狩りの女王』の標的となるに相応しい獲物たらしめる。
『だからこそ』――彼女は立ち向かうのだ。
「ここは狩場で……狩る側は私、獲物はあなたです」
恐怖と絶望を踏み越えた先にこそ、セルマは在るものを知っている。すでに得ている。
きらめくユーベルコードは疾駆する猟犬たちを絶対零度の冷気でもって凍結させる。
もはや氷の彫像と化した猟犬達に大地を疾駆する力はなく、標的に迫ることは一歩もできないでいた。
これこそが、ニヴルヘイム。
この領域にありてセルマは絶対たる力を有する。
1分39秒のカウントはすでに始まっている。見開かれた瞳は血に染まっていた。
凍てつく猟犬たちの数は意味をなさない。
彼女に近づいた瞬間、あらゆるものが凍結していく。
「冷たい、冷たい……これは、なんだ? 私は何を見ている? そこに恐怖はあるはずだ。そこに絶望はあるはずだ。なのに、なぜ私に歩んでくる?」
『狩りの女王』が喚く。
理解できないおぞましき何かが己に迫っていることを触覚で理解したのだろう。
恐怖も絶望も其処に在る。
けれど、己の獲物として絶たれることがない歩みだけが、『黒い炎』の向こう側から迫っていることを感じ混乱した。
されど、その四肢は大地に縫い留められている。
胴は穿たれ、身を焼く光と炎が彼女の足を後退させることさえ許さない。
「私は女王だ!『狩りの女王』! この狩場の主! 私こそが、この愉悦にふさわしき者のはずだ、なのに!」
なぜ、己に恐怖と絶望が迫っているのかを彼女は理解しない。理解できない。
「あなたがどこの誰だろうと……」
セルマはマスケット銃を構える。
銃口が煌き、絶対零度の弾丸が放たれる。
「……スコープの向こうにいるのは獲物だけです」
静かに告げる。
恐怖も絶望も胸の内にあるものだ。隠すことはできない。それをセルマは最も理解している。
いつかの日も、そうであったように。
恐怖がかじかむ指を絡め取り、絶望が思考を妨げる。けれど、『だからこそ』とセルマは立ち向かい続けた。
その結実が今、此処にある。
放たれた絶対零度の弾丸は狙い過たず『狩りの女王』の頭蓋を割る。
『黒い炎』すら凍りつかせる絶対零度の主は、瞳の端から溢れる血の涙を流しながら暗闇の天を、第四層と第三層を隔てる天井を見やる。
この世界で死す者の終わりは此処ではない。
天井の先にある世界にこそ、彼らは未だ強者の玩具として弄ばれ続けている。
ならばこそ、セルマは恐怖も絶望も抱きながら、前に進むと決め、霧消する『黒い炎』に背をむける。
絶望に咲くは、勇気。
その煌きを持って猟兵達は常闇の燎原を後にするのであった――。
大成功
🔵🔵🔵


 海鶴
海鶴
 儀水・芽亜
儀水・芽亜  ダンド・スフィダンテ
ダンド・スフィダンテ  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  ブラミエ・トゥカーズ
ブラミエ・トゥカーズ  リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル  ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー 
 儀水・芽亜
儀水・芽亜  ブラミエ・トゥカーズ
ブラミエ・トゥカーズ  ダンド・スフィダンテ
ダンド・スフィダンテ  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー  リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル 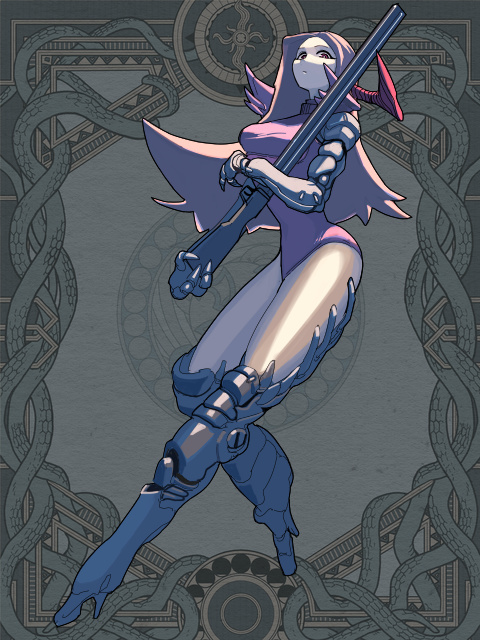
 儀水・芽亜
儀水・芽亜  ブラミエ・トゥカーズ
ブラミエ・トゥカーズ  ダンド・スフィダンテ
ダンド・スフィダンテ  リーヴァルディ・カーライル
リーヴァルディ・カーライル  ギヨーム・エペー
ギヨーム・エペー  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド