ロストアリスの手を引いて
●マーダー・ラビット
「は~い、こっちですよ『アリス御一行様』! 次の国にこそアリスさんの『自分の扉』があればいいですね!」
跳ねるように軽やかな足取りで時計ウサギがウサギ穴の中へとアリスと愉快な仲間たちの先頭を歩き、手招きする。
アリスたちは、そんなに急がなくってもいいよと言ってたけれど、時計ウサギは待ちきれなかった。
今か今かとウズウズワクワクしていたのだ。
彼女たちが本当の事を知ったら、どんな顔をするだろうかと、ずっと思っていたのだ。
「わからないけれど、これ以上大変な思いはしたくないかな。本当にたくさんの冒険をしてきたよね」
アリスが時計ウサギの言葉を横取りするみたいに言った。
そう、たくさんの冒険があった。マグマの花畑。雪が沈む湖。空に浮かんでいく水たまり。どれもこれもが、言葉で表せばそんな単語でしか表現できないけれど、それ以上に筆舌に尽くしがたいものばかりであったのだ。
大変な冒険ばかりだったのだけれど、アリスは笑っていた。
それは泣き笑いのような笑顔であった。
「本当に大変だったけれど。わたし、みんなと冒険できて嬉しかったの。本当よ」
その笑顔は希望に溢れていた。
きっと『自分の扉』を見つければ、深く傷つく原因となった元の世界に戻ってしまう。けれど、彼女ならばきっとだいじょうぶだと、彼女を取り囲む愉快な仲間たちが口々にアリスを元気づけるのだ。
涙が出そうに為るのならば、拭ってあげればいい。
そうやってこれまで彼等はがんばってきたのだ。
だから。
そう、だから此処でお別れの時間だ。
「……どうしてそんなことを言うの? まだ……」
「ええ、まだ『自分の扉』を見つけていない。そして、まだウサギ穴の途中。わかってますよね? ウサギ穴って僕らが先導しないと通れないんですよ。じゃあ逆に――」
「今みたいなウサギ穴のど真ん中で、時計ウサギ居なくなったら、一体どうなるの?」
「おつむの回転は早いですよね、アリスさんは。本当にくるっくる頭だけはいっちょ前なんですから。答えを急ぐのは、アリスさんの悪い癖ですよ。ええ、シンキングタイムを設けるまでもないですよね」
時計ウサギ……いや、猟書家『マーダー・ラビット』は笑っていた。
アリスを助ける一行に時計ウサギとして潜り込んでいたけれど、アリスの頭の回転の早さには舌を巻くことが多かったのもまた事実だ。
だから、なんとしても彼女を貶めたい。
彼女が泣き叫ぶ姿を見たいのだ。助けるはずの『愉快な仲間たち』はいつだって彼女に逆に助けられてきた。
どうしても見たい。
そんな彼女がもっと深く傷ついて涙をするところを。自分に懇願する姿を見たいと願ったのだ。命乞いする姿を見なければ、きっと自分は満足しないだろうし、満足したとしても、きっともっと彼女の悲嘆にくれる姿を求めてしまうだろう。
「とても悪いことが起こるのね」
ああ、その真っ直ぐな視線を歪めたい。
どうしてこんなにも、このアリスは自分の嗜虐心をくすぐるのだろう。ああ、でもどうしても。やっぱり。
見たい。今すぐ殺すことなんてもったいなくて仕方ない。もっともっと美味しく。肉叩きでお肉の繊維を断ち切るように。もっと上質なものに変えてしまいたい。
だから、猟書家『マーダー・ラビット』は狂気に満ちた笑顔のまま告げる。
「はいはい正解。もっと正確に言うなら『骸の海の藻屑と化す』でした~! てなわけでばいばい! きっと穴の出口で待ってるから、出てこれたのならご褒美をくださいね。きっとですよ~!」
楽しみを我慢することがこんなに楽しいだなんて、『マーダー・ラビット』は知らなかったのだ。
きっと彼女はたどり着くだろう。
そのときこそ極上の贄として、自分の喉を甘露で満たしてくれることを確信して、『マーダー・ラビット』は高らかに笑うのだった――。
●ウサギ穴
グリモアベースに集まってきた猟兵たちを迎えたのはナイアルテ・ブーゾヴァ(神月円明・f25860)だった。
「お集まり頂きありがとうございます。今回の事件はアリスラビリンス。猟書家『マーダー・ラビット』によってウサギ穴の途中で置きざりにされた『アリス御一行』を救って頂きたいのです」
ナイアルテは頭を下げ、集まった猟兵達を見やる。
アリスラビリンスは複合世界である。『不思議の国』という小さな世界がウサギ穴によってつながっているのだ。
けれど、そのウサギ穴は時計ウサギが先導しないと通れない。
猟書家『マーダー・ラビット』は何故か時計ウサギの力を持ち、『アリス御一行』をウサギ穴の途中で姿をくらまし、彼女たちを置きざりにするのだ。
「ウサギ穴は不安定になり、時空の絡み合った異世界へと変貌してしまうのです。そうなってしまえば、彼女たちは『骸の海の藻屑』となってしまうでしょう」
その予知をしたナイアルテにとって、それは救わなければならない事態である。
アリス御一行だけではウサギ穴を踏破することはできないし、例え仮に出来たとしてもウサギ穴の出口に待ち受ける『マーダー・ラビット』は彼女たちを殺すだろう。
それを避けなければならない。
「アリス御一行は、アリス適合者や愉快な仲間たち、オウガブラッドなど、アリス適合者のアリスさんが冒険で助けてきた大勢の仲間たちです。それはもうびっくりするくらい大所帯なのです」
アリス適合者のアリスが頭の回転の早い女の子であったからだろうか。
彼女は往く先々で冒険を乗り越え、仲間を増やしていったのだ。猟書家『マーダー・ラビット』が変装し潜り込むことがなければ、『自分の扉』を見つけて元いた世界に戻っていたことだろう。
「ですが、『マーダー・ラビット』に付け狙われたことによって、それは叶うことはないでしょう。『マーダー・ラビット』の狂気の犠牲になってはいけないのです」
どうか彼等を助け、危険な世界となったウサギ穴を脱出し、『マーダー・ラビット』を打倒してほしいのだと、ナイアルテは再び頭を下げる。
テレポートに寄る急行でなければ、きっと間に合わなくなってしまう。
救うべき対象は多い。
けれど、集まった猟兵たちならば余さず救ってくれると信じて、ナイアルテは彼等を見送るのだった――。
 海鶴
海鶴
マスターの海鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回はアリスラビリンスにおける猟書家との戦いになります。猟書家『マーダ・ラビット』が待ち受けるウサギ穴の出口へ、『アリス御一行』を救い脱出するシナリオになります。
※このシナリオは二章構成のシナリオです。
●第一章
冒険です。
複雑に入り組んだ世界は、マグマの花畑や雪が沈む湖、空に浮かび上がっていく水たまりなど、とりとめもなく変化し組み合わさっていく迷宮となっています。
そこにアリス適合者のアリスを含め、彼女御一行のメンバーである大勢の愉快な仲間たちやオウガブラッドがてんでバラバラに離れ離れになっています。
彼等を散らばった状態から、集合させてウサギ穴の出口へと向かわねばなりません。
●第二章
ボス戦です。
大所帯のアリス御一行と共にウサギ穴を脱出すると待ち構えていた猟書家『マーダー・ラビット』との戦いになります。
彼はとても陽気でるんるん気分ですが、アリス適合者であるアリスを殺すことに執着しています。
どうしても殺したいと願っているせいか、常にテンション高めの状態で襲いかかってくるでしょう。
またウサギ穴から共に脱出してきた『アリス御一行』はそこそこの戦力として、それなりに役に立つでしょう。
プレイングボーナス(共通)……アリス御一行にも手伝ってもらう。
それでは、狂気と陽気をかき混ぜたテンションでアリス殺戮に執着する『マーダー・ラビット』からアリス御一行を救う皆さんの物語の一片となれますよう、いっぱいがんばります!
第1章 冒険
『迷子の迷子のおともだち』
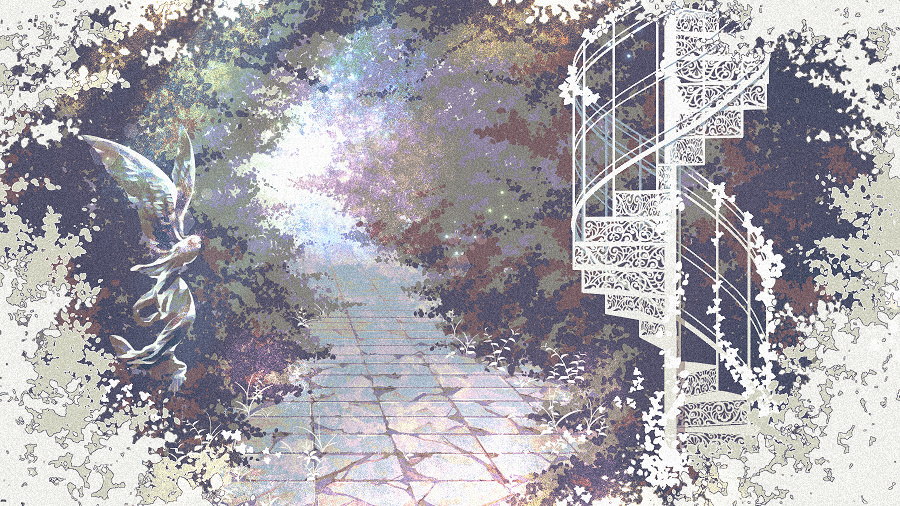
|
POW : 手を引いて連れて行こう
SPD : 障害を先に取り除いていこう
WIZ : こっそりと行き先を示してあげよう
イラスト:真雨 吟
|
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
最初からわかっていたことだけれど、時計ウサギの彼はずっと自分のことを見ていたような気がする。
自意識過剰かしらと思ったけれど、それはどうやら勘違いではなかったようだった。
この世界に放り出された時はどうしようかと涙が出そうだったけれど、それはいつしか楽しい思い出に塗りつぶされていった。
多くの冒険があった。
多くの不思議の国があった。
その度に仲間が増えていった。彼等はいつだって自分と一緒に歩いてくれた。
けれど、時計ウサギの彼はいつの間にか仲間に加わっていたから、気にしてもいなかった。
「あなたも迷子だったのかもしれないわね。その殺意を誰に向けていいのか品定めをしていたのかしら」
アリス適合者のアリスは、歪んだウサギ穴が見せる光景を前に、ぼんやりと立っていた。
あんなに大勢居た仲間たちは散り散りになってしまっていた。
またもう一度はじめから。
積み木を重ねて崩れてしまったことを嘆くのと同じような気持ちだった。それはつまり、大したことではないということだ。
「散り散りになったのなら、もう一度手を繋ぎにいけばいいだけだわ」
そんな風に彼女は気丈に振る舞っていたけれど、やっぱり一人は心細い。
はじめに戻ってしまった。
気弱な私。
自信のない私。
仲間がいないとこんなにも、自分は弱々しいのかと思う。
いつものように笑い飛ばせばいいじゃないかと思ったけれど、一人で笑うのは寂しい。
「こんなに私は弱かったのね――」
アリスは一人、どうしようもなくなって歪むウサギ穴の中で、ついには立ち止まってしまったのだ。
こらえようとしてこらえきれなくなりそうな涙を瞳に貯めて――。
 馬県・義透
馬県・義透
四人で一人の複合型悪霊。生前は戦友。
第三『侵す者』武の天才。最近は破壊神
一人称:わし 豪快古風
武器:黒燭炎
何でわしなんじゃ…とは思うたものの。うむ、たしかに…あの猟書家と程遠い話し方・性格しとるの、わしよな…。
アリスのそばに。助けにきたぞ。
あー、慰めるとか不得意なんじゃが!(騒がしい享年43な人)
だがの、動かねば始まらぬのよ。泣いてもいいが、止まらぬようにな。
黒燭炎の穂先に、炎を灯しつつ。これは、ある種の目印よ。
陰海月も呼んで、さらに目立つようにする。
その方が、仲間を見つけやすく、さらに集まりやすいであろ?
※
陰海月「ぷきゅるるる」
触手の先に炎灯して、目立つ気満々。
いつだってそうだけれど、人は一人で生きていかねばならない時がやってくる。
どれだけ恵まれていても、どれだけ貧しかろうとも。
必ずその時はやって来る。
その時、自分はどんな風になってしまうだろうかと考えた時、『アリス適合者』であるアリスは、きっとどうにかできるかもしれないとさえ思っていたのだ。
孤独には慣れている。
けれど、孤独を知るということは孤独ではないことを知るということであると、知ったのはこの不思議な世界に放り込まれてからだった。
「わたしにはこんなにもたくさんの孤独があったのね」
涙が零れそうに為るけれど、それをしてしまってはいけないと彼女は上を向いていた。
もうあんなに大勢居た愉快な仲間たちはウサギ穴の途中で散り散りになってしまった。大名行列とまでいわれたたくさんの仲間たち。
彼等がいないとこんなにも心細いのだ。
「なんでわしなんじゃ……」
馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)の中の一柱である『侵す者』は、テレポートした後に見つけたアリスの姿にたじろいでいた。
涙を浮かべる少女をどう慰めていいかわからない。
享年四十三歳とは言え、苦手なものは苦手なのだ。あの猟書家『マーダー・ラビット』とは程遠い話し方をする者といえば、確かに己であるのだが、どうにも不得意なのだ。
「あー」
なんと言っていいか。
「助けにきてくれたのでしょう? おじ様」
くるっと頭の回転の早いアリスは、『侵す者』の姿を認めて微笑んだ。あれだけ涙を浮かべていた瞳は、けれどすぐには涙が引くものではなかったけれど、一人ではないという事実が彼女を救う。
慰めるのとか不得意であるという自負があったが、慰める必要すらなかったのかもしれない。
「ああ。だがの、動かねば始まらぬのよ。泣いてもいいが、止まらぬようにな」
「泣いてなんかないわ。失礼ね、おじ様」
などと腕をぽかりと叩くアリスに『侵す者』はどうにも調子が狂う。
けれど、泣きわめかれたりしないだけ十分だった。
「ならば、まずは」
その瞳がユーベルコードに輝く。
彼の手にした黒色の槍の穂先が、それは火のように(シンリャクスルコトヒノゴトク)赤く燃える。
「目印のつもりなのね。篝火はみんなの目に止まるかしら?」
「一々先回りするの……ああ、その通り。さらに――」
『ぷきゅるるる』
奇妙な鳴き声と共に大きなミズクラゲが『侵す者』の影から飛び出す。
その姿は篝火にゆらゆらと揺れる不思議な道標となって不安定なウサギ穴の空間に輝くだろう。
「おじ様、この子のお名前は?」
アリスが目をキラキラさせながら、となりで揺れるミズクラゲの姿を見上げている。やはり女子にはこういうマスコット的なものが受けがいいのだろうかなどと考えながら、『侵す者』はさっきからおじ様と呼ばれているのが、微妙に気になっていたことだろう。
きっと彼女はこんなふうに愉快な仲間たちを引き連れて、不思議の国を旅していたのだろう。
たくさんの仲間達が彼女を助けたり、助けられたりしていた事実が彼女を此処まで成長させたのだ。
「陰海月と言う。これでさらに目立つだろう。仲間が見つけやすく、さらに集まりやすいであろ?」
「ええ、とても良いアイデアだわ。ふふ、お優しいおじ様、ありがとう」
アリスは笑顔のまま『陰海月』のふわふわ揺れるように空に浮かぶ姿を見つめ、まるで迷子の少女が風船を手にして親が来るのを待つように、けれど、どこにも不安げな顔などないというように微笑み続けるのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 神代・凶津
神代・凶津
一度手を繋ぎにいけばいい、ねぇ。
言うじゃねえか、アリスの嬢ちゃん。気に入ったぜッ!
あ、俺達?俺達は猟兵。まあ、正義の味方的なもんだよ。
「・・・貴女と貴女の仲間達を助けに来ました。」
先ずは散り散りになった嬢ちゃんの仲間達を見付けねえとな。任せたぜ、相棒。
「・・・式、召喚【捜し鼠】
コイツらをウサギ穴に放って嬢ちゃんの仲間達を捜索するぜ。
『式神【ヤタ】』で行き先を偵察して危険がないか確認して移動だぜ。
危険があったらアリスの嬢ちゃんを『結界霊符』で護りながら移動だ。
さあ、もう一度仲間達と手を繋いでクソウサギの鼻を明かしてやろうぜ。
【技能・式神使い、情報収集、偵察、結界術、手をつなぐ】
【アドリブ歓迎】
『もう一度手をつなぎにいけばいい、ねぇ……』
赤い鬼面がカタカタと揺れる。
ヒーローマスクである、神代・凶津(謎の仮面と旅する巫女・f11808)は、『アリス適合者』であるアリスの言葉に震えていた。
バラバラになってしまった仲間たち。
一人は心細いと涙をこらえる姿は健気であったし、もう一度と諦めない心はオウガであれ、オブリビオンであれ、きっと砕けぬ尊いものであったことだろう。
『言うじゃねえか、アリスの嬢ちゃん。気に入ったぜッ!』
凶津は昂ぶる正義の心と共にウサギ穴へとテレポートし、アリスの元に参じた猟兵の一人だった。
相棒である少女、桜と共にアリスの傍に降り立つ二人はまっすぐに彼女を見据える。
「……貴女と貴女の仲間たちを助けに来ました」
「まあ、正義の味方さんなのね。心強いわ。こんな素敵な方々がいらっしゃるなんて。きれいなお召し物。きっと名のある神官さんに違いないわ。ありがとう」
先程までの涙をこらえていた顔は、もう笑顔になっていた。
凶津は名乗る手間が省けたことを驚きつつも、全て先回りするように、こちらの言葉を奪うアリスの頭の回転の早さと順応性に舌を巻く。
なるほど、とも思うのだ。
これが彼女の強さであり、元いた世界で傷ついた要因なのだろう。
ともすれば、これはコミュニティにおいては異物として扱われても仕方のない才能であったのかもしれない。
けれど、それでも彼女は人間なのだ。
心無い言葉をいわれれば傷つく。当たり前のことだ。
『先ずは――』
「散り散りになった私の仲間たちを見つけてくださるのでしょう?」
『ああ、そうだ。だから、任せたぜ、相棒ッ!』
凶津の言葉と共に桜の瞳が輝く。
「・・・式、召喚【捜し鼠】」
桜の掌から式神【捜し鼠】(シキガミ・サガシネズミ)たちがあふれるようにしてウサギ穴へと駆け出していく。
その光景にアリスは驚いたようであるが、興味津々に桜の手元に食い入るように見つめるのだ。
「神官様、それってどういう理屈なの? 不思議だわ」
なんとも人懐っこい上に、なんでも聞きたがるアリスに桜はたどたどしくだけれど、丁寧に説明していく。
そんな彼女たちのやり取りをみやりながら、凶津は式神『ヤタ』を先行させ、不安定になっているウサギ穴を進む。
偵察で危険がないかを調べると同時に『探し鼠』たちが次々と散り散りになっていた愉快な仲間たちを捜索し、連れてくるのだ。
再会を喜ぶアリスと愉快な仲間たちの姿。
徐々にアリスの瞳に光が宿っていくのを見ただろう。あれだけ気丈に振る舞っていても、やはり少女である。
仲間たちとの再会を喜ぶ姿は、それだけで心温まる光景であった。
だからこそ、猟書家『マーダー・ラビット』を許してはおけないのだ。
凶津は燃え上がる己の正義の心と共に意気揚々と宣言する。
『さあ、もう一度仲間たちと手を繋いで、クソウサギの鼻を明かしてやろうぜッ!』
その言葉にアリスと愉快な仲間たちは両手を繋いで、行進のようにウサギ穴を進む。
マグマの花畑も、雪が沈む湖も。
どんな場所だって、どんなときだって、仲間が隣にいるのならば心強いものだ。
涙も枯れ果てるのではなく、いつしか雲に為るように上って行って。
花咲かす慈雨となって降り注ぐように。
歪なウサギ穴に朗らかな陽気を呼び込むのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 菫宮・理緒
菫宮・理緒
なかなか気丈なアリスさんだね。
これはなんとしても愛で……助けないと!
アリスさんに会えたら、
「がんばったねー! もうだいじょうぶだよっ」
と、声をかけて、いけそうなら頭を撫でてあげたいな。
落ち着いたと感じたら、ブルーノワールにご挨拶させてて、、
いっしょに遊んでもらって、元気を取り戻してもらおう。
「この子もけっこうかわいいでしょー♪」
そういいながら【E.C.O.M.S】を展開。
12機編成で40組作ったら、捜索に向かわせるね。
お友達を見つけたら、編隊運動でに、ALICE、とサインを送って、
アリスさんの仲間であることを伝えて、
援護しながら、こちらまで誘導しよう。
「元気にみんなをお出迎えしようねっ」
散り散りになっていた愉快な仲間たちは猟兵の活躍に寄って徐々に集まり始めていた。
けれど、それは全てのアリスの仲間たちが戻ったということではない。
彼女の仲間たちはあまりにも多い。
それほどまでに多くの冒険と不思議の国を渡り歩いてきたのだろう。だから、まだ全員ではない。
猟兵もアリスも、その愉快な仲間たちもみんなみんなこういうときには欲張りなのだ。
誰かと誰かを選んで助けることなんてできない。
「そうよね。やっぱりみんないっしょがいいわ。私も、みんなももっと欲張っていいと思うの。何一つ失う理由なんてないって、胸を張っていいのだわ」
そんな風に『アリス適合者』のアリスが言う。
彼女の言葉は徐々に自信に溢れたものに変わってきていた。
やはり仲間が戻ってくることは、彼女にとってかけがえのないことなのだろう。
「なかなか気丈なアリスさんだね。これはなんとしても愛で……助けないと!」
若干、雑念が漏れたような気がするが、菫宮・理緒(バーチャルダイバー・f06437)はウサギ穴の途中でアリスたちと合流する。
すでに多くの仲間たちが猟兵によって発見され、見つけ出されているがまだ全てではないことをしって微笑んだ。
「がんばったねー! もう大丈夫だよっ!」
「ありがとう。素敵なお姉さん。私ががんばったんじゃないわ。みんなが、がんばってくれたのよ」。あら、頭を撫でてくださるの? 嬉しいわ」
そんな風に先回りされてしまう。
えっ、いいの!? と理緒はわりかし驚きながらも特に躊躇うことなくアリスの頭を撫でるのだ。
こんなすんなり撫でさせて貰うことができるとは思わなかったのだけれど、彼女の回る頭は今日も絶好調なのである。
「あら、かわいい子。お姉さんのお友達かしら?」
翼の生えた黒兎の精霊が蠱惑の瞳を輝かせながら、理緒とアリスの周囲を飛ぶ。
おいでおいでという風にアリスが手招きすると、ブルーノワールと呼ばれた黒兎が彼女の腕の中に収まる。
小動物と少女のやり取りはとても微笑ましいものである。
「この子も結構……」
「いいえ、とてもかわいいわ。素敵なお友達ね」
また先回りされていわれてしまった。けれど、彼女が徐々に落ち着きを取り戻してきているのは素直に喜ばしいことだ。
猟書家『マーダー・ラビット』の目論見は、この時点で半分は防がれたと言ってもいいだろう。
「お姉さん、何をしていらっしゃるの? きれいな形……それで私の仲間を探してくださるのね」
「そうそう、だから元気にみんなをお出迎えしようね」
理緒の瞳がユーベルコードに輝く。
E.C.O.M.S(イーシーオーエムエス)によって召喚された正八角形のユニットたちが無数に飛ぶ。
編隊を組んでウサギ穴の中を探索し、アリスの仲間を見つけたらサインを送るように理緒がプログラムで指示を出しているのだ。
「作戦行動、開始! 発見次第、『ALICE』ってサインを出しているからね。援護しながら誘導してもらうんだよー」
「とっても難しそうなことをしていらっしゃるのね。けれど、ありがとう。とても心強いわ」
次々と理緒の操るヘッドセットとゴーグルにサインが投じられていく。
その反応はまだまだ増えていく。
彼女の仲間を見つけ、こちらに誘導していくのだ。ウサギ穴は未だ不安定だけれど、それでもアリスの仲間たちは再び戻ってくる。
きっとそれは彼女の微笑みを深くするであろうし、同時に愉快な仲間たちの笑顔にも繋がる。
これまでそうやってみんなで冒険を乗り越えてきたのだろう。
理緒はそんな彼女たちを微笑ましげに見つめながら、そして、理緒もまたアリスの仲間だというように手を伸ばすアリスの手を取るのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 遥・瞬雷
遥・瞬雷
年若いけど、幾多の冒険を乗り越えてきた知恵と胆力は本物だねぇ。一廉の人物と見るよ。
拱手と共に挨拶。「道士瞬雷と申します。貴女様のお力となるべく馳せ参じました。」
敬意をもって接する。
アリスの手を握る。
「卜占の秘術を用います。お仲間の方々の事を思い浮かべ下さい。」
【情報収集】を補佐する宝貝「央華飾」に手を添え目を閉じる。【仙術】による【失せ物探し】。
『我、時と空の理以て知らざるを知る…』
蕾が花啓く様に意識が拡大。彼女の記憶と合致する存在の位置を把握。
「…捉えました。さぁ、参りましょう」
不安定化した空間。だけど世の理を知り不可を可とするが仙術。
宝貝「八卦盤」にてウサギ穴の地流を識り仲間の元へ向かう。
『アリス適合者』のアリスの姿は少女そのものであった。
年若いという印象を受けるのもまた無理なからぬことであったが、彼女の頭の回転の早さは猟書家『マーダー・ラビット』も認める所のものであった。
それは集団というコミュニティにおいては……いや、時代という流れの中では、異物として捉えられる才能であったのかもしれない。
端的に言えば、生まれる時代を間違えた存在であるとも言える。
けれど、遥・瞬雷(瞬雷女仙・f32937)にとっては関係のない話であった。女仙である彼女にとって、彼女の瞳が捉える本質こそが瞬雷にとっての真実である。
「年若いけど、幾多の冒険を乗り越えてきた知恵と譚力は本物だねぇ」
一廉の人物と言っていい。
アリスをそう評価した瞬雷は、右拳を左手で包む封神武侠界の礼儀作法である拱手でもって、彼女に相対する。
見慣れぬ挨拶にアリスは面食らうことなく、瞬雷と同じように拱手を真似して一礼をするのだ。
その所作は美しいものであり、瞬雷は己の感じたことの正しさを実感するのだ。
「道士瞬雷と申します。貴女様のお力となるべく馳せ参じました」
彼女の言葉には敬意がにじみ出ていた。
戦乱を生き抜いた女傑であるが、仙術を学ぶ彼女の齢と外見はかけ離れたものであろう。彼女自身が仙人としては若輩であるという自覚はあれど、アリスは微笑んで言う。
「ありがとう、素敵な方。はじめて聞くお名前の響き、とても素敵だわ。しゅんれい、うまく言えなくってごめんなさい。けれど、助けにきてくれたこと、とても嬉しいわ」
瞬雷がアリスの手を取るよりも早く、アリスは彼女の手を取った。
先回りする頭の回転の早さは、瞬雷の意図を即座に汲み取ったのだ。
「しゅんれい、は易者様なのね。どうぞお願いするわ。私の仲間のことを」
「ええ、卜占の秘術を用います。お仲間の方々の事を思い浮かべ下さい」
瞬雷は髪に指した花型の髪飾りに触れ、その宝貝『央華飾』の力を発言させる。彼女とアリスの瞳が閉じられ、お互いの皮膚を介して頭に思い浮かべた仲間たちの姿をウサギ穴から探し出すのだ。
「我、時と空の理以て知らざるを知る……」
それは蕾が花開くように意識を拡大させていく。
流れ込んでくる膨大な記憶。
彼女が仲間たちとともに踏破した不思議の国の情景、出会って一緒に行こうと手を取った仲間たちの姿がウサギ穴に広がっていく。
不安定な空間となってしまったウサギ穴であるが、アリスの記憶と合致する姿がところどころに見受けられる。
「これが仙術というのね。すごいわ。こんなにも簡単に不可能を可能にするなんて! しゅんれいは、本当にすごい易者さんなのね! でもでも、もっとすごいことができるのよね?」
「ええ、これぞ宝貝『八卦盤』、吉兆を占い、周囲の魔力の流れや状態を探ることができるのです」
「じゃあ、これを辿っていけば……」
その通りだと瞬雷は微笑む。
はしゃぐように跳ねるアリスの姿を見れば、それが年相応の少女としての仕草であるとわかるだろう。
ウサギ穴の地流を識った瞬雷は、あちらです、と宝貝『八卦盤』が示す道を指差す。
けれど、アリスはそんな彼女の指を掴んで微笑むのだ。
「ありがとう、素敵な仙女さま。でもどうか、ご一緒してくださらない? 私、手をつなぐことがとても素敵なことだって思うの」
だから、と瞬雷と手をつなぎたいのだと屈託なく微笑む彼女に瞬雷は何を思っただろうか。
彼女よりも長き時を生きる自分に向ける笑顔はまるで鏡のようだった。
自分が彼女に敬意を以て相対するように、彼女もまた敬意と厚意を以て手を繋ぐ。
それは、彼女が生まれた時代を間違えたのではなく、きっとこれまでの冒険で得た傷ではなく練磨の結果であるのだと、瞬雷は知るのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
アリス適合者の嘆く顔を見るため、すぐに殺害することはせず弄ぶ……
趣味の悪さは吸血鬼といい勝負ですね。
アリスさんの方へは他の猟兵が向かったようですし、私は彼女の仲間たちを探しましょうか。
こういった場所を探索するのは適任でしょうしね。
マグマの花畑を集中的に捜索します。
【シェイプ・オブ・フリーズ】を使用し、戦場に氷雨を降らせてマグマを凍らせている間に捜索を行います。
寒すぎてもアリスさんの仲間達にとって良くないでしょうが、元々の地形と合わせれば寒くなりすぎることはないでしょう。
持ち前の『視力』でアリスさんの仲間の痕跡を辿り、仲間を見つけたら一緒にアリスさんの方へ向かいます。
時計ウサギの先導がなくなったウサギ穴は不安定極まりない世界へと変わってしまっていた。
マグマの花畑はうねり狂い、花弁が火の粉のように飛び交う危険地帯へと成り果てた。『アリス適合者』であるアリスたち一行が冒険した時よりも、ずっとマグマの勢いが酷いものとなっていた。
これではどうしようもない。
こんな場所に散り散りになってしまったアリスの仲間たちは無事であろうかと、セルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)は思わないでもなかったが、彼女にとってマグマの花畑は脅威ではなかっただろう。
「アリス適合者の嘆く顔を見るため、すぐに殺害することはせず弄ぶ……」
猟書家『マーダー・ラビット』の思惑。
それは狂気ともいえる彼の欲望を叶えるためだけのものであった。
『アリス適合者』のアリスの悲嘆にくれる顔が見たい。
ひどく傷ついた顔が見たい。
もっとひどい目に合わせてやりたい。
その思いは悪辣の一言で片付けるには、あまりにも人で無しであった。
「趣味の悪さは吸血鬼といい勝負ですね」
セルマはため息をつく。
彼女の吐き出す息はマグマの花畑にあって、なお白いものであった。うだるような熱さであったとしても、彼女の瞳にユーベルコードが輝く限り、マグマの花畑は彼女の園であった。
「ここは、私の領域です――シェイプ・オブ・フリーズ」
触れたものを凍り付かせる氷雨がセルマのユーベルコードと共に降りしきり、マグマの花畑は瞬時に氷の花園へと変わる。
極寒とも言うべき冷気がマグマの花畑を襲うが、マグマによって膨張した空気が冷やされ、ちょうどよい気温に変わっていく。
彼女はアリスの方へと向かうよりも早く、彼女の仲間を探すことを優先していた。
あれだけ荒れ狂っていたマグマが鳴りを潜め、ひょこひょことアリスの仲間であろう愉快な仲間たちが顔を出し始める。
「よかった。流石に寒くなりすぎることはないかと思っていましたが……」
セルマは彼女の素晴らしい視力でもって仲間たちの痕跡を次々と発見し、辿っていく。
その道程で仲間たちを引き連れる姿は、まるでアリスの再来のようでもあったし、仲間たちは散り散りになったアリスの仲間たちを次々と磁石のように引き寄せていくのだ。
「ありがとう、アリスではないけれど、アリスみたいな行動力の化身のお姉さん」
愉快な仲間たちが、その不思議な姿を踊らせるようにしながら、セルマの周囲でお辞儀をする。
彼等を一人として失うことは、『アリス適合者』のアリスにとって痛烈な痛手であろう。
欠けることなく彼等を救えたことは大きい。
「いいえ。礼には及びません。まだまだ皆さんの仲間は多いのですから。さあ、次の仲間たちを見つけましょう。そうしたのなら、アリスさんのところへ向かいましょう」
きっと彼女は喜んでくれるだろう。
猟書家『マーダー・ラビット』がどれだけ悪辣なる罠を仕掛けていたのだとしても、彼女の心は折れることはない。
「ああ、アリス。アリスだ! よかった、もう会えないのかもしれないとばかり思っていたから!」
喜ぶ彼等の声が聞こえる。そう、これはまたもう一度出会うための、そして再起を願う戦いだ。
何故なら、此処には猟兵がいるから。
そして、何よりも彼女に助けられ、彼女を助ける仲間たちが大勢、それも大名行列のように列をなしているのだから――。
大成功
🔵🔵🔵
 マグダレナ・クールー
マグダレナ・クールー
アリス。眩しいアリス。眩しいアリスのお仲間も、きっと輝かしいのでしょう
何処ですか。何処にいますか? 目を刺すほどに眩む光を辿れば、居ませんか
リィー、リィーは居ますか?
《マイゴニ? デイスイニ? ……ヨッパライカ!》
ええ、酔っていますから手を繋ぎましょう。コレでもっと感覚が共有されます。視界も、ええ。不浄な現実が、……ですが、見ないと。見落として、探せません。から
《ヨッパライニ。オヒヤヒヤ》
アリスを探しましょう。仲間たちを求め、集わせるのです。誰一人、欠ける事なく。皆で、皆で此処から抜け出すのです
ええ、勿論。兎の羽音に耳を傾け、兎の血肉を嗅ぎ求めてながら
先の事も、わたしはちゃんと考られていますよ
その瞳を刺すようなまばゆい輝きを感じて、マグダレナ・クールー(マジカルメンタルルサンチマン・f21320)はウサギ穴の中へと降り立った。
彼女の視界はすでにオウガ、『リィー・アル』に与えている。
それゆえに彼女の視界は色彩とピントが狂ったものであったが、それでもまばゆい輝きを放つ『アリス適合者』であるアリスの持つ光は一層強く貫いてくるのだ。
「アリス。眩しいアリス。眩しいアリスのお仲間も、きっと輝かしいのでしょう」
何処にいるのだろうか。
マグダレナは狂った視界の中、アリスと同じ輝きを放つ彼女の仲間を探し出すべく、不安定な世界、ウサギ穴の中を疾走る。
雪が沈む湖も、空に浮かぶ水たまりも、全てがアリスの嘗ての冒険であったことだろ。
それらが一斉に重なり合い、歪み、複雑怪奇なる迷路のようにマグダレナを阻む。
けれど、彼女にとってそれは問題ではなかったのだ。
「目を刺す程に眩む光を辿れば、居ませんか? 何処に、何処にいらっしゃいますか? 出ておいでなさい。何も心配することはありません。必ずわたくしが皆様を眩いアリスのもとへとお連れしましょう」
彼女の瞳はユーベルコードに輝く。
冥冥デカダンス(シーミンフゥーディエ)と名付けられたユーベルコードによって彼女の視界を得たオウガ『リィー・アル』が現れる。
「リィー、リィーは居ますか?」
『マイゴニ? デイスイニ? ……ヨッパライカ!』
その言葉にマグダレナは頭を横に降った。
この視界は彼女の視界ではない。
けれど、脳は正しく理解をしている。歪んだ世界であっても、歪められた世界であっても、たった一つ変わらぬものがある。
眩いアリスの輝きこそが、彼女の感覚を酔わせるのだ。
「ええ、酔っていますから手をつなぎましょう」
かつて、『アリス適合者』のアリスがそうしたように。
手を繋げば、それだけでいいのだ。別に不思議な力が湧き上がってくるわけではない。けれど、肌と肌とがつながれば、共有できるものがある。
きっとあの眩いアリスもそうしてきたのだ。
それがマグダレナには理解できる。
「コレでもっと感覚が共有されます。視界も、ええ。不浄な現実が」
けれど、見なければならないのだ。
アリスを助けるためには、その仲間たちを余さず救うためには。
見なければならない。
「ええ、見落として、探せません。から」
『ヨッパライニ。オヒヤヒヤ』
『リィー・アル』の戸惑いが肌から伝わってくる。
けれど、関係ない。そんなことは関係ないのだ。アリスを、そして仲間たちを探すのだ。
彼等を集わせ、誰一人欠けることなく。
「此処から抜け出すのです。ええ、もちろん。兎の羽音に耳を傾け、兎の血肉を嗅ぎ求めながら」
二人は歪む世界を走った。
くらくらと頭が揺れるようであったが、その瞳はユーベルコードに輝きながら、それに負けぬ輝きを見つめて走るのだ。
多くの愉快な仲間たちがった。その姿は誰一人として同じものはなく。けれど、輝きに満ちていた。
一層大きな光がマグダレナの前に現れる。
ああ、と自分が探していたのはこれであると感じることができるほどの明るさを持つ輝き。けれど、目を刺す輝きは不快ではなくて。
「ああ、なんてこと。ありがとうございます、聖女様。こんなに私の仲間を助けてきてくださるなんて」
「あなたがアリス。眩いアリス。輝きに紛れて視えなくてもわかりますよ。ええ、わたくしは」
「ちゃんと先のことも考えておられるのね。素晴らしいことだわ、きっと貴女は名のある聖女様。どうかお名前を教えてくださらない?」
アリスの言葉はマグダレナの言葉を全て先回りするものであったけれど、それでも不思議と不快感はない。
彼女の名前を求めるアリスの言葉に、マグダレナはどう応えただろうか――。
大成功
🔵🔵🔵
 ルクス・アルブス
ルクス・アルブス
フィア師匠と
「え?師匠、ぶっぱダッシュ以外の作戦あったんですか!?
っていうか、師匠って絶対勇者側じゃないですよね?」
最後まで聞いてください-!?
最終回手前に改心して、
敵を足止めしつつ相打ちになるむーぶですから!
ですから杖をしまってください-!?
それではわたしたちは迷路の出口で、
アリスさんのお友達を迎えればいいんですね。
お任せください師匠!
わたしの全力お見せしますよ-!
魔法少女に変身すると【ユーフォニアム】を構えて、
【協奏曲第1番】を演奏します。
「むぅむふ、むふむうむむむむうむふ!」
(どうです、わたしの実力のほど)
導きの演奏(不協和音)で、癒やしまで。
弟子の成長に師匠もびっくりですよね(どやぁ)
 フィア・シュヴァルツ
フィア・シュヴァルツ
弟子のルクスと
「ほほう、大勢の仲間を集めるカリスマのある少女か。
まさにそれは勇者の資質と言えるだろう。
ならば、ここは大魔法使いである我が、勇者を導く役割を担うとしようか!
って、ルクスよ、誰が悪の魔法使いだ!」(杖でぐりぐり
さて、ばらばらになった仲間に変幻自在な迷宮、か。
ならば我はこの世界の安定化を担当しよう。
【極寒地獄】の魔法で複雑に入り組んだ世界を凍結。
氷の迷宮だが、マグマや湖などよりはマシだろう。
「さあ、ルクス、あとはお前の実力を見せてみよ!」
楽器を構える弟子を見て、両耳を塞いで防御体勢をとるが……
その程度で防げるものではなかったか。
(不協和音で回復という貴重な体験をしながら)
カリスマとは如何なるものであったことだろうか。
人を引きつける魅力を持つ者であるのならば、何を持って人を惹きつけるのだろうか。
その答えは人によって異なるものであったことだろうが、『アリス適合者』であるアリスにとっては、なんてことのないものであった。
相手の言葉を先取りする頭の回転の早さ。
それは時代に寄っては傑物となり得る才能であったかもしれないが、閉鎖的なコミュニティにおいては異物でしかない。
だからこそ、異世界である不思議の国において、彼女の才能はカリスマとして開花したのだろう。
「ほほう、大勢の仲間を集めるカリスマのある少女か。まさにそれは勇者の資質と言えるだろう。ならば、ここは大魔法使いである我が、勇者を導く役割を担うとしようか!」
フィア・シュヴァルツ(漆黒の魔女・f31665)は、アリスの資質をそう評価していた。
それは類稀なるものであり、フィアにとって尊ぶべきものであったことだろう。
しかし、彼女の弟子であるルクス・アルブス(魔女に憧れる魔法少女・f32689)は、どちらかというと『悪の魔法使い』であるという認識のほうが強かった。
むしろ、デビルキングワールドにおいては、ハイセンスな二つ名であるのだが、フィアは残念ながらお気に召さなかったようだ。
杖でぐりぐりルクスを小突きながら、やめてくださいよーとぼやくのだ。
「さて、ばらばらになった仲間に変幻自在な迷宮か」
フィアはうなずく。
このウサギ穴は時計ウサギがいなくなったことで、不安定化し、いずれは『骸の海の藻屑』となってしまう。
それまでアリスの仲間たちを全て助け出し、ウサギ穴の出口へと脱出しなければならないのだ。
「ならば、我はこの世界の安定化を担当しよう」
「え? 師匠、ぶっぱダッシュ以外の作戦あったんですか!? ていうか、師匠って絶対勇者側じゃないですよね?」
ごりごりとルクスに振るわれる再びの杖。
余計なこと言うから……というのは野暮であろう。
「ほうほう、ならばルクスよお前は一体なんの役割を持つのだ?」
「え、それは最終回手前に改心して、敵を足止めしつつ相打ちになるむーぶです? ですから杖をしまってくださいー!?」
「うるさいのぉ。黙って師匠の手並みを見ているがいい。――我が魔力により、この世界に顕現せよ、極寒の地獄よ」
フィアのユーベルコードが詠唱を紡ぎ、その力を不安定なウサギ穴の世界に顕現させていく。
それは内部にいるものを徐々に凍りつかせる氷壁で出来た迷路――極寒地獄(コキュートス)である。
あらゆる情景が重なったような不安定なウサギ穴をフィアの魔術によって、すべて均一に、それこそ全てを塗りつぶして安定化させるのだ。
氷の迷宮だろうが、マグマや湖よりもマシだろう。
「さあ、ルクス、あとはお前の実力を見せてみよ!」
「お任せください師匠! わたしの全力お見せしますよー!」
キラキラと光り輝いて魔法少女の姿へと変身するルクス。手にしたユーフォニアム『ベッソン』に魔力が込められていく。
彼女が奏でるのは、協奏曲第1番(キョウソウキョクイチバン)。
「むぅむむむむむ、むむむむむー!」
壮麗なる音色が迷宮に響き渡るわけではない。師匠であるフィアが両耳を防いで防御態勢を取っていることが、事の重大さを物語っている。
「むぅむふ、むふむうむむむむうむふ!」
特別翻訳:(どうです、わたしの実力のほど)
ルクスがどやっとした顔でフィアを見やるが、肝心のフィアは耳をふさいで目をつむっている。
そう、ルクスの奏でる不協和音に対抗しようとしているのだが、その程度で防げるルクスの演奏ではない。
両手を突き抜けて骨伝導の如く頭に鳴り響く不協和音。
けれど、その音は不協和音故にはるか遠くまで響き、ふらふらになりながら次々とアリスの仲間たちがウサギ穴のあちこちから集まってくるのだ。
不思議なことに、不協和音でどうにも不快なのに、何故か回復しているのだ。
「どういうことなんじゃ。こんな魔法あるのか……?」
フィアは訝しむ。普通、音楽で癒やされるというのなら、美麗な音色でとか、そんな話であるはずなのだ。
けれど、ルクスのユーベルコードは、そんなことさえ超越する。
導きの演奏、とドヤァっとしているルクスの顔が若干気に食わないが、癒やされていることは事実なので、なんとも否定し難い。
「むむむふ! 弟子の成長に師匠もびっくりですよね!」
胸を張ってドヤ顔を続けるルクス。
確かに彼女の活躍でアリスの仲間たちを導くことはできた。けれど、なんとも釈然としないものをフィアは感じ、けれど、余計なことはいわないでおこうと、演奏の感想を胸に秘めるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 佐伯・晶
佐伯・晶
なんか歪んだ嗜好だなぁ
思い通りにさせたくないから
皆と協力して散らばった仲間達を探すよ
骸の海の藻屑と化すなんて美しくないですの
私も協力しますの
不安定になっている空間を固定して道を維持して差し上げますの
こっちの嗜好も負けず劣らずだけど
主義に沿ってるから信用しても良いか
…なんか可愛い愉快な仲間とかオウガブラッドとかばかり
見つけてきてる気がするけど
力持ちとかはこっちで探そうか
早くアリスと合流して安心させてあげないとね
名も知らぬアリス様
仲間の方々を連れてきて差し上げましたの
もし仲間達とずっと一緒にいたいと思ったら仰って下さいまし
私が永遠にして差し上げますの
まあ、程々に聞き流して
無理強いはしないと思うから
猟書家『マーダー・ラビット』が『アリス適合者』のアリスを付け狙う理由は単純であった。
歪んではいたけれど、簡単なことなのだ。
己の狂気が表す殺意を誰に向けようかと選り好みしていただけなのだ。
どうすれば己の殺意が最も満たされるのか。
どうすれば自分が気持ちよくなれるのか。ただそれだけを追求しただけに過ぎないのだ。
「なんか歪んだ嗜好だなぁ。思い通りにはさせたくないって思ってしまうよ」
もとより、オブリビオンと猟兵という間柄である。
『マーダー・ラビット』の嗜好以前に許しておけるものではないと、佐伯・晶(邪神(仮)・f19507)は歪むウサギ穴へと降り立った。
「他のみんなも順調に仲間たちを見つけているようだね。協力して僕も仲間たちを探すとしよう」
「骸の海の藻屑と化すなんて美しくないですの。私も協力しますの」
晶の体の内側から邪神の分霊が顕現する。
邪神の恩返し(ガッデス・リペイメント)というわけではないだろう。きっと彼女なりの価値観でもって、今現れたのだ。
まあ、なんとなく察することができるのもまた、彼女との付き合いが長いせいだろう。
「不安定になっている空間を固定して道を維持して差し上げますの」
固定と停滞と権能とする邪神の力によって不安定だったウサギ穴の道が一本道へと固定されていく。
長くは保たないだろうが、残されたアリスの仲間たちを見つけ出し、ウサギ穴の出口まで導くのには十分な時間だった。
「こっちの嗜好も負けず劣らずだけど、主義に沿ってるから信用しても良いか……って、なんか……」
晶は邪神の分霊が見つけ出してくる仲間たちの容姿が偏っていることに気がつく。
そう、かわいい愉快な仲間たちや、オウガブラッドばかりを見つけてきているような気がするのだ。
力持ちとかそういう類の仲間は見つけてこないところが、邪神の分霊の好みの分かれ道なのだろうか。
まだまだ晶もわからないというか、わかりやすい邪神の分霊と手分けをして仲間たちをウサギ穴の出口へと誘導していくのだ。
「早くアリスと合流して安心させてあげないとね」
そう言って、最後の仲間の手を引いて晶はウサギ穴の出口へと向かう。
其処に在ったのは、大名行列とでも言うのが正しいのか、それほどまでに大勢のアリスの仲間たちの姿であった。
仲間たちは手と手を取り合って、再会を喜んでいる。
その中心にいるのがアリスだ。彼女もまた喜ぶように笑顔を見せている。あれだけ不安そうだった顔も、『マーダー・ラビット』が望んだであろう悲嘆にくれるかもも、もう何処にもない。
「ありがとう、素敵なお兄様……ええっと、ごめんなさい、お姉さま。とても嬉しいわ。みんな全員、私の仲間が揃ったわ!」
ある意味在っているのだけれど、物事の本質を見抜く力も高いのだろう。
アリスが微笑むのに晶は、いいよ手で制して間違いを正すことはしなかった。
「名も知らぬアリス様」
邪神の分霊が彼女に近づく。
けれど、アリスは微笑んで手を差し伸ばすのだ。
「そちらの素敵な神様もありがとう。アリスはアリスよ。そう呼んで頂戴。でも、いいの。お気持ちだけで、とても胸がいっぱいだわ。いつまでも一緒にって素敵なことだけれど。永遠も素晴らしいことだけれど。みんな変わることをやめられない子たちなの」
遮るのではなく、邪神の言葉を先取りするアリスの言葉。
まあ、程々に聞き流しておいてと晶は言うつもりであったのだけれど、無理強いを彼女がしないこともまた識っていた。
だから、晶はアリスの言葉にうなずく。
「お二人が来てくださって、本当に嬉しいわ。素敵なお召し物。素敵な気持ち。私は、それだけでとっても、とっても……そう、とっても嬉しいの」
その笑顔はきっと、狂気に彩られた『マーダー・ラビット』の欲望さえも打倒せしめるものであろう。
それを晶は感じ、そしてこれから相まみえるであろう狂気彩る殺意との対決に決意と共に一歩を生みだすのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
第2章 ボス戦
『マーダー・ラビット』

|
POW : きす・おぶ・ざ・です
【なんとなく選んだ武器】による超高速かつ大威力の一撃を放つ。ただし、自身から30cm以内の対象にしか使えない。
SPD : ふぁんとむ・きらー
【糸や鋏、ナイフ等】による素早い一撃を放つ。また、【使わない武器を捨てる】等で身軽になれば、更に加速する。
WIZ : まさくーる・ぱーてぃ
自身の【殺戮への喜びによって瞳】が輝く間、【自身の全て】の攻撃回数が9倍になる。ただし、味方を1回も攻撃しないと寿命が減る。
イラスト:七雨詠
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠終夜・嵐吾」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
「……なんだ、そんなつまらないことになっているなんて」
猟書家『マーダー・ラビット』は心底つまらなそうな顔をしていた。
彼はきっとアリスが一人でウサギ穴から出てくることを予想していたし、望んでいたのだろう。
仲間を全て失い、失望と絶望のないまぜになった顔で自分に殺されてくれるのだとばかり思っていたのだ。けれど、今目の前にいる彼女の表情に一つの陰りもない。
そう、一欠片とて『マーダー・ラビット』は彼女から奪うことができなかったのだ。
それを為したのが猟兵である。
彼等はアリスの仲間を全て救い出し、彼女とともにウサギ穴から飛び出したのだ。
「まったくもう! 本当に猟兵の皆さんは邪魔ばかりしてくれるんですね。本当に度し難いです。楽しみにしていたご褒美を台無しにされた気分です」
「わからなくなってしまったのね。その殺意。その狂気。私はあなたの品定めに値しない存在だと最初からわかっていたはずなのに。調理をするような気安さで、誰かの生命をどうこうしようって思っていたのね」
アリスは『マーダー・ラビット』の言葉を先回りする。
そして、彼女を護るように愉快な仲間たちが勢揃いしているのだ。
「ああ、アリスさんは、いっつもそうですね。憎たらしいったらないですよ。そんなに簡単に人の心を読み解くように先回りして、こちらの言葉を奪っていく。そういうところですよ。あなたが気に食わないって言う人が多かったのは」
「ええ、けれど、それでもみんなと手を繋げば、些細な問題なのよ」
アリスと仲間たち、そして猟兵達が今、狂気の殺意すらも覆すユーベルコードの輝きでもって、『マーダー・ラビット』に鉄槌を下す時がきたのだ――。
 馬県・義透
馬県・義透
引き続き『侵す者』
武器持ち替え:灰遠雷
迷惑なウサギよの。
自分の良いように考え、疑わずにおると。
…このアリスをよく見ておれば、わかることなのにの。会ってそんなに経ってないわしでも、わかるぞ?
さて、早業にて防御用結界術を全員分張っておいて。
ここは先制攻撃での【四天境地・雷】だの。避けられぬよ?
わしが傷つくのはよい。その分、わしに近づいて…後ろに気づかない。
矢は追っておるし、陰海月は忍び寄っておるのにな。
しかも、見えぬ四天霊障という武器もあるのよ。押し潰して弾く。
※
陰海月、ふわふわこっそり近づいて鈍化呪詛ぺちり。ぷきゅ。
まだそんなことを言っているのかと猟書家『マーダー・ラビット』は鋏を手にして、嗤った。
手を繋ぐ。
ただそれだけのことで何ができるというのだろうか。
現に自分が時計ウサギとして潜り込んでいたこともわからなかったではないか。
だからこ、こんな事態になっているというのに。
「なのにアリスさんはナンデそんな顔をしているのでしょうかね? ああ、もうほんっとうに!」
鬱陶しい笑顔を浮かべてばかりだと『マーダー・ラビット』は一瞬でアリスの元へと走る。
其の手にした鋏を以て、彼女の喉元をカッ割いてやろうとしたのだ。
だが、その斬撃は視えぬ結界によって防がれていた。
「鬱陶しいのね。私が。けれど、私には新しい仲間がいるもの。ねえ、おじ様?」
「迷惑なウサギよの」
結界を瞬時に張り巡らせた馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)の一柱である『侵す者』が言う。
彼の瞳に映る『マーダー・ラビット』は憎々しげな顔しかしていなかった。飄々とした余裕たっぷりの顔など、最早何処にもなかったのだ。
「自分の良いように考え、疑わずにおると」
「そのつもりだったんですよ。そうなるはずだったんですよ。極上のご褒美がもらえると思っていたのに、あなた達が邪魔ばっかりするから!」
振るわれる鋏の斬撃。
未だ早さを捉えられないわけではない。けれど、打ち合った武器をはじき飛ばす度に斬撃の速度が上がるのだ。
「…・・・・このアリスをよく見て折れば、分かることなのにの。会ってそんなに経ってないわしでも、わかるぞ?」
『侵す者』は武の天才である。
そんな彼を前にして殺人技巧だけでは目的は達することはできないだろう。
猟書家『マーダー・ラビット』は距離を取るように後ずさったが、それは悪手であった。
「避けられぬよ? その位置ではな」
その瞳がユーベルコードに輝く。
手にした雷の力秘めし強弓が引き絞られる。四天境地・雷(シテンキョウチ・カミナリ)。それこそが彼の放つユーベルコードにして、一瞬の明滅とともに走る雷の弓矢となって『マーダー・ラビット』を襲うのだ。
「疾いっ、けどそれまでですね! ほぅら、こうやって鋏を取り替えれば、速度はもっともっと……!」
それは事実であった。
分裂し追尾する矢。
けれど、それらを上回る速度で『マーダー・ラビット』は鋏で矢を撃ち落としていくのだ。
避けられないのならば、撃ち落とせばいい。
単純なことであり、『侵す者』もまた理解していた。しかし、視えぬ霊障と呼ばれる武器もある。
「硬いばっかりですね! こちらにまったく届かないですけど!」
「そうさな。だが、わしばかりに気を取られて居て、気が付かぬのならば、お笑い草よ!」
何を、と『マーダー・ラビット』が呟いた瞬間、彼の背後に迫っていたのは巨大なミズクラゲ『陰海月』の巨体であった。
もとより彼の影に潜んでいたものであるが、『侵す者』ばかりに気を取られていては、気がつくこともできまい。
「ぷきゅ」
その小さな呟きと共に陰海月が呪詛の打撃を『マーダー・ラビット』に打ち据える。それは彼の速度を抑え、鈍らせる呪詛。
『侵す者』が存在するかぎり『マーダー・ラビット』の速度は上がることはないだろう。なにせ、こちらは――。
「おじ様は悪霊なのだから。そう簡単に逃げられるとは思わないことね」
そんな風に『侵す者』は自分の言葉をアリスに先取りされてしまいながらも、そのとおりであることを認めるほかなく。
けれど、そんなアリスの自信に満ちた笑顔は、彼等にとって得難いものであったことだろう――。
大成功
🔵🔵🔵
 神代・凶津
神代・凶津
はっはっはっ、どうやら御所望の展開にはならなかったようだな、クソウサギ。
アリスの嬢ちゃん達の物語をてめえの望んだバッドエンドにはさせねえぜ。その為に、
「・・・『マーダー・ラビット』、貴方を倒します。」
さあ、ウサギ狩りの時間だぜッ!
「・・・式、召喚【覚え狼】」
【覚え狼】をけしかけながら俺達も妖刀で攻撃を仕掛けるぜ。
クソウサギの攻撃を見切って妖刀で受け流しながら【覚え狼】と連携して攻撃していくぜ。敵を俺達に集中せざるおえなくしたらその隙に『アリス御一行』の攻撃も通るだろ。
アリスの嬢ちゃん達の邪魔はさせねえぜ。
「その狂気、ここで終わらせます。」
【技能・式神使い、見切り、受け流し】
【アドリブ歓迎】
鈍る猟書家『マーダー・ラビット』の動き。
呪詛に寄って速度を鈍らされてはいるものの、『マーダー・ラビット』の力が完全に衰えたわけではない。
「ええ、ええ、その通り。まだまだたくさん鋏はありますからね。速度を鈍らされるのなら、捨てればいいのですよ」
嗤って『マーダー・ラビット』はアリスを、仲間を、そして猟兵を殺そうと走るのだ。
『はっはっはっ、どうやらご所望の展開にはならなかったようだな、クソウサギ』
「誰です、一体。そんな口の悪いのは」
『お前のだいっきらいであろう正義の味方ってヤツよッ!』
その言葉は戦いの最中にあっても、よく響いた。
鬼面のヒーローマスクである神代・凶津(謎の仮面と旅する巫女・f11808)と、パートーナーである桜がウサギ穴から飛び出して『マーダー・ラビット』と打ち合う。
『アリスの嬢ちゃんたちの物語をてめえの望んだバッドエンドにはさせねえぜ。そのために』
「……『マーダー・ラビット』、貴方を倒します」
「できますかね! そんな簡単に! まだまだショウは始まったばかり! まだまだこちらにだって手はたくさんあるのですよ!」
鋏が投げ捨てられ、さらに速度を上げる『マーダー・ラビット』。
その速度は呪詛の力を拭い去るほどに上昇し、凶津と桜を翻弄するように飛び跳ねるのだ。
繰り出される鋏の斬撃は鋭く。一撃を加える度に鋏を捨てていくものだから、さらに速度を上げていく。
『ハンッ、虚仮威しのスピードスターってか! だがなッ! ウサギ狩りの時間だぜッ!』
「……式、召喚『覚え狼』」
桜の瞳がユーベルコードに輝く。
それは、式神【覚え狼】(シキガミ・オボエオオカミ)。巨大な狼の式神がウサギ穴から飛び出し、『マーダー・ラビット』へと襲いかかるのだ。
「おお、こわいこわい。こんなに大きな狼を呼び出すだなんて。でも、大きいだけじゃあね!」
速度で勝る『マーダー・ラビット』が飛び跳ねるようにして式神の狼の攻撃を躱していく。
桜と凶津もまた妖刀で斬撃を加え、けれど返される刃を受け流しながら立ち回るのだ。
「こんなに単調な攻撃ばかりで倒せるとでも? 見くびられたものですね! もうちょっと歯ごたえがないと困ります!」
だが、そんな嘲りは意味がなかった。
どれだけ躱されようとも、『覚え狼』は相手の習性と行動パターンを覚えていくのだ。
同じ敵に攻撃する度に、その覚えたパターンから最適な攻撃手段を生み出していく。
「歯ごたえがあっても歯が欠けてしまっては残念でしょう? なら、お医者様に見てもらわないと」
アリスの言葉とともに仲間たちが一斉に雪崩込んでくる。
「まったくもう! 本当にアリスさんはこちらを苛立たせる天才ですね! やってられませ――」
ん、とつぶやく前に『マーダー・ラビット』の肩に食い込むのは『覚え狼』の牙であった。
なんで、と『マーダー・ラビット』は呟いただろう。
何故、とも思っただろう。
『覚え狼』はこれまで『マーダー・ラビット』を捉えることができなかった。これからもそうであると思っていたのだ。
けれど、その力は相手の力量を覚えていく。
ならば、捉えられぬ道理などないのだ。
「その狂気、ここで終わらせます」
『そうさ、アリスの嬢ちゃんたちの邪魔はさせねえぜっ!』
相棒、と凶津が叫んだ瞬間、桜の振るう妖刀の斬撃の一撃『マーダー・ラビット』の体を袈裟懸けに切り裂き、鮮血をほとばしらせるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 遥・瞬雷
遥・瞬雷
気持ちはまぁ分からなくはないよ。
彼女は英傑って奴さ。友とすれば頼もしいけど敵とすれば恐ろしい。
無数の味方が出来るだろうけど、それ以上の敵も作りかねない。そういう危うさがある。
周りが守らないとね。
敵の技は暗器術の類いかな。
七星剣を構え【功夫】で対峙するよ。
間合いはこちらが有利。但し懐に飛び込まれたら不利となる。地を蹴る様な歩法で間合いを調節し斬り合う。
懐に飛び込まれたらあえて剣を手放し、地を転がる様に回避。
勝負はここからだよ。敵の捨てた武器を拾う。年の功でね、暗器術は私も心得てる。
歩法で地脈の流れは把握した。震脚で大地を踏みしめその力を利用。
敵の武器とこの世界、全ての力を借りた一撃を撃ち込むよ。
妖刀の斬撃の一撃が猟書家『マーダー・ラビット』の胸を袈裟懸けに切り裂く。
血が噴出し、彼に深手を負わせたことを知らしめる赤い華が咲いた。
けれど、それでもなお倒れぬのは強大なオブリビオンである猟書家所以であろう。その手にした狂気を手放し、さらに加速するのは、まるで己の血潮すらも捨てて加速するためであったことだろう。
「アハハッ! 痛いということは生きているということ。だというのに、傷を追うことを恐れて小さくなっていたアリスさんには理解し難いことかもしれませんが、今、とても生きてるって気がしますよ! これが生! これが実感なんですよ!」
「けれど、それでも痛いって涙する心がないから、そんな風に誰かの痛みでしか自分を実感できないのでしょう? そうやって自分が痛いって、傷を見せびらかしても、あなたが何も自分の痛みを感じていないってこと、みんなわかっているわ」
『アリス適合者』のアリスが言う。
彼女の言葉はまっすぐに『マーダー・ラビット』の心をえぐったかも知れない。
自分ではなく他者を傷付けて、他者の痛みを訴える表情からでしか、生を実感できぬからこそ、容易に人の生命を奪うことができる。
「だからっ! そういう先回りして人のことを見透かしたように言うのが!」
「気持ちはまぁわからなくはないよ」
『マーダー・ラビット』が振るう狂気の一撃はアリスを襲うが、すんでの所で受け止められる。
七つの宿星が描かれた剣がきらめいた。
それは遥・瞬雷(瞬雷女仙・f32937)の持つ剣あり、彼女の重ねられた功夫があればこそ、猟書家の強力な一撃を受け止められたのだ。
「彼女は英傑ってやつさ。友とすれば頼もしいけれど敵とすれば恐ろしい。無数の味方ができるだろうけど、それ以上の敵も作りかねない」
「それが危ういって言うのね、仙女様。けれど――」
ああ、と瞬雷はうなずく。
だからこそ、自分たちがいるのだ。
まわりに護る者が自ずと現れる。
主君に瑞獣が存在するように、アリスという天命を持つ者がいるからこそ、瞬雷を始めとした猟兵達が駆けつけたのだ。
ならば、そこに敗北の二字はない。
「猟兵さんには用はないんですよ! そのアリスを! 殺さないと、どうしたってこの飢えは満たされないッ!」
放たれる狂気の数々は、切りつけては捨てるをくり返して加速度的に、『マーダー・ラビット』の速度を上げていく。
間合いは瞬雷の得意とするものであったが、懐に入り込まれてはどうなるかわからない。
地を蹴るような歩法で瞬雷は加速する『マーダー・ラビット』の速度と間合いを調節する。
「防戦一方では――!」
斬撃の速度がまた上がる。宿星剣が切り払われ、宙へと舞い上がる。くるりくりると回転する刀身が煌めき、勝負を決したかのように『マーダー・ラビット』が笑っていた。
「勝負は――」
「ここからよ! 仙女様!」
アリスが叫んだ瞬間、瞬雷は地を蹴る。手を伸ばしたのは、宙で回転する宿星剣ではない。
『マーダー・ラビット』が投げ捨てた狂気であった。
「年の功でね。暗器術は私も心得ている。ならば、こういうことだってできるのさ!」
すでに歩法によって地脈の流れは把握している。
ならばこそ、踏み込む足は神速。そして、大地を蹴った瞬間、流れ込むは地脈の力である。
一瞬の爆発を思わせる加速。
それは『マーダー・ラビット』を上回り、手にした狂気を掌底で打ち込むのだ。
「大地の力を得て、人は己を支える地の力を識る。この大地は己以上の巨大さを持ち、その力に抗うことは即ち敗北を意味するのさ」
乱戦遊戯。
それは彼女の輝く瞳、そのユーベルコードの輝きの発露に寄って放たれた全力の一撃。
「ですが、それは届かない!」
狂気を打ち込む掌底の一撃はけれど、『マーダー・ラビット』に躱される。
「でも、体勢は崩したわね!」
アリスの声が響き渡る。彼女は手を伸ばしていた。宙に回転する宿星剣に。彼女の跳躍では絶対に届かない。
けれど、もう彼女は一人ではないのだ。彼女を肩車するように大勢の仲間たちが支える。手を伸ばし、宿星剣の柄を手にとって、投げるようにして瞬雷へと放つのだ。
「上出来! 流石は英傑! ならば応えようじゃあないか!」
瞬雷は自らの手元に戻った宿星剣を手にし、その一撃を『マーダー・ラビット』の心臓へと深々と突き立てるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド
人はあなたが思っているほど弱くはないということです。
単純な暴力の強さは私たちがカバーしましょう。
【氷銃精製】を使用、戦うことを希望するアリスさんの仲間達に氷の銃を渡し、アリスさんの仲間達と一緒に戦います。
あなたたちの彼との旅は終わりですが、これからもあなたたちとアリスさんの自分の扉を探すための旅は続く。
ここで終わりではないのですから、全員で戦って越えていきましょう。
彼らが直接相対をするのは危険ですし、前衛は私が。まずは防御と足止めに専念し、攻撃を『見切り』「フィンブルヴェト」の銃剣で『武器受け』し、アリスさんの仲間達による援護射撃で隙ができたら銃剣の『串刺し』からの氷の弾丸の『零距離射撃』を。
心臓を貫かれても、体を袈裟懸けに切り裂かれても猟書家『マーダー・ラビット』は笑っていた。
どれだけの傷が彼に痛みを与えているかわからない。
けれど、それでも彼は嗤っていた。
「アハハッ! こんな傷なんでもないんですよ! だってまだ消えない。消えない限り、痛みなんか二の次なんですから」
『マーダー・ラビット』によって、痛みとは他者が浮かべる極上のごちそうでしかなかった。
彼は痛みを感じないし、感じようともしない。
生を実感できるのは他者の痛みであるからこそ、悪辣なることができる。
自分ではない他者の痛みでしか、生を謳歌できない。
「だから、きっとアリスさんはご褒美に殺されてくれると思っていたんですけどね」
こんなにもあっさりと仲間たちをかき集めてくるなんて、と『マーダー・ラビット』は忌々しげに首を鳴らす。
なんとなく、そうなんとく思いついたように彼はナイフを手に取る。別に武器はなんでもよかったのだ。
「人はあなたが思っているほど弱くはないということです」
ユーベルコードの輝きが世界に満ちる。
セルマ・エンフィールド(絶対零度の射手・f06556)は疾走る。人の痛みでしか生を実感できぬ化け物がいる。
それが撒き散らす悪意は、きっと純粋な者も、尊いものも全て傷付けて台無しにするだろう。それが許せない。
「いいえ、きっと弱いはずだったんですよ。それなのにあなた達がやってくるから、台無しになったんです」
狂気に彩ろられた瞳がセルマを見つめる。
そこにあったのは、どうしようもない悪辣さだ。他者を虐げ、傷つけることに高揚するどうしようもなさ。
他者の苦しみに愉悦を見出す、救いようのない魂がそこにあった。
「それは悲しいことだって誰かが貴方に教えたのなら、そんなふうにはならなかったでしょうに」
哀れみの声が響く。
それはきっとアリスとその仲間たちの言葉であった。彼等の手には氷の礫を放つことができる、氷で出来た銃があった。
セルマのユーベルコード、氷銃精製(ヒョウジュウセイセイ)によって生み出された氷銃は、大名行列のように数の多い仲間たちに全て配られていた。
「あなたたちの彼との旅は終わりですが、これからもあなたたちとアリスさんの自分の扉を探すための旅は続く」
セルマは言う。
彼女の瞳は、今もユーベルコードに輝いていた。
それはともすれば、遠くない未来のことを告げていたのかも知れない。寂しさはある。けれど、それさえも喜びに変わることを彼女は知っている。
「ここで終わりではなのですから――」
「ええ、みんなで戦って越えていきましょう。狙撃手のお姉さん。あなたも、一緒に」
アリスが手を伸ばす。
手を繋ぐ。そして、離す。肌と肌が少しだけ触れ合っただけだったけれど、それでも十分だった。
もうこれで貴方と私は仲間。
ただそれだけでよかったのだ。それだけで紡がれる縁だってあったのだ。
それを『マーダー・ラビット』はふいにした。
「ごちゃごちゃとお綺麗な言葉を押し付けてくるものです!」
迫る『マーダー・ラビット』へとセルマが踏み込む。互いに必殺の距離は至近距離である。ならば、ここで退いてはだめだ。
アリスと仲間たちが直接相対するのは危険が伴う。ならば、その危険に対するのは自分しかいない。
「単純な暴力。それは私達がカバーできることです。だから、その力は容易なのです」
セルマは銃剣『アルマス』で『マーダー・ラビット』のナイフの一撃を受け止める。
骨が軋む音がした。それほどの一撃であったが、それでもセルマは踏みとどまった。
何故なら、ここで踏みとどまればアリスたちの援護射撃が飛んでくるとわかっていたからだ。氷の礫がセルマの背後から『マーダー・ラビット』を襲う。
それは決別の一撃であった。
彼との旅は終わりを告げる。
けれど、これからも彼等の旅路は続くだろう。どれだけの悪意が彼等を襲おうとも、くじけることなんて何一つないのだ。
「器の違いというやつです。あなたは、人の強さを見くびった。見誤った。それが――」
敗北の原因であるというようにセルマはマスケット銃『フィンブルヴェト』の銃口を『マーダー・ラビット』に押し付け、零距離による氷の弾丸の一撃を持って、別れの手向けとするのであった――。
大成功
🔵🔵🔵
 佐伯・晶
佐伯・晶
それじゃ元凶を倒して大団円といこうか
アリス様と仲間達は任せて下さいまし
私がお守りいたしますの
空間に干渉されないように固定しておきますの
…いっそ空間ごと固定した方が安全かもしれませんの
それは本当に必要な時だけにしてくれないかな…
まあ、アリス達を護ってくれるという点については信用できるか
遠距離から援護できる仲間がいるなら助かるかな
距離をとってガトリングガンで攻撃
相手の攻撃は射撃で迎撃したり
神気で攻撃を固定したりして防ぐよ
連続攻撃はガトリングガンの銃身で防ぎつつ
服や皮膚が斬られる程度は諦めて躱そう
凌いだらガトリングガンを投げつけて出来た隙に
UCで拘束しよう
さて、アリスの仲間達出番だよ
皆で攻撃しようか
無数の氷の礫と弾丸が猟書家『マーダー・ラビット』の体を貫く。
赤い血潮が吹き出してもなお、彼は嗤っていた。痛みこそが生を実感できるものであるが、けれど彼は他者の苦痛によってのみ生を実感できる悪辣さの体現者であった。
故に彼の瞳は殺戮に対する喜びで満ち溢れていた。
「抵抗する! どれだけ追い詰めても諦めずに抵抗する姿が、胸を高鳴らせてくれますね。それだけ生きたいという願いがあるからこそ、それを踏みにじる行いは高ぶらせてくれるのです」
爛々と輝く狂気は、彼が本当に喜んでいるからにほかならない。
手にした凶器による攻撃の速度は益々持って上がっていく。
「それじゃ、元凶を倒して大団円といこうか」
携行ガトリングガンを構えた佐伯・晶(邪神(仮)・f19507)の放つ弾丸は、凄まじい勢いで『マーダー・ラビット』へと打ち込まれるが、それらの尽くを凶器が弾いていく。
凶器に輝く瞳がユーベルコードの輝きを教えるのだ。
「アリス様と仲間たちは任せてくださいまし。私がお守りいたしますの」
空間に干渉されないように固定しておこうとした邪神の分霊の言葉を遮って、アリスが言う。
「いっそ空間毎固定したほうが安全かもしれないけれど、私達は目をそらしてはダメなの」
これは自分たちの冒険である。
誰かに変わってもらうことはできたとしても、自分たちがやらなければならないことなのだ。
「それは本当に必要なときだけにしてくれないかな……」
晶は弾丸を打ち出し続けながら、そう提案する。
邪神の分霊がアリスたちを護ってくれるという点については信用できる。だけど、他ならぬ彼女たちがそれを必要としていないのならば、保険として機能する程度でいいのだ。
「こそこそ打ち合わせは終わりましたか! 終わらなくっても殺してあげますからね!」
迫る『マーダー・ラビット』は猟兵たちの攻撃に寄って消耗しているのに、一向に速度が衰える気配はなかった。
流血しながらも、むしろ出血に寄って身体が軽くなっているとでも言うように鬼気迫る顔でアリスを襲わんとしている。
「そういう殺意ばかりを振りまき続けるから、誰にも相手をされなくなる。殺意が特別のことのように感じているから、そんな風に振る舞える。そんなものは当たり前の感情だって、理解できないから」
晶はガトリングガンの銃身で『マーダー・ラビット』の凶器の一撃を受け止める。凄まじい連撃は防ぎきれずに晶の服や皮膚を切り刻むが痛みは無視した。
その瞳は輝く。
『マーダー・ラビット』の攻撃速度が如何に速度を誇るのだとしても、息継ぎの瞬間は必ず訪れる。
それを彼女は待っていたのだ。
「試製電撃索発射銃(エレクトリック・パラライザー)――これは、そう簡単には千切れないよ」
ガトリングガンを投げつけ、その瞬間に晶は試製電撃索発射銃の引き金を引く。
飛び出した電撃策が『マーダー・ラビット』の体に巻き付き、もがく彼の体に電撃を流し込むのだ。
「これは、網……にっ! ビリビリきますなぁ!?」
流れ続ける電撃は、如何にスピードの上がった『マーダー・ラビット』と言えど抜け出すことはできない。
その隙を作り出した晶が叫ぶ。
「アリスの仲間たち出番だよ。みんなで攻撃しようか!」
その号令と共に固定していた空間から飛び出すアリスの仲間たち。
彼等は自分たちができる限りの攻撃を『マーダー・ラビット』へと叩き込む。
一緒に旅路を歩いた者であったけれど。
そこに悪意があるのならば。アリスへの悪意があるのならば、それはどうしたって許してはいけないものだった。
彼等はアリスに助けられた。
ならば、今度は自分たちの番だと『マーダー・ラビット』を追い込む攻撃を晶と共に打ち込み、その悪意を振り払うのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 ルクス・アルブス
ルクス・アルブス
ウサ、ギ……?(瞳の光がすぅっと消えかけ)
そうだ、ボルシチ作らないと……。
「え? あ、はい師匠!」
あぶなくあっちの世界にいきそうになっていた精神を、
師匠に引き戻してもらいはしたのですが……
「師匠は天才ですよね、ぺったんですけど。
それに異端でもありますよね。ぺったんですし。
気にしないというか、話聞いてないですね。ぺったんだけに。
胸もポジティブシンキングでいけばいいのに」
今日は師匠の全力ぶっぱ、頼もしいですね。
わたしも【Canon】で援護しちゃいますよ!
魔法中の師匠は、集中力でわたしの演奏も気になりませんしね!
もう鍋にはしませんよー!?
今日はちゃんとソテーにします(また光が消えかけて)
 フィア・シュヴァルツ
フィア・シュヴァルツ
弟子のルクスと
「アリスよ、そこのウサギの言葉など気にするな。
……などという言葉はすでにお前には必要なさそうだな。
我やお前のような天才は常に世の中から異端視される。
だが、そんな世の中、気にするだけ無意味よ。
な、ルクス」
そう、不死の魔術を極めし天才美少女魔法使いたる我は、世間から漆黒の魔女だのと呼ばれ妬まれようと、気になどしない。
なんだと、ルクス?
じゃあ胸のことも気にしてないのか、だと?
ええい、そこに触れるな!(めっちゃ気にしてる
「この世の中(の巨乳)に対する我の妬み、そこのウサギに食らわせてくれるわ!」(八つ当たり
全力の【竜滅陣】でウサギの丸焼きにしてくれるわ!
……あ、ルクス、鍋にはするなよ?
「ウサ、ぎ……?」
猟書家『マーダー・ラビット』の姿を見て、ルクス・アルブス(魔女に憧れる魔法少女・f32689)の瞳のハイライトが何故か行方不明になっていた。
過去のトラウマか。
それともウサギに故郷を焼かれたのか。
はたまた両親の仇か。
まあ、なんのことはない。ちょっと色々こう、言い難い何かがあったのだけれど、それはまた別の話である。
「そうだ、ボルシチ作らないと……」
そうそう、あの真っ赤なやつね。とあっちの世界に行きそうになったルクスを引っ張り上げたのは、師匠であるフィア・シュヴァルツ(漆黒の魔女・f31665)の言葉であった。
「アリスよ、そこのウサギの言葉など気にするな」
「ええ、その言葉は私には必要ないわ。けれど、ありがとう。貴方や私は常に世の中からはぶかれてしまう。みんなと違うから。みんなと同じ均一なのを求めてしまう心が在るのは仕方のないことだけれど」
それが間違っているとも言わないけれど。
それでもアリスとフィアは理解していたのだ。
「そう、そんな世の中気にするだけ無意味よ。な、ルクス」
な! と振り返った先にあったのはルクスのハイライトがいなくなった瞳であったのだが、はっ、と気を取り戻したルクスが目をパチクリさせている。
今、師匠すごくいいこと言ってたんだけど。
「え? あ、はい師匠!」
やべ、聞いてなかったみたいな雰囲気を出さずにルクスはうなずく。
「そう、不死の魔術を極めし天才美少女魔法使いたる我は、世間からは漆黒の魔女だのと呼ばれ妬まれようとも気にしなどしない」
『マーダー・ラビット』が迫るのも気にせず、フィアは胸を張っていた。
大胆不敵。
その表情は自信に満ち溢れていた。それこそが人生を生き抜く力であるのならば、それこそを『マーダー・ラビット』は苛立たしげに見つめるほか無い。
「師匠は天才ですよね、ぺったんですけど。それに異端でもありますよね。ぺったんですし。木にしないと言うか、話聞いてないですね。ぺったんだけに。胸もポジティブシンキングでいけばいいのに」
ルクスのディス。
ぺったん言いすぎじゃない?
「ぺったんぺったん餅つきでもしているつもりですか」
『マーダー・ラビット』が凶器を投げ捨てながら迫る。凄まじい速度で二人を排除し、アリスを亡き者にせんと迫るのだ。
だが、残念である。
今の彼女たちに、いや、フィアに近づくのは危険極まりない。あんまりにも弟子がぺったん言うものだから、すでに怒り心頭である。
「ええい、そこに触れるな!」
めちゃくちゃに気にしているのだ。
先程までの気にするだけ無意味といっていた言葉の重みがふわふわになってしまうではないか。
けれど、溢れ出るユーベルコードの輝きは本物であった。
「この世の中に対する我の妬み、そこのウサギに食らわせてくれるわ!」
八つ当たりである。理不尽である。
けれど、『マーダー・ラビット』にとっては良い薬かもしれない。それは言ってみれば鏡写しである。
誰かを害する、妬む、嫉む。
その感情は必ず自分に返ってくるのだという証拠となって、竜滅陣(ドラゴン・スレイヤー)の詠唱を紡がせるのだ。
「魔法中の師匠は、集中力でわたしの演奏も気になりませんよね!」
すごいな、と思わないでもない。
『マーダー・ラビット』は吹き荒れるような不協和音の中、詠唱を続けるフィアの集中力の凄まじさに舌をまく。
正直、耳を抑えていても通り抜けてくる凄まじい音。
演奏っていっていいのかわからぬほどの不快感が『マーダー・ラビット』を襲うのだ。
けれど、そんな不協和音の中でフィアとアリスだけが平気な顔をしているのだ。
「独創的な音色ね! 魔法少女さんはきっと未来の名バイオリニストだわ! 素敵!」
えぇ、とこれにはさすがのアリスの仲間たちもフォローしきれなかった。マジかよという顔をしているが、それでもルクスの瞳はユーベルコードに輝く。
Canon(カノン)流れる戦場にありて、フィアの詠唱の言葉が紡がれていく。
「漆黒の魔女の名に於いて、我が前に立ち塞がりし全てを消し去ろう」
そのユーベルコードはドラゴンすらも消し飛ばす大希望破壊魔法である。
この魔法のおかげで何度彼女たちは逃亡生活を強いられたかわからぬほどに強烈な威力でもって、『マーダー・ラビット』は不協和音に苦しみながら、それでもかわそうとしたが、もう遅い。
「これが全力である! ウサギの丸焼きにしてくれるわ!」
放たれた極大なる魔力の奔流が『マーダー・ラビット』を飲み込み吹き飛ばしていく。確かに丸焼きになってもおかしくない威力であった。
「……あ、ルクス。鍋にはするなよ?」
「もう鍋にはしませんよー!? 今日はちゃんとソテーにします」
「そういう問題かしら? でもお料理できるって素敵ね!」
そんな姦しい三人娘たちの談笑が凄まじい破壊の後で朗らかに行われるのであった――。
大成功
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
 菫宮・理緒
菫宮・理緒
なかなかマッドなウサギさんだね。
こーんな可愛いアリスさんを助けるのは当然のこと!
あなたのご褒美になんて、させないからね。
「悪いウサギさんは、よく焼きソテーにしてあげるよ!」
【Nimrud lens】で近づかれる前に焼いていこう。
火加減も調整はできるけど、
食べたくはないから炭になるまででいいよね。
わたしのブルーノワールのほうが、1000倍可愛いよね! ね!
そして、もーっと可愛賢いアリスさんに、
お姉さんからちょっとだけアドバイス。
相手がなにを言いたいか解っちゃうんだと思うけど、
お話を聞いてあげてからお返事してあげると、
みんなもーっと喜ぶと思うよ!
お話しって、たくさんできるだけで嬉しいしからね!
極大なる魔法の一撃とヴァイオリンの不協和音が奏でる猟兵のユーベルコードは、猟書家『マーダー・ラビット』を強かに打ち据え、その肉体を滅びへといざなうだろう。
けれど、未だ殺意は衰えることはなかった。
彼の瞳には未だアリスを嬲りたいという狂気が満ち溢れていた。
だから、どれだけ血を流そうとも、傷跡を刻まれようとも立ち上がってくるのだ。
「それはご褒美なんです。これだけの苦難が押し寄せるのは、きっとご褒美の大きさを示しているはずなんです。だからきっと大丈夫。アリスさんの絶望した顔は、殺意を満たしてくれるはず」
それは自身が特別であるという自負から生まれる言葉であったことだろう。
自分に滅びはないのだと、尽きぬ殺意が在る限り、必ず己の刃はアリスへと突き立てられるでろうと信じて疑っていないのだ。
「なかなかマッドなウサギさんだね」
けれど、と菫宮・理緒(バーチャルダイバー・f06437)の瞳はユーベルコードに輝いていた。
「こーんなかわいいアリスさんを助けるのは当然のこと! あなたのご褒美になって、させないからね!」
理緒はアリスを抱きかかえながら、きっと瞳でもって『マーダー・ラビット』をねめつける。
それは同時に彼女のユーベルコードの力の発現の瞬間でもあった。
「屈折率、固定……収斂」
世界に満ちる光が集束し、一気に点へと為す。
それこそが、Nimrud lens(ニムルド・レンズ)。彼女のユーベルコードにして熱線と化した光が『マーダー・ラビット』の凶器を溶かして落とすのだ。
「あっつ! なんです、そのとんでもない熱は! あーあ、もう、鋏が台無しです。でも――!」
それでもかまわない。
凶器はたくさんあるだと言うかのように何処からともなく『マーダー・ラビット』は凶器を手に走るのだ。
「悪いウサギさんは、よく焼きソテーにしてあげるよ!」
なんだかさっきからご飯の話ばかりになっているような気がするわ、とアリスのお腹の音が鳴る。
この状況、そしてウサギを示すのは『マーダー・ラビット』であるのだが、そこから食欲が湧くのは、確かに傑物としての器があるのかもしれないと理緒は抱えながら思ったが、全ては可愛いの前にひれ伏すのである。
「ウサギさんは可愛いけれど、わたしのブルーノワールのほうが、1000倍可愛いよね! ね!」
同意を求めながら、熱線で『マーダー・ラビット』を炭になるまで焼き尽くさんばかりの熱量をほとばしらせる理緒。
腕の中のアリスは決して目をそらさなかった。
これは彼女たちの冒険だ。
猟兵達にしかオブリビオンである『マーダー・ラビット』を打倒できないのはわかっているけれど、それでも彼女たちは自分たちの旅路の意味を知っている。
「そして、もーっと可愛賢いアリスさんにお姉さんからちょっとだけアドバイス」
「ええ、わかっているわ。相手が何を言いたい分かってしまう私はどうすればいいのか」
その瞳はもう分かっていたのだ。
けれど、アリスは理緒の言葉の次を待つ。待つことができるようになっていた。
それは今回の冒険によって得たものだろう。
全て先回りしてしまうほどの頭の回転の速さと、察する力。きっと方向性だけが間違っていたのだ。
「お話を聞いてあげてからお返事してあげると、みんなもーっと喜ぶと思うよ!」
「ええ、私もそう思うわ。みんなが喜ぶことをしてあげたい。誰かのために何かをしたげたいって思うことも、誰かをいじめたいって思う心も当たり前のことなんだって、私はわかったもの。誰の心にも在る当たり前なんだって」
だから、もう大丈夫と理緒の腕の中からアリスは降りて、彼女の手を握る。
そう、当たり前の感情。
特別で、特別じゃない。
誰もが持っていて、誰もが忘れてしまっていること。だから、あれだけ怖かった一人ぼっちももう、怖くなんて無いのだ。
何故なら。
「お話って、たくさんできるだけで――」
『嬉しいからね!』
二人の声は重なり合って、きっと元の世界に戻っても大丈夫だということを、世界に知らしめるのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
 マグダレナ・クールー
マグダレナ・クールー
貴方は、飢えているのですね。欲が満たされないのは、ひどく虚しい事。……かわいそう、ですね。だって、なんだか、痩せ痩けて見えます
……いけませんね、この視界は。広い視野はわたくしを困らせます
貴方はこれまでアリスを喰らった事はありましたか? 初めてですか? でも、貴方は眩いアリスを喰らおうとしましたね。今も殺そうとしてますね。じゃあ、仕返ししないといけませんね
わたくしはアリスを傷付けた貴方を許しません。アリスの行く道を阻むならば、殺します
……ねえ、どうして殺したいと思い至ったのですか? 何故、殺戮を楽しめるのですか。どうしたら罪悪を感じずに笑えるのですか
人を傷付けたら傷付けられる恐怖を、忘れましたか
放たれたユーベルコードの光が、熱線となって猟書家『マーダー・ラビット』の体を焼く。
けれど、その一撃で持ってもまだ滅びない。
その瞳に輝く爛々とした殺意が、殺戮への喜びが未だ消えないのだ。
痛みを感じない。
痛みを感じる他社によってのみ、己の生を実感できる歪な存在。しかし、誰の心にも在る悪意を特別のことのように思ってしまう幼児性が、『マーダー・ラビット』を支えていた。
「クフフっ、まだ、まだ、どれだけ肉が焦げようとも、どれだけ骨から削ぎ落とされようとも、どれだけ血を喪っても、まだまだ。まだまだですよ、アリスさん」
諦めることはない。
どこまでも、地の果てまでも追いかけ回して、必ずその血肉を喰らいたいという願いのままに『マーダー・ラビット』は一歩を踏み出す。
「貴方は、飢えているのですね。欲が満たされないのは、ひどく虚しいこと」
マグダレナ・クールー(マジカルメンタルルサンチマン・f21320)は、その正常なる視界の中で躊躇うように、けれど、戸惑うように呟いた。
目の前の『マーダー・ラビット』は、とても。そう、とても。
「……かわいそう、ですね。だって、なんだか、痩せこけて見えます」
いけませんね、とマグダレナは困ったような顔をしたが、それ以上に困惑していたのは『マーダー・ラビット』であった。
何を言っているのだという顔をしていた。
その瞳には未だ殺戮への愉悦が在った。だって、それが彼を支える唯一のものであったから。
してはいけないことをしている自分という特別。
それだけが彼の心を支えて、数多の猟兵のユーベルコードを絶えさせていたのに。それなのに、マグダレナの言葉はユーベルコードよりも何よりもえぐった。
「貴方はこれまでアリスを喰らったことはありましたか? 初めてですか? でも貴方は眩いアリスを喰らおうとしましたね。今も殺そうとしてますね。じゃあ――」
一気に捲し立てられるマグダレナの言葉。
それは不可解極まりないものであった。それが例え本当のことであったとしても、本当でなかったのだとしても、人として目の前に立つ存在があるのならば、罪を作り上げることができる。
存在しないものを想像できる人間ならではのユーベルコードであった。
『アリスを傷付け殺した食ったオウガであるという』――『冤罪』。
それがマグダレナのユーベルコードである。
食べるのにも、飲むのにも十分ではない。けれど何が欠けているというのだろう。ならば、それは罪だ。
罪が足りない。十分でないのならば、罪というスパイスを振るうのだ。
「じゃあ、仕返ししないといけませんね」
「なにを」
呟いた言葉は飲み込まれた。
昏い、昏い、虚の中に飲み込まれて消えていくのを『マーダー・ラビット』は感じたことだろう。
「わたくしはアリスを傷付けた貴方を許しません。アリスの行路を阻むならば、殺します」
一歩を踏み出すマグダレナの瞳がユーベルコードが輝く。
何故、こんなことになったのかという『正しい原因』なんてもう『マーダー・ラビット』にはわからなくなっていたことだろう。
だって、目の前に居るのだ。
その権化が。
共食いオウガブラッドが、目の前に居る。
「……ねえ、どうして殺したいと思い至ったのですか? 何故、殺戮を楽しめるのですか。どうしたら罪悪を感じずに笑えるのですか」
一歩を踏み出す度に『マーダー・ラビット』は己の魂が軋むのを感じただろう。
これは滅びではない。
ただの食物連鎖だ。
目の前にいるオウガブラッドに飲み込まれるだけの、光景。
歪む視界の中で、『マーダー・ラビット』はようやくつぶやくのだ。
「特別になるために、特別なことをしなければならないと思って。それで、特別でもなんでも無いことを、特別なことのように振る舞いたくて」
それで、ひけらかしたのだと。
殺意を、狂気を。
「人を傷付けたら傷付けられる恐怖を、忘れましたか」
例外なんて無い。
例外にもまた例外が存在する。それは、言うまでもなく。
――słuszna przyczyna(ショクモツレンサ)。
不条理と『マーダー・ラビット』は感じたままに。その一撃は、『マーダー・ラビット』を押しつぶし霧散させる。
因果応報とは言わない。
マグダレナは、眩いアリスの足元に転がっていたつまづきそうな石を払ったに過ぎない。けれど、それでも眩いアリスは、きっと彼女の視界を今もまだまばゆい輝きのような笑顔で、マグダレナの手を引くのだった――。
大成功
🔵🔵🔵
最終結果:成功
完成日:2021年04月26日
宿敵
『マーダー・ラビット』
を撃破!
|


 海鶴
海鶴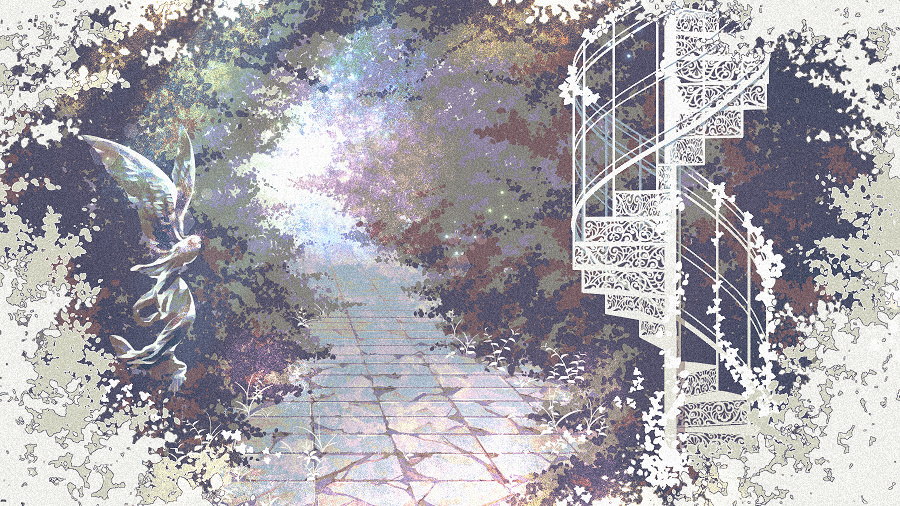
 馬県・義透
馬県・義透  神代・凶津
神代・凶津  菫宮・理緒
菫宮・理緒  遥・瞬雷
遥・瞬雷  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  マグダレナ・クールー
マグダレナ・クールー  ルクス・アルブス
ルクス・アルブス  フィア・シュヴァルツ
フィア・シュヴァルツ  佐伯・晶
佐伯・晶 
 馬県・義透
馬県・義透  神代・凶津
神代・凶津  遥・瞬雷
遥・瞬雷  セルマ・エンフィールド
セルマ・エンフィールド  佐伯・晶
佐伯・晶  ルクス・アルブス
ルクス・アルブス  フィア・シュヴァルツ
フィア・シュヴァルツ  菫宮・理緒
菫宮・理緒  マグダレナ・クールー
マグダレナ・クールー