スパヰパフュウムの残り香
●スパヰ大国
サクラミラージュおける帝都とは即ち、不死の帝が治める土地である。
世界統一は為されたが、露西亜や亜米利加といった国々は未だ残っている。故に未だに旧世代然とした利害関係や緊張関係は常にあるのだ。
そして、帝都において情報とは常に必要なものであり、各国、都市、あらゆる場所からスパイが送り込まれている。
それほどまでに帝都はスパイひしめく場所であるのだ。
それは一般の學徒兵たちは預かり知らぬことであり、積極的に取締が行われているわけではない。時折、管理するようにスパイたちがあぶり出されこそすれ、それは帝都の治安を脅かすものに発展することはないのだ。
だが、本当にそうだろうか。
帝都では今、『幻朧戦線』が暗躍し続けている。
グラッジ弾、影朧甲冑、籠絡ラムプ……猟兵達も知るところのものが多いであろう。その豊富な影朧兵器は一体どこからやってくるのだろうか。
それほどまでに『幻朧戦線』とは息の長い組織であろうか。
答えは否である。
彼らは『大正の世を終わらせる』、『戦乱こそが人を進化させる』……それだけの思想によって結びついた者たちにすぎないのだ。
そんな者たちがどうして、あれだけの豊富な禁止された兵器である『影朧兵器』を調達できよう。
そう、ここに来て浮上する存在がある。
幻朧戦線に加担する者たちである。その最も有力な存在―――それが、スパイたちである。
●スパヰのかほり
そこはお香を取り扱う専門店であった。
名を『香百貨』。
帝都にあって有名店であり、紳士淑女たちが香水やお香、匂い袋や香木を求めて足繁く通う者たちで溢れていた。
香りを焚き染めた布雑貨や、香りに関するものであれば何でも揃うことで評判だった。けれど、スパヰたちにとって、そこは在る種の香りを使った暗号による情報交換の場としても活用されていた。
なぜなら、香水やお香を買い求める場において、男女、年齢、人種は入り乱れて当然である。さらに言葉をかわさずとも、その場にあるだけで一般人には理解できない香りを使ったコミュニケーションが可能なのだ。
それこそスパヰたる真骨頂であるとも言えた。
言葉交わさぬ客、そして『香百貨』にて働く従業員や店主……この場において、誰がスパヰであってもおかしくない。
それほどにスパヰたちは巧妙に帝都の日常に入り込んでいるのだ―――。
●スパヰを追え
グリモアベースに集まってきた猟兵たちを迎えたのはナイアルテ・ブーゾヴァ(フラスコチャイルドのゴッドハンド・f25860)であった。
「お集まり頂きありがとうございます。今回の事件はサクラミラージュ。常に幻朧桜が舞い散る大正の世が続く世界です。今回は、このサクラミラージュの帝都におけるスパヰを捕まえて頂きたいのです」
そう言ってナイアルテは頭を下げる。
サクラミラージュは確かに不死の帝の元、世界統一が為された平和そのものの世界である。頻発する影朧の事件はあれど、それは學徒兵たちによって救済されている。
けれど、帝都には世界各国、都市から多数のスパヰたちが潜伏しているのだ。
「はい……これまで皆さんは『幻朧戦線』が引き起こす事件を幾度も解決してくださっています。ですが、禁止された影朧兵器を、ああも無数に用意できるのは、組織の成り立ちを考えれば無理なはずなのです」
そう、例えば後ろ盾が無い限りは。
ナイアルテが言わんとすることを猟兵達が理解するのに時間はかからなかったことだろう。
「―――裏で手引するスパヰの存在があるのです。彼らは己の国や都市の利益のために行動しているのでしょうが、それは帝都に住まう人々の安寧を脅かすものです。如何なる理由があろうとも、無辜の人々が傷ついて良い理由などあるはずがありません」
幻朧戦線の後ろ盾として影朧兵器を供給し、加担しているスパヰがいるのであれば、それを捕らえなければならない。
だが、相手はスパヰである。
情報、存在の隠蔽や撹乱は得意中の得意なものであろう。彼らを追い詰めるには、やはり猟兵の力が必要なのだ。
「今回私が予知したのは、とあるフレグランスショップ……帝都では『香百貨』と呼ばれているお店がスパヰたちの情報交換の場として用いられているようです。彼らは巧妙に姿を隠し、客として出入りしています。皆さんは、スパヰの痕跡を見つけ出し、スパヰを捕らえて頂きたいのです」
そう簡単に上手く行くとは思えない。
例え、スパヰであることを看破しても逃げられてしまっては元も子もない。それに、その場で見つけることのできるスパヰが一人であるとは限らないだろう。
「そうなのです。単独犯であるのなら確かに捕らえ易かったでしょう。ですが、相手は大量の影朧兵器を供給する者です。グループで動いている可能性もありえるのです」
故に、例えスパヰである証拠を突きつけても、逃走を図られる可能性がある。それはナイアルテの予知にもあるようだった。
「彼らはスパヰである証拠を突きつけると、逃走を図ります。その道行きにはありとあらゆる罠が仕掛けてあるのです。おそらく逃走用に用意されたルートなのでしょう。これらを踏破し、捕らえて下さい」
僅かにナイアルテの瞳が曇る。
どうやら、それだけでは終わらないであろう予感があるのだろう。
「危険であるのは重々承知しております。ですが、幻朧戦線を放置していれば、必ず人々が夜安心して眠れなくなる日々が訪れてしまいます。それだけは、なんとしても阻止しなければなりません……どうか、お願いいたします」
そう言ってナイアルテは再び頭を下げて猟兵達を見送る。
猟兵たちが知る世界の中でもサクラミラージュは表向きは平穏そのものである。例え、それが仮初めのものであり、容易に崩れてしまうものであったとしても、薄氷を踏むように平穏は維持されなければならない。
例え、それが本当に偽りの平穏なのだとしても、平穏を甘受する人々にとって、それもあた掛け替えのない日常であるのだから―――。
 海鶴
海鶴
マスターの海鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回はサクラミラージュにおいて、帝都にひしめくスパヰたちを捕らえ、幻朧戦線に加担している証拠を掴みましょう。
●第一章
日常です。
香水など香りにまつわるものを扱っている『香百貨』と呼ばれるお店がスパヰたちの香りを使った情報交換の場として存在しています。
店内にいる店員や、店主、品物を運んでくる業者、買い求める客など様々な人々が集まってきています。
誰もがスパヰである可能性が多いのです。
皆さんは転移した後、このお店を訪れ、香水やお香、香り袋などを楽しみつつ、店内にいるであろうスパヰの痕跡を見つけ出して下さい。
『これが証拠だ!』と突きつけ、スパヰを追い詰めましょう。
●第二章
冒険です。
第一章においてスパヰである証拠を突きつけられたスパヰは、店内から逃走します。
予め逃走ルートは存在していて、そこには追いかける皆さんを陥れようとする罠がひしめいています。
それらの罠を踏破し、時には利用しつつスパヰを追い詰めましょう。
●第三章
ボス戦です。
追い詰められたスパヰはいつの間にかよびよせた『スパヰ甲冑』と呼ばれる影朧甲冑の一種の高機動型の影朧兵器に乗り込み、皆さんを撃破しようと戦いを挑んでkます。
これを皆さんは撃破し、スパヰを官憲に突き出しましょう。
沢山捕まえれば、幻朧戦線を追い詰める手かがりとなることは確実です。
また捕らえたスパヰたちに関しては、帝都は政治的な都合により、彼らを送り込んだ国や都市をおおっぴらに咎めることはしません。
今回皆さんは、スパヰを捕らえることに注力して頂くことになります。
それでは、幻朧桜舞い散るサクラミラージュでの猟兵の戦いを綴る一片となれますように、いっぱいがんばります!
第1章 日常
『香煙を薫らせて』
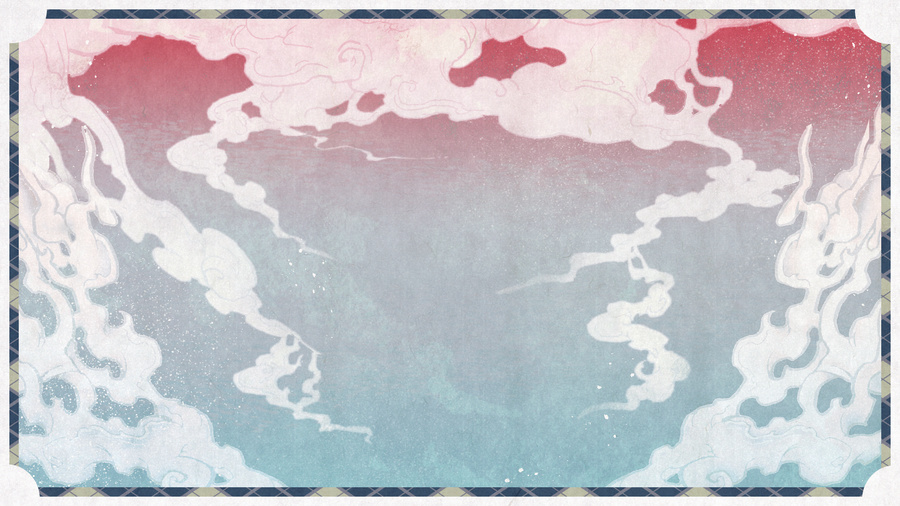
|
POW : 元気の出る香りを楽しむ
SPD : リラックスする香りを楽しむ
WIZ : ロマンチックな香りを楽しむ
イラスト:樫か
|
種別『日常』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
いわゆるフレグランスショップ。
それが『香百貨』である。そこには香水やお香だけでなく、香木、香り袋、焚き染めた布など、香りにまつわるものが取り揃えられていた。
そんな場所で如何にしてスパヰたちは情報交換をするだろうか。
まさか大声で言う訳はないだろう。
例えば暗号。商品名の羅列から読み取れるような会話であったり。
例えば特定の組み合わせの香りで暗号を送ったり。
想像しないような手法でもってスパヰたちは、互いの持つ情報をやり取りするだろう。
客の男だけとは限らない。
見目麗しい女性であるかもしれないし、店側の人間もまたスパヰであるかもしれない。
スパヰ大国となった帝都において、日常のどこにでもスパヰは潜んでいる。例え今、この『香百貨』が香りを楽しむ店であっても一枚めくればそこは、スパヰだらけであるかもしれないのだ。
ならば逆もまた然りである。
一般の客と見せかけて、猟兵が訪れてもなんの違和感もない。隠されているが故に、拒むことはできないのだ。拒めば、そこが後ろ暗いことをしている場所とさらけ出すものであるがゆえに。
様々な香り立つ店内のどこかにいるであろうスパヰ。その痕跡を見つけ、突きつけ、彼らを追い詰めなければ平穏を生きる人々を危険に晒すことになる。
それが幻朧戦線に加担しているスパヰを探す理由であった―――。
 アレクサンドル・バジル
アレクサンドル・バジル
スパヰね。ノーヒントってのは泣けてくるが……
とりあえず店内で会話をしている奴等をチェック。
(客、業者、店員問わず)
あーいう奴等は暗号で会話してるとしても周囲に気を配っているはず。
それが片方ならともかく両方なら怪しさ満点だ。
そういう奴等がいないかさりげなく観察。(第六感×見切り)
いれば感づかれない程度に近づいて会話を聞き、暗号のパターンを見切る
(目立たない×見切り×学習力)
まあ、それはかまをかけれる程度で良い。
ある程度、把握でき確信したら声掛け。
(覚えた暗号で重要そうな単語を述べ)……のことはばれてるぜ。よお、スパヰさん。『幻朧戦線』はやり過ぎだったな。(全部バレバレだという態度で)
一歩店内に足を踏み入れると、そこは様々な香りが充満する世界であった。
世界各国から集められ、選りすぐりのものばかりを陳列した戸棚はボトルの形やラベル、色などから人の目を楽しませてくれる。
『香百貨』。それがこの店の名前であり、帝都では名の知られたフレグランスショップだ。そんなフレグランスショップに訪れる大勢の客たちは、殆どが一般人であろう。
けれど、そこには確かにスパヰ同士でなければ見落としてしまうように些細な痕跡で溢れている。
そう、分かるものにしかわからない。そのような暗号があちらこちらに散りばめられているのだ。
「……さて、どうしたもんだか」
そんな『香百貨』に足を踏み入れたのは褐色の肌を持つ偉丈夫であった。すらりと伸びた足、けれど鍛えられた上半身は店内にいたご婦人方の瞳を輝かせるには十分過ぎる魅力であったことだろう。
けれど、その視線を集める主であるアレクサンドル・バジル(黒炎・f28861)は内心、スパヰを探し出すことに対して骨が折れそうな事件であることをすでに感じていた。
スパヰ。
それは世界各国から、このサクラミラージュの帝都に集まった者たちである。
不死の帝によって世界統一は為されているものの、その中でもやはり隣の芝生は青く見えるものである。
隣地とよりも優れた立ち位置を望む者がいないはずがない。
故に帝都は様々な国から他者より情報の領域で優位に立とうと送り込まれたスパヰで溢れかえっている。
そんな中に『幻朧戦線』に影朧兵器を提供している組織に属する者がいるのだ。
ただ、このフレグランスショップ『香百貨』にスパヰたちが情報交換に集まってくる、という情報しか得られていないのだ。
それはノーヒントであると言ってもよかった。
「とはいえ、何もやらないという選択肢はないわな……」
スパヰというものは、自分が得たい情報を得るまで、その場にとどまるものであろうし、まったくの無言でいることもしないだろう。
こんな場所で黙りこくっている方が怪しい。
「何かお探しでしょうか?」
そう言って思案するアレクサンドルの姿は、きっと誰かに贈り物をしようと悩んでいるようにも見えたのだろう。店員の一人が彼に話しかけてくる。
「ああ、ちょうど贈り物を考えていてな。何かおすすめはあるかい?」
店員とのやり取りをしながら、さりげなくアレクサンドルは周囲を見回す。
スパヰというくらいである。誰かと会話をしているとしても周囲に気を配るものだ。
それが店員と客、両方が気を配っているのであれば怪しさは満点である。アレクサンドルが商品を見ようと近づいた時、無用の警戒をしたものが一番怪しい。
「ああ、いや、少し考えさせてくれ。商品をもう少し見てみたい」
アレクサンドルは狙いをつけて、店員から離れる。
店員と会話をしている客。
その一組に当たりをつけて、会話に耳を澄ませる。
「女房に言われたよ。どこか女の『影』があるんじゃないかってね。そんなことないよと言ったのだが、取り合ってもらえない」
「ああ、なるほど。それでご機嫌取りにというわけですか。旦那さんは大変ですね」
なんてことない会話である。
けれど、そこにアレクサンドルは目星をつける。
いちいち、そんなことを一店員に言うだろうか。彼らの会話を聞いていると在る一種のパターンが見える。
言葉のイントネーションが鈍る瞬間があるのだ。その言葉をつなげて、言葉の意味や言語を変えていくと浮かび上がる。
―――『影朧兵器』。
「なるほどな。香水の名前と、それに付随する話題が符丁になってるのか―――」
確信を持ってアレクサンドルは客側の人間に声をかける。
それは他の誰にも届かないような、小さな声であったが、スパヰであれば見逃すわけもない。
びくりと動揺が走る店員と客。
彼らを前にしてアレクサンドルは自信たっぷりに、彼らの行いを見透かしていると言わんばかりに言う。
「―――全部バレてるぜ。よお、スパヰさん。『幻朧戦線』はやりすぎだったな」
店内がピリと嫌な空気が走る。
それはほぼ同時に起こっていた。他の猟兵達もまた、別のスパヰを発見した瞬間であったのだろう。
奇しくも同じタイミングで起こったそれは、これから引き起こされる騒動のはじまりにすぎないのだった―――。
成功
🔵🔵🔴
 馬県・義透
馬県・義透
四人で一人の複合型悪霊。生前は戦友。
第一『疾き者』のほほん唯一忍者
一人称:私/私たち
どの世界でも変わりませんねー、そういうの。
私も故郷じゃ似たようなものですしー。
こういうのって、会話だけではないですよねー。久々に『視覚』も使いますかー。
(常に目閉じな人格。笑顔は崩さない)
人々には気を配りましてー。
本来ならば、商品というのは規則正しく置いてあるもの。
なのに、混ざって置いてある場合、暗号になってる場合がありますから。
…選んでいるように見せかけて、並べかえるのは簡単ですしね?
把握できたら、穏やかに声をかけてみましょうか。
おやおやまあまあ、バレてますよー?
スパヰ。それは諜報を行うものであり、世界統一が為された世界にあっては必要無さそうな存在であったことだろう。
だが、不死の帝によって統一された世界であっても未だ人類は一枚岩になりきれていなかった。
隣の芝生は青く見える。
帝都に近ければ近いほどに世界での立場は上のものになる。どれだけ世界が平和になっても、その平穏の水面下で誰かよりも上になりたい、誰かよりも優れていたい、そう願い者はいなくならない。
それ故に各国、都市は帝都にスパヰを送り込み続ける。
誰かよりも、より良くあるために。
「どの世界でも変わりませんねー、そういうの」
馬県・義透(多重人格者の悪霊・f28057)は、説明を聞いた時、そんな風に思ったのだ。彼は悪霊であるが、元々四人の人間が死した後に一つの体となって現れた存在であり猟兵である。
そんな一人格『疾き者』である人格は生前忍者であったものだから、あまり強く言えないのだが、それでも故郷でスパヰと似たような事をしていたことから、彼の経験は今回の事件に置いて非常に役立つことであった。
フレグランスショップである『香百貨』はすでに多数のスパヰたちが入り込んでいる。一般客たちも多数いるが、それでも義透にはわかるのだ。
同じ穴のムジナがいると。
聞こえてくる会話。
その会話の断片に気がついた猟兵もいるようであった。そちらは任せることにして、うむ、と頷く。
「お客様、何かお探しですか?」
店員が声を掛けてくるのを笑顔のまま義透は制する。
「はい、ですが、少し商品を拝見させて頂いてよろしいか?」
それはもちろん、と彼の只者ならぬ雰囲気と人の良い笑顔に店員は離れていく。
無用に事を荒立てるのは得策ではない。
特にこの場にいるスパヰが一人ではない以上、下手に事を荒立ててしまえば、他のスパヰたちを逃がす口実になってしまう。
「こういうのは気取られぬように」
そう、それがスマートな立ち振舞であり、忍びとしての本分だ。
彼の目は閉じられているように細くなっているが、商品棚の陳列、その配置に目をつける。
「本来であれば、商売柄……商品は規則正しく置いてあるもの。例えば、製造日、香りの種類……それこそ、商品が多いのであれば、項目ごとに……」
それは店を営む側からもそうであるが、買い求める客の側から見ても助かることであった。
だが、義透が目をつけた商品棚は違う。
そう、その商品棚に置いてあるのは香水だけでなく、香木や香り袋など、どう見ても雑多な種類が並べられている。
それも店側が売りたいものであると、人気の商品であるとかは関係がない。
「なるほど……」
ずさんなやり方だと義透は微かに頷く。
一般人であれば疑問に思わないだろうが、こちらもまたその道の者である。気が付かないわけがない。
そう、混ざって商品が置いてあるということはそこに規則性があり、誰かに何かを伝えようとする意図があるものだ。
目の前の商品棚一つが暗号になっていることを義透は見抜いたのだ。
さ、と素早い手業でもって義透がは商品棚の位置を入れ替え、場所を移す。
早々に一人の客が義透が並べ替えた商品棚の前で小首をかしげる。暗号がわけのわからない文言に変わっている事に気がついたのだ。
ということは―――。
「おやおやまあまあ、バレてますよー?」
いつのまにか、その客の背後に立っている義透。
その声は穏やかな声色であったが、有無を言わさぬものであり、その圧は同じ道に生きるスパヰをして背筋が凍る思いであっただろう。
振り返ることもできない。
けれど、そこに浮かんでいるのはにこやかな笑顔を崩さぬ忍びの者―――義透。
すでに他の場所でも猟兵がスパヰを見つけ出しているようだ。
ここからが本番だと義透は追い詰めたスパヰを背後から、細めたまぶたの奥から見据えるのであった―――。
成功
🔵🔵🔴
 久瀬・了介
久瀬・了介
力だけで倒せるのは雑魚だけだ。奴らの奥深くに斬り込むには地道な調査が必要。
スパヰとやらを追えばいいんだな。心得た。
店を見て回る。確かに落ち着く香りだ。ささくれだった心が和やかになっていく…即ち俺にとっては毒だ。ここはまずい、長居は出来ない。
怨敵を探る怨霊としての超感覚を振り絞る。不自然な点は無いか…。あそこの客同士。読んでいたパンフレットをさりげなく交換している。あいつらか。
声をかけ冊子を取り上げる。不審な書き込みは…無い。誤解か。謝るか…いや。感覚を全開に。
これは香道…源氏香か。香りの組み合わせを識別する遊び。使い方次第で五十音を表せる。風流な暗号だ。
これが証拠だ。話を聞かせて貰おうか。
戦いとは力と力のぶつかりあいである。
けれど、力とは何も腕っぷしの強さだけで決まるものではない。敵を知り己を知れば百戦殆うからず。そんな言葉がる通り、力とは腕力だけのことを指すものではないことはすでに万人の知るところであろう。
つまるところ、知とは力である。
知ること、情報を共有すること、その力は計り知れなく時として劣勢を覆す一手になりえる。
「力だけで倒せるのは雑魚だけだ。奴らの奥深くに切り込むには地道な調査が必要……」
元軍人である久瀬・了介(デッドマンの悪霊・f29396)に、それを説くのは釈迦に説法というものであろう。
彼は元軍人であるがゆえに、情報の力の持つ意味を正しく理解していた。
「スパヰとやらを追えばいんだな。心得た」
グリモア猟兵からの得た情報から理解は早く、彼もまた素早くフレグランスショップである『香百貨』へと足を運んだ猟兵の一人であった。
店内に入ると彼の嗅覚に様々な香りが殺到する。
なるほど、百貨と看板に掲げるだけのことはある品揃えであった。
「確かに落ち着く香りだ……」
香りとは人の感情や神経に作用するものである。故に人々は癒やしを香りに求めるのである。
花の香り、爽やかな香り、それはら調和すれば人の心をいつまでも癒やすものであろう。
例えそれが悪霊である了介であっても例外はない。
ささくれだった心が和やかになっていく。
それは人にとっては癒やしであったとしても、彼にとっては即ち毒である。彼の心にある復讐心が削られていく。
癒やされるとしたらオブリビオンを殺すことでしか癒せぬ心の痛みや渇きが、この場にいることによって癒やされていくような気がした。
「ここは、まずい……長居できない」
思い出せ。
己を突き動かす『魂の衝動』を。怨敵を。
振り絞るようにして超感覚をもって、周囲を探る。不自然な点。
「―――」
あれか、と了介の瞳が捕らえたのは、店内に在るパンフレットを何度も手にとっては別の場所に入れ替えている男たち。
さり気なく、自然な振る舞いでそうしているのだろうが、超感覚を持つ了介にとっては、不自然極まりない動き方だった。
「おい―――、あんた」
了介が声をかけ、冊子を取り上げる。
男たちは突然のことに驚いたように互いに顔を見合わせる。一体何が起こっているのかわからない。何故、自分が了介に咎められたのかわらかないという顔をしている。
「……誤解か。すまな―――」
違う。パンフレットに不審な書き込みはない。
いや、違う。パンフレット自体は香道の案内だ。入門のような、初めて見る者にもわかりやすく例示しているような、そんなパンフレット。
縦線が引いてあるような、そんな記号めいたものが幾つも並んでいる。
「これは香道……源氏香か」
そう、香りの組み合わせを識別する遊び。
その並びを見ればわかる。意図的にずらされていたり、意味のない空欄が設けられていたり。パンフレットはどれも違う図式を示している。
―――ということは。
「なるほどな。五十音順を現しているのか。道理で、何度もパンフレットを手にとっては戻していたというわけか。風流な暗号だ」
なあ、スパヰ。
了介の唇が、その言葉を刻んだ瞬間、彼らの表情が崩れる。
それは突然のことに驚いたという表情の演技。それが崩れた瞬間、その動かぬ証拠を持って、彼らがスパヰであることを証明するもようなものだった。
「話を聞かせてもらおうか」
そう言った瞬間、店内に不穏な空気が流れる。
他の猟兵達もスパヰを見つけたのだろう。追い詰められた彼が次に起こす行動は―――。
大成功
🔵🔵🔵
 メンカル・プルモーサ
メンカル・プルモーサ
なるほど、香りを使った暗号ね…問題は暗号の内容では無く……誰が暗号のやりとりをしているか、だな…
…香りって言うのは案外慣れて麻痺しやすいんだよね…それを情報のやりとりに使っているとすれば…
定期的に嗅覚をリセットしているはず…自分の臭いや珈琲の臭いが有効らしいからそう言った匂い袋を持っていたり、頻繁に自分の体臭を嗅いでいる人間かな?
それを行っている人物に目星を付けて……その人物が1人になったところを狙って【想い溢れる怪硬貨】を仕掛けよう……
そうすれば心の声はだだ漏れになるから……後は問い詰めれば心の声が答えてくれるだろうね…
香りとは常に言葉以上に人の感情を示すものである。
人が生物である以上、無味無臭であることはない。汗腺の働きにより、その時々で感情から発露する物質は変わる。
故に冷や汗であったり脂汗であったりと、人間は人間が自覚する以上に匂いに対して敏感であり、それを表現する機能が備わっている。
そして、香水とはそうしたものを隠すために必要なものでもあった。
ならば、スパヰたちにとって香水とは必須なるものであったのかもしれない。
メンカル・プルモーサ(トリニティ・ウィッチ・f08301)は、フレグランスショップ『香百貨』に足を踏み入れる。
「なるほど、香りを使った暗号ね……問題は暗号の内容ではなく……誰が暗号のやりとりをしているか、だな……」
今回の事件の肝はそこである。
スパヰが居る事自体、スパイ大国であるサクラミラージュの帝都は、珍しいことではない。当然、その得た情報というものに価値があるのは間違いないが、世界を渡り歩き過去の化身を討つ目的を持つ猟兵にとっては、その情報事態にそこまで価値はない。
だからこそ、これまで猟兵たちとスパヰの間には特に接点はなかったのだ。
けれど、『幻朧戦線』とやりとりをしているスパヰがいて、彼らが影朧兵器を提供している組織とつながっているのであれば話は別だ。
「香りって言うのは案外慣れて麻痺しやすいんだよね……それを情報のやり取りに使っているとすれば……」
匂いとは慣れてしまう情報である。
常に脳が識別しつづければ、それは脳への負荷となり、感じなくていい香りとして認識されて意図的に人間の脳が感じなくなってしまう。
だが、それを回避する術もまた存在するのだ。
メンカルは周囲を見回す。
香りが情報のやり取りとして重要なファクターであるのならば、それを定期的にリセットする必要がある。
そして、そのリセット行為をしても、店内に在って誰にも咎められることない仕草や行動でなければならない、とするならば……。
「そう、必ずそうする」
彼女の瞳が捉えたのは一人の女性客。
女性にしては珍しく受付で店員にコーヒーを頼んでおり、時折匂い袋などを確認している。
それは頻繁、と言っていいほどに行われている。
暗号が香りの組み合わせとして使われているのであれば、納得の行動である。暗号の内容を確認するために何度も何度もリセットを行っているのだ。
「心見の怪異よ、読め、語れ。汝は感応、何は伝播。魔女が望むは想い見透かす心の魔」
店員が女性の元を離れた瞬間を狙って、メンカルは女性の背中に妖怪『サトリ』の描かれたメダルを貼り付ける。
それこそがメンカルのユーベルコード、想い溢れる怪硬貨(マインド・リーク)。
どれだけ強靭な精神力で持って、尋問や拷問を受けても口を割らぬスパヰであったとしても、そのユーベルコードに対抗する術はない。
『影朧兵器……すでに用意されているということね。ということは、どこからか桜學府に情報が漏れた? いいえ、幻朧戦線と言えど、自爆覚悟の連中のやることだから口を割ることはないでしょうに……』
それは決定的な証拠であった。
女性は目を丸くして周囲を見回す。
「私の声が聞こえる……!?」
それは動かぬ証拠であった。直前まで受け取っていた暗号の内容を心の中で整理していたのだろう。思考が柔軟で、即座に行動するために必要な訓練を受けけていたスパヰであるからこその落ち度。
振り返った彼女が見たのは、メンカルの冷静な瞳であった。
全て見透かしている。今は妖怪メダルの力で、心の中の声が漏れ続けてしまう。だからこそ、メンカルは言うのだ。
「貴方がスパヰ。幻朧戦線に影朧兵器を提供している組織の一員」
女性の背中に貼り付けられたメダルから次々と声が漏れてくる。
どうしようもないほどに動揺した声色のまま、女性スパヰは席を立つ。メンカルと対峙し、今から逃げるべきか、それともメンカルの口を封じるか。
それすらも全て妖怪メダルから漏れ出てしまい、判断が遅れた次の瞬間、店内に不穏な空気が流れ、ピリつく。
それが他の猟兵達もまたスパヰを見つけ出した証拠であり、彼らが次にどう出るかを知らしめていた。
つまるところ。
『―――逃げおおせなければ。逃走ルートは―――」
大成功
🔵🔵🔵
 ミネルバ・レストー
ミネルバ・レストー
幻朧戦線に加担する連中がいるとはね、予想できなくはなかったけど…
めんどくさいのは御免だけど、さすがに放ってはおけないわ
スパヰが一人じゃない、組織で行動してるってのはありがたい情報ね
となると、スパヰだけじゃなくて協力者――情報屋がペアで存在する
店舗を堂々と構えるのは情報屋、拠点にして文字通り情報を集める
スパヰが複数いたとしても、客を装って容易に出入りができるでしょ?
そう目星をつけて、客のフリで入店してしばらくお香を選ぶわね
店主の挙動に特に注意を払いましょ、誰かとやり取りをしてないか
でなければ会話に不自然なところがないか「情報収集」よ
機を見て手に取る香がわたしに似合うか、割り込んで聞いてみるわ
サクラミラージュは平和な世界だ。
影朧による事件はあれど、それらは救済することが叶う弱いオブリビオンでしかない。人々は安寧の日々を送り、平和な時間は文化を育む。
様々な文化が花開き、それを甘受する人々の心は豊かに、そして複雑になっていく。 けれど、不死の帝が統一した世界であったとしても、それは世界の中心たる帝都が最も栄えている事に変わりはない。
最も栄えているということは、栄えていない場所もあるということだ。
だからこそ、もっと、と願ってしまうのは人の性であろう。もっと優れた場所で、もっと優雅な暮らしを、もっと、もっと。その際限ない願いは願いから執着、そして妄執へと変わっていく。
スパヰは、そんな他の国々や都市から送り込まれた間諜である。
自国に有利になるような情報を帝都から引き出し齎す。他者よりも、もっとという願いのままに人々は暗躍する。
そんなスパヰ大国である帝都は、幻朧戦線と呼ばれる者たちによって、その安寧事態を脅かされているのだ。
「幻朧戦線に加担する連中がいるとはね。予想できなくはなかったけど……」
もしくは、幻朧戦線そのものを作り上げた存在があるのかもしれない。
それくらいのことは予想できた。
人はいつだって隣の芝生は青く見えるものであるのだから、とミネルバ・レストー(桜隠し・f23814)は、桜色の髪を揺らしてため息をついた。
どれだけ平穏な世界であっても、いざこざの種は尽きないものだ。
「めんどくさいのは御免だけど、流石に放ってはおけないわ」
そこが彼女の美徳であろう。
人はツンデレとか呼ぶかも知れないけれど、彼女にとってはそれだけで動くには十分な理由だったのだ。
「スパヰがひとりじゃない、組織で行動してるのってのは有り難い情報ね……」
となると、スパヰだけではなく協力者―――情報屋がペアで存在するはずだ。その場として設けられたのがフレグランスショップ『香百貨』だ。
なるほど、よく考えたものであるとミネルバは溜息をつく。何度目だろうかと思うほどであったが、それで踵を返すほどでもない。
店舗を堂々と構える情報屋が拠点として文字通り情報を集める。
数多のスパヰたちが集まるのであれば、そこは即ち情報の坩堝であろう。様々な情報が飛び交い、そこに在る情報全てが情報屋に齎される。
後はそれを扱えば、商売としては上々であろうというものだ。
「さて、なら話は簡単よね」
ミネルバは優雅な足取りで店内に入る。
スパヰが店に入ることができるというのであれば、猟兵である彼女もまた自由に出入りができるということだ。
すでに目星は付いている。
男性。それも身なりの良い男性だ。何も言われなければ、どこかの大企業の役員だとか、そういった身分の高い男性であると思う立ち振舞。
何やら店主が奥から出てきて、何事かをつぶやきあっている。上客、ということもあるのだろう。
けれど、ミネルバの瞳は、『それ』を見逃さなかった。
紙幣を手渡している。そして、その紙幣の裏に隠されたものも、ミネルバは見つけていたのだ。
「―――……迂闊ね」
他の人間であれば知覚することもできないような小さな動きであった。
けれど、猟兵にはそれも通用しない。ミネルバは軽い足取りで彼らへと向かう。店主が香水のラベルを見せている。
割り込むなら今しかない。
「あら、おじさま。それ、わたしにも見せてくださらない?」
ひょい、と店主から男性へと手渡されそうになった香水を横からミネルバが手を伸ばし取り上げる。
「素敵な香り。わたしに似合うかしら?」
可憐な少女が香水を手に取る姿は、コマーシャルの一場面のように美麗に映ったことだろう。
それにあっけに取られた彼らを尻目にミネルバは香水のラベルに仕込まれていた暗号を目ざとく見つける。
「―――これ、暗号ね? 『幻朧戦線』。この名前に聞き覚え、あるわよね?」
くるりと香水の瓶を裏返す。
しゅ、と音を立ててミネルバの指先に香水が吹き付けられ、その香水の付着した指先でラベルをなぞると浮き上がる文字。
確かに『幻朧戦線』の文字が浮かび上がり、それこそが男性と店主がスパヰと情報屋の間柄であることを示す決定的な証拠となって、彼らに突きつけられるのであった―――。
大成功
🔵🔵🔵
第2章 冒険
『矢弾が降ろうと槍が降ろうと』

|
POW : 罠を力ずくで破壊する、わざと罠にかかって仲間を守る
SPD : 紙一重で発動した罠を回避する、器用に罠を解除する
WIZ : 罠の配置を予測し、罠のありそうな場所を避けて進む
|
種別『冒険』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
スパヰの決定的な証拠を突きつけられた者たちは、一様に動揺したのかもしれない。
これまで日常に上手く潜んでいたからこそ、彼らは己たちの諜報能力に自信を持っていた。
けれど、それは猟兵には通用しない。
一瞬でそれを判断したことは褒めてもいいだろう。彼らは証拠を突きつけられた瞬間、それぞれが店外へと駆け出し、逃走する。
ただの人間が走って逃げたところで、生命の埒外にある猟兵から逃げられるわけもない。
だが、彼らには逃げる算段があったのだ。
こんなときのために、と用意された逃走ルート。逃げる彼らを追いかける猟兵達を阻むのは圧倒的な量の罠であった。
道をゆけば、あらゆる場所から火器が除き、催涙弾や煙幕弾が放たれる。
ときにそれは往来を往く人々を巻き込んでしまうかも知れない。
さらに手はず通りに荒くれ者達が小道の脇から飛び出し妨害する。人である必要もなく、時には車が飛び出してくることもあるのだ。
さらには袋小路に追い詰めたと思った瞬間、壁がぐるりと回ってスパヰが逃げおおせる場面もあるだろう。
けれど、猟兵は諦めない。
必ず彼らを捕まえ、『幻朧戦線』との繋がりを掴まなければならない。
これ以上、彼らの歪んだ思想の果に起こるテロ行為によって人々の安寧が脅かされぬために―――!
 馬県・義透
馬県・義透
四人で一人の複合型悪霊。
引き続き『疾き者』。
顔は覚えましたし、外へと逃走。好都合ですねー。
【それは陰のように】を使用しての追跡。人って、上を気にしないんですよね。これカラスですし。
私を一人だとは思わないことです。
地縛鎖での索敵と情報を行って、罠をできるだけ回避。
侵す者「右上に火器だの」(豪快古風)
不動なる者「その先の壁がどんでん返しか」(古風)
静かなる者「その道には車がいますね」(冷静沈着)
銃口に漆黒風でも投擲しておきますかー。
他の三人は、私と違って武士ですけれど、頼もしい戦友ですから。
なにより、平和を乱すのを許さない、というのは共通してますからねー。
※なお、三人とも『疾き者』より年下。
猟兵達によって証拠を突きつけられたスパヰたちは、皆一様に店内から外へと飛び出す。
彼らにとって自分たちが捕まることこそが、最も恐るべきことである。捕まってしまえば、情報を持ち帰るどころか、自分を送り出した国や都市にとっても都合の悪いことばかりである。
帝都は政治的な理由でスパヰたちをおおっぴらに断罪することはないが、それでも外交上の問題としてしこりを遺すことだけは避けたい。
故にスパヰは捕まってはならないのだ。
すでに逃走ルートは幾つも用意されている。
もちろん罠だってそうだ。こういう時があってはならないのだが、不測の事態とはいつだって起こり得るものだ。
「くそっ―――! あの店は完全中立じゃなかったのか!」
言わば、あのフレグランスショップはスパヰサロンとも言うべき場所だったのだ。
各国のスパヰたちが集いこそすれ、そこは絶対中立であるがゆえに、咎められることのできない安全な情報交換の場だったのだ。
けれど、それは猟兵たちの登場に寄って終わりを告げる。
「顔は覚えましたし、外へ逃走。好都合ですねー」
馬県・義透(多重人格者の悪霊・f28057)は、スパヰたちが逃走しても余裕のままであった。
むしろ好都合であるとも言えるほどに、彼の中の一人格『疾き者』は、細めた目のまま微笑んだ。
「人って、上を気にしないんですよね」
それは陰のように(シリガタキコトカゲノゴトク)ぴったりと逃走するスパヰの背中を追い続ける霊力でできた4羽のカラスであった。
極めて発見されにくい上に、義透と語感を共有しているがゆえに、スパヰを見失うことはない。
「これ、カラスですし。かと言って―――私を一人だとは思わないことです」
今、義透の体は地縛鎖によって大地の霊力と接続され、空から索敵するカラスの情報と大地を踏みしめるスパヰたちの動向を同時に処理しているのである。
それは本来一人の人間であれば処理しきれぬ程の情報の量であったが、義透は違う。彼は、否、彼らは4つで1つの複合悪霊である。
この程度の情報など4分割されているのと同じである。
「右上に火器だの」
義透が飛来する催涙弾を全て躱し、駆け抜ける。『侵す者』の豪快古風なる声が頭の中に響く。
踏み込んだ先にあったのは、壁が迫りくる光景。
「その先の壁がどんでん返しか」
『不動なる者』が、その一手先を読み切って、身を翻す。カラスの一羽がけたたましく無き、躱した先に突っ込んでくる車体を警告する。
「わかっていれば簡単なことです。その道には車が突っ込んできますね」
『静かなる者』が冷静に告げ、己達を狙う重火器の存在を知らしめる。
催涙弾や煙幕弾は、猟兵には脅威ではないが、スパヰを取り逃がすことだけは避けたい。
翻った体の勢いのままに棒手裏剣が投げ放たれ、重火器の中で爆発が起こり使用できなくなる。
これが複合悪霊たる義透の力である。
全てが違う者たちであるがゆえに、あらゆる状況の対処できる。
けれど、彼らの目的は合致していた。
「他の三人は、私と違って武士ですけれど、頼もしい戦友ですから。なにより―――」
その細められた瞳の奥で耀くのは義憤か、それとも強き意志か。
「平和を乱すのを許さない、というのは共通してますからねー」
そう、今のサクラミラージュは水面下で平穏を脅かす者たちが跋扈する状況である。表向きは平和そのものであっても、それを快く思わない者たちがいるのが、現状だ。
ならば、それらを討ち果たすのは、自分たちのような存在であると義透は理解していた。
「人が安心して夜眠れるように、何事もなかったように朝目覚めるように、そんなふうな生活を私達は願っているのですから」
スパヰの逃走ルートに仕掛けられたあらゆる罠を全て回避し、義透は街中を駆け抜けるのであった―――。
大成功
🔵🔵🔵
 アレクサンドル・バジル
アレクサンドル・バジル
さて、花の帝都でキツネ狩りと洒落込むか。
ナイアルテの予知だと罠が仕掛けられてるんだっけか?
あいつらやりたい放題だな。
黄金の魔力で体を覆い、5メートルほど宙に浮いて追跡開始。
(戦闘モードⅠ)
自身への攻撃はオド(オーラ防御)で撥ね退け、一般人を巻き込みそうな火器等には雷(属性攻撃)を放って破壊。
屋内は徒歩で。
壁がぐるりと回って見えなくなったらワンパンで壁破壊。
とまあ、どんどん追い込みますが、徐々に人気のない方向に逃げるように誘導しながら追い込みます。
窮鼠となった時に周りに人がいるとやりにくいので。
頑張れ頑張れ。諦めたらそこで終わっちまうぜ?
(さすがに拠点や仲間のもとには逃げないか)
「さて、花の帝都でキツネ狩りと洒落込むか」
グリモア猟兵の予知の情報で逃走ルートに罠が仕掛けられていることは、アレクサンドル・バジル(黒炎・f28861)たち猟兵に共有されている情報である。
罠とは本来予期せぬ場所に仕掛けられているからこそ、その威力を最大に発揮するものであるが、罠があるとわかっている以上、その効果は減ずるものである。
「あいつらやりたい放題だな……」
すでに先行した猟兵が追跡したスパヰが仕掛けた罠は、催涙弾や煙幕弾、壁がひっくり返ったり、ならず者を雇った当たり屋やら、もはやこの帝都が平穏であるとはいい難いほどにあちらこちらに凄まじい量の罠が仕掛けられていた。
だが、アレクサンドルが臆する理由など何処にもない。あろうはずがないのだ。
戦闘モード Ⅰ(ディアボルス・ウーヌム)。
アレクサンドルの体を黄金の魔力が覆っていく。それは神たる身であるアレクサンドルにとっては、準備運動のようなものであった。
その場で軽く跳躍する。
身体が軽いと感じるよりも、本来の力に戻っていると言ったほうがしっくりくるほどの力の高まり。
次の瞬間、アレクサンドルの身体が宙に飛ぶ。建物を飛び越え、その金色の瞳が捕らえるのは別の逃走ルートをひた走るスパヰの姿。
「さあ、窮鼠猫を噛むか、それとも蛇が出るかわからねーが……俺から逃げられると思うなよ」
アレクサンドルが空を疾駆する。
その姿は金の流星の如き姿であり、彼の姿を捉えた逃げるスパヰは驚愕した。その姿はあまりにも圧倒的であり、罠の全てが無意味であると悟るには十分すぎる威容であったからだ。
「ば、ばかな―――! 桜學府の連中、超弩級戦力を持ち出したっていうのか!」
サクラミラージュにおいて、猟兵とはユーベルコヲド使いとは一線を画する力を持つ存在として認知されている。
アレクサンドルのその力を持ってして、スパヰは悟ったのだ。
けれど、逃亡することは止められない。例え、超弩級戦力であったとしても、待ち受ける罠全てを持ち出せば、足止めくらいは叶うであろうと踏んだのだ。
「おーおー……重火器を使わないのは関心なこった。だが、よぉ……催涙弾や煙幕弾は後を片すのが大変なんだよ。一般人を巻き込むわけにはいかねーからな!」
雷撃が飛び、重火器が弾け飛ぶ。
破片が飛び、そのさなかをアレクサンドルが駆け抜ける。短い悲鳴を上げながら、スパヰが袋小路の先にある壁を作動し、ぐるりとまわって姿を消すが、その壁など在ってないがごとく、アレクサンドルは拳で持ってぶち破るのだ。
「め、めちゃくちゃだ……!」
「頑張れ頑張れ。諦めたらそこで終わっちまうぜ?」
如何なる障害も、罠もアレクサンドルには関係がない。どれだけ自分に罠が降りかかろうとも、拳の1つで全てを踏破することができる。
強者の余裕、傲慢と言えばいいのだろうか。
だが、それは否である。
一見豪快に見える行動であっても、アレクサンドルは全ての罠を自分に集中させ、周囲への被害を引き起こさないようにしていた。
それすらも彼にとっては当たり前のことで、為して当然ことだ。そこに善意や悪意といったものは介在しない。
できるからしている。
ただそれだけのことなのだ。
「く―――っ! かくなる上は!」
スパヰがまだ諦めずに逃走する。それを無理矢理に捕まえることをアレクサンドルはしない。
上手く泳がせることができれば、拠点や仲間の元へ駆け込むのではないかと思ったのだ。
「―――まあ、そう上手くは事が運ばねぇか……だが、窮鼠が何を見せてくれるのかは、気になった!」
そうしてアレクサンドルは再びスパヰを追跡する。
その先にあるであろう脅威。
それが歯ごたえのあるものであることを、彼は願うばかりであった―――。
大成功
🔵🔵🔵
 久瀬・了介
久瀬・了介
往生際の悪い連中だ。
【雷電】発動。加速して【ダッシュ】し追いかける。
電磁場感応能力…周囲を電磁気で探り、状況や攻撃の予兆を察知する能力を使用。妨害や罠を見切る。
民間人のいる場所で銃を使う訳にはいかない。雷の速度の【早業】で妨害を回避しながら進む。
体に巻いていた呪詛包帯をほどき、伸ばして【ロープワーク】で操る。妨害者を拘束し、銃撃や爆弾で一般人に被害が出ない様に攻撃を逸らす。
建造物が動いて道を塞ぐなら、こちらも奥の手だ。一般人を巻き込まない様に、爆破スイッチで壁を爆破し突破する。怨霊の呪いから逃げられると思うな。
泳がせてアジトまで案内させるのも手だが、町に被害が出続ける。捕えて尋問してみるか。
幻朧桜の花弁が帝都の小道に吹き荒れる。
それはつむじ風が花弁を舞い上げたものであったが、一つの黒き弾丸と化した久瀬・了介(デッドマンの悪霊・f29396)と共に駆け抜ける雷電(ライデン)によって引き起こされたものだった。
彼の速度は即ち雷と同じである。
「あれが、超弩級戦力だとでもいうのか―――! 化け物め!」
逃げ出したスパヰが毒づく。
迫る了介の姿は、彼らにとって脅威そのものであった。圧倒的な速度。
どれだけの妨害を用意したかもわからぬほどに逃走ルートは、了介の行動を阻もうと次々に罠が作動していく。
「遅い」
建物の影から現れる重火器。そこに収められているのは催涙弾や煙幕弾であるが、その尽くが電磁場感応能力によって、躱される。
周囲の電磁気を探ることに寄って、己へと放たれる弾丸の全てを雷の速度の如く加速した身体能力が回避せしめる。
今の了介にとって弾丸ほど意味のないものはない。
「民間人の居る場所で銃を使うわけにはいかない……だが、流れ弾を出す訳にもいかない」
それはデッドマンであるがゆえに為せる芸当であったことだろう。
彼は弾丸を恐れない。
放たれる弾丸の速度は圧倒的であるが、デッドマンである以上、弾丸程度で死ぬことはない。否。既に死んでいるからこそ、弾丸の一つや二つなど意味をなさない。
けれど、生きている人間は別だ。
サクラミラージュには、帝都には生きている人間がいる。
「意味はないと言った」
放たれた弾丸を指の間に挟み込むようにつかみ取り、煙幕や催涙剤が噴出する前に空へと放り投げる。
さらに呪詛包帯が己へと掴みかかってくるならず者たちを目にも留まらぬ速さで縛り上げ、そこらに転がす。
「引っ込んでいることだ。怪我をしたくなければな」
弾丸も、ならず者も、妨害になっていない。
その事実にスパヰは戦慄する。
これが超弩級戦力。桜學府のユーベルコヲド使いなど比にならぬ力。この戦力を持ってスパヰを拘束しようということは、帝都はすでに己達の目的に気がついているのかもしれない。
「こんなところで捕まるわけには―――!」
スパヰはスイッチらしきものをおして、壁が裏返ると同時に通路の先へと逃げ込む。同時に次々と建物が動き、その壁事態を隠してしまう。
「なるほど。それが奥の手か―――ならば、こちらも奥の手だ」
それは祟りの力が込められし爆破スイッチ。
悪霊である了介が持つ『魂の衝動』。それは恨みであり、オブリビオンを赦してはおけぬという怒りであり、また平穏を脅かすものへの憤りであった。
その祟ともいうべき力が次々と壁を爆破していく。
「怨霊の呪いから逃げられると思うな」
凄まじき勢いで壁を破壊し、けれど、繊細にコントールされた爆破は一般人を巻き込まぬように加減がされている。
「泳がせてアジトまで案内させるのも手だが……お前はここで終いだ」
遂に捉えたスパヰの背中。
呪詛包帯を放ち、その身を拘束する。忌々しげな瞳が自分を見上げているが、気にもならない。
「街に被害が出続ける……お前たちの思惑はなんだ。幻朧戦線を使って何をしようとしている―――」
そう尋問しようとした了介だったが、轟音が響き渡る。
それは別の猟兵たちが追っていたスパヰたちが駆け込んだ先であり、了介が捉えたスパヰもまた向かおうとしていた先であった。
「後は官憲に任せよう。俺は―――アレを討つ」
まだ戦いは終わらない。
魂の衝動が赴くままに、了介は稲妻の如く駆け出すのであった―――。
大成功
🔵🔵🔵
 メンカル・プルモーサ
メンカル・プルモーサ
ふむ…予想通り逃げ出したか…後は追いかけるのみ…
まずは箒に乗って…【戯れ巡る祝い風】にて私に有利な偶然を呼び込むよ…
罠使いの知識を用いて相手の移動の仕方、目線などから罠を予測…
予め回避したり…牽制射撃して罠に近寄らせなかったり
…固着術式を込めた弾を術式装填銃【アヌエヌエ】で撃ちだして罠を機能不全に陥らせたり…
発動しても「偶然」私や周囲の人間に被害が及ばなかったりさせよう…
…まあ、延々と追いかければそのうち隠し通路とか使いたがるだろうから…
……隠し通路の入り口の扉を凍らせるなりなんなりで固定化してしまえば袋小路になるね…後は捕まえるのみ…
……ま、何事もなければ、だけど……
逃げ出すスパヰ。
それはある意味で当然の結果であったことだろう。どれだけ動かぬ証拠があったとしても、スパヰ事態を捕らえなければ、元の木阿弥である。
そうなってしまえば、彼らはまた潜伏し再び帝都を混乱に陥れるような諜報活動を行うだろう。
「ふむ……予想道理逃げ出したか……なら、後は追いかけるのみ」
メンカル・プルモーサ(トリニティ・ウィッチ・f08301)にとって、それは予想の範囲の出来事であったがゆえに慌てること無く冷静に飛行術式を刻んだ箒であるリントブルムに跨る。
「遙かなる祝福よ、巡れ、廻れ、汝は瑞祥、汝は僥倖。魔女が望むは蛇の目祓う天の風」
ユーベルコードによって放たれる風が街中を駆け巡っていく。
それはスパヰたちが逃走ルートに選択した道全てに広がっていき、その全てをメンカルに有利な偶然が起こるように改変する凄まじき力。
まさに戯れ巡る祝い風(ブレス・オブ・ゴッデス)のように空飛ぶ箒にまたがったメンカルは罠がひしめく逃走ルートに飛び込んでいく。
「重火器―――……物騒」
建物の影や壁から設置されていた重火器が飛び出し、メンカルを狙う。
それは催涙弾や煙幕弾が装填された重火器であり、メンカルの行動を阻もうとしていた。けれど、固着術式の込められた弾丸の装填された回転式装填銃である『アヌエヌエ』が火を吹いて、その銃口を全て塞ぐ。
「これで重火器は塞がれた……あとは」
箒にまたがって空を飛ぶメンカルを捕まえようと、はした金で雇われたならず者たちが襲い掛かる。
けれど、その全ては今や逃走ルートという逃走ルート全てがメンカルに有利な状況になるようにと改変された空間である。
彼らはメンカルに掴みかかろうとしてゴミ箱に突っ込んだり、側溝に足を取られたり、はたまた唐突に建物窓から落ちてきた植木鉢などに妨害されて、這々の体で逃げ出すしかなかった。
「悪いね、とは思わないけれど……相手が悪かったね」
それは偶然という名の必然である。
メンカルのユーベルコードは、全てメンカルに有利な偶然を引き起こす。
どれだけ偶然に見えても、彼女の道行きにある障害は全て無いに等しい。それにメンカル自身がこうも思っている。
「周囲の人間に被害が及んだりしてはいけないから……」
ならば、彼女に有利な空間において、それは叶えられる必然である。どれだけスパヰが周囲を顧みずに行動したとしても、それは最終的に行われることなく全てが徐々にスパヰ自身を不利な状況へと追い込んでいくのだ。
「くっ―――! なんだんだ、罠が全て作動しないなんてことがあるのか!」
地団駄を踏みたくなるほどに理不尽な結果ばかりがスパヰに降り注ぐ。
壁のスイッチを押して、隠し通路へと逃げ込もうとした瞬間、その壁事態が凍りついた。
背後を振り返れば、そこにあったのは空飛ぶ箒の上に立ち、回転式装填銃『アヌエヌエ』の銃口を向けたメンカルの姿があった。
すでに先手をうち、隠し通路の扉を凍りつかせたのだ。
「……後は捕まえるのみ……」
その静かな瞳が言っている。
これが詰みであると。スパヰは観念したように手を上げる。良い子、とメンカルは微笑むことなく、スパヰを拘束する。
帝都は政治的な都合に寄って彼らや彼らの背後に在る国を断罪することはない。けれど、こうした一歩一歩が実を結んでいくのだ。
「……ま、何事もなければ、だけど……」
だが、そうはならないのが猟兵の戦いである。
目の前に拘束したスパヰが逃げ込もうとした隠し通路の先から轟音が響く。
なるほど、とメンカルは頷く。
思っていても口にするものではないな、と。きっと他の猟兵に追い詰められたスパヰが何かをしでかしたのだろう。
拘束したスパヰを放り出し、メンカルは空飛ぶ箒にまたがり、轟音の元へと飛翔するのだった―――。
大成功
🔵🔵🔵
 ミネルバ・レストー
ミネルバ・レストー
罠を仕掛けたですって、しかも一般人を巻き込むかも知れないのに!?
バカじゃないの、そんな――小細工が通用すると思って?
【Ctrl+C & Ctrl+V】でデジタルデータの分身を召喚
敢えて先を行かせつつ、わたしも「フラワリングドローン」を飛ばして
スパヰが通信機器を使ってるようなら「ハッキング」で盗み聞き
暗号も符牒もわたしたち超弩級戦力にかかれば、ね?
得た情報は分身に都度送って、解除できる罠なら事前にそうして
無理なら回避しましょ、相手が使う抜け道ならわたしたちだって使えるわ
「地形の利用」を逆転の発想で使いましょ、スパヰならどう逃げるか
どう罠を仕掛けるか、予想を立てながら分身と二人挟撃を狙いましょ
フレグランスショップ『香百貨』におけるスパヰを探し出す猟兵たちの目的は達成されつつあった。
だが、スパヰたちは猟兵に決定的な証拠を突きつけられても尚、逃走することを諦めなかった。
そんな中、ミネルバ・レストー(桜隠し・f23814)は自身が証拠を突きつけたスパヰと情報屋である店主を拘束した上で彼らから逃走ルートの仔細を明らかにされていた。
「罠を仕掛けたですって、しかも一般人を巻き込むかも知れないのに!?」
彼女は憤るようにして声を荒げた。
先程までの余裕ある女性としての振る舞いはどこかへ吹っ飛んでしまったようであった。それもそのはずである。
この『香百貨』に潜んでいたスパヰたちはすでに猟兵達に追われ、逃走ルートへと逃げ込んだのだ。それだけならばまだよかったのだ。
しかし、ミネルバが拘束したスパヰは言う。
「あれだけ大量の罠を仕掛けているのだ、周囲の住人たちはひとたまりもないだろうな。自分たちの情報はなんとしてでも持ち替える。それがスパヰというものだからだ」
そのスパヰの言葉にミネルバは嘆息する。
「バカじゃないの、そんな―――小細工が通用すると思って?」
それまで憤っていた表情が不敵なものに変わる。
例えどれだけの罠が用意されていようとも、猟兵が追っているのだ。遅れをとることなどありえない。
そう、不敵に笑ってミネルバは宣言したのだ。
目の前で生み出される分身。それは過去にプレイヤー対プレイヤーのネットゲームにおけるミネルバ……アバター時代のデジタルデータの自分自身を呼び出すユーベルコード。
Ctrl+C & Ctrl+V(コピー・アンド・ペースト)。
現実世界にデータを貼り付ける。現れたもうひとりのミネルバの姿にスパヰは目をむく。
それは桜學府のユーベルコヲド使いをしても足元にも及ばない精度の力であったからだ。
「バックアップは万全なの、データ体ならいくらでも喚べるわ」
「ええ、わたし。いつでもいけるわ」
二人のミネルバが微笑む姿は、スパヰを震撼させた。既に逃げているスパヰが居るとは言え、ミネルバのような力を振るえる存在が多数いるのだとしたら、彼らが逃げ切ることはできようはずもなかったからだ。
「じゃあね、おじさま。もう二度と会うことはないでしょうけど」
「あとは官憲におまかせね」
二人のミネルバが駆け出す。
すでに花の形をしたドローンが先を行く。逃走したスパヰたちを敢えて、先に行かせたのだ。
「スパヰというくらいだから通信機器は持っているわよね……」
「ならハッキングしましょう」
そこからはもうミネルバの独壇場であった。
どれだけ暗号で通信しても、会話しても、符牒も何もかもがミネルバにはガラスケースの中を覗くようなものでしかなかった。
「ここからは二手に分かれましょう。罠は解除できるなら解除しましょう」
「無理なら回避しましょ。相手が使う抜け道ならわたしたちだって使えるわ」
次々と逃走ルートに設置された罠を解除していく二人のミネルバ。
重火器であるのならば、それを作動させる回線を。
道をゆくならず者であるのならば、さっくり無力化を。隠し通路があるというのならば―――。
「逆転の発想でつかいましょ。スパヰならどう逃げるか」
「どう罠を仕掛けるか。予想を立てましょう」
それは平行に行われる思考。
全ての行動に意味がある。スパヰであるのならば当然逃走ルートに無駄があってはならない。ならば、最速最短で目的地にたどり着けるルートは……そう、それすらもミネルバの手の内だ。
二人のミネルバがドローンによって走査した街中の地形とおそらく目的地であろう鉄道の路線。
それを点と点、線が結ぶ先をスパヰは目指している。
「―――、な、何故、ここが……!?」
二人のミネルバが微笑む。
それは圧倒的なまでの戦略と洞察力であった。スパヰたちがやっとの思い出逃げ込んだと思われた倉庫。その背後に立っていたのがミネルバだった。
「あの程度の暗号、符牒もわたしたち超弩級戦力にかかれば、ね?」
「楽勝なのよ? さあ、観念しなさいな」
追い込まれたスパヰたちが歯噛みする。
だが、ここまで着て諦めるわけにはいかない。彼らは意を決し、倉庫の中にある彼らの切り札を起動させる。
即ち―――影朧兵器を!
大成功
🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『スパヰ甲冑』

|
POW : モヲド・零零弐
【マントを翻して高速飛翔形態】に変身し、レベル×100km/hで飛翔しながら、戦場の敵全てに弱い【目からのビーム】を放ち続ける。
SPD : 影朧機関砲
レベル分の1秒で【両腕に装着された機関砲】を発射できる。
WIZ : スパヰ迷彩
自身と自身の装備、【搭乗している】対象1体が透明になる。ただし解除するまで毎秒疲労する。物音や体温は消せない。
イラスト:8mix
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠山田・二十五郎」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
「ここまで来たというのに……諦めてなるものか! 我らの悲願のため! 我らのために!」
スパヰたちは追い詰められ、一機の影朧兵器―――高機動型影朧甲冑『スパヰ甲冑』へと乗り込む。
半数のスパヰたちは猟兵たちに拘束されたが、この『スパヰ甲冑』で助け出せばいい。その後で逃げおおせることができれば、今までの失態も取り戻せるだろう。
影朧兵器の瞳に光が灯る。
その動きはこれまで猟兵たちが出会ってきた影朧甲冑とはシルエットが違っていた。すらりとした体躯。それは言うまでもなく、これまでの影朧甲冑とは違い、速度を重視した形であることは想像に難くない。
「これならば、超弩級戦力と言えど―――! 何するものぞ!」
 久瀬・了介
久瀬・了介
これが奴等の切り札か。
市街地に出すとどれだけの被害が出るか分からない。ここで破壊する。
迷彩で透明化されたら、怨霊の目で強化された感覚で位置を探る。【聞き耳】を凝らし、物音や駆動音を探る。
敵もスパヰ。隠密活動のプロだ。自兵器の弱点を把握し、別の騒音で気配を隠す等の対策を取っているかもしれない。
その場合は、嗅覚に集中する。貴様達が先程までいた香料店の香りを消す暇は無かっただろう。香気で居場所を探る。
そこか。【天変地異】発動。ヴォルテックエンジンの高圧電流を暴走させ放電、「雷」属性の「激流」を放つ。
対象が見えてはいないが、機械の類なら電流を呼び寄せるだろう。頼みの兵器だった様だが相手が悪かったな。
高機動型影朧甲冑―――『スパヰ甲冑』。
それこそが逃走したスパヰたちが用意していた奥の手であり、切り札である。この強力なる影朧兵器であるのであれば、ユーベルコヲド使いと言えどひとたまりもない。
「我らはこのまま逃げ切ってみせる。必ずや情報を持ち帰るのだ!」
乗り込んだスパヰが叫ぶ。
それはどれだけ世界が平和になったとしても、人が人として存在し、社会を形成する以上切って捨てられるべき存在を示していた。
他の誰かよりも優れた立ち位置にいたい、良い生活がしたい。
それはある意味で生命として当然のことであったことだろう。けれど、久瀬・了介(デッドマンの悪霊・f29396)はそれを否定する。
「これが奴らの切り札か」
見上げる先にある影朧甲冑。
その威容は確かに切り札というのに相応しいものであったことだろう。これまで猟兵たちが対峙してきた影朧甲冑と似たフォルムでありながら、その機能はまったく違うものであった。
「『スパヰ甲冑』の力、思い知るがいい!」
ゆらりと『スパヰ甲冑』の姿が揺らめき、周囲の景色と透過していく。それは、了介の強化された怨霊の瞳であっても捕らえることのできないほどの完全なる透明化であった。
「なるほど、切り札というだけはあるな。完全なる透明化……視覚情報に頼り切っていては、捉えることは叶わないか……ならば」
完全に物音や駆動音までは消すことはできない。
体温もまた同じである。だが、まったく見えない透明化というのは、それだけで脅威である。
こちらの攻撃を当てるのが難しいだけではなく、相手の攻撃の動線もまた見極めることができないのだ。
「物音を拾おうするか、当然だな。だが、その程度のこと、対策を打っていないと思うか!」
反響する駆動音が倉庫内に響き渡る。指向を乱雑にした音が耳を塗りつぶすように響き渡る。これでは音がしたからといって、正確性を欠く。
了介の周囲を甲冑とは思えぬ速度の物体が飛び回っているのがわかる。ただそれだけだ。
「スパヰ。隠密行動のプロ……だが、その香りまでは消す暇もなかったようだな。俺は覚えているぞ。その香りを―――」
視覚、聴覚に頼ることができないというのならば、嗅覚がある。
それは先程までスパヰたちがいたフレグランスショップ『香百貨』の店内に香っていた香りだ。
「馬鹿な、香りで居場所を察知するなど―――」
できるはずがない。なぜなら、オイルや倉庫のカビ臭さ、それら全てを認識できる人間などいるはずがないのだから。
だが、了介は生命の埒外に在る者。
デッドマンにして悪霊であり、猟兵である。それができないわけがない。
「―――そこか。滅びろ……何もかも」
それは天変地異(テンペンチイ)の如き光景であった。
その体を突き動かす『魂の衝動』が電流に変換され、彼の体からほとばしる。ヴォルテックエンジンが唸りを上げ、放たれた高圧電流が放電される。
激流の如き奔流となって、『スパヰ甲冑』の機体を撃つ。
「ぐぁ―――!?」
姿は見えずとも、相手が機械であるのならば、放たれた電流は吸い込まれるようにして必中の一撃となる。
それは奇しくも、切り札であることが仇となった形であった。ぶすぶすと黒煙を上げながら、透明化が解除され膝をつく『スパヰ甲冑』の姿。
「頼みの兵器だった様だが相手が悪かったな」
了介はヴォルテックエンジンから溢れ出る電流をほとばしらせながら、『スパヰ甲冑』を見下ろす。
その雷撃の一撃は、『スパヰ甲冑』を市街地に出すことなく倉庫内に留めることに成功する。
どれだけの被害が出るかわからない。
その一念が、己の幸福追求する生命として基本原理をも穿つ。
「市街地に被害は出させない。おまえたち捕らえる。簡単なことだ。おまえたちに後はない。。此処がお前たちの終着点だ―――」
大成功
🔵🔵🔵
 馬県・義透
馬県・義透
四人で一人の複合型悪霊。
引き続き『疾き者』。
…次々と考えるものですねー、幻朧戦線って。
呪詛の影響は少なそうですけど。
透明になることは、関係ないですねー。とくに私は、生前からの習慣で慣れてますのでー(常に目閉じ)
風の流れ、動くときの物音…それらは消せませんから、第六感でわかりますし。
近くにいたら『四天霊障』でのオーラ防御にひっかかりそうですしねー。
漆黒風を属性攻撃:風と【連鎖する呪い】つき投擲攻撃を。ええ、傷が付けばいいんですよ。
整備不良じゃないかな、というくらいのになりそうですからねー。
ええ、私たち、悪霊ですからー。
「我々を倉庫内から出さないだと―――……まだ、決着が付かぬのに、我らをもう下したつもりか! ユーベルコヲド使い!」
凄まじき電流の一撃を受けて、影朧兵器である『スパヰ甲冑』が膝をつく。
けれど、すでに退路がない不退転の決意が決まっているスパヰたちにとって、ここが正念場である。立上ぬわけにはいかないのだ。
「……その意気や良し、といいたいところですが。次々と考えるものですねー、幻朧戦線って。呪詛の影響は少なそうですけど」
馬県・義透(多重人格者の悪霊・f28057)の中に存在する一人格『疾き者』が呆れたようにつぶやく。
不退転の決意は見上げたものである。
これだけの猟兵たちに追跡され、それでもなお逃げようとしている。それはある意味で諦めの悪い人種であり、そういった者がいつだって何かをしでかそうとすることを彼らはよく知っていたかも知れない。
「幻朧戦線……やはり、そこから気取られるか。だが、もう遅い。我らの撒いた種は帝都中に芽吹くことだろう! 我らはそれを見届けることは敵わないが……!」
影朧甲冑『スパヰ甲冑』の姿が再び消えていく。
先程見せた透明化だ。完全に透明化するが、駆動音と体温は消せない。けれど、ここは倉庫という屋内であれば、エンジン音をけたたましく鳴り響かせれば、反響して聴覚に頼った位置の判別はできない。
「なるほど。透明になることは、関係ないですねー」
細まっていた目が完全に閉じられる。
「とくに私は、生前からの習慣で慣れてますのでー……どれだけけたたましく音を立てようとも、風の流れ、動く時の物音の僅かな歪……それは消せませんから」
故に、今の義透には透明化など無意味である。
反響する音が彼の聴覚を乱す。けれど、その聴覚に捕らえられる音の反響は、全て。あらゆる音、己が知ろうとする音以外を除外していけば、自ずと物体の輪郭がわかるのだ。
さらに風の流れ。
「物体が動くのであれば必ず大気はゆらめきます。それを理解できれば、ほらこの通り―――」
放たれる『スパヰ甲冑』の拳の一撃をひらりと躱す義透。
まるで見えているかのような挙動であった。そこに4つの人格、その無念が形成する四天霊障のオーラに『スパヰ甲冑』が引っかかる。
「迂闊でしたねー……そうやって好機と見れば見逃さない洞察力は褒められたものですが、焦りすぎです」
スパヰは隠密行動が主であろう。
戦いの場、それも前に出て戦うことはなかった。故に、その勝機と見れば事を急くことは自明である。
それこそ4つの無念が集りし複合悪霊である義透にとってみれば、未だケツの青い若造の戦いである。
「戦いとは、機先を制するものが事を運ぶものです。ええ、例えば、こんな風に」
放たれるは棒手裏剣の一撃。
投擲された一撃が『スパヰ甲冑』の装甲に傷をつける。それは癒えることのない傷跡であるが、僅かな傷跡でしかなかった。
「何を言うかと思えば、ただの鉄杭……! その程度でこの『スパヰ甲冑』がやれるとでも!」
だが、それは連鎖する呪い。
彼らの持つユーベルコードであり、『癒えることのない傷跡』がつくかぎり『スパヰ甲冑』は次々と発生する『不慮の事故』に見舞われ続けるのだ。
「出力が下がる……!? 何故だ、整備は完璧に行われていたはず!」
どこまでも下がっていく出力。
それはあまりにも理不尽な出来事であった。どれだけ出力を上げるレバーを引いても、一定値までしか上がらない。
「整備不良ですかねー……ですが」
それは避け得ぬ不慮の事故の連続だった。
出力は上がらない。装甲が一部剥離する。これから次々と『スパヰ甲冑』は義透たちの放つ呪いによって、戦いを苦しめられることになるだろう。
「ええ、私達、悪霊ですからー」
義透たちの場違いなほどに朗らかな声が、スパヰたちを震撼させるのであった―――。
大成功
🔵🔵🔵
 アレクサンドル・バジル
アレクサンドル・バジル
おっ、噂の影朧甲冑、その高機動型ってとこか。
そんな健康に悪そーなものによく乗るもんだ。
再び黄金の魔力をその身に纏い。(戦闘モードⅠ)
敵POWUCとしばし高速空中戦を楽しみます。(空中戦)
なかなかのスピードだ。悪かねぇが、攻撃力がなさすぎるな。
目からビームとかは敢えて受けてオド(オーラ防御)でかき消します。
まあ、これ以上やっても仕方がねぇ。そろそろ終わるぞ。
と掴んで。まあ、影朧甲冑は人型なのでバンバン関節技でその腕や足をもぎ取ったうえで地面に叩き落とします……が中身がやばそうならそっと優しく落とします。
情報を吐いて貰わなきゃならねーからな。
整備不良というには、あまりにも頻発するエラー。
その音を聞きながら苛立たしげに操縦桿を叩くのはスパヰであった。
「どういうことだ! 先程から出力が上がらぬばかりか、機動性も下がっているだと!」
それは先行した猟兵達による攻撃の影響だった。
けれど、それでも影朧兵器である『スパヰ甲冑』がマントの如き装甲を翻し、飛翔形態へと変形する。
飛べさせすれば、この場から離れることができる。そうすれば、わざわざ超弩級戦力を相手取らなくてもいいのだ。
「モヲド零零式! 始動!」
エンジンに火が灯り、空へと舞い上がる。倉庫の屋根を突き破り、スパヰ甲冑は大空へと舞い上がるのだ。
屋根の破片が飛び散り、その最中を飛ぶ姿は高機動型と言うに相応しい。
だが、それをさせぬと黄金のオーラを纏て飛来する猟兵―――アレクサンドル・バジル(黒炎・f28861)の姿があった。
「おっ、噂の影朧甲冑、その高機動型ってとこか。そんな健康に悪そーなものによう乗るもんだ」
戦闘モード Ⅰ(ディアボルス・ウーヌム)に移行しているアレクサンドルにとって空を飛翔するのは不自由なものではない。
むしろ、その身に秘めている魔力の量に比例した力を発揮できるユーベルコードにおいて、飛翔能力はおまけでしか無い。
「ばかな、超弩級戦力は空を飛ぶのか! ありえない!」
その飛翔に追従してくる。アレクサンドルの影を見て、ぞっとするのだ。
まるで遊ばれている。
それがわかってしまう。それほどまでに圧倒的な能力差。どれだけ速度を上げても、ぴったりと後ろを獲ってくる。
ドッグファイトどころではない。ただ、興味本位でアレクサンドルはスパヰ甲冑がどれだけの速度を出せるのかを測っているだけなのだ。
「なかなかのスピードだ。悪かねぇが、攻撃力がなさすぎるな」
スパヰ甲冑の瞳から放たれるビームの乱射は確かにアレクサンドルへと命中していた。けれど、そのどれもが弱いものであるが故に、彼の身にまとった黄金の魔力に弾き返されるのだ。
「俺のオドに弾かれるような攻撃なら、どれだけしたって無駄だぜ。もっとも、高機動型っていうくらいだから、攻撃に回す出力を機動力に回しているんだろうが」
全て読み解かれている。
まるで仕様書を読んでいるかのような、そんな空中線。楽しまれている。
目の前の玩具がどんなことができるのか。たったそれだけの興味の為に飛ばされている。
それはあまりにも圧倒的な彼我の戦闘力の差であった。
「まあ、これ以上やっても仕方がねぇ。そろそろ終わるぞ」
やられるとスパヰが思った瞬間、空中でスパヰ甲冑に組み付くアレクサンドル。
「な、なにを―――!?」
スパヰ甲冑は人型である。
ならば、その関節、駆動部、それはら全て日になぞらえて作られたものである。
「関節技も決まるよなぁ―――!」
空中でアレクサンドルの関節技が腕に決まる。
痛ましいほどの音を立ててスパヰ甲冑の腕部の関節からもぎ取られるように脱落し、そのままアレクサンドルの蹴撃が背中に決まり、強制的に倉庫内部へと失墜させられる。
「おっ、と……中身は大丈夫か?」
つい楽しくなってしまって悪かったな、とでも言いたげにアレクサンドルは失墜したスパヰ甲冑を見下ろす。
起き上がろうとしているところを見るに、中身のパイロットであるスパヰは無事であろう。
変なところで安心するように胸をなでおろす。
「情報を吐いてもらわなきゃなんねーからな」
戦いというにはアレクサンドルにとっては児戯めいたものであったが、それは全て彼の掌の上の出来事にすぎない。
軽く髪をかきあげ、軽い運動に満足してアレクサンドルはスパヰ甲冑最後のあがきを見物することにするのだった―――。
大成功
🔵🔵🔵
 メンカル・プルモーサ
メンカル・プルモーサ
…速度重視で迷彩を纏えるとは言え…それで逃げないで打ってでるか…
それは流石に悪手じゃないかな…
高機動型といえど、どちらかと言えば隠密任務向けの機体だろうに…
迷彩を発動されたら…【輝ける真実の光】を発動…これでその迷彩は意味をなさなくなった…
…後は…高速行動重視となれば装甲はまあ、薄い方だよね…
…爆破術式を込めた銃弾を術式装填銃【アヌエヌエ】から発射…どんどん装甲を破壊していくよ…
…反撃の機関砲は障壁を張って防御…重奏強化術式【エコー】で効果を高めた拘束術式を発動……
…動けないようにしてトドメの銃撃の連射を放つとしよう…
上空より叩き落された影朧兵器、『スパヰ甲冑』が倉庫の外から再び開けた屋根の穴に落とされる。
轟音が響き渡り、その落下の凄まじさを物語る。
片腕は猟兵に寄って引きちぎられ、常に襲い来る不運なる偶然が重なり続け、出力を維持することしかできないでいた。
「ぐっ……! くそっ、なんで出力が……!」
すでに片腕は脱落しており、その姿はかろうじて人型を保っているだけにすぎない。
けれど、未だ健在であるがゆえに逃走を諦めきれていない。
「いいや、まだだ……! まだ、スパヰ迷彩が使える……!」
出力が上がりきっていないが、それでも迷彩を纏い姿を消す『スパヰ甲冑』。それは完全なる透明化。
だが、駆動音や体温までは消せない。それでもいい。姿が見えないということは、それだけ自分を追う猟兵たちの目を誤魔化すことができる。
今はせめて無事に情報を持ち帰ることが先決なのだ。
「……速度重視で迷彩を纏えるとは言え……それで逃げないで打ってでるか……それは流石に悪手じゃないかな……」
メンカル・プルモーサ(トリニティ・ウィッチ・f08301)の言う通りであった。
本来の影朧甲冑の使い方としては、あまりにも悪手である。スパヰの名が冠せられているのであれば、それは闇に乗じて猟兵を撃つべきであり、この状況では逃げる一手のほうが余程猟兵には効果的であったはずだ。
「高機動型といえど、どちらかと言えば隠密任務向けの機体だろうに……」
確かにメンカルの分析通りであった。
けれど、人は時として自分の力を過信するし、触れたことのない強大な力を手にすれば気が大きくなる。
万能感が人を狂わせる。
それは本来では違う使い方であったのだとしても、それで押し通せると思ってしまうのだ。
「それもまた人の性……仕方ないね」
メンカルの目の前でスパヰ迷彩によって姿を消す『スパヰ甲冑』。けれど、メンカルは慌てることなどなかった。
「輝く塵よ、踊れ、纏え。汝は白日、汝は天照。魔女が望むは秘め事許さぬ誠の灯」
ふわりとメンカルの掌から溢れるようにして光の粒が放たれる。
それは、輝ける真実の光(グリッター・ダスト)。意図的に隠されているものに付着し輝くのだ。
その輝きは『スパヰ甲冑』の姿を光り輝くことによって所在を知らしめる。
「な!? なんだ、この光は! 何故、機体が輝く……!」
「これでその迷彩は意味をなさなくなった……後は……」
メンカルが術式装填銃『アヌエヌエ』をか構える。爆破術式の込められた弾丸が装填された銃口を向ける。
そう、高速移動を可能としているのは装甲を薄くしているからだ。ならば、その装甲を破壊するのは容易い。
引き金を引くのを躊躇うことはなかった。放たれた弾丸は爆破術式が展開され、爆風が『スパヰ甲冑』の装甲を吹き飛ばす。
これまでの猟兵たちの攻撃も相まって、その装甲は簡単に引き剥がされていく。まるで紙のようであった。
「ぐっ、貴様っ!」
片腕を失ってしまったが、腕に装備された機関銃から弾丸をばらまく。けれど、それらは全てメンカルの張り巡らせた障壁に阻まれる。
迷彩に寄って透明化したどこから放たれるかわからない弾丸であるのならばいざしらず、ユーベルコードによって生み出された光の粒に寄って知覚できる『スパヰ甲冑』から放たれる弾丸を障壁が阻むのは簡単だった。
「重奏強化術式『エコー』展開……拘束術式―――起動」
メンカルの言葉と共に開放される拘束術式が『スパヰ甲冑』の動きを止める。幾重にも張り巡らされた拘束術式は、例え『スパヰ甲冑』がパワー重視の機体であっても身動きが取れることはなかっただろう。
「じゃあね。悪手続きであったけれど……」
メンカルの放った弾丸は全て空中で爆発し、次々と『スパヰ甲冑』の装甲を引き剥がしていく。
それはスパヰたちが帝都で貼り付けてきた偽りの身分や仮面、姿を引き剥がすかのように放たれ、その存在を白日の元に曝け出すように爆発が引き起こされ続けるのであった―――!
大成功
🔵🔵🔵
 ミネルバ・レストー
ミネルバ・レストー
ふぅん、ステルス…ううん、完全な透明化ね
なら、それが通用しないわたしのフィールドに引きずり込んであげる
【永久凍土に乙女よ踊れ】発動、戦場を雪景色に変えてみせましょう
物音や体温が消せないなら、まず降り積もる雪が甲冑に乗って
その形を露わにするはずよ
さもなくば、一歩でも動いてごらんなさい
雪原に足跡がつくか、蒸気で溶けるか、どうしたってボロは出るわよね
根比べをしてもいいけど、その技、疲れない?
そうでなくても影朧甲冑は、致死を免れたとしても心身を蝕むの
命までは取らないから安心して頂戴、いっそ殺せと叫んでもダメ
位置が特定でき次第「アブソリュート・ウィッチ」に念じて
氷柱で脆い所を「部位破壊」狙いで打ち込むわ
弾けるようにして影朧兵器『スパヰ甲冑』の装甲がひしゃげ、吹き飛ばされていく。
それは猟兵たちの攻撃の蓄積。
だが、それでもなお逃げようとするのは『スパヰ』たる所以か。
もっと速くそうしていればよかったのだと彼らが気がつくにはあまりにも遅かった。元々、高機動型とは言え諜報活動のための『スパヰ甲冑』である。
ならば、猟兵を打倒しようと考えることなく逃げの一手を討ち続ければ、彼らの目的である『情報』を国や都市……彼らの背後にある者たちに齎すことができたはずだ。
けれど、大きな力は時として人を狂わせる。
強大な力があれば、それをふるいたがる。それがどんなに合理的ではなくても、魅力的な力であればあるほどに抗いがたい。
「こんな、はずでは……何故、超弩級戦力が集まってくる……!」
誤算であったのは超弩級戦力―――猟兵が数多くこの事件に関与したことであろう。
桜學府のユーベルコヲド使い程度であるのならば、この『スパヰ甲冑』であっても十分に圧倒できたのだ。
もっと情報があれば。だが、この帝都に超弩級戦力が数多く集まっているということは、それだけで有益な情報である。それを持ち帰らねばと再びスパヰ迷彩を発動させる。
「ふぅん、ステルス……ううん、完全な透明化ね」
その声はつぶやくようでも在り、悪手を打ち続けたスパヰたちを憐れむようでもあった。
スパヰにとって、これが最後のスパヰ迷彩。
この機を失ってしまえば逃れる術はない。だが、彼らは何もわかっていなかった。彼らが呼ぶ超弩級戦力。猟兵がどれだけの世界を、どれだけのオブリビオンを相手にしてきたのか、その経験の質と量を。
「なら、それが通用しないわたしのフィールドに引きずり込んであげる」
ミネルバ・レストー(桜隠し・f23814)の桜色の髪が翻り、不敵に笑う声が紡ぐのはユーベルコードの旋律。
降り止まぬ冷たく白い雪が常に幻朧桜咲き乱れる薄桜色の世界を白く染め上げていく。それは戦場となった倉庫全体を氷雪地帯の如く染め上げていくユーベルコードであった。
「外気計……な、何だこの数字は! ここは帝都だぞ!?」
スパヰの声が響く。甲冑の中にあるモニターや計器が示す値は、それまでの数字を尽く下回る。
気温も、湿度も何もかも。そっくりそのまま世界を塗り替えられたような!
「ここはわたしの世界、誰が一緒について来られるかしら?」
戦場は雪化粧に彩られ、そこに存在する者を縁取る白き雪は透明化した『スパヰ甲冑』の姿を浮き彫りにする。
だが、『スパヰ甲冑』はその体を震わせ雪を払う。積もった雪が機体の輪郭を顕にするというのであれば、出力を上げて熱で持って溶かせばいい。
透明化を破ったと息巻くユーベルコヲド使いの鼻を明かしてやると、スパヰは動こうとしてギクリと動きを止めた。
「そうね。雪を払ったとしても、此処は雪原。足跡もつくでしょうし、なにより機体の装甲に付着した雪を出力を上げて蒸気で払おうとしたのが最悪だったわね?」
そう、この雪原において存在をひた隠すことなど不可能である。
キラキラと光を反射して舞い落ちるは雪と氷の結晶。
永久凍土に乙女よ踊れ(ソング・オブ・ツンドラ)と囁くように、雪と氷の結晶―――アブソリュート・ウィッチがミネルバの意志を受けて氷柱を生成し、装甲の剥離した『スパヰ甲冑』へと殺到する。
どれだけ姿を透明化していようとも関係ない。
この永久凍土と化した戦場におけるプリマドンナにしてプリマステラはミネルバ・レストーただ一人。
「まだ、まだだ! この甲冑が敗れるなど……!」
スパヰの咆哮が轟く。
この期に及んで、甲冑を捨てて逃げることができないのは、力に対する執着があるからだろう。
人は得たものを手放すことを決断することを躊躇う。何の躊躇もなく力を捨てられる人間など、そう多くは無いのだ。
「根比べをしてもいいけど、その技、疲れない? そうでなくても影朧甲冑は即死を免れたとしても心身を蝕むの。知らないとは言わせないわ」
それは幻朧戦線に影朧兵器を提供していたであろうスパヰたちであれば、知っていて当然の情報であったことだろう。
それが如何にして禁忌の兵器であるか。
だからこそ、後には退けない。
「そう……残念ね。でも、命までは取らないから安心して頂戴―――」
雪と氷の結晶が空より舞い降り、次々と氷柱で『スパヰ甲冑』を貫き、全身をズタズタに突き破る。
それはあまりにも強烈なる一撃であり、その甲冑全てが崩落するには十分であった。
同時に、それはスパヰが自死を選ぼうとしても無理であることを悟らせる。
「いっそ殺せと叫んでもダメ。貴方には沢山喋ってもらわないといけないから」
その口元を覆う氷雪。
舌を噛み切ることも、奥歯に仕込んだ爆発物を起爆することもできない。ミネルバはため息を付いて桜色の髪についた氷雪を払う。
「官憲ね……後は任せましょうか」
ふぅ、と吐息が漏れる。
きらきらと結晶が舞い散り、戦いの終わりを知らせる。何処か遠くで人々がざわめく喧騒が聞こえてくる。
これで帝都の平和が守られたとは未だいい難い。
けれど、戦いしか知らなかったミネルバが世界を知った。
「こんなにも綺麗なのだもの。徒に壊されてはたまらないわ―――」
大成功
🔵🔵🔵


 海鶴
海鶴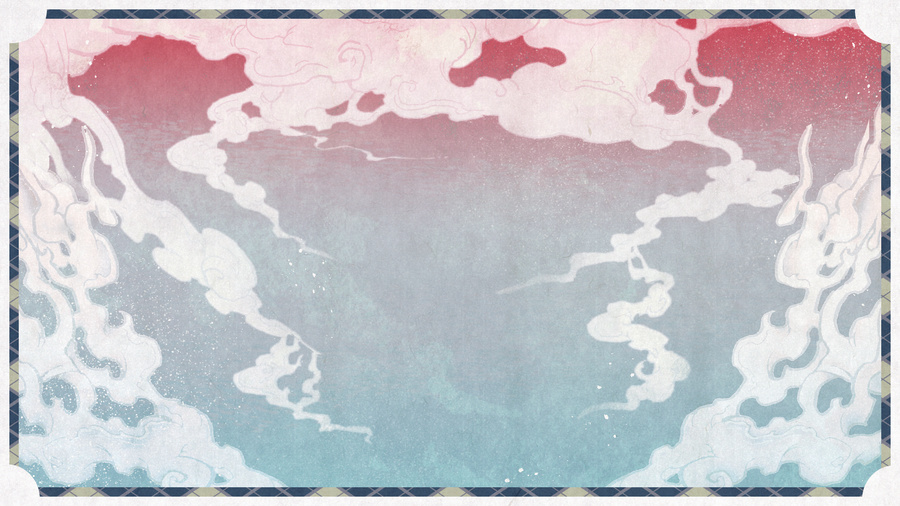
 アレクサンドル・バジル
アレクサンドル・バジル  馬県・義透
馬県・義透  久瀬・了介
久瀬・了介  メンカル・プルモーサ
メンカル・プルモーサ  ミネルバ・レストー
ミネルバ・レストー 
 馬県・義透
馬県・義透  アレクサンドル・バジル
アレクサンドル・バジル  久瀬・了介
久瀬・了介  メンカル・プルモーサ
メンカル・プルモーサ  ミネルバ・レストー
ミネルバ・レストー 
 久瀬・了介
久瀬・了介  馬県・義透
馬県・義透  アレクサンドル・バジル
アレクサンドル・バジル  メンカル・プルモーサ
メンカル・プルモーサ  ミネルバ・レストー
ミネルバ・レストー