迷宮災厄戦⑬〜うさぎ狩り
●
「あ〜ん、おなかすいたァ」
気怠く甘い声が、夕方空の下で聞こえた。
「ねぇ、ごちそうはまだ? 今日一日、なぁんにも食べてないんですけどぉ」
夕日に染まったか血に染まったか、真っ赤な断頭台を取り囲むようにしてオウガたちが不満を漏らす。いつもならば朝からたらふくアリスの肉にありつけるのに、なぜか今日は一人も現れない。
オウガ・オリジンのために設えられたこのギロチンは、アリスを召喚しさえすればすぐに素敵な食事を提供できる。そして、その“おこぼれ”に与ることでオウガたちも豊かな食生活を満喫していた。アリスとの追いかけっこも面倒な駆け引きも要らない。ここで口を開けて待っていれば、棚からぼたもちが落ちてくるがごとくアリスの柔らかくて甘い肉を味わえるのだ。
しかし今日は国中に作られた断頭台に一人のアリスも送り込まれて来ない。猟書家たちによって危機に追い込まれたオウガ・オリジンにとって、今が大事なときであることはオウガたちも理解している。それなのに糧となるべきアリスがいないのだ。一体これはどういうことなのか、とオウガの一人が声をあげた。自分が食えないのはまだしも、オウガ・オリジンに饗する食事すら用意できていないではないか、と。
「それってつまり――、猟兵がこの国にも迫ってきてるってこと?」
うさぎの耳をぴくぴく揺らして、彼女は言った。
どうやら、オウガ・オリジンにとっての補給線を維持できないまでに事態は逼迫しているらしい。持ち前の頭の回転の良さで、うさぎ耳の女オウガはそれを察した。
「ふぅん。猟兵ねェ」
最近、食べてばかりで運動もしてなかったし。たまには追いかけっこや駆け引きを愉しみたい。もちろん、とっても気持ちのいいことだってしたい。食欲が満たされているなら、他の欲求も満たさなくっちゃね。
――ニタリ。
目尻を下げて妖艶な笑みを作る。
「じゃ、アタシたちが追い払ってア・ゲ・ル♡」
くいっと蠱惑的に揺らした腰の上には、たっぷりとした贅肉が乗っていた。
●
「…………」
いつにも増して、アレクサンドラ・ルイス(サイボーグの戦場傭兵・f05041)は難しい顔で猟兵たちの顔を一人ずつ確認した。そして、「――嫌なら引き受けなくていいからな」とまで言う。およそそのような“親切”を言うタイプではないと知っている猟兵が、訝しげにアレクサンドラの目を見返した。
「……お前らには、アリスラビリンスのとある国に行ってもらう。その国は――」
何が起ころうとも任務を全うする、という意志を込めた視線を受けて、アレクサンドラは作戦の概要を説明し始めた。
今回の戦争で討伐しなければならないオウガ・オリジンに対して『アリス』を供給することに特化した国であるという。国内のあらゆる場所に設置されているのは、公衆トイレでもコンビニエンスストアでもなく、『召喚したアリスを即座に殺すことができる断頭台』だ。狙われたアリスはこの断頭台に直接召喚され、その場で首を落とされるのだという。
「そんな……、それじゃ助ける暇さえないじゃないか」
あまりに無残なシステムの存在を知って、誰かが震えるように呟いた。
「そうだな。……まあ、連中にとっては俺たちがコンビニで唐揚げを買うのと大した違いはないだろう。食生活の一致ってやつは、相互理解においては重要だ」
ジョークのつもりなのか、真面目な話なのか、アレクサンドラの言葉はイマイチ笑えない。
「だが、悪いニュースばかりじゃない。俺たちがその断頭台の国に攻め込むことができるようになったおかげで、連中は防衛に専念することになった。つまり、今は“アリスの召喚”自体は一時的に休止されている状態だ」
この機に乗じてここを制圧することができれば、理不尽に命を奪われるアリスたちを救うチャンスが増えるだろう。迎え撃ってくるオウガたちを一掃するのだ。
「で、だ。ここからがあんまり気持ちのいい話じゃないだろうが」
珍しく言葉を濁すアレクサンドラに、猟兵たちの胸にも悪い予感というやつが去来する。数秒置いて、グリモア猟兵はその指示を出した。
「――そこらじゅうに作られた断頭台を逆手に取れ」
相対するオウガどもの性質を利用して、断頭台に誘き出すのだ。そして、ギロチンをその頭上に落とす。そうすることでオウガたちを労せず“駆除”することができる。――幸い、ギロチンは国じゅうの至る所にある。オウガを嵌めて連れ出すのもさして難しくはないだろう。
「お前らが駆除するのは、“元時計うさぎ”とかいう触れ込みのオウガだ」
本当かどうかは知らないがな、と鼻で嗤う様子を見る限りでは、どうもロクな相手ではないようだ。左目を僅かに引きつらせて、アレクサンドラは続ける。
「あの手この手でハニートラップを仕掛けてくる。……『ハニートラップ』の意味がわからないキッズは今すぐおうちに帰ってミルクでも飲んでろ、わかったな」
ハニートラップ、ですか……と鼻の下を伸ばしたあなたはおそらく大丈夫である。ただし別の意味で大丈夫ではない。
「誘いに乗る振りをして誘い出すのが手堅いと思うが、相手もそれなりに知恵のある連中だ。あまりにも見え透いた誘いには乗らないと思っておいた方がいい。……愉しみたい奴は勝手に火遊びでもなんでもしやがれ。その報告は要らない。“オウガを断頭台に送り込め”、俺の指示はこれだけだ。遊ぶのに夢中でヘマする奴は要らない。いいな」
嫌なら引き受けなくていい――、猟兵たちが冒頭の言葉を理解するのに、そう時間はかからなかった。
ごくり、と唾を飲み込む一同に、アレクサンドラはもうひとつ情報を上乗せした。
「――うさぎ共は餌の供給過多と運動不足で体脂肪率が40%くらいある」
ググらない方がいい。
 本多志信
本多志信
こんにちは、本多志信です。私も40パーセントくらいあるんじゃないかな!ハハッ!よろしくお願いいたします。
本シナリオでは時計うさぎどころか五月うさぎ並みに発情したうさぎちゃんたちをざっくざっく狩っていただきます。男女の性別や性的嗜好は可変なので、都合のいい想定でやってもらって構いません。ただしお色気要素としては「青年誌程度」の想定でおります。成人誌レベルのプレイングは読めません。おっかしいなー。
性的アプローチについて、本シナリオではNGではありません。ただし露骨な表現は避けます。「かっこよさ」「面白さ」などを追求するためのプレイングを歓迎いたします。パートナーや気になるあの子がいらっしゃるキャラクターさんはご注意ください。リプレイ作成後に何があっても責任取りません。
断頭台でトドメを刺しますので、性的表現以外にもそこそこ踏み込んだ描写をする予定でおります。
以上。空気読んで責任取れる人はばっちこい。
第1章 集団戦
『人をダメにするラビット』

|
POW : 天国に逝かせてあげる♡
自身が操縦する【天国へと導くうさぎの穴】の【人をダメにする天国のような快楽】と【エナジードレイン】を増強する。
SPD : 極楽にご案内♡
自身が操縦する【極楽に導くうさぎの穴】の【人をダメにする極楽のような快楽】と【エナジードレイン】を増強する。
WIZ : 至福の時間をあなたに♡
自身が操縦する【至福の時間を与えるうさぎの穴】の【人をダメにする至福の時間を過ごす快楽】と【エナジードレイン】を増強する。
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『集団戦』のルール
記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
――石造りの街にはギロチンこそが相応しい。
家々の窓辺を飾るのは真っ赤に咲きこぼれるゼラニウムではなく、どす黒い血飛沫だ。
太陽は地平線に沈み、僅かに残った光の残渣が街並みを薄ぼんやりと照らしている。小高い丘の上にある王城にはまだオレンジ色の陽が当たっているが、それも間もなくひんやりとした色に染まるだろう。そうして昼間の熱を冷ます街を、今度は夜の灯が照らし始めるのだ。
満たされない空腹感を持て余したまま、元・時計うさぎは広場を突っ切った。石畳の敷き詰められた小さな広場は何軒かの建物に囲まれている。広場から放射状に細く伸びた路地はまた別の広場に繋がっていて、そうした小さな地区の集まりで街が構成されているのだった。
(ああ、早くこの広場が再び歓喜に満ちる日が来ないかしら)
薄暗い路地に脚を踏み入れたところで、時計うさぎが広場を振り返る。広場に面した家々の灯で、中央にある石造りの断頭台が美しく照らされていた。台の上では二本の太い木の柱が天を突くようにそそり立ち、柱の間には大きな刃が鈍く光っていつでも獲物の首を落とせるように待ち構えている。
うさぎは今しばらくお預けとなってしまった、甘美な時間を反芻するように目を閉じて思い返した。
断頭台に哀れなアリスが召喚される、その瞬間。何度も何度もこの目で絶望の表情を見、あるいは何が起こったのかすらわからないという無垢な瞳がゆっくりと弛緩していくのを覗き込み、勢いよく噴き出した熱い血を肌に浴び、――そして柔らかい肉を我先にと奪い合い喰らう。刃は手入れなどせずとも圧倒的な質量で少年少女の首を刎ね、頸動脈から溢れ出る血液はしばし優美な曲線を描いて血の噴水となる。そうしてオウガたちはひととき、悦びと熱気に浮かされたようにして動かぬ肉塊を貪るのだった。誰一人、血で汚れる石畳を気にする者はいない。清掃もされず、手入れもされない。あるいは滴る血の一滴すら逃しはせぬと、まるで上等な料理の最後のひと舐めまで惜しむようにしてアリスの血を味わう者はいたかもしれない。しかし広場も建物も木の柱も流れる血を吸い続け、断頭台を中心に黒い星の模様が刻まれていた。
 フィランサ・ロセウス
フィランサ・ロセウス
あら、まるまる太ってかわいいウサギちゃん♥
私といいことしたいの?私もあなたの事“好き”かも……
でも、こんなところじゃダメよ。
誰も見てない所で、ふたりっきりで…ね?
そう言って少し恥じらうふりをして、近くの物陰に連れ込むわ
そこで互いの息がかかる位に身体を寄せて……
かーらーの、【早業】の【だまし討ち】で手枷をガチャリ☆
それからロープで拘束してー、仕上げは猿轡!(UC【咎力封じ】)
あはっ、捕まえたわウサギさん♥
これからすごく、すっごくイイ事しましょうね♥
ところで、この国で手近な物陰って言ったら…そう、断頭台よね!
これから起こる事を想像しただけでゾクゾクしちゃう♥
それじゃあ、断頭台にごあんな~い♥
●
フィランサ・ロセウス(危険な好意・f16445)は人気のない広場に立って、黒い染みだらけの断頭台を見上げた。赤いフード付きの外套に手提げのバスケットを持った姿は、さながら童話の主人公のよう。遠目には「恐ろしい場所に招かれてしまった罪なきアリス」に見えたことだろう。
「どこに行くの? 赤ずきんちゃん」
その背後から優しい声音で呼びかけるのは、狼――ではなく、うさぎだ。しかも、ぶくぶくとよく肥えた白いうさぎ。
「――あなたを待っていたのよ、オオカミさん」
ゆっくりと振り向いて、フィランサが応えた。
おとぎ話をなぞって交わされた言葉は、出会いの合図。これから始まる素敵な猿芝居の合言葉。
(あら、あら――!)
時計うさぎの姿をまじまじと見て、フィランサは頬を赤く染めた。
(まるまる太って、なんてかわいいウサギちゃん!)
いかにも日がな一日ベッドに寝転んだまま食べ続けました、という丸い身体を包む燕尾服はなるほど『時計うさぎ』の面影を残している。しかし肥え太る身体に合わせて新調したのはいつが最後だったのだろうか。肩回りには窮屈そうな皺が不自然に寄っているし、本来はパフスリーブだったのだろうと思われる袖も膨らんだ二の腕に内側から圧迫されてぱつんぱつんだ。ジャケットの前は大きく開かれ、ぶるんと突き出した乳房とその下で激しく自己主張する腹の肉が今にもブルーのビスチェを引き千切りそうだ。これでは時計うさぎというよりもむしろ卵の王さまの方だろう。
「うふふ。オオカミさんじゃなくて、うさぎさんよ」
くね、と腰を揺らしてしなを作る太った女の頭からは白いうさぎの耳が生えているが、それがぴこぴこと動く度に「私はうさぎです」と必死に主張しているようで滑稽だ。
「そうなの? じゃあ、丸くてふわふわの尻尾もあるのかしら」
しなを作る度に太腿にぴっちりとまとわりついた丈の短いスカートが、肉に圧されてまくれ上がりそうになる。太腿を咥えきれないハイソックスの片方がついに力尽きて膝までずり落ちたのを見ながら、フィランサは時計うさぎの誘いに乗る。
「……アタシのおしりに興味があるの?」
意味深な言葉に乗せた声は徐々に湿り気を帯びていく。くるりと身体を半分回転させた時計うさぎの後ろ姿には、あの愛らしいうさぎの尻尾は見つからない。
「うさぎの尻尾は短いから、外からは見えないのよ♡」
そしてフィランサとの距離を一気に詰めて、耳元で囁く。
「服を脱がないとね」
――ぞくり。
フィランサの背筋を快楽の予感が駆け上った。知らず知らずのうちに息が上がり、心臓が期待に跳ねる。ああ、ああ。なんて素敵な感覚なのかしら。
「私といいことしたいの?」
前歯で軽く唇を噛み、赤い舌先で噛んだ後を舐める。顎を引くようにして上目遣いでうさぎを見た。きっと私もこんな顔をしているのね、と思うと、口内にじゅわりと唾液が満ちる。
「――でも、こんなところじゃダメよ」
外套の下に手を這わせてくるうさぎを制止して、フィランサは広場から伸びる路地を目で示した。家々の灯が届かない、一番暗くて細い道を。
「誰も見てない所で、ふたりっきりで、……ね?」
互いに手を取り合い、フィランサとうさぎは暗い路地へと転がり込む。飛び込んだところですぐにうさぎが抱き着いてきたが、フィランサは「まだ、まだ。もっと奥じゃなきゃいや」と恥じらいを滲ませて更に暗がりへと誘う。うふふ、くすくす、と少女たちの甘い笑い声を聞いているのは、空に昇り始めたチーズのようなお月さまだけだろう。
うさぎの太った身体は確かに「美しい」とは言い難いかもしれなかった。けれども抱き着かれたときの柔らかさは格別に心地よい。いざ殺す気になればその巨体でいかようにも相手を締め上げるのだろうが、今はじゃれあいに夢中で肌と肌を擦り合わせるような力加減だ。男女問わず誘い惑わし陥落させてきたのだろう、その微笑みもどこか愛らしさや妖艶さを感じさせる。
「私も、あなたのこと好きかも……」
うさぎの身体から立ち上がってくる甘い匂いと、それから血の匂い。どちらも人間の欲求や本能を腹の底から刺激するような匂いだった。とろんとした目つきでフィランサはうさぎを見つめた。
「そう? 嬉しいわ。……じゃあ、とっても気持ちのイイこと、しましょ?」
見つめ合ったまま、うさぎの顔が近づいてくる。二人の息が絡み合うほどになると、うさぎの手がフィランサの胸元へと伸びた。ぷちん、とボタンを外した音がする。
「ええ、したいわ。とっても――イイコト」
一番上のボタンが外され、胸の圧迫感が僅かに薄れる。夜の空気が火照った肌を冷やした。
うさぎのもう一方の腕はフィランサの腰をしっかりと抱き、自らの身体を細いフィランサへと押し付ける。はちきれそうな乳房が二人の身体の間で圧し潰され、奇妙な形に歪んだ。
がちゃり。
獲物の腰をしっかり捕らえたはずの右腕に冷たい感触が当たって、うさぎは我に返った。
「なに?」
咄嗟に腕を引こうとするが、冷たい何かがそれを阻む。引く力を強くすれば強くするほど、それは手首に食い込んで贅肉を傷めつけた。
「あはっ」
焦り始めたうさぎの様子に、フィランサが実に愉しげな声を漏らす。
「どう? 素敵でしょう?」
じゃらりと金属の音がする方を見れば、フィランサの手に鉄鎖が握られている。そしてそれを目で辿ると、自分の右腕に嵌められた手枷に繋がっているではないか。――ハメられた。うさぎは悔しそうに顔を歪ませた。
「とっても似合ってるわ、うさぎちゃん」
捕らえたつもりで捕らえられるとは。あまりにも間抜けな己に腹を立てながらも、フィランサから距離を取るべく身体を引き離す。ぎっ、と鎖が軋んで、右腕がねじ切れそうになる。いや、ここで捕らわれるくらいならばいっそ右腕などねじ切って棄ててくれよう。アリスの肉さえ得られれば、後からどうとでもなるのだから。
「ダメよ、逃げちゃイヤ。私、あなたのことが“好き”なのよ」
言ったでしょう?と囁くフィランサの表情は先程と変わらずうっとりとしている。
なんだ、この女は? うさぎの耳が後ろへ倒れた。逃げなければ。逃げなければ。
しかしフィランサは容赦なく、そして鮮やかな早業で、今度は麻縄でうさぎを縛り上げた。捕らえた右腕を起点に、巻き取るようにして身体へ縄を絡める。
「ぎ……っ」
不自然な方向へ曲がった腕が締め上げられ、うさぎは醜い悲鳴を漏らした。関節がみしりと鳴る。後ほんの少しの力で、この哀れな右肘は砕けてしまうだろう。むしろ、いっそそうなってしまった方が楽だったかもしれないとさえ思う。
うさぎが痛みに耐えるその間にも、フィランサは脂肪だらけの白い身体へと縄を食いこませた。
「ね? ぽっちゃりさんの方が、ロープが映えるのよ」
骨と皮ばかりの、あるいは機械の身体にどれほどロープを巻き付けたところで、きっとここまで気分は高揚しないだろう。柔らかく、そしてたっぷりとした肉に食い込む様こそ縄の美しさを最大限に引き出せるのだ。うさぎの乳房の上を、敢えて中途半端な位置で横切らせて肉の盛り上がりを形作る。
「尻尾は――……、脱がないと見えないんだっけ?」
フィランサを蹴り飛ばそうと暴れる脚も、もちろんしっかりと縛り付ける。だらしなく揺れる肉が縄できつく固定されることで、きゅっと締まったように見えるから不思議だ。麻縄は内腿を通ってうさぎの尻へと渡された。
「んっ、んん……っ!」
脚の内側、ひときわ敏感な肌の上を縄が這う感覚にうさぎは身を捩る。こんなときに、こんな声が漏れるなんて。屈辱と恐怖に身体が震えた。
「ほんとだ。可愛い尻尾、みーつけた♡」
スカートの布をくしゃくしゃに捲り上げて下着を露出させると、でっぷりとした尻に不釣り合いなほど小さく愛らしい、白くてふわふわの尻尾が現れた。
「せっかくだから、見やすくしておくね」
フィランサはそう言って、スカートをたくし上げたままの形で縄で固定する。腰の周りを縄が這うたびにうさぎの身体が跳ねるが、それにはさほど興味を示さない。
「仕上げはやっぱり、猿轡よね」
とっておきのがあるのよ、と、満面の笑みでフィランサは白い布をうさぎの眼前に広げた。
「んんーーーー!!」
うさぎの抵抗も、まったく歯が立たない。なぜ、なぜなの。私の力が。アリスをたっぷりと食べて蓄えたはずの私の力。なぜこの娘には抗えないの。
拘束具で縛り上げることで相手の力を徐々に封じていく、それがフィランサのユーベルコード。殺しの愉しみは快楽を味わったあとにとっておこうと油断したのが運の尽きであった。
「ステキよ、ウサギちゃん。とっても可愛い。あなたのこと、大好き。――めちゃくちゃに壊したいくらい」
フィランサの紅い瞳に宿るのは、狂気か、愛か。
「さあ、とっておきの場所に行きましょうね」
歪な形に固められた時計うさぎの身体は、もはや“肉塊”のようなものだ。鉄鎖と麻縄で肉塊を引きずって、フィランサは広場へと歩き始めた。目指すはもちろん――。
「ふふっ。これから起こる事を想像しただけでゾクゾクしちゃう」
断頭台を、月が照らしている。
大成功
🔵🔵🔵
 ブランク・ディッシュ
ブランク・ディッシュ
まぁ・・・全体的にふくよかなウサギさん。
そういうのが好きな殿方もいらっしゃるわ・・・。
過去、そういう人に変装した事があるもの。あの時はどう暗殺したのだったかしら・・・?・・・そういえば、此処に来
たのは戦う為でした。
『悪霊腕・遊刃』
カシン、とアームブレードを展開し、早業でなぎ払い暗殺。切断します
話の腰を折ってしまってごめんなさい。…本来の役目に戻ります。
空中浮遊させた片腕でウサギさんの頭を掴み、祟り糸で捕縛し生命力吸収。
そのまま念動力でウサギさんを浮かせ、断頭台へ叩きつける。
・・・たしか、こうすると楽だとか?
身動きを封じてギロチンの刃を落す
・・・まぁ・・・アームブレードと同じくらいよく切れますわ
●
「やだあ。脚の長〜い細身のイケメンを捕まえたと思ったのに!」
硬質な機械の身体を組み敷いた体勢で、時計うさぎが口を尖らせる。いくら日が暮れたからといって、そんなものとこの身を間違えるなんて、このうさぎの目は大丈夫だろうか――と、ブランク・ディッシュ(ウォーマシンの悪霊・f28633)はでっぷりと太った女の身体を見上げた。
二メートルを越す身長はどう見ても“一般的なイケメン”のレギュレーションから外れている気がするが、それはまあ「暗闇で遠近感を掴めなかったせい」と言い張れなくもない。しかしブランクのシルエットは確かに細身ではあるものの、すらりとした脚部が描く艶やかな曲線は実に女性的で優美だ。様々な機能が搭載されて、ちょうど人間の女性と同じようにツンと上を向いた胸部も、愛らしい少女を思わせる。
(まあ、女性のような立ち姿の殿方も、いないことはないのだけれど)
可憐な少女と見紛う男を見たことがないわけでもない。むしろ猟兵にはそういう男性が少なくないとさえ言える。よって、ブランクは自身が男性に間違われたことに対する疑問の反芻を中止した。
「機械相手じゃ、独りで“する”のと変わらないじゃん」
わざとらしく「あーあ」とため息をついて見せながらも、うさぎはブランクの身体の上から退く気配がない。“ハズレ”は“ハズレ”として、しっかり元は取っておこうという腹積もりなのだろう。すべすべと冷たい金属質のボディを確かめるように指を這わせた。
「アタシはこういうの初めてなんだけど……、“オモチャ”で気持ち良くなるのが好きな子もいるんだよね」
――曰く、「バテないし?」
「生身だと変なプライド持ってるオトコもいるしさぁ、面倒なときもあるわけ」
いやんなっちゃうよね、とクスクス笑いながら、指先から掌へ――触れる面積を少しずつ増やしていく。背中のくびれ、腰の丸み、下へ降りたかと思うと脇腹を撫で上げて胸部を両手で包み込む。
「そこいくと、オモチャなら文句言わずに励んでくれるから、ラクだよね?」
「…………」
「うーん。女の子タイプかぁ、残念」
うさぎのむっちりとした太腿が、ブランクの脚を挟む。柔らかい肉だけがたっぷりと余り、黒と白の金属に熱を移した。そして、ブランクに覆いかぶさりながらうさぎが囁く。
「でも、機械なんだし。……便利な道具とか、持ってるんでしょ?」
みしり。肥え太った身体の全体重をかけられて、ブランクの肩関節が軋んだ。
「――私は、“そういう風”にはできておりませんわ」
「あら、アナタ喋れるの?」
おそらく愉しげな笑みを浮かべているのだろう、上半身を跳ね起こしたうさぎは弾んだ声で応えた。起き上がる反動で肩がさらに悲鳴をあげそうになったが、ブランクの表情は変わらない。彼女の穏やかな拒絶には耳も貸さず、うさぎは続ける。
「そんな風にできてるかなんて、関係ないよ。机の角だって、電動歯ブラシだって、なんだって使いようだよ?」
ブランクの、膝を立てた片脚。その頂に腰を下ろして淫猥に揺らす。
「ほらぁ、一緒に遊ぼうよ。アタシ、オモチャで気持ちよくなってみたい」
だらしなく揺れる太腿の肉と、屈み込んだ姿勢ではちきれそうになった腹、それからその上で水風船のように揺れる乳房。三段揃って並ぶと、鏡餅か雪だるまのようにも見える肉塊が執拗にブランクを誘う。
「全体的にふくよかなうさぎさん。――確かに、“そういうの”が好きな殿方もいらっしゃるわ」
膝関節に熱く湿った身体が押しつけ荒れているが、帰還後の整備と同時に洗浄すれば問題ない。ただしいつもより入念に洗っておこう。
硬い身体から紡がれる柔らかい声は穏やかで、そして淡々と目の前の事実と過去の経験から得た知識を述べた。
「ちょっと、それどういう意味よ?」
事実ではある、――が、得てして事実とは、事実であると同時に突きつけられた側にとっては痛烈な皮肉でもあるのだ。うさぎは自分がブランクを“機械”と蔑んだことに意趣返しされたと受け取って、目つきを尖らせた。
「深い意味はありませんわ。『ふくよかな女性を好きな男性もいる』と申し上げただけ」
「――チッ」
忌々しげに舌打ちをして、うさぎはブランクの身体から飛び退った。
「これだから機械ってキライ! 正論だの事実だのばっかりで、気の利いたことひとつ言えやしない。事実だからって、なによ? アンタなんか、どんな男にも相手されないオモチャのくせに!」
(まぁ……。なにか逆鱗に触れてしまったのかしら)
くりっとした赤い目をぱちくりとさせるのは、“うさぎ”ではなくウォーマシンのブランクの方。白い渡り鳥によく似た造形のフェイスが、思慮深そうでもあり、また清純な佇まいを醸し出している。
「せっかく、ぶっ壊す前に気持ちよくしてあげようと思ったのに、恩知らずな機械だね!」
ぶよぶよした身体を怒りに震わせてうさぎが喚くのを、ブランクは相変わらず不思議そうに見つめ返している。
「話の腰を折ってしまって、ごめんなさい」
重しから解放されて立ち上がるブランクの動作は驚くほど静かだ。過剰な負荷をかけられて傷んだ肩からわずかに駆動音が聞こえるのみで、他の部位からはモーターの音ひとつしない。
「どうせ、アンタには“気持ちいい”なんて感覚、わからないんだろうけどさ」
「…………」
「かわいそうだよねえ、機械って!」
“キカイ”の音に最大級の侮蔑と悪意をたっぷりと乗せて、うさぎは唾を飛ばす。
「こーんなにステキで愉しいこと、宇宙のどこにもないっていうのに。できないんだもんねえ! そのカラダじゃさ!!」
優越感で醜く顔を歪ませて、うさぎはその巨体を驚くべき速度でブランクへとぶつけてきた。鈍い音が腰のパーツから聞こえる。先刻の茶番でベタベタと身体中を触ったときに、彼女の細い腰部分が弱点になるだろうとアタリをつけていたようだ。
「……っ!」
そして狙いも恐ろしく正確だ。半身になって回避行動を取ろうとしたブランクだったが、その動きをすら読んで白く細い腰を捉える。重心の高いブランクは衝撃を受け流しきれず、うさぎの質量に押されるがまま身体のバランスを崩した。
「ははッ、ちょっとのんびり屋さんすぎるんじゃない? 機械のクセに!」
ブルーのラインが入った金の“嘴”を掴むと、うさぎは反動をつけて機械仕掛けの白鳥を地に引き倒した。脂肪の詰まった短い腕がまるで鞭のようにしなり、ブランクのボディが派手な音を立てて石畳に激突する。先ごろからのダメージに加え、強かに打ち付けられた衝撃でブランクの右腕ががしゃんと外れて暗い路地の更に物陰へと吹き飛んでいった。
再び路地に倒れ伏し、ブランクはうさぎを見上げる。その向こうに、丸く大きな月が見えた。
――ああ。あなた、いとしいひと。
瞼を閉じれば、いつでも面影がそこにある。
再び目を開けて、ブランクは言った。
「知っていますわ。それが一体、どんな心地のものなのか」
「はぁ? そんなハッタリ、この局面で要らないんですけど?」
オモチャはオモチャらしく私に甚振られなさいよと、うさぎはブランクを足蹴にする。腹部を庇った脛にうさぎの蹴りを受けながらも、ブランクははっきりと答えた。
「いいえ、これは“事実”。――この身を焦がし、滅ぼしてしまうほど。あんなに心を揺さぶるものは、疑いようもなくほかにはありません」
身体を一度喪おうとも、覚えている。あるはずのない器官を求めて回路が暴れ狂う、あの切なく苦しい感覚を。会いたくて、触れたくて――、その腕に触れたら、その胸に抱かれたら、その唇に口づけしたらどんなにか幸せだろうと腹の底から沸き上がる欲求を。
ブランクの瞳が乙女の劣情を湛えてうさぎを真正面から捉えた。
「う、うそでしょ、アンタみたいな機械が……」
「はい。私のようなマシンをすら狂わせる、――それが、恋です」
「な――……ああああああああっ」
気圧されて後退りしたうさぎは、それ以上言葉を続けることができずに跳ね回った。身体の左右から熱い血が吹き出し、うさぎが跳ねるたびに飛沫が石畳を汚す。
「ごめんなさい、話が逸れてしまいましたね。……本来の役目に戻ります」
月光の中、ブランクの背後から二本のブレードが回転しながら飛来する。刃の端から飛び散る飛沫は、うさぎの両肩から滴るそれと同じ色をしていた。
「――あら」
肩から先を切り落とされたうさぎと両腕をパージした自分の姿を見比べて、ブランクは「私たち、お揃いですね」と事実を述べる。跳ね回っているうちにバランスを失ったうさぎは無様に石畳の上に転がったが、身体を支えるべき腕を失っては立ち上がることもできない。その上、いつの間にかうさぎを細いワイヤーが搦め捕り、身体の自由を奪ってしまっていた。
「あんなに暴れまわるから、絡まってしまいました」
カシャン、と軽快な音でブランクの両腕が戻る。その先から伸びる細い祟り糸を手繰り寄せ、うさぎの身体を引き摺った。
「いぃぃたいィィイ!! 許さない、許さないからッッ!!」
うぎが身を捩る度に糸が柔らかい肌に食い込み、擦る。そうしているうちに、まるでエッグカッターのようにうさぎの白い肌をプツリとワイヤーが破った。
「動くと余計に痛いですよ」
言いながら、ブランクは念動力でうさぎの身体を持ち上げる。腕の力で曳くよりは、まだ無用な痛みを与えずに済むだろう。
「“あの器具”も、本来は『苦痛を与えずに済ませる人道的な処置』として発明されたのですってね」
「……!」
ブランクの言葉と視線が示す先を悟って、うさぎが身体を硬直させた。
「待って、待ってよ!」
「ああ、言い忘れてしまいました。……本当はね、私の片恋だったのですよ」
寂しげな笑みを目に浮かべ、ブランクはうさぎを断頭台へと叩きつける。命乞いの叫び声が宙を舞った。「ここだけの秘密ですよ?」と付け加えられた言葉はうさぎの耳には届かなかった。が、その秘密は確実に守られるだろう。
「――まあ……。アームブレードと同じくらい、よく切れます」
ギロチンの刃が迷うことなく落下したのを見届けて、ブランクは独り呟いた。
大成功
🔵🔵🔵
 パウル・ブラフマン
パウル・ブラフマン
エッなにこの国女子多くない!?
出所後にちょっとずつ異性に慣れてきたとは云え
相変わらずの童貞ムーブ+挙動不審。
ママみのあるおねーさん系ウサギさんを標的に
【コミュ力】全開(必死)で庇護欲を煽ってみるね☆
オレ、実はまだ女性経験がなくって…
教えてくれるの?
折角ならスリリングに、特別なベッドの上で楽しみたいかな。
断頭台を軋ませて身体を重ねる寸前―UC発動!
現れたるは最愛の天使、自称悪魔の幻影。
彼女を逆に組み強いてニッコリ。
ゴメン、嘘じゃないんだ。
経験ないよ…女性相手はね?
触手で抑えつけて断頭台に固定、さぁ一気に幕を降ろそうか。
転げ落ちたうさぎさんの額に
おやすみのキスの代わりに、Krakeの弾丸を贈るよ。
●
(――エッ。なに、この国。女子多くない!?)
転送されるや否や速攻で元時計うさぎに襲われかけたパウル・ブラフマン(Devilfish・f04694)は、あまりにもびっくりし過ぎて思わず全力で逃走した。手頃な物陰に身を潜めるも、すぐに新手のうさぎがパウルを発見してしなだれかかってくる。それをまた必死に躱して“死地”を切り抜け、入国わずか数分で息も絶え絶えである。
生娘か、と宴会の席でおじさんたちにセクハラ発言を浴びせられそうなほどの初々しさは、彼が“人間らしく文化的な生活”を手に入れたのがごく最近のことである、という経歴に由来している。
なぜか漂う不思議な良い香り、柔らかい肌と皮下脂肪の感触、ドキリとさせる加減を知り尽くした絶妙なボディタッチ――オトコを狩る気満々な肉食系女子の濃厚な色香は、パウルにとって猛毒にも等しかった。『発情したうさぎどもを上手いこと誘い出して断頭台に乗せろ』というミッションを請け負ったにも関わらず、彼は反射的にうさぎたちを突き飛ばし、その場から逃げ出してしまう。
(多少は慣れてきたつもりだったけど、これは――……)
やっとの思いで確保した安息の物陰で、パウルは頭を抱えた。暗闇で実際には見ることができないが、彼の青白い肌が羞恥で真っ赤に染まっている。
ここに、“彼”がいてくれさえしたら少しは気持ちが安定するだろうに――と思いかけえて、いやいやと頭を振る。それはダメ、ぜったい。一番見られたら気まずい相手じゃないか。
(でも、やらなきゃ)
ぺちん、と両の手で自分の頰を挟む。確かに女性に対してはまったくのシロウトだ。女の子が半径1メートル以内に接近したら挙動不審になる。そういう自信だけはめちゃくちゃある。しかし、色恋に関してはもうシロウトとは誰にも言わせない。オレだってやるときはやるのだ――。
見開かれた青い左目ときつく結ばれた唇が、パウルの覚悟を物語っていた。
「もう〜。あの子、どこ行っちゃったのよ!」
「アタシも逃げられたぁ。彼、足めっちゃ速くない?」
細い路地の出口に近寄って外の様子を伺うと、先刻パウルを襲ってきたうさぎたちが息を切らしてぼやいているのが聞こえた。気配を殺しながら聞き耳を立てて、2対1でイケる――いや、ヤれる、いやどっちの表現もなんかアブナい――だろうか。とりあえず“ある程度は経なければならない過程”のことは無視して、純粋な勝算を見積もる。――が、
「アンタ、あの子の触手見た?」
「見た見た! ぶっとくて逞しいやつぅー」
「ぬるぬるしてたし、絶対アレって超キモチいいよね」
「わかるぅ、早く捕まえて最期の一滴まで搾り取りたぁい♡」
うさぎたちは身体をくねくねさせてあられもない会話に興じていた。息が乱れているのは、肥満体で走り回ったからだけではないようだ。
彼女たちの際どい言葉に、パウルは己の下半身へ視線を下ろした。衣服の端からニュルッと顔を覗かせているのは、ネオンブルーの色をした蛸の足である。――ああ、なぜ顔も知らない俺の創造主は、触手なんてものを与えたもうたのか。無垢さ故に自分の出自や身体にネガティブな感情を持つパウルではなかったが、こんなときばかりはちょっとくらい恨めしく思ってもいいのではないだろうか。きっと誰も怒らない。
(ダメだ。あの子たち、ニガテ……)
自分の得手不得手を過不足なく弁え、そして戦う相手を見定める。これは戦士として重要な能力である。蛸の因子を持つキマイラの青年は、そそくさとその場を後にした。
とはいえ、一体どんな相手ならば自分にも太刀打ちできだろうか。むしろそんな相手がこの戦場に存在するのだろうか。途方に暮れたまま路地を歩く。
――と、ついにその時が訪れた。
「あらぁ、可愛いタコちゃん。迷子になっちゃったの?」
だしぬけに、小径を挟んだ建物の上から艶めいた声が降ってきた。パウルがハッとして振り仰ぐと、月の光に照らされた時計うさぎがにっこりと微笑んでいる。波打つ長い髪が豊満な身体に沿って流れ落ち、目許には泣き黒子――「おねえさんが教えてアゲル♡」と効果音付きでイメージボイスが流れてきそうな、年上おねえさまうさぎの登場である。
(おねえさま、きみに決めた――!!)
タクシードライバーの業務で培ったコミュ力をフル稼働させて、「この相手ならば自分にも付け入る隙がある」と本能的に察知する。そのコミュ力を肉食系女子にも発揮したらええやんか、とは言ってはいけない。繰り返すが、己の得手不得手を心得た上で活用してこその特技なのだ。
「そ、そうなんです。その……押しの強いうさぎさんたちから逃げ回ってたら、自分がどこにいるのかわからなくなって」
そうと決まればパウルも必死に“おねえさま好みのウブな坊や”を演じる。
「うふふ。ガツガツした女の子は、苦手なの?」
恥じらうパウルの仕草にまんまと釣られたうさぎが、屋根の上から降りてきた。残念ながら“軽やかに”とはいかなかったが、どすんという重い音に続いて漂う甘い香りは、うさぎのまるまると太った体型を忘れさせる程度には心地好い。
「オレ、実はまだ経験なくって……。その、女の子と……」
白くぷっくりとしたうさぎの指に顎をくすぐられながら、パウルはもじもじしてみせた。うさぎも「いじり甲斐のある可愛い子」と思ったのだろう、目尻を下げてパウルの反応を楽しんでいる。
「そうなの? こぉんなに立派な……触手があるのに」
「……っ」
身体をぴったりとくっつけて、空いた手でパウルの触手を擦り上げる。ぷにっとして、それていて筋肉のたくましさを感じさせる手触り。うさぎはうっとりとした表情で「あん、ステキ……」と溜息まじりに呟いた。
「おねえさんが、教えてあげよっか?」
耳元にかかる熱い吐息。甘い体臭から醸し出される酔い心地に冷や水をかけるほどに、生臭い。――血の匂いがする。パウルは身を震わせたが、それは身体を撫で回される快感にではなかった。
「……せっかくなら、特別なベッドの上で教えてくれない?」
柔らかく軋む上等なベッドもいいけれど。こんなシチュエーションで経験するなら、行き着くところまで逝かせてほしい。スリルと快楽をぐちゃぐちゃにかき混ぜれば、それはきっと最高に気持ちがいいはず。
「うふっ。愉しいこと言うのね。アナタ、才能あるんじゃない?」
パウルが指し示した断頭台のシルエットを一瞥して、うさぎは唇を歪めて笑った。
禍々しい形をした処刑台の影に、男女の影が加わる。男は細い身体の下半分から触手を淫猥にうねらせ、それを太った女がもったいつけて玩ぶ。もしも一般的な感覚を持ち合わせる人がこの光景を目にしたならば、「なんて悪趣味な儀式だ」と顔をしかめたことだろう。
「震えちゃって、可愛い……♡」
ちゅ、とわざとらしくリップ音を立てて、うさぎが触手に口づけする。ぬめる粘膜に這わせた唇はだらしなく開き、這い出た舌の先端でちろちろと舐めてみせた。触れるたびにピクンと跳ねる軟体動物の足にすっかり満足したうさぎは「どう? 我慢できない?」と、上目遣いでパウルを見上げた。
「アナタの“はじめて”、おねえさんにちょうだいね。それから、“最期”も――、ッ!?」
肉欲と食欲に塗れたうさぎの瞳が驚愕に塗り替えられたのは一瞬のことだった。
「――騙したのね……っ?」
己の身体を絡め取り押さえつけるのは、先刻まで自分が可愛がっていたはずの青い触手。
「ゴメン、嘘じゃないんだ」
子猫のように震えていたウブな青年は、今や冷たい微笑で自分を見下ろしている。「経験ないよ――“女性”相手は、ね?」
その言葉が意味するものを察したうさぎの顔は、みるみる怒りの色に染まった。
「ちくしょうッ、年増だからってバカにしたわね!?」
「別に、年齢なんかで差別しないよ。好きになったのが“彼”だっただけ」
『彼』と熱を帯びた目線で示されたのは、まるで悪魔のような姿の青年。赤い角を持つ、オウガを裡に飼い慣らす男。その悪魔の幻影がパウルを守るようにして寄り添い、刺すような視線でうさぎを見た。
『俺の愛しい天使。大切な光――こいつの魂に手を出していいのは、俺だけだぜ』
燃える情熱がパウルの胸をちりちりと灼く。愛しい人。オレの居場所。
「オレの“はじめて”も“最期”も。ぜんぶ、彼のものだから」
ユーベルコードに託された愛と、月の光がパウルを包み込む。
「やめて! やめてェ!!」
声を枯らして力の限りもがくうさぎだったが、青くうねる触手ががっちりと抑え込んでぴくりとも動けない。さっきまで、あんなに弱々しそうに震えていたのに。蛸の締め上げる力は徐々に増していく。
仰向けに押さえつけられたうさぎの目に焼き付いたのは、可愛い獲物の絶望の表情ではなく、豪速で滑り落ちてくる鈍色の刃だった。
石畳の上にごろりと転がった首は何も言わない。ひとしきり吹き上がった血飛沫も止み、流れた血は石の上で凝固を始め、あるいは石と石の隙間に染み込んでゆく。そうして、うさぎの血はアリスたちのそれと同じように広場を染めた。
恨めしそうな表情のまま凍りついたうさぎの目許には、泣き黒子がひとつ。
「――おやすみ、おねえさん」
ドン、と銃声が広場に響いた。
大成功
🔵🔵🔵
 オルヒディ・アーデルハイド
オルヒディ・アーデルハイド
至福の時間とは
美味しいものをお腹いっぱい食べるとき
うさぎの穴には美味しそうな料理が所狭しと並べてあります
能力を使ったからお腹が空いて腹ペコなのです
状況を忘れて食べたい衝動にかられ無邪気にむしゃぼりつく
見事なハニートラップ
自覚したわけじゃないけど
無邪気に食べる事で逆に天然にハニートラップを仕掛けます
人をダメにするラビットが近づいてきたら
『華麗なる姫騎士』で変身して飛翔能力で
引き離し過ぎないようにある程度の距離を保って逃げ
断頭台がある場所まで誘導
断頭台のくぼみの間をすり抜け
人をダメにするラビットの脂肪がくぼみに引っかかったところで
至福のひと時をありがとうと御礼と言ってトドメ
●
月明かりに照らされて、オルヒディ・アーデルハイド(アリス適合者のプリンセスナイト・f19667)は石造りの街をてちてちと歩いていた。7歳という年齢にしても標準より小柄でぷにぷにとした身体つきに長く豊かな銀髪、リボンとフリルたっぷりのドレス姿は、まさに『不思議の国に迷い込んだアリス』そのもの。あどけなさが人の形を取ればこんな風だろうと誰もが納得するような幼児は、人気のない夜の街には似合わない。しかし、それは普通の街、普通の人間ならば、の話である。
自らの意志でこの国に降り立ったオルヒディは例に漏れず猟兵の一人であり、そしてかつてオウガの一人にこの世界へと呼び寄せられたアリスの一人でもあった。今夜はグリモアの力でここまでやってきたが――、
(あれは、いったいどういう意味だったんだろう?)
転送直前にグリモア猟兵が見せた心配そうな顔を、オルヒディは思い出していた。「本当に、大丈夫なのか」と、彼はそうも言っていた気がする。「嫌なら行かなくていいんだぞ」と。しかしオルヒディはこの世界に平和をもたらす一助になりたい一心で、「大丈夫!」と力強く応えた。自分と同じようにすべてを失くして逃げ惑うアリス達を救うために。そして、自分が失くした大切な何かを取り戻すために。
「……うさぎさん、出てこないね?」
ぽつり、とオルヒディが呟くと、その隣をぽてぽてと歩いていたピンク色の生き物が「なぁ~ん」と答えた。獣、というべきか、竜、と呼ぶべきか、それは“フワリン”とオルヒディが呼ぶ召喚獣であり、馬のように人間や荷物を運搬する能力を持ったオルヒディの相棒である。うさぎたちがいつ襲い掛かって来ても大丈夫なように到着した時から警戒態勢を取らせていたのだが、オルヒディがいくら歩き回ってもそれらしい敵の姿は見当たらない。
「どうしてだろう」
首を傾げるオルヒディに、「それはね、年端も行かないいたいけなお子さまにあんなことやそんなことなんてとても以下略」と丁寧に教えてくれる者はいない。
「はあ、おなかすいちゃった」
幼い脚で歩き回っていたオルヒディはついに立ち止まり、その場にぺたりと座り込む。フワリンに警戒態勢を取らせるのも猟兵の力を使う。消耗した分はダイレクトにオルヒディの胃袋を刺激した。
その時、
「――ん。あれっ?」
ほらほら、がんばって!と主を励まそうとするフワリンをよそに、オルヒディはパッと顔を上げた。幼子の五感を刺激するのは――、
「おいしそうな匂いがする!」
くんくんくんと鼻をひくつかせて、オルヒディは立ち上がった。疲れた身体を誘うスパイスの香り。胃袋を満たしてくれそうな肉の匂い。そしてこの香ばしさは――、チーズが焼ける匂いだろうか。甘いシナモンはデザートのアップルパイかもしれない。
オウガが治める国でアリスをもてなしてくれるところなどどこにもない。あったとしても、そのお代は自らの血と肉で支払わなければならない。――そんなことは、すっかり腹をすかせた幼いオルヒディにはわからない。ごちそうの匂いがする方向へ、疲れを忘れてアリス兼猟兵の幼子は走りだした。
「うわぁ……!!」
きのこのクリームシチューにラムチョップの香草焼き、カチョカヴァッロのステーキにほうれん草とジャガイモのスパニッシュオムレツ。ご丁寧に用意されたテーブルの向こう側にはおかわり自由とばかりに色とりどりの果物ジュースがガラスのピッチャーに入れられて行儀よく並んでいる。
オルヒディは目をきらきらと輝かせて、自分を出迎えたごちそうたちを一皿ずつ見比べた。どれもこれも、本当においしそう。いろんな世界のいろんな国から取り寄せたような、豪華な食卓。不思議の国にはこんな出来事はしょっちゅうだ。
しかしオルヒディの後ろでは、フワリンがそわそわと落ち着かない様子で不安げな顔をしていた。それもそのはず、ここは街角のレストランなどではなく、奇妙な洞穴の中なのだ。オルヒディがごちそうの香りを辿って走った先に、なぜかぽっかりと洞穴が口を開けて客を待っていた。石造りの街のど真ん中で。どう考えても不自然なシチュエーションである。フワリンは「いや、これ絶対罠ですよ、ご主人!」と全身で訴えているのだが、はらぺこオルヒディにはまったく届かない。不自然にランプで照らされた洞穴の中、不自然に整えられた席に躊躇なく座って、ごくごく自然な動作で「いただきまーす!」と手を合わせた。
――まずはスープから。ひんやりと冷やされたコーンポタージュは、丁寧に裏ごしされて舌触りは絹のように滑らかだ。採れたてとうもろこしの極上の甘さが疲れた身体に染み渡る。次は何にしよう? あのきらきらしたゼリーとお肉。金色のコンソメゼリーを砕いて散らした皿の真ん中には、四角いパテ・ド・カンパーニュが行儀よく座っている。スライスされた切り口から覗いているのは、黄緑色の枝豆だ。フォークで切って口に運べば、柔らかく蒸された肉とコリコリした豆の歯応えが楽しい。
「おいしい~!」
今度はグラタン。とろーりとしたホワイトソースにこんがりチーズ。あつあつ、はふはふと口をせわしなく動かしながら焼きたての味を隅から隅まで味わう。中に隠れているのはマカロニではなくジャガイモだった。骨付き肉には大胆に齧りつき、物語の登場人物になりきったようにワイルドに食いちぎる。パリッと焼けた皮の下には旨味たっぷりの肉。じゅわっと滴る肉汁がドレスを汚さないように、オルヒディは慌ててナプキンを添えた。
次の皿に進む前に口の中をすっきりさせなくては、と選んだのは、ブドウのジュース。濃い紫色の液体からはこれまた濃いブドウのふくよかな香りが立ち上る。オルヒディが大人であったなら、ここはきっとフルボディの赤ワインだっただろう。
ひとしきり食べて満足し、さて最後はどのデザートを選ぼうかな――と、オルヒディがドルチェのショーケースを物色していた頃。
「うふふ、美味しかった?」
――いつの間にか、背後に誰かが立っていた。
「誰っ?」
すっかり油断していたオルヒディは、驚いてぴょんと飛び退る。その拍子にドリンクのピッチャーにぶつかってしまい、リンゴジュースの入った器が倒れてがしゃんと砕けた。
「あ――、ご、ごめんなさい」
「あらあら、良い子ね。大丈夫よ、あとで片付けるから」
反射的に謝罪を口にしたオルヒディに、相手は顔を綻ばせた。頭を下げたまま、ちら、と目線をやれば、その頭には白いうさぎの耳が生えている。
(時計うさぎ――!)
ついに倒すべき相手を引きずり出した。そう確信すると同時に、オルヒディは自分がたいらげた絶品料理の数々を思い浮かべた。
(なるほど……! あれが『ハニートラップ』!)
「いや違う、そうじゃない」とツッコミを入れてくれる人はここにはいない。だがこの場合その勘違いはそっとしておくべきだろう。なにしろオルヒディは7歳のいたいけな子供である。まだ知らなくていいことはたくさんあるのだ。
やけにニヤついた顔をしたうさぎを目の前に、オルヒディはさてこの大きなうさぎさんをどうやって断頭台まで誘導しようか、と思案した。――事前に聞いていた「たいしぼうりつよんじゅっぱーせんと」というのがどういうことなのかをまざまざと見せつけられながら。
対してうさぎはオルヒディの頭のてっぺんからつま先まで、舐めるようにじっくりと品定めした。
「うぅん、かわいい♡ いっぱい食べる元気な子、だーい好き」
くね、と身体をしならせるたびに腹の肉がぷよんと揺れる。
「……でも私、おマメ料理よりもニンジン料理の方が好きなのよね」
ちょっぴり残念そうな声音に、オルヒディは「ボクはどっちも好きだよ?」と首を傾げる。言わんとするところを全く察しないその純粋さに、うさぎは満面の笑みで「好き嫌いのない子も、大好きよ~!」とぼよんぼよん飛び跳ねる。幼児を狙う不届き者は、やはり幼児ならではのピュアさに目がないらしい。ぎゅうううう、と力の限りオルヒディを抱きしめて、どさくさに紛れてドレス越しの手触りを楽しんでいる。
「ひゃ、く、くすぐったいよう」
おなかいっぱい食べて体温の上がった肌から立ち上る汗の香りにくんかくんかと鼻を動かすうさぎ、その仕草にたまらずオルヒディがもじもじした。
「いっぱい食べてぽんぽこりんになったおなか、たまんない……!」
幼い身体を抱きしめていた腕をじりじりと下へ動かし、子供の身体の頼りなげな細さ、そして幸せのかたまりとでも言うべき柔らかさを確かめていく。――おまわりさーん!この人です!!わたしじゃありません!!!
「――んっ。ちょっと待って!」
ナニかの感触に気付いて、うさぎはバッと顔を上げる。
「……っ!!」
ナニかに触れられた感触に気付いて、オルヒディも顔をこわばらせる。なんで、そんなところを触るの? 子供にはわからない。知らなくていい(二回目)
「あなた、男の子!?」
「う、うん――」
戸惑うオルヒディをよそに、うさぎはみるみると喜色を顕わにした。
「んもう、そういうことは早く言ってよね!」
どんだけ飢えてんだお前、と誰もツッコまないが、うさぎは「もう待ちきれない!」と自らの着ている服を次々と脱ぎ捨てていく。
「あわわわ。うさぎさん、服を着て!!」
おいしいごはんを食べただけなのに、どうしてこんなことになっているのか。オルヒディにはさっぱりわからない。わからないが、直視してはいけない。そんな空気は察した。顔を覆ってうさぎのぶよぶよと肥えた肥満体から必死に目を逸らしている。しかし久しぶりのドストライクな獲物を捕らえたうさぎの辞書にブレーキとか自重とかいう言葉はなかった。
「ボクの皮つきニンジン、おねーさんに食べさせて!」
おねーさん、もうちょっと言葉を選んだらいかがだろうか。それとも選んだ結果がこれなのだろうか。全裸になったうさぎは一片の恥じらいも見せることなく眼前の美少年に飛びかかった。
――が。
「愛と勇気と希望を抱きしめて――フェアクライドゥング!」
「――!?」
洞穴の中が一瞬にして光に満ちたかと思うと、オルヒディの姿が凛々しいプリンセスナイトに変身した。彼女――ではなく、彼の、飛翔能力を得る強化型ユーベルコードである。
「うさぎさん。そんなにニンジンが食べたいなら、ここまでおいで」
正直言ってオルヒディは「ボク、ニンジンなんて持ってないけどなあ?」とめちゃくちゃ思っている。思っているが、うさぎが「オルヒディはニンジンを隠し持っていて、それを食べたい」らしい、というのはなんとなく理解した。ならば自分がニンジンを持っているフリをしてこのまま断頭台まで誘き出せばいいのだ。
「ああん、鬼ごっこなの? いいわよぉ、付き合ってあげる!」
色欲に狂ったうさぎは「理想のショタとくんずほぐれつ鬼ごっこ、捕まえたあとはウフフ♡」という妄想にどっぷりと浸かったまま空飛ぶ男の娘を追いかけた。
「ほーら、こっちだよ!」
「待て待てぇ~」
月夜に浮かび上がる、プリンセスナイト(男)と脂肪の塊(痴女)。これはいったいどんな悪夢なんだろう。眩暈がしてきた。――が、幸いなことに悪夢は長くは続かない。
「――いやん!」
オルヒディが身体の小ささを活かして断頭台の間をすり抜けた後、うさぎがまんまとその肥えた身体を詰まらせたからだった。
「あ~ん、引っかかっちゃったあ。ねえ、ボク。ちょっと待ってくれない?」
あくまで「子供と遊んであげる優しいおねえさん」を演じようと努めるうさぎだったが、全裸な時点で全て台無しである。オルヒディはそんなうさぎを空から見下ろして、
「至福のひとときをありがとう、お姉さん」
ギロチンの刃を繋ぎ留めていた縄を断ち切った。
大成功
🔵🔵🔵
 ジャスパー・ドゥルジー
ジャスパー・ドゥルジー
かわいこちゃんが子兎ちゃんでも子豚ちゃんでも
男でも女でも
些細な問題っしょ?
誘いに乗った振りして抱きしめる
んふ、俺の手が回りきらないじゃん
たぷたぷしててかーわいい
その美味しそうな躰でさ、極楽に連れてってくれんだろ?
警戒…いや、緊張してる?
大丈夫、俺も半分くらいオウガだから
折角のお楽しみに敵だの味方だの野暮ってもんだろ
俺の事目いっぱい味わって?
差し出した身体は【ユーフォリアの毒】の塊
舌でも這わせようもんならたちまち抗えない多幸感が動きを阻害する
イかされるのはあんたの方ってね
俺こーみえて操立ててるんで!ざんねんでしたァ!
毒で動けねえ豚を断頭台に投げ…投げらんねェ!!
重い!!(ぜーはー引き摺って行く)
●
「みぃーつけたァ」
暗闇の中からぬうと突き出た腕に肩を掴まれ、元時計うさぎのオウガは息を呑んだ。慌てて振り向けば、その腕の先には悪鬼がニタリと歪な歯を覗かせて笑っている。
「ちょっ、……ヤダ、もう。驚かせないでヨ!」
不意の呼びかけに迂闊にも怯んでしまった己の不甲斐なさをごまかすように、うさぎはケラケラと姦しく笑ってみせた。青白い顔をした“悪鬼”の額からは、その病的な体躯に不釣り合いなほど存在感のある、太い角が前に突き出している。目の上や唇、そして身体の至る所にピアスが鈍く光り、闇の中でもチラチラと存在を主張している。きっと彼の身体はそこらじゅう穴だらけなのだろう。総じて外見の印象は“オウガ的”――つまり“お仲間”のように見えるのだが、うさぎは本能的に知っている。この悪魔が猟兵であることを。自分を殺しに来たことを。
「随分とんがった子が来たわね」
それでもうさぎは余裕めいた態度を崩すことなく、鬼を品定めする。この子は愉しませてくれるかしら? どんな啼き声を聞かせてくれるのかしら? ――どこまで壊したら、無様に命乞いをするかしら? その瞬間を想像するだけで氷のような快感が背筋を駆け上ってきた。
その一方で、ジャスパー・ドゥルジー("D"RIVE・f20695)もまた内心でうさぎを値踏みしていた。
(とんがってるだって? 否定はしねェが、ありきたりすぎてツマンネー評価だな)
淫猥な衝動を満たそうとするオウガのくせにぶよぶよの肉体を気にも留めない――そっちの方がよっぽど“とがってる”と思うがな。ぽっちゃり系女子を見下そうなどとは思ったこともないが、“効率よく”男を狩りたいのであれば最適解は『スレンダーでありつつ出るところは出ている、メリハリのある身体』だろう。なにも、ぽっちゃり系専門の男を探すとか、趣味じゃない女を前にした男を一生懸命誘惑すとかいう労力のコストをわざわざ支払う必要はないのだ。それとも、そういう苦労を味わうのも愉しみのひとつだとでも言うのだろうか。――なんて、ね。
「そう? まあ、俺ほどイカれた奴は俺も見たことねーケド」
ジャスパーは腹の裡をおくびにも出さず、しれっとした態度で耳のピアスを弄りながら答えた。
「そういう子豚ちゃんは、まるまると太っておいしそーじゃん」
「バカにしないでくれる? こう見えても皆よりは痩せてる方なンだから」
マジかよ。――とは、口には出さない。ジャスパーの言葉に抗議をしてみせるうさぎは、しかし真剣に腹を立てている様子でもない。わざとらしく口を尖らせたり、腕を組みかえるふりで胸を寄せてみせたりして、獲物の誘惑に余念がない。ジャスパーとの会話を楽しんでいる風さえある。
それにしても、この体形で『痩せている方』とは。ジャスパーは自分の身体を見下ろした。あばら骨が浮き出るほどに痩せた胸、女物のパンツも履けるくらいに細い腰。筋肉がないわけではないが、皮下脂肪という概念をどこかに忘れてきてしまったような身体つきは、うさぎとは対照的だった。
(どンだけ食っちゃ寝すりゃこんだけ肥えるんだよ……)
女の方が太りやすいって、聞いたことがないでもないけれど。
とはいえ、肥満という物差しでオウガたちを計ろうとしても、あまり意味はないのかもしれない。なにしろ、どんな巨体であっても素早く動き回るような物理的法則を無視する奴は腐るほどいる。ジャスパーはこの国にはびこる生活習慣病について考えるのをやめた。
「まァまァ、些細な問題っしょ?」
言いながら、ジャスパーはうさぎの肩に腕を回す。うさぎも「え~」と言いながらまんざらでもない表情でジャスパーに抱かれるがままだ。
「かわいこちゃんが子兎ちゃんでも子豚ちゃんでも。――男でも女でも、さ」
――やっべ、反対側の肩までが遠ッ! ワンアクションですっぽりと抱き寄せる予定が、目測を誤って背中の中途半端な場所に爪を引っかけた。
「あン」
幸い、うさぎは「積極的なボディタッチ」と受け取って無駄に甘い声を上げている。
「男でもって、――ふふ、あんたってやっぱりとんがってるわね」
「極楽に連れてってくれるかわいこちゃんは、みんな、だーいすきだぜ」
肩甲骨の上にもたっぷりと乗った脂肪をやわやわと摘まみながら、ジャスパーはうさぎの耳に吐息を吹きかける。ふわふわの白い毛に包まれた長い耳は、ぴくぴくと小刻みに震えていた。
「あ、……あっ」
「んふ。たぷたぷしてて、かーわいい」
「もう…っ。男って、ン、そうやって摘まむの好きよね。ぁ、やぁ、なんで?」
「んー? そりゃやっぱ、やーらかくてキモチイイからじゃん?」
むっちりとした背中の肉を伝って、指先を下へと下ろしていく。腰から脇腹へ指を伸ばそうとしたものの、うさぎが纏った燕尾型のジャケットは背中側の丈が長くて手を差し入れる隙間がない。それ以前に、太った身体を無理矢理詰め込んだようなフォーマルジャケットはあまりにも窮屈そうで、生地の切れ目を見つけたとしてもそこから指を中に入れようものなら縫い目が弾け飛んでしまいかねなかった。さてどうしたものかとジャスパーが思案していると、うさぎは、
「やーらかくてキモチイイところを触りたいなら、他の場所があるでしょ?」
と言って自らジャケットを脱ぎ捨てた。露わになった白い肩の肉は、ぷるんと揺れてまるでミルクゼリーのよう。逆の意味で“おいしそう”に見えた。――まあ、これはこれで、むっちりまあるい子豚ちゃんだって嫌いなワケじゃねーけど。スタイルのいいすっきりボディを美しいと思う気持ちだってあるけれど、ぷるぷる弾けそうなもっちりボディだって「噛みついて舐めたら楽しいだろうな」と思ってしまうものなのだ。唇で挟んで舐めればきっと吸い付くような舌ざわりだろうし、軽く歯でも立てれば弾力のある柔らかい食感がやみつきになるのは間違いない。
ジャスパーの繊細な男心には気づきもしない様子で、うさぎはビスチェの前をべろんとずり下げた。巨大な乳房をなんとか覆い隠していたカップが倒れ、解放されて自由になった脂肪の塊が重力に従ってぼろんと垂れ下がる。
(でっけぇナスみたい、とか言ったら怒られンだろーな……)
茄子紺という言葉があるように、UDCアースなどでは黒に近い濃紫の茄子が一般的ではある。それ故だろうか茄子はどちらかといえば男性を暗示するような隠語として使われる場面がなくもない――が、実は茄子は白い実をつける種類の方が浸透している世界や地域もあるのだ。形も千差万別で、細長いものから丸いものまで、大きさもさまざまだ。ジャスパーの目の前に惜しげもなく晒されたうさぎの乳房は、立派に育った白茄子によく似ていた。実が詰まってパンパンにはち切れそうな皮膚も、どこか得意げに突き出した先端もそっくりだ。
「ほら、好きなだけしゃぶっていいのよ?」
こんなに立派なオッパイなんだから、さぞかし飛びつきたいでしょう?と、男の本能を盲信して胸を張るうさぎに、ジャスパーは苦笑した。――わかってねーな、子豚ちゃん。
「子豚ちゃんこそ、俺にしゃぶりつきたくてしょうがないんじゃないの。さっきから腰が動いちゃってンよ?」
身体をまさぐる度に甘い声が弾け、身体を跳ねさせていたうさぎの瞳は、既に濡れて溶けそうになっている。
「久しぶりのデザートじゃん。遠慮なく、めいっぱい味わって?」
余裕のあるふりを演じていても、やはり飢えていたのだろう。アリスの供給が断たれたことで腹を満たすものがなくなってしまったし、何もせずにアリスを食える環境では情欲を満たす獲物にありつくこともできない。二重に渇いていたけだものは、ジャスパーが誘いのフレーズを言い切る前にその首筋に齧りついた。
「あハっ、おいしい、おいしい……っ!」
ちゅぱ、ちゅぱ、と幼子が母の乳房に吸い付くような音を立てて、ジャスパーの青白い肌をうさぎが吸う。舌で舐めれば骨の形まで伝わってくる。肉付きの悪さはちょっとばかり気になるところだけど――その分、めいっぱい愉しめばいい。ガリ――と、今度は鎖骨の浮き出た肩に強く歯を立てた。
「……っ」
舌を伝って口の中に滲む鉄の味。獲物から漏れる、苦痛とも快楽ともつかぬ呻き声。いい。いいわ。とっても素敵。もっと私を愉しませてちょうだい。うさぎは尋常でない速度で快楽に夢中になっていく。
「可愛い声じゃない。もっと、もっと気持ちよくしてあげる」
欲に濡れた声と息でジャスパーにしがみついたまま、うさぎは薄い胸板を撫でまわしていた腕を腹の下へ伸ばした。「いっぱい、イかせてあげるわ。天国にね」
「――……」
哀れみと軽蔑、それから慈悲の混ざった表情で、ジャスパーはうさぎを見下ろしていた。ユーベルコードの効果で猛毒に変化したジャスパーの身体をたっぷりと味わった憐れなうさぎは、狂気に堕ちた瞳で宙を見つめている。独りで己の身体を慰めながら、よだれ混じりに幸せそうな喘ぎ声を漏らしていた。
「……イかされるのはあんたの方、ってね」
既にうさぎは正気を失い、夢の世界から戻ってくることはない。
「さーて、この豚を断頭台にブン投げますか」
よっこらせ、と地べたにだらしなく横たわるうさぎの身体を持ち上げ――ようとして、ジャスパーは苛立たし気に放り投げた。
「重てーな、オイ!!」
意識を失って重心を保てない人の身体を持ち上げるのは、ただでさえ困難な仕事だ。それが更にフォアグラのガチョウよろしく存分に肥え太らされた獣であれば、尚更。仕方なく、ジャスパーは手近な断頭台へうさぎを引きずっていくことにしたのだった。
大成功
🔵🔵🔵
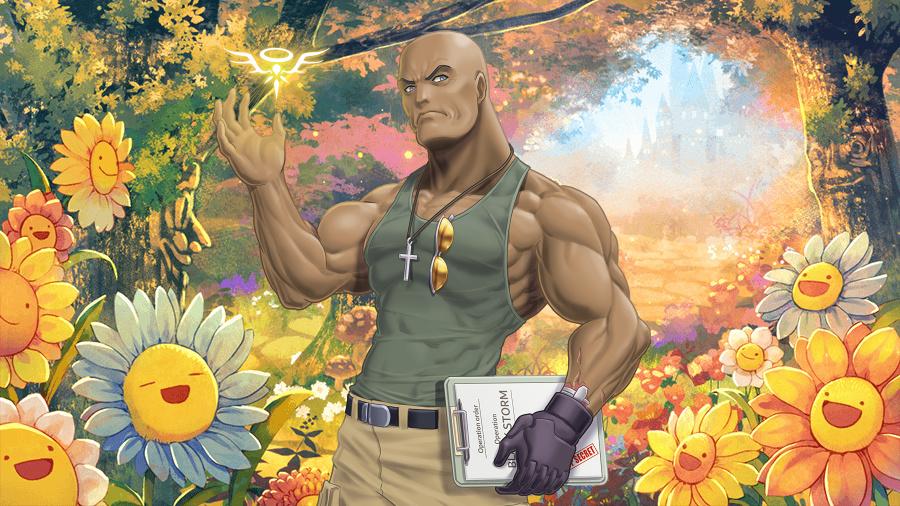
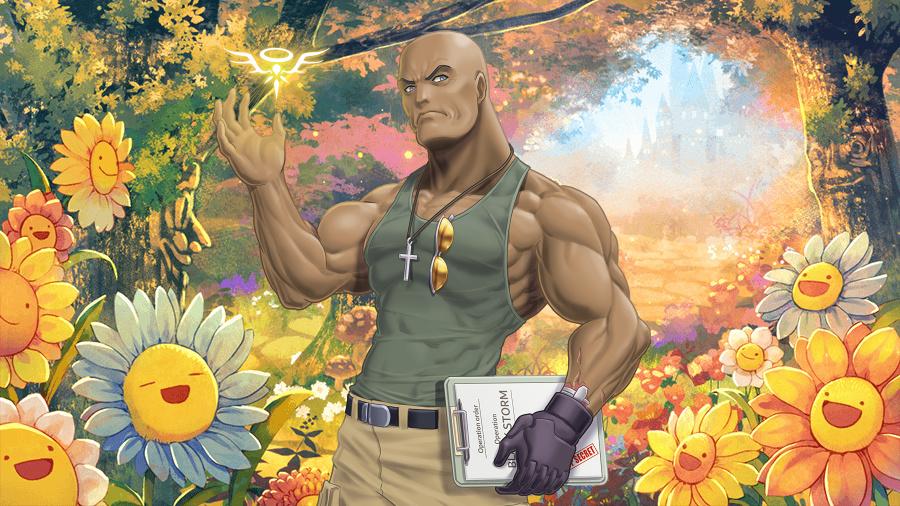

 フィランサ・ロセウス
フィランサ・ロセウス  ブランク・ディッシュ
ブランク・ディッシュ  パウル・ブラフマン
パウル・ブラフマン  オルヒディ・アーデルハイド
オルヒディ・アーデルハイド  ジャスパー・ドゥルジー
ジャスパー・ドゥルジー