#アリスラビリンス
タグの編集
現在は作者のみ編集可能です。
🔒公式タグは編集できません。
|
●
アリスラビリンスの中に生まれた世界。
無数にある、その一つ。つい最近に生まれたその世界で、アリス適合者として迷い込んだ者が殺される、そんな事件を球体が予知をした。
「まるで舞台装置のようです」
グリモアベースに映るのは、盤目のように菱形模様が並べられた平らな大地。その中心に聳えるのは、荘厳な城だ。
だが、そこに民の姿は無く、建造物だけが静かにたたずむその光景は、言葉通りに演者を待ち侘びるセット背景のようでもあった。
「オブリビオンは、この城の中心に存在しています」
猟兵達は、この城に侵入し、その先のオブリビオンを撃破して、アリスを危機から救わなければいけない。
オブリビオンは、城からは出てこない。
アリスが自ら逃げてくれるのであれば、オブリビオンの存在場所が明確な分、安全の確保は容易いはずだが、しかし、事態はそうはいってくれない。
「このアリスは自らのユーベルコードを使用しながら、オブリビオンの撃破を狙っています」
なんとも猛々しいアリスではあるが、しかし、アリス一人でこのオブリビオンに敵うはずもない。
更に、オブリビオンに至る前に、初めの障害となるのは、このアリスのユーベルコードによる妨害だという。
「妨害というには些か、変わった趣向である、と言わざるを得ませんが」
舞台に立つ資格がある者だけが城の中へと入れ、とばかりの妨害。
とはいえ、アリスであれば難しいかもしれないこの試練も、猟兵達にとっては容易いものに違いないと、球体は語り。
「アリスと共に」
そうある事をアリスが望むのなら。
「オブリビオンを撃破して下さい」
最後に告げて、球体は転移を開始した。
 雨屋鳥
雨屋鳥
アリスラビリンスです。
各章にオープニングを追加します。
よろしくお願いいたします。
第1章 日常
『ハッピー・ハッピー・ホリデイ!』
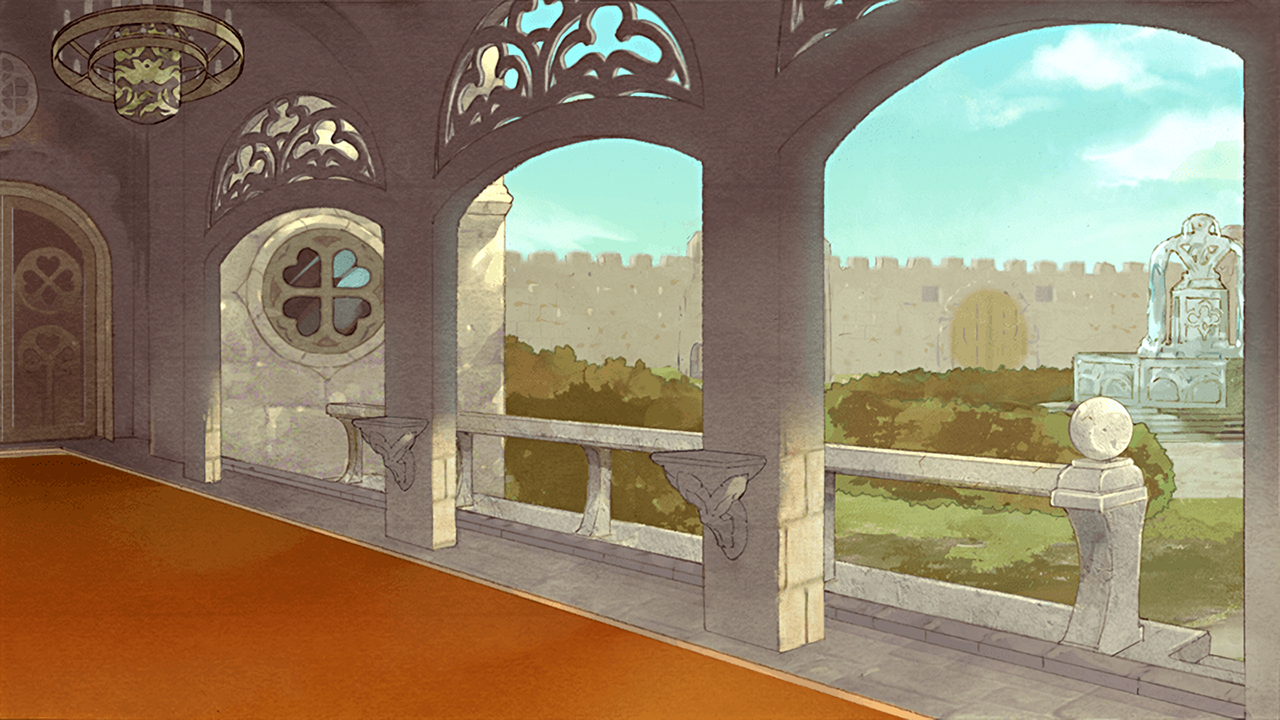
|
POW : 力強くお祝いをする。
SPD : 素早くお祝いをする。
WIZ : 繊細にお祝いをする。
|
種別『日常』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
「ああ、なんて素晴らしい日なんだ!」
その声は、喜色を満面に浮かべて響く。
アリスが城の門の前で、両手を広げてまるでスポットライトのように並ぶ太陽を見上げていた。
その立ち居姿は、その顔立ちや声、長い髪やシルエットまでも女性でありながらも、しかし、服装、指先や体の芯、仕草の節々から男性の色を感じさせていた。
まるで女性の体の中に男性の魂を宿したような所作。
そして、それは見る者全てに。
「さあ、開演の時間は差し迫っている」
舞台演劇を思わせた。
「野暮は要らない。ここはステージだ」
迂遠な選考は必要がない。と彼女は腕を振り仰ぐ。
すると、城の門の中、開けた庭園にガラスで出来たマネキンが次々と出現し、周囲をガラスの壁が覆っていく。それらは槍を一本ずつ携え、そうして直立の体制を取る。
それは、オブリビオンを擁する城を護る兵士のようですらあり、そしてその指揮官たるアリスは、高らかに宣言した。
「今日こそがこの記念すべき、最初で最後の公演日。オーディションはこの場で、題目はエチュードで。さあ! 素晴らしい戦いを演じてくれたまえ!」
その為の相手は用意した。台本はないが、不分相応な劇なら文字通り門前払い。
誰かが近づけば、それは上下四方を囲むガラスの籠になる。劇を演出すれば、籠は出口を開くだろう。
「ついにこの日が来た」
アリスは身を翻すと、聳える城の扉を潜っていく。その足取りは凛々しく、軽やかだ。
ああ、と歌うように、彼女は告げる。
「貴女を殺すこの日を、私は……、待っていたんだ」
ねえ、先輩。
私なら、そうある時、こう笑うだろう。
私は、そう配役された助演なのだから。
●第一章:日常、ハッピー・ハッピー・ホリデイ!
ガラスの槍兵、1体との戦いを演じる章です。
勝っても負けても、以降の展開には関わりません。好きに設定してください。
それでは、皆様の心躍るご活躍お待ちしております。
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト
劇、と
それらしく振る舞うことを心がけてみようか
界離で時の原理の端末召喚。淡青色の光の、格子状の針金細工
障害となりうる要素が存在しない時間に自身を置き、籠も槍兵も無視してそのまま進む
劇の出演者になるべきと把握した
つまり、理不尽な役柄であれば、理不尽に振る舞うのが正しい
この場を準備したアリス
立ちはだかったガラスの駒
待ち構えているオブリビオン
あるいは、もしかしてこれを見ているかもしれない誰か
何れから見てもこの行いは理不尽極まりなく、故に俺に最も相応しいだろう
抜けたらそのまま進むが、追い掛けて来るようなら顕理輝光を運用
『明鏡』で自滅させる
※アドリブ歓迎
重厚な歴史を感じさせる城ですら、周囲に一切の建造物が無ければその意義も、理解もひどく浅いものでしかない。
言ってしまえば、概念として薄い。アルトリウス・セレスタイト(忘却者・f01410)は、冷めた藍の眼を細め、世界を見つめた。
「門を潜れば、試験開始と言う事か」
何百年という時を経た荘厳なる城、としてほんの数日前に顕現したのだろう。形状としては、浅く。しかし、世界をこねて造られたこの場所の素材は深すぎる。
宛ら、遺跡のミニチュアを作るのに、更に古く重要な遺跡を削り取り、組み立てたようなちぐはぐさだ。
呆れはするが驚く事は無い。
その無茶苦茶を行うのが、ユーベルコードというものだ。
「劇の出演者に、か」
門を潜る、その手前で掌を眼前に開く。
岩肌から水が滴るかのように、呼吸から青白い光が漏れ出ては、やがて形を成していく。光の針金によって編まれた格子状の針金細工ともいうべき何か、が瞬きながらアルトリウスの指の間に揺蕩う。
正道ならば、そのままガラスの兵と対峙して道を開く。
だが。
「俺であるならば、そうではないだろう?」
アルトリウスというものは、邪道により生まれた産物だ。ならば、通る道も邪道であって然るべきだろう。
そうして、踏み出した彼の姿は、瞬く間に薄れて消える。
存在が消えたのではない。彼は確かにそこにある。だが、位相が違うのだ。
手にした端末で世界から、時間という概念を希釈し、摘取した要素を引き算する。そうして出来上がった僅かにずれた世界を彼は歩く。
時間を止める。時間の消費を止めて、過去を生み出さずに未来へと進む、それはともすれば骸の海に溺れてしまうような横紙破りだが、彼は一切臆さずに足を進め、庭園を抜けていく。
「……ああ、そういう事か」
だが、その足は、城の扉の前でとどまっていた。
「正しい位相にしか存在しないのか」そう、呟く。恐らく、障害となる要素を排したこの時間世界には、この先は存在しない。
理由は明白だ。
この城の中身は、オブリビオンを中心に造られている。核が無いのだから、そもそもこの先が存在することも無いのだ。
「仕方がない」
手の中の針金細工を操作し、位相を正す。世界に再び現れ、背後に立つアルトリウスにガラスの槍兵が間髪入れずに突進を仕掛けてくる。
アルトリウスは、用済みとなった端末を光に溶かしながら、しかし、振り返りすらしない。
聳えたガラスの檻が閉じる。それを待たずして、ガラスの槍が彼目掛け打ち放たれたその切っ先。灯る淡青の光球が染み出し、アルトリウスを貫かんと迫るその穂先に触れた瞬間。
ガラスの兵は粉々に砕け散った。
その光は、鏡の如く映し返す。アルトリウスを傷つけんとした槍という存在の反射に、生み出されたばかりのガラス兵の理が耐えられるはずも無く、ただ自壊したのだ。
アルトリウスは、ただ冷めた目で扉を見据えた。
「さあ、入れてもらおうか」
檻は閉じた刹那に、その役割を終え、霧散した。
大成功
🔵🔵🔵
 渦雷・ユキテル
渦雷・ユキテル
武器を振り回さなくても戦えますよね
恨まれる切欠も、殺したい衝動も
言葉から生まれることってよくあるでしょう?
つまりレスバです。槍兵の分もあたしが喋りますけど
一人二役の対話劇、いいえ唯の独白劇!
演じるのは狂気に取りつかれた敗者
なりたいものになれなくて
理想とする人と自身を重ね合わせるうち
自他の区別が曖昧になるんです
嘲笑う声、向けられる得物は本物?偽物?
眼前の敵は憧れた人か、無様な自分か
舞台を目一杯使った【演技】
大袈裟に動くくらいが綺麗です
情感込めて殺されそうな感じを出していきましょ
最後は槍兵の首でも刎ね飛ばしたら映えますかねー?
あはは、結局手出しちゃいました
はい、おしまい。死んじゃったのは誰でしょう
槍が地面を削る音が、耳をつんざいて、柄が空気を裂く風が頬を撫でる。
目の前を過ぎていく刃に、渦雷・ユキテル(さいわい・f16385)はハ、と一つ息を吐いては、吸い込んだ。
コンマ数秒以下の隙。だが、ガラスの兵はその間隙へと、素早く槍を舞わして攻撃を差し込んだ。
「理想を描いて、望んで……っ!」
ガラスの槍が、女性と見紛うようなその体を打つ。大きく回された柄の一撃が、咄嗟に振り上げた腕の防御ごと体をガラスの壁へと叩きつける。
「っ、結局は、なりたいものになんてなれない事をもう気付いているんでしょう!?」
「そんな事、ない! あたしはっ!」
紡ごうとしたユキテルの声は、振り下ろされた槍に中断される。地面に突きさす様に落とされた穂先を転がって避けたユキテルは、長い金の髪を乱し振るいながら、転がった勢いのまま起き上がると、吠える。
淡い桃色を乗せた唇の端を、彩った五指を備える手の甲で拭い、ユキテルは言葉を否定するように胸に手を当てた。
「あたしは」
震える足を抑えて立ち上がる。
屈してはいけないと、体全てを使って抵抗の意思を示す。
「なりたいあたしになるんですよッ!」
「――ふふ」
立ち上がる彼が吠えた声に、嘲笑が続く。
何がおかしいの。と問う彼に、目の前のガラス兵は彼女の言葉を打ち破らんとばかりに、突進の構えを取っている。
あざ笑う声は、無様とここにいるユキテルを揶揄する。
「分からないんですか? そうやって、出来もしない事を目指して」
ガラス兵の脚が大地を蹴る。
瞬くに肉薄した槍の一撃を体を逸らして避けたユキテルに、横薙ぎが追い討つ。
「……っ」
大きく横に飛び込んで、躱し切った彼に、ガラス兵は槍の石突を地面に打ち立て、余裕の態度だ。
弱者を嬲る強者のように。
幼子をあしらう熟練者のように。
「芋虫みたいに這い蹲るのが、どれだけ無様かって」
「……ああ、もううるさいですねっ、あなた!」
「ああ、もうどうしようもないですね、あなた」
そんな言葉が途切れるとともに、目の前のガラスの兵士が一気に迫る。
「煩い、うるさい!」
もはや、感情に狂うように髪を振り乱して、いささか乱暴に槍の攻撃を潜り抜けて。
「煩い、なんてひどい事を言うんですね」
足をもつれさせて、体を転ばせる。倒れ込んだガラスの壁に背を付いたユキテルは、見下ろされるガラスの兵士を見上げた。
「さあ、これで終わりです」
ユキテルは言う。
「まだ、……まだっ」
私は死ねない、と紡ぐ。まだ、叶えていないことがたくさんあると、消え入りそうな声を絞り出す、ユキテルの首を狙うように突き付けられた槍の穂先が一度引かれる。
ユキテルを仕留める事をやめた訳ではない。狙いを定め、そうして、刃で貫くための予備動作だ。
そして、槍の一撃が、ユキテルの首を撥ねんと風を切り。
「はい」
そして、槍の一撃が、薙ぎ払ったのはガラス兵の首であった。
「おしまい」
演技は終わり。
一瞬の交錯に、立ち位置が変化した。
差し出された槍を奪い取って、薙ぎ払われた勢いを流用した一撃がガラスの槍兵の首をたがわず砕き割ったのだ。
物言わぬガラスの兵隊を相手に一人二役で演じたユキテルの劇は、片方の死で終止符を打った。
だが、果たして劇の中で死んだのはどちらなのか。
あなた、なのか。
あたし、なのか。
砕けていくガラスの檻の残滓の中で、ユキテルは肩を竦めて、笑う。
「さあ、どっちなんでしょうね」
彼が殺したのは誰なのか。今いる彼が誰なのか。
それを知るのは、彼自身、只一人。
彼はその足を、城へと向けて歩き出した。
大成功
🔵🔵🔵
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン
(閉じ込められた。
が、壁は透けている)
……見たいのか。
(森番は、サーカスというものを知っていた。
小さな丸い舞台で、収まりきらないくらい様々な驚異を観せるのだと。かつて世話になった団長は語る。
素晴らしき舞台だと。)
……きらきらして。
わくわくするやつ。
……そういうのが、いいのか?
(囲まれた檻の中を【地形利用】
壁や天井を蹴り軽業のように跳ねて、硝子の槍兵を翻弄し
とどめは一気に肉薄、「燹咬」を煌めかせて首を刎ね飛ばそう)
あのアリスも。
そういうことが、したいのか?
両肩から力を抜いて、閉じるガラスの天井を見上げる。
ただ立ち竦むように見上げていた視線を落として、透明なガラスの壁を見回した。中から外が見える。透明度の高いガラスだ。
きっと外からも内側が、ロク・ザイオン(未明の灯・f01377)とガラスの兵が見えているのだろう。
見たいのか。と掠れた息に言葉を音無く混ぜる。
サーカス、とか言ったか。と彼女の脳裏に、知識が浮かんだ。ガラスの兵が大地を蹴る。サーカス、小さな舞台の上で様々な驚異を見せるのだという。
ロクは、脱力したままに、青い双眸を窄めた。問うように首を傾げた。
赤い髪が揺れる。逸らした顔のすぐ横を、ガラスの槍が貫いていた。
ああ、かつて世話になった人は、団長は言っていた。素晴らしき舞台だ、と。
それを望んでいるのか、アリスは。
成形されたガラスの槍に、ロクの赤が乱反射している。床の菱形と空の太陽と混ざった色は、煌めいて見える。
きらきらして、わくわくするような。
一瞬静止した、ガラスの兵が動く。突き出した槍を握る手をそのままに、後方を握っていた手で柄を殴りつけるように圧した。
それだけでロクの顔の数センチ横に留まっていた刃が、途端、頸動脈を切り裂く牙となる。
「そうか」
既に、身を屈めその軌道から逃れていたロクは、了解したとばかりに一言返す。通りすぎるかと思った刃が急停止する。透いた残光を残す槍の刃は、ロクが回避するのを知っていたとばかりに頭上に落とされていた。
その攻撃に、ロクは逃げた。
全速力を持って、赤を棚引かせ一目散にガラス兵を背に逃げる。
だが、逃げる先にあるのは逃さないと不動のガラスの壁。ロクは、その壁目掛けて、大きく跳躍した。
次の瞬間、彼女の体は天地を逆転し、菱形の床とガラスの兵を頭上に見上げていた。
三角跳びに飛び上がった彼女の脚が天井を踏む。腰の後ろに提げた剣鉈の柄を握り、ロクの体が弾き出された。
瞬く間に迫る頭上の敵へと、ガラス兵も即座に対応する。掲げた槍の柄に、旋回し透明な頭蓋を砕かんとするロクの刃が激しくぶつかってはガラス色の火花を散らした。
槍に攻撃を弾かれ、しかし地面へとしなやかに着地したロクは、その反動で浮いた髪が落ち着く前に次の行動へと移っていた。
移らなければ、その眼球はガラスに穿たれていただろう。頭から足までを縦軸に回転させた視界でガラスの槍が直前までいた場所を貫いたのを横目に、ロクは槍の間合い、その内側へと飛び込んだ。
槍は、棒の先に刃がある形状上、その内側の死角が広い。懐へ入ってしまえば防御のすべはない。
槍兵もそれを当然理解しているのだろう。距離を離すように身を引き、同時に突き出した槍の逆、石突による牽制を振るう。
「……っ」
聞こえるはずのない、息を呑むような音が聞こえた気がした。体ごと蹴り回したロクの後脚がその牽制の一撃を狩り、跳ね上げていたのだ。
瞬間、ガラスの兵は槍を離さなかった。槍の衝撃に体幹を崩されるならば、槍を手放いした方が賢明だっただろう。だが、もしガラス兵に学習能力が備わっていたとして、それを反省する事は無い。
無防備な隙を晒したガラス兵の首に、ロクの剣鉈が閃く。散るのはガラスではなく、炭化した炭と煤。
「これでよかったのか?」
紛れも無く、致命の一撃。それを為したロクは、ガラスが落ちる音を聞きながら、返らない答えを少しだけ待った。
大成功
🔵🔵🔵
 ラピタ・カンパネルラ
ラピタ・カンパネルラ
わたくしは、この場に相応しくはありませぬ。
何故なら、ほら、わたくしこんなに見窄らしい。
髪は伸び放題、服は継ぎ接ぎ、あなた様の御姿さえ見えませぬ
(滔々と語り、踏み出した)
(回避行動、[激痛耐性]、無抵抗)
襤褸は襤褸らしく、すっこんでいろと申しますか
されどわたくしは臆病で、ここから独り立ち退くことすら出来ませぬ。輝かしさへの望みを、棄てきる事が出来ませぬ
消してください、わたくしの灯を
ころしてください、あなたの自由に
それでもまだ、僕の息が吹き消されていないと言うことは。
『僕』はまだ、燃えていて良いということだ。
たとえ、君より醜くとも。
ーー御機嫌よう、アリス。
演劇は分からないけれど、これで合っていた?
何かに囲まれた。それは分かった。
何かが立っている。それも分かった。
もし、この目が見えたのなら、それが何かはっきり知る事が出来たのか。
求めるように足を進める。無造作に伸びた灰の髪を垂らし、つぎはぎの服を引きずるように、しかし、その足は戸惑い無く。
「わたくしは」
そうして、ラピタ・カンパネルラ(ランプ・f19451)は膝を折った。胸に手を当て、頭を垂れる。
傅く人を知っている。
「この場に相応しくはありませぬ」
その言葉を知っている。
「何故なら、ほら、わたくしこんなに見窄らしい」
低頭したまま、腕を広げて見せる。
その服装を、その姿を、隠さずに言葉を続ける。
「あなた様の御姿さえ見えませぬ」
そうして、目を開き、胡乱げに揺れる瞳を目の前の何かへ見上げさせる。息を吸う。まさしくその時に、冷たい何かがラピタの頬へと充てられた。
熱を奪われる冷たさが、僅かに裂かれた肌から伝わる。
浮いた液体が、一筋頬を伝い顎から零れ落ちた。
頭を不敬に警告するようなその槍に、しかし、ラピタは再び頭を下げる事は無かった。
「襤褸は襤褸らしく、すっこんでいろと申しますか」
世界を見る事を許さないというのだろうか。
幸福を望むことを許されないというのだろうか。
それが出来るなら、望むことを辞められるのなら、どれほど心が救われるか。ただただ、無為に、無感動に沈むことが出来るならば、どれほど楽だろうか。
「されどわたくしは臆病で、ここから独り立ち退くことすら出来ませぬ」
この体は光を追う事をやめてはくれない。
「輝かしさへの望みを、棄てきる事が出来ませぬ」
この瞳は光を願う事をやめてはくれない。
止まれはしない。足が痛もうと、喉が枯れようと、きっと止まる事は無い。
ああ。
だから、こうして傅くのだろうか。傅いたのだろうか。
正しくなどないと知っているから。
「消してください、わたくしの灯を」
願ったのだろうか。
「ころしてください、あなたの自由に」
太陽の光を、その檻に、体に、煌めかせて、ラピタを見下ろすそれは動かない。
その煌めきに、表情は見えない。
その煌めきの正しい形すら見えない。
期待を込めてラピタは瞼を閉じた。
この憧れを、吹き消してはくれないかと。
「……」
だが、いつしか、頬に触れていた感触は消えていた。
瞼を閉じる寸前、その隙間に僅かに藍が踊った気がして。
見開いた先に、既に乱反射する煌めきは無かった。その悉くは姿を消し、訴えた少女の願いが叶う事は無かった。
「わたくしのこの息が吹き消されていないのならば」
僕は、まだ燃えていて良いと言う事か。この身が醜くとも、進めというのか。
それとも、少女は命を絶たれて終わったのだろうか。
あの冷えた刃に貫かれて、熱を奪われたのだろうか。
もし、この目が見えたのなら、その結末を見届ける事ができたのか。
「演劇は分からないけれど」
跪いた体を起こし、先にいるのだろうアリスへと語り掛ける。
「これで合っていた?」
返る答えは無く、しかし、城の扉は彼女を迎え入れた。
大成功
🔵🔵🔵
第2章 日常
『暗い部屋なんて……』

|
POW : 何が出てきても力で解決だ!
SPD : 部屋に隠された物はないかな?
WIZ : 部屋の状態から推理してみようか
|
種別『日常』のルール
「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
城の中は、驚くほどに何もなかった。
ただ薄暗い空間が広がっていた。静かに熱を持った雑多な音が、冷えた空気を震わせている。
オブリビオンの姿は無い。
だが猟兵たちは、確かに、戦いの気配を感じ取っていた。
●
暗い。だが、見えない程じゃない。
音が重なっている。雑多に漏れ聞こえる音はその詳細を聞き分ける事は出来ないが、だが、何かへと向けての準備である事だけが伝わってくる。
発声。チューニング。設備。小道具の手直し。
懐かしさが込み上げる。
きっと、私が好きだった音だ。
「私的に演技って、その役に自分を置く事なんだよね」
柔軟をしながら、なんともなしに言われた先輩の言葉だ。何故か心に残った。
開演の時間が近づいている。
あくまで演じる自分を自分の中に見出す。それが先輩だった。
暗い道を歩く。
この先に、敵がいる。
キャスティングは、自分の中にその役を見出されたから配られるもんだ、と私が役に悩んでいた時に言われた言葉は、妙な説得感があった。
そんな事を思い出すのは、雑多な音に包まれたこの舞台袖に立っているからだろうか。
腰に下げた細剣を握りながら思う。
追いついた足音を、背で感じ取る。肺を膨らませた。
そうすれば胸を張れるから。
もうすぐ、灯りが照らされる。
●第二章:日常、暗い部屋なんて……
もうすぐ、オブリビオンとの戦いが始まります。
ですが、まだ始まりません。
来る戦いに向けて、心構えや準備をする章です。
一応、アリスも同じ空間にいますが、気にしなくても大丈夫です。
それでは、皆様の心躍るご活躍お待ちしております。
 ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック
(ザザッ)
(暗い場所にいる。自分の姿も闇に包まれて定かではない。)
舞台装置、か。
(グリモア猟兵曰く、此度はそのような状況での戦闘だと。)
(仮にこれが暗幕が降りているのだとして、ならば)
("僕"がするのは、いつも通りの事をするだけだ)
ーー"本機"はシリーズネーム:ジャガーノート、個体識別名:ジャック。
(臆病で弱いままの"僕"ではない、冷静な、歴戦の猟兵としての。"ジャガーノート・ジャック"の"役割"を被る。)
状況を理解した。
以後の戦闘に備え臨戦態勢に移行する。オーヴァ。(ザザッ)
(ルーチンをこなせば心も平静になり、思考も切り替わる。)
(――今はアリスも、この様な気持ちでいるのだろうか)
彼は、暗い中に立っていた。
目の前に広げた掌の輪郭も曖昧にぼやけるような暗さ。
僅かに奮える息を吐き出す。
何もかもが見えないわけではないが、何もかもが滲み合わさるような世界だ。
人の気配は殆どない、にも拘らず周囲を埋めるのは人の音。雑音。
「舞台装置、か」
ここへと彼を送り込んだグリモア猟兵は、この城をそう言った。
舞台装置があるのなら、すなわち、舞台が前提としてあるのだろう。
ならば、この暗がりは、暗幕が降りている故なのだろうか。
おかしな話だとも思う。
暗幕が降りているならば、その後ろ、舞台裏は、準備の為に明るくなっているだろうに。
これではまるで、閉じた暗幕に暗闇を思う客席からの視点のようだ。舞台に立っていながらに、観客になっているような。
不安定だ。
暗がりに、自らの手を広げ見たのは何故だ、と自分に問いかける。
自分が本当にここに存在しているか、無意識に恐怖に囚われていたのではないのか。淡い輪郭が、怖がって、震えているのを……。
「いや」
と、ナイズ雑じりの声で思考を断ち切り、彼は呟く。
ここがどこであろうと、自らがすることに変わりはない。
僕は誰だ。
「本機はシリーズネーム:ジャガーノート」
私は、誰だ。
「個体識別名:ジャック」
私は、ジャガーノート・ジャック(AVATAR・f02381)だ。オブリビオンを狩る、冷鉄なる兵士だ。
曖昧に映る掌を、強く握る。もう震えは無い。
震えていた息を豹鎧の中で、大きく吸い込んだ。声に迷いはない。
いつも通りに、さざめいている。
「状況を理解した」
凪いでいく。
静まっていく。
意識が沈み込んでいく。暗い海に呑まれるように、無数の泡が世界を映す。
全ては錯覚だ。この暗夜に応じて脳が産み出した幻。
ジャガーノートは、目を見開いた。
世界を正しく認識する。ここに海はなく、ただ、慌ただしく静けさが駆け抜ける、暗がりだ。
「以後の戦闘に備え臨戦態勢に移行する」
凛と立つ、アリスの背に思いを馳せる。
その背は、自らが何であるかを主張するように伸ばされ、一片の曇りもない。
何とも見事な、ロールプレイだと。
静めた心理と反して、体には力が滾っていく。
ジャガーノートはそのまま、静かに来るその時を待つ。
大成功
🔵🔵🔵
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン
(ざわざわ。物音に、声に、耳をそばだてる)
(ひとの声は。
ただの声であれば、とても、好きだ。
獣の呻きの何倍もの意味を持つ。物語を持つ。
たくさんの、相反する心を同時に持つ。)
(アリスはどんな顔をしているだろうか。
己ひとりでは、決してこの先に待つ病には勝てないと
知っていて、そこにいるのだろうか)
(自らの死を決めてしまった悲壮でなく。
強きものに、挑む目をしているのならば。
……そういう目をするものを。おれは、とても好ましく思うから)
(この薄闇に、己の声は邪魔だ。
ただ静かに、アリスに向かって拳を突き出す。
――――舞台(いくさ)の前には、激励を送るものだから。)
森が風にそよぐようだ。
ロク・ザイオン(未明の灯・f01377)が目を閉じ、耳をそばだて、音の中へと身を寄せれば、幾万もの陽の光を透かす葉が擦り合わさるように、生きる獣たちが血潮を示すように、彼女の体を満たす。
だが、その詳細までは分からない。
「……」
息を吸いこむ音がやけに大きく聞こえる。
雑音、その全ては人が立てる音で、人の意思が、物語が宿る。
断片でも聞き取れないかと集中すれど、拾えるものは無く。
ただ一つはっきりと拾った音に目を開けた。
息の音。
ロクのものではなく、少し先にいるアリスの息。
この暗闇の先を迷わず一心に見つめる先に、何を見るのか。
その目は、何を語るのか。
彼女一人では、ロクの危機感を煽るその病には勝てない。
それを知って彼女はここにいるのだろうか。
……いや、知っているのだろう。
彼女は猟兵が現れるこの日を祝っていた。
病を、敵を殺せる日が来たと。
一人では殺せないと知っていたから。
ならば、きっとその目が語るのは。
想悲ではなく。
自らの死を決めてしまったが故のくすんだ光でなく。
決意であるのだろう。
強きものに挑まんとするがゆえの光であるのだろう。
ロクは、また目を瞑る。雑音を聞くためではなく、彼女の声なき声を知るために。
「……」
僅かに震えている。
恐ろしいのか。
怒っているのか。
悲しんでいるのか。
喜んでいるのか。
その、全てなのか。
ああ、と心地よく思う。
それは感情に揺られる、か細い悲鳴だ。
ロクは、その悲鳴を快く思う自分を嫌悪せずにいた。気付くこと無く、しかし確かに。
瞬く。
暗闇に目を凝らす。
アリスは、こちらを見ることはない。
アリスの瞳は、振り返らない。ただ頑なに前を向いている。
きっと、挑む目をしている。
ロクは、なぜかそう確信していた。
だから彼女は自らの拳を、その背中へと掲げた。
ただ、彼女に激励を送るために突きだした拳に、燃える感情を乗せる。
「……」
声を送ることはない。
おれの声は、この思いを伝えるには足りない。
千の言葉も万の言葉も、きっとこの拳一つ分の感情には足りない。
柔く、剛く、握った拳に自らの覚悟も乗せて、ロクは口を閉ざして暗闇を見据えた。
大成功
🔵🔵🔵
 渦雷・ユキテル
渦雷・ユキテル
効率的で可愛げのない武器
鼻唄混じりにくるくる回して手持ち無沙汰
煌びやかなお城でなら口も回ったんでしょうけど!
弾数15のパラベラム
今日はまだひとつも使ってません
このあと何発減るのか考えると
どんな相手に撃ち込むのか楽しみで少しだけ怖い
いつもそう
鼓動が響くのは嫌じゃないんです
大事な身体が此処にあるんだって分かるから
壊さないように戦おうって誓い直せるから
彼の身体 あたしの身体
どっちなのかもう、
思考を切り替えるついでに雷光をばちりと
明るくなるのは一瞬で、また直ぐに元通り
こっちもいつもと変わりなく
ご大層な実験の成果が生きてます、今日も
息を吸って、吐いて
勝者で居続ける覚悟を
演技はずーっと続いてるんです
水底に沈み込んだような暗がりは、しかし、重々しさは無く、むしろどこか軽さすら感じられる。
艶めいた爪にトリガーガードを通して、弾丸をフル充填している銃を回す。普段から身に着けているお気に入りのアクセサリーのように、人の命を簡単に奪い取れるそれを取り扱いながら、渦雷・ユキテル(さいわい・f16385)は鼻歌を歌う。
その場限りの、聞いたことのあるようなフレーズをつなぎ合わせた即興のメロディを口ずさみながら、もうすぐ、この手に与えられる反動と硝煙のフレグランスに、どうしようもなく胸の高鳴りを感じていた。
この弾丸を、どれほど使う事になるのか。
この重みが、どれほど軽くなるのか。
二度ほど、同じフレーズを繰り返して、その先を少し思案するように鼻歌を止めると、ユキテルは周りにもう一度視線を投げた。
暗い部屋だ。
何もない部屋だ。
ただ、戦いを思わせる雰囲気が、漫然と響いている。
庭園を歩く、ほんの僅かな間に考えていた内装への語り文句が全て無駄になってしまった事を惜しみながら、代わりにここにあった、その雰囲気に少し、微笑む。
高鳴る胸。
静かに、それでも確かに跳ねる心臓の音。
それは弾丸を打ち込む相手へ向けた期待や、興味。それがどんな反応を見せるのか。それを見たいという、そこに相手を見出そうとする欲。
そして、少しの恐怖。
自分の中に、体の隅々に、高鳴る音とほんの少しだけ遅れて指の先を巡る血液の興りを、決して彼は嫌ってはいない。
「そうですよね」
回していた銃を捕まえ、引鉄に掛けずに、銃身に添えた人差し指を暗がりの中で、じ、と見つめて独り言ちた。
鉄に似合うようにほんの少し、骨ばったその指の先に光る爪色。
その色を選んだのあたしだ。
あたしの体に似合うかと選んだのはあたしだ。
あたしの好みに合うかと選んだのはあたしだ。
ならば、この色を選んだ身体は、あたしの身体なのか。
「……、そうですよね」
分からないことは分からず、分かる事は分かる。そんな単純な思考が、ユキテルに呆れたような笑みを浮かばせていた。
鼓動が示している。それで分かる。
大事な体が此処にある。
見つめる手甲に雷光を弾けさせる。黒金は、硬く光を反射し、肌は柔く光に浮かぶ。違う表皮に違う色を発しながら、しかし、一瞬で消える光に同じく影を再び纏う。
思考を切り替える。
浮かんだ笑みに、自らの意図する感情を乗せる。
今日もあたしは生きている。御大層な実験の成果だ。さぞや、喜ばしいでしょう、と笑む。
そこにあるのは強者でもなく弱者でもなく。
勝者として背を伸ばす姿だった。
大成功
🔵🔵🔵
 ラピタ・カンパネルラ
ラピタ・カンパネルラ
くらい。
熱を感じる。
皆も静かに、ここがくらいと言う。
心地いい。
皆同じ肚の中に、いるような。
呼吸ひとつひとつが、細胞を生んでいくような。
これが舞台の裏ならば、役者はここから産まれると分かる。
……僕は役者じゃないけどね。
継ぎ接ぎの外套の埃を払う
ごめんね、襤褸って言って
縫ってくれた人がいるのにね
もうそんな人もいないとこまで来たのにね
重いが身を守る枷が鳴る
私達がいるよと囁くように鎖が鳴る
うん、もうそこには帰れないけど。
だってもう欲してしまったから
淡い光
人々の衣摺れ
歩みの音
決意の呼吸
全てを溢さず、待っている
炎の呼吸を、聴いている
はじまるなら、幸福な終わりがいい。
くらい。
ラピタ・カンパネルラ(ランプ・f19451)は盲いた目に闇を見つめ、そうして縋るように残る四感へと手を伸ばした。
音が聞こえる。
雑踏の音。息。猟兵のだろう声。アリスの身じろぎする音。
香るものがある。
埃と籠る風も無い空気の匂い。僅かに焦げるような匂い。
空気を食む。
吸い込んだ空気が、喉の潤いを奪い去る。少し、煩わしい。息を長く吐く。
そして、熱を感じた。
アリスが放ち、この場に立つ誰もが放つ熱がある。
自らも、それを放てているのか。
揺れて閉ざされた目に、しかし、同じ暗がりの中で一つに繋がっているような感覚が、心地いいと思えていた。
同じ肚の中にいる様な。
呼吸のひとつひとつが、細胞を生んでいくような。
少しだけ肩からずり落ちた外套を、埃を払うように一度揺らして、胸に寄せる。
「ああ、ごめんね」
と、それに言った。思い返すのは、ガラスの檻の中で発した声だ。
「襤褸だなんて」
継ぎ接ぎの布は、しかし、上等に縫い合わされている。糸目など見えないラピタにその技は出来ない。それは、彼女の傍にいた人の証だ。
指に触れる解れた糸は、もうその人がいない証だ。もう、この足は、そんな人がいない所まで来てしまった。
外套を寄せた腕で鎖が揺れる。
その重みが告げる。ここにいると、ここにあると。
光を追い、願って、置いてきたはずのものの名残を押し抱いて、ラピタは自らの臆病を疎んだ。
このつながった暗がりが心地いい、と同時に、暗がりは怖いと思う。
一度一つになったものが、恐ろしい。
得るために失う、その代償を恐れて、残滓を握りしめている。
ならば、足を止めてしまえばいいのに。
ラピタは、しかしそれも出来ないでいる。
それと同時に、どうしようもなく喜ばしいと思ってしまう。
ここが舞台の裏だというのなら、役者というものは、ここから産まれる。
ステージというものの上に、生まれ落ちる。
輝かしいものを見る。その憧れに、抱えた物を失おうとも、手を伸ばしたいと感じてしまう。
帰れはしない。欲してしまったのだから。
告げる。
人の声が、熱の匂いが、風の味が、呼吸の荒びが、始まりを今、告げんとしている。
彼女は願ってしまう。
はじまるなら、その果ては幸福な終わりがいい、と。
それがきっと正しくなどないと、心のどこかで知っているから。
そう、願ってしまうのだ。
大成功
🔵🔵🔵
 セラ・ネヴィーリオ
セラ・ネヴィーリオ
(暗い場所)
(それはまるで夜のようで)
(色んなものを失くした虚の様で)
一人、暗闇に佇む
思い出されるのは、骸の海に還してあげたいと思っていた魂たちを根こそぎ奪われたあの日のこと
「参っちゃうねえ」
これが舞台袖なら私語厳禁だけど、思わずぽつり。笑顔はできてるかな?口元をさわり
身体の震えは武者震い?畏れ?
また失うかも、奪われるかも
そんな不安は確かにいつも抱えていて
「でもね、だからといって、立ち止まってはあげないよ!」
前を向く。にーっと柔らかく笑顔!
飲み込まれるのは簡単だけど、だってほら。俯いてばかりじゃ悲しいもんね!
さあ行こう、アリスさん。一緒に踊ろう、笑おうよ
舞台へ一歩、踏み出し
暗い。
騒めく。
まるで、夜、のようだ。とセラ・ネヴィーリオ(トーチ・f02012)は、乾いた笑みをその頬に浮かべて、空になった肺へと空気を押し込んだ。
音に反して、ここには何もない。
その様相が、この空間の空虚さを際立てているようだった。
まるで、ここにあった全てを失くして、虚ろなままで生きている。そんな空虚。
大抵の、一般人と呼べる人に聞いても首を傾げるだけだろうそんな感覚を、しかしセラは知っている。
はっきりと、それを、覚えている。
暗闇が、一人分の空間を埋めるようだ。
「……参っちゃうねえ」
力無く呟く。静かな空間に、彼の落とした言葉が、地面を這うように響いた。雑音に紛れて、その一つになって消えていく。
思わず零した声に、セラは口を結んで、息を少しだけ止めた。
意識せずとも、どうしようもなく浮かぶ記憶に、震えるように笑う。
いや。
ふと指先で触れた口角は、震えているように思えて、違うと気付いた。
震えているのは指先だ。
足が凍るように、かすかな痺れとともに動かない。
見下ろした足先も薄らとぼやけて見えない。足の踏み出し方を忘れたようだ。そんなセラに静寂がうるさいほどに語り掛ける。
カーテンが開くその瞬間を見逃すまいと、誰もが息を呑んだような静寂。
この指の震えは、そんな静けさへの武者震いか。
いいや。そんな強がりを確かに否定する心の声がする。
それならば、この足の震えは、どうしても忘れられぬ恐れか。
救いたいと伸ばした手が届かず、響かせた声が消え失せて。
全てが奪い去られる。そんな不安が、闇の中からその腕を広げている。
「……怖いね」
震える指先で、両頬を押し上げた。
不安だ。恐怖だ。知っている。
そんなものはいつも、付いて回っている。いつも感じている。
抱えて、歩いている。
「だからといって、立ち止まってはあげないよ」
大丈夫、笑顔は出来ている。
いつの間にか、暗い地面だけを見つめていた顔を前に向ける。
見えるものがある。数人の気配の中で、アリスの背が見えた。
ああ、笑えている。
自らの頬に触れる事も無く、セラは足を踏み出した。凍ってなどいない。
「行こう。アリスさん」
一緒に、踊ろう。ステージはここだ。とセラは、暗がりを進んだ。
影の中に飲み込まれるのは簡単だ。
それでも、きっとそれは、寂しいことだ。
俯いてばかりは、悲しいことだ。
「さあ!」
だから、笑うのだと。
失くさない様に、笑顔でつなぎ留めるように。
そう、彼は笑う。
「ああ」
アリスが、答えた。
胸を張り、しかし、前だけを見つめて、少しだけ微笑んだ気がした。
大成功
🔵🔵🔵
第3章 ボス戦
『オウガブラッド・レックレス』

|
POW : ライオネル・バイト
自身の身体部位ひとつを【真紅のライオン】の頭部に変形し、噛みつき攻撃で対象の生命力を奪い、自身を治療する。
SPD : ライオネル・クロウ
【両手の爪】で対象を攻撃する。攻撃力、命中率、攻撃回数のどれを重視するか選べる。
WIZ : ライオネル・ゴースト
自身の【肉1ポンド(約450g)】を代償に、【自身を飲み込んだオウガ】を戦わせる。それは代償に比例した戦闘力を持ち、【燃え盛る両腕と牙】で戦う。
イラスト:こぶじめ
👑11
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
|
種別『ボス戦』のルール
記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。
それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。
プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。
| 大成功 | 🔵🔵🔵 |
| 成功 | 🔵🔵🔴 |
| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |
| 失敗 | 🔴🔴🔴 |
| 大失敗 | [評価なし] |
👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。
ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。
※このボスの宿敵主は
「💠ロスティスラーフ・ブーニン」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。
※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。
●
満ちていた雑音は、もう既に文字通り息を潜めて、開幕の瞬間を今か今かと待ちわびている。息を吐き出したのは、自分か、それとも他の誰かか。
暗い。
光の少ない、その空間で猟兵達は確かに見た。
開幕のその瞬間を。
スポットライトが当たるように暗がりに浮かび上がる光。
燃える炎。細かい火の断片を散らし、燃え上がる女性の姿。炎のオウガに食われ、主導権を簒奪された元アリスの女性。
「さあ、劇の始まりだ」
光源が一つ、そうして、もう一つ灯りが点る。
散り咲かる火炎の群花に、アリスは踏み出した。
一輪、大輪の花の如く広がった炎を焦がれるように纏ったアリスは、猟兵達に懇願するように告げた。
「……私に、彼女を殺させてくれ」
依然として暗い世界に、二つの燃ゆる花片達が身を焼き、舞い踊る。
「あのオウガの脚本など、焼き捨ててしまおう」
●
「私が、王子様だなんて」
きっと先輩の方が、似合っている。
そんな悩みに、彼女が返した言葉に私は、改めて、やはりこの役は先輩にふさわしいとしか思えなかった。
先輩が王子に憧れる町娘、私は民を愛する王子。
そんな二人のありふれたような悲恋の作り話。
思えば、私は、王子を嫌ったのでなく、村娘に傾倒していたのだろう。だから、その役になりたいと思った。
私は、自分を自分として演じられないから。
私は、他人として装おうから。私ではなく、他人として自分を表すから。どうせなら、伝えられない思いを役に、別人に託してしまいたいと。
だけど、だから、私はこうして立っている。
先輩が演じる王子を、装って立っている。
「あのオウガの脚本など、焼き捨ててしまおう」
先輩ならば、そう言うだろう。
ぶっ壊してやろう、と。きっと、悪意の思惑に従う事を嫌うだろう。
私たちの記憶から作り出した、先輩と私の相対。暗い空間の中で、記憶が染み出してくる。
そうだ、これは、まるでここに迷い込む前の舞台のラストシーンだ。
町娘が王子を殺す最後のシーン。オウガが読み取った断片的な舞台設定から造られた、不出来なステージだ。
私は、やはりと、思う。
きっと、先輩は村娘を殺せない。殺せずその小さなナイフに殺される。
私は王子の戸惑いの隙に殺してしまうだろう、殺せてしまうだろう。
だからやはりこの配役は、間違っている、と思う。
私は役に乗じて、この炎を終わらせようとしているのだから。
●第一章:ボス戦、オウガブラッド・レックレス
アリスとの共闘です。
ガラスの壁による補助
ガラス兵の召喚
炎を纏い強化して細剣による攻撃
といった行動で、戦闘に参加します。
それでは、皆様の心躍るご活躍お待ちしております。
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン
(自分の知る舞台には、喝采があった。
皆、歓声が自分の技に降り注ぐのを望んでいた。
褒めてもらえるのはうれしいから。
それくらいは、森番も理解していた。)
(だから、
ここはさみしい舞台だと、思ったのだ)
……いいよ。
おれはキミを手伝う。アリス。
(病んだ炎に呑まれて、あの女のひとはもう、治らないのだろう。
それなら――病の苦しみは、断たなければならない)
(【先制攻撃、早業】の「轟赫」五十二条を操り炎の鬼を狙う。
暗い舞台の上を動き回る炎の帯で、アリスの纏う炎を【隠し】ながら
アリスが走り抜けられるよう、炎の花道を創ろう。)
(主役は、たくさんの光に包まれているものだから。)
静かだ。
燃え上がる群花と大輪が、互いを牽制しあうように向き合い、動かない。
誰もが息を潜めている。そんな気配のする静寂ではなく、空虚に閉じた静寂。
だが、それはほんの数秒でしかなかった。何かの合図を得たかのように、アリスとオウガは同時に暗い床を蹴りとばしていた。
流星の如く、二つの篝火が瞬く間に距離を詰めて激突する。拳と剣が交わり、盛大な火花と熱風を伴って光が爆ぜた。
咲いた爆炎にぶつかり合った体が離れて、また鍔迫り合う。
鼓膜を震わせる炎の慟哭がロクの身体を叩く。言葉など、声など一つとして聞こえないのに、振るわれる拳が、刃が言葉であるかのように交わされる。
だが、何かが足りない。
熱が走り髪を揺らす。暗い舞台の上で舞い踊る姿は、獰猛で、美しく、そして輝いていた。
だが、何かが足りない。
何かが違う。何が違うのか。
そうか、とロクは考え、思い出し、そして気付いた。
静かなのだ。
剣戟が鳴り響く、炎が大気を焦がす。それでも、ここが舞台であるというのなら、静かに過ぎる。
歓声が無いのだ。
いや、ロク自身分かっている。
この舞台に立つあの二人は、ロクの知る演者とは違い、賞賛など求めてはいない。
それでも、ロクは感じてしまう。吠える火炎が通った後は、まるで虚ろに残響だけが漂う。
瞬いた火花は、すぐに闇に溶けて消える。残るのは、冷めた暗闇だ。
主役は、光に包まれているものなのに、アリスとオウガを包むのは静寂と暗闇ばかり。
ロクはそれをさみしいと、感じてしまう。
「……アリス」
呼んだ声は、駆ける彼女には届かないはずだった。だが炎を纏ったアリスの眼が一瞬、ロクを捉えた。そんな感覚があった。
「いいよ、おれはキミを手伝う」
殺させてくれ、と請われた言葉にロクはそう返し、熱炎が宙を駆けた。
アリスとオウガが、肉薄する。
「……がっ」
正中から、アリスが突き出した細剣の刃の腹を拳が払い、剣を引き戻す暇も無くオウガの追撃が放たれる。
懐へ沈むように潜り込んだオウガの拳が、アリスの腹を真下から打ち上げる様な挙動で強かに捉え、地を這う爆炎と共にその体を跳ね上げていた。
アリスの身体は一秒も立たず、放物線の頂上を超え落下する。そして今度こそ致命傷を与えんと構えたオウガは、しかし、その拳を咄嗟に虚空へと突き出していた。
眩い炎の帯をその拳が受け流す。
「グ、ァアッ」
開いたオウガの口からは、意味を為さない言葉が漏れる。それは自らの行動を邪魔された事への怒りに震え、そして、目前に殺到する五十をも超える炎条への焦りに跳ねていた。
四肢を穿たんとした数本を躱し、逃げ道を潰そうとするそれを蹴り抜き、僅かな隙間に身を投げる。
人一人、それも決して大柄ではないオウガへ五十もの火炎の帯を殺到させるには複雑な操作はリスクが高い。全てをぶつからない様に操作するなど到底、出来はしない。それらは一直線にも近い単純な動きばかりで、避けた先で折り返すような事は出来ない。
だからこそ、オウガはその全てに対応してのけ、そして、その帯の根本であるロクへ理性無き瞳を向けた。
突貫されれば、対応する前に距離を詰められる。身軽な体捌きは、互いの干渉を警戒する帯で迎撃出来る事を期待させてはくれない。
それでいい。
ロクは、その視線を向けられながらも炎熱に巻かれた体とは対照的に、冷えた思考を展開する。
彼女の放った炎が全てオウガへと向かっていたのか。否、ロクは手伝う、と言ったのだ。
オウガが、野生じみた直感に踏み込もうとした足を留めた。
単調な動きの中で一つだけ、囚われない動きを見せる炎がある。それは、造り出したガラスの壁を蹴り、オウガの頭上から刃を振るう。
「どこを見ている」
声、そして、揺らめき。
ロクの炎が遮っていたアリスが、オウガへと再び急襲を仕掛けていく。
大成功
🔵🔵🔵
 ラピタ・カンパネルラ
ラピタ・カンパネルラ
あ。
あ、あ。
炎がくるくる舞い散って
二人が燃えて交わって
世界に暗闇が、二人の為のように満つ
見える、僕の弱い目にも君達が。
綺麗だ。ーー
羨ましい。
藍焔が、知らずのうちに、哭いた。
赤を、藍色が呑まんと燃え盛った。
アリスにも焔の手が伸びたろうな、そちらは僕が駆け付けて握りつぶしてしまわねば。
それはつまり、見惚れる時間が終わり、僕が壇上に上がってしまう意味だけど
自信が無いな。僕はちゃんと、君達を曇らせずに動けるかな。
僕の無骨な怪力や部位破壊は、この舞台に邪魔ではないだろうか。
五感を頼りに。共に演じる。
「アリス」
「消せるかい」
君と同じ色に燃えるあれを
君とも、僕とも、同じだったあれを
何処にいたのだろう。
何処にいるのだろう。
魂というものがあるのなら、体という入れ物に入れられている事を忘れているような。
炎が踊っている。
何も見えない。その光が交わり、離れ、火花を散らしては弾けて泳ぐ。
まるで、暗闇がただその二つの為だけに偏在しているかのような、その二つの為だけに世界から光を奪ったかのような感慨さえ浮かぶ。
体の在処を忘れたように、暗闇に溶ける魂が追いかけるは、その輝く輪舞だ。
炎が踊っている。
魂を焦がしながら、その彼女達の在り方に炎が踊っている。
「あ」
体の中に、炎が踊っている。
自らが何処にいるのか、体を焼く炎が伝えてくる。息を吐く感覚が戻る。
そして、烈火の舞に無数の火炎の帯が乱入していった。それによって更に熱量が、光量が増していく。
その熱に初めて体の在処を思い出したその時。
吐き出した声に端を発したか、それとも、吐き出す前からか。藍が零れて、ラピタの身体を食い破るようにあふれ出した。
意志を持つように、炎の塊は幾つかに別れて飛び出す。
それが、オウガにだけ向かうのであれば、そのままにしていただろう。だが、藍色の炎はアリスや猟兵にも向かっている。猟兵に向かった物は、対処できるだろう。
だが、アリスは、もはやオウガに集中しきって気付いてすらいない。理性の制御を離れた炎を止めねば、アリスに傷を負わせてしまう。
それを躊躇う理由など無い。
だと言うのに、ラピタの脚は逡巡を見せる。
藍炎を追う。つまり、ラピタ自身があの渦中へと身を投じる事に他ならない。
躊躇いも僅かに、その脚は強く床を蹴っていた。そこに逡巡を克服する要素があったわけではない。ただ、この炎が背を押そうとしたアリスの身を焼く事が嫌だっただけだ。
体を弾き出し、全速を持って炎をアリスに向かう寸前で掴む。それを自らの中へと押し流したラピタは、同時にオウガへと弾けた藍を視界の端に捉えていた。
赤に藍を散らしながら、オウガがラピタを敵と認める。少なくとも、ラピタにはその敵意が自分に向けられている、と直感した。
「……?」
何かが、自らの中で揺らいだ。
ラピタへとオウガが駆ける。
何かに震える手を握り、喉に迫り上がる苦い何かを腹に沈め、迫る拳に千切れた鎖を揺らした。
先んじて放たれた焔の獣の爪を藍炎纏わせた拳で弾き、胴体を砕く。
炎の獣を打ち砕いた藍色の残滓の輪を潜るように突き出された拳を掌に受け、そのまま力の流れを御し、怪力を遠心力に重ねオウガの身体を投げ飛ばす。振り回すような投げに、攻撃よりも早い速度で吹き飛んだオウガは、しかし、爪を床に突き立てその体を制して、体勢を立て直した。
「……」
緊迫に詰めていた呼気を吐く。
その拍子に、臓腑へと抑え込んでいたものが込み上げて、転び出る。
「は、っ」
それは笑いだ。紛れもしない喜びだ。
それを漏らしたのが、自らの口だと確かめるように自らの口を覆う。
何が嬉しいのか。どうして楽しいと思うのか。ゆるく弧を描く口を手で閉ざす。輝かしい中に自らがある事が嬉しいのか。
ならば、どうして、それを拒もうとするのか。
その困惑は、纏う炎の中に違う輝きを見せて傍に立ったアリスの姿に飲み込んだ。
「アリス」
同じくオウガを身に宿し、アリスと同じ色に燃えるあれを。
アリスとも、ラピタとも、かつて同じであったあれを。
「消せるかい」
間髪入れず、その答えは返される。
「ああ、私が殺して、消し去る」
静かに、しかし、瑕疵一つない確固とした意志がそこには宿っていた。
大成功
🔵🔵🔵
 ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック
(ザザッ)
熱線銃にて敵を射撃、アリスをサポートしつつ、彼女に話しかける。(援護射撃×スナイパー×コミュ力)
アレを討つのを望むなら。
請負おう。
それが君の望みならば。
この舞台の主役が、君ならば。
だが、替わりに一つだけ聴きたい。
――君がこの戦いの中で、何を思うのか。それが聴きたい。
(――同じく、演じ、装おう者が何を思うか。それを聴きたい。)
(――応えがどうあれ、望みのものを彼女に。)
――電気信号発射。
神経伝達速度向上・剣への雷撃エンチャント成功を確認。
"FLASH"。
行け、アリス。
同じく役を被る仲間として、君を助けよう。
――焔のみならず雷光を纏い、稲妻の如く剣を振るといい、王子よ。
(ザザッ)
火炎の帯の一つが、見知った顔の猟兵へと向かう藍色の炎を打ち払ったのを見て、ジャガーノートは、僅かに息を吐く。
「討つのか」
オウガを投げ飛ばしたアリスから引き剥がした猟兵が、その相手を担っている。攻撃の合間を縫い、熱線を放ちアリスを補助していたジャガーノートは、オウガを追おうとしたアリスを引き留める。
オウガの放った火炎の獣と猟兵がぶつかる、言葉を交わす時間くらいはあるだろう。
「アレを討つのを望むのなら、請負おう」
足りぬのならば、力を貸し与えようと、ジャガーノートは落ち着ききった言葉でアリスの注意を引いた。
その言葉には、今のアリスのままでは、オウガに勝つ事は難しいという彼の評価が含まれ、そして、アリス自身もそれを否定しない。
汗をぬぐい、アリスは焦るような、それでいてどこか余裕を持った笑みを浮かべて、ジャガーノートの助力を受ける事にしたようだ。
「ああ、頼もうか」
どうすればいい、と肩を竦めたアリスにジャガーノートは「動かなければいい」と答え、助力の代わりにと、交換条件を持ち掛けた。
僅かにアリスは眉をしかめ、怪訝に思う感情を隠さない。そんな彼女へとジャガーノートは短く。
「一つだけ、聴きたい」
――君がこの戦いの中で、何を思うのか。
そう、問うた。
彼女は、私と同じく、演じ、装うものだ。仮面を被ったものだ。
かつて共にあり、共に過ごしたものと対峙する。そんな状況で何を思うのか。
それが聴きたい、とジャガーノートの言葉に、アリスは一つ瞬きをして豹の鎧を見た。
「その質問が、私が何を望むのか、と言う意味なら」
顎を引き、威風堂々と彼女は言う。凛とした笑みを伴ってその問いに答えていた。
「何も望まないさ」
「……そうか」
標的を指定する。
纏わせるエンチャントを装填する。その出力を調整し、最高効率の実現を行っていく。
それが放たれる間際、ジャガーノートの肩へと鎧越しに、アリスの手が触れた。
返答はまだ続いていた。
「ただ、望まない事を思うなら」
その瞬間、傭兵と王子という肩書が払われたような気がした。
人とは、表情一つでこうまで印象を変えるのか。それは一瞬、視線を奪われる程で。
仮面を外した別人がそこにいて、淡い色の感情を見せる瞳をジャガーノートへと向けた。
彼女は静かに答える。
「殺されたい、かな」
仮面の下に見えた感情は、悲しみと憧憬と、そして嫌悪が滲んでいた。だが、その一瞬に垣間見えた表情を確かめようとした時には、その仮面は忽ちにその表情を覆い隠していた。
その装いは、やはり見事なもので。
ジャガーノートはその晒した素顔すら、アリスが意図してジャガーノートに見せた感情なのだと知れた。
「感謝するよ」
眩い光と共に発射された電気が、アリスの身を傷つける事無くその剣へと吸い込まれていく。
細剣へと纏わせた雷のエンチャントが纏う炎へと混ざり合う。鋭い光が走り、それを伝うように炎が弾ける。
行け、とジャガーノートは沈黙を返した。
アリスも、言葉が返るとは思っていないのだろう、その返事を待たずに駆けだしていた。
その背へ向けて、声に荒く擦れたような雑音を混ぜて言葉を送る。
「焔のみならず雷光を纏い、稲妻の如く剣を振るうといい、王子よ」
私はその道行きを称賛しよう。その熱を祝福しよう。
彼女が王子であるのならば、熱線銃を備えたこの身はその騎士と成ろう。
この舞台の主役が、君ならば。
駆けろ、と。
視線に乗せた想いに応えるように、バチリ、と焔雷が瞬いた。
大成功
🔵🔵🔵
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト
奪われたもの
残すものがあれば、聞こう
界離で時の原理の端末召喚。淡青色の光の、格子状の針金細工
オウガの攻撃を意図的に受け、オウガに簒奪された者に触れる
まだ其処にいるなら、今何を望むのか
終わった後なら情報を遡り、最後は何を思っていたか
いつまでと保証はできんが記憶にはとどめよう
或いはこちらに、言葉を残したい相手でもいれば届ける努力を
致命となりうる攻撃は「終わった後」に飛ばして回避し、それ以外は受けてから「癒えた後」に飛ばして回復
意に反し終わらされた者たちが何を残すものか
僅かなりこれで実感が持てるだろうか
アルトリウスの扱う原理とは、彼の認識によれば世界が構築される前の法則であるという。
本来、触れる事はおろか、認識する事すらできない世界というものの向こうに存在しているそんな物を、機能として彼が扱えているのは、彼自身がその原理から生み出された、ようなものだからだ。
彼はいうなれば、原理という脳が世界へと発した電気信号そのものと、いやそれを受け取る指先の神経と、置き換える事が出来るかもしれない。
当然、規模も詳細も全く違うものではあるはずだが、しかしその理解の必要性は今ここに於いて存在しない。
重要なのは、彼の操るものが、構築されたこの世界の外のものだと言う事だ。そして、その本質は、原なる理、という名称に異を唱えるものではないと言う事だ。
例えば料理であれば、盛り付けや皿によってその印象を変える。
例えば言葉であれば、それを届けられたものによって意味を変える。
そして、人の形をしながらにして、人とは違うアルトリウスには、その料理の与えうる印象も、言葉の持ちうる意味も、いまだその全てを想起しきれるものではない。
詰まる所、アルトリウスの持つ権能は、その世界というものによって、原理を根本にしてはいても別の要素が加算された世界なるもののフィルターによって、想起しえたそれより僅かなズレを持って顕現していた。
それは、猟兵達がオブリビオンと呼ぶものがこの世界においてはオウガと呼称されることであったり、ここに来る直前の庭園でアリスのオーディションとやらが強引な干渉を逃れた一幕であったり、そして、今彼が相対した焔の爪を受け止めた首筋に熱を感じたことであったりする。
「……」
炎舞の中へと足を踏み入れたアルトリウスに、アリスと猟兵達は、何かの思惑を感じ取り、その理性的な瞳が破綻的でない事を理解して、ひと呼吸の間、オウガの対応を彼へと投げ渡していた。
オウガは焔を纏う爪を一拍の間隙も置かずに、割り込んできたその男へと振り下ろす。本能がそうさせるのか、咄嗟に振るわれたようなその攻撃はしかし、首を掻き切るような軌道を最短で辿る。
それに対し、アルトリウスは体を動かし避ける気などは無い。展開した格子状の淡い青の光が無機質に瞬けば、その内包された原理の一端を現象化させた。
その攻撃がアルトリウスへと与えるであろう影響の一切を、その工程が全て終わった後へと飛ばしたのだ。
いや、先述した通りに、その全てを今この時点から喪失させることは出来ていなかった。僅かに皮膚を焼く熱に、アルトリウスは表皮の壊死を認識しながら、しかし、処置の必要性を否定していた。
「好都合だ」
炎と共に首の皮を僅かに破ったその爪は、オウガの肉体は物理的に接触している。
こちらから動く必要は無く、アルトリウスはそのまま、原理によって更なる世界への干渉を行使していた。
その瞬間、アルトリウスは五感から引き剥がされた。
「何を望んでいた」
淡い光が、精神を導く。五感を失った精神が光の速度を超え辿り着いたのは、オウガに呑まれる、呑まれた、アリスの精神だった。
「何を思う」
その声にそれは答えない。
「何を」
残すのか。
既に終わっている、奪われ、失ったそれが残そうとしたもの。残したもの。
声が返った。いや、それを声だと認識したのは、アルトリウスという人間単位の知覚であり、きっとそれは声ではないのだろう。
いうなれば、それは情報だ。寄せる細波の弾ける泡の一つのようなもの。
オウガの爪が首から離れる。
アルトリウスの精神が、見合った器へと逃げ込む。
「なんだそれは」
時間を超越したような一瞬の交わりに、彼が得たのは、酷く当然の事実でしかなかった。
彼女がそこにいた。在り続けていた。無数の文字とも記号とも言えない情報の中で、人ならざる彼が拾えたのは、有体の事実だけで。
「……そうか」
アルトリウスは、それを悟る。
端末としての、不足。人間という一つ個体を理解するための言語がまだ完全ではないのだ。
「いつか、今の情報を知る事が出来るだろうか」
目の前の残骸へと問いかける。
今度こそアルトリウスの頸動脈を裂き切らんと腕を振り上げたオウガの宿る残骸へと、雷撃が放たれ、その攻撃を阻んでいた。
大成功
🔵🔵🔵
 渦雷・ユキテル
渦雷・ユキテル
なーんか引っかかるんです
王子様みたいなアリス
お城の中心にいるオウガ
舞台の立ち位置って重要ですよね?
【属性攻撃】【マヒ攻撃】派手に電撃を放ち
相手が攻撃を受けるか避けるかした直後
さらに電撃【マヒ攻撃】込めた弾丸をオウガに
こちらに隙ができないよう
だけど無駄に撃つのは無粋
急所は外して演技続行できる程度に痺れてもらいます
ユーベルコードの力を借りて取り出したのは
……随分小さなナイフ
リーチ短すぎて使う気しませんね
剣の他に小道具のひとつくらいどうです
アリスの足元にポイと投げ
使うかどうかはご自由に
ね、違ってたら笑ってほしいんですけど
貴女と彼女(オウガ)
あべこべなんじゃないかと思って
演じてる役、本当に合ってます?
引鉄に掛けた指は、構えた銃口から夥しい雷の束ともいうべき雷撃の弾丸を発射させていた。
猟兵の一人へと向かっていったオウガの動きを完璧に阻止するような角度と速度。並みの反射神経であれば気付く事すら難しいだろうその一撃に、しかし、そのオウガは宙に弧を描くような後転によってその回避を為していた。
「やっぱり」
オウガがその猟兵からユキテルに標的を変えたようだ。
「引っかかるんですよねえ」
一気に、ユキテルへと駆けたオウガに彼は照準を合わせながら、空いた片手を遊ばせる。
否、ただ遊ばせるのではない。
その指は、上着のポケットへと差し込まれて、何も入っていないはずのそこから何かを引き出した。
「何ですか、これ」
焼き裂こうと飛び掛かってきたオウガの爪を、一歩飛びのいて避けるとユキテルは取り出したそれを手の中で確かめて、そう零した。
小さなナイフだ。子供か、体の小さな女性が護身用に持つような、武器として数えるには随分と頼りない存在。
握った拳銃の方がまだ近接武器としてもマシとも思える頼りなさ。
「使う気もしません、ねっ」
実際、オウガの次ぐ攻撃でその手首を強かに打って、攻撃を逸らしたのは、降り抜いた拳銃のグリップの底だ。火炎の腕を弾くと共に、腕をたたむような構えでその腕へと雷撃を撃ち放つ。
間近から放たれたその一撃は、その腕を穿ち抜いていた。肉を焼いて、骨を砕いたそれに、しかしオウガはまだ腕を振るわんとするが、それをアリスは追撃に飛び込んだ。
腕と剣が交わり、さらにオウガを狙う攻撃が殺到する。そして、アリスとオウガの距離がまた離されたのを見て、ユキテルは丁度いい、と照準を外さないように意識しながら、口を開く。
「ああ、少しいいですか?」
そうアリスを呼び止めた。
「……なんだい」
今にもオウガへと飛び込まんとしていたアリスは、その乱れた髪を不意に弾ませて、急くように、しかしユキテルに従う。
ユキテルは、そんな彼女へとええ、と息を整えるように、言う。
「ね、違ってたら笑ってほしいんですけど」
平たい筆を黒いキャンパスへと引いたように走る炎に、藍炎が光を喰らうように弾けて、オウガの炎が群花の火炎を開かせる。紅の熱線がその隙間を縫い、淡い青が幾何学に瞬いて、オウガを的確に追い詰めていく。
その傷の蓄積は、先ほどインファイトの距離にまで迫ったユキテルや、常にオウガへと接近戦を仕掛けるアリスには隠しきれるものではない。明らかに、動きが鈍っている。
そんな大詰めとも言うべき場面で、ユキテルは問いかける。
王子様みたいなアリス。
お城の中心にいるオウガ。
貴女と彼女。とユキテルが示すのは誰か。指で刺すまでも無く理解できるだろう。
アリスとオウガ。その立ち位置。
「あべこべなんじゃないかと思って」
城の中にいるべきは王子で、城の外にいるべきは、そこにいるオウガなのではないのか。
それが城の中にあるのは、どうしてか。
投じられた一石は、ともすればこの舞台の根本を揺らすものだ。静寂を叩くように齎された波紋は、紛れも無くアリスの瞳を見開かせ。
「演じてる役、本当に合ってます?」
そして、アリスは笑う。
「ああ」
その笑みは、僅かに寂し気な色を見せていた。
「私のような事を思うんだね」
「……」
今にも、駆けだそうと構えていたアリスは、その答えと共にその構えを緩め、ユキテルに意識を向ける。
「分からないんだ、合ってるのか、合っていないのか」
アリスは言う。私があちらでも良かった。でも、彼女は今の私になりたくはないだろうと。
「……」
なりたいと、思って欲しくない。が正しいのだろうと、ユキテルはその言葉になんとなく思う。
きっとアリスは、その配役が合っているかいないか、は既に執着していないのだろう。合っていようと、合っていなかろうと、今は剣を握るのが自らであることを認めて、求めてすらいる。
どうしてかは知らずとも、そう感じた。
「いいえ」
もしくは、あたしが彼女たちにそうあって欲しいと。
「そうですか」
瞼を少し細め思考を断つと、ユキテルは笑んで見せる。そうして、アリスへと手の中で少し弄んだ小さな刃を投げ渡した。
使い手に理解を求める武器だ。ユキテルにはその使い方を見いだせないが、彼女であれば分かるのかもしれない。
それを掴んだアリスの表情を確かめる気はしなかった。興味は沸くが、それ以上に面白くはなさそうだという直感があった。
ユキテルの視線は、オウガを射抜く。
「さて、幕引きのお時間にしましょうか」
「ああ、そうしよう」
●
ともすれば食われてしまいそうだ。
多彩な技に、鮮やかな体捌き。同じ場所に立っていながらに見惚けてしまいそうだ。
この場に集まって力ある者達と、そして、目の前のオウガへと。
「……っ」
やはり、私だけでは負けていたのだろう。
成すすべなく喰われていたのだろう。
炎を吐くオウガが何を思い、この舞台の再現などというものを行ったのかは分からない。紅の雷が走る。紅蓮の尾が瞬く。
踏み込めば世界は加速し、感覚は引き延ばされる。不思議な感覚だ。情報は膨大に過ぎるのに、その一つも零す事無く理解していく。
体がこれまでに無い程の速度を持っているのに、それに振り回される事も無く、どころか、恐るべき精度での制御を行えている。
目を焼くような劫火熱風の中で、アリスは駆ける。
私こそが、主役であると叫ぶように。
迸る炎が触れ合った端から、互いを焼きながら散っていく火花に変わっていく。
「ああ」
突いた刃が肩を貫く。その刃を戻す前に爪が腕を焼く。傷を無視して剣が爪を裂く。跳ねた足が剣を叩く。
爆炎の尾で円を描いた宙返りの蹴撃が、剣を激しく打ち上げて緩んだ握力から細剣が手の中を逃れてどこかへと消え去っていく。
この暗闇に、探す事すら出来ない。
指を柄が擦れる一瞬が、アリスの加速する思考の中で緩慢に過ぎる。
走馬灯というのだろうか。
溢れた記憶は、忘れていた物も含めて、遠くから近くまで千差万別で。
声が漏れた。
初めて会った時を覚えていない。緊張のるつぼで誰に挨拶をしたか等分からない。
それでも、それからは先輩の存在は大きい。そんなこともあったか、と指の摩擦の感覚が、ざらつきの一つ一つが光景を見せる。
爆炎の蹴り上げ。サマーソルトキック。体の身軽だったことを思い出す。それは一秒に至る衝撃だったのか。体感時間はやはり、一瞬で。
思考だけが、オウガの身体が一転する様を、延々と見続けていた。
ああ、なんてことだ。と呆れる。
オウガの脚が着地する。その瞬間に、アリスの身体はオウガへと迫っていた。胸へと飛び込むように、殴打すら満足に行えないような至近距離で、アリスは呆れる。
握った小さなナイフがオウガの首を貫いて、裂いた。
殺せてしまうじゃないか。
思考は、一瞬前の身体を追いかける。崩れ落ちるオウガの身体を見て、アリスは初めてそのズレを認識した。
血が吹き上がる事も無く、代わりに血を啜るように炎が燃えて体をも飲み込んでいく。
長い一瞬が終わる。
群花は悉くに散り、大輪が瞼を閉じるように蕾む。
残るのは、アリス一人で。
暗闇が消えていく。見れば、天井が、壁が、世界を包んでいた暗闇というものが紙細工を潰すように折り畳まれていき、いつしか、初めの菱形の地面へと立っている。
城は庭園も含め姿を消して、空に並ぶ太陽だけが変わらず熱を発していた。
静寂。それは暗がりの中よりも、静かに響いて。
そして、アリスが振り向く。
「これで、終幕だ」
その声は凛と、耳を打っていた。
大成功
🔵🔵🔵


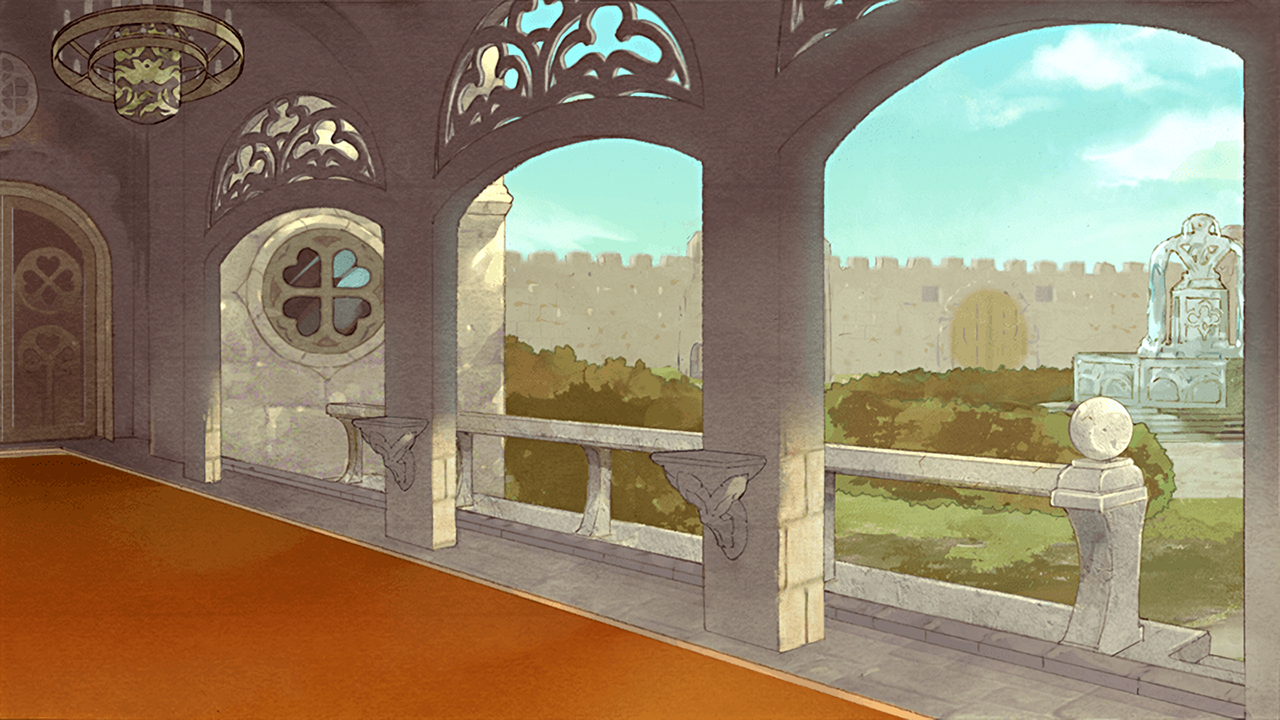
 アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト  渦雷・ユキテル
渦雷・ユキテル  ロク・ザイオン
ロク・ザイオン 
 セラ・ネヴィーリオ
セラ・ネヴィーリオ 
 ロク・ザイオン
ロク・ザイオン  ラピタ・カンパネルラ
ラピタ・カンパネルラ  ジャガーノート・ジャック
ジャガーノート・ジャック  アルトリウス・セレスタイト
アルトリウス・セレスタイト  渦雷・ユキテル
渦雷・ユキテル